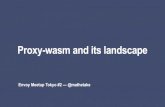必須・選択 開講時期 単位 時間/週 教科の区分 系基礎学科 必須 Ⅰ … ·...
Transcript of 必須・選択 開講時期 単位 時間/週 教科の区分 系基礎学科 必須 Ⅰ … ·...

科名:
必須・選択 開講時期 単位 時間/週
内線電話番号
No
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩
試験 小テスト レポート 制作物 成果発表 その他 合計
90 0 0 0 0 10 100
30
30
5
10
10
5 10
評価割合
授業内容の理解度
技能・技術の習得度
コミュニケーション能力
プレゼンテーション能力
論理的な思考力、推論能力
取り組む姿勢・意欲
協調性
評価の割合(例)
授業科目受講に向けた助言
予備知識・技能技術 高校で学んだコンピュータの基礎知識(コンピュータの仕組みや基本操作など)を見直しておいてください。
授業科目についての助言
企業では、コンピュータで作成した各種書類や資料、図面等がごく普通に扱われており、コンピュータを道具として使いこなすことは、専門的な職務をおこなううえでも必須となっています。コンピュータを使って書類等を作成するには、各種アプリケーションソフトの操作上の思想を把握することがポイントになります。また、意図する書類等を十分に把握し、作成後の書類データの活用も含めて、最も効果的効率的に作成できるアプリケーションソフトを選定することは重要なことです。さらに、これからの教育訓練活動を支えるレポート、プレゼンテーション資料や総合制作実習論文等をコンピュータによって効率的・効果的に作成するための能力を習得します。わからないことを積み残さないよう毎回の授業をしっかりと理解してください。本科目で習得する内容が今後の習得科目につながりますので、自分自身で学習することはもちろん、わからないことは質問や討議に応じますので積極的に申し出てください。課題は必ず期限内に提出してください。
教科書および参考書(例) 教科書:できるシリーズテキスト
授業科目の発展性
評価方法 指標・評価割合
表計算データ処理のグラフ機能の活用について知っている。
授業科目に対応する業界・仕事・技術
各種業界でのコンピュータ処理作業
授業科目の訓練目標
授業科目の目標 授業科目のポイント
コンピュータ及び情報技術の活用方法と関連知識を学びます。
コンピュータの構成要素について知っている。
コンピュータの仕組みについて知っている。
コンピュータの基本操作について知っている。
ファイルとフォルダの操作について知っている。
文書データ処理の文書データの作成について知っている。
文書データ処理のプリンタの設定と印刷について知っている。
文書データ処理の図形描画及び挿入について知っている。
表計算データ処理のデータ入力について知っている。
表計算データ処理の表計算及び集計について知っている。
担当教員 電子メールアドレス 教室・実習場
森本 恵 5204(機械系CAD室)
必須 Ⅰ・Ⅱ期 2 2教科の区分 系基礎学科
教科の科目 情報工学概論
生産技術科
訓練科目の区分 授業科目名
教育訓練課程 専門課程
コンピュータ基礎
コンピュータ基礎
情報処理実習
CAD実習Ⅱ
総合制作実習
CAD実習Ⅰ

回数 運営方法
1,2週
講義、実習、質疑
3,4週
実習、質疑
5,6週
実習、質疑
7,8週
実習、質疑
9,10週
実習、質疑
11,12週
実習、質疑
13,14週
実習、質疑
15,16週
実習、質疑
17,18週
実習、質疑、試験
5.表計算データ処理 (1)表計算ソフトの基本操作 (2)表の作成 ①文字と行の高さ・列幅の変更 ②文字の配置変更 ③表示形式の変更 ④罫線の活用 (3)データ入力 ①文字列・数値・計算式の入力とコピー ②連続データの自動入力
時間内に課題演習が終わらなかった場合は、次回までに終わらせてください。
(3)メールソフトの設定 (4)メールの送信、受信、転送 (5)アドレスや署名登録等 (6)ウイルス対策とセキュリティ、ネット使用上のマナーについて8.試験 課題試験
時間内に課題演習が終わらなかった場合は、次回までに終わらせてください。 ここまでの理解度を確認し、苦手な所を復習してください。
(4)表計算及び集計 ①相対参照と絶対参照 ②関数の活用
時間内に課題演習が終わらなかった場合は、次回までに終わらせてください。
(5)グラフ機能の活用 ①グラフの種類 ②棒グラフ・円グラフ・折れ線グラフ等の作成 ③グラフの変更方法6.ネットワーク (1)ネットワークの概要 (2)パソコンの接続
時間内に課題演習が終わらなかった場合は、次回までに終わらせてください。
(3)ネットワークの設定方法 (4)共有設定 (5)リソースの割り当て7.インターネットとメール (1)ホームページ閲覧ソフトの設定 (2)インターネット検索
時間内に課題演習が終わらなかった場合は、次回までに終わらせてください。
4.文書データ (1)文書作成ソフトの操作 (2)文書データの作成 ①文字の位置揃え ②文字装飾 ③箇条書きと段落番号 ④インデント ⑤行間の調整 ⑥表 ⑦段組 (3)プリンタの設定と印刷
時間内に課題演習が終わらなかった場合は、次回までに終わらせてください。
(4)図形描画及び挿入 ①図形描画の機能 ②オートシェイプ ③クリップアート ④テキストボックス ⑤写真 ⑥ワードアートの挿入
時間内に課題演習が終わらなかった場合は、次回までに終わらせてください。
(3)デスクトップの設定 (4)デスクトップのカスタマイズ (5)ファイルとフォルダの操作
時間内に課題演習が終わらなかった場合は、次回までに終わらせてください。
訓練の内容 訓練課題 予習・復習
1.ガイダンス (1)シラバスの提示と説明 (2)安全作業について2.コンピュータ (1)コンピュータの歴史 (2)コンピュータの構成要素 (3)コンピュータの仕組み3.コンピュータ操作 (1)コンピュータの基本操作 (2)キー操作と画面操作

科名:
必須・選択 開講時期 単位 時間/週
内線電話番号
No
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩
試験 小テスト レポート 制作物 成果発表 その他 合計
90 10 100
90
10
評価の割合(例)
評価方法 指標・評価割合
評価割合
協調性
論理的な思考力、推論能力
取り組む姿勢・意欲
プレゼンテーション能力
授業科目の訓練目標
授業科目の目標
教室・実習場
青木 節
授業科目のポイント
授業科目に対応する業界・仕事・技術
機械製造分野における加工・組立業務、機械製造分野における加工オペレータ、機械製造分野における品質・生産管理業務機械製造分野における設計業務、機械製造分野におけるラインオペレータ、機械製造分野における保全業務
5401教室
電子メールアドレス
生産技術科
訓練科目の区分
専門課程
授業科目名
工業材料Ⅰ系基礎学科
教科の科目 材料工学
教育訓練課程
機械的性質について知っている。
工業材料の物質構造、組織を理解し、鉄鋼材料の基礎を学びます。
鋳鉄について知っている。
工具鋼について知っている。
金属の成形について知っている。
加工硬化について知っている。
炭素鋼と合金鋼について知っている。
機械構造用鋼について知っている。
鉄鋼材料の分類について知っている。
鋼の熱処理について知っている。
ステンレス鋼について知っている。
2教科の区分
担当教員
必須 Ⅰ・Ⅱ期 2
教科書および参考書(例)
授業内容の理解度
コミュニケーション能力
教科書:絵ときでわかる機械材料
技能・技術の習得度
授業科目の発展性
予備知識・技能技術 基本的な元素記号を記憶しておいてください。「機械工作」「材料力学」などで学んだ専門用語について理解しておいてください。
多くの機械は高性能・高機能化の追求に加え、地球にやさしい、環境にやさしいことにも重点が置かれてきています。機械を構成する材料もこれらの性質を満足するため、改善が日々行われています。 本科目では、機械を製作する上で必要な材料の基本的性質についての基礎知識を習得することができます。また、各種材料の特徴について理解することができます。優れた機械を製作するには、材料についての基礎知識は不可欠であるので、興味を持って履修してください。わからないことを積み残さないよう毎回の授業をしっかりと理解してください。自分自身で学習することはもちろん、わからないことは質問や討議に応じますので積極的に申し出てください。
授業科目受講に向けた助言
授業科目についての助言
工業材料Ⅰ 工業材料Ⅱ

回数 運営方法
1~3講義、演習
質疑
4~6 講義、質疑
7~10 講義、質疑
11~15
講義、演習質疑
16~17
講義、質疑
18 試験
テキストP71~P82を予習してください。4章の章末問題を解答し、理解不十分な点について復習してください。 授業内容を復習し、合金鋼の種類について整理してください。
6.合金鋼 (1)合金鋼の種類 ①特殊元素による純鉄の強化 ②高張力鋼・ハイテン鋼 ③超強力鋼 (2)工具鋼 ①炭素工具鋼 ②合金工具鋼 ③高速度鋼 ④超硬合金 ⑤セラミック (3)ステンレス鋼 ①クロム系ステンレス鋼 ②クロム-ニッケル系ステンレス鋼 (4)耐熱鋼 ①加工用耐熱鋼 ②鋳造用耐熱鋼
訓練の内容
テキストP45~P70を予習してください。3章の章末問題を解答し、理解不十分な点について復習してください。 授業内容を復習し、炭素鋼の状態図と組織およびJISによる鉄鋼材料の分類について整理してください。
4.材料の化学 (1)金属の結晶構造 ①結晶格子 ②単位胞中に含まれる原子数 (2)格子欠陥 (3)平衡状態図
テキストP21〜P44を予習してください。第2章の章末問題を解答し、理解不十分な点について復習してください。
5.炭素鋼 (1)金属の精錬 ①製銑法 ②製鋼法 ③鋼塊 (2)炭素鋼の状態図と組織 ①全率固容体型状態図と組織 ②共晶型状態図と組織 (3)鋼の熱処理 ①焼なまし ②焼ならし ③焼入れ ④焼戻し (4)鋼の表面処理 ①高周波焼入れ ②浸炭 ③窒化 (5)鉄鋼材料の分類 ①JISによる鉄鋼材料の分類 ②炭素鋼の種類
7.鋳鉄 (1)鋳鉄とは (2)鋳鉄の種類
ここまでの理解度を確認し、苦手な所を復習してください。
テキストP1~P20を予習してください。 授業内容を復習し、材料の機械的性質について整理してください。 第1章の章末問題を解答し、理解不十分な点について復習してください。
訓練課題 予習・復習
1.ガイダンス (1)シラバスの提示と説明2.工業材料総論 (1)現代社会と工業材料 (2)工業材料の動向 (3)工業材料の分類3.材料の機械的性質 (1)機械的性質 ①引張試験法 ②硬さ試験法 ③衝撃試験法 ④疲労試験法 (2)物理的性質
8.試験 筆記試験
テキストP83~P90を予習してください。5章の章末問題を解答し、理解不十分な点について復習してください。 授業内容を復習し、鋳鉄について整理してください。

科名:
必須・選択 開講時期 単位 時間/週
内線電話番号
No
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩
試験 小テスト レポート 制作物 成果発表 その他 合計
90 10 100
90
10
評価方法 指標・評価割合
予備知識・技能技術
協調性
プレゼンテーション能力
論理的な思考力、推論能力
取り組む姿勢・意欲
授業科目についての助言
私たちの身の回りには、色々な材料があふれています。「工業材料Ⅱ」では、アルミなどの非鉄金属材料、プラスチックなどの高分子材料、陶器などのセラミック材料についてその特徴、活用法について習得します。上記材料は、その特長を活かし鉄鋼材料に替わり身の回りの自動車、家電製品、OA機器などその他各種分野で使用されいます。使用範囲も広く、種類も大変多くなっています。機械設計・加工を行う上でこのような材料の特徴と使用方法・用途を知り理解しておくことが、機械技術者にとって必要となっています。自身で学習することはもちろん、わからないことはどんどん質問し、しっかり身につけましょう。
授業科目受講に向けた助言
評価割合
教科書および参考書(例)
技能・技術の習得度
授業内容の理解度
評価の割合(例)
授業科目の発展性
コミュニケーション能力
既習の「工業材料Ⅰ」で学んだ金属材料の性質、製造法、強化法を整理しておいてください。特に最もよく使用される鉄鋼材料については、状態図の見方・熱処理法・表面処理法及び各種鉄鋼材料の性質について復習し十分に理解しておいてください。
教科書:絵ときでわかる機械材料
教育訓練課程
銅・アルミ・チタン・その他金属の合金等の特性・使用法について知っている。
高分子材料の特徴・分類・構造と物性について知っている。
高分子材料の成形加工について知っている。
電子メールアドレス 教室・実習場
教科の区分
教科の科目
系基礎学科
銅・アルミ・チタン・その他金属の特性・使用法について知っている。
機械製造分野における品質・生産管理業務、機械製造分野における設計業務に関連する。
授業科目の目標
青木 節
工業材料としての非鉄金属、高分子材料、セラミックス等の基礎を学習します。
5401教室
授業科目の訓練目標
エンジニアリングプラスチック・ゴム・接着剤について知っている。
生産技術科
授業科目のポイント
授業科目に対応する業界・仕事・技術
材料工学
工業材料Ⅱ 2必須
担当教員
授業科目名訓練科目の区分
専門課程
Ⅲ・Ⅳ期 2
セラミックス材料の特徴・分類・構造と物性について知っている。
セラミックスの製造プロセスについて知っている。
機能性先端材料についてその種類・特徴・物性について知っている。
工業材料Ⅱ 総合制作実習 工業材料Ⅰ

回数 運営方法
1~3講義、演習
質疑
4~6講義、演習
質疑
7~8講義、演習
質疑
9~10講義、演習
質疑
11~12
講義、演習質疑
13~14
講義、演習質疑
15~17
講義、演習質疑
18 試験
テキストP91~P108を読んでおいてください。 銅合金とアルミニウム合金について理解できるよう復習してください。
訓練の内容 訓練課題 予習・復習
1.ガイダンス (1)シラバスの提示と説明 .2.非鉄金属 (1)銅とその合金 ①銅 ②黄銅 ③青銅 (2)アルミニウムとその合金 ①展伸用合金 ②鋳造用合金 ③ロウ材 ④調質記号
5.試験 筆記試験
テキストP109~P116を読んでおいてください。 チタン合金とその他合金について理解できるよう復習してください。
テキストP117~P119を読んでおいてください。 高分子材料の概要と構造、物性について理解できるよう復習してください。
テキストP124~P133を読んでおいてください。 高分子材料の中のエンプラ・ゴム・接着剤とセラミックス材料の概要について理解できるよう復習してください。
テキストP134~P141を読んでおいてください。 セラミックス材料の製造プロセス及びセラミックス材料の構造と物性について理解できるよう復習してください。
講義・課題の内容を十分に理解し不明な点を質問などで明らかにし試験に臨んでください。
テキストP142~P146を読んでおいてください。 各種セラミックス材料について理解できるよう復習してください。
テキストP120~P123を読んでおいてください。 高分子材料の成形加工法と熱硬化性・熱可塑性樹脂について理解できるよう復習してください。
(5)シリカ系 ①製法 ②特性 ③製品 (6)アルミナ系 ①製法 ②特性 ③製品 (7)炭素系(合成ダイヤモンド) ①製法 ②特性 ③製品 (8)炭化物系 ①製法 ②特性 ③製品 (9)窒化物系 ①製法 ②特性 ③製品 (10)ガラス ①製法 ②特性 ③製品
(3)セラミックスの製造プロセス ①材料調整 ②成形 ③焼成 ④研削・接合 (4)セラミックスの構造と物性 ①材料構造 ②材料物性
(8)エンジニアリングプラスチック ①PA ②POM ③PC ④PET ⑤PBT (9)ゴム ①ACM ②NBR ③IR ④U ⑤BR ⑥IIR ⑦FKM (10)接着剤 ①無機系 ②有機系4.セラミックス (1)セラミックス材料の現状 (2)セラミックス材料の特徴
(5)高分子材料の成形加工 ①射出成形 ②押出し成形 ③ブロー成形 ④カレンダー成形 ⑤真空成形 (6)熱硬化性樹脂 ①PF ②EP ③MF ④UF ⑤PUR (7)熱可塑性樹脂 ①PE ②PP ③PVC ④PS ⑤テフロン ⑥ABS ⑦PMMA
3.高分子材料 (1)高分子材料の現状 (2)高分子材料の特徴 (3)高分子材料の分類 (4)高分子材料の構造と物性 ①共重合 ②架橋と網目構造 ③ガラス転移
(3)チタンとその合金 ①α 型 ②β 型 ③α +β 型 (4)その他の金属とその合金 ①マグネシウム合金 ②はんだ ③ウッドメタル ④バビットメタル ⑤超硬合金

科名:
必須・選択 開講時期 単位 時間/週
内線電話番号
No
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩
試験 小テスト レポート 制作物 成果発表 その他 合計
80 10 10 100
60 10
20
10
生産技術科
訓練科目の区分 授業科目名
教育訓練課程 専門課程
工業力学Ⅰ 必須 Ⅰ期 2 4教科の区分 系基礎学科
教科の科目 力学
担当教員 電子メールアドレス 教室・実習場
孫入 弘安 5401教室
授業科目に対応する業界・仕事・技術
製造業における設計業務、加工・組立業務、品質・生産管理業務及び保全業務
授業科目の訓練目標
授業科目の目標 授業科目のポイント
機械の設計や保守等において動力計算や機器・部品の選定、仕様計算等を行うに不可欠な工業力学分野の「つりあい」、「仕事と動力」、「摩擦」、「滑車」について学習する。
力のつりあいについて知っている。
モーメントのつりあいについて知っている。
支点の種類とその反力について知っている。
重心の定義について知っている。
仕事の定義と単位について知っている。
動力の定義と単位について知っている。
トルクと回転数と動力の関係について知っている
すべり摩擦、ころがり摩について知っている。
滑車の種類と特徴について知っている。
授業科目受講に向けた助言
予備知識・技能技術 高校で学んだ「物理」の静力学(力の合成・分解、偶力、力のモーメント)、運動学(速度と加速度、運動量と力積)、仕事とエネルギ(仕事の定義、位置エネルギと運動エネルギ、エネルギ保存則)の基本的事項を整理しておくことをお勧めします。
授業科目についての助言
工業力学は、高校の物理とこれから本校で学習する材料力学やメカニズムなどの力学を主体とした科目との間を取り持つ科目になります。したがって、本科目を十分に理解することで、今後の授業科目の習得度の向上が望めます。 工業力学Ⅰでは物体の静止状態での力学を学習します。高校までに学んだ力のつりあいについての復習と高校では学習しないモーメントについて説明します。また、さまざまな構造物や機械等における支点反力の求め方、および仕事と動力の関係などについて学びます。本科目の習得する内容が今後の習得科目につながりますから、自身で学習することはもちろん、わからないことはどしどし質問してください。
教科書および参考書(例)教科書:工業力学(森北出版)参考書:
授業科目の発展性
評価の割合(例)
評価方法 指標・評価割合
評価割合
授業内容の理解度
技能・技術の習得度
コミュニケーション能力
プレゼンテーション能力
論理的な思考力、推論能力
取り組む姿勢・意欲
協調性
工業力学Ⅰ 工業力学Ⅱ メカニズム
材料力学Ⅰ 物理

回数 運営方法
1~2講義、演習、
質疑
3~4講義、演習、
質疑
5~6講義、演習、
質疑
7~8講義、演習
質疑
9~10
講義、演習質疑
11~12
講義、演習質疑
13~14
講義、質疑
15~17
講義、演習質疑
18 試験
訓練の内容 訓練課題 予習・復習
1.ガイダンス (1)シラバスの提示と説明2.つりあい (1)力のつりあい (2)モーメントのつりあい
力およびモーメントのつりあいについて復習してください。
(3)支点反力の求め方 ①支点と支持反力、支持モーメント ②支持反力、支持反力の求め方
3種類の支点と支点に働く力とモーメントについて理解し、支点反力の求め方について復習してください。
③トラス構造に生じる力とモーメント (4)重心 ①物体の重心とすわり
トラス構造に生じる力とモーメントの求め方について復習してください。また課題に取り組んでください。重心の求め方を復習した下さい。
3.仕事と動力 (1)仕事の定義と単位 (2)動力の定義と単位
仕事および動力の定義と単位について復習してください。
(3)トルクと回転数と動力の関係 トルクと回転数と動力の関係について復習してください。
6.試験 筆記試験
ここまでの理解度を確認し、苦手な所を復習しておいてください。また、追試験は行いません。
4.摩擦 (1)すべり摩擦 (2)摩擦係数と摩擦角
摩擦の一つであるすべり摩擦と物体を移動させるのに必要な力との関係を理解してください。また摩擦係数と摩擦角について復習してください。
(3)ころがり摩擦5.滑車の力学 (1)定滑車
摩擦の一つであるころがり摩擦と物体を移動させるのに必要な力との関係を理解してください。
(2)動滑車、その他の滑車 定滑車、動滑車の力学を課題を解きながら復習してください。

科名:
必須・選択 開講時期 単位 時間/週
内線電話番号
No
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩
試験 小テスト レポート 制作物 成果発表 その他 合計
80 10 10 100
80 10
60
20
10
生産技術科
訓練科目の区分 授業科目名
教育訓練課程 専門課程
工業力学Ⅱ 必須 Ⅱ期 2 4教科の区分 系基礎学科
教科の科目 力学
担当教員 電子メールアドレス 教室・実習場
孫入 弘安 5401教室
製造業における機械設計・開発業務、品質・生産管理業務、保全業務
授業科目の訓練目標
授業科目の目標 授業科目のポイント
機械の設計や保守等において動力計算や機器・部品選定、仕様計算等を行うのに不可欠な工業力学分野の「回転運動」、「機械振動」について学習する。
点の運動について知っている。
直線運動の運動方程式について知っている。
回転運動の運動方程式について知っている。
剛体の慣性モーメントについて知っている。
主な形状物体の慣性モーメントを与える式について知っている。
慣性モーメントにおける平行軸の定理について知っている。
角速度と振動数と周期の関係について知っている。
固有振動数について知っている。
授業科目受講に向けた助言
予備知識・技能技術 既習の「物理」「工業力学Ⅰ」の静力学(力の合成・分解、偶力、力のモーメント)、運動学(速度と加速度、運動量と力積)の基本的事項を整理しておくことをお勧めします。
授業科目についての助言
工業力学は、高校の物理とこれから本校で学習する材料力学やメカニズムなどの力学を主体とした科目との間を取り持つ科目になります。したがって、本科目を十分に理解することで、今後の授業科目の習得度の向上が望めます。 工業力学Ⅰでは物体の静止状態での力学を学習します。高校までに学んだ質点の速度、加速度についての復習と高校では学ばない剛体の速度、加速度の求め方を取り扱い、その上で質点や剛体の慣性モーメントや運動方程式の求め方についての基本を学びます。また、機械を取り扱いう上で重要となる、機械振動の基礎についても学びます。本科目の習得する内容が今後の習得科目につながりますから、自身で学習することはもちろん、わからないことはどしどし質問してください。
教科書および参考書(例)教科書:工業力学(森北出版)参考書:
授業科目の発展性
評価の割合(例)
評価方法 指標・評価割合
評価割合
授業内容の理解度
技能・技術の習得度
コミュニケーション能力
プレゼンテーション能力
論理的な思考力、推論能力
取り組む姿勢・意欲
協調性
工業力学Ⅱ メカニズム
材料力学Ⅰ 材料力学Ⅱ
機械要素設計

回数 運営方法
1~2 講義、質疑
3 講義、質疑
4~5 講義、質疑
6~7 講義、質疑
8~9
講義、質疑
10~11
講義、質疑
12~13
講義、質疑
14~15
講義、質疑
16~17
講義、質疑
18 試験
訓練の内容 訓練課題 予習・復習
1.ガイダンス (1)シラバスの提示と説明2.点の運動 (1)直線運動
速度、加速度、等速度運動、等加速度運動について復習してください。
(2)平面運動 (3)相対運動
放物運動、回転運動について復習してください。
3.運動と力 (1)運動の法則 (2)慣性力 (3)向心力と遠心力
物体に力が働くと定量的にどのような運動の変化がおこるかという、力と運動の関係と運動の法則をよく復習して下さい。
4.剛体の運動 (1)直線運動の運動方程式 (2)回転運動の運動方程式
直線および回転運動の運動方程式について復習してください。
(3)剛体の慣性モーメント (4)連続体の慣性モーメント
慣性モーメントの基礎式を理解してください。また剛体や連続体の回転運動の運動方程式と慣性モーメントの関係を復習してください。
(6)共振現象と危険回転数 共振現象と危険回転数について復習してください。
6.試験 筆記試験
ここまでの理解度を確認し、苦手な所を復習しておいてください。また、追試験は行いません。
(5)主な形状物体の慣性モーメントを与える式 (6)慣性モーメントにおける平行軸の定理
主な形状物体の慣性モーメントを与える式と平行軸の定理について復習してください。
5.機械振動 (1)単振動 (2)角速度と振動数と周期の関係 (3)自由振動と強制振動
単振動の角速度と振動数と周期の関係について復習してください。
(4)固有振動数とは (5)主な振動系、振り子の固有振動数を計算する式
固有振動数について理解し、主な振動系、振り子の固有振動数を計算する式、について復習してください。

科名:
必須・選択 開講時期 単位 時間/週
内線電話番号
No
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩
試験 小テスト レポート 制作物 成果発表 その他 合計
60 30 10 100
50 20
10 10
10
評価割合
授業内容の理解度
技能・技術の習得度
コミュニケーション能力
プレゼンテーション能力
論理的な思考力、推論能力
取り組む姿勢・意欲
協調性
評価の割合(例)
授業科目受講に向けた助言
予備知識・技能技術 数学、工業力学を理解しておいてください。特に、力、モーメント、力のつりあいやモーメントのつりあいは、十分に理解しておいてください。
授業科目についての助言
材料力学では、自動車、飛行機や工作機械など形あるものの各部に作用している力や変形を調べ、安全設計に役立てるための基礎を習得することができます。その前提として、工業力学を十分に理解しておくことが重要です。材料力学を理解するための近道は、計算問題を数多く解くことが大切で、十分な演習を行う必要があります。わからないことを積み残さないよう毎回の授業をしっかりと予習・復習してください。本科目で習得する内容が今後の要素設計や設計製図などの専攻学科につながっています。関数電卓は必ず持参してください。
教科書および参考書(例)教科書:初めての材料力学(森北出版)参考書:
授業科目の発展性
評価方法 指標・評価割合
安全率と許容応力について知っている。
授業科目に対応する業界・仕事・技術
製造業における加工・組立業務、品質・生産管理業務、設計業務、保全業務
授業科目の訓練目標
授業科目の目標 授業科目のポイント
機械の設計や保守等において部材や部品の強度計算、剛性計算等を行うのに不可欠な材料力学について学びます。
応力について知っている。
ひずみについて知っている。
フックの法則について知っている。
縦弾性係数(ヤング率)について知っている。
横弾性係数(せん断弾性係数)について知っている。
横ひずみとポアソン比について知っている。
応力-ひずみ曲線について知っている。
引張強さと降伏応力について知っている。
応力集中について知っている。
担当教員 電子メールアドレス 教室・実習場
寺島 周平 5401教室
必須 Ⅲ期 2 4教科の区分 系基礎学科
教科の科目 力学
生産技術科
訓練科目の区分 授業科目名
教育訓練課程 専門課程
材料力学Ⅰ
材料力学Ⅰ 材料力学Ⅱ
メカニズム 機械要素設計
材料力学Ⅰ 材料力学Ⅱ
メカニズム 機械要素設計

回数 運営方法
1、2週講義、演習、
質疑
3,4週講義、演習
質疑
5,6週講義、演習
質疑
7,8週講義、演習
質疑
9,10週講義、演習
質疑
11,12週講義、演習
質疑
13,14週講義、演習
質疑
15,16週講義、演習
質疑
17,18週講義、演習質疑、試験
③伸び・縮みの計算方法 ④ひずみの計算方法 (3)横弾性係数(せん断弾性係数) ①せん断応力とせん断ひずみと横弾性係数(せん断弾性係数)の関係 ②横弾性係数の求め方 ③せん断ひずみの計算方法
授業内容を復習し、縦弾性係数と縦ひずみを整理してください。 与えられた課題についてレポートを作成し提出してください。授業時間内に終わらなかった場合は、次回の授業の始めに提出してください。
②基準強さのとり方 ③許容応力の求め方6.試験 筆記試験
章末問題を解答し、理解不十分な点について復習してください。 ここまでの理解度を確認し、苦手な所を復習してください。
(4)横ひずみとポアソン比 ①横ひずみと縦ひずみとポアソン比の関係 ②縦ひずみの計算方法 ③横ひずみの計算方法 ④伸び・縮みの計算方法5.安全率と許容応力 (1)応力-ひずみ曲線 ①応力-ひずみ曲線 ②比例限度と弾性限度 ③弾性ひずみと永久ひずみ ④軟鋼材料と非鉄金属の応力-ひずみ曲線
テキストを予習してください。 章末問題を解答し、理解不十分な点について復習してください。 授業内容を復習し、応力-ひずみ曲線を整理してください。
(2)引張強さと降伏応力 ①引張強さと降伏応力と0.2%ひずみ耐力 ②設計上の破壊とは (3)応力集中 ①応力集中と応力集中係数 ②応力集中の軽減方法
授業内容を復習し、引張強さ、降伏応力、0.2%ひずみ耐力と、応力集中を整理してください。
(4)疲労強度 ①疲労と繰返し荷重 ②疲労強度と繰返し回数 (5)安全率と許容応力 ①安全率と許容応力と基準強さの関係
与えられた課題についてレポートを作成し提出してください。授業時間内に終わらなかった場合は、次回の授業の始めに提出してください。
テキストを予習してください。 授業内容を復習し、応力の種類を整理してください。 与えられた課題についてレポートを作成し提出してください。授業時間内に終わらなかった場合は、次回の授業の始めに提出してください。
(2)縦ひずみ ①引張・圧縮荷重と縦ひずみの関係 ②縦ひずみの計算方法 (3)せん断ひずみ ①せん断荷重とせん断ひずみの関係 ②せん断ひずみの計算方法
与えられた課題についてレポートを作成し提出してください。授業時間内に終わらなかった場合は、次回の授業の始めに提出してください。 章末問題を解答し、理解不十分な点について復習してください。
4.応力とひずみの関係 (1)フックの法則 ①応力とひずみとフックの法則 (2)縦弾性係数(ヤング率) ①垂直応力と縦ひずみと縦弾性係数(ヤング率) ②縦弾性係数の求め方
テキストを予習してください。 授業内容を復習し、フックの法則を整理してください。
(3)せん断荷重とせん断応力 ①せん断荷重とせん断応力の関係 ②せん断応力の計算方法3.ひずみ (1)ひずみとは ①応力とひずみ ②ひずみの種類
テキストを予習してください。 章末問題を解答し、理解不十分な点について復習してください。また、授業内容を復習し、ひずみの種類を整理してください。
訓練の内容 訓練課題 予習・復習
1.ガイダンス (1)シラバスの提示と説明2.応力 (1)応力とは ①荷重と応力 ②荷重の種類 ③応力の種類 (2)引張・圧縮荷重と垂直応力 ①引張・圧縮荷重と垂直応力の関係 ②垂直応力の計算方法

科名:
必須・選択 開講時期 単位 時間/週
内線電話番号
No
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩
試験 小テスト レポート 制作物 成果発表 その他 合計
60 30 10 100
50 20
10 10
10
評価割合
授業内容の理解度
技能・技術の習得度
コミュニケーション能力
プレゼンテーション能力
論理的な思考力、推論能力
取り組む姿勢・意欲
協調性
評価の割合(例)
授業科目受講に向けた助言
予備知識・技能技術 既習の工業力学、材料力学Ⅰを理解しておいてください。特に、力のつりあい、モーメントのつりあい、応力、ひずみ、応力とひずみの関係は、十分に理解しておいてください。
授業科目についての助言
材料力学では、自動車、飛行機や工作機械など形あるものの各部に作用している力や変形を調べ、安全設計に役立てるための基礎を習得することができます。その前提として、工業力学を十分に理解しておくことが重要です。材料力学を理解するための近道は、計算問題を数多く解くことが大切で、十分な演習を行う必要があります。わからないことを積み残さないよう毎回の授業をしっかりと予習・復習してください。本科目で習得する内容が今後の要素設計や設計製図などの専攻学科につながっています。関数電卓は必ず持参してください。
教科書および参考書(例)教科書:はじめての材料力学(森北出版)参考書:
授業科目の発展性
評価方法 指標・評価割合
組合せ荷重について知っている。
授業科目に対応する業界・仕事・技術
製造業における加工・組立業務、設計業務、保全業務
授業科目の訓練目標
授業科目の目標 授業科目のポイント
機械の設計や保守等において部材や部品の強度計算、剛性計算等を行うのに不可欠な材料力学について学びます。
各種はりとその支持条件について知っている。
力のつりあいと支点反力について知っている。
はりのせん断力と曲げモーメントについて知っている。
断面係数と断面二次モーメントの計算式について知っている。
曲げ応力の計算式について知っている。
各種はりのたわみを計算する式について知っている。
ねじりモーメントとねじり応力、ねじり角の関係について知っている。
丸軸のねじり応力を計算する式について知っている。
座屈について知っている。座屈の計算が出来る。
担当教員 電子メールアドレス 教室・実習場
寺島 周平 5401教室
必須 Ⅳ期 2 4教科の区分 系基礎学科
教科の科目 力学
生産技術科
訓練科目の区分 授業科目名
教育訓練課程 専門課程
材料力学Ⅱ
材料力学Ⅱ
総合制作実習 機械要素設計 機械設計製図

回数 運営方法
1、2週講義、演習
質疑
3,4週講義、演習
質疑
5,6週講義、演習
質疑
7,8週講義、演習
質疑
9,10週講義、演習
質疑
11,12週講義、演習
質疑
13,14週講義、演習
質疑
15,16週講義、演習
質疑
17,18週講義、演習質疑、試験
(9)はりのたわみについて (10)断面二次モーメントとその計算式 ①断面二次モーメントとは ②各種断面の断面二次モーメントの計算方法 (11)各種はりのたわみを計算する式 ①各種はりのたわみの計算方法
授業内容を復習し、各種断面の断面二次モーメントの計算方法を整理してください。 章末問題を解答し、理解不十分な点について復習してください。
(2)座屈について (3)材料の破損条件について5.試験 筆記試験
章末問題を解答し、理解不十分な点について復習してください。 ここまでの理解度を確認し、苦手な所を復習してください。
3.軸のねじり (1)ねじりとは (2)ねじりモーメントとねじり応力の関係 ①ねじりモーメントと極断面係数 ②ねじりモーメントとねじり応力の関係式
テキストを予習してください。 授業内容を復習し、ねじりおよびねじりモーメント、極断面係数、ねじり応力を整理してください。
(3)ねじりモーメントとねじり角の関係 ①軸のこわさ ②ねじりモーメントとねじれ角の関係 ③ねじれ角と伝達動力 (4)中実丸軸のねじり応力を計算する式 ①中実丸軸のねじれ応力の計算方法
授業内容を復習し、軸のこわさ、ねじり角、中実丸軸のねじれ応力の計算方法を整理してください。
(5)中空丸軸のねじり応力を計算する式 ①中空丸軸のねじれ応力の計算方法4.その他の知識 (1)平面応力について ①平面応力 ②モールの応力円
テキストを予習してください。 章末問題を解答し、理解不十分な点について復習してください。 授業内容を復習し、平面応力とモールの応力円について整理してください。
「工業力学Ⅰ」で学んだ力のモーメント、力のつりあいを理解しておいてください。 テキストを予習してください。 授業内容を復習し、はりのつり合い条件、支点反力の計算方法を整理してください。
(5)各種はりの曲げモーメントを計算する式 ①各種はりの曲げモーメントの計算方法 ②曲げモーメント図BMDの作成方法
与えられた課題についてレポートを作成し提出してください。授業時間内に終わらなかった場合は、次回の授業の始めに提出してください。
(6)曲げ応力とは ①曲げによって生ずるひずみ ②曲げ応力とは (7)断面係数とその計算式 ①断面係数とは ②各種断面の断面係数の計算方法 (8)曲げ応力の計算式 ①各種断面のはりの曲げモーメントの計算方法
授業内容を復習し、各種断面の断面係数の計算方法と各種断面のはりの曲げモーメントの計算方法を整理してください。
(4)はりのせん断力と曲げモーメントとは ①はりのせん断力の計算方法 ②せん断力図SFDの作成方法 ③曲げモーメントとは
与えられた課題についてレポートを作成し提出してください。授業時間内に終わらなかった場合は、次回の授業の始めに提出してください。
訓練の内容 訓練課題 予習・復習
1.ガイダンス (1)シラバスの提示と説明2.はり (1)はりとは ①力のモーメント・力のつりあいの復習 ②はりとは (2)各種はりとその支持条件 ①はりの種類 ②回転支点、移動支点、固定支点等の支持条件 (3)力のつりあいと支点反力 ①はりのつり合い条件 ②力のつりあいと力のモーメントのつりあい ③支点反力の計算方法

科名:
必須・選択 開講時期 単位 時間/週
内線電話番号
No
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩
試験 小テスト レポート 制作物 成果発表 その他 合計
45 45 10 100
35 30
10
10 5
10
教室・実習場
取り組む姿勢・意欲
寺島 周平
生産技術科
評価の割合(例)
教科書および参考書(例)
幾何公差について知っている。
電子メールアドレス
教育訓練課程
3
予備知識・技能技術 製図の基礎は中学の技術で学んでいますが、さらに平面図形や立体図形の知識が必要になります。図形が苦手な学生は、中学・高校で習った図形を復習しておくとよいでしょう。
検図の必要性、方法について知っている。
断面図、他の図示法の描き方について知っている。
工業的に物を作ろうとするとき、その意図するところを伝達するために、言葉の代わりに用いられるのが図面です。この図面を作ることを製図と言います。その知識は機械加工、機械設計、CAD等を受講するうえで必要不可欠な知識です。ものつくりの世界では図面で情報を伝えるので、図面を読んだり、書いたりすることが大変重要になり、これができないと会話ができないことと同じです。製図には約束事がたくさんあり、一度に覚えることは大変ですが、わからないことを積み残さないよう、しっかりと理解し、覚えていってください。講義とともに演習も交え、実際に製図をしながら規格等を身に付けていきます。
協調性
評価方法 指標・評価割合
授業科目についての助言
教科書:最新機械製図
授業科目の発展性
論理的な思考力、推論能力
5304
図面の役割について知っている。
表面性状について知っている。
寸法記入の方法について知っている。
寸法公差とはめあいについて知っている。
製図用機器、各種製図用具の使い方について知っている。
線の種類と用途について知っている。
投影法、投影図の描き方について知っている。 生産現場における図形の表現方法と図面に関する規格等を正しく理解し、図面の読図及び基礎的な作図方法を学びます。
授業科目受講に向けた助言
評価割合
授業内容の理解度
コミュニケーション能力
技能・技術の習得度
プレゼンテーション能力
担当教員
基礎製図
基礎製図
教科の科目
seizu
機械製造分野における加工・組立業務、機械製造分野における加工オペレータ、機械製造分野における品質管理・生産管理業務、機械製造分野における設計業務、機械製造分野におけるラインオペレータ、機械製造分野における保全業務
授業科目の目標
授業科目の訓練目標
授業科目のポイント
6必須 Ⅱ期
訓練科目の区分
専門課程
系基礎学科
授業科目名
教科の区分
CAD実習Ⅰ 基礎製図 機械製図
機械加工実習
CAD実習Ⅰ 基礎製図 機械製図
機械加工実習

回数 運営方法
1週 講義、演習
2週 講義、演習
3週 講義、演習
4週 講義、演習
5週 講義、演習
6週 講義、演習
7週 講義、演習
8週 講義、演習
9週講義、演習、
試験
総合的な演習となります。投影法、寸法記入法等を復習しておいてください。
1.ガイダンス (1)シラバスの提示と説明2.図面の役割 (2)図形の表現方法、役割、JIS規格、図面の種類3.製図の準備 (1)製図用機器、各種製図用具の使用法 (2)平面用器画法
演習で行った授業内容を復習し、寸法記入法について整理してください。
線の種類と用途、投影法について整理してください。 演習での間違いを正し、整理してください。
(10)幾何公差5.各種投影図と活用法 (1)三角法の活用と作図法 ①三面図の作成
(8)面の肌の表現方法 (9)寸法公差とはめあい
(6)図形の省略及び特定部分の表示 (7)寸法記入の方法
6.図面の検図と変更 (1)図面の検図の必要性、検図の方法 (2)図面の変更法、図面の管理法7.試験 筆記試験
ここまでの理解度を確認し、苦手な所を復習しておいてください。
総合的な演習となります。投影法、寸法記入法等を復習しておいてください。
総合的な演習となります。投影法、寸法記入法等を復習しておいてください。
(2)部品のスケッチ ①部品図の作図 (3)展開図の活用と作図法
②寸法、加工情報の記入 ③断面図、省略等を含む課題
訓練課題 予習・復習
図面の役割と重要性、平面用器画法とコンパスの使い方を覚えてください。
訓練の内容
(4)投影図の描き方 ①補助投影 ②回転図示投影 (5)断面図の描き方 ①全断面 ②部分断面
4.製作図の基礎 (1)図面の大きさ、線の種類と用途 (2)投影法 (3)投影法の演習

科名:
必須・選択 開講時期 単位 時間/週
内線電話番号
No
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩
試験 小テスト レポート 制作物 成果発表 その他 合計
70 20 10 100
50 20
20
10
評価割合
授業内容の理解度
技能・技術の習得度
コミュニケーション能力
プレゼンテーション能力
論理的な思考力、推論能力
取り組む姿勢・意欲
協調性
評価の割合(例)
授業科目受講に向けた助言
予備知識・技能技術 「基礎製図」で学んだ機械製図のJIS規格を理解しておいてください。また、立体の第3角法による2次元図面化を行うことができるようにしておいてください。
授業科目についての助言
機械図面とは設計者のアイディアを第三者に正確に伝えるためのコミュニケーション手段で、ものの形状や寸法だけでなく、寸法公差や幾何公差など多くの情報を伝達できます。機械製図を学ぶ上で、投影図を正確に書けること、必要な情報を書き込めることが重要です。また、規格表の見方やその意味するところを理解することも大切です。わからないことは積極的に質問してください。製図の課題は授業時間内で終了させるよう、効率的な作業に心がけ、必ず期限内に提出してください。
教科書および参考書(例) 教科書:最新機械製図(基礎製図の教科書)
授業科目の発展性
評価方法 指標・評価割合
組立図から部品図の抽出ができる。
授業科目に対応する業界・仕事・技術
製造分野における加工・組立業務、オペレータ、品質・生産管理業務製造分野における設計業務、保全業務
授業科目の訓練目標
授業科目の目標 授業科目のポイント
製図通則や機械製図に関する規格に基づき、ねじや歯車等の機械要素について、作図方法を学びます。
製図通則と機械製図の規格について知っている。
機械製図の規格に基づく図面の描き方について知っている。
規格部品について知っている。
部品図と組立図の役割について知っている。
ボルト、ナットの描き方について知っている。
歯車について知っている。
軸と軸受について知っている。
軸とキーの結合について知っている。
部品図から組立図の作成ができる。
担当教員 電子メールアドレス 教室・実習場
神田 健一 5304・5204
必須 Ⅲ・Ⅳ期 3 3教科の区分 系基礎学科
教科の科目 機械設計及び製図
生産技術科
訓練科目の区分 授業科目名
教育訓練課程 専門課程
機械製図
機械設計製図 総合制作実習
基礎製図
機械製図

回数 運営方法
1~2 講義、質疑
3~5講義、実習
質疑
6~8講義、実習
質疑
9~10 実習、質疑
11~12
講義、実習質疑
13~14
講義、実習質疑
15~16
実習、質疑
17講義、実習
質疑
18 試験
6.ばね製図 (1)ばねについて ①ばねのはたらき ②ばねの種類 (2)ばねの図示法 ①コイルばねの一部省略図 ②コイルばねの簡略図 (3)引張りばね (4)ねじりコイルばね
授業内容を復習するとともに、与えられた課題は期限内に提出してください。
9.試験 筆記試験
ここまでの理解度を確認し、苦手な所を復習してください。
7.軸と軸受製図 (1)軸と軸受について (2)軸とキーの描き方 ①軸製図の注意点 ②センタ穴と簡略図示法 ③キーの図面への取扱い (3)軸継手の描き方 ①固定軸継手 ②たわみ軸継手 (4)転がり軸受の描き方 ①軸受の種類 ②転がり軸受の呼び番号 ③基本簡略図示法 ④個別簡略図示法
授業内容を復習するとともに、与えられた課題は期限内に提出してください。
(5)製図実習 授業内容を復習するとともに、与えられた課題は期限内に提出してください。
8.部品図、組立図作成 (1)組立図からの部品図作成法
授業内容を復習するとともに、与えられた課題は期限内に提出してください。
5.歯車製図 (1)歯車について ①歯車の種類 ②歯車の歯形曲線と各部の名称 ③歯形の大きさ (2)歯車の描き方 ①平歯車 ②はすば歯車・やまば歯車 ③かさ歯車 ④ねじ歯車 ⑤ハイポイド歯車 ⑥ウォーム歯車 ⑦歯車の要目表 ⑧かみ合う歯車の図示法
授業内容を復習するとともに、与えられた課題は期限内に提出してください。
(3)製図実習 授業内容を復習するとともに、与えられた課題は期限内に提出してください。
4.ねじ製図 (1)ねじについて ①ねじの原理 ②ねじの各部の名称と用語 ③ねじの種類と用途 (2)ねじの図示法 ①ねじの表わし方 ②ねじの描き方 ③ねじの寸法記入法 ④小径ねじの簡略図示法 ⑤多数の大きさのねじの表示法 (3)ボルト、ナットの描き方 ①ねじ部品の簡略図示法 ②略図によるボルト頭部の描き方 ③小ねじ、止めねじ、ばね座金
授業内容を復習するとともに、与えられた課題は期限内に提出してください。
訓練の内容 訓練課題 予習・復習
1.ガイダンス (1)シラバスの提示と説明 (2)安全作業について2.機械図面に関するJIS規格 (1)製図通則と機械製図の規格 (2)機械要素と関連する機械製図の規格 (3)機械製図の規格に基づく図面の描き方 (4)材料記号と表示法3.部品図と組立図 (1)部品図と組立図の役割 (2)部品図に必要な各種事項 ①部品番号 ②材料名 ③個数等

科名:
必須・選択 開講時期 単位 時間/週
内線電話番号
No
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩
試験 小テスト レポート 制作物 成果発表 その他 合計
50 50 100
20 20
20 20
10 10
評価の割合(例)
評価方法 指標・評価割合
評価割合
授業科目に対応する業界・仕事・技術
授業科目のポイント
品質とはなにか?品質管理とはどういうことなのかを理解する。
授業科目の目標
わが国の品質管理はよいモノ(顧客の求めるモノ)を生産し、販売するためには不可欠の管理技術である。過去から、なぜ、どのようにやってきたのか、今後どうすべきなのかを理解して考えて下さい。
QC7つ道具(パレート図)について理解する。
QC検定について。.
QC7つ道具(チェックシート)について理解する。
ISOの必要性と内容を理解する。
重点主義について考え方を理解する。
QC7つ道具(グラフ)について理解する。
QC7つ道具(データ)について理解する。
QC7つ道具(特性要因図)について理解する。
生産技術科
訓練科目の区分 授業科目名
品質管理
教育訓練課程 専門課程
品質管理
取り組む姿勢・意欲
協調性
試験、小テストの合計に出席率を乗じ
て、最終得点とします。論理的な思考力、推論能力
授業内容の理解度
技能・技術の習得度
コミュニケーション能力
プレゼンテーション能力
教科書:QC七つ道具
授業科目の発展性
授業科目受講に向けた助言
予備知識・技能技術 教科書の内容を予習すること+学習した項目への関連知識をフォローしておくこと。
授業科目についての助言
本講義は、生産過程における品質管理の基礎的事項を学び、職場で仕事をするにあたって、最低限知っておくべき考え方や用語を学ぶものです。この講義で身に付けたことは自分自身のレベルアップになるので是非理解して下さい。
教科書および参考書(例)
5Sとはなにか、どのように進めるのか理解する。
2教科の区分 系基礎学科
教科の科目
担当教員 電子メールアドレス 教室・実習場
藤井 裕 5401教室
必須 Ⅲ・Ⅳ期 2
製造現場における品質管理業務と生産管理
授業科目の訓練目標
実企業での品質管理 品質管理 品質管理Ⅱ

回数 運営方法
1週 講義、質疑
2週講義、演習、
質疑
3週 講義、質疑
4週講義、演習、
質疑
5週 講義、質疑
6週 講義、質疑
7週講義、演習
質疑
8週講義、演習
質疑
9週講義、質疑、
試験
10週講義、質疑、
試験
11週講義、質疑、
試験
12週講義、質疑、
試験
13週講義、質疑、
試験
14週講義、質疑、
試験
15週講義、質疑、
試験
16週講義、質疑、
試験
16.特性要因図の実例 (1)特性要因図の考え方と作成実習
特性要因図の作成方法について復習してください。
14.なぜなぜ分析 (1)なぜなぜ分析とは (2)なぜなぜ分析のコツ
なぜなぜ分析の手法と着眼点について理解しておいて下さい。
11.重点思考とパレート図 (1)重点思考とは (2)パレート図の作り方と目的
重点思考とパレート図の考え方について復習してください。
12.中間テスト (1)これまでで重要と説明した項目について理解度テストを行う
これまで習ったことをしっかりと復習しておいてください。
13.パレート図の実例 (1)パレート図の考え方と問題解決
QC七つ道具としてのパレート図の使い方について復習してください。
15.QC七つ道具(特性要因図) (1)特性要因図の作り方
QC七つ道具としての特性要因図の使い方について復習してください。
8.データとは (1)数値データと言語データ (2)データの取り方
データの意味について復習してください。
9.QC七つ道具(チェックシート) (1)チェックシートの分類、目的、作り方
QC七つ道具としてのチェックシートついて復習してください。
10.層別とは (1)層別の意味と目的 (2)層別の実施例
層別の目的について復習してください。
7.QC七つ道具(グラフとは) (1)データ分析のためのグラフの種類と使い方
QC七つ道具としてのグラフの使い方について学習してください。
4.ISOについて (1)品質改善活動におけるISOの意義
ISOの目的及び品質トラブルについて復習してください。
5.5Sとは (1)5Sの各ステップと実例 5Sの目的について復習してください。
6.品質ミス、ヒューマンエラーをゼロにするため (1)ユーザーに約束した品質を届けるためには (2)ヒューマンエラー防止の実例
ヒューマンエラーの撲滅について学習してください。
3.PDCAについて (1)各ステップの理解と実践での応用課題
PDCAについては特によく復習してください。
訓練の内容 訓練課題 予習・復習
1.ガイダンス (1)シラバスの提示と説明
「QC七つ道具」の教科書のまえがきをよく読んでおいてください。
2.安全第一と品質第二 (1)緑十字の考え方と安全旗 品質と安全について復習してください。

科名:
必須・選択 開講時期 単位 時間/週
内線電話番号
No
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩
試験 小テスト レポート 制作物 成果発表 その他 合計
80 20 100
80 20
評価割合
授業内容の理解度
技能・技術の習得度
コミュニケーション能力
プレゼンテーション能力
論理的な思考力、推論能力
取り組む姿勢・意欲
主体性・協調性
評価の割合(例)
授業科目受講に向けた助言
予備知識・技能技術事故、災害、環境破壊問題は世界中で毎日のように、起こっている。テレビ、新聞、雑誌等のマスコミでそれらのニュースを見るとき、なぜそのような事故,災害が起こったのか、なぜそのような環境破壊問題が発生したのか、という原因、理由を常に考える癖、習慣を身につける事が大切です。
授業科目についての助言
安全について理解を深めるには、色々な経験と広範囲な知識が必要です。安全は空気と同じでいつでも手に入ると思うのは間違いです。安全は求めなければ手に入りません。そのためには、安全について、よく勉強する事です。
教科書および参考書(例)
教科書:「安全基礎工学入門」この教科書はまさに、本大学校学生の為に作られた安全教育の入門書で、大変判り易く纏められている。教科書を最後まで読み切るつもりで取り組む事が、安全知識を向上させるポイントです。
授業科目の発展性
先ずは、身近な所で、自分が毎日安全に日常生活をおくるにはどうあれば良いか、あるいは、自分の家族が安全に生活するにはどうすれば良いか、自分の行動や家族の行動を安全面から点検してみて下さい。点検の結果、不安全な行動が見つかれば、安全な行動に修正する事が必要でしょう。日本人は安全については大変鈍感です。将来、製造現場を持っている会社に就職して初めて、自分の身を守るのは自分の安全に対する考え方と、自分の安全行動だと認識します。
評価方法 指標・評価割合
労働安全衛生法、ISO14000の概要を学ぶ.安全衛生ビデオを鑑賞し、作業現場における安全の大切さを認識する。
授業科目に対応する業界・仕事・技術
製造業、建設業,エンジニアリング業等全ての業界の設計、製造,建設業務
授業科目の訓練目標
授業科目の目標 授業科目のポイント
安全衛生に関する基本原理、労働災害に対する基本対策及び労働衛生に関する基礎を学習し、安全衛生管理に関して生産現場のリーダーとして基礎知識を習得する。
安全の状態とはどのような状態の事を言うのかを理解する。
自然災害と人工災害の違いと安全確認型システムとはどんなシステムか理解する。
労働災害の現状を把握する。
種々の地球環境問題と代表的な地域型環境問題を理解する。
物理の原理、法則を良く知った上で、安全工学に関する力、火(熱)、光、音、電気、放射線の基本事項について学び、それらが人体にどのように影響するかを学ぶ。
私達の生活は多くの化学物質に支えられており、住宅建材,電気電子機器材,薬品,繊維,化粧品,洗剤等に膨大な数の化学物質が使用されている。これら化学物質に関する正しい知識を学び,性質と扱い方を良く理解
安全作業の基本の3S、服装基準、安全防具を知る。
産業用ロボットの構造と危険性を知り、作業の安全を学ぶ。工作機械、プレス機械、溶接機等の種類と構造を知り、作業の安全を学ぶ。電気について、感電防止、電磁ノイズ、静電気、はんだ付け等を知り、作業の安全を学ぶ。【アーク溶接等の業務に係る特別教育】
建築、土木について、高所作業における墜落、飛来、落下物等の災害と防止対策の基本を知り、作業の安全を学ぶ。建設、移動式機械の種類と構造を知り、作業の安全を学ぶ。
担当教員 電子メールアドレス 教室・実習場
5401教室青木 節
必須 Ⅰ、Ⅲ期 2 2教科の区分 基礎学科
教科の科目 安全衛生工学
生産技術科・住居環境科
訓練科目の区分 授業科目名
教育訓練課程 専門課程
安全衛生工学

回数 訓練の運営方法
1週 講義
2週 講義
3週 講義
4週 講義
5週 講義
6週 講義
7週 講義
8週 講義
9週 講義
10週 講義
11週 講義
12週 講義
13週 講義
14週 講義
15週 講義
16週 講義
17週 講義
18週 講義
建築、土木の安全作業高所作業における安全・高所作業と労働災害 ・墜落災害防止対策の基本 ・足場 ・はしご、脚立 ・墜落防止設備
高所作業における安全について学ぶ。
期末試験 ノートによく纏め、試験に臨む。
建設、移動式機械の安全・クレーンの構造と安全作業 ・フォークリフトの構造と安全作業
建設土木作業の移動式機械の安全について学ぶ。
安全衛生作業まとめ
安全衛生ビデオ鑑賞/レポート作成 安全衛生ビデオ鑑賞と感想文作成
機械の安全作業産業用ロボット・産業用ロボットの構造と危険性 ・災害のパターン・
産業用ロボットについてよく知り、安全対策を学ぶ。工作機械の種類構造を知り、安全作業を学ぶ。
プレス機械 ・プレス機械の構造 ・プレス機械の安全システム ・プレス機械作業の安全
プレス機械の構造を知り、安全作業を学ぶ。溶接法の種類を知り、アーク溶接の安全作業を学ぶ。
電気の安全作業/感電の防止・漏電 ・漏電による感電 ・感電の危険性 ・感電の防止策
感電について知り、感電防止を学ぶ。電磁波障害、人体に対する影響について知り、電磁波対策を学ぶ。静電気、はんだ付け作業の安全を学ぶ。
安全衛生ビデオ鑑賞/レポート作成 安全衛生ビデオ鑑賞と感想文作成
中間試験 ノートによく纏め、試験に臨む。
安全作業の基本・3S ・服装労働安全衛生法、ISO14000
安全作業の3S,服装を知る事。労働安全衛生法、ISO14000の概要を知る。
光と安全 ・光の領域 ・光の性質 ・レーザ光の特徴 ・レーザの種類と性質 ・レーザ光の人体に及ぼす影響 ・問題音と安全 ・音の性質 ・人体に及ぼす影響 ・問題
レーザ、音、電気に関する物理的特性と人体に及ぼす影響を理解し、安全を学ぶ為の基礎知識とし役に立てる。節末の練習問題をやってみて更に理解を深める。
放射線と安全・放射線の種類と性質 ・放射線の人体に及ぼす影響 ・放射線災害の防止策 ・練習問題
放射線の特徴と人体に及ぼす影響、化学の基本事項を理解し、安全を学ぶ為の基礎知識とし役に立てる。節末の練習問題をやってみて更に理解を深める。
気体と安全・ガスの種類と性質・高圧ガスについて ・ガス保安用の安全設備 ・問題液体、固体と安全
ガスの種類と特性を学び、保安用安全設備を理解する事。火災が発生する化学物質、人体に有害な化学物質、環境に有害な化学物質について学ぶ。節末の練習問題をやり更に理解を深める。
安全に関する基本的事項を理解する。
地球環境問題・オゾン層の破壊 ・地球の温暖化 ・酸性雨等
地球環境問題に関する事を理解する。地域型環境問題を知る。資源のリサイクルを知る。
力と安全・力の性質・重心・運動・回転運動・問題火と安全・熱の性質・燃焼・
力、火について物理的特性を理解し、安全を学ぶための基礎知識とし役に立てる。節末の練習問題をやってみて更に理解を深める。
労働災害の現状・全産業における死傷者の推移 ・業種別死傷災害発生状況
労働災害の現状を知ること。安全工学の特徴と目的を理解する。安全対策の意味、各社の取り組みを勉強する。
訓練の内容 訓練課題 予習・復習
安全の基礎/安全に対する基本的な考え方・安全とは ・自然災害と人工災害 ・安全技術の原則 ・安全確認型システム