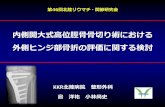装具療法の効果を 見える化するためのツールとし...
14
Transcript of 装具療法の効果を 見える化するためのツールとし...

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
装具療法の効果を 見える化するためのツールとしてGJシステムをご紹介いたします

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
まず、この動画をごらんください はじめにこちらは底屈制動の装具 続いては底背屈固定の装具です 動画だけでの所見では漠然とした足間接の動きがわかるだけで、この時の体の中の動きまでの評価が難しいです それらを見える化する事ができるのがGJです(クリック) GJにより計測することで下の図のようなデータを見ることができます ここで注目していただきたいのは青・紫で表示されている前脛骨筋と下腿三等筋の筋電です 底屈制動の装具では踵接地時に大きく前脛骨筋が働き下腿三頭筋が休んでおり、健常者の歩行と同じように筋電が出ていることがわかります 逆に底背屈固定の装具では踵接地時に下腿三頭筋が働き前脛骨筋が休んでいる状態になっているのがグラフを見ることで分かります このように体の中の動きをリハビリ室で見ることができるのがGJです

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
製品概要についてご説明いたします 継手部分に計測用のアタッチメントとUSBの無線送信機を取り付ることで、装具にかかる力と角度を計測することができます 対応装具はGSD・金属支柱付GS・Wクレンザック215に対応しております�

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
先ほどご紹介したGIにももちろん取り付けすることができます

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
読み取った足関節の情報を無線で WiFiコンバータに送りWiFiコンバータを経由して、 iPad上で簡単に計測したり、計測データを確認できます 利点としては三次元動作解析装置や床反力計のような大掛かりな設備が必要ないので、 電源があればどこでも使用することができ即時的に確認することができる点です

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
続いては健常者の歩行についてご存知の方も多いでしょうが少し説明させていただきます 健常者の歩行は、倒立振り子運動により、上下への重心移動によって生じる位置エネルギーを 運動エネルギーに効率よく変換することで、前方への移動を可能にしています。 そして、この効率の良い運動を可能にしているのが、 ヒールロッカー、アンクルロッカー、フォアフットロッカーの3つのロッカー機能です。 ヒールロッカーは、回転中心が床と踵の接点にある「揺りてこ」です。 立脚初期の底屈に対し、前脛骨筋が遠心性収縮することで、 落下する身体重量によって生じる勢いを受け止め、 前方への勢いに変換する重要な役割を担っています そして、アンクルロッカーは、足関節を回転中心とする「揺りてこ」です。 引き続き起こっている脚の前方への動きを下腿三頭筋により制御します。 フォアフットロッカーは、中足指節間関節を回転中心とする「揺りてこ」です。 下腿三頭筋が最も働く時であり、 遊脚期に必要な振り出しの初速を形成する底屈トルク、 SSC(ストレッチショートニングサイクル)のメカニズムに関与しています。 このように、選択された筋が3つのロッカー機能を制御し、 それぞれの回転中心を支点にして、身体重量を前方へと移動させます。 これが健常者の歩行です。

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
それらを踏まえた上でGJでは、倒立振り子運動をこのように見ることができます 上の緑が底屈制動モーメント・白が足関節角度です。 GJでは筋電計を用いた計測評価もできます。 赤が前脛骨筋・緑が腓腹筋です 立脚初期の底屈運動しているときに前脛骨筋が働いてブレーキをかけ 立脚中期の背屈運動の時には下腿三頭筋が働きます。そして、蹴り出す手前の底屈運動が始まるときには下腿三頭筋の活動がなくなり 立脚後期に前脛骨筋が働くということが、 このiPad上で簡単に計測して確認することができます。 装具を装着しなくても、筋電だけでも計測ができます。 最大6チャンネルまで計測することができます

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
ゲイトジャッジの計測したデータでは、今ご説明した3つのロッカー機能 を基準に評価します。 足関節運動は、 ヒールロッカーに底屈運動、 アンクルロッカーに背屈運動 フアフットロッカーに底屈運動 となります。 この時の底屈運動時にロードセルがカムを押し上げる力を 底屈制動モーメントとしてデータで確認できます。

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
これは、GJの計測したデータの画面 データが何をしめしているかを説明します。 この赤の矢印で示したが一歩行周期です。 上の緑が底屈制動モーメント 健常者では、底屈制動モーメントは 一歩行周期に2つの山ができます。一つ目の山が踵接地の時にできる力の山でFPと呼んでいます。 2つ目の山は、蹴りだしたときにできる山でSPと呼んでいます。 白が足関節角度です 基線より下が底屈で上が背屈をしめします 筋活動は、 緑が前脛骨筋 赤が腓腹筋です これらと合わせて映像で歩容状態を確認することができます

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
そして計測したデータから周期分析をIPAD上で行うことができます 選択した範囲の平均の値を見ることができます

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
また、動画だけではなく20%おきの画像も自動的に抽出することができます

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
そして、IPAD上で二つのデータを同時に出し、比較評価することもできます

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
計測したデータは、このようにPDFに出力して保存が可能です。 これにより全体のデータ1歩行周期の底屈制動モーメントと足関節角度を示すことができます。 また各相ごとの写真が自動的に貼り付けされます

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
ゲイトジャッジシステムによる計測で、関節角度、底屈モーメント、筋電図、動画などを情報収集することで、 ・装具の機能が正しく使用できているか、客観的に評価できる。 ・歩行訓練の前後の効果の比較、また、継続的な訓練効果を記録し確認できる。 ・ボットクス治療後の関節角度の比較や、筋収縮の比較、また、その後の経過観察と、それに伴ったトレーニング内容の効果を検証できる。 ・データの蓄積によりエビデンスの構築に有用である。 ・治療から装具処方⇒リハビリまでの装具療法のエビデンスの構築に寄与する。 いままでは治療の効果が目で見て分かりにくかったのですが、本計測器により変化を客観的に捉えることができます。





![KEY CHART FOR MODEL Circulatory System with ......33. Tibia 33.脛骨 34. Fibula 34.腓骨 2 24. Cervical vertebrae[C1-C7] 25. Thoracic vertebrae[T1-T12] 26. Lumbar vertebrae[L1-L5]](https://static.fdocument.pub/doc/165x107/6094bfd05d03d21fc74cac1e/key-chart-for-model-circulatory-system-with-33-tibia-33ee-34-fibula.jpg)