気候と社会の共振現象 - 名古屋大学ercscd.env.nagoya-u.ac.jp/envgcoe/nakatsuka_2.pdfO...
Transcript of 気候と社会の共振現象 - 名古屋大学ercscd.env.nagoya-u.ac.jp/envgcoe/nakatsuka_2.pdfO...
-
気候と社会の共振現象問題発見への新しい切り口-問題発見への新しい切り口-
1. 環境問題の本質的構造と「予測・発見型研究」の必要性
2 気候と社会の関わりから探る-問題発生の法則性?
中塚 武
2.気候と社会の関わりから探る 問題発生の法則性?
中塚 武
環境学研究科・地球環境科学専攻・環境学研究科・地球環境科学専攻・地球環境変動論講座
-
診断と治療を融合した臨床環境学は、何故、必要か?
これまでの環境問題の研究とは?
治療診断 治療型研究診断型研究ex. CO2による地球温暖化
ズ 解ex. CO2の吸収技術、遺 組 換 植物メカニズムの解明、CO2
の自然吸収源評価…
遺伝子組み換え植物の開発、環境税導入
…
「診断」と「治療」は関係しているが、一方通行の関係であり、別 究これまでは、それぞれ、別々に研究が行われてきた。果して
この関係は妥当なのか? 「診断に根ざした治療」と同時に、「治療を前提にした診断」も 必要なのではないか?「治療を前提にした診断」も、必要なのではないか?
-
「環境問題を治療する」とは、どういうことか?-人類は “環境問題”を どのように治療してきたか?-人類は、 環境問題 を、どのように治療してきたか?-
与えられた問題 解決方法 新たに発生した問題
狩猟採集社会における慢性的食料不足
農業の発明 人口爆発・土地不足
耕作可能な土地の不足 灌漑農法の発明
森林の伐採と
塩害・水資源枯渇
森林の伐採と木材燃料の不足
化石燃料の利用
洪水の頻発と産業ダム 河 堰
資源枯渇・地球温暖化
水圏生態系 変質洪水の頻発と産業・生活用水の不足
ダム・河口堰
感染症による寿命 抗生物質の発明
水圏生態系の変質
人口急増 / 薬剤耐性菌の慢性的な短さ
抗生物質の発明 人口急増 / 薬剤耐性菌
・人類史上、環境問題の治療の先にあったのは、常に、
・・
人類史上、環境問題の治療の先にあったのは、常に、新たな環境問題の発生であった!
-
環境問題の「負の連鎖」を断ち切るためには?-「問題予測・発見型」研究の重要性-問題予測 発見型」研究の重要性
既にある問題 既にある問題既にある問題
の診断型研究既にある問題
の治療型研究
この部分の研究は、
診断型と治療型
治療策の導入により、これから起こる問題、或いは密かに起きている問題を
予測 発見
地球温暖化研究は、実は、この問
の両研究者の協力
抜きには
予測・発見する研究題予測・発見型研究の典型例!
成り立たない!
“治療策導入後の当面の影響”だけを検討する「従来の環境アセスメント」ではなく、時空間スケールを広げ、あらゆる分野 の影響を予測して 起こりうる問題をあらゆる分野への影響を予測して、起こりうる問題を、
できるだけたくさん発見することが必要。
-
これから起こるかもしれない(既に密かに起こっているかもしれない)新たな環境問題の予測や発見は、かもしれない)新たな環境問題の予測や発見は、
如何にすれば可能か?‐常識的には、非常に難しいはず…‐常識的には、非常に難しいはず…
1.自然・社会に対する認識のSecurity Holeを埋める!環境問題の周辺にあって、我々の認識が及んでいない部分を埋めていく!=ありとあらゆる学問を、とにかく進歩させる <個別的環境学個別的環境学>
2.診断型研究と治療型研究が緊密に連携する!
「診断に基づく治療」だけでなく、「治療に根ざした診断(副作用の予測)」を!「診断に基づく治療」だけでなく、「治療に根ざした診断(副作用の予測)」を!=そのために、両者が問題を共有して、協力する <臨床環境学臨床環境学>
3.問題発生に至る因果関係を理解し、未来を予想する!未来に起きる環境問題に向けて、現在がどの段階にあるのかを把握する!=歴史に学ぶと共に、その知見を未来予測に生かす<歴史環境学歴史環境学>
-
「環境問題」が発現するに至る因果関係とは?-環境問題のもつ「進化論」的構造の中にある-
「ミクロ(短期・局所)スケールでの適応的な技術や制度」が、しばしば、「マクロ(長期・広域)スケールでの不合理な結果」を招く、ということ!
耕作可能な土地の不足 灌漑農法の発明 農業生産力の増大
人口の増大灌漑の拡大・強化 「短期的適応」による増殖
「長期的不合理」
塩害・水資源枯渇 食料需 増大
による増殖による崩壊
過ぎたるは過ぎたるは及ばざるが及ばざるが塩害・水資源枯渇 食料需要の増大
課題-1 :現在 目の前で導入されつつある技術や制度が こうした一連の因果関係を
及ばざるが及ばざるが如し!如し!
課題-1 :現在、目の前で導入されつつある技術や制度が、こうした 連の因果関係をもたらしうるのか、について論理的な想像力を膨らませる!
課題-2 :マクロなスケールで不合理な結果が生じそうになったとき、どのように社会は、課題 2 :マク なスケ ルで不合理な結果が生じそうになったとき、どのように社会は、それを予知し、対応できたのか、について歴史的に検証する!
気候変動からの視点!
-
樹木年輪を用いた古気候復元とその潜在的な能力
●樹木年輪とは?●樹木年輪とは?
春にできる材(早材)と秋にできる材(晩材)の性質(色や堅さなど)が違うことにより生じる 材木の縞模様 1年に 早材と晩材ど)が違うことにより生じる、材木の縞模様。1年に、早材と晩材の1セットが繰り返すことから、「年輪」と言われる。
●「年輪幅」による古気候復元 : 従来の方法●「年輪幅」による古気候復元 : 従来の方法気温や降水量など、“その場所でその木の成長量を支配している要因”が変動すると、樹木の肥大成長量=年輪幅が変わる、という単純なメカニズムを利用するという単純なメカニズムを利用する。
年輪幅の変化=気候変動の記録 !?★非常 古くから知られ た伝統的な方法
・数10、数100、数1000年の連続データを提供できる!
★非常に古くから知られていた伝統的な方法。
数10、数100、数1000年の連続デ タを提供できる!
・樹木は、どこにでも生えている=空間分解能も高い!
・時間分解能が極めて細かく、かつ正確!時間分解能が極めて細かく、かつ正確!
・倒壊・埋没、伐採・加工後も、記録としての能力を失わない。
-
年輪幅(樹木成長量)解析の問題点
年輪幅は、「気候以外の要因」の影響を、強く受けてしまう。1.年輪幅は木の成長に伴って変化する(一般に、樹齢と共に狭くなる)
2.隣接する木との関係(日本のように樹木が密生する所で、特に深刻)
年輪幅だけでは、長期的な気候変動の復元が難しい!
数10年後…数 年後隣の木が枯死…
隣の大きな木のせいで、日光が当らず、年輪幅が狭い
日光が十分に当るようになり、年輪幅は、突然、大きくなる
★“気候の影響だけを受けて変化するもの”として、セルロースの酸素同位体比に注目!
-
年輪セルロース酸素同位体比の優位性(高い個体間相関性≒気候による決定性の強さ)(高い個体間相関性 気候による決定性の強さ)
カムチャッカ中央低地における3本のカラマツ個体から取った「年輪幅」の時系列変化
同じ3本のカラマツ個体の「年輪セルロース酸素同位体比」の時系列変化を測定すると
27
28
KL11比(1
8 O)
5
6
KL11 KL6
…
25
26KL11 C637
素同
位体
比
4
m/y
r)
KL6
23
24
ース
の酸
素
2
3
年輪
幅(m
m
21
22
KL6年
輪セ
ルロ
ー
1
2年
201800 1840 1880 1920 1960 2000
Year(AD)
年
01800 1840 1880 1920 1960 2000
Year(AD)
C637
長周期の変動パターンは、全く一致しない!=個体生態学的要因で、変動!
3個体間で変動パターンは、ピタリと一致!=外部環境(気候)因子で、変動!
-
木曽ヒノキの年輪セルロースの酸素同位体比と月降水量・平均相対湿度の相関関係
0.6
飯田の気象データ(1898-2005)との相関
22 90
6月の相対湿度(破線)と年輪18Oの変化
0 2
0.4
22
23 85
90
SM
OW
)
6月
0
0.2
24
25
75
80
位体
比(V の相
対湿
-0.4
-0.225
26 65
70
輪酸
素同
位
湿度
(%
)
飯田 松本相対湿度 降水量
-0.61 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Month
27 601880 1900 1920 1940 1960 1980 2000
Year(AD)年
輪
松本相対湿度 降水量
Month
夏季(特に6月)の相対湿度及び
前年データ
年輪セルロースの酸素同位体比は 夏季の水循環変動の夏季(特に6月)の相対湿度及び
降水量と、強い負の相関がある。比は、夏季の水循環変動の
指標になることが分った
-
北海道北部のミズナラ 1773~2002(2個体個別測定)
年輪18O値○と気象要素(月別相対湿度)★の相関0 8 0 6
0.8
山形RH vs 秋田 18O(スギ)
⑪
(2個体個別測定)
★0
0.2
0.4
0.6
0.8
境港RH vs 安木 18O(スギ) 1942-1991
0 2
0
0.2
0.4
0.61937-1986
0 2
0.4
0.6
0.8
旭川RH vs 天塩 18O(ミズナラ)1953-2002
⑯
-0.6
-0.4
-0.2
0
-0.8
-0.6
-0.4
-0.2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12-0.4
-0.2
0
0.2
秋田県中部の杉1818~1986(2個体個別測定)
島根県東部の杉16341991(1個体 倒木)
⑯
茨城県南部の杉1750~
★
-0.81 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Month
Month-0.8
-0.6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Month
少なくとも、最近の50年間に関しては、18Oは、どこでも
(2個体個別測定)~1991(1個体-倒木)⑤
長野県南部のヒノキ
⑫⑭
茨城県南部の杉17501996(1個体-倒木)
鹿児島県・屋久島の杉1700~2002
★ ★ ★
0.6
0.8
銚子RH vs 鹿島 18O(スギ)1947-1996
夏季の相対湿度に対応-理論的予測の通り-長野県南部 キ
1730~2005(2個体-個別測定)
⑬
(多数個体混合測定)
★0.6
0.8
枕崎RH vs 屋久島 18O(スギ)1953-2002 0.4
0.6
0.8
飯田RH vs 上松 18O(ヒノキ)1956-2005
-0.2
0
0.2
0.4
-0.2
0
0.2
0.4
0 4
-0.2
0
0.2
-0.8
-0.6
-0.4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Month
-0.8
-0.6
-0.4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12Month
-0.8
-0.6
-0.4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Month
Month
最近50年分の相関
-
江戸時代後期における古日記資料から復元された梅雨期の降水量(水越、1993)と木曽ヒノキの酸素同位体比の変化
600 -3
ean>
> 18O
at
-
弥生時代後期(紀元1-2世紀)頃の日本の状況-水田稲作技術の普及と気候変動 戦争の勃発--水田稲作技術の普及と気候変動、戦争の勃発-
初期水田稲作社会
後漢の衰退
―
そ
七、八
共に、
と曰う後漢の衰退
鉄器の普及
洪水の頻発
その国、本
八十年。倭
、一女子を
う。
洪水の頻発
戦争の勃発…
★大規模(第2次)
本男子を以
倭国乱れ相
を立てて王★大規模(第2次)
な高地性集落の出現
具体的には?
以て王とな
相攻伐す
王となす。:2世紀前半
★倭国大乱(戦争)
2世紀後半
なし、住ま
ること歴
。名づけて
『魏志倭:2世紀後半
★卑弥呼の登場
:3世紀初頭
まること、
年、乃ち
て卑弥呼
倭人伝』よ:3世紀初頭
「図説最新日本古代史」より
より
-
倭国大乱(2世紀末)の原因としての諸説倭国大乱( 世紀末)の原因としての諸説
0.農耕の発展による、生産物の余剰の発生
→余剰生産物を巡る争いの発生*現在は、否定的。そもそも、余剰など無かった !?!
1.後漢の衰退(三国志の時代へ…)漢による倭国の統制が取れなくな てくる→漢による倭国の統制が取れなくなってくる…
2.鉄器(農具&武具)の普及武→鉄器の獲得を巡る主導権争い
3 天変地異( 洪水による遺跡の全国的埋没)3.天変地異(←洪水による遺跡の全国的埋没)*具体的には、どんな天変地異が起こったのか ???
-
ちなみに、水害は、何故起こるのか?
1) 大雨が降るから。
→だけではない。だけではない。2) 大雨が降ったら水に浸かる場所に、家や田んぼ
があったからがあったから。
→では、何故、そんな場所に家や田んぼを作るのかか?
3) そこは、かつて、水に浸からない場所だったから。
つまり 水害は 降水量が多いことで起こるのではなく 降水量つまり、水害は、降水量が多いことで起こるのではなく、降水量が変動し、乾燥気候が、湿潤気候に変化することで起きる。
逆も同じ 旱魃は 降水量が少ないことで起こるのではなく 降逆も同じ。旱魃は、降水量が少ないことで起こるのではなく、降水量が変動し、湿潤気候が、乾燥気候に変化することで起きる。
-
埋没木の樹木年輪の酸素同位体比を使えば、遠い過去の夏季の水環境の経年変動(数年~数10年)の解析が可能になるはず!
紀元前1世紀~紀元2世紀における木曽の埋没ヒノキ2個体の年輪セルロース18Oの経年変動を、分析した
Combined time series of d18O anomaly
3.005年移動平均
の経年変動を、分析した…
1.00
2.00
O
旱魃
-2.00
-1.00
0.00
d18
洪水
-3.00
-100 -50 0 50 100 150 200 250 300 350
Year
紀元前後には安定していた18Oも、紀元50年頃には、変動幅が大きくなり、紀元2世紀になると、長い周期(数10年周期)での変動を繰り返すようになる
魃 が が 紀 紀 び 変(洪水や旱魃の期間が長期化する)が、紀元3世紀になると、再び、変動の周期が短くなる。
-
紀元前1世紀~紀元3世紀の木曽の埋没ヒノキの年輪18Oの変動のWavelet解析図の年輪 Oの変動のWavelet解析図
100年70年50年
30年
20年20年
10年周期
①長期安定期 ②短周期変動期 ③長周期変動期 ②短周期変動期①長期安定期 ②短周期変動期1年
③長周期変動期 ②短周期変動期
中国における洪倭国大乱 卑弥呼の登場
中国における洪水・旱魃の頻発から黄巾の乱へ
-
弥生時代の水田稲作社会と水環境の関係<浮かび上がってくるメカニズム><浮かび上がってくるメカニズム>
安定した高収穫の元で人口増大常に少ない収穫の元で人口停滞 or
変動を前提にした農業の展開
河川水位が毎年一定
低地の広大な水田の利用
が可能
河川水位が2~10年周期
で上下
高地の水田に依存 で上下依存
①長期安定型 ②短周期変動型①長期安定型 ②短周期変動型
人の寿命は30年程度なので
河川水位が20 50年
増大した人口が飢饉に直面
低地水田への依存
人の寿命は30年程度なので、短期の記憶は残るが、長期変動の
記憶は残らない。10年豊作が続けば、高生産に依存した社会システム20~50年
周期で変動への依存
と放棄
高生産に依存した社会システムができてしまう。
③長周期変動型③(数10年周期の変動)が、稲作社会にとっては、一番危険?
-
気候変動の周期性と人間社会の変動の関係般的法則かも れな
米国ニュ メキシコ州 北西部チャコ渓谷付近における水環境の変遷
は、一般的法則かもしれない…
米国ニュ-メキシコ州・北西部チャコ渓谷付近における水環境の変遷(Cook et al., 2004: 樹木年輪幅による復元データ)
人口急増
4
湿潤
★崩壊
人口急増
0
2
PD
SI
湿潤
-2
P
乾燥-4
500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500
Year (AD)
乾燥
細線:生データ 太線:20年平均
Y軸: Palmer Drought Severity Index
-
チャコ渓谷のアナサジ遺跡とは?-先史時代の北米最大級の高層建築-
チャコ渓谷
先史時代の北米最大級の高層建築
石板を巧みに石板を巧みに組み合わせた高度な建築技術!術!
12世紀初頭に12世紀初頭に最盛期を迎え、
その直後に崩壊!
アメリカ合衆国ニューメキシコ州
荒涼とした荒涼とした原野の真中に5,6階建てのビルをてのビルを含む、都市があった。
-
4
先述のデータを、Wavelet解析すると…湿潤(繁栄)
0
2
PDSI
湿潤(繁栄)
-4
-2
800 850 900 950 1000 1050 1100 1150 1200 1250 1300
乾燥(崩壊)
Year (AD)
チャコ渓谷のアナサジ族が滅びる直前には、確かに、長周期の変動が卓越!
800 850 900 950 1000 1050 1100 1150 1200 1250 1300
-
アナサジ族が滅びた直接の原因(考古学的知見)-長期の乾燥期の直前に、最大の湿潤期が現れたこと-長期の乾燥期の直前に、最大の湿潤期が現れたこと
●11世紀~12世紀初頭(稀に見る、湿潤期)食糧生産が好調 人 増大 高層建築 上層階級(都食糧生産が好調 → 人口増大 → 高層建築ラッシュ → 上層階級(都市)と農民(周辺)の格差の拡大 (*巨大建造物、輸入贅沢品の蓄積、農民住居は貧弱)
●12世紀半ば(1130年代~:長期の乾燥期)水不足のため食糧生産の停滞 未耕作地が既に無い 増えすぎ水不足のため食糧生産の停滞 → 未耕作地が既に無い → 増えすぎた人口を養えず飢饉が発生 → チャコ渓谷の中央と周辺の間での軋轢→ 紛争・食人・逃散
2
4
-2
0
PD
SI
-4
500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500
Year (AD)
-
江戸時代の飢饉の場合(小氷期の気候変動との関係)(小氷期の気候変動との関係)
1615 「元和の飢饉」 奥羽で冷害1641 42 「寛永の飢饉 全国的に旱魃 洪水1641-42 「寛永の飢饉」 全国的に旱魃・洪水1674-75 「延宝の飢饉」 諸国で風水害1680-81 「天和の飢饉」 諸国(特に西国)で風水害1695 「元禄の飢饉」 奥羽・北陸で冷害1695 「元禄の飢饉」 奥羽 北陸で冷害1732 「享保の飢饉」 西国で“虫害”1749 「寛延の飢饉 北奥で冷害1749 「寛延の飢饉」 北奥で冷害1755 「宝暦の飢饉」 東北地方で冷害1783 「天明の飢饉」 東北地方で冷害
*30万人以上餓死・疫病死:近世最悪30万人以上餓死 疫病死:近世最悪1833-38 「天保の飢饉」 東北地方で冷害
-
江戸時代の飢饉の特徴江戸時代の飢饉の特徴
東北から関東の飢饉と 西日本の飢饉は 気東北から関東の飢饉と、西日本の飢饉は、気候災害との関係が違う。
1 冷害型飢饉(東北~関東)1.冷害型飢饉(東北~関東)
2.風水害(虫害・干害)型飢饉(西日本)
江戸時代(小氷期)には 1 が多いが 2 が江戸時代(小氷期)には、1.が多いが、2.が集中する時代(17世紀後半)もある。
-
屋久島のスギ(屋久杉)の年輪セルロースの酸素同位体比-1700~(1年刻み。約10個体プール)の一部-1700 (1年刻み。約10個体プ ル)の 部
27 00
享保の
寛延の
宝暦の
天明の
天保の寒冷(乾燥)
11年移動平均
26 00
26.50
27.00
体比
の飢饉
の飢饉
の飢饉
の飢饉
の飢饉
寒冷(乾燥)
25 00
25.50
26.00
同位
体
24 00
24.50
25.00
酸素
★ ★ ★ ★★温暖(湿潤)24.00
1700 1720 1740 1760 1780 1800 1820 1840 1860
西暦
★ ★ ★ ★温暖(湿潤)
★西日本の飢饉 =温暖期に発生
西暦
東北地方の巨大飢饉は、約20年続くミニ温
★東北日本の飢饉=寒冷期に発生は、約20年続くミ 温暖期の後に、発生。
-
何故、江戸時代の飢饉は、それほど悲惨になったか?
【第一の原因】 幕藩体制の元で、米などの商品作物を中心に 『市場経済』 の対応を余儀なくされた中心に、『市場経済』への対応を余儀なくされた。
→藩の財政を成り立たせるには、米などを増収して、上方に運藩の財政を成り立たせる は、米などを増収して、 方 運び、売却することが必要だった。しかも、飢饉の年ほど、米価が上がるので、無理にでも、売却を強行した(飢餓輸出)。
【第二の原因】 小氷期の気候が『長周期変動成分』を持っていたから持っていたから。
→水田稲作が困難な寒冷地域であるにも拘らず、多収量品種(冷害に弱い晩生種)の作付けを強行し(領主、農民共に)、しかも、それが、ある期間、成功してしまう…という問題。
-
何故、人間社会は数10年周期の気候変動に弱いのか?
環境収容力環境収容力
生 水準
数10年周期の気候変動
人口 生活水準
の拡大
人口・生活水準 人口・生活水準
①
破綻
環境収容力に見合った人口や生活水準の拡大
②
破綻環境収容力
人口・生活水準の拡大
数10年周期の気候変動環境収容力
人口・生活水準の維持
の継続
人口 生活水準の拡大
の縮小
人口 生活水準の維持
③
数10年周期の変動は、人間の記憶に残りにくいが、人間の寿命の期間内で起きる。→ つまり、「予測」が難しく、(人口調整などの社会的な)「対応」も難しい。まり、 予測」 難 く、(人 調整な 社会的な) 対応」も難 。
★“より短周期”の変動であれば、②が生じないし、短期備蓄で乗り切れる(予測可能)。★“より長周期”の変動であれば、③に対して、対応の時間的余裕がある(対応可能)。
-
しかし、数10年周期の気候変動に「強い」社会と「弱い」社会があるはず…技術革新 大量死
再生 破綻
」 あ ず
環境収容力環境収容力
技術革新
人口・生活水準
大量死
の縮小
人口・生活水準の維持人口・生活水準
人口・生活水準
富の分配
移住
人口・生活水準人口・生活水準
環境収容力が
固定社会侵略
増大しても、積極的(もしくは、消極的)な理由
生活
人口・生活水準 人口・生活水準
で、人口・生活水準を増大させない(させられ
ない)場合ない)場合
異民族
-
【検討すべき課題】【検討す き課題】
① なぜ、気候の平均場だけでなく、変動周期までが、歴史的に変化するのか(気候学的課題)歴史的に変化するのか(気候学的課題)
② 人類史上の各々の出来事は、どのような気候変動の周期性の中で起きていたのか(歴史学的課題)
★どのような社会が、どのような周期の気候変動から、★どのような社会が、どのような周期の気候変動から、どのような影響を受けた(受けなかった)のか?
★まず、古気候データを、拡充する必要あり(ほとんどのデータは、まだ世界に、埋もれている…)
★その上で 気候変動の周期性と人間社会の応答の関係を★その上で、気候変動の周期性と人間社会の応答の関係を、様々な時代・地域毎に、データ(古気候、歴史文献)に基づいて、より詳細に解析することが、必要。
-
(これが環境問題の理解に役立つのか?)(これが環境問題の理解に役立つのか?)“数10年周期の気候変動”と“人為的な環境変動”の相同性
環境収容力 環境収容力気候変動
深刻化する環境問題とは 通常 数
の拡大
人口・生活水準 人口・生活水準
環境収容力
技術・制度の革新
は、通常、数10年(以上)かかって顕在化するも
破綻
拡環境収容力に見合った人口や生活水準の拡大
の革新在化するものである…
環境収容力
人口・生活水準の拡大
気候変動環境収容力
人口・生活水準の維持
水準の拡大
の継続の縮小 技術・制度革新の副
作用作用
★“環境収容力の拡大と縮小のメカニズム”(自然科学的側面) は、「気候変動」と「人為的な環境変動」の間では、全く違うが…
★環境収容力の増減に対する “人口 生活水準の応答のメカニズム”(人文 社会★環境収容力の増減に対する、 人口・生活水準の応答のメカニズム (人文・社会科学的側面)は、「気候変動」と「人為的な環境変動」の間で、相同である。【(人為的)環境問題における、後者の課題は、気候変動を対象に、考察可能】
-
(研究プロジェクトの可能性)(研究プロジェクトの可能性) 高分解能古気候学と歴史・考古学の連携による“気候変動に強い社会システム”の探索
再生 破綻
環境収容力
①樹木年輪の酸素・水素同位体比などの高時空間分解能プロキシーを用いた、過去約2000年間の
の縮小
人口・生活水準の維持詳細かつ正確な気候変動の復元と、Wavelet解析等による気候変動周期自身の時空間変化の解析
★気候変動のメカニズムの解明 周期性の時空間★気候変動のメカニズムの解明:周期性の時空間変化を復元して、その発現の蓋然性を理解する。
②数 年周期等 特定 周期を持 気候変動が生じた時代と場所 おける②数10年周期等の特定の周期を持つ気候変動が生じた時代と場所における人間社会の変動の分類(飢饉、移民、戦乱、技術革新、革命等の“有無”)
★「実験歴史学」的アプローチ:“特定の周期性を持つ気候変動”という 外部★「実験歴史学」的アプローチ: 特定の周期性を持つ気候変動 という、外部からの刺激に対して、様々な人間社会がどのように応答するかを観察する。
③「気候変動と人間社会の関係」についての“一般性”と“個別性”の把握、及びその背後にある様々な要因の詳細な人文・社会科学的な解析
★気候 環境変動に強い社会システムの探索 数10年周期の変動が生じた★気候・環境変動に強い社会システムの探索:数10年周期の変動が生じたときに破綻しない社会システムを発見し、その背後にある要因を理解する。
![lZ~~11kn,~~ 1 ~Llln,Ul,~WLn,~~@~ 1 ~]'-~~Lll n t ~n,lj~~lbkl~~n,tt 1~ t~~kl11 ~Ull Lll.~~L Ii\, ru, ~~1'](https://static.fdocument.pub/doc/165x107/60b08af26f4b311ab910cdd7/lz-11kn-1-lllnulwln-1-lll-n-t-nljlbklntt-1-tkl11-ull.jpg)







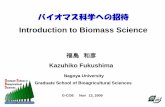






![Nouvelle SEAT Leon. · 2020-06-04 · fiscale (CV) Émissions de CO 2 WLTP* Bonus / Malus (2020)** Conso mixte WLTP REFERENCE STYLE XCELLENCE ONE FR ONE [Codes modèles] KL11 KL12](https://static.fdocument.pub/doc/165x107/5f07e7c77e708231d41f5889/nouvelle-seat-leon-2020-06-04-fiscale-cv-missions-de-co-2-wltp-bonus-malus.jpg)



