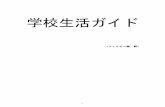大出正篤の「対訳法」に基づく日本語教科書...大出正篤の「対訳法」に基づく日本語教科書...
Transcript of 大出正篤の「対訳法」に基づく日本語教科書...大出正篤の「対訳法」に基づく日本語教科書...

23
大出正篤の 「対訳法」に基づく日本語教科書
前 田 均
〔要 旨〕 日本語教育の教授法に関して昭和十年代に 「直接法」「対訳法」の論争が起
こった。「対訳法」の旗手だった大出正篤は自らの教授法理論に基づく教科書を多数執
筆 ・発行していたが,その萌芽たる 『速修国語読本』から始め,国定教科書の訳証本,
自習教材等,これまで言及されることのなかった大出の教科書を紹介するとともに,大
出の協力者の業席もあわせ紹介し,大出の教授法の今日的意義を考えた。
〔キーワード〕 大出正篤,対訳法,日本語教科書,成人用教科書,日本語教育史
1.「直接法」「対訳法」論争
昭和十年代の日本語教育界では教授法をめぐって 「直接法」「対訳法」の論争がさかんにお(l)
こなわれた。その様子は日本語教育振興会の機関誌であった 『日本語』で知ることができる。
本稿では 「対訳法」の中心人物であった大出正篤の言説と,彼の作成した教科書等をたどり,
大出の教授法を明らかにすることにする。特にこれまで言及されることのなかった文献を紹介
することにつとめる。
以下,引用にあたっては,仮名の踊り字 ・旧漢字は現行表記に直し,記号 ・改行箇所の変更,
ルビ・「注」を示した数字の省略を行うことがある。「満州」「滴洲」は引用文献の表記に従う。
私の文章中では 「満洲」を使う。煩項を避けるため 「満洲」「満州国」等の括弧付けはしない。
下線はすべて筆者による。
(2)まず,「直接法」「対訳法」の論争を多仁安代の解説で確認 しておく。
中国占領地における日本語教育の中心となったのは華北であったが,ここでは教授法に
ついて,直接法と対訳法の有効性をめぐる論争が起きた。同法の根本的な相違は,学習者
の母国語を常用するか否かにあり,常用する方法を対訳法,しないのを直接法と称 した。
大出正篤が編み出した 「速成式教授法」は総ルビつきで全訳のついた教科書で予習をさせ
ておき,教室では教科書を柾れて主に会話の練習を行うという対訳教授法の一種であった。
直接法に固執する人々から,この方法は予習の段階で母国語を使用するので,「母国語の
常用」に相当し,有効性を疑問視されていた従来の対訳法と同列のものであるとして,排
斥の理由にされたのである。
(3)大出正篤がその教授法を編み出すに至った経緯を次の駒込武の文章で確認しておく。駒込は
(4)1940年4月に発行された 『文学』に掲載された大出の 「日本語の世界的進出と教授法の研究」
を引用しつつ,次のように述べる。以下の引用文中の 「引用者」は駒込である。

24 天 理 大 学 学 報
出正篤は (南満洲教育会- 前田注)教科書編輯部主事を退き,南満中学堂教頭 (一九≡
〇~一九三四)の職にあった。その頃,満州事変が起こる。満州国建国以前は大出も山口
と同じように直接法 ・話し言葉重視という方針を持っていた。しかし,満州国が建国され
ても教員不足等のためいっこうに日本語教育の効果があがらない情勢を前にして大出は
「多年指導的立場にあった自分としてその責任をも感 じ」て新たな教育方法を模索する。
大出によれば 「(元来我々の従来行ってきた教授法は- 引用者注)小い子供を目標とし
て,相当年月をかけて会話を完成する教授法である。然るに満什個 建国直後の日語教育が
要求するところは,そんなまだるい長年月を要する教授法ではなくて,短時日の間に手取
り早く効果を現す教授なのであった。」という情勢であり,この情勢に即する形で 「速成
法 (速成式話方教授法)」を考案する。
2.大出正蔦の 「対訳法」の萌芽としての 『速修国語読本』
大出はおなじ文章中で 「速成法 (速成式話方教授法)」の 「萌芽」として以前作成した成人
用教科書について言及している。
成人に対する速成教授法はどうであったかといふと,この朝鮮時代に於てその萌芽を認
めることが出来るのである。大正六年頃かと思ふが,朝鮮総督府の編輯課で 「速修国語読
本」といふ一冊本が発行された。これが大人式の日本語読本として発行された最初のもの
ではあるまいかと思ふ。自分はその当時京城の教員養成所 (師範学校前身学校)に居って
編輯課の仕事も兼務し,その速修読本の原稿を執筆したのである。この本は正規の学校以
外で相当広 く用ひられ,非常な発行部数を見たやうである。但し実をいふと,教材は大人
向きのものを採用し,編纂の方法等も大人向きにはしたけれども,それに即した教授法等
は考-なかったのである。従ってその本を用ひても,教授法は幼少年向の教授法をするか,
或は対訳式の教授法等をしてゐた訳である。今度は満洲に話を移すと,満洲も初めは対訳
式教授一点張であったのが,朝鮮から話方教授を取り入れて初等教育等はそれで統一され
るやうになった。速成教授法の方はといふと,朝鮮の 「速修国語読本」が 「速修日本語読
本」と改名されて,内容も殆どそのままで使用された。併 しその教授法も殆ど研究されな
かったので,日本語学校の如き成人教育に於ても,小学校用の読本が採用され,その教授
法も小学校と何等変らないといふ状態であった。これが満洲事変前までの状態である。
大出自身も 「速成教授法」の 「萌芽」と認識している 「速修国語読本」についてこれまでま
ったく触れられることがなかった。まず,この 「速修国語読本」を紹介する。
手元の本は,『朝鮮総督府編纂 速修国語読本』と表紙にあり,「大正四年一月二十日発行」
「大正十-年八月二十日増刷」である。大出は 「大正六年頃か」と言っていたが,2年の違い
でしかないので大出の言っている本はこの本のことであろう。「朝鮮総督府」として発行 した
本なので,大出の個人名はない。そのため,日本語教育史上の重要人物である大出が 「原稿を
執筆した」にもかかわらず,この本に注目されずにいたのであろう。
まず,「大正三年十二月」の 「緒言」(但し,これには対訳なし)を紹介する。
-,本書ハ国語ヲ速修セシムガタメニ編纂シタルモノナリ。
一,本書ハ独習ノ便ヲ計リテ全部振仮名ヲ施シ,又,第一編ヨリ第四編マデハ朝鮮語ノ対

大出正篤の 「対訳法」に基づく日本語教科書 25
訳ヲ附セリ。
-,本書ノ仮名遣ハ普通学校国語読本 卜全然同一 トスo但シ,第五編ニハ文語体文章ヲ掲
ゲ,若干候文体ヲモ加-テ歴史的仮名遣ヲ用ヒ,之二習熟セシムルノ便ヲ計レリ。サ
レドモ字音ノ振仮名ノミハ表音的仮名遣 トセリ。
一,本書第一編第二編第三編ハ片仮名及ビ単語ヨリ始メテ,秩序的二教材ヲ提出シタルヲ
以テ,順次二学習スルヲ要スルモ,第四編会話又ハ第五編文章ハ,何 レモ日常生活二
須要ナル事項ヲ蒐メタルモノナレバ,必ズシモ順ヲ追フヲ要セズO国語夜学会等教授
時間数ノ少キ所ニテハ,適当二取捨選択シテ教フベシ。
一,本書ニハ,一般的知識ヲ修得セシメムガ為,附録 トシテ,参考 トナルベキ諸種ノ事項
ヲ記載シタリ。
内容は上記のように 「第-編」から 「第五編」まであり,次のようである。省略部分を多 く
して目次を紹介する。期待されている勉強量 ・教授時間数を想像してもらうため,ページ数を
入れておく。
第-編 片仮名及単語
第二編 単句及単文
第三編 平仮名
第四編 会話
第一 朝ノ挨拶
第二 晩ノ挨拶
第四 初対面ノ挨拶
第五 道ヲ聞ク
第十一 病気見舞
第十三 買物
第十五 我学校
第二十一 汽車旅行
第二十四 内地観光問答
第二十九 郵便局
第五編 文章
第六課 地球の話
第七課 浦島太郎ノ話
第九課 禁酒
第十四課
第十六課
第十二課
第二十一課
第二十二課
第二十三課
第二十五課
第三十課
水の変態
租税
日露戦役
伝染病
裁判所
皇室
我国の大祭日
書籍問合せの文/右返事
1-25ページ
26-66ページ
67--76ページ
77-197ページ
198-288ページ

26
附録
天 理 大 学 学 報
第三十二課 病気見舞の文/右返事
第三十七課 出生申告書 卜死亡申告
「君がよ」ノ歌
朝鮮総督府及所属官署一覧
変体仮名表
度量衡一覧表
朝鮮地方主要都市の人口
本邦条約国の首府
(附録としての) 1-24ページ
「第一編 片仮名及単語」はまずカタカナを掲げ,読みをハングルで示し,次に学習したば
かりのカタカナで簡単な単語を挙げ,漢字 (日本語での普通の表記法)と朝鮮語訳を付したも
のである。「練習」の指示も日本語と朝鮮語の二言語でしてある。
「第二編 単句及単文」は,「ト」「ノ」といった助詞,「高イ山」という修飾,「ココガ学校
デス。」という名詞述語文,というように現在の日本語教科書でもとられている文法事項を積
み重ねる課の組み立てになっている。すべての例文が対訳となっていて,教科書の上段に日本
請,下段に朝鮮語訳を配置してある。
「第三編 平仮名」はひらがなを学習したあと,「第一編」「第二編」での学習内容をひらが
なによって復習するもの。
「第四編 会話」は上記のように場面に応じた会話文を学習するもの。「緒言」にもあった
ように 「全部振仮名ヲ施シ」「朝鮮語ノ対訳ヲ附」してある。
「第五編 文章」には,「口語崇敬体」「口語常体」「文語体」「口語手紙文」「候文」と当時
の文章に用いられる文体が網羅されている。内容は当時の初等教育用の 「国語読本」にもよく
あったように,「第六課 地球の話」「第十四課 水の変態」のような理科的教材,「第十六課
租税」「第二十二課 裁判所」のような社会科的教材を配したもので,言語教育とともに近代
社会の構成員たる教養を同時につけさせようとするものである。事実,「国語普及」の目的は
単に言語学習だけではなく,近代国家の一月としての常識をも教え込もうとするものであった。(S)
まさしく,のちに大出が世に問う 『効果的速成式標準日本語読本』の 「萌芽」というべきも
のである。ただ,「緒言」に 「独習ノ便ヲ計 リテ」とあったように 「独習」をも目的としてい
る一方,「国語夜学会等」での使用も想定している。いずれにせよ成人用教科書であったわけ
である。
大出が,満洲では 「朝鮮の 『速修国語読利】が 『速修日本語読本』と改名されて,内容も殆
どそのままで使用された。」と言っていたが,次にはこの 「速修日本語読本」を紹介しよう。
手元のものは,奥付を見ると 「大正十三年四月十日初版発行,昭和十二年八月十日第百十九
版発行」で,「編纂者兼発行者兼印刷者 飯河道雄」とあり,飯河の住所 と同じ番地である
「奉天商埠地十一経路第一一七号」の 「東方文化会」「東方印書館」の名も並んでいる。表紙
には著者名として 「前河南省高等師範学校教授 前旅順第二中学校長 飯河道雄」,書名とし
て 『対訳速修日本語読本』と書かれている。内容は 「殆どそのままで使用された」とあったよ
うに,「緒言」,「第-編」から 「第五編」に至るまでほとんど同じである。すべて振 り仮名と
中国語の対訳を付している姿も同様である。但し,『速修国語読本』にあった 「附録」や 「第
五編 第十二課 目露戦役」が削除されていたり,「第二十四 内地観光問答」が 『速修日本

大出正篤の 「対訳法」に基づく日本語教科書 27
語読本』では 「日本見物」となっていたりするのは学習者 ・地域の実態にあわせたものであろ
う。特に 『速修国語読本』の 「附録」は,日本の一部としての朝鮮で 「国語」として日本語を
教えるという目的がはっきり出たものである。『速修国語読本』「第五編 第三十七課 出生申
告書 卜死亡申告」も朝鮮総督府の地方行政機関に提出する書類の書き方を教えるもので,『速
修日本語読本』では削除されている。端的に言えば,表題のとおり 『速修国語読本』は 「国
語」としての日本語教科書であり,『速修日本語読本』は外国語としての日本語教科書であっ
た,と言えよう。そのように目的が違っていてもそのまま使われたのは言語教育教材としてす
ぐれていたからではないだろうか。なお,細かい相違点の検討は今後の課題である。
この飯河はどういう人物かというと,駒込によると 「大出正篤 (一八八六~一九四九)と飯
河道雄 (一八八二~一九三七?)は,ともに東京高等師範学校卒業生であり,満鉄による中国Lい
人教育の中核に位置した人物である」。
今の著作権を重視する社会の常識からすると,朝鮮総督府の発行した教科書の本文をほとん
どそのまま用い,朝鮮語部分を中国語に置き換えただけの本を出版するとは考えられないこと
であるが,当時は日本語教育のためか問題にされず大出も堂々と 「朝鮮の 『速修国語読本」】が
『速修日本語読本』と改名されて,内容も殆どそのままで使用された。」と述べるほどであっ
た。いずれにせよ,この二冊が 「対訳法」「速成教授法」の 「萌芽」として果たした役割を忘
れてはならないだろう。
3.大出の教科音訳証本
この大出の教授法を満洲国政府の教育当局はどう見ていたのか,駒込は次のように言ってい(7)る。
こうした大出の方法を,満洲国政府はどのように評価していたのだろうか。結論的なこ
とを先に述べれば,そこには協力しつつ競合する奇妙な関係が見られる。まず協力関係と
いう点では,大出は,中等学校用の 『国民高等学校 ・女子国民高等学校日本語読本」】仝八
巻の巻五以降を検定教科書として編修している。満洲国の検定教科書は,原則的に各教科
目に-種類しかなく (中略)検定教科書編纂の事実は満洲国政府と大出の協力関係を示す
ものといえる。他方,大出は自ら編纂した検定教科書に対する 「訳注本」を作成して,自
習用として出版している.たとえば,大出正篤 『師道学校日本語読本』巻- (一九三八年
三月発行)と,大出正篤 『師道学校日本語読本 訳注本』巻- (一九三九年三月発行)と
いう二種類の教科書が存在するのである。そのことは,満洲国政府が 「訳注本」の採用を
認めていなかったことを示している。
Lf=新内康子も満洲国政府と大出との教科書をめぐる関係を次のように述べている。
(b)(引用者注- 国民高等学校女子国民高等学校日本語読本 (1938ごろ-1942)巻 1ママ-4 大出正篤著 巻5-8 満州帝国政府民政部編)は,中等教育用教材で,本冊のほ
か,速成式教授法を唱える大出正篤による訳注本 (C)がある。急に難度の上がった教材
に苦慮する学習者のために,実践派の大出が直接法と対訳法の折衷案として教材化したも
のである。

28 天 理 大 学 学 報
この他にも新内は 「(C)国民高等学校用女子国民高等学校用師道学校特修科用日本語読本
訳注本 (1939)大出正篤著など」があることも指摘 している。『国民高等学校 ・女子国民高等
学校日本語読本』の著作者が巻により駒込と新内とで異なっているが,大出が 「訳注本」を作
成 ・出版していた事実にはかわりがない。関正昭も,
中等教育用教科書は,そのすべてについて本冊とは別に民間の出版社から 『訳注本』が
出されているのが特徴的である。3-5-1-h(引用者注- 中等日本語読本 仝4巻
1929-1930 改訂版1934-1935)の訳注本には,山口の直接法を支持推進した飯河道雄の
『対訳詳注中等日本語読本』(奉天東方印書館)と大出正篤の 『中等日本語読本訳注本』
(大亜印書局発行)があり,3-5- 1-i(引用者注- 国民高等学校女子国民高等学
校 日本語読本 巻 1-4 大出正篤著 巻5-8 民生部 ?~1942),3-5- 1-1
(引用者注- 師道学校 日本語読本 仝3巻 大出正篤著 1938-?),3-5-1-k
(引用者注- 師道学校特修科日本語読本 全3巻 大出正篤著 ?-1942)用には,大
出の 『国民学校女子国民学校用師道特修科用日本語読本訳注本』(満州文化協会発行)が
ある。いずれも本文の上欄に新出語の中国語訳と簡単な語法説明をほどこし,下欄に本文
の中国語訳を掲げている。
(9)
と述べている。
これを見る限り,「訳注本」は 「中等」学校の段階の教科書に対してのみ作成されたようで
ある。「訳注」に使われている中国語が理解できる学力がなければ 「訳注」の意味をなさない
からである。また,「師道学校」では日本政府の方針に基づ く教育を忠実に実行できる現地人
教員の養成が急務だったことは容易に想像できる。ただ,関の言う 『国民学校女子国民学校用
師道特修科用日本語読本訳注本』に出てくる 「国民学校女子国民学校」は現在の日本の学校体
系を例にとって説明すると小学校 1-4年生に該当する学校なので初等教育というべき段階の(LO)
学校であり,矛盾が生じる。新内の記述とも微妙な違いが見られる。この件は後述する。
しかし,私の手元に 『国民優級学校日語国民読本訳註本 巻-』という本がある。「国民優ail‖6
級学校」は四年制の 「国民学校」の上に接続する二年制の学校であるから,これは初等教育と
呼ぶべきであろう。その本は表紙に 『民生部編纂 満洲文化普及会訳註 国民優級学校日語国
民読本訳註本 巻一 発行満洲図書文具株式会社』とあり,奥付には 「昭和十二年七月十五日
初版発行 昭和十四年五月二十日十五版発行 著作者 奉天市大和区藤浪町三十一番地 大出
正篤 発行者 奉天市大和区千代田通四十番地 森川昇二 給批発処 奉天市大和区千代田通
四十番地 満洲図書文具株式会社」とある。森川については後述する。なお関は発行元を 「満
州文化協会」と言っているが,私の確認したところでは 「満洲文化普及会」である。時期によ
って名称が異なるのかもしれないのでなお研究の余地がある。「満洲文化普及会」と 「満洲図
書文具株式会社」とは所在地が同じなので編集を担当する部門と販売を担当する部門に分かれ
ていたのかとも思われるがこれもまた解明は今後の課題である。
また,これまで引用した諸論文には 「訳注」となっていたが,私が本稿で言及する原本を見
た限り,「訳註」である。以下,引用は元の論文等に従い,原本からはその表記どおりに写す
ことにする。
「康徳四年 (1937年- 前田注)五月」の 「緒言」には大出の主張がよく出ているので引用
する。

大出正篤の 「対訳法」に基づく日本語教科書 29
-,国民優級学校に於ける日本語教授の実情を見ると,生徒の実力と教科書の程度とに非
常な相違がある。その為に教授者も生徒も共に困ってゐるといふ一原因はここにある
と思ふ。
-,これを救済するには,生徒の実力を大に上げるか,教科書の程度を大に下げるかする
より外に方法がない。併し,この何れも急には実現出来ない事である。さうすれば,
現場の急を救ふ他の方法を講じなければならぬ。其の目的の為に生れたのが本書であ
る。
一,本書を使ふことによって教授者は語句の解釈の為に多大な時間を費して,然も不徹底
を嘆いてゐたのが政ほれると思ふ。そして其の余った時間が話方の取扱や語句の活用
等に向けられて,生徒の力が進むであらう。
一,生徒は又本書によって語句の解釈や文の意義が徹底的に了解され,教授前の予習も十
分に出来,家庭に於ける復習も完全に出来て,彼等の熱心な目語研究慾を滴足させる
事が出来るのではあるまいか。
一,但し,本書を教室に於ける正教科書として使用するか否かは,学校の種類,其他の事
情によって御研究を願ひたい。家庭の自習用とする事によっても,十分前記の目的は
達せられる。猶訳註本を使用する事を対訳教授であると思ほれて,この種の本の利用
を蒔措せられる教授者は一度編者の意見と主張を聴いて戴きたい。
内容は中段に日本語の本文を配し,漢字には振 り仮名をすべて付してあるばかりでなく,カ
タカナ表記の単語には漢字をあててある。たとえば 「チョット」には 「一寸」,「ココ」には
「此処」,「アリガトオ」には 「有難」というようにである。これは漢字を多く知っている中国
語話者の期待にこたえるものであろう。現在でも中国語話者の日本語学習者は,日本の現行表
記では漢字を用いない語についても漢字での表記を知りたがるということがある。いわば 「振
り漢字」をしておくとその場で一応の理解が得られ,記憶にも有効だからであろう (日本語と
中国語で意味の異なる漢字や漢字熟語の問題はあるが単なる一時の便宜のためなのでマイナス
面はそうはない)。上段には新出語の説明,下段には全文の中国語訳を書いてある。関は 「中
等教育用教科書は,そのすべてについて本冊とは別に民間の出版社から 『訳注本』が出されて
いる」と言っていたが初等教育用教科書にも同様のものがあることが明らかになった。
これは一種のいわゆる 「虎の巻」「教科書ガイド」とでも呼べるものである。大出は学校教
育の実際をよく知っていたのではないか。日本語担当の教師が日本人で直接法で日本語を教え
ていた場合,このような本で予習 ・復習するのは有益である。また,教科書は段階を追って編
纂されているから,学校へ行かず独学で日本語を学ぶ人にも公的な教科書に注をつけたこの種
の本はすぐれた自習書になりうる。
この本の巻末には 「満洲文化普及会介紹各種優良書籍」として本の広告が出ている。当時の
日本語教科書の出版状況を知るため日本語関係に限って紹介する。
(新刊)『国民高等学校 日本語読本 (訳証本)巻-』
『効果的速成式標準日本語読本 巻-』『効果的速成式標準日本語読本 巻二』『目語研究宝鑑 全』
『新撰日本語読本 正篇』『新撰日本語読本 続篇』『簡易日本語読本 仝』

30 天 理 大 学 学 報
『学生自習日文 模範辞典』
『漢字索引 模範日語辞典 全』
『民衆日本語課本 全』
『初級中学校日本語教科書 訳註 上冊』『初級中学校日本語教科書 訳註 中冊』『初級
中学校日本語教科書 訳註 下冊』『高級小学校日本語教科書 上冊 訳註本』『高級小学校日本語教科書 下冊 訳註本』
『初等目語読本 訳註本 巻-』『初等日語読本 訳註本 巻二』『初等日語読本 訳註本
巻三』『初等日語読本 訳註本 巻四』
『中等日語読本 訳註本 巻-』『中等日語読本 訳註本 巻二』『中等目語読本 訳註本
巻三』『中等E]語読本 訳註本 巻四』『日支材訳解註 日本語趣味読本 正編』『日支対訳解註 日本語趣味読本 続編』『警察日語会話』
『鉄路日語会話 全』
『日支対訳 実用日語会話 全』
『対訳明解 女子実相日語新典』
「満洲文化普及会」「満洲図書文具株式会社」は日本語教育の分野でかなり活躍していたよ
うである。これらの本の著者がすべて大出だとは今,確認できないが 「対訳」「訳註」を前面
に押し出した日本語教科書であることは間違いなく,大出の教授法の具体化が進んでいたこと
が見て取れる。
関は 「中等教育用教科書は,そのすべてについて本冊とは別に民間の出版社から 『訳注本』
が出されているのが特徴的である。3-5-1-hの訳注本には,山口の直接法を支持推進し
た飯河道雄の 『対訳詳注中等日本語読本』(奉天東方印書館)(中略)がある。」と言っていた
が,同様のものとして 『対訳詳注初等日本語読本』があることもあわせて紹介しておこう。手
元のものは 「巻三巻四」で 「二年生ニナリマシタ」の本文から始まるので今で言う小学校二年
生用のものである。もちろん飯河の手によるもので出版社も同じ,「昭和六年二月二十一日初
版 康徳五年三月十日廿四版」であるOどうやら 「中等教育用教科書」のみに 「訳註本」があ
るかのような記述は検討 しなおさなければならない。
大出の著書ではないが 『国民学校対訳精解日語国民読本巻-』という本も手元にある。奥付
によると 「康徳八年一月十日印刷 康徳八年四月十日発行 訳解者任重遠 発行所大陸書局」
である。奥付の署名は 「国民学校対訳精解日語国民読本重量宣巻-」となっている。まさしく
「虎の巻」「教科書ガイド」である。「国民学校」の 「読本巻-」なので小学校一年生というこ
とである。内容も中段の 「トリ」に上段の新出単語として 「鳥,雀」を,下段の全訳に 「鳥」
を付 したものである。むしろこの中国語が理解できるかどうか心配になるところではある。こ
のような参考書が出版されていたことを考えると,戦後の日本で雨後のたけのこのように英会
話の本が出版されたが,それと同様の現象が当時の満洲にあったのか否か,日本語教育を地元
の人々がどう受けとめていたのか,いわば 「教育される側」の実態を知る必要を感じる。その
一つの手がかりとはなるだろう。
私はかつて,日本統治下の台湾においてこの種の 「虎の巻」「教科書ガイド」や中等学校-(LZ)
の受験準備書が多く出版されていたことを指摘 したことがあるが,そのことは 「公学校」(日

大出正篤の 「対訳法」に基づく日本語教科書 31
本統治下の台湾での台湾人児童のための初等教育機関)での勉強を意義あるものと認め,かつ
中等教育をも目指そうとする経済的に余裕があり,植民地教育とはいいながらそこで教えられ
る近代的学問を出世の手段ととらえる階層が存在していたことを証明することになる。
4.大出の独習用読本
大出には 『日本語趣味読本 正編』という著書もある。次にその本を紹介することにする。
手元の本は表紙に 『日本語趣味読本 正編 大出正篤著 満洲文化普及協会発行』とあり,奥
付には 「昭和九年七月五日印刷」「昭和十四年三月三十日五版発行」「総批発処 満洲図書文具
金ノ卵」「一〇,鼠ノ相談」「一四,司馬温公」「三二,桃太郎」「四〇,待チボオケ」「五五,
羽衣」がある。初級読解教材として適切な,イソップ寓話 ・中国の話 ・日本の昔話が採用され
ていることがわかる。各ページの中段には日本語の本文が漢字カタカナまじり文で提示され,
すべての漢字に振 り仮名が施されている。表記は次に掲げる 「緒言」を見てわかるように表音
式のものである。上段には重要語とその中国語での説明,下段には本文の全文中国語訳が書か
れている。「康徳元年五月」の 「緒言」を全文引用する。
一,日本語オ少シ習ッタ人二続イテ面白ク勉強シテ貰りタメニ作ッタ本デス。
マシタ。
一,ナルベク日本語 トシテ難シクナイヨオニ平易二書マシタ。仮名遣イワ最モ発音二近イ
モノオ便イマシタ。
一一,「教科書」 トシテモ 「副読本」 トシテモ,「自習書」 トシテモ,「オ話ノ本」 トシテモ
便エル ト思イマス。
-,コノ本二引続キー層面白イオ話オ集メテ 「続編」 トシテ発行スルソモリデス。
これはこれまで紹介されてきた大出の日本語教科書とは少し異なる本である。なぜなら冒頭
に多仁の文章から引用したように大出の 「『速成式教授法』は総ルビつきで全訳のついた教科
書で予習をさせておき,教室では教科書を離れて主に会話の練習を行うという対訳教授法の一
種であったo」からである。「自習書」「オ話ノ本」としての使用は教師の指導下の教室での学
習を前提としていないし,「副読本」としての使用も場合によっては教室での学習を欠 くか,
自学自習の占める部分を大きく想定するかだからである。「趣味読本」という書名も,楽 しく
読んで日本語学習を,という意図を示 している。事実,大出も 「面白イオ話バカリ探ッテ集メ
マシタ」とも 「一層面白イオ話オ集メテ 『続編』 トシテ発行スルツモリ」とも言っているわけ
だから。この点では,学習者の母語に頼る部分が多くなり,多仁の指摘のとおり 「直接法に固
執する人々から,この方法は予習の段階で母国語を使用するので,『母国語の常用』に相当し,
有効性を疑問視されていた従来の対訳法と同列のものであるとして,排斥の理由にされた」と
しても当然である。ただ,学習者によっては,「日本語 トシテ難シクナイヨオニ平易二書」か
れた日本語の文章を読み進んでいく教材として利用したとも考えられる。その点では,現在も
ある制限された語桑 ・文型で初級 ・中級の読解教材を作成するという方法と同じ流れにあるも
のとも言えよう
この本の巻末には 『国民優級学校日語国民読本訳注本 巻-』の巻末同様,広告が載ってい

32 天 理 大 学 学 報
る。先ほどのと重複するのは省き,重複しないもののみ掲載する。
『国民高等学校師道特修科 日本語読本 (訳註本)巻-』
『師道学校女子師道学校 日本語読本 (訳註本)巻-』
『国民優級学校日語国民読本 訳註本 巻11
関が 「大出の 『国民学枚女子国民学校用師道特修科用日本語読本訳注本』(満州文化協会発
行)がある。」と言っていたことに対 して先に疑問を述べておいたが,上記の 『国民高等学校
師道特修科 日本語読本 (訳註本)巻-』のこと,またはそのシリーズ本のことではないか。
つまり 「国民高等学校」の 「高等」を抜かして紹介したのではないか0「師道特修科」とは師
範教育 ・教員養成のことであろう。そのような学校が 「国民学校」のような初等教育機関と同
等の教科書を使用するはずがない。
なお,『国民優級学校日語国民読本訳注本 巻-』の巻末では 『初等日語読本 訳註本 巻
-』『中等目語読本 訳註本 巻-』『目支対訳解註 日本語趣味読本』『日支対訳 実用日語
会話 仝』となっているが,『日本語趣味読本 正編』の巻末では 『初等 日本語読本 訳註
本』『中等日本語読本 訳註本』『日満対訳解註 日本語趣味読本』『日満対訳 実用日語会話
仝』となっている。
5.大出の影響下の日本語教科書
上記の日本語教科書の巻末の広告に 『民衆日本語課本 仝』というのがあった。それとほぼ
同名の本が手元にあるので次にそれを紹介する。表紙は 『民衆日本語課本 仝一冊』で,「昭
和十二年十二月十五日印刷 昭和十二年十二月二十日発行」,つまり初版である。奥付の 「著
作兼発行者」は 「北京崇文大街一九二号 大亜印書局編輯部 森川昇二」となっている。この
本に出てくる個人名は先ほどの 『国民優級学校日語国民読本訳注本 巻-』の 「発行者」のこ
の森川のみである。大出の教科書を扱う本稿でこの本を扱うのは奇異に感じられるかもしれな
いが,この本の巻末の広告が先ほど引用 した 『国民優級学校 目語国民読本訳注本 巻-』や
『日本語趣味読本 正編』の巻末の広告とほとんど同じものだからである。つまり 「大亜印書
局」や森川は北京を中心とする華北で大出の教授法に基づく教科書を発行し,大出に協力して
いたのではないか。同じく昭和12年発行の 『国民優級学校日語国民読本訳註本 巻-』での森
川の住所 (会社所在地)は 「奉天千代田通四〇番地」である。森川は奉天でも北京でも出版社
を持ち,大出の事業に協力していたようである。
内容を見てみる。まずカタカナを提示し,注音字母と発音の近い漢字で発音を示したあと,
カタカナを組み合わせて簡単な単語をカタカナと日本語の漢字表記で提示していくというもの
である。続いてすべて振り仮名を付した簡単な文を提示し,下段に中国語訳を記するというも
の。このスタイルで徐々にむずかしい文へと導いていく。まさしく大出の教授法である。
飯河道雄が 『速修日本語読本』を編纂し,大出の教授法を踏襲していたことは既に述べたが,
この森川も飯河と同じく大出の協力者だったのだろう。森川や 「大亜印書局」についての研究
は今後の課題である。

大出正篤の 「対訳法」に基づく日本語教科書 33
6.大出の教授法の今日的意義
現在広 く用いられている日本語教科書に 『みんなの日本語初級 Ⅰ』『みんなの日本語初級
Ⅱ』(スリーエーネットワーク)がある。本学国際文化学部アジア学科日本語コースでも,本
学日本語教員養成課程の 「日本語教育実習」をさせていただいている天理教語学院でも初級教
科書として採用されている。この教科書の 「本冊」は日本語だけであるが,「本冊 ・ローマ字
版」,各言語の 「翻訳 ・文法解説」が別に販売されている。「ローマ字版」は大出の振 り仮名に,
「翻訳 ・文法解説」は 「訳註」に該当するとしたら,まさしく大出の主張どおりの教科書であ
る。しかも 「教え方の手引き」もあるがそれを見ると実際の授業では直接法を用いることにな
っている。「絵教材」や 「導入 ・練習イラス ト集」まであるのだから。この教科書を使ってい
る私たち日本語教師は 「直接法」と思い込んでいるが,大出の 「対訳法」を日々実践 している
のではないか。
昭和十年代の 「直接法」「対訳法」論争は敗戦にともなう日本語教育の (一時的)停止によ
って終ったが,しょせんは多仁も言うように,「『日本語は日本語によってのみ教えられるもの
であります。外国語に依存 して真髄を掴ませようなど以ての外であります』(引用者注- 松(L3)宮弥平の言)とする直接法は (中略)皇国史観 と都合よく結びついていった」だけであり,
「『外地』や占領地での日本語教育は,直接法を主張する人々が教授法を精神論に結びつけた
から,純粋に語学教育上の効果を認めていく道を封印して しまった」結果に終った。現在は
「皇国史観」も 「精神論」も日本語教育の教授法に入り込むすきはない。今,あらためて大出
の教授法と教科書を見直し,日々の実践に結び付けていくq)が大出の後進たる私たち現在の日
本語教師のつとめだろう。そのためにこれからも過去の教科書の研究をはじめとして,日本語
教育史の研究を続けていかなくてはならない。
(ll)(付記)大出正篤の名前の読みは,木村宗男によると 「おおいでまきあっ」である。本稿の英
語題名はそれによった。
注
(1) 現在では,1985年に発行所を教育出版センター,発売元を冬至書房として発行された復刻版
を使用するのが便利である。この論争は以下のとおり。
第2巻第6号,
第2巻第6号,
第2巻第6号,
第2巻第7号,
第2巻第7号,
第2巻第8号,
1942年6月。大出正篤 「日本語教授の効果に就いての考察」0
1942年6月。益田信夫 「直接法と教材 (-)」。
1942年6月。日野成美 「対訳法の論拠」。
1942年7月.大出正篤 「日野氏の F対訳法の論拠』を読みて」0
1942年7月。益田信夫 「直接法と教材 (二)」。1942年8月。益田信夫 「直接法と教材 (≡)」。
第2巻第8号,1942年8月O山口喜一郎 「直接法と対訳法 (-)」。
第2巻第9号,1942年9月。山口喜一郎 「直接法と対訳法 (二)」。
第2巻第9号,1942年9月。堀敏夫 「速成日本語教授私見」。
(2) 多仁安代 『大東亜共栄圏と日本語』2000年,勃葦書房,18-19ページ。
(3) 「戦前期中国大陸における日本語教育」F講座日本語と日本語教育 15 日本語教育の歴史』
1991年,明治書院,138-139ページQ
これとほぼ同内容の記述が,駒込武 F植民地帝国日本の文化統合』(1996年,岩波書店)339

34 天 理 大 学 学 報
-340ページにもある。
(4) 第8巻第4号,岩波書店。この号は 「東亜に於ける日本語」の 「特輯」である。大出のこの
文章は,「満洲国」教育史研究会監修 『「満洲国」教育資料集成Ⅲ期 「満洲 ・満洲国」教育資料
集成 第10巻 教育内容 ・方法Ⅱ』(1993年,エムティ出版)に収録されている。
(5) この本は同じ表蓮でレベルの違うものも含めて何種類も刊行されたが,その一冊が (4)の
『「満洲国」教育資料集成Ⅲ期 「満洲 ・満洲国」教育資料集成 第10巻 教育内容 ・方法Ⅱ』に
収録されているo
(6) (3)の 『植民地帝国日本の文化統合』303ページ。
(7) (3)の 『植民地帝国日本の文化統合』341ページ。
(8) 「『満州』の教科書- 多様化教材の源流」『NAFL選書 13 日本語教育史』1997年,アル
ク,98-99ページo次の引用も同じ。
(9) 『日本語教育史研究序説』1997年,スリーエーネットワーク,161ページ。
(10) 『康徳四年十一月一日 学校令及学校規程 民生部教育司』。「満洲国」教育史研究会監修
『「満洲国」教育資料集成Ⅲ期 「満洲 ・満洲国」教育資料集成 第3巻 教育法規』(1993年,
エムティ出版)に収録されている。
(ll) (10)に同じ。
(12) 拙稿 「第二次大戦時 ・大戦前の日本語教育関係文献目録- 補遺4」『天理大学学報』199
韓,2002年。
(13) (2)の32-33ページ。次の引用も同じ。
(14) 日本語教育学会 『日本語教育事典』大修館書店,1982年,727ページ。







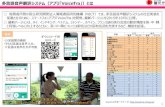








![[初習外国語インテンシブ] - kufs.ac.jp...翻訳通訳中国語Ⅳ 2 4 春 プレゼン中国語 2 4 春 速読中国語 2 4 秋 中国語資格検定試験(113ページ参照)](https://static.fdocument.pub/doc/165x107/5ec8acbf2de86909173c3934/ceffff-kufsacjp-ceeeea-2.jpg)