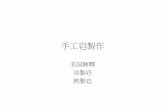加糖調製品をめぐる動向等について(補足説明)...2020/11/30 ·...
Transcript of 加糖調製品をめぐる動向等について(補足説明)...2020/11/30 ·...

加糖調製品をめぐる動向等について(補足説明)
令 和 2 年 1 1 月 3 0 日関 税 ・ 外 国 為 替 等 審 議 会関 税 分 科 会農 林 水 産 省
資料1-3

背景・課題 政策手段 効果 波及効果
○ 政策効果の検証
・ 加糖調製品について、TPP11交渉等の結果、10万トン程度の関税割当枠をはじめて設定
・枠内は無調整金、TPP11税率等に応じて関税を徴収・枠外は関税と調整金を徴収・関税割当枠のきめ細かい設定により、輸入量を管理
・消費者の小売価格の低下
<関税割当制度(輸入加糖調製品) >・ユーザーの調達価格の低下例えば、ソルビトール調製品では、枠内税率の引下げにより、枠内について約20円/kgの関税削減効果
◆輸入原料糖からの調整金・国内産の原料糖と競合する安い輸入原料糖のユーザー(受益者)から調整金を徴収し、それを財源としてダイレクトに国内産の原料糖との価格調整を機動的に実施・価格調整は調整金を財源とした交付金の交付により、さとうきび、てん菜と国内産の原料糖の生産・製造を支える◆国費の充当・調整金でも埋まらない生産・製造コストを補てん
・輸入原料糖の平均輸入価格に調整金単価を加えた調整金を輸入量に応じて徴収(毎年500億円程度)
・生産者・産地製糖工場のコストと販売価格の差額の算定により交付金を交付生産者:毎年400億円程度製糖工場:毎年200億円程度
・このほか、上記では埋まらない生産・製造コスト差を国費支援(毎年100億円程度)
・安い輸入原料糖と高い国内産の原料糖の価格差を調整
・交付金の交付により、国内産の原料糖の安定的な供給を実現
・さとうきびやてん菜の持続的な生産の確保、産地製糖工場の経営安定を通じて、代替作物の乏しい沖縄・鹿児島南西諸島や北海道の輪作地域の経済・雇用を維持
・精製糖企業など関連産業の健全な発展
・国内産の原料糖の安定供給を確保し、国民生活の安定に寄与
<糖価調整制度>
◆輸入加糖調製品から調整金を徴収し、国内の砂糖との価格差を縮小することを通じた糖価調整制度の安定運営。◆輸入加糖調製品と国内の砂糖の価格差の縮小を通じた国内の砂糖需要の確保及び菓子類などの加工食品を通じた国内外の需要拡大。◆産地における省力化や機械化、単収向上の取組、産地製糖工場の自動化設備等の省力化の取組など生産・製造コストの削減。◆生産者のみならず消費者やユーザーのニーズも踏まえ、甘味に関する情報交換等を通じて双方の立場の理解を深めつつ、国内産の原料糖の安定供給の確保が図られるよう努める。
<中長期的なあり方>
1
◆輸入加糖調製品からの調整金
・輸入加糖調製品と国内の砂糖には大きな価格差が存在・国内の砂糖と代替する安価な輸入加糖調製品から調整金を徴収し、さとうきびやてん菜の持続的な生産基盤を支える糖価調整制度の安定運営を図る
・消費者の国内の砂糖の小売価格の低下・安価な加糖調製品から国内の砂糖への需要の奪還・輸入原料糖と国内の砂糖の価格調整を行う糖価調整制度(輸入原料糖の調整金を財源として生産者等に交付金を交付する仕組み)の安定運営
・輸入加糖調製品からの調整金収入を財源とした輸入原料糖の調整金の軽減等により、国内の砂糖の価格を引下げ
・国内の砂糖価格の低下による国内の砂糖の競争力強化
・ユーザーの調達価格の低下輸入加糖調製品と国内の砂糖には、依然として大幅な価格差(25~55円/kg)
・国内の砂糖の競争力を向上させ、糖価調整制度の維持を図る
H30→R1 5円/kg程度輸入原料糖の調達コスト増がある中で、国内の砂糖価格引下げを実現
<糖価調整制度(輸入加糖調製品)>

○ 砂糖及び加糖調製品における需要構造の変化◆ 加糖調製品の輸入が平成2年に自由化されて以降、安価な加糖調製品の輸入量は大幅に増加。異性化糖の供給量は近年ほぼ横ばいで
ある中、加糖調製品が需要シェアを大きく伸ばしており、これが国内の砂糖の需要と代替していることは明らか。(輸入加糖調製品の甘味全体に占めるシェア:3% → 17%、砂糖:76%→57%)
◆ 特に、砂糖の最大の仕向先は菓子類(約26%)であり、輸入加糖調製品もその用途の大半が菓子類であり、砂糖と競合しており、代替関係が顕著。なお、異性化糖の菓子類への仕向割合(約2%)は低く、輸入加糖調製品が砂糖の需要を奪っていることで、需要シェアを年々拡大。
◆ また、加糖調製品の使用理由は、ほぼ全てのユーザーが製造原価(コスト)を抑えるためと回答。加糖調製品に含まれる砂糖と国内の砂糖との違いを消費者は認識できない中では、ユーザーにとっては価格のみが競争の源泉であり、加糖調製品の価格優位性は際立つ。これは、砂糖との強い代替関係を裏付けるもの。一方、国内の砂糖は品質が高いとされ、価格が下がれば使いたいというユーザーの声も存在。
◆ このように、中長期的にもコロナ禍の中でも輸入加糖調製品は砂糖との代替関係にあり、構造的に需要シェアを拡大している状況。特に、令和元砂糖年度は砂糖を含めた甘味需要の大幅減少となる中、国内の砂糖の需要量は対前年比約6%減、輸入加糖調製品の輸入量は対前年比約4%減となっており、安価な輸入加糖調製品の相対的な市場優位性は高まっている状況。
○ 加糖調製品の用途について(複数回答)
○ 加糖調製品を使用する理由について(複数回答)
出典:ALIC「食品メーカーにおける加糖調製品およびその他甘味料の利用形態」調査資料(H30年度)注:加糖調製品を使用する企業46社への調査。図中の「n」は有効回答数を表す。
76%257
76%259
75%255 74%
245 72%241
71%241
69%238 69%
232 68%226
67%225
67%224
67%224
66%221
66%223 65%
217 64%216 63%
210 63%212
63%214 63%
208 62%204
61%202 60%
197 60%197
60%195
59%191
59%192
58%189
58%186
58%184 57%
172
21%72
21%73 21%
71 20%67
22%74
21%73 21%
73 22%74 22%
74 23%76
23%76
22%74
23%76
23%77 24%
79 24%80 24%
79 24%80
24%82 24%
78 24%80 24%
81 25%81
25%83
25%81 25%
79 25%82 26%
83 26%83 26%
82 26%78
3%9
3%10 4%
14 5%17 6%
20 7%25
10%33 10%
33 10%33
10%34
10%35
11%36
11%36
11%39 12%
40 13%42 13%
44 13%44
13%43 13%
43 14%45
14%47 15%
50 15%51 15%
51 16%52
16%51
16%54 16%
53 16%52 17%
50
338 341 340 329 335 338 344 339 333 335 335 334 334 339 336 338 333 336 339 329 330 329 328 330 327 323 325 326 322 318
301
0
50
100
150
200
250
300
350
400
H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1
(万トン)
砂糖
異性化糖
加糖調製品
(SY)(実績見込み)
構成比数量
97%257
96%259 95%
255 94%245 92%
241 91%241 88%
238 88%232 87%
226 87%225
86%224
86%224
86%221
85%223 84%
217 84%216 83%
210 83%212
83%214 83%
208 82%204
81%202 80%
197 80%197
79%195 78%
191 79%192
78%189
78%186
78%184 77%
172
3%9
4%10
5%14 6%
17 8%20
9%25
12%33 12%
33 13%33
13%34
14%35
14%36 14%
36 15%39 16%
40 16%42 17%
44 17%44
17%43 17%
43 18%45 19%
47 20%50
20%51
21%51 22%
52 21%51
22%54 22%
53 22%52 23%
50
266 269 269 262 262 266 271 265 259 259 259 260 257 262 257 258 254 256 256 251 250 249 247 247 246 244 243 243 239 236 222
0
50
100
150
200
250
300
H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1
(万トン)
砂糖
加糖調製品
(SY)(実績見込み)
構成比数量
2出典:農林水産省「砂糖及び異性加糖の需給見通し」、財務省「貿易統計」 (SY(砂糖年度)とは、当該年の10月から翌年の9月までの期間)注1:加糖調製品の数量は、製品ベースの数量。2:異性化糖とは、主にとうもろこし由来のコーンスターチを原料としたぶどう糖と果糖が混合した液糖。主に清涼飲料の原料となる。3:四捨五入の関係で各項目の和が合計と一致しない場合がある。

92 86 92 83 78 76 83 71 80 85 79 72
83 86 90 91 83 79 85 87 85 65 67 68 68 73 81
68 78 73 78
166 174 169
158 161 167 158 159 149 146
146 147
140 144 130 127 128 132 127 122 126
135 137 131 127 123 116119
112 115 100
0
50
100
150
200
250
300
H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1
0
10
20
30
40
50
60
70
H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2
59円/kg(H23.1)
13円/kg(H12.3)
33円/kg(R2.9)
(円/kg)
0
20
40
60
80
100
120
H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2
(円/kg)
47円/kg(H17.1)
104円/kg(H3.1)
71円/kg(R2.9)
(単位:円/kg)H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1
輸入加糖調製品の価格
95~110 80~95 80~95 75~90 75~90 75~95 85~110 100~120 105~125 100~120 100~120 110~130 115~130 115~130 120~140 120~140 120~140 120~140 120~140 120~140 115~135
国内の砂糖の価格
120~160 105~145 105~145 105~140 105~145 110~145 120~155 125~165 130~165 135~170 145~180 150~190 150~190 145~185 150~190 145~190 145~195 150~200 145~195 145~195 140~190
価格差 25~50 25~50 25~50 30~50 30~55 35~50 35~45 25~45 25~40 35~50 45~60 40~60 35~60 30~55 30~50 25~50 25~55 30~60 25~55 25~55 25~55
○ 砂糖と輸入加糖調製品の各種データ ①
◆ 国内の砂糖と輸入加糖調製品との価格差を長期的にみると、現在と同水準か、海外の原料糖相場が高い時にはそれ以上の30~60円/kg程度と、以前から大きな価格差は存在し、現在も同程度の価格差がある。
◆ 国内産の原料糖の生産量は、30年前に比べ10万t程度減少。一方、砂糖の総需要が減少する中で、海外からの輸入原料糖も減少している状況。
○ 国内価格の推移
出典:輸入加糖調製品の価格はALIC調べを基に農林水産省地域作物課作成、国内の砂糖の価格は農林水産省地域作物課調べ (砂糖年度(当該年の10月から翌年の9月までの期間)ベース)注:輸入加糖調製品は、主要な例としてソルビトール調製品(含糖率80%程度)とした。
○ 原料糖の国際価格(NY原料糖先物価格)の推移
○ 輸入加糖調製品(ソルビトール調製品)の国際価格(平均CIF価格)の推移
出典:財務省「貿易統計」注:輸入自由化されたH2以前は現在の貿易コードと異なるため、欧米からの少量輸入のみの月の時に平均CIF価格が異常に高い場合がある。
出典:ロイターES時事、TTS相場(三菱UFJ銀行)
○ 国内産の原料糖生産量及び海外からの原料糖輸入量の推移
出典:農林水産省「砂糖及び異性加糖の需給見通し」
3
(実績見込み)
(万トン)
(SY)
国内産の原料糖生産量
原料糖輸入量

◆ 糖価調整制度では、国内産の原料糖と競合する安価な輸入原料糖等から徴収する約450~500億円と国費約100億円を財源とし、甘味資源作物生産者及び産地製糖工場におけるコストと販売価格の差額に対して交付金を交付するなど使途を明確にして支援。
◆ 産地製糖工場は、豊凶に応じて操業率が変化し、それにより製造コストも増減。省力化に向けた自動化設備の導入、人員配置の最適化等の取組を推進。
○ 砂糖勘定の収入と支出の流れ(イメージ※1)
○ さとうきび及びてん菜の交付金の推移(生産コストが販売価格を大きく上回ることから、その差額を交付金として交付)
○ 砂糖と輸入加糖調製品の各種データ ②
経営所得安定対策
糖価調整法に基づく支援
さとうきび生産者(約200億円)約2万戸
農畜産業振興機構(
)
精製糖企業等
調整金
交付金国庫納付金
生産者交付金
工場交付金 甘しゃ糖工場 (約100億円)てん菜糖工場 (約100億円)
てん菜生産者約7千戸
国費国
(約100億円)
(約450~500億円※2)
(約200億円)
(約200億円)
(約200億円)
ALIC
※1 毎年の豊凶変動等により、支出や収入が変動するため、概数(過去7年平均(平成24~30年度))を記載。2 令和元砂糖年度においては、調整金収入のうち約60億円が輸入加糖調製品からの収入。3 経営所得安定対策の交付金交付額は、てん菜の支払数量及び平均糖度を用いて概数(過去7年平均(平成24~30年度))として試算。
また、交付金交付額には国庫納付金分を含む。
H26 H27 H28 H29 H30
10a当たり交付金 (千円)
さとうきび 89 96 117 97 89
てん菜 54 55 47 50 50
1戸当たり交付金 (千円)
さとうきび 802 898 1,194 949 940
てん菜 3,734 4,026 3,290 4,064 3,994
原料1kg当たり交付金 (円/kg)
さとうきび 16 16 16 16 17
てん菜 7 7 7 7 7
出典:農林水産省地域作物課調べ
86 81 90 96 127 108 103 104 100 81
104 110
78 84
78 76
52 57 62 60
74
93
74 69
0
20
40
60
80
100
120
0
50
100
150
200
250
300
19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
製造コスト 操業率
(年産)
操業率
製造コスト
○ 甘しゃ糖工場の合理化状況(製造コスト・操業率の推移)
○ てん菜糖工場の合理化状況(製造コスト・操業率の推移)
60 62 63 78 68 70 69 63 59
72 61 64
104 103
88
74
85 90 82 85
94
75
92 85
0
20
40
60
80
100
120
0
50
100
150
19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
製造コスト 操業率
(年産)
操業率
製造コスト
出典:農林水産省地域作物課調べ (操業率=原料処理量(t) / (製糖日数(100日) × 公称能力(t/日)) )
出典:農林水産省地域作物課調べ (操業率=原料処理量(t) / (製糖日数(100日) × 公称能力(t/日)) )
○ 甘しゃ糖工場の整備状況・産地パワーアップ事業等を活用し、鹿児島県5島(種子島、奄美大島、喜界島、徳之島、沖永良部島)、沖縄県1島(南大東島)で施設整備を実施。
・沖縄県一括交付金を活用し、沖縄県4島(沖縄本島、久米島、南大東島、北大東島)で施設整備を実施。
○ てん菜糖工場の整備状況・原料中間受入場の開設:ホクレン中斜里工場において、中間受入場の開設を進めており、原料輸送車両の削減により、原料輸送効率を向上させることにしている。
4
(年産)
(約250億円※3)

◆ 諸外国と生産条件の格差により不利がある一部農作物を対象に、その生産費と販売価格の差額分に該当する交付金を直接交付。
◆ 品目により生産費や販売価格が異なるため、その差額を埋める交付単価の水準も品目ごとに異なる。
◆ 農家経営については、さとうきび作経営に比べ、てん菜作経営は規模が大きく、収入及び経営費は畑作経営の規模や豊凶に応じて異なってくる。
【交付単価のイメージ】
○ 他の農作物の状況と農家経営の状況(さとうきび作経営、てん菜作経営)
生産費
販売価格(品代)
交付単価差額
5
○ 他の農作物の状況
小麦(円/60kg)
二条大麦(円/50kg)
大豆(円/60kg)
でん粉原料用ばれいしょ(円/1t)
そば(円/45kg)
てん菜(円/1t)
さとうきび(円/1t)
生産費 9,490 9,100 20,240 22,090 28,920 17,720 22,250
販売価格 2,780 2,320 10,310 8,530 15,750 10,880 5,390
交付単価 6,710 6,780 9,930 13,560 13,170 6,840 16,860
出典:農林水産省「畑作物の直接支払交付金(ゲタ対策)の数量単価の改定について」、さとうきびについては農林水産省地域作物課調べ注1:単位は各農作物の量目(1俵)当たりの金額。でん粉原料用ばれいしょ、てん菜、さとうきびは1t当たりの金額。2:上記の交付単価について、小麦~てん菜は令和2~4年度までのもの、さとうきびは令和2砂糖年度のもの。
注3:生産費には消費税率改定への対応分を含む。小麦、二条大麦、てん菜及びさとうきびの販売価格には、TPP11・日米貿易協定等対応分を含む。
○ 農家経営の状況(さとうきび作経営、てん菜作経営)
(単位:千円/経営体)H26年 H27年 H28年 H29年 H30年
さとうきび作経営(沖縄)
農家収入(農業粗収益)
1,422 1,589 2,162 2,729 2,476
農業経営費 1,067 1,249 1,343 1,427 1,592
てん菜作経営(北海道)
農家収入(農業粗収益)
37,922 41,018 37,755 41,635 37,881
農業経営費 25,362 27,578 27,161 26,683 25,568
出典:農林水産省「農業経営統計調査(営農類型別経営統計)」を基に農林水産省地域作物課作成
注1:さとうきび作経営(沖縄)は、畑作経営の中で、さとうきびの販売収入が農業販売収入全体の10%以上を占め、かつ麦類、大豆、かんしょ、ばれいしょ、茶及びさとうきびの販売収入のうちさとうきびの販売収入が上位2位までの経営体が集計対象。平成30年をみると、集計経営体数78戸、畑作作付延べ面積215.4a、さとうきび作付面積213.6a、月平均農業経営関与者(農業経営主夫婦及び年間60日以上当該経営体の農業に従事する世帯員である家族)数は1.84人。
2:てん菜作経営(北海道)は、畑作経営の中で、てん菜の販売収入が農業販売収入全体の10%以上を占め、かつ麦類、大豆、小豆、いんげん、ばれいしょ及びてん菜の販売収入のうちてん菜の販売収入が上位3位までの経営体が集計対象。平成30年をみると、集計経営体数118戸、畑作作付延べ面積2,983.8a、てん菜作付面積832.5a、月平均農業経営関与者数は2.61人。
3:農家収入には畑作物の直接支払交付金、甘味資源作物交付金を含む。
4:農業経営費には家族労賃は含まない。交付金算定に用いる生産費には家族労賃を含むため、農業経営費とは一致しない。
5:さとうきび作経営(沖縄)の農家収入の内数としての交付金は、本経営体を対象とした集計値はないが、P4の1戸当たり交付金として平成26年は約802千円、平成27年は約898千円、平成28年は約1,194千円、平成29年は約949千円、平成30年は約940千円と推計。
6:てん菜作経営(北海道)の農家収入の内数としての交付金は、麦類、大豆、でん粉原料用ばれいしょ、てん菜の畑作物の直接支払交付金全ての合計値として、平成26年は約10,985千円、平成27年は約13,368千円、平成28年は約10,440千円、平成29年は約12,936千円、平成30年は約10,945千円。