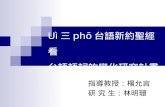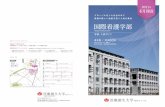業務改善に取り組む看護師長の暗黙知 -...
Transcript of 業務改善に取り組む看護師長の暗黙知 -...

67日看管会誌 Vol. 13, No. 1, 2009
The Journal of the Japan Academy of Nursing Administration and Policies Vol. 13, No. 1, PP 67-75, 2009
資料
業務改善に取り組む看護師長の暗黙知Tacit Knowledge of Nurse Manager Working to Improve Nursing Services
寺島ひとみHitomi Terajima
Key words : Tacit Knowledge, Nursing Service improvement, Nurse Manager, Nursing Management
キーワード : 暗黙知,業務改善,看護師長,看護管理
AbstractThe objective of this study is to examine the types of tacit knowledge that nurse managers
accumulate through their experiences and then actually practice to improve nursing services on the wards. Participant observation and semi-structured interviews were conducted with three nurse managers working at Hospital A, and the data were analyzed qualitatively to explore their insights and intentions about nursing services. Eight categories and twenty-two subcategories were distilled from the data. This paper describes nurse managers’ tacit knowledge, which is the “key to change”, used to implement effective nursing services. Integrating the staff’s capabilities and the insights of patients and their families to acknowledge needs, nurse managers made the best use of the “key to change” to generate and enhance nursing services. This demonstrated knowledge leaders’ wisdom when promoting innovations, and enabled them to improve nursing services while coping with changing nursing environments.
Results from analyzing distributions of the data showed that subjects tended to supervise the staff, and not to delegate authority in the supervision of chief clerks. This finding suggests that it is necessary for nurse managers to attend to matters beyond the wards, and to engage the whole organization in nursing service improvement.
要 旨
本研究の目的は,看護師長個人が,病棟の業務改善に対処するためにその経験を通してどのような暗黙知を蓄積し,使っているのかを明らかにすることである.A 病院に勤務する 3 名の看護師長を対象に,参加観察と半構成的面接法により業務改善における意図や考えを,質的に内容分析した.その結果,8 つのカテゴリーと,22 のサブカテゴリーを抽出した.本論文では,看護師長の業務改善を効果的に実践していく中で用いられていた暗黙知である【変化につながる鍵】について詳述した.【変化につながる鍵】は,看護師長がスタッフの生み出す効果的な力量とニーズの発見につながる患者や家族からの声を用い,自分の行動によってその場を生成・活用させるものであった.それは変革につながるナレッジ・リーダの知を表すもので,看護を取り巻く環境の変化に対処できる業務改善を可能にするものであった.
記録単位数の分布から,看護師長はスタッフを管理する傾向にあること,係長に対して積極的な権限委譲が行えていないことが推測された.このことから看護師長は,より病棟の外に目を向け,組織で業務改善に取り組むことが必要であることが示唆された.
受付日:2008 年 4 月 15 日 受理日:2009 年 2 月 6 日元 大森赤十字病院 Former Omori Red Cross Hospital

68 日看管会誌 Vol. 13, No. 1, 2009
Ⅰ.研究の背景
医療制度における構造改革,診療報酬の改定,国民の医療に対するニーズの高まりなど,医療を取り巻く環境は変化している.看護管理者は,そのような環境の変化に対応しながら安全で質の高い看護を提供することが求められている.そのため看護師長は,範囲の広さや種類の多さが医療職の中でも群を抜く(川島,1993)といわれる看護業務を常に見直していくことが,重要な役割となっている.
経営の分野において,1990 年代,企業における競争優位の源泉としての知識への関心が高まり,ナレッジ・マネジメントについて議論されるようになった.Nonaka&Takeuchi(1995)は,20年以上に及ぶ日本企業のイノベーションにおける過程から,企業における競争力の源泉として知識
(knowledge)をあげた.彼らは,既存の知識を活用するだけでは変革につながらず,個人に蓄積された暗黙知を共有し組織の知識に変換することが重要であるという組織的知識創造理論を展開した.その中で,個人の知識を共有するためには暗黙知を明らかにすることが必要であると述べている.
看護師長は日々の実践における経験を通してさまざまな暗黙知を蓄積している.しかし,ひとつのユニットを一人で管理することが多いため,実践の中で他の看護師長とその知を共有することは難しい状況にある.実践の中で使われている暗黙知を他の看護師長と共有するためには,形にすることが必要であると考える.看護師の実践の中にある知を明らかにする研究は数多く報告されているが,看護師長に焦点をあてた研究はまだ少ない.そこで,医療を取り巻く環境に対処していくために必要な業務改善に着目し,その中にある看護師長の暗黙知を明らかにする研究に取り組んだ.
Ⅱ.目的
本研究の目的は,看護師長個人が,病棟の業務改善に対処するためにその経験を通してどのような暗黙知を蓄積し,使っているのかを明らかにすることである.
Ⅲ.用語の定義
暗黙知:個人の経験を通じて獲得された知識で,看護師長が保有・活用しているが言語化が困難またはされていないために経験的にしか伝えたり共有したりすることができないもの.
Ⅳ.研究方法
1.データ収集期間データ収集期間は,2006 年 6 月末から 8 月末の約
2 ヶ月間であった.
2.研究参加者研究参加者は,関東圏にある A 病院に勤務し,
入院病棟を担当している看護師長である.A 病院は,19 の診療科と約 350 の病床数を持つ
二次救急指定病院で,在院平均日数約 14 日,病床利用率は約 81% である.看護単位数は外来,手術室・中央材料室,7 病棟の 9 単位で,看護配置は 10 対 1,看護職員数は約 230 名である.2006 年 4 月よりオーダリングシステムを開始し,その後電子カルテの順次導入や DPC の導入に向けてさまざまなプロジェクトチームが結成され活動していた.
3.データ収集方法データ収集は,参加観察と半構成的インタビュー
によって行った.参加観察は週に 2 回,日勤帯(8:30-16:50)の時間
の中で,2 ~ 4 時間看護師長と一緒に行動しながら観察を実施した.観察の場所は病棟内を中心としたが,患者のプライバシーに配慮するため病室における観察は行わなかった.
インタビューは,参加観察において観察された中から業務改善に関すると思われる場面を抜き出し,その場面の確認,看護師長の行動の意図,業務改善における看護師長の考えなどについて自由に語ってもらった.場所はプライバシーが守られる個室で行った.インタビュー内容は,研究参加者の了承を得た上でエム・ディー(Mini Disk)に録音した.

69日看管会誌 Vol. 13, No. 1, 2009
4.データ分析方法研究参加者が語ったインタビュー内容から逐語録
を作成し,データとした.内容分析(Krippendolff,1980)を参考にして質的分析を行った.作成した逐語録から,意味のある文節ひとつひとつの記録単位ごとに切り取り,全てを Excel に入力し「各単位はコード化し,分析可能な形態に変換」(Krippendolff,1980)する方法をとった.その後「分析対象とする記述を意味内容の類似性に従い分類し,その分類を忠実に反映したカテゴリーネームをつける」(舟島,1999)ことを行い,各カテゴリーに包含された記録単位の出現頻度を数量化し,カテゴリーごとに集計した.
データ分析の妥当性を高めるために,定期的に研究指導者のスーパーバイズを受けた.
5.倫理的配慮本研究は日本赤十字看護大学における研究倫理審
査委員会における承諾と,研究参加施設における倫理審査委員会の承諾を以って開始された.研究参加者には口頭と文書により研究の趣旨を説明し,同意を得た.研究の参加は自由であり,辞退による不利益は生じないこと,途中での参加辞退が可能なことを予め約束した.また,全て個人が特定されることはなくプライバシーの保護に努めること,研究の結果は学会などで発表する可能性があることも伝えた.得られたデータは,後日,研究協力者に逐語録の形にしてから内容について削除の有無を確認し,了解が得られた内容をデータとした.
Ⅴ.研究結果
1.研究参加者の概要研究参加者は A 病院に所属する看護師長 9 名の
うち,承諾が得られた 3 名であった.A 看護師長は 40 代前半,5 年の看護師長経験を
持つ.担当していた小児・産婦人科病棟は 60 床で,2 つのチームに分け看護を実践していた.安全を確保するためにスタッフ同士の連携強化を課題としていた.また,病棟独自に患者からアンケートを集め,病棟内の環境整備やハード面の改善に取り組んでいた.
B 看護師長は 50 代前半,9 年の看護師長経験を持つ.担当していた内科系病棟は 60 床で,患者は高齢者や重症者,入院期間が長期になる人が多い病棟であった.そのため看護師がやりがいをもって,患者に対して入院時から退院を見据え,一貫した看護を提供できるようになることを課題としていた.
C 看護師長は 40 代前半,6 年の看護師長経験を持つ.担当していた外科系病棟は 50 床で,毎日のように手術や処置が行われていた.緊急手術も頻繁に行われ,その度に部屋移動やスタッフの調整が行われていた.そのため,安全の確保が大きな課題となっていた.
2.データの収集時間参加観察の時間は合計 2,015 分で,平均は約 670
分であった.また,インタビューの時間は合計 293分で,平均は約 97 分であった(表 1).
3.分析結果逐語録から記録単位ごとに切り取った全数は
1,219 であった.それらをさらに意味内容の類似性に従い分類し,8 つのカテゴリーとそれらを構成する 22 のサブカテゴリーにまとめられた(表2).以下,カテゴリーを【 】,サブカテゴリーを<>,インタビュー内容を「 」で示した.1)カテゴリーの関係とその中から見えてきた現象
カテゴリーとして【変化につながる鍵】【スタッフへの介入】【パワーレスな状態】【看護師長のこだわり】【看護師長としての役割の模索】【スタッフの自律】【看護師長の試み】【看護師長の確信】が抽出された.これら 8 つのカテゴリーをインタビュー内容と照らし合わせて分析した結果,各カテゴリーの関係が見られた(図 1).
看護師長が業務改善に取り組んでいた病棟は【パワーレスな状態】であった.病棟は病院組織からの
表1 データ収集時間
参加観察 インタビュー
A看護師長 525分 108分
B看護師長 660分 91分
C看護師長 830分 94分
合計 2,015分 293分
平均 約670分 約97分

70 日看管会誌 Vol. 13, No. 1, 2009
トップダウンによる指示・命令が次々とおりてきている状況であった.スタッフはジレンマを抱きながら時間に追われるように仕事をし,実践した看護を振り返る余裕もなかった.看護師長は組織における役割が拡大する中で,病棟の管理を自分だけで抱えていくのは限界であるという思いを持っていたが,
【看護師長のこだわり】を原動力として業務改善に取り組んでいた.それはスタッフに対する思いと,自分が頑張ることによって病棟を良くしたいという思いであった.それを核として【スタッフへの介入】や【看護師長の試み】を実施していた.そして,看護師長は【スタッフの自律】というスタッフの変化と【看護師長の確信】という自信を獲得しながら業務改善に取り組んでいた.また【看護師長としての役割の模索】を行いながらそこで気付いたことを新
たな自分の役割として実践に結び付けようとしていた.このような中において,看護師長が業務改善において用いられていたのは【変化につながる鍵】という暗黙知であった.2)【変化につながる鍵】という暗黙知
【変化につながる鍵】は,4 つのサブカテゴリーによって構成された.(1).<スタッフの力量>:<スタッフの力量>は,
業務改善に取り組む際に,看護師長がスタッフに“任せられる”と認識する手がかりとなったものである.それはリーダシップを発揮できる,役割モデルが取れる,病棟の問題を感じることができるスタッフなどの存在であった.「(そのスタッフは)“そうなんですよ,私もすっごい感じるんですよ”っていう反応だったんですよ.
表2 抽出されたカテゴリーおよび構成される記録単位の数
カテゴリー サブカテゴリー 数 合計
a.変化につながる鍵 (1)スタッフの力量 145
(2)患者の声 96
(3)行動に移すタイミングを計る 65
(4)場を読むことで効果的な行動をとる 63
369
b.スタッフへの介入 (1)スタッフをコントロールする 115
(2)スタッフが抱く抵抗感を和らげる 71
(3)スタッフに関心を示す 64
250
c.パワーレスな状態 (1)多忙を極めた病棟 125
(2)看護師長の感じる限界 74
(3)スタッフの抱えるジレンマ 31
230
d.看護師長のこだわり (1)スタッフに期待 82
(2)看護師長の強い思い 67
149
e.看護師長としての役割 (1)他病院の看護管理者との情報交換 41
の模索 (2)継続教育の機会 35
(3)スタッフからの評価 14
90
f.スタッフの自律 (1)患者の希望に添える看護の実践 34
(2)自ら行動できる 23
57
g.看護師長の試み (1)病棟を超えた協力体制の試み 28
(2)病棟内の看護体制の変更 14
42
h.看護師長の確信 (1)看護に対する自信 14
(2)ちょっとした工夫でどうにかなる 12
(3)スタッフに任せた方がいい 6
32
合計 1,219 1,219

71日看管会誌 Vol. 13, No. 1, 2009
実際に自分が夜勤をいっぱいやっている中で,恐いって思っていてくれんたんですよね.だから,任せちゃいましたね.」「その任せたスタッフは,看護のやりがいっていうのを後輩に伝えたいって思っている人なんですよ.看護の良さ,看護の楽しさっていうのはこんなところにあるんだよみたいなのを話せる人だったので.」
また,スタッフの能力を活用することは業務改善に効果的であるという経験も,スタッフに任せたほうがいいという認識につながっていた.「私なんかの意見より,スタッフが提案したものの方が患者さんに近いんだっていうことが分ってきて,依頼もできるし.」「当初,私と係長でやってたんですが,それをスタッフに任せて,もっと細かいところまで改善できるようになって,これはよかったですね」
看護師長は,スタッフを観察したり意識的に話す場を作ったりして彼らの考えを把握し,業務改善を任せられるという認識から行動へとつながっていた.(2).<患者の声>:<患者の声>は,患者や家
族から言われる意見やクレームとは,ナースが求められていることを表す重要なものだととらえている看護師長の認識である.
看護師長は,意見やクレームをもらうことをマイナスの体験として受け止めるのではなく,変化へのチャンスであるととらえていた.また,積極的にその声を集めることによって病棟を改善するためのエッセンスをその中から探し出そうとしていた.「患者さんからの要望だとかクレームだとかは,本当にナースが何をすべきかっていうことを求められているそのものだと思うから,そのことが何なのかっていうのはやっぱりスタッフと一緒に考えていかななければならないとは思っているんだけれども.」「患者さんからのクレームだとか意見だとか,たくさんやっぱり,ラウンドをしている中では,たくさん聞こうと思っているのと,ひとつはクレームを強みに変えていかなきゃならない内容だから,クレームをもらったときこそやっぱりチャンスだと思って ・・・」(3).<行動に移すタイミングを計る>:<行動
に移すタイミングを計る>は,看護師長が効果的に
スタッフの抱えるジレンマ 多忙を極めた病棟 看護師長の感じる限界
�看護師長の試み�病棟内の看護体制の変更病棟を超えた
協力体制の試み
�看護師長のこ����スタッフに期待看護師長の強い思い
�変�に�ながる��スタッフの力量 患者の声
行動に移すタイミングを計る
場を読むことで効果的な行動をとる
����レスな���
�看護師長の�信�看護に対する自信スタッフに任せたほうがいいちょっとした工夫で どうにかなる
�看護師長とし�の��の���他病院の看護管理者との情報交換継続教育の機会スタッフからの評価
�スタッフ�の���スタッフをコントロールするスタッフが抱く抵抗感を和らげるスタッフに関心を示す
�スタッフの自��患者の希望に添える
看護の実践
自ら行動できる
図1 抽出されたカテゴリーの関係

72 日看管会誌 Vol. 13, No. 1, 2009
業務改善を進めるために,タイミングを計りながら行動に移すことや,時には自分が発案し方向性を示すという手段を表したものである.看護師長はスタッフの反応や人の異動など,病棟で起こった変化をタイミングとしてとらえ行動に移していた.「(看護方式を変えたのは)私が押し付けてのこう強引な変え方ではなくって,スタッフから意見もちょうど出た時期だったので,いいんじゃないかって進めたんですよね.」
スタッフの中で停滞している状況が見えたり,スタッフの能力がまだ不足していると判断した時は,自ら行動することによって方向性を示し,軌道修正を行っていた.「(病棟にある問題を)分かった上で情報を取り合おうという意識が低かった.みんなが共有してないんじゃないのって言ったら,“うーーん”っていう感じで.じゃあさ,そこ決めちゃおうよっていう感じでもっていったんですけどね.」「薬のインシデントがあったときから,やっぱりある時期自分がちゃんと目で確認しないといけないんだなっていうことがあった ・・・ ずっとやっている必要もないだろうけど,ある意味やっぱりね意識が高まるまでは直接関わりにいくことも必要かもしれない」(4).<場を読むことで効果的な行動をとる>:<場を読むことで効果的な行動をとる>は,看護師長が病棟や組織に流れるその場における状況を感じ取り,効果的に働きかけをしようとしているというものであった.それは相手によって自分の行動を変えたり,自分の役割を柔軟にしたりして,相手や状況にあわせた行動をとろうとしていたものであった.また,トップダウンによる方針は時に「曖昧なところがある」と語られたように中途の状態で病棟に流れてくることがあり,そのため看護師長はあらかじめその動きを察し,行く末を見守り,現状のやり方が決定なのか見極めることで,それに流されてしまうことなく対応していた.「どういう方法で流そうかって思うし,まあ,○○課のほうもこれで形決めているのかどうか曖昧なところもあるので,ちょっと今のうちは私がやって.はっきりするまではね,もうちょっと私がやっておこうなんて思っているのね.」
また,看護師長が病棟内の看護体制の変更を決定した場面では,「同じ病棟でありながらチームが違
うと,まるっきり他人だったりして.夜勤やるたびに苦情が出たりとか・・・人にお任せっていう意識が抜けない」という病棟の状況を読むことで行動していた.
これら 4 つのサブカテゴリーは業務改善に関する場面の中で単独ではなく,複数のサブカテゴリーが存在していることもあった.例えば,<行動に移すタイミングを計る>という場面では「暗黙の了解でやっているつもりになってた」という病棟スタッフの中にある行動を読み,スタッフが停滞していると判断したタイミングで看護師長が提案をしていた.<スタッフをコントロールする>という場面の中では,スタッフの中にどこかずさんなところがあるという病棟の雰囲気を読み,薬のインシデントがあったというタイミングで自分の目で確認するという行動を決断していた.<患者の希望に添える看護の実践>の場面では,患者の声を活用したことで「臨機応変というか融通を利かせられるようになった」という看護師長が“任せられる”としたスタッフの姿をとらえ,そのことが業務改善を任せることにつながっていた.<病棟内の看護体制の変更>の場面では,スタッフの姿から受け持ち患者に対する意識が持てていないと読み,スタッフが大きく入れ替わったタイミングでリーダー制の廃止をしていた.<スタッフに任せたほうがいい>という場面では,患者の声によって今まで自分が気付かなかったスタッフの姿に気が付き,一層スタッフの力量を活用することにつながっていた.このようにさまざまな場面において 4 つのサブカテゴリーが存在し,看護師長は日常におけるスタッフとの関わりや,患者家族との経験の中から獲得された<スタッフの力量><患者の声>を活用し<行動に移すタイミングを計る><場を読むことで効果的な行動をとる>ことによって業務改善に取り組んでいた.
以上のことから,業務改善の実践の中で活用されていた【変化につながる鍵】という看護師長の暗黙知の存在が示された.3)カテゴリーの分布カテゴリーは全て【パワーレスな状態】にある病
棟の中に含まれるものであった.業務改善の取り組みの中で看護師長から抽出されたサブカテゴリーを,スタッフ・看護師長・病棟・患者の 4 つに分けた(表 3).

73日看管会誌 Vol. 13, No. 1, 2009
スタッフに関するものは<スタッフの抱えるジレンマ><スタッフに期待><スタッフの力量><スタッフをコントロールする><スタッフが抱く抵抗感を和らげる>など,10 のサブカテゴリーであった.データ数の合計は 585 で,全データの 48.0%を占めていた.看護師長に関するものは<看護師長の感じる限界><看護師長の強い思い><行動に移すタイミングを計る><場を読むことで効果的な行動をとる><他病院の看護管理者との情報交換>など,10のサブカテゴリーであった.データ数の合計は 413で,全データの 33.9% を占めていた.病棟に関わるサブカテゴリーは<多忙を極めた病棟>の 1 つで,データ数は 125 で全体の 10.3%であった.患者について語られたものを表すサブカテゴリーは<患者の声>の1つで,データ数は 96 で全体の 7.8% であった.係長に関するデータは存在していたが,サブカ
テゴリーとしては抽出されなかった.
Ⅵ.考察
1.変革につながる業務改善における看護師長の知【変化につながる鍵】は,【看護師長のこだわ
り】という組織や職業に対して抱いている思いと,スタッフと共に自分が頑張ることによって病棟を良くしたいという思いからうまれたものであった.Polanyi(1958)は,人が知識を獲得できるのは,経験を能動的に形成,統合するという個人の主体的な関与によってであるとし,そこには自己投出すなわちコミットメントが必要であるとしている.これは Polanyi において重要な概念である.Nonaka&Takeuchi(1995)もまた,個人の価値体系
表3 抽出されたサブカテゴリーの分布
サブカテゴリー 数 合計 出現率
スタッフに関わる スタッフの力量 145
サブカテゴリー スタッフをコントロールする 115
スタッフに期待 82
スタッフが抱く抵抗感を和らげる 71
スタッフに関心を示す 64
患者の希望に添える看護の実践 34
スタッフの抱えるジレンマ 31
自ら行動できる 23
スタッフからの評価 14
スタッフに任せた方がいい 6
585 48.0%
看護師長に関わる 看護師長の感じる限界 74
サブカテゴリー 看護師長の強い思い 67
行動に移すタイミングを計る 65
場を読むことで効果的な行動をとる 63
他病院の看護管理者との情報交換 41
継続教育の機会 35
病棟を超えた協力体制の試み 28
病棟内の看護体制の変更 14
看護に対する自信 14
ちょっとした工夫でどうにかなる 12
413 33.9%
病棟に関わる 多忙を極めた病棟 125
サブカテゴリー
125 10.3%
患者に関わる 患者の声 96
サブカテゴリー
96 7.8%
合計 1,219 1,219 100%

74 日看管会誌 Vol. 13, No. 1, 2009
に深く根ざしたコミットメントや信念を,組織的知識創造理論の重要な基礎であることを述べている.
【看護師長のこだわり】はまさに組織や職業に対するコミットメントであり,【変化につながる鍵】は看護師長が経験を能動的に統合した結果として獲得されたものであるといえる.
業務改善をスタッフに任せていた看護師長は,スタッフが持っている力を発揮できるような場所の設定をしたり,意見を取り上げたりしていた.野中,紺野(2003)は「新たなリーダーの役割は,ナレッジワーカーを理解し,彼らの生み出す内部価値を最大化すること」であると述べている.価値観が多様化してきたのは患者や家族だけではなく,スタッフも同様であると考える.看護師長が,スタッフの持つさまざまな教育背景や価値観を認識しないまま人材育成を行ってしまえば,彼らの生み出す内部価値を最大化することはできない.看護師長が日常の中でスタッフの反応などを注意深く観察し,スタッフとの関わりを通して一人ひとりが持っている色々な考えを理解しようとすることは,彼らの生み出す内部価値を最大化することにつながると考える.次に,看護師長は患者や家族からの意見やクレームを重要なものであるととらえ,業務改善を行っていた.企業においてフェイス・トゥ・フェイスで顧客と向き合う場を意識的に作ることは「顧客ニーズの吸収,顧客関係維持の媒介としても重要」(野中,紺野,1999)であるとされる.患者サービスの最前線に立つ看護師長が,患者の病室を訪問するなどして顧客となる患者や家族との接触の機会を持ち,集めた声を業務改善に活用することは,病院という組織の信頼に対処することにつながるものであると考える.さらに,看護師長はタイミングを計って行動に移したり,その場の空気を読み行動することで業務改善に対処していた.野中・紺野(2003)は,企業がイノベーションにつながる知識経営に向けた取り組みをするうえで,最も大切なのは知の共有と創造が行われる「場」の生成と活用であるとしている.そのためには知の媒介者となる人材が自律的に対話し,顧客やパートナーとの知の共創を行うという,知の変革を担うナレッジ・リーダーシップが必要であると述べている.【変化につながる鍵】は,看護師長がスタッフや患者と知の共有と創造を行い,自分がその「場」に対して働きかけることで場を生成・活
用して,業務改善を進めていくものであったといえる.そしてそれは,変革につながるナレッジ・リーダーの知を表すものであると考える.
看護や医療を取り巻く環境が変化する中,既存の知識・方法だけで行う業務改善では,患者・家族のニーズにあった看護を提供することは難しい.しかし,この変革につながる看護師長の知こそが病棟における業務改善を可能にし,これからも環境の変化に対処できる知であると考える.
2.実践を語りあうことで新たな知識を創造する本研究において抽出されたカテゴリーは,全て病
棟の中に含まれるものであった.患者について語られた内容は少なく,逆にスタッフに関わる内容が約半分のデータ量を持っていた.これは,看護師長がトップダウンによってさまざまな課題が与えられる現状の中で,患者よりもスタッフに意識を向け,管理を強めることで自分の病棟,自分のスタッフを守ろうとする内向きの力が働き,その結果,病棟を越え組織で取り組んでいくエネルギーにまで及んでいないことが考えられる.今田(2003)は,環境に適応していくための組織全体の変化の要因はメンバー一人ひとりで,その中におけるリーダーの役割は,管理しないことであると明言している.そして管理の強化によって構造は強化されるものの変化することはできずに取り残されてしまうと警告している.したがって,慎重のあまり管理を強める形になれば,それは変革につながらない可能性がある.また,業務改善を進める中において,係長に関するサブカテゴリーが作られなかった.このことから,看護師長が係長に対する権限委譲が十分に行えていないということが考えられる.Sullivan&Decker(2005)は,権限委譲は他の者の技能と能力を見出し,その者と信頼を築きあげることになることから,組織における調和を促進するツールにもなり得ると説明している.それによるマネジャーの利益はより多くの時間を得ることとし,マネジャーとしての新しい技能や能力を見出すことにつながるとしている.看護師長が係長に対して権限委譲を積極的に行うことは,人材育成の機会になると共に,看護師長としての役割を見出す時間を作り出すことになるのである.
Nonaka&Takeuchi(1995)による組織的知識創造理論は,既存の知識を模倣するのではなく個人に

75日看管会誌 Vol. 13, No. 1, 2009
留まっている暗黙知を表出・共有し,新しい組織の知識を創り出すことが重要であるというものである.看護師長は変化する環境の中で,どのような看護管理を実践しているのか,なぜスタッフへの介入が多くなってしまうのか,なぜ係長に対して権限委譲が行えないのかという現状を,看護師長同士で話し合う必要があると考える.フェイス・トゥ・フェイスで経験や思いを表出できる休憩室や,自分の考えを概念化しながらディスカッションを行う会議といった場の中で,自分たちの実践を語り合うことが個人個人に蓄積された暗黙知を共有する機会となり,それが業務改善に対処していくための課題や新しい組織の知識を創りだすことにつながっていくと考える.また,看護師長同士が実践を語り合うことによって,自分たちの周りに存在するパワーレスな状態を引き上げることにもつながるのではないかと考える.
Ⅶ.結論
1.業務改善に取り組む看護師長の暗黙知は【変化につながる鍵】であった.それは,スタッフが生み出す効果的な力量とニーズの発見につながる患者や家族からの声を用い,自分の行動によってその場を生成・活用させるものであった.それは変革につながるナレッジ・リーダーの知を表すもので,環境の変化に対処できる業務改善を可能にするものであった.
2.看護師長は,積極的に係長に権限委譲をすることで病棟の外に目を向け,組織で業務改善に取り組むことが必要であると示唆された.
謝辞:本研究をまとめるにあたり,ご指導頂きました
日本赤十字看護大学鶴田惠子教授に深謝いたします.ま
た,研究フィールドを快く提供いただきました A 病院
の皆様,ご協力いただいた 3 名の看護師長,病棟スタッ
フの皆様に心より感謝申し上げます.なお,本研究は,
2006 年度日本赤十字看護大学大学院修士論文の一部を加
筆修正したもので,第 11 回日本看護管理学会学術集会で
一部を発表いたしました.
■引用文献
舟島なをみ (1999) 質的研究の挑戦: 47,医学書院,東京.今田高俊 (2003) 自己組織化の条件: Diamond Harvard Business
Review,28 (3),88-101.川島みどり (1993) 看護業務改善の意義と専門職の視点: 看護展
望,18 (2),9-12.Krippendorff,K. (1980) /三上俊治,椎野信雄,橋元良明訳 (1989)
メッセージ分析の技法―「内容分析」への招待: 76,勁草書房,東京.
Nonaka,I.&Takeuchi,H. (1995) / 梅本勝博訳 (1996) 識創造企業: 85-87, 東洋経済新報社,東京.
野中郁次郎,紺野登 (1999) 知識経営のすすめ ナレッジマネジメントとその時代: 171,ちくま新書,東京.
野中郁次郎,紺野登 (2003) 知識創造の方法論 ナレッジワーカーの作法: 263,259-276, 東洋経済新報社,東京.
Polanyi,M. (1958) /長尾史郎訳 (1985) 個人的知識 脱批判哲学をめざして: 55-58, ハーベスト社,東京.
Polanyi,M. (1966) /佐藤敬三訳 (1980) 暗黙知の次元 言語から非言語へ: 紀伊国屋書店,21, 東京.
Sullivan,E.J.&Decker,P.J.(2005) Effective Leadership and Management in Nursing: 6th ed.,143-154, Prentice Hall,New Jersey