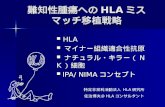「エミリーへのバラ」解釈の推移...邪知上佑:「エミリーへのパラ」解釈の推移 45 「エミリーへのバラ」解釈の推移 一E〕ゆ絢π餓r誌上論争を中心に一
発生主義への移行 - JICPA発生主義への移行 - 1 - 第Ⅰ節-序論 第Ⅰ節-序論...
Transcript of 発生主義への移行 - JICPA発生主義への移行 - 1 - 第Ⅰ節-序論 第Ⅰ節-序論...
-
2002 年 4 月
研究報告第 14 号
発生主義への移行 -政府及び政府主体のための指針-
日本公認会計士協会 公会計委員会 訳
IFAC
Public
Sector
Committee
Issued by the
International
Federation of
Accountants
-
- i -
国際会計士連盟
アメリカ合衆国 10017 ニューヨーク州ニューヨーク市
5番街 535 番地 26 階
Copyright©2002 により国際会計士連盟が著作権のすべての権利を所有している。
本刊行物のどの部分についても、複写・複製し、また電子的、機械的ないかなる形式また手段によっ
てでもそれを検索できるシステムに保存し、転送し、また写真電送し、記録を取るほかの行為をする
ことは、国際会計士連盟の事前の文書による許可なしで行うことはできない。
国際会計士連盟についての情報及び本研究報告のコピーは、ウェブ・サイト http://www.ifac.org で
見ることができる。
本研究報告の承認された本文は、英語で刊行されているものである。
本研究報告には、2002 年1月現在で発行されている国際公会計基準及び公開草案の議論が含まれてい
る。
謹 告
パブリックセクター委員会(PSC)は、国際公会計基準(IPSASs)の一式を作成中である。国際公会
計基準の当初の中心的な基準の一式は、国際会計基準委員会(IASC)により公表された国際会計基準
書(IASs)を基礎としている。国際会計基準審議会(IASB)及び国際会計基準財団(IASCF)は 2001
年に IASC に代わるものとして設立されたものである。IASC により発行された国際会計基準は、それら
が IASB によって修正又は撤回されない限り有効である。
IASC の国際会計基準、公開草案その他の刊行物に関する著作権は IASCF が有している。「IAS」、
「IASB」、「IASC」、「IASCF」及び「International Accounting Standards」は、IASCF の登録商標であ
り、IASCF の承認なくして使用してはならない。
IASs からの限定された引用又は抜粋は、IASB の了解の下に国際会計士連盟のパブリックセクター委
員会による本刊行物で再生されている。承認されている国際会計基準の本文は、英語版で IASB より刊
行されており、コピーは直接 IASB から得ることができる。IASB の連絡先は、英国ロンドン市 EC4A 2DY、
フリート通り 166 番地7階、IASB 出版局である。
E-mail アドレス: [email protected]
Internet: http://iasb.org.uk
-
- ii -
謹告
本研究報告は、国際会計士連盟のパブリックセクター委員会を代理して Public Sector Performance
(NZ)Ltd(http://www.pspnz.co.nz)により作成されたものである。
免責の表明
正確性の確保のためあらゆる努力が払われているが、Public Sector Performance(NZ)Ltd 及び Public
Sector Performance(NZ)Ltd の代表者若しくは従業員並びに国際会計士連盟は、いかなる当事者に対
しても本研究報告を使用することにより取られる意思決定又は行為に関して一切の責任は負わないも
のとする。本刊行物に含まれる情報は、個別の状況又は事情に関する勧告に代わるものとして取り扱
ってはならない。
-
- iii -
ごあいさつ
現在、現金主義により報告を行っている国々からの代表者を含めて、国際会計士連盟のパブリックセ
クター委員会の代表者の多くが、政府の財務報告に対する発生主義の適用に支持を表明しています。
この支持は、発生主義による情報は、現在提供されている現金主義の情報を含み、補完し、向上させ、
内部及び外部の財務諸表の利用者の双方に便益を与えるという見解に基づいています。また、これら
多くの代表者は、パブリックセクター委員会による現金主義から発生主義への移行プロセスに関する
指針を要求しています。本研究報告は、この要求に応えるために作成されました。研究報告は、現金
主義から発生主義への移行の過程で取り組むべき主要な問題を識別しています。また、研究報告は、
公的部門において、発生主義を効率的、かつ、効果的に実施するために適用できる代替的なアプロー
チについても識別しています。
パブリックセクター委員会は、発生主義又は現金主義のいずれかが採用される場合に適用されるべき
1組の中心的な国際公会計基準の作成に著しい貢献をして参りました。私は、2002 年の末には、パブ
リックセクター委員会は、発生主義に関する 20 の国際公会計基準、及び現金主義の1つの包括的な国
際公会計基準を発行しているだろうと予想しています。これらの国際公会計基準は、公的部門組織の
政府及びその他の機関のための1組の権威ある独立した国際的な財務報告基準を確立します。国際公
会計基準の適用は、意思決定、財務管理及び説明責任の改善に向けた公的部門の財務報告における発
展を支えることでしょう。パブリックセクター委員会は、国際公会計基準を社会及び経済発展の促進
を目標とした改革の不可分の要素であると考えています。
パブリックセクター委員会は、政府及び政府主体が、発生主義システムを実施するために必要とされ
る多くの、また、複雑な技術的なシステムや文化的な問題に取り組むに当たり、本研究報告が有用で
あることを認識するであろうと確信しています。研究報告は、国際公会計基準の重要な要求事項を識
別しています。また、研究報告は、国際公会計基準では、取り扱われていない論題に関して、その他
のソースの有用な指針も取り上げています。しかしながら、読者は、本研究報告は、新たな追加的な
権威ある要求事項を定めるものではなく、また、それが国際公会計基準自体に代わるものではないと
いうことに注意すべきです。研究報告は、「生きた資料」になること、及び更なる国際公会計基準の発
行がなされ、追加的な実施上の問題や経験が認識されるにつれて定期的に更新されることを意図して
います。
Ian Mackintosh
国際会計士連盟パブリックセクター委員会委員長
2002 年4月
-
- iv -
発生主義への移行: 政府及び政府主体のための指針
目 次
頁
第Ⅰ節-序論.............................................................. 1
第1章 緒論 .............................................................. 2
第2章 プロセス管理 ..................................................... 19
第3章 技能評価及び訓練 ................................................. 40
第Ⅱ節-全般的な財務報告問題 ............................................. 53
第4章 会計方針に関する問題 ............................................. 54
第5章 報告主体に関する問題 ............................................. 67
第Ⅲ節-財務構成要素..................................................... 79
第6章 資産 ............................................................. 80
第7章 負債 ............................................................ 125
第8章 収益及び費用 .................................................... 145
第Ⅳ節-特定論題........................................................ 162
第9章 現金 ............................................................ 163
第10章 無形資産 ........................................................ 175
第11章 金融商品 ........................................................ 186
第12章 従業員関連負債 .................................................. 196
第13章 社会政策債務から生ずる負債 ...................................... 210
第14章 非交換取引による収益 ............................................ 221
第15章 外貨 ............................................................ 232
補遺.................................................................... 238
付録1 パブリックセクター委員会基準プログラム資料の要約(省略)
付録2 国際公会計基準の定義用語集(省略)
-
- v -
IFAC COPYRIGHT AND ACKNOWLEDGEMENT FOR TRANSLATIONS:
Copyright © International Federation of Accountants
All standards, guidelines, discussion papers and
other IFAC documents are the copyright of the
International Federation of Accountants (IFAC), 545
Fifth Avenue, 14th Floor, New York, New York, 10017,
USA; tel: 1-212/286-9344, fax: 1-212/286.9570,
Internet http://www.ifac.org
All rights reserved. No part of this publication may
be reproduced, stored in a retrieval system, or
transmitted, in any form or by any means, electronic,
mechanical, photocopying, recording or otherwise,
without the prior written permission of IFAC.
The IFAC pronouncements in this volume have been
translated into Japanese by/under the supervision of
The Japanese Institute of Certified Public
Accountants and are reproduced with the permission of
IFAC. The approved text of all IFAC documents is that
published by IFAC in the English language.
翻訳に関する国際会計士連盟(IFAC)のコピーライト及
び承認について:
Copyright © International Federation of Accountants
すべての基準、ガイドライン、ディスカッション・ペ
ーパー及びその他の IFAC の文書に、IFAC はコピーライト
を持つ。
International Federation of Accountants(IFAC), 545
Fifth Avenue, 14th Floor, New York, New York 10017,
USA; tel: 1-212/286-9344, fax: 1-212/286.9570,
Website: http://www.ifac.org
すべての権利は IFAC が保有する。IFAC の書面による事
前許可なしに、本出版物のいかなる部分も、電子的、機
械的、写真複製、録音、その他のいかなる形態又はいか
なる方法によっても複製し、検索システムで保存し、又
は転送することは認められない。
IFAC の本公表物は、日本公認会計士協会公会計委員会
により日本語に翻訳されたものであり、IFAC の許可の下
に複製されている。承認されたすべての IFAC の文書の正
文は、IFAC により英文で公表されるものである。
-
発生主義への移行 - 1 -
第Ⅰ節-序論
第Ⅰ節-序論
本研究報告は、国際公会計基準に準拠して発生主義へ移行することを望んでいる政府及
び政府主体の手助けを行うことを意図したものである。また、研究報告は、国際公会計
基準公開草案第9号「現金主義による財務報告」から発展的に作成される将来の国際公
会計基準の主要な原則の採用を含めた包括的な現金主義により報告を行うことを望ん
でいる政府及び政府主体の手助けにもなるだろう。
本研究報告の第Ⅰ節は、移行の内容と速度に影響を与える要素、移行経路に関する選択
肢、及び移行プロセスの管理を含めた発生主義への移行に関係した全般的な問題を取り
上げる。また、研究報告は、識別、訓練の設計と実施に関連した問題も考察する。
本研究報告の主な目的は、発生主義へ移行し、発生主義に基づく国際公会計基準を順守
しようとしている主体の手助けを行うことである。また、研究報告は、現在の国際公会
計基準や公開草案で取り上げられていないいくつかの論題の議論も含んでいる。本研究
報告が、現在の国際公会計基準や公開草案で取り上げていない論題について議論してい
る場合、国際会計基準書などの他の権威ある会計上の公表された要求事項が、当該論題
に関連した実務的実施問題を説明するために使用されている。国際会計基準は、国際会
計基準委員会によって作成され公表されている。2001 年には、国際会計基準委員会に取
って代わるものとして、国際会計基準審議会が設立されている。国際会計基準審議会は、
それが発行する基準書について、国際財務報告基準(IFRS)という名称で呼ばれること
になるであろうと述べている。最初の 17 号までにわたる国際公会計基準は、公的部門
に適切である限りにおいて、国際会計基準を基礎にしている。これらの論題の説明に使
用される国際財務報告基準、国際会計基準又は他の基準書は、論題に関して必ずしもパ
ブリックセクター委員会の見解を反映するものではない。本研究報告は、会計マニュア
ルではなく、また、命令的な会計慣行や基準を確立することを試みるものでもない。
本研究報告は、進行中の作業として考慮されるべきである。研究報告は、国際公会計基
準の発展、また、発生主義による報告への移行における読者の経験についてパブリック
セクター委員会が得たインプットなどを反映して定期的に改訂されることになろう。
-
発生主義への移行 - 2 -
第 1 章
第1章:緒論
要点
• 本研究報告は、発生主義に基づく国際公会計基準に準拠して発生主義により報告
することを望んでいる政府及び政府主体の手助けとなるであろう。また、研究報
告は、国際公会計基準公開草案第9号「現金主義による財務報告」から発展的に
作成される将来の国際公会計基準の主要な原則の採用を含めた包括的な現金主
義により報告を行うことを望んでいる政府及び政府主体の手助けにもなろう。
• 研究報告には、パブリックセクター委員会によりまだ取り上げられていないいく
つかの論題も含め現在の発生主義による国際公会計基準で対象とされている論
題の議論を含んでいる。
• 本章は、政府による発生主義の採用に関連するいくつかの便益について要約して
いる。
• パブリックセクター委員会は、発生主義に移行する過程における経験について読
者からの情報提供を求めている。こうしたインプットは、本研究報告の今後の改
訂版に影響を与えるであろう。
はじめに
1.1 本研究報告は、国際会計士連盟のパブリックセクター委員会によって発行され
た。国際会計士連盟は、公共の実務、事業及び産業、公的部門及び教育の分野
に従事している会計士を代表する各国の職業的会計人の組織により構成される
組織である。パブリックセクター委員会は、会計、監査並びに中央政府、地域
及び地方の政府、関連する政府主体及びそれらが奉仕する選挙民の財務報告ニ
ーズに焦点を当てている。パブリックセクター委員会は、標準的な指針の発行
と推進、教育及び調査施策の実施、会計士及び公的部門の従事者の間での情報
交換の促進などによってこれらのニーズに取り組んでいる。
1.2 パブリックセクター委員会は、国際公会計基準に準拠して発生主義により報告
することを望んでいる政府及び政府主体の手助けをするために本研究報告を作
成した。パブリックセクター委員会は、発生主義へ移行する政府及び政府主体
のための実務的な指針及びそれを支える情報の必要性を認識している。本研究
報告は、この過程で要求される多くの課題の内容及び範囲を識別している。
1.3 本研究報告の指針には次の配慮を含んでいる:
-
発生主義への移行 - 3 -
第 1 章
• 発生主義への移行が生じ得る広範囲な背景の概観;
• 追加的な実施過程を選択する主体が採用することになるかもしれない様々な移
行経路の議論;
• 資産、負債、収益及び費用の認識に関連する主要な課題の認識(これらの構成要
素の識別及び測定に関係する論点も含めて);
• 発生主義に基づく国際公会計基準の採用についてのいくつかの関連問題;及び
• 他の主体又は法域の経験に基づく実務的提案
国際公会計基準
発生主義に基づく基準書
1.4 パブリックセクター委員会は、公的部門のための発生主義による財務報告に関
する一連の国際公会計基準を作成中である。現在発行されている基準書の本文
及び公開草案は、http://www.ifac.org で見ることができる。
1.5 本研究報告の主な目的は、発生主義へ移行し、発生主義に基づく国際公会計基
準を順守しようとしている主体の手助けを行うことである。また、研究報告は、
現在の国際公会計基準や公開草案で取り上げられていないいくつかの論題の議
論も含んでいる。本研究報告が、現在の国際公会計基準や公開草案で取り上げ
ていない論題について議論している場合、国際会計基準書などの他の権威ある
会計上の公表された要求事項が、当該論題に関連した実務的な実施問題を説明
するために使用されている。国際会計基準は、国際会計基準委員会によって作
成され公表されている。2001 年には、国際会計基準委員会に取って代わるもの
として、国際会計基準審議会が設立されている。国際会計基準審議会は、それ
が発行する基準書について、国際財務報告基準という名称で呼ばれることにな
るであろうと述べている。最初の 17 号までにわたる国際公会計基準は、公的部
門に適切である限りにおいて、国際会計基準を基礎にしている。これらの論題
の説明に使用される国際財務報告基準、国際会計基準又は他の基準書は、問題
に関して必ずしもパブリックセクター委員会の見解を反映するものではない。
本研究報告は、会計マニュアルではなく、また、規制的な会計慣行や基準を確
立することを試みるものでもない。
1.6 国際公会計基準が存在しない場合、個々の主体はその会計方針の作成の指針と
するため、他の適切な権威のある公表基準を適用することを要求される。パブ
リックセクター委員会は、一定の論題に関する一般に認められた会計慣行が法
-
発生主義への移行 - 4 -
第 1 章
域によって異なることを認識している。国際公会計基準第1号「財務諸表の表
示」は、経営者は、主体の財務諸表の利用者に対して最も有用な情報を提供す
る会計方針の作成に当たり判断を行使する必要性があるであろうと説明してい
る。国際公会計基準第1号は、経営者がこの判断を行う際の指針を提供してい
る。
現金主義に基づく基準書
1.7 また、パブリックセクター委員会は、国際公会計基準公開草案第9号「現金主
義による財務報告」を発行している。本研究報告の焦点は、発生主義への移行
に置かれているが、研究報告の一部分は、国際公会計基準公開草案第9号に基
づき作成された現金主義による国際公会計基準に準拠するために有用な情報を
求めている読者にも役立つであろう。本章の付録2は、国際公会計基準公開草
案第9号に準拠しようとしている主体のために本研究報告の特定の章との関連
性を説明している。さらに、第4章の付録2は、主体が国際公会計基準公開草
案第9号 1に準拠するために要求される会計方針を例示している。
指針の他のソース
1.8 公的部門分野の発生主義に関するパブリックセクター委員会の刊行物(国際公
会計基準、研究報告及び事例研究)の完全なリストは、国際会計士連盟のウェ
ブ・サイト(http://www.ifac.org)で見ることができる。研究報告第 11 号「政
府の財務報告」を含むこれらの多くの刊行物は、無料で電子的に見ることがで
きる。
1.9 国際公会計基準がまだ作成されていない論題について、本研究報告は、主体が
直面する可能性のある報告要求事項のタイプを例示するために国際会計基準又
は他の国の会計基準書を使用している。これは、必ずしもこれらの論題に関し
パブリックセクター委員会が熟慮した結果の立場を示すものではない。これに
ついては、国際公会計基準第1号の説明文が指針の階層関係を設けていること
に注意すべきである。特定の論点に関し国際公会計基準が存在しない場合、主
体は、最初に、類似した関連する論点を取り扱っている他の国際公会計基準、
1 国際公会計基準が追加発行されるにつれ、現金主義に対する一定の会計上の問題の影響が考慮され、
最終的には、国際公会計基準公開草案第9号(又はその後の国際公会計基準)を基にした国際公会
計基準及び現金主義の下で要求される開示事項の改訂に至ることになるかもしれない。
-
発生主義への移行 - 5 -
第 1 章
国際会計士連盟のその他の刊行物、その他の基準設定機関の公表基準書(例え
ば、国際会計基準など)、又はそれらが国際公会計基準と一貫性がある限りにお
いて認められている公共又は民間部門の実務を参照すべきである。
1.10 可能な限り、情報源のウェブ・サイトの参照先を提供している。様々な法域及
び主体の財務報告に関する情報を含んだウェブ・サイトの一覧表は、本章に付
録1として添付してある。
研究報告の構成
1.11 現金主義から発生主義へ移行するには多様な経路が考えられる。本研究報告は、
主体がどのような移行経路を考慮している場合にも読者にとって有用であるよ
うに意図して構成されている。また、研究報告は、資産及び負債に関して現在
利用できる情報及びその情報の信頼性の程度が法域及び個々の主体間で大きく
異なることも認識している。移行の段階について自らの政府又は機関が既に取
り組んで完了した分野と更なる作業が必要とされる分野を識別するための手段
として研究報告を利用することを読者に奨励する。
1.12 研究報告は、次の4つの主なパートから成っている:
• 序論:(第1章から第3章)このパートは、全般的な計画及びプロジェクト管理
問題を取り上げる;
• 全般的な財務報告問題:(第4章及び第5章)このパートは、会計方針の選択、
作成及び承認、並びに報告主体の定義及び識別に関係する問題を取り扱う;
• 財務構成要素:(第6章から第8章)このパートは、資産、負債、収益及び費用
の識別、認識、測定及び開示に要求される広範囲な段階について説明する。これ
らの章で説明される幅広いアプローチは、特定の項目に対して適合された上適用
されることがあり得る;及び
• 特定論題:(第9章から第 15 章)このパートは、2つの特定の国際公会計基準に
関連した実施上の論題に焦点を当て、既存の国際公会計基準により取り上げられ
ていないか、又は一部分のみ取り上げている論題の選択に関連した指針を提供す
る
1.13 本研究報告は、読者が助言を求める問題のすべてについて包括的な解説を提供
するものではない。本研究報告は、発生主義採用を支援するため適時の援助を
提供するために発行されたものである。読者には、本研究報告の将来の改訂版
に反映されるべく提案をなし、また、資料の提供を行っていただきたい。下記
-
発生主義への移行 - 6 -
第 1 章
で述べるように、様々な法域の経験を説明する将来の事例研究も有用な資料と
なろう。
事例研究
1.14 パブリックセクター委員会は、発生主義へ移行する過程における特定の法域の
ケース・研究報告を文書化した事例研究を本研究報告のサポート材料にするこ
とを考慮している。現在までに発行された事例研究には次のものがある:
• 事例研究第1号「政府における発生主義の実施」:ニュージーランドの経験;
• 事例研究第2号「政府全体レベル財務諸表の監査」:ニュージーランドの経験;
• 事例研究第3号「発生主義の視点」;及び
• 事例研究第4号「フランスの公共サービスの委任、公共管理の根源的方法」:委
任された公共サービス
• 「フランスの政府会計制度の近代化」及び「英国の資源会計及び予算」について
の事例研究は、現在出版に向けて完成しつつある。
1.15 パブリックセクター委員会は、個々の公的部門の主体又は法域が、発生主義を
採用する際にその経験を分かち合うために一連の事例研究を参考にすることを
勧めたい。パブリックセクター委員会は、将来的に考えられる事例研究の構成
と内容を例示した概要を作成している(コピーはパブリックセクター委員会の
事務局から得ることができる。)。
1.16 将来の事例研究は、法域の環境及び財務管理に適した改革を考慮した特定の法
域の発生主義に対する移行過程の内容を説明し得るものと考えられる。発生主
義への変更は、それのみが単独で実施されるものではない。発生主義の導入は、
多くの場合、より大きな改革プロジェクトの単なる一部分であり、それらの広
範囲な改革の内容が、発生主義への移行速度と方法に影響を与え得る。変化は、
広範囲な政府機能の分権化の枠内及び/又は集中的な財務管理制度(単一で組
織化された制度内部の基本的財務機能と責任の統合)の発展の枠内で起こるこ
とがある。事例研究は、発生主義導入の背景、改革以前の会計・管理制度の内
容、並びに法域内の法制の枠組み、会計制度及び予算制度の変化の説明を含む
ことがある。独自の実施計画を決定しようとしている法域にとって、計画され
た実施計画及びその計画を選択した理由の説明は有用であろう。より細かなレ
ベルにおいては、会計方針問題、特定の資産、負債、収益及び費用の識別、認
識及び測定の問題は関心のあるところであろう。さらに、事例研究には、政府
全体レベルの報告上の問題の記述及び移行期間の内部及び外部監査人の役割の
-
発生主義への移行 - 7 -
第 1 章
説明を含むこともある。
発生主義の便益
1.17 パブリックセクター委員会は、今までの研究報告(研究報告第5、6、8、9、
10 及び 11 の各号)及び事例研究(事例研究第1号及び第3号)で政府及び個々
の公的部門の主体のための発生主義の便益について広範囲な説明を行ってきた。
パブリックセクター委員会の他の刊行物に馴染みのない読者に多少の背景事情
を提供するために、本章は、発生主義による報告の便益に関する要約を含めて
いる。
1.18 発生主義により作成された報告に含まれる情報は、説明責任及び意思決定目的
の双方に有用である。発生主義で作成される財務報告は、財務諸表の利用者に
次のことを可能にさせる:
• 主体が支配するすべての資源及びそれらの資源の配置の説明責任に関する評価
を可能にする;
• 主体の業績、財政状態及びキャッシュ・フローの評価を可能にする;及び
• 主体に資源を提供し、若しくは主体と取引を行うかどうかの意思決定を可能にす
る
1.19 より詳細なレベルでは、発生主義による報告は、次のことを可能にする:
• 政府がどのようにしてその活動の資金手当てを行い、現金の需要を満たしたかを
示す;
• 財務諸表の利用者が、活動の資金手当てを行い、また、負債及び契約債務の支払
いを行うことについての政府の継続的な能力を査定することを可能にする;
• 政府の財政状態及びその財政状態の変動を示す;
• 政府が、その資源を成功裡に管理したことを示す機会を提供する;及び
• サービスコスト、効率性及び達成度について政府の業績を評価する際に有用とな
る
財政状態
1.20 発生主義は、主体の全体的な財政状態及びその時点の資産及び負債の存在につ
いての情報を提供する。政府は、次のことを行うためにこの情報を必要とする:
• 提供しようとするサービスの資金手当ての可能性について意思決定を行う;
-
発生主義への移行 - 8 -
第 1 章
• 財務諸表で認識された資産及び負債の管理について公共に対して説明責任を果
たす;
• 資産の維持管理及び取替の将来の資金需要を計画する;
• 存在する負債の返済又は履行を計画する;及び
• 現金ポジション及び資金需要を管理する
1.21 発生主義は、資産及び負債の完全な記録を維持するための組織を要求する。そ
うすることは、より良い維持管理、より適切な取替の方針、余剰資産の識別と
処分を含めたより良い資産管理、及び盗難又は損傷による損失などのより良い
リスク管理を促進する。資産の識別及び減価償却の認識は、管理者がサービス
提供における固定資産使用の影響を理解することを助け、管理者がコスト管理
及びサービス提供の代替的な方法を検討することを奨励する。
1.22 発生主義は、存在する負債及び潜在的、又は偶発的な債務の識別に首尾一貫し
た枠組みを提供する。負債の定義及び認識規準を満たす債務の認識は、次のこ
とに役立つ:
• 政府に、単に借入だけでなくすべての認識された負債を認めさせ返済の計画を行
わせる;
• 将来の資源に対する既存の負債の影響の情報を提供する;
• すべての負債の管理のために責任を割り振ることが可能であることを示す;
• 政府が現在のサービスの提供を継続できるかどうか、また、新たな施策やサービ
スをどの程度賄うことができるかを査定するために必要な情報を提供する
1.23 発生主義は、純資産・持分に関する財務上の影響を明らかにし、政府が財務上
の意思決定を行う場合に、現金主義又は修正現金主義の報告に依存する場合に
比較して、より長期的な視野に立てるようにするであろう。また、純資産・持
分の情報は、政府が、意思決定が現在及び将来の純資産・持分の双方に与える
財政上の影響について説明責任を負うことになるであろうことを意味する。2
つの報告日にまたがる主体の純資産・持分の変動は、財務諸表で採用され開示
される特定の測定原則の下で、その期間中の財産の増減を反映する。発生主義
では、財務諸表には、資産及び負債に関する情報を開示する財政状態報告書が
含まれる。資産及び負債が等しくない場合、純資産・持分という残余の数字が
報告される。この数字が、プラスの場合にはその数字は将来における財貨又は
サービスの提供に充てることができる正味資源であり、したがって報告主体に
対する公共の投資であると解釈することができる。数字がマイナスである場合
には、既に支払うことがコミットされた債務又はその他の負債に充てられる将
-
発生主義への移行 - 9 -
第 1 章
来の税収又はその他の収益の金額とみることもできる。純資産・持分は、次の
構成要素のいくつか、又はすべてから構成されるものである:
• 拠出資本;
• 累積余剰金及び欠損金;及び
• 積立金(例えば、再評価積立金;外貨換算積立金)
財務業績
1.24 発生主義は、現金がまだ受領されていないか、又は支払われていない場合の取
引の効果も含んだ収益及び費用の情報を提供する。収益の正確な情報は、政府
の財政上の状態に与える税収及びその他の収益の影響の査定、及び長期的な借
入の必要性を査定する上で必要不可欠である。収益に関する情報は、財務諸表
の利用者及び政府それ自体の双方が、現在の収益が現在の施策及びサービスの
コストを賄うに十分であるかどうかの査定を行うのに役立つ。
1.25 政府は、必要収入額、既存の施策の維持可能性、提案された活動及びサービス
の見込まれるコストを査定するために、費用についての情報を必要とする。発
生主義は、政府にその活動に要する総コストの情報を提供するので、政府は次
のことを行うことができる:
• 特定の政策目標のコストの帰結額及びそれらの目標達成のための代替的な方策
を考慮する;
• 政府の下部主体内部でのサービスの生産に資金を使うか、又は非政府組織から直
接財貨及びサービスを購入するかを決定する;
• 利用料によりサービスに関連するコストを回収できるかどうかを決定する;及び
• 特定のコストを管理する責任を割り振る
1.26 発生主義は、下部主体が指定されたサービスを提供しているかどうか、また、
承認された予算の範囲内でそれを行っているかどうかの情報を提供することが
できる。同じ情報は、より細かいレベルで、下部主体間での活動及び施策のコ
ストの管理に利用することが可能である。
1.27 発生主義は、個々の主体が次のことを行うことを可能にする:
• 有形資産の減価償却及び無形資産の償却を含んだ特定の活動を実行する総コス
トを記録する;
• すべての従業員関連コストを認識し、雇用又は報酬のオプションの様々なコスト
-
発生主義への移行 - 10 -
第 1 章
を比較する;
• 財貨及びサービスの生産及び権限が委譲されている資源管理の最も効率的な方
法を査定する;
• コスト回収方針の妥当性を決定する;及び
• 予算上のコストと実際のコストの監視を行う
キャッシュ・フロー
1.28 発生主義は、借方勘定及び貸方勘定に関連したキャッシュ・フローを含めて、
現状のキャッシュ・フロー及び計画されたキャッシュ・フローに関する包括的
な情報を提供する。したがって、発生主義は、より良い現金管理をもたらし、
より正確な現金予算の作成に貢献するであろう。
-
発生主義への移行 - 11 -
第 1 章
参照資料
オーストラリア会計制度調査財団(Australian Accounting Research Foundation -
AARF)、「公的部門の財務報告-論点の分析及び認識のフレーム・ワーク」、AARF
会計理論論文第5号、1985 年
Greenall, D., and Sutcliffe, P.、「地方政府の財務報告」、AARF 討議ペーパー第 12
号、1988 年
国際会計士連盟、国際公会計基準第1号、「財務諸表の表示」、2000 年5月
国際会計士連盟、国際公会計基準 公開草案第9号、「現金主義による財務報告」、2000
年5月
国際会計士連盟、研究報告第5号、「資産の定義と認識」、1995 年8月
国際会計士連盟、研究報告第6号、「負債の会計処理と報告」、1995 年8月
国際会計士連盟、研究報告第8号、「政府の財務報告主体」、1996 年7月
国際会計士連盟、研究報告第9号、「収益の定義と認識」、1996 年 12 月
国際会計士連盟、研究報告第 10 号、「費用・支出の定義と認識」、1996 年 12 月
国際会計士連盟、研究報告第 11 号、「政府の財務報告-会計上の論点と実務」、2000 年
5月
国際会計士連盟、事例研究第1号、「政府における発生主義の実施-ニュージーランド
の経験」、1994 年 10 月
国際会計士連盟、事例研究第2号、「政府全体レベルの財務諸表監査-ニュージーラン
ドの経験」、1994 年 10 月
国際会計士連盟、事例研究第3号、「発生主義の視点」、1997 年5月
-
発生主義への移行 - 12 -
第 1 章
国際会計士連盟、事例研究第4号、「フランスの公共サービスの委任、公共管理の根源
的方法」、2001 年9月、http://www.ifac.org
Micallef, F., Sutcliffe, P., and Doughty, P.、AARF 討議ペーパー12 号、「政府の財
務報告」、1994 年
Sutcliffe, P., Micallef, F., and Parker, L.D.、AARF 討議ペーパー16 号、「政府省
庁の財務報告」、1991 年
-
発生主義への移行 - 13 -
第 1 章
付録1:ウェブ・サイト参照先
オーストラリア
オーストラリア会計基準審議会(Australian Accounting Standards Board) http://www.aasb.com.au
オーストラリア会計検査院(Australian National Audit Office) http://www.anao.gov.au
オーストラリア州及び領地政府(共通参加点)(Australian State and Territory Governments(general entry point))
http://www.gov.au 予算及び行政省庁:卓越性のための会計センター(Department of Finance and Administration:Accounting Centre for Excellence)
http://www.finance.gov.au/ace 予算及び行政省庁(オーストラリア連邦政府)( Department of Finance and Administration(Commonwealth Government of Australia))
http://www.finance.gov.au 財政及び金融局(タスマニア)(Department of Treasury and Finance(Tasmania))
http://www.tres.tas.gov.au/domino/dtf/dtf.nsf ニューサウスウェールズ財務局:金融管理事務所(New South Wales Treasury:Office of Financial Management)
http://www.treasury.nsw.gov.au
カナダ
オンタリオ州政府(Government of Ontario) http://www.gov.on.ca/MBS/english/index.html
カナダ会計検査院長及び環境及び維持開発コミッショナー(Auditor General of Canada and the Commissioner of the Environment and Sustainable Development)
http://www.oag-bvg.gc.ca カナダ公共工事及び政府サービス局(Public Works and Government Service Canada)
http://www.pwgsc.gc.ca カナダ財政委員会事務局(Treasury Board of Canada Secretariat)
http://www.tbs-sct.gc.ca カナダ財政委員会事務局:財務情報戦略(Treasury Board of Canada Secretariat:Financial Information Strategy)
-
発生主義への移行 - 14 -
第 1 章
http://www.tbs-sct.gc.ca/fin/fis-sif
香港
香港特別行政区政府:財務省(Government of the Hong Kong Special Administrative Region:Treasury)
http://www.info.gov.hk/tsy
国際機関
アジア開発銀行(Asian Development Bank) http://www.adb.org
国際会計基準審議会 http://www.iasb.org.uk
国際会計士連盟 http://www.ifac.org
国際農業開発基金(International Fund for Agricultural Development) http://www.ifad.org
国際通貨基金(International Monetary Fund) http://www.imf.org
最高会計検査機関国際組織(International Organization of Supreme Audit Institutions) http://www.intosai.org
経済協力開発機構:公共管理及び統治(Organization for Economic Co-operation and Development:Public Management and Governance)
http://www.oecd.org/puma 世界銀行グループ(The World Bank Group)
http://www.worldbank.org
メキシコ
財団法人メキシコ公認会計士協会(Instituto Mexicano de Contadores Públicos, A.C.) http://www.imcp.org.mx
ニュージーランド
ニュージーランド政府・オンライン(New Zealand Government Online)
-
発生主義への移行 - 15 -
第 1 章
http://www.govt.nz ニュージーランド地方政府管理者協会(New Zealand Society of Local Government Managers)
http://www.solgm.org.nz ニュージーランド会計検査院長事務所(Office of the Controller and Auditor - General of New Zealand)
http://www.oag.govt.nz 財務省(The Treasury)
http://www.treasury.govt.nz
南アフリカ共和国
財務省(National Treasury) http://www.finance.gov.za
会計検査院長事務所(Office of the Auditor General) http://www.agsa.co.za
南アフリカ準備銀行(South African Reserve Bank) http://www.resbank.co.za
南アフリカ勅許会計士協会(The South African Institute of Chartered Accountants) http://www.saica.co.za
公共財政及び監査協会(The Institute for Public Finance and Auditing) http://ipfa.pwv.gov.za
スウェーデン
スウェーデン国家財政管理局(Ekonomistyrningsverket - Swedish National Financial Management Authority)
http://www.esv.se スウェーデン会計検査院(Riksrevisionsverket - Swedish National Audit Office)
http://www.rrv.se
英国
HM 政府:HM 財務省(HM Government:HM Treasury) http://www.hm-treasury.gov.uk
会計検査院(National Audit Office)
-
発生主義への移行 - 16 -
第 1 章
http://www.nao.gov.uk/ 資源会計マニュアル:HM 財務省(Resource Accounting Manual:HM Treasury)
http://www.resource-accounting.gov.uk 勅許公共財務会計協会(The Chartered Institute of Public Finance and Accountancy)
http://www.cipfa.org.uk 政府全体レベル会計計画(Whole of Government Accounts Programme)
http://www.wga.gov.uk
米国
防衛財政及び会計局(Defense Finance and Accounting Service) http://www.dfas.mil
政府会計基準審議会(Governmental Accounting Standards Board) http://www.gasb.org
財務会計基準審議会(Financial Accounting Standards Board) http://www.fasb.org
連邦会計基準助言審議会(Federal Accounting Standards Advisory Board) http://www.fasab.gov
会計検査院(The General Accounting Office) http://www.gao.gov
-
発生主義への移行 - 17 -
第 1 章
付録2:現金主義の報告と本研究報告の関連性
本付録は、国際公会計基準公開草案第9号「現金主義による財務報告」から発展的に作
成される将来の国際公会計基準に準拠しようとする主体を含め、包括的な現金主義の財
務諸表を作成することを望んでいる主体に対し本研究報告の様々な章の関連性を要約
したものである。
第Ⅰ節-序論
第1章 緒論 全般的関連性
第2章 プロセス管理 全般的関連性-会計制度の変更が計画される範囲において
第3章 技能評価及び訓練 現金主義を適用している主体内の能力の規格の問題が起こり得る。しかし、本章の指
針は、技能の著しい変化が要求され、又は
予想されない限り一般的に無関係である。
第Ⅱ節-全般的な財務報告問題 第4章 会計方針に関する問題 本章は、主体が現金主義の報告を行うため
に必要な会計方針の例示を含んでいる。
第5章 報告主体に関する問題 全般的関連性
-
発生主義への移行 - 18 -
第 1 章
第Ⅲ節-財務構成要素 第6章 資産 現金主義の報告には要求されない。主体が
一定の資産の記録を維持し、発生主義を導
入する計画の開始を望む場合に関連する。
第7章 負債 現金主義の報告には要求されない。現金主義を採用している多くの主体で債務及び借
入の包括的な記録を維持している場合に関
連する。
第8章 収益及び費用 現金主義の報告には要求されない。一定の受取勘定及び支払勘定を認識している一部
の主体に関連する。収益の構成要素の識別
及び開示の議論は関連性がある。
第Ⅳ節-特定論題 第9章 現金 全般的関連性
第 10 章 無形資産 現金主義の報告では要求されない。
第 11 章 金融商品 現金主義の報告では要求されない。
第 12 章 従業員関連負債 現金主義の報告では要求されない。
第 13 章 社会政策債務から生じる負債 現金主義の報告では要求されない。
第 14 章 非交換取引による収益 現金主義の報告では要求されない。
第 15 章 外貨 現金主義の報告では要求されない。国際公
会計基準公開草案第9号は、キャッシュ・
フロー及びキャッシュ残高の換算について
の提案を含んでいる。
-
発生主義への移行 - 19 -
第2章
第2章:プロセス管理
要点
本章は次の議論を含んでいる:
• 発生主義への移行の内容と速度に影響を与え得るいくつかの要素。また、いくつ
かの移行オプションについても述べている;
• 公的部門を形成する個々の主体及び全体としての政府の双方のための発生主義
の採用;
• 移行経路における外部監査人の役割;
• ヨーロッパ連合への加盟を考慮中の国々の予算編成、管理及び監査に与えるいく
つかの影響;及び
• 政府の様々な制度の潜在的影響及び移行過程に関する現在の政治的環境につい
て行い得るいくつかの分類化。この目的で考慮された区分けは、先進国、移行経
済国及び途上国である。
はじめに
2.1 本章は、発生主義へ至る移行の速度と形態に影響を与え得るいくつかの幅の広
い問題について説明している。本指針の焦点は、会計制度の変更についてであ
るが、発生主義の採用は、それ自体独立して行われるものではなく、移行の形
態は、それが実施される背景により影響される。
2.2 発生主義への移行の内容と速度に影響を与える要素には、次のものがある:
• 政府の制度及び政治的環境;
• 改革が単に会計制度の変更のみを目指しているのか、あるいは他の更に規模の大
きい改革を包含したものであるかの事情;
• 変更が、「トップ・ダウン」又は「ボトム・アップ」のどちらに主導されたもの
であるかの事情。例えば、変更が政府の最高レベルにより主導される場合には、
通常、政府内部のすべての主体に対して強制的なものであり、固定された時間的
枠組みが設けられるであろう。本章は、公的部門を形成する主体及び全体として
の政府(政府全体レベルの財務諸表が作成されているかどうかを問わない)の双
方を対象とした発生主義の採用について議論する。しかしながら、本章の多くの
解説は、発生主義への移行を計画している個々の主体に等しく関連性がある;
• 主体により現在使用されている会計基準、既存の情報システムの能力、及び特に
-
発生主義への移行 - 20 -
第2章
資産と負債に関する既存の情報の完全性と正確性;
• 予算書の作成に使用される会計基準。予算作成及び承認手続の変更は、全体的な
移行の別な構成部分になるばかりでなく、情報システムの必要事項にも影響を与
える;
• 発生主義採用に向けた政治的なかかわり合いのレベル;及び
• 変更の実施に責任を有する人と組織の能力と技能
2.3 本章は、主要な要素及びそれらが移行の形態にどのような影響を与え得るかに
ついてより詳細な議論を含んでいる。また、本章は、様々な移行オプションに
ついても述べている。
経済及び政府の制度
2.4 それぞれの法域は、移行過程の設計に影響を与える多くの独特の特徴を持つで
あろうが、政府の様々な制度の潜在的影響及び移行過程に関する現在の政治的
環境についていくつかの分類を行うことが可能である。この目的で考慮された
区分けは、先進国、移行経済国及び途上国である。本書の議論の目的で使用さ
れるその分類された見出しは次のとおりである:
• 先進国
• 移行経済国
• 途上国
2.5 これらの分類された見出しは、一定の要素が、いかに移行経路に影響を与え得
るかを例証する目的のみのために使用される。それらは包括的なものでなく、
場合によっては、相互に排他的なものではない。それぞれの分類された見出し
で議論される移行経路のタイプは、その分類が当てはまる法域内でより生ずる
可能性が高いと見込まれる移行経路の例示にすぎない。
先進国
2.6 資源及び専門知識に関する制約についての問題は、途上国や移行経済国に比べ
てより少ないといえる。しかし、先進国の政治制度は、これらの経済国家に現
に存在する財務報告及び管理制度の改革の障害になることがある。先進国の政
府の2つの共通した制度は、大統領制度と議会制度である。
2.7 大統領制度では、一人の人物が、一定の期間における執行部(日常の管理職務
-
発生主義への移行 - 21 -
第2章
を実行する政府の機関)の指導者として民主的に選出される。当該人物は、例
外的な状況を除いて立法府により解任されることはない。この執行機関と立法
府の間の権限の分離は、立法府は、提案される法律の本案について独立した意
見を提供するものであることを意味する。こうした独立性は、大統領制度の強
みである。しかし、この制度は、法律の成立の遅延又は阻止につながることも
ある。提案された財政改革が法律の変更を要する場合、立法府のための意思疎
通戦略の展開などを含む詳細な計画が、期間内に法律が通過する可能性を高め
るために必要とされるであろう。さらに、改正後の財政制度による予算及び財
務諸表の法律的な検討が要求される提案については、立法府の内部的手続及び
その検討までの必要な時間を考慮に入れなければならない。
2.8 政府の議会制度では、一院制の議院又は二院制の場合は上位の議院の議員から
最も多くの投票を得ることができる政党により政府が形成される。政府は、必
ずしも議会の過半数を支配しているわけではなく、したがってその法案が常に
成立するとは限らない。議会において法案について厳しい討議が行われること
があるが、財務管理改革を推し進めようと望む政府は、通常は、執行部を支配
し法案の通過を確保するに足る議会内部の支持者を有する。議会制度の中で、
移行の初期段階における主要な側面は、改革に対する支配政党による十分なか
かわり合いがあることを確実にすることである。一度この支持が得られた場合
には、情報に裏付けられた提案の討議を可能にし、対立政党の主要メンバーか
ら支持が取り付けられるように対立政党に情報を提供することに気を配ること
も重要なことである。議会制度の下では、移行の期間は著しく短いこともあり
得る。
2.9 また、政府の議会制度は、今までにも大規模な財務管理改革と関係してきた。
大規模な財務管理改革の潜在的な範囲、及びこうした改革への様々なアプロー
チの方法については本章の後半で議論する。
2.10 大統領制度又は議会制度が、実効性を持っているかどうかにかかわりなく、一
部の法域は、政府の予算編成及び報告を支持する法律又は規則が、特に細かく
決められ、それが、政治体制の根幹であるという見方がなされる制度の下で事
業を行っている。このような場合、既存の法律又は規則の変更をもたらすこと
が極めて難しいという点で移行に影響を与えることがある。このような場合、
個々の主体には、一方で既存の予算制度を維持しながら、発生主義を採用する
ことを奨励することになろう。この主体ごとのアプローチでは、変更に関する
正式な政治的承認は必要とされず、集中的管理の度合いがより低い改革になる
-
発生主義への移行 - 22 -
第2章
であろう。しかしながら、その場合でも、個々の主体は、会計方針一式を作成
する必要があり、また、規制力のある会計基準の情報源及び適用についての指
針を必要とするであろう。このような主体の財務情報が、将来において連結さ
れる見込みであれば、中心主体による一定の会計方針の早い時期での設計仕様
は、後日の問題を未然に防ぐことになるかもしれない。
移行経済国
2.11 移行経済国は、多くの場合、急激な経済上及び制度上の変化を経験しており、
財務管理を公的部門の継続した再発展過程の必要な一段階としてとらえるかも
しれない。この点で、提案される変更に政治的な支持を得られる可能性がある。
変更の政治的な承認は、広範囲な改革(例えば、財務管理制度の大きな変更、
及びすべてのタイプの政府主体にわたる発生主義の採用)がより実現性を帯び
ることを意味する。
2.12 移行経済国は、しばしば購入された資産の記録を持っている。比較的完全な資
産記録の存在は、資産の識別と認識を非常に容易にする。資産の会計方針は、
その後も更に発展させ、適用されなければならない(例えば、既存の資産記録
に適用される足切りの認識)が、資産の識別及び検証に費やされる時間と資源
は大幅に削減できる。
途上国
2.13 政府主体によって使用されている会計基準の変更という点で、途上国が直面し
ている主要な制約は、会計制度及び熟練スタッフという点での主体の既存の能
力、及びその能力を開発する政府の内部又は外部の利用可能な資源の問題であ
る。こうした資源に関する制約は、途上国は、より段階的な実施過程を考慮す
る傾向になることを意味する。
2.14 特に、途上国について、財政改革の一環として管理権限を法的に付与すること
の便益を巡る論議がある。この論議は、発生主義の採用の中心的な問題ではな
いので、本研究報告では取り上げない。しかし、管理権限の付与が、発生主義
採用に関連して生じる場合には、その変更過程の管理は改革の成功のための重
大な要素になるであろう。
2.15 途上国は、改革を実行するために外部からの支援に頼るかもしれない。ある法
-
発生主義への移行 - 23 -
第2章
域が、発生主義への移行のための資源の援助を受けるために、こうした支援(例
えば、融資又は寄付)に依存する場合、利用できる支援の金額及び種類は、移
行過程に影響を与え得る。例えば、支援機関は、限定された数の試験的な主体
内部の一定の発展のために資金を提供したり、あるいは、専門家を提供すると
いう形での支援を望むかもしれない。財務管理支援プロジェクトの詳細を含む
いくつかのウェブ・サイトは、本章の付録に列記してある。
2.16 途上国は、内部訓練の開発及び訓練を行う主体の人員の活用(「訓練者の訓練」
アプローチ)に重きを置いた訓練計画の利用を重視しがちである。「訓練者の訓
練」アプローチは、どのような法域にとっても1つのオプションであるが、資
源が限定されている場合、又は法域が2か国語又は多国語の通用国である場合
に特に有効である。
移行経路
2.17 法域の間でも、移行の形態と速度は大きく違うであろう。多様なアプローチが
取り得る。考えられるアプローチは下記で議論されるが、これらのアプローチ
の様々な組合せも考えられる。
主体のタイプに対する改革の適用
2.18 改革は、政府内のすべての公的部門の主体に適用される場合と、一定のタイプ
の主体に限定される場合がある。例えば、発生主義の実施がセクター単位で行
われることもある。実施は、既に支配下にある資源を管理する責任の一部分を
有し、集中的会計制度の枠外にある自治政府又は準自治政府から開始されるこ
ともある。自治主体の会計基準の変更について政治的な承認を得て、その後こ
れらの変更を実施することは、その変更が、既存の集中的な予算編成及び報告
の制度に与える影響が少ないと考えられるため、多くの場合に比較的容易であ
る。あるいは、改革は、それらが政府の活動の中心になっていることから、最
初に予算セクター主体に焦点が置かれることもある。
2.19 発生主義への移行は、一定のタイプの主体に強制的である場合と、一部又はす
べての主体に任意である場合がある。主体が発生主義の採用を選択することを
認めることの利点は、個々の主体が、それにより改革過程への移行を動機付け
られてそれに邁進することである。しかし、自主的な移行は、政府内部の様々
な主体による異なる会計基準の使用が、政府全体レベル主体の連結財務諸表作
-
発生主義への移行 - 24 -
第2章
成の妨げとなるという点で困難性を生む可能性がある。政府レベル内の個々の
主体による異なる会計基準の使用は、異なる予算編成とその監視の制度を伴う
こともある。任意の選択(自己選択とも呼ばれる。)は、少数の試験的主体が改
革に試行を求める場合にしばしば使用される。試験的主体の利用は、政府が改
革をどのように取り扱うかについて、また、遭遇しそうな問題についての経験
を得て、中核となる訓練された要員の開発を行うことに役立つ。
2.20 タイプや規模の異なる主体について異なる移行経路を設計することは可能であ
る。例えば、規模の大きい主体は、その財務情報システムの開発を設計し、監
督する権限を委任されるであろうし、規模の小さい主体は、特定の財務情報シ
ステムの実施も含めて、中央で定められた移行経路に従うことを要求されるか
もしれない。例えば、多くの政府系企業は、既に発生主義を使用しているであ
ろう。そのため、このような政府系企業の移行経路は、会計方針の首尾一貫性
の確保とその他の連結の問題に重点を置くことになろう。
政府全体レベルの報告
2.21 政府が、政府全体レベル報告の実施を決定する場合、それが取り得る過程は数
多くある。最初の発生主義による政府全体レベルの報告書は、個々の主体によ
る最初の発生主義による報告書と同時に要求されることもある。また一方で、
このような報告の作成が、個々の主体による移行、報告主体の範囲及びその他
の連結上の問題に集中するための期間を認めることで遅れることもある。他の
オプションとしては、中間的なステップとして、政府全体レベルの様々な分類
されたセクターの発生主義による連結報告書を作成し、次に政府全体レベルの
報告書を完成するという過程である。
段階的な実施
2.22 発生主義は、資産及び負債の定義に合致し、資産及び負債の認識規準を満たす
すべての資産及び負債の認識を要求する。しかし、これは、主体が、段階的に
資産及び負債を認識することによって全面的な発生主義に移行することを選択
する道を妨げるものではない。例えば、最初に受取勘定及び支払勘定などの短
期性資産及び負債の認識に焦点を当てることが可能である。有形資産の認識も、
最初に容易に識別又は測定できる資産とともに認識されることがあるが、多く
の場合、その次の段階になるであろう。非交換取引(租税)受取勘定及び無形
資産の認識は、これらの資産の測定に関する問題を解決するため、一定の期間
-
発生主義への移行 - 25 -
第2章
は繰り延べられることになろう。
2.23 同様に、負債の認識も段階的に起こり得る。公共からの債務は、主体が、通常、
既存の借入金に関する相当に正確な記録を有していることから、多くの場合最
初に認識される。年金及びその他の長期性債務は、段階的に認識されることに
なろう。
発生主義の予算編成と承認
2.24 改革の一環として発生主義による予算化が導入されようとしている場合、予算
化及び承認手続の変更は、発生主義による報告への最初の変更とともに生ずる
であろう。しかし、多くの法域において、その変更は、発生主義による報告書
が導入された後、少なくとも1期又は2期遅れて起きている。この遅延は、し
ばしば、予算の承認に責任を有する者に対して新しい財政制度が、予算承認の
基となる信頼性のある情報を提供し得るものであるという保証を与えるために
必要とされている。
改革の期間
2.25 通常、利用できる資源又は政治的なかかわり合いの範囲が、改革の期間を決め
ることになる。これらの期間は、法域により異なるであろう。改革の期間は、
短期(約1年から3年)、中期(約4年から6年)及び長期(約6年超)に分け
られるであろう。
2.26 短期の改革期間は、強力な政治的支持があり、主体の数が限られている場合に
適当であろう。中期の改革期間は、実施計画の詳細の策定、会計方針の作成及
び新制度の実施とそのテストでより多くの時間を要する。また、それには、そ
の変更に関連して政府の職員及び政治家などのグループの教育にも相当に長期
の時間を要するであろう。長期の実施期間からの便益は、「改革疲労」のリスク
とのバランスを取らなければならない。改革疲労は、政府主体内の変更の先導
者達が、特にその過程で便益が早期に現れない場合に、改革の実行に必要な緊
急性の感覚と情熱を失う場合に起こる。
2.27 移行の時間的枠組みを選定する場合、政府も改革の様々な側面を達成するため、
目標期日又はマイルストーンを設定することがある。主体は、実施の次の段階
に進むために一定の期日ごとに一定の規準を満たすように要求されるであろう。
-
発生主義への移行 - 26 -
第2章
例えば、キャッシュ・マネジメントの実施を許可される前に主要な又はすべて
の資産及び負債を認識した上で、事業の情報システムを確立するように要求さ
れるかもしれない。
2.28 発生主義を採用してきた政府は、異なる時間的な枠組み、様々な状況の中でそ
れを実行してきた。例えば、英国は、個別の政府省庁の最初の資源(発生主義)
勘定を 1999 年-2000 年に作成し資源会計基準(発生主義)による歳出の最初の
議会承認申請を 2001 年-2002 年に行った。現在は政府全体レベル公的部門の連
結財務諸表作成へ向けた段階的なアプローチが計画されている。この過程は、
2001年-2002年の国民勘定による情報を使用した監査未了の中央政府勘定の連
結、一般に認められた会計原則を使用した 2003 年-2004 年の中央政府勘定と
2005 年-2006 年の政府全体レベルの勘定の連結を含むことになろう。
移行及び外部監査
2.29 多くの法域は、政府全体レベル及び/又は個々の被支配主体による監査済みの
財務諸表の作成を要求する。選択された移行経路のタイプにより、法域は、移
行期間中の監査要求を満たすためにいくつかのオプションを開発する必要があ
るかもしれない。オプションの受容性は、その法域の法的な要求に左右される
であろう。移行期間中の監査要求を処理するオプションには、次のことが必要
であろう:
• 移行が完了するまでの間、既存の会計基準による監査済みの財務諸表の作成を継
続する。これは、一定の期間は、併行した報告書の作成を伴うであろう;
• 会計基準への準拠性について表明した監査報告書。このオプションは、主体が一
定の期間に会計基準の必要事項を段階的に取り入れることを許容する;
• 試行的作成としての監査未了で未公表の財務諸表一式を作成する(多くの場合、
既存の会計基準による監査済みの財務諸表一式の作成と併行して);
• 中間的な段階として、また、限定された報告期間のものとしての監査未了の財務
諸表一式を公表する;及び
• いくつかの限定意見が付された監査済みの財務諸表一式を公表する。政府は、こ
れらの問題を設定された期間で解決するという公のかかわり合いを行うことも
できる
2.30 執行部門と外部又は独立した監査人との関係の性格は、法域によって異なるで
あろう。監査人が独立性を維持することは、必要不可欠であるが、移行過程の
当初は、監査人と協調的な作業協力関係を築くことで多くの便益が得られるで
-
発生主義への移行 - 27 -
第2章
あろう。これには、外部の監査人に提案される移行経路の正式な相談を行うこ
とも含まれるであろう。監査人は、特定の制度又は過程が、監査の要求事項を
満たすという絶対的な保証を与えることはないであろう。しかし、監査人は、
その制度又は過程を査定する際に使われる規準に関して有用な助言を与えるこ
とができるかもしれない。
実施計画
2.31 移行経路についての決定を終えると、主体は次にその目標を達成するために実
施計画を策定しなければならない。本章の付録は、検討が必要な多くの問題を
示した包括的な実施計画の主要な見出しを設けている。
成功する移行
2.32 発生主義への移行は、多くの政府にとって大きなプロジェクトである。他の大
規模なプロジェクトと同様に、それには、周到な計画と管理が要求される。移
行は、下記の特徴が存在していれば、よりスムースで速いものとなる:
• 明確な委任指図関係;
• 政治的かかわり合い;
• 中央主体及び主要な上級役人のかかわり合い;
• 十分な資源(人的及び資金的);
• 効果的なプロジェクト管理及び調整組織;
• 十分な技能的能力及び情報システム;及び
• 正式な権限を与える立法の活用及び変更に対するかかわり合いの示唆
明確な委任指図関係
2.33 改革には何を含むのか、予定される時期及び要求される変更を開始するための
様々な政府機関の権限を述べた政府の適切なレベルからの明確な委任指図は重
要である。明確な委任指図は、関連する上級役人及び主体に変更を開始し、改
革を監督する権限を与える。
政治的かかわり合い
2.34 一般的に、支配政党及びその支配政党を取り仕切る議員、並びに対立政党から
の政治的かかわり合いは、提案された変更の初期の承認を確保すること、及び
-
発生主義への移行 - 28 -
第2章
障害や反対が起こった場合に変更の継続した支持を受けるために必要である。
会計基準の変更には相当の資源が必要である。移行過程において政治的かかわ
り合いが形成されていない場合、移行過程の後半の段階において問題解決不能
に陥ることは乏しい資源の浪費に帰することになる。
中央主体及び主要な上級役人のかかわり合い
2.35 政府の最高位の役人及び政治家の積極的な支持及び指導力が必要とされる1つ
の理由は、資源に対する権限の法的な移転などのその他の財務管理改革を伴う
会計基準の変更には権利構造の変更を伴うことである。変更に対して公に賛成
している主要な人物は、事態がうまく行かなかったときには「解決屋」として
の役目も果たす。このような主要な人物の存在は必要不可欠であるが、一人の
重要人物が支持を撤回したり、又は利用できなくなった場合にプロジェクトが
失敗するリスクを防ぐことが必要となる。また、財政改革には公共サービスに
関する文化認識の変化も必要かもしれない。例えば、個人には、財務管理に対
してより大きな責任が与えられ、また、新たな財務報告を理解し利用すること
が期待されるかもしれない。こうした文化認識の変化には時間と努力を必要と
する。最高位役人の「取込み」はこの過程に役立つ。
十分な資源
2.36 発生主義への変更を管理し維持するためには様々な技能が必要とされる。必要
とされる技能のタイプの識別、及びこれらの技能の利用可能性を確保するため
の計画は、移行の成功への重要な事項である。一般に主体には次の資源が必要
である:
• プロジェクト管理及び変更管理の技能を持つ人物;
• 会計方針の問題及びシステムの要求事項に理解と経験を持つ人物;
• 改革過程の異なる構成要素間の相互関連性を理解する主要な要員;
• 発生主義システムのデータを記録し、そのシステムから情報を抽出し説明する能
力を持つ個人。これには、通常、追加的なスタッフの求人及び既存のスタッフに
対する何らかの訓練を伴うことになろう(第3章「技能評価及び訓練」はこれら
の問題について詳細に議論している);及び
• 追加スタッフ、専門家技能の習得及び財務情報システムの開発及び設置を含む必
要な追加的資源のための十分な資金供給
-
発生主義への移行 - 29 -
第2章
プロジェクト管理
2.37 プロジェクト管理は、通常、プロジェクトを、その後に適切な技能と経験を持
つ個人によって管理することができる独立した構成要素に分割することを伴う。
改革プロジェクトは、次の内容を持たなければならない:
• 文書化されたフレーム・ワーク又は理念。合意されたアプローチは、改革の意思
疎通の一貫した基礎を形成するため、また、スタッフが変更の理由及び採用され
るアプローチを理解することを手助けするため、さらに実際の実施がこれらの意
思決定に準拠していることを確実にするために文書化される必要がある;
• 正式な実施計画。実施計画の内容は、改革の形態と規模によって異なるであろう。
発生主義の採用のための実施計画の例示(主要な見出しのみ)は、本章の付録に
含まれている;
• 個々の任務に対する明確な責任の分担及び主要主体及び役人のそれぞれの役割
と責任;
• そのマイルストーンに対する主体及び個人の成績を監視する手続を含むマイル
ストーン表。一部の法域(例えば、フィリィピン及びタイ)は、主体がプロジェ
クトの一定の段階で満たさなければならない一連の文書化された規準である「ト
リガー・ポイント」を作成している。これらのトリガー・ポイントは資源の法的
権限の移転が生ずるかどうかを決定する基準を定めており、各段階での監査報告
書は、リスクが存在するか、是正的行動が必要である分野について明らかにする;
• 誰が特定の意思決定の権限を持つのかを明らかにした承認又は決済手続;
• 主体に情報を提供し、また、主体から情報を収集する正式な通信及び調整機能;
及び
• 予算。当初のコストは、明確に識別され予算確保されなければならない。移行に
関係した個々の主体が、既存の予算の範囲内又は通常の追加予算の範囲内で変更
の管理を行うことが見込まれる場合、そのことはプロジェクトの開始時に明確に
識別されていることを要する。
技術力及び情報システム
2.38 他の公的部門改革と関連した発生主義財務報告は、多くの場合、広い範囲の情
報システムの変更を伴う。発生主義への移行を検討している主体は、財務報告
制度とリンクしているすべての既存のシステムの評価を実施しなければならな
い。例えば、変更は以下のシステムに対して必要であろう:
• 収益システム;
• 購買システム;
-
発生主義への移行 - 30 -
第2章
• 旅費システム;
• 補助金及び給付金システム;
• 人事及び給与システム;
• 固定資産システム;
• 不動産管理システム;
• 棚卸資産システム;
• 借入債務システム;
• 予算システム;及び
• 非財務システム
2.39 既存のシステムの評価には以下の問題も含むであろう:
• システム内部に現在どのような情報が保有されているか
• どのような追加的情報が必要か(発生主義に基づく国際公会計基準に準拠するた
めに必要とされる情報の評価も含む)
• どの範囲まで集中的システムが分散化されるべきか(これは、より広範囲な改革
の基となる政策フレーム・ワークによって左右されるであろう)
• 望ましい統合の程度に比較して、現在の財務及び他のシステムの統合はどの程度
の状態にあるか
• 既存のシステムは取り替えるべきか、あるいは、適合させるべきか。また、シス
テムが取り替えられる場合には、取替システムは、「規格品」システムにするか、
又は別注のシステムにするか
2.40 政府が、新たな財務管理制度の導入を計画している場合、既存の記帳システム
がその財務管理制度を支えることを確かなものにするために、そのシステムの
再設計を考慮することが必要なこともある。既存の制度及びシステムを評価す
る手法は、Barata、Cain、Routledge(2001 年)に記述されている。こうした手
法は、記帳システムが権限のないスタッフによる記録へのアクセスを制限する
ことができるか、また、監査人が、原始証憑、手作業による取引記入帳、仕訳
帳及び元帳から取引を容易に追跡して逐次的な要約に至ることができるかどう
かなどの事項について、検査人に評価を要求する評価ワークシートの利用を含
んでいる。
立法の活用
2.41 提案される変更に関する法案の起草と主要なグループとの協議は、多くの便益
を与える。立法の活用は、変更に対する政府のかかわり合いの強固さを明示す
-
発生主義への移行 - 31 -
第2章
る。通常、立法上の変更を伴う協議過程は、他の政党及び政府内の影響力を有
するグループに変更の便益を知らせ、また、教育する機会を提供する。法案の
起草は、計画及び発展過程の追加的な段階を示す。したがって、それは、変更
が包括的であり一貫性があるものであることを確かめるために提案された変更
を見直す機会を提供する。第 2.10 項で述べたように、主体ごとのアプローチで
は、財務報告及び財務管理制度の変更の正式な政治的な承認は必要とされない。
資源を効果的に利用するための集中努力
2.42 発生主義へ移行することを計画している多くの主体は限られた資源しか持って
いない。そのため、主体は、それらの資源を可能な限り効率的に、かつ、効果
的に利用することが非常に重要である。明確な目標の識別、責任分担、適時性
及び独立性を備えた優れたプロジェクト管理は、資源を賢く利用する重要な側
面である。
2.43 さらに、重要性の適用は、特に移行の速度に関して移行の側面に重要な影響を
与え得る。情報は、その脱漏や虚偽記載が、財務諸表に基づいて利用者が行う
意思決定又は査定に影響を与えるならば、重要性がある。例えば、完全で正確
な開始財政状態報告書は、発生主義を実施する場合の最初のステップの1つで
ある。すべての資産及び負債の識別及び評価には相当の時間を要すことがある。
しかし、それは、移行過程の基本的な段階であり、主体が無限定意見監査報告
書を得ようとするならば、開始残高は、信頼性のある記録及び適正な評価によ
り裏付けられなければならない。財政状態報告書の開始残高を決めるに際して、
重要性の概念は、最高度の外部の精査の対象とされるそれらの資産及び負債の
識別とともに役立つであろう。それゆえ、最初の段階においては、他の事項よ
りもこれらの資産及び負債の識別と評価により多くの時間と資源を費やすこと
が適切であろう。
2.44 より重要性のない資産及び負債も内部又は外部の監査人に受入れられる方法で
識別され評価される必要がある。しかし、他の資産及び負債に適用されるアプ
ローチよりも少ない時間と資源を要するアプローチを適用して容認される短期
的な情報を作成することは可能かもしれない。ある種の状況の中で容認される
考えられる暫定的な処理には次のものを含むであろう:
• 最終的に意図されている評価方法の簡便法を使う;
• 項目ごとに保有される情報を検証しないで情報の信頼性及び正確性を決定する
-
発生主義への�