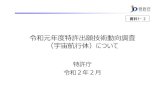平成19年度 特許出願技術動向調査報告書 電子ゲー …...平成19年度 特許出願技術動向調査報告書 電子ゲーム (要約版) 平成20年4月 特
平成30年度 特許出願技術動向調査報告書 - jpo.go.jp...平成30年度...
Transcript of 平成30年度 特許出願技術動向調査報告書 - jpo.go.jp...平成30年度...
- 1 -
資料編
第7部
第6部
第5部
第3部
第2部
第1部
本編
要約
目次
第4部
第 1 章 調査概要
第 1 節 調査目的
近年フィンテックの進展に伴い、国内における金融関連発明の特許出願件数は大きく
伸長しており(2016 年は前年比約 46%増)、従来の金融機関や大企業だけでなく、新規企
業による参入も多いことに特徴が見られる(金融関連発明における新規出願人比率は 40%
~50%前後の高い比率の推移)。また海外に目を向けると、世界的な ICT 企業が集積され
た米国シリコンバレーからは、革新的な新サービスが創出され、グローバルに影響を与
えている状況である。
フィンテックに関連する「仮想通貨・電子マネーによる決済システム」の分野におい
ても、国内外で多様な企業から多くの技術が産出されている。インターネット取引のみ
ならず、リアル店舗等での取り扱いが全世界的に急速に拡大しつつある仮想(暗号)通
貨や、現在、日本において広く普及している電子マネーなどの目に見えないお金による
決済は年々増加している。仮想(暗号)通貨や電子マネーの取り扱いの機会が増えるに
つれて、それらの決済を行うための電子決済システム・電子決済サービスも様々なシー
ンに対応したものが出現しており、セキュリティやネットワーク障害対応等を含めて電
子決済システム・電子決済サービスは今後も発展が見込まれる。
以上のような背景の下、本調査では、仮想通貨・電子マネーによる決済システムに関
する国内外の技術動向、日本及び外国の技術競争力の状況と今後の展望を明らかにする
ことを目的として、本技術に関する特許や研究開発論文等の解析を行い、今後日本企業
が取り組むべき課題や方向性について提言を行った。
第 2 節 技術俯瞰図と対象技術の概要
本調査では、「仮想通貨・電子マネーによる決済」のための電子情報処理システムに関
する技術と、その一部である「仮想通貨の基幹技術であるブロックチェーン技術」の電
子決済以外も含む用途への応用方法としての技術を扱う(図 1-1)。
図 1-1 本調査の対象技術
本調査で対象とする技術を俯瞰する技術俯瞰図を図 1-2 に示す。仮想通貨・電子マネ
ーによる決済システムの「利用場面」、「決済手段」、決済システムの「要素技術」、技術が
解決しようとする「課題」を整理している。
仮想通貨・電⼦マネーによる決済システムに関する技術
仮想通貨の基幹技術としてのブロックチェーン技術
ブロックチェーン技術の電⼦決済以外も含む⽤途への応⽤⽅法
仮想通貨・電⼦マネーによる決済システムの各種使⽤場⾯への応⽤⽅法、課題解決⼿段、要素技術
ブロックチェーンに関する技術
調査範囲
- 2 -
資料編
第7部
第6部 第5部
第3部
第2部
第1部
本編
要約
目次
第4部
図 1-2 仮想通貨・電子マネーによる決済システムの技術俯瞰図
仮想通貨・電子マネーによる決済システムの利用場面は、大きく、商取引と金融取引
に分かれる。商取引としては、実店舗、自動販売機、交通、病院などにおけるオンサイト
商取引と、仮想店舗、通信、公共料金、税、デジタルコンテンツ、オークションにおける
支払などのオンライン商取引がある。金融取引としては、海外送金、一斉送金、寄付、個
人送金などの送金、クラウドファンディング、証券取引、リース、保険・資産形成などの
投融資がある。
対象とする決済手段としては、電子マネー、仮想通貨、ポイント・クーポン、それらの
組み合わせ(マルチ)を含む。
要素技術としては、仮想通貨・電子マネーによる決済システム一般の要素技術と、仮
想通貨の基幹技術であるブロックチェーン特有の技術があり、さらにそのブロックチェ
ーン技術の決済以外も含む利用場面を対象に含めている。
仮想通貨・電子マネーによる決済システム一般の要素技術としては、各種の認証媒体・
ウォレット、リーダー/ライター、ネットワーク、センターなどのシステムに関するも
の、暗号技術、認証、セルフレジ、レジレスなどの取引対象の管理、決済処理、記録、不
正検出、チャージなどがある。
ブロックチェーン特有の技術としては、鍵の管理、データ管理、コンセンサス、参加者
構成、スクリプト記述、ブロックチェーン間接続、スケーラビリティのための技術など
がある。
ブロックチェーンを含め、要素技術としては、情報セキュリティ技術、配信技術など、
新規技術というより、既存技術の組み合わせにより、新たな機能や用途を生み出すもの
- 3 -
資料編
第7部
第6部
第5部
第3部
第2部
第1部
本編
要約
目次
第4部
といえる。
そのため、本テーマにおいては、要素技術が解決しようとする技術課題の把握が重要
となる。
課題は、安全性、利便性、経済性、スケーラビリティ、追跡性とまとめられる。安全性
は、盗難防止、改ざん防止、間違い防止、滅失防止、プライバシー保護など、本技術が扱
う対象となる価値(マネー)を損なわないようにすることであり、価値(マネー)の交換
を目的とする本テーマの性質上、 も重要な機能といえる。利便性は、ユーザーインタ
ーフェイスの向上を含む円滑な決済、多様な決済手段への対応などで、一般に、安全性
とトレードオフになる。これらの両立が、利用者にとっての各システムの魅力度の主要
な差異となる。経済性は、端末導入の低コスト、ネットワーク・センターシステムの低
コスト化などで、利用者が負担する手数料などに反映されることとなる。スケーラビリ
ティは、利用者数等の拡大に対応できるようにすることであり、将来的に市場拡大フェ
ーズで求められる機能といえる。追跡性は、ブロックチェーン技術を活用する仮想通貨
に特徴的な機能である。
ブロックチェーン技術の決済以外も含めた用途としては、ゲーム内通貨、SNS、証券取
引、クラウドファンディング、チケット・ギフトカード、ポイント・クーポンなどの価値
の記録、不動産取引、為替取引、知的財産権、デジタルコンテンツ利用、投票などの権利
の記録、サプライチェーン、ヘルスケア、偽造防止・真正性担保、貴重品管理、オークシ
ョン、各種届出、シェアリングエコノミー、スマートモビリティ、広告・広報などの関与
者の記録、スマートコントラクト、エスクロー自動化、デリバティブ、エネルギー管理、
消耗品管理、遺言・会社清算など処理の自動化など、非常に多様な用途への活用が期待
されているところである。これらの中には既存の業務におけるブロックチェーン技術や
仮想通貨の活用の他、シェアリングエコノミーやブロックチェーンゲームなど、新たな
経済活動を形成する用途が想定されている。
- 4 -
資料編
第7部
第6部 第5部
第3部
第2部
第1部
本編
要約
目次
第4部
本調査における「電子マネーによる決済」とは、オンサイト又はオンラインでの商取
引における代価弁済や送金又は投融資のための資金移動等の使用場面において、現金交
付や預金振込(小切手・手形などの指図手段、オンラインバンキング、ネッティングを
含む)に加えて、通貨の価値の移動を媒介する手段であって、価値の媒介のためのプロ
セスや、認証、不正検出等の安全対策を実現する主要な要素として電子情報処理システ
ムを用いるものをいう。ただし、乗車券、興行チケットなど特定目的にのみ用いられる
ものは含まず、多様な場面で汎用的に使用できるものとする。
従来からあるクレジット決済は、“電子マネー”の概念に含まれると言い難いが、IC チ
ップによる決済処理の迅速性、サインレス決済などの技術的特徴を付加したものはポス
トペイ型電子マネーの一種といえる。そもそも新規性がなければ特許にならないため、
本調査においてはクレジット決済やデビット決済も広く電子マネーに含むと考えてよい。
本調査における「仮想通貨による決済」とは、国家、その他の統治主体によらない技術
的な価値保証の仕組み(ブロックチェーン技術)を用いて、同様な使用場面における決
済を行うものをいう。
図 1-3 本調査における「仮想通貨・電子マネーによる決済」の定義
決済⼿段
現⾦交付
⼿形・⼩切⼿振り出し
預⾦振込(窓⼝・ATM)
オンラインバンキング
仮想通貨・電⼦マネーによる決済
調査範囲
クレジット決済
デビット決済
電⼦マネー決済
リアルタイム/ジャストペイ型
仮想通貨決済
ポストペイ型
プリペイド型
特定⽬的のeチケット等
ネッティング
- 5 -
資料編
第7部
第6部
第5部
第3部
第2部
第1部
本編
要約
目次
第4部
第 2 章 市場環境調査
第 1 節 電子決済市場の概況と背景
1. 事業構造
近年、情報通信技術の成熟と金融サービスが融合する形である「FinTech」という言葉
が官民を通じて良く使われるようになっている。それに伴い、金融サービスでも消費者
の生活に直接関わりをもち、非常に大きな市場である電子決済の動きが活性化している。
電子決済とは、物品の購入やサービスの対価を現金ではなく電子的なデータで処理する
取引のことをいう。
現在、電子決済の中心的な役割を担っているのはクレジットカードであるが、1980 年
代頃から登場したデビットカードとプリペイドカード、2000 年代頃から普及した Suica
等の交通系 IC カードに代表される非接触 IC 技術の活用、2010 年代のスマートフォンの
急速な普及、特に中国で爆発的に普及した QR コード決済から仮想通貨による決済まで、
利用シーンにおいても多彩な様相を示している。
このように様々な電子決済のサービスを整理する主な観点には、決済方法(与信型、
預金口座、プリペイド)や価値の記録場所(サーバ側、IC 側)、利用シーン(実店舗等の
対面取引、改札や自動販売機等の非対面取引、オンライン取引)、利用可能範囲(ハウス
型、ブランド型)等がある。しかし、対面取引中心のプリペイドカードに非対面取引に
適したインターフェイスを持たせたり、クレジットカードにプリペイド機能を追加した
り、利用シーンや技術的工夫の融合が進み、単純な分類は難しくなりつつある。
2. 電子決済が普及する背景
(1) 日本
日本の電子マネー決済は、ソニーが開発した非接触型 IC カードの技術方式「Felica」
を採用し、2001 年に開始された「Suica」の普及をきっかけに大きく市場が広がった。
その後、2004 年には同じく「Felica」を採用した「おサイフケータイ」の登場がモバイ
ル決済の 初である。なお、「Felica」は処理速度に優れて実績のある近距離無線通信
の規格だが、日本以外ではあまり採用されておらず、海外では「NFC Type-A/B」方式が
主流である。 近の世界的なスマートフォンの普及によって、多くの人が手元に備えて
手軽に使えるモバイル決済のシーンが拡大している。
我が国では、少子高齢化や人口減少に伴う労働者人口の減少の影響から、産業の生産
性向上が喫緊の課題となっている。電子決済の普及によって社会のキャッシュレス化を
推進することは、金融機関や商店等の店舗の無人化や省力化による労働生産性向上が見
込まれる他、現金を維持するために必要な社会インフラコスト(硬貨の鋳造、紙幣の発
行、現金の輸送や警備、現金の廃棄等)を軽減する効果がある。さらに、生活のあらゆ
る場面で決済が簡単に行えるようになることで消費者の生活を豊かにし、かつ支払いデ
ータを消費者自身や第三者が利活用することは双方の利便性を高め、消費行動の活性化
につながると期待されている。
一つの例として、経済産業省とコンビニエンスストア各社は 2017 年 4 月に「コンビ
ニ電子タグ 1000 億枚宣言」を策定し、2025 年までに全ての取扱商品に「電子タグ」を
- 6 -
資料編
第7部
第6部 第5部
第3部
第2部
第1部
本編
要約
目次
第4部
付与し、物流をスマート化することを計画している1。このようなモノの動きに加えて、
取引の流れと金の流れをすべて把握・分析できるようにすることで、サプライチェーン
全体を効率化し、新たな価値による新産業の創造に繋がる可能性がある。
この他、2020 年に開催される東京オリンピック・パラリンピック競技大会をはじめと
する観光振興の施策としても電子決済は注目されている。 近では事前にインターネッ
トで調べた日本各地の隠れた名所を訪れる外国人観光客も増加しており、地方の観光地
や商店街においては、現金しか扱えないことで少額のカード決済に慣れた外国人旅行者
の消費機会を逸しないようにする取組みが必要である。
(2) 海外
米国では、クレジットカードの審査が厳しい為、国民の約半数はクレジットカードを
持つことができず、約 2 割はデビットカードも持っていない。このようなカード決済が
できない人も携帯端末から商品やサービスを購入できるようにするという社会的課題
の解決が電子決済の目的の一つとなっている。
スウェーデンでは、2000 年代まで銀行強盗事件が多発し、現金を所持するリスクを軽
減することを目的の一つとしてキャッシュレス化施策が実施された。2007 年には公共
交通機関での現金取扱いを中止し、2010 年代には多くの金融機関の店舗が現金の取扱
いを中止した。さらに、スウェーデンの主要銀行 11 行による共同開発で 2012 年に登場
した電子マネー「Swish」がスマートフォンの電話番号と国民個人識別番号を統合した
決済アプリケーションとして 2017 年末には総人口の約 60%が利用するまでに成長し、
事実上のデファクトスタンダードとなった。 近では体内に埋め込んだマイクロチップ
認証による決済システムがスウェーデン鉄道で導入されている。
インドでは、テロ組織による偽造紙幣や不正蓄財等の犯罪対策として、2016 年に高額
紙幣である 500 ルピー(約 815 円)と 1,000 ルピー(約 1,630 円)の流通を差し止め
た。法定通貨の効果を停止された旧紙幣は、短い期間で銀行への預入を通じて新紙幣に
交換された。インドは、政府が把握できない違法な経済活動が GDP の 20%以上あるとい
われており、これらを可視化する必要があったことが背景にある。結果として、国民が
タンス預金をもてなくなることで目に見える預貯金が大幅に増加し、長期的には徴税が
容易になるというメリットも挙げられたが、不正資金の撲滅の効果は思ったほど上がら
ず、一時的に消費が冷え込むという反動もあった2。
中国では、2012 年以降にスマートフォンが爆発的に普及した。中国のモバイルインタ
ーネットユーザ数は 2010 年の約 3.0 億人から 2013 年には約 5.0 億人に増え、2017 年
には 7.5 億人以上に達している3。このような巨大なインフラが構築されたことにより、
中国ではあらゆるネットサービスが、パソコンよりもスマートフォンを優先して作られ
るようになった。このことが中国でモバイル決済が急速に普及した一因となっている。
韓国では、2000 年に開始した政府の積極的なキャッシュレス化施策(年間クレジット
1 経済産業省 商務・サービスグループ 消費・流通政策課「キャッシュレス・ビジョン」(2018/4)
http://www.meti.go.jp/press/2018/04/20180411001/20180411001-1.pdf 2 産経ニュース「インド高額紙幣廃止1年 不正資金撲滅の“奇策”も効果薄く…「経済低迷の原因」指
摘も」(2017/11/18) 3 CNNIC「中国インターネット発展情況統計報告」(2018/1)
- 7 -
資料編
第7部
第6部
第5部
第3部
第2部
第1部
本編
要約
目次
第4部
カード利用額の 20%の所得控除、宝くじの権利付与、年商 240 万円以上の店舗にクレジ
ットカード取引義務付け)が功を奏し、世界で も高いキャッシュレス決済比率を保持
している。
第 2 節 市場規模
1. 国内市場
日本国内における電子決済の比率は民間 終消費支出の約 4 分の 1 であり、2025 年に
は約 4 割になると見られている。また、電子決済の大部分を占めるクレジットカード決
済の取引高は、2017 年の 58 兆円から 2020 年には約 73 兆円(伸び率:約 26%)になると
予測されている(図 2-1)。この他、デビットカード決済は 2017 年の 9,911 億円から 2020
年には約 1.5 兆円(伸び率:約 51%)、プリペイドカード決済は 2017 年の 10 兆円から
2020 年には 13 兆円(伸び率:約 30%)と、クレジットカードと同様に伸長すると予測さ
れている1。
図 2-1 日本国内における現金等と電子決済の比率推移予測
出典 カード・ウェーブ「電子決済総覧 2017-2018」(2017/8)
1 カード・ウェーブ「電子決済総覧 2017-2018」(2017/8)p25
- 8 -
資料編
第7部
第6部 第5部
第3部
第2部
第1部
本編
要約
目次
第4部
2. 海外市場
日本における電子決済はクレジットカード決済が中心で、かつ海外諸国と比較すると
非常に低い水準に留まっているが、この数年間に各国のキャッシュレス決済比率は大幅
に増加している。特に電子決済先進国であるスウェーデンやノルウェー等の北欧諸国で
は電子決済に留まらず、紙幣や硬貨を用いないデジタル通貨の社会が実現しようとして
いる。北米や欧州、アジア太平洋の先進国は非現金決済の比率が着実に増加しており、
また東南アジア等の新興国においても総じてスマートフォンの普及が進み、モバイル決
済が普及し始めている。
図 2-2 諸外国におけるキャッシュレス決済比率の変化とキャッシュレス化の施策例
出典 経済産業省「キャッシュレス化推進に向けた国内外の現状認識」(2017/8)
第 3 節 決済以外も含むブロックチェーン技術の市場
1. 仮想通貨
世界で流通する仮想通貨は 1,500 種類以上あり、これに ICO 等を含めると数百万種類
に上るといわれている。代表的な仮想通貨は、ビットコイン、イーサリアム、リップル
等である。仮想通貨の取引量は近年急激に増えており、例えばビットコインの一日あた
りの取引量は、2015 年迄は 100 億円程度で推移していたが、2017 年以降は 大で 3 兆円
に迫る状況となっている。また、ビットコイン取引の約 6 割は日本の投資家によるもの
と見られている1。
また、国内でビットコインやイーサリアム等の仮想通貨で決済ができる店舗が増えて
いる。2018 年 3 月現在、国内にはビットコインが使える店舗数は 52,190 店舗、イーサリ
アムが使える店舗は 80 店舗ある 1。仮想通貨による決済には、「海外と取引をする際に外
1 一般社団法人日本仮想通貨交換業協会「仮想通貨取引についての現状報告」(2018/4)
- 9 -
資料編
第7部
第6部
第5部
第3部
第2部
第1部
本編
要約
目次
第4部
貨両替の為替リスクや手数料を軽減できる」「カード会社等を介さず直接顧客と取引でき
るため、送金にかかるコストと時間を圧縮できる」というメリットがあり、その一方で
デメリットとしては「価格変動が大きい」や「オフライン環境で利用できない」といっ
た点がある。
仮想通貨を決済に利用することは既存取引の合理化だけでなく、新しい領域の開拓に
つながるとの期待もある。例えば、これまで従来のクレジット決済では加盟店手数料が
かかり実現が難しかったマイクロペイメント(1 円単位の少額課金)の仕組みを活用した
事業や、低コストでシステムを構築して通貨同士の連携を進めたいと考える地域通貨の
活性化、小規模なポイントサービスの相互連携によるコミュニティ形成等が考えられる。
2. ブロックチェーン技術の適用分野
現在、進行しているブロックチェーン技術の適用分野とユースケースを以下に挙げる。
金融分野では、国際送金における時間とコストの問題を解消するために、ブロックチ
ェーンを活用して銀行と銀行が直接、分散型台帳で情報を共有し、リアルタイムに送金
を行う取組みが行われている。また、中小企業向けの貿易決済向けにも複数のプロジェ
クトが進行している。
証券分野では、各国の証券取引所において分散型台帳による証券決済の分散管理の実
証研究が進んでいる。
保険分野では、保険申込書類の確認作業において、証券の発行や管理における時間と
コスト、セキュリティの問題を解決するための実証実験が行われている。
医療分野では、電子カルテや投薬や検査記録等ビッグデータとして非常に価値がある
が、個人情報としては機微で取り扱いに注意を要するデータをブロックチェーン技術で
管理する取組みが行われている。具体的には、医療データそのものはブロックチェーン
に記録せず、データを保持する機関へのパスを管理するという手法がとられる。
ブロックチェーンのトレーサビリティ機能を生かした応用例として、ダイヤモンド等
高額商品の所有履歴管理による信頼性の担保、権利移転をスムーズにする不動産取引、
食品の流通経路管理による安全性の担保、部品の出所を管理するサプライチェーンマネ
ジメント等に活用され始めている。
一定条件を満たす場合に自動的に処理を行うスマートコントラクト機能を生かした応
用例として、証券の売り注文と買い注文に伴う複雑な業務や、保険金支払いに伴う煩雑
な業務の自動化による時間とコストの削減等が期待されている。
音楽・映像・広告・出版・ゲーム等のコンテンツ分野においても、バリューチェーン
の各段階(企画・制作、流通、管理)において、透明性の高い情報共有の仕組みや違法
コピー・改ざん等の権利侵害を防止するブロックチェーン技術の活用が多くの実証実験
を通じて検討されている。
- 10 -
資料編
第7部
第6部 第5部
第3部
第2部
第1部
本編
要約
目次
第4部
第 3 章 政策動向調査
第 1 節 電子決済の推進政策
1. 日本
我が国は、日本経済の再生に向けた「3 本の矢」の 1 つである「日本再興戦略」(2016
改定版)1において、2020 年に開催されるオリンピック・パラリンピック東京大会開催等
を視野に入れたキャッシュレス化の推進を目指している。
政府は、電子メール等の電磁的方法によってクレジットカード利用時の加盟店におけ
る書面交付義務を緩和することや、クレジットカードデータ利用に係わる API 連携の促
進、レシートの電子化促進のためのフォーマット統一等の環境整備を実施する等の施策
を通じて、2027 年 6 月までにキャッシュレス決済比率を現在の 2 割弱程度から 4 割程度
2に引き上げ、さらに将来的には世界 高水準の 80%3を目指すことを目標に掲げている。
経済産業省の資料4によると、日本の現金決済インフラには年間 1 兆円を超えるコスト
が発生しており、キャッシュレス化の推進による潜在的経済効果(家計所得の向上、消
費者余剰、電子決済関連産業の成長等)は、6 兆円以上に上ると推測されている。この他、
キャッシュレス化が進まないことによる社会負担として、訪日外国人の利便性低下によ
る機会損失、現金決済のレジ待ちによる時間的損失等があげられる。日本政府はこのよ
うな社会負担を軽減し、キャッシュレス化推進による潜在的経済効果を上げる為、2020
年の東京オリンピックや 2025 年の大阪万博等のイベントを契機としたキャッシュレス
化施策を推進している。
2. 海外
(1) スウェーデン
スウェーデンでは、冬期期間の現金輸送の困難さや現金強盗事件等の犯罪対策を背景
に早くからキャッシュレス化が進んだ。特に、2012 年 12 月に登場した個人間送金・支
払サービスを提供するスマートフォンアプリ「Swish」は、2017 年 10 月末時点でスウェ
ーデン総人口約 1,000 万人の約 60%が利用するデファクトスタンダードなサービスに成
長している。また、2013 年には高額紙幣である 1,000 クローナ5紙幣を廃止している。
(2) デンマーク
デンマーク政府は、2030 年を目処に完全なキャッシュレス社会を目指し、現金からの
移行を進めている。デンマーク国立銀行では国内での通貨製造を廃止することを決定し、
2017 年以降紙幣の造幣を行っていない。
デンマークにおけるキャッシュレス化の土台は「Dankort」と呼ばれるデンマーク独
1 首相官邸「日本再興戦略 2016」(2016/6) 2 首相官邸「未来投資戦略 2017」(2017/6) 3 経済産業省 商務・サービスグループ 消費・流通政策課「キャッシュレス・ビジョン」(2018/4)P53-71 4 経済産業省 平成 29 年度産業経済研究委託事業「我が国における FinTech 普及に向けた環境整備に関す
る調査検討」(2018/3) 5 2018 年 7 月現在、1,000 クローナは約 12,500 円。
- 11 -
資料編
第7部
第6部
第5部
第3部
第2部
第1部
本編
要約
目次
第4部
自のデビットカードの普及にある。その後、2013 年にはデンマーク 大の銀行である
Danske Bank がクレジットカードに紐付けられた「MobilePay」というモバイル決済サー
ビスを開始し、現在の主流となっている。2015 年には公共サービスや健康への影響と直
結するような場所以外において現金での支払を拒否する権利を付与する指針を打ち出
す等、国をあげたキャッシュレス化推進に取り組んでいる。
(3) カナダ
VISA の調査1によると、カナダは個人消費支出におけるカード支払いの比率が 68%と、
非常に高い水準にある。特に、オタワやトロントは電子決済の利用が も発展している
都市の一つと位置づけられている。
カナダ政府は 2013 年 2 月、製造コストの削減を理由に 1 セント硬貨の発行を廃止し
た。廃止以降も 1 セントの価値はそのままで、クレジットカードやデビットカードの場
合は今まで通り 1 セント単位で処理され、現金の場合は 5 セントか 10 セントに切上げ
または切捨てして支払いが行われる。
(4) 米国
米国は、クレジットカードやオンラインペイメントの発祥であり、キャッシュレス先
進国の一つである。世界をリードする大規模な金融機関や ICT 企業が数多く存在し、民
間主導による技術及びサービス開発が進んでいる。また、国が注力するスマートシティ
プロジェクトの一環として、スマートモビリティにおける非接触運賃決済ソリューショ
ンや RFID による自動料金徴収といった具体的な取組みがなされている。
(5) 韓国
韓国では、政府主導によるクレジットカード利用促進策によって世界でも非常に高い
キャッシュレス化を実現している。その施策は年間クレジットカード利用額の 20%の所
得控除やクレジット利用者に対する宝くじの権利付与、年商 240 万円以上の店舗にクレ
ジットカード取引を義務付けする等、消費者が直接的にメリットを享受できるものとな
っている。これらの施策によって、1999 年から 2002 年にかけて、クレジットカード利
用金額は 6.9 倍に急拡大した2。
(6) 中国
中国では、2002 年 3 月に国内 80 強の金融機関によって共同で設立された中国銀聯に
よって金融機関間の決済システムやルールの標準化及びオンラインネットワークの整
備が進んだこと、2004 年 12 月にショッピングサイトにおける代金と商品の受渡の安全
を保証するスマートフォン決済サービスアプリ「アリペイ」が登場し、急速に浸透した
こと等を背景にキャッシュレス化が進んだ。
1 CNET Japan「Visa、日本の“現金社会”を変え『キャッシュレス・ジャパン』目指す」(2016/2/11), https://japan.cnet.com/article/35077687/ 2 経済産業省 商務・サービスグループ 消費・流通政策課「キャッシュレス・ビジョン」(2018/4)
- 12 -
資料編
第7部
第6部 第5部
第3部
第2部
第1部
本編
要約
目次
第4部
(7) インド
インド政府は、2016 年 11 月に今まで流通していた高額紙幣の 1,000 ルピー1紙幣と
500 ルピー紙幣の廃止を突然に宣言し、世界を驚かせた。この政策の主な目的は不透明
な国内経済を「見える化」することにあったが、同時にキャッシュレス経済へ向けて大
きく舵取りを取っている。政府では高速道路の料金や運転免許発行手数料の支払い電子
化、デジタル決済の場合に国営石油会社のガソリン代や国営保険会社の保険料、国営鉄
道の乗車券を値引きするといった施策を実施している2。
3. 標準化の動向
代表的な電子決済手段である非接触 IC 電子マネーの近距離無線通信技術は、NFC(Near
Field Communication)として国際規格(ISO/IEC 14443)で定められている。NFC には、
オランダの NXP Semiconductor(旧 Phil Philips 社半導体部門)が開発し、比較的安価
に使用できることから世界で も多く普及している Type-A と米国のモトローラが開発
し、セキュリティレベルの高さから運転免許証やパスポート等に使われる Type-B とがあ
る。
また、国内の非接触 IC 電子マネーで も普及している Felica は NFC の一種であり、
ソニーが開発した。Felica は、他の技術に比べて通信速度が圧倒的に早いという特長が
あり、大量の人が行きかう日本の電車の改札等では欠かせないものだが、海外ではこれ
まであまり普及していなかった3。Felica は、国内で標準化(JISX6319-)された後、上
位互換をもつ方式が Type-F(ISO/IEC 18092)として国際標準化されている。
QR コードは、デンソーウェーブが開発し、国内では 1999 年に JIS 規格として標準化
(JIS X 0510)、ISO 規格としても 2000 年に国際標準化(ISO/IEC 18004)された技術で
ある。特許権者のデンソーウェーブは、規格化された技術に対し特許権を行使しないと
宣言しており、世界中で普及が進んでいる。
中国において近年、QR コードとスマートフォンを活用した電子決済が急速に普及した
ことを受け、日本でも QR コードがキャッシュレス化推進の切り札として期待されてい
る。2018 年 7 月に設立されたキャッシュレス推進協議会では、喫緊の課題として QR コ
ード決済にまつわる技術的・業務的な使用の標準化に取り組んでいる。
第 2 節 仮想通貨とデジタル通貨
1. 日本の動向
日本の中央銀行である日本銀行は、政府発行による仮想通貨の研究を具体的に行って
いる4。現時点では解決すべき課題も多く、新しい通貨を発行する具体的な計画はないも
のの、技術的には発行可能との見解5を示している。
1 2018 年 7 月現在、1,000 ルピーは約 1,600 円。 2 時事ドットコムニュース「『キャッシュレス経済』を推進せよ インド『高額紙幣廃止』の遠大な狙い」
(2017/1/16)https://www.jiji.com/jc/v4?id=foresight_00199_201701160001 3 2017 年に、米アップル社が 新の iPhone や Apple Watch の世界標準モデルに Felica を搭載したことは
大きな話題となった。 4 日本銀行「日本銀行・欧州中央銀行による分散型台帳技術に関する共同調査」(2017/9) 5 Bloomberg News「日銀・河合氏:法定デジタル通貨は技術的に可能-検討段階にない」(2018/1/29)
- 13 -
資料編
第7部
第6部
第5部
第3部
第2部
第1部
本編
要約
目次
第4部
民間においては、法定通貨と連動する形(1 コインを約 1 円として)で、三菱 UFJ フィ
ナンシャルグループが「MUFG コイン」を、みずほフィナンシャルグループが「J コイン」
の発行を計画している。従来の銀行サービスは台帳データの管理に多大なコストをかけ
ており、他業種からの新規参入障壁が高かったが、ブロックチェーン技術によってデー
タの信頼性が担保され運営コストが軽減されると、銀行事業そのものがコモディティ化
する恐れがある。これらの伝統的な金融機関は主体的に仮想通貨を手がけて主導権を得
ることにより、先んじてコスト削減を行い、さらにはユーザ行動情報の入手やグローバ
ルな販路の拡大を狙っている。
2. 海外の動向
(1) 米国
米国では、FedCoin と呼ばれる FRS(Federal Reserve System:連邦準備制度)発行
のデジタル通貨が検討されている。2018 年 7 月に開催された米国下院金融サービス委
員会では、政府が発行する仮想通貨のメリットと FRS での導入可能性の検討が行われ、
世界中の多くの中央銀行が何らかの形態でデジタル通貨を導入することを検討してい
ることや紙幣の有用性の低下とデジタル経済への急速な変化を認識しつつも、早急に結
論を出すべきでなく、デジタル通貨のあらゆる側面を慎重に検討すべきとしている1。
(2) 英国
英国では、中央銀行であるイングランド銀行がデジタル通貨を主要研究テーマの一つ
に位置づけている。その中で、2018 年 5 月にはデジタル通貨が商業銀行に脅威を与え
る可能性があるという報告書2やデジタル通貨が民間信用や経済への総流動性供給に悪
影響を与えないとする報告書3が公表され、近い将来のデジタル通貨発行を否定しつつ
も、将来の見通しには柔軟な姿勢を示している。
(3) 欧州
欧州連合(EU)も、各国の中央銀行で導入が検討されているデジタル通貨について、
慎重かつ肯定的な立場を取っている。また、2018 年 7 月に公表した欧州議会経済金融
委員会の要請に基づく調査報告書4においては、銀行や中央銀行による独自の仮想通貨
(デジタル通貨)が発行された場合、ビットコインのような非政府機関による仮想通貨
の市場を脅かす可能性があると報告された。
この他、欧州連合では ECB(European Central Bank:欧州中央銀行)がマネーロンダ
リング対策を目的に 500 ユーロ5券の発行を 2018 年まで停止することを公表している。
500 ユーロ券はその後も無期限で法定通貨として使用でき、他の紙幣と交換できる。
1 FINANCIAL SERVICES COMMITTEE,「The Future of Digital Currency」(2018/7) 2 BANK OF ENGLAND,「Competition for retail deposits between commercial banks and non-bank
operators: a two-sided platform analysis」(2018/5) 3 BANK OF ENGLAND,「Central bank digital currencies — design principles and balance sheet
implications」(2018/5) 4 EU Policy Department for Economic, Scientific and Quality of Life Policies,「Competition
issues in the Area of Financial Technology」(2018/7) 5 2018 年 8 月現在、500 ユーロは約 64,000 円。
- 14 -
資料編
第7部
第6部 第5部
第3部
第2部
第1部
本編
要約
目次
第4部
(4) 中国
中国は、かつてマイニングを中心として仮想通貨市場の中心的存在であったが、現在
では仮想通貨の取締りが強化され、世界で も仮想通貨に厳しい国へと変貌している。
中国政府は 2017 年 9 月に ICO による資金調達を禁止し、仮想通貨取引所は実質的な閉
鎖に追い込まれた。その一方で、中国人民銀行では 2014 年頃から多額の資金を投じて
仮想通貨の研究が続けられており、近い将来にブロックチェーン技術を用いた政府によ
る仮想通貨が発表される可能性もある。
(5) スウェーデン
スウェーデンでは、2017 年 3 月にデジタル通貨「E-krona」の 3 段階の導入工程表を
発表した。2018 年末をめどに発行の是非を決定するとしている。スウェーデンではキャ
ッシュレス化が進み、スマートフォンベース用の決済アプリである「Swish」が人口の
半数以上に普及している等、現金の流通量が大きく減少している。その為、経済的な事
情等でカードやスマートフォンが使えない市民への民主主義的な問題への対応として
もデジタル通貨の必要性が捉えられている。
(6) スイス
税率が低く生活水準が高いことから多くの多国籍企業が集まるスイスのツーク州は、
暗号通貨大手のイーサリアムをはじめとするブロックチェーン関連企業が集中し、仮想
通貨版シリコンバレーを意味する「クリプトバレー」と称されている。ベンチャーキャ
ピタルの調査1によれば、クリプトバレーの仮想通貨やブロックチェーン関連企業数は
約 600 社で、評価額の総額では 440 億ドル(約 4.9 兆円)に上っている。
クリプトバレーには、多くの ICO で指名されている法律事務所の MME や ICO を支援し
ているビットコイン・スイスといった企業や人材が集まることにより、ブロックチェー
ン業界を支えるエコシステムが形成2されている。こうした動きに合わせて、ツーク州政
府は世界で初めて公共料金のビットコイン払い( 大 205 ドル)に対応3している。
(7) マルタ
イタリアと北アフリカの間に位置する小さな島国のマルタは税率が低い国として有
名で、多くの企業や資金を世界中から呼び込んでいる。また、政府はブロックチェーン
技術による産業振興にも積極的な姿勢を示しており、モルガン・スタンレーの調査4によ
ると、マルタの仮想通貨取引高は世界で突出して 1 位である。
2018 年 7 月には、ICO 発行から仮想通貨取引所までをカバーした 3 つの法案(仮想金
融資産法案:ICO の法的な枠組みを定めたもの、マルタ・デジタル・イノベーションオ
ーソリティ法案:マルタ・デジタル・イノベーション庁の設立によるブロックチェーン
産業の規制と推進、テクノロジーアレンジメントおよびサービスプロバイダー法案:取
1 CV VC AG, "The Crypto Valley's Top 50" (2018/10) 2 富士通ジャーナル「スイスの『クリプトバレー』に見るブロックチェーン 新事情」(2017/12) 3 NBC News, "Bitcoin Breakthrough: Cryptocurrency Welcome in Zug, Switzerland"(2016/5) 4 BUSINESS INSIDER, "MORGAN STANLEY: Here's where cryptocurrencies are traded around the globe"(2018/5)
- 15 -
資料編
第7部
第6部
第5部
第3部
第2部
第1部
本編
要約
目次
第4部
引所の規制)が可決され、仮想通貨を扱う社会基盤を整備している。
第 3 節 決済以外も含むブロックチェーン技術
1. 標準化の動向
ブロックチェーン技術に対する国際的な関心の高まりを受け、2016 年 4 月に ISO(国
際標準化機構)において、ブロックチェーンの標準化を行う技術委員会設置の国際提案
が行われ、2016 年 9 月に ISO/TC307 Blockchain and electronic distributed ledger
technologies(ISO/TC307 ブロックチェーンと電子分散台帳技術に係る専門委員会)が
発足した。本委員会では「ブロックチェーンと電子分散台帳におけるシステム」「アプリ
ケーション、ユーザ間の互換性やデータ交換」に関わる国際標準化活動が開始された。
日本からは、工業標準化法に基づいて経済産業省に設置される審議会である日本工業標
準調査会(JISC)が参加している。
ブロックチェーン技術を推進する主な国際的なプロジェクトは 3 つある。一つは、
Linux 財団が開発する Hyperledger で、ブロックチェーンベースの分散元帳をサポート
したオープンソースのプラットフォームを提供している。日本からは、初期メンバーと
して富士通、日本電気、日立製作所、NTT データの 4 社が参画している。もう一つは、R3
コンソーシアムが開発する Corda で、金融機関における銀行間送金やデータ管理のコス
ト及び時間短縮を目指したオープンソースの分散型プラットフォームを提供している。
R3 コンソーシアムには、米 R3 社の他に日本のメガバンク 3 社を含む世界各国の有力な
金融機関 200 社以上が参加している。また、日本の SBI ホールディングスは、米 R3 社の
外部筆頭株主である。 後は、米 Ripple 社が提唱する Interledger Protocol で、世界
中の異なる台帳やネットワークをまたがる取引における決済方法のプロトコルとして現
在は W3C(World Wide Web Consortium)が開発を行っている。
なお、Ripple と R3 コンソーシアムは、2016 年に締結したパートナーシップに基づく
同意書に基づく仮想通貨リップルの購入価格をめぐって争っていたが、2018 年 11 月に
和解に至っている。和解の条件等は公開されていない。
2. 実証実験やサービス化の動向
ブロックチェーン技術の社会実装の促進には、国や民間による実証実験を通じ、事業
としての成果や課題の集積、技術的検証、法制度の検討と見直しが不可欠である。既に
様々な分野でブロックチェーン技術を用いた実証実験やサービス化の取り組みが行われ
ている。これまでに実施された実証実験やサービス化の例を以下に挙げる。
<業務効率化>
業態をまたいだ複数の企業による貿易情報連携基盤による業務効率化(株式会社
NTT データ、川崎汽船株式会社、株式会社商船三井、双日株式会社、損害保険ジ
ャパン日本興亜株式会社、東京海上日動火災保険株式会社、豊田通商株式会社、
日本通運株式会社、日本郵船株式会社、丸紅株式会社、株式会社みずほフィナン
シャルグループ/株式会社みずほ銀行、三井住友海上火災保険株式会社、株式会
- 16 -
資料編
第7部
第6部 第5部
第3部
第2部
第1部
本編
要約
目次
第4部
社三井住友銀行、株式会社三菱東京 UFJ 銀行:ブロックチェーン技術を活用した
貿易情報連携基盤実現に向けたコンソーシアム)
複数のユーザや拠点によるドキュメント制作と改訂履歴管理(アイティメディア
株式会社、ナレッジオンデマンド株式会社、テックビューロ株式会社:ブロック
チェーンを使ったドキュメント改訂履歴管理と恒久記録)
損害保険会社と鑑定会社の情報共有による業務効率化及びセキュリティ確保(三
井住友海上火災保険株式会社、一般社団法人日本損害保険鑑定人協会、株式会社
電縁、株式会社 Orb:ブロックチェーンや分散台帳技術を活用した損害鑑定業務
の実証実験)
スマートコントラクトによる携帯ショップのオペレーション効率化(KDDI 株式会
社、株式会社 KDDI 総合研究所、クーガー株式会社:携帯ショップでの店頭修理
申し込みから修理完了までの情報共有を対象とし、リアルタイム性、プライバシ
ー情報の流通制御、オペレーション効率化の可能性を検証)
<情報共有>
不動産情報一元化におけるブロックチェーン技術の有効性確認(株式会社
LIFULL、株式会社カイカ、テックビューロ株式会社:ブロックチェーンを活用し
た不動産情報共有・利用実証実験)
インターネット広告市場における広告配信実績データの透明性改善(デジタル・
アドバタイジング・コンソーシアム株式会社、日本アイ・ビー・エム株式会社:ブ
ロックチェーン活用によるデジタル広告効果透明化実証実験)
楽曲や画像情報の権利情報をデータベース化(米国 Dot Blockchain Music 社:
ブロックチェーンを活用したあらゆる楽曲情報のデータベース構築をめざすオー
プンソースプロジェクトを推進、スウェーデン Spotify 社:アーティストへの適
正なロイヤリティ支払いの為に分散化したピアツーピア権利帰属情報データベー
スを構築、NTT サービスエボリューション研究所:ブロックチェーンによる動画
コンテンツの権利情報記録と権利者による直接管理)
保険会社と医療機関での情報連携とセキュリティ確保(米国 Planetway
Corporation 社、東京海上日動火災保険株式会社:医療情報に対するセキュリテ
ィを確保しつつ、保険金支払業務の簡略化・迅速化が実現可能かを検証)
<消費者向けサービス>
中古カー用品の個人間売買(株式会社オートバックスセブン、株式会社ベイカレ
ント・コンサルティング:ブロックチェーン技術を活用した中古カー用品の個人
間売買の実証実験)
野菜の生産・流通履歴管理(株式会社電通国際情報サービス、エストニア
Guardtime 社、シビラ株式会社:ブロックチェーン技術を活用して地方創生を支
援する研究プロジェクト)
食肉の生産・流通履歴管理(米国 Walmart 社、米国 IBM 社、中国清華大学:中国
における豚肉の生産・流通経路を記録するブロックチェーンシステムの開発)
- 17 -
資料編
第7部
第6部
第5部
第3部
第2部
第1部
本編
要約
目次
第4部
ブロックチェーンと IoT を活用した「本人のみが受け取れる宅配ボックス」(GMO
インターネット株式会社、GMO グローバルサイン株式会社、株式会社セゾン情報
システムズ:本人のみが受け取れる宅配ボックスの実証実験)
トークンを用いた投稿記事の評価・配信プラットフォーム(株式会社 ALIS:記事
投稿者とそれをいち早く評価した評価者の相互評価によって記事内容の信頼性を
担保する SNS を構築)
トークンで価値を担保したゲームアイテムの取引(スイス EverdreamSoft 社:ブ
ロックチェーン技術でゲーム内カードの発行枚数を管理し、カードの価値が担保
したトレーディングカードゲーム)
転売を抑止する電子チケット(GMO インターネット株式会社:ブロックチェーン
を活用したチケットの転売抑止とチケットレス化の実現)
高級品の真贋証明(英国 Everledger 社:ダイヤモンドの取引履歴の管理、英国
DE BEERS 社他ダイヤメーカー各社:ダイヤモンドの取引履歴の管理、紛争ダイヤ
モンドでないことの証明)
<社会インフラ>
地域通貨による決済(近鉄グループホールディングス株式会社、株式会社三菱総
合研究所:ブロックチェーン技術を活用した仮想地域通貨「近鉄ハルカスコイ
ン」の社会実験)
決済用デジタル通貨を用いた銀行間決済(富士通、みずほ銀行、三菱 UFJ 銀行、
三井住友銀行、りそな銀行、常陽銀行、福岡銀行、西日本シティ銀行、三井住友
信託銀行、京葉銀行:ブロックチェーン技術を活用した新たな銀行間決済の実証
実験)
分散型電力取引サービスの可能性検証(株式会社エナリス、ソラミツ株式会社:
ブロックチェーン技術を活用した電力取引サービス等の商用化に向けた検討)
<医療>
個人の医療・健康情報や保険情報の管理(米国 Medicalchain 社:ブロックチェ
ーン技術により、健康記録を安全に保管し、医師、 病院、研究所、薬剤師、健
康保険会社などが、患者の許可を得た上でレコードにアクセスするための仕組
み)
治験データ管理プラットフォームの構築(サスメド株式会社:治験データの登
録・閲覧をネットワーク上で行うプラットフォームをブロックチェーン技術で実
装)
遠隔医療支援におけるセキュリティの確保(株式会社 TRIART、名古屋大学医学部
附属病院:モバイル遠隔医療支援システムを活用した医師間のオンライン医療支
援の運用実験)
<その他>
株主総会における議決権行使(インフォテリア株式会社:上場企業の株主総会議
決権行使におけるブロックチェーンの実証実験)
- 18 -
資料編
第7部
第6部 第5部
第3部
第2部
第1部
本編
要約
目次
第4部
指紋認証を始めとする生体認証技術とブロックチェーン技術の組合せによって、
本人確認の精度向上とユーザ利便性向上を両立する取組み(カレンシーポート株
式会社、株式会社ディー・ディー・エス:生体認証技術とブロックチェーンを融合
した製品開発)
マイナンバーを活用したインターネット投票(茨城県つくば市:ブロックチェー
ンとマイナンバーカードを使ったネット投票)
地域活性化を促進する電子スタンプラリー(株式会社富士通総研:ブロックチェ
ーンによる地域活性化支援)
テーマパークでの独自デジタル通貨を活用したトークン発行、決済サービス、ユ
ーザウォレット等のキャッシュレス決済基盤サービス(株式会社 Liquid:キャッ
スレステーマパーク)
- 19 -
資料編
第7部
第6部
第5部
第3部
第2部
第1部
本編
要約
目次
第4部
第 4 章 特許出願動向調査
第 1 節 調査対象範囲と調査方法
1. 調査対象範囲
仮想通貨・電子マネーによる決済システム技術に関する特許出願動向について、全体
動向調査、技術区分別動向調査、出願人別動向調査を行った。
(1) 調査対象とした出願先国
今回調査した特許の出願先国は、日本、米国、欧州、中国、韓国(以下、日米欧中韓
と略す場合がある)及び PCT(特許協力条約)に基づく国際出願である。欧州への出願
については、欧州特許庁への出願(EPC 出願)だけでなく、EPC 加盟国の内で検索に使
用した特許データベース(後述)の収録国(アイルランド、イギリス、イタリア、オー
ストリア、オランダ、スイス、スウェーデン、スペイン、スロヴァキア、チェコ、デン
マーク、ドイツ、トルコ、ノルウェー、ハンガリー、フィンランド、フランス、ベルギ
ー、ポーランド、ポルトガル、ルーマニア、ルクセンブルク)への出願も対象とした。
(2) 使用したデータベースと調査対象期間
特許検索に使用したデータベースは、パナソニックソリューションテクノロジー社が
提供する PatentSQUARE 及び、欧州特許庁が提供する Espacenet を用い、 先の優先権
主張年が 2010 年から 2016 年までを調査対象期間とした。
(3) 調査対象技術範囲
本調査における特許データベース検索では、仮想通貨・電子マネーによる決済システ
ム技術に関するキーワード及び IPC(国際特許分類)を使用し、表 4-1 に示した検索式
で検索した結果を調査対象母集団とした。
- 20 -
資料編
第7部
第6部 第5部
第3部
第2部
第1部
本編
要約
目次
第4部
表 4-1 特許データベース検索式
集合
番号 ヒット件数 検索項目 検索式 備考
S001 21,733,265 優先日(D) 20100101:20161231 先の優先権主張年
2010-2016 年 S002 61,946,826 優先日(D) :20091231
S003 20,796,182 論理式 S001#S002
S004 47,201 IPC G06Q20/06?+G06Q20/30?+G06Q20/32?+G06Q20/34?+
G06Q20/36?+G06Q20/22?+G06Q20/24?+G06Q20/26?+
G06Q20/28?
支払経路、電子マネー
/無線/IC カード等、支
払スキーム
S005 85,675 CPC G06Q20/06?+G06Q20/30?+G06Q20/32?+G06Q20/34?+
G06Q20/36?+G06Q20/22?+G06Q20/24?+G06Q20/26?+
G06Q20/28?
S006 35,623 論理式 S003*(S004+S005)
S007 126,683 IPC G06Q20/? 支払アーキテクチャ,
スキーム,またはプロ
トコル
S008 168,021 CPC G06Q20/?
S009 203,656 論理式 S007+S008
S010 860,686 IPC G06Q? 管理目的,商用目的,
金融目的,経営目的,
監督目的または予測目
的に特に適合したデー
タ処理システムまたは
方法;他に分類されな
い,管理目的,商用目
的,金融目的,経営目
的,監督目的または予
測目的に特に適合した
システムまたは方法
S011 712,835 CPC G06Q?
S012 1,043,231 論理式 S010+S011
S013 5,196 文章系組合せ
(英語)
[electronic,digital,internet,web*wallet?,pur
se?]A10//[@発明の名称+要約+請求の範囲]
電子マネー
S014 2,965 文章系組合せ
(英語)
[mobile,”cell phone”?,cellphone?,cell-
phone?*wallet?,purse?]A10//[@発明の名称+要約
+請求の範囲]
S015 67 文章系組合せ
(英語)
[”cellular
phone”?,cellularphone?,cellular-
phone?*wallet?,purse?]A10//[@発明の名称+要約
+請求の範囲]
S016 772 文章系組合せ
(英語)
[smart?,Intelligen?*wallet?,purse?]A10//[@発
明の名称+要約+請求の範囲]
S017 28,620 文章系組合せ
(英語)
[electronic,digital,internet,web*currenc?,mo
ne?,cash?,coin?]A10//[@発明の名称+要約+請求
の範囲]
S018 8,404 文章系組合せ
(英語)
[mobile,”cell phone”?,cellphone?,cell-
phone?*currenc?,mone?,cash?,coin?]A10//[@発
明の名称+要約+請求の範囲]
S019 276 文章系組合せ
(英語)
[”cellular
phone”?,cellularphone?,cellular-
phone?*currenc?,mone?,cash?,coin?]A10//[@発
明の名称+要約+請求の範囲]
S020 4,075 文章系組合せ
(英語)
[smart?,Intelligen?*currenc?,mone?,cash?,coi
n?]A10//[@発明の名称+要約+請求の範囲]
- 21 -
資料編
第7部
第6部
第5部
第3部
第2部
第1部
本編
要約
目次
第4部
S021 884 文章系組合せ
(英語)
electronic-wallet?+electronic-
purse?+electronic-currenc?+electronic-
mone?+electronic-cash?+electronic-coin?+e-
wallet?+e-purse?+e-currenc?+e-mone?+e-
cash?+e-coin?+digital-wallet?+digital-
purse?+digital-currenc?+digital-
mone?+digital-cash?+digital-coin?+internet-
wallet?+internet-purse?+internet-
currenc?+internet-mone?+internet-
cash?+internet-coin?+web-wallet?+web-
purse?+web-currenc?+web-mone?+web-cash?+web-
coin?+electronicwallet?+electronicpurse?+ele
ctroniccurrenc?+electronicmone?+electronicca
sh?+electroniccoin?+ewallet?+epurse?+ecurren
c?+emone?+ecash?+ecoin?+digitalwallet?+digit
alpurse?+digitalcurrenc?+digitalmone?+digita
lcash?+digitalcoin?+internetwallet?+internet
purse?+internetcurrenc?+internetmone?+intern
etcash?+internetcoin?+webwallet?+webpurse?+w
ebcurrenc?+webmone?+webcash?+webcoin?//[@発
明の名称+要約+請求の範囲]
S022 7,402 文章系組合せ
(英語)
suica+edy+waon+nanaco+?au-
wallet?+pasmo+icoca+manaca+pitapa+quicpay?+
”quic pay”?+quic-pay?+applepay?+”apple
pay”?+apple-pay?+googlepay?+”google
pay”?+google-pay?+linepay?+”line
pay”?+line-pay?+alipay?+”ali pay”?+ali-
pay?+wechatpay?+”wechat pay”?+wechat-
pay?+androidpay?+”android pay”?+android-
pay?+unionpay?+”union pay”?+union-
pay?+samsungpay?+”samsung pay”?+samsung-
pay?+?paypal?+?pay-pal?+?”pay
pal”?+webmoney+bitcash+?visa-paywave?+”
visa paywave”+paypass//[@発明の名称+要約+請
求の範囲]
S023 15,031 文章系組合せ
(英語)
[point,points*settle?,pay,paid,payment?,tran
sact?]A5//[@発明の名称+要約+請求の範囲]
S024 48,475 文章系組合せ
(英語)
[point,points,loyalty*card,cards,program?]A5
//[@発明の名称+要約+請求の範囲]
S025 1,035 文章系組合せ
(英語)
[virtual?,?crypt?,?cipher?,?cypher?,cyber*wa
llet?,purse?]A10//[@発明の名称+要約+請求の範
囲]
S026 9,338 文章系組合せ
(英語)
[virtual?,?crypt?,?cipher?,?cypher?,cyber*cu
rrenc?,mone?,cash?,coin?]A10//[@発明の名称+
要約+請求の範囲]
- 22 -
資料編
第7部
第6部 第5部
第3部
第2部
第1部
本編
要約
目次
第4部
S027 620 文章系組合せ
(英語)
virtual-wallet?+virtual-purse?+virtual-
currenc?+virtual-mone?+virtual-
cash?+virtual-coin?+?crypto-wallet?+?crypto-
purse?+?crypto-currenc?+?crypto-
mone?+?crypto-cash?+?crypto-coin?+?cipher-
wallet?+?cipher-purse?+?cipher-
currenc?+?cipher-mone?+?cipher-
cash?+?cipher-coin?+?cypher-wallet?+?cypher-
purse?+?cypher-currenc?+?cypher-
mone?+?cypher-cash?+?cypher-coin?+cyber-
wallet?+cyber-purse?+cyber-currenc?+cyber-
mone?+cyber-cash?+cyber-
coin?+virtualwallet?+virtualpurse?+virtualcu
rrenc?+virtualmone?+virtualcash?+virtualcoin
?+?cryptowallet?+?cryptopurse?+?cryptocurren
c?+?cryptomone?+?cryptocash?+?cryptocoin?+?c
ipherwallet?+?cipherpurse?+?ciphercurrenc?+?
ciphermone?+?ciphercash?+?ciphercoin?+?cyphe
rwallet?+?cypherpurse?+?cyphercurrenc?+?cyph
ermone?+?cyphercash?+?cyphercoin?+cyberwalle
t?+cyberpurse?+cybercurrenc?+cybermone?+cybe
rcash?+cybercoin?//[@発明の名称+要約+請求の
範囲]
S028 79,749 文章系組合せ
(英語)
(QR+(”Quick Response”?+Quick-
Response?)*code?+barcode?+bar-code?+”bar
code”?)//[@発明の名称+要約]
QR コード、バーコード
S029 23,787 文章系組合せ
(英語)
[2D?,two-d?,2-d?,”two d”?,”2
d”?*code?]W10//[@発明の名称+要約]
二次元コード
S030 12,753 論理式 S003*S009*(S013+S014+S015+S016+S017+S018+S01
9+S020+S021+S022+S023+S024+S025+S026+S027+S0
28+S029)
電子マネー・仮想通貨
に関する集合 A
S031 638,284 文章系組合せ
(英語)
settle?+pay+paid+payment?+transact?//[@発明
の名称+要約+請求の範囲]
決済
S032 15,157 論理式 S003*S012*(S013+S014+S015+S016+S017+S018+S01
9+S020+S021+S022+S023+S024+S025+S026+S027+S0
28+S029)*S031
電子マネー・仮想通貨
に関する集合 B
S033 5,200 文章系組合せ
(英語)
blockchain?+”block chain”?+block-
chain?//[@発明の名称+要約+請求の範囲]
ブロックチェーン関連
技術
S034 378 文章系組合せ
(英語)
proof-of-work?+proof-of-stake?+”proof of
work”?+”proof of stake”?+”smart
contract”?+smart-
contract?+hyperledger?+cryptoNote?+Ethash+”
initial coin offering”?//[@発明の名称+要約+
請求の範囲]
S035 1,951 文章系組合せ
(英語)
[distribut?,decentral?*ledger?,currenc?]A20/
/[@発明の名称+要約+請求の範囲]
S036 14,601 文章系組合せ
(英語)
[mining,”multi
sig”?,consensus,token?,hash*block,blocks,ch
ain?,”distributed ledger”?]A20//[@発明の名
称+要約+請求の範囲]
S037 8,603 文章系組合せ
(英語)
[PoW,PoS,DLT,ICO,P2P*block,blocks,chain?,”
distributed ledger”?]A20//[@発明の名称+要約
+請求の範囲]
S038 642 文章系組合せ
(英語)
[SHA,SHA1?,SHA-1?,SHA2?,SHA-
2?*block,blocks,chain?,”distributed
ledger”?]A20//[@発明の名称+要約+請求の範囲]
- 23 -
資料編
第7部
第6部
第5部
第3部
第2部
第1部
本編
要約
目次
第4部
S039 20 文章系組合せ
(英語)
[SHA3?,SHA-3?,SHA5?,SHA-
5?*block,blocks,chain?,”distributed
ledger”?]A20//[@発明の名称+要約+請求の範囲]
S040 10 文章系組合せ
(英語)
[RIPEMD?,RIPEMD-1?,RIPEMD-2?,RIPEMD-
3?*block,blocks,chain?,”distributed
ledger”?]A20//[@発明の名称+要約+請求の範囲]
S041 24 文章系組合せ
(英語)
[micropayment?,”micro payment”?,”
lightning network”?,”payment channel”?,”
markle tree”?*block,blocks,chain?,”
distributed ledger”?]A20//[@発明の名称+要約
+請求の範囲]
S042 1,902 文章系組合せ
(英語)
[”block height”?*block,blocks,chain?,”
distributed ledger”?]A20//[@発明の名称+要約
+請求の範囲]
S043 210 文章系組合せ
(英語)
[”number used
once”?,nonce*block,blocks,chain?,”
distributed ledger”?]A20//[@発明の名称+要約
+請求の範囲]
S044 112 文章系組合せ
(英語)
[”Elliptic
Curve”?,ECDSA*block,blocks,chain?,”
distributed ledger”?]A20//[@発明の名称+要約
+請求の範囲]
S045 3 文章系組合せ
(英語)
[”Pay To Script
Hash”?,P2SH*block,blocks,chain?,”
distributed ledger”?]A20//[@発明の名称+要約
+請求の範囲]
S046 109,089 文章系組合せ
(英語)
bitcoin?+ethereume+ripple+eos+stellar+liteco
in?//[@発明の名称+要約+請求の範囲]
仮想通貨の固有名称
S047 2,306 論理式 S003*S012*(S033+S034+S035+S036+S037+S038+S03
9+S040+S041+S042+S043+S044+S045+S046)
ブロックチェーンに関
する集合
S048 44,563 論理式 S006+S030+S032+S047
S049 3,343,047 出願国 WO
S050 18,008,700 出願国 JP
S051 12,893,074 出願国 US
S052 22,763,313 出願国 EP+AL+AT+BE+BG+CH+CY+CZ+DE+DK+EE+ES+FI+FR+GB
+GR+HR+HU+IE+IS+IT+LI+LT+LU+LV+MC+MK+MT+NL+N
O+PL+PT+RO+RS+SE+SI+SK+SM+TR
S053 15,719,449 出願国 CN
S054 3,598,962 出願国 KR
S055 6,275 論理式 S048*S049 PCT
S056 2,158 論理式 S048*S050 日本
S057 12,833 論理式 S048*S051 米国
S058 4,219 論理式 S048*S052 欧州および欧州各国
S059 8,616 論理式 S048*S053 中国
S060 5,577 論理式 S048*S054 韓国
S061 39,678 論理式 S055+S056+S057+S058+S059+S060 調査母集団候補(公報
単位)
- 24 -
資料編
第7部
第6部 第5部
第3部
第2部
第1部
本編
要約
目次
第4部
(4) その他の留意事項
出願人国籍は、日本国籍、米国籍、欧州国籍、中国籍、韓国籍及びその他国籍(地域
も含む)に分けて集計を行った。出願人国籍は「筆頭出願人名または筆頭出願人の住所」、
「発明者の住所」、「優先権主張国」の優先順位で付与した。なお、香港(HK)は中国籍
に合算し、台湾(TW)はその他として集計した。
出願人国籍別出願動向調査において、欧州国籍の出願とは、2018 年 12 月現在の EPC
加盟国である 38 か国(アルバニア、オーストリア、ベルギー、ブルガリア、スイス、
キプロス、チェコ、ドイツ、デンマーク、エストニア、スペイン、フィンランド、フラ
ンス、イギリス、ギリシア、モナコ、クロアチア、ハンガリー、アイルランド、アイス
ランド、イタリア、リヒテンシュタイン、リトアニア、ルクセンブルグ、ラトビア、マ
ケドニア、マルタ、オランダ、ノルウェー、ポーランド、ポルトガル、ルーマニア、ス
ウェーデン、スロヴニア、スロヴァキア、サン・マリノ、トルコ、セルビア)の国籍を
対象とした。
特許の出願先国によってデータベースに収録されるまでの時間差があるため、全ての
特許データが収録されている期間が各国で異なっている。このため、特に 2015 年以降
は全データが取得されていない可能性があることに留意が必要である。さらに PCT 出願
については、国内段階へ移行するまでの期間が長く(国内段階移行手続期間(国内書面
提出期間):優先日から 30 月以内)、国内書面提出期間の経過後となる公表公報発行時
期は、通常の国内出願の公開公報発行時期(出願から 1 年 6 か月)より遅くなることに
留意が必要である。
登録件数の年次推移については、審査請求制度の有無、特許出願から審査請求までの
期間、及び審査にかかる期間が各国で異なることを念頭において評価する必要がある。
2. 調査方法
第1節で示した条件での特許データベース検索で得られた特許文献のファミリー単位
での件数は 23,970 件であり、その内日本への出願があるファミリーが 2,449 件、日本へ
の出願がないファミリーが 21,521 件である。これらの詳細調査を行い、仮想通貨・電子
マネーによる決済システム技術に関連があるファミリー17,930 件を抽出し、表 4-2~表
4-6 に示す技術区分の付与を行った。
- 25 -
資料編
第7部
第6部
第5部
第3部
第2部
第1部
本編
要約
目次
第4部
表 4-2 「決済手段」に関する技術区分
第 1 階層 第 2 階層 第 3階層 第 4階層 付与ルール 区分番号
電子マネ
ー
取 引 と 支
払 の 時 間
関係
プリペイド 取引に先行して予め現金又は預金口座から通貨の価
値をチャージしておき、その価値を決済に用いるも
の。
A.1.1.1
リアルタイム/ジ
ャストペイ
デビッドなど、取引に応じて行った送金指示に引き続
いて預金口座から通貨の価値の移転・決済の処理を行
うもの。
A.1.1.2
ポストペイ 取引に先行して予め価値をチャージしておくことな
く、取引に応じて行う支払に使え、その時点で引き続
き決済まで行うのでなく、後に一定期間の取引を取り
まとめるなどして預金口座等から価値の移転・決済を
行うもの。
A.1.1.3
その他 上記に分類されない、電子マネーを決済手段に用いる
もの。
A.1.1.4
オ ン ラ イ
ン性
オンライン決済 取引時に通信を行って決済処理を行うもの。 A.1.2.1
オフライン決済 取引時に通信を行わず決済処理を行うもの。 A.1.2.2
双方向性 一方向 別の決済手段からの価値のチャージはできるが、チャ
ージした価値を別の決済手段として引き出すことが
できないもの。
A.1.3.1
双方向 別の決済手段からの価値のチャージも、チャージした
価値の別の決済手段としての引き出しも双方向にで
きるもの。
A.1.3.2
仮想通貨 仮想通貨を決済手段に用いるもの。ブロックチェーン
上で発行される各種のトークン(代替通貨)を含む。
A.2
ポイント・クーポン ポイントやクーポン、マイレージを決済手段に用いた
り、そのためにポイント等を管理したりするもの。
A.3
マルチ 複数の決済手段から選択できるようにするもの。 A.4
- 26 -
資料編
第7部
第6部 第5部
第3部
第2部
第1部
本編
要約
目次
第4部
表 4-3 「要素技術」に関する技術区分
第 1 階層 第 2 階層 第 3階層 第 4階層 付与ルール 区分番号
決 済 シ ス
テム一般
システム 認 証 媒
体・ウォ
レット
磁 気 カ
ード
磁気ストライプを付加した磁気カードを用いるもの。 B.1.1.1.1
接 触 型
IC カ ー
ド
IC カードを認証媒体として用いるもので、カードとリ
ーダー/ライター端末が直接接触してデータ交換す
るもの。
B.1.1.1.2
非 接 触
型 IC カ
ード
IC カードを認証媒体として用いるもので、カードとリ
ーダー/ライター端末の間で無線通信によりデータ
交換するもの。
B.1.1.1.3
携 帯 端
末
スマートフォンなどの携帯端末を認証媒体として用
いるもの。
B.1.1.1.4
ウ ェ ア
ラ ブ ル
端末
腕時計、メガネ、ヘッドセットなど、ウェアラブル端
末を認証媒体に用いるもの。
B.1.1.1.5
バ ー コ
ード
一次元バーコードを認証媒体として用いるもの。 B.1.1.1.6
QR コ ー
ド
QR コードを認証媒体として用いるもの。 B.1.1.1.7
ウ ェ ブ
ウ ォ レ
ット
PC やスマートフォンなどからアクセスする、インター
ネット上で提供されるサービスのオンラインサイト
で暗号鍵が管理されるもの。
B.1.1.1.8
リ ー ダ
ー / ラ
イター
マ ル チ
サ ー ビ
ス リ ー
ダ ー /
ラ イ タ
ー
一つのリーダー/ライターで複数種類の決済手段を
扱えるようにしたマルチサービスリーダー/ライタ
ーに関するもの。
B.1.1.2.1
人 体 通
信
スマートコンタクト、表皮電子装置、人体埋め込みタ
グなど、人体の表面や体内に付ける装置に通信機能を
組み込み、非接触決済の通信に用いるもの。
B.1.1.2.2
近 傍 決
済
認証媒体や取引対象をユーザがリーダー/ライター
に近づけて通信を行うのではなく、10m~100m 程度の
距離で、非接触決済の通信を行うもの。
B.1.1.2.3
モ バ イ
ル端末
リーダー/ライターにモバイル POS など、モバイル端
末を用いるもの。
B.1.1.2.4
その他 その他、認証媒体やウォレットとのデータの読み取り
や書き込みのやり取りをするリーダー/ライターに
関するもの。認証媒体やウォレットとリーダー/ライ
ター間の通信に関する技術を含む。
B.1.1.2.4
ネットワーク リーダー/ライターや認証媒体とサーバーとの通信
に関するもの。
B.1.1.3
センター インターネット上で利用者の識別情報や価値情報を
記録するサーバーやクラウド、そのサイト(ウェブウ
ォレット)などセンターシステムに関するもの。
B.1.1.4
暗号技術 共通鍵 共通鍵暗号方式を用いるもの。 B.1.2.1
公開鍵 公開鍵暗号方式を用いるもの。 B.1.2.2
ハッシュ関数 ハッシュ関数を用いるもの。 B.1.2.3
電子署名 電子署名を用いるもの。 B.1.2.4
メッセージ認証コ
ード
決済処理の通信メッセージに共通鍵を加えて暗号化
することで生成したメッセージ認証コードを用いる
もの。
B.1.2.5
認証 パ ス ワ
ー ド 認
証
ワ ン タ
イ ム パ
ス ワ ー
ド
ワンタイムパスワード認証を行うもの。 B.1.3.1.1
- 27 -
資料編
第7部
第6部
第5部
第3部
第2部
第1部
本編
要約
目次
第4部
その他 その他、パスワードや PIN など本人のみが知り得る情
報の提供を認証に用いるもの。
B.1.3.1.2
生 体 認
証
指 紋 認
証
指紋を認証に用いるもの。 B.1.3.2.1
顔認証 顔の画像認識を認証に用いるもの。 B.1.3.2.2
静 脈 認
証
静脈の認識を認証に用いるもの。 B.1.3.2.3
虹 彩 認
証
虹彩の認識を認証に用いるもの。 B.1.3.2.4
音 声 認
証
音声の認識を認証に用いるもの。 B.1.3.2.5
動 作 認
証
マウスの軌跡やキーボードのタッチ、携帯端末の動
き、歩き方などの動作やしぐさの特徴を学習するなど
して、そのパターン認識を認証に用いるもの。
B.1.3.2.6
取 引 履
歴 に よ
る認証
位 置 に
よ る 認
証
取引履歴の特徴を学習するなどして、そのパターンと
のマッチングを認証に用いるもののうち、履歴として
位置情報を用いるもの。
B.1.3.3.1
その他 その他、取引履歴の特徴を学習するなどして、そのパ
ターンとのマッチングを認証に用いるもの。
B.1.3.3.2
第三者による認証・
仲介
認証局など第三者による認証やエスクローによる認
証を用いるもの。
B.1.3.4
多段階認証 複数の認証手段を用いるもの。 B.1.3.5
オーソリ 提示された支払手段での決済が可能かどうかを確認
し、決済枠を押さえる手続きに関するもの。
B.1.3.6
取 引 対 象
の管理
セルフレジ・レジレ
ス
小売店で顧客が購買する商品を自動的に識別するな
ど取引対象を管理し、セルフレジやレジレス決済を実
現するもの。
B.1.4.1
その他 その他、決済を必要とする取引対象の管理に関するも
の。
B.1.4.2
決済処理 画面遷移 決済処理を行う際の画面遷移の工夫に関するもの。 B.1.5.1
API 決済処理や利用者登録画面内に、外部サイトからの情
報を表示したり、そのデータを利用した処理を行った
り す る な ど 、 API ( Application Programming
Interface)を決済等の処理に用いるもの。
B.1.5.2
トークナイゼーシ
ョン
決済処理においてクレジットカード番号などをその
まま送信するのではなく、暗号化したトークンと呼ば
れる代用符号を生成して使用するもの。
B.1.5.3
MST 決済処理においてスマートフォンなどから磁気端末
で読み取り可能な信号を生成し無線電波で転送する
磁気セキュア伝送(magnetic secure transmission)
技術を用いるもの。
B.1.5.4
データベース設計 決済処理で使うデータベースのテーブル設計に関す
るもの。
B.1.5.5
メッセージ設計 決済処理で使う通信メッセージの設計に関するもの。 B.1.5.6
記録 第三者による記録
の保管
取引の記録を信頼できる第三者に保管させるもの。 B.1.6.1
タイムスタンプ 何度も入金があったように見せかけて価値を不正取
得するのを防ぐなどのために、取引情報にタイムスタ
ンプやシーケンス番号を付加するもの。
B.1.6.2
不正検出 耐タンパ 端末等の内部を解析されにくくしたり、解析を検知し
たり、対応策を講じたりするもの。
B.1.7.1
ヒューリスティッ
ク不正検知
今まで少額取引しかしたことがない人が高額決済を
するとか、短期間に複数の支払を繰り返すとか、今ま
で日本でしか決済したことがない人が突然海外で決
済するなど、経験的知識に基づく不正発見の仕組みを
用いるもの。
B.1.7.2
Bot 検出 自動プログラムによる攻撃を検出したり、ブロックし B.1.7.3
- 28 -
資料編
第7部
第6部 第5部
第3部
第2部
第1部
本編
要約
目次
第4部
たりするもの。
チャージ 端末・媒
体
専 用 端
末
チャージにおいて、店舗端末等の専用端末を用いるも
の。
B.1.8.1.1
チ ャ ー
ジ 用 カ
ード
iTunes カード等、チャージ用カードを用いるもの。 B.1.8.1.2
オートチャージ オートチャージ機能を用いるもの。 B.1.8.2
電子マネー同士の
交換
電子マネー、ポイントを別の電子マネー、ポイントに
交換するもの。
B.1.8.3
ポイント・クーポン
の付与
支払時にポイントを付与したり、店に近づくと自動的
にクーポンを付与したりするもの。
B.1.8.4
ブ ロ ッ ク
チ ェ ー ン
特有
鍵の管理 マルチシグナチャ
ー
秘密鍵を分割して複数の主体で持ち、送金を行うには
一定数以上の鍵を合わせる必要がある方法を用いる
もの。
B.2.1.1
ハードウェアウォ
レット
秘密鍵を専用の周辺機器に保管するタイプの仮想通
貨ウォレットを用いるもの。
B.2.1.2
ペーパーウォレッ
ト
秘密鍵を紙に出力して保管するタイプの仮想通貨ウ
ォレットを用いるもの。
B.2.1.3
データの管理 各ブロックに記録する取引の記録のデータ容量を小
さく済ませる方法や、各ノードのデータの持ち方な
ど、データの管理方法を示すもの。
B.2.2
コ ン セ ン
サス
ファイナリティ 合意転覆をさせない、または転覆する確率を下げた
り、確率的ファイナリティまでに掛かる時間を短くし
たりする方法を示すもの。
B.2.3.1
その他 その他、PoW(Proof of Work)、PoS(Proof of Stake)
を改善する提案など、不特定多数の参加者の合意をと
るための方法を示すもの。
B.2.3.2
参 加 者 構
成
パブリック型 不特定多数のノードが参加可能なもの。 B.2.4.1
コンソーシアム型 管理された範囲内の成員のみが参加可能なもの。 B.2.4.2
プライベート型 特定組織内でのみ構築されるもの。 B.2.4.3
スクリプト記述 ブロックチェーンで管理する取引の記録の内容とし
て、自動的に処理を行わせるスクリプトを記述するも
の。
B.2.5
ブロックチェーン間接続 異なる仮想通貨の交換や用途ごとのブロックチェー
ンをセキュアに連携させて利用できるようにするも
の。
B.2.6
スケーラビリティ ネットワークに参加するノードやそれを利用するユ
ーザ、扱うトランザクション量の増加に伴う、レスポ
ンスの遅さ、トランザクションの処理遅延、コスト増
等への対策を示すもの。データ管理方法の工夫はこの
課題の解決手段になり得るが、その場合は「データ管
理」と本区分の両方に付与する。
B.2.7
- 29 -
資料編
第7部
第6部
第5部
第3部
第2部
第1部
本編
要約
目次
第4部
表 4-4 「利用場面」に関する技術区分
第 1 階層 第 2 階層 第 3階層 第 4階層 付与ルール 区分番号
商取引 オ ン サ イ
ト商取引
実店舗 実店舗での商品購入代金等の支払に用いるもの。 C.1.1.1
自動販売機 自動販売機での商品購入代金支払に用いるもの。 C.1.1.2
交通 鉄道 鉄道料金の支払に用いるもの。 C.1.1.3.1
道路 ETC など、道路料金の支払に用いるもの。 C.1.1.3.2
バス・タ
クシー
バス、タクシー、配車サービスなどの料金の支払に用
いるもの。
C.1.1.3.3
レ ン タ
カー
レンタカーやシェアリングカー、レンタル自転車など
の料金の支払に用いるもの。
C.1.1.3.4
駐車場 駐車場などの料金の支払に用いるもの。 C.1.1.3.5
施 設 サ
ービス
病院 待ち時間を短くするなどのため、大病院等での会計に
用いるもの。
C.1.1.4.1
その他 その他、施設サービスの料金支払に用いるもの。 C.1.1.4.2
その他 商品 その他、オンサイトでの商品の支払に用いるもの。 C.1.1.5.1
サ ー ビ
ス
その他、オンサイトでのサービス料金の支払に用いる
もの。
C.1.1.5.2
オ ン ラ イ
ン商取引
仮想店舗 仮想店舗などオンラインでの商取引の支払に用いる
もの。
C.1.2.1
通信 通信料金の支払などに用いるもの。 C.1.2.2
公共料金 電気、ガス、水道等、公共料金の支払に用いるもの。 C.1.2.3
税 税の支払に用いるもの。 C.1.2.4
デジタルコンテン
ツ
オンラインでデジタルコンテンツを購入するのに用
いるもの。音楽・動画の他、ゲームも含む。
C.1.2.5
オークション オークション、フリーマーケット等の個人間取引に用
いるもの。
C.1.2.6
その他 その他、オンライン商取引に用いるもの。 C.1.2.7
金融取引 送金 海外送金 海外送金や資金移動に用いるもの。 C.2.1.1
一斉送金 給与支払など一斉送金に用いるもの。 C.2.1.2
寄付 募金、ギフトなど寄付に用いるもの。 C.2.1.3
個人送金 個人間送金に用いるもの。 C.2.1.4
その他 その他、送金、資金移動に用いるもの。 C.2.1.5
投融資 クラウドファンデ
ィング
ネット上で不特定多数の人々が特定の組織に資金の
提供を行うクラウドファンディングや、ネット上でお
金を借りたい人と貸したい人を結び付けて貸し借り
を行うソーシャルレンディングに用いるもの。
C.2.2.1
証券取引 証券取引の決済に用いるもの。 C.2.2.2
リース リース取引に用いるもの。 C.2.2.3
保険・資産形成 保険の支払や資産形成に用いるもの。 C.2.2.4
その他 その他、投融資に用いるもの。 C.2.2.5
- 30 -
資料編
第7部
第6部 第5部
第3部
第2部
第1部
本編
要約
目次
第4部
表 4-5 「決済以外も含むブロックチェーン技術の利用場面」に関する技術区分
第 1 階層 第 2 階層 第 3階層 第 4階層 付与ルール 区分番号
価 値 の 記
録
通 貨 の 代
替
ゲーム内通貨 ゲーム内通貨の発行や流通など価値の管理に用いる
もの。
D.1.1.1
SNS SNS 上での送金や広告閲覧報酬等における価値の管理
に用いるもの。
D.1.1.2
その他 その他、プリペイドカード、仮想通貨等、通貨を代替
する価値の発行、流通、管理に用いるもの。
D.1.1.3
証券取引 電子化された証券の取引に利用するもの。 D.1.2
クラウドファンディング クラウドファンディングによる調達資金の価値の管
理に用いるもの。
D.1.3
チケット・ギフトカード チケットやギフトカードの発行や流通販売における
価値の管理に用いるもの。
D.1.4
ポイント・クーポン 商店等が発行するポイントやクーポンの価値の管理
に用いるもの。
D.1.5
権 利 の 記
録
不動産取引 土地や建物の物理的現況や権利関係の履歴等の管理
に用いるもの。
D.2.1
為替取引 貿易取引における船荷証券や信用状を管理したり、マ
ネーオーダー、ペイメントオーダーを管理したりする
など、為替取引の手続の円滑化等に役立てるもの。
D.2.2
知的財産権 特許等の知的財産権の内容や権利関係の履歴等の管
理に用いるもの。
D.2.3
デジタルコンテンツ利用 コンテンツ配信や電子図書館等におけるデジタルコ
ンテンツの利用権、著作権の管理に用いるもの。
D.2.4
投票 選挙における投票権の管理に用いるもの。 D.2.5
関 与 者 の
記録
サプライチェーン 製品の原材料から製造過程、流通・販売までの過程の
履歴管理に用いるもの。
D.3.1
ヘルスケア 電子カルテや通院記録、投薬記録等のヘルスケアに関
する情報を管理し、複数医療機関での一貫した治療等
に役立てるもの。
D.3.2
偽造防止・真正性担保 証憑や芸術品、薬品等の偽造防止や真正性担保等のた
めに、データの作成、更新の履歴を管理するのに用い
るもの。
D.3.3
貴重品管理 金やダイヤモンド等の貴金属・宝石類、骨董品、芸術
品等の貴重品の採掘や制作、所有や取引等の履歴を管
理し、真正性等、商品としての信頼性向上等に役立て
るもの。
D.3.4
オークション オークションで出品された商品の落札状況、商品の送
付状況、支払状況等を管理し、取引が着実に行われる
こと等に役立てるもの。
D.3.5
各種届出 出生、転居、結婚等、主に行政における各種の届出や
電子申請等の手続の管理に用いるもの。
D.3.6
シェアリングエコノミー シェアリング対象資産の利用権の保有者情報、利用権
の移転情報、支払情報、提供者や利用者の評価情報等
の管理に用いるもの。
D.3.7
スマートモビリティ 先を急ぐドライバーとゆっくりで良いドライバーの
間で仮想通貨をやり取りして、ゆっくりで良いドライ
バーが先を急ぐドライバーに道を譲るなど、交通状況
に応じた交通インフラの利用や料金収受に用いるも
の。
D.3.8
広告・広報 自動化された広告の支払や転々と流通していく広告
情報の管理、その過程での貢献度合いの評価、対価付
けなど、広告や広報に用いるもの。
D.3.9
処 理 の 自
動化
スマートコントラクト 契約条件、処理すべき手続、履行内容等を記録し、業
務プロセスの自動化等に役立てるもの。
D.4.1
エスクロー自動化 取引の双方の履行を担保するための処理を自動化す D.4.2
- 31 -
資料編
第7部
第6部
第5部
第3部
第2部
第1部
本編
要約
目次
第4部
るもの。条件に応じて債権・債務の内容が分岐する場
合の自動処理を含む。
デリバティブ デリバティブ取引における資金のやり取りの条件と
処理方法等を記録し、取引の自動化に役立てるもの。
D.4.3
エネルギー管理 電気機器等の利用や発電、充電、省エネ、売電、送電、
その他の制御に関する条件や制御方法、決済方法を記
録し、エネルギー管理の自動化に役立てるもの。
D.4.4
消耗品管理 消耗品や補充剤の購入に関する条件や手続を記録し、
自動発注、補充、決済に役立てるもの。
D.4.5
遺言 遺言の内容を記録し、遺言者が死亡したことをきっか
けとして遺言が自動的に執行されることに役立てる
もの。
D.4.6
会社清算 会社清算時の資産や権利の配分の条件や処理方法を
記録し、清算手続の自動処理に役立てるもの。
D.4.7
その他 その他、上記に分類されない、決済以外も含むブロッ
クチェーン技術の利用場面に特徴があるもの。
D.5
- 32 -
資料編
第7部
第6部 第5部
第3部
第2部
第1部
本編
要約
目次
第4部
表 4-6 「課題」に関する技術区分
第 1 階層 第 2 階層 第 3階層 第 4階層 付与ルール 区分番号
安全性 盗難防止 価値を盗難されにくくしたり、他人に不正使用されに
くくしたりするための対策。送金先のすり替えやなり
すましを防止する対策を含む。
E.1.1
改ざん防止 価値や取引の記録等を改ざんしたり偽造したりされ
るのを防止するもの。改ざんの検知や検知時の対処を
含む。
E.1.2
間違い防
止
送金先間違い防止 送金先の間違いを防止するもの。 E.1.3.1
二重払い防止 二重払いを防止するもの。 E.1.3.2
ユニーク性確保 他人の債務を支払うことを防止するなどのため、支払
者や受取者の識別番号等がユニークであることを確
保するもの。
E.1.3.3
不適切取引防止 子供の夜間取引や企業ユーザの土・日・休日の利用ブ
ロック、役職ごとの取引上限額設定など、利用状況を
適切にコントロールするもの。
E.1.3.4
未処理トランザクションの防止 未処理のトランザクションが生じるのを防止するこ
とを課題とするもの。
E.1.4
滅失防止 パスワードの忘却や災害で失う等、価値の滅失を防止
するもの。
E.1.5
プライバシー保護 取引の内容等に関するプライバシー保護を目的とす
るもの。
E.1.6
耐量子計算機暗号 量子コンピュータが実用化された場合でも解読され
ない暗号化方法を示すもの。
E.1.7
安全性評価 決済システムの安全性を評価する手法を示すもの。 E.1.8
レピュテーション管理 利用者の取引履歴等を管理し、不正なシステム利用を
防止することを課題とするもの。
E.1.9
利便性 円滑な決
済
ユーザーインター
フェイスの向上
決済処理を行うためのユーザーインターフェイスを
簡便化したり、操作性を向上したり、手間を減らすな
ど、円滑な決済を実現するもの。
E.2.1.1
即時性 決済処理に掛かる時間を短縮し、円滑な決済を実現す
るもの。
E.2.1.2
多様な決済手段への対応 複数の決済手段を統合した同じ基盤(カード、端末、
サービス 等)で利用できるようにすることを課題と
するもの。
E.2.2
決済以外の機能との統合 家や車の電子キー、身分証、チケット管理との統合や
家計簿管理との統合など、決済以外の機能との統合を
課題とするもの。ただし、ポイントプログラムを付け
るだけのものは本区分には付与せず、「決済手段」の
「ポイント」に付与する。
E.2.3
入力の自動化 各種の登録作業の手間を軽減するため、名刺や免許証
から情報を読み取ったり、GPS から位置情報を取得し
たりするなど、入力を自動化するもの。
E.2.4
経済性 端末導入コストの低減 決済処理に使用する端末の導入コストやそれと連携
する店舗端末の保守コスト等を低減させるもの。
E.3.1
ネットワーク・センターシステ
ムの低コスト化
高速データ配信や処理アルゴリズムなど、決済処理の
ネットワーク、センターシステムの構築、運用コスト
を低減させるもの。
E.3.2
与信業務の効率化 与信業務を効率化することを課題とするもの。 E.3.3
マーケティング活用 決済情報を POS データと連携させるなどして、顧客分
析、商品分析を行ったり、位置情報を活用して、クー
ポンを発行したりするなど、電子決済システムのデー
タをマーケティングに用いるもの。
E.3.4
スケーラビリティ 利用者数や取引に関する情報量の増加への対策を示
すもの。
E.4
追跡性 有効性確認 否認の防止など、取引の有効性を確認するためのも E.5.1
- 33 -
資料編
第7部
第6部
第5部
第3部
第2部
第1部
本編
要約
目次
第4部
の。
取引履歴の管理 過去の取引等の履歴を追跡、管理できるようにするも
の。
E.5.2
不正金融
取引防止
マネーロンダリン
グ防止
マネーロンダリングを防止するために電子的に管理
可能な決済手段を用いるもの。
E.5.3.1
目的外利用制限 後進国への支援金が本当に人道支援に使われている
かを管理したり、生活保護などの社会福祉支援金がギ
ャンブル、嗜好品などに使用されていないかを管理し
たりするなど、目的外利用を制限するために電子的に
管理可能な決済手段を用いるもの。
E.5.3.2
3. 調査対象特許件数
調査対象は、検索結果から調査対象外の技術に関する特許を除いたものとし、調査対
象の特許ファミリーに含まれる出願に対して、上記の技術区分(表 4-2 から表 4-6)を用
いて分類した。調査対象の出願先国別出願件数を表 4-7 に示す。なお、登録特許は検索
日時点で公報がデータベースに収録されたものを対象とし、公開特許と登録特許が重複
する場合等は 1 件の出願とカウントした。
表 4-7 対象とした出願先国別特許出願件数
出願先国 分析対象の出願件数
PCT 出願 5,215
日本 1,960
米国 11,813
欧州 3,681
中国 7,952
韓国 4,115
日米欧中韓への出願 合計 29,521
- 34 -
資料編
第7部
第6部 第5部
第3部
第2部
第1部
本編
要約
目次
第4部
第 2 節 全体動向調査
1. 出願先国別出願動向
日米欧中韓への出願における出願先国別の出願件数推移と出願件数比率を図 4-1 に示
す。
出願先国ごとの全出願件数に対する比率は、米国への出願が 40.0%(11,813 件)と
も高く、次いで中国への出願が 26.9%(7,952 件)、韓国への出願が 13.9%(4,115 件)、
欧州への出願が 12.5%(3,681 件)と続いている。
全体の出願件数は 2010 年から 2012 年にかけて大きく増加した後、2016 年まで緩やか
な増加傾向にある。
出願先別の推移では、2010 年から 2012 年までは米国の出願が突出していたが、2013 年
以降は米国の出願が減少する一方で中国や韓国の出願が増加し、2015 年以降、中国が米
国を上回っている。
図 4-1 出願先国別出願件数推移及び出願件数比率(日米欧中韓への出願、出願年(優先権主張
年):2010-2016 年)
2. 出願人国籍別出願動向
日米欧中韓への出願における出願人国籍別のファミリー件数推移及びファミリー件数
比率を図 4-2 に示す。
出願人国籍としては中国籍が 5,973 件(33.3%)で も多く、次いで米国籍の 5,298 件
(29.5%)と、韓国籍の 3,426 件(19.1%)が続いている。
出願件数全体の推移は、2010 年から 2012 年にかけて増加し、2013 年にいったん横ばい
となった後、2014 年以降は大きく増加している。
国籍別の推移では、2010 年から 2016 年にかけて米国籍の継続的な出願が見られる。ま
た、2013 年頃から 2016 年にかけては中国籍の出願が急激に増加しており、2015 年以降
は中国籍ほどではないが韓国籍の出願が急増している。一方、日本国籍はどの年代にお
いても出願件数が比較的少ない。
日本
1,960件
6.6%
米国
11,813件
40.0%
欧州
3,681件
12.5%
中国
7,952件
26.9%
韓国
4,115件
13.9%
合計
29,521件
3,012
3,858
4,505 4,229 4,499 4,533
4,885
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
4,500
5,000
5,500
0
250
500
750
1,000
1,250
1,500
1,750
2,000
2,250
2,500
2,750
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
合計
出願件数
出願年(優先権主張年)
日本 米国 欧州 中国 韓国 合計
出願先国(地域)
優先権主張
2010-2016年
注)2015 年以降はデータベース収録の遅れ、PCT 出願の各国移行のずれ等で、
全データを反映していない可能性がある。
- 35 -
資料編
第7部
第6部
第5部
第3部
第2部
第1部
本編
要約
目次
第4部
図 4-2 出願人国籍別ファミリー件数推移及びファミリー件数比率(日米欧中韓への出願、出願
年(優先権主張年):2010-2016 年)
日本国籍
1,151件
6.4%
米国籍
5,298件
29.5%
欧州国籍
1,319件
7.4%
中国籍
5,973件
33.3%
韓国籍
3,426件
19.1%
その他
763件
4.3%
合計
17,930件
1,386
1,902
2,273 2,297
2,694
3,126
4,252
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
4,500
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
合計
出願件数
出願年(優先権主張年)
日本国籍 米国籍 欧州国籍 中国籍 韓国籍 その他国籍 合計
出願人国籍(地域)
優先権主張
2010-2016年
注)2015 年以降はデータベース収録の遅れ、PCT 出願の各国移行のずれ等で、
全データを反映していない可能性がある。
- 36 -
資料編
第7部
第6部 第5部
第3部
第2部
第1部
本編
要約
目次
第4部
第 3 節 技術区分別動向調査
1.技術区分「決済手段」に関する動向
(1) 技術区分別ファミリー件数推移
技術区分「決済手段」の大分類におけるファミリー件数推移を図 4-3 に示す。
「電子マネー」が他の技術区分と比較して大きく突出しており、2010 年から 2016 年
の間に大きく増加している。
次に多い「ポイント・クーポン」は 2010 年から 2016 年にかけてほぼ横ばい、「仮想
通貨」及び「マルチ」は共に 2014 年から 2016 年にかけて件数の増加が見られる。
図 4-3 技術区分「決済手段(大分類)」‐ファミリー件数推移(日米欧中韓への出願、出願年
(優先権主張年):2010-2016 年)
電子マネー 1,111 1,507 1,814 1,767 2,123 2,163 2,690
仮想通貨24 36 35 44 112 114 205
ポイント・クーポン303 371
426348 316 347 362
マルチ33 45 66 44 62 93 90
決済手段(大分類)
出願年(優先権主張年)
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
注)2015 年以降はデータベース収録の遅れ、PCT 出願の各国移行のずれ等で、
全データを反映していない可能性がある。
- 37 -
資料編
第7部
第6部
第5部
第3部
第2部
第1部
本編
要約
目次
第4部
技術区分「決済手段」の「電子マネー」における中分類及び小分類のファミリー件数
推移を図 4-4 に示す。
「取引と支払の時間関係」が も多く、「リアルタイム/ジャストペイ」と「ポストペ
イ」はほぼ横ばいだが、「プリペイド」は 2014 年以降増加傾向にある。
「オンライン性」とその下位分類である「オンライン決済」は、2010 年から 2016 年
にかけて顕著に増加している。
「双方向性」については、目立った動きが見られない。
図 4-4 技術区分「決済手段(電子マネーの中分類・小分類)」‐ファミリー件数推移(日米欧
中韓への出願、出願年(優先権主張年):2010-2016 年)
取引と支払の時間関係 655 762 927 852 986 1,002 1,152
プリペイド117 114 158 117 150 189 226
リアルタイム/ジャストペイ168 163 180 123 168 181 154
ポストペイ 301 350 387 278 312 266 280
その他32 19 26 34 21 35 14
オンライン性 52 94 137 231 203 228401
オンライン決済43 82 118 212 174 195
356
オフライン決済 14 18 30 29 40 58 63
双方向性 15 10 20 18 16 8 17
一方向 7 5 12 7 7 5 8
双方向 9 5 10 11 9 3 9
決済手段「電子マネー」
中分類・小分類
出願年(優先権主張年)
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
注)2015 年以降はデータベース収録の遅れ、PCT 出願の各国移行のずれ等で、
全データを反映していない可能性がある。
- 38 -
資料編
第7部
第6部 第5部
第3部
第2部
第1部
本編
要約
目次
第4部
(2) 技術区分別-出願人国籍別ファミリー件数
技術区分「決済手段」の大分類における出願人国籍別のファミリー件数を図 4-5 に示
す。
「電子マネー」は、中国籍が突出しており、次に米国籍と韓国籍が続いている。
「仮想通貨」は、米国籍が も多く、次に中国籍と韓国籍が続いている。
いずれの決済手段においても、中国籍の件数が多い。一方、日本国籍はいずれの決済
手段においても少ない。
図 4-5 技術区分「決済手段(大分類)」‐出願人国籍別‐ファミリー件数(日米欧中韓への出
願、出願年(優先権主張年):2010-2016 年)
電子マネー827
3,702940
4,475
2,698 533
仮想通貨49 198 43 168 72 40
ポイント・クーポン259 824 99 310 870 111
マルチ61 201 24 63 67 17
決済手段
大分類
出願人国籍
日本 米国 欧州 中国 韓国 その他
- 39 -
資料編
第7部
第6部
第5部
第3部
第2部
第1部
本編
要約
目次
第4部
技術区分「決済手段」の「電子マネー」における中分類・小分類の出願人国籍別ファ
ミリー件数を図 4-6 に示す。
「ポストペイ」において韓国籍が突出して多く、それに米国籍が続いている。中国籍
と日本国籍も比較的多い。
「オンライン性」において、中国籍が大きく突出している。
図 4-6 技術区分「決済手段(電子マネーの中分類・小分類)」‐出願人国籍別‐ファミリー件
数(日米欧中韓への出願、出願年(優先権主張年):2010-2016 年)
取引と支払の時間関係 499 1,760 418 1,489 1,930240
プリペイド140 212 40
341 30335
リアルタイム/ジャスト
ペイ 38 44693 126
37460
ポストペイ206
521138
303 895111
その他1
5 3 172
オンライン性73 208 60 848
108 49
オンライン決済62 180 53 759 82 44
オフライン決済9 37
13 132 53 8
双方向性31 19
13 14 23 4
一方向16 10 6 8 8 3
双方向16 10 8 6 15 1
決済手段「電子マネー」
中分類・小分類
出願人国籍
日本 米国 欧州 中国 韓国 その他
- 40 -
資料編
第7部
第6部 第5部
第3部
第2部
第1部
本編
要約
目次
第4部
2.技術区分「要素技術」に関する動向
(1) 技術区分別ファミリー件数推移
技術区分「要素技術」の「決済システム」における中分類のファミリー件数推移を図
4-7 に示す。
「システム」が も多く、2010 年から 2016 年にかけて継続的に増加している。次に
多い「決済処理」は 2010 年から 2012 年に急速に件数を伸ばし、2013 年にいったん減少
した後、2014 年以降は再び増加に転じている。続いて件数の多い「認証」や「暗号技術」
だけでなく、「取引対象の管理」「記録」「不正検出」「チャージ」も一様に 2014 年頃か
ら件数の伸びが見られる。
図 4-7 技術区分「要素技術(決済システムの中分類)」‐ファミリー件数推移(日米欧中韓へ
の出願、出願年(優先権主張年):2010-2016 年)
システム
1,284
1,786 2,120 2,011 2,497 2,871 3,898
暗号技術248 318 389 435 633 718 900
認証732 982 1,063 960 1,254 1,419 1,658
取引対象の管理 44 62 76 87 94 134 285
決済処理585 923 1,105 715 945 1,338 2,216
記録 130 150 198 115 118 260 399
不正検出49 51 50 56 61 108 111
チャージ 281 355 399 366 331 419 499
要素技術「決済システム」
中分類
出願年(優先権主張年)
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
注)2015 年以降はデータベース収録の遅れ、PCT 出願の各国移行のずれ等で、
全データを反映していない可能性がある。
- 41 -
資料編
第7部
第6部
第5部
第3部
第2部
第1部
本編
要約
目次
第4部
技術区分「要素技術」の「決済システム」から、「システム」の小分類ファミリー件数
推移を図 4-8 に示す。
「認証媒体・ウォレット」が突出しており、なかでも「携帯端末」が目立っている。
その他の媒体やウォレットはいずれも増加傾向にあるが、特に「QR コード」や「ウェブ
ウォレット」が 2014 年以降急速に増えている。
「リーダー/ライター」では「近傍決済」が 2014 年以降、件数が特に増加している。
また、「ネットワーク」や「センター」も 2014 年以降、件数が伸びている。
図 4-8 技術区分「要素技術(決済システム-システムの小分類)」‐ファミリー件数推移(日
米欧中韓への出願、出願年(優先権主張年):2010-2016 年)
認証媒体・ウォレット 1,090 1,531 1,837 1,724 2,082 2,378 2,965
磁気カード 466 525 659 596 744 781 879
接触型ICカード55 84 91 92 97 108 145
非接触型ICカード118 204 230 224 241 299 309
携帯端末 697 1,035 1,212 1,068 1,240 1,366 1,683
ウェアラブル端末4 8 15 33 60 127 98
バーコード97 169 142 143 157 163 195
QRコード74 185 211 208 283
363 677
ウェブウォレット13 32 43 49 92 131 146
リーダー/ライター319
519 619 585 764 796 1,161
マルチサービスリーダー/ライター12 10 12 20 18 14 13
人体通信 1 3 6 11
近傍決済106 229 284 271 316
428 630
その他13 9 17 19 14 19 15
ネットワーク245 290
354 396 571 624 593
センター 652 869 1,040 776 1,124 1,226 1,789
要素技術「決済システム-
システム」小分類
出願年(優先権主張年)
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
注)2015 年以降はデータベース収録の遅れ、PCT 出願の各国移行のずれ等で、
全データを反映していない可能性がある。
- 42 -
資料編
第7部
第6部 第5部
第3部
第2部
第1部
本編
要約
目次
第4部
技術区分「要素技術」の「決済システム」から「暗号技術」の小分類ファミリー件数
推移を図 4-9 に示す。
「公開鍵」「ハッシュ関数」「電子署名」が、2014 年以降大きく件数を伸ばしている。
図 4-9 技術区分「要素技術(決済システム-暗号技術の小分類)」‐ファミリー件数推移(日
米欧中韓への出願、出願年(優先権主張年):2010-2016 年)
共通鍵7 3 5 7 9 16 11
公開鍵45 45 69 90 162 152
229
ハッシュ関数23 27 37 57 69 96 197
電子署名 59 79 92100 181 181 273
メッセージ認証コード17 12 18 20 22 21 19
要素技術「決済システム-
暗号技術」小分類
出願年(優先権主張年)
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
注)2015 年以降はデータベース収録の遅れ、PCT 出願の各国移行のずれ等で、
全データを反映していない可能性がある。
- 43 -
資料編
第7部
第6部
第5部
第3部
第2部
第1部
本編
要約
目次
第4部
技術区分「要素技術」の「決済システム」から「認証」の小分類ファミリー件数推移
を図 4-10 に示す。
「パスワード認証」と「生体認証」が突出しており、2015 年以降増加が見られる。「生
体認証」では、いずれの認証方法も増加傾向にあるが、特に「指紋認証」と「顔認証」
が 2014 年以降急速に増えている。
「取引履歴による認証」や「位置による認証」は 2014 年に多く出願されており、年
によって件数に変動が見られる。「第三者による認証・仲介」は 2010 年から 2013 年に
かけて増加傾向を示し、2014 年以降はやや減少傾向にある。「多段階認証」や「オーソ
リ」の件数は少ないが、増加傾向にある。
図 4-10 技術区分「要素技術(決済システム-認証の小分類)」‐ファミリー件数推移(日米欧
中韓への出願、出願年(優先権主張年):2010-2016 年)
パスワード認証 219 308 332 377 383 435 486
ワンタイムパスワード40 57 57 61 79 88 118
その他43 50 47 71 69 87 52
生体認証69 139 143 174 250 343 450
指紋認証27 42 59 64
115 165 248
顔認証9 24 30 31 51 62
122
静脈認証3 4 3 10 5 16 30
虹彩認証7 20 15 14 25 44 64
音声認証19 29 31 39 47 59 57
動作認証8 33 19 23 24 24 36
取引履歴による認証82
147 159 88 20484 83
位置による認証 73 133 138 62 173 75 68
その他1 1 3 3 7 4 2
第三者による認証・仲介33 42 54 73 46 35 41
多段階認証14 12 16 10 15 32 34
オーソリ23 16 19 29 23 38 31
要素技術「決済システム-
認証」小分類
出願年(優先権主張年)
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
注)2015 年以降はデータベース収録の遅れ、PCT 出願の各国移行のずれ等で、
全データを反映していない可能性がある。
- 44 -
資料編
第7部
第6部 第5部
第3部
第2部
第1部
本編
要約
目次
第4部
技術区分「要素技術」の「決済システム」に含まれる「取引対象の管理」「決済処理」
「記録」の 3 つの中分類について、小分類のファミリー件数推移を図 4-11 に示す。
「取引対象の管理」では、「セルフレジ・レジレス」が 2016 年に急増している。
「決済処理」では、「トークナイゼーション」が も多く、2014 年以降に増加が見ら
れる。
「記録」では、「タイプスタンプ」が 2016 年に大きく件数を伸ばしている。
図 4-11 技術区分「要素技術(決済システム-その他 1(取引対象の管理、決済処理、記録の小
分類)」‐ファミリー件数推移(日米欧中韓への出願、出願年(優先権主張年):2010-2016 年)
取引対象の管理44 62 76 87 94 134 285
セルフレジ・レジレス24 33 46 59 64 68 161
その他20 26 29 28 29 61 121
決済処理 585 923 1,105 715 945 1,338 2,216
画面遷移6 5 12 5 8 12 19
API9 19 25 46 37 30 37
トークナイゼーション33 44 59 47 111 90 95
MST 2 25 19
データベース設計21 48 63 13 3 30 15
メッセージ設計40 63 53 36 28 16 18
記録130 150 198 115 118 260 399
第三者による記録の保管2 1 1 6 1 5 5
タイムスタンプ18 23 27 30 19 27 66
要素技術「決済システム-
その他1」小分類
出願年(優先権主張年)
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
注)2015 年以降はデータベース収録の遅れ、PCT 出願の各国移行のずれ等で、
全データを反映していない可能性がある。
- 45 -
資料編
第7部
第6部
第5部
第3部
第2部
第1部
本編
要約
目次
第4部
技術区分「要素技術」の「決済システム」に含まれる「不正検出」「チャージ」の 2 つ
の中分類について、小分類のファミリー件数推移を図 4-12 に示す。
「不正検出」では、「耐タンパ」「ヒューリスティック不正検知」「Bot 検出」の件数が
一定数あるが、比較的少ない。
「チャージ」では、「ポイント・クーポンの付与」が も多く、件数はほぼ横ばいであ
る。また、「端末・媒体」の内、「専用端末」「チャージ用カード」「オートチャージ」の
いずれも比較的件数は少ないが、2015 年頃から増加傾向にある。一方で、「電子マネー
同士の交換」はほぼ横ばいである。
図 4-12 技術区分「要素技術(決済システム-その他 2(不正検出、チャージ)」‐ファミリー
件数推移(日米欧中韓への出願、出願年(優先権主張年):2010-2016 年)
不正検出49 51 50
56 61 108 111
耐タンパ6 8 8 3 7 10 11
ヒューリスティック不正検知6 3 5 2 7 5 13
Bot検出 3 6 2 2 2 4 4
チャージ 281 355 399 366 331 419 499
端末・媒体12 16 23 27 22 34 69
専用端末3 5 10 11 5 13 39
チャージ用カード6 9 12 17 12 20 46
オートチャージ9 14 8 8 6 7 12
電子マネー同士の交換16 11 15 9 13 13 18
ポイント・クーポンの付与 209 267 326 273 213 242 271
要素技術「決済システム-
その他2」小分類
出願年(優先権主張年)
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
注)2015 年以降はデータベース収録の遅れ、PCT 出願の各国移行のずれ等で、
全データを反映していない可能性がある。
- 46 -
資料編
第7部
第6部 第5部
第3部
第2部
第1部
本編
要約
目次
第4部
技術区分「要素技術」の「ブロックチェーン特有」における中分類及び小分類のファ
ミリー件数推移を図 4-13 に示す。
いずれの技術区分でも 2014 年頃を端緒として、2015 年から 2016 年に大きく件数を
伸ばしている。また、 も件数が多いのは「コンセンサス」であり、「データの管理」と
「鍵の管理」が続いている。
図 4-13 技術区分「要素技術(ブロックチェーン特有)」‐ファミリー件数推移(日米欧中韓へ
の出願、出願年(優先権主張年):2010-2016 年)
鍵の管理4
9 38
マルチシグナチャー
1 3 7
ハードウェアウォレット1 1 4
ペーパーウォレット 1 2
データの管理 5 4 48
コンセンサス1 3
20 72
ファイナリティ1 2 11
その他1 11
参加者構成1 2 8
32
パブリック型1 2 8 19
コンソーシアム型4
プライベート型 8
スクリプト記述2 4 24
ブロックチェーン間接続1 1 2 7 22
スケーラビリティ5
30
要素技術「ブロックチェー
ン特有」中分類・小分類
出願年(優先権主張年)
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
注)2015 年以降はデータベース収録の遅れ、PCT 出願の各国移行のずれ等で、
全データを反映していない可能性がある。
- 47 -
資料編
第7部
第6部
第5部
第3部
第2部
第1部
本編
要約
目次
第4部
(2) 技術区分別-出願人国籍別ファミリー件数
技術区分「要素技術」の「決済システム」における中分類の出願人国籍別ファミリー
件数を図 4-14 に示す。
「システム」「暗号技術」では、中国籍が も多く、次に米国籍と韓国籍の順で続いて
いる。
「認証」では、中国籍が も多く続く米国籍と拮抗している。次に韓国籍が続く。
「取引対象の管理」では、中国籍が も多く続く韓国籍と米国籍が拮抗している。
「決済処理」では、中国籍の突出が目立つ。
「記録」と「不正検出」では、米国籍が も多く中国籍が続いている。
「チャージ」では、米国籍が も多く韓国籍と拮抗している。
図 4-14 技術区分「要素技術(決済システムの中分類)」‐出願人国籍別‐ファミリー件数(日
米欧中韓への出願、出願年(優先権主張年):2010-2016 年)
システム
1,022
4,796
1,173
5,888 2,899689
暗号技術77 916 403 1,581 502 162
認証 299 2,412 631 2,6971,657 372
取引対象の管理52 120 44 411 138 17
決済処理 2231,699 272
4,941 412 280
記録62 582 99 433 119 75
不正検出30 198 54 135 43 26
チャージ291 834 99 553 773 100
要素技術「決済システ
ム」中分類
出願人国籍
日本 米国 欧州 中国 韓国 その他
- 48 -
資料編
第7部
第6部 第5部
第3部
第2部
第1部
本編
要約
目次
第4部
技術区分「要素技術」の「決済システム」から「システム」の小分類における出願人
国籍別ファミリー件数を図 4-15 に示す。
「非接触型 IC カード」では、中国籍が も多く、次に韓国籍、米国籍の順で続いて
いる。
「携帯端末」では、中国籍が も多く、米国籍、韓国籍の順に続いている。
「QR コード」では、中国籍が大きく突出しており、米国籍が続いている。
「ウェブウォレット」では、米国籍が突出している。
「近傍決済」では、中国籍が も多く、続く米国籍と韓国籍が拮抗している。
「ネットワーク」では、米国籍が も多く、次に韓国籍、中国籍の順に続いている。
「センター」では、中国籍が突出しており、次に米国籍が続いている。
- 49 -
資料編
第7部
第6部
第5部
第3部
第2部
第1部
本編
要約
目次
第4部
図 4-15 技術区分「要素技術(決済システム-システムの小分類)」‐出願人国籍別‐ファミリ
ー件数(日米欧中韓への出願、出願年(優先権主張年):2010-2016 年)
認証媒体・ウォレット 764 3,818 980 4,987 2,504554
磁気カード390
1,506332
1,150 1,092180
接触型ICカード62 89 42 332 121 26
非接触型ICカード115 232 126 630 451 71
携帯端末296
2,424 636 3,282 1,296367
ウェアラブル端末 8 93 26 166 40 12
バーコード33 330 75 392 170 66
QRコード34
36282
1,286162 75
ウェブウォレット9 376 42 24 21 34
リーダー/ライター259
1,143335
1,914 893 219
マルチサービスリーダー /ライター25 32 8 13 17 4
人体通信1 18 1 1
近傍決済 82 589177 889 412 115
その他5 66 9 8 7 11
ネットワーク214
1,163293 552
700151
センター491 2,222
4373,477
500 349
要素技術「決済システム
-システム」小分類
出願人国籍
日本 米国 欧州 中国 韓国 その他
- 50 -
資料編
第7部
第6部 第5部
第3部
第2部
第1部
本編
要約
目次
第4部
技術区分「要素技術」の「決済システム」から「暗号技術」の小分類における出願人
国籍別ファミリー件数を図 4-16 に示す。
「公開鍵」「ハッシュ関数」では、米国籍が も多く、続く中国籍と拮抗している。
「電子署名」では、中国籍が突出しており次いで米国籍が続いている。欧州国籍と韓
国籍も比較的多く拮抗している。
「メッセージ認証コード」では、中国籍が突出している。
図 4-16 技術区分「要素技術(決済システム-暗号技術の小分類)」‐出願人国籍別‐ファミリ
ー件数(日米欧中韓への出願、出願年(優先権主張年):2010-2016 年)
共通鍵4 15 12 10 14 3
公開鍵26
255 116 234 121 40
ハッシュ関数 10 167 76 13397 23
電子署名21
241 124 418 121 40
メッセージ認証コード4 22 15 70 12 6
要素技術「決済システム
-暗号技術」小分類
出願人国籍
日本 米国 欧州 中国 韓国 その他
- 51 -
資料編
第7部
第6部
第5部
第3部
第2部
第1部
本編
要約
目次
第4部
技術区分「要素技術」の「決済システム」から「認証」の小分類における出願人国籍
別ファミリー件数を図 4-17 に示す。
「パスワード認証」では、中国籍が も多く、韓国籍、米国籍の順に続いている。
なお、「パスワード認証」の「その他」には、PIN(個人識別番号)や電話番号を用い
たものが含まれる。
「生体認証」で も多い「指紋認証」では、中国籍が突出している。
「顔認証」「虹彩認証」では、中国籍が も多く、次に米国籍が続いている。
「音声認証」では、中国籍と米国籍が拮抗している。
「動作認証」では、米国籍が も多く、次に中国籍が続いている。
「位置による認証」では、米国籍が突出しており、次に中国籍が続いている。
「第三者による認証・仲介」では、米国籍が突出している。
「多段階認証」では、韓国籍が も多い。
「オーソリ」では、米国籍が突出している。
- 52 -
資料編
第7部
第6部 第5部
第3部
第2部
第1部
本編
要約
目次
第4部
図 4-17 技術区分「要素技術(決済システム-認証の小分類)」‐出願人国籍別‐ファミリー件
数(日米欧中韓への出願、出願年(優先権主張年):2010-2016 年)
パスワード認証62
551 220 900 681126
ワンタイムパスワード12 76 44
130 21226
その他6
12776 11
18118
生体認証46 465 132 647 196
82
指紋認証10
13752
40286 33
顔認証12 95 21
16324 14
静脈認証7 16 4 34 9 1
虹彩認証2 48 13
8628 12
音声認証2 102 31 106 21 19
動作認証2 52 15 47 42 9
取引履歴による認証 56 444 60 19449 44
位置による認証30
377 49184
43 39
その他3 13 1 3 1
第三者による認証・仲介9 154
33 42 59 27
多段階認証12 19 6 33 55 8
オーソリ30
9810 9 27 5
要素技術「決済システム
-認証」小分類
出願人国籍
日本 米国 欧州 中国 韓国 その他
- 53 -
資料編
第7部
第6部
第5部
第3部
第2部
第1部
本編
要約
目次
第4部
技術区分「要素技術」の「決済システム」から「取引対象の管理」「決済処理」「記録」
の小分類の出願人国籍別ファミリー件数を図 4-18 に示す。
「セルフレジ・レジレス」では、中国籍が突出しており、次に米国籍が続いている。
なお、「取引対象の管理」の「その他」には、ユーザ位置や店舗管理が含まれる。
「決済処理」では、中国籍が大きく突出しており、次に米国籍が続いている。その他
国籍(地域も含む)には、台湾、カナダ、インド等が含まれる。
「API」「トークナイゼーション」「データベース設計」では、米国籍が突出している。
「メッセージ設計」では、中国籍が突出している。
「MST」では、韓国籍が突出している。
「記録」では、米国籍が も多く、次に中国籍が続いている。
「タイムスタンプ」では、中国籍が も多く、次に米国籍が続いている。
- 54 -
資料編
第7部
第6部 第5部
第3部
第2部
第1部
本編
要約
目次
第4部
図 4-18 技術区分「要素技術(決済システム-その他 1(取引対象の管理、決済処理、記録の小
分類)」‐出願人国籍別‐ファミリー件数(日米欧中韓への出願、出願年(優先権主張年):
2010-2016 年)
取引対象の管理52 120 44 411 138 17
セルフレジ・レジレス20 90 26 259 50 10
その他27 25 16
15089 7
決済処理223 1,699
272
4,941412 280
画面遷移7 16 4 35 4 1
API 9 103 20 39 21 11
トークナイゼーション7 311 56 28 57 20
MST5 40 1
データベース設計3 106 4 63 9 8
メッセージ設計1 64 16
146
18 9
記録62
58299
433119 75
第三者による記録の保
管 3 4 3 6 5
タイムスタンプ15 62 28 71 24 10
要素技術「決済システム
-その他1」小分類
出願人国籍
日本 米国 欧州 中国 韓国 その他
- 55 -
資料編
第7部
第6部
第5部
第3部
第2部
第1部
本編
要約
目次
第4部
技術区分「要素技術」の「決済システム」から「不正検出」「チャージ」の小分類の出
願人国籍別ファミリー件数を図 4-19 に示す。
「不正検出」では、米国籍が も多く、次に中国籍が続いている。
「チャージ」では、米国籍が も多く、次に韓国籍、中国籍、日本国籍の順で続いて
いる。
「専用端末」「チャージ用カード」では、中国籍が突出している。
「電子マネー同士の交換」では、米国籍が も多く、次に日本国籍が続いている。
「ポイント・クーポンの付与」では、米国籍が も多く、次に韓国籍が続いている。
図 4-19 技術区分「要素技術(決済システム-その他 2(不正検出、チャージ)」‐出願人国籍
別‐ファミリー件数(日米欧中韓への出願、出願年(優先権主張年):2010-2016 年)
不正検出30
198 54 135 4326
耐タンパ9 17 16 4 1 6
ヒューリスティック不正検
知 2 16 3 14 6
Bot検出14 6 1 1 1
チャージ 291 834 99 553 773 100
端末・媒体47 28 6 82 38 2
専用端末19 2 1 49 15
チャージ用カード21 19 4
697 2
オートチャージ23 7 5 18 10 1
電子マネー同士の交換21 31 5 18 14 6
ポイント・クーポンの付
与193 677 71 207 573 80
要素技術「決済システム
-その他2」小分類
出願人国籍
日本 米国 欧州 中国 韓国 その他
- 56 -
資料編
第7部
第6部 第5部
第3部
第2部
第1部
本編
要約
目次
第4部
技術区分「要素技術」の「ブロックチェーン特有」における中分類・小分類の出願人
国籍別ファミリー件数を図 4-20 に示す。
「鍵の管理」「データの管理」では、中国籍が も多い。
「コンセンサス」「参加者構成」「スクリプト記述」では、中国籍が も多く、次に米
国籍が続いている。
「ブロックチェーン間接続」では、米国籍と中国籍が拮抗している。
「スケーラビリティ」では、中国籍が突出している。
図 4-20 技術区分「ブロックチェーン特有」‐出願人国籍別‐ファミリー件数(日米欧中韓へ
の出願、出願年(優先権主張年):2010-2016 年)
鍵の管理 4 5 6 29 61
マルチシグナチャー2 2 2
5
ハードウェアウォレット1
4 1
ペーパーウォレット2 1
データの管理 5 7 435 6
コンセンサス 5 26 12 39 113
ファイナリティ2 1 2
81
その他 61
5
参加者構成2 13 6 19
2 1
パブリック型2
9 6 102 1
コンソーシアム型1 3
プライベート型 8
スクリプト記述 6 5 13 51
ブロックチェーン間接続1 13
112
4 2
スケーラビリティ2 5 1
241 2
要素技術「ブロック
チェーン特有」中分類・
小分類
出願人国籍
日本 米国 欧州 中国 韓国 その他
- 57 -
資料編
第7部
第6部
第5部
第3部
第2部
第1部
本編
要約
目次
第4部
3.技術区分「利用場面」に関する動向
(1) 技術区分別ファミリー件数推移
技術区分「利用場面」の「商取引」における中分類及び小分類のファミリー件数推移
を図 4-21 に示す。
「オンサイト商取引」は、2010 年から 2016 年にかけて継続的に増加している。中で
も「実店舗」は 2010 年から 2016 年にかけて継続的に増加しているのに対し、「交通」
「施設サービス」は 2014 年頃から急激に件数を伸ばしている。
「オンライン商取引」は、2011 年から 2014 年までほぼ横ばいだが、2015 年以降は件
数が増加している。中でも「公共料金」は 2015 年から急激に件数を伸ばしている。
図 4-21 技術区分「利用場面(商取引)」‐ファミリー件数推移(日米欧中韓への出願、出願年
(優先権主張年):2010-2016 年)
オンサイト商取引 530 697 877 797 943 1,240 1,888
実店舗282 337
475 474 515 608 821
自動販売機24 33 40 37 38 75 96
交通84 95 130 112 139 214
470
鉄道13 18 18 16 17 29 65
道路15 15 22 15 24 31 53
バス・タクシー15 17 39 26 43 57 115
レンタカー8 11 10 7 4 14 65
駐車場20 37 33 40 42 74 177
施設サービス61 77 87 63 101 167 250
病院14 19 15 6 11 29 38
その他49 56 71 56 89 137 210
その他39 50 64 61 63 126 163
商品19 20 31 20 29 48 53
サービス30 34 47 47 52 104 133
オンライン商取引322
427 474 454 464 665 709
仮想店舗137 189 226 212 215 311 321
通信8 11 7 9 8 2 5
公共料金7 13 12 24 27 47 90
税10 7 9 13 7 11 22
デジタルコンテンツ45 74 73 62 54 48 67
オークション11 9 9 17 8 13 4
その他73 109 97 64 74 91 119
利用場面「商取引」
中分類・小分類
出願年(優先権主張年)
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
注)2015 年以降はデータベース収録の遅れ、PCT 出願の各国移行のずれ等で、
全データを反映していない可能性がある。
- 58 -
資料編
第7部
第6部 第5部
第3部
第2部
第1部
本編
要約
目次
第4部
技術区分「利用場面」の「金融取引」における中分類及び小分類のファミリー件数推
移を図 4-22 に示す。
「送金」は、2011 年から 2012 年にかけて増加した後、2013 年にいったん減少し、
2014 年以降急増している。中でも「個人送金」は 2013 年から 2016 年にかけて急激に件
数を伸ばしている。
「投融資」は、2011 年から 2014 年までほぼ横ばいだが、2015 年以降は件数が増加し
ている。中でも「保険・資産形成」「証券取引」は 2016 年に件数が大きく伸びている。
図 4-22 技術区分「利用場面(金融取引)」‐ファミリー件数推移(日米欧中韓への出願、出願
年(優先権主張年):2010-2016 年)
送金 76 79 104 62 96 147 186
海外送金4 4 5 3 8 17 13
一斉送金1 1
寄付14 14 37 15 15 32 17
個人送金9 11 15 21 36 48
65
その他10 9 12 10 14 22 24
投融資32 43 47 44 41
58 87
クラウドファンディング 1 1 6 4 5 7 11
証券取引2 9 10 12 8 9 17
リース 3 3 3 4 3 12
保険・資産形成 7 15 6 9 4 9 22
その他11 7 13 8 3 12 9
利用場面「金融取引」
中分類・小分類
出願年(優先権主張年)
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
注)2015 年以降はデータベース収録の遅れ、PCT 出願の各国移行のずれ等で、
全データを反映していない可能性がある。
- 59 -
資料編
第7部
第6部
第5部
第3部
第2部
第1部
本編
要約
目次
第4部
(2) 技術区分別-出願人国籍別ファミリー件数
技術区分「利用場面」の「商取引」における中分類・小分類の出願人国籍別ファミリ
ー件数を図 4-23 に示す。
「オンサイト商取引」では、中国籍が突出しており、続く米国籍と韓国籍が拮抗して
いる。
「実店舗」では、韓国籍と米国籍が拮抗しており、次に中国籍が続いている。
「交通」では、中国籍が突出しており、次に韓国籍、米国籍の順で続いている。
「バス・タクシー」「レンタカー」「駐車場」では、中国籍が突出している。
「施設サービス」では、中国籍が も多いが、続く米国籍、韓国籍と拮抗している。
なお、「施設サービス」の「その他」には、ホテル、レストラン、ガソリンスタンド、
学校等が含まれる。
「オンライン商取引」では、中国籍が も多いが、続く米国籍、韓国籍と拮抗してい
る。
「仮想店舗」では、韓国籍が も多く、次に米国籍、中国籍の順に続いている。
「公共料金」では、中国籍が大きく突出している。
「デジタルコンテンツ」では、米国籍が も多く、次に中国籍が続いている。
なお、「オンライン商取引」の「その他」には、ゲーム、チケット、広告、SNS 等が含
まれる。
- 60 -
資料編
第7部
第6部 第5部
第3部
第2部
第1部
本編
要約
目次
第4部
図 4-23 技術区分「利用場面(商取引)」‐出願人国籍別‐ファミリー件数(日米欧中韓への出
願、出願年(優先権主張年):2010-2016 年)
オンサイト商取引 514 1,725 424 2,468 1,610231
実店舗 314 1,010 221 797 1,054116
自動販売機28 110 43 114 33 15
交通69 171 88
626 25535
鉄道14 13 9 98 38 4
道路11 28 7 60 66 3
バス・タクシー13 35 8 171 73 12
レンタカー4 7 10 77 18 3
駐車場13 74 44 234 44 14
施設サービス45 210 57
270204 20
病院4 46 3 64 14 1
その他38 163 52 208 188 19
その他41 167 63 216 52 27
商品18 109 38 22 20 13
サービス28 133 36 194 36 20
オンライン商取引180 973
2341,054 925
149
仮想店舗40 428
107393 586
57
通信4 9 3 12 16 6
公共料金12 8 2 175 19 4
税10 24 6 26 10 3
デジタルコンテンツ37 139 36 108 81 22
オークション 5 31 3 12 17 3
その他53 155 25 205 161 28
利用場面「商取引」
中分類・小分類
出願人国籍
日本 米国 欧州 中国 韓国 その他
- 61 -
資料編
第7部
第6部
第5部
第3部
第2部
第1部
本編
要約
目次
第4部
技術区分「利用場面」の「金融取引」における中分類・小分類の出願人国籍別ファミ
リー件数を図 4-24 に示す。
「送金」では、米国籍が突出しており、次に中国籍と韓国籍が続いている。
「投融資」では、中国籍が も多く、次に米国籍が続いている。
図 4-24 技術区分「利用場面(金融取引)」‐出願人国籍別‐ファミリー件数(日米欧中韓への
出願、出願年(優先権主張年):2010-2016 年)
送金 50 341 59 144 11838
海外送金2 24 6 7 12 3
一斉送金 1 1
寄付 6 83 8 12 30 5
個人送金 6 136 17 16 20 10
その他 2044
5 5 20 7
投融資23
101 15 142 43 28
クラウドファンディング3 14 6 9 3
証券取引 7 20 2 24 4 10
リース 1 7 2 17 1
保険・資産形成 17 1 38 9 7
その他4 17 7 11 21 3
利用場面「金融取引」
中分類・小分類
出願人国籍
日本 米国 欧州 中国 韓国 その他
- 62 -
資料編
第7部
第6部 第5部
第3部
第2部
第1部
本編
要約
目次
第4部
4.技術区分「決済以外も含むブロックチェーン技術の利用場面」に関する動向
(1) 技術区分別ファミリー件数推移
技術区分「決済以外も含むブロックチェーン技術の利用場面」の大分類におけるファ
ミリー件数推移を図 4-25 に示す。
いずれの技術区分でも 2014 年頃を端緒として、2015 年から 2016 年に大きく件数を
伸ばしている。また、 も件数が多いのは「価値の記録」であり、「処理の自動化」が続
いている。
図 4-25 技術区分「決済以外も含むブロックチェーン技術の利用場面」‐ファミリー件数推移
(日米欧中韓への出願、出願年(優先権主張年):2010-2016 年)
価値の記録1 1 7 38
151
権利の記録1 3 5 31
関与者の記録 2 1 3 16 47
処理の自動化17 95
その他 1 1 15 88
決済以外も含むブロック
チェーン技術の利用場面
大分類
出願年(優先権主張年)
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
注)2015 年以降はデータベース収録の遅れ、PCT 出願の各国移行のずれ等で、
全データを反映していない可能性がある。
- 63 -
資料編
第7部
第6部
第5部
第3部
第2部
第1部
本編
要約
目次
第4部
技術区分「決済以外も含むブロックチェーン技術の利用場面」に含まれる「価値の記
録」「権利の記録」の 2 つの大分類について、中分類のファミリー件数推移を図 4-26 に
示す。
「価値の記録」では、「通貨の代替」が突出して多い。また、「証券取引」が 2016 年
に大きく件数を伸ばしている。
「権利の記録」では、具体的な利用場面を示すものは多くないが、いずれも 2015 年
から 2016 年に件数を伸ばしている。
図 4-26 技術区分「決済以外も含むブロックチェーン技術の利用場面(価値の記録、権利の記
録)」‐ファミリー件数推移(日米欧中韓への出願、出願年(優先権主張年):2010-2016 年)
価値の記録1 1 7
38 151
通貨の代替1 5
33 112
ゲーム内通貨1
SNS
その他25 19
証券取引6 26
クラウドファンディング4
チケット・ギフトカード1 4
ポイント・クーポイン1 1 11
権利の記録1 3 5 31
不動産取引7
為替取引1 1 5
知的財産権2 8
デジタルコンテンツ利用1 4
投票2 1 3
決済以外も含むブロック
チェーン技術の利用場面
「価値の記録」「権利の記録」中分類
出願年(優先権主張年)
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
注)2015 年以降はデータベース収録の遅れ、PCT 出願の各国移行のずれ等で、
全データを反映していない可能性がある。
- 64 -
資料編
第7部
第6部 第5部
第3部
第2部
第1部
本編
要約
目次
第4部
技術区分「決済以外も含むブロックチェーン技術の利用場面」に含まれる「関与者の
記録」「処理の自動化」「その他」の 3 つの大分類について、中分類のファミリー件数推
移を図 4-27 に示す。
「関与者の記録」では、「サプライチェーン」が も多い。いずれも 2015 年から 2016
年に大きく件数を伸ばしている。
「処理の自動化」では、「スマートコントラクト」が突出して多い。
「その他」には、資産やデータの管理等が含まれており、2015 年から 2016 年に件数
を伸ばしている。
図 4-27 技術区分「決済以外も含むブロックチェーン技術の利用場面(関与者の記録、処理の
自動化、その他)」‐ファミリー件数推移(日米欧中韓への出願、出願年(優先権主張年):
2010-2016 年)
関与者の記録2 1 3
16 47
サプライチェーン1 3 6
24
ヘルスケア2 1 5 8
偽造防止・真正性担保2 6
貴重品管理1
オークション3
各種届出3
シェアリングエコノミー
スマートモビリティ
広告・広報1
処理の自動化17
95
スマートコントラクト13 84
エスクロー自動化2
デリバティブ2
エネルギー管理2 7
消耗品管理
遺言
会社清算1
その他1 1 15
88
決済以外も含むブロック
チェーン技術「関与者の記
録」「処理の自動化」「その他」中分類
出願年(優先権主張年)
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
注)2015 年以降はデータベース収録の遅れ、PCT 出願の各国移行のずれ等で、
全データを反映していない可能性がある。
- 65 -
資料編
第7部
第6部
第5部
第3部
第2部
第1部
本編
要約
目次
第4部
(2) 技術区分別-出願人国籍別ファミリー件数
技術区分「決済以外も含むブロックチェーン技術の利用場面」の大分類における出願
人国籍別ファミリー件数を図 4-28 に示す。
「価値の記録」では、中国籍が大きく突出している。
「権利の記録」「関与者の記録」「処理の自動化」では、米国籍と中国籍が拮抗してい
る。
なお、「その他」では、個人情報や信用の記録や管理等、様々な利用場面が含まれる。
図 4-28 技術区分「決済以外も含むブロックチェーン技術の利用場面(大分類)」‐出願人国籍
別‐ファミリー件数(日米欧中韓への出願、出願年(優先権主張年):2010-2016 年)
価値の記録 12 23
14
118 274
権利の記録3 14 5 12 6
関与者の記録 2 25 6 258 3
処理の自動化4 38
1350
2 5
その他 3 3311
39 9 10
決済以外も含むブロック
チェーン技術の利用場
面 大分類
出願人国籍
日本 米国 欧州 中国 韓国 その他
- 66 -
資料編
第7部
第6部 第5部
第3部
第2部
第1部
本編
要約
目次
第4部
技術区分「決済以外も含むブロックチェーン技術の利用場面」の「価値の記録」「権利
の記録」における中分類・小分類の出願人国籍別ファミリー件数を図 4-29 に示す。
「価値の代替」では、中国籍が大きく突出している。
「権利の記録」では、米国籍と中国籍が拮抗している。
図 4-29 技術区分「決済以外も含むブロックチェーン技術の利用場面(価値の記録、権利の記
録の中分類・小分類)」‐出願人国籍別‐ファミリー件数(日米欧中韓への出願、出願年(優先
権主張年):2010-2016 年)
価値の記録 12 23 14 118 274
通貨の代替10 9
12 97 194
ゲーム内通貨1
SNS
その他3 7 9 4 19 2
証券取引1 12 1 16 1 1
クラウドファンディング2 2
チケット・ギフトカード 4 1
ポイント・クーポイン2 2 5 4
権利の記録 3 14 5 126
不動産取引3 2 1 1
為替取引 3 2 2
知的財産権3 2 5
デジタルコンテンツ利用 1 1 2 1
投票 3 1 2
決済以外も含むブロック
チェーン技術の利用場
面「価値の記録」「権利の記録」中分類・小分類
出願人国籍
日本 米国 欧州 中国 韓国 その他
- 67 -
資料編
第7部
第6部
第5部
第3部
第2部
第1部
本編
要約
目次
第4部
技術区分「決済以外も含むブロックチェーン技術の利用場面」の「関与者の記録」「処
理の自動化」「その他」における中分類・小分類の出願人国籍別ファミリー件数を図 4-
30 に示す。
「関与者の記録」では、米国籍と中国籍が拮抗している。
「処理の自動化」「スマートコントラクト」では、中国籍が も多く、次に米国籍が続
いている。
「その他」では、個人情報や信用の記録や管理等、様々な利用場面が含まれる。
図 4-30 技術区分「決済以外も含むブロックチェーン技術の利用場面(関与者の記録、処理の
自動化、その他の中分類・小分類)」‐出願人国籍別‐ファミリー件数(日米欧中韓への出願、
出願年(優先権主張年):2010-2016 年)
関与者の記録2
256
25 83
サプライチェーン 132
172
ヘルスケア 92 4 1
偽造防止・真正性担保3 1 4
貴重品管理1
オークション2 1
各種届出1 1 1
シェアリングエコノミー
スマートモビリティ
広告・広報1
処理の自動化4
38 13 502 5
スマートコントラクト3
33 11 451 4
エスクロー自動化1 1
デリバティブ2
エネルギー管理1 2 2 3 1
消耗品管理
遺言
会社清算1
その他3 33 11 39 9 10
決済以外も含むブロック
チェーン技術の利用場
面「関与者の記録」「処理の自動化」「その他」
中分類・小分類
出願人国籍
日本 米国 欧州 中国 韓国 その他
- 68 -
資料編
第7部
第6部 第5部
第3部
第2部
第1部
本編
要約
目次
第4部
5.技術区分「課題」に関する動向
(1) 技術区分別ファミリー件数推移
技術区分「課題」の大分類におけるファミリー件数推移を図 4-31 に示す。
「利便性」の件数が も多く、2010 年から 2011 年にかけて増加した後、2011 年から
2013 年までほぼ横ばいに推移し、2014 年以降に急増している。
次いで、「安全性」が多く、「利便性」と同様に 2011 年から 2013 年までほぼ横ばいに
推移した後、2014 年以降に急増している。
次に件数が多い「経済性」は、2011 年から 2014 年までほぼ横ばいに推移し、2015 年
以降に急増している。
「スケーラビリティ」と「追跡性」は、他の課題と比較して件数が少ないが、2015 年
ないし 2016 年に件数が急増している。
図 4-31 技術区分「課題」‐ファミリー件数推移(日米欧中韓への出願、出願年(優先権主張
年):2010-2016 年)
安全性534 729
834 791
1,102 1,280
1,604
利便性746
1,025 1,191 1,009 1,370
1,650 2,520
経済性381 539 621 521 525 632 1,065
スケーラビリティ 17 13 22 20 34 33 65
追跡性103 110 147 115 100 170 252
課題
大分類
出願年(優先権主張年)
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
注)2015 年以降はデータベース収録の遅れ、PCT 出願の各国移行のずれ等で、
全データを反映していない可能性がある。
- 69 -
資料編
第7部
第6部
第5部
第3部
第2部
第1部
本編
要約
目次
第4部
技術区分「課題」に含まれる「安全性」「利便性」の 2 つの大分類について、中分類・
小分類のファミリー件数推移を図 4-32 に示す。
「安全性」では、「盗難防止」が突出して多く、「改ざん防止」「間違い防止」「プライ
バシー保護」が続いている。
「利便性」では、「円滑な決済」が突出しており、中でも「即時性」が多い。いずれも
増加傾向にあり、2015 年から 2016 年にかけて大きく伸びている。
図 4-32 技術区分「課題(安全性、利便性)」‐ファミリー件数推移(日米欧中韓への出願、出
願年(優先権主張年):2010-2016 年)
安全性 534 729 834 791 1,102 1,280 1,604
盗難防止84 96 107
134 164 224 229
改ざん防止37 41 59 42 71 91 145
間違い防止16 40 42 52 55 84 116
送金先間違い防止1 2 3 6 3 1 2
二重払い防止1 7 5 5 4 6 17
ユニーク性確保3 7 6 12 16 21 40
不適切取引防止6 19 14 11 23 32 22
未処理トランザクションの防止6 9 7 2 3 15 15
滅失防止9 15 21 19 15 29 33
プライバシー保護44 56 41 60 48 69 96
耐量子計算機暗号 1
安全性評価1 3 1 3 4
8 11
レピュテーション管理4 3 9 4
1 7
利便性 746 1,025 1,191 1,009 1,370 1,650 2,520
円滑な決済373
520 552464
583 734 1,283
ユーザーインターフェイスの向上31 44 39 43 80 54 69
即時性76 117 125 175 206 267 482
多様な決済手段への対応49 51 60 74 69 93 127
決済以外の機能との統合11 14 19 27 19 22 27
入力の自動化15 20 11 17 9 22 22
課題「安全性」「利便性」
中分類・小分類
出願年(優先権主張年)
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
注)2015 年以降はデータベース収録の遅れ、PCT 出願の各国移行のずれ等で、
全データを反映していない可能性がある。
- 70 -
資料編
第7部
第6部 第5部
第3部
第2部
第1部
本編
要約
目次
第4部
技術区分「課題」に含まれる「経済性」「スケーラビリティ」「追跡性」の 3 つの大分
類について、中分類・小分類のファミリー件数推移を図 4-33 に示す。
「経済性」では、継続的に「マーケティング活用」が多い。「端末導入コストの低減」
「ネットワーク・センターシステムの低コスト化」「与信業務の効率化」は、他の課題
と比較して件数が少ないが、2015 年ないし 2016 年に件数が急増している。
「スケーラビリティ」は、他の課題と比較して件数が少ないが、継続して増加傾向に
あり、2016 年に件数が急増している。
「追跡性」では、「取引履歴の管理」が多く、2015 年から 2016 年にかけて急増してい
る。
図 4-33 技術区分「課題(経済性、スケーラビリティ、追跡性)」‐ファミリー件数推移(日米
欧中韓への出願、出願年(優先権主張年):2010-2016 年)
経済性 381 539 621 521 525 632 1,065
端末導入コストの低減18 46 53 36 46 55 98
ネットワーク・センターシス
テムの低コスト化 16 17 32 35 20 38 62
与信業務の効率化23 17 13 17 21 26 55
マーケティング活用129 215 213 190 151 140 234
スケーラビリティ17 13 22 20 34 33 65
追跡性103 110 147 115 100 170 252
有効性確認 5 4 6 5 5 9 20
取引履歴の管理82 85 118 85 72 103 145
不正金融取引防止13 10 12 12 11 17 30
マネーロンダリング防止3 4 3 8 4 10 11
目的外利用制限2 1 2
課題「経済性」「スケーラビ
リティ」「追跡性」
中分類・小分類
出願年(優先権主張年)
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
注)2015 年以降はデータベース収録の遅れ、PCT 出願の各国移行のずれ等で、
全データを反映していない可能性がある。
- 71 -
資料編
第7部
第6部
第5部
第3部
第2部
第1部
本編
要約
目次
第4部
(2) 技術区分別-出願人国籍別ファミリー件数
技術区分「課題」の大分類における出願人国籍別ファミリー件数を図 4-34 に示す。
「安全性」「利便性」では、中国籍が突出しており、次に米国籍、韓国籍の順で続いて
いる。
「経済性」「スケーラビリティ」では、中国籍が も多く、次に米国籍が続いている。
「追跡性」では、中国籍が も多く、次に韓国籍と米国籍が拮抗している。
図 4-34 技術区分「課題(大分類)」‐出願人国籍別‐ファミリー件数(日米欧中韓への出願、
出願年(優先権主張年):2010-2016 年)
安全性279
1,693571
2,955 1,059317
利便性644
2,255405
4,038 1,854 315
経済性285 1,145
208 1,811668 167
スケーラビリティ31 50 17 91 9 6
追跡性76 264 29 323 271 34
課題
大分類
出願人国籍
日本 米国 欧州 中国 韓国 その他
- 72 -
資料編
第7部
第6部 第5部
第3部
第2部
第1部
本編
要約
目次
第4部
技術区分「課題」の「安全性」「利便性」における中分類・小分類の出願人国籍別ファ
ミリー件数を図 4-35 に示す。
「盗難防止」では、米国籍が も多く、次に中国籍、韓国籍の順で続いている。
「改ざん防止」では、韓国籍が も多く、次に中国籍が続いている。
「間違い防止」では、中国籍が も多く、次に米国籍、日本国籍の順で続いている。
「ユニーク性確保」では、中国籍が突出している。
「プライバシー保護」では、韓国籍が突出しており、次に中国籍、米国籍の順で続い
ている。
「耐量子計算機暗号」は、殆ど出願されていない。
「円滑な決済」「即時性」では、中国籍が大きく突出しており、次に米国籍が続いてい
る。
「多様な決済手段への対応」では、韓国籍が も多く、次に中国籍、米国籍の順で続
いている。
「決済以外の機能との統合」「入力の自動化」では、米国籍が も多い。
- 73 -
資料編
第7部
第6部
第5部
第3部
第2部
第1部
本編
要約
目次
第4部
図 4-35 技術区分「課題(安全性、利便性の中分類・小分類)」‐出願人国籍別‐ファミリー件
数(日米欧中韓への出願、出願年(優先権主張年):2010-2016 年)
安全性279
1,693 571 2,955 1,059317
盗難防止82 317 98 282 204 55
改ざん防止26 67 36 157 178 22
間違い防止62 95 24 163 42 19
送金先間違い防止1 11 3 1 2
二重払い防止6 10 3 9 15 2
ユニーク性確保6 7 8 78 2 4
不適切取引防止33 50 5 24 12 3
未処理トランザクション
の防止 14 10 2 26 4 1
滅失防止17 28 10 26 59 1
プライバシー保護17 69 18 92 205 13
耐量子計算機暗号1
安全性評価14 4 9 1 3
レピュテーション管理3 13 1 6 5
利便性 644 2,255 4054,038
1,854315
円滑な決済220 899 167 2,713
367 143ユーザーインターフェイ
スの向上 86 105 27 59 73 10
即時性51 284 36 1,010
29 38多様な決済手段への対
応 94 102 15 126 174 12決済以外の機能との統
合 24 45 11 35 19 5
入力の自動化20 40 6 26 23 1
課題「安全性」「利便性」
中分類・小分類
出願人国籍
日本 米国 欧州 中国 韓国 その他
- 74 -
資料編
第7部
第6部 第5部
第3部
第2部
第1部
本編
要約
目次
第4部
技術区分「課題」の「経済性」「スケーラビリティ」「追跡性」における中分類・小分
類の出願人国籍別ファミリー件数を図 4-36 に示す。
「端末導入コストの低減」では、中国籍が も多く、次に米国籍、日本国籍の順で続
いている。
「ネットワーク・センターシステムの低コスト化」「与信業務の効率化」では、中国籍
が も多い。
「マーケティング活用」では、米国籍が も多く、次に中国籍が続いている。
「取引履歴の管理」では、韓国籍が も多く、次に中国籍、米国籍の順で続いている。
図 4-36 技術区分「課題(経済性、スケーラビリティ、追跡性の中分類・小分類)」‐出願人国
籍別‐ファミリー件数(日米欧中韓への出願、出願年(優先権主張年):2010-2016 年)
経済性285
1,145208
1,811 668167
端末導入コストの低減 56 80 23 147 38 8ネットワーク・センターシ
ステムの低コスト化 22 43 23 85 43 4
与信業務の効率化 34 27 4 92 5 10
マーケティング活用 67 554 58 449 73 71
スケーラビリティ 31 50 17 91 9 6
追跡性76 264 29 323 271 34
有効性確認 5 15 1 22 9 2
取引履歴の管理62 150 18 191 247 22
不正金融取引防止8 27 4 41 16 9
マネーロンダリング防止22 2 14 1 4
目的外利用制限2 2 1
課題「経済性」「スケーラ
ビリティ」「追跡性」
中分類・小分類
出願人国籍
日本 米国 欧州 中国 韓国 その他
- 75 -
資料編
第7部
第6部
第5部
第3部
第2部
第1部
本編
要約
目次
第4部
第 4 節 出願人別動向調査
1. 全体のファミリー件数上位出願人ランキング
日米欧中韓へのファミリー件数の合計が多い出願人の上位 30 位までを表 4-8 に示す。
も多いのがマスターカード(733 件)、次いでバンク・オブ・アメリカ(317 件)、VISA
(307 件)と米国籍出願人が続いている。上位 30 者を国籍別に見ると、日本国籍が 3 者、
米国籍 12 者、欧州国籍 1 者、中国籍 7 者、韓国籍 7 者となっている。
表 4-8 全体のファミリー件数上位出願人ランキング(日米欧中韓への出願、出願年(優先権主
張年):2010-2016 年)
順位 出願人名称 件数
1 マスターカード(米国) 733
2 バンク・オブ・アメリカ(米国) 317
3 VISA(米国) 307
4 ビズモードライン(韓国) 293
5 ペイパル(米国) 280
6 SK グループ(韓国) 197
7 サムスン(韓国) 173
8 LG(韓国) 161
9 アリババ(中国) 145
10 東芝 138
11 テンセント(中国) 131
12 IBM(米国) 125
13 中国銀聯(中国) 121
14 グーグル(米国) 109
14 スクエア(米国) 109
16 ウォルマート(米国) 107
17 三井住友フィナンシャルグループ 94
18 JP モルガン・チェース銀行(米国) 89
19 コリアインフォメーション&コミュニケー
ションズ(韓国) 88
20 KT(韓国) 78
20 ZTE(中国) 78
22 インジェニコ(フランス) 72
23 TENDYRON(中国) 70
24 楽天 67
25 キャピタル・ワン(米国) 61
26 アップル(米国) 60
27 インフォバンク(韓国) 59
28 クールパッド(中国) 57
28 国家電網(中国) 57
30 アメリカン・エキスプレス(米国) 54
- 76 -
資料編
第7部
第6部 第5部
第3部
第2部
第1部
本編
要約
目次
第4部
2. ブロックチェーン特有技術のファミリー件数上位出願人ランキング
要素技術「ブロックチェーン特有」における出願人の上位 10 位を表 4-9 に示す。
も多いのがコインプラグ(16 件)、次いで、IBM(11 件)、Bubi ネットワーク(10 件)
が続いている。日本国籍から 1 者、米国籍から 2 者、欧州国籍から 2 者、中国籍から 6
者、韓国籍から 1 者がランクインしている。
表 4-9 要素技術「ブロックチェーン特有」 - ファミリー件数上位出願人ランキング(日米欧
中韓への出願、出願年(優先権主張年):2010-2016 年)
順位 出願人名称 件数
1 コインプラグ(韓国) 16
2 IBM(米国) 11
3 Bubi ネットワーク(中国) 10
4 バンク・オブ・アメリカ(米国) 9
5 nChain(英国) 7
6 マスターカード(米国) 6
7 CloudMinds(中国) 5
7 HANGZHOU FUZAMEI TECHNOLOGY(中国) 5
7 NTT 5
10 BRITISH TELECOMM(英国) 4
10 SHENZHEN'S FIGURE SPIRIT SINGULAR
POINT INTELLIGENT TECHNOLOGY(中国) 4
10 中国銀聯(中国) 4
10 飛天テクノロジーズ(中国) 4
3.ブロックチェーン利用場面のファミリー件数上位出願人ランキング
「決済以外も含むブロックチェーン技術の利用場面」における出願人の上位 10 位を
表 4-10 に示す。
も多いのが nChain(47 件)とコインプラグ(47 件)で、次いで、トロント・ドミニ
オン銀行(21 件)、Dacadoo(15 件)、マスターカード(15 件)が続いている。日本国籍
ななく、米国籍から 3 者、欧州国籍から 3 者、中国籍から 1 者、韓国籍から 1 者がラン
クインしている。
表 4-10 「決済以外も含むブロックチェーン技術の利用場面」 - ファミリー件数上位出願人ラ
ンキング(日米欧中韓への出願、出願年(優先権主張年):2010-2016 年)
順位 出願人名称 件数
1 nChain(英国) 47
1 コインプラグ(韓国) 47
3 トロント・ドミニオン銀行(カナダ) 21
4 Dacadoo(スイス) 15
4 マスターカード(米国) 15
6 IBM(米国) 14
7 TRAN BAO(個人:米国) 13
8 BRITISH TELECOMM(英国) 11
8 Bubi ネットワーク(中国) 11
8 T0.com Inc(米国) 11
- 77 -
資料編
第7部
第6部
第5部
第3部
第2部
第1部
本編
要約
目次
第4部
第 5 章 研究開発動向調査
第 1 節 調査対象範囲と調査方法
1. 調査対象範囲
仮想通貨・電子マネーによる決済システムに関する研究開発動向について、全体動向
調査、技術区分別動向調査、研究者所属機関・研究者別動向調査及び注目論文の調査を
行った。
(1) 使用したデータベースと調査対象期間
論文検索には、IEEE(米国電気電子学会)が提供する IEEE Xplore Digital Library
を用い、発行年が 2010 年から 2017 年を調査対象期間とした。IEEE Xplore は世界の通
信・電子・情報工学分野の論文コレクションとして世界 大規模のデータベースだが、
特にブロックチェーン関連技術分野においては、査読を伴わないプレプリントサーバ型
サービスへの投稿やオープン参加型の開発者コミュニティを通じた議論も活発であり、
研究者や所属機関の網羅性には限界があることに留意が必要である。
(2) 調査対象技術範囲
本調査における論文データベース検索では、仮想通貨・電子マネーによる決済システ
ムに関するキーワードを使用し、表 5-1 に示した検索式で検索した結果を調査対象母集
団とした。
表 5-1 論文データベース検索式
集合
番号 検索式
ヒッ
ト
件数
備考
#1 electronic-wallet* OR electronic-purse OR electronic-currenc*
OR electronic-money OR electronic-cash OR electronic-coin OR
e-wallet* OR e-purse OR e-currenc* OR e-money OR e-cash OR e-
coin
424 電子マネー
#2 digital-wallet* OR digital-purse OR digital-currenc* OR
digital-money OR digital-cash OR digital-coin OR internet-
wallet* OR internet-purse OR internet-currenc* OR internet-
money OR internet-cash
82
#3 mobile-wallet* OR mobile-purse OR mobile-currenc* OR mobile-
money OR mobile-cash OR mobile-coin OR smart-wallet* OR
smart-purse OR smart-currenc* OR smart-money OR smart-cash OR
smart-coin
58
#4 quicpay OR quic-pay OR applepay OR apple-pay OR linepay OR
line-pay OR googlepay OR google-pay OR wechatpay OR wechat-
pay OR alipay OR ali-pay OR paypal OR pay-pal
63 電子マネーの固有名称
#5 suica OR "edy" OR waon OR nanaco OR au-wallet OR pasmo OR
icoca OR manaca OR pitapa OR webmoney OR bitcash OR visa-
paywave OR paypass
73
#6 androidpay OR android-pay OR UnionPay OR Union-Pay OR
samsungpay OR samsung-pay
7
- 78 -
資料編
第7部
第6部 第5部
第3部
第2部
第1部
本編
要約
目次
第4部
#7 electronic-payment OR electronic-settlement OR e-payment OR
e-settlement OR digital-payment OR digital-settlement OR
internet-payment OR internet-settlement OR mobile-payment OR
mobile-settlement OR smart-payment OR smart-settlement
487 電子決済
#8 mobile-payment OR smartphone-payment OR mobile-settlement OR
smartphone-settlement
296 モバイル決済
#9 loyalty-program OR loyalty-card* OR point-program OR point-
card*
91 ポイント
#10 (virtual OR crypto* OR cyber*) AND (currenc* OR mone* OR
wallet* OR purse OR cash OR coin)
1,016 仮想通貨・暗号通貨
#11 (cipher* OR cypher* OR encipher OR encypher) AND (currenc* OR
mone* OR wallet* OR purse OR cash OR coin)
20
#12 cryptocurrenc* OR cryptomone* OR cryptowallet* OR cryptopurse
OR cryptocash OR cryptocoin
121
#13 (QR OR Quick-Response OR barcode OR bar-code OR 2D OR 2-D OR
two-dimension* OR 2-dimension*) AND (payment OR settlement OR
"Abstract":transact*)
135 QR コード、二次元バーコ
ード × (支払・決済)
#14 blockchain* OR block-chain* OR ((distribut* OR decentral*)
AND (ledger OR currenc*)) OR proof-of-work OR proof-of-stake
OR smart-contract OR hyperledger OR cryptoNote OR Ethash
583 ブロックチェーン、分散型
台帳
#15 (micropayment* OR micro-payment* OR block-height* OR number-
used-once OR nonce) AND (block OR blocks OR distributed-
ledger*)
13 ブロックチェーン技術関連
#16 bitcoin* OR ethereum OR litecoin* 310 仮想通貨の固有名称
※ ripple, eos, stellar
についてはノイズがかなり
多いため除外
#17 (cryptography OR "cryptographic protocols" OR "Trusted
computing" OR Authorization OR "digital signatures" OR
"security of data" OR "data privacy") AND ("financial data
processing" OR "transaction processing" OR "Bank data
processing" OR "credit transactions" OR payment OR
settlement)
1,137 (暗号・信頼性・認証・電
子署名・セキュリティ) ×
(支払・決済・金融データ
処理)
#18 ("biometrics (access control)" OR "near-field communication"
OR "radiofrequency identification" OR Bluetooth OR
"fingerprint identification" OR "face recognition" OR eye OR
"Smart cards") AND ("financial data processing" OR
"transaction processing" OR "Bank data processing" OR "credit
transactions" OR payment OR settlement)
447 (生体認証・NFC・RFID・ス
マートカード) × (支払・
決済・金融データ処理)
#19 ("peer-to-peer computing" OR "cloud computing") AND
("financial data processing" OR "transaction processing" OR
"Bank data processing" OR "credit transactions" OR payment OR
settlement)
598 (P2P・クラウドコンピュー
ティング) × (支払・決
済・金融データ処理)
#20 ("mobile commerce" OR "electronic commerce" OR "mobile
handsets" OR "smart phones" OR "Mobile computing" OR
"telecommunication computing") AND ("financial data
processing" OR "transaction processing" OR "Bank data
processing" OR "credit transactions" OR payment OR
settlement)
1,276 (モバイルコマース・E コ
マース・モバイルコンピュ
ーティング) × (支払・決
済・金融データ処理)
#21 ("Financial data processing" OR "Bank data processing" OR
"Retail data processing" OR "credit transactions" OR
"Transaction processing") AND (payment OR settlement)
392 (金融データ処理) × (支
払・決済)
#22 (cryptography OR "cryptographic protocols" OR "Trusted
computing" OR Authorization OR "digital signatures" OR
"security of data" OR "data privacy") AND ("mobile commerce"
OR "electronic commerce" OR "credit transactions")
1,145 (暗号・信頼性・認証・電
子署名・セキュリティ) ×
(モバイルコマース・E コ
マース・クレジット処理)
- 79 -
資料編
第7部
第6部
第5部
第3部
第2部
第1部
本編
要約
目次
第4部
#23 ("biometrics (access control)" OR "near-field communication"
OR "radiofrequency identification" OR Bluetooth OR
"fingerprint identification" OR "face recognition" OR eye OR
"Smart cards") AND ("mobile commerce" OR "electronic
commerce" OR "credit transactions")
251 (生体認証・NFC・RFID・ス
マートカード) × (モバイ
ルコマース・E コマース・
クレジット処理)
#24 ("peer-to-peer computing" OR "cloud computing") AND ("mobile
commerce" OR "electronic commerce" OR "credit transactions")
470 (P2P・クラウドコンピュー
ティング) × (モバイルコ
マース・E コマース・クレ
ジット処理)
#25 ("retail data processing") AND ("mobile commerce" OR
"electronic commerce" OR "credit transactions")
441 リテールデータ処理 ×
(モバイルコマース・E コ
マース・クレジット処理)
#26 #1 ~ #25 の和演算 5,740
2. 調査方法
1.で示した条件での論文データベース検索で得られた文献件数は 5,740 件である。
これらの詳細調査を行い、仮想通貨・電子マネーによる決済システムに関連がある論
文 2,047 件を抽出し、特許出願動向調査と同じ技術区分(表 4-2~表 4-6)の付与を行っ
た。
また、研究者所属機関の国籍を用いた分析を行う為、筆頭著者の所属機関名を名寄せ
し、その住所等から国籍の付与を行った。但し、調査対象である 2,047 件の内、738 件は
データベースから所属機関を入手することができない為、研究者所属機関の国籍を用い
た分析の対象外とした。
- 80 -
資料編
第7部
第6部 第5部
第3部
第2部
第1部
本編
要約
目次
第4部
第 2 節 調査結果
1. 論文発表件数推移
2010 年から 2017 年までにおける、研究者所属機関国籍別の論文発表件数推移と論文
発表件数比率を、図 5-1 に示す。
論文発表件数比率では、その他国籍(地域も含む)を除くと中国籍が も多く 24.4%
(320 件)であり、欧州国籍 20.9%(273 件)、米国籍 9.1%(119 件)の順で続いてい
る。その他国籍(地域も含む)ではインド国籍(180 件)が目立って多く、次にインドネ
シア国籍(47 件)と台湾籍(46 件)が続く。
発表件数全体の推移は、2010 年から 2013 年にかけて緩やかに減少した後、2015 年頃
から反転して急増している。特に 2016 年から 2017 年にかけての伸長率が高い。
国籍別では、特に中国籍と欧州国籍が 2016 年から 2017 年にかけて急増している。
図 5-1 研究者所属機関国籍別論文発表件数推移及び論文発表件数比率(発行年:2010-2017
年)
日本国籍
35件2.7%
米国籍
119件
9.1%
欧州国籍
273件
20.9%
中国籍
320件24.4%
韓国籍
38件
2.9%
その他
524件40.0%
合計
1,309件
170
128 120
111 112
154
189
325
0
50
100
150
200
250
300
350
0
20
40
60
80
100
120
140
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
合計
発表件数
発行年
日本 米国 欧州 中国 韓国 その他 合計
研究者所属機関国籍(地域)
発行年
2010-2017年
- 81 -
資料編
第7部
第6部
第5部
第3部
第2部
第1部
本編
要約
目次
第4部
2. 論文発表件数上位ランキング
研究者所属機関別の論文発表件数上位ランキングを表 5-2 に示す。
も多いのが北京郵電大学(24 件)、次いでテレコムパリテック(16 件)、バンドン工
科大学(14 件)と続いている。上位 28 機関を国籍別に見ると、中国が 13 機関と突出し、
次いでインドネシア 3 機関、米国 2 機関、欧州 2 機関、インド 2 機関、韓国、イラン、
マレーシア、タイ、カナダ、オーストラリアが各 1 機関となっている。日本はランクイ
ンしていない。
表 5-2 全体の研究者所属機関別上位ランキング(発行年:2010-2017 年)
順位 研究者所属機関 発表件数
1 北京郵電大学(中国) 24
2 テレコムパリテック(フランス) 16
3 バンドン工科大学(インドネシア) 14
4 国立工科大学(インド) 12
5 IBM(米国) 10
5 イスラーム自由大学(イラン) 10
7 ビナ・ヌサンタラ大学(インドネシア) 9
8 西安交通大学(中国) 8
8 中国科学院(中国) 8
8 北京航空航天大学(中国) 8
11 カリフォルニア大学(米国) 7
11 国防科技大学(中国) 7
11 石家庄鉄道大学(中国) 7
14 インド工科大学(インド) 6
14 マレーシア工科大学(マレーシア) 6
14 電子科技大学(中国) 6
14 北京交通大学(中国) 6
18 Mahanakorn University of Technology(タ
イ) 5
18 Universitat Pompeu Fabra(スペイン) 5
18 インドネシア大学(インドネシア) 5
18 コンコルディア大学(カナダ) 5
18 ニューサウスウェールズ大学(オーストラ
リア) 5
18 華南理工大学(中国) 5
18 韓国電子通信研究院(韓国) 5
18 江西科技師範学院(中国) 5
18 重慶郵電大学(中国) 5
18 上海大学(中国) 5
18 中南大学(中国) 5
- 82 -
資料編
第7部
第6部 第5部
第3部
第2部
第1部
本編
要約
目次
第4部
3. ブロックチェーン関連技術の主な開発コミュニティ動向
オープン参加型の開発者コミュニティにおいて、ブロックチェーン関連技術の仕様に
関する提案が開発者によって議論され、「Draft(草案)」や「Accepted(承認)」といった
プロセスを経て採用・実装に至っている。主な開発コミュニティに、ビットコインの
Bitcoin Improvement Proposals(BIP)と、イーサリアムの Ethereum Improvement
Proposals(EIP)があり、いずれも米国 GitHub 社が提供するソフトウェア開発プラット
フォーム「GitHub」上で運営されている。
これらの開発動向を調べるため、BIP 及び EIP における技術提案とその著者、および当
該提案の議論に加わったコントリビュータ(寄与者)数を表 5-3 から表 5-41に、著者別
の提案件数上位ランキングを表 5-5 に示す。
表 5-3 (a) Bitcoin Improvement Proposals(BIP)における提案リスト
1 2019 年 1 月 15 日時点の調査による。ネットワークプロトコルやトランザクション等に関する提案である
「Standard」を対象とし、コミュニティの運営やガイドラインに関する提案や承認を伴わない提案である
「Informational」「Process」「Meta」は除外した。
bip番号 レイヤー タイトル 著者 タイプ ステータスコントリビュータ数
bip-0011 Applications M-of-N Standard Transactions Gavin Andresen Standard Final 4bip-0013 Applications Address Format for pay-to-script-hash Gavin Andresen Standard Final 5bip-0015 Applications Aliases Amir Taaki Standard Deferred 3bip-0019 Applications M-of-N Standard Transactions (Low SigOp) Luke Dashjr Standard Draft 4bip-0020 Applications URI Scheme Luke Dashjr Standard Replaced 3bip-0021 Applications URI Scheme Nils Schneider, Matt Corallo Standard Final 7bip-0038 Applications Passphrase-protected private key Mike Caldwell, Aaron Voisine Standard Draft 8bip-0039 Applications Mnemonic code for generating deterministic
keysMarek Palatinus, Pavol Rusnak,Aaron Voisine, Sean Bowe
Standard Proposed 30
bip-0044 Applications Multi-Account Hierarchy for DeterministicWallets
Marek Palatinus, Pavol Rusnak Standard Proposed 13
bip-0045 Applications Structure for Deterministic P2SH MultisignatureWallets
Manuel Araoz, Ryan X. Charles,Matias Alejo Garcia
Standard Proposed 5
bip-0063 Applications Stealth Addresses Peter Todd Standard BIP numberallocated -
bip-0067 Applications Deterministic Pay-to-script-hash multi-signature addresses through public key sorting
Thomas Kerin, Jean-PierreRupp, Ruben de Vries
Standard Proposed 4
bip-0070 Applications Payment Protocol Gavin Andresen, Mike Hearn Standard Final 15bip-0071 Applications Payment Protocol MIME types Gavin Andresen Standard Final 4bip-0072 Applications bitcoin: uri extensions for Payment Protocol Gavin Andresen Standard Final 6bip-0073 Applications Use "Accept" header for response type
negotiation with Payment Request URLsStephen Pair Standard Final 3
bip-0074 Applications Allow zero value OP_RETURN in PaymentProtocol
Toby Padilla Standard Draft 2
bip-0075 Applications Out of Band Address Exchange using PaymentProtocol Encryption
Justin Newton, Matt David,Aaron Voisine, James MacWhyte
Standard Draft 5
bip-0083 Applications Dynamic Hierarchical Deterministic Key Trees Eric Lombrozo Standard Draft 2bip-0120 Applications Proof of Payment Kalle Rosenbaum Standard Withdrawn 3bip-0121 Applications Proof of Payment URI scheme Kalle Rosenbaum Standard Withdrawn 3bip-0122 Applications URI scheme for Blockchain references /
explorationMarco Pontello Standard Draft 3
bip-0125 Applications Opt-in Full Replace-by-Fee Signaling David A. Harding, Peter Todd Standard Proposed 4bip-0142 Applications Address Format for Segregated Witness Johnson Lau Standard Withdrawn 5bip-0171 Applications Currency/exchange rate information API Luke Dashjr Standard Draft 1bip-0174 Applications Partially Signed Bitcoin Transaction Format Andrew Chow Standard Proposed 5bip-0178 Applications Version Extended WIF Karl-Johan Alm Standard Draft 1bip-0199 Applications Hashed Time-Locked Contract transactions Sean Bowe, Daira Hopwood Standard Draft 2bip-0322 Applications Generic Signed Message Format Karl-Johan Alm Standard Draft 1
- 83 -
資料編
第7部
第6部
第5部
第3部
第2部
第1部
本編
要約
目次
第4部
表 5-3 (b) Bitcoin Improvement Proposals(BIP)における提案リスト
bip番号 レイヤー タイトル 著者 タイプ ステータスコントリビュータ数
bip-0022 API/RPC getblocktemplate - Fundamentals Luke Dashjr Standard Final 4bip-0023 API/RPC getblocktemplate - Pooled Mining Luke Dashjr Standard Final 4bip-0040 API/RPC Stratum wire protocol Marek Palatinus Standard BIP number
allocated -
bip-0041 API/RPC Stratum mining protocol Marek Palatinus Standard BIP numberallocated -
bip-0145 API/RPC getblocktemplate Updates for SegregatedWitness
Luke Dashjr Standard Final 2
bip-0101 Consensus (hf) Increase maximum block size Gavin Andresen Standard Withdrawn 2bip-0102 Consensus (hf) Block size increase to 2MB Jeff Garzik Standard Draft 2bip-0103 Consensus (hf) Block size following technological growth Pieter Wuille Standard Draft 3bip-0104 Consensus (hf) 'Block75' - Max block size like difficulty t.khan Standard Draft 1bip-0105 Consensus (hf) Consensus based block size retargeting
algorithmBtcDrak Standard Draft 2
bip-0106 Consensus (hf) Dynamically Controlled Bitcoin Block Size MaxCap
Upal Chakraborty Standard Draft 3
bip-0107 Consensus (hf) Dynamic limit on the block size Washington Y. Sanchez Standard Draft 2bip-0109 Consensus (hf) Two million byte size limit with sigop and
sighash limitsGavin Andresen Standard Rejected 2
bip-0131 Consensus (hf) "Coalescing Transaction" Specification(wildcard inputs)
Chris Priest Standard Draft 2
bip-0134 Consensus (hf) Flexible Transactions Tom Zander Standard Draft 2bip-0012 Consensus (sf) OP_EVAL Gavin Andresen Standard Withdrawn 3bip-0016 Consensus (sf) Pay to Script Hash Gavin Andresen Standard Final 8bip-0017 Consensus (sf) OP_CHECKHASHVERIFY (CHV) Luke Dashjr Standard Withdrawn 3bip-0018 Consensus (sf) ashScriptCheck Luke Dashjr Standard Proposed 3bip-0030 Consensus (sf) Duplicate transactions Pieter Wuille Standard Final 5bip-0034 Consensus (sf) Block v2, Height in Coinbase Gavin Andresen Standard Final 4bip-0042 Consensus (sf) A finite monetary supply for Bitcoin Pieter Wuille Standard Final 3bip-0062 Consensus (sf) Dealing with malleability Pieter Wuille Standard Withdrawn 6bip-0065 Consensus (sf) OP_CHECKLOCKTIMEVERIFY Peter Todd Standard Final 11bip-0066 Consensus (sf) Strict DER signatures Pieter Wuille Standard Final 6bip-0068 Consensus (sf) Relative lock-time using consensus-enforced
sequence numbersMark Friedenbach, BtcDrak,Nicolas Dorier, kinoshitajona
Standard Final 7
bip-0091 Consensus (sf) Reduced threshold Segwit MASF James Hilliard Standard Final 2bip-0098 Consensus (sf) Fast Merkle Trees Mark Friedenbach, Kalle Alm,
BtcDrakStandard Draft 3
bip-0112 Consensus (sf) CHECKSEQUENCEVERIFY BtcDrak, Mark Friedenbach, EricLombrozo
Standard Final 8
bip-0113 Consensus (sf) Median time-past as endpoint for lock-timecalculations
Thomas Kerin, MarkFriedenbach
Standard Final 5
bip-0114 Consensus (sf) Merkelized Abstract Syntax Tree Johnson Lau Standard Draft 3bip-0115 Consensus (sf) Generic anti-replay protection using Script Luke Dashjr Standard Draft 2bip-0116 Consensus (sf) MERKLEBRANCHVERIFY Mark Friedenbach, Kalle Alm,
BtcDrakStandard Draft 3
bip-0117 Consensus (sf) Tail Call Execution Semantics Mark Friedenbach, Kalle Alm,BtcDrak
Standard Draft 3
bip-0118 Consensus (sf) SIGHASH_NOINPUT Christian Decker Standard Draft 3bip-0140 Consensus (sf) Normalized TXID Christian Decker Standard Draft 2bip-0141 Consensus (sf) Segregated Witness (Consensus layer) Eric Lombrozo, Johnson Lau,
Pieter WuilleStandard Final 16
bip-0143 Consensus (sf) Transaction Signature Verification for Version 0Witness Program
Johnson Lau, Pieter Wuille Standard Final 6
bip-0146 Consensus (sf) Dealing with signature encoding malleability Johnson Lau, Pieter Wuille Standard Draft 2bip-0147 Consensus (sf) Dealing with dummy stack element malleability Johnson Lau Standard Final 3bip-0148 Consensus (sf) Mandatory activation of segwit deployment Shaolin Fry Standard Final 2bip-0149 Consensus (sf) Segregated Witness (second deployment) Shaolin Fry Standard Withdrawn 1
- 84 -
資料編
第7部
第6部 第5部
第3部
第2部
第1部
本編
要約
目次
第4部
表 5-3 (c) Bitcoin Improvement Proposals(BIP)における提案リスト
bip番号 レイヤー タイトル 著者 タイプ ステータスコントリビュータ数
bip-0014 Peer Services Protocol Version and User Agent Amir Taaki, Patrick Strateman Standard Final 4bip-0031 Peer Services Pong message Mike Hearn Standard Final 3bip-0033 Peer Services Stratized Nodes Amir Taaki Standard Draft 3bip-0035 Peer Services mempool message Jeff Garzik Standard Final 2bip-0036 Peer Services Custom Services Stefan Thomas Standard Draft 3bip-0037 Peer Services Connection Bloom filtering Mike Hearn, Matt Corallo Standard Final 6bip-0060 Peer Services Fixed Length "version" Message (Relay-
Transactions Field)Amir Taaki Standard Draft 3
bip-0061 Peer Services Reject P2P message Gavin Andresen Standard Final 4bip-0064 Peer Services getutxo message Mike Hearn Standard Draft 2bip-0111 Peer Services NODE_BLOOM service bit Matt Corallo, Peter Todd Standard Proposed 3bip-0130 Peer Services sendheaders message Suhas Daftuar Standard Proposed 2bip-0133 Peer Services feefilter message Alex Morcos Standard Draft 3bip-0144 Peer Services Segregated Witness (Peer Services) Eric Lombrozo, Pieter Wuille Standard Final 8bip-0150 Peer Services Peer Authentication Jonas Schnelli Standard Draft 4bip-0151 Peer Services Peer-to-Peer Communication Encryption Jonas Schnelli Standard Draft 4bip-0152 Peer Services Compact Block Relay Matt Corallo Standard Draft 7bip-0154 Peer Services Rate Limiting via peer specified challenges Karl-Johan Alm Standard Draft 1bip-0156 Peer Services Dandelion - Privacy Enhancing Routing Brad Denby, Andrew Miller,
Giulia Fanti, Surya Bakshi,Shaileshh BojjaVenkatakrishnan, PramodViswanath
Standard Draft 1
bip-0157 Peer Services Client Side Block Filtering Olaoluwa Osuntokun, AlexAkselrod, Jim Posen
Standard Draft 2
bip-0158 Peer Services Compact Block Filters for Light Clients Olaoluwa Osuntokun, AlexAkselrod
Standard Draft 6
bip-0159 Peer Services NODE_NETWORK_LIMITED service bit Jonas Schnelli Standard Draft 3bip-0180 Peer Services Block size/weight fraud proof Luke Dashjr Standard Draft 1
- 85 -
資料編
第7部
第6部
第5部
第3部
第2部
第1部
本編
要約
目次
第4部
表 5-4 (a) Ethereum Improvement Proposals(EIP)における提案リスト
eip番号 カテゴリ タイトル 著者 タイプ ステータス コントリビュータ数
eip-0002 Core Homestead Hard-fork Changes Vitalik Buterin Standard Final 3eip-0003 Core Addition of CALLDEPTH opcode Martin Holst Swende Standard Deferred 3eip-0005 Core Gas Usage for `RETURN` and `CALL*` Christian Reitwiessner Standard Superseded 6eip-0007 Core DELEGATECALL Vitalik Buterin Standard Final 6eip-0086 Core Abstraction of transaction origin and signature Vitalik Buterin Standard Draft 2eip-0100 Core Change difficulty adjustment to target mean block time
including unclesVitalik Buterin Standard Final 3
eip-0101 Core Serenity Currency and Crypto Abstraction Vitalik Buterin Standard Draft 1eip-0140 Core REVERT instruction Alex Beregszaszi, Nikolai
MushegianStandard Final 5
eip-0141 Core Designated invalid EVM instruction Alex Beregszaszi Standard Final 3eip-0145 Core Bitwise shifting instructions in EVM Alex Beregszaszi, Paweł Bylica Standard Accepted 6eip-0150 Core Gas cost changes for IO-heavy operations Vitalik Buterin Standard Final 4eip-0155 Core Simple replay attack protection Vitalik Buterin Standard Final 8eip-0158 Core State clearing Vitalik Buterin Standard Replaced 2eip-0160 Core EXP cost increase Vitalik Buterin Standard Final 3eip-0161 Core State trie clearing (invariant-preserving alternative) Gavin Wood Standard Final 3eip-0170 Core Contract code size limit Vitalik Buterin Standard Final 3eip-0196 Core Precompiled contracts for addition and scalar
multiplication on the elliptic curve alt_bn128Christian Reitwiessner Standard Final 2
eip-0197 Core Precompiled contracts for optimal ate pairing check onthe elliptic curve alt_bn128
Vitalik Buterin, ChristianReitwiessner
Standard Final 4
eip-0198 Core Big integer modular exponentiation Vitalik Buterin Standard Final 3eip-0210 Core Blockhash refactoring Vitalik Buterin Standard Draft 3eip-0211 Core New opcodes: RETURNDATASIZE and
RETURNDATACOPYChristian Reitwiessner Standard Final 2
eip-0214 Core New opcode STATICCALL Vitalik Buterin, ChristianReitwiessner
Standard Final 3
eip-0615 Core Subroutines and Static Jumps for the EVM Greg Colvin, Paweł Bylica,Christian Reitwiessner
Standard Draft 3
eip-0616 Core SIMD Operations for the EVM Greg Colvin Standard Deferred 4eip-0649 Core Metropolis Difficulty Bomb Delay and Block Reward
ReductionAfri Schoedon, Vitalik Buterin Standard Final 2
eip-0658 Core Embedding transaction status code in receipts Nick Johnson Standard Final 1eip-0665 Core Add precompiled contract for Ed25519 signature
verificationTobias Oberstein Standard Draft 2
eip-0689 Core Address Collision of Contract Address CausesExceptional Halt
Yoichi Hirai Standard Draft 2
eip-0858 Core Reduce block reward and delay difficulty bomb Carl Larson Standard Draft 2eip-0908 Core Reward clients for a sustainable network James Ray, Micah Zoltu Standard Draft 1eip-0969 Core Modifications to ethash to invalidate existing dedicated
hardware implementationsDavid Stanfill Standard Draft 2
eip-0999 Core Restore Contract Code at0x863DF6BFa4469f3ead0bE8f9F2AAE51c91A907b4
Afri Schoedon Standard Draft 1
eip-1010 Core Uniformity Between0xAb5801a7D398351b8bE11C439e05C5B3259aeC9Band0x15E55EF43efA8348dDaeAa455F16C43B64917e3c
Anderson Wesley Standard Draft
1
eip-1011 Core Hybrid Casper FFG Danny Ryan, Chih-Cheng Liang Standard Draft 2eip-1014 Core Skinny CREATE2 Vitalik Buterin Standard Draft 3eip-1015 Core Configurable On Chain Issuance Alex Van de Sande Standard Draft 1eip-1051 Core Overflow checking for the EVM Nick Johnson Standard Draft 1eip-1052 Core EXTCODEHASH opcode Nick Johnson, Paweł Bylica Standard Draft 3eip-1057 Core ProgPoW, a Programmatic Proof-of-Work IfDefElse Standard Draft 2eip-1087 Core Net gas metering for SSTORE operations Nick Johnson Standard Draft 2eip-1108 Core Reduce alt_bn128 precompile gas costs Antonio Salazar Cardozo Standard Draft 2eip-1109 Core PRECOMPILEDCALL opcode (Remove CALL costs for
precompiled contracts)Jordi Baylina Standard Draft 1
eip-1153 Core Transient storage opcodes Alexey Akhunov Standard Draft 1eip-1227 Core Defuse Difficulty Bomb and Reset Block Reward SmeargleUsedFly Standard Draft 1eip-1234 Core Constantinople Difficulty Bomb Delay and Block
Reward AdjustmentAfri Schoedon Standard Accepted 1
eip-1240 Core Remove Difficulty Bomb Micah Zoltu Standard Draft 1eip-1276 Core Eliminate Difficulty Bomb and Adjust Block Reward on
Constantinople ShiftEOS Classic Standard Draft 0
eip-1283 Core Net gas metering for SSTORE without dirty maps Wei Tang Standard Accepted 2eip-1295 Core Modify Ethereum PoW Incentive Structure and Delay
Difficulty BombBrian Venturo Standard Draft 2
eip-1352 Core Specify restricted address range forprecompiles/system contracts
Alex Beregszaszi Standard Draft 1
eip-1355 Core Ethash 1a Paweł Bylica, Jean M. Cyr Standard Draft 1eip-1380 Core Reduced gas cost for call to self Alex Beregszaszi, Jacques
WagenerStandard Draft 1
eip-1482 Core Define a maximum block timestamp drift Maurelian Standard Draft 1
- 86 -
資料編
第7部
第6部 第5部
第3部
第2部
第1部
本編
要約
目次
第4部
表 5-4 (b) Ethereum Improvement Proposals(EIP)における提案リスト
表 5-4 (c) Ethereum Improvement Proposals(EIP)における提案リスト
eip番号 カテゴリ タイトル 著者 タイプ ステータス コントリビュータ数
eip-0006 Interface Renaming SUICIDE opcode Hudson Jameson Standard Final 3eip-0107 Interface safe "eth_sendTransaction" authorization via html
popupRonan Sandford Standard Draft 2
eip-0234 Interface Add `blockHash` to JSON-RPC filter options. Micah Zoltu Standard Draft 2eip-0695 Interface Create `eth_chainId` method for JSON-RPC Isaac Ardis, Wei Tang, Fan
TorchzStandard Draft 3
eip-0712 Interface Ethereum typed structured data hashing and signing Remco Bloemen, LeonidLogvinov, Jacob Evans
Standard Draft 4
eip-0758 Interface Subscriptions and filters for completed transactions Jack Peterson Standard Draft 4eip-1102 Interface Opt-in account exposure Paul Bouchon Standard Draft 1eip-1186 Interface RPC-Method to get Merkle Proofs - eth_getProof Simon Jentzsch, Christoph
JentzschStandard Draft 1
eip-1193 Interface Ethereum Provider JavaScript API Ryan Ghods, Marc Garreau Standard Draft 1eip-0008 Networking devp2p Forward Compatibility Requirements for
HomesteadFelix Lange Standard Final 3
eip-0627 Networking Whisper Specification Vlad Gluhovsky Standard Draft 2eip-0706 Networking DEVp2p snappy compression Péter Szilágyi Standard Final 2eip-0778 Networking Ethereum Node Records (ENR) Felix Lange Standard Draft 3eip-0868 Networking Node Discovery v4 ENR Extension Felix Lange Standard Draft 2eip-1459 Networking Node Discovery via DNS Felix Lange, Péter Szilágyi Standard Draft 1eip-1571 Networking EthereumStratum/2.0.0 Andrea Lanfranchi, Pawel Bylica,
Marius Van Der WijdenStandard Draft 1
eip番号 カテゴリ タイトル 著者 タイプ ステータス コントリビュータ数
eip-0020 ERC ERC-20 Token Standard Fabian Vogelsteller, VitalikButerin
Standard Final 9
eip-0055 ERC Mixed-case checksum address encoding Vitalik Buterin Standard Final 9eip-0137 ERC Ethereum Domain Name Service - Specification Nick Johnson Standard Final 3eip-0162 ERC Initial ENS Hash Registrar Maurelian, Nick Johnson, Alex
Van de SandeStandard Final 4
eip-0165 ERC ERC-165 Standard Interface Detection Christian Reitwießner, NickJohnson, Fabian Vogelsteller,Jordi Baylina, Konrad Feldmeier,William Entriken
Standard Final
4
eip-0173 ERC ERC-173 Contract Ownership Standard Nick Mudge, Dan Finlay Standard Draft 1eip-0181 ERC ENS support for reverse resolution of Ethereum
addressesNick Johnson Standard Final 1
eip-0190 ERC Ethereum Smart Contract Packaging Standard Piper Merriam, Tim Coulter,Denis Erfurt, RJ Catalano, IuriMatias
Standard Final4
eip-0191 ERC Signed Data Standard Martin Holst Swende, NickJohnson
Standard Draft 3
eip-0205 ERC ENS support for contract ABIs Nick Johnson Standard Draft 1eip-0634 ERC Storage of text records in ENS Richard Moore Standard Draft 2eip-0681 ERC URL Format for Transaction Requests Daniel A. Nagy Standard Draft 3eip-0721 ERC ERC-721 Non-Fungible Token Standard William Entriken, Dieter Shirley,
Jacob Evans, Nastassia SachsStandard Final 11
eip-0725 ERC Proxy Identity Fabian Vogelsteller Standard Draft 5eip-0777 ERC A New Advanced Token Standard Jacques Dafflon, Jordi Baylina,
Thomas ShababiStandard Draft 1
eip-0801 ERC ERC-801 Canary Standard ligi Standard Draft 2eip-0820 ERC Pseudo-introspection Registry Contract Jordi Baylina, Jacques Dafflon Standard Final 4eip-0823 ERC Token Exchange Standard Kashish Khullar Standard Draft 2eip-0831 ERC URI Format for Ethereum ligi Standard Draft 3eip-0875 ERC A better NFT standard Weiwu Zhang, James Sangalli Standard Draft 1eip-0884 ERC DGCL Token Dave Sag Standard Draft 3eip-0897 ERC ERC DelegateProxy Jorge Izquierdo, Manuel Araoz Standard Draft 1eip-0900 ERC Simple Staking Interface Dean Eigenmann, Jorge
IzquierdoStandard Draft 3
eip-0902 ERC Token Validation Brooklyn Zelenka, TomCarchrae, Gleb Naumenko
Standard Draft 1
eip-0918 ERC Mineable Token Standard Jay Logelin, Infernal_toast,Michael Seiler, Brandon Grill
Standard Draft 2
eip-0926 ERC Address metadata registry Nick Johnson Standard Draft 1eip-0927 ERC Generalised authorisations Nick Johnson Standard Draft 1eip-0998 ERC ERC-998 Composable Non-Fungible Token Standard Matt Lockyer, Nick Mudge,
Jordan SchalmStandard Draft 2
eip-1046 ERC ERC20 Metadata Extension Tommy Nicholas, Matt Russo,John Zettler, Matt Condon
Standard Draft 1
eip-1047 ERC Token Metadata JSON Schema Tommy Nicholas, Matt Russo,John Zettler
Standard Draft 1
eip-1062 ERC Formalize IPFS hash into ENS(Ethereum Name Service)resolver
Phyrex Tsai, Portal NetworkTeam
Standard Draft 1
- 87 -
資料編
第7部
第6部
第5部
第3部
第2部
第1部
本編
要約
目次
第4部
表 5-4 (d) Ethereum Improvement Proposals(EIP)における提案リスト
eip番号 カテゴリ タイトル 著者 タイプ ステータス コントリビュータ数
eip-1066 ERC Status Codes Brooklyn Zelenka, TomCarchrae, Gleb Naumenko
Standard Draft 2
eip-1077 ERC Executable Signed Messages refunded by the contract Alex Van de Sande, RicardoGuilherme Schmidt
Standard Draft 2
eip-1078 ERC Universal login / signup using ENS subdomains Alex Van de Sande Standard Draft 1eip-1080 ERC Recoverable Token Bradley Leatherwood Standard Draft 1eip-1081 ERC Standard Bounties Mark Beylin, Kevin Owocki,
Ricardo Guilherme SchmidtStandard Draft 1
eip-1123 ERC Revised Ethereum Smart Contract Packaging Standard g. nicholas dʼandrea, PiperMerriam, Nick Gheorghita,Danny Ryan
Standard Draft1
eip-1129 ERC Standardised DAPP announcements Jan Turk Standard Draft 1eip-1132 ERC Extending ERC20 with token locking capability nitika-goel Standard Draft 1eip-1154 ERC Oracle Interface Alan Lu Standard Draft 1eip-1155 ERC ERC-1155 Multi Token Standard Witek Radomski, Andrew Cooke,
Philippe Castonguay, JamesTherien, Eric Binet
Standard Draft1
eip-1167 ERC Minimal Proxy Contract Peter Murray, Nate Welch, JoeMesserman
Standard Final 3
eip-1175 ERC Wallet & shop standard for all tokens (erc20) Jet Lim Standard Draft 1eip-1178 ERC Multi-class Token Standard Albert Chon Standard Draft 1eip-1185 ERC Storage of DNS Records in ENS Jim McDonald Standard Draft 1eip-1191 ERC Add chain id to mixed-case checksum address
encodingJuliano Rizzo Standard Draft 1
eip-1202 ERC Voting Standard Zainan Victor Zhou, Evan, Yin Xu Standard Draft 1eip-1203 ERC ERC-1203 Multi-Class Token Standard (ERC-20
Extension)Jeff Huang, Min Zu Standard Draft 1
eip-1207 ERC DAuth Access Delegation Standard Xiaoyu Wang, Bicong Wang Standard Draft 1eip-1261 ERC Membership Verification Token (MVT) Chaitanya Potti, Partha
BhattacharyaStandard Draft 1
eip-1271 ERC Standard Signature Validation Method for Contracts Francisco Giordano, MattCondon, Philippe Castonguay,Amir Bandeali, Jorge Izquierdo,Bertrand Masius
Standard Draft
2
eip-1319 ERC Smart Contract Package Registry Interface Piper Merriam, ChristopherGewecke, g. nicholas d'andrea
Standard Draft 1
eip-1328 ERC WalletConnect Standard URI Format ligi, Pedro Gomes Standard Draft 1eip-1386 ERC Attestation management contract Weiwu Zhang, James Sangalli Standard Draft 1eip-1387 ERC Merkle Tree Attestations with Privacy enabled Weiwu Zhang, James Sangalli Standard Draft 1eip-1388 ERC Attestation Issuers Management List Weiwu Zhang, James Sangalli Standard Draft 1eip-1417 ERC Poll Standard Chaitanya Potti, Partha
BhattacharyaStandard Draft 2
eip-1438 ERC dApp Components (avatar) & Universal Wallet Jet Lim Standard Draft 1eip-1444 ERC Localized Messaging with Signal-to-Text Brooklyn Zelenka, Jennifer
CooperStandard Draft 1
eip-1450 ERC ERC-1450 John Shiple, Howard Marks,David Zhang
Standard Draft 2
eip-1462 ERC Base Security Token Maxim Kupriianov, Julian Svirsky Standard Draft 1eip-1484 ERC Digital Identity Aggregator Anurag Angara, Andy Chorlian,
Shane Hampton, NoahZinsmeister
Standard Draft1
eip-1577 ERC contenthash field for ENS Dean Eigenmann, Nick Johnson Standard Draft 2eip-1581 ERC Non-wallet usage of keys derived from BIP-32 trees Michele Balistreri Standard Draft 1eip-1592 ERC Address and ERC20-compliant transfer rules Cyril Lapinte, Laurent Aapro Standard Draft 1eip-1613 ERC Gas stations network Yoav Weiss, Dror Tirosh Standard Draft 2eip-1616 ERC ERC-1616 Attribute Registry Standard 0age, Santiago Palladino, Leo
Arias, Alejo Salles, StephaneGosselin
Standard Draft1
- 88 -
資料編
第7部
第6部 第5部
第3部
第2部
第1部
本編
要約
目次
第4部
表 5-5 BIP、EIP における提案件数の著者上位ランキング
順位 著者名 提案件数 種類
1 Vitalik Buterin 18 eip
2 Nick Johnson 13 eip
3 Gavin Andresen 11 bip
4 Luke Dashjr 10 bip
5 Pieter Wuille 9 bip
6 BtcDrak 7 bip
7 Christian Reitwiessner 6 eip
7 Johnson Lau 6 bip
7 Mark Friedenbach 6 bip
10 Alex Beregszaszi 5 eip
- 89 -
資料編
第7部
第6部
第5部
第3部
第2部
第1部
本編
要約
目次
第4部
第 6 章 総合分析と提言
第 1 節 総合分析
1. 仮想通貨・電子マネーによる決済システムに関する技術全体の動向に関する分析
(1) 国内外全体の出願傾向
日本におけるキャッシュレス決済比率(家計 終消費支出のうち、カード決済(電子
マネー除く)+E-money 決済の割合)は、海外諸国と比較して非常に低い水準に留まっ
ており、2007 年から 2016 年の変化で見ても、進展が遅れている状況にある(図 6-1)。
図 6-1 諸外国におけるキャッシュレス決済比率の変化とキャッシュレス化進展の施策例(再
掲)
出典 経済産業省「キャッシュレス化推進に向けた国内外の現状認識」(2017/8)
経済産業省(2018)「我が国における FinTech 普及に向けた環境整備に関する調査検
討」によると、日本の現金決済による直接コストは、レジ締め等の現金関連業務人件費、
ATM 機器設置費など、年間 1.6 兆円を超える。
一方、キャッシュレス化の推進による潜在的経済効果は、資産運用の活性化による家
計所得の向上、電子決済関連市場の成長、訪日外国人による消費支出増などで、約 6 兆
円になると試算されている。
日本政府はこのような社会負担を軽減し、キャッシュレス化推進による潜在的経済効
果を上げるため、2020 年の東京オリンピックや 2025 年の大阪万博等のイベントを契機
としたキャッシュレス化政策を推進している。
このキャッシュレス化を支える技術の蓄積状況を、仮想通貨・電子マネーによる決済
システムに関する特許出願ファミリー件数推移で見ると、全体として増加傾向にある
- 90 -
資料編
第7部
第6部 第5部
第3部
第2部
第1部
本編
要約
目次
第4部
(図 6-2)。その中で、日本国籍のファミリー件数は低い水準で推移している。また、
2014 年までは米国籍によるファミリー件数が も多かったが、2015 年以降、中国籍に
よるファミリー件数が米国籍を上回って も多くなっており、急速な伸長が見られる。
韓国籍にも米国籍、中国籍に次ぐ存在感が見られる。
図 6-2 出願人国籍別ファミリー件数推移及びファミリー件数比率(日米欧中韓への出願、出願
年(優先権主張年):2010-2016 年)(再掲)
出願先国別も同様に、全体として増加傾向にあり、2014 年までは米国への出願件数が
も多かったが、2015 年以降、中国への出願件数が米国への出願件数を上回って も多
くなっている。日本への出願件数は低い水準で推移している(図 6-3)。
図 6-3 出願先国別出願件数推移及び出願件数比率(日米欧中韓への出願、出願年(優先権主張
年):2010-2016 年)(再掲)
日本国籍
1,151件
6.4%
米国籍
5,298件
29.5%
欧州国籍
1,319件
7.4%
中国籍
5,973件
33.3%
韓国籍
3,426件
19.1%
その他
763件
4.3%
合計
17,930件
1,386
1,902
2,273 2,297
2,694
3,126
4,252
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
4,500
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
合計
出願件数
出願年(優先権主張年)
日本国籍 米国籍 欧州国籍 中国籍 韓国籍 その他国籍 合計
出願人国籍(地域)
優先権主張
2010-2016年
注)2015 年以降はデータベース収録の遅れ、PCT 出願の各国移行のずれ等で、
全データを反映していない可能性がある。
日本
1,960件
6.6%
米国
11,813件
40.0%
欧州
3,681件
12.5%
中国
7,952件
26.9%
韓国
4,115件
13.9%
合計
29,521件
3,012
3,858
4,505 4,229 4,499 4,533
4,885
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
4,500
5,000
5,500
0
250
500
750
1,000
1,250
1,500
1,750
2,000
2,250
2,500
2,750
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
合計
出願件数
出願年(優先権主張年)
日本 米国 欧州 中国 韓国 合計
出願先国(地域)
優先権主張
2010-2016年
注)2015 年以降はデータベース収録の遅れ、PCT 出願の各国移行のずれ等で、
全データを反映していない可能性がある。
- 91 -
資料編
第7部
第6部
第5部
第3部
第2部
第1部
本編
要約
目次
第4部
(2) 日本への出願全体の傾向
キャッシュレス化推進は国内の政策課題となっており、まずは、日本への出願の全体
傾向を見る。
仮想通貨・電子マネーによる決済システムに関する日本への出願の傾向を、日本国籍
による出願と外国籍による出願に分けて見ると、図 6-4 のようになっている。
データベース収録の遅れ、PCT 出願の各国以降のずれ等の影響を受けない 2010 年~
2014 年で見ると、外国籍による出願が横ばいであるのに対し、日本国籍による自国への
出願は増加している。
図 6-4 出願人国籍別(日本国籍と外国籍)日本への出願件数推移(出願年(優先権主張年):
2010-2016 年)
注)2015 年以降はデータベース収録の遅れ、PCT 出願の各国以降のずれ等で、
全データを反映していない可能性がある。
020406080
100120140160180200220240
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
出願
件数
出願年(優先権主張年)
出願人国籍(地域)
日本 日本以外計
- 92 -
資料編
第7部
第6部 第5部
第3部
第2部
第1部
本編
要約
目次
第4部
外国籍による出願を出願人国籍別に分解すると、図 6-5 のようになる。
2010 年~2014 年で見ると、米国籍による出願が相対的に大きく減少し、中国籍、韓
国籍による出願が増加している。
図 6-5 出願人国籍別(日本国籍以外)日本への出願件数推移(出願年(優先権主張年):2010-
2016 年)
注)2015 年以降はデータベース収録の遅れ、PCT 出願の各国以降のずれ等で、
全データを反映していない可能性がある。
日本国内への出願に関しては、中国籍、韓国籍の動向に留意しつつ、日本国籍による
出願の強化を図ることが課題となると考えられる。
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
出願
件数
出願年(優先権主張年)
出願人国籍(地域)
米国 欧州 中国 韓国 その他
- 93 -
資料編
第7部
第6部
第5部
第3部
第2部
第1部
本編
要約
目次
第4部
(3) 国際出願の全体傾向
仮想通貨・電子マネーによる決済システムに関する国際出願の傾向を PCT 出願件数比
率で見ると、米国籍の件数の多さが突出している(図 6-6)。
国内外全体の出願傾向では中国籍の伸長が著しかったが、国際出願では依然として米
国籍が突出している状況であり、国内向け出願と国際出願では技術の質の違いがあると
想定される。国際出願されている技術の特徴に着目する必要がある。
図 6-6 出願人国籍別 PCT 出願件数推移及び出願件数比率(出願年(優先権主張年):2010-2016
年
日本国籍
244件
4.7%
米国籍
2,556件
49.0%
欧州国籍
805件
15.4%
中国籍
580件
11.1%
韓国籍
500件
9.6%
その他
530件10.2%
合計
5,215件
515
700 754 755
819 775
897
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1,000
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
合計
出願件数
出願年(優先権主張年)
日本 米国 欧州 中国 韓国 その他 合計
出願人国籍(地域)
優先権主張
2010-2016年
- 94 -
資料編
第7部
第6部 第5部
第3部
第2部
第1部
本編
要約
目次
第4部
出願人国籍別出願件数収支で見ると、米国と欧州の間での国際出願件数の多さが目立
つ(図 6-7)。米国は、いずれの国籍からも も多くの国際出願がなされており、かつ、
いずれの出願先国へも も多くの国際出願をしている国となっている。
図 6-7 出願先国別‐出願人国籍別出願件数収支(日米欧中韓への出願、出願年(優先権主張
年):2010-2016 年)
日本国籍
394件
3.3%
米国籍
8,670件
73.4%
欧州国籍
1,008件
8.5%
中国籍
330件
2.8%
韓国籍
495件
4.2%
その他
916件
7.8%
米国への出願
11,813件
日本国籍
137件
3.7%
米国籍
1,277件
34.7%欧州国籍
1,636件
44.4%
中国籍
149件
4.0%
韓国籍
198件
5.4%
その他
284件
7.7%
欧州への出願
3,681件
日本国籍
197件
2.5%米国籍
687件
8.6%
欧州国籍
317件
4.0%
中国籍
6,196件
77.9%
韓国籍
258件
3.2%
その他
297件
3.7%
中国への出願
7,952件
日本国籍
41件
1.0%
米国籍
292件
7.1% 欧州国籍
71件
1.7%
中国籍
64件
1.6%
韓国籍
3,596件
87.4%
その他
51件
1.2%
韓国への出願
4,115件
日本国籍
1,254件
64.0%米国籍
347件
17.7%
欧州国籍
89件
4.5%
中国籍
87件
4.4%
韓国籍
93件
4.7%
その他
90件
4.6%
日本への出願
1,960件
394件 137件
197件
347件
89件
87件
93件
1,277件
687件
292件
1,008件
330件
495件
317件
71件
149件
198件
64件
258件
41件
- 95 -
資料編
第7部
第6部
第5部
第3部
第2部
第1部
本編
要約
目次
第4部
国際出願の件数推移を見ると、図 6-8 のようになっている。ここでは、日本国籍によ
る日本以外への出願、米国籍による米国以外への出願、欧州国籍による欧州域外への出
願(欧州域内の A 国から B 国への出願は含まない)、中国籍への中国以外への出願、韓
国籍による韓国以外への出願を国際出願とした。
データベース収録の遅れ、PCT 出願の各国以降のずれ等の影響を受けない 2010 年~
2014 年で見ると、国際出願は全体として増加傾向にある。
図 6-8 国際出願件数推移(日米欧中韓への出願、出願年(優先権主張年):2010-2016 年)
注)2015 年以降はデータベース収録の遅れ、PCT 出願の各国以降のずれ等で、
全データを反映していない可能性がある。
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1,000
1,100
1,200
1,300
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
出願
件数
出願年(優先権主張年)
- 96 -
資料編
第7部
第6部 第5部
第3部
第2部
第1部
本編
要約
目次
第4部
国際出願を出願人国籍別に分解すると、図 6-9 のようになる。
2010 年~2014 年で見ると、米国籍、中国籍、韓国籍、日本国籍による国際出願はそ
れぞれ増加傾向にある。
図 6-9 出願人国籍別国際出願件数推移(日米欧中韓への出願、出願年(優先権主張年):2010-
2016 年)
注)2015 年以降はデータベース収録の遅れ、PCT 出願の各国以降のずれ等で、
全データを反映していない可能性がある。
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
550
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
出願
件数
出願年(優先権主張年)
出願人国籍(地域)
日本 米国 欧州 中国 韓国
- 97 -
資料編
第7部
第6部
第5部
第3部
第2部
第1部
本編
要約
目次
第4部
さらに出願人国籍別に、出願先国別の件数推移を見ていく。
日本国籍による出願先国別の国際出願の件数推移を見ると、図 6-10 のようになる(日
本国籍による日本への出願件数推移は、図 6-4 のとおり。)。
2010 年~2014 年で見ると、米国への出願が大きく伸長し、中国、欧州への出願も増
加している。韓国への出願は横ばいである。
図 6-10 出願先国別(日本以外)日本国籍による出願件数推移(米欧中韓への出願、出願年
(優先権主張年):2010-2016 年)
注)2015 年以降はデータベース収録の遅れ、PCT 出願の各国以降のずれ等で、
全データを反映していない可能性がある。
米国籍による出願先国別の出願件数推移を見ると、図 6-11 のようになっている。
2010 年~2014 年で見ると、米国内への出願が全体的に横ばいなのに対し、欧州と中
国への出願が増加、日本、韓国への出願はむしろ減少している。
図 6-11 出願先国別米国籍による出願件数推移(日米欧中韓への出願、出願年(優先権主張
年):2010-2016 年)(左:米国内への出願、右:国際出願)
注)2015 年以降はデータベース収録の遅れ、PCT 出願の各国以降のずれ等で、
全データを反映していない可能性がある。
0
20
40
60
80
100
120
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
出願
件数
出願年(優先権主張年)
出願先国(地域)
米国 欧州 中国 韓国
0
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
1,600
1,800
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
出願
件数
出願年(優先権主張年)
020406080
100120140160180200220240260
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
出願
件数
出願年(優先権主張年)
出願先国(地域)
日本 欧州 中国 韓国
- 98 -
資料編
第7部
第6部 第5部
第3部
第2部
第1部
本編
要約
目次
第4部
欧州国籍による出願先国別の出願件数推移を見ると、図 6-12 のようになっている。
2010 年~2014 年で見ると、欧州域内への出願が少し増加傾向にあり、国際出願では、
米国と中国への出願が少し増加、日本、韓国への出願は減少傾向にある。
図 6-12 出願先国別欧州国籍による出願件数推移(日米欧中韓への出願、出願年(優先権主張
年):2010-2016 年)(左:欧州域内への出願、右:国際出願)
注)2015 年以降はデータベース収録の遅れ、PCT 出願の各国以降のずれ等で、
全データを反映していない可能性がある。
中国籍による出願先国別の出願件数推移を見ると、図 6-13 のようになっている。
2010 年~2014 年で見ると、中国内への出願が大きく増加し、国際出願も、米国への
出願が大きく増加、欧州、日本、韓国への出願もいずれも増加させている。
図 6-13 出願先国別中国籍による出願件数推移(日米欧中韓への出願、出願年(優先権主張
年):2010-2016 年)(左:中国内への出願、右:国際出願)
注)2015 年以降はデータベース収録の遅れ、PCT 出願の各国以降のずれ等で、
全データを反映していない可能性がある。
0255075
100125150175200225250275300325
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
出願
件数
出願年(優先権主張年)
0
25
50
75
100
125
150
175
200
225
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
出願
件数
出願年(優先権主張年)
出願先国(地域)
日本 米国 中国 韓国
0
250
500
750
1,000
1,250
1,500
1,750
2,000
2,250
2,500
2,750
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
出願
件数
出願年(優先権主張年)
0
10
2030
40
5060
70
8090
100
110
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
出願
件数
出願年(優先権主張年)
出願先国(地域)
日本 米国 欧州 韓国
- 99 -
資料編
第7部
第6部
第5部
第3部
第2部
第1部
本編
要約
目次
第4部
韓国籍による出願先国別の出願件数推移を見ると、図 6-14 のようになっている。
2010 年~2014 年で見ると、韓国内への出願が横ばいまたは増加傾向にあり、国際出
願も、米国への出願が大きく増加、中国、欧州、日本への出願もいずれも増加させてい
る。
図 6-14 出願先国別韓国籍による出願件数推移(日米欧中韓への出願、出願年(優先権主張
年):2010-2016 年)(左:韓国内への出願、右:国際出願)
注)2015 年以降はデータベース収録の遅れ、PCT 出願の各国以降のずれ等で、
全データを反映していない可能性がある。
以上から、国際出願に圧倒的な強みのある米国籍の出願技術の特徴、国際出願を大き
く増加させている中国籍、韓国籍の国際出願の技術の特徴に着目する必要があると考え
られる。
0
100
200
300
400
500
600
700
800
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
出願
件数
出願年(優先権主張年)
0102030405060708090
100110120130
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
出願
件数
出願年(優先権主張年)
出願先国(地域)
日本 米国 欧州 中国
- 100 -
資料編
第7部
第6部 第5部
第3部
第2部
第1部
本編
要約
目次
第4部
2. 仮想通貨・電子マネーによる決済システムに関する技術区分別の動向に関する分析
(1) 仮想通貨・電子マネーによる決済システムの利用場面
本調査では、仮想通貨・電子マネーによる決済システムの用途として想定される代表
的な利用場面を技術区分として設定し、仮想通貨・電子マネーによる決済システムに関
する特許文献を分類した。
利用場面を大きく「商取引」と「金融取引」に分け、「商取引」を「オンサイト商取引」
と「オンライン商取引」に、「金融取引」を「送金」と「投融資」に分けている。「商取
引」に関するファミリー件数推移を図 6-15 に、「金融取引」に関するファミリー件数推
移を図 6-16 に示す。
「商取引」のうち、「オンサイト商取引」は 2010 年から 2016 年にかけて継続的に増
加しているのに対し、「オンライン商取引」は 2014 年までほぼ横ばいで、2015 年以降に
増加している。「オンサイト商取引」では、「実店舗」の他、「自動販売機」、「鉄道」、「道
路」、「バス・タクシー」、「レンタカー」、「駐車場」などの「交通」、「病院」などの「施
設サービス」などの出願が見られる。「オンライン商取引」では、「仮想店舗」の他、「通
信」、「公共料金」、「税」、「デジタルコンテンツ」、「オークション」などの出願が見られ
る。
「金融取引」のうち、「送金」は 2010 年から 2016 年にかけて、増減しつつも大きな
傾向としては継続的に増加しているのに対し、「投融資」は 2014 年までほぼ横ばいで、
2015 年以降に増加している。「送金」では、「海外送金」、「寄付」、「個人送金」などの出
願が見られる。それらに比べ、給与支払などの「一斉送金」に関する出願は少ないのが
現状である。「投融資」では、「クラウドファンディング」、「証券取引」、「リース」、「保
険・資産形成」などの出願が見られる。
- 101 -
資料編
第7部
第6部
第5部
第3部
第2部
第1部
本編
要約
目次
第4部
図 6-15 技術区分「利用場面(商取引)」‐ファミリー件数推移(日米欧中韓への出願、出願年
(優先権主張年):2010-2016 年)(再掲)
オンサイト商取引 530 697 877 797 943 1,240 1,888
実店舗282 337
475 474 515 608 821
自動販売機24 33 40 37 38 75 96
交通84 95 130 112 139 214
470
鉄道13 18 18 16 17 29 65
道路15 15 22 15 24 31 53
バス・タクシー15 17 39 26 43 57 115
レンタカー8 11 10 7 4 14 65
駐車場20 37 33 40 42 74 177
施設サービス61 77 87 63 101 167 250
病院14 19 15 6 11 29 38
その他49 56 71 56 89 137 210
その他39 50 64 61 63 126 163
商品19 20 31 20 29 48 53
サービス30 34 47 47 52 104 133
オンライン商取引322
427 474 454 464 665 709
仮想店舗137 189 226 212 215 311 321
通信8 11 7 9 8 2 5
公共料金7 13 12 24 27 47 90
税10 7 9 13 7 11 22
デジタルコンテンツ45 74 73 62 54 48 67
オークション11 9 9 17 8 13 4
その他73 109 97 64 74 91 119
利用場面「商取引」
中分類・小分類
出願年(優先権主張年)
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
注)2015 年以降はデータベース収録の遅れ、PCT 出願の各国移行のずれ等で、
全データを反映していない可能性がある。
- 102 -
資料編
第7部
第6部 第5部
第3部
第2部
第1部
本編
要約
目次
第4部
図 6-16 技術区分「利用場面(金融取引)」‐ファミリー件数推移(日米欧中韓への出願、出願
年(優先権主張年):2010-2016 年)(再掲)
送金 76 79 104 62 96 147 186
海外送金4 4 5 3 8 17 13
一斉送金1 1
寄付14 14 37 15 15 32 17
個人送金9 11 15 21 36 48
65
その他10 9 12 10 14 22 24
投融資32 43 47 44 41
58 87
クラウドファンディング 1 1 6 4 5 7 11
証券取引2 9 10 12 8 9 17
リース 3 3 3 4 3 12
保険・資産形成 7 15 6 9 4 9 22
その他11 7 13 8 3 12 9
利用場面「金融取引」
中分類・小分類
出願年(優先権主張年)
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
注)2015 年以降はデータベース収録の遅れ、PCT 出願の各国移行のずれ等で、
全データを反映していない可能性がある。
- 103 -
資料編
第7部
第6部
第5部
第3部
第2部
第1部
本編
要約
目次
第4部
(2) 日本国内への出願に関する技術区分別動向分析
技術全体の動向分析から、仮想通貨・電子マネーによる決済システムに関する日本へ
の出願は、外国籍による出願が横ばいであるのに対し、日本国籍による自国への出願が
増加していた。外国籍による出願を出願人国籍別に分解すると、米国籍による出願が相
対的に大きく減少し、中国籍、韓国籍による出願が増加していた。
日本国内への出願の検討にあたっては、日本国籍の自国への出願と、中国籍や韓国籍
の国際出願の技術動向に留意すべきと考えられる。
そこで、日本への出願のうち日本国籍によるものの比率をヨコ軸に、中国籍による出
願のうち中国以外への出願や韓国籍による出願のうち韓国以外への出願の比率(以下そ
れぞれ「中国籍の国際出願比率」、「韓国籍の国際出願比率」と言う。)をタテ軸にとり、
技術区分をプロットした。中国籍の国際出願をタテ軸にとり要素技術に関する技術区分
をプロットしたのが図 6-17、課題に関する技術区分をプロットしたのが図 6-18、韓国
籍の国際出願をタテ軸にとり要素技術に関する技術区分をプロットしたのが図 6-19、
課題に関する技術区分をプロットしたのが図 6-20 である。
日本への出願のうち日本国籍によるものの比率が大きい技術区分(図の右側の領域)
は、日本への出願においては日本国籍による出願でカバーされている技術分野、図の左
側の領域は、日本への出願において外国籍の進出を許している技術分野と考えることが
できる。中国籍や韓国籍の国際出願比率が高い技術区分(図の上側の領域)は、中国籍
や韓国籍による出願の中でも質の高い出願がされている技術分野と考えることができ
る。図の下側の領域はそれぞれの自国内出願が多い分野である。
なお、全技術区分での日本への出願のうち日本国籍によるものの比率は 0.64、中国
籍、韓国籍の国際出願比率はそれぞれ、0.09、0.23 である。
要素技術の「ウェブウォレット」、「生体認証」、「取引履歴による認証」、「第三者によ
る認証・仲介」などは、日本への出願においても日本国籍による出願が少なく、中国籍
や韓国籍の進出を許している分野となっている。
要素技術の「QR コード」や「バーコード」、「携帯端末」、「ウェアラブル端末」、「決済
処理」、「暗号技術」、課題の「マーケティング活用」などは、中国籍は目立たないが、日
本への出願においても日本国籍による出願が少なく、韓国籍の進出が目立つ分野となっ
ている。
一方、要素技術の「取引対象の管理」、「チャージ」、課題の「端末導入コストの低減」、
「ネットワーク・センターシステムの低コスト化」、「多様な決済手段への対応」、「取引
履歴の管理」、「プライバシー保護」などは、少なくとも日本への出願においては、日本
国籍に強みがあり、中国籍や韓国籍の進出を許していない分野となっている。
なお、日本国籍の出願件数が国内外全体で 20 件に満たない要素技術の「多段階認証」、
課題の「未処理トランザクションの防止」、「有効性確認」、「不正金融取引防止」、中国
籍の出願件数が国内外全体で 20 件に満たない要素技術の「オーソリ」、韓国籍の出願件
数が国内外全体で 20 件に満たない課題の「未処理トランザクションの防止」、「与信業
務の効率化」、「スケーラビリティ」、「有効性確認」、「不正金融取引防止」はプロットか
ら除外している。
- 104 -
資料編
第7部
第6部 第5部
第3部
第2部
第1部
本編
要約
目次
第4部
図 6-17 技術区分「要素技術」 - 日本への出願のうち日本国籍によるものの比率×中国籍の国
際出願比率(日米欧韓への出願)(出願年(優先権主張年):2010 年-2016 年)
図 6-18 技術区分「課題」 - 日本への出願のうち日本国籍によるものの比率×中国籍の国際出
願比率(日米欧韓への出願)(出願年(優先権主張年):2010 年-2016 年)
磁気カード接触型ICカード
非接触型ICカード
携帯端末
ウェアラブル端末
バーコード
QRコード
ウェブウォレット
リーダー
/ライター
ネットワーク
センター
暗号技術
ワンタイムパスワード
生体認証
取引履歴による認証
第三者による認証・仲介
取引対象の管理
決済処理
記録
不正検出
チャージ
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1
中国
籍の
国際
出願
比率
日本への出願のうち日本国籍によるものの比率
盗難防止
改ざん防止 間違い防止
滅失防止
プライバシー保護円滑な決済
多様な決
済手段へ
の対応
決済以外の
機能との統合
入力の自動化
端末導入コ
ストの低減
ネットワーク・センター
システムの低コスト化
与信業務の効率化
マーケティング活用
スケーラビリティ
取引履歴の管理
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1
中国
籍の
国際
出願
比率
日本への出願のうち日本国籍によるものの比率
- 105 -
資料編
第7部
第6部
第5部
第3部
第2部
第1部
本編
要約
目次
第4部
図 6-19 技術区分「要素技術」 - 日本への出願のうち日本国籍によるものの比率×韓国籍の国
際出願比率(日米欧中への出願)(出願年(優先権主張年):2010 年-2016 年)
図 6-20 技術区分「課題」 - 日本への出願のうち日本国籍によるものの比率×韓国籍の国際出
願比率(日米欧中への出願)(出願年(優先権主張年):2010 年-2016 年)
磁気カード
接触型ICカード
非接触型ICカード
携帯端末
ウェアラブル端末
バーコード
QRコード
ウェブウォレット
リーダー
/ライター
ネットワーク
センター
暗号技術
ワンタイムパスワード
生体認証
取引履歴による認証
第三者による認証・仲介
オーソリ
取引対象の管理
決済処理
記録
不正検出
チャージ
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1
韓国
籍の
国際
出願
比率
日本への出願のうち日本国籍によるものの比率
盗難防止
改ざん防止
間違い防止
滅失防止
プライバシー保護
円滑な決済
多様な決
済手段へ
の対応
決済以外の
機能との統合
入力の自動化
端末導入コ
ストの低減ネットワーク・センター
システムの低コスト化
マーケティング活用
取引履歴の管理
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1
韓国
籍の
国際
出願
比率
日本への出願のうち日本国籍によるものの比率
- 106 -
資料編
第7部
第6部 第5部
第3部
第2部
第1部
本編
要約
目次
第4部
(3) 国際出願に関する技術区分別動向分析
技術全体の動向分析から、仮想通貨・電子マネーによる決済システムに関する国際出
願は、全体として増加傾向にあり、国際出願を出願人国籍別に分解すると、米国籍の国
際出願が圧倒的であり、中国籍、韓国籍による国際出願はそれぞれ大きな増加傾向にあ
った。
日本国籍による国内外への出願は、外国籍に比べて全体として低水準となっているの
が現状であるが、日本国内への出願、国際出願ともに増加させてきている。その中で、
日本国籍による出願が増加している技術分野は、日本国籍が注力している技術分野と考
えることができる。
そこで、日本国籍の日米欧中韓への出願のデータベース収録の遅れ、PCT 出願の各国
以降のずれ等の影響を受けない 2010 年~2014 年の間の年平均成長率(以下「日本国籍
出願増加率」と言う。)をタテ軸に、日米欧中韓への出願全体に占める米国籍の出願の
割合(以下「米国籍の出願比率」と呼ぶ。)や中国籍の国際出願比率、韓国籍の国際出願
比率をヨコ軸にとり、技術区分をプロットした。米国籍の出願比率をヨコ軸にとり要素
技術に関する技術区分をプロットしたのが図 6-21、課題に関する技術区分をプロット
したのが図 6-22、中国籍の国際出願比率をヨコ軸にとり要素技術に関する技術区分を
プロットしたのが図 6-23、課題に関する技術区分をプロットしたのが図 6-24、韓国籍
の国際出願比率をヨコ軸にとり要素技術に関する技術区分をプロットしたのが図 6-25、
課題に関する技術区分をプロットしたのが図 6-26 である。中国籍や韓国籍は自国向け
出願の増加も目覚ましいが、中でも国際出願されているものは質も高いと考えられ、中
国籍や韓国籍については特にそれぞれの国際出願比率を指標として採用した。一方、米
国籍については、米国籍による米国への出願技術も競争対象として想定し、日米欧中韓
への出願全体に占める米国籍の出願の割合を、米国籍の出願技術の強みを見る指標とし
て採用した。
米国籍の出願比率が低い技術区分、中国籍や韓国籍の国際出願比率が低い技術区分
(図の左側の領域)は、今後日本国籍の国際出願を増やすことによって大きな存在感を
持たせられる可能性が比較的高い分野と考えられる。日本国籍出願増加率が高い技術区
分(図の上側の領域)は、日本国籍が注力している分野、図の下側の領域は、これまで
のところ日本国籍の注力が少ない分野と考えることができる。
なお、全技術区分での日本国籍出願増加率は 0.08、米国籍の出願比率は 0.30、中国
籍、韓国籍の国際出願比率はそれぞれ、0.09、0.23 である。
要素技術の「取引対象の管理」、課題の「端末導入コストの低減」は日本国籍が注力し
ており、かつ、今後国際出願における日本国籍の大きな存在感を持たせられる可能性が
比較的高い分野となっている。
要素技術の「生体認証」、「QR コード」は、日本国籍が注力しているが、今後国際出願
における日本国籍の大きな存在感を持たせるために、韓国籍の動向に留意する必要があ
る技術分野と考えられる。
一方、課題の「円滑な決済」、「携帯端末」は、これまでのところ日本国籍の注力が少
ないが、今後注力していくことにより、韓国籍の動向に留意しつつ、国際出願における
日本国籍の割合を増やせる可能性もある技術分野と言える。
なお、日本国籍の各年の出願件数が 10 件に満たない要素技術の「ウェアラブル端末」、
- 107 -
資料編
第7部
第6部
第5部
第3部
第2部
第1部
本編
要約
目次
第4部
「ウェブウォレット」、「ワンタイムパスワード」、「第三者による認証・仲介」、「多段階
認証」、「オーソリ」、「不正検出」、課題の「改ざん防止」、「間違い防止」、「未処理トラン
ザクションの防止」、「滅失防止」、「プライバシー保護」、「多様な決済手段への対応」、
「決済以外の機能との統合」、「入力の自動化」、「ネットワーク・センターシステムの低
コスト化」、「与信業務の効率化」、「スケーラビリティ」、「有効性確認」、「取引履歴の管
理」、「不正金融取引防止」はプロットから除外している。
- 108 -
資料編
第7部
第6部 第5部
第3部
第2部
第1部
本編
要約
目次
第4部
図 6-21 技術区分「要素技術」 - 米国籍の出願比率×日本国籍の出願増加率(日米欧中韓への
出願)(出願年(優先権主張年):2010 年-2014 年)
図 6-22 技術区分「課題」- 米国籍の出願比率×日本国籍の出願増加率(日米欧中韓への出
願)(出願年(優先権主張年):2010 年-2014 年)
磁気カード
接触型ICカード
非接触型ICカード
携帯端末バーコード
QRコード
リーダー/ライターネットワークセンター
暗号技術
生体認証
取引履歴による認証
取引対象の管理
決済処理記録
チャージ
‐0.2
‐0.1
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8
日本
国籍
出願
増加
率
米国籍の出願比率
盗難防止
円滑な決済
端末導入コ
ストの低減
マーケティング活用
‐0.2
‐0.1
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8
日本
国籍
出願
増加
率
米国籍の出願比率
- 109 -
資料編
第7部
第6部
第5部
第3部
第2部
第1部
本編
要約
目次
第4部
図 6-23 技術区分「要素技術」 - 中国籍の国際出願比率×日本国籍の出願増加率(日米欧中韓
への出願)(出願年(優先権主張年):2010 年-2014 年)
図 6-24 技術区分「課題」- 中国籍の国際出願比率×日本国籍の出願増加率(日米欧中韓への
出願)(出願年(優先権主張年):2010 年-2014 年)
磁気カード
接触型ICカード
非接触型ICカード
携帯端末
バーコード
QRコード
リーダー/ライターネットワーク
センター
暗号技術生体認証
取引履歴による認証
取引対象の管理
決済処理 記録
チャージ
‐0.2
‐0.1
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3
日本
国籍
出願
増加
率
中国籍の国際出願比率
盗難防止
円滑な決済
端末導入コ
ストの低減
マーケティング活用
‐0.2
‐0.1
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3
日本
国籍
出願
増加
率
中国籍の国際出願比率
- 110 -
資料編
第7部
第6部 第5部
第3部
第2部
第1部
本編
要約
目次
第4部
図 6-25 技術区分「要素技術」 - 韓国籍の国際出願比率×日本国籍の出願増加率(日米欧中韓
への出願)(出願年(優先権主張年):2010 年-2014 年)
図 6-26 技術区分「課題」- 韓国籍の国際出願比率×日本国籍の出願増加率(日米欧中韓への
出願)(出願年(優先権主張年):2010 年-2014 年)
磁気カード
接触型ICカード
非接触型ICカード
携帯端末
バーコード
QRコード
リーダー/ライター
ネットワーク センター
暗号技術
生体認証
取引履歴による認証
取引対象の管理
決済処理記録
チャージ
‐0.2
‐0.1
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7
日本
国籍
出願
増加
率
韓国籍の国際出願比率
盗難防止
円滑な決済
端末導入コ
ストの低減
マーケティング活用
‐0.2
‐0.1
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7
日本
国籍
出願
増加
率
韓国籍の国際出願比率
- 111 -
資料編
第7部
第6部
第5部
第3部
第2部
第1部
本編
要約
目次
第4部
(4) 今後の仮想通貨・電子マネーによる決済システムを支える基盤技術に関する分析
① 決済システムの安全性を確保するための基盤技術
決済システムの安全性を確保するための技術のうち、現時点で出願件数は多くない
が、ここ数年で出願が急激に増加している技術として、「生体認証」の細目の各種技術、
「暗号技術」の細目である「ハッシュ関数」がある。
決済システムに活用される生体認証に関する特許出願としては、総出願件数が多い
ものから順に、「指紋認証」、「顔認証」、「音声認証」、「虹彩認証」、「動作認証」、「静脈
認証」によるものが見られた(図 6-27~図 6-32)。
いずれも伸び足の速い増加傾向にあり、中国籍が全般的に優位である。「音声認証」、
「動作認証」については米国籍と中国籍が拮抗している。日本国籍は存在感を発揮し
ていないのが現状であるが、これらの中でも相対的に未熟な開発・適用段階にあると
考えられる「音声認証」、「虹彩認証」、「動作認証」、「静脈認証」については、今後、技
術開発を進めることで日本国籍が優位に立つことも可能と考えられる。
図 6-27 技術区分「指紋認証」 - 出願人国籍別ファミリー件数推移及びファミリー件数比率
(日米欧中韓への出願、出願年(優先権主張年):2010 年-2016 年)
日本国籍
10件
1.4%
米国籍
137件
19.0%
欧州国籍
52件
7.2%
中国籍
402件
55.8%
韓国籍
86件
11.9%
その他
33件
4.6%
合計
720件
27 42
59 64
115
165
248
0
50
100
150
200
250
300
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
合計
出願件数
出願年(優先権主張年)
日本 米国 欧州 中国 韓国 その他 合計
出願人国籍(地域)
優先権主張
2010-2016年
注)2015 年以降はデータベース収録の遅れ、PCT 出願の各国移行のずれ等で、
全データを反映していない可能性がある。
- 112 -
資料編
第7部
第6部 第5部
第3部
第2部
第1部
本編
要約
目次
第4部
図 6-28 技術区分「顔認証」 - 出願人国籍別ファミリー件数推移及びファミリー件数比率(日
米欧中韓への出願、出願年(優先権主張年):2010 年-2016 年)
図 6-29 技術区分「音声認証」 - 出願人国籍別ファミリー件数推移及びファミリー件数比率
(日米欧中韓への出願、出願年(優先権主張年):2010 年-2016 年)
図 6-30 技術区分「虹彩認証」 - 出願人国籍別ファミリー件数推移及びファミリー件数比率
(日米欧中韓への出願、出願年(優先権主張年):2010 年-2016 年)
日本国籍
12件
3.6%
米国籍
95件
28.9%
欧州国籍
21件
6.4%
中国籍
163件
49.5%
韓国籍
24件
7.3%
その他
14件
4.3%
合計
329件
9
24 30 31
51
62
122
0
20
40
60
80
100
120
140
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
合計
出願件数
出願年(優先権主張年)
日本 米国 欧州 中国 韓国 その他 合計
出願人国籍(地域)
優先権主張
2010-2016年
注)2015 年以降はデータベース収録の遅れ、PCT 出願の各国移行のずれ等で、
全データを反映していない可能性がある。
日本国籍
2件
0.7%
米国籍
102件
36.3%
欧州国籍
31件
11.0%
中国籍
106件
37.7%
韓国籍
21件
7.5%
その他
19件
6.8%
合計
281件
19
29 31
39
47
59 57
0
10
20
30
40
50
60
70
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
合計
出願件数
出願年(優先権主張年)
日本 米国 欧州 中国 韓国 その他 合計
出願人国籍(地域)
優先権主張
2010-2016年
注)2015 年以降はデータベース収録の遅れ、PCT 出願の各国移行のずれ等で、
全データを反映していない可能性がある。
日本国籍
2件
1.1%
米国籍
48件
25.4%
欧州国籍
13件
6.9%
中国籍
86件
45.5%
韓国籍
28件
14.8%
その他
12件
6.3%
合計
189件
7
20
15 14
25
44
64
0
10
20
30
40
50
60
70
0
5
10
15
20
25
30
35
40
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
合計
出願件数
出願年(優先権主張年)
日本 米国 欧州 中国 韓国 その他 合計
出願人国籍(地域)
優先権主張
2010-2016年
注)2015 年以降はデータベース収録の遅れ、PCT 出願の各国移行のずれ等で、
全データを反映していない可能性がある。
- 113 -
資料編
第7部
第6部
第5部
第3部
第2部
第1部
本編
要約
目次
第4部
図 6-31 技術区分「動作認証」 - 出願人国籍別ファミリー件数推移及びファミリー件数比率
(日米欧中韓への出願、出願年(優先権主張年):2010 年-2016 年)
図 6-32 技術区分「静脈認証」 - 出願人国籍別ファミリー件数推移及びファミリー件数比率
(日米欧中韓への出願、出願年(優先権主張年):2010 年-2016 年)
日本国籍
2件
1.2%
米国籍
52件
31.1%
欧州国籍
15件
9.0%
中国籍
47件
28.1%
韓国籍
42件
25.1%
その他
9件
5.4%
合計
167件
8
33
19
23 24 24
36
0
5
10
15
20
25
30
35
40
0
5
10
15
20
25
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
合計
出願件数
出願年(優先権主張年)
日本 米国 欧州 中国 韓国 その他 合計
出願人国籍(地域)
優先権主張
2010-2016年
注)2015 年以降はデータベース収録の遅れ、PCT 出願の各国移行のずれ等で、
全データを反映していない可能性がある。
日本国籍
7件
9.9%
米国籍
16件
22.5%
欧州国籍
4件
5.6%
中国籍
34件
47.9%
韓国籍
9件
12.7%
その他
1件
1.4%
合計
71件
3 4
3
10
5
16
30
0
5
10
15
20
25
30
35
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
合計
出願件数
出願年(優先権主張年)
日本 米国 欧州 中国 韓国 その他 合計
出願人国籍(地域)
優先権主張
2010-2016年
注)2015 年以降はデータベース収録の遅れ、PCT 出願の各国移行のずれ等で、
全データを反映していない可能性がある。
- 114 -
資料編
第7部
第6部 第5部
第3部
第2部
第1部
本編
要約
目次
第4部
また、「暗号技術」の細目である「ハッシュ関数」も、現時点で出願件数は多くない
が、ここ数年で出願が急激に増加しており、発展途上であって、今後、日本国籍が優位
に立てる余地が十分にある重要な技術分野と考えられる(図 6-33)。
図 6-33 技術区分「ハッシュ関数」 - 出願人国籍別ファミリー件数推移及びファミリー件数比
率(日米欧中韓への出願、出願年(優先権主張年):2010 年-2016 年)
② 決済システムの将来の安全性に対する脅威に備える基盤技術
IBM やグーグル、アリババがクラウドサービスとして利用できる量子コンピュータ
を公開するなど、量子コンピュータは単なる理論上の可能性ではなく、物理的な実験
システムとして既に実現してきており、実用化に向けた開発の段階に差し掛かりつつ
ある。
現在の社会のあらゆる場面で使われている公開鍵暗号は、桁数の大きな数の素因数
分解や離散対数問題などの問題は、 新のスーパーコンピュータを使っても解くこと
ができないという事実に基づいて、秘密情報の安全性を担保している。
量子コンピュータは、指数関数的に組み合わせが増えるこれらの問題を、桁数に比
例する程度の時間で解ける可能性が高い。実用化のためには大規模化が必要であるが、
実用化された場合、スーパーコンピュータなどでも、宇宙の年齢をはるかに超えた時
間が掛かるなど、現実的な時間で解けなかった問題を、現実的な時間で解くことがで
きるようになる懸念が大きい。
そうした将来の安全性の脅威に備えるため、例えば、米国立標準技術研究所(NIST)
は、2016 年から、耐量子計算機暗号のアルゴリズムの収集、分析、標準化に向けた取
り組みを開始した。NIST の内部文書によると、大規模な量子コンピュータが既存の暗
号技術を脅かす時期は不透明としながらも、例えば、M. Mosca の論文を紹介し、20 年
程度内で、基本的に現在使われている全ての公開鍵暗号を破る大規模量子コンピュー
タができる可能性があるとしている(NIST( 2016)「Report on Post-Quantum
Cryptography」)。引用元論文では、2026 年までに RSA-2048 が 7 分の 1 の確率で、2031
年までに 2 分の 1 の確率で破られると見積もられている。そして、暗号技術の社会配
備には 20 年くらいかかっているので、現段階で備えに着手する必要があるとしてい
る。
仮想通貨や電子マネーによる決済システムの将来にわたっての安全性を確保し、持
日本国籍
10件
2.0%
米国籍
167件
33.0%
欧州国籍
76件
15.0%
中国籍
133件
26.3%
韓国籍
97件
19.2%
その他
23件
4.5%
合計
506件
23 27 37
57 69
96
197
0
50
100
150
200
250
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
合計
出願件数
出願年(優先権主張年)
日本 米国 欧州 中国 韓国 その他 合計
出願人国籍(地域)
優先権主張
2010-2016年
注)2015 年以降はデータベース収録の遅れ、PCT 出願の各国移行のずれ等で、
全データを反映していない可能性がある。
- 115 -
資料編
第7部
第6部
第5部
第3部
第2部
第1部
本編
要約
目次
第4部
続的な社会基盤を保護するためには、量子コンピュータが実用化された場合でも解読
されない暗号方式や技術が求められる。
代表的な技術としては、格子に基づく暗号、符号に基づく暗号、多変数多項式に基づ
く暗号、同種写像に基づく暗号などが挙げられる。 そのような中、仮想通貨・電子マネーによる決済システムに関する特許を抽出した
中では、決済システムにおける耐量子計算機暗号に関する特許出願は、現時点ではほ
ぼない状況である。
③ 仮想通貨とその基幹技術としてのブロックチェーン技術
電子的な新たな決済システムとして、仮想通貨に関する特許出願は、2014 年以降急
激に増加している。2016 年には中国籍の出願が突出してきているが、日本国籍の出願
比率は低いままなのが現状である(図 6-34)。
図 6-34 技術区分「仮想通貨」 - 出願人国籍別ファミリー件数推移及びファミリー件数比率
(日米欧中韓への出願、出願年(優先権主張年):2010 年-2016 年)
日本国籍
49件
8.6%
米国籍
198件
34.7%
欧州国籍
43件
7.5%
中国籍
168件
29.5%
韓国籍
72件
12.6%
その他
40件
7.0%
合計
570件
24 36 35
44
112 114
205
0
50
100
150
200
250
0
20
40
60
80
100
120
140
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
合計
出願件数
出願年(優先権主張年)
日本 米国 欧州 中国 韓国 その他 合計
出願人国籍(地域)
優先権主張
2010-2016年
注)2015 年以降はデータベース収録の遅れ、PCT 出願の各国移行のずれ等で、
全データを反映していない可能性がある。
- 116 -
資料編
第7部
第6部 第5部
第3部
第2部
第1部
本編
要約
目次
第4部
仮想通貨による決済システムの基幹技術であるブロックチェーン特有の要素技術も、
2014 年まではほとんど出願がなく、2015 年から急激に出願が増加している(図 6-35)。
出願人国籍別には、やはり中国籍が突出している(図 6-36)。
図 6-35 技術区分「要素技術(ブロックチェーン特有)」‐ファミリー件数推移(日米欧中韓へ
の出願、出願年(優先権主張年):2010-2016 年)(再掲)
鍵の管理4
9 38
マルチシグナチャー
1 3 7
ハードウェアウォレット1 1 4
ペーパーウォレット 1 2
データの管理 5 4 48
コンセンサス1 3
20 72
ファイナリティ1 2 11
その他1 11
参加者構成1 2 8
32
パブリック型1 2 8 19
コンソーシアム型4
プライベート型 8
スクリプト記述2 4 24
ブロックチェーン間接続1 1 2 7 22
スケーラビリティ5
30
要素技術「ブロックチェー
ン特有」中分類・小分類
出願年(優先権主張年)
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
注)2015 年以降はデータベース収録の遅れ、PCT 出願の各国移行のずれ等で、
全データを反映していない可能性がある。
- 117 -
資料編
第7部
第6部
第5部
第3部
第2部
第1部
本編
要約
目次
第4部
図 6-36 技術区分「ブロックチェーン特有」‐出願人国籍別‐ファミリー件数(日米欧中韓へ
の出願、出願年(優先権主張年):2010-2016 年)(再掲)
鍵の管理 4 5 6 29 61
マルチシグナチャー2 2 2
5
ハードウェアウォレット1
4 1
ペーパーウォレット2 1
データの管理 5 7 435 6
コンセンサス 5 26 12 39 113
ファイナリティ2 1 2
81
その他 61
5
参加者構成2 13 6 19
2 1
パブリック型2
9 6 102 1
コンソーシアム型1 3
プライベート型 8
スクリプト記述 6 5 13 51
ブロックチェーン間接続1 13
112
4 2
スケーラビリティ2 5 1
241 2
要素技術「ブロック
チェーン特有」中分類・
小分類
出願人国籍
日本 米国 欧州 中国 韓国 その他
- 118 -
資料編
第7部
第6部 第5部
第3部
第2部
第1部
本編
要約
目次
第4部
一方、仮想通貨による決済システムの基幹技術であるブロックチェーン特有の要素
技術に関する論文発表件数推移を見ると、2012 年~2013 年頃から発表が見られ横ばい
で推移し、2017 年に急激な増加が見られる。特許出願では 2017 年以降の出願状況がデ
ータからは分からないが、2017 年以降、より多くの出願がなされていると予想される。
(図 6-37)。
図 6-37 技術区分「要素技術(ブロックチェーン特有)」-論文発表件数推移(発行年:2010-
2017 年)
鍵の管理1 2
5
マルチシグナチャー
ハードウェアウォレット
ペーパーウォレット
データの管理1
1 2 28 21
コンセンサス1 5
6 10 31
ファイナリティ1 4
その他1 2 2 4
参加者構成1 3 4 5
8 19
パブリック型 1 3 4 5 4 4
コンソーシアム型1
7
プライベート型 1 9
スクリプト記述1 1
ブロックチェーン間接続2 1
3
スケーラビリティ3 4 2
5 21
要素技術「ブロックチェー
ン特有」中分類・小分類
発行年
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
- 119 -
資料編
第7部
第6部
第5部
第3部
第2部
第1部
本編
要約
目次
第4部
④ その他今後の出願が期待される基盤技術
①~③までの他、現時点で出願件数は多くないが、ここ数年で出願が急激に増加し
ている、仮想通貨・電子マネーによる決済システムの基盤技術として、「ウェブウォレ
ット」、「MST」、「ウェアラブル端末」、「人体通信」がある(図 6-38~図 6-41)。
これらの技術も、発展途上で今後、日本国籍が優位に立てる余地は十分にあると考
えられる。
図 6-38 技術区分「ウェブウォレット」 - 出願人国籍別ファミリー件数推移及びファミリー件
数比率(日米欧中韓への出願、出願年(優先権主張年):2010 年-2016 年)
図 6-39 技術区分「MST」 - 出願人国籍別ファミリー件数推移及びファミリー件数比率(日米
欧中韓への出願、出願年(優先権主張年):2010 年-2016 年)
日本国籍
9件
1.8%
米国籍
376件
74.3%
欧州国籍
42件
8.3%
中国籍
24件
4.7%
韓国籍
21件
4.2%
その他
34件
6.7%
合計
506件
13
32
43 49
92
131
146
0
20
40
60
80
100
120
140
160
0
20
40
60
80
100
120
140
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
合計
出願件数
出願年(優先権主張年)
日本 米国 欧州 中国 韓国 その他 合計
出願人国籍(地域)
優先権主張
2010-2016年
注)2015 年以降はデータベース収録の遅れ、PCT 出願の各国移行のずれ等で、
全データを反映していない可能性がある。
日本国籍
0件
0.0%
米国籍
0件
0.0%
欧州国籍
0件
0.0%
中国籍
5件
10.9%
韓国籍
40件
87.0%
その他
1件
2.2%
合計
46件
0 0 0
2
0
25
19
0
5
10
15
20
25
30
0
5
10
15
20
25
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
合計
出願件数
出願年(優先権主張年)
日本 米国 欧州 中国 韓国 その他 合計
出願人国籍(地域)
優先権主張
2010-2016年
注)2015 年以降はデータベース収録の遅れ、PCT 出願の各国移行のずれ等で、
全データを反映していない可能性がある。
- 120 -
資料編
第7部
第6部 第5部
第3部
第2部
第1部
本編
要約
目次
第4部
図 6-40 技術区分「ウェアラブル端末」 - 出願人国籍別ファミリー件数推移及びファミリー件
数比率(日米欧中韓への出願、出願年(優先権主張年):2010 年-2016 年)
図 6-41 技術区分「人体通信」 - 出願人国籍別ファミリー件数推移及びファミリー件数比率
(日米欧中韓への出願、出願年(優先権主張年):2010 年-2016 年)
日本国籍
8件
2.3%
米国籍
93件
27.0%
欧州国籍
26件
7.5%
中国籍
166件
48.1%
韓国籍
40件
11.6%
その他
12件
3.5%
合計
345件
4 8
15
33
60
127
98
0
20
40
60
80
100
120
140
0
10
20
30
40
50
60
70
80
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
合計
出願件数
出願年(優先権主張年)
日本 米国 欧州 中国 韓国 その他 合計
出願人国籍(地域)
優先権主張
2010-2016年
注)2015 年以降はデータベース収録の遅れ、PCT 出願の各国移行のずれ等で、
全データを反映していない可能性がある。
日本国籍
0件
0.0%
米国籍
1件
4.8%
欧州国籍
0件
0.0%
中国籍
18件
85.7%
韓国籍
1件
4.8%
その他
1件
4.8%
合計
21件
0 0 0
1
3
6
11
0
2
4
6
8
10
12
0
2
4
6
8
10
12
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
合計
出願件数
出願年(優先権主張年)
日本 米国 欧州 中国 韓国 その他 合計
出願人国籍(地域)
優先権主張
2010-2016年
注)2015 年以降はデータベース収録の遅れ、PCT 出願の各国移行のずれ等で、
全データを反映していない可能性がある。
- 121 -
資料編
第7部
第6部
第5部
第3部
第2部
第1部
本編
要約
目次
第4部
3. ブロックチェーン技術の決済以外も含む利用場面の技術動向に関する分析
本調査では、仮想通貨・電子マネーによる決済システムに関する特許文献に加え、「管
理目的、商用目的、金融目的、経営目的、監督目的または予測目的」に使われる、ブロッ
クチェーン関連技術に関する特許文献についても抽出した。
ここでは、これらブロックチェーン技術の決済以外も含む利用場面の技術動向に関す
る分析を示す。
経済産業省(2016)「我が国経済社会の情報化・サービス化に係る基盤技術(ブロック
チェーン技術を利用したサービスに関する国内外動向調査)」では、ブロックチェーン技
術の活用動向を調査・分析し、想定され得る様々なユースケースの中から、「真正性の保
証された取引が可能(二重支払の防止)」や「データのトレーサビリティが可能で、透明
性の高い取引が可能(改ざんが困難)」、「中央管理者が不在でも、悪意を持つユーザがい
てもエコシステムが安定維持される」といった特にブロックチェーンに特徴的な技術の
機能との適合性が高いと期待されるユースケースを整理・分析している。
その整理を踏まえた体系的な技術区分を設定して、抽出された特許文献を分類した。
利用場面を大きく、「価値の記録」、「権利の記録」、「関与者の記録」、「処理の自動化」に
分けている。「価値の記録」、「権利の記録」に関するファミリー件数推移を図 6-42 に、
「関与者の記録」、「処理の自動化」に関するファミリー件数推移を図 6-43 に示す。
先に図 6-35 で、仮想通貨による決済システムの基幹技術であるブロックチェーン特有
の要素技術が、2014 年まではほとんど出願がなく、2015 年から急激に出願が増加してい
るのを見た。決済以外も含む利用場面についても、それと同様に、全般的に、2014 年ま
ではほとんど出願がなく、2015 年から大きく件数を伸ばしてきているところである。
図 6-42 を見ると、「価値の記録」では、決済システムにおける代表的な利用場面とな
る「通貨の代替」が突出して多いが、「その他」、「証券取引」や「ポイント・クーポン」
に関する出願がそれに続いており、「ゲーム内通貨」、「クラウドファンディング」、「チケ
ット・ギフトカード」を利用場面として想定した出願も少ないながら見られる。
「権利の記録」では、「不動産取引」、「為替取引」、「知的財産権」、「デジタルコンテン
ツ利用」、「投票」の権利を記録する利用場面についての出願が、件数は多くないが見ら
れる。
図 6-43 を見ると、「関与者の記録」では、「サプライチェーン」の製造業者、流通業者
等、「ヘルスケア」の診療記録や投薬記録等の関与者を記録する利用場面についての出願
が比較的多く、「偽造防止・真正性担保」、「貴重品管理」、「オークション」、「各種届出」、
「広告・広報」における関与者を記録することを想定した出願も少ないながら見られる。
「処理の自動化」では、契約手続の自動化を図る「スマートコントラクト」に関する出
願が多くみられ、「エスクロー自動化」、「デリバティブ」、「エネルギー管理」「会社清算」
に関する手続を管理することを想定した出願が少ないながら見られる。
- 122 -
資料編
第7部
第6部 第5部
第3部
第2部
第1部
本編
要約
目次
第4部
図 6-42 技術区分「決済以外も含むブロックチェーン技術の利用場面(価値の記録、権利の記
録)」‐ファミリー件数推移(日米欧中韓への出願、出願年(優先権主張年):2010-2016 年)
(再掲)
価値の記録
1 1 738 151
通貨の代替1 5
33 112
ゲーム内通貨1
SNS
その他25 19
証券取引6 26
クラウドファンディング4
チケット・ギフトカード1 4
ポイント・クーポイン1 1 11
権利の記録1 3 5 31
不動産取引7
為替取引1 1 5
知的財産権2 8
デジタルコンテンツ利用1 4
投票2 1 3
決済以外も含むブロック
チェーン技術の利用場面
「価値の記録」「権利の記録」中分類
出願年(優先権主張年)
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
注)2015 年以降はデータベース収録の遅れ、PCT 出願の各国移行のずれ等で、
全データを反映していない可能性がある。
- 123 -
資料編
第7部
第6部
第5部
第3部
第2部
第1部
本編
要約
目次
第4部
図 6-43 技術区分「決済以外も含むブロックチェーン技術の利用場面(関与者の記録、処理の
自動化、その他)」‐ファミリー件数推移(日米欧中韓への出願、出願年(優先権主張年):
2010-2016 年)(再掲)
関与者の記録2 1 3
16 47
サプライチェーン1 3 6
24
ヘルスケア2 1 5 8
偽造防止・真正性担保2 6
貴重品管理1
オークション3
各種届出3
シェアリングエコノミー
スマートモビリティ
広告・広報1
処理の自動化17
95
スマートコントラクト13 84
エスクロー自動化2
デリバティブ2
エネルギー管理2 7
消耗品管理
遺言
会社清算1
その他1 1 15
88
決済以外も含むブロック
チェーン技術「関与者の記
録」「処理の自動化」「その他」中分類
出願年(優先権主張年)
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
注)2015 年以降はデータベース収録の遅れ、PCT 出願の各国移行のずれ等で、
全データを反映していない可能性がある。
- 124 -
資料編
第7部
第6部 第5部
第3部
第2部
第1部
本編
要約
目次
第4部
「価値の記録」、「権利の記録」に関する出願人国籍別ファミリー件数を図 6-44 に、「関
与者の記録」、「処理の自動化」に関する出願人国籍別ファミリー件数を図 6-45 に示す。
「価値の記録」、中でも「通貨の代替」については中国籍が大きく突出している。一方、
「権利の記録」、「関与者の記録」、「処理の自動化」では米国籍と中国籍が拮抗している。
中国籍は「通貨の代替」に注力し出願を伸ばしており、米国籍は「通貨の代替」以外も含
めた多様な用途の開発に取り組んでいる状況となっている。
図 6-44 技術区分「決済以外も含むブロックチェーン技術の利用場面(価値の記録、権利の記
録の中分類・小分類)」‐出願人国籍別‐ファミリー件数(日米欧中韓への出願、出願年(優先
権主張年):2010-2016 年)(再掲)
価値の記録 12 23 14 118 274
通貨の代替10 9
12 97 194
ゲーム内通貨1
SNS
その他3 7 9 4 19 2
証券取引1 12 1 16 1 1
クラウドファンディング2 2
チケット・ギフトカード 4 1
ポイント・クーポイン2 2 5 4
権利の記録 3 14 5 126
不動産取引 3 2 1 1
為替取引 3 2 2
知的財産権 3 2 5
デジタルコンテンツ利用 1 1 2 1
投票 3 1 2
決済以外も含むブロック
チェーン技術の利用場
面「価値の記録」「権利の記録」中分類・小分類
出願人国籍
日本 米国 欧州 中国 韓国 その他
- 125 -
資料編
第7部
第6部
第5部
第3部
第2部
第1部
本編
要約
目次
第4部
図 6-45 技術区分「決済以外も含むブロックチェーン技術の利用場面(関与者の記録、処理の
自動化、その他の中分類・小分類)」‐出願人国籍別‐ファミリー件数(日米欧中韓への出願、
出願年(優先権主張年):2010-2016 年)(再掲)
関与者の記録2
256
25 83
サプライチェーン 132
172
ヘルスケア 92 4 1
偽造防止・真正性担保3 1 4
貴重品管理1
オークション2 1
各種届出1 1 1
シェアリングエコノミー
スマートモビリティ
広告・広報1
処理の自動化4
38 13 502 5
スマートコントラクト3
33 11 451 4
エスクロー自動化1 1
デリバティブ2
エネルギー管理1 2 2 3 1
消耗品管理
遺言
会社清算1
その他3 33 11 39 9 10
決済以外も含むブロック
チェーン技術の利用場
面「関与者の記録」「処理の自動化」「その他」
中分類・小分類
出願人国籍
日本 米国 欧州 中国 韓国 その他
- 126 -
資料編
第7部
第6部 第5部
第3部
第2部
第1部
本編
要約
目次
第4部
「価値の記録」、「権利の記録」に関する論文発表件数推移を図 6-46 に、「関与者の記
録」、「処理の自動化」に関する論文発表件数推移を図 6-47 に示す。
特許出願では、2014 年まではほとんど出願がなく、2015 年から大きく件数を伸ばして
いたが、論文発表では、2012 年~2013 年頃から発表が見られ横ばいで推移し、2017 年に
急激な増加が見られる。特許出願では、2017 年以降の出願状況がデータからは分からな
いが、2017 年以降、より多くの出願がなされていると予想される。
図 6-46 技術区分「決済以外も含むブロックチェーン技術の利用場面(価値の記録、権利の記
録)」-論文発表件数推移(発行年:2010-2017 年)
価値の記録1 7 12
14 18 43
通貨の代替7 12
14 18 39
ゲーム内通貨
SNS
その他7 12 14
18 38
証券取引2
クラウドファンディング2
チケット・ギフトカード
ポイント・クーポイン
権利の記録1 4 3 12
不動産取引3
為替取引1
知的財産権3
デジタルコンテンツ利用1 2 2 2
投票1 2
決済以外も含むブロック
チェーン技術の利用場面
「価値の記録」「権利の記録」中分類
発行年
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
- 127 -
資料編
第7部
第6部
第5部
第3部
第2部
第1部
本編
要約
目次
第4部
図 6-47 技術区分「決済以外も含むブロックチェーン技術の利用場面(関与者の記録、処理の
自動化、その他)」-論文発表件数推移(発行年:2010-2017 年)
関与者の記録1 1 4
34
サプライチェーン1 10
ヘルスケア3
22
偽造防止・真正性担保1 1 1
貴重品管理
オークション2
各種届出1
シェアリングエコノミー
スマートモビリティ
広告・広報
処理の自動化3 9
69
スマートコントラクト3 9
49
エスクロー自動化
デリバティブ
エネルギー管理 29
消耗品管理
遺言1
会社清算3
その他4
15115
決済以外も含むブロック
チェーン技術「関与者の記
録」「処理の自動化」「その他」中分類
発行年
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
- 128 -
資料編
第7部
第6部 第5部
第3部
第2部
第1部
本編
要約
目次
第4部
第 2 節 今後の展望・方向性と提言
1. 今後の展望・方向性
【方向性Ⅰ】 キャッシュレス化推進に向けた技術蓄積の活用・強化
1. 経済産業省(2018)「我が国における FinTech 普及に向けた環境整備に関する調査検
討」によると、日本の現金決済による直接コストは、レジ締め等の現金関連業務人
件費、ATM 機器設置費など、年間 1.6 兆円を超える(第 6 章第 1 節 1.)。
2. 一方、キャッシュレス化の推進による潜在的経済効果は、資産運用の活性化による
家計所得の向上、電子決済関連市場の成長、訪日外国人による消費支出増などで、
約 6 兆円になると試算されている(第 6 章第 1 節 1.)。
3. また、全国銀行協会内に設置された、経済・金融・財政等の研究に携わる研究者によ
る、金融調査研究会(2018)「キャッシュレス社会の進展と金融制度のあり方」では、
キャッシュレスの定義を、「単にキャッシュレスな決済手段の利用比率が高まるとい
う量的な側面だけでなく、利用者利便に資する新たな価値が付加されたり、従来よ
りも安価に提供されたりするなど、質的な改善も含むもの」としている。
4. 日本政府はこのような社会負担を軽減し、キャッシュレス化推進による経済効果、
その他の付加価値を上げるため、2020 年の東京オリンピックや 2025 年の大阪万博
等のイベントを契機としたキャッシュレス化政策を推進している(第6章第1節 1.、
第 3 章第 1 節 1.)。
5. キャッシュレス化推進に向けた技術蓄積の活用・強化を図るべきである。
【方向性Ⅱ】 仮想通貨・電子マネーによる決済システムを支える基盤技術への注力・デ
ータの囲い込みへの対抗
1. 現状、日本のキャッシュレス決済比率は諸外国と比べて非常に低い水準にある(第
6 章第 1 節 1.、第 2 章第 2 節)。
2. キャッシュレス化を実現していくことは大きな社会変革となるため、仮想通貨や電
子マネーによる決済システムの更なる普及・展開にあたり、金融システムとその利
用者にとっての安全性を維持・確立し、将来における技術の可能性も加味した持続
的な基盤構築が求められる。
3. それを支える基盤技術は、国内はもとより、広く国際展開も可能と考えられる。
4. また、世の中で広く使われる決済サービスや取引基盤から得られるデータは、新た
なマーケットニーズや潮流の把握、サービス開発、技術開発に有用なものである。
海外勢のプラットフォーマによるこれらのデータの囲い込みが、日本によるデータ
の利活用推進を難しくする可能性がある。これに対抗するためにも基盤技術への注
力が必要である。
5. 仮想通貨・電子マネーによる決済システムを支える基盤技術への注力・データの囲
い込みへの対抗を図るべきである。
- 129 -
資料編
第7部
第6部
第5部
第3部
第2部
第1部
本編
要約
目次
第4部
2. 提言
【方向性Ⅰ】 キャッシュレス化推進に向けた技術蓄積の活用・強化
に関する提言
【提言Ⅰ-1】 キャッシュレス化推進に向けた経済性を向上させる技術蓄積の活用・強化
日本企業は、キャッシュレス化推進に向け、仮想通貨・電子マネーによる決済シス
テムの「端末導入コストの低減」や「ネットワーク・センターシステムの低コスト化」、
「与信業務の効率化」など、低コスト化に関するこれまでの技術蓄積を活かして引き
続き注力するとともに、仮想通貨・電子マネーによる決済で得られる取引データの「マ
ーケティング活用」により、消費の刺激や広告・販売促進の投資対効果の向上、顧客
の囲い込みなどの経済的メリットを引き出す取り組みにも今後注力していき、技術蓄
積を強化すべきである。
1. 日本のキャッシュレス推進に向けた環境・課題を調査し対応の方向性を検討した、
経済産業省(2018)「キャッシュレス・ビジョン」によると、キャッシュレス支払に
対応していない実店舗等の存在がキャッシュレス普及に向けた大きなボトルネック
の一つとなっている。実店舗等におけるキャッシュレス支払の導入が普及しにくい
背景には、「決済手数料」、「端末導入コスト」など追加コストの発生があり、その一
方で、本来はキャッシュレス化による支払データの利活用で、消費の刺激や広告・
販売促進の投資対効果の向上、顧客の囲い込みなどが期待されるはずであるが、そ
うした経済的メリットがあまり実感されていないという要因が存在する。
2. ボトルネック解消のためには、特に、零細事業者等に対し、決済手数料や端末導入
に掛かる費用への補助金の支給や税制面での優遇措置などの施策も考えられるが、
技術的な工夫も期待される。
3. 低コスト化に関する「端末導入コストの低減」についての特許出願を見ると、日本
国籍が出願を増やしている注力分野であり、少なくとも日本への出願において日本
国籍に強みがあり、中国籍や韓国籍の進出を許しておらず、国際出願においても今
後日本国籍の存在感を増すことのできる可能性が比較的高い技術分野となっている
(第 6 章第 1 節 2.(2)、同(3)、図 6-18、図 6-20、図 6-22)。
4. 「ネットワーク・センターシステムの低コスト化」、「与信業務の効率化」について
も、少なくとも日本への出願において日本国籍に強みがあり、中国籍や韓国籍の進
出を許していない技術分野となっている(第 6 章第 1 節 2.(2)、図 6-18、図 6-20)。
5. 一方、経済的メリットの発揮に関する「マーケティング活用」については、日本への
出願においても日本国籍による出願が少なく、中国籍は目立たないが、米国籍や韓
国籍の技術蓄積が進んでおり(第 6 章第 1 節 2.(2)、同(3)、図 6-18、図 6-22、図 6-
26)、顧客情報の蓄積が他国籍企業に先んじられてしまうおそれがある。
6. 日本企業は、キャッシュレス化推進に向け、仮想通貨・電子マネーによる決済シス
テムの「端末導入コストの低減」や「ネットワーク・センターシステムの低コスト
化」、「与信業務の効率化」など、低コスト化に関するこれまでの技術蓄積を活かし
- 130 -
資料編
第7部
第6部 第5部
第3部
第2部
第1部
本編
要約
目次
第4部
て引き続き注力するとともに、仮想通貨・電子マネーによる決済で得られる取引デ
ータの「マーケティング活用」により、消費の刺激や広告・販売促進の投資対効果の
向上、顧客の囲い込みなどの経済的メリットを引き出す取り組みにも今後注力して
いき、技術蓄積を強化すべきである。
【提言Ⅰ-2】 キャッシュレス化推進に向けた利便性を向上させる技術蓄積の活用・強化
日本企業は、キャッシュレス化推進に向け、「多様な決済手段への対応」や「取引対
象の管理」など利便性向上に関するこれまでの技術蓄積を活かして引き続き注力する
とともに、中国における爆発的なモバイル決済普及につながった「QR コード」や「携
帯端末」、「円滑な決済」に関する技術への注力を増し、技術蓄積を強化すべきである。
また、「ウェブウォレット」、「ウェアラブル端末」、「人体通信」などは、決済システ
ムにおいて今後活用が増すと考えられる発展途上の技術活用分野であり、今後注力し
ていくことにより、要素技術における国際的に優位な地位を築ける余地が十分にある
と考えられる。
1. キャッシュレス社会への期待を調査した、博報堂(2017)「お金に関する生活者意識
調査」によると、キャッシュレス社会に賛成の理由として、「現金を持たなくてよい
から」、「利便性が高いから」、「お得だから」、「やり取りがスムーズだから」、「管理
しやすいから」が自由回答のトップ 5 となっており、利便性の向上が、消費者にと
ってのメリットを感じさせ、キャッシュレス化を促進する要因になると考えられる。
2. 利便性に関する「多様な決済手段への対応」、「取引対象の管理」についての特許出
願を見ると、少なくとも日本への出願においては日本国籍に強みがあり、中国籍や
韓国籍の進出を許していない技術分野となっている(第 6 章第 1 節 2.(2)、図 6-17
~図 6-20)。特に、「取引対象の管理」は、日本国籍が出願を増やしている注力分野
であり、今後の国際出願においても日本国籍の存在感を増すことのできる可能性が
比較的高い技術分野と考えられる(第 6 章第 1 節 2.(3)、図 6-21)。
3. カード・ウェーブ「電子決済総覧 2017-2018」によると、中国ではスマートフォンを
用いたモバイル決済が急激に拡大しており、アリババの「Alipay」とテンセントの
「WeChat Pay」が牽引する形で、2016 年の取引高は 38 兆元にのぼり、既に米国を超
えて世界 大のモバイル決済市場となっている。「Alipay」や「WeChat Pay」はとも
に QR コードによる決済システムであり、スマートフォンさえあれば利用者にとって
手軽に円滑に利用することができる。店舗側にとっても、端末導入コストが低く、
小規模な小売店や飲食店にも浸透して爆発的に広がった。
4. 中国における爆発的なモバイル決済普及につながった「QR コード」やこれに関する
「携帯端末」、「円滑な決済」についての特許出願を見ると、日本への出願において
も日本国籍による出願が少ない技術分野となっている(第 6 章第 1 節 2.(2)、同(3)、
図 6-17、図 6-19、図 6-21~図 6-26)。ただし、「QR コード」は、日本国籍が出願を
増やしている注力分野であり、今後国内の技術蓄積を図るとともに、国際出願にお
ける日本国籍の存在感を増すために、サムスンなど、韓国籍の動向に留意しつつ取
り組むべきと考えられる。
- 131 -
資料編
第7部
第6部
第5部
第3部
第2部
第1部
本編
要約
目次
第4部
5. 日本企業は、キャッシュレス化推進に向け、「多様な決済手段への対応」や「取引対
象の管理」など利便性向上に関するこれまでの技術蓄積を活かして引き続き注力す
るとともに、中国における爆発的なモバイル決済普及につながった「QR コード」や
「携帯端末」、「円滑な決済」に関する技術への注力を増し、技術蓄積を強化すべき
である。
6. その他、暗号鍵を持ち歩かなくても、インターネット上で管理される暗号鍵を利用
する「ウェブウォレット」や、媒体・端末を持ち歩いていることを感じさせにくい
「ウェアラブル端末」、「人体通信」など、決済システムの利便性向上に資する技術
については、現時点で特許出願件数は多くないが、ここ数年で急激に増加している
発展途上の技術活用分野であり、今後日本国籍が注力していくことで優位に立てる
余地は十分にあると考えられる(第 6 章第 1 節 2.(4)④、図 6-38、図 6-40、図 6-
41)。
【方向性Ⅱ】 仮想通貨・電子マネーによる決済システムを支える基盤技術への注力・デ
ータの囲い込みへの対抗
に関する提言
【提言Ⅱ-1】 決済システムの安全性を確保するための基盤技術への注力・データの囲い
込みへの対抗
日本企業は、仮想通貨・電子マネーによる決済システムの安全性を確保するための
基盤技術として、「プライバシー保護」や「取引履歴の管理」など、安全性関連技術に
関するこれまでの技術蓄積を活かして引き続き注力するとともに、「生体認証」、「取引
履歴による認証」、「第三者による認証・仲介」など、取引に関する安全性をオンタイ
ムで確保する技術への注力を増し、技術蓄積を強化すべきである。
特に、「生体認証」技術の中では、「音声認証」、「虹彩認証」、「動作認証」、「静脈認
証」は、「指紋認証」、「顔認証」に比べ、相対的に未熟な開発・適用段階にあると考え
られ、今後注力していくことにより、要素技術における国際的に優位な地位を築ける
余地が十分にあると考えられる。
また、そうした基盤技術への注力を通じ、安全性確保の技術の中でも、今後益々新
たなマーケットニーズや潮流の把握、サービス開発、技術開発に有用になっていくと
考えられる、決済サービスや取引基盤の利用に伴うデータの入り口となる「認証媒体・
ウォレット」の部分を担える体制を確保していくことが期待される。
1. 経済産業省(2018)「我が国における FinTech 普及に向けた環境整備に関する調査検
討」によると、現金・キャッシュレス決済に関するアンケート調査で、キャッシュレ
ス決済が導入されている店舗であっても、現金を選択する消費者の方が多い実態に
あることが示されている。
2. 日本のキャッシュレス推進に向けた環境・課題を調査し対応の方向性を検討した、
経済産業省(2018)「キャッシュレス・ビジョン」によると、キャッシュレス支払に
対応していない実店舗等の存在がキャッシュレス支払への移行を躊躇させている他、
- 132 -
資料編
第7部
第6部 第5部
第3部
第2部
第1部
本編
要約
目次
第4部
キャッシュレス支払にまつわる各種不安がキャッシュレス普及を阻害する要因とな
っている。
3. 金融調査研究会(2018)「キャッシュレス社会の進展と金融制度のあり方」では、そ
うした不安として、「キャッシュレスな決済手段を利用する場合には、現金取引の場
合における取引の匿名性が必ずしも担保されず、支払者が意図しないかたちで取引
情報が利用されるおそれがある」、「キャッシュレスな決済手段が不正利用されたり、
サイバー攻撃を受けたりした場合などは、多額の被害を受けることも生じ得る」な
どの要因があると分析している。
4. こうした不安感の解消のためには、キャッシュレス支払手段を提供する事業者が、
適切な個人情報保護ポリシーを設定し厳格な管理を行ったり、不真正利用や商品・
サービスが未提供などの場合に、事業者の定める条件を満たしていれば、消費者は
免責されるといった、適切な消費者保護の仕組みを提供したりし、それらを消費者
に十分に周知することが有効と考えられるが、技術的な仕組みによって安全性を担
保していくことも重要と考えられる。
5. また、企業秘密の流出防止という観点も重要である。他社が提供する決済サービス
や取引基盤を利用することは、その他社に、経営データや取引履歴などの企業秘密
を委ねることにつながる。企業秘密の流出防止のためにも、技術的な安全性を十分
に担保することが前提として必要である。
6. 決済システムの安全性確保に関連する技術として、「プライバシー保護」や「取引履
歴の管理」についての特許出願を見ると、少なくとも日本への出願において、日本
国籍に強みがあり、中国籍や韓国籍の進出を許していない技術分野となっている(第
6 章第 1 節 2.(2)、図 6-18、図 6-20)。これら「プライバシー保護」や「取引履歴の
管理」は、米国籍や韓国籍の技術蓄積が進んでいる取引データの「マーケティング
活用」においても(提言Ⅰ-1、第 6 章第 1 節 2.(2)、図 6-18、図 6-20)、顧客情報を
蓄積する上で不可欠な技術である。
7. ただし、「プライバシー保護」に関しては、欧州で一般データ保護規則(General Data
Protection Regulation(GDPR))が 2016 年 5 月に発効になり、2018 年からは行政罰
を伴う適用開始となる点に留意を要する。インターネット取引などで域内における
所在者の個人情報を取得・移転する場合にも適用対象となり、それだけで個人を特
定できる情報のみならず他の情報と照合することで初めて個人を特定できる情報も
含めて対象となるなど、日本の個人情報保護法よりも厳しい規制となっており、追
加の対応が必要になる。
8. 一方、「生体認証」、「取引履歴による認証」、「第三者による認証・仲介」など、取引
に関する安全性をオンタイムで確保する技術については、日本への出願においても
日本国籍による出願が少ない(第 6 章第 1 節 2.(2)、図 6-17、図 6-19)。ただし、
「生体認証」は、日本国籍が出願を増やしている注力分野であり、今後国内の技術
蓄積を図るとともに、国際出願における日本国籍の存在感を増やしていく必要があ
る技術分野であると考えられる(第 6 章第 1 節 2.(3)、図 6-21)。
9. 日本企業は、仮想通貨・電子マネーによる決済システムの安全性を確保するための
基盤技術として、「プライバシー保護」や「取引履歴の管理」など、安全性関連技術
に関するこれまでの技術蓄積を活かして引き続き注力するとともに、「生体認証」、
- 133 -
資料編
第7部
第6部
第5部
第3部
第2部
第1部
本編
要約
目次
第4部
「取引履歴による認証」、「第三者による認証・仲介」など、取引に関する安全性をオ
ンタイムで確保する技術への注力を増し、技術蓄積を強化すべきである。
10. 「生体認証」に関する特許出願の細目を見ると、総出願件数が多いものから順に、
「指紋認証」、「顔認証」、「音声認証」、「虹彩認証」、「動作認証」、「静脈認証」による
ものが見られる。いずれも伸び足の速い増加傾向にあるが、これらの中でも相対的
に未熟な開発・適用段階にあると考えられる「音声認証」、「虹彩認証」、「動作認証」、
「静脈認証」については、今後、技術開発を進めることで日本国籍が優位に立つこ
とも十分可能と考えられる(第 6 章第 1 節 2.(4)①、図 6-27~図 6-32)。
11. さらにより広い観点から見れば、海外勢のプラットフォーマによる、新たなマーケ
ットニーズや潮流の把握、サービス開発、技術開発に有用なデータの囲い込みが、
日本によるデータの利活用推進を難しくする可能性がある。
12. 経済産業省の産業構造審議会新産業構造部会でも、「データを囲い込むのではなく、
個人がデータを管理しつつ、データを共有し利活用する社会」を目指すべきとの議
論がなされているところである(産業構造審議会新産業構造部会(2016)第 7 回資
料 4-1「データの利活用等に関する制度・ルールについて」)。
13. また、公正取引委員会でも、「事業者誰しもがデータの収集・利用を公正・自由な競
争環境で行えることが必要」であるが、「データが競争者の事業に不可欠であって、
代替する情報が入手できない場合に、競争者や顧客によるアクセスを正当な理由な
く認めない場合」も考えられることから、「データに関する諸課題を巡る独占禁止法
の適用の在り方や競争政策上の論点について検討するため」、「データと競争政策に
関する検討会」を設置して検討を行っているところである(公正取引委員会競争政
策研究センター(2017)「データと競争政策に関する検討会報告書」)。
14. 日本にとってコントロールできないデータの囲い込みに対抗するためには、金融・
決済サービス関連ビジネスとして、提供するサービスの魅力度や経営的な体力等で
対抗できるようにする方策も必要となるが、技術的にも、日本として、取引などの
情報を、特定の個人や個企業と紐づける役割を有する「認証媒体・ウォレット」(IC
カード、携帯端末、ウェアラブル端末、QR コード、ウェブウォレットなど)の部分
を担える体制を確保していくことが期待される。
【提言Ⅱ-2】 決済システムの将来の安全性に対する脅威に備える基盤技術である耐量子
計算機暗号技術の開発・国際的な地位の確保
日本企業は、量子コンピュータが実用化された場合でも解読されない暗号方式や技
術(「耐量子計算機暗号」技術)の開発に取り組み、仮想通貨・電子マネーによる決済
システムの将来にわたっての持続的な安全性を確保するための技術において、国際的
に優位な地位を築くべきである。
1. IBM やグーグル、アリババがクラウドサービスとして利用できる量子コンピュータ
を公開するなど、量子コンピュータは単なる理論上の可能性ではなく、物理的な実
験システムとして既に実現してきており、実用化に向けた開発の段階に差し掛かり
つつある(第 6 章第 1 節 2.(4)②)。
- 134 -
資料編
第7部
第6部 第5部
第3部
第2部
第1部
本編
要約
目次
第4部
2. 現在の社会のあらゆる場面で使われている公開鍵暗号は、桁数の大きな数の素因数
分解や離散対数問題などの問題は、 新のスーパーコンピュータを使っても解くこ
とができないという事実に基づいて、秘密情報の安全性を担保している(第 6 章第
1 節 2.(4)②)。
3. 量子コンピュータは、指数関数的に組み合わせが増えるこれらの問題を、桁数に比
例する程度の時間で解ける可能性が高い。実用化のためには大規模化が必要である
が、実用化された場合、スーパーコンピュータなどでも、宇宙の年齢をはるかに超
えた時間が掛かるなど、現実的な時間で解けなかった問題を、現実的な時間で解く
ことができるようになる懸念が大きい(第 6 章第 1 節 2.(4)②)。
4. そうした将来の安全性の脅威に備えるため、例えば、米国立標準技術研究所(NIST)
は、2016 年から、耐量子計算機暗号のアルゴリズムの収集、分析、標準化に向けた
取り組みを開始した。NIST の内部文書によると、大規模な量子コンピュータが既存
の暗号技術を脅かす時期は不透明としながらも、例えば、M. Mosca の論文を紹介し、
20 年程度内で、基本的に現在使われている全ての公開鍵暗号を破る大規模量子コン
ピュータができるとしている(NIST(2016)「Report on Post-Quantum Cryptography」)。
引用元論文では、2026 年までに RSA-2048 が 7 分の 1 の確率で、2031 年までに 2 分
の 1 の確率で破られると見積もられている。そして、暗号技術の社会配備には 20 年
くらいかかっているので、現段階で備えに着手する必要があるとしている(第 6 章
第 1 節 2.(4)②)。
5. 仮想通貨や電子マネーによる決済システムの将来にわたっての安全性を確保し、持
続的な社会基盤を保護するためには、量子コンピュータが実用化された場合でも解
読されない暗号方式や技術が求められる(第 6 章第 1 節 2.(4)②)。
6. 代表的な技術としては、格子に基づく暗号、符号に基づく暗号、多変数多項式に基
づく暗号、同種写像に基づく暗号などが挙げられる(第 6 章第 1 節 2.(4)②)。
7. そのような中、仮想通貨・電子マネーによる決済システムに関する特許を抽出した
中では、決済システムにおける耐量子計算機暗号に関する特許出願は、現時点では
ほぼない状況である(第 6 章第 1 節 2.(4)②)。
8. 日本企業は、量子コンピュータが実用化された場合でも解読されない暗号方式や技
術(「耐量子計算機暗号」技術)の開発に取り組み、仮想通貨・電子マネーによる決
済システムの将来にわたっての持続的な安全性を確保するための技術において、国
際的に優位な地位を築くべきである。
【提言Ⅱ-3】 仮想通貨の基幹技術となるブロックチェーン技術に関する技術蓄積と利用
場面の開拓により新たに形成される市場に備えた取り組み
日本企業は、仮想通貨の基幹技術となるブロックチェーン技術に関する技術蓄積に
取り組み、従来の決済の枠組みを超えた様々な取引のプロセスへの適用により新たに
形成される市場に備えた取り組みを推進すべきである。
そうした基盤技術への注力を通じ、ブロックチェーン技術の中でも、今後決済以外
も含む様々な利用場面において、新たなマーケットニーズや潮流の把握、サービス開
発、技術開発に有用になっていくと考えられる決済サービスや取引基盤の利用に伴う
- 135 -
資料編
第7部
第6部
第5部
第3部
第2部
第1部
本編
要約
目次
第4部
データの入り口となる「鍵の管理」の部分を担える体制を確保していくことが期待さ
れる。
ただし、ブロックチェーン技術では中小企業の参画も多い。中小企業にとっては、
個社では事業を守れるだけの十分な特許ポートフォリオを形成しにくい、知財のリテ
ラシー不足や国際出願の経済的負担が大きいといった問題もある。特許を集団でまと
め、取り決めた条件の下、使用できるようにするパテントプール/コモンズの形成や、
政策的に、この分野における知財の専門家の育成、中小企業に対する国際出願の支援
を行うべきである。
1. 一般社団法人日本仮想通貨交換業協会(2018)「仮想通貨取引についての現状報告」
を見ると、世界で流通する仮想通貨は 1,500 種類以上あり、取引量は近年急激に増
えている。例えば、ビットコインの一日当たりの取引量は 2015 年までは 100 億円程
度で推移していたが、2017 年以降は 大で 3 兆円に迫る状況となっている。その中
で、ビットコインの取引の約 6 割は日本の投資家によるものと見られている。国内
でビットコインやイーサリアム等の仮想通貨で決済ができる店舗も増えており、
2018 年 3 月現在、国内でビットコインが使える店舗数は 52,190 店舗、イーサリア
ムが使える店舗は 80 店舗となっている(第 2 章第 3 節 1.)。
2. 仮想通貨の基幹技術となるブロックチェーン技術は、従来の決済の枠組みを超えて、
様々な取引のプロセスを媒介することができ、決済以外の用途も含む新たな市場形
成をもたらす可能性があり、少なくとも将来の市場を見据えた幅広い用途開発に取
り組んでいくべきである。
3. 実際に、決済以外も含むブロックチェーン技術の利用場面に関する特許出願を見る
と、2014 年まではほとんど出願がないが、2015 年から、「通貨の代替」のみならず、
「証券取引」や「ポイント・クーポン」、「サプライチェーン」、「ヘルスケア」、「スマ
ートコントラクト」など様々な利用場面を想定した出願が増加しつつあるところで
ある。さらに、「ゲーム内通貨」、「クラウドファンディング」、「チケット・ギフトカ
ード」、「不動産取引」、「為替取引」、「知的財産権」、「デジタルコンテンツ」、「投票」、
「偽造防止・真正性担保」、「貴重品管理」、「オークション」、「各種届出」、「広告・公
報」、「エスクロー自動化」、「デリバティブ」、「エネルギー管理」、「会社清算」などを
想定した出願も少ないながら見られ、幅広い利用場面が開拓されているところであ
る(第 6 章第 1 節 3.、図 6-42~図 6-43)。
4. また、仮想通貨による決済システムに使われるブロックチェーン特有の要素技術に
関する特許出願は、2014 年までほとんどなく、2015 年から急激に増加しているが、
中国籍の出願が突出してきている一方、日本国籍の出願は非常に少ないのが現状で
ある(第 6 章第 1 節 2.(4)③、図 6-35~図 6-36)。
5. 一方、決済以外も含むブロックチェーン技術の利用場面や仮想通貨による決済シス
テムに使われるブロックチェーン特有の要素技術に関する論文発表を見ると、2012
年~2013 年頃から発表が見られ横ばいで推移し、2017 年に急激な増加が見られる
(第 6 章第 1 節 3.、図 6-47)。特許出願では 2015 年以降はデータベース収録の遅
れ、PCT 出願の各国移行のずれ等があるため 2017 年以降の出願状況がデータからは
分からないが、論文発表の動向からすると、2017 年以降、より多くの出願がなされ
- 136 -
資料編
第7部
第6部 第5部
第3部
第2部
第1部
本編
要約
目次
第4部
ていると予想される。
6. 内容としては、秘密鍵の持ち方に関する「鍵の管理」、各ブロックに記録する取引の
記録の仕方や各ノードのデータの持ち方などに関する「データの管理」、「コンセン
サス」の方法に関するもの、パブリック型、コンソーシアム型、プライベート型など
「参加者構成」のさせ方、スマートコントラクトなどの「スクリプト記述」、「ブロッ
クチェーン間接続」、ネットワークに参加するノードやそれを利用するユーザ、扱う
トランザクション量の増加に伴うレスポンスの遅さ、トランザクションの処理遅延、
コスト増などへの対策を示す「スケーラビリティ」に関するものなどの出願が見ら
れる。
7. 仮想通貨に関する特許出願競争は始まったばかりであるが、日本国籍もこれら基盤
技術の蓄積を進め、国際的な地位の確保に取り組むべきである。
8. 特に、「鍵の管理」については、提言Ⅱ-1 で前述したのと同じく、仮想通貨やブロッ
クチェーン技術の決済以外も含む利用場面におけるデータの入り口となる部分でも
あり、技術蓄積を進める中で、「鍵の管理」の部分を担える体制を確保していくこと
が期待される。
9. ただし、ブロックチェーン技術では中小企業の参画も多い。中小企業にとっては、
個社では事業を守れるだけの十分な特許ポートフォリオを形成しにくい、知財のリ
テラシー不足や国際出願の経済的負担が大きいといった問題もある。特許を集団で
まとめ、取り決めた条件の下、使用できるようにするパテントプール/コモンズの
形成や、政策的に、この分野における知財の専門家の育成、中小企業に対する国際
出願の支援を行うべきである。
登録商標
Alibaba(アリババ グループ ホウルディング リミテッドの登録商標)
Alipay(アリババ グループ ホウルディング リミテッドの登録商標)
Cirrus(マスターカード インターナシヨナル インコーポレイテツドの登録商標)
Corda(R3 LLC の登録商標)
eBay(イーベイ インコーポレイテッドの登録商標)
Espacenet(ヨーロピアン・パテント・オーガナイゼーションの登録商標)
ETHEREUM(Stiftung Ethereum / Foundation Ethereum の登録商標)
Felica(ソニー株式会社の登録商標)
FinTech(フィンテックグローバル株式会社の登録商標)
freee(フリー株式会社の登録商標)
Garmin(ガーミン スウィッツァーランド ゲーエムベーハーの登録商標)
GitHub(ギットハブ, インコーポレイテッドの登録商標)
Hyperledger(ザ リナックス ファウンデーションの登録商標)
iD(株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモの登録商標)
Interledger Protocol(リップル・ラブズ・インコーポレーテッドの登録商標)
Interlink(ビザ・インターナショナル・サービス・アソシエイションの登録商標)
iTunes(アップル インコーポレイテッドの登録商標)
Maestro(Mastercard International Incorporated の登録商標)
MasterCard(マスタ-カ-ド インタ-ナシヨナル インコ-ポレ-テツドの登録商標)
Masterpass(マスターカード インターナシヨナル インコーポレイテツドの登録商標)
MUFG(株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループの登録商標)
nanaco(株式会社セブン・カードサービスの登録商標)
Netflix(ネットフリックス インコーポレーテッドの登録商標)
OK CASHBAG(エスケイ プラネット カンパニー リミテッドの登録商標)
Paidy(株式会社エクスチェンジコーポレーションの登録商標)
PatentSQUARE(パナソニック株式会社の登録商標)
Ponta(株式会社ロイヤリティマーケティングの登録商標)
QR コード(株式会社デンソーウェーブの登録商標)
QUICPay(株式会社ジェーシービーの登録商標)
RIPPLE(Ripple Labs Inc.の登録商標)
Suica(東日本旅客鉄道株式会社の登録商標)
VISA(ビザ・インターナショナル・サービス・アソシエーションの登録商標)
Visa Checkout(ビザ・インターナショナル・サービス・アソシエーションの登録商標)
WAON(イオン株式会社の登録商標)
WeChat(テンセント ホールディングス リミテッドの登録商標)
WeChat Pay(テンセント ホールディングス リミテッドの登録商標)
アリペイ(アリババ グループ ホウルディング リミテッドの登録商標)
おサイフケータイ(株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモの登録商標)
スマートコントラクト(株式会社来夢の登録商標)
タオバオ(アリババ グループ ホウルディング リミテッドの登録商標)
天猫(アリババ グループ ホウルディング リミテッドの登録商標)
ハルカス(近鉄グループホールディングス株式会社の登録商標)
微信(テンセント ホールディングス リミテッドの登録商標)
ビットコイン(株式会社bitFlyerの登録商標)
ペイパル(ペイパル インコーポレイテッドの登録商標)
楽天 Edy(楽天株式会社の登録商標)
平成30年度特許出願技術動向調査 -仮想通貨・電子マネーによる決済システム- アドバイザリーボード名簿
(敬称略、所属・役職等は平成31年2月現在)
委員長 岡田 仁志 大学共同利用機関法人 情報・システム研究機構
国立情報学研究所(NII) 情報社会相関研究系 准教授
委員 楠 正憲 Japan Digital Design 株式会社 CTO
杉井 靖典 カレンシーポート株式会社 代表取締役 CEO
轟木 博信 株式会社 Liquid 経営管理部長 弁護士
盛合 志帆 国立研究開発法人情報通信研究機構(NICT)
サイバーセキュリティ研究所 セキュリティ基盤研究室 室長
*委員は五十音順に記載
オブザーバ 中野 裕二 特許庁 審査第四部 電子商取引(データベース・言語処理)室長
木方 庸輔 特許庁 審査第四部 電子商取引(金融・決済)室長
月野 洋一郎 (前)特許庁 審査第四部 電子商取引(金融・決済)室長
緑川 隆 特許庁 審査第四部 電子商取引 主任上席審査官
関 博文 特許庁 審査第四部 電子商取引(金融・決済)先任上席審査官
塩田 徳彦 特許庁 審査第四部 電子商取引(金融・決済)審査官
杉浦 孝光 特許庁 審査第四部 審査調査室 副査
薄井 義明 特許庁 総務部 企画調査課 知財動向班長
小堺 行彦 特許庁 総務部 企画調査課 知財動向班 技術動向係長
衣笠 静一郎 経済産業省 製造産業局 製造産業技術戦略室 課長補佐
三島 崇 経済産業省 産業技術環境局 国際電気標準課 課長補佐
渡辺 雅 経済産業省 産業技術環境局 国際電気標準課 係長
村嶋 清孝 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構
技術戦略研究センター 電子・情報・機械システムユニット 研究員
*五十音順に記載 ○本調査の実施と報告書の作成に当たっては、本調査のために設置された上記委員から構成さ
れるアドバイザリーボードからの助言を活用した。