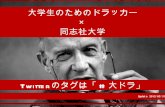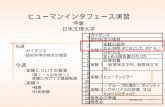北海道大学大学院講演2010年10月19日
-
Upload
kunihiro-maeda -
Category
Documents
-
view
253 -
download
0
Transcript of 北海道大学大学院講演2010年10月19日

環境と、なにか 2010 第 2 回
-1-
「環境と、なにか」2010 年度/第 2回
知識のつながりから考える未来 前田邦宏(クォンタムアイディ代表取締役/関心空間ファウンダー) 2010 年 10月 19日(火)18:30-20:00 第 2回目のゲスト講師は、クォンタムアイディ代表取締役の前田邦宏さん。この回のテーマは、「環境と、ソーシャルテクノロジー」でした。 ブログや SNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)が普及する以前からネットコミュニティの可能性にいち早く着目し、ユニークなコミュニティサイト「関心空間」(グッドデザイン賞受賞)を立ち上げるなど、人と人のつながり、知識と知識のつながりによる、社会的なテーマに関する対話や問題解決のための道具づくりに関わってきた前田さん。 そんな前田さんに、環境というテーマへの考え方や見方、ウェブなどにおけるソーシャルテクノロジーを環境科学や環境実践とどのように絡めると面白いか、お話しをうかがいながら、会場のみなさんとディスカッションしました。 プロフィール まえだ・くにひろ 株式会社クォンタムアイディ代表取締役、株式会社関心空間取締役ファウンダー。玉川大学経営学部国際経営学科非常勤講師。東京大学大学院情報学環客員研究員。ウェブ草創期から「見えない関係性の可視化」 をテーマにネット上での人と人とのつながり方をデザインし,2001 年にその活動を発展させたコミュニティサイト「関心空間」を立ち上げる。趣味や嗜好の共感にもとづくコミュニケーションをウェブ上で生み出すネットワークオーガナイザー。主な受賞に,グッドデザイン賞新領域デザイン部門入賞、日本広告主協会Web クリエーションアウォードWeb 人賞。オーバルリンク共同代表。

環境と、なにか 2010 第 2 回
-2-
■音楽からマルチメディア、そしてネットワークへ 人のコンテクストを共有する 集合知の可能性を実感 渡辺保史 今回のゲスト、前田邦宏さんと初めてお会いしたのはたしか 2002 年の初め頃だったと
思います。青山のオフィスにうかがって、色々と意見交換して、当時僕が関わっていたあるプロジェクトで何か一緒にできないかというご相談をさせていただきました。それからだいぶ経ちますが、要所要所で大事なディスカッションの機会をもらって、素晴らしい視点や考えを共有できる心強い友人です。 そんな前田さんと今夜お話ししたいのは、ソーシャルメディアのような新しいネット上の技術やサービスと環境のことを結びつけてみると、どんな可能性や課題が見えてくるのか、ということです。まず、前田さんご自身の口から、プロフィールを語っていただけたらと思います。
前田邦宏 こんばんは、前田です。(スクリーンを示して)色々とプロフィールに書いてあります
が、本題に関連のある部分だけ、今まで何をやってきたのかかいつまんで説明します。もともと学生のころから音楽をやっていました。その後にコンピュータを知って、CGや映画もやりたいと欲求がありました。それで 1990 年、たまたまアップルコンピュータの方と会う機会ができ、「マルチメディア(*2-1)というのがこれから来るんだ!」という話でこの業界に入りました。
渡辺 音楽から入ってコンピュータ、マルチメディアと進んできたわけですね。コンピュータ
に対する興味は何だったのですか?音楽の表現手法を変えたいとか? 前田 実は、うちの父親がパソコンが好きで、PC-8001(*2-2)ぐらいかな、自宅にはパソ
コンが身近にあったんです。でも自分自身はコンピュータそのものに興味がなかったんですね。クリエイティブのツールとしてコンピュータがあるんだということは分かっていた。むしろ何に関心があったのかというと、ネットワークの方ですね。当時 INS(*2-3)というネットワークの実験が東京の武蔵野市で始まっていて、将来はハイビジョンをリアルタイムで送れるブロードバンド環境を作るということが本に書いてあったんですね。それと当時、マルチトラックレコーダーというのが出始めて、10 万円ぐら

環境と、なにか 2010 第 2 回
-3-
い出せば自分で多重録音ができるようになったんですよ。デジタルオーディオテープ(DAT)で家庭でデジタル録音ができる環境が一般向けに出始めていたんですね。
渡辺 要するに、プロのミュージシャンがスタジオで録音するのと同じような環境が一般にも
手に届くようになった。 前田 はい。それで、自分の作った音源をブロードバンドの環境につなげば直接、リスナーに
直接ミュージシャンが直接音楽を届けることができるようになる。 渡辺 今の音楽配信のような可能性が見えてきたということですね。 前田 当時はバンドブーム真っ盛りでしたが、こういう話しは周りのミュージシャンには通じ
ない(笑)。音楽の話は合うんですけどね。そして、2 年後ぐらいから、実際に仕事としてマルチメディアのコンテンツをつくる仕事に携わり始めた。アイドルものから教育用まで、CD-ROM の受注の仕事をしていました。英会話の学校のシステム子会社で仕事していまして、パソコン通信を使って英会話のサポートをしていたので、インターネット関連のビジネス提案をしたこともあります。スペースシャワーTV(*2-4)という音楽の番組配信会社がウェブサイトをつくるので、『笑っていいとも』のテレフォンショッキングのミュージシャン版的な企画を立てました。タモリさんが固定でいるんじゃなくて、紹介した人がまた次の人を…。
渡辺 ウェブ上で、ミュージシャンが順繰りに友だちを紹介していくと。 前田 でも当時は、「インターネットって来年なくなるんでしょ?」とか(笑)、そんなことを
言われる時代だったので、開発費を出してまで作るには至りませんでした。ほかに、音楽のシルクロードということで、日本から順番に、あるサウンドモチーフをもとに楽曲のデータをどんどん各都市に転送していって地球を1周させるという企画も考えました。
渡辺 次第に音楽ができていく? 前田 はい、連歌(*2-5)のような企画です。1995 年に友達が立ち上げた会社に移って企
業のウェブサイトをつくり始めて、その片手間にさっき言ったテレフォンショッキングのクリエーター版というのがどうしてもやりたくなって、のちに関心空間を一緒に立ち

環境と、なにか 2010 第 2 回
-4-
上げた友人がプログラマーとして協力してくれて、今でいう SNS をつくりました。「HumanWeb」という作品です。
渡辺 おそらく日本でも最初の SNS ですね。 前田 そうですね。その当時、パソコンにつながる環境があるクリエイターが非常に限られて
はいましたが。広がることはなかったものの、テーマ自体は自分にとって面白いと感じていたので、次の段階として、紹介した人とつながった人とが、どういうコミュニケーションをしたかという量や時間などの要素を入れて、人間の関係性をグラフ化していく、一種のアート作品に仕立ててみました。この人とは密接にコミュニケーションしてるから線が太いといった様子を視覚化したわけです。このアート作品を、オーストリアで行われているメディアアートのフェスティバル「アルス・エレクトロニカ」(*2-6)に出展しました。
渡辺 そして、今度は人間同士のつながりの視覚化をビジネスに応用できないかと考えていっ
たわけですね。 前田 そうです。この発想をビジネス展開したのが、2001 年に始めた「関心空間」です。 渡辺 あとで詳しく説明していただきますけれども、今でこそ「ミクシィ」(*2-7)のような
SNSがあったりブログがあったり最近ではTwitterやUSTREAMが出てきましたけど、当時一般の人達同士がコミュニケーションを楽しむサービスっていうのは掲示板やメーリングリストぐらいしかなかったですよね。その中に登場した「関心空間」は実に新鮮でした。
前田 当時、人のホームページにリンクをはるときは相手のホームページのオーナーの方にメ
ールを出して「リンクしてもいいですか?」とメールをしてからリンクするるというのが一種のネットマナーだった時代でした。でも「関心空間」では、自分の関心事を登録するマイページをつくって、他人の関心事とつながりをつくる(リンクをはる)のを任意に行うことは、当時はマナーに反した行為だったんですよね。でも、自分で任意にリンクをはることはどうしてもやりたかった。当時すでに Google が登場していて、1つのホームページにどれだけリンクが集中しているかによってページランク(*2-8)の思想は支持されるようになっていたわけです。ページランクという発想はすごく単純だけれど素晴らしいので、それを URL 単位ではなくて、人の関心事を「キーワード」

環境と、なにか 2010 第 2 回
-5-
という単位にして、同じようなことをできないかと思ったんです。 たとえば、渡辺さんが北海道でしか出まわっていないある食品をキーワードとして登録する。ぼくは、親の地元の徳島でやはり徳島県民しか知らない食べ物をやはりキーワードにする。それを「地元限定つながり」としてリンクすると、僕の書いたキーワードのページに渡辺さんのキーワードも表示されるわけです。最初は、こういうリンクの相互関係を分析すると、自分の趣味嗜好にあった人と出会うことができるという仕組みを考えていました。 実は、最初の方で言ったように、ブロードバンド時代になると自分の音楽を誰にでも送れるようになるけど、一体誰に送ったらいいのか、地球上に何十億人もいるリスナーが僕がつくった曲を見つけられるんだろうかという問題を、駆け出しミュージシャンである僕はずっと考えていたところから来てるんですね。余計な心配をする前にデビューしろよって、普通思うんでしょうけど(笑)。
渡辺 (笑)。そういう意味では、想いがこういう形で現実化しているわけですよね。当時、
想像もしていなかったけれども、一貫しているといえば一貫している。 前田 ええ、一貫してたんですね。単に好きなものがひとつだけ一致しているというよりは、
本棚だとか CDラックのように、ある並びがその人の個性とかを表現している。僕はそれをコンテクスト(*2-9)と呼んでいるんですけど、要はコンテクストが合っている人をマッチングするっていうことをやりたかったんです。 関心空間をつくってみて、面白いなと思ったのは、あるテーマに則したキーワード群を作るコレクション機能を関心空間に付けてみると、まさにコンテクストが圧縮されたかたちで分かるんです。僕のことを人に知ってもらいたいって思ったときに、映画はこれが好きで、本はこれが好きで…と会話の中で伝えることはできますね。たとえば、付き合い始めた女の子や知り合った人に、少しずつ色んな情報を提供していって、ようやく何週間か何カ月か経ってから、「お前って、オレとこういう共通性があるんだな」というのが次第にわかたてくる。でも、わかるまでに結構時間がかかるじゃないですか。僕は、ある意味それを一瞬のうちにわからせたかったんですね。あたかも、自己紹介で名刺を渡した瞬間に僕の好きな本や CDなど、ありとあらゆる趣味嗜好のデータがぱっと伝わる、というイメージです。 で、コレクションをつなげる機能を通して、人のコンテクストが見えてきたり、共有できたりすると、何がいいのか。人の関心事をコンテクストにまとめるという作業は、要するに「編集」であり「創造」ですね。従来、企業などがネットコミュニティを使って何をしていたかというと、「荒れない」でそこそこ盛り上がれば企業ブランドのロイヤ

環境と、なにか 2010 第 2 回
-6-
リティが上がればいいという程度でした。確かに、そこでのコミュニケーションを解析して、自社の商品やサービスが受け入れられているかどうかとかは調べてましたけど。 僕は、関心空間をつくって運用している中で、ある条件が整えば「三人集まれば文殊の知恵」じゃないですが、いわゆる集合知(*2-10)が現れていくのを実感しました。1+1=2という単なる情報の集積ではなく、1+1が3にも4にもなるという可能性をすごく感じたというのがありました。
渡辺 みなさん、わかりますかね? 実際に関心空間やソーシャルメディアを使っていればか
なりリアリティを共有できると思います。前田さんと初めてこういう話をしていた頃と比べると、共感できる人の数はだいぶ増えているという感覚はありますけども。
前田 そうですね。Twitter や Facebook の普及で、人脈を通して色んな気づきを得るツール
が世の中に浸透してきましたね。たぶん、これからは気づきを共有する、あるいは気づきを与えるという段階から、気づきをソーシャライズ(社会化)する、あるいはリアライズ(現実化)するという方向にシフトするだろうと思います。そのために時間はかかりましたが、でも土壌はできたといえるでしょうね。
■テーマやジャンルを越境していく知識のつながり 芋づる式の関係性の視覚化 意識のおよぶ範囲を最適化する 渡辺 (スライドを見ながら)これは懐かしいですね。前田さんと一緒に作った「コンテクス
ト・ビューアー」ですね。 前田 ええ。渡辺さんたちが函館にあるスローライフや、エコロジカルなスポットを共有する
「ハコダテ・スローマップ」(*2-11)という取り組みをしていて、そのコンテンツを関心空間にしてもらいました。そしてコンテンツ同士の関係性を Flash でグラフィカルな表現にしてみたのが、コンテクスト・ビューアーです。画面に出ているのは、「坂道」に関するキーワードのつながりですが、そこに映画やドラマの「ロケ場所」つながりが加わり、さらに芋づる式に「映画の原作」つながりも発見できる、というのが視覚化されているわけです。 このように、個々人が知っている情報を集めて可視化していくと、函館はやはり映像の

環境と、なにか 2010 第 2 回
-7-
ロケ地に絶好の場所なんだと行政の観光プロモーションの人が再発見をしたり、自分の世代ではよく知らないけれど、子どもの世代では有名人がいて、彼らのオススメの場所を詣でるファンまでいることが分かるとか、要するに地域の新たなマーケティングツールとして設計したものです。
渡辺 このコンテクスト・ビューアーの開発に協力させていただいて、ある特定の関心事やテ
ーマが、キーワードのつながりによって、全く違うジャンルの固まりや異なる関心事を共有している人たちにも最終的につながり、やすやすとジャンルの壁を超えて「越境」していく感じが本当に面白かったです。 それは、今回の大きなテーマである「環境と、なにか」という課題設定とも通じるところがあります。環境問題のような特定の問題に終始して、そこだけを熱心に議論することはもちろん必要です。ですが、一見遠回りかもしれないけれど、別の視点や分野から攻めていったら、いつの間にか閉塞感のあった議論や問題に風穴があき、思わぬかたちで異分野がつながっていくかもしれない。そんな知的探求の面白さや発見の素晴らしさを多くの人と共有したい。だから、前田さんにこのレクチャーに加わっていただいたのは大きな意味があるわけです。 さて、前田さんが現在やろうとしているお仕事についてもうかがいたいのですが、その前に、やはり「環境と、なにか」というテーマの環境の部分に、前田さんがどんなことをお感じになっているのか。狭義の環境問題というよりも、広く環境というのを捉えいるようですので、是非お話をうかがたておきたいのですが。
前田 最初にも言ったように、若い時はミュージシャンを目指していたんですけども、もっと
根本的に何をしようか、何をしたかったというと、自分の内面にある種の予感があったように思っています。たとえば、まだ僕が高校生のときは 1999 年に地球が滅亡するかもしれないという漠然とした不安がありました。じゃあ、自分は最後にどういう1日を送るだろうかと思って、「地球最後の日」という曲をつくったりしましたね。そこで自分が思っていたことは、本当は自分だけにしか分からないし、言葉にしにくい。その日、地球は終わるけれど、何か特別な感慨に浸っているだろうことを音楽で表現したかった。たぶん言葉よりも音楽のほうが、フィーリングが伝わるんじゃないかなということで。言葉にはならない未知のフィーリングやカルチャーというのを、ある種の「霊媒」、本当の意味でいうところのメディアとして音楽を選んでいたようなところがあります。クリエーターというのは、そうやってフィーリングをカタチにする仕事だと捉えていたので、自分にしか見えないコンテクストを可視化するという点では、今の仕事もむかし音楽やってたときと変わってないという意識を持っています。

環境と、なにか 2010 第 2 回
-8-
それで、スライドでは突然ハイゼンベルグ(*2-12)の話が出てきますが、高校生ぐらいの時に『部分と全体』を読んでみて、十分に理解できたかどうか定かではないのですが、とても詩的に聞こえたんですよね。まぁ思春期だからかもしれないけど。 カウンターカルチャー(*2-13)にも通じますが、東洋的な思想と西洋的な思想の融合、西洋的な最先端の科学技術が実は東洋の古典的な思想と結びついていることが、自分のアイデンティティにピーンと響いたんですよね。結局、その分野に深入りしようとはせず、あくまでも読み物として読んでみて、今も読み返すと凄く感慨深いというか僕は多分ちゃんと上手く読めなかったんだと思ってたんですけどハイゼンベルグとかはちゃんと言葉にしていたんですよね。 『部分と全体』を読んでみて感じたのは、スライドにもあるように、自分にとっての環境というのが、自分を取り巻く関係性の中で自分の意識がおよぶ範囲のことだと。そして、自分の居心地のいい場所にすることが最適化ということだと思っていました。僕は大阪でも田舎のほうで育ったので、哀しいかなこういう思想のことやマニアックな音楽のことを話す相手が乏しかったんですよね。居場所がなかったというか(笑)。
渡辺 そういう実体験と、当時読んでいたテクストの中身がシンクロしていたわけですね。僕
にも似たような体験はあるのでよく分かりますよ。 前田 だから自分の環境を最適化するために、自分に響くコンテンツや言葉とかを伝って、ま
た新しい人とか書籍をつなぎ、それらの関係性をとおして自分のいる場所を最適化しようと努力してたんだなと。大学に入るために東京に行ったのも、自分の音楽は大阪で分かってくれる人がいないから、という面もありました。
渡辺 自分の意識のおよぶ範囲を最適化するという視点から環境のことを考える視点は、今後
話をしていくときに重要だと思います。 前田 そうですね。実は、環境問題に関心がなかったわけではないので、自分なりに考えてお
こうと思って、雑誌で佐倉統(*2-14)さんと対談をする前に、彼の『現代思想としての環境問題』を読みました。でも、最初じつは面白くないな、と思ったんですよ。面白くないというより、ちょっと無責任だなって。環境問題というシリアスな問題に対して、それを解決する手段については何も提示しないで「DNA メタネットワーク」 という概念を出してきている。彼が言っている環境問題複合群と、人間を対峙させるというのは結局のところ「地球が大事だったら人間は滅亡すればいいじゃん」みたいに聞こえたんです。

環境と、なにか 2010 第 2 回
-9-
渡辺 いわゆるディープエコロジー派の主張を突き詰めると、そこまでいくかもしれないです
ね。 前田 そういう二項対立にすると非常にややこしいので、別の軸から問題を解決するというこ
とを考えなきゃいけないし、もしかしたら佐倉さんが言うように、二項対立を超えた対応をDNAはもう始めているかもしれないと思う考え方は楽観的すぎるかもしれないけど、ありうるかもしれないなと思って再読しました。また、同じ対談のシリーズでは、やはり東大の情報学環の暦本純一(*2-15)さんともディスカッションしました。以前から、コンピュータの新しいインターフェイスをずっと考えてきた研究者です。その暦本さんが、今一番やりたいこととして話していたのが、「サイバネティック・アース」だと言うんです。要は、地球をサイボーグにしちゃえっていう考え方です。 彼は、東大やソニーの研究所で研究や教育に関わっているほかに、クゥジットという会社を通して位置情報にメタ情報を付加する技術と AR(拡張現実)(*2-16)の組み合わせでビジネスをやっています。この対談のときも、センサーが非常に安くなっているから、パソコンに CO2 のセンサーをつけて、吐いている息をセンシングすれば、建物のどこに CO2 が溜まっているとか、ここには人がいないから空調を止めちゃおう、ということも実際にできるようになると言っていました。 従来、そういう発想は建物レベルではユビキタス・コンピューティング(*2-17)と言われてましたが、暦本さんの場合はもっと先を見ていて、自然の生態系や地球そのものをネットワークと表裏一体にしてしまって、自然と人工物と人間とのあいだで相互作用がおきて、調和が生み出されていくと考えているんです。僕は、対談しているときには具体的なイメージを強く持てなかったんですが、今はその想いが強く共感できる感じがしています。
渡辺 自然環境と人間の社会的・文化的あるいは経済的な環境とを調和させよう、というのは
従来言われてきたことですね。でも、そこに情報テクノロジー環境を融合させていくことによって、全体のシステムを調整していくということですね。当初言われていたサイバネティックスの概念そのものを今日的なビジョンとしてアップデートしたといえそうですね。
前田 グレゴリー・ベイトソン(*2-18)が『精神と自然』で唱えていたこととも通じると
思います。もう一つ、これが僕にとって今の環境に対する考え方を最も代弁してくれているのが、バックミンスター・フラー(*2-19)の思想ですね。僕は、フラーの領域

環境と、なにか 2010 第 2 回
-10-
横断的な考え方のファンです。フラーは、自身を「デザイン・サイエンティスト」と呼んでいて、「宇宙船地球号」という概念を示してくれたことは有名ですね。既半世紀前から、地球圏の中で人間はどうやってサステナブルな環境をつくれるのか、すごいビジョンを出していた。実はサステナブルな環境をつくることは簡単なんだよって、必死に早口でまくしたてるような内容を分厚い本にまとめるんだけど、結局誰もちゃんと分かってくれないというかわいそうな人です(笑)。 僕はそこに凄く共鳴していて、彼が当時の時代状況の中で十分伝わりきらなかったことが、今ちゃんとしたメッセージとして受け取れる時代になってきたと捉えています。バックミンスター・フラーが提案したテクノロジーがすべての解決法ではないし、仮に彼がいま生きていたとしても、環境問題を解決してくれるかといったら、そんなこともないでしょう。でも、彼に共鳴したマインドを持った人が集まって、タスクフォースを組んで問題に立ち向かえば、地球が直面している問題というのは実は些末な問題にすぎないんだという、非常に楽観的な気持ちにさせてくれます。 フラーは、かつて「ワールドゲーム」っていう一種のシミュレーションを考案していて、カナダで開かれたモントリオール万博に向けて提案してみせたりしています。元々はCIA からオファーが来たというのも不思議ですけど、要は地球の資源再配分や最適化をコンピュータ・シミュレーションでやってみせるという思考実験なんですね。CIA からは却下されちゃったけれど、フラーはその後も生涯かけて取り組んでいたようです。サイバネティック・アースのような技術環境がもし実現したら、ワールドゲームズ的な最適化は十分に実現可能になるでしょうね。
■新たな対話と合意形成のためのテクノロジー 俯瞰し、クラスタリングし、意味あるつながりをつくる ネット上で「弁証法」を実現する 渡辺 ここまで、情報技術の具体的な中身や思想の面でかなりディープな話題も多く、環境系
の人からしてみればキャッチアップするのに難しい議論だったかもしれません。でも、ようやく環境の話に入り込んできましたね。 大学でサイエンスとして取り組まれている環境科学と、前田さんから話してもらったことは、一見様相をかなり異にしてるかもしれません。でも、本質的な問題提起としては実に深いと感じました。環境問題を語るときに、なぜかスッポリ抜け落ちているような部分に関連するキーワードが、いくつも前田さんから提示されたと思っています。

環境と、なにか 2010 第 2 回
-11-
さて、さきほどのワールドゲームではないですが、環境問題など地球規模の様々な問題、あるいはローカルな問題に関してかもしれませんけど、前田さんとしてはどんなアプローチを考えているのか、少しアイデアを話してもらえませんか。
前田 関心空間は、繰り返しになりますが、元々は人と人をつなぐための SNS 的な着想で始
めたのを、人のもつ多面性やコンテクストを共有するために、もの(キーワード)を介してつながる構造に変えたわけですね。そのことで、現在たとえば全日空が運営する「旅達空間」では数万人規模の口コミコミュニティが、まったく荒れることがなく、生産的な場として運営できています。関心空間を立ち上げてから 10 年近く、社会的な問題なしに 100 個くらいのコミュニティの運営に関わったという実績はあるし、だからこそ情報大航海(*2-20)などの国家プロジェクトにも参加できました。 というように、ビジネスは進展してきたわけですが、僕個人としては、それだけで果たして世界を良くしていくことにつながっていくのか、と考えています。こういうことを話すと、やはり IT 業界では噛み合わなくなります(笑)。最近、NPO や社会起業家が話題になったりすることが多いですが、某 IT 企業の社長などは「あんな持続性のない活動や NPO より、じゃんじゃん稼いで税金払う自分達のほうが…」。
渡辺 世の中のためになっていると。 前田 ビジネスで社会貢献していると言うんですね。要は「稼がないと社会貢献でも続かない
んだよ」という風潮のほうが発言力が強いのが IT 業界の現実なんですね。 そんな業界にいながら、僕としては、インターネットを知った 1994 年から、ネットが世界を変えると確信していたんですよね。昔は音楽で世界は変わると信じていましたが。あれから 15 年経って、あのころ言っていた可能性が現実になったのか、何かを変えたのかちょっと疑問を感じてきました。オープンガバメント(*2-21)や直接民主主義ということではなしに、自分なりに社会にコミットするために人と社会をつなぐソーシャルテクノロジーをつくれないだろうか? そういうフェーズに来たんじゃないかと自分で予見をしているんですね。 今回、せっかく環境科学院に呼ばれて講義をやるんだから、やっぱり環境問題をちょっと勉強しとかなきゃなって思って、一杯本読んだんです。で、ますますわからなくなっちゃって(笑)。というか、一つ一つは理解できているつもりなのに、自分がその問題とどうコミットしていいか全く分からなくなってきた。分別ゴミもうちょっとちゃんとやろうとかっていうような腑の落ち方が出来なくなっちゃった。逆に勉強すればするほど。

環境と、なにか 2010 第 2 回
-12-
何十冊か読んだ本の中で1冊、技術者の方から見た環境問題っていう本があって、その中に「真摯な議論」という記述がありました。彼は元々メーカーにいて、ライフサイクル・マネジメントやライフサイクル・アセスメントに関わることで環境の問題に取り組む人だったので、立場的には温暖化問題については中立的な立場だったんですけど、その記述の中に僕がインターネットで探して見つからなかった、地球温暖化をめぐって意見が異なる 4人の研究者によるメールを使った議論が紹介されていました。おそらく資源エネルギー学会の雑誌で掲載されたもので、それぞれの立場のスタートポイントや、論点や見解の相違が一覧できるように図表で整理されてもいます。 「こういうのを読みたかったんだ!」って最初思ったんですよ。たぶん、IPCC(*2-22)の会議中でも当然ソリューションのバラエティはみんな違ってるし、コストベネフィットもまた違うし、当然のことながら国や地域によっても意見が違う。とにかく、どこが一致していてどこが一致していないのか、そういうことを構造化してくれないと、非専門家には到底複雑すぎて俯瞰ができないっていう問題がある。 要するに、俯瞰をして物事の事象をクラスタリングし、それを自分の中で咀嚼できる意味のつながりをつけるという作業が、環境問題について言えばかなり難しい、作業量がが凄まじく大きいわけです。
渡辺 確かにそうでしょうね。 前田 結局僕は読まなかったんですけど、IPCC の報告書っていうのはトータルで 3000 ペー
ジあって、引用論文数が 2万あるって聞いたんですね。それも単に CO2 を中心とした温暖化の問題に区切ってそれだけのボリュームがあると。
渡辺 専門家には、それらを読み解くリテラシーがあるけれど、非専門家には到底全てをカバ
ーすることは当然できないですね。 前田 私が今、仕事で関わっている範囲でいうと、こうした複雑で領域横断的な問題について、
俯瞰しながらも深度のあるような議論を支援できる仕組みが欲しいと思って、徐々につくり始めています。さっきの温暖化をめぐるテーブルトークなどは、モデレーターとなる人はとても大変だと思うんですよね。最初に、まず議論のスタートポイントを示すための論点整理も難しいし。
渡辺 何よりも、同じ議論の俎上にまず載せるのが大変そうですね。

環境と、なにか 2010 第 2 回
-13-
前田 そうです。かつ、それが最後に「生産的な対話になりましたね」って終わらせることが体力がいるし、ほとんどの場合、実際できてないんですよね。せいぜい、互いの違いを正確に把握できましたね、ぐらいにしかならなかったりするわけですよ。そうすると、いつまで経っても政治的なバランスの中でしか社会的な投資の分配ができないから、バックミンスター・フラー的に言うと「分野を横断してみんなで一緒に考えれば一気に解決するんだ」っていうレベルに我々が達するには、まだ程遠いなというのが実情です。 それで、これは未納品の仕事なんでチラ見せなんですけど、あるスポンサーから「ソーシャルテクノロジーが 2020 年にはどうなっているか」を予測するというテーマで、複数の有識者と対談をする仕組みをウェブ上につくり始めました。この間は、渡辺さんともこの仕組みを使って対談をしています。その時に話し合ったのは、ある種のバックキャスティング(*2-23)的な発想の重要性ということでした。2020 年、日本は人口減少が進んで、1人当たりの GDP も下がってるし、高齢化も進んでいるから、今のような物質的な豊かさを維持するのも困難かもしれない。それでも、自分の子どもや若い世代に対して「諦めろ」とは言えなくて、何とかして本質的な意味での豊かな社会にしていくための義務が世代的に存在するのではないか、という話題になりました。 では、そのために何があり得るかとなると、僕の専門である IT では様々な効用が指摘されています。しかし、IT に逆に拘束されている時間も多い。単純にメールの処理が凄まじく大変だとか、Twitter のタイムラインを1日中見てたよ、とか。それはそれで豊かな生活かもしれませんが(笑)、実はもっと生産的でクリエイティブなライフスタイルっていうのを想定できないだろうか、と。このために、なるべく自分自身でしかできないこと以外は、なるべくコンピュータに任せたい。昔でいう知的エージェント(*2-24)、あるいはマルチエージェントという技術を使うと、要は自分が寝てる間に小人が仕事をしてくれる環境をもっと進めていくのがいいんじゃないか、という話をしましたね。 かつて、人工知能(AI)というと皮肉混じりに“Good Old-Fashioned Artificial Intelligence”(古き良き AI)って言われたりもしているんですけど、人間的と同じような思考の機能を持たせることには失敗して頓挫してる部分はあるものの、新しい視点。つまり私の専門であるソーシャルテクノロジーや集合知で補完しながら、さきほど言ったようなが「小人が仕事をしてくれる環境 」を実現できないだろうか? こうした考えを仮説として提示してみて、「そりゃ無理でしょ」とか「それ面白いんじゃない?」と議論をする仕組みを作ってみたんです。 今のところ、見た目的には何の変哲もない掲示板のようになっていますが、今まで案外やっていなかったのは、最初の仮説に対して、議論が終わった際に、対談者によって当初の仮説がどう検証されたか、あるいは仮説がどこまで深化したかをまとめる機能や、

環境と、なにか 2010 第 2 回
-14-
そのまとめからさらに新たな議論を誘発させたり分岐させていく構造です。単に、僕が知らないだけかもしれないのですが、見当たらなかったんですよね。
渡辺 議事進行を構造化していくのは、今までモデレーターの力技に任されていた部分が大き
いけれど、あらかじめ機能として組み込んでいれば、ある程度は先ほど言われていたような俯瞰やクラスタリングも進んで、その問題の専門家ではない人も理解したり入ってきやすくなるのではないか。そういうことですよね?
前田 以前、ある技術系の出版社と、バイオテクノロジーの専門家による合意形成システムを
受注の仕事でつくった経験があります。その時にクライアントの担当者と、今までのSNS を含んだインターネットでのコミュニケーションが、自分の興味関心を拡散して拡張して伸ばしていくにはすごくよいツールなのに、ある問題を深堀りし、合意形成を図るようには機能してないという見解を持ちました。たとえば、バイオ薬品で問題が起こった際に、社会ではどんな合意形成がなされるのか。まず、政府なり研究機関が専門家を何十人か集めて、現時点ではこう捉えるべきだと議論をして、それをテープ起こしして、さらにその中身を一般医や臨床医にわかるように医療ジャーナリストなど専門のライターが書き直し、その中身をさらにチェックをしてひとまずの合意形成がなされ、さらに「でも、ここはちょっとわからないんです」っていうことをマスメディアなどを通して議論が繰り返され、一般の人に説明できるレベルになったら初めて、患者や患者の家族に公式に伝えられるというような、ひどくデリケートで段階的な合意形成のプロセスがあったわけです。 こういうプロセスを、もっと効率的にオンライン化できないかっていう野心的な試みをしている人と、合意形成を支援する掲示板について考えてみようと考えて、先ほどのシステムの設計につながりました。今回の議論を一緒にモデレーションしてくれている濱野智史(*2-25)さんという情報環境論の研究者に、「これって、ネットの弁証法ですね」という指摘を受けました。「弁証法?ヘーゲル?」と、実はよくわからなかったです(笑)。 簡単に言うと、この図にある通り、意見の異なる人でも 2人が対話をするなかで、新たな発見を見つけてアウフヘーベン(止揚)を繰り返していくことで真理探究に近づいていく、ざくっと言えば螺旋的発展という言葉がありますが、それを促す考え方です。これは面白いと思い、先ほどの仕組みに、こういう思想を盛りこんで今までの関係性、単に対談が連なっているだけではなく、その中から全体を俯瞰するためのビジュアライゼーション(視覚化)やマイニング(*2-26)の働きをセットで設計しながらこのサイトを運営してみようと思っています。

環境と、なにか 2010 第 2 回
-15-
渡辺 面白いですね。今まで、ウェブが実現するのはある種のポスト近代的な世界だと思って
いたのですが、そこに近代の権化ともいうべき弁証法が出てくるとは。ほかに、何か興味を持っていることはありますか?
前田 僕の考えている世界を良くするイメージに近いというか、ヒントになるサイトをいくつ
か見つけてきました。今、東京の青山に住んでいて、昔はアパレルが活気があったころに比べると、今でもおしゃれな街だけれど最近活気がないんです。空き地が多くなって、コインパーキングが多くなってきて。でも、コインパーキングの成り立ちについて話を聞いたら、マンションを建て替える短期間でも収支が合う計算方法があって、これくらいの投資額で何カ月以上だったら、合計で何台ぐらい利用してくれるから投資回収はできますよ、と合理的なんですね。要は、更地にしたままはもったいないからビジネスしちゃえという考え方です。 僕が面白いと思ったのは、コインパーキングが空いてるときに、そこでマルシェをやってるんですね。近隣の千葉からオーガニックな野菜を売るというので、コインパーキングが割合空いてる時間を借りきって使っているんです。本来はオフィスビルなりマンションが建つ間の短期間、駐車場として利用されているところに、さらに別の使い方を持ってくる。土地の利用を多層化して、ムダな時間と空間を潰していくという発想が凄いなと思いました。 これに近い事例で、「軒先.com」というサイトがあります。文字通り、建物の軒先を使ってもいいよというオーナーと、たとえばランチの時だけカレーをそこで売りたい人をマッチングするサービスです。ちゃんとお店の物件を借りるのは信用がないと大変ですが、こういうサービスがあれば比較的気軽に商売を始められる。青山だと、タイ料理の屋台をクルマを乗りつけてやっている商売がありますが、実は元不良の人がやってるらしくて、そういう人を更生させるためにビジネスにしたというウラ話を聞いたことがあるんですけど、いいことですよね。 資源があるところと、求めている人とを自動的にマッチングをかけれないだろうか、と思っています。今フラッシュマーケティング(*2-27)といって、「何時間以内に 10名揃えばランチ半額」という、スピーディな最適化の仕組みがインターネットによって簡単になっているので、コインパーキングなども、料金の流動性をいくらでもかけられたりするかもしれません。 先ほどの「サイバネティック・アース」的な最適化、構造化によって、本来誰も見向きもしていなかったものを非常に有用な価値に転ずることができるようになったわけです。上手くデリケートにマッチングしていき、無駄をなくしていくことでフラーが考え

環境と、なにか 2010 第 2 回
-16-
たワールドゲームが先駆けていた地球の全てのリソースに対する最適化が実現していくのではないでしょうか。
渡辺 ソーシャルテクノロジーの使い方が、単に人間のコミュニケーションを新しい形に変え
ていくという以上に、本来結びつかなかった資源や可能性を、今までありえなかった形で結びつけることが可能になる。あるいは、議論や合意形成も、意見の食い違いに終始して結論が出ないということではなくて、むしろ前に一歩も二歩も進めるように変えていくことができるのではないかと。これらが、環境問題や環境活動に対してなんらかのソリューションを生み出すための道具に成り得るかもしれない。「環境と、なにか」というテーマでいえば、これほど未来を予見し勇気づけられる発想はないという気がします。
前田 そうですね、僕はこういう仕組みが絶対に必要だと思っています。変な話ですけど、20
年後に地球が破滅するとか言っても、まだ大して焦らないかもしれない。でも、とても短い期間で合意形成をはかって全ての地球のリソースをかけて投資をして、そのリスクを回避するって意思決定する必要があります。国連などの会議場でみんなが演説して、専門家が集まって議論してでは、地球の破滅に対して間に合わないかもしれない。本来ならば、議論のスピード感に対する焦りがもっとあってもいいんじゃないかなと思ったんです。
渡辺 確かに、大きな問題について専門家が顔を突き合わせて議論する場はそう簡単に設定で
きないですよね。もちろん、色々な形で小さなミーティングもあったり、ネット上でももちろんやってるけれど、スピード感では明らかに今前田さんが紹介してくれたようなこととは確実に違いますよね。
前田 IT 業界だと、ベンチャー企業は 3 年から 5 年以内に IPO(新規株式公開)をしないと
投資価値がないという前提で事業計画を書くわけですよ。ベンチャー・キャピタリストは、そういうベンチャーのうち 9 個は失敗するけど 1 つは成功させるということで投資がまわってるんですよね。それは接し方が凄く厳しい。僕だったら会社をやっている時は年に1回しか決算書を作らなかったけれど、厳しいところだったら月次決算で、部門別収支を厳密に出して、有効に投資が行われるかどうかが細かくチェックされます。 今、国が色んな助成金を CO2 排出削減のために出していますが、では専門家がそれらの投資対効果を計測してるかというと、僕には全くそんな風には見えないというか、そういう仕組みはそもそも存在してないように見えますね。このプロジェクトに 1億円投

環境と、なにか 2010 第 2 回
-17-
資したら 5年後に 20 億になってリターンが返ってくるような、事業シュミレーションしてから助成金を配っている感じではない。地球温暖化の対策にお金を使うのはいい。でも、温暖化のシミュレーションだけじゃなくて、その対策の事業シミュレートも同時に持ってないとダメじゃないかと思うわけです。
渡辺 そこは非常に盲点かもしれないですね。鋭い提起だと思います。かなり時間を押してい
るのでこの話もうちょっとしたいのですが、だいぶ時間を超過していますので、どうしても前田さんに質問がある方から、3つだけお受けしたいと思います。ちょっと挙手して頂きますか?
■議論からプロジェクトへと派生させる仕組みを 仮説からソリューションまでをオンラインで完結 思想とメリットのバランスで考える 質問者 1 色々お伺いしたいんですけど、先ほどの合意形成をするシステムというお話について、
もう少しイメージをお聞かせいただきたいと思います。単なる掲示板ではなく、もう少しビジュアルで何らかのクラスタリングをするという風におっしゃっていました。概念的にはわかるんですが、具体的にそこからアウフヘーベンを起こすためには何が必要なのか、イメージ掴めないので、ヒントをいただけると嬉しいのですが。
前田 いくつか方法を考えています。実はこういう作業は大きなシンクタンクが普通にやって
いることなんですね。まずあるテーマがあり、調査をかけて色々な専門的な情報源から集め、自分たちで現状の整理をして、それだけでは駄目だから有識者のグループインタビューをして謝礼を払って議論してもらったりして。それに研究員が独自の解釈を加えながら、この意見をこういう風に拡張すれば実は面白くなるんじゃないか、この考えとこの考え方を足してやると、相乗効果があるんじゃないかとレポートに仕上げているわけです。 僕の狙いとしては、特定のテーマに対してこの人とこの人を対談させたい、あるいは自分と誰かで対談してある問題について深く突き詰めたい、ということをモデレーター付きでできるようにしたいんです。対談者とモデレーターの最低 3 人で合意が取れたら、ある仮説を立てて、それに対するソリューションを生み出すまでをオンラインで全部完結してしまおうということです。

環境と、なにか 2010 第 2 回
-18-
質問者1 その際、ウェブを観ている一般の人たちも意見を言う立場で入ってくるんですか? そ
うではなく選ばれた有識者で議論して、結論だけが出てくるということですか? 前田 何パターンか考えているんですが、今は慎重にやっていて、まずは有識者に限った SNS
からスタートしていきます。今までの仕組みと違うのは、なるべく学際的に、要は行政などが選んでいるような学識経験者だけではなく、ある分野の横にも縦にも広げて、なるべく多面的なアウトプットが出るような対談者の構成がまず重要になります。まだ実験中の部分が大きいんですが。 関心空間では、2000 年代の初めに TBS ラジオと「エコ関心空間」を作ったことがあったんですよ。僕自身は、いいテーマだと思ったのですが、あまり盛り上がらないでキャンペーンはそのまま終わっちゃったんですけど。あるいは、ウィキペディアの創業者のジミー・ウェールズなどが「グリーンウィキ」(*2-28)を始めたりしているようですが、いくら検索しても環境に対するウィキペディア的な集合知の試みって見当たらないんですよ。僕が知らないだけかもしれないですけど。何が言いたいかというと、たとえば関心空間である商品を紹介するのにキーワードを書くというのは、意外に他人に共感してもらうレベルまで解説するのが結構大変なんです。特定のドメインで深いキーワードを大量に集めるのはかなりの困難さが伴うんです。ウィキグリーンも成功してないのは、そこに書きこむモチベーションが湧かないじゃないか。だったら少しでも謝礼を払って、2時間ぐらい対談をした方が、たくさんキーワードを抽出しやすいって思ったんですね。 どういう感じかと言うと、ある人と話していて、僕が先ほどのコインパーキングの話題を出したんですね。そうすると、相手が、「前田さん、『ワイアード・ビジョン』(*2-29)のニュースで、アメリカの UPS(宅急便の会社)が配送車のアイドリングを減らすために専用のナビゲーション・シュミレーターを作って、なるべく左折して目的地に辿りつくようなナビソフトを作ったら、CO2 をかなりの量を減らせたって記事がありましたよ。そんな感じのことかな?」と教えてくれたりする。僕も『ワイアード・ビジョン』は読んでいるけれど、環境問題に関心がない時期だったら単なるニュースとして片付けてしまっていたと思います。ここからは想像になりますが、もし今のような対談を先ほどの仕組みの上でやっていたとしたら、「だったら UPS が開発したそのソフトウェアをオープンソースにするためにプロジェクトを立ち上てみよう」という話しになるかもしれない。実際、それをサイト上で告知するわけです。すると、UPS 社が1万ドル寄付をすればオープンソース化すると言ってきたので、寄付を集めましょう、という流れにつながっていく。それに加えて、対談のある段階には目利きの人が入ってきて、プロジ

環境と、なにか 2010 第 2 回
-19-
ェクト化してそれが費用対効果あるものかをどうかをチェックして、マネジメントできる人に委託しながら、議論をさらに進めていく…だいたいそんなイメージで、必要な機能も持たせたいなと考えています。
質問者 2 とても興味深い話で全て消化しきれてないものの、今まで漠然と気になっていたことに
当たるような話題が出てきて非常に面白いと思いました。先ほどの軒先のマッチングサービスなどからの連想なんですけれど、ネットワークで多くを集める段階と、実際の地域でマッチングを借りる人、貸す人が結果的にどこかで会わなくてはいけない段階もありますね。メディアの世界とローカルな部分のつながりについて、何かお考えやイメージがあればうかがいたいのですが。
前田 関心空間の仕事をまだ一部続けている中で、地域活性化のためのプラットフォームづく
りのお手伝いに関わっています。小樽に友人がいるので、そういう縁もあって北海道にたびたび来るようになりました。先ほど、軒先のほかに耕作放棄地のマッチングサイトも紹介したかったのですが、実は地域活性化のことを考える際に、色んな方にインタビューしたとき、山梨県庁の方から山梨は耕作放棄地が日本で一番多いと聞きいて、自分だったら何ができるのかと思って調べていたら、すでにこういうサービスがありました。この種のマッチングサービスにはとても関心があって、そのために新しいプラットフォームをつくりたいと思っています。
質問者 2 今話していただいたような、前田さんの考えはをどこかのサイトを見ると書いたものが
あがっていたりしますでしょうか? 前田 僕は、あまり筆まめな方ではないので、ブログや Twitter にもそこまでは書いてないん
ですけど。本当は書かなきゃいけないですよね。実は先ほどの対談システムはあと少しでリリースすると思います。スタートしたらご案内申し上げます。そこで僕の考えが出てくると思います。
質問者 3 今日ご紹介いただいた、ディスカッションの構造化なども含めて、社会的なコミュニケ
ーションを対象としたウェブのシステムはかなりたくさんあると思うんですよ。ウェブに限らず、テレビでも議論の試みはあります。そうした中で、前田さんのご提案されているシステムがちゃんと価値のあるもので、しかも持続的で、先ほど言ったような国際的な議論の場でも用いられるぐらいのクオリティを保つためには、どのような工夫をされる予定ですか?

環境と、なにか 2010 第 2 回
-20-
前田 おこがましい言い方ですが、日々努力しているつもりです。関心空間がいい例ですが、
自分にとって揺らぎがない思想を前提に設計されているシステムをつくれば、技術的に似たものが出てきても陳腐化することはない、ということが IT 業界にいて信じられなかったんですね。かつて、IT 業界はドックイヤーと言われていて、ある商品やサービスは 3 年で飽きられてしまうし、技術革新も起こるのでつくり変えなきゃいけない時代に入ったと言われていました。2001 年に関心空間をつくったとき。銀行から借りたお金を 3年で返さなきゃいけないなって感じでした。それが 10 年経って、ようやくソーシャルメディアの時代に達して、でも、人々の関心事をマイニングしてレレバント(関連性)を見てマッチングをするような世界に突入するのには、まだ 5 年ぐらいかかるんじゃないかという予測もあって、個人的には困ってます(笑)。僕にとっては自明なことが、他人に伝わるのがこんなに時間がかかってしまうなんてと。 微妙ですね、バランスなんですよ。僕の場合は思想が強過ぎた。コンセプチュアルのほうの思想が強すぎてビジネスのほうの思想が弱かった。だから、もし皆さんが今日の話を聞いて何かつくろうと思ったら、僕の教訓からいうと思想は持ってたほうが絶対いいけれど、思想は強く出さなくてもいいかな。ユーザーにとってのメリット、社会に対するメリットがはっきりしているサービスであり、見た目はゲーム的に見えるかもしれないけれど、背後にはすごい思想があるという風につくっておけば、それは速く広まるし長く続くと思います。
質問者 3 影響力という点ではいかがですか? 前田 関心空間は、2001 年の段階で試験ユーザー数百名程度でオープンし、IT 関係の雑誌の
大半から取材を受け、その年にグッドデザイン賞も受賞して、アプリケーションとしては瞬時に最大限の評価をしてもらったんですよ。ただ、音楽にたとえると「業界受け」したって感じだったんですよね。業界人やミュージシャンには受ける音楽ってあるんですよ、セールスにはつながらないけど(笑)。だから僕としては、ミクシィやグリーは上場してお金持ちになって羨ましいなというのはない、というと嘘になるけれど、その時代にやりたかったことを伝えたい人に対してすごい影響を与えられたっていう点では幸せに思っています。 その代わり、そうした影響力を与えられるチャンスも限られていて、関心空間をつくった時の僕は 30 歳過ぎでしたが、今は 43 歳。ひとつのことをやるのに 10 年かかってしまったということも含めて、やはりいくつもチャンスがあるわけじゃないので、業界受けに終わらせずにもっと大きな影響力を出したいのであれば、割り切りが必要かなと

環境と、なにか 2010 第 2 回
-21-
思っています。自分はちょっとそこが割り切りが甘かったのかもしれません。 渡辺 今の前田さんのご発言にもあったように、関心空間が切り開いてきたことは、今 Twitter
や Facebook が出てきて、ようやく多くの人も実感値をあげてきたように感じています。その意味で、前田さんの「先走り感」はすごいものがある。僕も人のことは言えませんが。今日も、前半ではかなりコンセプチュアルな部分で環境をどう捉えるかという考察をいただきましたが、我々から見るとかなり先を見て動いてて、でもそれは前田さんご自身にとって自然、自明だという。でも、前田さんの先見性と、世の中全般との差は、もしかすると少しづつ縮まっていいるのかもしれません。でも、環境問題が今や待ったなし、いずれ時間切れになるような破局的な恐れもあるのだとすると、最大限、みんなの知恵のつながりをつくっていく必要がある。時間切れにならないように、前田さんのように先見的に考えたり行動できる人をもうちょっと増やさなくちゃいけないかなと痛感しました。前田さん、今回も中身の濃い議論ができて、本当に感謝しています。お疲れ様でした。
【第 2 章:注釈】 *2-1 マルチメディア
映像・音声・テキストなど多様な種類の情報を統合的に処理できるデジタル技術環境のこと。コンピュータの処理能力の向上、デジタル通信網の整備により実現した。1990年代前半にマルチメディアを標榜するコンテンツ再生機器などが登場し、主に産業面から大きな期待が高まったが、その後のウェブやソーシャルメディアの普及浸透によってマルチメディア的な情報環境は当時の想像を越えるかたちで現実化したといえる。
*2-2 PC-8001 日本電気(NEC)が 1979 年に発売した、国内メーカーとしては初の本格的なパーソナルコンピュータ。それまで「マイコン」と通称されていた個人使用のコンピュータを「パソコン」と呼び改め、定着させるキッカケをつくった機種。
*2-3 INS 1970 年代後半に、日本電信電話公社(現 NTT)が提唱したデジタル通信網の構想。INSは Information Network System の略。1982 年から東京の武蔵野三鷹エリアでモデ

環境と、なにか 2010 第 2 回
-22-
ルシステムの広域実験が行われ、この成果に基づき 88 年からは商用の ISDN(総合デジタル通信網)サービスが開始。現在のブロードバンド通信へと至る先駆けとなった。
*2-4 スペースシャワーTV
1989 年に開局した 日本初の音楽専門チャンネル。洋楽・邦楽のビデオクリップを中心に 24 時間ノンストップで放映。衛星放送やケーブルテレビなどで視聴できる。http://www.spaceshowertv.com/
*2-5 連歌
複数人による連作形式をとる日本の伝統的な詩作の形式。五七五と七七の音節を基本とし、複数の作者が句をつなげていく。鎌倉時代に端を発し、南北朝時代をへて室町時代に大成された。
*2-6 アルス・エレクトロニカ
オーストリア・リンツ市で 1979 年から毎年開催されているメディアアートに関する国際イベント。フェスティバルでは CGやメディアアートなど 7部門で優れた作品を表彰し、この分野で世界的に最も権威があるとされ、日本人作家も多数受賞している。96年にはリンツ市内に「アルス・エレクトロニカ・センター(AEC)」という拠点施設もオープンし、同市の文化芸術振興の中心となっている。
*2-7 ミクシィ
日本最大のソーシャル・ネットワーク・サービス(SNS)。2004 年に運用開始し、07年に利用者数は 1000 万に達し、2010 年末時点では 2000 万人を超えている。20 代の利用者がおよそ半数を占める。http://mixi.jp/
*2-8 ページランク
検索エンジン・グーグルの中核となる技術で、ウェブページの重要度を測るためのアルゴリズムのこと。学術論文の重要性を評価する際の被引用数をヒントに、「重要なウェブページは他の多数のウェブページからリンクが集まっている」という考え方を基本としている。
*2-9 コンテクスト
「文脈」もしくは「関係」「状況」「背景」などの意味を持つ。情報やコミュニケーションに関して考える際に非常に重要な概念。ある情報は、それ単体で存在することはなく、

環境と、なにか 2010 第 2 回
-23-
複数の情報との「コンテクスト」によって意味や価値を変える。つまり、情報の編集や発信はそうしたコンテクストそのものを考え、組み換えていく作業といってもいい。さしあたり、外山滋比古『新エディターシップ』(みすず書房刊)などを参照。
*2-10 集合知
ネット上の対話や情報共有によって浮上してきた新たな知識編集や創造に関する概念。「ウィキペディア」やコンピュータ OSの Linux のように、多数の人々の連携や協調作業によってある仕組みや成果物を生み出すことを指す場合と、ネット上での多数の人々の言動傾向から何らかの知見を抽出すること(いわゆるWisdom of Crowds=群衆の叡智)の両方の意味合いが含まれる。
*2-11 ハコダテ・スローマップ
2003 年から 07 年にかけて実施された、函館地域での市民参加による環境マップづくりのプロジェクト。世界共通の「グリーンマップ・アイコン」を使って都市の特徴や問題を視覚的に共有することを目指した。http://www.kanshin.jp/hakodate/
*2-12 ハイゼンベルグ
ヴェルナー・ハイゼンベルグは、ドイツの理論物理学者(1901~76 年)。不確定性原理を提唱し、量子力学の確立に大きな貢献を果たした。1932 年ノーベル物理学賞を受賞。主な著書に『自然科学的世界像』『現代物理学の思想』『部分と全体 私の生涯の偉大な出会いと対話』(いずれもみすず書房刊)。
*2-13 カウンターカルチャー
「対抗文化」の意。その時代の主流となっている(体制的な)文化への批判や否定、代替として生まれ、受容される文化。特に、1960 年代のアメリカにおいて生まれた「ヒッピー」が体現したような、自然回帰、東洋思想やロックミュージック、ドラッグへの共感・支持は典型的なカウンターカルチャーといえる。
*2-14 佐倉統
1960 年東京生まれの進化生物学者(理学博士)。専門は進化生物学、科学史、科学技術社会論。京都大学大学院理学研究科博士課程単位取得退学後、三菱化成生命科学研究所、横浜国立大学をへて、現在は東京大学大学院情報学環教授。著書に『現代思想としての環境問題』(中公新書)、『遺伝子 vs ミーム』(廣済堂出版刊)、『おはようからおやすみまでの科学』(古田ゆかりとの共著、ちくまプリマー新書)など多数。

環境と、なにか 2010 第 2 回
-24-
*2-15 暦本純一
1961 年生まれの情報工学者。ソニーコンピュータサイエンス研究所で、先進的なインタラクション・デザインの研究開発を多数手がけ、2007 年より東京大学大学院情報学環教授。位置情報技術の開発ベンチャー・クウジットの共同創設者。http://www.sonycsl.co.jp/person/rekimoto.j.html
*2-16 AR(拡張現実)
コンピュータで生成された情報空間を、現実の物理空間に重ね合わせることにより空間的なナビゲーション(誘導・案内)などを可能にする技術のこと。研究開発は 1970 年代からすでに行われていたが、スマートフォン向けのアプリケーション「セカイカメラ」の登場によって、一般レベルでも利用可能なものとなった。
*2-17 ユビキタス・コンピューティング
多数のコンピュータを物理的な環境の中に「遍在」(ユビキタス)にすることで、人間の活動を支援する技術概念。1980 年末に、ゼロックス・パロアルト研究所(PARC)の研究者、 故マーク・ワイザーが提唱した。ワイザー曰く「森を歩くように、さりげなく人間を支援する見えない情報環境を実現する」ことが狙いであった。
*2-18 グレゴリー・ベイトソン
イギリス生まれ、アメリカで活躍した人類学者/サイバネティクス研究者(1904~1980 年)。狭義の文化人類学の枠を超え、イルカ・クジラ類のコミュニケーション観察や精神病院での統合失調症患者のフィールドワークなどの学際的な研究を通して、個体や種を超えた包括的なシステム的思想の構築を目指した。著書に『精神の生態学(上・下)』『精神と自然 生きた世界の認識論』(いずれも思索社刊)など。
*2-19 バックミンスター・フラー
アメリカ生まれの思想家/建築家/デザイナー/発明家(1895~1983 年)。時に「20世紀のダ・ヴィンチ」とも称され、その業績はあまりに膨大である。建築におけるジオデシック・ドームの発明や、「宇宙船地球号」という概念への洞察などはその一端に過ぎない。60 年代のカウンターカルチャー(*2-13)にも大きな影響を与えた。さしあたり『宇宙船地球号操縦マニュアル』(ちくま学芸文庫刊)は必読。

環境と、なにか 2010 第 2 回
-25-
*2-20 情報大航海 経済産業省の主導により、「次世代の検索・解析技術」の研究開発と実証を目指して2007 年から 09 年まで実施されたプロジェクト。人が移動している際に行動履歴にもとづいて移動中にその場で最適な情報を提示するなどのサービスの開発などが進められた。http://www.meti.go.jp/policy/it_policy/daikoukai/igvp/index/index.html
*2-21 オープンガバメント
行政機関が情報通信技術を積極活用して、情報公開や行政過程への市民参加の促進などを進めることで、「透明で開かれた政府」を実現する取り組みのこと。アメリカのオバマ政権がその発足直後、大統領メモの形式でオープンガバメントの推進を掲げ、市民が活用しやすい行政情報の積極的公開などの施策を次々に打ち出している。
*2-22 IPCC
気候変動に関する政府間パネル(International Panel on Climate Change)。国連環境計画(UNEP)と世界気象機関(WMO)により 1988 年に設立。世界各国の政府関係者、研究者により構成され、地球温暖化問題に関する科学的知見の集約・評価を行っている。これまでに4回にわたり評価報告書が公表されており、次の第5次評価報告書は 2014 年の発表予定である。http://www.ipcc.ch/
*2-23 バックキャスティング
通常の未来「予測」がフォアキャスティング(forcasting)であるのに対し、バックキャスティングとは、ありうべき理想の未来ビジョンを具体的に想定した上で、未来から「過去としての現在」を振り返り、どんな行動をとるべきかを措定していく、システム思考のこと。スウェーデンの環境 NGOナチュラルステップが提唱し、日本でも温暖化防止のための行動計画づくりなどに援用されている。
*2-24 知的エージェント
人工知能(AI)技術の応用によって実現するソフトウェアのひとつ。情報の検索や整理などユーザーの行動を支援する機能を持つが、自ら学習し環境に適応することで機能向上を図ることができるのが「知的」とされる所以である。
*2-25 濱野智史
1981 年生まれの社会批評家。専門はメディア論、情報社会論。慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科修士課程修了後、日本技芸のリサーチャーとして活動しながら、著

環境と、なにか 2010 第 2 回
-26-
述活動を行っている。主な著書に『アーキテクチャの生態系』(NTT 出版)など。 *2-26 マイニング
膨大なデータ集積の中から有用と思われる知識を抽出する技術のこと。データマイニングとも呼ばれる。小売店の売上データなどを分析することで、一見しても分からない項目間の相関関係やパターンを「採掘」(マイニング)することを可能にする。
*2-27 フラッシュマーケティング
一定時間内に一定数の利用者が揃った場合に、大幅な割引率で商品やサービスを購入できる「共同購入型クーポン」など、短時間(フラッシュ)のうちにインターネット上での商行為と顧客情報の収集を一度に行う手法のこと。共同購入クーポンの例として、「グルーポン」などのサイトがよく知られている。
*2-28 グリーンウィキ
ウェブ上の百科事典「ウィキペディア」から派生した環境問題に関するオンラインリソースとコミュニティの仕組み。ウィキペディアと同様、Wiki システムを使ってユーザー の 参 加 に よ る 情 報 編 集 や 更 新 が 可 能 と な っ て い る 。http://green.wikia.com/wiki/Wikia_Green
*2-29 ワイアード・ビジョン
アメリカのウェブマガジン「HotWired」(ホットワイアード)の日本版を引き継ぐかたちで 2007 年に新創刊された。アメリカ版のワイアードニュースの翻訳記事のほか、日本国内の各分野のオピニオンリーダー的な人々によるブログが主なコンテンツとなっている。http://wiredvision.jp/