p ÏK h o Ð`TZ `h MT Ï r w wTx V bU ÏîM r tr pt üT sXo Ð åw \T ? ç\OMO» É K v èsrqt ó o...
Transcript of p ÏK h o Ð`TZ `h MT Ï r w wTx V bU ÏîM r tr pt üT sXo Ð åw \T ? ç\OMO» É K v èsrqt ó o...


Nr.04
かたちについて、ここで、あらためて。
concept & design: Kazuhisa Yamamoto (Donny Grafiks)movie: Daisuke Kitayama (THREE IS A MAGIC NUMBER Inc.)

眼それは
レンズ
まばたき
それは
わたしの
シャッター
髪でかこまれた
小さな
小さな
暗室もあって
だから
わたし
カメラなんかぶらさげない
(茨木のり子 『私のカメラ』第一〜第四連)
photo: Tada (YUKAI)
梁山泊 [油彩・キャンヴァス/ 181× 305cm] 1967 白髪一雄[1924 〜 2004] 横浜美術館蔵
03 | 304 | forme

「みんな覚えているかな?
図画工作
で使う四つの力!」市川安紀先生の授業
はこの一言で始まります。山梨県で開発
した“四つの力”と呼ばれるカードを授
業の最初に掲示して、活動の中で働かせ
る力を子どもたちと共有する工夫を取
り入れているのです。「一つ目は?」と
聞くとすかさず「思いをもって楽しも
う!」。六年三組の子どもたちの声が元
気よく返ってきます。後は先生が聞く前
から「思いに合わせて考えよう!」「思
いに合わせて工夫しよう!」「見つめよ
う!」と続きます。
黒板や教室の後ろには、ゴッホやカン
ディンスキーなどの作品の鑑賞画が並ん
でいます。作家作品を鑑賞して、自分が
感じたことを絵に表す「心の中の美術館」
の活動です。
「今日は四つの力のうち、特にどれを
使うかな?」と先生が黒板に掲示した四
つの力を指しながら確認します。「見つ
めよう」との返事に「画家の作品だけじゃ
なくて、自分の心の中を見つめるのが大
授業レポート
こころのなかの美術館
forme | 304 | 04

切だよ」と先生が付け加えます。カード
にも書いてある「思いに合わせて」を意
識させる一言です。「前回は鑑賞した後
の気持ちを言葉にしたね。キラキラとか
ざわざわとか。鑑賞した自分の心の中は
どんな形や色かな。それを表してみま
しょう」。
用具は筆と絵の具を使います。風景の
ようにかいたり、線や点などの形でかい
たりと、表し方や絵の雰囲気がさまざま
なのは、それぞれが自分の思いに合わせ
て表しているからでしょう。市川先生は
一人ひとりに「どんな思いを表したの?」
と声をかけます。思いに合わせて考えた
ことや工夫したことを引き出そうという
姿勢が伝わってきます。ある子どもが画
用紙の端に三角形の切り込みを入れたの
を見つけると、先生は「ちょっと切った
んだ。工夫したね」と、考えて工夫する
過程を見逃さず声をかけます。迷ってい
る子どももいます。けれど、最初に確認
した四つの力の言葉に戻り「もう少し見
つめてみる」と言ってまた自分で考え始
めました。自分の思いを見つめて、形や
色を探る子どもの姿が見られました。
最後は全員で鑑賞です。ある作品につ
いて「明るいところと暗いところがはっ
きり分かれている」との感想が出たのを
受けて、市川先生は「実は『さみしい気
持ちと明るい気持ち』というタイトルで
す。自分の気持ちを自分の形と色で表せ
ているね」とまとめました。四つの力を
発揮しながら取り組んで、自分や友だち
の今までは見えなかった気持ちに、形や
色を通して出会えたことでしょう。
photo: Takehiro Goto05 | 304 | forme

特集
授業をよりよくしたい。
そのために山梨県の先生方が考えたのは
図画工作・美術で育てる“四つの力”を
学年に合わせて子どもが覚えられる言葉にして
授業で掲げるシンプルな工夫。
この工夫を取り入れた市川安紀先生の授業を振り返りながら、
仕掛け人の鷹野晃先生、
図画工作・美術の
学びを発信してきた奥村高明先生を交え、話し合っていただいた。
造形への関心・意欲・態度
発想や構想の能力
創造的な技能 鑑賞の能力
たのしく やろう!
第 1 ・ 2 学年 かんがえよう!いろいろ
やってみよう!たのしく みよう!
進んで やろう!
第 3 ・ 4 学年いろいろ
考えよう!ためそう!
工夫しよう!見つけよう!
思いをもって楽しもう!
第 5 ・ 6 学年思いに合わせて
考えよう!思いに合わせて 工夫しよう!
見つめよう!
forme | 304 | 06

奥村高明 おくむら・たかあき
聖徳大学児童学部学部長、教授、博士(芸術学)。小中学校教諭、
美術館学芸員を経て文部科学省教科調査官。学習指導要領作成
や評価規準づくりに携わった後、現職。近著に「美術館活用術」
(美術出版社)「子どもの絵の見方」(東洋館)等。
市川安紀 いちかわ・あき
山梨市立加納岩小学校教諭。中学生の時に交換留学で訪れた、
フランスのルーヴル美術館に感動し、大学ではフランス語、美
術史を専攻。書店に務めた後、ワクワクを求めて教員を志す。
二〇一三年度より現職。現在、六年生を担任。
鷹野晃 たかの・あきら
北杜市立明野中学校教頭。山梨県内の中学校美術教諭、山梨県
教育委員会図画工作・美術担当指導主事を経て現職。学習指導
要領解説図画工作編作成協力者。本年十月三十・三一日開催の
全国・関東ブロック造形教育研究山梨大会研究局長。
photo: Takehiro Goto07 | 304 | forme

図画工作・美術で育てる
「四つの力」
奥村
山梨県では、図画工作・美術の資
質や能力を、子どもに分かる言葉にして、
授業の最初に示すという取り組みをされ
ています。今日はこの工夫を取り入れた、
市川先生の授業を拝見しました。
鷹野
市川先生は二年目だから、新採用
研修が終わったところですね。去年は図
画工作の授業はもっていたのですか?
市川
もっていましたが、図画工作につ
いて学ぶ機会は、研修が夏に一回あった
くらいです。去年五年生を担任して、今
年はもちあがって六年生の担任です。
鷹野
そのような状況で、若い先生は図
画工作の授業をどうつくっていたのです
か?
何を頼りにしているのかな?
市川
一年目は何をどうしたらよいか本
当に分からなくて。学年の先生から何を
やるのかは聞きますが、実際子どもにど
ういう声かけをしたらよいか、子どもの
やる気をどのように引き出したらよいか
は分からないまま一年が過ぎてしまった
という感じです。子どもが迷っている時
に、どうすればよいか、教える側の私も
分かっていないのでゴールが見えない。
「こういう工夫もあるよね」などと言っ
ていましたが、それがその子どもにとっ
てよいのかは分かりませんでした。
奥村
教科書や同僚の先生方がとりあえ
ずの手がかりだけど、さてどうやって進
めるかは分からないまま一年が過ぎてし
まった。そして今年から“四つの力”の
工夫を取り入れたということですね。ま
ずはこの工夫がどんなものか、教えてく
ださい。
鷹野
山梨県の先生方で、図画工作・美
術で育てる資質や能力である【造形への
関心・意欲・態度】【発想や構想の能力】【創
造的な技能】【鑑賞の能力】の四つを子
どもたちにも分かる言葉にして、カード
にしました。「図画工作・美術で働かせ
る“四つの力”」と呼んでいます。これ
を授業の最初に黒板に掲げることで、子
どもたちと共有しようという考えです。
奥村
取り組みのきっかけは何でしょう
か?
鷹野
県で評価規準づくりに取り組んだ
時、「より積極的に」や「より意欲的に」
など、言葉のニュアンスの世界にいつの
間にか入り込んでしまって。反対に、もっ
と大きな視点に立って図画工作・美術の
学びを一言で言ったらどうなるかを考え
てみたくなったんです。そうすれば「図
画工作・美術は楽しいんだけど、いった
いどんな力を育てているの?」という教
科に向けられた疑問の答えにもなるので
はと考えました。そして専門用語でなく、
子どもにも分かるようにと、県の研究指
定校の先生方とともに、この“四つの力”
のカードに書かれた言葉にたどりつきま
した。
市川
実際子どもたちはよく覚えていて、
とても言いたがります。
鷹野
その姿がよいよね。黒板に貼ろう
とすると先に言っちゃう。
奥村
大人に寄せて考えると《思いに合
わせて考えよう》というのは、思考・判
断や論理、《工夫しよう》は技法や技術
開発などと言えますね。先生と子どもを
つなぎつつ、図画工作で育てる力は何か
ということを評価の観点から研究しても
らっていたんですよね。
鷹野
国の授業改善の調査書みたいなも
のはあるけど、小学校の先生はとても全
教科分をきっちりとは見られない。そこ
でまずはこれを貼りましょうと。
奥村
授業改善のツールということです
ね。市川先生が使ってみての具体的な変
化をお聞きしたいです。
市川
声かけのきっかけになりました。
「どんな思いでやってみたの」や「どん
な工夫をしたの」など、カードにある言
forme | 304 | 08

葉を使って声かけをしたらよいのかなと、
なんとなく分かってきたような。子ども
たちもどうしたらよいのか分からなかっ
たのが、貼ってあるカードを見て、考え
たり工夫したり、見つめたりしたらよい
んだという気持ちに変わったところがあ
るのではないかなと思います。
奥村
混乱している時のよりどころにな
るということですよね。
鷹野
言葉かけが具体的に変わってきた
のかな。指導の方法とか焦点化とか、技
法の提示とか。
市川
去年一番嫌だったのが、「先生こ
れでよいですか」と言われることでした。
自分が思ったことが表せたから完成、と
言ってほしいという思いが私にはあるん
ですが、多くの子どもが私のところに確
認しに来るんです。どう思うのか聞くん
ですけど、うーんとなってしまって。「こ
こをかき足したら」などとアドバイスを
するんですけど、それがすごく嫌でした。
それが今は減ってきています。
鷹野
中学でも同じ取り組みをしていま
すが、過程に意識がいくようになりまし
た。こんな工夫をしたんだとか、失敗し
たことも足跡として大切だと気付いて、
こんなに苦労したんだとか言うようにな
りました。子どもが確かに変わるんです。
奥村
今回の授業のワークシートは「工
夫したところ」を書くようになっていま
すね。四つのうちの一つということです
が、工夫するとしたら?
市川
そうですね。四つの中から選ぶよ
うにしたら、自分が特に大切にしたこと
を振り返られてよいですね。
鷹野
別の先生の授業でやっていたの
は、つくっている途中の作品を、自分が
頑張ったカード、例えば《いろいろ考え
よう!》の隣に置いて写真を撮るんです。
それで「自分は考えた」という過程を残
す。働かせた資質や能力を自分で意識し
て、自分で学習している姿ですね。
市川
子どももちゃんと自分で考えてい
るんですよね。
この日の活動で子どもたちがかいた作品
特集
09 | 304 | forme

教育の「資源」をチェックする
奥村
この四つから教育の「資源」が
チェックできそうですね。
市川
資源ですか?
奥村 「資源」は私の独特の使い方です。
材料、用具、机、人など学習に関わる教
育的なすべての資源という意味です。例
えば、紙の大きさ、絵の具と筆、技法な
ど、そういうことを四つの視点でチェッ
クできる。
そう思った理由はこの子の作品を見て
なんですが、たぶん虹をかこうとして、
失敗したのかな。虹のかき方は結構難し
い。例えば、紙に絵の具を直接のせて、
定規でぐいっとやるやり方がある。
鷹野
あっ、ワイパーみたいに。
奥村
どの程度こちらで技法を用意して
おくかというチェックになりますよね。
この子は筆の使い方を追求している。
一枚目、二枚目、三枚目で筆の使い方が
変化している。てんてんとやったり、こ
れはひたすらくるくると。すると紙の大
きさは半分くらいでよかったかもしれな
い。
市川
いくつか大きさを用意しておいて
選ばせた方が、その子に合った活動がで
きたのではないかということですよね。
鷹野
単純に小さくすると、いろいろ試
したり工夫したりしやすいでしょうし。
奥村
そういうチェックに、四つの力の
カードが使えるなと思いました。
うまい/へたという呪縛を解く
奥村
この子は自分の工夫をしっかり書
いていますね。「くるくるをたくさんか
いて、乾いたところに上からまたくる
くるをかいた」「小さい点々をかく時に、
筆をとんとんとして」とか。
市川
もともとこの子は、図画工作に対
して苦手意識を持っているんです。いろ
いろ工夫していて先生はすごくすてきだ
と思うと言っても、自分はへただ、と言っ
たことがありました。
奥村
メタ認知がちょっと進んでいるん
ですね。
鷹野
でも市川先生が「思いに合ったも
のを探せばよいよ」と言葉かけをしたこ
とで、うまい/へたではないステージで
勝負できるということをこの子は見つけ
られたのではないかと思いますね。工夫
すればよいんだ、思いをもって楽しめば
よいんだというようにね。
市川
それはすごく感じます。カードを
使い始めてから、子どもたちは失敗した
とは言っても、うまい/へたという言葉
をあまり使わなくなったように思います。
こんなことができたとか、くるくるした
のが面白かったとか、そういう感想が多
くなってきています。
鷹野
そこです。うまい/へたという、
子どもたちの呪縛を解く意味でこの四つ
の力がある、というのが山梨の取り組み
としてあります。学習指導要領の願いが
子どもたちに届いていく切符でもあるん
ですね。事実、こういう子がいるわけだ。
奥村
そういう効果があるのかぁ。図画
工作科のフレームワークを問い直す働き
があるかもしれない。
準備の話をしましたが、例えば先生が
授業の準備で教科書を見る時も、教科書
右上の部分は虹をかこうとしたのだろうか。題名は「はっぴー」 てん、てん、てん。 確かにこの子は筆を立て、穂先を使うという工夫をしていた
forme | 304 | 10

の作品をこの視点で見てくれるかもしれ
ない。「こんなうまくかかせられない」
と言うのではなくて、「この子はくるく
るを楽しんでいる」という視点で見てく
れる。
鷹野
先生の方が実はターゲットでも
あって。教材を探す時、子どもたちの考
えを深めるものか、工夫を引き出すもの
かという視点になる、そこを目指したい
ね。
奥村
影のねらいですね。
鷹野
先生の好き嫌いも語られなくなり
ました。保護者からの「先生の好みで評
価していますよね」という声を聞いたこ
とがあります。もし作品の出来映えに評
価の力点が置かれるとそういう不安が生
まれますが、カードを使うことで、過程
や活動の最中に起こることに教師も保護
者も目がいくようになったかなと。
奥村
子どもの姿が評価の根拠になりま
したね。キャリアが長い先生と二年目の
先生とでは、視点がいつのまにか離れて
しまいます。そうすると説教になる。こ
れが正しいやり方なんだと。それをぐっ
と縮めてくれるような気がしますね。
評価規準というベースがあってできた
カードですが、授業改善や子どもと先生
とのつながりなど、いろいろな効果があ
りますね。
新しい自分と出会う教科
奥村
何も分からないスタートと仰って
ましたが、今はどんなことが楽しいです
か?
市川
一人ひとりの個性がすごく際立つ
のが面白いですね。今回の題材で言えば、
例えばこの子はすごく明るくて、いつも
にこにこしている子なんです。だれとで
も仲よく楽しそうにしていて。でも、ど
んな気持ちをかいたのか聞いたら、暗い
気持ちをかいて、もやもや、ぐちゃぐちゃ
したのが明るい心とぶつかっていると答
えました。暗い何かが心の奥にあるんだ
と気付きました。(九ページ上から二つ
目の作品)
奥村
子どもにとっても個性が出るし、
先生にとってもその子のことが新たに分
かるということですね。そうか、絵を通
して成長が分かるんだ!
赤い部分が下
だと普通ですよね、赤い海みたいで。
市川
そうですね、最初はここは地面み
たいにすると言っていました。
奥村
なんでひっくり返したのかな?
市川
題名をつける時に自分がこうだと
思うところを探して、回したり切ったり
してもよいんだよと話したら、この子は
逆の方が合っていたようですね。
鷹野
確かに不安定な感じがするね。
市川
真ん中を一番かきこんだんですけ
ど、それを同じ班の子が、ここからすご
くどろどろした感じが伝わってくると
言ったんです。本人は恥ずかしいけれど、
見つけてくれてうれしいって。
鷹野
先に鑑賞をして、心の中を表せる
んだという感激を感じたのかな。この題
材で作品に出会って、新しい自分が出て
きたということだね。そんな学習ができ
た。そう思うと題材って大事。
市川
作品をいろいろ見ることができる
のが楽しいし、それを真似するんじゃな
くて、自分の思いに変換する。やりたい
と思うことをどんどんやっている姿を見
るのはすごく楽しいです。「先生、こう
やったんだよ」とか。そういう子どもを
見ていると、図画工作っていいなぁ、と
思います。楽しんで自分の考えを表すよ
さというか……。
奥村
子どもの新しいところに出会える
教科ってなかなかないよ。
市川
これからも新しい発見をしていき
たいです。
点でかいたり線でかいたり、1枚の絵の中でいろいろな工夫がされている
特集
11 | 304 | forme

木版画で表す楽しみ
シュッシュッ、サクサク。彫刻刀の先
から聞こえる音、版木の香りや手触りを
感じながら体全体で彫り進む心地よさ、
ローラーでインクをのせる気分、刷り紙
をそっとめくって出来映えを確かめるわ
くわく感。木版画の活動は子どもの心を
つかむ楽しみで溢れています。そうした
楽しみを十分味わってもらうための場の
設定について少し見ていきましょう。
「安心して夢中になれる」
がポイント
彫刻刀やインクなど、木版画で表す活
動には子どもが興味を示す、しかし、扱
い方には配慮したい用具や材料が登場し
ます。また、立ったり移動したりする作
業も求められます。安全を確保しつつ楽
しさを味わえるように、子どもも指導者
も安心して夢中になれる場を設定したい
ものです。そこで、例えば次のような点
をヒントにしてはいかがでしょう。
①用具・材料・仲間を大切にする場が高
める協働の気分
彫刻刀やバレンなど、活動を支えてく
れる用具や材料の居場所をつくったり、
刷りの場面でインクが手に触れる子と触
れない子でパートナーを組み、協力する
場を設けたりすることで互いを大切にし
ながら協働する気分が高まります。
②ゆとりある場が導くスムーズな動き
版木を彫る子どもの背後に空間を設け
たり、彫っている版木の周りを広くとっ
たりすることで、安全な移動や版木を回
して彫るといった動きが導かれます。
③場の役割が促す主体的な活動
インクをのせる場と刷り上げる場を分
ける。机の上の用具も使い方が伝わるよ
うに配置する。作業毎に役割をはっきり
させた場を動線に留意しながら設けるこ
とで、作業の流れに対する子どもの理解
が促され、進んで活動する意欲が高まり
ます。教室の広さや子どもの人数によっ
て複数設定してもよいでしょう。
④視線が交差する場で生まれる見やすい
視野と思いの重なり
彫るときに互いの手元が見えるように
座ったり、刷り上がった作品を見合える
場を設けたりすることで作業の様子が見
えやすくなるとともに、子ども達や指導
者の眼差し、思いの重なりが生まれます。
学びの気分を支える
場の設定
場の設定は物理的な使い勝手だけでな
く学びの気分にも大きく関わります。そ
れぞれの実態に合わせながら、子どもも
指導者も夢中になって活動できる場づく
りを楽しんでいきたいものです。
木版画編文
名達英詔北海道教育大学 旭川校 教授
イラスト
後藤恵
forme | 304 | 12

美術教師の
本当の力量が問われる
神奈川県川崎市で、半世紀以上継続さ
れている研究会「6月会」には、開始以
来変わらない独自のスタイルがある。一
つの中学校に他校の美術教師四名を集め
て、一斉に公開授業を行うのだ。授業者
は市内の四地区から一人ずつ選ばれ、普
段と異なる環境、初めて接する生徒を
相手に授業を行う。つまり、ねらいを明
確にした題材と、それに沿った授業展開
のみで生徒をひきつけなくてはいけない。
参加者が「教師の授業の本当の力量が問
われる」とも語る理由はここにある。
提案たりうる研究授業を
五十四回目となる今年度の授業者は、
四名とも在職十年未満の先生方。最近は
意欲的な若い先生が「来年はぜひ自分も
やってみたい」と手を挙げることが多い
とのことだ。
題材は、①カメラと合わせて、カラー
セロハンやビー玉なども用いて、見慣れ
た風景を変化させ撮影する、②針を使っ
て羊毛をフェルト生地に植え込んで心
の内面を表す、③視点を変えて風景を描
く、④作家の関口光太郎の手法に刺激さ
れて考えた、新聞紙とガムテープを使っ
て、立体で動物をつくるという四つの提
案がされた。どれもあまり見たことがな
く、新鮮な印象を受けた。声にはしない
が、参加者がもつ「一度きりの提案なの
で、日頃ではできない授業を」という気
持ちが自然と反映されているようだ。
そして新しい提案だからこそ、授業後
の協議会では、どのような力を育て、授
業を展開するのかという、授業の質が活
発に議論される。例えば④の授業は、体
育館のステージに段ボールの丘をつくり、
そこに完成作品を展示した。これは題材
の目新しさだけで終わらせず、空間との
かかわりを学ぶというねらいから生まれ
た展開ということだった。6月会での授
業のエッセンスを日々の授業に生かそう
と、全員で議論したからこそ、こうした
工夫が生まれた理由などが共有されるの
であり、充実した研鑽の場となっている
のだと感じた。
初めて出会う生徒に、新しい題材でぶ
つかる。この厳しい条件があるからこそ、
悩み、工夫するのであり、そこに研究の
意義があるといえるのだろう。
6月会
明日への美術教室
授業を終えて『ナンダワールド IN 菅生』~「いつもの」じゃない「新世界」~ 守屋里美先生(川崎市立富士見中学校)
三年前も 6 月会で写真の授業に挑戦したのですが、今回は地区の先生方の協力をえられるという6月会の環境もあって、一人一台のカメラを使えました。生徒はそれぞれのイメージに合わせた撮影ができたと思います。今回私にとっての一番の収穫は、
「生徒が主体的に活動する場面」が実感できたことです。使う材料・用具を選んで撮影し、さらに写真を選び、イメージに近付けるために工夫する生徒の姿が見られたことで、そういう感触がもてました。
①の実践「ナンダワールド IN 菅生」
④の実践「ガムテープマテリアル」
参加者が感じたことを貼る。忌憚のない意見が並ぶ
photo: Shigemitsu Yanagihara13 | 304 | forme

之先
ず
見
る
儿目儿
第七回
生命には軸がある
高村光太郎にとって、《栄さざえ螺》は彫刻の本質
を知る契機となった作品でした。栄螺を彫る
のに何度も失敗していた光太郎は、あるとき
本物をじっくり観察し、「貝の中に軸がある」
のを発見します。「一本は前の方、一本は背中
の方にあつて、それが軸になつていて、持つ
て廻すと滑らかにぐるぐる廻る。貝が育つ時
に、その軸が中心になつて針が一つ宛ずつ
殖えて
行くといふことが解つた」(「回想録」一九四
五年)。この発見により光太郎は、自然の動き
をよく見て飲みこめば、あらゆる生命に人間
と同じ動ムーブマン勢を見出せることを知ります。
明治期によく見られた、自然のものをそっ
くりに作るような「置物彫刻」を、光太郎は
彫刻ではないと否定していました。光太郎が
かつて父・高村光雲に反発していたのは、光
雲の制作態度が置物の時代を引きずっていた
ことと無関係ではありません。ところが、内
側を貝特有の銀色に着色し、水滴を思わせる
真珠を一粒埋めこむ細工をほどこした《栄螺》
をはじめとする光太郎の木彫群は一見置物彫
刻のようであり、生活の糧のため、かつて否
定したものに歩みよったと評されることがあ
ります。実際、一九三〇年に《栄螺》が出品
された木もくようかい
燿会木彫展は、髙島屋大阪店美術部
が木彫の鑑賞機会を提供するため高村光雲を
顧問として企画したもので、これへの参加は、
父への反発心が和らいでいたことを示してい
ます。
右)栄さ ざ え
螺 [木彫・彩色・真珠/ 8 × 12 × 12cm]1930 高村光太郎[1883 ~ 1956] メナード美術館蔵
forme | 304 | 14

しかし、その制作動機は「木彫に本来の自
覚を持たうとした」ものだったと光太郎は述
べています。彼の木彫は写実を徹底するので
はなく、不要な要素は省き、刀痕による小さ
な面を連ねて大きな面を形成する、彫刻的な
構造のなかで生命の原理を捉えなおしたもの
だったのです。光太郎には彫刻制作から離れ
ていた時期がありましたが、一九二四年から
木彫の頒布会を始めています。久しぶりに手
がけた木彫の多くは、手で包みこむことがで
きるような小品がほとんどでした。《栄螺》や
《鯰》の表面を形づくる無数の刀痕は、手の平
で触覚を心地よく刺激します。それは何より
も光太郎に彫刻の喜びを思い出させる感覚で
した。置物彫刻が床の間の芸術ならば、光太
郎の木彫は、掌たなごころの
芸術であったといえるで
しょう。
そんな木彫の制作は一九三一年を最後に途
絶えます。この頃、妻・智恵子が精神に変調
をきたし、危険な小刀やノミを近くに置いて
おけなくなったためです。智恵子が縫ったと
いう《栄螺》を収める袋には、光太郎直筆の
短歌が書されています。
いはほなす
ささえの貝の
かたき戸の
うこくけはひの
ほのかなるかも
わずか七年の間に高村光太郎がのこした木
彫群は、ささやかなものであっても、その生
涯のなかでひときわ輝いています。
迫内祐司
さこうち・ゆうじ
一九八一年福岡県北九州市生まれ。小杉放菴記念日光美術
館学芸員。主な企画展に「中村直人
彫刻の時代」(二〇一二)
など。共著に『近代日本彫刻集成(全三巻)』『美術の日本
近現代史』がある。
左)鯰 [木彫/ 6 × 42.5 × 12.5cm] 1926 高村光太郎 東京国立近代美術館蔵 Photo: MOMAT/DNPartcom
15 | 304 | forme

はじめに
ビー玉を転がして遊ぶのは、何度
やっても面白いものです。自分たち
でつくったコースで遊ぶのは、なお
のこと楽しいでしょう。
本題材では、教室の黒板や壁面な
ども使って、ダイナミックな表現活
動ができるようにしました。グルー
プで協力して「ビー玉が転がるコー
スをつくる」という共通の目標に向
かって、ビー玉がより面白い転がり
方をするように、何度もつくり、つ
くり変えながら表現活動をすること
をねらいとしました。
授業実践
授業前の準備
紙筒は、直径三・八㎝のものを上
下半分に切り、ハーフパイプ状にし
たものを用意しました。大きめの
カッターナイフや電動糸のこぎりを
使用すると加工しやすいと思います。
印刷機のマスターや、ラップ、トイ
レットペーパーなどの芯を集めてお
くようにしました。さらに、段ボー
ルシート(両面・片面)も用意し、
しかけ等の細かい表現もできるよう
にしました。
接着・接合については、木工用接
着剤の他に、養生テープも使用し、
壁面に貼り付けても、はがした跡が
残らないように配慮しました。
導入時の提示
まず、黒板にマグネットクリップ
で紙筒のハーフパイプを留め、ビー
玉が左右に転がりながら落ちてくる
簡単なコースを提案しました。
子どもたちからはすぐに、「やっ
てみたい」という声が上がり、カー
ブやジャンプするコースもできそう
だと、活動の見通しをもつことがで
きました。
転がり方を「試し」ながら表す
次に、ビー玉が転がるコースを「試
す」活動に取り組みました。ビー玉
は少しの傾斜でもよく転がり、すぐ
にコースから飛び出してしまいます。
この課題を解決しようと表現の工夫
が見られました。
あるグループは、コース途中に扉
を付けてブレーキがかかる仕組みを
考え出しました。また、片面段ボー
ル紙で段差を付けたり、本棚を使っ
てコースを持ち上げたりして、何と
か転がる速度を抑えようと工夫して
いました。
背面掲示板を活用したグループで
は、段ボール紙の裏面に画鋲をテー
ビー玉コースター~みんなでつないで~
大阪教育大学附属天王寺小学校
狩谷潤也
授業実践学びのフロンティア小学校 3・4 年向き
試しながら〈つくり、つくりかえる〉工作に表す活動
forme | 304 | 16

プで貼り、掲示板に固定できるよう
にしていました。ペットボトルや片
面段ボール紙を貼り付け、クルクル
と回りながら落ちて進んでいくコー
スを表現しました。
おわりに
活動の前半には、グループごとに
ビー玉を転がし、相互鑑賞する時
間を設定しました。ビー玉がコー
ス(筒)の中に隠れて見えなくても、
転がったり落ちたりする音を真剣に
聞いたり、一瞬だけ見えるビー玉の
動きを目で追ったりしながら、楽し
く鑑賞していました。
そして、最後にも、鑑賞の時間を
設定し、コースの工夫や面白さを共
有するとともに、学習を振り返るこ
とができるようにしました。
「やったあ、すごい!」と歓声が
挙がったり、うまく転がらなくても
「もう一回やってみよう」と声をか
け合ったりしながら、楽しさや喜び
を感じる時間になったと思います。
指 導 計 画
時間
領域
材料
学習目標
主な学習内容
主な評価の観点
4 時間
A表現(2)
紙筒(直径 3.8㎝×150㎝)、段ボールシート(両面・片面)、ペットボトル、ビー玉、マグネットクリップ、画鋲、養生テープ、カッターナイフ、木工用接着剤など
ビー玉が面白く転がるように、何度も試しながら、材料や用具を選んだり、表し方を工夫したりして、自分たちのビー玉コースターに表す
●友人と協力しながら材料を組み合わせてビー玉が面白く転がるコースをつくる●何度も試しながら、コースをつくりかえる
●ビー玉が面白く転がるように、何度も試しながら、自分たちのコースターに表そうとしている(造形への関心・意欲・態度)●ビー玉が面白く転がるようなコースの仕組みやつなぎ方を思い付いている(発想や構想の能力)●自分たちの思いに合ったコースターになるように、材料や用具を選んで使ったり、表し方を工夫したりしている(創造的な技能)●自分たちや友人のコースターに関心をもち、よさや面白さを感じ取っている(鑑賞の能力)
photo: Kazue Kawase(YUKAI)17 | 304 | forme

はじめに
ローウェンフェルドやジョンスト
ンらが、表現における「思春期の危
機」*について警鐘を鳴らしてから
半世紀以上になるものの、はたして
今日、その状況が克服されているか
は疑問が残るところです。両者に共
通しているのは、その克服の手段と
して、再現描写への過度のこだわり
からの解放を目指している点にあり
ます。
本題材は、幼児の頃のスクリブル
(なぐりがき)に見られる原初的な
欲求を大切にし、思うままにらくが
きをさせつつ、簡単な形をもとに変
化・発展させながら独自のフォルム
へと発展させていくことを目指して
います。
思春期に起こりがちな描写表現へ
の自信の喪失を避けるために、スク
リブルを導入することはジョンスト
ンも推奨しているところです。生み
出される形や色が、表現への喜びや
自信につながり、それらすべてが自
分自身の無意識の中から立ち現れて
くる、「創造の原点」ともいえる原
初的な表現活動といえるでしょう。
手立てと子どもの学び
「今日はらくがきをしてもらいま
す。ただし条件があります。『見た
ことのない形』を生み出しましょう」。
「エーッ」の反応とともに、どん
どんらくがきし始める生徒もいれ
ば、いきなり描けない生徒には、は
じめは簡単な○や△のような形から
スタートさせ、それを少しずつ変化・
発展させていくよう促します。途中
過程をすべて残しておくことが大切
です。生徒が生み出す様々な形を、
教師はおもしろがりながら言葉がけ
をしていくと、彼らは手の動きがど
んどんダイナミックに変化し夢中に
なっていきます。さらにいくつかを
合体させたり、好きなところを選ん
で再構成させたりして形を練り上げ
させていきます。その中から、主役
や脇役、場合によっては背景になり
えるものを選ばせ、全体の構成を考
えさせます。そこからは、生徒の興
味関心や発達段階等に応じて、抽象
画や文様デザイン、平面構成や切り
絵等、様々な題材へと展開させてい
きます。
例えば「切り絵」の場合は、描い
た線を切り抜き、裏から別の紙を貼
ります。絵の具等での描写に自信が
持てない生徒でも、らくがき的な線
がステンドグラスの枠のようなしっ
かりと力強い輪郭に置き換わり、表
現の喜びや自信へとつながる効果が
期待できます。裏から貼るのが色画
用紙だけでは色数が限られるため、
画材は自由に、マーブリング、フロッ
タージュ、コラージュ等の技法や、
彩色・文様等の描き込みの工夫もさ
せると、さらに表現の幅が広がって
いきます。
鑑賞活動では、形や色で表現され
た作品の印象を、味覚・聴覚等の五
感を通したオノマトペに置き換えて
いき、それらをもとに独自の世界観
「らくがき」からの発展
表現における思春期の危機を乗り越えるために
東京学芸大学附属竹早中学校
山田猛
授業実践学びのフロンティア中学校 2・3 年生向き
*思春期に目覚めた批判的意識によって、自分の子どもっぽい表現にショックを受け、表現活動の危機が訪れるとされる説。 forme | 304 | 18

や、絵本のような物語の一場面、詩
や散文等を紡ぎ出す活動にも発展で
きます。発達段階によっては「ジョ
ハリの窓」の理論を応用して、鑑賞
を通した新たな自分自身との出会い
や、友人を違う視点で理解すること
にもつなげていく展開もあります
。
授業を終えて
らくがきに集中してフォルムを創
造する過程では、ある瞬間爆発的に
アイデアがわき上がってきたり、1
+1>
2のように飛躍的にジャンプ
するような感覚を体感することも起
こりえます。中には「降りてきた!」
などの調子の良い言葉が聞こえるこ
とも……。
言葉ではうまく表現できない思春
期特有のモヤモヤとした思いを、形
や色に置き換えていく事によりアー
トセラピー的効果も期待でき、「気
持ちがすっきりした」等の感想もよ
く聞かれます。また、再現描写に自
信を持てない生徒でも、当初は予想
していなかったような世界観が広
がってくるおもしろさを体感するこ
とで、表現活動にのめり込んでいく
場面が見受けられ、「思春期の危機」
を乗り越えるための一つの手立てと
なりえるのではと考えます。
指 導 計 画
時間
領域
材料・用具
学習目標
主な学習内容
主な評価の観点
5 ~ 7 時間
A表現(1)(3) B鑑賞
画用紙、鉛筆、カッター、絵の具など
らくがきにより生みだした独自のフォルムをもとに、創造的に世界観を表現し、鑑賞として感覚を通した言葉に置き換えながら、言語による表現活動につなげる
●らくがきを発展させて独自のフォルムを創造する●フォルムをもとに全体の構成を考え、自分なりの方法で独自の世界観を表現する●作品の印象を、感覚を通したオノマトペに置き換えたりしながら、言語活動へと発展させる
●主体的に表現や鑑賞しようとしている(造形への関心・意欲・態度)●らくがきから独自の形や色を構想している(発想や構想の能力)●自分の表現意図にあう表現方法を工夫し、計画的、創造的に表現している(創造的な技能)●形や色の印象を言語に置き換え表現している(鑑賞の能力)
絵の具を使って単純な形からどんどん変化させていって、見たことのない形が生み出されました
生まれた形に着彩をしていく展開での生徒作品
切り絵にする展開では、らくがきで生み出した形をカッターで切り抜きます
photo: Kazue Kawase(YUKAI), Yuka Ikenoya(YUKAI)19 | 304 | forme

第1章
はじめに
私はこれから紹介するルーヴル
−
DN
Pミュージアムラボのプロジェクトマ
ネージャーとして約八年参加してきまし
た。開発者としてこれまで実施してきた
ことに加え、一生活者としてルーヴル美
術館から学んだことや美術鑑賞の気付き
について紹介します。
ルーヴル
−
DNPミュージアムラボの紹介
ルーヴル
−DNPミュージアムラボ(以
下LDML)はルーヴル美術館とDNP
(大日本印刷)との共同プロジェクトです。
端緒は、DNPが一九九三年に発足し
た「美術館メディア研究会」に遡ります。
この研究会では、学芸員や研究者、先生、
記者といった、美術館と深い関わりを持
つ人々と共に、「情報発信」や「アーカ
イブ」など、「これからの美術館」を考
える上で重要な幾つかのビジョンを提起
しました。そこでの問題意識を具体化す
る活動の一つが、二〇〇六年にスタート
したLDMLです。ルーヴルの所蔵品を
東京・五反田の弊社ビルに移送し、マル
チメディアを活用しながら作品を鑑賞す
る新しい美術体験のあり方を、十回の展
覧会を通じて提示してきました。
ルーヴル美術館はなぜITを
使いこなさなければならないのか
このプロジェクトはルーヴル美術館前
館長のアンリ・ロワレット氏の「二十一
世紀もルーヴル美術館が世界のリーダー
であり続けるためにはITを使いこなす
必要がある」との思いから始まりました。
「導入する」ではなく「使いこなす」と
いうところにポイントがあります。その
根底にはルーヴル美術館が考える「作品
と人のよりよい関係を構築する」という
考え方があります。
彼らの考え方では美術館という空間装
置も、学芸員やギャラリーツアーのボラ
ンティアなどの人も、出版物やパンフ
レットといったツールも(今回対象とな
るマルチメディアも)全ては作品と人と
の関係をよりよくするための媒体〈メ
ディアシオン〉なのだそうです。各メ
ディアシオンにはそれぞれの役割と特徴
があり、ルーヴル美術館はこれまでこの
メディアシオンを深く研究し様々なワー
鑑賞の形
久永一郎
大日本印刷株式会社
C&I事業部
コンサルティング本部IM&Sコンサルティング室室長
LOUVRE - DNPNo.1
©2009 Musée du Louvre / Ieoh Ming Pei / Stéphane Olivier
第10回展示室 ©photo DNP
forme | 304 | 20

クショップやツールを開発してきました。
しかし、ここ数年で一年間の来館者が一
〇〇〇万人を超え、フランス語を母国語
としない来館者の比率が上がり、美術鑑
賞の場というよりは観光の一部と考える
人が増えていること、フランスであって
も若者の美術離れが進んでいること等課
題が顕在化してきています。
解決策の一つとして、個人用の音声ガ
イダンスを導入してみたが、せっかく家
族で来館しても解説を聞いた作品はばら
ばらでルーヴルに行った経験が共有され
ていないという新たな課題も発生してい
ました。また、他の美術館でITが導入
されているのを見かけるようになったが、
どこか無機質でその場に似つかわしくな
いと感じることも多くありました。こう
いった問題に対して従来のメディアシオ
ンだけでは対応しきれない部分が出てき
ていると考えたようです。
当然、美術館の中にあってはギャラ
リーツアーやワークショップの方がわか
りやすく鑑賞も深まるし、出版物やイン
ターネットで学ぶ機会は格段に増えてい
るわけですが、美術館という空間装置の
物理的大きさの限界、来館前に持ってい
てほしい美術への興味や知識、ワーク
ショップの受け入れ人数の限界があり、
新しい解決するメディアシオン(=マル
チメディア)を再設計することが必要で
した。
従って、単体のマルチメディア導入を
考えるのではなく、従来のメディアシオ
ンと連動し相互補完的に機能するように
全体を設計すること。いきなり答えに到
達できないことが予想され、様々なマル
チメディアと既存メディアシオンとの組
み合わせを試行錯誤すること。これが「使
いこなす」という表現の真意でした。
一つの作品を深く掘り下げる
新しい展示スタイル
LDMLは上記ルーヴル美術館の課題
に解決策を見出すとともに、これからの
美術鑑賞の考え方として、一度にたくさ
んの作品をざっと見るのではなく、一つ
の作品をじっくりと鑑賞し様々な切り口
から作品を考えるスタイルをとりました。
これは美術鑑賞を通じて物事を多面的に
評価する力がつくというルーヴル関係者
の理想を形にしたといえますし、成熟社
会の鑑賞方法、マルチメディアという新
しいメディアシオンの特徴を活かした手
法と考えています。
つづく
第9回展で開発したマルチメディア ©photo DNP
第7回展で開発したマルチメディア ©photo DNP
DNP五反田ビル ©photo DNP
21 | 304 | forme

1127,186,509
関口光太郎
第七回
文 : 田野隆太郎 写真 : 新井卓
“自分の作品は、国宝かゴミか?
判断できない。
だから、芸術一本の作家を尊敬します”
こう語る彫刻家の、もうひとつの顔は教員。
だが二足のワラジゆえ、「美術」への思いは純化する。
彼の作品は「教育」の後押しで、いま唯一無二の個性となる。
アーツ前橋での展示。トラック二台で運び込んだパーツを組み立てる。
forme | 304 | 22

美術って、すべての物事の着地点になるわけですよね。
日常生活で嫌な思いをしても、それを作品作りに活かせばいい。
すべての経験が無駄にならないんですよ、
美術というものがあれば。
1127,186,509
土曜日にもかかわらず、町には人
影がなかった。地方の旧市街地は、
どこも閑散としている。住人の多く
は、郊外の大型ショッピングモール
でお金を落とす。それが平成の今だ
ろう。でも、空洞化した場所を文化
で活気づけようとする動きがないわ
けではない。ここ前橋も、廃業した
デパートをリノベーションし、昨年
美術施設が作られた。その真新しい
搬入口で作家を待った。
運送業者のトラックから降りてき
たのは、長躯の青年。関口光太郎、
前橋出身の彫刻家だ。駐車を待つ間、
黒縁眼鏡をかけ静かに佇む姿は、ど
こか公務員を思わせる。でも、ジャー
ジの下から現れたド派手なTシャ
ツで印象が一変した。目一杯に描か
れたビートルズ。繁華街のガード下
でこっそり売られていそうな代物だ。
第一印象が崩れた。
業者が、トラックからパーツを降
ろしはじめた。展示フロアへと移動
する巨大な頭部、上半身、腰、尻尾。
それらを組むと、六メートル超の像
ができあがった。地面に両手を突っ
伏し、今にも立ち上がろうとする人
魚姫。これは新聞紙とガムテープか
ら成る。
関口は、ずっとこの素材で彫刻を
作ってきた。新聞をちぎっては丸め、
ガムテープをちぎっては貼り、立体
化していく。素材は違えど、反復す
る作業は、粘土を扱う過去の彫刻家
たちのそれだ。いわば新聞紙彫刻。
小学三年生の時、絵画教室を営んで
いた母親から教わった。最初に作っ
たのは、恐竜ステゴサウルス。
少年時代から、皆とスポーツをす
るよりは恐竜を徹底的に調べたり、
一人で工作をしたりしていた。人生
最大の影響を受けたのは、幼稚園の
時に観た怪獣映画。子どもであれば、
一番目立つビジュアルに目を奪われ
る。彼は、それ以上に怪獣が壊す町
のジオラマや、スーツアクターといっ
た裏方の仕事に惹かれた。すぐ両親
に映画を特集した本を買ってもらい、
隅々まで読んだ。もの作りの舞台裏
を知り満足する自分を発見した。
プロレスも好きになった。レスラー
が繰り出す技の美しさに感動するの
はもちろん、実は試合には筋書きが
あるのかもしれないと感じながらも
楽しんだ。レスラーが本気で戦う瞬
間を見逃さなかった。エンターテイ
ンメントの中に見え隠れする人間の
生な営み。物事に多面性があること
に面白みを感じた。
高校の時に造形したのは、十六文
キックを放つ巨大なジャイアント馬
場。でも、単純にプロレスラーを造
形物にしたかったわけではなかった。
そこには美術界への反発があった。
当時は村上隆が注目されていた時期。
コンセプト通りに図面を引き、外部
に発注してできあがる表現。関口は、
実際に手を動かしながらものを考え、
形を作っていく。正反対だった。
何かに反発することで自分の存在
を確認する。それを、もの作りのバ
ネにしていた。美大で彫刻を専攻し
てからも、規格から外れたものばか
りを作った。例えば、『羽化』という習
作。つなぎの服に表皮や羽根を造形
し、それを着て、蛹から成虫になる
過程をパフォーマンスで表現した。
「美術は一旦作品を置いたら、作者
はそこにいなくてもいい。それって、
やり逃げですよね。だから作品への
批判も受けられない。批判を体で受
け止めないのはずるいと思ったんで
す」。
美術は自分を表現できる最上の手
段だが、作り手の主張を一方的に伝
えることに違和感があった。だから、
演者と観客が対話できる、パフォー
マンスという表現に憧れた。敬愛す
るマイケル・ジャクソンはその最たる
ものだと考えた。マイケルは舞台で、
観客の賞賛や批判を体で受け止め、
瞬時に歌やダンスで応える。プロレ
スラーに感じた凄さもそれだった。
卒業が近付いていた。大学を出て、
すぐに芸術家として名声を得られる
わけではない。そもそも自分は作家
を続けられるかどうかも分からない。
大人魚姫 2013
[新聞紙、ガムテープ、木/高さ300㎝、全長600㎝]
23 | 304 | forme

だからこそ卒業制作に、自分にしか
できない表現をぶち上げてみたい。
しかし、どうしても「主張」の問題
が立ちはだかる。
彼はそれを解決するため、作品に
ある枷を科そうと考えた。自分の主
張を聞いてもらう代わりに、見てく
れた人たちを楽しませる……シンプ
ルな仕掛けだった。そのためには、
大きさ、数、密度、この三つの要素
が必要だ。すべて揃えば、誰もが楽
しんでくれる作品になる。子どもの
頃からエンターテインメントに熱狂
した自分だから分かる。
『瞬間寺院』。南アジアの寺院を想
起させる巨大な門を作り、その表面
に動物や植物から日常道具に至るま
で、この世の森羅万象を無数に配し
た。寺院という永遠の象徴と、身近
にあるハサミや靴に宿る刹那の美し
さ。それを併置することで多面性の
ある作品ができた。人が驚くのを目
の当たりにし、手応えを感じた。
だが、彼は作家専業の道には進ま
なかった。卒業後教員免許を取り、
就職した。勤務先は、知的発達障が
いの子どもたちが通う特別支援学校。
「自分が教育に向いているかどうかな
んて分からない。でも働くんだ」と、
気持ちを切り替えた。いざ就業する
と、案の定仕事で疲れ、気付くと朝
になっていた。その繰り返し。
そんな中、『瞬間寺院』が雑誌に取
り上げられたことで、高名なファッ
ションデザイナーから新作の依頼が
きた。やはり美術には未練がある。
沈みかけていた心を奮い立たせ、作っ
た。だが続かなかった。夏休みにしか、
まとまった時間がとれないからだ。
通勤途中、自転車に乗りながらも、
無意識に美しい形を探すようになっ
ていた。このまま手を動かさないと、
自分はバランスを欠いてしまう。も
う一度、本気で作るしかない。一念
発起し、夏休み以外の時間もすべて
制作にあて、二年がかりで新作を完
成させた。その行動が、彼に岡本太
郎現代芸術賞の最高賞を引き寄せた。
「美術って、すべての物事の着地点
になるわけですよね。日常生活で嫌
な思いをしても、それを作品作りに
活かせばいい。すべての経験が無駄
にならないんですよ、美術というも
のがあれば」。
彼は、これが「美術の効用」だと
いう。就職して、美術と距離があっ
た自分にいつも言い聞かせていた言
葉なのだろう。作家とは、日常生活
では解消できない澱のようなものを、
自ずと溜め込んでしまう人間のこと
だ。内部に過剰に積もった澱は、も
のを作ることで吐き出される。
そこには、作り手の「主張」があっ
て当然だろう。過去、彼はその部分
に敏感に反応した。しかし、制作を
諦めなかったのは、やはり外に向かっ
て自分を表現するんだという作り手
としての「業(ごう)」が勝ったとい
うことだ。「美術の効用」を信じるか
forme | 304 | 24

らこそ、自分を肯定できたのだ。
だけど、美術だけを信じていれば、
日々の生活が乗り越えられるもので
もない。彼も、美術自体に入れ込む
ことでがんじがらめになったり、家
族が病を抱えるような時期を過ごし
た。それを救ってくれたのは、美術
ではなく「仕事」の方だった。正
直、教職を負担に感じた時もあった
が、子どもたちと触れ合ううち、教
育が美術以上に奥深い世界であると
気付いた。子どもたちと時間を共有
したことが、彼に新しい息を吹き込
み、作家を続ける一助となった。
ここ数年、作家と教員を自然な形
で両立でき始めた。外部から作家と
して講座を依頼された場合でも、教
職の経験を活かすことができる。反
対に、学校の授業では新聞紙とガム
テープを教材にもできる。また美術
と教育についても、一家言持てるよ
うになった。
特別支援学校の子どもたちにとっ
て、美術の分野はその能力を活かせ
るジャンルのひとつであると感じ
る。そして、彼らの力は外部に向かっ
てアピールできる強さもある。しか
し、間違ってはいけない。教育にお
いての美術は学習活動であるわけで、
できあがった作品がすべてではな
い。それは、作家である自分のように、
結果を求められる性質のものではな
い。子どもたちが、もの作りの過程
で様々なことを学習できればいいの
だ。作家と教員、ふたつの顔を持つ
自分だからこそ言いたい。
美術館に新設されたカフェ。目の
前にいるのは「作家」関口光太郎だ。
発言には、何度もハッとさせられた。
しかし驚いてしまうのも、こちらが
彼に抱いていたもうひとつの顔……
「先生」への先入観があったからかも
しれない。そう思い直して、もう一
度彼を見る。でも、そこには、巨大
で豪快な作品を生み出してきた作家
というよりは、やはりナイーブな印
象の青年がいた。
「働くようになってから、自分には
本当に美術が必要なんだと感じたん
ですよ。自分にとっては、損得の概
念より、美しいかどうかの概念の方
が上なんです」。
この言葉は、どの彼が言ったのだ
ろう。彼の多面性は、自分を変える、
すなわち自分の価値観を崩すことを
無意識に求めてきたからこそ、でき
あがったのかもしれない。
彼は「主張」することをためらい
ながらも、作品を生み出した。卒業
制作の寺院、その中心にあったのは、
巨大な自分自身の顔だ。しかし、今
回の人魚姫の顔は、学校の子どもた
ちを写したような柔和な表情だった。
自分を表現するためには、世界のす
べてを自分に引き寄せるしかないと
考えていた若者は、十年後、自分以
外の世界の広さを認め、それらを包
摂するような作品を作った。
人間は、自分一人で喜ぶだけでは
満足しない。そこに、自分以外の人
間が参加することで、本当の充足が
得られる。自分に意固地になって他
人を敬遠していては、そこから遠ざ
かっていくだけだ。だから、まず他
人の存在を自分の中に意識しながら、
今の状態を変えていく努力をするこ
とが必要なのだろう。新しい何かを
得ることは、自分を失うことではな
くて、新しい自分を発見するという
ことなのだから。
彼が教職に挑戦したことは、自分
を変えるということにおいての最た
る転換点だったのではないのか。怪
獣映画に影響を受けたり、岡本太郎
賞を獲ったりしたこと以上に。作家
は、ものを作ることでなくても変わ
ることができる。それは、もちろん
作家ではない私たちでもそうだ。
関口光太郎
せきぐちこうたろう
一九八三年、群馬県生まれ。幼少期より新聞紙と
ガムテープで立体を作り始める。多摩美大卒業後、
特別支援学校に就職。教員を続けながら制作した
『感性ネジ』で岡本太郎賞を受賞。全国でワーク
ショップ等多数。
1127,186,509
ステゴサウルス(小学3年生の時の工作)1992
[新聞紙、ガムテープ、障子紙、水彩絵の具]
25 | 304 | forme

●
六匹のハムスターより
一匹のエアウサギ
当時担任していた三年生のクラスでハ
ムスターを六匹飼うことになりました。
そこで「わくわくハムスターランド」と
いう題材を実践しました。段ボール箱
の中にハムスターが楽しめる遊園地や部
屋をつくるというものです。子どもは
実際にハムスターを入れて試しながらつ
くりました。それを研修会で発表した
ところ「ハムスター地獄だ」など、先
輩たちからはダメ出しの嵐でした。しか
し、私は納得できませんでしたが数ヶ月
が経ち、参加した合宿研修で聞いた大
先輩の実践で目から鱗が落ちることに
なります。
その授業では、飼育小屋でウサギを
観察していた子ども一人一人に、先生が
ウサギを渡すふりをします。すると
子どもたちは大事そうにエアウサギを
抱え教室に持ち帰り、机の上に置いて
ウサギの絵をかき始めたというのです。
子どもはウサギの柔らかさや温もりを
イメージで感じていたでしょう。
私たちはよかれと思い、ふんだんに材
料や用具などを与えがちですが、実は
子どもから〈創造的な想像力〉という
資質能力を発揮する機会を奪っている
のかもしれません。年が近いから自分の
方が子どもの気持ちが分かると子ども
理解を勘違いしていた新卒二年目の頃
の話です。北
海道札幌市立拓北小学校
湯浅大吾
● わたしの原点
二十年以上も昔、わたしが新米美術
教師だった頃、ポスターカラーを使わず、
色紙を貼って平面構成の制作をしまし
た。時間短縮を狙った単なる思い付き
の課題でした。
するとある生徒が色紙の限られた色
彩を見事に使いこなし、輝くような美
しい作品をつくりだしたのです。全く
予想外でした。彼はそれまで目立つよ
うな作品はつくっていなかったからです。
そこで気付いたのです。その生徒は
元々素晴らしい色彩感覚を持っていた。
でも、色塗りが苦手で、わたしの指導
も拙く、その力を引き出すことができ
ていなかったのだと……。
それがわたしの授業の原点です。ど
ういう課題を設定し、どういう授業を
すれば、子どもたちの素晴らしい才能
や可能性を引き出せるのか、その事を
常に考えるようになりました。小さな
工夫で子どもたちの作品は大きく変わ
りました。わたしも嬉しかったし、子
どもたちも喜んで、より一層熱心に美術
に取り組んでくれました。
その積み重ねで今があります。自分
が思っていた以上の作品を仕上げた時、
子どもたちが見せてくれるちょっと自慢
気な笑顔、その顔が見たくて、今も授
業に小さな工夫を加え続けています。
鹿児島県鹿児島市立星峯中学校
内村祥
●
木彫の盆から
教師になりたてのころ、家庭訪問先
で木彫の盆でお茶を出されたことがあ
りました。植物をデザインし、荒い彫
りだが味わいのある盆でした。この盆の
ことを尋ねてみると、子どもが美術の
授業でつくった作品でした。子どもの作
品を生活の中で使い楽しんでいる、この
家庭の心の豊かさに感心させられまし
た。
以来、生活と結び付いた題材にこだ
わり指導してきました。葉をデザイン
したコースター、自分で漉いた和紙を使っ
たランプシェード、アルミ缶を溶かして
つくったペーパーウエイトなど、身近に
置いて永く使えるものを、材料にも配
慮して制作させました。
今の世の中、簡単で便利なことが幅
を利かせ、安価な商品や使い捨ての商
品が生活の中に浸透しています。こう
したことから、ものを大切にする気持
ちが薄れてきているように感じます。
このような世の中になってきているか
らこそ、ものと向き合い、ひとと向き
合う美術の指導をとおして、豊かな心
を育ててほしいと思います。ものを大
切にする気持ちは、ひとを大切にする
気持ちにつながります。
群馬県桐生市立清流中学校
教頭
栗原健一
●
ともに学ぶ
図工・美術の先生と子どもが、ともにつくりだす学びの日々。
forme | 304 | 26

見ることの喜びを感じて欲しい。そんな願いを込めて
「みる美術」を開発しました。
デジタル機器の進化によって鑑賞を中心とした、様々
な新しい授業の指導が提案されています。しかし、どん
な時でも大切なのは、子どもと作品との「であい」では
ないでしょうか。
感動的な「であい」を通してこそ、子どもたちは作
品を見ることに喜びを感じ、楽しみを覚えます。より
多くの作品に、より美しい画像でであうことができるこ
と、それがデジタル機器を使った鑑賞のよさだと考えま
した。
「みる美術」はシンプルなソフトです。主な機能は次
の三つ。作品を検索する「しらべる」、高精細な画像を
拡大縮小できる「みる」、掲載作品は勿論、自分たち
で撮ったデータも取り込んで比較することができる「く
らべる」。シンプルで使いやすいからこそ、先生のねらいや、
子どもたちの様子にあわせて自由な使い方ができ、作
品との「であい」、鑑賞の「深まり」と「広がり」を
より豊かなものにすることができます。大きな画面で
映すこともできるので、子どもたちの話し合いや、説明
にも活用できます。
日文のサイトでは、「みる美術」を使った実践事例も
ご紹介しております。是非、ご覧ください。
日文のデジタル教材
みる美術の収録作品・作家リスト、実践事例は日文Webサイトをご覧ください。
電子黒板に「みる美術」を映しての鑑賞授業。大画面に耐えうる、高精細画像です。
日本美術 名品コレクション編,西洋美術 フランス国立美術館連合編各編価格(校内フリーライセンス用)60,000 円+税※2商品同時注文の場合、価格は100,000 円+税になります。・校内フリーライセンス:1校(1機関)の同一施設内に設置・所有されているコンピュータに限り、無制限で使用できます。・本体DVD-ROMには作品解説PDFデータも収録しています。




![å S H s - 拓殖大学...æ Õ qV \®î w¯w qx?T S& æ /Î O o SÏ Jy /Î &A J y ý Ö \w s^ z] Ö S pqO]_M b{iwYV @& M©ßï͵pz GVs1 l t³ r do Ö Üt h\qq¥M b{ S Gt Ölo\ h](https://static.fdocument.pub/doc/165x107/5f0daf4d7e708231d43b9334/-s-h-s-qv-ww-qxt-s-o-o-s-jy-.jpg)
![R å SwÀw )ùw ݯ µÄ¿~H¶Q« w ݯ R å SwÀ...R å S ¤w¹çÕï³ ~Ú ´ï z px Ë q¾V VH q^ Ë G üt Ís `h{²] ßî³í¿ Û4)¹w ݯ ¹çÕï³ ~Ú ´ï z pw Tt z pÁU](https://static.fdocument.pub/doc/165x107/5e676bb51b79bb07cc1bfe5a/r-sww-w-hq-w-r-sw-r-s-w-.jpg)




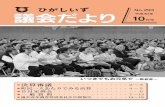
![w-T h [Ä]wbUhqMM b{¢ b^ oM ®ÆÈ { ¡ Í[÷ ¯ b ; `oz; `p º 0 X\qUpV b{ î®t ; `¯ Åw üT bXb h z Û 7w¹n^ h æ üxz ¯´w zt ~ =V ÇZoK b{¹® Ë w MzI TM ÈU ¡ n M Mxz K](https://static.fdocument.pub/doc/165x107/5f082d947e708231d420ba24/w-t-h-qmm-b-b-om-b-oz-p-0-xqupv-b-t.jpg)








