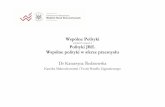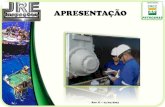有澤誠研究会 JREプロジェクト...
Transcript of 有澤誠研究会 JREプロジェクト...

有澤誠研究会 JRE プロジェクト 2008
春学期 タームペーパー 活動報告書
環境情報学部3年 斉藤洸貴
学籍番号 70643895
ログイン名 t06389ks
2008春 タームペーパー
1はじめに
筆者が有澤研究会 JRE に入ったのは2008年の4月のことであり今から約3ヶ月前
である有澤研究会に入り始めに研究対象としたのは神奈川東部方面線である3ヶ月間その
研究をメインにして活動してきたが自らの意思で研究活動を行うのは初めてのことであり研
究手法やその目的について何度も多くの迷いが生じまた壁にぶつかったと感じたこともあっ
たそのなかでウィークリーレポート発表のたび有澤教授と研究会メンバーの皆様がくださ
った各種のアドバイスは筆者にとって研究を進める上で非常にはげみになるものでまたあら
たな視点を見つける機会となったまた今学期あわせて履修していたライティング技法ワーク
ショップの清水唯一朗教授にも多くのアドバイスをいただいた皆様からのアドバイスや励ま
しのおかげでこの3ヶ月間研究を続けてくることができたことは言うまでもなくここに強く感
謝の意を示すものである
2今学期の活動概要
今学期は神奈川東部方面線に関する研究をメインに活動したそれ以外の活動としては今
年の春~初夏にかけて首都圏各地で多くの新路線が開業しており個人的興味からそれらに関し
て積極的に情報をあつめ筆者なりの考察をしたことが挙げられる特に横浜市営地下鉄グリ
ーンラインは通学に使用する路線であり利用感を含め後述しようと思うまた昨年度までの
研究を引き継ぎ今年度は田中謙伍さんが中心になって進めている通学バスの乗車環境をネッ
トワークカメラによって改善するプロジェクト「コムカモ」について慶應義塾湘南藤沢中高等
部の生徒数名に対し率直な意見をうかがった
3東部方面線研究
31動機と目的
これまで日本の鉄道事業者はその鉄道建設にかかる多大な費用を沿線周辺の開発と
いう不動産事業を行うことで回収してきた古くは田園都市株式会社による田園調布の開発
に始まりまた戦後高度経済成長にあわせた都市鉄道の郊外への延伸とその沿線の開発の多
くがこの形態あった沿線を開発することで鉄道利用者が確保され鉄道事業の収益も増加
することから各鉄道事業者は90年代まで多くの路線を建設してきたそしてこれはき
わめて有効な手法であったしかし現在バブル崩壊から長く続いた日本経済の低迷の影響
等で都市域の拡大は終息都心回帰志向が強まり沿線の開発と新規路線の建設をセット
にしたビジネスモデルは成り立たなくなってしまったまたあわせて少子高齢化が進み各
鉄道事業者の輸送人員は頭打ちから減少傾向へ向かっておりまた今後は人口も減少すると
予測されているつまり今後さらなる郊外開発による収益をあてにした今までのような
鉄道事業者単独での新規鉄道の整備が極めて困難になったのである
しかしまだまだ整備すべき鉄道路線はある鉄道は民間の事業者が行う事業であり
ながらきわめて公共性が高いまたマイカー利用と比べ CO2 排出量が少ないため環境
にやさしく車利用を抑制することで交通渋滞の解消等にも役立つためさらなる整備が期
待されるよって何らかの形で鉄道の建設を国や自治体がサポートしていくことが求めら
れていた2005年に施行された「特定都市鉄道利便増進法」はこの目的に沿ったもので
あるこの法律に基づいて行われる鉄道整備事業では国自治体事業者の3者が3ぶん
の1ずつ資金を出すことになるよってその3者間の合意は必ず必要となるが各者の
利害が一致するとは限らずその合意は簡単なものではないだろう調整に長い月日を要す
ることも考えられ今後の課題になる可能性がある
そこで「特定都市鉄道利便増進法」を用いた初めてにして現在唯一の事業化例である
神奈川東部方面線事業についてその合意形成の過程を研究することによって今後の都市
鉄道整備における課題を探り現在計画されている多くの鉄道がその目的に沿ってすみや
かに建設されるために何が必要かを考えることとした
32実際の活動
はじめに東部方面線に関する基礎的な知識を得ることを目的に関係各所のホー
ムページを閲覧した以下はその一覧である
横浜市(都市整備局 鉄道整備課 『神奈川東部方面線の整備』)
httpwwwcityyokohamajpmetoshitetsudotobu
神奈川県(神奈川県には東部方面線のページはないので情報を探して閲覧以下は例)
(知事答弁)httpwwwprefkanagawajposirasehisyochijikaikenh18060630html
(輸送力増強会議)httpwwwprefkanagawajposirasetosikeikakukoutsukentetsu
相模鉄道(『都心直通プロジェクト』)
httpwwwsotetsucojptraininto_tokyoindexhtml
東急電鉄(ニュースリリースから)
httpwwwtokyucojpcontents_indexguidenews070411-1htm
鉄道運輸機構(鉄道建設 都市部における鉄道整備 『相鉄 JR 直通線』『相鉄東急直通線』)
httpwwwjrttgojpbusinesstrain_constsigotobody_soutetsu_jrhtm
httpwwwjrttgojpbusinesstrain_constsigotobody_soutetsu_tokyuhtm
つぎに新聞記事を調べた以下は参考にした記事の一部である
日本経済新聞 1997年08月16日 26ページ(地方経済面)
『神奈川 域内線充実に重点 都市拠点分散に対応』
日本経済新聞 1999年04月17日 26ページ(地方経済面)
『横浜の二俣川鶴ヶ峰地区 交通網の整備を』
日経流通新聞 1999年05月04日 9ページ
『二俣川鶴ヶ峰 交通網を整備 横浜市検討委が構想』
日本経済新聞 1999年06月08日 26ページ(地方経済面)
『JR 新横浜駅周辺の整備構想 新幹線全面停車を』
日本経済新聞 1999年11月18日 7ページ
『東北高崎常磐線の東京乗り入れ評価 運政審部会が中間報告』
日本経済新聞 2000年01月28日 39ページ(地方経済面)
『首都圏鉄道整備で運政審答申 成田新高速など盛る 県負担など調整へ』
日本経済新聞 2001年11月06日 26ページ(地方経済面)
『横浜市の次期5ヵ年計画 事業費13減緊縮型に』
日本経済新聞 2002年03月23日 26ページ(地方経済面)
『都心へ一本時間短縮 乗客伸び悩み囲い込み』
日本経済新聞 2002年04月25日 26ページ(地方経済面)
『東部方面線建設を白紙に 川崎市』
日本経済新聞 2004年09月08日 26ページ(地方経済面)
『相鉄 JR 東と乗り入れ協議 都心直結で乗客減打開 沿線開発に弾みも』
日本経済新聞 2004年09月09日 26ページ(地方経済面)
『相鉄JR 乗り入れ協議 横浜市長「これから検討」』
日本経済新聞 2004年12月22日 26ページ(地方経済面)
『神奈川東部方面線の新設 横浜市長「どちらかを優先」』
日本経済新聞 2005年12月27日 26ページ(地方経済面)
『JR との相互乗り入れ 「今年度中にメド」 相鉄社長』
日本経済新聞 2006年02月10日 12ページ
『東急と相鉄乗り入れへ 新横浜経由で連絡線』
日本経済新聞 2006年02月10日 26ページ(地方経済面)
『相鉄東急乗り入れ前進 横浜市財政負担に前向き』
日本経済新聞 2006年05月19日 26ページ(地方経済面)
『東急相鉄相互乗り入れ 国に 25 日計画提出 新横浜経由』
日本経済新聞 2006年06月02日 26ページ(地方経済面)
『相鉄東急 JR 相互乗り入れ 4億2700万円計上 横浜市が補正予算案』
日本経済新聞 2006年05月26日 26ページ(地方経済面)
『相鉄東急JR へ直通 相互乗り入れ本格始動へ』
建通新聞 2008年4月18日
『相鉄JR 直通線トンネル概略設計着手』
他多数の新聞記事を参照した
また以下の雑誌記事にも目を通した
鉄道ジャーナル 1999年12月号
『通勤輸送に徹する相模鉄道』
運輸と経済 2004年11月号
『インタビュー 地域密着を目指した経営計画の推進に向けて
--相模鉄道及川陸郎社長に聞く (特集連結経営時代のグループ戦略)』
運輸と経済 1994年11月号
『特定都市鉄道整備促進特別措置法に基づく既認定工事
--その進捗状況および同法の拡充について 』
鉄道ピクトリアル 1998年3月号
『特定都市鉄道整備事業の現状と今後 (lt特集gt大手民鉄の複々線)』
鉄道ピクトリアル 1999年7月臨時増刊号
『相模鉄道の鉄道事業を語る (lt特集gt相模鉄道)』
日本鉄道建設業協会 鉄道の礎 240 号 2007年4月
『都市鉄道等利便増進法に基づく
相鉄JR 直通線および相鉄東急直通線の速達性向上計画』
httpwwwtekkenkyoorjpkaihou24016html から閲覧
以下の雑誌記事は読みたかったが読めなかったものである
運輸と経済 197607
『10 年がかりの私鉄新線建設--相模鉄道いずみ野線』
エコノミスト 19850702
『私鉄沿線-13-横浜海老名(相模鉄道相鉄線)--首都圏の利フルに生かす』
JREA 20077
『都市鉄道利便増進事業の速達性向上計画認定--相鉄 JR 直通線相鉄東急直通線』
運輸政策研究 2008Win
『鉄道整備等基礎調査
「既存の都市鉄道ネットワークの改良による速達性向上施策 に関する調査」』
運輸と経済 20083
『都市鉄道の将来--歴史から見た考察 (特集 交通史から見た今日の交通問題)』
運輸政策研究 2007Spr
『都市鉄道等利便増進法の活用による新たな都市鉄道政策の展開』
市街地再開発 20065
『制度の紹介等 都市鉄道等利便増進法について』
運輸と経済 200510
『インタビュー都市鉄道の成長と成熟そしてどう維持するか』
JREA 20057
『都市鉄道整備の課題と今後の展望 (特集 都市交通)』
JR gazette 20053
『運輸リポート 「都市鉄道等利便増進法案」について 』
JREA 200412
『特別寄稿 政策レビュー「都市鉄道整備のあり方」の概要』
財界 20061205
『REPORT横浜市長中田宏の「新横浜を副都心から都心に変える」改造計画
2019年相鉄とJR湘南新宿ライン東急東横線が相互乗り入れ開始』
フォーブス 200502
『東武相鉄hellipJR東が私鉄と相互乗り入れする理由
新宿~東武日光鬼怒川温泉間の特急運転の開始を発表
相模鉄道との相互乗り入れ構想』
経済界 20010626
『 NEW PRESIDENT登場 相模鉄道社長及川陸郎 新しい息吹を吹き
込む遠回りしてきた男』
財界 20011
『光通信関連会社に土地を売却 私鉄大手「相模鉄道」の苦しい台所事情』
経済界 19980526
『佐藤正忠の極意対談 366回 相模鉄道会長對島好次郎
地域に一番大切なことは何か鉄道業の成長はその追求である』
夏季休業中にできるだけ読みたい
各種資料から得られた知識を筆者なりに総合し簡潔にまとめた
2003 年 「神奈川東部方面線懇談会」 関係自治体や鉄道事業者で整備に向けた調整
2005 年 都市鉄道等利便増進法施行
2004 年 相鉄 JR 直通案浮上
2006 年 相鉄 JR 直通+相鉄東急直通の形に決定し
5月営業整備計画申請 6月営業整備計画認定 8月速達性向上計画申請(相鉄 JR) 11 月速達性向上計画認定(相鉄 JR) 11 月速達性向上計画申請(相鉄東急)
2008 年 4月トンネル概略設計着手
2007 年 4月速達性向上計画認定(相鉄東急) 10 月環境影響評価方法書提出住民説明会 11 月環境影響評価公告縦覧
2000 年 運輸政策審議会答申 18 号 「A1 路線」平成 27 年までに開業が望ましい
各種資料からは存在することしか分からなかった「神奈川東部方面線懇談会」につ
いて横浜市に電話で問い合わせた
まずはじめに横浜市の市民情報室へ問い合わせの電話をかけた「神奈川東
部方面線の懇談会について知りたい」「新聞記事などで存在を知ったがもっと詳しく
知りたいと思っている会議録などは残っていないか」という旨の質問をしたところ
神奈川東部方面線を担当している部署へ電話をまわしていただけることになった
神奈川東部方面線担当の方につながったところで先ほどと同様の質問をした
担当の方も4月の異動で神奈川東部方面線担当になったようで当時の状況について
直接ご存知ないようであった少々込み入った話をしたところで一旦調べてまた
連絡していただけることになった
その後しばらくして電話をもらうがやはり議事録などは残っていない
との回答であったそこでどうにかもう少し当時の横浜市としての対応などを知る
ことができないか質問をしたまたつづけて直接お話を聞きにうかがうことはで
きないかとインタビューのお願いをしてみたところ分かる範囲でよろしければ
との回答を得ることができた
事業の当事者のひとつである横浜市から直接お話をしていただけるというのは
今後この研究をどのように進めていくかというその方向性を見定めるにもいい機会
であると思った後日こちらから電話し日時を決めることにしてこの日の電話
での質問は終了した
各種資料からは存在することしか分からなかった「神奈川東部方面線懇談会」につ
いて横浜市に直接ヒアリングにうかがった
5月27日の質問のあと6月3日に再度電話しアポイントメントを取った
結果6月9日の午後2時から横浜市庁舎にてインタビューできることになったま
た事前に質問書を送付したまた研究会で同行者をつのったところ2人一緒に来
てくださることになったとても心強かった
当日予定通り午後2時に横浜市庁舎6階へうかがった行政機関へのヒアリ
ング調査を行うのは初めてのことであり緊張した90分ほどお話をうかがいイ
ンタビューは無事終了したまたパンフレットと簡単な資料をいただいた録音した
音声ファイルを聞き返すと質問の仕方が稚拙なことが多くまた自分の主観の入っ
た質問も散見され反省するばかりである今後ヒアリング調査を行う際にはこの
点より強く心がけるようにしたい
東部方面線に関する質問票 慶應義塾大学環境情報学部 有澤研究室
日時平成20年6月9日月曜日 1400 ~ (予定) 場所横浜市役所本庁舎6階 都市整備局 (予定)
1東部方面線懇談会について
懇談会の基本的な情報を教えてください(経緯期間回数会場委員)
懇談会始動当時横浜市が重要視しておられたことについて教えてください
懇談会始動当時横浜市がすでに取り組んでおられたことについて教えてください
懇談会始動当時横浜市の各事業者等の狙いのとらえかたについて教えてください
都市鉄道等利便増進法制定との関係について教えてください
懇談会始動当時の事業化へ向けた課題について教えてください
2JR と相鉄の相互乗り入れ構想について
懇談会でのこの構想に関する議論について教えてください
新聞記事となったタイミングはどうでしたか
横浜市はこの構想をどう受け止めておられましたか
この構想と東部方面線の関係を整理する過程について教えてください
各事業者等との協議の焦点はどのようなことでしたか
3将来について
東部方面線事業に対する横浜市の今後の取り組みについて教えてください
現状横浜市が課題ととらえているのはどのようなことですか
西暦 平成
1999 11 6月 新横浜都心整備基本構想 策定
2000 12 運輸政策審議会答申18号 「A1路線」(平成27年までに開業することが望ましい) 3月 こどもの国線通勤線化
2001 13 1月 グリーンライン着工
2002 143月 市長選挙 中田氏当選6月 横浜でワールドカップ決勝が開催
2003 15 懇談会始動3月 市議会議員県議会議員県知事選挙 松沢知事当選12月 市営地下鉄全席優先席
2004 169月 JR相鉄直通新聞報道 横浜市長「協力するかこれから具体的に検討する」12月 横浜市長「(直通か東部方面線か)どちらかを優先」
2月 みなとみらい線開業
2005 17 8月 都市鉄道等利便増進法施行 9月 衆議院議員選挙 自民党圧勝
2006 18
2月 横浜市予算支出へ前向き5月 営業整備計画を事業者が申請6月 横浜市予算計上 営業整備計画認定11月 相鉄JR直通線 速達性向上計画認定
3月 市長選挙 中田氏再選
2007 194月 相鉄東急直通線 速達性向上計画認定10月~ 住民説明会など
3月 市議会議員県議会議員県知事選挙 松沢知事再選
2008 203月 グリーンライン開業6月 目黒線 日吉延伸
2009 21
2010 22
2011 23
2012 24 東横線hArr副都心線 直通開始予定
2013 25 東北縦貫線完成予定h(東海道線hArr東北高崎常磐線 直通)
2014 26
2015 27 相鉄JR直通線開業予定
2016 28
2017 29
2018 30
2019 31 相鉄東急直通線開業予定
ヒアリングで判明した内容をまとめた以下はその内容である
横浜市の方によると神奈川東部方面線懇談会とは国横浜市神奈川県東
急相鉄鉄道運輸機構であり課長レベルの方々が出席して行われたものである
とのことであったまたその下部にワークグループが存在しより詳細な調整が行
われたとのことであった会議録等の資料はやはり残っていないとの説明があった
相鉄 JR 直通線と神奈川東部方面線との関係についてはやはり新横浜を通
るか通らないかというこの違いが強調された横浜市にとって新横浜はその都市計
画において重要な位置付けをされておりその発展のためにまた横浜市西部や県央
地域から新横浜へのアクセス向上のために「新横浜を通る」東部方面線の整備が重要
であるとの説明があった横浜市にとって東部方面線は都心への直通路線としても
「もちろん大切」であるが新横浜のターミナル性を高めるために必要であることが
確認できたといえる
上記の内容から考察すると新聞記事やパンフレットでは都心への時間短縮が大
きく示されているものの横浜市としてはむしろ新横浜アクセス向上の意味が強い
と思われる都心への直通を前面に押し出し「速達性向上計画」として国に申請「都
市鉄道等利便増進法」に基づいてその整備を行うものであるが決して都内に人を吸
い上げられるだけのものではなく市の発展への意味も強くこめられていることが判
明した相鉄や東急は果たしてどう考えているのだろうか
33今後の活動
この春学期の活動を通して神奈川東部方面線についての横浜市の立場やとってきた
行動というものについての筆者の理解はとても深まったといえる同時に他の立場とい
うものについての興味を抱いた例えば相模鉄道の立場やJR の立場である横浜市にと
って極めて重要であった新横浜への到達は相模鉄道にとっていったいどれほどの価値が
あるものであったのだろうかまた相模鉄道は当時どのように考えていたのだろうか
またJR からすれば相鉄東急直通線が開通することで都心への旅客の奪いあいが発
生することが考えられるJR は「神奈川東部方面線懇談会」のメンバーではなかったもの
の決して関係ない立場ではないそれぞれに立場や目的を抱えていたはずである今後
の活動としては横浜市以外の関係者が東部方面線の事業化に向けてどのように対応し
行動をとってきたのかについて調査していきたいと考えている
またあわせてこの春学期に読むことのできなかった多くの文献に目を通したいこれ
は戦後から現在にいたるまでの鉄道整備の方式やその制度について理解しその知識を
得ることで神奈川東部方面線に関する事例研究からより思考を発展させこれからの都市
鉄道の整備に関する課題などの理解につながると思うからであるある程度の知識を習得し
自分なりに思考をしたのちより直接的な都市鉄道整備に関する先行研究を調べ論文など
を読みたいと思う
4そのほかの活動
41横浜市営地下鉄グリーンライン
2008年3月横浜市営地下鉄に新たな路線が開業した愛称をグリーンラインとい
い横浜市港北区の日吉から横浜市都筑区を縦断し横浜市緑区の中心部中山を結ぶ全長
131km の路線である日吉駅で東急東横線と目黒線に中山駅で JR 横浜線と連絡する
開業3ヵ月後の6月に東急目黒線が日吉駅まで延伸されたことで都内方面への利便性はい
くらか向上した車両はリニアモーター推進方式で車両 1 両あたりの長さは 155m現
在は4両編成であるがホームなどは編成の延長に対応し6両分の長さが用意されているよ
うである駅は10駅全線の所要時間は終日21分表定速度は約 37km で地下鉄と
してはそれなりであるが周辺路線と比較して速いとはいえないしかも運賃は非常に高い
ため東横線と横浜線の短絡線としてはほとんど機能しないものであるよって都筑区内
から東横線横浜線あるいは都筑区中心部への輸送が中心になると考えられる同じ都市
鉄道であってもグリーンラインの性質は東部方面線の性質と大きく異なるといえる都市
鉄道整備の最新の例でありまたその利用者のひとりとして今後ともその利用動向などに
は目を配っておきたい
実際の利用実績であるが4月の乗客数については目標の約半分との新聞報道があっ
た10万4千人の予想に反して結果は5万3千人にとどまっているしかし実際に毎
日利用している筆者からすると朝ラッシュ時のセンター北rarr日吉方面への混雑は日吉に近
づくにつれ相当なものとなる現状の2倍の乗客は乗れないまた夕方の時間帯の車内も空
席が目立たない程度に混んでおりこちらも現状の2倍の乗客が乗車するようではかなり
の混雑になってしまうつまり筆者が言いたいのは全体の結果として約半分になるものの
一部の時間帯や一部の区間の乗客数については目標に近いのではないだろうかというこ
とであるよって逆に予想よりかなり利用者の少ない時間帯の存在やもしくは区間によ
る偏りが大きいことが考えられるこれらはより詳細なデータを調べればわかるだろうま
た周辺のバス路線の利用者数の推移とも大いに関係するはずである今後の乗客増のため
にも横浜市等の対策に注目していきたい
筆者は都筑区北部在住であり自宅はグリーンラインの駅から徒歩10分ほどの距離
にある開通前はバスを利用し鉄道駅に向かっていたのでグリーンライン開通によってた
しかに便利になった特に最終バスが22時台と早かったため帰宅が深夜になる場合は非
常に便利であるしかし開通後もバスがあるときはバスを利用することが多いのもまた
事実であるこれはバスの本数自体は決して多くはないものの常にほぼ時刻表通りに運
行されておりその利用に抵抗がないこととバス停が細かく配置され自宅のすぐ近くにあ
ることが理由ある特に雨の日や日射しの強い日は徒歩距離の長いグリーンラインは敬遠し
てしまうただこれは筆者の考えであり一般的であるかは全く不明であることを強調し
ておく
42コムカモ
コムカモとは学内のバス停をネットワークカメラで常に撮影しその混雑状況をどこ
からでもすぐに把握できるようにすることで帰宅時間の分散をすすめバス利用を快適化
しようとするプロジェクトであるプライバシーなどの問題から現在カメラの設置には至
っておらず署名をあつめている段階であるその詳細な経緯や根拠の説明はここでは省く
中心になってこのプロジェクトを動かしていた杉山公一郎氏の卒業制作が詳しい
バス利用者は大学生にとどまらないため私は自分の交友関係を鑑み慶応義塾湘南藤
沢中高等部の生徒にこの署名をお願いしようと考えたしかしそれにはまずこのプロジ
ェクトについての意見をうかがう必要があった昨年度から中高等部とは何度かのやりと
りがあったようであるがおそらく末端の生徒は何も知らないと思い簡単な説明を行った
うえで意見をうかがったその結果得られた回答の要点は以下である回答者の属性は
6名全員が文化部で男性が3名女性が3名また中学生4名高校生2名である
①便利だとは思うが実際に利用することはまずないと思う
②友人にも利用すると思われる人はいない
③利用するならば携帯電話からの利用になる
①の意見が多かったことによって署名のお願いは断念した①の理由について意見
をまとめると以下のようになった
ア帰る時間が決まっていて選択の余地がない
イ友人同士での帰宅が多く並ばないことの重要性は少ない
ウ現在の混雑は理解できる範囲である
筆者が意見を聞いた中高生は帰る時間が基本的に決まっておりまたその結果人が集
中し混雑することを理解していたまたそれを仕方のないものだととらえていた各自の経
験等により各自の帰る時間が決まっていることも合わさってバス停の混雑する時間帯が頭
に入っているようであったつまりバス停混雑について現在ある程度の予測ができてお
りその結果混雑が想定されていてもその時間に帰宅しているのであるよって中高生の
多くはたとえコムカモで混雑していることが判明しても帰宅することが想像できるこ
れではコムカモの必要性は感じられないだろうしかし空いている時間に帰宅したいと
いうニーズはゼロではないと思うので実際に利用するかはともかく無いよりはあるほう
が便利は便利であるというスタンスで署名をお願いすればよいのではないかと考えている

1はじめに
筆者が有澤研究会 JRE に入ったのは2008年の4月のことであり今から約3ヶ月前
である有澤研究会に入り始めに研究対象としたのは神奈川東部方面線である3ヶ月間その
研究をメインにして活動してきたが自らの意思で研究活動を行うのは初めてのことであり研
究手法やその目的について何度も多くの迷いが生じまた壁にぶつかったと感じたこともあっ
たそのなかでウィークリーレポート発表のたび有澤教授と研究会メンバーの皆様がくださ
った各種のアドバイスは筆者にとって研究を進める上で非常にはげみになるものでまたあら
たな視点を見つける機会となったまた今学期あわせて履修していたライティング技法ワーク
ショップの清水唯一朗教授にも多くのアドバイスをいただいた皆様からのアドバイスや励ま
しのおかげでこの3ヶ月間研究を続けてくることができたことは言うまでもなくここに強く感
謝の意を示すものである
2今学期の活動概要
今学期は神奈川東部方面線に関する研究をメインに活動したそれ以外の活動としては今
年の春~初夏にかけて首都圏各地で多くの新路線が開業しており個人的興味からそれらに関し
て積極的に情報をあつめ筆者なりの考察をしたことが挙げられる特に横浜市営地下鉄グリ
ーンラインは通学に使用する路線であり利用感を含め後述しようと思うまた昨年度までの
研究を引き継ぎ今年度は田中謙伍さんが中心になって進めている通学バスの乗車環境をネッ
トワークカメラによって改善するプロジェクト「コムカモ」について慶應義塾湘南藤沢中高等
部の生徒数名に対し率直な意見をうかがった
3東部方面線研究
31動機と目的
これまで日本の鉄道事業者はその鉄道建設にかかる多大な費用を沿線周辺の開発と
いう不動産事業を行うことで回収してきた古くは田園都市株式会社による田園調布の開発
に始まりまた戦後高度経済成長にあわせた都市鉄道の郊外への延伸とその沿線の開発の多
くがこの形態あった沿線を開発することで鉄道利用者が確保され鉄道事業の収益も増加
することから各鉄道事業者は90年代まで多くの路線を建設してきたそしてこれはき
わめて有効な手法であったしかし現在バブル崩壊から長く続いた日本経済の低迷の影響
等で都市域の拡大は終息都心回帰志向が強まり沿線の開発と新規路線の建設をセット
にしたビジネスモデルは成り立たなくなってしまったまたあわせて少子高齢化が進み各
鉄道事業者の輸送人員は頭打ちから減少傾向へ向かっておりまた今後は人口も減少すると
予測されているつまり今後さらなる郊外開発による収益をあてにした今までのような
鉄道事業者単独での新規鉄道の整備が極めて困難になったのである
しかしまだまだ整備すべき鉄道路線はある鉄道は民間の事業者が行う事業であり
ながらきわめて公共性が高いまたマイカー利用と比べ CO2 排出量が少ないため環境
にやさしく車利用を抑制することで交通渋滞の解消等にも役立つためさらなる整備が期
待されるよって何らかの形で鉄道の建設を国や自治体がサポートしていくことが求めら
れていた2005年に施行された「特定都市鉄道利便増進法」はこの目的に沿ったもので
あるこの法律に基づいて行われる鉄道整備事業では国自治体事業者の3者が3ぶん
の1ずつ資金を出すことになるよってその3者間の合意は必ず必要となるが各者の
利害が一致するとは限らずその合意は簡単なものではないだろう調整に長い月日を要す
ることも考えられ今後の課題になる可能性がある
そこで「特定都市鉄道利便増進法」を用いた初めてにして現在唯一の事業化例である
神奈川東部方面線事業についてその合意形成の過程を研究することによって今後の都市
鉄道整備における課題を探り現在計画されている多くの鉄道がその目的に沿ってすみや
かに建設されるために何が必要かを考えることとした
32実際の活動
はじめに東部方面線に関する基礎的な知識を得ることを目的に関係各所のホー
ムページを閲覧した以下はその一覧である
横浜市(都市整備局 鉄道整備課 『神奈川東部方面線の整備』)
httpwwwcityyokohamajpmetoshitetsudotobu
神奈川県(神奈川県には東部方面線のページはないので情報を探して閲覧以下は例)
(知事答弁)httpwwwprefkanagawajposirasehisyochijikaikenh18060630html
(輸送力増強会議)httpwwwprefkanagawajposirasetosikeikakukoutsukentetsu
相模鉄道(『都心直通プロジェクト』)
httpwwwsotetsucojptraininto_tokyoindexhtml
東急電鉄(ニュースリリースから)
httpwwwtokyucojpcontents_indexguidenews070411-1htm
鉄道運輸機構(鉄道建設 都市部における鉄道整備 『相鉄 JR 直通線』『相鉄東急直通線』)
httpwwwjrttgojpbusinesstrain_constsigotobody_soutetsu_jrhtm
httpwwwjrttgojpbusinesstrain_constsigotobody_soutetsu_tokyuhtm
つぎに新聞記事を調べた以下は参考にした記事の一部である
日本経済新聞 1997年08月16日 26ページ(地方経済面)
『神奈川 域内線充実に重点 都市拠点分散に対応』
日本経済新聞 1999年04月17日 26ページ(地方経済面)
『横浜の二俣川鶴ヶ峰地区 交通網の整備を』
日経流通新聞 1999年05月04日 9ページ
『二俣川鶴ヶ峰 交通網を整備 横浜市検討委が構想』
日本経済新聞 1999年06月08日 26ページ(地方経済面)
『JR 新横浜駅周辺の整備構想 新幹線全面停車を』
日本経済新聞 1999年11月18日 7ページ
『東北高崎常磐線の東京乗り入れ評価 運政審部会が中間報告』
日本経済新聞 2000年01月28日 39ページ(地方経済面)
『首都圏鉄道整備で運政審答申 成田新高速など盛る 県負担など調整へ』
日本経済新聞 2001年11月06日 26ページ(地方経済面)
『横浜市の次期5ヵ年計画 事業費13減緊縮型に』
日本経済新聞 2002年03月23日 26ページ(地方経済面)
『都心へ一本時間短縮 乗客伸び悩み囲い込み』
日本経済新聞 2002年04月25日 26ページ(地方経済面)
『東部方面線建設を白紙に 川崎市』
日本経済新聞 2004年09月08日 26ページ(地方経済面)
『相鉄 JR 東と乗り入れ協議 都心直結で乗客減打開 沿線開発に弾みも』
日本経済新聞 2004年09月09日 26ページ(地方経済面)
『相鉄JR 乗り入れ協議 横浜市長「これから検討」』
日本経済新聞 2004年12月22日 26ページ(地方経済面)
『神奈川東部方面線の新設 横浜市長「どちらかを優先」』
日本経済新聞 2005年12月27日 26ページ(地方経済面)
『JR との相互乗り入れ 「今年度中にメド」 相鉄社長』
日本経済新聞 2006年02月10日 12ページ
『東急と相鉄乗り入れへ 新横浜経由で連絡線』
日本経済新聞 2006年02月10日 26ページ(地方経済面)
『相鉄東急乗り入れ前進 横浜市財政負担に前向き』
日本経済新聞 2006年05月19日 26ページ(地方経済面)
『東急相鉄相互乗り入れ 国に 25 日計画提出 新横浜経由』
日本経済新聞 2006年06月02日 26ページ(地方経済面)
『相鉄東急 JR 相互乗り入れ 4億2700万円計上 横浜市が補正予算案』
日本経済新聞 2006年05月26日 26ページ(地方経済面)
『相鉄東急JR へ直通 相互乗り入れ本格始動へ』
建通新聞 2008年4月18日
『相鉄JR 直通線トンネル概略設計着手』
他多数の新聞記事を参照した
また以下の雑誌記事にも目を通した
鉄道ジャーナル 1999年12月号
『通勤輸送に徹する相模鉄道』
運輸と経済 2004年11月号
『インタビュー 地域密着を目指した経営計画の推進に向けて
--相模鉄道及川陸郎社長に聞く (特集連結経営時代のグループ戦略)』
運輸と経済 1994年11月号
『特定都市鉄道整備促進特別措置法に基づく既認定工事
--その進捗状況および同法の拡充について 』
鉄道ピクトリアル 1998年3月号
『特定都市鉄道整備事業の現状と今後 (lt特集gt大手民鉄の複々線)』
鉄道ピクトリアル 1999年7月臨時増刊号
『相模鉄道の鉄道事業を語る (lt特集gt相模鉄道)』
日本鉄道建設業協会 鉄道の礎 240 号 2007年4月
『都市鉄道等利便増進法に基づく
相鉄JR 直通線および相鉄東急直通線の速達性向上計画』
httpwwwtekkenkyoorjpkaihou24016html から閲覧
以下の雑誌記事は読みたかったが読めなかったものである
運輸と経済 197607
『10 年がかりの私鉄新線建設--相模鉄道いずみ野線』
エコノミスト 19850702
『私鉄沿線-13-横浜海老名(相模鉄道相鉄線)--首都圏の利フルに生かす』
JREA 20077
『都市鉄道利便増進事業の速達性向上計画認定--相鉄 JR 直通線相鉄東急直通線』
運輸政策研究 2008Win
『鉄道整備等基礎調査
「既存の都市鉄道ネットワークの改良による速達性向上施策 に関する調査」』
運輸と経済 20083
『都市鉄道の将来--歴史から見た考察 (特集 交通史から見た今日の交通問題)』
運輸政策研究 2007Spr
『都市鉄道等利便増進法の活用による新たな都市鉄道政策の展開』
市街地再開発 20065
『制度の紹介等 都市鉄道等利便増進法について』
運輸と経済 200510
『インタビュー都市鉄道の成長と成熟そしてどう維持するか』
JREA 20057
『都市鉄道整備の課題と今後の展望 (特集 都市交通)』
JR gazette 20053
『運輸リポート 「都市鉄道等利便増進法案」について 』
JREA 200412
『特別寄稿 政策レビュー「都市鉄道整備のあり方」の概要』
財界 20061205
『REPORT横浜市長中田宏の「新横浜を副都心から都心に変える」改造計画
2019年相鉄とJR湘南新宿ライン東急東横線が相互乗り入れ開始』
フォーブス 200502
『東武相鉄hellipJR東が私鉄と相互乗り入れする理由
新宿~東武日光鬼怒川温泉間の特急運転の開始を発表
相模鉄道との相互乗り入れ構想』
経済界 20010626
『 NEW PRESIDENT登場 相模鉄道社長及川陸郎 新しい息吹を吹き
込む遠回りしてきた男』
財界 20011
『光通信関連会社に土地を売却 私鉄大手「相模鉄道」の苦しい台所事情』
経済界 19980526
『佐藤正忠の極意対談 366回 相模鉄道会長對島好次郎
地域に一番大切なことは何か鉄道業の成長はその追求である』
夏季休業中にできるだけ読みたい
各種資料から得られた知識を筆者なりに総合し簡潔にまとめた
2003 年 「神奈川東部方面線懇談会」 関係自治体や鉄道事業者で整備に向けた調整
2005 年 都市鉄道等利便増進法施行
2004 年 相鉄 JR 直通案浮上
2006 年 相鉄 JR 直通+相鉄東急直通の形に決定し
5月営業整備計画申請 6月営業整備計画認定 8月速達性向上計画申請(相鉄 JR) 11 月速達性向上計画認定(相鉄 JR) 11 月速達性向上計画申請(相鉄東急)
2008 年 4月トンネル概略設計着手
2007 年 4月速達性向上計画認定(相鉄東急) 10 月環境影響評価方法書提出住民説明会 11 月環境影響評価公告縦覧
2000 年 運輸政策審議会答申 18 号 「A1 路線」平成 27 年までに開業が望ましい
各種資料からは存在することしか分からなかった「神奈川東部方面線懇談会」につ
いて横浜市に電話で問い合わせた
まずはじめに横浜市の市民情報室へ問い合わせの電話をかけた「神奈川東
部方面線の懇談会について知りたい」「新聞記事などで存在を知ったがもっと詳しく
知りたいと思っている会議録などは残っていないか」という旨の質問をしたところ
神奈川東部方面線を担当している部署へ電話をまわしていただけることになった
神奈川東部方面線担当の方につながったところで先ほどと同様の質問をした
担当の方も4月の異動で神奈川東部方面線担当になったようで当時の状況について
直接ご存知ないようであった少々込み入った話をしたところで一旦調べてまた
連絡していただけることになった
その後しばらくして電話をもらうがやはり議事録などは残っていない
との回答であったそこでどうにかもう少し当時の横浜市としての対応などを知る
ことができないか質問をしたまたつづけて直接お話を聞きにうかがうことはで
きないかとインタビューのお願いをしてみたところ分かる範囲でよろしければ
との回答を得ることができた
事業の当事者のひとつである横浜市から直接お話をしていただけるというのは
今後この研究をどのように進めていくかというその方向性を見定めるにもいい機会
であると思った後日こちらから電話し日時を決めることにしてこの日の電話
での質問は終了した
各種資料からは存在することしか分からなかった「神奈川東部方面線懇談会」につ
いて横浜市に直接ヒアリングにうかがった
5月27日の質問のあと6月3日に再度電話しアポイントメントを取った
結果6月9日の午後2時から横浜市庁舎にてインタビューできることになったま
た事前に質問書を送付したまた研究会で同行者をつのったところ2人一緒に来
てくださることになったとても心強かった
当日予定通り午後2時に横浜市庁舎6階へうかがった行政機関へのヒアリ
ング調査を行うのは初めてのことであり緊張した90分ほどお話をうかがいイ
ンタビューは無事終了したまたパンフレットと簡単な資料をいただいた録音した
音声ファイルを聞き返すと質問の仕方が稚拙なことが多くまた自分の主観の入っ
た質問も散見され反省するばかりである今後ヒアリング調査を行う際にはこの
点より強く心がけるようにしたい
東部方面線に関する質問票 慶應義塾大学環境情報学部 有澤研究室
日時平成20年6月9日月曜日 1400 ~ (予定) 場所横浜市役所本庁舎6階 都市整備局 (予定)
1東部方面線懇談会について
懇談会の基本的な情報を教えてください(経緯期間回数会場委員)
懇談会始動当時横浜市が重要視しておられたことについて教えてください
懇談会始動当時横浜市がすでに取り組んでおられたことについて教えてください
懇談会始動当時横浜市の各事業者等の狙いのとらえかたについて教えてください
都市鉄道等利便増進法制定との関係について教えてください
懇談会始動当時の事業化へ向けた課題について教えてください
2JR と相鉄の相互乗り入れ構想について
懇談会でのこの構想に関する議論について教えてください
新聞記事となったタイミングはどうでしたか
横浜市はこの構想をどう受け止めておられましたか
この構想と東部方面線の関係を整理する過程について教えてください
各事業者等との協議の焦点はどのようなことでしたか
3将来について
東部方面線事業に対する横浜市の今後の取り組みについて教えてください
現状横浜市が課題ととらえているのはどのようなことですか
西暦 平成
1999 11 6月 新横浜都心整備基本構想 策定
2000 12 運輸政策審議会答申18号 「A1路線」(平成27年までに開業することが望ましい) 3月 こどもの国線通勤線化
2001 13 1月 グリーンライン着工
2002 143月 市長選挙 中田氏当選6月 横浜でワールドカップ決勝が開催
2003 15 懇談会始動3月 市議会議員県議会議員県知事選挙 松沢知事当選12月 市営地下鉄全席優先席
2004 169月 JR相鉄直通新聞報道 横浜市長「協力するかこれから具体的に検討する」12月 横浜市長「(直通か東部方面線か)どちらかを優先」
2月 みなとみらい線開業
2005 17 8月 都市鉄道等利便増進法施行 9月 衆議院議員選挙 自民党圧勝
2006 18
2月 横浜市予算支出へ前向き5月 営業整備計画を事業者が申請6月 横浜市予算計上 営業整備計画認定11月 相鉄JR直通線 速達性向上計画認定
3月 市長選挙 中田氏再選
2007 194月 相鉄東急直通線 速達性向上計画認定10月~ 住民説明会など
3月 市議会議員県議会議員県知事選挙 松沢知事再選
2008 203月 グリーンライン開業6月 目黒線 日吉延伸
2009 21
2010 22
2011 23
2012 24 東横線hArr副都心線 直通開始予定
2013 25 東北縦貫線完成予定h(東海道線hArr東北高崎常磐線 直通)
2014 26
2015 27 相鉄JR直通線開業予定
2016 28
2017 29
2018 30
2019 31 相鉄東急直通線開業予定
ヒアリングで判明した内容をまとめた以下はその内容である
横浜市の方によると神奈川東部方面線懇談会とは国横浜市神奈川県東
急相鉄鉄道運輸機構であり課長レベルの方々が出席して行われたものである
とのことであったまたその下部にワークグループが存在しより詳細な調整が行
われたとのことであった会議録等の資料はやはり残っていないとの説明があった
相鉄 JR 直通線と神奈川東部方面線との関係についてはやはり新横浜を通
るか通らないかというこの違いが強調された横浜市にとって新横浜はその都市計
画において重要な位置付けをされておりその発展のためにまた横浜市西部や県央
地域から新横浜へのアクセス向上のために「新横浜を通る」東部方面線の整備が重要
であるとの説明があった横浜市にとって東部方面線は都心への直通路線としても
「もちろん大切」であるが新横浜のターミナル性を高めるために必要であることが
確認できたといえる
上記の内容から考察すると新聞記事やパンフレットでは都心への時間短縮が大
きく示されているものの横浜市としてはむしろ新横浜アクセス向上の意味が強い
と思われる都心への直通を前面に押し出し「速達性向上計画」として国に申請「都
市鉄道等利便増進法」に基づいてその整備を行うものであるが決して都内に人を吸
い上げられるだけのものではなく市の発展への意味も強くこめられていることが判
明した相鉄や東急は果たしてどう考えているのだろうか
33今後の活動
この春学期の活動を通して神奈川東部方面線についての横浜市の立場やとってきた
行動というものについての筆者の理解はとても深まったといえる同時に他の立場とい
うものについての興味を抱いた例えば相模鉄道の立場やJR の立場である横浜市にと
って極めて重要であった新横浜への到達は相模鉄道にとっていったいどれほどの価値が
あるものであったのだろうかまた相模鉄道は当時どのように考えていたのだろうか
またJR からすれば相鉄東急直通線が開通することで都心への旅客の奪いあいが発
生することが考えられるJR は「神奈川東部方面線懇談会」のメンバーではなかったもの
の決して関係ない立場ではないそれぞれに立場や目的を抱えていたはずである今後
の活動としては横浜市以外の関係者が東部方面線の事業化に向けてどのように対応し
行動をとってきたのかについて調査していきたいと考えている
またあわせてこの春学期に読むことのできなかった多くの文献に目を通したいこれ
は戦後から現在にいたるまでの鉄道整備の方式やその制度について理解しその知識を
得ることで神奈川東部方面線に関する事例研究からより思考を発展させこれからの都市
鉄道の整備に関する課題などの理解につながると思うからであるある程度の知識を習得し
自分なりに思考をしたのちより直接的な都市鉄道整備に関する先行研究を調べ論文など
を読みたいと思う
4そのほかの活動
41横浜市営地下鉄グリーンライン
2008年3月横浜市営地下鉄に新たな路線が開業した愛称をグリーンラインとい
い横浜市港北区の日吉から横浜市都筑区を縦断し横浜市緑区の中心部中山を結ぶ全長
131km の路線である日吉駅で東急東横線と目黒線に中山駅で JR 横浜線と連絡する
開業3ヵ月後の6月に東急目黒線が日吉駅まで延伸されたことで都内方面への利便性はい
くらか向上した車両はリニアモーター推進方式で車両 1 両あたりの長さは 155m現
在は4両編成であるがホームなどは編成の延長に対応し6両分の長さが用意されているよ
うである駅は10駅全線の所要時間は終日21分表定速度は約 37km で地下鉄と
してはそれなりであるが周辺路線と比較して速いとはいえないしかも運賃は非常に高い
ため東横線と横浜線の短絡線としてはほとんど機能しないものであるよって都筑区内
から東横線横浜線あるいは都筑区中心部への輸送が中心になると考えられる同じ都市
鉄道であってもグリーンラインの性質は東部方面線の性質と大きく異なるといえる都市
鉄道整備の最新の例でありまたその利用者のひとりとして今後ともその利用動向などに
は目を配っておきたい
実際の利用実績であるが4月の乗客数については目標の約半分との新聞報道があっ
た10万4千人の予想に反して結果は5万3千人にとどまっているしかし実際に毎
日利用している筆者からすると朝ラッシュ時のセンター北rarr日吉方面への混雑は日吉に近
づくにつれ相当なものとなる現状の2倍の乗客は乗れないまた夕方の時間帯の車内も空
席が目立たない程度に混んでおりこちらも現状の2倍の乗客が乗車するようではかなり
の混雑になってしまうつまり筆者が言いたいのは全体の結果として約半分になるものの
一部の時間帯や一部の区間の乗客数については目標に近いのではないだろうかというこ
とであるよって逆に予想よりかなり利用者の少ない時間帯の存在やもしくは区間によ
る偏りが大きいことが考えられるこれらはより詳細なデータを調べればわかるだろうま
た周辺のバス路線の利用者数の推移とも大いに関係するはずである今後の乗客増のため
にも横浜市等の対策に注目していきたい
筆者は都筑区北部在住であり自宅はグリーンラインの駅から徒歩10分ほどの距離
にある開通前はバスを利用し鉄道駅に向かっていたのでグリーンライン開通によってた
しかに便利になった特に最終バスが22時台と早かったため帰宅が深夜になる場合は非
常に便利であるしかし開通後もバスがあるときはバスを利用することが多いのもまた
事実であるこれはバスの本数自体は決して多くはないものの常にほぼ時刻表通りに運
行されておりその利用に抵抗がないこととバス停が細かく配置され自宅のすぐ近くにあ
ることが理由ある特に雨の日や日射しの強い日は徒歩距離の長いグリーンラインは敬遠し
てしまうただこれは筆者の考えであり一般的であるかは全く不明であることを強調し
ておく
42コムカモ
コムカモとは学内のバス停をネットワークカメラで常に撮影しその混雑状況をどこ
からでもすぐに把握できるようにすることで帰宅時間の分散をすすめバス利用を快適化
しようとするプロジェクトであるプライバシーなどの問題から現在カメラの設置には至
っておらず署名をあつめている段階であるその詳細な経緯や根拠の説明はここでは省く
中心になってこのプロジェクトを動かしていた杉山公一郎氏の卒業制作が詳しい
バス利用者は大学生にとどまらないため私は自分の交友関係を鑑み慶応義塾湘南藤
沢中高等部の生徒にこの署名をお願いしようと考えたしかしそれにはまずこのプロジ
ェクトについての意見をうかがう必要があった昨年度から中高等部とは何度かのやりと
りがあったようであるがおそらく末端の生徒は何も知らないと思い簡単な説明を行った
うえで意見をうかがったその結果得られた回答の要点は以下である回答者の属性は
6名全員が文化部で男性が3名女性が3名また中学生4名高校生2名である
①便利だとは思うが実際に利用することはまずないと思う
②友人にも利用すると思われる人はいない
③利用するならば携帯電話からの利用になる
①の意見が多かったことによって署名のお願いは断念した①の理由について意見
をまとめると以下のようになった
ア帰る時間が決まっていて選択の余地がない
イ友人同士での帰宅が多く並ばないことの重要性は少ない
ウ現在の混雑は理解できる範囲である
筆者が意見を聞いた中高生は帰る時間が基本的に決まっておりまたその結果人が集
中し混雑することを理解していたまたそれを仕方のないものだととらえていた各自の経
験等により各自の帰る時間が決まっていることも合わさってバス停の混雑する時間帯が頭
に入っているようであったつまりバス停混雑について現在ある程度の予測ができてお
りその結果混雑が想定されていてもその時間に帰宅しているのであるよって中高生の
多くはたとえコムカモで混雑していることが判明しても帰宅することが想像できるこ
れではコムカモの必要性は感じられないだろうしかし空いている時間に帰宅したいと
いうニーズはゼロではないと思うので実際に利用するかはともかく無いよりはあるほう
が便利は便利であるというスタンスで署名をお願いすればよいのではないかと考えている

2今学期の活動概要
今学期は神奈川東部方面線に関する研究をメインに活動したそれ以外の活動としては今
年の春~初夏にかけて首都圏各地で多くの新路線が開業しており個人的興味からそれらに関し
て積極的に情報をあつめ筆者なりの考察をしたことが挙げられる特に横浜市営地下鉄グリ
ーンラインは通学に使用する路線であり利用感を含め後述しようと思うまた昨年度までの
研究を引き継ぎ今年度は田中謙伍さんが中心になって進めている通学バスの乗車環境をネッ
トワークカメラによって改善するプロジェクト「コムカモ」について慶應義塾湘南藤沢中高等
部の生徒数名に対し率直な意見をうかがった
3東部方面線研究
31動機と目的
これまで日本の鉄道事業者はその鉄道建設にかかる多大な費用を沿線周辺の開発と
いう不動産事業を行うことで回収してきた古くは田園都市株式会社による田園調布の開発
に始まりまた戦後高度経済成長にあわせた都市鉄道の郊外への延伸とその沿線の開発の多
くがこの形態あった沿線を開発することで鉄道利用者が確保され鉄道事業の収益も増加
することから各鉄道事業者は90年代まで多くの路線を建設してきたそしてこれはき
わめて有効な手法であったしかし現在バブル崩壊から長く続いた日本経済の低迷の影響
等で都市域の拡大は終息都心回帰志向が強まり沿線の開発と新規路線の建設をセット
にしたビジネスモデルは成り立たなくなってしまったまたあわせて少子高齢化が進み各
鉄道事業者の輸送人員は頭打ちから減少傾向へ向かっておりまた今後は人口も減少すると
予測されているつまり今後さらなる郊外開発による収益をあてにした今までのような
鉄道事業者単独での新規鉄道の整備が極めて困難になったのである
しかしまだまだ整備すべき鉄道路線はある鉄道は民間の事業者が行う事業であり
ながらきわめて公共性が高いまたマイカー利用と比べ CO2 排出量が少ないため環境
にやさしく車利用を抑制することで交通渋滞の解消等にも役立つためさらなる整備が期
待されるよって何らかの形で鉄道の建設を国や自治体がサポートしていくことが求めら
れていた2005年に施行された「特定都市鉄道利便増進法」はこの目的に沿ったもので
あるこの法律に基づいて行われる鉄道整備事業では国自治体事業者の3者が3ぶん
の1ずつ資金を出すことになるよってその3者間の合意は必ず必要となるが各者の
利害が一致するとは限らずその合意は簡単なものではないだろう調整に長い月日を要す
ることも考えられ今後の課題になる可能性がある
そこで「特定都市鉄道利便増進法」を用いた初めてにして現在唯一の事業化例である
神奈川東部方面線事業についてその合意形成の過程を研究することによって今後の都市
鉄道整備における課題を探り現在計画されている多くの鉄道がその目的に沿ってすみや
かに建設されるために何が必要かを考えることとした
32実際の活動
はじめに東部方面線に関する基礎的な知識を得ることを目的に関係各所のホー
ムページを閲覧した以下はその一覧である
横浜市(都市整備局 鉄道整備課 『神奈川東部方面線の整備』)
httpwwwcityyokohamajpmetoshitetsudotobu
神奈川県(神奈川県には東部方面線のページはないので情報を探して閲覧以下は例)
(知事答弁)httpwwwprefkanagawajposirasehisyochijikaikenh18060630html
(輸送力増強会議)httpwwwprefkanagawajposirasetosikeikakukoutsukentetsu
相模鉄道(『都心直通プロジェクト』)
httpwwwsotetsucojptraininto_tokyoindexhtml
東急電鉄(ニュースリリースから)
httpwwwtokyucojpcontents_indexguidenews070411-1htm
鉄道運輸機構(鉄道建設 都市部における鉄道整備 『相鉄 JR 直通線』『相鉄東急直通線』)
httpwwwjrttgojpbusinesstrain_constsigotobody_soutetsu_jrhtm
httpwwwjrttgojpbusinesstrain_constsigotobody_soutetsu_tokyuhtm
つぎに新聞記事を調べた以下は参考にした記事の一部である
日本経済新聞 1997年08月16日 26ページ(地方経済面)
『神奈川 域内線充実に重点 都市拠点分散に対応』
日本経済新聞 1999年04月17日 26ページ(地方経済面)
『横浜の二俣川鶴ヶ峰地区 交通網の整備を』
日経流通新聞 1999年05月04日 9ページ
『二俣川鶴ヶ峰 交通網を整備 横浜市検討委が構想』
日本経済新聞 1999年06月08日 26ページ(地方経済面)
『JR 新横浜駅周辺の整備構想 新幹線全面停車を』
日本経済新聞 1999年11月18日 7ページ
『東北高崎常磐線の東京乗り入れ評価 運政審部会が中間報告』
日本経済新聞 2000年01月28日 39ページ(地方経済面)
『首都圏鉄道整備で運政審答申 成田新高速など盛る 県負担など調整へ』
日本経済新聞 2001年11月06日 26ページ(地方経済面)
『横浜市の次期5ヵ年計画 事業費13減緊縮型に』
日本経済新聞 2002年03月23日 26ページ(地方経済面)
『都心へ一本時間短縮 乗客伸び悩み囲い込み』
日本経済新聞 2002年04月25日 26ページ(地方経済面)
『東部方面線建設を白紙に 川崎市』
日本経済新聞 2004年09月08日 26ページ(地方経済面)
『相鉄 JR 東と乗り入れ協議 都心直結で乗客減打開 沿線開発に弾みも』
日本経済新聞 2004年09月09日 26ページ(地方経済面)
『相鉄JR 乗り入れ協議 横浜市長「これから検討」』
日本経済新聞 2004年12月22日 26ページ(地方経済面)
『神奈川東部方面線の新設 横浜市長「どちらかを優先」』
日本経済新聞 2005年12月27日 26ページ(地方経済面)
『JR との相互乗り入れ 「今年度中にメド」 相鉄社長』
日本経済新聞 2006年02月10日 12ページ
『東急と相鉄乗り入れへ 新横浜経由で連絡線』
日本経済新聞 2006年02月10日 26ページ(地方経済面)
『相鉄東急乗り入れ前進 横浜市財政負担に前向き』
日本経済新聞 2006年05月19日 26ページ(地方経済面)
『東急相鉄相互乗り入れ 国に 25 日計画提出 新横浜経由』
日本経済新聞 2006年06月02日 26ページ(地方経済面)
『相鉄東急 JR 相互乗り入れ 4億2700万円計上 横浜市が補正予算案』
日本経済新聞 2006年05月26日 26ページ(地方経済面)
『相鉄東急JR へ直通 相互乗り入れ本格始動へ』
建通新聞 2008年4月18日
『相鉄JR 直通線トンネル概略設計着手』
他多数の新聞記事を参照した
また以下の雑誌記事にも目を通した
鉄道ジャーナル 1999年12月号
『通勤輸送に徹する相模鉄道』
運輸と経済 2004年11月号
『インタビュー 地域密着を目指した経営計画の推進に向けて
--相模鉄道及川陸郎社長に聞く (特集連結経営時代のグループ戦略)』
運輸と経済 1994年11月号
『特定都市鉄道整備促進特別措置法に基づく既認定工事
--その進捗状況および同法の拡充について 』
鉄道ピクトリアル 1998年3月号
『特定都市鉄道整備事業の現状と今後 (lt特集gt大手民鉄の複々線)』
鉄道ピクトリアル 1999年7月臨時増刊号
『相模鉄道の鉄道事業を語る (lt特集gt相模鉄道)』
日本鉄道建設業協会 鉄道の礎 240 号 2007年4月
『都市鉄道等利便増進法に基づく
相鉄JR 直通線および相鉄東急直通線の速達性向上計画』
httpwwwtekkenkyoorjpkaihou24016html から閲覧
以下の雑誌記事は読みたかったが読めなかったものである
運輸と経済 197607
『10 年がかりの私鉄新線建設--相模鉄道いずみ野線』
エコノミスト 19850702
『私鉄沿線-13-横浜海老名(相模鉄道相鉄線)--首都圏の利フルに生かす』
JREA 20077
『都市鉄道利便増進事業の速達性向上計画認定--相鉄 JR 直通線相鉄東急直通線』
運輸政策研究 2008Win
『鉄道整備等基礎調査
「既存の都市鉄道ネットワークの改良による速達性向上施策 に関する調査」』
運輸と経済 20083
『都市鉄道の将来--歴史から見た考察 (特集 交通史から見た今日の交通問題)』
運輸政策研究 2007Spr
『都市鉄道等利便増進法の活用による新たな都市鉄道政策の展開』
市街地再開発 20065
『制度の紹介等 都市鉄道等利便増進法について』
運輸と経済 200510
『インタビュー都市鉄道の成長と成熟そしてどう維持するか』
JREA 20057
『都市鉄道整備の課題と今後の展望 (特集 都市交通)』
JR gazette 20053
『運輸リポート 「都市鉄道等利便増進法案」について 』
JREA 200412
『特別寄稿 政策レビュー「都市鉄道整備のあり方」の概要』
財界 20061205
『REPORT横浜市長中田宏の「新横浜を副都心から都心に変える」改造計画
2019年相鉄とJR湘南新宿ライン東急東横線が相互乗り入れ開始』
フォーブス 200502
『東武相鉄hellipJR東が私鉄と相互乗り入れする理由
新宿~東武日光鬼怒川温泉間の特急運転の開始を発表
相模鉄道との相互乗り入れ構想』
経済界 20010626
『 NEW PRESIDENT登場 相模鉄道社長及川陸郎 新しい息吹を吹き
込む遠回りしてきた男』
財界 20011
『光通信関連会社に土地を売却 私鉄大手「相模鉄道」の苦しい台所事情』
経済界 19980526
『佐藤正忠の極意対談 366回 相模鉄道会長對島好次郎
地域に一番大切なことは何か鉄道業の成長はその追求である』
夏季休業中にできるだけ読みたい
各種資料から得られた知識を筆者なりに総合し簡潔にまとめた
2003 年 「神奈川東部方面線懇談会」 関係自治体や鉄道事業者で整備に向けた調整
2005 年 都市鉄道等利便増進法施行
2004 年 相鉄 JR 直通案浮上
2006 年 相鉄 JR 直通+相鉄東急直通の形に決定し
5月営業整備計画申請 6月営業整備計画認定 8月速達性向上計画申請(相鉄 JR) 11 月速達性向上計画認定(相鉄 JR) 11 月速達性向上計画申請(相鉄東急)
2008 年 4月トンネル概略設計着手
2007 年 4月速達性向上計画認定(相鉄東急) 10 月環境影響評価方法書提出住民説明会 11 月環境影響評価公告縦覧
2000 年 運輸政策審議会答申 18 号 「A1 路線」平成 27 年までに開業が望ましい
各種資料からは存在することしか分からなかった「神奈川東部方面線懇談会」につ
いて横浜市に電話で問い合わせた
まずはじめに横浜市の市民情報室へ問い合わせの電話をかけた「神奈川東
部方面線の懇談会について知りたい」「新聞記事などで存在を知ったがもっと詳しく
知りたいと思っている会議録などは残っていないか」という旨の質問をしたところ
神奈川東部方面線を担当している部署へ電話をまわしていただけることになった
神奈川東部方面線担当の方につながったところで先ほどと同様の質問をした
担当の方も4月の異動で神奈川東部方面線担当になったようで当時の状況について
直接ご存知ないようであった少々込み入った話をしたところで一旦調べてまた
連絡していただけることになった
その後しばらくして電話をもらうがやはり議事録などは残っていない
との回答であったそこでどうにかもう少し当時の横浜市としての対応などを知る
ことができないか質問をしたまたつづけて直接お話を聞きにうかがうことはで
きないかとインタビューのお願いをしてみたところ分かる範囲でよろしければ
との回答を得ることができた
事業の当事者のひとつである横浜市から直接お話をしていただけるというのは
今後この研究をどのように進めていくかというその方向性を見定めるにもいい機会
であると思った後日こちらから電話し日時を決めることにしてこの日の電話
での質問は終了した
各種資料からは存在することしか分からなかった「神奈川東部方面線懇談会」につ
いて横浜市に直接ヒアリングにうかがった
5月27日の質問のあと6月3日に再度電話しアポイントメントを取った
結果6月9日の午後2時から横浜市庁舎にてインタビューできることになったま
た事前に質問書を送付したまた研究会で同行者をつのったところ2人一緒に来
てくださることになったとても心強かった
当日予定通り午後2時に横浜市庁舎6階へうかがった行政機関へのヒアリ
ング調査を行うのは初めてのことであり緊張した90分ほどお話をうかがいイ
ンタビューは無事終了したまたパンフレットと簡単な資料をいただいた録音した
音声ファイルを聞き返すと質問の仕方が稚拙なことが多くまた自分の主観の入っ
た質問も散見され反省するばかりである今後ヒアリング調査を行う際にはこの
点より強く心がけるようにしたい
東部方面線に関する質問票 慶應義塾大学環境情報学部 有澤研究室
日時平成20年6月9日月曜日 1400 ~ (予定) 場所横浜市役所本庁舎6階 都市整備局 (予定)
1東部方面線懇談会について
懇談会の基本的な情報を教えてください(経緯期間回数会場委員)
懇談会始動当時横浜市が重要視しておられたことについて教えてください
懇談会始動当時横浜市がすでに取り組んでおられたことについて教えてください
懇談会始動当時横浜市の各事業者等の狙いのとらえかたについて教えてください
都市鉄道等利便増進法制定との関係について教えてください
懇談会始動当時の事業化へ向けた課題について教えてください
2JR と相鉄の相互乗り入れ構想について
懇談会でのこの構想に関する議論について教えてください
新聞記事となったタイミングはどうでしたか
横浜市はこの構想をどう受け止めておられましたか
この構想と東部方面線の関係を整理する過程について教えてください
各事業者等との協議の焦点はどのようなことでしたか
3将来について
東部方面線事業に対する横浜市の今後の取り組みについて教えてください
現状横浜市が課題ととらえているのはどのようなことですか
西暦 平成
1999 11 6月 新横浜都心整備基本構想 策定
2000 12 運輸政策審議会答申18号 「A1路線」(平成27年までに開業することが望ましい) 3月 こどもの国線通勤線化
2001 13 1月 グリーンライン着工
2002 143月 市長選挙 中田氏当選6月 横浜でワールドカップ決勝が開催
2003 15 懇談会始動3月 市議会議員県議会議員県知事選挙 松沢知事当選12月 市営地下鉄全席優先席
2004 169月 JR相鉄直通新聞報道 横浜市長「協力するかこれから具体的に検討する」12月 横浜市長「(直通か東部方面線か)どちらかを優先」
2月 みなとみらい線開業
2005 17 8月 都市鉄道等利便増進法施行 9月 衆議院議員選挙 自民党圧勝
2006 18
2月 横浜市予算支出へ前向き5月 営業整備計画を事業者が申請6月 横浜市予算計上 営業整備計画認定11月 相鉄JR直通線 速達性向上計画認定
3月 市長選挙 中田氏再選
2007 194月 相鉄東急直通線 速達性向上計画認定10月~ 住民説明会など
3月 市議会議員県議会議員県知事選挙 松沢知事再選
2008 203月 グリーンライン開業6月 目黒線 日吉延伸
2009 21
2010 22
2011 23
2012 24 東横線hArr副都心線 直通開始予定
2013 25 東北縦貫線完成予定h(東海道線hArr東北高崎常磐線 直通)
2014 26
2015 27 相鉄JR直通線開業予定
2016 28
2017 29
2018 30
2019 31 相鉄東急直通線開業予定
ヒアリングで判明した内容をまとめた以下はその内容である
横浜市の方によると神奈川東部方面線懇談会とは国横浜市神奈川県東
急相鉄鉄道運輸機構であり課長レベルの方々が出席して行われたものである
とのことであったまたその下部にワークグループが存在しより詳細な調整が行
われたとのことであった会議録等の資料はやはり残っていないとの説明があった
相鉄 JR 直通線と神奈川東部方面線との関係についてはやはり新横浜を通
るか通らないかというこの違いが強調された横浜市にとって新横浜はその都市計
画において重要な位置付けをされておりその発展のためにまた横浜市西部や県央
地域から新横浜へのアクセス向上のために「新横浜を通る」東部方面線の整備が重要
であるとの説明があった横浜市にとって東部方面線は都心への直通路線としても
「もちろん大切」であるが新横浜のターミナル性を高めるために必要であることが
確認できたといえる
上記の内容から考察すると新聞記事やパンフレットでは都心への時間短縮が大
きく示されているものの横浜市としてはむしろ新横浜アクセス向上の意味が強い
と思われる都心への直通を前面に押し出し「速達性向上計画」として国に申請「都
市鉄道等利便増進法」に基づいてその整備を行うものであるが決して都内に人を吸
い上げられるだけのものではなく市の発展への意味も強くこめられていることが判
明した相鉄や東急は果たしてどう考えているのだろうか
33今後の活動
この春学期の活動を通して神奈川東部方面線についての横浜市の立場やとってきた
行動というものについての筆者の理解はとても深まったといえる同時に他の立場とい
うものについての興味を抱いた例えば相模鉄道の立場やJR の立場である横浜市にと
って極めて重要であった新横浜への到達は相模鉄道にとっていったいどれほどの価値が
あるものであったのだろうかまた相模鉄道は当時どのように考えていたのだろうか
またJR からすれば相鉄東急直通線が開通することで都心への旅客の奪いあいが発
生することが考えられるJR は「神奈川東部方面線懇談会」のメンバーではなかったもの
の決して関係ない立場ではないそれぞれに立場や目的を抱えていたはずである今後
の活動としては横浜市以外の関係者が東部方面線の事業化に向けてどのように対応し
行動をとってきたのかについて調査していきたいと考えている
またあわせてこの春学期に読むことのできなかった多くの文献に目を通したいこれ
は戦後から現在にいたるまでの鉄道整備の方式やその制度について理解しその知識を
得ることで神奈川東部方面線に関する事例研究からより思考を発展させこれからの都市
鉄道の整備に関する課題などの理解につながると思うからであるある程度の知識を習得し
自分なりに思考をしたのちより直接的な都市鉄道整備に関する先行研究を調べ論文など
を読みたいと思う
4そのほかの活動
41横浜市営地下鉄グリーンライン
2008年3月横浜市営地下鉄に新たな路線が開業した愛称をグリーンラインとい
い横浜市港北区の日吉から横浜市都筑区を縦断し横浜市緑区の中心部中山を結ぶ全長
131km の路線である日吉駅で東急東横線と目黒線に中山駅で JR 横浜線と連絡する
開業3ヵ月後の6月に東急目黒線が日吉駅まで延伸されたことで都内方面への利便性はい
くらか向上した車両はリニアモーター推進方式で車両 1 両あたりの長さは 155m現
在は4両編成であるがホームなどは編成の延長に対応し6両分の長さが用意されているよ
うである駅は10駅全線の所要時間は終日21分表定速度は約 37km で地下鉄と
してはそれなりであるが周辺路線と比較して速いとはいえないしかも運賃は非常に高い
ため東横線と横浜線の短絡線としてはほとんど機能しないものであるよって都筑区内
から東横線横浜線あるいは都筑区中心部への輸送が中心になると考えられる同じ都市
鉄道であってもグリーンラインの性質は東部方面線の性質と大きく異なるといえる都市
鉄道整備の最新の例でありまたその利用者のひとりとして今後ともその利用動向などに
は目を配っておきたい
実際の利用実績であるが4月の乗客数については目標の約半分との新聞報道があっ
た10万4千人の予想に反して結果は5万3千人にとどまっているしかし実際に毎
日利用している筆者からすると朝ラッシュ時のセンター北rarr日吉方面への混雑は日吉に近
づくにつれ相当なものとなる現状の2倍の乗客は乗れないまた夕方の時間帯の車内も空
席が目立たない程度に混んでおりこちらも現状の2倍の乗客が乗車するようではかなり
の混雑になってしまうつまり筆者が言いたいのは全体の結果として約半分になるものの
一部の時間帯や一部の区間の乗客数については目標に近いのではないだろうかというこ
とであるよって逆に予想よりかなり利用者の少ない時間帯の存在やもしくは区間によ
る偏りが大きいことが考えられるこれらはより詳細なデータを調べればわかるだろうま
た周辺のバス路線の利用者数の推移とも大いに関係するはずである今後の乗客増のため
にも横浜市等の対策に注目していきたい
筆者は都筑区北部在住であり自宅はグリーンラインの駅から徒歩10分ほどの距離
にある開通前はバスを利用し鉄道駅に向かっていたのでグリーンライン開通によってた
しかに便利になった特に最終バスが22時台と早かったため帰宅が深夜になる場合は非
常に便利であるしかし開通後もバスがあるときはバスを利用することが多いのもまた
事実であるこれはバスの本数自体は決して多くはないものの常にほぼ時刻表通りに運
行されておりその利用に抵抗がないこととバス停が細かく配置され自宅のすぐ近くにあ
ることが理由ある特に雨の日や日射しの強い日は徒歩距離の長いグリーンラインは敬遠し
てしまうただこれは筆者の考えであり一般的であるかは全く不明であることを強調し
ておく
42コムカモ
コムカモとは学内のバス停をネットワークカメラで常に撮影しその混雑状況をどこ
からでもすぐに把握できるようにすることで帰宅時間の分散をすすめバス利用を快適化
しようとするプロジェクトであるプライバシーなどの問題から現在カメラの設置には至
っておらず署名をあつめている段階であるその詳細な経緯や根拠の説明はここでは省く
中心になってこのプロジェクトを動かしていた杉山公一郎氏の卒業制作が詳しい
バス利用者は大学生にとどまらないため私は自分の交友関係を鑑み慶応義塾湘南藤
沢中高等部の生徒にこの署名をお願いしようと考えたしかしそれにはまずこのプロジ
ェクトについての意見をうかがう必要があった昨年度から中高等部とは何度かのやりと
りがあったようであるがおそらく末端の生徒は何も知らないと思い簡単な説明を行った
うえで意見をうかがったその結果得られた回答の要点は以下である回答者の属性は
6名全員が文化部で男性が3名女性が3名また中学生4名高校生2名である
①便利だとは思うが実際に利用することはまずないと思う
②友人にも利用すると思われる人はいない
③利用するならば携帯電話からの利用になる
①の意見が多かったことによって署名のお願いは断念した①の理由について意見
をまとめると以下のようになった
ア帰る時間が決まっていて選択の余地がない
イ友人同士での帰宅が多く並ばないことの重要性は少ない
ウ現在の混雑は理解できる範囲である
筆者が意見を聞いた中高生は帰る時間が基本的に決まっておりまたその結果人が集
中し混雑することを理解していたまたそれを仕方のないものだととらえていた各自の経
験等により各自の帰る時間が決まっていることも合わさってバス停の混雑する時間帯が頭
に入っているようであったつまりバス停混雑について現在ある程度の予測ができてお
りその結果混雑が想定されていてもその時間に帰宅しているのであるよって中高生の
多くはたとえコムカモで混雑していることが判明しても帰宅することが想像できるこ
れではコムカモの必要性は感じられないだろうしかし空いている時間に帰宅したいと
いうニーズはゼロではないと思うので実際に利用するかはともかく無いよりはあるほう
が便利は便利であるというスタンスで署名をお願いすればよいのではないかと考えている

3東部方面線研究
31動機と目的
これまで日本の鉄道事業者はその鉄道建設にかかる多大な費用を沿線周辺の開発と
いう不動産事業を行うことで回収してきた古くは田園都市株式会社による田園調布の開発
に始まりまた戦後高度経済成長にあわせた都市鉄道の郊外への延伸とその沿線の開発の多
くがこの形態あった沿線を開発することで鉄道利用者が確保され鉄道事業の収益も増加
することから各鉄道事業者は90年代まで多くの路線を建設してきたそしてこれはき
わめて有効な手法であったしかし現在バブル崩壊から長く続いた日本経済の低迷の影響
等で都市域の拡大は終息都心回帰志向が強まり沿線の開発と新規路線の建設をセット
にしたビジネスモデルは成り立たなくなってしまったまたあわせて少子高齢化が進み各
鉄道事業者の輸送人員は頭打ちから減少傾向へ向かっておりまた今後は人口も減少すると
予測されているつまり今後さらなる郊外開発による収益をあてにした今までのような
鉄道事業者単独での新規鉄道の整備が極めて困難になったのである
しかしまだまだ整備すべき鉄道路線はある鉄道は民間の事業者が行う事業であり
ながらきわめて公共性が高いまたマイカー利用と比べ CO2 排出量が少ないため環境
にやさしく車利用を抑制することで交通渋滞の解消等にも役立つためさらなる整備が期
待されるよって何らかの形で鉄道の建設を国や自治体がサポートしていくことが求めら
れていた2005年に施行された「特定都市鉄道利便増進法」はこの目的に沿ったもので
あるこの法律に基づいて行われる鉄道整備事業では国自治体事業者の3者が3ぶん
の1ずつ資金を出すことになるよってその3者間の合意は必ず必要となるが各者の
利害が一致するとは限らずその合意は簡単なものではないだろう調整に長い月日を要す
ることも考えられ今後の課題になる可能性がある
そこで「特定都市鉄道利便増進法」を用いた初めてにして現在唯一の事業化例である
神奈川東部方面線事業についてその合意形成の過程を研究することによって今後の都市
鉄道整備における課題を探り現在計画されている多くの鉄道がその目的に沿ってすみや
かに建設されるために何が必要かを考えることとした
32実際の活動
はじめに東部方面線に関する基礎的な知識を得ることを目的に関係各所のホー
ムページを閲覧した以下はその一覧である
横浜市(都市整備局 鉄道整備課 『神奈川東部方面線の整備』)
httpwwwcityyokohamajpmetoshitetsudotobu
神奈川県(神奈川県には東部方面線のページはないので情報を探して閲覧以下は例)
(知事答弁)httpwwwprefkanagawajposirasehisyochijikaikenh18060630html
(輸送力増強会議)httpwwwprefkanagawajposirasetosikeikakukoutsukentetsu
相模鉄道(『都心直通プロジェクト』)
httpwwwsotetsucojptraininto_tokyoindexhtml
東急電鉄(ニュースリリースから)
httpwwwtokyucojpcontents_indexguidenews070411-1htm
鉄道運輸機構(鉄道建設 都市部における鉄道整備 『相鉄 JR 直通線』『相鉄東急直通線』)
httpwwwjrttgojpbusinesstrain_constsigotobody_soutetsu_jrhtm
httpwwwjrttgojpbusinesstrain_constsigotobody_soutetsu_tokyuhtm
つぎに新聞記事を調べた以下は参考にした記事の一部である
日本経済新聞 1997年08月16日 26ページ(地方経済面)
『神奈川 域内線充実に重点 都市拠点分散に対応』
日本経済新聞 1999年04月17日 26ページ(地方経済面)
『横浜の二俣川鶴ヶ峰地区 交通網の整備を』
日経流通新聞 1999年05月04日 9ページ
『二俣川鶴ヶ峰 交通網を整備 横浜市検討委が構想』
日本経済新聞 1999年06月08日 26ページ(地方経済面)
『JR 新横浜駅周辺の整備構想 新幹線全面停車を』
日本経済新聞 1999年11月18日 7ページ
『東北高崎常磐線の東京乗り入れ評価 運政審部会が中間報告』
日本経済新聞 2000年01月28日 39ページ(地方経済面)
『首都圏鉄道整備で運政審答申 成田新高速など盛る 県負担など調整へ』
日本経済新聞 2001年11月06日 26ページ(地方経済面)
『横浜市の次期5ヵ年計画 事業費13減緊縮型に』
日本経済新聞 2002年03月23日 26ページ(地方経済面)
『都心へ一本時間短縮 乗客伸び悩み囲い込み』
日本経済新聞 2002年04月25日 26ページ(地方経済面)
『東部方面線建設を白紙に 川崎市』
日本経済新聞 2004年09月08日 26ページ(地方経済面)
『相鉄 JR 東と乗り入れ協議 都心直結で乗客減打開 沿線開発に弾みも』
日本経済新聞 2004年09月09日 26ページ(地方経済面)
『相鉄JR 乗り入れ協議 横浜市長「これから検討」』
日本経済新聞 2004年12月22日 26ページ(地方経済面)
『神奈川東部方面線の新設 横浜市長「どちらかを優先」』
日本経済新聞 2005年12月27日 26ページ(地方経済面)
『JR との相互乗り入れ 「今年度中にメド」 相鉄社長』
日本経済新聞 2006年02月10日 12ページ
『東急と相鉄乗り入れへ 新横浜経由で連絡線』
日本経済新聞 2006年02月10日 26ページ(地方経済面)
『相鉄東急乗り入れ前進 横浜市財政負担に前向き』
日本経済新聞 2006年05月19日 26ページ(地方経済面)
『東急相鉄相互乗り入れ 国に 25 日計画提出 新横浜経由』
日本経済新聞 2006年06月02日 26ページ(地方経済面)
『相鉄東急 JR 相互乗り入れ 4億2700万円計上 横浜市が補正予算案』
日本経済新聞 2006年05月26日 26ページ(地方経済面)
『相鉄東急JR へ直通 相互乗り入れ本格始動へ』
建通新聞 2008年4月18日
『相鉄JR 直通線トンネル概略設計着手』
他多数の新聞記事を参照した
また以下の雑誌記事にも目を通した
鉄道ジャーナル 1999年12月号
『通勤輸送に徹する相模鉄道』
運輸と経済 2004年11月号
『インタビュー 地域密着を目指した経営計画の推進に向けて
--相模鉄道及川陸郎社長に聞く (特集連結経営時代のグループ戦略)』
運輸と経済 1994年11月号
『特定都市鉄道整備促進特別措置法に基づく既認定工事
--その進捗状況および同法の拡充について 』
鉄道ピクトリアル 1998年3月号
『特定都市鉄道整備事業の現状と今後 (lt特集gt大手民鉄の複々線)』
鉄道ピクトリアル 1999年7月臨時増刊号
『相模鉄道の鉄道事業を語る (lt特集gt相模鉄道)』
日本鉄道建設業協会 鉄道の礎 240 号 2007年4月
『都市鉄道等利便増進法に基づく
相鉄JR 直通線および相鉄東急直通線の速達性向上計画』
httpwwwtekkenkyoorjpkaihou24016html から閲覧
以下の雑誌記事は読みたかったが読めなかったものである
運輸と経済 197607
『10 年がかりの私鉄新線建設--相模鉄道いずみ野線』
エコノミスト 19850702
『私鉄沿線-13-横浜海老名(相模鉄道相鉄線)--首都圏の利フルに生かす』
JREA 20077
『都市鉄道利便増進事業の速達性向上計画認定--相鉄 JR 直通線相鉄東急直通線』
運輸政策研究 2008Win
『鉄道整備等基礎調査
「既存の都市鉄道ネットワークの改良による速達性向上施策 に関する調査」』
運輸と経済 20083
『都市鉄道の将来--歴史から見た考察 (特集 交通史から見た今日の交通問題)』
運輸政策研究 2007Spr
『都市鉄道等利便増進法の活用による新たな都市鉄道政策の展開』
市街地再開発 20065
『制度の紹介等 都市鉄道等利便増進法について』
運輸と経済 200510
『インタビュー都市鉄道の成長と成熟そしてどう維持するか』
JREA 20057
『都市鉄道整備の課題と今後の展望 (特集 都市交通)』
JR gazette 20053
『運輸リポート 「都市鉄道等利便増進法案」について 』
JREA 200412
『特別寄稿 政策レビュー「都市鉄道整備のあり方」の概要』
財界 20061205
『REPORT横浜市長中田宏の「新横浜を副都心から都心に変える」改造計画
2019年相鉄とJR湘南新宿ライン東急東横線が相互乗り入れ開始』
フォーブス 200502
『東武相鉄hellipJR東が私鉄と相互乗り入れする理由
新宿~東武日光鬼怒川温泉間の特急運転の開始を発表
相模鉄道との相互乗り入れ構想』
経済界 20010626
『 NEW PRESIDENT登場 相模鉄道社長及川陸郎 新しい息吹を吹き
込む遠回りしてきた男』
財界 20011
『光通信関連会社に土地を売却 私鉄大手「相模鉄道」の苦しい台所事情』
経済界 19980526
『佐藤正忠の極意対談 366回 相模鉄道会長對島好次郎
地域に一番大切なことは何か鉄道業の成長はその追求である』
夏季休業中にできるだけ読みたい
各種資料から得られた知識を筆者なりに総合し簡潔にまとめた
2003 年 「神奈川東部方面線懇談会」 関係自治体や鉄道事業者で整備に向けた調整
2005 年 都市鉄道等利便増進法施行
2004 年 相鉄 JR 直通案浮上
2006 年 相鉄 JR 直通+相鉄東急直通の形に決定し
5月営業整備計画申請 6月営業整備計画認定 8月速達性向上計画申請(相鉄 JR) 11 月速達性向上計画認定(相鉄 JR) 11 月速達性向上計画申請(相鉄東急)
2008 年 4月トンネル概略設計着手
2007 年 4月速達性向上計画認定(相鉄東急) 10 月環境影響評価方法書提出住民説明会 11 月環境影響評価公告縦覧
2000 年 運輸政策審議会答申 18 号 「A1 路線」平成 27 年までに開業が望ましい
各種資料からは存在することしか分からなかった「神奈川東部方面線懇談会」につ
いて横浜市に電話で問い合わせた
まずはじめに横浜市の市民情報室へ問い合わせの電話をかけた「神奈川東
部方面線の懇談会について知りたい」「新聞記事などで存在を知ったがもっと詳しく
知りたいと思っている会議録などは残っていないか」という旨の質問をしたところ
神奈川東部方面線を担当している部署へ電話をまわしていただけることになった
神奈川東部方面線担当の方につながったところで先ほどと同様の質問をした
担当の方も4月の異動で神奈川東部方面線担当になったようで当時の状況について
直接ご存知ないようであった少々込み入った話をしたところで一旦調べてまた
連絡していただけることになった
その後しばらくして電話をもらうがやはり議事録などは残っていない
との回答であったそこでどうにかもう少し当時の横浜市としての対応などを知る
ことができないか質問をしたまたつづけて直接お話を聞きにうかがうことはで
きないかとインタビューのお願いをしてみたところ分かる範囲でよろしければ
との回答を得ることができた
事業の当事者のひとつである横浜市から直接お話をしていただけるというのは
今後この研究をどのように進めていくかというその方向性を見定めるにもいい機会
であると思った後日こちらから電話し日時を決めることにしてこの日の電話
での質問は終了した
各種資料からは存在することしか分からなかった「神奈川東部方面線懇談会」につ
いて横浜市に直接ヒアリングにうかがった
5月27日の質問のあと6月3日に再度電話しアポイントメントを取った
結果6月9日の午後2時から横浜市庁舎にてインタビューできることになったま
た事前に質問書を送付したまた研究会で同行者をつのったところ2人一緒に来
てくださることになったとても心強かった
当日予定通り午後2時に横浜市庁舎6階へうかがった行政機関へのヒアリ
ング調査を行うのは初めてのことであり緊張した90分ほどお話をうかがいイ
ンタビューは無事終了したまたパンフレットと簡単な資料をいただいた録音した
音声ファイルを聞き返すと質問の仕方が稚拙なことが多くまた自分の主観の入っ
た質問も散見され反省するばかりである今後ヒアリング調査を行う際にはこの
点より強く心がけるようにしたい
東部方面線に関する質問票 慶應義塾大学環境情報学部 有澤研究室
日時平成20年6月9日月曜日 1400 ~ (予定) 場所横浜市役所本庁舎6階 都市整備局 (予定)
1東部方面線懇談会について
懇談会の基本的な情報を教えてください(経緯期間回数会場委員)
懇談会始動当時横浜市が重要視しておられたことについて教えてください
懇談会始動当時横浜市がすでに取り組んでおられたことについて教えてください
懇談会始動当時横浜市の各事業者等の狙いのとらえかたについて教えてください
都市鉄道等利便増進法制定との関係について教えてください
懇談会始動当時の事業化へ向けた課題について教えてください
2JR と相鉄の相互乗り入れ構想について
懇談会でのこの構想に関する議論について教えてください
新聞記事となったタイミングはどうでしたか
横浜市はこの構想をどう受け止めておられましたか
この構想と東部方面線の関係を整理する過程について教えてください
各事業者等との協議の焦点はどのようなことでしたか
3将来について
東部方面線事業に対する横浜市の今後の取り組みについて教えてください
現状横浜市が課題ととらえているのはどのようなことですか
西暦 平成
1999 11 6月 新横浜都心整備基本構想 策定
2000 12 運輸政策審議会答申18号 「A1路線」(平成27年までに開業することが望ましい) 3月 こどもの国線通勤線化
2001 13 1月 グリーンライン着工
2002 143月 市長選挙 中田氏当選6月 横浜でワールドカップ決勝が開催
2003 15 懇談会始動3月 市議会議員県議会議員県知事選挙 松沢知事当選12月 市営地下鉄全席優先席
2004 169月 JR相鉄直通新聞報道 横浜市長「協力するかこれから具体的に検討する」12月 横浜市長「(直通か東部方面線か)どちらかを優先」
2月 みなとみらい線開業
2005 17 8月 都市鉄道等利便増進法施行 9月 衆議院議員選挙 自民党圧勝
2006 18
2月 横浜市予算支出へ前向き5月 営業整備計画を事業者が申請6月 横浜市予算計上 営業整備計画認定11月 相鉄JR直通線 速達性向上計画認定
3月 市長選挙 中田氏再選
2007 194月 相鉄東急直通線 速達性向上計画認定10月~ 住民説明会など
3月 市議会議員県議会議員県知事選挙 松沢知事再選
2008 203月 グリーンライン開業6月 目黒線 日吉延伸
2009 21
2010 22
2011 23
2012 24 東横線hArr副都心線 直通開始予定
2013 25 東北縦貫線完成予定h(東海道線hArr東北高崎常磐線 直通)
2014 26
2015 27 相鉄JR直通線開業予定
2016 28
2017 29
2018 30
2019 31 相鉄東急直通線開業予定
ヒアリングで判明した内容をまとめた以下はその内容である
横浜市の方によると神奈川東部方面線懇談会とは国横浜市神奈川県東
急相鉄鉄道運輸機構であり課長レベルの方々が出席して行われたものである
とのことであったまたその下部にワークグループが存在しより詳細な調整が行
われたとのことであった会議録等の資料はやはり残っていないとの説明があった
相鉄 JR 直通線と神奈川東部方面線との関係についてはやはり新横浜を通
るか通らないかというこの違いが強調された横浜市にとって新横浜はその都市計
画において重要な位置付けをされておりその発展のためにまた横浜市西部や県央
地域から新横浜へのアクセス向上のために「新横浜を通る」東部方面線の整備が重要
であるとの説明があった横浜市にとって東部方面線は都心への直通路線としても
「もちろん大切」であるが新横浜のターミナル性を高めるために必要であることが
確認できたといえる
上記の内容から考察すると新聞記事やパンフレットでは都心への時間短縮が大
きく示されているものの横浜市としてはむしろ新横浜アクセス向上の意味が強い
と思われる都心への直通を前面に押し出し「速達性向上計画」として国に申請「都
市鉄道等利便増進法」に基づいてその整備を行うものであるが決して都内に人を吸
い上げられるだけのものではなく市の発展への意味も強くこめられていることが判
明した相鉄や東急は果たしてどう考えているのだろうか
33今後の活動
この春学期の活動を通して神奈川東部方面線についての横浜市の立場やとってきた
行動というものについての筆者の理解はとても深まったといえる同時に他の立場とい
うものについての興味を抱いた例えば相模鉄道の立場やJR の立場である横浜市にと
って極めて重要であった新横浜への到達は相模鉄道にとっていったいどれほどの価値が
あるものであったのだろうかまた相模鉄道は当時どのように考えていたのだろうか
またJR からすれば相鉄東急直通線が開通することで都心への旅客の奪いあいが発
生することが考えられるJR は「神奈川東部方面線懇談会」のメンバーではなかったもの
の決して関係ない立場ではないそれぞれに立場や目的を抱えていたはずである今後
の活動としては横浜市以外の関係者が東部方面線の事業化に向けてどのように対応し
行動をとってきたのかについて調査していきたいと考えている
またあわせてこの春学期に読むことのできなかった多くの文献に目を通したいこれ
は戦後から現在にいたるまでの鉄道整備の方式やその制度について理解しその知識を
得ることで神奈川東部方面線に関する事例研究からより思考を発展させこれからの都市
鉄道の整備に関する課題などの理解につながると思うからであるある程度の知識を習得し
自分なりに思考をしたのちより直接的な都市鉄道整備に関する先行研究を調べ論文など
を読みたいと思う
4そのほかの活動
41横浜市営地下鉄グリーンライン
2008年3月横浜市営地下鉄に新たな路線が開業した愛称をグリーンラインとい
い横浜市港北区の日吉から横浜市都筑区を縦断し横浜市緑区の中心部中山を結ぶ全長
131km の路線である日吉駅で東急東横線と目黒線に中山駅で JR 横浜線と連絡する
開業3ヵ月後の6月に東急目黒線が日吉駅まで延伸されたことで都内方面への利便性はい
くらか向上した車両はリニアモーター推進方式で車両 1 両あたりの長さは 155m現
在は4両編成であるがホームなどは編成の延長に対応し6両分の長さが用意されているよ
うである駅は10駅全線の所要時間は終日21分表定速度は約 37km で地下鉄と
してはそれなりであるが周辺路線と比較して速いとはいえないしかも運賃は非常に高い
ため東横線と横浜線の短絡線としてはほとんど機能しないものであるよって都筑区内
から東横線横浜線あるいは都筑区中心部への輸送が中心になると考えられる同じ都市
鉄道であってもグリーンラインの性質は東部方面線の性質と大きく異なるといえる都市
鉄道整備の最新の例でありまたその利用者のひとりとして今後ともその利用動向などに
は目を配っておきたい
実際の利用実績であるが4月の乗客数については目標の約半分との新聞報道があっ
た10万4千人の予想に反して結果は5万3千人にとどまっているしかし実際に毎
日利用している筆者からすると朝ラッシュ時のセンター北rarr日吉方面への混雑は日吉に近
づくにつれ相当なものとなる現状の2倍の乗客は乗れないまた夕方の時間帯の車内も空
席が目立たない程度に混んでおりこちらも現状の2倍の乗客が乗車するようではかなり
の混雑になってしまうつまり筆者が言いたいのは全体の結果として約半分になるものの
一部の時間帯や一部の区間の乗客数については目標に近いのではないだろうかというこ
とであるよって逆に予想よりかなり利用者の少ない時間帯の存在やもしくは区間によ
る偏りが大きいことが考えられるこれらはより詳細なデータを調べればわかるだろうま
た周辺のバス路線の利用者数の推移とも大いに関係するはずである今後の乗客増のため
にも横浜市等の対策に注目していきたい
筆者は都筑区北部在住であり自宅はグリーンラインの駅から徒歩10分ほどの距離
にある開通前はバスを利用し鉄道駅に向かっていたのでグリーンライン開通によってた
しかに便利になった特に最終バスが22時台と早かったため帰宅が深夜になる場合は非
常に便利であるしかし開通後もバスがあるときはバスを利用することが多いのもまた
事実であるこれはバスの本数自体は決して多くはないものの常にほぼ時刻表通りに運
行されておりその利用に抵抗がないこととバス停が細かく配置され自宅のすぐ近くにあ
ることが理由ある特に雨の日や日射しの強い日は徒歩距離の長いグリーンラインは敬遠し
てしまうただこれは筆者の考えであり一般的であるかは全く不明であることを強調し
ておく
42コムカモ
コムカモとは学内のバス停をネットワークカメラで常に撮影しその混雑状況をどこ
からでもすぐに把握できるようにすることで帰宅時間の分散をすすめバス利用を快適化
しようとするプロジェクトであるプライバシーなどの問題から現在カメラの設置には至
っておらず署名をあつめている段階であるその詳細な経緯や根拠の説明はここでは省く
中心になってこのプロジェクトを動かしていた杉山公一郎氏の卒業制作が詳しい
バス利用者は大学生にとどまらないため私は自分の交友関係を鑑み慶応義塾湘南藤
沢中高等部の生徒にこの署名をお願いしようと考えたしかしそれにはまずこのプロジ
ェクトについての意見をうかがう必要があった昨年度から中高等部とは何度かのやりと
りがあったようであるがおそらく末端の生徒は何も知らないと思い簡単な説明を行った
うえで意見をうかがったその結果得られた回答の要点は以下である回答者の属性は
6名全員が文化部で男性が3名女性が3名また中学生4名高校生2名である
①便利だとは思うが実際に利用することはまずないと思う
②友人にも利用すると思われる人はいない
③利用するならば携帯電話からの利用になる
①の意見が多かったことによって署名のお願いは断念した①の理由について意見
をまとめると以下のようになった
ア帰る時間が決まっていて選択の余地がない
イ友人同士での帰宅が多く並ばないことの重要性は少ない
ウ現在の混雑は理解できる範囲である
筆者が意見を聞いた中高生は帰る時間が基本的に決まっておりまたその結果人が集
中し混雑することを理解していたまたそれを仕方のないものだととらえていた各自の経
験等により各自の帰る時間が決まっていることも合わさってバス停の混雑する時間帯が頭
に入っているようであったつまりバス停混雑について現在ある程度の予測ができてお
りその結果混雑が想定されていてもその時間に帰宅しているのであるよって中高生の
多くはたとえコムカモで混雑していることが判明しても帰宅することが想像できるこ
れではコムカモの必要性は感じられないだろうしかし空いている時間に帰宅したいと
いうニーズはゼロではないと思うので実際に利用するかはともかく無いよりはあるほう
が便利は便利であるというスタンスで署名をお願いすればよいのではないかと考えている

32実際の活動
はじめに東部方面線に関する基礎的な知識を得ることを目的に関係各所のホー
ムページを閲覧した以下はその一覧である
横浜市(都市整備局 鉄道整備課 『神奈川東部方面線の整備』)
httpwwwcityyokohamajpmetoshitetsudotobu
神奈川県(神奈川県には東部方面線のページはないので情報を探して閲覧以下は例)
(知事答弁)httpwwwprefkanagawajposirasehisyochijikaikenh18060630html
(輸送力増強会議)httpwwwprefkanagawajposirasetosikeikakukoutsukentetsu
相模鉄道(『都心直通プロジェクト』)
httpwwwsotetsucojptraininto_tokyoindexhtml
東急電鉄(ニュースリリースから)
httpwwwtokyucojpcontents_indexguidenews070411-1htm
鉄道運輸機構(鉄道建設 都市部における鉄道整備 『相鉄 JR 直通線』『相鉄東急直通線』)
httpwwwjrttgojpbusinesstrain_constsigotobody_soutetsu_jrhtm
httpwwwjrttgojpbusinesstrain_constsigotobody_soutetsu_tokyuhtm
つぎに新聞記事を調べた以下は参考にした記事の一部である
日本経済新聞 1997年08月16日 26ページ(地方経済面)
『神奈川 域内線充実に重点 都市拠点分散に対応』
日本経済新聞 1999年04月17日 26ページ(地方経済面)
『横浜の二俣川鶴ヶ峰地区 交通網の整備を』
日経流通新聞 1999年05月04日 9ページ
『二俣川鶴ヶ峰 交通網を整備 横浜市検討委が構想』
日本経済新聞 1999年06月08日 26ページ(地方経済面)
『JR 新横浜駅周辺の整備構想 新幹線全面停車を』
日本経済新聞 1999年11月18日 7ページ
『東北高崎常磐線の東京乗り入れ評価 運政審部会が中間報告』
日本経済新聞 2000年01月28日 39ページ(地方経済面)
『首都圏鉄道整備で運政審答申 成田新高速など盛る 県負担など調整へ』
日本経済新聞 2001年11月06日 26ページ(地方経済面)
『横浜市の次期5ヵ年計画 事業費13減緊縮型に』
日本経済新聞 2002年03月23日 26ページ(地方経済面)
『都心へ一本時間短縮 乗客伸び悩み囲い込み』
日本経済新聞 2002年04月25日 26ページ(地方経済面)
『東部方面線建設を白紙に 川崎市』
日本経済新聞 2004年09月08日 26ページ(地方経済面)
『相鉄 JR 東と乗り入れ協議 都心直結で乗客減打開 沿線開発に弾みも』
日本経済新聞 2004年09月09日 26ページ(地方経済面)
『相鉄JR 乗り入れ協議 横浜市長「これから検討」』
日本経済新聞 2004年12月22日 26ページ(地方経済面)
『神奈川東部方面線の新設 横浜市長「どちらかを優先」』
日本経済新聞 2005年12月27日 26ページ(地方経済面)
『JR との相互乗り入れ 「今年度中にメド」 相鉄社長』
日本経済新聞 2006年02月10日 12ページ
『東急と相鉄乗り入れへ 新横浜経由で連絡線』
日本経済新聞 2006年02月10日 26ページ(地方経済面)
『相鉄東急乗り入れ前進 横浜市財政負担に前向き』
日本経済新聞 2006年05月19日 26ページ(地方経済面)
『東急相鉄相互乗り入れ 国に 25 日計画提出 新横浜経由』
日本経済新聞 2006年06月02日 26ページ(地方経済面)
『相鉄東急 JR 相互乗り入れ 4億2700万円計上 横浜市が補正予算案』
日本経済新聞 2006年05月26日 26ページ(地方経済面)
『相鉄東急JR へ直通 相互乗り入れ本格始動へ』
建通新聞 2008年4月18日
『相鉄JR 直通線トンネル概略設計着手』
他多数の新聞記事を参照した
また以下の雑誌記事にも目を通した
鉄道ジャーナル 1999年12月号
『通勤輸送に徹する相模鉄道』
運輸と経済 2004年11月号
『インタビュー 地域密着を目指した経営計画の推進に向けて
--相模鉄道及川陸郎社長に聞く (特集連結経営時代のグループ戦略)』
運輸と経済 1994年11月号
『特定都市鉄道整備促進特別措置法に基づく既認定工事
--その進捗状況および同法の拡充について 』
鉄道ピクトリアル 1998年3月号
『特定都市鉄道整備事業の現状と今後 (lt特集gt大手民鉄の複々線)』
鉄道ピクトリアル 1999年7月臨時増刊号
『相模鉄道の鉄道事業を語る (lt特集gt相模鉄道)』
日本鉄道建設業協会 鉄道の礎 240 号 2007年4月
『都市鉄道等利便増進法に基づく
相鉄JR 直通線および相鉄東急直通線の速達性向上計画』
httpwwwtekkenkyoorjpkaihou24016html から閲覧
以下の雑誌記事は読みたかったが読めなかったものである
運輸と経済 197607
『10 年がかりの私鉄新線建設--相模鉄道いずみ野線』
エコノミスト 19850702
『私鉄沿線-13-横浜海老名(相模鉄道相鉄線)--首都圏の利フルに生かす』
JREA 20077
『都市鉄道利便増進事業の速達性向上計画認定--相鉄 JR 直通線相鉄東急直通線』
運輸政策研究 2008Win
『鉄道整備等基礎調査
「既存の都市鉄道ネットワークの改良による速達性向上施策 に関する調査」』
運輸と経済 20083
『都市鉄道の将来--歴史から見た考察 (特集 交通史から見た今日の交通問題)』
運輸政策研究 2007Spr
『都市鉄道等利便増進法の活用による新たな都市鉄道政策の展開』
市街地再開発 20065
『制度の紹介等 都市鉄道等利便増進法について』
運輸と経済 200510
『インタビュー都市鉄道の成長と成熟そしてどう維持するか』
JREA 20057
『都市鉄道整備の課題と今後の展望 (特集 都市交通)』
JR gazette 20053
『運輸リポート 「都市鉄道等利便増進法案」について 』
JREA 200412
『特別寄稿 政策レビュー「都市鉄道整備のあり方」の概要』
財界 20061205
『REPORT横浜市長中田宏の「新横浜を副都心から都心に変える」改造計画
2019年相鉄とJR湘南新宿ライン東急東横線が相互乗り入れ開始』
フォーブス 200502
『東武相鉄hellipJR東が私鉄と相互乗り入れする理由
新宿~東武日光鬼怒川温泉間の特急運転の開始を発表
相模鉄道との相互乗り入れ構想』
経済界 20010626
『 NEW PRESIDENT登場 相模鉄道社長及川陸郎 新しい息吹を吹き
込む遠回りしてきた男』
財界 20011
『光通信関連会社に土地を売却 私鉄大手「相模鉄道」の苦しい台所事情』
経済界 19980526
『佐藤正忠の極意対談 366回 相模鉄道会長對島好次郎
地域に一番大切なことは何か鉄道業の成長はその追求である』
夏季休業中にできるだけ読みたい
各種資料から得られた知識を筆者なりに総合し簡潔にまとめた
2003 年 「神奈川東部方面線懇談会」 関係自治体や鉄道事業者で整備に向けた調整
2005 年 都市鉄道等利便増進法施行
2004 年 相鉄 JR 直通案浮上
2006 年 相鉄 JR 直通+相鉄東急直通の形に決定し
5月営業整備計画申請 6月営業整備計画認定 8月速達性向上計画申請(相鉄 JR) 11 月速達性向上計画認定(相鉄 JR) 11 月速達性向上計画申請(相鉄東急)
2008 年 4月トンネル概略設計着手
2007 年 4月速達性向上計画認定(相鉄東急) 10 月環境影響評価方法書提出住民説明会 11 月環境影響評価公告縦覧
2000 年 運輸政策審議会答申 18 号 「A1 路線」平成 27 年までに開業が望ましい
各種資料からは存在することしか分からなかった「神奈川東部方面線懇談会」につ
いて横浜市に電話で問い合わせた
まずはじめに横浜市の市民情報室へ問い合わせの電話をかけた「神奈川東
部方面線の懇談会について知りたい」「新聞記事などで存在を知ったがもっと詳しく
知りたいと思っている会議録などは残っていないか」という旨の質問をしたところ
神奈川東部方面線を担当している部署へ電話をまわしていただけることになった
神奈川東部方面線担当の方につながったところで先ほどと同様の質問をした
担当の方も4月の異動で神奈川東部方面線担当になったようで当時の状況について
直接ご存知ないようであった少々込み入った話をしたところで一旦調べてまた
連絡していただけることになった
その後しばらくして電話をもらうがやはり議事録などは残っていない
との回答であったそこでどうにかもう少し当時の横浜市としての対応などを知る
ことができないか質問をしたまたつづけて直接お話を聞きにうかがうことはで
きないかとインタビューのお願いをしてみたところ分かる範囲でよろしければ
との回答を得ることができた
事業の当事者のひとつである横浜市から直接お話をしていただけるというのは
今後この研究をどのように進めていくかというその方向性を見定めるにもいい機会
であると思った後日こちらから電話し日時を決めることにしてこの日の電話
での質問は終了した
各種資料からは存在することしか分からなかった「神奈川東部方面線懇談会」につ
いて横浜市に直接ヒアリングにうかがった
5月27日の質問のあと6月3日に再度電話しアポイントメントを取った
結果6月9日の午後2時から横浜市庁舎にてインタビューできることになったま
た事前に質問書を送付したまた研究会で同行者をつのったところ2人一緒に来
てくださることになったとても心強かった
当日予定通り午後2時に横浜市庁舎6階へうかがった行政機関へのヒアリ
ング調査を行うのは初めてのことであり緊張した90分ほどお話をうかがいイ
ンタビューは無事終了したまたパンフレットと簡単な資料をいただいた録音した
音声ファイルを聞き返すと質問の仕方が稚拙なことが多くまた自分の主観の入っ
た質問も散見され反省するばかりである今後ヒアリング調査を行う際にはこの
点より強く心がけるようにしたい
東部方面線に関する質問票 慶應義塾大学環境情報学部 有澤研究室
日時平成20年6月9日月曜日 1400 ~ (予定) 場所横浜市役所本庁舎6階 都市整備局 (予定)
1東部方面線懇談会について
懇談会の基本的な情報を教えてください(経緯期間回数会場委員)
懇談会始動当時横浜市が重要視しておられたことについて教えてください
懇談会始動当時横浜市がすでに取り組んでおられたことについて教えてください
懇談会始動当時横浜市の各事業者等の狙いのとらえかたについて教えてください
都市鉄道等利便増進法制定との関係について教えてください
懇談会始動当時の事業化へ向けた課題について教えてください
2JR と相鉄の相互乗り入れ構想について
懇談会でのこの構想に関する議論について教えてください
新聞記事となったタイミングはどうでしたか
横浜市はこの構想をどう受け止めておられましたか
この構想と東部方面線の関係を整理する過程について教えてください
各事業者等との協議の焦点はどのようなことでしたか
3将来について
東部方面線事業に対する横浜市の今後の取り組みについて教えてください
現状横浜市が課題ととらえているのはどのようなことですか
西暦 平成
1999 11 6月 新横浜都心整備基本構想 策定
2000 12 運輸政策審議会答申18号 「A1路線」(平成27年までに開業することが望ましい) 3月 こどもの国線通勤線化
2001 13 1月 グリーンライン着工
2002 143月 市長選挙 中田氏当選6月 横浜でワールドカップ決勝が開催
2003 15 懇談会始動3月 市議会議員県議会議員県知事選挙 松沢知事当選12月 市営地下鉄全席優先席
2004 169月 JR相鉄直通新聞報道 横浜市長「協力するかこれから具体的に検討する」12月 横浜市長「(直通か東部方面線か)どちらかを優先」
2月 みなとみらい線開業
2005 17 8月 都市鉄道等利便増進法施行 9月 衆議院議員選挙 自民党圧勝
2006 18
2月 横浜市予算支出へ前向き5月 営業整備計画を事業者が申請6月 横浜市予算計上 営業整備計画認定11月 相鉄JR直通線 速達性向上計画認定
3月 市長選挙 中田氏再選
2007 194月 相鉄東急直通線 速達性向上計画認定10月~ 住民説明会など
3月 市議会議員県議会議員県知事選挙 松沢知事再選
2008 203月 グリーンライン開業6月 目黒線 日吉延伸
2009 21
2010 22
2011 23
2012 24 東横線hArr副都心線 直通開始予定
2013 25 東北縦貫線完成予定h(東海道線hArr東北高崎常磐線 直通)
2014 26
2015 27 相鉄JR直通線開業予定
2016 28
2017 29
2018 30
2019 31 相鉄東急直通線開業予定
ヒアリングで判明した内容をまとめた以下はその内容である
横浜市の方によると神奈川東部方面線懇談会とは国横浜市神奈川県東
急相鉄鉄道運輸機構であり課長レベルの方々が出席して行われたものである
とのことであったまたその下部にワークグループが存在しより詳細な調整が行
われたとのことであった会議録等の資料はやはり残っていないとの説明があった
相鉄 JR 直通線と神奈川東部方面線との関係についてはやはり新横浜を通
るか通らないかというこの違いが強調された横浜市にとって新横浜はその都市計
画において重要な位置付けをされておりその発展のためにまた横浜市西部や県央
地域から新横浜へのアクセス向上のために「新横浜を通る」東部方面線の整備が重要
であるとの説明があった横浜市にとって東部方面線は都心への直通路線としても
「もちろん大切」であるが新横浜のターミナル性を高めるために必要であることが
確認できたといえる
上記の内容から考察すると新聞記事やパンフレットでは都心への時間短縮が大
きく示されているものの横浜市としてはむしろ新横浜アクセス向上の意味が強い
と思われる都心への直通を前面に押し出し「速達性向上計画」として国に申請「都
市鉄道等利便増進法」に基づいてその整備を行うものであるが決して都内に人を吸
い上げられるだけのものではなく市の発展への意味も強くこめられていることが判
明した相鉄や東急は果たしてどう考えているのだろうか
33今後の活動
この春学期の活動を通して神奈川東部方面線についての横浜市の立場やとってきた
行動というものについての筆者の理解はとても深まったといえる同時に他の立場とい
うものについての興味を抱いた例えば相模鉄道の立場やJR の立場である横浜市にと
って極めて重要であった新横浜への到達は相模鉄道にとっていったいどれほどの価値が
あるものであったのだろうかまた相模鉄道は当時どのように考えていたのだろうか
またJR からすれば相鉄東急直通線が開通することで都心への旅客の奪いあいが発
生することが考えられるJR は「神奈川東部方面線懇談会」のメンバーではなかったもの
の決して関係ない立場ではないそれぞれに立場や目的を抱えていたはずである今後
の活動としては横浜市以外の関係者が東部方面線の事業化に向けてどのように対応し
行動をとってきたのかについて調査していきたいと考えている
またあわせてこの春学期に読むことのできなかった多くの文献に目を通したいこれ
は戦後から現在にいたるまでの鉄道整備の方式やその制度について理解しその知識を
得ることで神奈川東部方面線に関する事例研究からより思考を発展させこれからの都市
鉄道の整備に関する課題などの理解につながると思うからであるある程度の知識を習得し
自分なりに思考をしたのちより直接的な都市鉄道整備に関する先行研究を調べ論文など
を読みたいと思う
4そのほかの活動
41横浜市営地下鉄グリーンライン
2008年3月横浜市営地下鉄に新たな路線が開業した愛称をグリーンラインとい
い横浜市港北区の日吉から横浜市都筑区を縦断し横浜市緑区の中心部中山を結ぶ全長
131km の路線である日吉駅で東急東横線と目黒線に中山駅で JR 横浜線と連絡する
開業3ヵ月後の6月に東急目黒線が日吉駅まで延伸されたことで都内方面への利便性はい
くらか向上した車両はリニアモーター推進方式で車両 1 両あたりの長さは 155m現
在は4両編成であるがホームなどは編成の延長に対応し6両分の長さが用意されているよ
うである駅は10駅全線の所要時間は終日21分表定速度は約 37km で地下鉄と
してはそれなりであるが周辺路線と比較して速いとはいえないしかも運賃は非常に高い
ため東横線と横浜線の短絡線としてはほとんど機能しないものであるよって都筑区内
から東横線横浜線あるいは都筑区中心部への輸送が中心になると考えられる同じ都市
鉄道であってもグリーンラインの性質は東部方面線の性質と大きく異なるといえる都市
鉄道整備の最新の例でありまたその利用者のひとりとして今後ともその利用動向などに
は目を配っておきたい
実際の利用実績であるが4月の乗客数については目標の約半分との新聞報道があっ
た10万4千人の予想に反して結果は5万3千人にとどまっているしかし実際に毎
日利用している筆者からすると朝ラッシュ時のセンター北rarr日吉方面への混雑は日吉に近
づくにつれ相当なものとなる現状の2倍の乗客は乗れないまた夕方の時間帯の車内も空
席が目立たない程度に混んでおりこちらも現状の2倍の乗客が乗車するようではかなり
の混雑になってしまうつまり筆者が言いたいのは全体の結果として約半分になるものの
一部の時間帯や一部の区間の乗客数については目標に近いのではないだろうかというこ
とであるよって逆に予想よりかなり利用者の少ない時間帯の存在やもしくは区間によ
る偏りが大きいことが考えられるこれらはより詳細なデータを調べればわかるだろうま
た周辺のバス路線の利用者数の推移とも大いに関係するはずである今後の乗客増のため
にも横浜市等の対策に注目していきたい
筆者は都筑区北部在住であり自宅はグリーンラインの駅から徒歩10分ほどの距離
にある開通前はバスを利用し鉄道駅に向かっていたのでグリーンライン開通によってた
しかに便利になった特に最終バスが22時台と早かったため帰宅が深夜になる場合は非
常に便利であるしかし開通後もバスがあるときはバスを利用することが多いのもまた
事実であるこれはバスの本数自体は決して多くはないものの常にほぼ時刻表通りに運
行されておりその利用に抵抗がないこととバス停が細かく配置され自宅のすぐ近くにあ
ることが理由ある特に雨の日や日射しの強い日は徒歩距離の長いグリーンラインは敬遠し
てしまうただこれは筆者の考えであり一般的であるかは全く不明であることを強調し
ておく
42コムカモ
コムカモとは学内のバス停をネットワークカメラで常に撮影しその混雑状況をどこ
からでもすぐに把握できるようにすることで帰宅時間の分散をすすめバス利用を快適化
しようとするプロジェクトであるプライバシーなどの問題から現在カメラの設置には至
っておらず署名をあつめている段階であるその詳細な経緯や根拠の説明はここでは省く
中心になってこのプロジェクトを動かしていた杉山公一郎氏の卒業制作が詳しい
バス利用者は大学生にとどまらないため私は自分の交友関係を鑑み慶応義塾湘南藤
沢中高等部の生徒にこの署名をお願いしようと考えたしかしそれにはまずこのプロジ
ェクトについての意見をうかがう必要があった昨年度から中高等部とは何度かのやりと
りがあったようであるがおそらく末端の生徒は何も知らないと思い簡単な説明を行った
うえで意見をうかがったその結果得られた回答の要点は以下である回答者の属性は
6名全員が文化部で男性が3名女性が3名また中学生4名高校生2名である
①便利だとは思うが実際に利用することはまずないと思う
②友人にも利用すると思われる人はいない
③利用するならば携帯電話からの利用になる
①の意見が多かったことによって署名のお願いは断念した①の理由について意見
をまとめると以下のようになった
ア帰る時間が決まっていて選択の余地がない
イ友人同士での帰宅が多く並ばないことの重要性は少ない
ウ現在の混雑は理解できる範囲である
筆者が意見を聞いた中高生は帰る時間が基本的に決まっておりまたその結果人が集
中し混雑することを理解していたまたそれを仕方のないものだととらえていた各自の経
験等により各自の帰る時間が決まっていることも合わさってバス停の混雑する時間帯が頭
に入っているようであったつまりバス停混雑について現在ある程度の予測ができてお
りその結果混雑が想定されていてもその時間に帰宅しているのであるよって中高生の
多くはたとえコムカモで混雑していることが判明しても帰宅することが想像できるこ
れではコムカモの必要性は感じられないだろうしかし空いている時間に帰宅したいと
いうニーズはゼロではないと思うので実際に利用するかはともかく無いよりはあるほう
が便利は便利であるというスタンスで署名をお願いすればよいのではないかと考えている

日本経済新聞 2000年01月28日 39ページ(地方経済面)
『首都圏鉄道整備で運政審答申 成田新高速など盛る 県負担など調整へ』
日本経済新聞 2001年11月06日 26ページ(地方経済面)
『横浜市の次期5ヵ年計画 事業費13減緊縮型に』
日本経済新聞 2002年03月23日 26ページ(地方経済面)
『都心へ一本時間短縮 乗客伸び悩み囲い込み』
日本経済新聞 2002年04月25日 26ページ(地方経済面)
『東部方面線建設を白紙に 川崎市』
日本経済新聞 2004年09月08日 26ページ(地方経済面)
『相鉄 JR 東と乗り入れ協議 都心直結で乗客減打開 沿線開発に弾みも』
日本経済新聞 2004年09月09日 26ページ(地方経済面)
『相鉄JR 乗り入れ協議 横浜市長「これから検討」』
日本経済新聞 2004年12月22日 26ページ(地方経済面)
『神奈川東部方面線の新設 横浜市長「どちらかを優先」』
日本経済新聞 2005年12月27日 26ページ(地方経済面)
『JR との相互乗り入れ 「今年度中にメド」 相鉄社長』
日本経済新聞 2006年02月10日 12ページ
『東急と相鉄乗り入れへ 新横浜経由で連絡線』
日本経済新聞 2006年02月10日 26ページ(地方経済面)
『相鉄東急乗り入れ前進 横浜市財政負担に前向き』
日本経済新聞 2006年05月19日 26ページ(地方経済面)
『東急相鉄相互乗り入れ 国に 25 日計画提出 新横浜経由』
日本経済新聞 2006年06月02日 26ページ(地方経済面)
『相鉄東急 JR 相互乗り入れ 4億2700万円計上 横浜市が補正予算案』
日本経済新聞 2006年05月26日 26ページ(地方経済面)
『相鉄東急JR へ直通 相互乗り入れ本格始動へ』
建通新聞 2008年4月18日
『相鉄JR 直通線トンネル概略設計着手』
他多数の新聞記事を参照した
また以下の雑誌記事にも目を通した
鉄道ジャーナル 1999年12月号
『通勤輸送に徹する相模鉄道』
運輸と経済 2004年11月号
『インタビュー 地域密着を目指した経営計画の推進に向けて
--相模鉄道及川陸郎社長に聞く (特集連結経営時代のグループ戦略)』
運輸と経済 1994年11月号
『特定都市鉄道整備促進特別措置法に基づく既認定工事
--その進捗状況および同法の拡充について 』
鉄道ピクトリアル 1998年3月号
『特定都市鉄道整備事業の現状と今後 (lt特集gt大手民鉄の複々線)』
鉄道ピクトリアル 1999年7月臨時増刊号
『相模鉄道の鉄道事業を語る (lt特集gt相模鉄道)』
日本鉄道建設業協会 鉄道の礎 240 号 2007年4月
『都市鉄道等利便増進法に基づく
相鉄JR 直通線および相鉄東急直通線の速達性向上計画』
httpwwwtekkenkyoorjpkaihou24016html から閲覧
以下の雑誌記事は読みたかったが読めなかったものである
運輸と経済 197607
『10 年がかりの私鉄新線建設--相模鉄道いずみ野線』
エコノミスト 19850702
『私鉄沿線-13-横浜海老名(相模鉄道相鉄線)--首都圏の利フルに生かす』
JREA 20077
『都市鉄道利便増進事業の速達性向上計画認定--相鉄 JR 直通線相鉄東急直通線』
運輸政策研究 2008Win
『鉄道整備等基礎調査
「既存の都市鉄道ネットワークの改良による速達性向上施策 に関する調査」』
運輸と経済 20083
『都市鉄道の将来--歴史から見た考察 (特集 交通史から見た今日の交通問題)』
運輸政策研究 2007Spr
『都市鉄道等利便増進法の活用による新たな都市鉄道政策の展開』
市街地再開発 20065
『制度の紹介等 都市鉄道等利便増進法について』
運輸と経済 200510
『インタビュー都市鉄道の成長と成熟そしてどう維持するか』
JREA 20057
『都市鉄道整備の課題と今後の展望 (特集 都市交通)』
JR gazette 20053
『運輸リポート 「都市鉄道等利便増進法案」について 』
JREA 200412
『特別寄稿 政策レビュー「都市鉄道整備のあり方」の概要』
財界 20061205
『REPORT横浜市長中田宏の「新横浜を副都心から都心に変える」改造計画
2019年相鉄とJR湘南新宿ライン東急東横線が相互乗り入れ開始』
フォーブス 200502
『東武相鉄hellipJR東が私鉄と相互乗り入れする理由
新宿~東武日光鬼怒川温泉間の特急運転の開始を発表
相模鉄道との相互乗り入れ構想』
経済界 20010626
『 NEW PRESIDENT登場 相模鉄道社長及川陸郎 新しい息吹を吹き
込む遠回りしてきた男』
財界 20011
『光通信関連会社に土地を売却 私鉄大手「相模鉄道」の苦しい台所事情』
経済界 19980526
『佐藤正忠の極意対談 366回 相模鉄道会長對島好次郎
地域に一番大切なことは何か鉄道業の成長はその追求である』
夏季休業中にできるだけ読みたい
各種資料から得られた知識を筆者なりに総合し簡潔にまとめた
2003 年 「神奈川東部方面線懇談会」 関係自治体や鉄道事業者で整備に向けた調整
2005 年 都市鉄道等利便増進法施行
2004 年 相鉄 JR 直通案浮上
2006 年 相鉄 JR 直通+相鉄東急直通の形に決定し
5月営業整備計画申請 6月営業整備計画認定 8月速達性向上計画申請(相鉄 JR) 11 月速達性向上計画認定(相鉄 JR) 11 月速達性向上計画申請(相鉄東急)
2008 年 4月トンネル概略設計着手
2007 年 4月速達性向上計画認定(相鉄東急) 10 月環境影響評価方法書提出住民説明会 11 月環境影響評価公告縦覧
2000 年 運輸政策審議会答申 18 号 「A1 路線」平成 27 年までに開業が望ましい
各種資料からは存在することしか分からなかった「神奈川東部方面線懇談会」につ
いて横浜市に電話で問い合わせた
まずはじめに横浜市の市民情報室へ問い合わせの電話をかけた「神奈川東
部方面線の懇談会について知りたい」「新聞記事などで存在を知ったがもっと詳しく
知りたいと思っている会議録などは残っていないか」という旨の質問をしたところ
神奈川東部方面線を担当している部署へ電話をまわしていただけることになった
神奈川東部方面線担当の方につながったところで先ほどと同様の質問をした
担当の方も4月の異動で神奈川東部方面線担当になったようで当時の状況について
直接ご存知ないようであった少々込み入った話をしたところで一旦調べてまた
連絡していただけることになった
その後しばらくして電話をもらうがやはり議事録などは残っていない
との回答であったそこでどうにかもう少し当時の横浜市としての対応などを知る
ことができないか質問をしたまたつづけて直接お話を聞きにうかがうことはで
きないかとインタビューのお願いをしてみたところ分かる範囲でよろしければ
との回答を得ることができた
事業の当事者のひとつである横浜市から直接お話をしていただけるというのは
今後この研究をどのように進めていくかというその方向性を見定めるにもいい機会
であると思った後日こちらから電話し日時を決めることにしてこの日の電話
での質問は終了した
各種資料からは存在することしか分からなかった「神奈川東部方面線懇談会」につ
いて横浜市に直接ヒアリングにうかがった
5月27日の質問のあと6月3日に再度電話しアポイントメントを取った
結果6月9日の午後2時から横浜市庁舎にてインタビューできることになったま
た事前に質問書を送付したまた研究会で同行者をつのったところ2人一緒に来
てくださることになったとても心強かった
当日予定通り午後2時に横浜市庁舎6階へうかがった行政機関へのヒアリ
ング調査を行うのは初めてのことであり緊張した90分ほどお話をうかがいイ
ンタビューは無事終了したまたパンフレットと簡単な資料をいただいた録音した
音声ファイルを聞き返すと質問の仕方が稚拙なことが多くまた自分の主観の入っ
た質問も散見され反省するばかりである今後ヒアリング調査を行う際にはこの
点より強く心がけるようにしたい
東部方面線に関する質問票 慶應義塾大学環境情報学部 有澤研究室
日時平成20年6月9日月曜日 1400 ~ (予定) 場所横浜市役所本庁舎6階 都市整備局 (予定)
1東部方面線懇談会について
懇談会の基本的な情報を教えてください(経緯期間回数会場委員)
懇談会始動当時横浜市が重要視しておられたことについて教えてください
懇談会始動当時横浜市がすでに取り組んでおられたことについて教えてください
懇談会始動当時横浜市の各事業者等の狙いのとらえかたについて教えてください
都市鉄道等利便増進法制定との関係について教えてください
懇談会始動当時の事業化へ向けた課題について教えてください
2JR と相鉄の相互乗り入れ構想について
懇談会でのこの構想に関する議論について教えてください
新聞記事となったタイミングはどうでしたか
横浜市はこの構想をどう受け止めておられましたか
この構想と東部方面線の関係を整理する過程について教えてください
各事業者等との協議の焦点はどのようなことでしたか
3将来について
東部方面線事業に対する横浜市の今後の取り組みについて教えてください
現状横浜市が課題ととらえているのはどのようなことですか
西暦 平成
1999 11 6月 新横浜都心整備基本構想 策定
2000 12 運輸政策審議会答申18号 「A1路線」(平成27年までに開業することが望ましい) 3月 こどもの国線通勤線化
2001 13 1月 グリーンライン着工
2002 143月 市長選挙 中田氏当選6月 横浜でワールドカップ決勝が開催
2003 15 懇談会始動3月 市議会議員県議会議員県知事選挙 松沢知事当選12月 市営地下鉄全席優先席
2004 169月 JR相鉄直通新聞報道 横浜市長「協力するかこれから具体的に検討する」12月 横浜市長「(直通か東部方面線か)どちらかを優先」
2月 みなとみらい線開業
2005 17 8月 都市鉄道等利便増進法施行 9月 衆議院議員選挙 自民党圧勝
2006 18
2月 横浜市予算支出へ前向き5月 営業整備計画を事業者が申請6月 横浜市予算計上 営業整備計画認定11月 相鉄JR直通線 速達性向上計画認定
3月 市長選挙 中田氏再選
2007 194月 相鉄東急直通線 速達性向上計画認定10月~ 住民説明会など
3月 市議会議員県議会議員県知事選挙 松沢知事再選
2008 203月 グリーンライン開業6月 目黒線 日吉延伸
2009 21
2010 22
2011 23
2012 24 東横線hArr副都心線 直通開始予定
2013 25 東北縦貫線完成予定h(東海道線hArr東北高崎常磐線 直通)
2014 26
2015 27 相鉄JR直通線開業予定
2016 28
2017 29
2018 30
2019 31 相鉄東急直通線開業予定
ヒアリングで判明した内容をまとめた以下はその内容である
横浜市の方によると神奈川東部方面線懇談会とは国横浜市神奈川県東
急相鉄鉄道運輸機構であり課長レベルの方々が出席して行われたものである
とのことであったまたその下部にワークグループが存在しより詳細な調整が行
われたとのことであった会議録等の資料はやはり残っていないとの説明があった
相鉄 JR 直通線と神奈川東部方面線との関係についてはやはり新横浜を通
るか通らないかというこの違いが強調された横浜市にとって新横浜はその都市計
画において重要な位置付けをされておりその発展のためにまた横浜市西部や県央
地域から新横浜へのアクセス向上のために「新横浜を通る」東部方面線の整備が重要
であるとの説明があった横浜市にとって東部方面線は都心への直通路線としても
「もちろん大切」であるが新横浜のターミナル性を高めるために必要であることが
確認できたといえる
上記の内容から考察すると新聞記事やパンフレットでは都心への時間短縮が大
きく示されているものの横浜市としてはむしろ新横浜アクセス向上の意味が強い
と思われる都心への直通を前面に押し出し「速達性向上計画」として国に申請「都
市鉄道等利便増進法」に基づいてその整備を行うものであるが決して都内に人を吸
い上げられるだけのものではなく市の発展への意味も強くこめられていることが判
明した相鉄や東急は果たしてどう考えているのだろうか
33今後の活動
この春学期の活動を通して神奈川東部方面線についての横浜市の立場やとってきた
行動というものについての筆者の理解はとても深まったといえる同時に他の立場とい
うものについての興味を抱いた例えば相模鉄道の立場やJR の立場である横浜市にと
って極めて重要であった新横浜への到達は相模鉄道にとっていったいどれほどの価値が
あるものであったのだろうかまた相模鉄道は当時どのように考えていたのだろうか
またJR からすれば相鉄東急直通線が開通することで都心への旅客の奪いあいが発
生することが考えられるJR は「神奈川東部方面線懇談会」のメンバーではなかったもの
の決して関係ない立場ではないそれぞれに立場や目的を抱えていたはずである今後
の活動としては横浜市以外の関係者が東部方面線の事業化に向けてどのように対応し
行動をとってきたのかについて調査していきたいと考えている
またあわせてこの春学期に読むことのできなかった多くの文献に目を通したいこれ
は戦後から現在にいたるまでの鉄道整備の方式やその制度について理解しその知識を
得ることで神奈川東部方面線に関する事例研究からより思考を発展させこれからの都市
鉄道の整備に関する課題などの理解につながると思うからであるある程度の知識を習得し
自分なりに思考をしたのちより直接的な都市鉄道整備に関する先行研究を調べ論文など
を読みたいと思う
4そのほかの活動
41横浜市営地下鉄グリーンライン
2008年3月横浜市営地下鉄に新たな路線が開業した愛称をグリーンラインとい
い横浜市港北区の日吉から横浜市都筑区を縦断し横浜市緑区の中心部中山を結ぶ全長
131km の路線である日吉駅で東急東横線と目黒線に中山駅で JR 横浜線と連絡する
開業3ヵ月後の6月に東急目黒線が日吉駅まで延伸されたことで都内方面への利便性はい
くらか向上した車両はリニアモーター推進方式で車両 1 両あたりの長さは 155m現
在は4両編成であるがホームなどは編成の延長に対応し6両分の長さが用意されているよ
うである駅は10駅全線の所要時間は終日21分表定速度は約 37km で地下鉄と
してはそれなりであるが周辺路線と比較して速いとはいえないしかも運賃は非常に高い
ため東横線と横浜線の短絡線としてはほとんど機能しないものであるよって都筑区内
から東横線横浜線あるいは都筑区中心部への輸送が中心になると考えられる同じ都市
鉄道であってもグリーンラインの性質は東部方面線の性質と大きく異なるといえる都市
鉄道整備の最新の例でありまたその利用者のひとりとして今後ともその利用動向などに
は目を配っておきたい
実際の利用実績であるが4月の乗客数については目標の約半分との新聞報道があっ
た10万4千人の予想に反して結果は5万3千人にとどまっているしかし実際に毎
日利用している筆者からすると朝ラッシュ時のセンター北rarr日吉方面への混雑は日吉に近
づくにつれ相当なものとなる現状の2倍の乗客は乗れないまた夕方の時間帯の車内も空
席が目立たない程度に混んでおりこちらも現状の2倍の乗客が乗車するようではかなり
の混雑になってしまうつまり筆者が言いたいのは全体の結果として約半分になるものの
一部の時間帯や一部の区間の乗客数については目標に近いのではないだろうかというこ
とであるよって逆に予想よりかなり利用者の少ない時間帯の存在やもしくは区間によ
る偏りが大きいことが考えられるこれらはより詳細なデータを調べればわかるだろうま
た周辺のバス路線の利用者数の推移とも大いに関係するはずである今後の乗客増のため
にも横浜市等の対策に注目していきたい
筆者は都筑区北部在住であり自宅はグリーンラインの駅から徒歩10分ほどの距離
にある開通前はバスを利用し鉄道駅に向かっていたのでグリーンライン開通によってた
しかに便利になった特に最終バスが22時台と早かったため帰宅が深夜になる場合は非
常に便利であるしかし開通後もバスがあるときはバスを利用することが多いのもまた
事実であるこれはバスの本数自体は決して多くはないものの常にほぼ時刻表通りに運
行されておりその利用に抵抗がないこととバス停が細かく配置され自宅のすぐ近くにあ
ることが理由ある特に雨の日や日射しの強い日は徒歩距離の長いグリーンラインは敬遠し
てしまうただこれは筆者の考えであり一般的であるかは全く不明であることを強調し
ておく
42コムカモ
コムカモとは学内のバス停をネットワークカメラで常に撮影しその混雑状況をどこ
からでもすぐに把握できるようにすることで帰宅時間の分散をすすめバス利用を快適化
しようとするプロジェクトであるプライバシーなどの問題から現在カメラの設置には至
っておらず署名をあつめている段階であるその詳細な経緯や根拠の説明はここでは省く
中心になってこのプロジェクトを動かしていた杉山公一郎氏の卒業制作が詳しい
バス利用者は大学生にとどまらないため私は自分の交友関係を鑑み慶応義塾湘南藤
沢中高等部の生徒にこの署名をお願いしようと考えたしかしそれにはまずこのプロジ
ェクトについての意見をうかがう必要があった昨年度から中高等部とは何度かのやりと
りがあったようであるがおそらく末端の生徒は何も知らないと思い簡単な説明を行った
うえで意見をうかがったその結果得られた回答の要点は以下である回答者の属性は
6名全員が文化部で男性が3名女性が3名また中学生4名高校生2名である
①便利だとは思うが実際に利用することはまずないと思う
②友人にも利用すると思われる人はいない
③利用するならば携帯電話からの利用になる
①の意見が多かったことによって署名のお願いは断念した①の理由について意見
をまとめると以下のようになった
ア帰る時間が決まっていて選択の余地がない
イ友人同士での帰宅が多く並ばないことの重要性は少ない
ウ現在の混雑は理解できる範囲である
筆者が意見を聞いた中高生は帰る時間が基本的に決まっておりまたその結果人が集
中し混雑することを理解していたまたそれを仕方のないものだととらえていた各自の経
験等により各自の帰る時間が決まっていることも合わさってバス停の混雑する時間帯が頭
に入っているようであったつまりバス停混雑について現在ある程度の予測ができてお
りその結果混雑が想定されていてもその時間に帰宅しているのであるよって中高生の
多くはたとえコムカモで混雑していることが判明しても帰宅することが想像できるこ
れではコムカモの必要性は感じられないだろうしかし空いている時間に帰宅したいと
いうニーズはゼロではないと思うので実際に利用するかはともかく無いよりはあるほう
が便利は便利であるというスタンスで署名をお願いすればよいのではないかと考えている

建通新聞 2008年4月18日
『相鉄JR 直通線トンネル概略設計着手』
他多数の新聞記事を参照した
また以下の雑誌記事にも目を通した
鉄道ジャーナル 1999年12月号
『通勤輸送に徹する相模鉄道』
運輸と経済 2004年11月号
『インタビュー 地域密着を目指した経営計画の推進に向けて
--相模鉄道及川陸郎社長に聞く (特集連結経営時代のグループ戦略)』
運輸と経済 1994年11月号
『特定都市鉄道整備促進特別措置法に基づく既認定工事
--その進捗状況および同法の拡充について 』
鉄道ピクトリアル 1998年3月号
『特定都市鉄道整備事業の現状と今後 (lt特集gt大手民鉄の複々線)』
鉄道ピクトリアル 1999年7月臨時増刊号
『相模鉄道の鉄道事業を語る (lt特集gt相模鉄道)』
日本鉄道建設業協会 鉄道の礎 240 号 2007年4月
『都市鉄道等利便増進法に基づく
相鉄JR 直通線および相鉄東急直通線の速達性向上計画』
httpwwwtekkenkyoorjpkaihou24016html から閲覧
以下の雑誌記事は読みたかったが読めなかったものである
運輸と経済 197607
『10 年がかりの私鉄新線建設--相模鉄道いずみ野線』
エコノミスト 19850702
『私鉄沿線-13-横浜海老名(相模鉄道相鉄線)--首都圏の利フルに生かす』
JREA 20077
『都市鉄道利便増進事業の速達性向上計画認定--相鉄 JR 直通線相鉄東急直通線』
運輸政策研究 2008Win
『鉄道整備等基礎調査
「既存の都市鉄道ネットワークの改良による速達性向上施策 に関する調査」』
運輸と経済 20083
『都市鉄道の将来--歴史から見た考察 (特集 交通史から見た今日の交通問題)』
運輸政策研究 2007Spr
『都市鉄道等利便増進法の活用による新たな都市鉄道政策の展開』
市街地再開発 20065
『制度の紹介等 都市鉄道等利便増進法について』
運輸と経済 200510
『インタビュー都市鉄道の成長と成熟そしてどう維持するか』
JREA 20057
『都市鉄道整備の課題と今後の展望 (特集 都市交通)』
JR gazette 20053
『運輸リポート 「都市鉄道等利便増進法案」について 』
JREA 200412
『特別寄稿 政策レビュー「都市鉄道整備のあり方」の概要』
財界 20061205
『REPORT横浜市長中田宏の「新横浜を副都心から都心に変える」改造計画
2019年相鉄とJR湘南新宿ライン東急東横線が相互乗り入れ開始』
フォーブス 200502
『東武相鉄hellipJR東が私鉄と相互乗り入れする理由
新宿~東武日光鬼怒川温泉間の特急運転の開始を発表
相模鉄道との相互乗り入れ構想』
経済界 20010626
『 NEW PRESIDENT登場 相模鉄道社長及川陸郎 新しい息吹を吹き
込む遠回りしてきた男』
財界 20011
『光通信関連会社に土地を売却 私鉄大手「相模鉄道」の苦しい台所事情』
経済界 19980526
『佐藤正忠の極意対談 366回 相模鉄道会長對島好次郎
地域に一番大切なことは何か鉄道業の成長はその追求である』
夏季休業中にできるだけ読みたい
各種資料から得られた知識を筆者なりに総合し簡潔にまとめた
2003 年 「神奈川東部方面線懇談会」 関係自治体や鉄道事業者で整備に向けた調整
2005 年 都市鉄道等利便増進法施行
2004 年 相鉄 JR 直通案浮上
2006 年 相鉄 JR 直通+相鉄東急直通の形に決定し
5月営業整備計画申請 6月営業整備計画認定 8月速達性向上計画申請(相鉄 JR) 11 月速達性向上計画認定(相鉄 JR) 11 月速達性向上計画申請(相鉄東急)
2008 年 4月トンネル概略設計着手
2007 年 4月速達性向上計画認定(相鉄東急) 10 月環境影響評価方法書提出住民説明会 11 月環境影響評価公告縦覧
2000 年 運輸政策審議会答申 18 号 「A1 路線」平成 27 年までに開業が望ましい
各種資料からは存在することしか分からなかった「神奈川東部方面線懇談会」につ
いて横浜市に電話で問い合わせた
まずはじめに横浜市の市民情報室へ問い合わせの電話をかけた「神奈川東
部方面線の懇談会について知りたい」「新聞記事などで存在を知ったがもっと詳しく
知りたいと思っている会議録などは残っていないか」という旨の質問をしたところ
神奈川東部方面線を担当している部署へ電話をまわしていただけることになった
神奈川東部方面線担当の方につながったところで先ほどと同様の質問をした
担当の方も4月の異動で神奈川東部方面線担当になったようで当時の状況について
直接ご存知ないようであった少々込み入った話をしたところで一旦調べてまた
連絡していただけることになった
その後しばらくして電話をもらうがやはり議事録などは残っていない
との回答であったそこでどうにかもう少し当時の横浜市としての対応などを知る
ことができないか質問をしたまたつづけて直接お話を聞きにうかがうことはで
きないかとインタビューのお願いをしてみたところ分かる範囲でよろしければ
との回答を得ることができた
事業の当事者のひとつである横浜市から直接お話をしていただけるというのは
今後この研究をどのように進めていくかというその方向性を見定めるにもいい機会
であると思った後日こちらから電話し日時を決めることにしてこの日の電話
での質問は終了した
各種資料からは存在することしか分からなかった「神奈川東部方面線懇談会」につ
いて横浜市に直接ヒアリングにうかがった
5月27日の質問のあと6月3日に再度電話しアポイントメントを取った
結果6月9日の午後2時から横浜市庁舎にてインタビューできることになったま
た事前に質問書を送付したまた研究会で同行者をつのったところ2人一緒に来
てくださることになったとても心強かった
当日予定通り午後2時に横浜市庁舎6階へうかがった行政機関へのヒアリ
ング調査を行うのは初めてのことであり緊張した90分ほどお話をうかがいイ
ンタビューは無事終了したまたパンフレットと簡単な資料をいただいた録音した
音声ファイルを聞き返すと質問の仕方が稚拙なことが多くまた自分の主観の入っ
た質問も散見され反省するばかりである今後ヒアリング調査を行う際にはこの
点より強く心がけるようにしたい
東部方面線に関する質問票 慶應義塾大学環境情報学部 有澤研究室
日時平成20年6月9日月曜日 1400 ~ (予定) 場所横浜市役所本庁舎6階 都市整備局 (予定)
1東部方面線懇談会について
懇談会の基本的な情報を教えてください(経緯期間回数会場委員)
懇談会始動当時横浜市が重要視しておられたことについて教えてください
懇談会始動当時横浜市がすでに取り組んでおられたことについて教えてください
懇談会始動当時横浜市の各事業者等の狙いのとらえかたについて教えてください
都市鉄道等利便増進法制定との関係について教えてください
懇談会始動当時の事業化へ向けた課題について教えてください
2JR と相鉄の相互乗り入れ構想について
懇談会でのこの構想に関する議論について教えてください
新聞記事となったタイミングはどうでしたか
横浜市はこの構想をどう受け止めておられましたか
この構想と東部方面線の関係を整理する過程について教えてください
各事業者等との協議の焦点はどのようなことでしたか
3将来について
東部方面線事業に対する横浜市の今後の取り組みについて教えてください
現状横浜市が課題ととらえているのはどのようなことですか
西暦 平成
1999 11 6月 新横浜都心整備基本構想 策定
2000 12 運輸政策審議会答申18号 「A1路線」(平成27年までに開業することが望ましい) 3月 こどもの国線通勤線化
2001 13 1月 グリーンライン着工
2002 143月 市長選挙 中田氏当選6月 横浜でワールドカップ決勝が開催
2003 15 懇談会始動3月 市議会議員県議会議員県知事選挙 松沢知事当選12月 市営地下鉄全席優先席
2004 169月 JR相鉄直通新聞報道 横浜市長「協力するかこれから具体的に検討する」12月 横浜市長「(直通か東部方面線か)どちらかを優先」
2月 みなとみらい線開業
2005 17 8月 都市鉄道等利便増進法施行 9月 衆議院議員選挙 自民党圧勝
2006 18
2月 横浜市予算支出へ前向き5月 営業整備計画を事業者が申請6月 横浜市予算計上 営業整備計画認定11月 相鉄JR直通線 速達性向上計画認定
3月 市長選挙 中田氏再選
2007 194月 相鉄東急直通線 速達性向上計画認定10月~ 住民説明会など
3月 市議会議員県議会議員県知事選挙 松沢知事再選
2008 203月 グリーンライン開業6月 目黒線 日吉延伸
2009 21
2010 22
2011 23
2012 24 東横線hArr副都心線 直通開始予定
2013 25 東北縦貫線完成予定h(東海道線hArr東北高崎常磐線 直通)
2014 26
2015 27 相鉄JR直通線開業予定
2016 28
2017 29
2018 30
2019 31 相鉄東急直通線開業予定
ヒアリングで判明した内容をまとめた以下はその内容である
横浜市の方によると神奈川東部方面線懇談会とは国横浜市神奈川県東
急相鉄鉄道運輸機構であり課長レベルの方々が出席して行われたものである
とのことであったまたその下部にワークグループが存在しより詳細な調整が行
われたとのことであった会議録等の資料はやはり残っていないとの説明があった
相鉄 JR 直通線と神奈川東部方面線との関係についてはやはり新横浜を通
るか通らないかというこの違いが強調された横浜市にとって新横浜はその都市計
画において重要な位置付けをされておりその発展のためにまた横浜市西部や県央
地域から新横浜へのアクセス向上のために「新横浜を通る」東部方面線の整備が重要
であるとの説明があった横浜市にとって東部方面線は都心への直通路線としても
「もちろん大切」であるが新横浜のターミナル性を高めるために必要であることが
確認できたといえる
上記の内容から考察すると新聞記事やパンフレットでは都心への時間短縮が大
きく示されているものの横浜市としてはむしろ新横浜アクセス向上の意味が強い
と思われる都心への直通を前面に押し出し「速達性向上計画」として国に申請「都
市鉄道等利便増進法」に基づいてその整備を行うものであるが決して都内に人を吸
い上げられるだけのものではなく市の発展への意味も強くこめられていることが判
明した相鉄や東急は果たしてどう考えているのだろうか
33今後の活動
この春学期の活動を通して神奈川東部方面線についての横浜市の立場やとってきた
行動というものについての筆者の理解はとても深まったといえる同時に他の立場とい
うものについての興味を抱いた例えば相模鉄道の立場やJR の立場である横浜市にと
って極めて重要であった新横浜への到達は相模鉄道にとっていったいどれほどの価値が
あるものであったのだろうかまた相模鉄道は当時どのように考えていたのだろうか
またJR からすれば相鉄東急直通線が開通することで都心への旅客の奪いあいが発
生することが考えられるJR は「神奈川東部方面線懇談会」のメンバーではなかったもの
の決して関係ない立場ではないそれぞれに立場や目的を抱えていたはずである今後
の活動としては横浜市以外の関係者が東部方面線の事業化に向けてどのように対応し
行動をとってきたのかについて調査していきたいと考えている
またあわせてこの春学期に読むことのできなかった多くの文献に目を通したいこれ
は戦後から現在にいたるまでの鉄道整備の方式やその制度について理解しその知識を
得ることで神奈川東部方面線に関する事例研究からより思考を発展させこれからの都市
鉄道の整備に関する課題などの理解につながると思うからであるある程度の知識を習得し
自分なりに思考をしたのちより直接的な都市鉄道整備に関する先行研究を調べ論文など
を読みたいと思う
4そのほかの活動
41横浜市営地下鉄グリーンライン
2008年3月横浜市営地下鉄に新たな路線が開業した愛称をグリーンラインとい
い横浜市港北区の日吉から横浜市都筑区を縦断し横浜市緑区の中心部中山を結ぶ全長
131km の路線である日吉駅で東急東横線と目黒線に中山駅で JR 横浜線と連絡する
開業3ヵ月後の6月に東急目黒線が日吉駅まで延伸されたことで都内方面への利便性はい
くらか向上した車両はリニアモーター推進方式で車両 1 両あたりの長さは 155m現
在は4両編成であるがホームなどは編成の延長に対応し6両分の長さが用意されているよ
うである駅は10駅全線の所要時間は終日21分表定速度は約 37km で地下鉄と
してはそれなりであるが周辺路線と比較して速いとはいえないしかも運賃は非常に高い
ため東横線と横浜線の短絡線としてはほとんど機能しないものであるよって都筑区内
から東横線横浜線あるいは都筑区中心部への輸送が中心になると考えられる同じ都市
鉄道であってもグリーンラインの性質は東部方面線の性質と大きく異なるといえる都市
鉄道整備の最新の例でありまたその利用者のひとりとして今後ともその利用動向などに
は目を配っておきたい
実際の利用実績であるが4月の乗客数については目標の約半分との新聞報道があっ
た10万4千人の予想に反して結果は5万3千人にとどまっているしかし実際に毎
日利用している筆者からすると朝ラッシュ時のセンター北rarr日吉方面への混雑は日吉に近
づくにつれ相当なものとなる現状の2倍の乗客は乗れないまた夕方の時間帯の車内も空
席が目立たない程度に混んでおりこちらも現状の2倍の乗客が乗車するようではかなり
の混雑になってしまうつまり筆者が言いたいのは全体の結果として約半分になるものの
一部の時間帯や一部の区間の乗客数については目標に近いのではないだろうかというこ
とであるよって逆に予想よりかなり利用者の少ない時間帯の存在やもしくは区間によ
る偏りが大きいことが考えられるこれらはより詳細なデータを調べればわかるだろうま
た周辺のバス路線の利用者数の推移とも大いに関係するはずである今後の乗客増のため
にも横浜市等の対策に注目していきたい
筆者は都筑区北部在住であり自宅はグリーンラインの駅から徒歩10分ほどの距離
にある開通前はバスを利用し鉄道駅に向かっていたのでグリーンライン開通によってた
しかに便利になった特に最終バスが22時台と早かったため帰宅が深夜になる場合は非
常に便利であるしかし開通後もバスがあるときはバスを利用することが多いのもまた
事実であるこれはバスの本数自体は決して多くはないものの常にほぼ時刻表通りに運
行されておりその利用に抵抗がないこととバス停が細かく配置され自宅のすぐ近くにあ
ることが理由ある特に雨の日や日射しの強い日は徒歩距離の長いグリーンラインは敬遠し
てしまうただこれは筆者の考えであり一般的であるかは全く不明であることを強調し
ておく
42コムカモ
コムカモとは学内のバス停をネットワークカメラで常に撮影しその混雑状況をどこ
からでもすぐに把握できるようにすることで帰宅時間の分散をすすめバス利用を快適化
しようとするプロジェクトであるプライバシーなどの問題から現在カメラの設置には至
っておらず署名をあつめている段階であるその詳細な経緯や根拠の説明はここでは省く
中心になってこのプロジェクトを動かしていた杉山公一郎氏の卒業制作が詳しい
バス利用者は大学生にとどまらないため私は自分の交友関係を鑑み慶応義塾湘南藤
沢中高等部の生徒にこの署名をお願いしようと考えたしかしそれにはまずこのプロジ
ェクトについての意見をうかがう必要があった昨年度から中高等部とは何度かのやりと
りがあったようであるがおそらく末端の生徒は何も知らないと思い簡単な説明を行った
うえで意見をうかがったその結果得られた回答の要点は以下である回答者の属性は
6名全員が文化部で男性が3名女性が3名また中学生4名高校生2名である
①便利だとは思うが実際に利用することはまずないと思う
②友人にも利用すると思われる人はいない
③利用するならば携帯電話からの利用になる
①の意見が多かったことによって署名のお願いは断念した①の理由について意見
をまとめると以下のようになった
ア帰る時間が決まっていて選択の余地がない
イ友人同士での帰宅が多く並ばないことの重要性は少ない
ウ現在の混雑は理解できる範囲である
筆者が意見を聞いた中高生は帰る時間が基本的に決まっておりまたその結果人が集
中し混雑することを理解していたまたそれを仕方のないものだととらえていた各自の経
験等により各自の帰る時間が決まっていることも合わさってバス停の混雑する時間帯が頭
に入っているようであったつまりバス停混雑について現在ある程度の予測ができてお
りその結果混雑が想定されていてもその時間に帰宅しているのであるよって中高生の
多くはたとえコムカモで混雑していることが判明しても帰宅することが想像できるこ
れではコムカモの必要性は感じられないだろうしかし空いている時間に帰宅したいと
いうニーズはゼロではないと思うので実際に利用するかはともかく無いよりはあるほう
が便利は便利であるというスタンスで署名をお願いすればよいのではないかと考えている

JREA 20077
『都市鉄道利便増進事業の速達性向上計画認定--相鉄 JR 直通線相鉄東急直通線』
運輸政策研究 2008Win
『鉄道整備等基礎調査
「既存の都市鉄道ネットワークの改良による速達性向上施策 に関する調査」』
運輸と経済 20083
『都市鉄道の将来--歴史から見た考察 (特集 交通史から見た今日の交通問題)』
運輸政策研究 2007Spr
『都市鉄道等利便増進法の活用による新たな都市鉄道政策の展開』
市街地再開発 20065
『制度の紹介等 都市鉄道等利便増進法について』
運輸と経済 200510
『インタビュー都市鉄道の成長と成熟そしてどう維持するか』
JREA 20057
『都市鉄道整備の課題と今後の展望 (特集 都市交通)』
JR gazette 20053
『運輸リポート 「都市鉄道等利便増進法案」について 』
JREA 200412
『特別寄稿 政策レビュー「都市鉄道整備のあり方」の概要』
財界 20061205
『REPORT横浜市長中田宏の「新横浜を副都心から都心に変える」改造計画
2019年相鉄とJR湘南新宿ライン東急東横線が相互乗り入れ開始』
フォーブス 200502
『東武相鉄hellipJR東が私鉄と相互乗り入れする理由
新宿~東武日光鬼怒川温泉間の特急運転の開始を発表
相模鉄道との相互乗り入れ構想』
経済界 20010626
『 NEW PRESIDENT登場 相模鉄道社長及川陸郎 新しい息吹を吹き
込む遠回りしてきた男』
財界 20011
『光通信関連会社に土地を売却 私鉄大手「相模鉄道」の苦しい台所事情』
経済界 19980526
『佐藤正忠の極意対談 366回 相模鉄道会長對島好次郎
地域に一番大切なことは何か鉄道業の成長はその追求である』
夏季休業中にできるだけ読みたい
各種資料から得られた知識を筆者なりに総合し簡潔にまとめた
2003 年 「神奈川東部方面線懇談会」 関係自治体や鉄道事業者で整備に向けた調整
2005 年 都市鉄道等利便増進法施行
2004 年 相鉄 JR 直通案浮上
2006 年 相鉄 JR 直通+相鉄東急直通の形に決定し
5月営業整備計画申請 6月営業整備計画認定 8月速達性向上計画申請(相鉄 JR) 11 月速達性向上計画認定(相鉄 JR) 11 月速達性向上計画申請(相鉄東急)
2008 年 4月トンネル概略設計着手
2007 年 4月速達性向上計画認定(相鉄東急) 10 月環境影響評価方法書提出住民説明会 11 月環境影響評価公告縦覧
2000 年 運輸政策審議会答申 18 号 「A1 路線」平成 27 年までに開業が望ましい
各種資料からは存在することしか分からなかった「神奈川東部方面線懇談会」につ
いて横浜市に電話で問い合わせた
まずはじめに横浜市の市民情報室へ問い合わせの電話をかけた「神奈川東
部方面線の懇談会について知りたい」「新聞記事などで存在を知ったがもっと詳しく
知りたいと思っている会議録などは残っていないか」という旨の質問をしたところ
神奈川東部方面線を担当している部署へ電話をまわしていただけることになった
神奈川東部方面線担当の方につながったところで先ほどと同様の質問をした
担当の方も4月の異動で神奈川東部方面線担当になったようで当時の状況について
直接ご存知ないようであった少々込み入った話をしたところで一旦調べてまた
連絡していただけることになった
その後しばらくして電話をもらうがやはり議事録などは残っていない
との回答であったそこでどうにかもう少し当時の横浜市としての対応などを知る
ことができないか質問をしたまたつづけて直接お話を聞きにうかがうことはで
きないかとインタビューのお願いをしてみたところ分かる範囲でよろしければ
との回答を得ることができた
事業の当事者のひとつである横浜市から直接お話をしていただけるというのは
今後この研究をどのように進めていくかというその方向性を見定めるにもいい機会
であると思った後日こちらから電話し日時を決めることにしてこの日の電話
での質問は終了した
各種資料からは存在することしか分からなかった「神奈川東部方面線懇談会」につ
いて横浜市に直接ヒアリングにうかがった
5月27日の質問のあと6月3日に再度電話しアポイントメントを取った
結果6月9日の午後2時から横浜市庁舎にてインタビューできることになったま
た事前に質問書を送付したまた研究会で同行者をつのったところ2人一緒に来
てくださることになったとても心強かった
当日予定通り午後2時に横浜市庁舎6階へうかがった行政機関へのヒアリ
ング調査を行うのは初めてのことであり緊張した90分ほどお話をうかがいイ
ンタビューは無事終了したまたパンフレットと簡単な資料をいただいた録音した
音声ファイルを聞き返すと質問の仕方が稚拙なことが多くまた自分の主観の入っ
た質問も散見され反省するばかりである今後ヒアリング調査を行う際にはこの
点より強く心がけるようにしたい
東部方面線に関する質問票 慶應義塾大学環境情報学部 有澤研究室
日時平成20年6月9日月曜日 1400 ~ (予定) 場所横浜市役所本庁舎6階 都市整備局 (予定)
1東部方面線懇談会について
懇談会の基本的な情報を教えてください(経緯期間回数会場委員)
懇談会始動当時横浜市が重要視しておられたことについて教えてください
懇談会始動当時横浜市がすでに取り組んでおられたことについて教えてください
懇談会始動当時横浜市の各事業者等の狙いのとらえかたについて教えてください
都市鉄道等利便増進法制定との関係について教えてください
懇談会始動当時の事業化へ向けた課題について教えてください
2JR と相鉄の相互乗り入れ構想について
懇談会でのこの構想に関する議論について教えてください
新聞記事となったタイミングはどうでしたか
横浜市はこの構想をどう受け止めておられましたか
この構想と東部方面線の関係を整理する過程について教えてください
各事業者等との協議の焦点はどのようなことでしたか
3将来について
東部方面線事業に対する横浜市の今後の取り組みについて教えてください
現状横浜市が課題ととらえているのはどのようなことですか
西暦 平成
1999 11 6月 新横浜都心整備基本構想 策定
2000 12 運輸政策審議会答申18号 「A1路線」(平成27年までに開業することが望ましい) 3月 こどもの国線通勤線化
2001 13 1月 グリーンライン着工
2002 143月 市長選挙 中田氏当選6月 横浜でワールドカップ決勝が開催
2003 15 懇談会始動3月 市議会議員県議会議員県知事選挙 松沢知事当選12月 市営地下鉄全席優先席
2004 169月 JR相鉄直通新聞報道 横浜市長「協力するかこれから具体的に検討する」12月 横浜市長「(直通か東部方面線か)どちらかを優先」
2月 みなとみらい線開業
2005 17 8月 都市鉄道等利便増進法施行 9月 衆議院議員選挙 自民党圧勝
2006 18
2月 横浜市予算支出へ前向き5月 営業整備計画を事業者が申請6月 横浜市予算計上 営業整備計画認定11月 相鉄JR直通線 速達性向上計画認定
3月 市長選挙 中田氏再選
2007 194月 相鉄東急直通線 速達性向上計画認定10月~ 住民説明会など
3月 市議会議員県議会議員県知事選挙 松沢知事再選
2008 203月 グリーンライン開業6月 目黒線 日吉延伸
2009 21
2010 22
2011 23
2012 24 東横線hArr副都心線 直通開始予定
2013 25 東北縦貫線完成予定h(東海道線hArr東北高崎常磐線 直通)
2014 26
2015 27 相鉄JR直通線開業予定
2016 28
2017 29
2018 30
2019 31 相鉄東急直通線開業予定
ヒアリングで判明した内容をまとめた以下はその内容である
横浜市の方によると神奈川東部方面線懇談会とは国横浜市神奈川県東
急相鉄鉄道運輸機構であり課長レベルの方々が出席して行われたものである
とのことであったまたその下部にワークグループが存在しより詳細な調整が行
われたとのことであった会議録等の資料はやはり残っていないとの説明があった
相鉄 JR 直通線と神奈川東部方面線との関係についてはやはり新横浜を通
るか通らないかというこの違いが強調された横浜市にとって新横浜はその都市計
画において重要な位置付けをされておりその発展のためにまた横浜市西部や県央
地域から新横浜へのアクセス向上のために「新横浜を通る」東部方面線の整備が重要
であるとの説明があった横浜市にとって東部方面線は都心への直通路線としても
「もちろん大切」であるが新横浜のターミナル性を高めるために必要であることが
確認できたといえる
上記の内容から考察すると新聞記事やパンフレットでは都心への時間短縮が大
きく示されているものの横浜市としてはむしろ新横浜アクセス向上の意味が強い
と思われる都心への直通を前面に押し出し「速達性向上計画」として国に申請「都
市鉄道等利便増進法」に基づいてその整備を行うものであるが決して都内に人を吸
い上げられるだけのものではなく市の発展への意味も強くこめられていることが判
明した相鉄や東急は果たしてどう考えているのだろうか
33今後の活動
この春学期の活動を通して神奈川東部方面線についての横浜市の立場やとってきた
行動というものについての筆者の理解はとても深まったといえる同時に他の立場とい
うものについての興味を抱いた例えば相模鉄道の立場やJR の立場である横浜市にと
って極めて重要であった新横浜への到達は相模鉄道にとっていったいどれほどの価値が
あるものであったのだろうかまた相模鉄道は当時どのように考えていたのだろうか
またJR からすれば相鉄東急直通線が開通することで都心への旅客の奪いあいが発
生することが考えられるJR は「神奈川東部方面線懇談会」のメンバーではなかったもの
の決して関係ない立場ではないそれぞれに立場や目的を抱えていたはずである今後
の活動としては横浜市以外の関係者が東部方面線の事業化に向けてどのように対応し
行動をとってきたのかについて調査していきたいと考えている
またあわせてこの春学期に読むことのできなかった多くの文献に目を通したいこれ
は戦後から現在にいたるまでの鉄道整備の方式やその制度について理解しその知識を
得ることで神奈川東部方面線に関する事例研究からより思考を発展させこれからの都市
鉄道の整備に関する課題などの理解につながると思うからであるある程度の知識を習得し
自分なりに思考をしたのちより直接的な都市鉄道整備に関する先行研究を調べ論文など
を読みたいと思う
4そのほかの活動
41横浜市営地下鉄グリーンライン
2008年3月横浜市営地下鉄に新たな路線が開業した愛称をグリーンラインとい
い横浜市港北区の日吉から横浜市都筑区を縦断し横浜市緑区の中心部中山を結ぶ全長
131km の路線である日吉駅で東急東横線と目黒線に中山駅で JR 横浜線と連絡する
開業3ヵ月後の6月に東急目黒線が日吉駅まで延伸されたことで都内方面への利便性はい
くらか向上した車両はリニアモーター推進方式で車両 1 両あたりの長さは 155m現
在は4両編成であるがホームなどは編成の延長に対応し6両分の長さが用意されているよ
うである駅は10駅全線の所要時間は終日21分表定速度は約 37km で地下鉄と
してはそれなりであるが周辺路線と比較して速いとはいえないしかも運賃は非常に高い
ため東横線と横浜線の短絡線としてはほとんど機能しないものであるよって都筑区内
から東横線横浜線あるいは都筑区中心部への輸送が中心になると考えられる同じ都市
鉄道であってもグリーンラインの性質は東部方面線の性質と大きく異なるといえる都市
鉄道整備の最新の例でありまたその利用者のひとりとして今後ともその利用動向などに
は目を配っておきたい
実際の利用実績であるが4月の乗客数については目標の約半分との新聞報道があっ
た10万4千人の予想に反して結果は5万3千人にとどまっているしかし実際に毎
日利用している筆者からすると朝ラッシュ時のセンター北rarr日吉方面への混雑は日吉に近
づくにつれ相当なものとなる現状の2倍の乗客は乗れないまた夕方の時間帯の車内も空
席が目立たない程度に混んでおりこちらも現状の2倍の乗客が乗車するようではかなり
の混雑になってしまうつまり筆者が言いたいのは全体の結果として約半分になるものの
一部の時間帯や一部の区間の乗客数については目標に近いのではないだろうかというこ
とであるよって逆に予想よりかなり利用者の少ない時間帯の存在やもしくは区間によ
る偏りが大きいことが考えられるこれらはより詳細なデータを調べればわかるだろうま
た周辺のバス路線の利用者数の推移とも大いに関係するはずである今後の乗客増のため
にも横浜市等の対策に注目していきたい
筆者は都筑区北部在住であり自宅はグリーンラインの駅から徒歩10分ほどの距離
にある開通前はバスを利用し鉄道駅に向かっていたのでグリーンライン開通によってた
しかに便利になった特に最終バスが22時台と早かったため帰宅が深夜になる場合は非
常に便利であるしかし開通後もバスがあるときはバスを利用することが多いのもまた
事実であるこれはバスの本数自体は決して多くはないものの常にほぼ時刻表通りに運
行されておりその利用に抵抗がないこととバス停が細かく配置され自宅のすぐ近くにあ
ることが理由ある特に雨の日や日射しの強い日は徒歩距離の長いグリーンラインは敬遠し
てしまうただこれは筆者の考えであり一般的であるかは全く不明であることを強調し
ておく
42コムカモ
コムカモとは学内のバス停をネットワークカメラで常に撮影しその混雑状況をどこ
からでもすぐに把握できるようにすることで帰宅時間の分散をすすめバス利用を快適化
しようとするプロジェクトであるプライバシーなどの問題から現在カメラの設置には至
っておらず署名をあつめている段階であるその詳細な経緯や根拠の説明はここでは省く
中心になってこのプロジェクトを動かしていた杉山公一郎氏の卒業制作が詳しい
バス利用者は大学生にとどまらないため私は自分の交友関係を鑑み慶応義塾湘南藤
沢中高等部の生徒にこの署名をお願いしようと考えたしかしそれにはまずこのプロジ
ェクトについての意見をうかがう必要があった昨年度から中高等部とは何度かのやりと
りがあったようであるがおそらく末端の生徒は何も知らないと思い簡単な説明を行った
うえで意見をうかがったその結果得られた回答の要点は以下である回答者の属性は
6名全員が文化部で男性が3名女性が3名また中学生4名高校生2名である
①便利だとは思うが実際に利用することはまずないと思う
②友人にも利用すると思われる人はいない
③利用するならば携帯電話からの利用になる
①の意見が多かったことによって署名のお願いは断念した①の理由について意見
をまとめると以下のようになった
ア帰る時間が決まっていて選択の余地がない
イ友人同士での帰宅が多く並ばないことの重要性は少ない
ウ現在の混雑は理解できる範囲である
筆者が意見を聞いた中高生は帰る時間が基本的に決まっておりまたその結果人が集
中し混雑することを理解していたまたそれを仕方のないものだととらえていた各自の経
験等により各自の帰る時間が決まっていることも合わさってバス停の混雑する時間帯が頭
に入っているようであったつまりバス停混雑について現在ある程度の予測ができてお
りその結果混雑が想定されていてもその時間に帰宅しているのであるよって中高生の
多くはたとえコムカモで混雑していることが判明しても帰宅することが想像できるこ
れではコムカモの必要性は感じられないだろうしかし空いている時間に帰宅したいと
いうニーズはゼロではないと思うので実際に利用するかはともかく無いよりはあるほう
が便利は便利であるというスタンスで署名をお願いすればよいのではないかと考えている

経済界 20010626
『 NEW PRESIDENT登場 相模鉄道社長及川陸郎 新しい息吹を吹き
込む遠回りしてきた男』
財界 20011
『光通信関連会社に土地を売却 私鉄大手「相模鉄道」の苦しい台所事情』
経済界 19980526
『佐藤正忠の極意対談 366回 相模鉄道会長對島好次郎
地域に一番大切なことは何か鉄道業の成長はその追求である』
夏季休業中にできるだけ読みたい
各種資料から得られた知識を筆者なりに総合し簡潔にまとめた
2003 年 「神奈川東部方面線懇談会」 関係自治体や鉄道事業者で整備に向けた調整
2005 年 都市鉄道等利便増進法施行
2004 年 相鉄 JR 直通案浮上
2006 年 相鉄 JR 直通+相鉄東急直通の形に決定し
5月営業整備計画申請 6月営業整備計画認定 8月速達性向上計画申請(相鉄 JR) 11 月速達性向上計画認定(相鉄 JR) 11 月速達性向上計画申請(相鉄東急)
2008 年 4月トンネル概略設計着手
2007 年 4月速達性向上計画認定(相鉄東急) 10 月環境影響評価方法書提出住民説明会 11 月環境影響評価公告縦覧
2000 年 運輸政策審議会答申 18 号 「A1 路線」平成 27 年までに開業が望ましい
各種資料からは存在することしか分からなかった「神奈川東部方面線懇談会」につ
いて横浜市に電話で問い合わせた
まずはじめに横浜市の市民情報室へ問い合わせの電話をかけた「神奈川東
部方面線の懇談会について知りたい」「新聞記事などで存在を知ったがもっと詳しく
知りたいと思っている会議録などは残っていないか」という旨の質問をしたところ
神奈川東部方面線を担当している部署へ電話をまわしていただけることになった
神奈川東部方面線担当の方につながったところで先ほどと同様の質問をした
担当の方も4月の異動で神奈川東部方面線担当になったようで当時の状況について
直接ご存知ないようであった少々込み入った話をしたところで一旦調べてまた
連絡していただけることになった
その後しばらくして電話をもらうがやはり議事録などは残っていない
との回答であったそこでどうにかもう少し当時の横浜市としての対応などを知る
ことができないか質問をしたまたつづけて直接お話を聞きにうかがうことはで
きないかとインタビューのお願いをしてみたところ分かる範囲でよろしければ
との回答を得ることができた
事業の当事者のひとつである横浜市から直接お話をしていただけるというのは
今後この研究をどのように進めていくかというその方向性を見定めるにもいい機会
であると思った後日こちらから電話し日時を決めることにしてこの日の電話
での質問は終了した
各種資料からは存在することしか分からなかった「神奈川東部方面線懇談会」につ
いて横浜市に直接ヒアリングにうかがった
5月27日の質問のあと6月3日に再度電話しアポイントメントを取った
結果6月9日の午後2時から横浜市庁舎にてインタビューできることになったま
た事前に質問書を送付したまた研究会で同行者をつのったところ2人一緒に来
てくださることになったとても心強かった
当日予定通り午後2時に横浜市庁舎6階へうかがった行政機関へのヒアリ
ング調査を行うのは初めてのことであり緊張した90分ほどお話をうかがいイ
ンタビューは無事終了したまたパンフレットと簡単な資料をいただいた録音した
音声ファイルを聞き返すと質問の仕方が稚拙なことが多くまた自分の主観の入っ
た質問も散見され反省するばかりである今後ヒアリング調査を行う際にはこの
点より強く心がけるようにしたい
東部方面線に関する質問票 慶應義塾大学環境情報学部 有澤研究室
日時平成20年6月9日月曜日 1400 ~ (予定) 場所横浜市役所本庁舎6階 都市整備局 (予定)
1東部方面線懇談会について
懇談会の基本的な情報を教えてください(経緯期間回数会場委員)
懇談会始動当時横浜市が重要視しておられたことについて教えてください
懇談会始動当時横浜市がすでに取り組んでおられたことについて教えてください
懇談会始動当時横浜市の各事業者等の狙いのとらえかたについて教えてください
都市鉄道等利便増進法制定との関係について教えてください
懇談会始動当時の事業化へ向けた課題について教えてください
2JR と相鉄の相互乗り入れ構想について
懇談会でのこの構想に関する議論について教えてください
新聞記事となったタイミングはどうでしたか
横浜市はこの構想をどう受け止めておられましたか
この構想と東部方面線の関係を整理する過程について教えてください
各事業者等との協議の焦点はどのようなことでしたか
3将来について
東部方面線事業に対する横浜市の今後の取り組みについて教えてください
現状横浜市が課題ととらえているのはどのようなことですか
西暦 平成
1999 11 6月 新横浜都心整備基本構想 策定
2000 12 運輸政策審議会答申18号 「A1路線」(平成27年までに開業することが望ましい) 3月 こどもの国線通勤線化
2001 13 1月 グリーンライン着工
2002 143月 市長選挙 中田氏当選6月 横浜でワールドカップ決勝が開催
2003 15 懇談会始動3月 市議会議員県議会議員県知事選挙 松沢知事当選12月 市営地下鉄全席優先席
2004 169月 JR相鉄直通新聞報道 横浜市長「協力するかこれから具体的に検討する」12月 横浜市長「(直通か東部方面線か)どちらかを優先」
2月 みなとみらい線開業
2005 17 8月 都市鉄道等利便増進法施行 9月 衆議院議員選挙 自民党圧勝
2006 18
2月 横浜市予算支出へ前向き5月 営業整備計画を事業者が申請6月 横浜市予算計上 営業整備計画認定11月 相鉄JR直通線 速達性向上計画認定
3月 市長選挙 中田氏再選
2007 194月 相鉄東急直通線 速達性向上計画認定10月~ 住民説明会など
3月 市議会議員県議会議員県知事選挙 松沢知事再選
2008 203月 グリーンライン開業6月 目黒線 日吉延伸
2009 21
2010 22
2011 23
2012 24 東横線hArr副都心線 直通開始予定
2013 25 東北縦貫線完成予定h(東海道線hArr東北高崎常磐線 直通)
2014 26
2015 27 相鉄JR直通線開業予定
2016 28
2017 29
2018 30
2019 31 相鉄東急直通線開業予定
ヒアリングで判明した内容をまとめた以下はその内容である
横浜市の方によると神奈川東部方面線懇談会とは国横浜市神奈川県東
急相鉄鉄道運輸機構であり課長レベルの方々が出席して行われたものである
とのことであったまたその下部にワークグループが存在しより詳細な調整が行
われたとのことであった会議録等の資料はやはり残っていないとの説明があった
相鉄 JR 直通線と神奈川東部方面線との関係についてはやはり新横浜を通
るか通らないかというこの違いが強調された横浜市にとって新横浜はその都市計
画において重要な位置付けをされておりその発展のためにまた横浜市西部や県央
地域から新横浜へのアクセス向上のために「新横浜を通る」東部方面線の整備が重要
であるとの説明があった横浜市にとって東部方面線は都心への直通路線としても
「もちろん大切」であるが新横浜のターミナル性を高めるために必要であることが
確認できたといえる
上記の内容から考察すると新聞記事やパンフレットでは都心への時間短縮が大
きく示されているものの横浜市としてはむしろ新横浜アクセス向上の意味が強い
と思われる都心への直通を前面に押し出し「速達性向上計画」として国に申請「都
市鉄道等利便増進法」に基づいてその整備を行うものであるが決して都内に人を吸
い上げられるだけのものではなく市の発展への意味も強くこめられていることが判
明した相鉄や東急は果たしてどう考えているのだろうか
33今後の活動
この春学期の活動を通して神奈川東部方面線についての横浜市の立場やとってきた
行動というものについての筆者の理解はとても深まったといえる同時に他の立場とい
うものについての興味を抱いた例えば相模鉄道の立場やJR の立場である横浜市にと
って極めて重要であった新横浜への到達は相模鉄道にとっていったいどれほどの価値が
あるものであったのだろうかまた相模鉄道は当時どのように考えていたのだろうか
またJR からすれば相鉄東急直通線が開通することで都心への旅客の奪いあいが発
生することが考えられるJR は「神奈川東部方面線懇談会」のメンバーではなかったもの
の決して関係ない立場ではないそれぞれに立場や目的を抱えていたはずである今後
の活動としては横浜市以外の関係者が東部方面線の事業化に向けてどのように対応し
行動をとってきたのかについて調査していきたいと考えている
またあわせてこの春学期に読むことのできなかった多くの文献に目を通したいこれ
は戦後から現在にいたるまでの鉄道整備の方式やその制度について理解しその知識を
得ることで神奈川東部方面線に関する事例研究からより思考を発展させこれからの都市
鉄道の整備に関する課題などの理解につながると思うからであるある程度の知識を習得し
自分なりに思考をしたのちより直接的な都市鉄道整備に関する先行研究を調べ論文など
を読みたいと思う
4そのほかの活動
41横浜市営地下鉄グリーンライン
2008年3月横浜市営地下鉄に新たな路線が開業した愛称をグリーンラインとい
い横浜市港北区の日吉から横浜市都筑区を縦断し横浜市緑区の中心部中山を結ぶ全長
131km の路線である日吉駅で東急東横線と目黒線に中山駅で JR 横浜線と連絡する
開業3ヵ月後の6月に東急目黒線が日吉駅まで延伸されたことで都内方面への利便性はい
くらか向上した車両はリニアモーター推進方式で車両 1 両あたりの長さは 155m現
在は4両編成であるがホームなどは編成の延長に対応し6両分の長さが用意されているよ
うである駅は10駅全線の所要時間は終日21分表定速度は約 37km で地下鉄と
してはそれなりであるが周辺路線と比較して速いとはいえないしかも運賃は非常に高い
ため東横線と横浜線の短絡線としてはほとんど機能しないものであるよって都筑区内
から東横線横浜線あるいは都筑区中心部への輸送が中心になると考えられる同じ都市
鉄道であってもグリーンラインの性質は東部方面線の性質と大きく異なるといえる都市
鉄道整備の最新の例でありまたその利用者のひとりとして今後ともその利用動向などに
は目を配っておきたい
実際の利用実績であるが4月の乗客数については目標の約半分との新聞報道があっ
た10万4千人の予想に反して結果は5万3千人にとどまっているしかし実際に毎
日利用している筆者からすると朝ラッシュ時のセンター北rarr日吉方面への混雑は日吉に近
づくにつれ相当なものとなる現状の2倍の乗客は乗れないまた夕方の時間帯の車内も空
席が目立たない程度に混んでおりこちらも現状の2倍の乗客が乗車するようではかなり
の混雑になってしまうつまり筆者が言いたいのは全体の結果として約半分になるものの
一部の時間帯や一部の区間の乗客数については目標に近いのではないだろうかというこ
とであるよって逆に予想よりかなり利用者の少ない時間帯の存在やもしくは区間によ
る偏りが大きいことが考えられるこれらはより詳細なデータを調べればわかるだろうま
た周辺のバス路線の利用者数の推移とも大いに関係するはずである今後の乗客増のため
にも横浜市等の対策に注目していきたい
筆者は都筑区北部在住であり自宅はグリーンラインの駅から徒歩10分ほどの距離
にある開通前はバスを利用し鉄道駅に向かっていたのでグリーンライン開通によってた
しかに便利になった特に最終バスが22時台と早かったため帰宅が深夜になる場合は非
常に便利であるしかし開通後もバスがあるときはバスを利用することが多いのもまた
事実であるこれはバスの本数自体は決して多くはないものの常にほぼ時刻表通りに運
行されておりその利用に抵抗がないこととバス停が細かく配置され自宅のすぐ近くにあ
ることが理由ある特に雨の日や日射しの強い日は徒歩距離の長いグリーンラインは敬遠し
てしまうただこれは筆者の考えであり一般的であるかは全く不明であることを強調し
ておく
42コムカモ
コムカモとは学内のバス停をネットワークカメラで常に撮影しその混雑状況をどこ
からでもすぐに把握できるようにすることで帰宅時間の分散をすすめバス利用を快適化
しようとするプロジェクトであるプライバシーなどの問題から現在カメラの設置には至
っておらず署名をあつめている段階であるその詳細な経緯や根拠の説明はここでは省く
中心になってこのプロジェクトを動かしていた杉山公一郎氏の卒業制作が詳しい
バス利用者は大学生にとどまらないため私は自分の交友関係を鑑み慶応義塾湘南藤
沢中高等部の生徒にこの署名をお願いしようと考えたしかしそれにはまずこのプロジ
ェクトについての意見をうかがう必要があった昨年度から中高等部とは何度かのやりと
りがあったようであるがおそらく末端の生徒は何も知らないと思い簡単な説明を行った
うえで意見をうかがったその結果得られた回答の要点は以下である回答者の属性は
6名全員が文化部で男性が3名女性が3名また中学生4名高校生2名である
①便利だとは思うが実際に利用することはまずないと思う
②友人にも利用すると思われる人はいない
③利用するならば携帯電話からの利用になる
①の意見が多かったことによって署名のお願いは断念した①の理由について意見
をまとめると以下のようになった
ア帰る時間が決まっていて選択の余地がない
イ友人同士での帰宅が多く並ばないことの重要性は少ない
ウ現在の混雑は理解できる範囲である
筆者が意見を聞いた中高生は帰る時間が基本的に決まっておりまたその結果人が集
中し混雑することを理解していたまたそれを仕方のないものだととらえていた各自の経
験等により各自の帰る時間が決まっていることも合わさってバス停の混雑する時間帯が頭
に入っているようであったつまりバス停混雑について現在ある程度の予測ができてお
りその結果混雑が想定されていてもその時間に帰宅しているのであるよって中高生の
多くはたとえコムカモで混雑していることが判明しても帰宅することが想像できるこ
れではコムカモの必要性は感じられないだろうしかし空いている時間に帰宅したいと
いうニーズはゼロではないと思うので実際に利用するかはともかく無いよりはあるほう
が便利は便利であるというスタンスで署名をお願いすればよいのではないかと考えている

各種資料から得られた知識を筆者なりに総合し簡潔にまとめた
2003 年 「神奈川東部方面線懇談会」 関係自治体や鉄道事業者で整備に向けた調整
2005 年 都市鉄道等利便増進法施行
2004 年 相鉄 JR 直通案浮上
2006 年 相鉄 JR 直通+相鉄東急直通の形に決定し
5月営業整備計画申請 6月営業整備計画認定 8月速達性向上計画申請(相鉄 JR) 11 月速達性向上計画認定(相鉄 JR) 11 月速達性向上計画申請(相鉄東急)
2008 年 4月トンネル概略設計着手
2007 年 4月速達性向上計画認定(相鉄東急) 10 月環境影響評価方法書提出住民説明会 11 月環境影響評価公告縦覧
2000 年 運輸政策審議会答申 18 号 「A1 路線」平成 27 年までに開業が望ましい
各種資料からは存在することしか分からなかった「神奈川東部方面線懇談会」につ
いて横浜市に電話で問い合わせた
まずはじめに横浜市の市民情報室へ問い合わせの電話をかけた「神奈川東
部方面線の懇談会について知りたい」「新聞記事などで存在を知ったがもっと詳しく
知りたいと思っている会議録などは残っていないか」という旨の質問をしたところ
神奈川東部方面線を担当している部署へ電話をまわしていただけることになった
神奈川東部方面線担当の方につながったところで先ほどと同様の質問をした
担当の方も4月の異動で神奈川東部方面線担当になったようで当時の状況について
直接ご存知ないようであった少々込み入った話をしたところで一旦調べてまた
連絡していただけることになった
その後しばらくして電話をもらうがやはり議事録などは残っていない
との回答であったそこでどうにかもう少し当時の横浜市としての対応などを知る
ことができないか質問をしたまたつづけて直接お話を聞きにうかがうことはで
きないかとインタビューのお願いをしてみたところ分かる範囲でよろしければ
との回答を得ることができた
事業の当事者のひとつである横浜市から直接お話をしていただけるというのは
今後この研究をどのように進めていくかというその方向性を見定めるにもいい機会
であると思った後日こちらから電話し日時を決めることにしてこの日の電話
での質問は終了した
各種資料からは存在することしか分からなかった「神奈川東部方面線懇談会」につ
いて横浜市に直接ヒアリングにうかがった
5月27日の質問のあと6月3日に再度電話しアポイントメントを取った
結果6月9日の午後2時から横浜市庁舎にてインタビューできることになったま
た事前に質問書を送付したまた研究会で同行者をつのったところ2人一緒に来
てくださることになったとても心強かった
当日予定通り午後2時に横浜市庁舎6階へうかがった行政機関へのヒアリ
ング調査を行うのは初めてのことであり緊張した90分ほどお話をうかがいイ
ンタビューは無事終了したまたパンフレットと簡単な資料をいただいた録音した
音声ファイルを聞き返すと質問の仕方が稚拙なことが多くまた自分の主観の入っ
た質問も散見され反省するばかりである今後ヒアリング調査を行う際にはこの
点より強く心がけるようにしたい
東部方面線に関する質問票 慶應義塾大学環境情報学部 有澤研究室
日時平成20年6月9日月曜日 1400 ~ (予定) 場所横浜市役所本庁舎6階 都市整備局 (予定)
1東部方面線懇談会について
懇談会の基本的な情報を教えてください(経緯期間回数会場委員)
懇談会始動当時横浜市が重要視しておられたことについて教えてください
懇談会始動当時横浜市がすでに取り組んでおられたことについて教えてください
懇談会始動当時横浜市の各事業者等の狙いのとらえかたについて教えてください
都市鉄道等利便増進法制定との関係について教えてください
懇談会始動当時の事業化へ向けた課題について教えてください
2JR と相鉄の相互乗り入れ構想について
懇談会でのこの構想に関する議論について教えてください
新聞記事となったタイミングはどうでしたか
横浜市はこの構想をどう受け止めておられましたか
この構想と東部方面線の関係を整理する過程について教えてください
各事業者等との協議の焦点はどのようなことでしたか
3将来について
東部方面線事業に対する横浜市の今後の取り組みについて教えてください
現状横浜市が課題ととらえているのはどのようなことですか
西暦 平成
1999 11 6月 新横浜都心整備基本構想 策定
2000 12 運輸政策審議会答申18号 「A1路線」(平成27年までに開業することが望ましい) 3月 こどもの国線通勤線化
2001 13 1月 グリーンライン着工
2002 143月 市長選挙 中田氏当選6月 横浜でワールドカップ決勝が開催
2003 15 懇談会始動3月 市議会議員県議会議員県知事選挙 松沢知事当選12月 市営地下鉄全席優先席
2004 169月 JR相鉄直通新聞報道 横浜市長「協力するかこれから具体的に検討する」12月 横浜市長「(直通か東部方面線か)どちらかを優先」
2月 みなとみらい線開業
2005 17 8月 都市鉄道等利便増進法施行 9月 衆議院議員選挙 自民党圧勝
2006 18
2月 横浜市予算支出へ前向き5月 営業整備計画を事業者が申請6月 横浜市予算計上 営業整備計画認定11月 相鉄JR直通線 速達性向上計画認定
3月 市長選挙 中田氏再選
2007 194月 相鉄東急直通線 速達性向上計画認定10月~ 住民説明会など
3月 市議会議員県議会議員県知事選挙 松沢知事再選
2008 203月 グリーンライン開業6月 目黒線 日吉延伸
2009 21
2010 22
2011 23
2012 24 東横線hArr副都心線 直通開始予定
2013 25 東北縦貫線完成予定h(東海道線hArr東北高崎常磐線 直通)
2014 26
2015 27 相鉄JR直通線開業予定
2016 28
2017 29
2018 30
2019 31 相鉄東急直通線開業予定
ヒアリングで判明した内容をまとめた以下はその内容である
横浜市の方によると神奈川東部方面線懇談会とは国横浜市神奈川県東
急相鉄鉄道運輸機構であり課長レベルの方々が出席して行われたものである
とのことであったまたその下部にワークグループが存在しより詳細な調整が行
われたとのことであった会議録等の資料はやはり残っていないとの説明があった
相鉄 JR 直通線と神奈川東部方面線との関係についてはやはり新横浜を通
るか通らないかというこの違いが強調された横浜市にとって新横浜はその都市計
画において重要な位置付けをされておりその発展のためにまた横浜市西部や県央
地域から新横浜へのアクセス向上のために「新横浜を通る」東部方面線の整備が重要
であるとの説明があった横浜市にとって東部方面線は都心への直通路線としても
「もちろん大切」であるが新横浜のターミナル性を高めるために必要であることが
確認できたといえる
上記の内容から考察すると新聞記事やパンフレットでは都心への時間短縮が大
きく示されているものの横浜市としてはむしろ新横浜アクセス向上の意味が強い
と思われる都心への直通を前面に押し出し「速達性向上計画」として国に申請「都
市鉄道等利便増進法」に基づいてその整備を行うものであるが決して都内に人を吸
い上げられるだけのものではなく市の発展への意味も強くこめられていることが判
明した相鉄や東急は果たしてどう考えているのだろうか
33今後の活動
この春学期の活動を通して神奈川東部方面線についての横浜市の立場やとってきた
行動というものについての筆者の理解はとても深まったといえる同時に他の立場とい
うものについての興味を抱いた例えば相模鉄道の立場やJR の立場である横浜市にと
って極めて重要であった新横浜への到達は相模鉄道にとっていったいどれほどの価値が
あるものであったのだろうかまた相模鉄道は当時どのように考えていたのだろうか
またJR からすれば相鉄東急直通線が開通することで都心への旅客の奪いあいが発
生することが考えられるJR は「神奈川東部方面線懇談会」のメンバーではなかったもの
の決して関係ない立場ではないそれぞれに立場や目的を抱えていたはずである今後
の活動としては横浜市以外の関係者が東部方面線の事業化に向けてどのように対応し
行動をとってきたのかについて調査していきたいと考えている
またあわせてこの春学期に読むことのできなかった多くの文献に目を通したいこれ
は戦後から現在にいたるまでの鉄道整備の方式やその制度について理解しその知識を
得ることで神奈川東部方面線に関する事例研究からより思考を発展させこれからの都市
鉄道の整備に関する課題などの理解につながると思うからであるある程度の知識を習得し
自分なりに思考をしたのちより直接的な都市鉄道整備に関する先行研究を調べ論文など
を読みたいと思う
4そのほかの活動
41横浜市営地下鉄グリーンライン
2008年3月横浜市営地下鉄に新たな路線が開業した愛称をグリーンラインとい
い横浜市港北区の日吉から横浜市都筑区を縦断し横浜市緑区の中心部中山を結ぶ全長
131km の路線である日吉駅で東急東横線と目黒線に中山駅で JR 横浜線と連絡する
開業3ヵ月後の6月に東急目黒線が日吉駅まで延伸されたことで都内方面への利便性はい
くらか向上した車両はリニアモーター推進方式で車両 1 両あたりの長さは 155m現
在は4両編成であるがホームなどは編成の延長に対応し6両分の長さが用意されているよ
うである駅は10駅全線の所要時間は終日21分表定速度は約 37km で地下鉄と
してはそれなりであるが周辺路線と比較して速いとはいえないしかも運賃は非常に高い
ため東横線と横浜線の短絡線としてはほとんど機能しないものであるよって都筑区内
から東横線横浜線あるいは都筑区中心部への輸送が中心になると考えられる同じ都市
鉄道であってもグリーンラインの性質は東部方面線の性質と大きく異なるといえる都市
鉄道整備の最新の例でありまたその利用者のひとりとして今後ともその利用動向などに
は目を配っておきたい
実際の利用実績であるが4月の乗客数については目標の約半分との新聞報道があっ
た10万4千人の予想に反して結果は5万3千人にとどまっているしかし実際に毎
日利用している筆者からすると朝ラッシュ時のセンター北rarr日吉方面への混雑は日吉に近
づくにつれ相当なものとなる現状の2倍の乗客は乗れないまた夕方の時間帯の車内も空
席が目立たない程度に混んでおりこちらも現状の2倍の乗客が乗車するようではかなり
の混雑になってしまうつまり筆者が言いたいのは全体の結果として約半分になるものの
一部の時間帯や一部の区間の乗客数については目標に近いのではないだろうかというこ
とであるよって逆に予想よりかなり利用者の少ない時間帯の存在やもしくは区間によ
る偏りが大きいことが考えられるこれらはより詳細なデータを調べればわかるだろうま
た周辺のバス路線の利用者数の推移とも大いに関係するはずである今後の乗客増のため
にも横浜市等の対策に注目していきたい
筆者は都筑区北部在住であり自宅はグリーンラインの駅から徒歩10分ほどの距離
にある開通前はバスを利用し鉄道駅に向かっていたのでグリーンライン開通によってた
しかに便利になった特に最終バスが22時台と早かったため帰宅が深夜になる場合は非
常に便利であるしかし開通後もバスがあるときはバスを利用することが多いのもまた
事実であるこれはバスの本数自体は決して多くはないものの常にほぼ時刻表通りに運
行されておりその利用に抵抗がないこととバス停が細かく配置され自宅のすぐ近くにあ
ることが理由ある特に雨の日や日射しの強い日は徒歩距離の長いグリーンラインは敬遠し
てしまうただこれは筆者の考えであり一般的であるかは全く不明であることを強調し
ておく
42コムカモ
コムカモとは学内のバス停をネットワークカメラで常に撮影しその混雑状況をどこ
からでもすぐに把握できるようにすることで帰宅時間の分散をすすめバス利用を快適化
しようとするプロジェクトであるプライバシーなどの問題から現在カメラの設置には至
っておらず署名をあつめている段階であるその詳細な経緯や根拠の説明はここでは省く
中心になってこのプロジェクトを動かしていた杉山公一郎氏の卒業制作が詳しい
バス利用者は大学生にとどまらないため私は自分の交友関係を鑑み慶応義塾湘南藤
沢中高等部の生徒にこの署名をお願いしようと考えたしかしそれにはまずこのプロジ
ェクトについての意見をうかがう必要があった昨年度から中高等部とは何度かのやりと
りがあったようであるがおそらく末端の生徒は何も知らないと思い簡単な説明を行った
うえで意見をうかがったその結果得られた回答の要点は以下である回答者の属性は
6名全員が文化部で男性が3名女性が3名また中学生4名高校生2名である
①便利だとは思うが実際に利用することはまずないと思う
②友人にも利用すると思われる人はいない
③利用するならば携帯電話からの利用になる
①の意見が多かったことによって署名のお願いは断念した①の理由について意見
をまとめると以下のようになった
ア帰る時間が決まっていて選択の余地がない
イ友人同士での帰宅が多く並ばないことの重要性は少ない
ウ現在の混雑は理解できる範囲である
筆者が意見を聞いた中高生は帰る時間が基本的に決まっておりまたその結果人が集
中し混雑することを理解していたまたそれを仕方のないものだととらえていた各自の経
験等により各自の帰る時間が決まっていることも合わさってバス停の混雑する時間帯が頭
に入っているようであったつまりバス停混雑について現在ある程度の予測ができてお
りその結果混雑が想定されていてもその時間に帰宅しているのであるよって中高生の
多くはたとえコムカモで混雑していることが判明しても帰宅することが想像できるこ
れではコムカモの必要性は感じられないだろうしかし空いている時間に帰宅したいと
いうニーズはゼロではないと思うので実際に利用するかはともかく無いよりはあるほう
が便利は便利であるというスタンスで署名をお願いすればよいのではないかと考えている

各種資料からは存在することしか分からなかった「神奈川東部方面線懇談会」につ
いて横浜市に電話で問い合わせた
まずはじめに横浜市の市民情報室へ問い合わせの電話をかけた「神奈川東
部方面線の懇談会について知りたい」「新聞記事などで存在を知ったがもっと詳しく
知りたいと思っている会議録などは残っていないか」という旨の質問をしたところ
神奈川東部方面線を担当している部署へ電話をまわしていただけることになった
神奈川東部方面線担当の方につながったところで先ほどと同様の質問をした
担当の方も4月の異動で神奈川東部方面線担当になったようで当時の状況について
直接ご存知ないようであった少々込み入った話をしたところで一旦調べてまた
連絡していただけることになった
その後しばらくして電話をもらうがやはり議事録などは残っていない
との回答であったそこでどうにかもう少し当時の横浜市としての対応などを知る
ことができないか質問をしたまたつづけて直接お話を聞きにうかがうことはで
きないかとインタビューのお願いをしてみたところ分かる範囲でよろしければ
との回答を得ることができた
事業の当事者のひとつである横浜市から直接お話をしていただけるというのは
今後この研究をどのように進めていくかというその方向性を見定めるにもいい機会
であると思った後日こちらから電話し日時を決めることにしてこの日の電話
での質問は終了した
各種資料からは存在することしか分からなかった「神奈川東部方面線懇談会」につ
いて横浜市に直接ヒアリングにうかがった
5月27日の質問のあと6月3日に再度電話しアポイントメントを取った
結果6月9日の午後2時から横浜市庁舎にてインタビューできることになったま
た事前に質問書を送付したまた研究会で同行者をつのったところ2人一緒に来
てくださることになったとても心強かった
当日予定通り午後2時に横浜市庁舎6階へうかがった行政機関へのヒアリ
ング調査を行うのは初めてのことであり緊張した90分ほどお話をうかがいイ
ンタビューは無事終了したまたパンフレットと簡単な資料をいただいた録音した
音声ファイルを聞き返すと質問の仕方が稚拙なことが多くまた自分の主観の入っ
た質問も散見され反省するばかりである今後ヒアリング調査を行う際にはこの
点より強く心がけるようにしたい
東部方面線に関する質問票 慶應義塾大学環境情報学部 有澤研究室
日時平成20年6月9日月曜日 1400 ~ (予定) 場所横浜市役所本庁舎6階 都市整備局 (予定)
1東部方面線懇談会について
懇談会の基本的な情報を教えてください(経緯期間回数会場委員)
懇談会始動当時横浜市が重要視しておられたことについて教えてください
懇談会始動当時横浜市がすでに取り組んでおられたことについて教えてください
懇談会始動当時横浜市の各事業者等の狙いのとらえかたについて教えてください
都市鉄道等利便増進法制定との関係について教えてください
懇談会始動当時の事業化へ向けた課題について教えてください
2JR と相鉄の相互乗り入れ構想について
懇談会でのこの構想に関する議論について教えてください
新聞記事となったタイミングはどうでしたか
横浜市はこの構想をどう受け止めておられましたか
この構想と東部方面線の関係を整理する過程について教えてください
各事業者等との協議の焦点はどのようなことでしたか
3将来について
東部方面線事業に対する横浜市の今後の取り組みについて教えてください
現状横浜市が課題ととらえているのはどのようなことですか
西暦 平成
1999 11 6月 新横浜都心整備基本構想 策定
2000 12 運輸政策審議会答申18号 「A1路線」(平成27年までに開業することが望ましい) 3月 こどもの国線通勤線化
2001 13 1月 グリーンライン着工
2002 143月 市長選挙 中田氏当選6月 横浜でワールドカップ決勝が開催
2003 15 懇談会始動3月 市議会議員県議会議員県知事選挙 松沢知事当選12月 市営地下鉄全席優先席
2004 169月 JR相鉄直通新聞報道 横浜市長「協力するかこれから具体的に検討する」12月 横浜市長「(直通か東部方面線か)どちらかを優先」
2月 みなとみらい線開業
2005 17 8月 都市鉄道等利便増進法施行 9月 衆議院議員選挙 自民党圧勝
2006 18
2月 横浜市予算支出へ前向き5月 営業整備計画を事業者が申請6月 横浜市予算計上 営業整備計画認定11月 相鉄JR直通線 速達性向上計画認定
3月 市長選挙 中田氏再選
2007 194月 相鉄東急直通線 速達性向上計画認定10月~ 住民説明会など
3月 市議会議員県議会議員県知事選挙 松沢知事再選
2008 203月 グリーンライン開業6月 目黒線 日吉延伸
2009 21
2010 22
2011 23
2012 24 東横線hArr副都心線 直通開始予定
2013 25 東北縦貫線完成予定h(東海道線hArr東北高崎常磐線 直通)
2014 26
2015 27 相鉄JR直通線開業予定
2016 28
2017 29
2018 30
2019 31 相鉄東急直通線開業予定
ヒアリングで判明した内容をまとめた以下はその内容である
横浜市の方によると神奈川東部方面線懇談会とは国横浜市神奈川県東
急相鉄鉄道運輸機構であり課長レベルの方々が出席して行われたものである
とのことであったまたその下部にワークグループが存在しより詳細な調整が行
われたとのことであった会議録等の資料はやはり残っていないとの説明があった
相鉄 JR 直通線と神奈川東部方面線との関係についてはやはり新横浜を通
るか通らないかというこの違いが強調された横浜市にとって新横浜はその都市計
画において重要な位置付けをされておりその発展のためにまた横浜市西部や県央
地域から新横浜へのアクセス向上のために「新横浜を通る」東部方面線の整備が重要
であるとの説明があった横浜市にとって東部方面線は都心への直通路線としても
「もちろん大切」であるが新横浜のターミナル性を高めるために必要であることが
確認できたといえる
上記の内容から考察すると新聞記事やパンフレットでは都心への時間短縮が大
きく示されているものの横浜市としてはむしろ新横浜アクセス向上の意味が強い
と思われる都心への直通を前面に押し出し「速達性向上計画」として国に申請「都
市鉄道等利便増進法」に基づいてその整備を行うものであるが決して都内に人を吸
い上げられるだけのものではなく市の発展への意味も強くこめられていることが判
明した相鉄や東急は果たしてどう考えているのだろうか
33今後の活動
この春学期の活動を通して神奈川東部方面線についての横浜市の立場やとってきた
行動というものについての筆者の理解はとても深まったといえる同時に他の立場とい
うものについての興味を抱いた例えば相模鉄道の立場やJR の立場である横浜市にと
って極めて重要であった新横浜への到達は相模鉄道にとっていったいどれほどの価値が
あるものであったのだろうかまた相模鉄道は当時どのように考えていたのだろうか
またJR からすれば相鉄東急直通線が開通することで都心への旅客の奪いあいが発
生することが考えられるJR は「神奈川東部方面線懇談会」のメンバーではなかったもの
の決して関係ない立場ではないそれぞれに立場や目的を抱えていたはずである今後
の活動としては横浜市以外の関係者が東部方面線の事業化に向けてどのように対応し
行動をとってきたのかについて調査していきたいと考えている
またあわせてこの春学期に読むことのできなかった多くの文献に目を通したいこれ
は戦後から現在にいたるまでの鉄道整備の方式やその制度について理解しその知識を
得ることで神奈川東部方面線に関する事例研究からより思考を発展させこれからの都市
鉄道の整備に関する課題などの理解につながると思うからであるある程度の知識を習得し
自分なりに思考をしたのちより直接的な都市鉄道整備に関する先行研究を調べ論文など
を読みたいと思う
4そのほかの活動
41横浜市営地下鉄グリーンライン
2008年3月横浜市営地下鉄に新たな路線が開業した愛称をグリーンラインとい
い横浜市港北区の日吉から横浜市都筑区を縦断し横浜市緑区の中心部中山を結ぶ全長
131km の路線である日吉駅で東急東横線と目黒線に中山駅で JR 横浜線と連絡する
開業3ヵ月後の6月に東急目黒線が日吉駅まで延伸されたことで都内方面への利便性はい
くらか向上した車両はリニアモーター推進方式で車両 1 両あたりの長さは 155m現
在は4両編成であるがホームなどは編成の延長に対応し6両分の長さが用意されているよ
うである駅は10駅全線の所要時間は終日21分表定速度は約 37km で地下鉄と
してはそれなりであるが周辺路線と比較して速いとはいえないしかも運賃は非常に高い
ため東横線と横浜線の短絡線としてはほとんど機能しないものであるよって都筑区内
から東横線横浜線あるいは都筑区中心部への輸送が中心になると考えられる同じ都市
鉄道であってもグリーンラインの性質は東部方面線の性質と大きく異なるといえる都市
鉄道整備の最新の例でありまたその利用者のひとりとして今後ともその利用動向などに
は目を配っておきたい
実際の利用実績であるが4月の乗客数については目標の約半分との新聞報道があっ
た10万4千人の予想に反して結果は5万3千人にとどまっているしかし実際に毎
日利用している筆者からすると朝ラッシュ時のセンター北rarr日吉方面への混雑は日吉に近
づくにつれ相当なものとなる現状の2倍の乗客は乗れないまた夕方の時間帯の車内も空
席が目立たない程度に混んでおりこちらも現状の2倍の乗客が乗車するようではかなり
の混雑になってしまうつまり筆者が言いたいのは全体の結果として約半分になるものの
一部の時間帯や一部の区間の乗客数については目標に近いのではないだろうかというこ
とであるよって逆に予想よりかなり利用者の少ない時間帯の存在やもしくは区間によ
る偏りが大きいことが考えられるこれらはより詳細なデータを調べればわかるだろうま
た周辺のバス路線の利用者数の推移とも大いに関係するはずである今後の乗客増のため
にも横浜市等の対策に注目していきたい
筆者は都筑区北部在住であり自宅はグリーンラインの駅から徒歩10分ほどの距離
にある開通前はバスを利用し鉄道駅に向かっていたのでグリーンライン開通によってた
しかに便利になった特に最終バスが22時台と早かったため帰宅が深夜になる場合は非
常に便利であるしかし開通後もバスがあるときはバスを利用することが多いのもまた
事実であるこれはバスの本数自体は決して多くはないものの常にほぼ時刻表通りに運
行されておりその利用に抵抗がないこととバス停が細かく配置され自宅のすぐ近くにあ
ることが理由ある特に雨の日や日射しの強い日は徒歩距離の長いグリーンラインは敬遠し
てしまうただこれは筆者の考えであり一般的であるかは全く不明であることを強調し
ておく
42コムカモ
コムカモとは学内のバス停をネットワークカメラで常に撮影しその混雑状況をどこ
からでもすぐに把握できるようにすることで帰宅時間の分散をすすめバス利用を快適化
しようとするプロジェクトであるプライバシーなどの問題から現在カメラの設置には至
っておらず署名をあつめている段階であるその詳細な経緯や根拠の説明はここでは省く
中心になってこのプロジェクトを動かしていた杉山公一郎氏の卒業制作が詳しい
バス利用者は大学生にとどまらないため私は自分の交友関係を鑑み慶応義塾湘南藤
沢中高等部の生徒にこの署名をお願いしようと考えたしかしそれにはまずこのプロジ
ェクトについての意見をうかがう必要があった昨年度から中高等部とは何度かのやりと
りがあったようであるがおそらく末端の生徒は何も知らないと思い簡単な説明を行った
うえで意見をうかがったその結果得られた回答の要点は以下である回答者の属性は
6名全員が文化部で男性が3名女性が3名また中学生4名高校生2名である
①便利だとは思うが実際に利用することはまずないと思う
②友人にも利用すると思われる人はいない
③利用するならば携帯電話からの利用になる
①の意見が多かったことによって署名のお願いは断念した①の理由について意見
をまとめると以下のようになった
ア帰る時間が決まっていて選択の余地がない
イ友人同士での帰宅が多く並ばないことの重要性は少ない
ウ現在の混雑は理解できる範囲である
筆者が意見を聞いた中高生は帰る時間が基本的に決まっておりまたその結果人が集
中し混雑することを理解していたまたそれを仕方のないものだととらえていた各自の経
験等により各自の帰る時間が決まっていることも合わさってバス停の混雑する時間帯が頭
に入っているようであったつまりバス停混雑について現在ある程度の予測ができてお
りその結果混雑が想定されていてもその時間に帰宅しているのであるよって中高生の
多くはたとえコムカモで混雑していることが判明しても帰宅することが想像できるこ
れではコムカモの必要性は感じられないだろうしかし空いている時間に帰宅したいと
いうニーズはゼロではないと思うので実際に利用するかはともかく無いよりはあるほう
が便利は便利であるというスタンスで署名をお願いすればよいのではないかと考えている

各種資料からは存在することしか分からなかった「神奈川東部方面線懇談会」につ
いて横浜市に直接ヒアリングにうかがった
5月27日の質問のあと6月3日に再度電話しアポイントメントを取った
結果6月9日の午後2時から横浜市庁舎にてインタビューできることになったま
た事前に質問書を送付したまた研究会で同行者をつのったところ2人一緒に来
てくださることになったとても心強かった
当日予定通り午後2時に横浜市庁舎6階へうかがった行政機関へのヒアリ
ング調査を行うのは初めてのことであり緊張した90分ほどお話をうかがいイ
ンタビューは無事終了したまたパンフレットと簡単な資料をいただいた録音した
音声ファイルを聞き返すと質問の仕方が稚拙なことが多くまた自分の主観の入っ
た質問も散見され反省するばかりである今後ヒアリング調査を行う際にはこの
点より強く心がけるようにしたい
東部方面線に関する質問票 慶應義塾大学環境情報学部 有澤研究室
日時平成20年6月9日月曜日 1400 ~ (予定) 場所横浜市役所本庁舎6階 都市整備局 (予定)
1東部方面線懇談会について
懇談会の基本的な情報を教えてください(経緯期間回数会場委員)
懇談会始動当時横浜市が重要視しておられたことについて教えてください
懇談会始動当時横浜市がすでに取り組んでおられたことについて教えてください
懇談会始動当時横浜市の各事業者等の狙いのとらえかたについて教えてください
都市鉄道等利便増進法制定との関係について教えてください
懇談会始動当時の事業化へ向けた課題について教えてください
2JR と相鉄の相互乗り入れ構想について
懇談会でのこの構想に関する議論について教えてください
新聞記事となったタイミングはどうでしたか
横浜市はこの構想をどう受け止めておられましたか
この構想と東部方面線の関係を整理する過程について教えてください
各事業者等との協議の焦点はどのようなことでしたか
3将来について
東部方面線事業に対する横浜市の今後の取り組みについて教えてください
現状横浜市が課題ととらえているのはどのようなことですか
西暦 平成
1999 11 6月 新横浜都心整備基本構想 策定
2000 12 運輸政策審議会答申18号 「A1路線」(平成27年までに開業することが望ましい) 3月 こどもの国線通勤線化
2001 13 1月 グリーンライン着工
2002 143月 市長選挙 中田氏当選6月 横浜でワールドカップ決勝が開催
2003 15 懇談会始動3月 市議会議員県議会議員県知事選挙 松沢知事当選12月 市営地下鉄全席優先席
2004 169月 JR相鉄直通新聞報道 横浜市長「協力するかこれから具体的に検討する」12月 横浜市長「(直通か東部方面線か)どちらかを優先」
2月 みなとみらい線開業
2005 17 8月 都市鉄道等利便増進法施行 9月 衆議院議員選挙 自民党圧勝
2006 18
2月 横浜市予算支出へ前向き5月 営業整備計画を事業者が申請6月 横浜市予算計上 営業整備計画認定11月 相鉄JR直通線 速達性向上計画認定
3月 市長選挙 中田氏再選
2007 194月 相鉄東急直通線 速達性向上計画認定10月~ 住民説明会など
3月 市議会議員県議会議員県知事選挙 松沢知事再選
2008 203月 グリーンライン開業6月 目黒線 日吉延伸
2009 21
2010 22
2011 23
2012 24 東横線hArr副都心線 直通開始予定
2013 25 東北縦貫線完成予定h(東海道線hArr東北高崎常磐線 直通)
2014 26
2015 27 相鉄JR直通線開業予定
2016 28
2017 29
2018 30
2019 31 相鉄東急直通線開業予定
ヒアリングで判明した内容をまとめた以下はその内容である
横浜市の方によると神奈川東部方面線懇談会とは国横浜市神奈川県東
急相鉄鉄道運輸機構であり課長レベルの方々が出席して行われたものである
とのことであったまたその下部にワークグループが存在しより詳細な調整が行
われたとのことであった会議録等の資料はやはり残っていないとの説明があった
相鉄 JR 直通線と神奈川東部方面線との関係についてはやはり新横浜を通
るか通らないかというこの違いが強調された横浜市にとって新横浜はその都市計
画において重要な位置付けをされておりその発展のためにまた横浜市西部や県央
地域から新横浜へのアクセス向上のために「新横浜を通る」東部方面線の整備が重要
であるとの説明があった横浜市にとって東部方面線は都心への直通路線としても
「もちろん大切」であるが新横浜のターミナル性を高めるために必要であることが
確認できたといえる
上記の内容から考察すると新聞記事やパンフレットでは都心への時間短縮が大
きく示されているものの横浜市としてはむしろ新横浜アクセス向上の意味が強い
と思われる都心への直通を前面に押し出し「速達性向上計画」として国に申請「都
市鉄道等利便増進法」に基づいてその整備を行うものであるが決して都内に人を吸
い上げられるだけのものではなく市の発展への意味も強くこめられていることが判
明した相鉄や東急は果たしてどう考えているのだろうか
33今後の活動
この春学期の活動を通して神奈川東部方面線についての横浜市の立場やとってきた
行動というものについての筆者の理解はとても深まったといえる同時に他の立場とい
うものについての興味を抱いた例えば相模鉄道の立場やJR の立場である横浜市にと
って極めて重要であった新横浜への到達は相模鉄道にとっていったいどれほどの価値が
あるものであったのだろうかまた相模鉄道は当時どのように考えていたのだろうか
またJR からすれば相鉄東急直通線が開通することで都心への旅客の奪いあいが発
生することが考えられるJR は「神奈川東部方面線懇談会」のメンバーではなかったもの
の決して関係ない立場ではないそれぞれに立場や目的を抱えていたはずである今後
の活動としては横浜市以外の関係者が東部方面線の事業化に向けてどのように対応し
行動をとってきたのかについて調査していきたいと考えている
またあわせてこの春学期に読むことのできなかった多くの文献に目を通したいこれ
は戦後から現在にいたるまでの鉄道整備の方式やその制度について理解しその知識を
得ることで神奈川東部方面線に関する事例研究からより思考を発展させこれからの都市
鉄道の整備に関する課題などの理解につながると思うからであるある程度の知識を習得し
自分なりに思考をしたのちより直接的な都市鉄道整備に関する先行研究を調べ論文など
を読みたいと思う
4そのほかの活動
41横浜市営地下鉄グリーンライン
2008年3月横浜市営地下鉄に新たな路線が開業した愛称をグリーンラインとい
い横浜市港北区の日吉から横浜市都筑区を縦断し横浜市緑区の中心部中山を結ぶ全長
131km の路線である日吉駅で東急東横線と目黒線に中山駅で JR 横浜線と連絡する
開業3ヵ月後の6月に東急目黒線が日吉駅まで延伸されたことで都内方面への利便性はい
くらか向上した車両はリニアモーター推進方式で車両 1 両あたりの長さは 155m現
在は4両編成であるがホームなどは編成の延長に対応し6両分の長さが用意されているよ
うである駅は10駅全線の所要時間は終日21分表定速度は約 37km で地下鉄と
してはそれなりであるが周辺路線と比較して速いとはいえないしかも運賃は非常に高い
ため東横線と横浜線の短絡線としてはほとんど機能しないものであるよって都筑区内
から東横線横浜線あるいは都筑区中心部への輸送が中心になると考えられる同じ都市
鉄道であってもグリーンラインの性質は東部方面線の性質と大きく異なるといえる都市
鉄道整備の最新の例でありまたその利用者のひとりとして今後ともその利用動向などに
は目を配っておきたい
実際の利用実績であるが4月の乗客数については目標の約半分との新聞報道があっ
た10万4千人の予想に反して結果は5万3千人にとどまっているしかし実際に毎
日利用している筆者からすると朝ラッシュ時のセンター北rarr日吉方面への混雑は日吉に近
づくにつれ相当なものとなる現状の2倍の乗客は乗れないまた夕方の時間帯の車内も空
席が目立たない程度に混んでおりこちらも現状の2倍の乗客が乗車するようではかなり
の混雑になってしまうつまり筆者が言いたいのは全体の結果として約半分になるものの
一部の時間帯や一部の区間の乗客数については目標に近いのではないだろうかというこ
とであるよって逆に予想よりかなり利用者の少ない時間帯の存在やもしくは区間によ
る偏りが大きいことが考えられるこれらはより詳細なデータを調べればわかるだろうま
た周辺のバス路線の利用者数の推移とも大いに関係するはずである今後の乗客増のため
にも横浜市等の対策に注目していきたい
筆者は都筑区北部在住であり自宅はグリーンラインの駅から徒歩10分ほどの距離
にある開通前はバスを利用し鉄道駅に向かっていたのでグリーンライン開通によってた
しかに便利になった特に最終バスが22時台と早かったため帰宅が深夜になる場合は非
常に便利であるしかし開通後もバスがあるときはバスを利用することが多いのもまた
事実であるこれはバスの本数自体は決して多くはないものの常にほぼ時刻表通りに運
行されておりその利用に抵抗がないこととバス停が細かく配置され自宅のすぐ近くにあ
ることが理由ある特に雨の日や日射しの強い日は徒歩距離の長いグリーンラインは敬遠し
てしまうただこれは筆者の考えであり一般的であるかは全く不明であることを強調し
ておく
42コムカモ
コムカモとは学内のバス停をネットワークカメラで常に撮影しその混雑状況をどこ
からでもすぐに把握できるようにすることで帰宅時間の分散をすすめバス利用を快適化
しようとするプロジェクトであるプライバシーなどの問題から現在カメラの設置には至
っておらず署名をあつめている段階であるその詳細な経緯や根拠の説明はここでは省く
中心になってこのプロジェクトを動かしていた杉山公一郎氏の卒業制作が詳しい
バス利用者は大学生にとどまらないため私は自分の交友関係を鑑み慶応義塾湘南藤
沢中高等部の生徒にこの署名をお願いしようと考えたしかしそれにはまずこのプロジ
ェクトについての意見をうかがう必要があった昨年度から中高等部とは何度かのやりと
りがあったようであるがおそらく末端の生徒は何も知らないと思い簡単な説明を行った
うえで意見をうかがったその結果得られた回答の要点は以下である回答者の属性は
6名全員が文化部で男性が3名女性が3名また中学生4名高校生2名である
①便利だとは思うが実際に利用することはまずないと思う
②友人にも利用すると思われる人はいない
③利用するならば携帯電話からの利用になる
①の意見が多かったことによって署名のお願いは断念した①の理由について意見
をまとめると以下のようになった
ア帰る時間が決まっていて選択の余地がない
イ友人同士での帰宅が多く並ばないことの重要性は少ない
ウ現在の混雑は理解できる範囲である
筆者が意見を聞いた中高生は帰る時間が基本的に決まっておりまたその結果人が集
中し混雑することを理解していたまたそれを仕方のないものだととらえていた各自の経
験等により各自の帰る時間が決まっていることも合わさってバス停の混雑する時間帯が頭
に入っているようであったつまりバス停混雑について現在ある程度の予測ができてお
りその結果混雑が想定されていてもその時間に帰宅しているのであるよって中高生の
多くはたとえコムカモで混雑していることが判明しても帰宅することが想像できるこ
れではコムカモの必要性は感じられないだろうしかし空いている時間に帰宅したいと
いうニーズはゼロではないと思うので実際に利用するかはともかく無いよりはあるほう
が便利は便利であるというスタンスで署名をお願いすればよいのではないかと考えている

東部方面線に関する質問票 慶應義塾大学環境情報学部 有澤研究室
日時平成20年6月9日月曜日 1400 ~ (予定) 場所横浜市役所本庁舎6階 都市整備局 (予定)
1東部方面線懇談会について
懇談会の基本的な情報を教えてください(経緯期間回数会場委員)
懇談会始動当時横浜市が重要視しておられたことについて教えてください
懇談会始動当時横浜市がすでに取り組んでおられたことについて教えてください
懇談会始動当時横浜市の各事業者等の狙いのとらえかたについて教えてください
都市鉄道等利便増進法制定との関係について教えてください
懇談会始動当時の事業化へ向けた課題について教えてください
2JR と相鉄の相互乗り入れ構想について
懇談会でのこの構想に関する議論について教えてください
新聞記事となったタイミングはどうでしたか
横浜市はこの構想をどう受け止めておられましたか
この構想と東部方面線の関係を整理する過程について教えてください
各事業者等との協議の焦点はどのようなことでしたか
3将来について
東部方面線事業に対する横浜市の今後の取り組みについて教えてください
現状横浜市が課題ととらえているのはどのようなことですか
西暦 平成
1999 11 6月 新横浜都心整備基本構想 策定
2000 12 運輸政策審議会答申18号 「A1路線」(平成27年までに開業することが望ましい) 3月 こどもの国線通勤線化
2001 13 1月 グリーンライン着工
2002 143月 市長選挙 中田氏当選6月 横浜でワールドカップ決勝が開催
2003 15 懇談会始動3月 市議会議員県議会議員県知事選挙 松沢知事当選12月 市営地下鉄全席優先席
2004 169月 JR相鉄直通新聞報道 横浜市長「協力するかこれから具体的に検討する」12月 横浜市長「(直通か東部方面線か)どちらかを優先」
2月 みなとみらい線開業
2005 17 8月 都市鉄道等利便増進法施行 9月 衆議院議員選挙 自民党圧勝
2006 18
2月 横浜市予算支出へ前向き5月 営業整備計画を事業者が申請6月 横浜市予算計上 営業整備計画認定11月 相鉄JR直通線 速達性向上計画認定
3月 市長選挙 中田氏再選
2007 194月 相鉄東急直通線 速達性向上計画認定10月~ 住民説明会など
3月 市議会議員県議会議員県知事選挙 松沢知事再選
2008 203月 グリーンライン開業6月 目黒線 日吉延伸
2009 21
2010 22
2011 23
2012 24 東横線hArr副都心線 直通開始予定
2013 25 東北縦貫線完成予定h(東海道線hArr東北高崎常磐線 直通)
2014 26
2015 27 相鉄JR直通線開業予定
2016 28
2017 29
2018 30
2019 31 相鉄東急直通線開業予定
ヒアリングで判明した内容をまとめた以下はその内容である
横浜市の方によると神奈川東部方面線懇談会とは国横浜市神奈川県東
急相鉄鉄道運輸機構であり課長レベルの方々が出席して行われたものである
とのことであったまたその下部にワークグループが存在しより詳細な調整が行
われたとのことであった会議録等の資料はやはり残っていないとの説明があった
相鉄 JR 直通線と神奈川東部方面線との関係についてはやはり新横浜を通
るか通らないかというこの違いが強調された横浜市にとって新横浜はその都市計
画において重要な位置付けをされておりその発展のためにまた横浜市西部や県央
地域から新横浜へのアクセス向上のために「新横浜を通る」東部方面線の整備が重要
であるとの説明があった横浜市にとって東部方面線は都心への直通路線としても
「もちろん大切」であるが新横浜のターミナル性を高めるために必要であることが
確認できたといえる
上記の内容から考察すると新聞記事やパンフレットでは都心への時間短縮が大
きく示されているものの横浜市としてはむしろ新横浜アクセス向上の意味が強い
と思われる都心への直通を前面に押し出し「速達性向上計画」として国に申請「都
市鉄道等利便増進法」に基づいてその整備を行うものであるが決して都内に人を吸
い上げられるだけのものではなく市の発展への意味も強くこめられていることが判
明した相鉄や東急は果たしてどう考えているのだろうか
33今後の活動
この春学期の活動を通して神奈川東部方面線についての横浜市の立場やとってきた
行動というものについての筆者の理解はとても深まったといえる同時に他の立場とい
うものについての興味を抱いた例えば相模鉄道の立場やJR の立場である横浜市にと
って極めて重要であった新横浜への到達は相模鉄道にとっていったいどれほどの価値が
あるものであったのだろうかまた相模鉄道は当時どのように考えていたのだろうか
またJR からすれば相鉄東急直通線が開通することで都心への旅客の奪いあいが発
生することが考えられるJR は「神奈川東部方面線懇談会」のメンバーではなかったもの
の決して関係ない立場ではないそれぞれに立場や目的を抱えていたはずである今後
の活動としては横浜市以外の関係者が東部方面線の事業化に向けてどのように対応し
行動をとってきたのかについて調査していきたいと考えている
またあわせてこの春学期に読むことのできなかった多くの文献に目を通したいこれ
は戦後から現在にいたるまでの鉄道整備の方式やその制度について理解しその知識を
得ることで神奈川東部方面線に関する事例研究からより思考を発展させこれからの都市
鉄道の整備に関する課題などの理解につながると思うからであるある程度の知識を習得し
自分なりに思考をしたのちより直接的な都市鉄道整備に関する先行研究を調べ論文など
を読みたいと思う
4そのほかの活動
41横浜市営地下鉄グリーンライン
2008年3月横浜市営地下鉄に新たな路線が開業した愛称をグリーンラインとい
い横浜市港北区の日吉から横浜市都筑区を縦断し横浜市緑区の中心部中山を結ぶ全長
131km の路線である日吉駅で東急東横線と目黒線に中山駅で JR 横浜線と連絡する
開業3ヵ月後の6月に東急目黒線が日吉駅まで延伸されたことで都内方面への利便性はい
くらか向上した車両はリニアモーター推進方式で車両 1 両あたりの長さは 155m現
在は4両編成であるがホームなどは編成の延長に対応し6両分の長さが用意されているよ
うである駅は10駅全線の所要時間は終日21分表定速度は約 37km で地下鉄と
してはそれなりであるが周辺路線と比較して速いとはいえないしかも運賃は非常に高い
ため東横線と横浜線の短絡線としてはほとんど機能しないものであるよって都筑区内
から東横線横浜線あるいは都筑区中心部への輸送が中心になると考えられる同じ都市
鉄道であってもグリーンラインの性質は東部方面線の性質と大きく異なるといえる都市
鉄道整備の最新の例でありまたその利用者のひとりとして今後ともその利用動向などに
は目を配っておきたい
実際の利用実績であるが4月の乗客数については目標の約半分との新聞報道があっ
た10万4千人の予想に反して結果は5万3千人にとどまっているしかし実際に毎
日利用している筆者からすると朝ラッシュ時のセンター北rarr日吉方面への混雑は日吉に近
づくにつれ相当なものとなる現状の2倍の乗客は乗れないまた夕方の時間帯の車内も空
席が目立たない程度に混んでおりこちらも現状の2倍の乗客が乗車するようではかなり
の混雑になってしまうつまり筆者が言いたいのは全体の結果として約半分になるものの
一部の時間帯や一部の区間の乗客数については目標に近いのではないだろうかというこ
とであるよって逆に予想よりかなり利用者の少ない時間帯の存在やもしくは区間によ
る偏りが大きいことが考えられるこれらはより詳細なデータを調べればわかるだろうま
た周辺のバス路線の利用者数の推移とも大いに関係するはずである今後の乗客増のため
にも横浜市等の対策に注目していきたい
筆者は都筑区北部在住であり自宅はグリーンラインの駅から徒歩10分ほどの距離
にある開通前はバスを利用し鉄道駅に向かっていたのでグリーンライン開通によってた
しかに便利になった特に最終バスが22時台と早かったため帰宅が深夜になる場合は非
常に便利であるしかし開通後もバスがあるときはバスを利用することが多いのもまた
事実であるこれはバスの本数自体は決して多くはないものの常にほぼ時刻表通りに運
行されておりその利用に抵抗がないこととバス停が細かく配置され自宅のすぐ近くにあ
ることが理由ある特に雨の日や日射しの強い日は徒歩距離の長いグリーンラインは敬遠し
てしまうただこれは筆者の考えであり一般的であるかは全く不明であることを強調し
ておく
42コムカモ
コムカモとは学内のバス停をネットワークカメラで常に撮影しその混雑状況をどこ
からでもすぐに把握できるようにすることで帰宅時間の分散をすすめバス利用を快適化
しようとするプロジェクトであるプライバシーなどの問題から現在カメラの設置には至
っておらず署名をあつめている段階であるその詳細な経緯や根拠の説明はここでは省く
中心になってこのプロジェクトを動かしていた杉山公一郎氏の卒業制作が詳しい
バス利用者は大学生にとどまらないため私は自分の交友関係を鑑み慶応義塾湘南藤
沢中高等部の生徒にこの署名をお願いしようと考えたしかしそれにはまずこのプロジ
ェクトについての意見をうかがう必要があった昨年度から中高等部とは何度かのやりと
りがあったようであるがおそらく末端の生徒は何も知らないと思い簡単な説明を行った
うえで意見をうかがったその結果得られた回答の要点は以下である回答者の属性は
6名全員が文化部で男性が3名女性が3名また中学生4名高校生2名である
①便利だとは思うが実際に利用することはまずないと思う
②友人にも利用すると思われる人はいない
③利用するならば携帯電話からの利用になる
①の意見が多かったことによって署名のお願いは断念した①の理由について意見
をまとめると以下のようになった
ア帰る時間が決まっていて選択の余地がない
イ友人同士での帰宅が多く並ばないことの重要性は少ない
ウ現在の混雑は理解できる範囲である
筆者が意見を聞いた中高生は帰る時間が基本的に決まっておりまたその結果人が集
中し混雑することを理解していたまたそれを仕方のないものだととらえていた各自の経
験等により各自の帰る時間が決まっていることも合わさってバス停の混雑する時間帯が頭
に入っているようであったつまりバス停混雑について現在ある程度の予測ができてお
りその結果混雑が想定されていてもその時間に帰宅しているのであるよって中高生の
多くはたとえコムカモで混雑していることが判明しても帰宅することが想像できるこ
れではコムカモの必要性は感じられないだろうしかし空いている時間に帰宅したいと
いうニーズはゼロではないと思うので実際に利用するかはともかく無いよりはあるほう
が便利は便利であるというスタンスで署名をお願いすればよいのではないかと考えている

西暦 平成
1999 11 6月 新横浜都心整備基本構想 策定
2000 12 運輸政策審議会答申18号 「A1路線」(平成27年までに開業することが望ましい) 3月 こどもの国線通勤線化
2001 13 1月 グリーンライン着工
2002 143月 市長選挙 中田氏当選6月 横浜でワールドカップ決勝が開催
2003 15 懇談会始動3月 市議会議員県議会議員県知事選挙 松沢知事当選12月 市営地下鉄全席優先席
2004 169月 JR相鉄直通新聞報道 横浜市長「協力するかこれから具体的に検討する」12月 横浜市長「(直通か東部方面線か)どちらかを優先」
2月 みなとみらい線開業
2005 17 8月 都市鉄道等利便増進法施行 9月 衆議院議員選挙 自民党圧勝
2006 18
2月 横浜市予算支出へ前向き5月 営業整備計画を事業者が申請6月 横浜市予算計上 営業整備計画認定11月 相鉄JR直通線 速達性向上計画認定
3月 市長選挙 中田氏再選
2007 194月 相鉄東急直通線 速達性向上計画認定10月~ 住民説明会など
3月 市議会議員県議会議員県知事選挙 松沢知事再選
2008 203月 グリーンライン開業6月 目黒線 日吉延伸
2009 21
2010 22
2011 23
2012 24 東横線hArr副都心線 直通開始予定
2013 25 東北縦貫線完成予定h(東海道線hArr東北高崎常磐線 直通)
2014 26
2015 27 相鉄JR直通線開業予定
2016 28
2017 29
2018 30
2019 31 相鉄東急直通線開業予定
ヒアリングで判明した内容をまとめた以下はその内容である
横浜市の方によると神奈川東部方面線懇談会とは国横浜市神奈川県東
急相鉄鉄道運輸機構であり課長レベルの方々が出席して行われたものである
とのことであったまたその下部にワークグループが存在しより詳細な調整が行
われたとのことであった会議録等の資料はやはり残っていないとの説明があった
相鉄 JR 直通線と神奈川東部方面線との関係についてはやはり新横浜を通
るか通らないかというこの違いが強調された横浜市にとって新横浜はその都市計
画において重要な位置付けをされておりその発展のためにまた横浜市西部や県央
地域から新横浜へのアクセス向上のために「新横浜を通る」東部方面線の整備が重要
であるとの説明があった横浜市にとって東部方面線は都心への直通路線としても
「もちろん大切」であるが新横浜のターミナル性を高めるために必要であることが
確認できたといえる
上記の内容から考察すると新聞記事やパンフレットでは都心への時間短縮が大
きく示されているものの横浜市としてはむしろ新横浜アクセス向上の意味が強い
と思われる都心への直通を前面に押し出し「速達性向上計画」として国に申請「都
市鉄道等利便増進法」に基づいてその整備を行うものであるが決して都内に人を吸
い上げられるだけのものではなく市の発展への意味も強くこめられていることが判
明した相鉄や東急は果たしてどう考えているのだろうか
33今後の活動
この春学期の活動を通して神奈川東部方面線についての横浜市の立場やとってきた
行動というものについての筆者の理解はとても深まったといえる同時に他の立場とい
うものについての興味を抱いた例えば相模鉄道の立場やJR の立場である横浜市にと
って極めて重要であった新横浜への到達は相模鉄道にとっていったいどれほどの価値が
あるものであったのだろうかまた相模鉄道は当時どのように考えていたのだろうか
またJR からすれば相鉄東急直通線が開通することで都心への旅客の奪いあいが発
生することが考えられるJR は「神奈川東部方面線懇談会」のメンバーではなかったもの
の決して関係ない立場ではないそれぞれに立場や目的を抱えていたはずである今後
の活動としては横浜市以外の関係者が東部方面線の事業化に向けてどのように対応し
行動をとってきたのかについて調査していきたいと考えている
またあわせてこの春学期に読むことのできなかった多くの文献に目を通したいこれ
は戦後から現在にいたるまでの鉄道整備の方式やその制度について理解しその知識を
得ることで神奈川東部方面線に関する事例研究からより思考を発展させこれからの都市
鉄道の整備に関する課題などの理解につながると思うからであるある程度の知識を習得し
自分なりに思考をしたのちより直接的な都市鉄道整備に関する先行研究を調べ論文など
を読みたいと思う
4そのほかの活動
41横浜市営地下鉄グリーンライン
2008年3月横浜市営地下鉄に新たな路線が開業した愛称をグリーンラインとい
い横浜市港北区の日吉から横浜市都筑区を縦断し横浜市緑区の中心部中山を結ぶ全長
131km の路線である日吉駅で東急東横線と目黒線に中山駅で JR 横浜線と連絡する
開業3ヵ月後の6月に東急目黒線が日吉駅まで延伸されたことで都内方面への利便性はい
くらか向上した車両はリニアモーター推進方式で車両 1 両あたりの長さは 155m現
在は4両編成であるがホームなどは編成の延長に対応し6両分の長さが用意されているよ
うである駅は10駅全線の所要時間は終日21分表定速度は約 37km で地下鉄と
してはそれなりであるが周辺路線と比較して速いとはいえないしかも運賃は非常に高い
ため東横線と横浜線の短絡線としてはほとんど機能しないものであるよって都筑区内
から東横線横浜線あるいは都筑区中心部への輸送が中心になると考えられる同じ都市
鉄道であってもグリーンラインの性質は東部方面線の性質と大きく異なるといえる都市
鉄道整備の最新の例でありまたその利用者のひとりとして今後ともその利用動向などに
は目を配っておきたい
実際の利用実績であるが4月の乗客数については目標の約半分との新聞報道があっ
た10万4千人の予想に反して結果は5万3千人にとどまっているしかし実際に毎
日利用している筆者からすると朝ラッシュ時のセンター北rarr日吉方面への混雑は日吉に近
づくにつれ相当なものとなる現状の2倍の乗客は乗れないまた夕方の時間帯の車内も空
席が目立たない程度に混んでおりこちらも現状の2倍の乗客が乗車するようではかなり
の混雑になってしまうつまり筆者が言いたいのは全体の結果として約半分になるものの
一部の時間帯や一部の区間の乗客数については目標に近いのではないだろうかというこ
とであるよって逆に予想よりかなり利用者の少ない時間帯の存在やもしくは区間によ
る偏りが大きいことが考えられるこれらはより詳細なデータを調べればわかるだろうま
た周辺のバス路線の利用者数の推移とも大いに関係するはずである今後の乗客増のため
にも横浜市等の対策に注目していきたい
筆者は都筑区北部在住であり自宅はグリーンラインの駅から徒歩10分ほどの距離
にある開通前はバスを利用し鉄道駅に向かっていたのでグリーンライン開通によってた
しかに便利になった特に最終バスが22時台と早かったため帰宅が深夜になる場合は非
常に便利であるしかし開通後もバスがあるときはバスを利用することが多いのもまた
事実であるこれはバスの本数自体は決して多くはないものの常にほぼ時刻表通りに運
行されておりその利用に抵抗がないこととバス停が細かく配置され自宅のすぐ近くにあ
ることが理由ある特に雨の日や日射しの強い日は徒歩距離の長いグリーンラインは敬遠し
てしまうただこれは筆者の考えであり一般的であるかは全く不明であることを強調し
ておく
42コムカモ
コムカモとは学内のバス停をネットワークカメラで常に撮影しその混雑状況をどこ
からでもすぐに把握できるようにすることで帰宅時間の分散をすすめバス利用を快適化
しようとするプロジェクトであるプライバシーなどの問題から現在カメラの設置には至
っておらず署名をあつめている段階であるその詳細な経緯や根拠の説明はここでは省く
中心になってこのプロジェクトを動かしていた杉山公一郎氏の卒業制作が詳しい
バス利用者は大学生にとどまらないため私は自分の交友関係を鑑み慶応義塾湘南藤
沢中高等部の生徒にこの署名をお願いしようと考えたしかしそれにはまずこのプロジ
ェクトについての意見をうかがう必要があった昨年度から中高等部とは何度かのやりと
りがあったようであるがおそらく末端の生徒は何も知らないと思い簡単な説明を行った
うえで意見をうかがったその結果得られた回答の要点は以下である回答者の属性は
6名全員が文化部で男性が3名女性が3名また中学生4名高校生2名である
①便利だとは思うが実際に利用することはまずないと思う
②友人にも利用すると思われる人はいない
③利用するならば携帯電話からの利用になる
①の意見が多かったことによって署名のお願いは断念した①の理由について意見
をまとめると以下のようになった
ア帰る時間が決まっていて選択の余地がない
イ友人同士での帰宅が多く並ばないことの重要性は少ない
ウ現在の混雑は理解できる範囲である
筆者が意見を聞いた中高生は帰る時間が基本的に決まっておりまたその結果人が集
中し混雑することを理解していたまたそれを仕方のないものだととらえていた各自の経
験等により各自の帰る時間が決まっていることも合わさってバス停の混雑する時間帯が頭
に入っているようであったつまりバス停混雑について現在ある程度の予測ができてお
りその結果混雑が想定されていてもその時間に帰宅しているのであるよって中高生の
多くはたとえコムカモで混雑していることが判明しても帰宅することが想像できるこ
れではコムカモの必要性は感じられないだろうしかし空いている時間に帰宅したいと
いうニーズはゼロではないと思うので実際に利用するかはともかく無いよりはあるほう
が便利は便利であるというスタンスで署名をお願いすればよいのではないかと考えている

ヒアリングで判明した内容をまとめた以下はその内容である
横浜市の方によると神奈川東部方面線懇談会とは国横浜市神奈川県東
急相鉄鉄道運輸機構であり課長レベルの方々が出席して行われたものである
とのことであったまたその下部にワークグループが存在しより詳細な調整が行
われたとのことであった会議録等の資料はやはり残っていないとの説明があった
相鉄 JR 直通線と神奈川東部方面線との関係についてはやはり新横浜を通
るか通らないかというこの違いが強調された横浜市にとって新横浜はその都市計
画において重要な位置付けをされておりその発展のためにまた横浜市西部や県央
地域から新横浜へのアクセス向上のために「新横浜を通る」東部方面線の整備が重要
であるとの説明があった横浜市にとって東部方面線は都心への直通路線としても
「もちろん大切」であるが新横浜のターミナル性を高めるために必要であることが
確認できたといえる
上記の内容から考察すると新聞記事やパンフレットでは都心への時間短縮が大
きく示されているものの横浜市としてはむしろ新横浜アクセス向上の意味が強い
と思われる都心への直通を前面に押し出し「速達性向上計画」として国に申請「都
市鉄道等利便増進法」に基づいてその整備を行うものであるが決して都内に人を吸
い上げられるだけのものではなく市の発展への意味も強くこめられていることが判
明した相鉄や東急は果たしてどう考えているのだろうか
33今後の活動
この春学期の活動を通して神奈川東部方面線についての横浜市の立場やとってきた
行動というものについての筆者の理解はとても深まったといえる同時に他の立場とい
うものについての興味を抱いた例えば相模鉄道の立場やJR の立場である横浜市にと
って極めて重要であった新横浜への到達は相模鉄道にとっていったいどれほどの価値が
あるものであったのだろうかまた相模鉄道は当時どのように考えていたのだろうか
またJR からすれば相鉄東急直通線が開通することで都心への旅客の奪いあいが発
生することが考えられるJR は「神奈川東部方面線懇談会」のメンバーではなかったもの
の決して関係ない立場ではないそれぞれに立場や目的を抱えていたはずである今後
の活動としては横浜市以外の関係者が東部方面線の事業化に向けてどのように対応し
行動をとってきたのかについて調査していきたいと考えている
またあわせてこの春学期に読むことのできなかった多くの文献に目を通したいこれ
は戦後から現在にいたるまでの鉄道整備の方式やその制度について理解しその知識を
得ることで神奈川東部方面線に関する事例研究からより思考を発展させこれからの都市
鉄道の整備に関する課題などの理解につながると思うからであるある程度の知識を習得し
自分なりに思考をしたのちより直接的な都市鉄道整備に関する先行研究を調べ論文など
を読みたいと思う
4そのほかの活動
41横浜市営地下鉄グリーンライン
2008年3月横浜市営地下鉄に新たな路線が開業した愛称をグリーンラインとい
い横浜市港北区の日吉から横浜市都筑区を縦断し横浜市緑区の中心部中山を結ぶ全長
131km の路線である日吉駅で東急東横線と目黒線に中山駅で JR 横浜線と連絡する
開業3ヵ月後の6月に東急目黒線が日吉駅まで延伸されたことで都内方面への利便性はい
くらか向上した車両はリニアモーター推進方式で車両 1 両あたりの長さは 155m現
在は4両編成であるがホームなどは編成の延長に対応し6両分の長さが用意されているよ
うである駅は10駅全線の所要時間は終日21分表定速度は約 37km で地下鉄と
してはそれなりであるが周辺路線と比較して速いとはいえないしかも運賃は非常に高い
ため東横線と横浜線の短絡線としてはほとんど機能しないものであるよって都筑区内
から東横線横浜線あるいは都筑区中心部への輸送が中心になると考えられる同じ都市
鉄道であってもグリーンラインの性質は東部方面線の性質と大きく異なるといえる都市
鉄道整備の最新の例でありまたその利用者のひとりとして今後ともその利用動向などに
は目を配っておきたい
実際の利用実績であるが4月の乗客数については目標の約半分との新聞報道があっ
た10万4千人の予想に反して結果は5万3千人にとどまっているしかし実際に毎
日利用している筆者からすると朝ラッシュ時のセンター北rarr日吉方面への混雑は日吉に近
づくにつれ相当なものとなる現状の2倍の乗客は乗れないまた夕方の時間帯の車内も空
席が目立たない程度に混んでおりこちらも現状の2倍の乗客が乗車するようではかなり
の混雑になってしまうつまり筆者が言いたいのは全体の結果として約半分になるものの
一部の時間帯や一部の区間の乗客数については目標に近いのではないだろうかというこ
とであるよって逆に予想よりかなり利用者の少ない時間帯の存在やもしくは区間によ
る偏りが大きいことが考えられるこれらはより詳細なデータを調べればわかるだろうま
た周辺のバス路線の利用者数の推移とも大いに関係するはずである今後の乗客増のため
にも横浜市等の対策に注目していきたい
筆者は都筑区北部在住であり自宅はグリーンラインの駅から徒歩10分ほどの距離
にある開通前はバスを利用し鉄道駅に向かっていたのでグリーンライン開通によってた
しかに便利になった特に最終バスが22時台と早かったため帰宅が深夜になる場合は非
常に便利であるしかし開通後もバスがあるときはバスを利用することが多いのもまた
事実であるこれはバスの本数自体は決して多くはないものの常にほぼ時刻表通りに運
行されておりその利用に抵抗がないこととバス停が細かく配置され自宅のすぐ近くにあ
ることが理由ある特に雨の日や日射しの強い日は徒歩距離の長いグリーンラインは敬遠し
てしまうただこれは筆者の考えであり一般的であるかは全く不明であることを強調し
ておく
42コムカモ
コムカモとは学内のバス停をネットワークカメラで常に撮影しその混雑状況をどこ
からでもすぐに把握できるようにすることで帰宅時間の分散をすすめバス利用を快適化
しようとするプロジェクトであるプライバシーなどの問題から現在カメラの設置には至
っておらず署名をあつめている段階であるその詳細な経緯や根拠の説明はここでは省く
中心になってこのプロジェクトを動かしていた杉山公一郎氏の卒業制作が詳しい
バス利用者は大学生にとどまらないため私は自分の交友関係を鑑み慶応義塾湘南藤
沢中高等部の生徒にこの署名をお願いしようと考えたしかしそれにはまずこのプロジ
ェクトについての意見をうかがう必要があった昨年度から中高等部とは何度かのやりと
りがあったようであるがおそらく末端の生徒は何も知らないと思い簡単な説明を行った
うえで意見をうかがったその結果得られた回答の要点は以下である回答者の属性は
6名全員が文化部で男性が3名女性が3名また中学生4名高校生2名である
①便利だとは思うが実際に利用することはまずないと思う
②友人にも利用すると思われる人はいない
③利用するならば携帯電話からの利用になる
①の意見が多かったことによって署名のお願いは断念した①の理由について意見
をまとめると以下のようになった
ア帰る時間が決まっていて選択の余地がない
イ友人同士での帰宅が多く並ばないことの重要性は少ない
ウ現在の混雑は理解できる範囲である
筆者が意見を聞いた中高生は帰る時間が基本的に決まっておりまたその結果人が集
中し混雑することを理解していたまたそれを仕方のないものだととらえていた各自の経
験等により各自の帰る時間が決まっていることも合わさってバス停の混雑する時間帯が頭
に入っているようであったつまりバス停混雑について現在ある程度の予測ができてお
りその結果混雑が想定されていてもその時間に帰宅しているのであるよって中高生の
多くはたとえコムカモで混雑していることが判明しても帰宅することが想像できるこ
れではコムカモの必要性は感じられないだろうしかし空いている時間に帰宅したいと
いうニーズはゼロではないと思うので実際に利用するかはともかく無いよりはあるほう
が便利は便利であるというスタンスで署名をお願いすればよいのではないかと考えている

33今後の活動
この春学期の活動を通して神奈川東部方面線についての横浜市の立場やとってきた
行動というものについての筆者の理解はとても深まったといえる同時に他の立場とい
うものについての興味を抱いた例えば相模鉄道の立場やJR の立場である横浜市にと
って極めて重要であった新横浜への到達は相模鉄道にとっていったいどれほどの価値が
あるものであったのだろうかまた相模鉄道は当時どのように考えていたのだろうか
またJR からすれば相鉄東急直通線が開通することで都心への旅客の奪いあいが発
生することが考えられるJR は「神奈川東部方面線懇談会」のメンバーではなかったもの
の決して関係ない立場ではないそれぞれに立場や目的を抱えていたはずである今後
の活動としては横浜市以外の関係者が東部方面線の事業化に向けてどのように対応し
行動をとってきたのかについて調査していきたいと考えている
またあわせてこの春学期に読むことのできなかった多くの文献に目を通したいこれ
は戦後から現在にいたるまでの鉄道整備の方式やその制度について理解しその知識を
得ることで神奈川東部方面線に関する事例研究からより思考を発展させこれからの都市
鉄道の整備に関する課題などの理解につながると思うからであるある程度の知識を習得し
自分なりに思考をしたのちより直接的な都市鉄道整備に関する先行研究を調べ論文など
を読みたいと思う
4そのほかの活動
41横浜市営地下鉄グリーンライン
2008年3月横浜市営地下鉄に新たな路線が開業した愛称をグリーンラインとい
い横浜市港北区の日吉から横浜市都筑区を縦断し横浜市緑区の中心部中山を結ぶ全長
131km の路線である日吉駅で東急東横線と目黒線に中山駅で JR 横浜線と連絡する
開業3ヵ月後の6月に東急目黒線が日吉駅まで延伸されたことで都内方面への利便性はい
くらか向上した車両はリニアモーター推進方式で車両 1 両あたりの長さは 155m現
在は4両編成であるがホームなどは編成の延長に対応し6両分の長さが用意されているよ
うである駅は10駅全線の所要時間は終日21分表定速度は約 37km で地下鉄と
してはそれなりであるが周辺路線と比較して速いとはいえないしかも運賃は非常に高い
ため東横線と横浜線の短絡線としてはほとんど機能しないものであるよって都筑区内
から東横線横浜線あるいは都筑区中心部への輸送が中心になると考えられる同じ都市
鉄道であってもグリーンラインの性質は東部方面線の性質と大きく異なるといえる都市
鉄道整備の最新の例でありまたその利用者のひとりとして今後ともその利用動向などに
は目を配っておきたい
実際の利用実績であるが4月の乗客数については目標の約半分との新聞報道があっ
た10万4千人の予想に反して結果は5万3千人にとどまっているしかし実際に毎
日利用している筆者からすると朝ラッシュ時のセンター北rarr日吉方面への混雑は日吉に近
づくにつれ相当なものとなる現状の2倍の乗客は乗れないまた夕方の時間帯の車内も空
席が目立たない程度に混んでおりこちらも現状の2倍の乗客が乗車するようではかなり
の混雑になってしまうつまり筆者が言いたいのは全体の結果として約半分になるものの
一部の時間帯や一部の区間の乗客数については目標に近いのではないだろうかというこ
とであるよって逆に予想よりかなり利用者の少ない時間帯の存在やもしくは区間によ
る偏りが大きいことが考えられるこれらはより詳細なデータを調べればわかるだろうま
た周辺のバス路線の利用者数の推移とも大いに関係するはずである今後の乗客増のため
にも横浜市等の対策に注目していきたい
筆者は都筑区北部在住であり自宅はグリーンラインの駅から徒歩10分ほどの距離
にある開通前はバスを利用し鉄道駅に向かっていたのでグリーンライン開通によってた
しかに便利になった特に最終バスが22時台と早かったため帰宅が深夜になる場合は非
常に便利であるしかし開通後もバスがあるときはバスを利用することが多いのもまた
事実であるこれはバスの本数自体は決して多くはないものの常にほぼ時刻表通りに運
行されておりその利用に抵抗がないこととバス停が細かく配置され自宅のすぐ近くにあ
ることが理由ある特に雨の日や日射しの強い日は徒歩距離の長いグリーンラインは敬遠し
てしまうただこれは筆者の考えであり一般的であるかは全く不明であることを強調し
ておく
42コムカモ
コムカモとは学内のバス停をネットワークカメラで常に撮影しその混雑状況をどこ
からでもすぐに把握できるようにすることで帰宅時間の分散をすすめバス利用を快適化
しようとするプロジェクトであるプライバシーなどの問題から現在カメラの設置には至
っておらず署名をあつめている段階であるその詳細な経緯や根拠の説明はここでは省く
中心になってこのプロジェクトを動かしていた杉山公一郎氏の卒業制作が詳しい
バス利用者は大学生にとどまらないため私は自分の交友関係を鑑み慶応義塾湘南藤
沢中高等部の生徒にこの署名をお願いしようと考えたしかしそれにはまずこのプロジ
ェクトについての意見をうかがう必要があった昨年度から中高等部とは何度かのやりと
りがあったようであるがおそらく末端の生徒は何も知らないと思い簡単な説明を行った
うえで意見をうかがったその結果得られた回答の要点は以下である回答者の属性は
6名全員が文化部で男性が3名女性が3名また中学生4名高校生2名である
①便利だとは思うが実際に利用することはまずないと思う
②友人にも利用すると思われる人はいない
③利用するならば携帯電話からの利用になる
①の意見が多かったことによって署名のお願いは断念した①の理由について意見
をまとめると以下のようになった
ア帰る時間が決まっていて選択の余地がない
イ友人同士での帰宅が多く並ばないことの重要性は少ない
ウ現在の混雑は理解できる範囲である
筆者が意見を聞いた中高生は帰る時間が基本的に決まっておりまたその結果人が集
中し混雑することを理解していたまたそれを仕方のないものだととらえていた各自の経
験等により各自の帰る時間が決まっていることも合わさってバス停の混雑する時間帯が頭
に入っているようであったつまりバス停混雑について現在ある程度の予測ができてお
りその結果混雑が想定されていてもその時間に帰宅しているのであるよって中高生の
多くはたとえコムカモで混雑していることが判明しても帰宅することが想像できるこ
れではコムカモの必要性は感じられないだろうしかし空いている時間に帰宅したいと
いうニーズはゼロではないと思うので実際に利用するかはともかく無いよりはあるほう
が便利は便利であるというスタンスで署名をお願いすればよいのではないかと考えている

4そのほかの活動
41横浜市営地下鉄グリーンライン
2008年3月横浜市営地下鉄に新たな路線が開業した愛称をグリーンラインとい
い横浜市港北区の日吉から横浜市都筑区を縦断し横浜市緑区の中心部中山を結ぶ全長
131km の路線である日吉駅で東急東横線と目黒線に中山駅で JR 横浜線と連絡する
開業3ヵ月後の6月に東急目黒線が日吉駅まで延伸されたことで都内方面への利便性はい
くらか向上した車両はリニアモーター推進方式で車両 1 両あたりの長さは 155m現
在は4両編成であるがホームなどは編成の延長に対応し6両分の長さが用意されているよ
うである駅は10駅全線の所要時間は終日21分表定速度は約 37km で地下鉄と
してはそれなりであるが周辺路線と比較して速いとはいえないしかも運賃は非常に高い
ため東横線と横浜線の短絡線としてはほとんど機能しないものであるよって都筑区内
から東横線横浜線あるいは都筑区中心部への輸送が中心になると考えられる同じ都市
鉄道であってもグリーンラインの性質は東部方面線の性質と大きく異なるといえる都市
鉄道整備の最新の例でありまたその利用者のひとりとして今後ともその利用動向などに
は目を配っておきたい
実際の利用実績であるが4月の乗客数については目標の約半分との新聞報道があっ
た10万4千人の予想に反して結果は5万3千人にとどまっているしかし実際に毎
日利用している筆者からすると朝ラッシュ時のセンター北rarr日吉方面への混雑は日吉に近
づくにつれ相当なものとなる現状の2倍の乗客は乗れないまた夕方の時間帯の車内も空
席が目立たない程度に混んでおりこちらも現状の2倍の乗客が乗車するようではかなり
の混雑になってしまうつまり筆者が言いたいのは全体の結果として約半分になるものの
一部の時間帯や一部の区間の乗客数については目標に近いのではないだろうかというこ
とであるよって逆に予想よりかなり利用者の少ない時間帯の存在やもしくは区間によ
る偏りが大きいことが考えられるこれらはより詳細なデータを調べればわかるだろうま
た周辺のバス路線の利用者数の推移とも大いに関係するはずである今後の乗客増のため
にも横浜市等の対策に注目していきたい
筆者は都筑区北部在住であり自宅はグリーンラインの駅から徒歩10分ほどの距離
にある開通前はバスを利用し鉄道駅に向かっていたのでグリーンライン開通によってた
しかに便利になった特に最終バスが22時台と早かったため帰宅が深夜になる場合は非
常に便利であるしかし開通後もバスがあるときはバスを利用することが多いのもまた
事実であるこれはバスの本数自体は決して多くはないものの常にほぼ時刻表通りに運
行されておりその利用に抵抗がないこととバス停が細かく配置され自宅のすぐ近くにあ
ることが理由ある特に雨の日や日射しの強い日は徒歩距離の長いグリーンラインは敬遠し
てしまうただこれは筆者の考えであり一般的であるかは全く不明であることを強調し
ておく
42コムカモ
コムカモとは学内のバス停をネットワークカメラで常に撮影しその混雑状況をどこ
からでもすぐに把握できるようにすることで帰宅時間の分散をすすめバス利用を快適化
しようとするプロジェクトであるプライバシーなどの問題から現在カメラの設置には至
っておらず署名をあつめている段階であるその詳細な経緯や根拠の説明はここでは省く
中心になってこのプロジェクトを動かしていた杉山公一郎氏の卒業制作が詳しい
バス利用者は大学生にとどまらないため私は自分の交友関係を鑑み慶応義塾湘南藤
沢中高等部の生徒にこの署名をお願いしようと考えたしかしそれにはまずこのプロジ
ェクトについての意見をうかがう必要があった昨年度から中高等部とは何度かのやりと
りがあったようであるがおそらく末端の生徒は何も知らないと思い簡単な説明を行った
うえで意見をうかがったその結果得られた回答の要点は以下である回答者の属性は
6名全員が文化部で男性が3名女性が3名また中学生4名高校生2名である
①便利だとは思うが実際に利用することはまずないと思う
②友人にも利用すると思われる人はいない
③利用するならば携帯電話からの利用になる
①の意見が多かったことによって署名のお願いは断念した①の理由について意見
をまとめると以下のようになった
ア帰る時間が決まっていて選択の余地がない
イ友人同士での帰宅が多く並ばないことの重要性は少ない
ウ現在の混雑は理解できる範囲である
筆者が意見を聞いた中高生は帰る時間が基本的に決まっておりまたその結果人が集
中し混雑することを理解していたまたそれを仕方のないものだととらえていた各自の経
験等により各自の帰る時間が決まっていることも合わさってバス停の混雑する時間帯が頭
に入っているようであったつまりバス停混雑について現在ある程度の予測ができてお
りその結果混雑が想定されていてもその時間に帰宅しているのであるよって中高生の
多くはたとえコムカモで混雑していることが判明しても帰宅することが想像できるこ
れではコムカモの必要性は感じられないだろうしかし空いている時間に帰宅したいと
いうニーズはゼロではないと思うので実際に利用するかはともかく無いよりはあるほう
が便利は便利であるというスタンスで署名をお願いすればよいのではないかと考えている

行されておりその利用に抵抗がないこととバス停が細かく配置され自宅のすぐ近くにあ
ることが理由ある特に雨の日や日射しの強い日は徒歩距離の長いグリーンラインは敬遠し
てしまうただこれは筆者の考えであり一般的であるかは全く不明であることを強調し
ておく
42コムカモ
コムカモとは学内のバス停をネットワークカメラで常に撮影しその混雑状況をどこ
からでもすぐに把握できるようにすることで帰宅時間の分散をすすめバス利用を快適化
しようとするプロジェクトであるプライバシーなどの問題から現在カメラの設置には至
っておらず署名をあつめている段階であるその詳細な経緯や根拠の説明はここでは省く
中心になってこのプロジェクトを動かしていた杉山公一郎氏の卒業制作が詳しい
バス利用者は大学生にとどまらないため私は自分の交友関係を鑑み慶応義塾湘南藤
沢中高等部の生徒にこの署名をお願いしようと考えたしかしそれにはまずこのプロジ
ェクトについての意見をうかがう必要があった昨年度から中高等部とは何度かのやりと
りがあったようであるがおそらく末端の生徒は何も知らないと思い簡単な説明を行った
うえで意見をうかがったその結果得られた回答の要点は以下である回答者の属性は
6名全員が文化部で男性が3名女性が3名また中学生4名高校生2名である
①便利だとは思うが実際に利用することはまずないと思う
②友人にも利用すると思われる人はいない
③利用するならば携帯電話からの利用になる
①の意見が多かったことによって署名のお願いは断念した①の理由について意見
をまとめると以下のようになった
ア帰る時間が決まっていて選択の余地がない
イ友人同士での帰宅が多く並ばないことの重要性は少ない
ウ現在の混雑は理解できる範囲である
筆者が意見を聞いた中高生は帰る時間が基本的に決まっておりまたその結果人が集
中し混雑することを理解していたまたそれを仕方のないものだととらえていた各自の経
験等により各自の帰る時間が決まっていることも合わさってバス停の混雑する時間帯が頭
に入っているようであったつまりバス停混雑について現在ある程度の予測ができてお
りその結果混雑が想定されていてもその時間に帰宅しているのであるよって中高生の
多くはたとえコムカモで混雑していることが判明しても帰宅することが想像できるこ
れではコムカモの必要性は感じられないだろうしかし空いている時間に帰宅したいと
いうニーズはゼロではないと思うので実際に利用するかはともかく無いよりはあるほう
が便利は便利であるというスタンスで署名をお願いすればよいのではないかと考えている

多くはたとえコムカモで混雑していることが判明しても帰宅することが想像できるこ
れではコムカモの必要性は感じられないだろうしかし空いている時間に帰宅したいと
いうニーズはゼロではないと思うので実際に利用するかはともかく無いよりはあるほう
が便利は便利であるというスタンスで署名をお願いすればよいのではないかと考えている