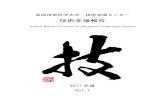医療のTQM推進協議会 - 外来から始める退院支援を!! · 2015. 10. 15. · 1...
Transcript of 医療のTQM推進協議会 - 外来から始める退院支援を!! · 2015. 10. 15. · 1...

1
外来から始める退院支援を!!
~多職種で取り組んだ患者さま目線の退院支援~
公立大阪法人 大阪市立大学医学附属病院 15階 西病棟 中西なかにし
麻美ま み
柴田 利彦(診療科部長)、中 麻里子、吉本 千鶴(師長)、関 則子(MSW)、上森 育代(医事課)
1 テーマの選定 私たちが勤務する 15階西病棟は、外科混合病棟であり、消化器・乳腺・内分泌・呼吸器・心臓血管外科で構成
されています。
消化器・乳腺・内分泌・呼吸器外科に関してはクリニカルパスに沿った経過をたどることが
ほとんどですが、心臓血管外科においては、手術による侵襲が大きく、また合併症が起きると
重症化するケースもあり、入院期間が一定ではありませんでした。
そこで、私たちメンバーは、看護師がより専門性を発揮できる退院支援について重要性を
感じ、外来から始める退院支援について見直したいと考え、今回このテーマに取り組むことに
しました。
2 活動計画
活動計画です。当初計画したスケジュールと実際の状況を比較すると、「対策の立案と実施」に予定より早くから取り
組んだことがわかります。これは、テーマ選定・現状把握の中で、今回の取り組みが多職種と連携したものであったた
め、多職種の方から様々なアイデアを収集することや、調整のための時間を長めに想定したことが主な理由です。
ステップ 担当 5月 10月 12月 1月 2月 3月
テーマ選定 中師長・中西
現状把握 中師長・中西上森
要因解析 全員
目標設定 全員
対策の立案と実施 全員
効果確認 中西
標準化と管理の定着 全員
反省と課題 全員
発表準備 全員
計画実践
看護師だからできる
退院支援の実現を目指そう!!

2
3 現状把握
経験年数の浅い看護師を中心に
構成されている病棟である
わかば(1年目)
13%
ラダー
レベルⅠ
21%
ラダー
レベルⅡ
33%
ラダーレベルⅢ
29%
ラダーレベルⅣ
4%
【現状把握①~病棟看護師の人員構成】
現状把握です。まず、現状把握の入口と
して病棟に所属する看護師の人員構成を
調べてみました。
その結果、「わかば」と呼ばれる 1年目の
看護師や、ラダーレベルⅠ・Ⅱの若手看護
師で全体の 7 割以上を占めていることがわ
かりました。
0 100 200 300
平成24年度
平成25年度
次に、平成 24 年度、25 年度における心
臓血管外科の手術件数を調べてみました。
手術件数は増加傾向にあり、その件数は
250件を超える状況となっています。
【現状把握②~心臓血管外科の手術件数】 手術件数は増加傾向にある
0
5
10
15
20
25
30
35
40
関
MSW
38件平成25年から心臓血管外科を担当しています
なかなか心臓血管外科の患者さまは転院調整が大変なんですよ
【現状把握③~平成25年度における心臓血管外科の転院調節件数】
手術後、順調な経過をたどった患者さま
も多くいらっしゃいますが、自宅へ退院する
ためのリハビリが必要な患者さま、合併症を
併発した患者さまには転院調整を行いま
す。平成 25 年度の転院調整数は 38 件に
のぼりました。
予後が不安な状態にある患者さまに
対する転院調整業務を行うMSWの
存在は、病棟において非常に重要な
役割を担っている
はい
41%いいえ
59%
Q1
退院支援の意味を
知っていますか?
はい
23%
指導をうけて実施した
77%
いいえ
0%
Q2
退院支援を実際に
行ったことはありますか?
N=22
【現状把握④~病棟看護師の退院支援認知度~】
退院支援とは「患者さまが、自分の病名
や障害を理解し、退院後どこで療養するの
か、どのような生活を送るのかを自己決定
するための支援」のことです。
15 西病棟の看護師が、退院支援につい
て理解できているのかアンケート調査したと
ころ、半数以上が理解できていませんでし
た。退院支援を実際行ったことがある看護
師は 2 割であり、指導を受け実施できたと
答えた看護師は 7割でした。
重要な退院支援業務について、看護師の認知度や習熟度が低いという事実が判明した。
対する転院調節業務を行うMSWの
存在は、病棟において非常に重要な
役割を担っている

3
3 現状把握
4 目標設定
これまで行ってきた現状把握から、以下のことが明らかになりました。
①15階西病棟は、経験年数の浅い看護師が 7割以上を占めている。
②心臓血管外科の手術件数は前年度に比べ増加傾向にある。
③心臓血管外科において転院調節は重要な業務であり、件数も他の病棟に比べても多い状況である。
④上記の状況であるにも関わらず、看護師の退院支援に関する業務認知度・知識は総じて低い。
⑤退院支援については必ずしも積極ではない看護師も存在する。
⑥一方では自分の担当患者さまに対しては、入院期間や退院・転院について感心を持っている。
そこで、今回の活動の目標を、
「すべての看護師が退院支援の意味を理解し、意欲的に取り組むことができる!」
「患者さまの在院日数を短縮する!」
に決定しました。
【現状把握⑤~看護師が退院支援を意識したタイミング~】
アンケートの結果を受け、ど
のような場面で退院支援を考
えたかとの問いを行いました。
入院時基礎情報聴取時や
手術後と、早期から関われてい
るスタッフもいましたが、患者さ
ま、家族、PTに聞かれてから、
と消極的な意見もありました。
ある
55%
ない
45%
Q4 担当患者の
入院期間に関心は?
ある
55%
どちらかと
言えばある
41%
どちらかと言えばない
4%
Q5 退院・転院に関心は?
N=22
【現状把握⑥~担当患者さまへの入院期間や退院・転院の関心~】
さらにアンケートを繰り返した
ところ、担当患者さまの入院期
間や退院・転院の時期につい
ては半数以上のスタッフが興
味を持っているということが判
明しました。
退院支援について
消極的な意見も見られた
自分の担当患者さまには
関心を持っているものの、
裏返せば、他の患者さま
には関心を持っていない
ということがわかった

4
4 要因解析
有効な退院支援ができていない要因を特性要因図で分析し、「看護師が退院支援に関わったことがない」、「多職種
カンファレンスに参加できていない」、「患者さまが医師からの説明を十分に理解できていない」という主要因を導き出し
ました。
5 対策の立案と実施
対策案を「外来からのMSWの関わり」「病棟会での勉強会の開催」「他職種カンファレンスの開催」と絞り込みました。
【表:特性要因図】
【表:対策の立案と評価】

5
5 対策の立案と実施
(1)MSWの外来受診時からの介入
(2)退院支援についての病棟での教育
Part1 MSWの外来からの介入
まず、1つ目の対策です。患者さまの外来初
診時に、外来主治医が患者さまにパンフレット
をお渡しし、医療ソーシャルワーカーの説明を
行います。
また、退院支援の取り組みについても外来で
説明を行い、患者さまに治療の流れを十分ご理
解していただきます。退院後、かかりつけ医を
持つことの必要性も説明しています。
その後、MSWとも面談を行い入院前からの
サポートが始まります。
医療経済ニュース
15西
No.1
「退院支援①」
大阪市立大学医学部附属病院は、
特定機能病院です。
高度先端医療を行う病院として機能しています。
平均在院日数26日以内、一般用病棟用の重症度・看護必要度15%以上を満たすことが要件となっています。
しかし、当院にはHCUがありますので、HCUの算定要件を満たすためには
一般病床が平均在院日数19日以内となります。
今後、市大病院が地域住民に対して高度な医療を提供していくためには、早期治癒を目指した医療・看護の提供及び亜急性期や回復期病院、在宅へのスムーズな移行が必要となります!!
Q:退院支援とは?A:患者が自分の病気や障害を理解し、退院後も継続が必要な医療や看護を受けながら、ど
こで療養するか、どのような生活を送るか自己決定するための支援
患者に安心でスムーズな退院支援を目指そう!
Q:退院調整とは?A:患者の自己決定を実現するために、患者・家族の意向を踏まえて環境・もの・人を社会保障制度や社会資源につなぐなどのマネジメントの過程
⇒退院調整は、MSWの役割が大きいところです。看護師には、MSWに患者の意向を伝え、患者が安心して転院・在宅につなげれるようMSWと患者の橋渡しの役割があるので
す。
病院側としては上記のような社会的背景もあり、早期の退院を進めていますが、患者側としてはどうでしょう?「急に、退院と言われても困る!!」「家に帰るのは不安」など医療者側だけで退院を進めていくと、患者・家族の不安感は強まりますよね。そこで、入院早期から患者と共に治療を終えてからの療養について考える事が必要になってくるのです。ここで、まず「退院支援」と「退院調整」の言葉の意味を知ろう♪
看護師が力を発揮できるところ!
患者が安心して次のステップに向かうためには何が必要かしら?
患者・家族と共に考えよう!
退院支援 退院調整
第1段階
•退院支援が必要な患者の把握
第2段階
•生活の場に帰るためのチームアプローチ
第3段階
•地域・社会資源との連携調整
•患者の意向 ・IC内容・看取りの場所
•治療後のADL状況の予測 ・医療技術習得の必要性患者に関すること
•家族の意向 ・主介護者の年齢理解度
•キーパーソン ・日中・夜間の家族の状況家族に関すること
•住宅環境(階段の有無・トイレ・浴室までの距離)
•患者の主に過ごす部屋 ・通院方法居住に関すること
•介護保険申請の必要性の有無 ・かかりつけ医の有無
•ケアマネージャーの有無 ・福祉サービスの必要性
保険・医療・福祉制度の利用に関すること
退院してからも患者が日常生活を不安なく過ごせるよう、患者目線にたった退院支援ができる看護師を目指そう~♪♪
入院時から退院支援は始まっています。あなたは聞けてる?
入院している患者としてではなく、生活者として捉えていますか?退院後の生活状況の想像が重要です!
入院時スクリーニング
多職種カンファレンス(方向性・退院
前)
入院前
退院後
退院支援のプロセスを知ろう!Part2
退院支援について
の教育
医療経済ニュース
15西
No.2
「退院支援②」
退院支援に関する評価表 中間評価結果
2.953.05
3.62.75
3.353.453
3.93.7
3.653.65
0 2 4 6
在宅療養指導管理料の入…
ケアマネージャーや訪問看…
MSWへの介入依頼ができる
家族状況・介護体制につい…
退院支援に関する評価表
中間評価 (平均値)
5:よくできた 4:できた 3:努力が必要 2:できていない
上記グラフは、退院支援に関する評価表の中間評価結果となります。
MSWへの介入依頼や加算は、15西病棟ではスタッフが実施していないことが多
いため平均値も低いことは仕方のないことですが、赤枠で示している項目について
は上昇が見込める項目と思いますので、「4:できた」を目指して頑張りましょ
う。
患者プロファイルの中に退院支援に関する情報を記載できる画面ができました。
入院時に情報収集していきましょう。
今後、退院支援に関するアナムネ用紙を作成しますので、活用して下さい。
情報収集をしっかり行い、退院支援が必要な患者さんであるか早期にアセスメントできるようにしていきましょう。
退院支援に関連する診療報酬について
退院支援の必要性を判断退院支援計画書の作成
*退院調整加算114日以内 340点30日以内 150点31日以上 50点
機能評価*総合評価加算 100点
*在宅療養指導管理料算定予定患者に対して
患者・家族への指導*在宅療養指導料 170点
試験外泊*退院前在宅療養指導管理料
120点
指導管理・必要な医療材料の供与*在宅療養指導管理料
一般病院自宅・居住系施
設など
退院支援計画の共有*地域連携計画加算 300点
ケアマネージャーとの連携*介護支援連携指導料 300点
退院前カンファレンス*退院時共同指導料1
*退院時共同指導料2 300点医師-医師 +300点医師-3者 +2000点
回復期リハビリテーション
病院
*診療情報提供料(1) 250点
転院先との連携*地域連携診療計画管理料
*地域連携診療計画退院時指導料
マークの診療報酬は、医師に依頼すれば算定できます。該当患者を受け持った場合は実施できるようにしましょう。算定方法は、退院支援関連ファイルを見てください。
どういう場合に算定可能なの?
・院内の医療関係職種がケアマネージャと協働して、患者に対して介護サービスなどの情報提供した場合に算定可。ケアマネージャーが来院したときのみ算定。電話のみでは不可。
・ケアマネージャーに情報提供を求める前に、患者の同意が必要。退院支援計画書を作成し、患者または家族のサインをもらう。
・行った指導の要点をカルテに記載すること。
ケアマネージャーとの連携*介護支援連携指導料 300点
の場合・・・
その他の診療報酬についての説明は別紙をご参照ください♪♪♪
2つ目は、病棟の主任看護師による教育です。上記のような資料を継続的に作成し、退院支援と退院調節の違
い、患者さま目線に立った退院支援についてスタッフ一人ひとりに伝達しました。
柴田診療科部長

6
(3)多職種カンファレンスの開催
6 効果の確認(1)~目標に対する効果~
3つ目は、多職種カンファレンスです。毎週火曜
日15時から、開催しています。
内容は、入院して1週間以内に行う、方向性カン
ファレンスです。MSW が入院前から関わっていま
すし、病棟看護師と情報を共有することで、手術後
どのような支援が必要となるかの把握が大変しやす
くなりました。
その後、手術後の患者さまを対象に退院支援カ
ンファレンスを行い、退院に向けた必要な情報を意
見交換し、スタッフへの指導の場ともなっています。
はい
48%
指導を受け
理解できた
52%
いいえ
0%
退院支援を理解できたか?
はい
33%
指導を受け実施した
62%
いいえ
5%
退院支援を実践できたか?
N=20 効果の確認です。まず、一つ目の目標であった「すべての看護師が退院支援の意味
を理解し、意欲的に取り組むことができる!」については、上表のとおりとなりました。
N=20
目標達成!
【表:目標設定(1)に関する看護師へのアンケート結果】
Part3
他職種カンファレンスの風景
毎週火曜日 15時から 15西ナースステーションで開催
外来で、介護保険の案内はしました
息子さんと同居していますが、不在が多いそうです
では、介護保険申請の進み具合を確認しておきます
手術後は、自宅退院と転院を視野にいれておきましょう
方向性カンファレンス
先日、入院してきた末広さんです

7
6 効果の確認(1)~目標に対する効果~
引き続き、効果の確認です。二つ目の目標であった「在院日数を減らす!」
についても、今回の取り組みの結果、前年より短縮されていることがわかります。
6 効果の確認(2)~波及効果~
【表:平均在院日数の前年比較】
目標達成!
また、副次的な効果として、心臓血管外科での手術件数は年々増加していますが、
転院調整件数も、倍のスピードで増加しています。これは今回、多職種が協力して取り
組んだ活動による波及効果の一つと考えます。
【表:転院調整件数の推移】
安心して治療が続けられますね♪

8
7 標準化と管理の定着
標準化と管理の定着です。今後は、3つの対策が定着できるよう取り組みを継続していきます。
8 反省と課題
反省と今後の課題は以上のとおりです。今回の取り組みで達成できなかった点を、今後の継続的な取り組みの中で
実現していきたいと考えます。
手術を受けられる患者さまはさまざまな不安を抱いています。安心して
治療を受けることができ、医療スタッフが統一した、退院支援に取り組むこ
とで、「大阪市大病院に入院してよかった」と思われる病院であるために、
病院が一丸となって今後もチャレンジを続けていきたいと考えます。
When Who What Why How
4月・9月 副主任 他職種カンファレンスの手順
定着させるために
手順の見直しを行う
定期的に 業務委員 患者用パンフレット 変更、修正があるため
見直し後修正
6月 主任 退院支援についての教育
退院支援が取り組めるように
学習会の開催
みんなでがんばりましょう!