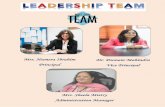MRS-J - FortheInterdisciplinaryMaterialsResearch Vol.31No...
Transcript of MRS-J - FortheInterdisciplinaryMaterialsResearch Vol.31No...

細ほそ
野の
秀ひで
雄お
東京工業大学教授
鈴すず
木き
淳あつ
史し
横浜国立大学教授
1
For the Interdisciplinary Materials ResearchVol.31 No.1 February 2019
発行 ©一般社団法人 日本MRS事務局〒231-0002 横浜市中区海岸通 3-9横浜ビル 507Dhttp://www.mrs-j.org/ Tel. 045-263-8538
日本MRS設立 30 周年記念国際会議 MRM2019 の開催について
組織委員長・東京工業大学教授 細ほそ
野の
秀ひで
雄お
事務局長・横浜国立大学教授 鈴すず
木き
淳あつ
史し
本年 12 月 10 日~14 日に、横浜シンポジア(横浜市中区山下町 2)とその周辺を会場として、上記の国際会議を開催することになり、準備を進めています。ここでは、この国際会議を開催するに至った背景、具体的内容と目指すものについて紹介させていただきます。材料研究は日本が国際的に強い分野の一つで、これまで世界に誇る素晴らしい成果を挙げてきたことは周知のとお
りです。しかしながら、昨今では他の分野と同様に、いろいろな評価の指標が急速に低下しつつあり、世界の中で存在感が薄れつつあります。この問題について、日本学術会議材料工学委員会(当時委員長:吉田豊信東大教授)は、新材料科学検討分科会を設置し、日本の材料系学会の現状と課題について 2年間にわたり議論してまいりました。その中で正会員数の急激な減少や海外会員が極めて少ない、論文誌で国際的に通用するものが殆どないなど、いろいろと深刻な問題があることが明らかになりました。これらの多くの課題の中で、直ぐに対処できるものはかなり限られています。そこで、できるところから着手しようということになりました。その最初の課題が、日本の材料研究はハイレベルで国際的に強いのに、国内で開催する大規模で広い材料分野を網羅した国際会議がないので、これを何とか立ち上げられないかということでした。そこで、分野横断型の材料研究を標榜している日本MRS の関係者と相談をしてご賛同を頂き、ここにMaterial Research Meeting(MRM)を開催することになった次第です。MRMは、材料研究が強い日本が主催する国際会議に相応しいものにしたいと思います。アカデミアだけではな
く、企業の研究者や技術者が本気で参加したくなるようなトピックスについてハイレベルの内容を発表し議論できる場を提供することを目指しています。もちろん、会議の構成は分野別の学会では難しい分野横断型といたします。会議の方式は、米国のMRSと同様なシンポジウム形式で、今回のMRM2019 では公募などでエントリーがあったシンポジウムの数は 36 に達しました。それらを分野横断型になるように表-1のように 9つのクラスターに分類し、クラスター内で自由に合同の企画ができるようにしました。もちろん、世界の Leading Scientists による全体講演のセッションを設けます。今回の特徴は、進行中の国家プロジェクトや科研費の新学術研究領域の中の物質・材料関連プロジェクトの全面的な協力を得て、その主題に関するシンポジウムが数多く含まれていることです。また、全く新しい組み合わせにより、これまでになかったコンゼプトのクラスターも提案しています。いずれも国際的に評価の高いテーマで、かつマテリアルズ・インフォマティックスなどホットなトピックスに加え、今や先端材料研究に不可欠になった放射光など大型研究施設の活用や先端計測などに役立つ基礎についてのシンポジウムも取り込み、関連分野と連携した魅力あるクラスターを設けています。各クラスターの構成は材料別ではなく機能を中心に据え、設計-創成-プロセスー解析という一連の材料研究に対して最新の情報が得られるようになっています。各シンポジウムのオーガナイザーの半数は海外の方とすることを開催条件にしており、国際的に存在感のある会議を目指しています。日本の物質・材料研究が世界の中で存在感を示す
ようになった経緯は、古くは本多光太郎先生の金属研究、そして 1980 年代のアモルファス水素化シリコンと銅酸化物高温超電導体の研究などが契機となっています。これらの研究には共通点があります。実用に対する大きな期待と、それを実現するための物理、化学、工学などの既存の分野を超えた学際的研究、そして厳しい国際競争です。これらの共通点は現在でも存在感のある材料研究には不可欠だと思います。この新しい国際会議が「さすがに日本が主催する物質・材料の会議だ。レベルとスコープが一味違う。」と海外からの参加者に感じさせたいものです。そして、日本のプレゼンスを世界に示し、海外の研究者がMRMに参加して発表したくなるような魅力ある会議にしたいと思います。昨今では大きな成果に繋がる国際共同研究の実施、科研費の新学術領域や科学技術振興機構(JST)の戦略創造研究に採択されるには、従来の狭い分野での連携では不十分で、分野横断の新しい連携が必要になってきています。このMRMをその機会と捉えて活用して頂きたいと思います。また、企業の方には米国のMRS に行かなくても、それと同等の最新で有益な情報がこの会議で得られるように企画しております。なお、MRM2019 の詳細については web site(https://mrm2019.jmru.org/)をご覧ください。これから随時更新されます。是非、ご参加とご支援のほど宜しくお願いいたします。
||||||||やあ こんにちは ||||||||
表-1 36 のシンポジウムを 9つにまとめたクラスター。各クラスターには 3~5のシンポジウムが属し、クラスターごとに合同セッションを開催するなどフレキシブルな運営を行う。
A.Fundamentals for MaterialsB.New Trend of Materials ResearchC.Novel Structural Materials Based on New PrinciplesD.Advanced Electronic MaterialsE.Magnet and SpintronicsF.EnergyG.Materials for Smart SystemsH.Green Technology and ProcessingI .Biopolymers

第 28 回日本MRS年次大会開催報告―循環型社会のためのマテリアルズイノベーション―
2018 年 12 月 18 日(火)~20 日(木) 北九州国際会議場・西日本総合展示場ほか福岡県北九州市小倉北区浅野 3-9-30
第 28 回 MRS-J 年次大会が本年は北九州市の共催のもと、12 月 18 日(火)~20 日(木)の会期で北九州国際会議場・西日本総合展示場・ミクニワールドスタジアム北九州で開催された。本年次大会では「循環型社会のためのマテリアルズイノベーション」というテーマのもと、領域・分野融合的な材料研究に関する情報・技術交換を行いながら、循環型社会のためのマテリアルズイノベーションにつなげることを目指して、27 のシンポジウム(国際シンポジウム 5 件)を開催した。その中で 1218 件の発表(610 件の口頭発表、608件のポスター発表)が行われ、参加者は約 1400 名にのぼった。今回は、参加者が一堂に会する特別講演、MRS-J の創設にご尽力された宗宮重行先生(1928~2018)の追悼シンポジウム、異分野の参加者が意見交換できるポスターセッション、七校の工業高等専門学校がある北部九州・山口の立地を生かした高専シンポジウム、若手研究者が参加しやすい雰囲気の懇親会を開催した。特別講演では無機材料、エネルギー政策、ソフトマテリアルに関連した 3名の著名な先生にご講演頂いた。12 月 18 日は神奈川工科大学名誉教授・MRS-J 前会長の伊熊泰郎先生の「ルチル型酸化チタン(001)面の表面X線回折と光触媒活性」という演題でご講演頂いた。応用が活発に展開されているルチル型酸化チタンの光触媒活性に(001)表面結晶構造が密接に関わっていることを放射光表面X線回折の結果に基づき解りやすく解説頂いた。12 月 19 日は北九州市環境局環境国際経済部地域エネルギー推進課政策係長・高丸司様に「北九州市の環境とエネルギー戦略について」という演題でご講演頂いた。北九州市の環境の歴史的な変遷と北九州市が力を注いでいる洋上風力発電を用いた再生エネルギーの事業化と将来展望について、さらに SDGs 先進未来都市づくりについて最近の動向について御紹介頂いた。最終日は東京大学大学院新領域創成科学研究科教授・ImPACTプログラムマネージャーの伊藤耕三先生により、「タフポリマーを実現する新規分子・材料設計コンセプト」という演題で講演頂いた。ImPACT 伊藤プログラムの研究成果の紹介としなやかなタフポリマーを用いたコンセプトカーの紹介、更にロタキサンを使った新規高分子材料の創製について最近の成果を御紹介頂いた。いずれも 120 名以上の参加者があり、領域・分野融合的な材料研究あるいは社会実装に極めて有意義な特別講演であった。懇親会は 12 月 19 日の 18:30 から隣接するミクニワールドスタジアム北九州 3F特別会議室/ビジネスラウンジで開催され、学生も含めて 150 名以上御参加頂いた。懇親会は松田直樹実行副委員長の司会で始まり、高原淳MRS-J 会長・組織委員長の挨拶、吉村昌弘元会長の乾杯のご挨拶で開宴し、内外の様々な分野の研究者・学生間で大いに話が弾んだ。会場では北九州観光コンベンション協会による地酒のサービスもあり大いに盛り上がった。予定の 1時間半があっという間に過ぎ、白谷正治実行委員長の締めの挨拶で閉会した。本年会をご支援してくださった北九州市、協賛・展示・広告をご快諾頂いた企業、また遠方からお越し頂いた参加者に深く感謝します(文責:組織委員長 高原 淳、実行委員長 白谷正治)。
日本MRS第 28 回年次大会奨励賞受賞者一覧 表彰委員会委員長 手嶋勝弥
*:国際シンポジウム▽A-1 先進機能性酸化物材料―作製プロセスおよび物性評価―Processing and characterization of advanced multi-functionaloxides
代表チェア 岡 伸人(近畿大)酸化物には強い電子相関に起因する多種多様な機能性を示す材料が豊富に存在し、次世代の電気・光学・磁気材料などとして注目されている。そこで本セッションでは、機能性酸化物分野の材
料研究において潜在的・顕在的な機能の高度性を見出すべく、活発な討論が行われた。発表件数は基調講演 1件、招待講演 10 件、一般講演 21 件、ポスター講演 43 件の合計 75 件であり、2 日間にわたり行われた。口頭発表の会場では基調講演 40 分、招待講演 25 分、一般講演 15 分の時間をとったが、質問時間が短く感じられるほど自由闊達な討論がなされた。初日には基調講演:岡島敏浩氏(九州シンクロトロン光研究セ
ンター)、招待講演:永村直佳氏(物材機構)及び内山裕士氏
MRS-J NEWS Vol.31 No.1 February 2019
2
A-1 増田彩花(近畿大)A-1 糸島 遼(岡山大)A-1 岩崎慎平(青山学院大)A-2 石井裕人(北大)A-3 安井伸太郎(東京工大)A-3 西岡大貴(東京理科大)B-1 中島達哉(東京ガス)B-1 David Samuel RIVERA
ROCABADO(九大)B-3 渡邉誠一朗(東京理科大)B-3 林あやね(上智大)B-4 土戸良高(東京工大)B-4 坂本 遼(九大)B-4 ジャベッド バーベール
(物材機構)B-4 田村紗也佳(東海大)B-5 岩間智紀(東北大)
B-5 李 相昊(東北大)B-5 梅澤雅和(東京理科大)C-1 市川知範(名大)C-1 青木健輔(千葉大)C-2 細井祐吾(名大)C-2 岩田直幸(名城大)C-3 榊原教貴(東大)C-3 原 尚志(九大)D-1 Pooreun SEO(九大)D-2 松下雄一郎(東京工大)D-2 望月泰英(東京工大)D-2 宮崎秀俊(名工大)D-2 藤井 進(大阪大)E-1 玉井奈々子(東大)E-1 鎗野目健二(東海大)E-1 陳 兆恒(東京理科大)E-1 尾﨑純也(山梨大)
E-2 松岡拓磨(三重大)E-2 山本雅貴(県立広島大)F-1 村上大樹(九大)F-2 江口 裕(京大)F-3 坂巻達記(九大)F-3 呉羽拓真(東大)F-3 伊藤希望(名工大)F-3 中西智亮(AGC)F-3 浅海雄太(大阪工大)F-4 安 潁俊(山梨大)F-5 Ajendra Kumar Vats
(九工大)F-6 松井秀介(信州大)F-7 濱口和馬(東大)F-7 永井薫子(九大)F-7 向井孝次(名大)F-7 橋本彩加(東京理科大)
F-7 杉原由季(東大)F-8 村本卓也(首都大東京)F-8 石谷 創(名工大)F-8 Soroush MEHDIZADEH
(山口大)F-8 原田美冬(山口大)F-9 眞弓皓一(東大)F-9 伊藤由実子(東京工大)F-9 鄭 朝鴻(九大)G-1 橋本 歩(石川高専)G-1 上條利夫(鶴岡高専)G-1 伊藤滋啓(鶴岡高専)G-1 阪口祐紀(奈良高専)G-2 井元誠志(和歌山高専)G-2 押木 守(長岡高専)G-2 八杉憲彰(和歌山高専)

(JASRI)により、シンクロトロン光を用いた物性評価法の最前線について情報が提供され、活発な質疑応答がなされた。初日、二日目にわたって、機能性酸化物のバルク、薄膜、ヘテロ構造、ナノ構造及びその作製プロセスに関して、植田和茂氏(九工大)、藤井達生氏(岡山大)、柳田剛氏(九大)、高瀬浩一氏(日大)、及び板垣奈穂氏(九大)による招待講演が行われた。さらに機能性酸化物材料を用いたデバイスやエネルギー分野への応用に関して、東脇正高氏(NICT)、湯浅雅賀氏(近畿大)、及び大島孝仁氏(佐賀大)による招待講演がなされ、示唆に富む問題意識や最新の研究成果について熱く語った。64 件の一般講演・ポスター講演では機能性酸化物特有の多様で優れた特性を示す研究成果が発表され、質の高い議論が展開された。近未来への先進的分野を支える新規機能を提案する内容も多かった。機能性酸化物をキーワードに分野横断的に議論し、高度機能性を探る「場」が提供されたと確信する。
▽A-2 特異なスピン構造から創発する物質の新しい性質と機能性Functional properties emergent from unusual spin structure inmaterials
代表チェア 吉田紘行(北大院)本シンポジウムでは電子の持つファンダメンタルな自由度であるスピンの織りなす特異なスピン状態およびそこから創発する新しい機能性について活発な討論が行われた。発表は招待講演 7件、オーラル 4 件、ポスター 7 件の合計 18 件で、2 日間にわたり行われた。招待講演では、遷移金属を含む酸化物や金属間化合物を対象として、幾何学的フラストレーションやスピン軌道相互作用、ジャロシンスキー守谷相互作用によるスピン液体状態、磁気多極子秩序、トポロジカルに保護されたスキルミオン格子、エントロピクス、秩序型ペロフスカイトにおける多彩な磁性をトピックとして詳細な発表と議論がなされた。更に、一般講演では学生を中心とした若い科学者による瑞々しい講演が行われ、シニアの研究者にとっても良い刺激となったと思う。初日午後のポスター発表では、相互作用の競合から生じる多彩な磁性やスピン軌道相互作用に由来する特異な物性、高温高圧合成・低温合成による新物質探索などについて幅広いトピックの講演があり、活発な議論が行われた。以上のように本シンポジウムでは、スピンの相関によって発現する特異なスピンテクスチャを実現する新規物質の合成、新研究手法開発、物性評価および先端的な機能性の開拓などのテーマについて時間をかけた深い議論が行われ、最近の進展について多くの知見を共有することができた。▽A-3 分極に由来する物性発現と新機能材料Polarization related ferroic properties and new functionalmaterials
代表チェア 樋口 透(東京理科大理)
本セッションでは誘電体酸化物および関連物質の作製と構造・機能評価ならびにその応用を視野に入れ、分極の視点から活発な討論が行われた。発表は招待講演 4 件、オーラル 14 件、ポスター 17 件の合計 35 件で、2 日間にわたり行われた。口頭発表の会場では、招待講演 30 分、一般講演 15 分と標準的な発表時間であったが、時間的に余裕のあるスケジュールであったため、突っ込んだ討論がなされていた。初日午後には、まず招待講演として東京理科大理の宮川宣明氏
が「光学式浮遊帯域溶融法による InGaZnO4 単結晶育成」と九大院の北條元氏が「Co 置換 BiFeO3 薄膜における電場印加による磁化反転」、一般講演としてイオン伝導や分極に起因した基礎物性およびナノイオニクスデバイスの研究発表が行われた。2日目午前には、招待講演として九工大院の堀部陽一氏が「遷
移金属酸化物の局所構造に由来したトポロジカルドメイン構造」、一般講演として構造的な視点から新規誘電体材料やドメイン構造に関する研究発表がなされた。2日目午後には、招待講演として大阪府大の森茂生氏が「相関
不規則系物質の構造と機能性」、一般講演として誘電体の新機能性に関する研究発表がなされた。その後のポスターセッションでは、誘電体酸化物薄膜の作製と
物性・応用に関する研究や各種元素やガスを置換した誘電体酸化物の構造相転移に関する新しい研究成果が示された。ポスター会場では、口頭発表を終えた全参加者が発表者と活発な議論が行われた。今回は、発表件数は 35 件であったが、発表者以外の聴講者も
多く、口頭発表の会場では立ち見が出るほどの大盛況であった。▽B-1 燃料電池用材料、デバイス、及びシステム設計によるラジカル・イノベーションへの試みChallenges to radical innovation by the design of field of fuelcell materials, devices and its systems
代表チェア 森 利之(物材機構)本セッションでは、グリーンイノベーションを達成するうえで
必要不可欠である燃料電池の研究開発を加速させる目的で、燃料電池用材料・デバイス及びシステム設計を視野に入れ、従来のコンセプト・価値とは連続性を持たない革新的取り組みを目指すための研究開発のありかたについて、活発な討論が行われた。発表はオーラル 28 件、ポスター 18 件の合計 46 件で、2 日間にわたり行われた。初日の講演で注目を集めたのは、東京ガスの中島達哉氏の「燃
料再生を搭載した二段化 SOFC システムの開発と実証」という講演内容であり、高効率燃料電池システムの社会実装化に関する研究開発成果が発表されたこととに加え、自然科学研究機構分子科学研究所の小林玄器研究員が、現在、各方面において、注目をあつめているヒドリド(H-)に関する発表として「アニオン欠陥の無秩序化に伴う Sr2LiH3O の H- 超イオン導電性」に関する講演であったと思われる。このように、イオン伝導の基礎的現象に関する研究から、燃料電池システムの高効率化に関する研究開発成果発表まで、通常の学会発表では、同一の会場で議論を交わすことがない研究開発課題について意見交換がなされたことは、有意義であったと思われる。2日目の講演では、物材機構のDavid Samuel RIVERA ROCA-
BADO 博士の「Theoretical Study of SnO2 as Support Materialfor Polymer Electrolyte Fuel Cell Electrocatalyst」と題する発表が注目を集め、電極と酸化物サポート界面における電荷移動現象の解釈に関し、理論の面から整理された考えが提案されたこと
MRS-J NEWS Vol.31 No.1 February 2019
3

は、今後のこうした分野の発展に大きな影響を与えるとの期待を感じさせる内容であったと思う。その他 2日目の午後におけるポスター発表においても、若手研究者の意欲的な取り組みに関する発表が多数みられ、日本MRSの年次大会を通して交わされた意見交換のなかから、新たな革新的取り組みが生まれる予感を強く抱かせる活発なシンポジウムが開催できたと思う。▽B-2 価数転移を示す強相関電子材料の電子・光機能Electronic and optical functions in strongly correlated materi-als with change of the valence state
代表チェア 沖本洋一(東工大)本セッションは、主として遷移金属化合物を中心に、遷移金属の示す価数の変化が引き起こす興味深い磁性・誘電現象を中心トピックスとして、新物質合成から最先端光源を駆使した研究まで最先端の研究成果が発表、議論された。発表件数は基調講演が 1件、招待講演 8 件、一般講演 5 件、ポスター講演 4 件の計 18 件で、2日間にわたり行われた。シンポジウム初日は、最初に東京理科大の斎藤智彦氏よりLaCoO3 結晶における 3価のコバルトイオンの示すスピンクロスオーバー現象の歴史的経緯も含んだレビューがなされ、次に東京医大の小林義彦氏により、高輝度光源を用いたコンプトン散乱からみたスピン転移に伴う d 軌道の変化とそのイメージングについて詳細な議論がなされた。次に、東北大の富安啓輔氏から、非弾性 X線散乱の結果から見た LaCoO3 のスピンクロスオーバー研究の発表がなされ、また慶応大の杉山晴紀氏より錯体配位子場を持つ新しいコバルト系スピンクロスオーバー現象の報告がなされた。シンポジウム前半では、これらの発表を踏まえスピンクロスオーバー現象の起源に関する集中的な議論が行われた。本シンポジウムの基調講演は岡山大の池田直氏によって行われ、氏によって発見された鉄イオンの整列によって起きる電子強誘電体(LuFe2O4)についてのレビューがなされた。それとともに、最近の中性子散乱と非線形光学測定から提唱された電荷整列モデルの説明がなされ、強相関電子材料としての電子強誘電体の起源と今後の展望が提示された有意義な講演となった。更に名工大の漆原大典氏から、Tmイオンを含む新しい電子強誘電酸化物の発表がなされ、電子線散乱からみた結晶構造の対称性と電子強誘電性の関連について基調講演を踏まえた議論がなされた。東工大の石川忠彦氏は、Fe イオンを含む有機無機ハイブリッド結晶におけるスピンクロスオーバー現象について報告し、光によるスピンクロスオーバー転移を赤外分光の立場から論じた。2 日目は、物材機構の辻本吉廣氏により Zn を含む新型強誘電体の合成に関する発表が行われ、従来の強誘電体より大きな第二
次高調波発生を示すことが報告された。また名大の谷口博基氏からは、不純物のドープにより酸化アルミニウムの誘電率とその寿命が光照射によって大きく制御できることが示され、その起源についての報告があった。当日は多数の聴講者が本シンポジウム会場を訪れ、会場はほぼ
満席となり、本シンポジウムに関する様々なテーマに議論を深めることができ有意義なシンポジウムとなったと考える。▽B-3 暮らしを豊かにする材料―環境・エネルギー・医療―Materials for living-environment・energy・living-
代表チェア 小松隆一(山口大工)本セッションでは環境のための素材、新エネルギーや省エネル
ギーのための材料、医療・福祉のための生体材料など暮らしを支える材料に関する研究開発の視点から活発な討論が行われた。発表は、ポスター 20 件、招待講演 2 件、オーラル 10 件の合計 32件が行われた。初日午後のポスターセッションでは、会場では積極的な議論がなされたが、特に学生による躍進が目立った。2日目の口頭発表の会場では、一般講演は 15 分で実施され、会場からは積極的に質問が挙がった。一昨年度のシンポジウム(第 26回)に比べて、口頭発表で発表する人数が少なかったため、発表はアットホームな雰囲気の中行われた。まず、午前中は、磁性材料、触媒材料、生体材料について 7件の報告があり、そのうち 1件は招待講演として九工大の宮崎敏樹氏によるセラミックスの有機修飾による新規バイオマテリアルの特徴についての説明があった。午後からは、本同宏成氏の招待講演により、食品を作る上での油脂の結晶成長の重要性について説明があった。本同氏の狭い温度領域内で複雑に進行する融液成長のその場観察動画は多くの聴衆を魅了していた。続いて 6件の発表では、主として触媒や圧電材料、セメント材料などの新規材料の生成機構に関する報告がなされた。▽B-4 環境・エネルギー物質、デバイス、プロセスEnvironmental and energy materials, devices and process
代表チェア 小坂田耕太郎(東工大化生研)二日目に行われた本シンポジウムでは、環境及びエネルギー問
題の解決を志向した物質、デバイスに関する 87 件(口頭 21 件、ポスター 66 件)が発表された。研究内容は基礎物理から触媒、半導体、電子機器、電池、医療、など広い分野にわたるものであった。新規性、発展性にすぐれた発表のうち、特に以下の 5件を紹介
したい。阪大産研・小林悠輝氏は「シリコン成分剤による体内水素発生と酸化ストレス性疾病の防止」において、高純度シリコンを製剤化し、慢性腎不全やパーキンソン病の予防医薬として用いる研究について発表した。東工大化生研・神戸徹也氏による「典型金属集積デンドリマーによる超原子合成」では、単一原子と類似の電子状態をもつ金属クラスターを新概念によって合成した成果が発表された。東北大多元研・高橋正彦氏による「ネットワーク型共同研究拠点・アライアンスと横串活動」では、最新の理論、測定手法を多彩な共同研究に活かしていく、組織的な活動の現状と今後の可能性が紹介された。北大電子研・石橋晃氏は、「フォノン・フォトンキャリア直交型マルチストライプ太陽電池の導波路結合応用」と題し、新しい光エネルギーの高効率利用についての概念と研究成果を発表した。これら発表内容について、参加者による活発な討論が行われた。ポスターにも、若手を含めて多くの研究者が参加した。坂本遼氏(九大先導研)による「DSC 測定および EPSR 計算による濃厚NaClO4 水系電解液の局所構造解析」では、水溶液系ながら広い電位窓をもつ次世代電池
MRS-J NEWS Vol.31 No.1 February 2019
4
岡山大・池田直氏(左)、B-2 のポスター会場

用濃厚電解液の動作機構が紹介され、多数の聴講者から質問を受けていた。本シンポジウムは電子研、多元研、化生研、産研、先導研が構成する共同研究事業「ダイナミックアライアンス」(http://alliance.tagen.tohoku.ac.jp/)の、環境エネルギー、物質・デバイス・プロセスグループメンバーが中心となる形で企画され、同グループメンバーの研究発表と一般からの応募研究発表によって、幅広い視点をもつ参加者が集まった。このような理由もあって、複数機関による国内共同研究(28 件)、海外機関との共同研究(5 件)、英語発表(7 件)が多く、特徴あるシンポジウムとなった。
大会初日夜のB-4 セッション懇親会 Restaurant & Bar AJO
大会 2日目午前のB-4 ポスターセッション 北九州国際会議場イベントホール
▽B-5 スマート社会・スマートライフのためのバイオセンサ・バイオ燃料電池Biosensors and biofuel cells for smart community and smart life
代表チェア 四反田 功(東京理科大)スマート社会・スマートライフに関連する領域はここ数年で研究の進展が目覚ましく、注目度を増している。生体とデジタルのインターフェイス、すなわち生体情報の高感度ケミカルセンシングデバイス、およびそれに最適なウェアラブル電源の開発に関しては材料科学のみならず、電気化学、生物工学、応用物理学の学際的融合領域であり、異分野間のスムーズな連携がその発展に必須といえる。こうした状況において、本セッションは本大会より新たに立ち上げた。発表はキーノート講演(40 分)3件、招待講演(20 分)19 件、オーラル(15 分)14 件、ポスター 21 件の合計 57 件で、2 日間にわたり様々な視点からの活発な討論が行われた。初日午前はキーノート講演として山形大の時任静士教授による「フレキシブル・プリンテッド有機エレクトロニクスの研究開発と IoT センサ応用」から開始した。続いて 3件の新規バイオデバイスに関する招待講演、4件の酵素工学に関する招待講演が発表された。午後には、元ソニーの酒井秀樹氏による「実用化を目指したバイオ
電池の研究開発」と題したキーノート講演、7件のデバイスの設計や材料に関する招待講演が行われた。2日目には、ノースカロライナ大チャペルヒル校・早出広司教授による「未来のスマートバイオセンシングを志向する生命分子エンジニアリング」と題するキーノート講演で始まり、2件の招待講演ののち、ポスター発表があった。午後には 3件の招待講演に引き続き、一般および学生の講演となった。会場には常時 70~100 名程度の聴衆を集め、最後まで活気のあ
る質の高いディスカッションが行われた。なお、開催後のアンケートでも、大変好評で来年度以降も開催することを希望する声が多数あった。当初の予想よりも多くの講演件数が集まり、講演時間および休憩時間が十分にとれなかったことが反省点である。協賛企業(11 社)にもこの場を借りて御礼申し上げる。▽C-1 カーボンナノマテリアル研究の最前線Frontier of carbon nano materials
代表チェア 青木伸之(千葉大院工)本セッションではフラーレンを含むカーボン系ナノマテリアル
の構造・機能評価ならびに応用を視野に入れた広範囲にわたる研究成果が発表された。発表は招待講演 1件を含むオーラル 22 件、ポスター 16 件の合計 38 件と、大変ありがたいことに昨年度に比べて 2倍以上の発表件数となった。今回は午後の始めに特別講演があったため、22 件の口頭発表は少々タイトなスケジュールであったが、皆様のご協力のもと時間を大幅に押すことなくプログラムを進行することができた。比較的小さな会場であったが、座席数を上回る聴講者に参加いただき、活発な討議が行われた。午前の前半のセッションではダイヤモンドとフラーレルに関す
る発表を中心に行われた。そのセッションの最後では韓国・三育大学のKo 教授を招待者として招き、フラーレンナノウィスカーの触媒応用に関する講演をいただいた。前半の中盤のセッションでは、メソポーラスカーボンやマリモカーボンのキャパシタ応用に関する講演が、午前の後半にはカーボンナノウォールに関する話題を中心に講演が行われた。午後は主にカーボンナノチューブの研究を中心に発表が行われた。また、今回シンポジウムではナノダイヤモンドやグラフェンを利用したがん治療等の医用応用に関する発表もいただき、カーボンナノマテリアルのポテンシャルの高さを改めて実感させられた。発表会場には常時 30 名近い聴講者が確認され、講演時間いっぱいまで有意義な議論がなされていた。16:20 からのポスターセッションでは 16 件の発表があり、主に学生による発表が多かったため、奨励賞の審査も相まって、活発な議論が行われていた。今回は海外からの発表申し込みが招待講演を含めて 5件あり、次回からは国際シンポジウムとして開催するのが良いかと思われる。
▽C-2 プラズマライフサイエンスPlasma lifescience
MRS-J NEWS Vol.31 No.1 February 2019
5

代表チェア 古閑一憲(九大システム情報)本シンポジウムは近年注目を集めている低温プラズマ技術のバイオ工学、医療、環境応用、農業、製薬などへの応用いわゆるプラズマライフサイエンスの基礎と応用に焦点を当て国際セッションとして開催された。発表は、基調講演 4 件、招待講演 12 件、一般講演 10 件、ポスター 19 件の合計 35 件で、3 日間にわたり活発な議論が行われた。初日午前には、まず基調講演として韓国 Kwangowoon Univ.
の Gyungwoon Park 教授が「Plasma Application to MicrobialCell Differentiation and Inactivation」として、プラズマ照射による細胞の活性や分化制御に関する最新の研究成果を講演された。2 件目の基調講演は初日午後に、九大の山西陽子教授が「Inves-tigation of Plasma-induced Bubble Metallization」というタイトルで、細胞加工などへ応用展開されているプラズマ誘起場高速気泡に関する研究について紹介された。3 件目の基調講演は、2 日目午前に、東北大の金子俊郎教授が「Short-Lived Reactive Spe-cies Enhancing Cell Membrane Transport in Gas-Liquid Interfa-cial Plasmas」というタイトルで、従来技術に比べてプラズマでは特異的に高濃度で照射可能な活性種のうち短寿命活性種の細胞膜透過に関する研究成果について講演された。4件目の基調講演は大阪大の北野勝久准教授でタイトルは「Application of peroxy-nitric acid in plasma-treated water for safe and effectivedisinfection」である。北野准教授により見出されたプラズマ処理水における過硝酸の殺菌利用に関する研究成果を講演された。その他にもプラズマの基礎研究から農業応用に至るまで広範囲の研究成果が発表され質の高い討論が行われた。▽C-3* 先端プラズマ技術が拓くナノマテリアルズフロンティアFrontier of nano-materials based on advanced plasma technolo-gies
代表チェア 金子俊郎(東北大院工)本セッションは、先端プラズマプロセスにおけるサブサーフェス反応の計測・制御、新機能ナノ材料の合成、ナノ構造制御法とナノ構造による新物性の発現等に関する最新の成果を議論することを目的として、基調講演 4 件、招待講演 19 件、一般講演(オーラルおよびポスター)30 件、合計 53 件の発表・討論が 3日間にわたり行われた。初日の 18 日午前には基調講演として、Kwang-Ryeol Lee 氏
(Korea Inst. Sci. Technol.)から「Computational Research ofSurface Phenomena」の題目で、酒井道氏(滋賀県立大)から「プラズマ化学におけるウェブ上ネットワークとそのプラズマナノサイエンスのための理解」の題目で発表があり、プラズマプロセスにおける計算科学の重要性をアピールされた。午後の基調講演では、板垣奈穂氏(九大)が「逆 SKモードを利用した超高品質スパッタエピタキシー―格子整合条件を超えて単結晶成長を実現する―」の題目で発表され、高品質酸化物薄膜を高格子不整合基板上に作製できることを示された。3 日目の 20 日午前の基調講演では、平松美根男氏(名城大)が「カーボンナノ構造体のプラズマプロセシング」の題目で、プラズマ支援化学気相堆積法(PECVD)によるカーボンナノウォールを中心としたナノカーボンの位置制御高品質合成について発表された。招待講演では、種々の大気圧および低圧下のプラズマプロセスによる金属や半導体のナノ粒子・ナノロッド合成、構造制御されたグラフェン、カーボンナノチューブ、カーボンナノコイル等のナノカーボン合成、さらにはこれらの太陽電池、光電子デバイスへの応用、トライボロジーへの活用など、多彩な発表がなされた。口頭講演では
常に 30 人以上の聴講者がおり、ポスター講演でも多くの参加者により、非常に活発なディスカッションが行われた。▽D-1* イオンビームを利用した革新的材料創製Innovative material technologies utilizing ion beams
代表チェア 雨倉 宏(物材機構)本シンポジウムは国際シンポジウム(Official 言語:英語)と
して開催された。12 月 18 日と 19 日の 2 日間にわたりイオンビーム技術を利用した新材料合成、材料改質、構造及び特性の制御、計測・評価技術等に関する研究発表と活発な討論が行われた。招待講演 6 件(うち 2 件が中国、1 件が米国からの参加)、一般口頭講演 10 件、ポスター発表 13 件の合計 29 件で、一般講演者として中国から 4名、アルジェリアから 2名、また日本の大学等に所属する外国人講演者も数名参加した。招待講演は、吉岡聡氏(九大)「イオンビームに誘起された欠
陥構造の X 線吸収分光及び第一原理スペクトル計算による解析」、石丸学氏(九工大)「ナノ構造とアモルファス材料における耐照射性の透過電子顕微鏡法による解析」、F. Chen 氏(山東大)「Embedded metallic nanoparticles in dielectric crystals by ionimplantation for generation of laser pulses」, D. Ila 氏(Fayette-ville State Univ., USA)「Fabrication of nano- to micro-optical-structures in silica」, X. Ou 氏(SIMIT、中国)「Universal “Ion-cut” for nanopatterning, modification and heterointegration ofsemiconductors」,吉武剛氏(九大)「同軸型アークプラズマ堆積法による超ナノ微結晶ダイヤモンド膜の作製とハードコーティングへの応用」、であった。
▽D-2 計算機シミュレーションによる先端材料の解析・機能創成Creation and characterization of advanced materials throughcomputer simulation
代表チェア 吉矢真人(大阪大工)本シンポジウムでは電子・原子レベルから結晶粒レベルの多様
な計算材料科学的手法を対象とし、様々な材料のアプリケーションに関する大局的な議論から基礎的理論に関する詳細な議論まで、分野横断的な活発な討論がなされた。初日には、田村亮先生(物材機構/東大)、横井達矢先生(名
MRS-J NEWS Vol.31 No.1 February 2019
6

大)、小野頌太先生(岐阜大)による 3 件の招待講演をはじめとし、21 件の口頭発表、2 日目には、東後篤史先生(京大)、吉田大輔先生(Academia Sinica、台湾)、合田義弘先生(東工大)による 3件の招待講演をはじめに、11 件の口頭発表と 20 件のポスター発表がなされた。口頭発表並びにポスター発表も非常に盛況で、口頭発表及びポスター発表双方では休憩時間を削りつつ時間一杯、横断的かつ深い活発な議論がなされた。口頭発表ではほぼすべての座席が埋め尽くされるのみならず立ち見まで生じ、時折、立ち見の場所すらなく一度部屋から出たら部屋に戻れぬほどであった。奨励賞受賞候補となる学生や若手研究者の発表の質が全ての面で高く、競争は激烈を極め、受賞を逃した方々にも十分に受賞に資する発表をされた方々が少なからずみられた。審査には発表形式によらず同一基準を用いたが、高得点者と発表形式との相関は見られず、発表形式を問わずシンポジウム全体の議論の活発さを裏づけることとなった。
▽E-1 マテリアルズ・フロンティアMaterials frontier
代表チェア 伊藤 建(東海大理)本シンポジウムでは金属、セラミックスなどの無機材料および生体・合成ポリマーなどの有機材料とそれらの複合材料に関して、新しい合成方法、加工方法、優れた特性を有する材料の開発や実用化への展開について、合成や物性、機能の視点から活発な討論が行われた。今回の発表件数は、招待講演 3件、一般口頭発表 20 件、ポスター 30 件の合計 53 件となり、二日間にわたり活気ある討論が行われた。二日目の口頭発表では招待講演として、東海大の小口真一氏による「イオン液体を用いた再利用可能な酸化反応系の構築」と題した講演があり、イオン液体の一般的性質および実験での抽出挙動の特徴が述べられ、それらを巧みに利用した独自のイオン液体の合成と酸化反応系の例が示された。続いて、九大の安田琢麿氏による「発光材料・デバイス設計の新パラダイム」と題した講演では、有機物を利用した発光材料(有機 EL材料)の発展の歴史を紐解きながら、革新的な設計指針に基づく種々の発光材料の合成と優れた特性が紹介された。さらに、広島大の定金正洋氏による「Preyssler 型リンタングステートの精密設計とウイルス染色剤への応用」と題した講演では、電子顕微鏡によるウィルスの観察には欠かせない染色剤として、従来のものを凌ぐ性能を示し商品化もされている Preyssler 型リンタングステートの開発について報告がなされた。一般口頭発表では質疑応答を含めて 15 分と時間が限られていたが、新しい有機材料、無機材料、および有機-無機複合材料など様々な材料創製、およびそれらの電子機能、光機能、生体機能など種々の機能と応用研究に関する発表がなされ、異分野の発表者・聴講者の間で質の高い議論がなされた。一方、初日の午後に行われたポスター発表では、マテリアルを
キーワードとして、高分子材料、イオン液体、バイオ材料、クラスター錯体、光触媒、太陽電池、磁性体、電子材料、ナノ材料など多岐にわたる分野の研究者、学生が一同に会した。約 2時間の限られた発表時間ではあったが、活発な討論が展開された。「マテリアルズ・フロンティア」のシンポジウム名にふさわしく、有意義な異分野交流の場を提供できたと思われる。▽E-2 エコものづくりセクションEco products session
代表チェア 岡部敏弘(芝浦工大)本セッションではバイオマス利用を中心とし、バイオマス資源
外の材料も視野に取り入れ、エコプロダクトの多分野にわたり横断的な討議が行われた。発表は招待講演 4 件、オーラル 15 件、ポスター 25 件の合計 44 件で、2 日間にわたり行われた。口頭発表の会場では一般講演 15 分の中で、盛んに討論がなされた。初日午前には、一般講演 4件の後に、招待講演として関東職能
開発大の渡邉信公氏による「雷にまつわる技術開発と変遷」、一般講演 3件の後に招待講演として株式会社アルフアの北村新比古氏による「大江戸の暮らしとリサイクル」と多岐にわたる研究成果ならびに適用事例等が発表された。初日午後はポスターセッションに会場を変え、25 件のポスター発表の前で個々の研究に対して活発な質疑応答が行われた。2日目午前に 9件の一般講演の後、山口大の合田公一氏による
招待講演「セルロース系材料の力学的特性発現性と実用化動向」、午後に 2件の一般講演の後、招待講演として明星大の吉澤秀治氏による「廃菌床の新たなリサイクル法の開発」、さらに 6 件の一般講演により、今回のすべての講演が発表された。いずれの講演も質疑応答では発表者と質問者の双方の研究に資するディスカッションが行われた。
▽E-3 新しい多価値循環のための材料の信頼性・修復技術Technology of materials’ reliability and repairing for a newcirculation society
代表チェア 村上秀之(物材機構)資源の有効活用が叫ばれている昨今、機材や部品、それに用い
られている材料を再利用する循環社会を構築することは材料研究者の夢でもある。すなわち、リマニュファクチャリング、リファービッシュ、リペアを可能とする技術開発が求められている。その際「カギ」となるのは修復技術と信頼性の評価技術であり、本シンポジウムでは上記トピックに関心のある研究者に集まって頂き、各々の専門分野の観点から循環社会構築にどう貢献できるかについて議論を行った。発表は循環社会の重要性を説く物材機構・原田幸明氏の基調講演に始まり、リマニュファクチャリング社会構築を目指した研究プロジェクトの紹介、それらを実現させるための信頼性評価技術や修復技術の紹介といったシンポジウムの本線といったものから、建築構造物リサイクルにおけるアスベスト無毒化技術、自己治癒セラミックスの寿命評価や新規
MRS-J NEWS Vol.31 No.1 February 2019
7

自己治癒機構の解明。熱電材料における信頼性評価、更にこれら循環社会に貢献する所謂エコ材料のデータベース化と多岐にわたり、上述したように様々な視点から循環社会を考える実り多いシンポジウムであった。会場は終始和やかな雰囲気に包まれ、休憩時間、シンポジウム後の懇親会でも活発な質疑応答が続いた。異分野からの視点は今後の研究にとって新しいアイディアを頂くことも多く、懇親会では今後とも継続すべきだということで意見が一致した。▽F-1* 界面におけるナノバイオテクノロジーNano-biotechnology on interfaces
代表チェア 田中 賢(九大)本セッションは「界面」、「バイオテクノロジー」および「ナノテクノロジー」をキーワードとして、産総研・松田直樹先生の発案で、未来の医療工学やバイオ関連デバイスに関連する分野開拓を目指す方向性を示し、新材料、界面その場観察方法、細胞チップ、バイオエレクトロニクス、表面修飾などを対象とする研究発表が行われてきた。今回、発表は口頭発表 14 件、ポスター発表10 件の合計 24 件であった。口頭発表は通常の学会発表よりは時間を長めに確保することで、活発な討論につながった。また、本セッションは国際シンポジウムであり発表は英語で行われているため、例年通り留学生や外国人ポスドクの参加も多かった。今回はいつもの横浜を離れて九州開催とのことで、12 月 19 日のポスター発表の前に外国人招待講演者、セッションオーガナイザーを始め総勢 9名で TOTO(株)の小倉工場及びTOTOミュージアムを見学し(写真)、日常生活に関して非常に貴重な水回りの技術や歴史に触れる貴重な機会を得た。12 月 19 日午後にポスター発表を行った。学生を中心とした発表で有意義な議論が行われた。毎年、学生を中心とする発表者のプレゼン能力が向上しているように感じられ、オーガナイザー一同にとってもうれしいことであった。12 月 20 日午前、最初は奨励賞候補の若手による 5件の発表から開始された。本年は特に英語での発表技術の向上が顕著に認められ、成果や内容とともに非常に素晴らしい発表であった。本年も 2 名の外国人招待講演者の Shaoyi Jiang 先生(ワシントン大学、USA)から「Recent Advances in Zwitterionic Mate-rials」、及びMark A. Birch 先生(ケンブリッジ大学、UK)から「Understanding how implanted biomaterials influence the
surrounding repair environment」というタイトルで基調講演が行われ、最新のバイオ・医療技術に関する研究成果が示された。その他も新規な研究成果が報告され、午前中には発表者も加えると最大 40 名が参加し立ち見も出るという、本セッション始まって以来の大盛況であった。非常に活発な議論が繰り返され、これからもバイオ・医療分野だけでなく、ソフトエレクトロニクス、ロボティクス、エネルギー分野で必要となる多機能材料の表面・界面設計にかかわる本分野が重要であることが再確認された。最後にセッション懇親会を行い本年も盛会の裡に終了できた。▽F-2 ソフトマテリアルによるスマートトライボロジーへの新展開New development of smart tribology by soft materials
代表チェア 松川公洋(科学技術振興機構)本セッションでは、濃厚ポリマーブラシ、膨潤ゲル、高分子多
孔体などのソフトマテリアルによる表面処理とそれらの低摩擦材料への応用、さらなる高性能を伴うスマートトライボロジーへの展開についての議論を行われた。発表は基調講演 1件、招待講演4件、一般講演 10 件、ポスター 18 件の合計 33 件で、2日間にわたり行われた。初日午後のポスターセッションでは、ソフトマテリアルの合
成、それらの表面処理、摩擦特性について、幅広い研究成果が発表された。1 時間 50 分のポスター掲示時間であったが、各ポスターで熱心な議論がなされ、とても短く感じられた。2日目は、招待講演 30 分、一般講演 20 分の口頭発表で、比較
的時間的に余裕もあり、深い討論がなされた。最初に、基調講演として、京大化研の辻井敬亘氏が「“SRT”システム構築に向けた濃厚ポリマーブラシに関する研究開発」について、JST AC-CEL プログラムの紹介とトライボロジーへの最近の取り組みを述べられた。午前中に 2件の招待講演があり、九大の高原淳氏が「ポリマーブラシ固定化表面の良溶媒中における摩擦特性」と題する講演で、ポリマーブラシの幅広い応用について熱く語られた。午前中のもう 1件の招待講演として、九工大の松田健次氏が「規則性凹凸面が全面接触に至るまでの真実接触面積の追跡」を講演され、トライボロジーに大きく関与する凹凸面の特性について、深く議論できた。午後の招待講演では、宇宙航空研究開発機構(JAXA)の塩見
裕氏の「宇宙機用機構要素のトライボロジー的課題とソフトマターへの期待」と題する講演で、宇宙用途における低摩擦材料の現状とソフトマテリアルに期待について多角的に紹介された。最後の招待講演として、兵庫県立大の鷲津仁志氏が「ソフトマター界面におけるトライボ分子シミュレーション」について興味深い講演をされ、シンポジウム参加者と質の高いディスカッションが行われた。これら 4件の招待講演の間にプログラムされた一般講演では、最新の研究成果が発表され、活発な討論で盛り上がった。シンポジウム後に、発表者を中心にした懇親会を会場近くで開催し、トライボロジー関連の研究者の交流を楽しんだ。▽F-3 先導的スマートインターフェイスの確立Frontier of smart-interfaces
代表チェア 三浦佳子(九大)本セッションではあらゆるマテリアルを機能させるうえで重要
となる界面に着目し「先導的スマートインターフェイスの確立」を目指したバイオや材料、高分子に関連する研究発表が行われ、活発な議論が行われた。発表は基調講演 1 件、招待講演 4 件、オーラル 25 件、ポスター 39 件の合計 69 件で、2 日間にわたり行われた。口頭発表の会場では一般講演は 15 分と比較的時間の
MRS-J NEWS Vol.31 No.1 February 2019
8

余裕があったが、発表それぞれで深い議論がなされ、議論は休憩時間にまで持ち越すほどであった。初日午後には、基調講演として北九州市立大の櫻井和朗氏が
「DDS 用ナノメディシンの特性評価」と題し、ドラッグデリバリーシステムに利用可能な担体の構造解析の重要さとその精密な手法についてご講演頂いた。招待講演としては初日に山形大の干場隆志氏が「細胞培養中のバイオ界面リモデリング現象を利用して作製したバイオミメティック材料」、九大の井藤彰氏が「機能性磁性ナノ材料の開発と医療応用」、二日目には東大の久代京一郎氏が「トポグラフィーインターフェイスと勾配を組み合わせたがん細胞移動操作」、東工大の澤田敏樹氏が「繊維状ウイルスからなる階層的な集合体の構築とその機能化」とそれぞれ題した精力的な研究成果が発表され、いずれも活発な質疑が行われた。二日目午後にはポスターセッションが行われ、前半後半に分かれての各自の持ち時間は 55 分であったが、いずれの発表者の前でも常に活発な議論が行われ、ポスター発表も盛況であった。▽F-4 ソフトアクチュエータSoft actuators
代表チェア 奥崎秀典(山梨大)本セッションでは、ソフトアクチュエータの材料、デバイス、モデル、制御、応用に焦点を当て、高分子材料を用いたアクチュエータやフレキシブルセンサ等に関する最新の研究成果が発表され、活発な議論が行われた。18 日に開催された「ソフトアクチュエータ産業化研究会」では、橋本稔先生(信州大)による「PVC ゲルソフトアクチュエータの開発と展望」、新竹純先生(電通大)による「シリコーンエラストマーを用いたトランスデューサーとロボット」、川口伸明先生(アスタミューゼ(株))による「世界の特許・グラント・ベンチャー情報から読み解くソフトアクチュエータの未来」、中村太郎先生(中央大)による「高出力な空気圧ゴム人工筋肉の開発とソフトロボティクスへの応用:ベンチャー企業による事業化への挑戦」、高嶋一登先生(九工大)による「形状記憶ポリマーを用いたアクチュエータ・センサ」、松永直人先生(豊田合成(株))による「e-Rubber の活用事例について」の 6件の講演を行い、産学官におけるソフトアクチュエータの最新技術と開発動向、工業化に向けた取り組みについて活発な議論が行われた。引き続き 19 日から 2 日間にわたり「ソフトアクチュエータ」のセッションが開催され、口頭発表 15 件(うち招待講演 2 件)、ポスター発表 1件が行われた。初日の午後に行われた 2件の招待講演では、金藤敬一先生(大阪工大)が「導電性高分子ソフトアクチュエータにおける収縮メカニズム」、三塚雅彦先生(三菱化学(株))が「光弾性を利用した触覚センサ」について講演し、6件の一般講演と合わせ、ナノカーボン高分子アクチュエータ、釣糸人工筋、光駆動アクチュエータ、フレキシブルセンサに関する活発な議論がなされた。2日目午前に行われた講演では、杉野卓司先生(産総研)が「ナノカーボン高分子アクチュエータの変位の戻り現象に関するメカニズム」について発表し、他 6件の一般講演と合わせ、導電性高分子を用いたソフトアクチュエータ、形状記憶ポリマーアクチュエータ、PVC ゲルアクチュエータに関する活発な質疑応答と質の高いディスカッションが行われた。▽F-5 有機イオントロニクス―バイオマテリアルによるエネルギーと生体デバイス―Organic iontronics-Energy and bio devices based on biomateri-als-
代表チェア 金藤敬一(大阪工大工)
生命を支える食物、生体材料、エネルギーはいつの時代も科学技術の不可欠な要素として、従来の材料と技術を基盤として進化している。生命活動は有機化合物を構成材料とし、物質、エネルギーおよび情報変換により自立的に行われている。これらの機能は、従来の電子のみを扱うエレクトロニクスから物質移動を含めたイオンの動的制御によって模倣が可能である。これまで有機イオントロニクスを主題として、材料と技術に関する話題を持ち寄り、未来技術への基礎と現状を議論してきた。今回も、本シンポジウムが将来の持続的な循環社会を目指す人間親和性、環境・エネルギー問題を解決する技術の一翼を担う重要な科学技術と認識し、継続して開催した。本シンポジウムでは有機イオントロニクスに基づく生体模倣デ
バイス、例えば、光電変換や情報変換の有機デバイス、バイオ燃料電池や太陽電池などの環境エネルギーデバイス、酵素センサー、ニューラルネット、シナプス素子、および人工筋肉などのバイオデバイスなどのトピックスに重点を置いた。発表は招待講演(40 分)1件、依頼講演(35 分)1件、および一般講演(オーラル 25 分)24 件、合計 26 件の発表を初日午前 10 時から二日目午後 5時まで 2日間にわたって開催した。一般講演も十分な時間をとったので、活発な議論が行われた。招待講演は、産総研電池技術研究部門の藤原直子氏による「イ
オン伝導性高分子膜を電解質としたバイオ燃料電池の発電特性」と題して、グルコース、アルコールおよびアスコルビン酸などのバイオ燃料電池の基礎から応用および課題について解説して頂いた。一時期、アルコール燃料電池がモバイル機器の電源として市販されていたが現在は姿を消したこと、家庭用都市ガス燃料電池、自動車用水素燃料電池の課題など、貴重な内容であった。依頼講演として新潟大工の新保一成氏による「表面プラズモン共鳴および水晶振動子微量天秤特性の複合測定による薄膜堆積・構造評価」について発表して頂いた。一般講演はいずれも創造的かつ挑戦的な研究内容で、活発な討
MRS-J NEWS Vol.31 No.1 February 2019
9
招待講演者・藤原直子氏と、その聴衆(小野田光宣(兵庫県立大工)撮影、2018 月年 12 月 18 日)

論が行われ有意義なセッションであった。初日午前中は、色素増感およびペロブスカイト太陽電池 4件が何れも外国人による発表であった。午後は主にバイオ燃料電池、および酵素センサーに関する発表であった。二日目午前中は新潟大から表面プラズモンに関する発表 3件、有機エレクトロニクス材料の物性に関する 3件の発表があった。午後はバイオ素子 2件、有機分子素子およびナノグラフェンに関する研究発表およびその他 5 件あった。特に、九工大のA. S. Tripathi 氏らはグラフェンと導電性高分子の溶液を不溶溶媒に展開して高い異方性配向膜を作製し、キャリア移動度の高い異方性を実現した研究は、印象深かった。今回は会場を、初めて横浜以外の北九州市に移して開催された。地方都市での開催で参加者の確保が危惧されたが、オーガナイザーの努力もあって、例年の発表件数を上回るシンポジウムとなった。特に九工大を始め地元から約半数の 12 件の発表件数があった。写真は講演中の、招待講演者の藤原直子氏と、その聴衆である。▽F-6 機能性ソフトマテリアルとしての高分子ゲルPolymer gels as functional soft materials
代表チェア 田中 穣(福井大工)本セッションではゲル・エラストマーの関連材料について合成、構造、物性、機能、応用の視点から討論を交わした。申し込みのあった発表はオーラル 14 件、ポスター 10 件であった。これに招待講演 1件を加え、一日目にポスター、二日目にオーラルのセッションを開いた。ポスターセッションでは生体医療分野の機能性向上をめざした「ポリビニルアルコール会合体を用いるStaphylococcus aureus の病原性抑制」、「メチル-�-シクロデキストリンのアガーゲル表面におけるバイオフィルム成長阻害効果」が見られ光学材料としての機能向上をめざした「ロタキサン構造を導入した機械的刺激に応答する発光性エラストマーの創製」がみられた。二日目午前中にはカゼイン・アルギン酸ナトリウム水溶液にみられる相分離とカルシウムイオンによるゲル形成を巧みに利用するゲルファイバーの作成例が示された。とりわけ相分離を活用する例として関心を寄せた。また導電性ポリマーを取入れたゲル電極を生体細胞へ接着する例が紹介された。午前中の最後に「水溶性高分子の相挙動」という題で九大名誉教授・鴇田昌之先生による特別講演会が開かれた。UCST 系の液-液相分離とゲル形成の競合する水溶液(実験系はゼラチン・ポリエチレングリコールとアガロース)について、相挙動を包括的にとらえ、解説がなされた。午後からは汎用高分子として広く使われているポリ塩化ビニルの新規可塑剤の開発、層状無機化合物によるゲル同士の接着技術が紹介された。特に無機物へのインターカレーションはハイドロゲルの医療分野への応用を見据えた重要な課題に挑戦する研究であり関心を集めた。一部の時間帯で満席になるほど参加者が集まり盛況となった。▽F-7 自己組織化材料とその機能XVSelf-assembled materials and their functions XV
代表チェア 永野修作(名大VBL)自己組織化材料に主眼を置いた本シンポジウムは、本年にて15 回目を迎えた。小倉にて開催された本年も、メイン会場にて行われ、ますます活発な議論がなされた。発表は、招待講演 5件、口頭発表 25 件、ポスター発表 45 件が 19 日と 20 日の 2日間にて行われた。19 日には、2件の招待講演が行われた。北大の角五彰先生による招待講演は、「感じて考えて行動するソフトマター」としてキ
ネシンを表面に固定化した基板上にて並進運動する微小管の動的な集合構造を制御する研究の紹介がなされた。微小管にDNAや光応答性置換基を結合させることで、分子モーターにて動く微小管にプログラムとセンサー機能を組み込み、微小管の集合構造の誘起、光照射により集合-乖離状態をスイッチなど動的な自己組織構造を制御する分子ロボットへの可能性を示す発表であった。また、名大の河野慎一郎先生による招待講演は、「大環状化合物および大環状金属錯体を用いたナノ空間の開発」と題した、巨大環状分子をカラムナー液晶化することで、新たな多孔質材料へ展開する研究の発表がなされた。数 nm 径の空隙を有するカラムナー液晶構造や基板表面へ 2次元結晶のように固定化できる環状分子を紹介され、明確な液晶構造解析とともに多孔質を持つ液体材料という新しい材料コンセプトを示されていた。夕方のポスターセッションでは、学生の発表を中心とした熱の入った議論が行われた。20 日は、北大の磯野拓也先生による「オリゴ糖鎖含有ブロック共重合体の精密合成と自己組織化」、九大の小野利和先生による「光機能特性のための多成分結晶の分子デザイン:発光材料と光学センサーへの応用」、山口東京理科大の舟浴佑典先生による「光応答性イオンで創るソフトマテリアル:構造と機能の光制御」の 3件の招待講演が行われ、分子の多彩な自己集合・自己組織化構造、また、無定形構造の設計とその機能に関する活発な議論がなされた。その他、鳥取大の松浦先生によるチューブリン微小管の内部を材料空間として用いる研究や物材機構の吉尾先生によるイオン性液晶化合物の多様な集合構造とアクチュエーターへの応用などの口頭発表が行われた。本セッションでは、高いレベルの学生の口頭発表も多く、多く
の質の高い議論がなされていたと感じている。例年にも増して、生体分子など多様な物質系での自己組織化材料にて様々な応用展開が提案された会であった。▽F-8 分離膜研究の新展開New development of separation membrane research
代表チェア 比嘉 充(山口大)本セッションでは分離膜の開発とそのプロセス開発への応用を
視野に入れ、有機・無機・生体分子など様々な機能材料を活用した分離膜研究が報告され、活発な討論が行われた。発表は招待講演 2 件、オーラル 22 件、ポスター 42 件の合計 66 件で、2 日間にわたり行われた。今回、有機・無機材料を利用して、水処理・ガス分離・発電・電池など様々な分野における膜を研究している研究者の方々に御参加頂いた。初日(学会 2日目)の午前より、ガス分離・水処理等を志向し
た口頭発表が行われ、午後より神戸大先端膜工学センターのセンター長の松山秀人教授による招待講演が行われた。招待講演では「神戸大学先端膜工学センターにおける正浸透膜プロセスの研究」と題して、正浸透膜プロセスのみならず同センターにおける活発な研究成果が数多く報告された。その後のポスター発表では多数の学生の発表があり、活発な議論が行われていた。二日目の午前より、前日に引き続き口頭発表が行われ、奨励賞
候補の若手からの研究発表も行われた。最後に工学院大総合研究所教授、(公財)地球環境産業技術研究機構の中尾真一氏による「新しい膜分離技術の開発と応用」と題する基調講演が行われ、特に実用化を志向した様々な膜分離技術の最先端のお話を熱く語って頂く中で会場一杯に詰めかけた参加者を多く魅了し、盛会の裡にシンポジウムを終えた。
MRS-J NEWS Vol.31 No.1 February 2019
10

中尾真一先生の基調講演 松山秀人先生の招待講演
▽F-9* タフポリマー創製を目指した構造解析と物性評価Design and characterization of tough polymers
代表チェア 高原 淳(九大先導研)本セッションは、しなやかで強靱な高分子材料の創製を目指している ImPACT 伊藤プログラムの研究内容である高分子科学の最新の理論、実験、シミュレーションなどに関する深い討論を目的として提案されたもので、12 月 19 日、20 日の日程で国際シンポジウムとして開催された。トピックスとして、①ゲル・エラストマーの破壊現象の実験的検証、②放射光 X 線回折・散乱測定を利用した破壊機構評価、③シミュレーションに基づく破壊機構の解明、④複合材料の界面凝集構造などが挙げられた。国内外からの招待講演 8件を含む 17 件の口頭発表、38 件のポスター発表が行われ、口頭発表の会場には約 60 名程度の聴講者数であった。初日午後、伊藤浩志先生(山形大)のポリマー材料の成型加工に関するご講演を皮切りに、高分子のダイナミクスに関する研究発表がなされた。また、Ya-sen Sun 先生(国立中央大、台湾)による視射角入射 X線散乱法を用いたブロック共重合体膜のミクロ相分離構造、Yongsok Seo 先生(ソウル国立大、韓国)による結晶性高分子/非晶性高分子界面接着と力学物性の関係、Hung-Jue Sue 先生(テキサスA&M大、米国)による高分子系ナノ複合材料の破壊現象に関して、さらに一般発表では様々な機能性高分子膜の構造に関する研究発表が行われ、活発な討論が展開された。2日目午前は、田中敬二先生(九大)の埋もれた界面の分子運動とタフ化の関係とシミュレーションおよび放射光 X線散乱技術を用いたタフ化に関する分子論的な発表が行われ、さらに、ポスターセッションでは、分子設計に基づいた新規ポリマー材料の合成に関する発表も多くなされ、タフポリマー創製に関する活発なディスカッションが行われた。午後は、陣内浩司先生(東北大)の電子顕微鏡による一軸変形化におけるゴム材料の構造変化の観察、Eamor Woo 先生(国立成功大、台湾)の生分解性結晶性高分子が形成する多彩な表面構造、岡崎進先生(名大)の全原子分子動力学計算に基づく衝撃破壊現象に関する研究とともに様々な時空間評価に基づいたポリマー材料のタフ化を達成するための深い議論が行われた。また、セッション終了後は西日本工業倶楽部に移動し、北九州市の歴史を学ぶとともに懇親を深めた。最後に、セッションに協賛および広告をご提供いただいた企業・各種団体に感謝申し上げる。▽G-1 全国高専社会実装材料研究シンポジウム(高専シンポジウム 1)National college of technology collaboration 1, Applicationmaterial research symposium
代表チェア 佐藤貴哉(鶴岡高専)
本セッションでは全国高専社会実装材料シンポジウムとして、主に材料に関する研究開発について実用性を視野に入れた議論が展開された。発表は招待講演 1件、オーラル 35 件、ポスター 37件の合計 73 件で、3 日間にわたり行われた。口頭発表の会場では講演時間 10 分、質疑応答 4 分で進行し、ほぼ時間通りに進行した。発表時間に対して十分な質疑応答の時間が取られており、異なる専門分野の研究者間においても活発な討論がなされていた。初日午後は、鶴岡高専の森永教授と富山高専の高田教授を座長
として、無機系機能材料に関する題目を中心として発表がなされた。2日目は午前から午後にかけて、大分高専の松本教授、阿南高専の西野教授、富山高専の袋布教授、鶴岡高専の佐藤貴哉教授の進行のもと活発な議論が行われた。招待講演として一関高専の小野寺丈氏が「色素増感太陽電池の条件最適化」の題目で発表を行った。本件は、去る平成 30 年 9 月に行われた高専生サミットにおいて優秀賞を受賞した功績を讃えるべく、当セッションに招待されたものである。色素増感太陽電池の酸化チタン粒子の粒子径の変化ならびに、赤紫キャベツから抽出した色素の添加が発電効率に与える効果を追跡するという研究内容であったが、学生ならではの視点で研究が展開されており、今後の活躍がさらに期待されるものであった。3日目は午前中にポスターセッションが開催された。奨励賞の審査対象は 28 件(全 37 件中)にのぼり、審査員を前にして真摯な姿勢で発表を行う学生や若手研究者の姿が印象的であった。▽G-2 全国高専バイオ・マテリアル研究シンポジウムNational college of technology collaboration 2, Bio・mateialsresearch symposium
代表チェア 兼松秀行(鈴鹿高専)日本MRS における高専シンポジウムは本年で 2 回目となる。
今大会では材料系(G-1)とバイオ系(G-2)に分けて高専セッションを設け、合わせて 129 件の発表があった。G-2 ではバイオマテリアルを中心とした演題を募集し、オーラル 27 件(うちKeynote 2 件、高専生サミット招待 2件)、ポスター 28 件の発表があった。18 日の Keynote は沖縄高専の池松真也先生から、高専生サミットの紹介と研究室学生が行う沖縄固有の生物資源を利用した研究内容をお話しいただいた。19 日の Keynote は理研の田中信行先生から「バイオフィルム形成における液体除去による濡れ性評価」について講演していただいた。オーラルセッション参加者は、初日、2 日目ともそれぞれ 15 名程度で、研究領域が広いこともありその場の議論はそこまで白熱したものとはいえなかった。一方で、新たな人のつながりが生まれ、異分野コラボレーションが期待できそうな雰囲気が高まったように感じる。MRS-J 高専シンポジウムは、バイオ系と材料系の研究者が顔をあわせてディスカッションできる貴重な場なので、来年度も機会をいただけたならばバイオ-マテリアル領域がうまく混ざりあえるような工夫を凝らし、より活発な議論ができるような会にしたい。高専シンポジウムでは、「高専生サミット」において日本MRS
理事の伊熊泰郎先生(神奈川工科大)から選抜いただいた優秀発表学生の招待発表が行われた。高専生サミットは全国高専の低学年の学生が研究発表を行うイベントで、本年 9月に 3回目を終えた。G-2 では鶴岡高専、米子高専のそれぞれ高専 3 年生が、「燻製中の香り成分クマリン濃度と成分を徹底比較」(髙橋萌さん/鶴岡)、「アボカドの着色劣化現象を UV クリームの機能性評価に用いる研究」(田中泰斗さん/米子)の演題を発表した。内容は高専が目指す社会実装に即した興味深いものであり、2 名ともに
MRS-J NEWS Vol.31 No.1 February 2019
11

堂々とした素晴らしい発表だった。10 代の学生が研究者を前に学会発表を行ったことはかけがえのない経験となったはずである。最後に、バイオ領域と高専の若い学生研究者を本学会に受け入れていただいたことに感謝を申し上げ、学会報告とさせていただきます。
▽宗宮重行先生 追悼シンポジウムProfessor Shigeyuki SŌMIYA Memorial Symposium
神奈川工科大学・伊熊泰郎日本MRS の創設と運営に多大なご尽力をされた宗宮重行先生が 2018 年 8 月 8 日に逝去された。その先生を追悼するシンポジウムが 12 月 19 日(水)、14:30~16:30、年次大会の会場:北九州国際会議場 11 会議室(B会場)、で開催された。その内容は次のとおり(役職など省略)。1.開会の辞/Opening 高原淳(九州大学/日本MRS)
2.宗宮先生の足跡と日本MRS/Achievements of prof. Somiyaand his contribution to MRS-Japan 吉村昌弘(国立成功大学/東京工業大学)3.Somiya remembered R. P. H. Chang(Northwestern Uni-versity/IUMRS)(代読)4.Somiya and IUMRS Soo Wohn Lee(Sun Moon Univer-sity/IUMRS)5.宗宮先生の思い出/Memory of Prof. Somiya 渡邉友亮(明治大学)6.宗宮先生と私の材料研究/Prof. Somiya and my research伊熊泰郎(神奈川工科大学)7.閉会の辞/Closing 松下伸広(東京工業大学)会場では研究業績リスト、受賞リストも配布され、故宗宮先生
を偲んだ。
■IUMRS報告第 4 回ヨーロッパMRSと日本MRSのバイラテラルシンポジウム(4th E-MRS & MRS-J Bilateral Symposium)報告
青山学院大学・重里有三2018 年 10 月 14 日~19 日にギリシャのクレタ島で開催された 7th InternationalSymposium on Transparent ConductiveMaterials(IS-TCMs)をプラットフォームとして 4th E-MRS & MRS-J BilateralSymposium が開催されました(開催場所:Platanias, Chania, Crete, Greece)。2015 年は MRS-J 年次大会にて 1st E-MRS/MRS-J Bilateral Symposium(横浜開港記念館)を、2016 年は E-MRS Springmeeting にて 2nd E-MRS/MRS-J BilateralSymposium(Lille, France)を、2017 年には IUMRS-ICAM にて 3rd E-MRS/MRS-J
Bilateral Symposium(京都大学)を開催し、MRE-J と E-MRS の最先端での情報交換、共同研究や、人的ネットワーク構築の場として企画運営されてきました。これらは年に一回、開催場所は日本と EUが交互になるように計画されています。2018 年はヨーロッパ文明発祥の地であり「神々の愛でし海」エーゲ海に囲まれたクレタ島で開催されました。多くの研究者が EU、日本のみならず北米や他のアジアの国々からも集まり以下の 3つのシンポジウムに関して多くの招待講演を含む高度な講演会並びに活発な討論会が行われました(図-左、
中)。Symposium 1 : Nitrides and Diamond Ma-terials and Devices(Wide Bandgap Semi-conductors)Symposium 2 : Processing and Character-ization of Advanced Multifunctional Ox-idesSymposium 3 : Oxide-based devices ; Fron-tier for energy and environmental issuesこれらの講演の Proceedings は現在査読
中で、Elsevier から発刊されている ThinSolid Films の special issue として出版される予定です。次回の 5th E-MRS/MRS-J Bilateral Sym-
posium は、2019 年 12 月に横浜で開催され る Materials Research Meeting(MRM2019)をプラットフォームとして 3つのシンポジウムを企画しています(図-右)。
■IUMRS報告ICYRAM2018 報告
物質・材料研究機構・山浦一成
2018 年度の ICYRAM(the Internation-al Conference of Young Researchers onAdvanced Materials)に参加しました。2018 年度はオーストラリア MRS(以下、A-MRS)が主体となり、アデレードで2018 年 11 月 5~7 日の日程で開催されました。実質 3 日間で、3 パラレルセッションの構成でした。会議冒頭の、議長を務めた Drew Evans 准 教 授(University ofSouth Australia)による挨拶では、本会議の特徴として以下の 3点を挙げました。⑴
参加者のジェンダーバランスが約 50/50、⑵口頭発表 100 件以上、⑶海外からの参加者が約 1/3。確かに、女性参加者が多かったのは際
立っていたと思います。2022 年度の福岡開催でも課題になると予想されます。冒頭イベントでは、議長挨拶の後、A-MRS 会長の Chennupati Jagadish 教授と CarolineMcMillan 教授が挨拶しました。会議がカバーする分野は広範でしたが、
大きくエネルギー、環境、バイオ、新材料と分類し、他は一括して基礎研究としていました。また学会賞は、事前に選考が行われ、会議二日目セッション後にセレモニーを行い、授賞講演は三日目のプログラムに
入っていました。学会賞の名称は“MRSSingapore Young Investigator Award”となっていて、シンガポールMRS の冠がついていました。議長の Drew Evans に伺ったら、本会議のスポンサーとして大きな貢献があったそうです。授賞セレモニーで は、MRS Singapore 会 長 の B. V. R.Chowdari 教授が挨拶しました。日本からは、MRS-J の参加費支援を受
けた 9名が講演しました(内、若手 4名が招待講演)。MRS インドネシアの YudiDarma 教授のように、日本に留学経験がある他国の研究者も多数が参加し、交流を楽しんでいました。
MRS-J NEWS Vol.31 No.1 February 2019
12

ご 案 内■Materials Research Meeting 2019(MRM2019)―MaterialsInnovation for Sustainable Development Goals主 催:MRM2019日時・場所:2019 年 12 月 10~14 日、横浜シンポジア(横浜市
中区山下町 2 産業貿易センタービル 9F)MRM2019 は、広範な分野の物質研究者が一堂に会して持続的発展目標 SDGs のための新材料の開発原理、製法を紹介する場となるであろう。背景の異なる参加者間での濃密な意見交換により次世代材料研究のために、革新的発想と戦略的開発が生まれることが期待されている。若手の研究者にとっては、活発な討論の場を設けることが若手研究者たちの研究計画に対して討論の場が生まれるであろう。MRM2019 における討論を経て、若手研究者間に役に立つ研究網と相乗的協調の基盤形成と拡大が期待される。下記の分野のシンポジウムが予定されている。A. Fundamentals for MaterialsB. New Trend of Materials ResearchC. Novel Structural Materials Based on New PrinciplesD. Advanced Electronic MaterialsE. Magnet and SpintronicsF. EnergyG. Materials for Smart SystemsH. Green Technology and ProcessingI. Biopolymers詳細Secretary of the Meeting, MRM2019 Secretariat, c/o Head Officeof MRS-Japan, 507D, Yokohama Bldg. 3-9 Kaigan dori, Naka-ku,Yokohama, 231-0002 Japanhttps://mrm2019.jmru.org/Email : [email protected]■協賛・共催▽The 3rd International Symposium on Coatings on Glass andPlastics “ICCG International Organizing Committee & 一般社団法人光融合技術協会、日時・場所:2019 年 4 月 4 日~5日、青山学院大アイビーホール、詳細:https://www.i-opt.org/▽ナノ学会第 17 回大会、日時・場所:2019 年 5 月 9 日(木)~11日(土)、かごしま県民交流センター、連絡先:http://mtg-officepolaris.com/nano17/▽20th International Symposium on Boron, Borides and RelatedMaterials(ISBB 2019)、日時・場所:2019 年 9 月 22 日~27 日、朱鷺メッセ新潟コンベンションセンター、連絡先:日本ホウ素・ホウ化物研究会、http://www.sogalabo.jp/isbb2019/■IUMRS関係▽2019 E-MRS IUMRS ICAM Spring Meeting、日時・場所:2019 年 5 月 27 日~31 日、Acropolis Congress Centre, Nice、詳細:https://www.european-mrs.com/meetings/2019-spring-meeting▽10th International Conference on Materials for AdvancedTechnologies(ICMAT)、日時・場所:2019 年 6 月 23 日~28日、Marina Bay Sands, Singapore連絡先:[email protected]
▽20th IUMRS-ICA 2019
20th IUMRS-ICA 2019,日時・場所:2019 年 9 月 22 日~26 日、Perth Convention and Exhibition Centre, Australia,詳 細:[email protected]▽17th IUMRS-ICEM
日時・場所:2020 年 9 月 13 日~17 日、Iguassu Falls, Brazil連絡先:[email protected]■12th IUMRS-Somiya Award 2019(2019 年宗宮賞)募集宗宮賞は、東京工業大学名誉教授、帝京科学技術大学部長
Dean、宗宮重行博士の業績を称えて設けられた賞。2019 年の宗宮賞の選考がすすめられている、応募締め切り、2018 年 12 月 28日。詳細問い合わせ先:宗宮賞委員会・森利之博士[email protected].■日本MRS―2018 年度 JNTO国際会議誘致・開催貢献賞受賞日本MRS は、日本政府観光局 JNTO より 2017 年京都で開催された「IUMRS-ICAM2017」が 2018 年度国際会議誘致・開催貢献賞受賞に選定され、2019 年 2 月 28 日(木)、東京都千代田区国際フォーラムで開催される授賞式で表彰される、と発表。■新刊紹介Transactions of the Materials Research Society of Japan, vol. 43,No. 5, October, 2018、が刊行されました。著者、論文標題は下記のとおりです。Trans. MRS-J, Vol. 43, No. 5, 2018Review Paper▽Combinatorial Thin Film Synthesis for Developments of NewHigh Dielectric Constant Thin Film MaterialsTakahiro Nagata, Somu Kumaragurubaran, Yoshihisa Suzuki,Kenichiro Takahashia, Sung-Gi Ri, Yoshifumi Tsunekawa, SetsuSuzuki, Toyohiro ChikyowRegular Papers▽Synthesis of Titanium Dioxide Nanoparticles with DesiredRatio of Anatase and Rutile Phases and the Effect of HighTemperature AnnealingShanmugam Saravanan, Madheswaran Balamurugan, TetsuoSoga▽Change of LPSO Phases Morphology in Extruded Mg96Zn2Y2Alloy Joints during Ultrasonic Spot Welding ProcessYuichi Higashi, Chihiro Iwamoto, Yoshihito Kawamura▽Application of simple formulas to track potential in heavy-ion-beam simulationKengo Moribayashi▽Surface Modification of PLA Nanofibers for Coating withCalcium PhosphateAoi Suzuki, Fukue Nagata, Masahiko Inagaki, Katsuya Kato▽Effect of Oxygen Plasma Treatment on Film Structure forDifferent Types of DLC filmTatsuya Mayama, Masanori Hiratsuka, Hideki Nakamori, AkihikoHomma, Kenji Hirakuri, Yasuharu Ohgoe▽Surface modification of highly gas permeable membrane bynanosheets composed of ionic-functionalized polyimidesChihiro Umede, Botakoz Sulcimenova, Taptha Naruemon,Shinichi Koguchi, Yosuke Okamura, Yu Nagase▽High-Intensity Laser Irradiation Inducing Au Nanoparticles inViscous GlycerinRikuto Kuroda, Takahiro Nakamura, Masaru Nakagawa▽Pulsed Laser Drilling of Engineering Plastic Films to Fabricate
MRS-J NEWS Vol.31 No.1 February 2019
13

Through-Hole Membranes For Print-and-Imprint MethodTakahiro Nakamura, Kento Seki, Kazuro Nagase, MasaruNakagawa▽Sterilization for Bacillus Subtillis var. natto by Low PressureSputtering and Laser Ablation Plasma using Metal PowderTargetHiroharu Kawasaki, Yoshihito Yagyu, Tamiko Ohshima, TakeshiIhara, Masanori Shinohara▽Relationship between the Presence and Absence of Oxygen atthe Time of Carbonization of Rice Hull Charcoal and AdsorptionAbilities toward Cesium and StrontiumMasato Sasaki, Shinya Kobayashi, Norihisa Kawamura, Toru
Nonami▽Octadecylphosphonic Acid Self-Assembled Monolayers Ob-tained Using Rapid Dipping TreatmentsToshiya Bamba, Tadashi Ohtake, Yusuke Obata, Heng-yong Nie,Takahiko Ban, Shin-ichi Yamamoto▽Optical and electronic transport properties of single-crystallineBi2Te3 hexagonal nanoplates determined by infrared spectro-scopy and first-principles calculationsKodai Wada, Satoshi Morikawa, Masayuki Takashiri▽Fluorescence Emission Mechanism of Three N, N-dimethyla-minotryptanthrins by Density Functional Theory CalculationsJun Kawakami, Chika Osanai, Shunji Ito
MRS-J NEWS Vol.31 No.1 February 2019
14
To the Overseas Members of MRS-J
■Invitation to Materials Research Meeting(MRM2019)as the30th Anniversary of MRS-J㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀p. 1
Hideo HOSONO, Professor, Tokyo Institute of Technology andAtsushi SUZUKI, Professor, Yokohama National UniversityMRS-J cordially invites you to the Materials Research Meeting2019 (MRM2019 : https://mrm2019.jmru.org/) as the 30th Anni-versary of MRS-J, which will be held on December 10-14, 2019 atYokohama, Japan. The MRM 2019 is intended to offer a newplatform for materials researchers from different disciplines todiscuss recent scientific developments and applications ofadvanced materials for the Sustainable Development Goals(SDGs). The MRM2019 consists of 36 scientific symposia,categorized into 9 Clusters, and many outstanding researchers,including 7 Plenary and 27 Keynote speakers, will be invited. We
are looking forward to seeing you at Yokohama, Japan inDecember 2019■The 28th Annual Meeting of MRS-J㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀p. 2The annual meeting of the MRS-J was held December 18-20,
2018, in the Kitakyushu International Conference Center,Kitakyushu-shi.For further information :https://www.mrs-j.org/meeting2018/en/,E-mail : [email protected]
■Shigeyuki SOMIYA Memorial Symposium : Yasuro IKUMA㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀p. 12■4th E-MRS & MRS-J Bilateral Symposium :Yuzo SHIGESATO㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀p. 12■ICYRAM2018 : Kazunari YAMAURA㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀p. 12
目 次01 やあ こんにちは 日本 MRS 設立 30 周年記念国際会議 MRM2019の開催について 細野秀雄・鈴木淳史
02 第 28 回日本MRS年次大会開催報告12 宗宮重行先生 追悼シンポジウム 伊熊泰郎
12 4th E-MRS & MRS-J Bilateral Symposium報告 重里有三12 ICYRAM 2018 報告 山浦一成13 ご案内 新刊紹介14 To the Overseas Members of MRS-J 編集後記
編 後集 記
奨励賞受賞者決定を待っての遅れた発行になるなど、何時にも増しての難産となりましたが、なんとか 1号ニュースを出すことができました。本号では、昨年 12 月の年次大会シンポジウム報告の特集とともに、「やあこんにちは」で本年12 月の 30 周年記念国際会議MRM2019 についてご紹介頂くことに致しました。このようにMRS-J は、これまで通りに
国内研究者・技術者の情報交換・交流の場であり続けることはもちろん、日本の材料研究のプレゼンスを世界に示す場となることも重要です。微力ながら私も貢献して参りたいと思います。 (文責・松下伸広)
©日本MRS 〒274-8501 千葉県船橋市習志野台 7-24-1 日本大学理工学部 岩田展幸研究室E-mail : [email protected] 年日本MRSニュース編集委員会 第 31 巻 第 1号 2019 年 2 月 10 日発行委員長:岩田展幸(日本大学理工学部)委 員:鮫島宗一郎(鹿児島大学学術研究院)、西本右子(神奈川大学)、川又由雄(芝浦メカトロニクス(株))、狩野 旬(岡山
大学大学院)、新國広幸(東京工業高等専門学校)、寺迫智昭(愛媛大学大学院)、松下伸広(東京工業大学物質理工学院材料系)、寺西義一(東京都立産業技術研究センター)、鈴木俊之((株)パーキンエルマージャパン)、籠宮 功(名古屋工業大学)
顧 問:山本 寛(日本大学理工学部)、岸本直樹(国立研究開発法人物質・材料研究機構)、中川茂樹(東京工業大学大学院電気電子系)、伊藤 浩(東京工業高等専門学校)、小林知洋(国立研究開発法人理化学研究所)、Manuel E. BRITO(山梨大学クリーンエネルギー研究センター)、寺田教男(鹿児島大学大学院理工学研究科)、小棹理子(湘北短期大学情報メディア学科)
編 集:清水正秀(東京CTB) 出 版:株式会社内田老鶴圃 印 刷:三美印刷株式会社