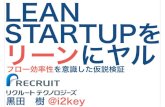HaarHaar----likelike 特徴をををを使使使使ったった 実験 (1)顔の輪郭に一致させるために、プログラムの顔位置に円を描画する箇所を楕円に変えて
09MM332yankee.cv.ics.saitama-u.ac.jp/~kunolab/research/thesis/...のYousufによってF陣形を用いた複数人に対応した立ち位置モデルと説明を始める...
Transcript of 09MM332yankee.cv.ics.saitama-u.ac.jp/~kunolab/research/thesis/...のYousufによってF陣形を用いた複数人に対応した立ち位置モデルと説明を始める...

ICS-12-M-932
ガイドロボットの適切な観賞位置への人の誘導法
指導教員 久野 義徳 教授
平成24年2月6日提出
埼玉大学大学院 理工学研究科数理電子情報系専攻 情報システム工学コース
09MM332
望月 博康
埼玉大学 理工学研究科・工学部久野研究室
埼玉県さいたま市桜区下大久保 255

概要
人とロボットとの相互作用についての研究が盛んに行われている中,人と対話を行うコミュニケーションロボットの研究が進んでいる.人のような身体性コミュニケーションを行うことができるコミュニケーションロボットの開発が期待されている。従来の心理学で知られている対人距離や空間配置に注目した.Hallによると,人は相手との親密度に応じて対人距離を変化させている人同士における相互作用における距離について述べている.Kendonは,人と物を介した相互作用を行う際に,O-spaceと呼ばれる空間が形成されると述べている.O-spaceとは人の下半身から前に投影する空間が 2人以上の人によって重なり合う空間である.Kendonは、このO-spaceを形成するために参与者らはF陣形を取ることを示している.人同士の相互作用における距離や空間配置の研究をロボットと人との対話に利用できるかを確かめる研究が行われている.その中で,O-spaceは人とロボットとの対話でも形成されることが示されている.
我々の研究室では,人同士の相互作用を分析し,博物館や美術館などで鑑賞者を話に引き込むガイドを行うロボットの開発を目指し,研究を行っている.同研究室のYousufによってF陣形を用いた複数人に対応した立ち位置モデルと説明を始める前の初期インタラクションに PauseとRestartを行うガイドロボットの研究を行っている.そこでは,鑑賞者の立ち位置を考慮することの有効性を示している.ただし,Yousufの研究では,ガイドロボットは複数の絵の説明を行うが、説明を行う 4
つの絵の大きさはほぼ同じであり、ロボットと絵の距離=絵とロボットと鑑賞者の距離という設定とロボットの視野の設定だけであった.絵と鑑賞者の関係性については述べられていなかった.絵の大きさによって,立ち位置が変わるのは明らかである.また,学芸員さんにより,絵の見やすく説明しやすい位置は絵の位置から絵の対角線の長さの距離を離れた位置と伺っている.絵の大きさに応じて,鑑賞者の絵の見やすい位置が変わるのなら,絵の大きさに応じて,絵の見やすい位置を見つけることができると考えた.そこで,絵の大きさによって,鑑賞者の位置がどのようになるかを観察する.また,他の条件で絵の見やすい位置に関する情報が得られるほかを調べるために絵の対角線の長さと絵と鑑賞者の間の距離の関係性,絵の対角線の長さと隣り合う人の間の距離の関係性について調査した.また,絵とロボットと鑑賞者の配置から,ガイドロボットと鑑賞者の間で形成されるF陣形を考慮した鑑賞者の最適な立ち位置について調査する.そこから,絵の見やすいと思われる領域を設定して,領域外にいる鑑賞者を領域内に誘導する.複数人の鑑賞者が領域

外にいるときは左の鑑賞者から音声,首振り,指差しを行い適切に誘導する方法について提案し,ロボットに実装して動かしてみることにした.


目 次
概要 i
第 1章 序論 1
1.1 研究背景 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
1.2 本研究の目的 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
1.3 課題の整理 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
1.4 本論文の構成 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
第 2章 空間配置とロボット 4
2.1 関連研究 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
2.2 デモの観察 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
2.3 F陣形とガイドロボット . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
第 3章 システム概要 9
3.1 ガイドロボット概要 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
3.2 レーザ測域センサの概要 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
3.3 用いた絵画について . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
第 4章 鑑賞者の立ち位置 15
4.1 目的 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
4.2 鑑賞者の位置の観察方法 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
i

4.3 結果 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
第 5章 最適な立ち位置について 22
5.1 データの考察 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
5.2 最適な位置領域の検討 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
第 6章 最適な位置への誘導 26
6.1 適切な位置領域の設定の準備 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
6.2 誘導システムについて . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
6.3 ロボットへの実装 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
6.4 ロボットのデモ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
6.5 考察 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
第 7章 本研究のまとめと今後の課題 32
7.1 まとめ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
7.2 今後の課題 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
参考文献 35
ii

表 目 次
3.1 Robovie-R ver.3の仕様 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
3.2 スキャナ式レンジセンサ (UTM-30LN)の仕様 . . . . . . . . . . . . 11
3.3 用いた絵画のデータ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
4.1 絵の大きさと鑑賞者における平均距離と平均角度 . . . . . . . . . . 17
4.2 隣合う人同士の平均距離 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
iii

図 目 次
2.1 F陣形におけるO空間,P空間,R空間 . . . . . . . . . . . . . . . 5
2.2 ガイドロボットにおける F陣形 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
2.3 F陣形の空間配置例 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
2.4 大原美術館でのデモの様子 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
3.1 Robovie-R ver.3の外観 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
3.2 スキャナ式レンジセンサ(UTM-30LN)の外観 . . . . . . . . . . . 11
3.3 センサの角度系 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
3.4 レーザマップ画像 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
3.5 ピカソ作の「頭蓋骨のある静物」 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
4.1 実験結果例 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
4.2 実験結果例を解説 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
4.3 鑑賞者別のセンサと鑑賞者の距離の平均 . . . . . . . . . . . . . . . 18
4.4 絵を中心として左右鑑賞者とできる角度 . . . . . . . . . . . . . . . 19
4.5 鑑賞者別のY座標の平均 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
4.6 絵と鑑賞者の距離の平均 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
4.7 隣り合う人同士の距離 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
4.8 絵の大きさと絵と鑑賞者の距離の関係 . . . . . . . . . . . . . . . . 21
5.1 真ん中鑑賞者が後ろになる配置 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
iv

5.2 鑑賞者が斜めとなる配置 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
6.1 鑑賞者にとって適切な位置 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
6.2 フローチャート . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
6.3 システムの解説 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
6.4 デモの様子 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
v

第1章 序論
本章では,研究背景・関連研究から問題点や解決方法を整理し,本研究の目的について述べる.
1.1 研究背景
近年,人とロボットとの相互作用 (Human-Robot-Interaction)の研究が盛んになってきている [1].人同士のコミュニケーション研究によって,適切な身体配置を行うことが身体性コミュニケーションにおいて重要であることが知られている.人のような身体性コミュニケーションを行うことができるロボット開発が期待されている.より円滑な人とロボットとの相互作用を行うことができると考えられるからである.ロボット自らが移動して距離や空間配置を調整することが求められる.
美術館や博物館には,展示物の解説を行う,音声ガイドがある.場所によっては,展示物について深い知識を持つ,学芸員がおり,展示物の解説を行って頂ける.学芸員と音声ガイドのどちらが展示物の解説が伝わりやすかを考える.学芸員は音声に加えて,視線や表情,身振り・手振り,間の取り方など,音声ガイドよりも多くの情報を相手に伝えている.学芸員が音声ガイドよりも優れていることは明らかである.人間のように言語と非言語を上手に組み合わせて用いたガイドロボットによる解説が可能になれば,ロボットのコミュニケーション技術を高め,介護や商業分野などへの応用も期待することができ,社会的意義が大きい.
1.2 本研究の目的
コンピュータビジョンシステムから得られる映像から人物を観察し,社会学的知見に基づいて,言語行動と非言語行動を連携させて,鑑賞者と円滑なコミュニケー
1

ションを行うガイドロボットを開発することが目的である.実現には,人間の学芸員の解説行動の調査・分析が必要となる.
ガイドロボットにも絵の説明を行うときに必要な身体配置がある.絵の大きさとの鑑賞者位置について注目した.説明する絵に応じて,適当と思われる位置に絵とロボットを配置した.以前の実験では,鑑賞者の位置を指定したこともあった.絵の大きさによって,鑑賞者の立ち位置は変わることが予想される.異なる大きさの絵を用いて,絵の大きさと鑑賞者位置の関係性を示す.そこから鑑賞者にとって絵の見やすく,ロボットがインタラクションを行いやすい位置に鑑賞者を適切に誘導する方法について検討する.
1.3 課題の整理
ガイドロボット Rovobieが Ver.3となり,以前使用していた Ver.2よりも移動面では走破性と移動スピードが向上し,機能面では操作性と拡張性が向上した.移動が用意になり,同研究室の Yousufはある絵から移動して別の絵に行き鑑賞者誘導しガイドを行う研究を行なっている.そこではロボットに適したF陣形について述べておりロボットと絵の距離=絵とロボットと鑑賞者の距離が最適な配置としている.しかし,絵と鑑賞者の位置については述べられていない.また,用いていた絵の大きさがほぼ同じであり,絵の大きさが異なるときの立ち位置について考える必要がある.学芸員によると絵の見やすい位置は,絵の対角線の距離を取った位置であると伺っている.ガイドロボットを用いたとき,大きさの異なる絵で,鑑賞者の立ち位置を調べる必要がある.実際にガイドロボットがいる中で,鑑賞者が絵の見やすい位置に立ってもらい,絵のみやすい位置について調べ,鑑賞者の立ち位置について詳しく知ることで,説明を始める前に絵に興味を持っていると思われる鑑賞者を誘導して,説明を行うことができるようにすることで,人間に近いインタラクションを行うことができるようになると考えた.
大きさは異なる複数の絵を用意して,絵の対角線の長さを測る.複数人の鑑賞者それぞれの絵の見やすいに立ってもらう.レーザ側域センサによって鑑賞者の立ち位置情報を取得して,絵の大きさと鑑賞者の立ち位置の関係性を示す.また,絵の中心点の座標をあらかじめ取得することで,絵と鑑賞者間の距離と角度を求める.また,鑑賞者の立ち位置座標から,隣り合う鑑賞者の距離を調べる.それから,絵の見やすいと思われる最適な位置を推定する.絵の見やすい位置にいない鑑賞者を適切な位置に近づけるように,適切に誘導するシステムを作ることを考えた.実際に,ロボットに実装してうまくいくかどうかを調べる必要がある.
2

1.4 本論文の構成
本論文の構成は,以下の通りである.1章 : 序論2章 : 空間配置とロボット3章 : システム概要4章 : 鑑賞者の立ち位置5章 : 適切なの立ち位置6章 : 適切な位置への誘導7章 : 本研究のまとめと今後の課題
1章では背景,目的及び問題点について整理し,その解決法を示す.2章では,人と対話を行うロボットの空間配置について述べる.3章では用いたミュージアムガイドロボット,センサ,絵画について述べる.4章では大きさの異なる絵と 3人の鑑賞者の立ち位置についての観察して絵の大きさと立ち位置の関係性について示す.5章では行った実験から,鑑賞者にとって絵の見やすい位置について推定する方法について述べる.6章では鑑賞者にとって絵の見やすいと思われる位置へ誘導する方法について述べる.7章では本研究のまとめと今後の課題について述べる.
3

第2章 空間配置とロボット
本章では,空間配置とガイドロボットの関連について述べる.
2.1 関連研究
物を介した人同士の身体配置について,Kendonによる分析が行われている [2].Kendonは人と物を介した相互作用を行う際に,O空間と呼ばれる空間が形成されると述べている.このO空間とは,人の下半身から前に投影する空間が 2人以上の人によって重なり合うことでできる空間のことを示していて,話したり,見たりするときにできる空間である.このKendonによる複数人インタラクションを現代のネットを使ったコミュニケーションまで説明した記事がある [3].ここで,O空間を構成するために,参与者が身体配置することによってつくられるO空間の外側の円形部の空間であるP空間について述べられている.また,参与者の外側の空間であるR空間についても述べられている.図 2.1で F陣形におけるO空間,P空間,R
空間を示す.Hallは親密度と対人距離の関係について示しており,身体性コミュニケーションを行うときの距離の関係も重要である [4].状況に応じて対人距離は変化する.コミュニケーションロボットとの対話距離に関する研究も行われている [5].また,ロボットの身体位置や向きが注意対象にどう関係しているのか検証を行う研究も行われている [6].ロボットの位置の取り方や向きなどの身体配置が対話を行うときに重要であるとわかっている.他者を近づけたがらない,縄張りのような空間をパーソナルスペースと呼ぶ,パーソナルスペースはその範囲以内に他人が入ってほしくないと感じ,他人と距離を防衛をとるために本能的にとる距離である.しかし,ロボットでは人同士のとき以上に接近するという事例がある [7].ロボットに対しては,近づいても不快に感じなかったことを示している.
対人距離は 1対 1の関係を説明する理論であった.絵を説明するときの空間配置のように会話にモノが含まれるときは複雑な空間配置が取られる.図 2.3でO空間が構成される空間配置例を示す.(a)では互いに向かい合っている場合,(b)は L字
4

型の場合,(c)は横並びの場合である.いずれの場合も両者が互いに見える領域がO字型に構成されている.この領域の重なりが生じることが重要である.ガイドロボットにも絵の説明を行うときに適した身体配置がある.図 2.2はガイドロボットにおけるF陣形を用いた空間配置である.ロボットが人間にアプローチするときに,適した方法を提案する研究が行われている [8].ガイドロボットが鑑賞者に最適なアプローチを行う研究を目指す.
図 2.1: F陣形におけるO空間,P空間,R空間
5

図 2.2: ガイドロボットにおける F陣形
図 2.3: F陣形の空間配置例
6

2.2 デモの観察
岡山県倉敷市にある大原美術館で絵の説明を行ったデモの観察を行った.美術館に訪れた一般人にガイドロボットが説明を行った.首振りや指差しなどのジェスチャーと音声を用いた説明を行った.鑑賞者が 1人のときは絵の正面に立ち,ロボットと一定の距離をとって,絵の説明を聞いていた.鑑賞者が複数人のときは,それぞれの鑑賞者がロボットと一定の距離をとっていた.そして,鑑賞者同士の距離もある程度取り,絵の見やすい位置にいた.ガイドロボット,鑑賞者,絵によって,F
陣形が形成されていることが観察できた.図 2.4は大原美術館での様子である.鑑賞者が絵を見やすく,説明が聞きやすい位置にいて,ロボットがジェスチャーが行えて,説明が伝えやすい位置にいるときにできる空間が今回,利用する空間配置である.
図 2.4: 大原美術館でのデモの様子
2.3 F陣形とガイドロボット
観察により,ガイドロボットによる絵の説明を聞いている鑑賞者とロボットと絵画の間で,自然にF陣形が形成できることがわかったが,説明途中にO空間内に入っ
7

てきた新たな鑑賞者ともF陣形ができる.移動中の人や説明途中で退出する鑑賞者は対話の外の空間であるR空間にいるとしている.今回,O空間内にいるが絵の説明を行うには適したところにいないと思われる鑑賞者を適切な位置に誘導する方法を提案することにした.誘導する方法は動かしたい人に顔を向けて,指差しと音声を用いて誘導することにした.
8

第3章 システム概要
本章では,ミュージアムガイドロボットの構造と用いたレーザ側域センサ,使用する絵画について述べる.
3.1 ガイドロボット概要
本研究では,ATRロボティクス研究所が開発したコミュニケーションロボットの図Robovie-R Ver.3を利用している.外観を図 3.1で示す.表 3.1で仕様を示す.
図 3.1: Robovie-R ver.3の外観
9

表 3.1: Robovie-R ver.3の仕様
名称 Robovie-R Ver.3
全高 1080mm
全幅 500mm
全長 520mm
重量 37.0kg(バッテリ搭載時)バッテリ 12V 28Ah
自由度 全体 17
腕 4 × 2(肩ピッチ,肩ロール,肘ヨー,肘曲げ) 首 3 (ロール,ピッチ,ヨー)
眼球 2 × 2(パン,チルト) 車輪 2
センサ カメラ 2(USBカメラ,640 × 480 pixel,30fps)
マイク 2(ステレオマイク) 距離センサ 1(レーザ式,前面 180度)
接触センサ 11(バンパー 6,頭頂部 1,肩部 2,腕部 2)
移動機構 方式 PWS(Power Wheel Steeling)
最大速度 500mm/sec
10

3.2 レーザ測域センサの概要
人物の位置を測定するために,北陽電機株式会社のスキャナ式レンジセンサ (UTM-
30LN)をポールに取り付けて用いた.最大距離は 30m,周囲 270度の広範囲のスキャンを行える.レーザ測域センサの外観と仕様を示す.レーザ測域センサの外観を図 3.2に示し,仕様を表 3.2に示す.図 3.3で示す角度は正面を 0◦として時計回りに 135◦(+135◦),反時計回りに 135◦(-135◦)となっている.
図 3.2: スキャナ式レンジセンサ(UTM-30LN)の外観
表 3.2: スキャナ式レンジセンサ (UTM-30LN)の仕様型番 UTM-30LN
電源電圧 DC12V± 10%光源 半導体レーザ λ=870nm
測距範囲 0.1~30m
測距精度 0.1~10m:± 30mm 10~30m:± 50mm
角度分解能 ステップ角:0.25°出力応答時間 60ms
騒音 25dB以下インターフェース USB2.0
質量 約 370g(ケーブル含む)
11

図 3.3: センサの角度系
図 3.4はレーザ測域センサでスキャンし,出力した画像である.鑑賞者の位置の距離,座標を求める.センサは角度順にソートをしている.
12

図 3.4: レーザマップ画像
13

3.3 用いた絵画について
本研究で用いる絵画について述べる.大きさが異なる絵を使用した.バブロ・ピカソが描いた「頭蓋骨のある静物」の模写とそれを縮小コピーした異なる大きさの絵を 2枚,計 3枚の絵を用いた.図 3.5 で示した.絵のタイトル,作者,絵の大きさ,後に比較に使う対角線の長さを表 3.3 にまとめた.今後,絵画の大きさ順に,大きい絵,中くらいの絵,小さい絵と称す.
図 3.5: ピカソ作の「頭蓋骨のある静物」
表 3.3: 用いた絵画のデータ絵のタイトル 作者 大きさ (横×縦) 対角線の長さ
130.5cm×97.0cm 162.6cm 頭蓋骨のある静物 バブロ・ピカソ 55.6cm×39.8cm 63.4cm
28.5cm×19.8cm 34.7cm
14

第4章 鑑賞者の立ち位置
本章では,ガイドロボットが絵の説明を行うときに鑑賞者の立ち位置について検証する.学芸員によると絵の見やすい位置は絵から絵の対角線の距離を離れた位置だと伺っている.これは,人が絵の説明を行う場合であるが,ガイドロボットを用いたときでも適用されるのかを調べた.
4.1 目的
鑑賞者にとって絵の見やすいと思われる最適な位置を知りたい.絵の説明を始める前に,最適な位置に鑑賞者を誘導することができればよりロボットに親しみを持ってもらえて,より有効なインタクラションが行うことができると考えた.また,今後より多くの鑑賞者や異なる大きさの絵の説明を行うときに,役立つと考えた.
4.2 鑑賞者の位置の観察方法
大きさの異なる 3枚の絵を用いて,ガイドロボットが絵の説明を始めるときに 3
人の鑑賞者はどこに立つのかを調べる.鑑賞者の座標情報 (X座標とY座標),センサからの距離と角度を測定することができる.センサは一般的な成人の肩くらいの高さの 140cmの高さにして座っている人が映らないようにして,鑑賞者を正面にロボットの背後にロボットに接するように配置した.ガイドロボットは腕を伸ばして絵の説明を行える位置に配置した.今回ロボットは絵の大きさが異なっても位置は変えない.距離を計測したところ絵から縦 60cm,横 60cmの位置であった.鑑賞者は左,真ん中,右の順でデータを出力したいと考えたため,角度順にソートを行い出力することにした.絵は人の目線の高さが絵の真ん中となるような高さにそれぞれ配置した.ロボットが絵の説明を始める前に,鑑賞者が絵の見やすい位置に立つという状況を想定した実験を行う.鑑賞者に絵ごとに,それぞれが自分が見やすい
15

と思われる位置に立ってもらった.絵を変えるごとに一度離れてから,絵に近づいて絵を見てもらうようにした.久野研究室の男女 12人を被験者として用いた.3人1グループで絵は 3枚,計 36回の実験を行った.
4.3 結果
実験結果の説明をする.図 4.1は実験結果の一例である.3人の鑑賞者が図の下方向にある絵画を見ている.XはX座標,YはY座標,AはPTZカメラの角度Dr
はセンサの角度,Dsはセンサからの距離を示している.センサにロボットと絵画は映っていない.今回は PTZカメラのデータは使用しないので,Aの値は使用しない.さらにわかりやすく,ロボットと絵画を図示して,距離・角度について解説しているものを図 4.2で示す.センサを用いてわかったことを以下で述べる.絵が小さいほど,鑑賞者はセンサから近い位置で絵を見ようとすることがわかった.また,ロボットと鑑賞者の距離は全実験 36回中 35回でで一番近いのがロボットから見て左の鑑賞者,一番遠いのが右の鑑賞者となった.図 4.3はセンサとそれぞれの鑑賞者の距離の平均である.
以下でまとめた実験データを示す.表 4.1は 異なる大きさの絵を用いたときの距離と角度のデータを示す. 表記しているデータは大きさの異なる 3枚の絵で 3人の鑑賞者それぞれの平均の距離である.絵の中心がある位置で人が立ち,座標を得た.そしてそこから,絵からの鑑賞者の距離の平均と絵から右回りの鑑賞者の位置の平均角度を求めた.そこから,絵を中心として左右鑑賞者とできる角度を求めた.また,隣り合う人同士の距離も求めた.表 4.2は絵の大きさごとの隣り合う鑑賞者同士の距離のデータである.図 4.7で,若干ながらも,左と真ん中の鑑賞者の間の距離は絵が大きくなると隣り合う人同士の距離も増加傾向にあることがわかる.絵を中心として左右鑑賞者とできる角度は 69◦
で,中くらいの絵では 61◦で小さい絵のときは 124◦であった.図 4.4は絵の大きさごとに絵を中心として左右鑑賞者とできる角度をグラフ化した.実験を行った 36
回のデータのY座標平均を求めた.図 4.5は鑑賞者別のY座標の平均をグラフ化した.これにより,真ん中の鑑賞者は左右の鑑賞者よりも若干後ろにいることがわかる.また,絵の大きさ別の絵と鑑賞者の距離の平均を求めた.図 4.6は絵の大きさ別の絵と鑑賞者の距離の平均をグラフ化したものである.これにより,絵の大きい絵ほど絵と鑑賞者の距離は増加傾向にあることがわかる.絵の対角線の長さと絵と鑑賞者の距離について関係を調べた.図 4.8で示す.小・中の絵のときは,値が近いが,大きい絵のときに,差が大きくなっていることがわかる.
16

図 4.1: 実験結果例
表 4.1: 絵の大きさと鑑賞者における平均距離と平均角度 鑑賞者 大きい絵 中くらいの絵 小さい絵
左 センサからの距離の平均 1623mm 1469mm 1113mm
平均角度 66◦ 56◦ 26◦ 絵と鑑賞者の距離の平均 2120mm 1431mm 998mm
真ん中 センサからの距離の平均 2170mm 1563mm 1346mm
平均角度 56◦ 89◦ 106◦ 絵と鑑賞者の距離の平均 2538mm 1224mm 851mm
右 センサからの距離の平均 2545mm 2015mm 1729mm
平均角度 135◦ 117◦ 150◦ 絵と鑑賞者の距離の平均 1727mm 1340mm 937mm
17

図 4.2: 実験結果例を解説
図 4.3: 鑑賞者別のセンサと鑑賞者の距離の平均
18

表 4.2: 隣合う人同士の平均距離 大きい絵 中くらいの絵 小さい絵
左と真ん中の鑑賞者間の距離 546mm 478mm 278mm
真ん中と右の鑑賞者間の距離 503mm 479mm 377mm
図 4.4: 絵を中心として左右鑑賞者とできる角度
19

図 4.5: 鑑賞者別のY座標の平均
図 4.6: 絵と鑑賞者の距離の平均
20

図 4.7: 隣り合う人同士の距離
図 4.8: 絵の大きさと絵と鑑賞者の距離の関係
21

第5章 最適な立ち位置について
本章では,鑑賞者を観察して求めたデータの考察を述べる.そして,これまでのデータをまとめることによって構成することができる絵の見やすいと思われる最適な位置について調べる.
5.1 データの考察
センサの出力結果から,鑑賞者の左から順に,距離と角度と x座標の値が小さい順に並ぶことがわかった.また,全鑑賞者のデータから y座標から真ん中の鑑賞者が他の鑑賞者よりも若干後ろに,いることがわかったが,真ん中の鑑賞者が左と右の鑑賞者よりも後ろにいるときが,実験 12回中 6回であった.大きい絵のとき,4
回中 3回で,中くらいの絵のときは 4回中 3回であった.センサーからの距離が大きい順に左,真ん中,右の鑑賞者に並ぶのが,実験 12回中 5回であり,小さい絵のときに,4回中 4回で,中くらいの絵のときは 4回中 1回であった.つまり,最初に示した図 5.1の配置が 6回,図 5.2の配置が 5回であった.小さい絵のときは,真ん中の鑑賞者が左右鑑賞者よりも後ろの配置となる傾向にあり,大きい絵のときは,センサーからの距離が大きい順に左,真ん中,右の鑑賞者に並ぶ配置となる傾向にあることがわかった.絵はセンサに移らないので,座標 1あたりの距離を求め,約 18.2mmということがわかった.絵の中心座標と鑑賞者の立ち位置座標から,絵と鑑賞者の距離を求めた.小・中の絵のときは,絵の対角線の長さと絵と鑑賞者の距離は近い値になった.しかし、大きい絵のときは絵の対角線の長さの値と絵と鑑賞者の距離に大きな差が生じた.理由は,まず実験を行った場所が,美術館のような広い場所ではなかったために,大きい絵のときは十分な距離を取った状態から絵を見ることができていなかったため,うまくいかなかったと考えられる.また,絵によっても,見やすい位置が異なり,必ずしも絵の説明しやすい位置と見やすい位置が同じにはならないと考えられる.絵を原点とする左右の鑑賞者とできる角度は中・大の絵のときは,近い値であった.しかし,小さい絵のときは中の絵の角度の倍ほどであった.隣合う人同士の距離を計算したところ小さい絵では,3人が横一
22

列に並んで絵を見ようとするとぶつかってしまう.隣り合う人同士を一定以上に取りつつ,絵と適度に距離を取って見ようとすると鑑賞者は前後に動くよりも横に動いた方が絵が見やすくなるために横に広がった配置になったと考えられる.大きい絵,中くらいの絵では,前後に動く余裕ができて,隣り合う人に対して一定の距離を取ることが容易で,なるべく正面から絵を見たいと思うので,絵を中心として左右鑑賞者とできる角度は小さい絵ときの半分で済むと考えられる.隣合う人同士の距離も絵の大きさに比例して,大きくなることがわかった.ただし,数値的には絵の大きさに比べたら,それほど大きな差ではない.3人の鑑賞者の配置について調べた.大きさの異なる絵の種類を増やし,鑑賞者の配置について検討を行う必要がある.ロボットの配置が固定しており,ロボットの配置との関係も検討を行う必要がある.
23

図 5.1: 真ん中鑑賞者が後ろになる配置
図 5.2: 鑑賞者が斜めとなる配置
5.2 最適な位置領域の検討
全ての絵に適用できる傾向を発見することは出来なかった.今後,3人よりも多くの絵で説明することと,鑑賞者の配置に余裕がある方が閾値の設定が容易である
24

と思われることから,一番大きい絵での適切な位置領域について検討し,ロボットに実装することにした.絵の座標はロボットの配置,絵の配置によって変化してしまうので,用いるデータはセンサーと鑑賞者の距離と鑑賞者の位置の X座標である.鑑賞者の前後の動きは現在のセンサーと鑑賞者の距離と求めた平均値を利用して,決定する.鑑賞者の左右の動きは現在の鑑賞者の位置のX座標と求めた平均値を利用して,決定する.それぞれの鑑賞者の適切な位置領域が重なるかを調べ,重なる場合は,鑑賞者同士が近づきすぎて,パソーナルスペースに侵入して不快にならないようにするために数値の設定が必要となるかを調べる.
25

第6章 最適な位置への誘導
本章では,鑑賞者を観察してわかった,鑑賞者にとって絵の見やすいと思われる位置に誘導するシステム開発を行った.システムの説明を実際にロボットに実装してみてわかったことを述べる.
6.1 適切な位置領域の設定の準備
用いる絵は今回利用した一番大きい絵とした.理由は,大きい絵だと絵と鑑賞者の距離が離れるためレーザーセンサの測定の誤差の影響が少ない考えたため.また,大きい絵だと今より,鑑賞者を増やしても一列を維持できる立ち位置となり,今後役立つと考えたため,用いた.鑑賞者の人数は絵の見やすい位置を調べる実験でも鑑賞者を 3人としていたので,適切な位置領域の作成にも鑑賞者を 3人と決めた.先ほどの鑑賞者の立ち位置の観察と同様にロボットとセンサを配置した.センサは高さで,140cm,ロボットの真後ろ 30cmの位置であった.鑑賞者を正面にして配置した.角度順にソートされるため,鑑賞者は左,真ん中,右の順で誘導する.絵は人の目線の高さが絵の真ん中となるような高さにして 絵の端とロボットとの距離が同じになるようにして,それぞれ配置した.
6.2 誘導システムについて
平均値±標準偏差*2
のとき全データの 95.45%が分布し,今回は閾値の設定を容易にするために絵と鑑賞者の距離の平均値±標準偏差×2以内にいるときと絵の中心とそれぞれの鑑賞者とできる角度の平均値±標準偏差×2以内にいるときに最適な位置にいることとした.絵と鑑賞者の距離の平均 ds[a],その標準偏差をHd[a],現在の絵と鑑賞者の距離をDIS[a],その標準偏差をHx[a] とおく.絵と鑑賞者がなす角度の平均をα [a],
26

その標準偏差をT[a],現在の絵の中心とそれぞれの鑑賞者とできる角度を Z[a]とおく.aの値は鑑賞者の人数を示しており,左から順に 0,1,2として,左・真ん中・右の鑑賞者を表す.プログラムには以下の式を用いた.鑑賞者を絵の方向に近づけるときは,
DIS[a] > ds[a] + Hd[a] × 2 (6.1)
鑑賞者を絵の方向から遠ざけるときは
DIS[a] < ds[a] − Hd[a] × 2 (6.2)
鑑賞者を右に移動させるときは
Z[a] <α [a] + T [a] × 2 (6.3)
鑑賞者を左に移動させるときは
Z[a] >α [a] − T [a] × 2 (6.4)
今回,利用する鑑賞者の適切な位置のイメージを図 6.1で示す.絵と鑑賞者の距離の平均値は 2128mm,標準偏差は 573.6mm,絵と左鑑賞者がなす角度の平均値は68◦,絵と真ん中がなす角度の平均値は 108◦,絵と右鑑賞者がなす角度の平均値は137◦,角度の標準偏差は 13.3◦であった.したがって絵と鑑賞者の距離の最適な距離範囲ついて,980.8mm<絵と鑑賞者の距離<3275.2mm
となった.絵と左鑑賞者がなす角度の最適な角度範囲について,41.4<絵と左鑑賞者がなす角度<94.6
真ん中鑑賞者について,81.4<絵と真ん中がなす角度<134.6
右鑑賞者について,110.4<絵と右鑑賞者がなす角度<163.6
となった.適切な位置空間が重なることがわかる.鑑賞者を左から順にデータの処理を行っているので,適切な領域内にいない鑑賞者を左から順に誘導を行うように誘導を行うシステムの開発を行った.フローチャートを図 6.2 で示す.結果画面の説明を図 6.3 で行う.ロボットに実装する前に,適切にシステムが動いているかを確認するためにレーザのデータ画面とは別の画面で誘導する方向を示すシステムを作った.P1が左の鑑賞者で P2が真ん中の鑑賞者と P3が右の鑑賞者として,近づけたいときは”front”と出力,遠ざけたいときは,”back”と出力,右に移動させたいときは right,左に移動させたいときは,”left”と表示する.適切な領域内にいるときは”OK”と出力する.見やすくするために出力は一列に並ばないようにした.これにより,絵の見やすい位置に誘導を行うことができるシステムを開発できることを確認することができた.
27

図 6.1: 鑑賞者にとって適切な位置
6.3 ロボットへの実装
ロボットは音声により,対象の鑑賞者に呼びかけを行い,前後・左右の方向指示を行う.そして,鑑賞者に指差し,首振りを行い誘導を行うシステムを開発した.まず,左の鑑賞者がいる現在位置と適切な領域にいるかを調べて, 鑑賞者が設定した適切な領域外にいると判断したとき,適切な位置に行くように指示を出す.次に真ん中の鑑賞者に対して,同様に切な領域にいるかを調べて,指示を出す.右の鑑賞者に対しても指示を出す.そして,3人の鑑賞者が適切な領域内にいると判断したら,パブロ・ピカソ作の「頭蓋骨のある静物」の絵の説明を行う.
6.4 ロボットのデモ
ロボットへ実装を行いデモを行った.適切な領域外にいる鑑賞者それぞれを適切に誘導することができた.音声,ジェスチャーも鑑賞者に適切に伝った.適切な領域設定外にいる鑑賞者の誘導を行うシステムをロボットに適切に実装することができた. それぞれの適切な領域が重なっていたが,特に問題なく誘導することができた.デモ様子を図 6.4で示す.
28

図 6.2: フローチャート
6.5 考察
確かに鑑賞者に指示を出すことができたが,鑑賞者が適切な領域内に来るまで指示を繰り返し行ってしまう.なかなか絵の説明を開始することができず,適切な領域内に誘導し終えるまでに 10分くらい掛かってしまうことがあり,待つ時間が長いことで 鑑賞者に不快感を与えてしまうと考えられる.また,3人までなら音声で,左・真ん中・右と言うことで,誘導したい人を指示することができたが,それより多い人数では難しいと考えられ,誘導対象となる鑑賞者に適切に顔を向けて,指差しを行わないとならないと思われる. あらかじめ,絵の座標を調べておかないと,絵からの距離,絵となす角度がわからないので,絵の位置をわかるようにする装置,システムが必要になる.それぞれの鑑賞者の適切な領域が重なっていたが,前後・左右に十分に動くことができるスペースがあり,鑑賞者の判断でうまくスペースを取ることができたので,重なっている空間の配置の設定が必要なかったと考えられる.
29

図 6.3: システムの解説
30

図 6.4: デモの様子
31

第7章 本研究のまとめと今後の課題
7.1 まとめ
絵の鑑賞者の立ち位置を観察したところ,絵の大きさと鑑賞者の立ち位置は絵が小さいと近くに,絵が大きいと離れて立つということがわかった.小・中の絵のときは絵の対角線の長さと絵と鑑賞者の距離の値は近かった.大きい絵のときは絵と鑑賞者の距離は絵の対角線の長さよりも小さくなり,値に大きな差が生じた.また,絵が大きくなると隣り合う鑑賞者同士の距離も若干ながらも増加することがわかった.絵を中心とした左右の鑑賞者との角度は小さい絵のときは大きいということがわかった.そのときの角度は,中くらいの絵のときの 2倍の値になった.全ての絵に対応できる傾向を見つけることができなかったので,誘導のしやすいと思われる大きい絵について,検討を行った.距離と角度から,3人の鑑賞者が絵の見やすいと思われる位置領域を実験の結果のデータの平均値と標準偏差を用いて,作ることにした.この領域を鑑賞者にとって適切な領域として,それぞれの鑑賞者に応じた領域の設定を行った.そして,適切な領域内にいない鑑賞者を音声,首振り,指差しを用いて鑑賞者を 1人ずつ誘導するシステムを作った.ロボットにシステムの実装を行い,デモを行い,適切な領域内にいない鑑賞者を領域内へ誘導することができた.
7.2 今後の課題
実験で,小さい絵のときにガイドロボットの位置が絵から離れて過ぎているのではないかという感想を頂いた.また,小さい絵では,左の鑑賞者がロボットと距離を離すために距離を取り,絵との距離も離れてしまう傾向にあった.今回は絵が異なる場合でも,ロボットの位置を固定していた.ロボットの立ち位置も絵の大きさや説明に応じて,変える必要性を感じた.ロボットの立ち位置決定のための実験,観察を行い,適切な位置を決めるようにしたいと考えている.今回は鑑賞者を 3人
32

のときの絵の見やすい位置を推定したが,4人以上とき,小さい絵では,1列では並べなくなってしまう.2列以上となるときは対話を行うことが難しくなり,絵の見やすい位置を求めることは困難になる.また,1列に並べたとしても,3人までなら指示語で誘導できるが,それより多くなると音声だけでは誘導したい人を特定することは困難である.音声とジェスチャで誘導したい人を適当な位置に誘導できるかどうか検討する必要がある.大きさの異なる絵をより多く用いて,絵の大きさと絵と鑑賞者の距離などの傾向を細かに調べて,全ての絵に対応できるような適切な領域の設定ができるかを調べる必要がある.今後,一般の参加者を用いて,多くの実験を行い,今回作成したシステムの有効性を示すことが必要である.
33

謝辞
本研究の遂行,並びに本論文の執筆において,多大なご指導を賜りました久野義徳教授に心より深く御礼申し上げます.本研究の遂行,プログラミング,実験など幅広くお世話になりました小林貴訓助教に深く感謝申し上げます.
研究生活において,日頃から様々な形で御支援して頂きました糟谷氏,笛木氏,星氏をはじめとするミュージアムガイドロボットグループの先輩方,幅広く手伝って頂いた柴田氏,ロボットの動作に協力して頂いた大山氏,音声を作って頂いた森氏,実験を手伝って頂いた行田氏,福田氏,宮田氏,研究の参考とさせて頂きました留学生のYousuf氏をはじめとする久野研究室の皆様に大変お世話になりました.皆様のご厚意に深く感謝申し上げます.
最後に,博士前期課程に進学する機会を与えて頂き,貴重な学生生活を支援してくれた両親をはじめとする周囲のすべての皆様に深く感謝致します.
34

参考文献
[1] 山岡史亭,神田崇行,石黒浩,萩田紀博,”情報提示ロボットのための立ち位置モデル”,日本ロボット学会誌,Vol.27 No.2,pp.230-238,2009
[2] A.Kendon: Conducting Interaction-Patterns of Behaivior in Focused Encoun-
ters: Cambridge University Press,1990
[3] 坊農真弓,”会話構造理解のための分析単位 : F陣形 (<連載チュートリアル>多人数インタラクションの分析手法〔第 6回〕) ”,人工知能学会誌 23(4), 545-551,
2008
[4] E.T.Hall: The Hidden Dimension:Man’s Use of Space in Public and Private:
The Bodley Head Ltd.,1966
[5] 神田崇行,”コミュニケーションロボットと人間との距離”,情報処理Vol.49 No.1
Jan.2008
[6] 山岡史亭,神田崇行,石黒浩,萩田紀博,”協調的移動に基づく対話ロボットによる注意共有の実現”,日本ロボット学会誌,Vol.28 No.3,pp338-348,2010
[7] Huettenrauch,H.,Eklundh,K.S.,Green,A.and Topp,E.A.:Investigating Spatial
Relationships in Human-Robot Interaction, Proceedings of the 2006 IEE/RSJ
International Conference on Intelligent Robots and Systemes,pp.5052-
5059(2006).
[8] 佐竹聡,神田崇行,Dylan F.Glas,今井倫太,石黒浩,萩田紀博,”対話ロボットの人間へのアプローチ方法-対話ロボットの対話開始に対する戦略-”,日本ロボット学会誌,Vol.28 No.3,pp327-337,2010
[9] 坊農真弓,”会話構造理解のための分析単位 : F陣形 (<連載チュートリアル>多人数インタラクションの分析手法〔第 6回〕) ”,人工知能学会誌 23(4), 545-551,
2008
35