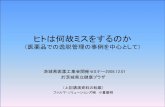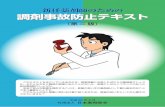医薬品に共通する特性と基本的な知識 c a b c 1 誤 正 2 正 誤 正2018/11/15 · 問2 医薬品のリスク評価に関する記述の正誤について、正しい組み合わせはどれか。
Japan Convention Services, Inc. - 当院における誤薬...
Transcript of Japan Convention Services, Inc. - 当院における誤薬...
第 24 回日本慢性期医療学会 in 金沢2-1-1 医療安全・事故対策(1)当院における誤薬事故の分析
三条東病院
せいだ しゅん
○清田 俊(准看護師),小川 京子,大石 和也,岡田 栄子,中山 恵子
『はじめに』当院は(介護病棟 120 床、医療病棟 120 床)240 床の療養型医療施設である。医療事故防止のための基本的事項として、(1)医療従事者は常に危機意識を持ち業務にあたる。(2)患者様優先の医療を徹底する。(3)医療行為においては再確認を徹底するとして真摯に業務にあたっていたが H26 年に点滴の患者様間違いという事故があった。これをきっかけに事故要因を分析しエラーの起こる状況について調査・検討を行った結果を報告する。
【方法】① H26 年 4 月~ H27 年3月と② H27 年 4 月~ 3 月までの 1 年間に報告されたヒヤリハットと事故報告を比較、分析を行う。H 27 年度からベッドサイドでのダブルチェックを行った。
【結果】どの時点で発見されたかH26 年度の点滴の誤薬施行前 86.5% 施行中 1.3% 施行後 12.2%H27 年度の点滴の誤薬施行前 95.6% 施行中 0% 施行後 4.4%施行前に発見できたケースとして・薬剤を間違えて払い出してしまう。・薬剤の過不足。(払い出し時)・薬剤を間違えて溶解してしまう。・薬剤を多く溶解してしまう。などいったものがあった。H 26 年、H 27 年ともに同様の事例があったがベッドサイドでのダブルチェックを徹底して行うことで事故に至るケースが減った。
【考察及び課題】思い込みなど初歩的な事例に対して未然に防ぐことは難しいことがわかった。指差し呼称をすることで冷静に判断できた。又、ベッドサイドでのダブルチェックを行うことを確立したことで H27 年度は事故に至る前に間違いに気づくことが出来たと考えられる。今後も指差し呼称、ダブルチェックを継続していく。又、内服薬や外用薬についても事故に至ったケースを検証しチェック体制や手順を見直し改善していく必要がある。
第 24 回日本慢性期医療学会 in 金沢2-1-2 医療安全・事故対策(1)安全な服薬自己管理に向けて ~アセスメントシート・フローチャート・チェックシートの効果~
鹿島病院 看護部
おむら かずみ
○小村 和美(看護師),佐々木 季実子,西田 重美,永田 舞,桑谷 昌子
1. はじめに 近年、高齢、独居や老々介護、認知症などの問題が多く、在宅で多様な薬剤を安全に自己管理することが重要視されている。 当回復期病棟でも服薬自己管理のインシデントを経験したことをきっかけに、服薬自己管理支援システムを導入し、有効であったので報告する。2. 方法 1) インシデント要因分析 2) 服薬自己管理支援システム(アセスメントシート、フローチャート、チェックシート)での服薬自己管理訓練実施 3) アンケートによる看護師の意識調査3. 結果1) インシデント要因は、看護師側は思い込み等の確認不足が多く、患者側は日時違い、紛失、飲みこぼしなど、疾患、身体能力や障害、認知機能、生活習慣と考えられた。2) アセスメントシート、フローチャートによって、患者の管理能力を判断し、適切な服薬管理方法の選択ができ安全な自己管理訓練を行うことができた。 チェックシートによって、継時的な観察ができ、自己管理が継続できるかの指標となり退院後の指導に役立った。3) 看護師へのアンケート調査では、服薬自己管理のアセスメントが容易になり、問題なく導入できたという意見だった。患者個人に合わせた管理方法を具体化し、早期より多職種で介入することで、自己管理患者が増加した。4.考察・まとめ 支援システム導入により、安全で適切な方法を指導することができた。 看護師は退院後の生活を想定した支援意識が向上し、カンファレンスで根拠ある意見が伝えられ、他職種に専門的支援を働きかけることができた。同時に家族や生活期の関係機関に明確な情報を伝達し、協力を得ることができた。さらには、患者自身が服薬自己管理できることにより、セルフケア意欲も高まると考えられる。支援システム導入は効果があった。 課題として、評価時の看護師の認識度が一定ではないことが挙げられており、今後も取り組みを続け、システムの習熟度の向上を目指したい。
第 24 回日本慢性期医療学会 in 金沢2-1-3 医療安全・事故対策(1)2015 年度 薬剤課の5S活動への取り組み
北中城若松病院 薬剤課
やまぐち みちる
○山口 ミチル(薬剤師助手),比嘉 望,榎本 三樹,村山 愛香,桑江 芙美子,中村 苗美,小田垣 勝世
【はじめに】5S 活動は整理、整頓、清潔、清掃、しつけである。当院においては 2007 年から医療安全の一環として “5S したい環境・業務 ” と題した 5S 活動に取り組んでいる。薬剤課においても年度計画を立て評価を行っているが、今回 2015 年度の薬剤課 5S 活動計画(1、監査台の整理:台上の物品は最小限とする 2、陳列棚の整理 3、業務動線 4、在庫管理 5、調剤済交付棚の整理整頓)による払い出しミス減少と在庫薬品の状況及び 5S 活動の結果、出来た時間を新しい業務に展開したので報告する。
【方法】従来の薬剤払い出しミス防止対策に対し、整理・整頓の再認識・徹底を行った前後のミス及び在庫薬品数について 2014 年度と 2015 年度で比較した。また 2015 年度に整理・整頓で業務短縮した時間の有効利用による新業務、すなわち修正処方の未返薬分を病棟に連絡した件数、持参薬を薬剤課保管した件数を調査した。
【結果】1、払い出しミスは 2014 年度処方箋数 58,665 枚中 82 件(0.13%:薬品取違い 内外用薬 4 件、注射薬 1 件)、2015 年度は処方箋枚数 56,400 枚中 69 件(0.12%:同 内外用薬 2 件、注射薬 1 件)で 0.01%の減であった。2、在庫管理としては特定使用患者に対して薬品棚にカードを作成し、より処方動向を把握し易くした結果、全採用薬が 2014 年度は 797 品だったが 2015 年度は 776 品と 21 品目削減した。3、医療安全に向け、修正処方で返却されていない薬剤を病棟へ連絡した件数は 15 件、持参薬保管は 201 件であった。
【考察】5S 活動として年度計画と半期に一度の評価を行っているが、「完璧」ということはない。課題と対策 (PDCA)が、我々医療従事者の使命と考える。今回の 5S 活動はミスの減少には大差はなかったが、新しい業務とした返薬数の確認、持参薬の確実な管理(鑑別後の病棟保管を薬剤課管理とし、1 週間毎に交付)は、医療安全に必要な事だと考える。今後も 5S 活動を基に、業務改革を行い、職種を超えたチーム医療・協働を行っていきたい。
第 24 回日本慢性期医療学会 in 金沢2-1-4 医療安全・事故対策(1)内服薬に関する患者誤認事故の要因分析から原因を明らかにする
刈谷豊田総合病院高浜分院 看護・介護部
かとう けん
○加藤 賢(看護師),杉浦 理沙,長沼 久江,古橋 香代,泉 ゆかり
【はじめに】平成 25 年度の A 病院の処方に関するエラーは 101 件で、患者誤認は 10 件あった。患者誤認は重大な事故を繋がるため、手順の改定や教育、内部監査を実施していたが、発生件数は減少していない。そこで、患者誤認事例について新たな切り口で要因分析を行い、原因を明らかにした。
【方法】患者誤認事例 10 件について、「発生場面」と「手順順守」を分類した。また、事例についてブレインストーミングで発生した要因を抽出しラベル化した。関連性のあるラベルをカテゴリ化し、中ラベル及び大ラベルにグループ化した。
【結果】10 件全てが経管栄養患者の事例であった。発生場面は「配薬車から出し薬杯に入れる時」3 件、「溶解時」2 件、「栄養剤と照合する時」2 件、不明 2 件であった。手順を順守していないものが 7 件で、全て「氏名確認を怠った」であった。要因ラベルは全部で 44 個、中ラベルは 9 個、大ラベルは 4 個であった。大ラベルは①手順順守の問題、②手順自体の問題、③物品の問題、④人的な問題であった。中ラベルは、①は栄養剤・薬杯の氏名確認不足、指差呼称をしていない、②は氏名を照合する回数・物が多い、③はベッドネーム・薬袋の氏名が見にくい、④は作業中断等作業に集中していない、であった。要因ラベル数は① 10 個、② 8 個、③ 14 個、④ 12 個であった。
【考察】薬が患者に投与されるまでに氏名を確認する場面は、配薬車から取り出す、薬杯に入れる、溶解、トレイに乗せる、栄養剤と照合する、注入の 6 場面である。氏名照合が多いこと、物品の氏名が見にくいこと、作業に集中していないことが氏名確認不足に繋がるのではないかと考えた。
【結論】患者誤認を引き起こす原因としては、氏名を照合する回数・物が多いこと、ベッドネームや薬袋の氏名が見えにくいこと、作業に集中していないことがわかった。これらの原因を解消することが、患者誤認を減少させることに繋がる。
第 24 回日本慢性期医療学会 in 金沢2-1-5 医療安全・事故対策(1)クリーンベンチの無い環境下の輸液の混注での、調整者の違いによる輸液への細菌混入の可能性を検証
千木病院 薬局
いなば なほこ
○稲葉 奈保子(薬剤師)
[ 目的 ] 輸液の混注作業を行う上で、クリーンベンチの無い環境下での調整者の手技、経験、服装などの違いにより輸液の細菌混入の生ずる度合にどれだけの影響を及ぼすかを検証してみた。[ 方法 ] 調査対象は、輸液の混注作業に携わっている薬剤師3名(A、B、C)、土日混注作業を行っている看護師2名(D、E) を抽出し、経験年数、服装、手技、消毒の状況、手洗い法などを調べたうえ、各々につき混注アンプル数3A 以上のもの2例(11A、10A)、3A 未満のもの2例(2A、1A)、計20例をサンプルとして採取し、一般細菌培養同定試験を行いその結果を検証した。[ 結果 ] 薬剤師 A、B、C、看護師 D、E のそれぞれ4サンプル全てから細菌(主に目的菌を表皮ブドウ球菌、バチルス、セラチア菌、黄色ブドウ球菌、緑膿菌、大腸菌とする。)は検出されなかった。[ 考察 ] クリーンベンチでの無菌操作ができない環境下での調査対象の5名に服装、手技などに多少の違いがあり、何かしらの細菌の混入があるのかと考えていたが、全てのサンプルから細菌の混入が認められなかったという結果より、準清潔操作が保たれ細菌の混入をさせずに輸液の混注作業が行われていると思われる。[ 結論 ] 多少の不安はあったが今回の結果より、今まで通りの作業を維持するため、時にチェック、指導しながら輸液の混注作業を行っていくとよいのではないか考える。
第 24 回日本慢性期医療学会 in 金沢2-1-6 医療安全・事故対策(1)注射薬ダブルチェックの効果的な方法についての検討 時間差確認法を用いたチェックマニュアルの統一
堺温心会病院
あみや まゆみ
○網屋 真由美(准看護師),馬場 美穂子
[はじめに]当院外来では注射点滴がひと月約 400 件行なわれており、それに関するインシデント報告が過去 1 年間に 89件発生した。そのうち注射薬ミキシング前の確認ミスによるものが 9 件あり、そのすべてがダブルチェックをしていたにも関わらず発生していたため、インシデント件数の減少を目的に、効果的な確認方法について検討した。
[方法]平成 26 年 10 月~平成 27 年 10 月。対象は、当院外来勤務の看護師 19 名。過去1年間のインシデント報告の分析と看護師の意識調査をもとに、ダブルチェック方法を統一し、その後の実施状況と看護師の意識調査から評価を行なった。
[結果]先行研究を参考に、1人が確認し終わった後にもう1人が時間差で確認することとし、また投与量の間違いがあったことから投与量に赤丸を記入するという「時間差確認法」を導入した。その後 1 年間のインシデント報告は1件のみに減少した。看護師の意識調査では、確認不足や思い込みがあったという意見が多かったが、導入後には確認時の注意力に変化が見られた。
[考察]薬剤確認は目視だけの確認より、独立して1人での確認作業を行ない確認㊞をつけることによって、自己への責任を強く自覚するとともに、確認作業時の注意力向上につながったと考えられる。ダブルチェック方法の問題点を改善したことにより、インシデント件数の減少につながった。ダブルチェックは効果的な面も大きく、本研究においても成果を出すことができたが「完全」なものではない。今後もデジタル化が進むであろうが最終的な確認責任はやはり人であり、患者さんの一番近くでケアを行なっている看護師は最終行為者となることが多い。エラーを指摘するという意識を高め、有効に機能するチェック体制の実現が重要である。
第 24 回日本慢性期医療学会 in 金沢2-2-1 医療安全・事故対策(2)予期しない院内死亡の現状と今後の課題について
坂本病院 看護部
なんば まさえ
○難波 優恵(看護師),菊谷 さとみ,赤嶺 智子,齋藤 みゆき,前野 良人,坂本 勇二郎
【はじめに】 慢性期・終末期医療では、合併症の管理・エンドオブライフケアに取り組んでいるが、予期せず死亡する患者も認められ、リスク管理が重要である。
【目的】 予期しない院内死亡の現状を知り、終末期のリスク管理・看護のケアにつなげる。
【対象と方法】 2013 年から 2015 年の 3 年間で 335 名が死亡し、その中で予期せず死亡した 47 名について、調査・分析を行った。予期しない院内死亡の定義は「死亡当日、バイタルサインが安定しており、積極的治療を行っていない」「病状が発症してから 24 時間以内の死亡」とした。また入院時面談にて、入院中の急変リスクはインフォームドコンセントを行っている。
【結果】 予期せず死亡した患者を急変群、死亡が予期された患者を予期群とする。急変群は 47 名で全体の 14%、男女比は、男性 21 名、女性 26 名であり、女性に割合が高く、有意差が認められた。入院日数は両群で有意差は認めなかったが、年齢は急変群は平均値 76 歳、予期群は平均値 80 歳で、有意差が認められた。急変群は 47 名全員が寝たきりで、41 名 87% に意識障害があり、40 名 85% に嚥下障害があり、嚥下障害、意識障害、寝たきりの3つの障害を同時に抱えている患者が大半であり、経管栄養の患者が 38 名 80% であった。気管切開は、有りが 23 名、無しが 24 名であり、有意差は認めなかった。死亡時間帯は、注入食後や体位変換後に増加傾向を認め、夜勤帯での死亡者率が有意に高かった。
【考察】嚥下障害、意識障害、寝たきり、肺炎の既往歴と呼吸状態の変調を来すリスクの高い患者が大半を占めている。病態の変化を早期にアセスメントし、必要な患者に嚥下評価や気管切開など、呼吸の管理を行う必要がある。また今後は、リスク因子を軽減できるよう、注入食の時間、回数、体位変換などについて検討・見直しをする必要がある。
第 24 回日本慢性期医療学会 in 金沢2-2-2 医療安全・事故対策(2)遷延性意識障害患者に認められた歯科補綴物誤嚥の1例
鶴巻温泉病院 診療部
かわはら けんじ
○河原 健司(歯科医師),中島 雅士,鈴木 龍太
【諸言】歯科補綴物の誤飲・誤嚥は歯科治療中だけではなく、様々な場所で認められる。今回われわれは、遷延性意識障害患者認められた歯科補綴物(金属ブリッジ)の誤嚥の1例を経験したので報告する。
【症例】患者:76 歳、男性。平成 25 年 2 月右視床出血を発症、脳室内穿破より非交通性水頭症きたした為緊急穿頭脳室ドレナージを施行された。3 月、遷延性意識障害 ( 最小意識状態 ) で当院転院。入院時歯科検診では中等度歯周病、左下ブリッジ部に関しては中~高度動揺と診断された。歯科治療として歯垢、歯石除去などを行い、その後は Ns.、DH による口腔ケアが継続された。平成 27 年 7 月、ブリッジの動揺が増加し抜歯を考慮したが、血小板数の低下、炎症反応の増加を認め抜歯を断念、隣在歯との固定が行われた。平成 28 年 5 月 14 日、DH がブリッジの脱落に気づき、担当医により口腔内の観察、胸部および腹部単純 X 線検査にて精査したが、ブリッジの確認は出来なかった。同年 6 月 1 日、発熱、酸素飽和度低下を認め胸部単純 X 線検査を施行、左下葉無気肺と左優位の両側胸水貯留の所見、左主気管支内にブリッジと思われる不透過像を確認した。同日、某大学病院呼吸器内科を受診、即日気管支鏡によって気管支内異物を除去した。除去後は当院に戻り入院を継続、状態は安定している。
【考察】当院では全患者に対して歯科医師による「入院時口腔内検診」を実施している。高度動揺歯や残根状齲蝕歯などについてはリスクを考え、可能な限り抜歯を行っている。今回の症例は入院時に中~高度動揺の為、しばらく保存可能と判断し非抜歯とした。その後動揺度が増し、抜歯を考慮したが全身状態不良の為、抜歯に至らなかった。ブリッジはその重量や形状の為、仰臥位の場合脱落することにより容易に咽頭部に落下する。今後は積極的な歯科処置の実施とチーム医療の充実を図り医療安全に努めたいと考える。
第 24 回日本慢性期医療学会 in 金沢2-2-3 医療安全・事故対策(2)回復期リハビリテーション病棟における急変時対応 ~シミュレーションで個々の役割行動を理解向上しよう~
千里リハビリテーション病院
ふじの あすか
○藤野 明日香(看護師),橋本 康子,新崎 恵,柴尾 京子
[ はじめに ] 当院は回復期病院 116 症 3 病棟で構成され、各病棟に看護師、PT、OT、ST、CW、MSW、CD が病棟配置となっています。 リハビリの対象になる患者は主に身体機能に障害を持つ患者です。高齢者や何か合併症を持つ、全身状態の安定しない患者が必然的に多くなります。また早期離床の観点から、全身状態が安定しない発症早期からのリハビリが求められるようになってきています。リハビリ中に患者が体調、気分不良を訴え、急変を生じることも日常的に生じる可能性が高く、緊急性を判断し対応能力を高めることが重要となってきます。急変時の対応は看護師でだけでなく、他職種も対応する必要があり、それぞれの役割がとても重要になります。職種それぞれが役割を理解し、適切な行動をとれるようシミュレーションを行いその効果と今後の課題について報告します。 [ 方法 ]所属病棟でアンケートを実施所属病棟全スタッフ参加 6 つのグループにわけシミュレーション学習会開催学習会で、シミュレーションの振り返りディスカッションを行い再度シミュレーションアンケート実施。前後での自己の役割、チームでの行動についての意識調査をおこないました。 [ 考察課題 ] シミュレーションだけでは自己の役割、行動理解につながりにくいことがアンケートでわかり、学習会をしシミュレーションを行うことで、振り返りができより自己の役割行動についての理解につながったと考えます。また病棟内での想定で今回実施しましたが、病棟外でのリハビリも行われるため、病棟外での想定でどのように連携をはかっていくかも必要であるこが研修を通じて改めて振り返りわかることができました。さまざまな場面での対応、連携を考えていくこも重要で課題であることもわかりました。さまざまな場面でのシミュレーション、学習会をおこなっていき、看護師はじめ他職種との連携、それぞれの役割、行動の理解し急変時の対応の向上に深めていきたいです。
第 24 回日本慢性期医療学会 in 金沢2-2-4 医療安全・事故対策(2)医療療養病床における皮下埋没型中心静脈ポート留置後の管理方法の検討
池田病院
いけじま ゆみこ
○池島 由美子(看護師),表 隼人,山口 美穂
Ⅰ . 目的終末期の高齢患者の中には、皮下埋没型中心静脈ポート(以下 CV ポートとする)を選択する場合がある。CV ポートは利点と欠点があり、当院ではカテーテル感染とポート管理後のトラブルに至る症例や、CV ポートを管理するにあたり看護職員の不安な言動が挙げられた。そこで本研究は、看護職員の CV ポート留置後の管理場面に焦点を当て、CV ポート留置後の管理について必要な方法を明らかとする。 Ⅱ . 方法1. 対象者と調査方法看護職員 11 名とし、インタビューガイドに沿って半構成的面接調査法を行った。調査期間は 6 月から 14 日間とした2. 倫理的配慮本研究は当院の倫理委員会の承認を得た後に実施したⅢ . 結果1.CV ポートの管理経験11 名中4名は経験があった2.CV ポート留置後の管理マニュアルの効果11 名中 10 名は効果があると答え、「手順どおりに実施でき、安全である」「マニュアルで手順が確認でき、職員の手技が統一できた」と答えた3.CV ポート留置後の管理する上で気になる点11 名中 8 名が「感染しないよう注意して管理している」「清潔操作を心掛けているが、感染が繰り返され手技が不安である」とカテーテル感染に関する回答であった。また 3 名は「輸液を投与する上での時間調整が難しい」「カテーテルの閉塞や狭小化のトラブル」「穿刺の手技の不安」「薬剤の露出」など CV ポートトラブルに関する結果が得られた。Ⅳ.考察1.CV ポート留置後の管理マニュアルの視覚的効果2.CV ポートトラブル回避するためのポート留置後の管理体制づくり3. 輸液ポンプを用いた安全な栄養輸液の投与方法の必要性 Ⅴ . 結論医療療養病床における CV ポート管理の留置後の管理は、カテーテル関連血流感染対策とトラブルを回避するため、視覚的効果のあるマニュアルを作成し、手順の統一化を図ること。また安全で清潔操作ができる管理体制を整える。加えて輸液ポンプを用いて正確に投与することであった。
第 24 回日本慢性期医療学会 in 金沢2-2-5 医療安全・事故対策(2)安全な看護・介護の提供 ~高齢者の表皮剥離対策から得られたもの~
藤民病院 医療安全対策委員
こいけ まゆ
○小池 麻友(看護師),上山 久美,牧本 知香子,田尻 てい子,早山 未来
【はじめに】 高齢者は表皮剥離を起こしやすく、看護師・介護職員にとって日常的に注意が必要な医療事故である。 今回、当院でも夏季に入浴介助に伴う表皮剥離が発生したことで、医療安全対策委員を中心に対策を行った結果、短期間で表皮剥離減少と共にスタッフのリスク対策への気持ちの変化も認めることができた為ここに報告する。
【研究方法】期間:平成 27 年 1 ~ 12 月対象:医療病棟・介護病棟入院中の患者方法:平成 27 年 1 月~ 7 月までの剥離に関するインシデントを分析、業務見直し・変更による表皮剥離対策
【看護の実際】 平成 27 年 1 ~ 7 月までに計 16 件の剥離報告があり、入浴介助による剥離は 7 件であった。この結果より会議やカンファレンスを行い、①患者の病衣のサイズアップ②入浴用ストレッチャーの柵にクッションを巻く③入浴時間の延長④脱衣所へ入れるベッド数の減少⑤剥離発生時は大きさや状態に関わらず直ちに医師へ報告し受診という 5 つの剥離対策を行った。
【結果と考察】 上記対策後、入浴介助時の剥離報告は 8 月 2 件、9 月 0 件となった。 入浴介助に伴う業務変更に関して「以前は時間に追われ流れ作業で業務を行っていた部分があったが、時間にも気持ちにも余裕がもてるようになった。」というスタッフからの意見があった。 今までは時間内に業務をこなすことが第一となっていたが、入浴環境を見直したことで患者を中心と考える業務が行えるようになったと考える。
【おわりに】 今回、表皮剥離という日常的におこりうる事故がきっかけではあったが、2 か月という短期間で剥離件数減少を認めただけでなく、スタッフの「剥離をさせない」という意識づけに繋がった。 また、患者の個別性を把握し、入院時から患者の剥離予防を提案するようになったことで、より安全な看護・介護の提供に繋げることができた。 今後も医療安全対策委員として研鑽に努め、医療安全の取り組みに努めていきたい。
第 24 回日本慢性期医療学会 in 金沢2-2-6 医療安全・事故対策(2)表皮剥離危険度アセスメントシート作成の効果
出水郡医師会立第二病院 看護部
たけひら ゆうすけ
○竹平 優介(介護福祉士),川俣 正浩,本田 神奈
Ⅰ.はじめに 療養病床では、高齢に伴い皮膚が脆弱化した患者が多く、表皮剥離のリスクが高い。表皮剥離の実態を分析し、表皮剥離危険度アセスメントシート(以下評価シート)を作成・導入したので報告する。
Ⅱ.研究方法 ・期間 平成 26 年 4 月~平成 28 年 3 月 ・対象 入院全患者 ・方法及び検討項目 1)平成 26 年度の表皮剥離インシデント分析 2)評価シート作成・導入 3)平成 26 年度 7 月~ 3 月と平成 27 年度 7 月~ 3 月の表皮剥離件数の比較 4)評価シート活用率と表皮剥離件数の関連性の分析
Ⅲ.結果 1)平成 26 年度のインシデント報告では、影響度分類 3a の中で 408 件中 160 件 39%が表皮剥離で報告件数が最も多かった。患者要因では寝たきり度、認知症が重いほど多く、発生部位は上肢が多かった。ケア要因では、オムツ交換、車椅子移乗、更衣、処置時に多く発生していた。 2)評価シートは危険度を三段階に分け、危険部位、対策内容が一目で分かるように作成した。 3)表皮剥離件数比較では 102 件から 78 件へと減少した。 4)評価シートの活用率は全体で 67%であった。病棟別に評価シートの活用率と発生件数の相関をみると、高い関連性がみられたのは、3 病棟中 1 病棟のみであった。
Ⅳ.考察・課題 今回、作成した評価シートの有用性は認識されているものの、効果にはバラツキがみられ、評価シートの活用不足と注意喚起不足が考えられる。また、評価シート導入後も表皮剥離発生を繰り返すスタッフがおり、上記に加え技術訓練不足も否定できない。今後は、評価シートに基づいた危険度別の対策の追加や技術訓練など対応方法の浸透を図りたい。
第 24 回日本慢性期医療学会 in 金沢2-2-7 医療安全・事故対策(2)介護職員を対象とした皮膚剥離を減少させるための学習会の効果
相原病院 看護部
やまや ひろみ
○山谷 浩美(介護福祉士),宮澤 和美
【目的】療養病棟は医療必要度の高い高齢者が大半である。こうした高齢者の皮膚は脆弱であり、わずかな外力によって皮膚剥離が生じ、痛みや出血などの不利益をあたえる。また、介護する側にとっても精神的な負担となる。そこで、介護職を対象とした皮膚剥離予防のための学習会を実施し、その効果を検証する。【方法】療養病棟に勤務する看護助手 12 名を対象に、皮膚剥離に関する知識および予防のための講義と実技の学習会を 2 回実施した。評価は、学習会前・直後・1 ヶ月後に知識確認の自作のアンケートと、学習会前後で更衣技術の実技をビデオで撮影し、既存の技術チェックリストを用いて行い、記述内容の比較と Wilcoxon の符号付順位検定で分析した。【倫理的配慮】所属施設の承諾を得た後、研究対象者に、研究の目的及び方法、研究の任意性について文書と口頭で説明し、文書で同意を得た。【結果】対象者は、男性 5 名、女性 7 名、資格保有者 3 名で、学習会前に皮膚剥離を起こしたことがあると答えた者は 7 名であった。学習会直後のアンケートでは、皮膚剥離の原因について、情報不足や予めの保護不足、衣類選定等の記述が増え、皮膚剥離好発部位では、手の甲、足の甲など具体的な部位が学習会前より増えた。皮膚剥離の予防では、技術向上、衣類選定等の項目が新たに挙がった。これらの内容は 1 ヶ月後アンケートでも同様であった。更衣技術のチェックリストの合計得点は、学習前 16 ~ 42 点,平均 28.7 点、学習後 29 ~ 45 点、平均 35.6 点で、有意に得点が上昇した(p = 0.005)。
【考察】本研究の対象者は、学習会により高齢者の皮膚の特徴や皮膚剥離の原因や予防のための注意点を理解することができ、知識の定着もみられた。これらの知識は実際の介護技術にも生かされており、技術向上にも繋がった。これは、本学習会が知識と技術の確認を組み合わせた事と、皮膚剥離を起こしたくないという対象者の意欲によるものと推察される。
第 24 回日本慢性期医療学会 in 金沢2-3-1 医療安全・事故対策(3)回復期リハ病棟での KYT -転倒防止の鋭い眼を養う-
1 信愛病院 看護部,2 信愛病院 医局
おいかわ ひろゆき
○及川 裕行(看護師)1,川野 かおり 1,井出 愛子 1,高野 典子 1,立花 エミ子 1,越永 守道 2
回復期リハビリテーション病棟 ( 以下回リハ病棟 ) において転倒事故が多い事は、どこの施設でも悩みの種となっている。しかし、回リハ病棟の特殊性を考えると臥床安静で入院生活を過ごさせる事は難しく、患者の安全を確保する為に抑制を行なっている施設も多い。当院は 2000 年より抑制廃止宣言を行っており、当病棟においても抑制に依存しない転倒防止のための様々な対策を行っているが、転倒件数は減りにくいのが現状である。そこで今回、「危険予知トレーニング ( 以下 KYT)」を学ぶ事により、スタッフの観察力を向上させる事により転倒事故の減少に役立つのではないかと考え KYT を病棟の勉強会で取り入れた結果、一定の効果が得られたので報告する。目的としては、KYT をスタッフ全員で行う事で危険個所に対する着眼点をスタッフ同士が共有する事で適切な対策を取れるようにした。方法としては①当病棟内で危険な状況を含む写真をスタッフに配布して、各自が危険と思われる個所をチェックする。②病棟で KYT の学習会を開催する。(説明・グループワーク)③再び写真を配布して危険と思われる個所を各自にチェックしてもらう。④ KY T前後のアンケートから観察力の変化を確認・分析する。結果は、KYT を回リハ病棟の学習会で行う事により、スタッフ全員が危険個所についての共通認識・着眼点を多く持つ事が出来た。また、日常的に転倒の恐れのある危険な個所に対して注目するようになり、それに対して適切な対策を取れるようになった。
第 24 回日本慢性期医療学会 in 金沢2-3-2 医療安全・事故対策(3)当院における転倒の実態と予防策の検討 ~回復期リハビリテーション病棟脳血管疾患患者を対象として~
青森敬仁会病院 看護部
まつやま あやの
○松山 綾乃(看護師),葛西 あずみ,吉田 周子,成田 勉
【目的】日本転倒予防学会(2010)によると、高齢者に介護が必要となった原因として転倒骨折が第 5 位(10.2%)に挙げられ、健康寿命の延伸のために転倒予防の重要性が述べられていた。当院回復期リハビリテーション病棟 ( 以下リハ病棟 ) の入院患者の多くは脳血管疾患患者(以下 CVD 患者)であり、症状の改善に伴い ADL が改善される場合も多い。その一方、CVD 患者の転倒件数過去 5 年分をまとめたところ、転倒・転落は一定数あることが分かった。そこで今回、当病棟における転倒予防策を検討するため、実態を明らかにした。
【方法】1)研究デザイン:量的記述研究デザイン2)研究期間:H27 年 6 月~ H28 月 5 月3)研究場所:当院リハ病棟4)研究対象:CVD 患者 17 名うち転倒した事例 29 件5)データ収集・分析方法:H26 年度インシデント・アクシデント報告書からデータ収集6)倫理的配慮:氏名、入院期間の公表はしない。病院長をはじめとした倫理委員会の許 可を得たものとする。
【結果】転倒時間は 9 時~ 21 時に多く、転倒場所はベッドサイドが最も多かった。60 ~ 70 歳代に最も多く、性別では男性 5 名、女性 12 名であった。転倒・転落アセスメントスコアシートでは、入院時評価で危険度Ⅲの患者が多かったが、HDS-Rは今回未判定の症例が多く、高次脳機能障害は 82%が有していた。その中でも約半数に注意障害が認められた。
【考察】転倒を起こしたCVD患者では重篤な麻痺や、高次脳機能障害を有している症例が多かった。事前に予防策を講じていても、ベッドサイド等目の届かない場所で起こる場合も多く、繰り返し転倒する原因であると考えられる。生活時間帯での転倒が多く、日勤帯での転倒予防策を検討する必要がある。入院時転倒・転落アセスメントスコアシートでの評価が有用であったことから、一定期間での再評価が必要であると考えられる。
第 24 回日本慢性期医療学会 in 金沢2-3-3 医療安全・事故対策(3)転倒・転落インシデント減少に向けた情報共有の取り組み ~検証アルバム作成を試みて~
聖ヶ丘病院 看護部
さとう ひとみ
○佐藤 仁美(准看護師),岡倉 華織,小田島 佐恵子
【はじめに】当院の医療安全委員会の過去 2 年間の、転倒・転落インシデント総件数は、H25 年 427 件、26 年436 件と増加し、A 病棟も同様に増加した。患者の多くは高齢で認知症を有しており、リスクが高い。対策を講じても、現在使用のインシデントファイルでは、情報共有が周知されず意識の低迷が明らかとなった。そこで情報共有を徹底しインシデント減少を目指すため、インシデントを再現した「検証アルバム」の作成を試みた結果、インシデント減少に成果が得られた。
【研究目的 】 ①検証アルバムによりスタッフへの情報共有の徹底を図る。②インシデントを減少し、患者の安全を守る。
【研究方法】アルバム作成前後でアンケート調査を 3 回実施し、分析方法は単純集計とした。【結果 考察】 作成前アンケート調査では 28 名が見て理解したつもり」と回答し、情報共有に至らず対策 も周知徹底されず、ケアに反映されていなかった。しかしアルバム作成後では、30 名が情報共有可能となり、インシデントへの意識が高まったと答えた。要因として①検証アルバム作成により発生時のインシデント写真が、視覚からの画像により記憶度を高め「見える・気づき・意識」と変化し意識向上に繋がった。②情報共有化の深度から漠然としていた対策が、事実情報・意味(目的)・考え方の波長が揃ったと考えられた。反面、アルバム作成の遅延により、対策浸透まで時間を要することが懸念されるため課題となった。今後は、環境整備とカンファレンスに充実を図り、転倒・転落のみならずアルバムを活用したインシデント減少に努めていきたい。
第 24 回日本慢性期医療学会 in 金沢2-3-4 医療安全・事故対策(3)認知症を有する患者の転倒転落減少にむけて ~行動・心理症状観察チェック表の活用~
1 加治木温泉病院 看護科,2 加治木温泉病院 院長
でぐずまん でぃヴぁいん
○デグズマン ディヴァイン(介護福祉士)1,上村 成美 1,清水 優里恵 1,東堂園 一矢 1,松元 奈美子 1,堂園 八重子 1,新本 紀子 1,髙田 昌実 2
Ⅰ . はじめに認知症患者は、自分自身のニーズや思いを的確に伝えるコミュニケーション能力、注意力が低下している為、同じような転倒・転落が繰り返される恐れがあります。当病棟の転倒・転落によるインシデント・アクシデント報告書は 2013 年 58 件、2014 年 97 件であり増加の傾向が見られる。そこで患者 2 名を対象に、行動・心理症状のパターンの把握を行い、スタッフ間で意識を統―することによって、転倒・転落減少につなげることが出来たのでここに報告する。Ⅱ . 研究方法1.実施期間:2015 年 6 月 30 日~ 2015 年 11 月末日2.研究対象:転倒・転落によるインシデント・アクシデント報告されている2名3.データー収集方法1.)2014 年~ 2015 年インデント・アクシデント報告書の集計・分析2.)行動・心理症状観察を行い、観察表を用いて分析Ⅲ.結果
【A 氏】当初は介護拒否強く、自分の思いが伝わらない場合などに、感情失禁、暴力行為、自傷行為等みられていたが、スタッフ間で意識を統―することによって、環境に慣れ、また毎日の声かけや、スキンシップを図ることによって表情が穏やかな日も増えてきている。
【B 氏】 当初は、排泄に関する不安が強く、日中は車椅子自走し、トイレに行かれる事が多かったが、スタッフ間で意識を統―することにより、現在、排尿間隔は 1 時間おきにトイレ誘導をおこなっている。Ⅴ.考察今回、行動・心理症状観察を行い、24 時間観察チェック表を用いることでどの時間に、どの場面で行動・心理症状が起こるのか把握し分析することで転倒・転落を減少することが出来た。
第 24 回日本慢性期医療学会 in 金沢2-3-5 医療安全・事故対策(3)医療安全における骨折のリスク管理 ~その①:ハイリスク管理のシステム構築について~
坂本病院 看護部
あづみ あすか
○安積 明日香(看護師),木村 節子,山口 順子,髙野 淳子,齋藤 みゆき,坂本 勇二郎
【はじめに】慢性期・終末期医療では、寝たきりによる合併症の管理を行っているが、その中でも二次的合併症である骨折を起こす症例が認められた。「骨折のリスク管理」の強化に取り組み 5 年が経過、多職種が協働しハイリスク管理が出来るシステムを構築したので報告する。
【対象と方法】2011 年~ 2015 年の 5 年間で発生した骨折症例 11 件について、調査・分析を行った。
【結果】 過去 5 年間の入院患者は述べ 1145 人で、そのうち骨折を起したのが 10 人の 11 件であり (1 人は 2 件 ) 全体の0.8%であった。全症例が身体介護場面で発生しており、全員寝たきりで関節拘縮を認め、9 割が麻痺側での骨折で、骨折部位は上肢、下肢ともに長幹骨末端に集中していた。8 割に意識障害と骨折の既往歴があった。以上の結果から、寝たきり・意識障害・関節拘縮・麻痺側・骨折の既往歴が骨折のハイリスク因子であることが明らかになった。
【対策】多職種全員がハイリスク因子を視覚的に捉え、捉えた情報を基に医学的根拠に基づいた個別的対応が取れるようにシステム化した。視覚的情報を強化して、健側と麻痺側を把握し、ケアが提供できるようベッドネームに健側 ( 可動 ) を表記し、赤枠で強調した。病棟では入院患者情報に骨折ハイリスクとなる情報を追加した。
【考察】ハイリスクは各々スタッフが経験的には認識していたが、全てのスタッフ共通の認識ではなかったことも、骨折が発生した要因の一つではないかと考える。患者には看護師・介護士・療法士など多職種が関わっており、骨折予防の意識づけを行うには、情報の共有が不可欠である。骨折は全体の 0.8%であるが、一個人の重大な健康上の問題であり、看護介護では起こしてはならないことであると考える。
第 24 回日本慢性期医療学会 in 金沢2-3-6 医療安全・事故対策(3)医療安全における骨折のリスク管理 ~その②:教育の視点~
坂本病院 看護部
きむら せつこ
○木村 節子(看護師),安積 明日香,山口 順子,髙野 淳子,齋藤 みゆき,坂本 勇二郎
【はじめに】慢性期・終末期医療では、合併症の管理を行っているが、入院中に骨折を起す事例が発生しており、リスク管理が重要である。当院で起きた骨折の発生数を調査したところ、2011 年~ 2014 年までは減少傾向にあったが、2015 年には増加した。そのため、骨折の原因におけるスタッフ側の要因を把握し、再発防止の教育へつなげる必要がある。
【対象と方法】2011 年~ 2015 年までの骨折事例 11 件について、原因の調査・分析を行った。
【結果】過去 5 年間で入院患者は述べ 1145 人で、その中で骨折を発生した患者は 10 人、11 件(1 人が 2 件)で、発生率は 0.8% であった。日常業務の申し送り時に全員で骨折予防の唱和を行っており「無理な力を加えない」「丁寧に扱う」「二関節支持」をケア時に遵守するように教育を行ってきた。しかし骨折場面で共通していることは、体位変換、オムツ交換、車椅子移乗の身体介護場面に発生していたことであった。インシデントレポートの情報から、3 つの手順遵守が徹底されていなかったことが明らかになった。
【考察】 骨折の予防には 3 つの手順の全てを遵守することが必要であるが、骨折の症例では 3 つの手順のうちいずれかが遵守できていないことが、骨折の発生につながったのではないかと考えられる。唱和を継続することでスタッフの骨折予防への意識付けになっていると思われたが、骨折が再び増加したことで教育が十分ではないということがわかった。そのため中途採用者を含め、経験の有無に関わらず、定期的に骨折に関する勉強会を開催し、「骨折の成り立ち」を学び、エビデンスに基づいて「二関節支持し丁寧に無理な力を加えない」意義を教育する必要がある。また視覚的なシステムを導入し、骨折のハイリスクをスタッフに浸透できるように、さらに教育を継続していく必要がある。
第 24 回日本慢性期医療学会 in 金沢2-4-1 医療安全・事故対策(4)外傷事故ゼロを目指して ~ヒヤリハットで一番多い事例を用いる~
水城病院 看護部
さかい ひとみ
○阪井 ひとみ(介護福祉士),石﨑 千栄子
【はじめに】 当病棟は、比較的落ち着いた36床の介護病棟であったが、医療病棟への転換に向けて動き出した。それに伴い入退院が増え患者層が変わり、ナースコールやトイレ介助等が増えた為に日々の介護業務も忙しくなりインシデントレポートが増えていった。その中でも、外傷件数が増えており、スタッフの意識付けを図り工夫することで、少しでも改善ができるのではないかと考え取り組んだのでここに報告する。
【研究目的】・患者様に対し統一した対策が出来、外傷事故を減少することが出来る
【結果】 これまで当病棟では、外傷事故を防ぐ為に様々な予防策を行ってきたが、減少には繋がらなかった。しかし、外傷の内容には、調査開始前の報告と期間中の報告では内容に大きく変化が見られた。 以前は、小さな内出血等は報告にあがることが少なく、皮膚剥離が中心であった。しかし、継続的な呼び掛けでスタッフ間の意識変化や技術の向上が出来た。さらに情報の共有と周知、観察と報告の徹底を行ったことで皮膚剥離での報告は減少したが、今まで報告にあがらなかった非常に小さな内出血等の報告があがってくるようになった。今回は小さな内出血まで、数を引き下げることは出来なかった。
【考察】①患者様自身の体動で、ベッド柵や車椅子の手すりなどにぶつかっているのではないか②スタッフ個人の能力の差があるので、患者様の状態に合わせたケアができていないのではないか③患者様個人個人に合わせた環境設定に不備があるのではないか以上の項目検討により、観察と環境設定とケアを統一することで今後は減少傾向に向かうと考える。
【おわりに】 今回の取り組みにより、 限られた時間の中で患者様に対しての観察や勉強会を行うことで、インシデントを減らすことに繋がることがわかった。今後もより情報を共有し発信させながら、スタッフ間の意識をより向上させ、早期発見と予防に努めケアを充実させていきたいと思う。
第 24 回日本慢性期医療学会 in 金沢2-4-2 医療安全・事故対策(4)インシデントレポートの提出増加をめざして ~特に 0 レベルに注目して~
福角病院
やつづか みなえ
○八束 皆恵(看護師),藏本 正美,黒岩 幸枝
<はじめに> 当院ではインシデントレポートには、ヒヤリハット報告書、事故体験報告書、事故報告書と3種類あり、どれに書いてよいかわからない状態であった。職員間で混乱があり、報告件数も少なかった。職員アンケートにより意識の改善がみられ、書式の変更にて、インシデント報告、特に 0 レベルの増加につながったため報告する。 <目的> 職員のインシデントレポートに対する意識を変え、インシデント報告、特に 0 レベルの報告増加をめざす。 <研究期間> H.27.11 月~ H.28.3 月 <方法> 1. 対象者:看護師、介護士 2. インシデントレポートに関するアンケートの実施と、結果報告で職員の意識改革を行う。 3. 様式の変更 4. H.28.3 月までのインシデントレポートを解析した。 <結果>アンケートの結果、インシデントレポートの必要性がわからない、様式が分かりにくい、書く時間がない、などの意見があった。 インシデントの必要性は重大事故を防ぎ、職員自身も助けることになる事を説明し、様式がわかりにくい、書く時間がないという問題に対しては、様式を簡潔に記入できるものに変更した。各インシデントの対策もレポート提出者が書くのではなく、病棟カンファレンスで考えるようにした。職員間同士の声かけによる意識付けも行った。その結果、1 月~ 3 月のインシデントレポートは 351 件で前年の 147 件の約 2.3 倍になった。 レベル 0 は、1 月~ 3 月で 119 件と著明に増加した。 <考察> アンケートを行い、報告・説明したこと、また、様式を簡潔にしたため、職員の意識が変わり、インシデントレポート件数が増加したと考えられる。 対策を病棟カンファレンスで考えるようにしたことにより、具体的な対策が立てられるようになった。また、インシデント 0 レベルの報告件数が、著明に増加したことにより、その解析が今後の看護、介護に役立つと思われる。今後もインシデントレポートに取り組んでいきたい。
第 24 回日本慢性期医療学会 in 金沢2-4-3 医療安全・事故対策(4)医療療養型病棟における介護職のヒヤリハット対策 SHELL分析導入による効果
花の丘病院
さかもと しょういち
○坂本 翔一(介護福祉士),浦城 さちよ,藤川 みほ,松本 隆史,田中 まり子,山本 惠子
はじめに 当病棟は 51 床の医療療養病棟2です。過去 3 年間(H25 ~ H27)のヒヤリハット件数は月 9 件で多いと考え、従来の報告書にSHELL分析を追加した。詳細な要因分析を行う事から意識改善につながり一定の改善が見られるようになってきたので報告する。Ⅰ.研究期間・対象・方法 研究期間:平成 26 年 12 月 1 日~平成 28 年 5 月 31 日 対象:医療療養病棟介護士 16 名 方法:1.1 年間に出たヒヤリハット発生要因の分析 2.再度方法1を SHELL 分析にかけたⅡ.結果介護経験年数では 1 年未満 10%、1 年以上 2 年未満 33%、2 年以上 3 年未満 16%、3 年以上 4 年未満 29%、4年以上 12%でした。主な要因としてミトン忘れ 12%、柵忘れ 8%、配膳ミス 4%でした。 意識調査では、確認不足 25%、急いでいて忘れてしまった 19%、慣れ 13%でした。 これらに SHELL 分析を追加したことで、 1) ヒヤリハットの発生しやすい環境として、週末など職員の少ない時が発生しやすい 2) 人的ミスの要因として複数の業務が重なっている時、確認不足が生じやすい事が明らかになった。 これらの対策として、介護本の読み合わせを追加したことにより、知識の共有ができ、意見を出し合うことで意識改善につながり、ヒヤリハット件数は月 5 件に減少した。Ⅲ.考察 SHELL分析を追加したことにより、①知識を深められた。② 1 件ずつの具体的な要因が共有出来た。③意見交換により自分が持っていない気づきが出来た。以上のことから、ヒヤリハット件数が減少したのではないかと考えられた。Ⅳ.まとめ 今回の取り組みにより、ヒヤリハットが提出された翌日にSHELL分析のショートミーティングを活用した事で、1 人 1 人の意識や注意力の向上がみられた。今後も継続して意識や知識の向上に努めていく。
第 24 回日本慢性期医療学会 in 金沢2-4-4 医療安全・事故対策(4)私たちの業務改善~インシデント報告からの取り組み~
江藤病院
やまぐち じゅんこ
○山口 潤子(事務職),壺田 美華,松本 美由紀,田村 泉,由宇 教浩
[はじめに]医事課の受付業務は煩雑で、様々なミスが続いていた。そこで、インシデント報告を4M・4E方式で分析を重ね業務を見直したので報告する。
[方法]①平成27年4月から11月までのインシデント報告29件の原因を分析②手順を見直し、業務改善
[結果]インシデント報告29件の内訳は、処方箋の入力ミス(10 件)、書類(4件)、受付(10 件)、請求(1件)、その他(4件)であった。月別にみると、4月(2 件)、5月(1 件)、6月(4 件)、7月(0 件)、8月(3 件)、9月(8 件)、10月(10 件)、11月(1件)であった。その原因として業務を中断することが考えられ、対策として「業務中断札」を9月に作成した。しかし、ミスが続くため第二の対策として、10月に「業務改善報告書」を提出して医療安全管理者による追跡調査が開始した。また、全ての事務机を待合室に正対するように配置を換え、職員全員が全体を見渡せるようにして、待合状況の確認や患者様への声掛けが可能になった。さらに、受付後にカルテ出しの時間短縮のために患者様全員に診察券を渡し、カルテ棚を増設し、棚全体を見やすくした。
[考察]当院の事故等検討部会には全ての部署からリスクマネージャーが参加し対策等を検討して部署へフィードバックしている。しかし、医事課では対策をたてても報告書は減少せず、10月には増加した。そこで、医療安全管理者に業務改善報告書の提出を求められ、原因、対策を話し合い作成した。その結果、11月には減少した。また、業務改善をすることによって医事課で生じたミスに伴うタイムロスが減少し、さらに待ち時間の短縮にも繋がったと考えている。部署での問題は個人レベルで考えるのではなく組織全体で取り組み業務改善を行うことで、患者様の満足度へ繋がっていくと考える。今後も日常業務を改善し、患者様に気持ちよく病院で過ごして頂けるように努力を続けたい。
第 24 回日本慢性期医療学会 in 金沢2-4-5 医療安全・事故対策(4)ヒューマンエラーによるインシデントの発生防止について
ナカムラ病院 B4病棟
うえだ こうじ
○上田 幸司(介護福祉士),森川 好彦,坂口 亜希子,泊 紀子,藤田 葉子,森重 華子
【はじめに】 当院では、医療安全対策委員会作業部会よりヒューマンエラーによる医療事故をゼロにするために、指示呼称を行うこととなっているが、インシデント件数の結果で確実に指示呼称を行なえていない状況があるのではないかと考えた。この度、指示呼称によるヒューマンエラーの発生防止についてとりあげ、チェックリストを使用し意識づけにつながったので詳細を報告する。
【目的】・ヒューマンエラーによるインシデントを減少することができる。・指示呼称の意識づけができる。【研究方法】1.H26年とH27年の同時期に病棟で起こったインシデントを集計する。2.業務の中でヒューマンエラーが起こる可能性が高い箇所をピックアップする。3.毎日、指示呼称ができるようにチェックリストを作成する。4.期間終了後アンケートを行う。
【経過】 指示呼称が定着するまでに時間がかかったためか、月の前半は与薬や患者の衣類間違えなど、ヒューマンエラーによるインシデントが多かった。しかしそれ以降は、ヒューマンエラーによるインシデント件数は減少していた。昨年との比較においてもインシデント件数は大幅に減少していた。
【考察】1.インシデント件数 前半はインシデントが多かったものの指示呼称を確実に行うことで徐々に減少していった。アンケート結果をみても、ほぼ全員が事前にミスに気付くことができたと回答している。また、昨年と比較してもインシデント件数は減少していた。2. 指示呼称の意識づけ チェックリストを記入することで意識づけに繋げることができた。アンケートでは、指示呼称への重要性に理解ある意見が多くみられたが、人数や時間的問題により指示呼称が行いづらいという意見も多くあった。そのため今後は、スタッフ間での声掛け等を促し、指示呼称の重要性を訴え続けていく必要があると考える。
第 24 回日本慢性期医療学会 in 金沢2-4-6 医療安全・事故対策(4)患者誤認防止に向けての取り組み ~お名前お伺いできますか?~
いわき湯本病院 看護部
たいらこ まゆみ
○平子 真由美(看護師),齋藤 愛子,大和田 理加子,佐藤 智恵子,村上 美奈
はじめに 患者誤認防止対策は、安全な医療を提供するために「名前の確認」がすべての基本である。患者確認が必要な場面において、患者にフルネームで名乗って頂くことが最も有効であり、患者の理解と協力があって実践できるものと言われている。 当院外来においての患者確認方法は、個人フォルダー・受付票での呼名による確認のみであったため、外来業務における問題点の一つとして患者誤認の危険性が考えられた。そこで、安全な医療を提供するために患者誤認防止に向けて、患者確認方法を周知徹底する必要性があると考え取り組んだ。目的 患者確認方法を周知徹底することで患者誤認防止ができる。方法 1. 期間:H27 年 5 月~ H28 年 4 月 2. 対象:外来に関わる職員 23 名(医師・看護師・放射線技師・検査技師・医事課) 3. 方法 1)患者確認方法の実態を把握するためにアンケートを作成する。 (実施前と実施後 2 回)で調査する。 2)職員及び患者・家族へ名乗ってもらうよう周知する。 ①職員向け・患者向けのポスター作成・掲示 ②患者確認方法の徹底 3)外来での患者確認状況のチェックリストを作成し評価する。結果 1.「患者を間違えそうになった」のは実施前 78%(18 名)、実施後は 0%(0 名)であった。 2.「患者に名乗ってもらう」のは実施前 17%(4 名)で実施後は 100% (23 名 ) であった。 また、患者も自ら名乗るなど行動の変化が見られた。 3. 確認状況を把握するためのチェックリストによる評価は、全部署できていた。考察 患者を巻き込んだ取り組みを行ったことで患者確認に対する双方の意識が高まり、患者誤認防止につながった。しかし、長期通院患者から「自分の名前を覚えていないのか」などの声もあり、更に十分な説明を行い患者の理解と協力を得ながら継続していく必要があると考える。
第 24 回日本慢性期医療学会 in 金沢2-5-1 医療安全・事故対策(5)療養病床における臨床工学技士の役割を考える ~安心・安全な医療を提供するために~
並木病院 看護部
ながお かなえ
○長尾 佳奈江(臨床工学技士),西田 雅典
病床区分の明確化・機能分化が進み療養病床においてもその役割は大きく変化し、介護を主体とする長期療養から急性期の後方支援・在宅療養支援などが主な役割となってきている。医療必要度の高い患者は全体の90%を超え、ターミナル期にある患者やレスパイト入院の受け入れなども求められその内容は多岐にわたる。 しかし、療養病床では、マンパワーや設備、機材なども限られ十分な医療提供体制が整えられているわけではない。このような環境の中で、医療の質と安全の確保は重要な課題となる。 並木病院は 212 床が全て療養病床であるが、透析センター(維持透析)を併設するために臨床工学技士が 5名配置されている。そこで、臨床工学技士が透析業務のみに留まることなく、院内の医療機器管理に積極的に関わることで、医療安全に貢献できるのではないかと考え今回の研究に取り組んだ。 急性期病院では、医療機器の中央管理などは一般化されているが、療養病床では臨床工学技士の配置や医療機器の中央管理がされている実例も少ないことが予測される。本研究では医療機器の中央管理化に伴い、臨床工学技士の各フロアーの担当制と毎日の病棟ラウンドを行う中で専門性を生かした知識・技術を強く求められているという気付きから、療養病床における臨床工学技士の役割を明確にすると共にその働きがどのように安全の確保につながるかを考察する。
第 24 回日本慢性期医療学会 in 金沢2-5-2 医療安全・事故対策(5)医療機器管理の実際 ~当院での業務内容と今後の課題~
芳珠記念病院 医療機器管理室
きむら ふみひと
○木村 史人(臨床工学技士),小野 佳代子,篠田 憲,森 舞果,山外 希実,尾島 駿介,神保 佳奈
臨床工学技士はメディカルスタッフの一職種であり、医師の指示の下に、生命維持管理装置の操作及び保守点検を行う事を業とする医療機器の専門医療職種です。臨床工学技士関連法令では、生命維持管理装置の操作とは診療の補助行為で各生命維持管理装置による治療の一連の流れに沿って示されている。例えば、医師から透析の指示があれば、透析治療前の準備・透析治療の開始・透析治療中の患者観察と記録・患者愁訴の対応やトラブル対応・医師、看護師など多職種との情報交換・透析治療の終了までを行い、更に治療が終われば機器の保守点検を行っている。特に、医療機器保守点検は臨床工学技士が専門的に行っている業務であり責任重大である。保守点検業務は、院内の医療機器が安全で安心して使用できることを目標としているが安全確保のためには、管理部署を明確にすることや医療機器使用前・使用中・使用後の点検を実施すること。また、医療機器を使用するスタッフに対して適切な研修を受講していただき、正しい使用方法を習得していただくことも重要である。更に、医療機器の特性を十分理解し、定期的な電気試験や精密試験、部品の劣化などを事前に予測した予防保守なども大切である。当院の臨床工学技士は7名常勤でローテーションによる医療機器保守点検業務を行っている。当院での臨床工学技士が行っている実際の医療機器管理業務は、医療機器の台帳管理 ( 購入から廃棄までのライフサイクルの管理 )、保守点検の実施、医療機器の中央管理業務、修理状況の管理、院内安全ラウンド、院内医療機器研修、在宅療法導入と導入後の管理などを行っている。また、医療安全や感染に関する会議・委員会への参加や医療機器購入時に審議する会議などにも参加している。今回は、臨床工学技士の医療機器管理での役割と現状の問題点や今後の課題について報告する。
第 24 回日本慢性期医療学会 in 金沢2-5-3 医療安全・事故対策(5)保健衛生分野における職業性腰痛に対するセラピストの参画状況について ―アンケート調査からの検討―
鳴門山上病院
よねず きんご
○米津 金吾(作業療法士),松下 征司,佐々木 寛和,直江 貢
はじめに 保健衛生分野 ( 介護・看護 ) では,最近の 10 年間で腰痛発生件数が増加(2.7 倍)している状況にあり産業医学の視点からセラピストが腰痛予防に参画する意義は高いと考える. 本稿ではセラピストの職業性腰痛に対する意識や取り組みの状況を把握する事を目的にアンケート調査を実施し,保健衛生分野における効果的な対策を推進するべく今後の課題を検討したので報告する.
対象と方法 徳島県内医療機関に従事するセラピスト 68 名 ( 男性 42 名,女性 26 名,年齢 32.0 ± 7.5 歳,経験年数 8.8 ± 6.2年 ) を対象とした. 調査方法は,対象者の①福祉用具使用経験の有無,②福祉用具や腰痛予防に関する知識・技術の有無③研修会の実施頻度,④他職種に対する介助方法・福祉用具使用の提案や使用方法伝達の有無等,職業性腰痛に関する設問を網羅したアンケート用紙を作成し,郵送にて回収した.本調査は当法人倫理委員会の規定に従い実施したものである.
結果①福祉用具使用経験の有無については , トランスファーボード 64 名 (93%), スライディングシート 45 名 (68%)であり使用経験が高い機種である傾向を示した.②福祉用具や腰痛予防に関する知識・技術の有無については , 十分あると回答したのは 2 名に留まった.③研修会の実施頻度については , 約半数がほとんど開催していないと回答した.④他職種に対する介助・福祉用具の提案や使用方法・伝達の有無等については , 時々ある:28 名,あまりない:24 名であり , 職業性腰痛予防に向けた他職種との協業は低値を示した. 考察 今回の調査結果は , 職業性腰痛に対する知識と併せ専門性を活かした他職種との連携に多くの課題を残す結果となった. 今後 , 職業性腰痛に対する意識や知識・技術の向上を図るべく啓発活動を強化するとともに , これを基盤とした多職種との連携・協業促進など保健衛生分野における職業性腰痛対策の体系化が急務である.
第 24 回日本慢性期医療学会 in 金沢2-5-4 医療安全・事故対策(5)伝わるコミュニケーションを ~SBARを導入して~
北中城若松病院 看護部第 1 病棟
なかち みのり
○仲地 美祝(看護師),西島本 政一,比嘉 則子
【はじめに】:医療安全のコミュニケーションツール「SBAR」というコミュニケーション技法を、1病棟で活用し、看護師の医師への報告をスムーズにしたいと考え実践した。また、報告の標準化により、ヒューマンエラーを予防、軽減し、医師への情報伝達を安全に効率良く、スムーズにしたいと考え実践したのでここに報告する。
【方法】1.10月、医師からアンケート調査実施、看護からの療養者の報告について問題点抽出。2.リスク部会へSBARの取り組み実施を伝え、報告や伝達のインシデント、ヒヤリハットの院内の発生件数を把握。3.10月下旬、SBAR を学んだ1病棟看護師からSBARについて勉強会を行い、コミュニケーション技法、療養者の状況報告の重要性を学ぶ。新人看護師へは、医師へ報告する時などに指導を行う。電話のそばにSBARの報告方法と手順をラミネートして見やすいように置く。また看護スタッフへポケットサイズの SBAR 表を配布し、意識づけをさせる。4.1月上旬、看護師へアンケートを行い、問題点や報告しにくい事例を上げ、検討、指導していく。5.1月下旬、状況報告の中から、さらに具体的な指導を行い、SBARに沿った療養者の状況報告ができるように指導継続していく。
【結果】:急性期病院では、新人看護師などに導入されているSBAR技法であるが、当院ではSBAR技法を知る看護師は一部であった。医師からのアンケート結果で、状況報告については、① 大事な事を先に報告してほしい70% ② 回りくどい40% ③ 緊急かどうか分からない40%④ 状況把握がしにくい30% ⑤ 何をして欲しいのか分からない30%⑥ 状況報告は分かりやすい30%参考文献:ヒューマンエラー防止の SBAR/teamSTEPPS:日本看護協会出版会2014
第 24 回日本慢性期医療学会 in 金沢2-5-5 医療安全・事故対策(5)高齢者の足を守りたい -メディカルフットケアの導入-
総泉病院 看護部
さいとう みずえ
○齋藤 瑞恵(看護師)
【目的】千葉県で療養型病院として最大である当院では、入院患者の平均年齢は 81 歳前後である。以前より医療安全委員会へ提出される報告書の中で、「爪に関する外傷」が絶えることがなかった。そこで、リスクの高い足爪に関して外傷を減らす取り組みをおこなった。
【方法】対象は入院患者 306 名、実施期間はH 25 年 9 月~ H28 年 4 月。まず、取り組みを始めるために、現状の把握を行った。異常な形状の爪が足爪に多く、通常の道具しかなかった為、フットケア専用器具を導入。抗真菌薬も積極的に検討し、定期的にメディカルフットケアを提供する院内連携を整えた。実施には必ず爪の前後の写真を撮り、カルテに写真とアセスメントと実施内容を記録した。H 26 年 9 月より医療安全への報告形式がデジタル化され、内容分析ができるデーターのみを集計比較した。
【説明と同意】メディカルフットケアの対象であることを説明し、家族から同意書を得た。今回の発表の症例に関しては、個人を特定できない足の写真のみを使用。
【結果】介入した患者数 147 名。実施回数 405 回。取り組みを始める前年度の報告書は 36 件、爪に関する外傷の原因は、道具と技術と知識の不足だった。取り組み後は、毎月の報告数を合算し、半年ごとに比較すると 21 件、21 件、7 件と大きく減少した。
【考察】自分で整容ができなくなった高齢者は、爪切りなども他人に頼るしかない。高齢化社会であるにもかかわらず、現在は、医療の中でフットケアは特定の疾患に限定される傾向だ。今回の取り組みで分かったことは、年月や白癬感染などで変形してしまった爪に対応する教育も道具も取り組みもなされておらず、事故に繋がっていたということだ。医療の中に適切なメディカルフットケアを提供できるシステムを作ればこのように結果が出る。その上に、異常な形状がきれいな形状の爪に変わり喜ぶ患者の症例を多く得られた。