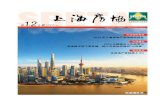ポーランド・ヴロツワフの街並み(解説p.2) 地理 …...2...
Transcript of ポーランド・ヴロツワフの街並み(解説p.2) 地理 …...2...
-
2011年度 3学期号
地理・地図資料ポーランド・ヴロツワフの街並み(解説p.2)
-
写真はすべて2010年9月撮影/帝国書院
ポーランド表紙写真でめぐる旅 ⑩
2010年9月、ポーランドを取材した。この国が経験して
きたさまざまな歴史から、急速な経済発展を遂げる現在の
ようすをレポートする。
●⑤
●⑦
●③ ●④●②
●⑥
●①
-
2
ポーランド西部シロンスク[シュレジエン(独)]地方にある都市ヴロツワフ(Wrocław)は、市内をオドラ川[オーデル川(独)]が流れ、長い歴史を抱いた美しい町である。しかし、この町の名称をめぐっては、第二次世界大戦後、ドイツ人とポーランド人の間に厳しい対立もあった。ドイツ人には、ここはブレスラウ(Breslau)という名で知られている。 事実、歴史をひも解けば、この町の帰属が幾度となく変更されてきたことをみてとれよう。ヴロツワフは、西暦1000年頃ポーランドのキリスト教化の始まるなかで、ポーランドの司教座として歴史に登場した。だが14世紀になると、ポーランド王カジミエシ3世(大王)は、ここの宗主権をボヘミア王に譲る。16世紀にはハプスブルク家がボヘミア王を相続し、シロンスクはオーストリアに帰属した。しかし、オーストリア継承問題に介入したプロイセン国王フリードリヒ2世が1742年にここを獲得して以来、1871年のドイツ帝国成立を経て第二次世界大戦終結にいたるまでヴロツワフは、ドイツの都市ブレスラウとよばれたのであった。 第二次世界大戦終結に際し、ドイツ・ポーランド国境は大きく西へと移動し、ヴロツワフはポーランド領となった。このとき、ナチスの占領を被ってきた東ヨーロッパ諸地域から1200万人以上のドイツ人難民・強制移住民が西方へと追いやられたが(ドイツ連邦共和国では、これを「追放」とよぶ)、ヴロツワフもその渦中にあった。 戦争中、ヴロツワフでは約30000戸の建物のうち、21000戸がほぼ全壊ないしは大きな損傷を被った。市内の600の歴史的建造物のうち、大きな被害をまぬかれたのは180に過ぎなかった。表紙写真の有名なゴシック建
築の市庁舎はその一つであった。戦争末期からドイツ住民が自主的に退去・強制的に退去させられたあと、町にはやはり国境変更によってソ連領となった、かつてのポーランド東部地域から、多くのポーランド人移住者が新住民として流入した。ドイツ人の都市ブレスラウは、ポーランド人の都市ヴロツワフへと実態としても変貌した。これは、住民構成ばかりでなく、建造物の再建にもみられた。歴史的建造物の再建にあたっては、新ゴシック様式はドイツ的とみなされたため、ほとんど維持されず、19世紀の多くの建物が破壊されたのに対して、ゴシック様式はポーランド的とみなされて、その維持が図られたのである。 戦後、町の再建をめぐる議論では、たとえば、1955年のドイツ連邦共和国のNATO加盟のときのように、ドイツ人の「仕返し」「帰還」が話題となることがしばしばあった。事実、ドイツの「被追放民同盟」は、国境の修正や失ったドイツ人財産の補償を繰り返し求めてきており、近年では、2004年のポーランドのEU加盟に際して、この同盟が、ドイツ人「被追放民」の失った財産の返還と補償、謝罪を加盟の条件としたことで、両国間に緊張をもたらした。 しかし、その一方で、ポーランド・ドイツ間の歴史教科書対話のような和解の試みも進展してきた。ヴロツワフの学校や大学は、ポーランド・ドイツの青少年交流・学術交流の先頭を走り、同市にはポーランド・ドイツ間の協働の多くの会議や活動もみられる。確かに、この町にはいまも多くのドイツ人「ノスタルジー旅行客」が頻繁に訪れる。だが、かつてドイツ人、ポーランド人、そしてユダヤ人が住んだこの町は、ナショナリズムの相克を超えて、次世代の未来を創っていくのではないだろうか。
ヴロツワフ:ポーランドとドイツの狭間に立つ都市解説東京学芸大学教授 川手圭一
取材レポート帝国書院取材班
午前12時に成田を発ち、ミュンヘンを経由しポーランドのクラクフに到着したのは深夜。9月上旬にもかかわらず、気温は10℃前後。クラクフの街へ向かう途中、我々を出迎えてくれたのは濃霧だった。 クラクフは、第二次世界大戦において国内の他都市が壊滅的な打撃を受けたなかで戦火をまぬかれた。そのため、旧王宮のヴァヴェル城などの歴史的な街並みが残り、古都の風情が漂う(写真③)。また、ポーランドの歴史で忘れてはならないのが、アウシュヴィッツ強制収容所である(写真⑥)。現在も当時のガス室やユダヤ人の持ち物が残されており、負の世界遺産として語り継いでいくべきものであると痛感させられた。ポーランドといえば、シロンスク地方の炭
鉱も有名だ。取材したカトヴィツェのウジェク炭鉱では、地下630mから地上まで石炭を引きあげる工程を1日300回、24時間行っている。石炭の採掘量は以前と変わっておらず、向こう30年は掘れるとのこと。ポーランドでは脱石炭依存により原発推進へ向かっているが、石炭は脱原発へ向かう他国での需要が高まっている。採掘された石炭は国際列車などによって西ヨーロッパへ輸出される(写真⑦)。 産業面では、近年「EUの工場」としてPCやテレビなどの情報家電がさかんに生産されている。東芝などの大手企業は、EU内の他国に比べて人件費や土地が格段に安いという理由から、ヨーロッパではポーランドを拠点としている。取材したヴロツワフ近郊の東芝テレビ中欧社では、日本でもお馴染みのレグザが大量生産されていた(写真⑤)。また、2012年にサッカー
のヨーロッパ選手権がポーランドで開催されることもあり、インフラ整備がさかんで2009年度のヨーロッパ経済では唯一プラス成長であった(写真②)。 取材時に食した、ジューレック(発酵させたライ麦ベースのスープ)やグジボヴァ(キノコスープ)の伝統料理は格別においしかった(写真④)。さまざまな苦難を乗り越えて発展へ向かうポーランドの思いが、料理の温かさからも伝わってきた。
バルト海
オドラ川
ヴィスワ川
ワルシャワワルシャワ
クラクフ
リトアニア
ベラルーシ
ウクライナ
スロバキア
チェコ
ドイツ
ポーランド
ヴロツワフ
①②⑤⑦⑥③④
ロシア連邦ロシア連邦
0 300km
-
3
南スーダン共和国の独立の背景と現在の状況
地図にみる現代世界
二度のスーダン内戦と南部スーダンの独立
スーダン共和国の南部スーダンは、2011年7月9日に
南スーダン共和国として独立した。初代大統領は、スー
ダン人民解放運動/スーダン人民解放軍(SPLM/SPLA)
の議長兼最高司令官であり、スーダン共和国の第1副大
統領でもあったサルヴァ・キールである。日本の面積の
約1.7倍の国土に約800万人が居住する、世界でもっとも
新しい国家が誕生したのである。これによって、一つの
国であったスーダンは、アラブ系のイスラーム教徒(ム
スリム)が多数を占めるスーダン共和国(北部スーダン)
と、アフリカ系(黒人)の諸民族集団から構成され、キ
リスト教徒が多い南スーダン共和国という二つの国家に
分裂した。この独立は、同年1月に実施された住民投票
(Referendum)において、南部スーダンの有権者の98%
という圧倒的多数が、分離独立を支持したことの結果で
ある。住民投票は、スーダン共和国の政権党である国民
会議党(NCP)と反政府組織であるSPLM/SPLAとのあい
だで2005年1月9日に調印され、22年間にわたった内戦
に終止符を打った「包括的和平合意」(CPA)の規定に
基づいて実施された。
CPAでは、南部スーダンに民族自決権が認められて
おり、6年間の移行期間の最後に、南部が統一された
スーダンの枠内にとどまるか、分離独立するかの選択を
問う住民投票が実施されることになっていた。したがっ
て、南スーダン共和国の独立は、南部スーダンの人々が
民族自決権を行使した結果である。この権利は、人々が
多大の犠牲を払って22年に渡った内戦を戦いぬいた結果、
勝ち取ったものである。内戦の死者は250万人といわれ
ている。また、数百万人が故郷を追われて、難民と国内
避難民となっていた。
1983年に開始され2005年に終結した内戦は、第2次内
戦とよばれている。南部スーダン人の、自らの運命を
自分で決定する権利を求める闘争の歴史はもっと長い。
スーダンは、1899年に開始されたイギリス=エジプトの
共同統治から、1956年に独立した。その前年に、エクア
トリア地方のトリットで、植民地政府軍の南部人兵士に
よる反乱が発生した。これは第1次内戦の開始を告げた
事件とみなされている。この当時、南部の分離独立運
動は、まだ明確なかたちをとっていなかったが、イギリ
ス人に代わってアラブ人に支配されることに対する反発
は強かった。1958年の軍事クーデタで実権を掌握したア
ブード政権は、南部に対するイスラーム化とアラビア語
化政策を強圧的に推進し、キリスト教宣教団を追放し、
反乱を武力で弾圧した。こうした状況下で、反政府の感
情は、1960年代前半に南部の分離独立を求める政治・軍
事運動に発展していく。東アフリカに亡命していた指導
者たちによって、「スーダンアフリカ民族主義者同盟」
(SANU)が結成され、国内各地では「アニャニャ」と
よばれるゲリラが組織され、武力闘争を展開した。
数十万人の犠牲者を生んだ第1次内戦は、1972年にエ
チオピアの首都で調印されたアディスアベバ和平協定に
よって終息した。分離独立という目標は達成できなかっ
たが、南部は自治政府を獲得したのだった。
内戦集結後の数年間は、北部と南部の関係は良好だっ
たが、1970年代末になるとさまざまな問題が露呈してく
る。南部自治政府は、財政難のため復興・開発プロジェ
クトをいっこうに実施できなかった。当時スーダン大統
領であったヌマイリーは、イスラーム主義政党であるイ
スラーム国民戦線(NIF)と手を結ぶことで、権力の強
化を図った。このことは、イスラーム化とアラビア語化
が再び国是となることを意味したので、南部人の同意は
得られなかった。
ヌマイリー政権が推進していた南部における二つの巨
大開発プロジェクト──油田とジョングレイ運河──
は、南部人の合意形成なしに進められたので、南部人の
反発は強まった。南部の政治家たちは、石油は南部のも
のなので、精油所は南部に建設されるべきだと主張した
が、中央政府には認められなかった。ジョングレイ運河
大阪大学大学院 教授 栗 本 英 世
-
4
は、南部スーダンのほぼ中央部、白ナイル川の東側に建
設が進められていた、全長360kmの大運河である。南部
人の視点からは、どちらの開発プロジェクトも、たんに
南部を搾取するためのプロジェクトにすぎなかった。
こうした状況下で、1970年代から南部人による反政府
武装闘争が散発的に再開されていた。1983年5月17日、
上ナイル地方に駐屯していた政府軍の2個大隊が反乱を
起こした。この反乱は、第2次内戦の起点とされている。
この部隊の将兵は、主として元アニャニャのゲリラから
構成されていた。部隊はエチオピア領内のガンベラに
撤退し、エチオピア政府の支援を得て、スーダン政府軍
の大佐だったジョン・ガランを指導者に据えてSPLM/
SPLAが結成されるに至った。
1970年代末、ヌマイリー政権は社会主義路線を放棄し、
親米路線に転換した。そのため、内戦当初SPLM/SPLA
は、ソ連をはじめとする東側諸国から支援を受けた。ヌ
マイリー政権は、大衆蜂起によって1985年に崩壊する。
その後、1986年には総選挙によって文民の連立政権が成
立したが、1989年にはNIFと結びついた軍部によるクー
デタが成功し、バシール将軍が実権を掌握する。のちに
NIFはNCPと改称した。この政権が現在まで継続してい
るバシール政権である。
バシール政権は、反対勢力に苛酷な弾圧を加え権力
基盤を固めるとともに、イスラーム化政策を推進した。
1990年代にはイスラーム主義運動の世界的な中心地とな
り、ビン・ラーディンとアルカイダも庇護した。中国と
マレーシアの援助のもと、内戦の開始以降中断していた
油田開発を推進し、1999年以降は石油の輸出国となった。
反政府勢力を軍事的に殲せん
滅めつ
することを目標に掲げ、内戦
の勝利に向けて全力を注いだ。SPLM/SPLAは、後ろ盾
であったエチオピアの社会主義政権が1991年に崩壊し、
また同年には路線対立を原因として主流派と反主流派に
分裂したため弱体化し、政府軍の攻勢を受けて敗北を重
ね、支配地域のほとんどを失った。態勢を立て直し、攻
勢に転じることができたのは、1995年以降である。
以上のように、SPLM/SPLAは、国内情勢と国際情勢
が変化するなかで、組織の内部対立や分裂という問題を
抱えながら、22年にわたって内戦を戦い抜いたのだった
(地図1)。
地図1 各武装勢力の支配地域(2002年)
エチオピア
ケニア
中央アフリカ
南ダールフール州
青ナイル州
東エクアトリア州
西コルドファン州
0 200
凡例
スーダン政府軍(GOS)スーダン人民解放軍(SPLA)南スーダン防衛軍(SSDF)南部スーダン解放運動(SSLM)
競合地域コンゴ民主共和国
ジョングレイ州
中央エクアトリア州
西エクアトリア州
レイク州
ワラブ州西バハル
アルガザル州
ジュバ
ユニティ州
ウガンダ
東エクアトリア州
ケニア
エチオピア
上ナイル州
南コルドファン州
北バハルアルガザル州
-
5
二つのスーダンと近代史
スーダンの紛争は、アラブ=イスラームの北部とアフ
リカ=キリスト教(および伝統宗教あるいはアニミズム)
の南部との対立であると説明されることが多い。この枠
組みによると、スーダンの紛争は、人種・宗教上の対立
が原因ということになる。この枠組みは、事態を単純化
しすぎている。SPLM/SPLAは、自らをキリスト教徒の
組織と位置づけたことは一度もないし、宗教としてのイ
スラームを否定したこともない。同組織を支持し、内戦
を戦った人々には南部人だけでなく、北部人も含まれて
いた。また単純な二分法的図式は、北部の多様性を無視
している。南部人が民族的に多様であるのと同様、北部
人の民族的構成も多様である。ヌバ人(南コルドファン
州)、フール人(ダールフール地方)、ベジャ人(紅海地方)
など、アラブではない諸民族の人々が多数存在する。こ
れらの民族的少数派(エスニック・マイノリティ)の人々
は、19世紀以降、政治経済的な中心であるハルツームに
根拠を置いた政治・軍事勢力によって搾取し続けられて
きたのである。この状況は、現在のスーダンがエジプト
の影響下にあった1820年代から80年代はじめにかけても、
それに続くマフディー国家の支配下にあった時代も同様
であった(地図2)。1956年の独立後も、少数派の人々
は国民としての正当な扱いを受けてこなかった。彼らは、
南部人と同様、国家体制のなかで「周辺化」された存在
であるといえる。
さらに、北部のアラブ人も政治経済的には同質ではな
いことに注意しておく必要がある。現在の支配階層の多
数がアラブ人であることは確かだが、彼らはアラブ人全
体のごく一部にすぎない。農民、牧畜民、商人、都市居
住民である多数のアラブ人は、支配体制のなかで中下層
に位置づけられている。
2003年以降世界の注目を集めるようになったダール
フール紛争も、単純な二分法ではなく複眼的な視点から
捉えられるべきだ。ダールフールは、16世紀に成立した
といわれるダールフール王国(スルタン国)の版図で
あった。フール人を支配階層とし、アラブ系牧畜民が被
支配階層であったこの多民族王国は1916年まで存続して
いた。17、18世紀には、のちに中心になるハルツーム周
辺より繁栄しており、エジプトやアラビア半島と直接外
交関係を結んでいた。スーダンへの併合後、この地域の
政治経済的自律性は失われ、国家のなかで周辺化され
低開発の状態のまま放置されることになった。NCPと
SPLM/SPLAとの和平交渉が本格化していた2003年の段
階で、反政府勢力が武装蜂起した背景には、こうした状
況と、「問題は南部だけではない。私たちのことも忘れ
るな」という主張があったのである。
独立後の課題
第2次内戦は、南部だけで戦われたのではない。南部
と接する南コルドファン州と青ナイル州、およびエリトリ
ア国境の東部地域も重要な戦線であった。SPLM/SPLA
は、これらの地域を国家の構造のなかで不当に抑圧され
てきた「周辺化」された地域と規定し、南部同様に解放
の対象とみなしてきた。CPAは、SPLM/SPLAが北部の
周辺化された地域の解放を断念し、南部に撤退したとい
う意味あいをもっていた。現在、CPAが積み残した課題が、
地図2 エジプト支配時代のスーダン 1820年代~1883年
エジプト支配下のスーダンは、現在のエリトリアとエチオピア(ア
ビシニア)、およびウガンダの一部を含んでいた。南北スーダンが
政治経済的空間として成立したのはこの時期である。
紅
海
エジプト
スーダン
アビシニア
川
ナイル
トアバラ川
ドンゴラベルベル
カサラ
タナ湖
センナール・ゲジラ
ダールフールマッラ山
コルドファン
ヌバ山地
ジャバル・カディール
バハルアルガザル
エクアトリア(赤道州)
ブニョーロ
アルバート湖
ヴィクトリア湖
白
ルナイ
ナイル
青
バハルアルジャバル
(白ナイル川)
バフル・アル・カザール
ソバト川
ワディハルファ
メロエ
サワーキン
ハルトゥームハルトゥーム
エルオベイドファーシル
ゴンドコロ
ファショダ
オムドゥルマン
-
6
武力紛争というかたちをとって噴出している。
北部の周辺化された地域のなかで、アビエイ地域だけ
は、CPAで民族自決権が認められていた。南部の住民
投票と同時に住民投票が実施され、南部と北部のどちら
に帰属するのか、住民自身が決定すると規定されている。
この住民投票はいまだに実施されておらず、アビエイの
情勢はきわめて不安定で軍事的衝突が発生している。南
コルドファン州と青ナイル州では、NCPとSPLMの勢力
が拮抗しており、前者は2011年5月から、後者は同年9
月以降、実質的な内戦状態にあり、多数の難民が発生し
ている。反政府勢力との和平交渉が継続しているものの
いっこうに進展しないダールフールとあわせて、スーダ
ン共和国の今後が注目される(地図3)。南スーダン共
和国の平和と安定には、スーダン共和国の平和と安定が
不可欠であり、両国のあいだに友好関係が樹立される必
要がある。
南スーダンの国内に目を転じれば、政治・軍事的な安
定が達成されているとは言い難い。10ある州のうち、と
くに治安が悪いのは、ジョングレイ、上ナイル、ユニティ
の3州である。内戦中、南部人は敵味方に複雑に分断さ
れ、お互いに戦った経緯があり、この傷はいまだに癒さ
れていない(地図1)。自動小銃などで武装している市
民・村人の武装解除も進展していない。また、2010年以
降、現体制に不満を抱くSPLAの将軍たちが反乱を起こ
している。インフラの整備や政府・議会・司法制度の確
立とともに、国民の和解と平和構築が、新生南スーダン
共和国に課せられた課題であるといえる。
地図3 二つのスーダンと「周辺化地域」
国旗の説明:黒は南部スーダンの黒人を、白は平和を、赤は勇敢な戦士の血を、緑は肥沃な土壌を、青はナイル川を、星は 国家の団結を表している。
南スーダン共和国赤赤
緑緑青
黄
青
黄(The Republic of South Sudan)
基本情報面積:64万km2
人口:826万(2008年)(第5回人口調査)
首都:ジュバ
言語:英語(公用語)、その他
宗教:キリスト教、伝統宗教
識字率:27%
貿易品目 :輸出 原油
輸入 機械・設備、工業製品、輸送機材、
小麦・小麦粉
貿易相手国:輸出 中国、アラブ首長国連邦、日本、
サウジアラビア、インド
輸入 中国、インド、ルーマニア、
サウジアラビア、アラブ首長国連邦
通貨:南スーダン・ポンド(SSP)
(外務省HPより)
戦後スーダンの歩み
年月 事項
1956年1月
1972年3月
1983年1月
1989年6月
2003年2月
2005年1月
2008年7月
2011年1月
7月
10月
スーダン共和国独立
第1次内戦(1955年開始)終結
第2次内戦勃発
軍事クーデタによりバシール軍事政権成立
ダールフール紛争勃発
南北包括的和平合意(CPA)に署名
国際刑事裁判所(ICC)よりバシール大統領逮
捕状請求
南部スーダン住民投票実施、独立が決定
南スーダン共和国が分離独立
国連加盟
UNESCO加盟
エリトリア
エチオピア
ケニアウガンダ
コンゴ民主共和国
中央アフリカ
南ダールフール州
西ダールフール州
チャド
北ダールフール州
リビア
エジプト 紅
海
アビエイ地域
ジュバジュバ
ハルツームハルツーム
青ナイル州 凡例
油田 パイプライン 州界 国境
0 250km0 250km
南コルドファン州
-
7
世界の今知りたい!
独立行政法人 石油天然ガス・金属鉱物資源機構(JOGMEC)石油調査部 伊原 賢
シェールガスの可能性と課題
国際エネルギー機関IEAは2011年6月、世界が「ガス
黄金時代」を迎えたとするレポートを公表した。そのシ
ナリオによれば、世界の天然ガス需要は2035年に08年比
で62%も増加すると予測。エネルギー全体の需要が年率
1.2%で増えるなか、天然ガスは年率2%と約2倍の勢
いで伸び続け、世界のエネルギー構成での役割が飛躍す
るとの見方だ。それを支えるのが非在来型天然ガスの存
在だといわれる。
①非在来型天然ガスとは何か、その可能性は? 賦ふ
存そん
環境
エネルギー需給のひっぱく懸念、技術の進歩に伴い、
地下からの回収が難しいと考えられていた「非在来型」
の天然ガスが、シェールガスを中心に注目されている。
天然ガスは化石燃料のなかでは、同じ発熱量に対する二
酸化炭素の排出量が少ないため(石炭100:石油80:天
然ガス55)、天然ガス供給増への期待感の高まりとみて
とれる。開発ブームの先駆けとなったアメリカ合衆国で
は、「シェールガス」の供給量と埋蔵量の伸びが大きい
ため、世界の天然ガス市場の4分の1を占める「アメリ
カ合衆国内のガス需給見通し」が近年一変した。
非在来型天然ガスには、現状、タイトガス、コールベッ
ドメタン、シェールガス*1という三つの開発対象がある
が、その期待される資源量は膨大だ(図1)。2008年に
はアメリカ合衆国の天然ガス日産量562億立方フィート
/日(年間20.56兆立方フィート*2)の50%が非在来型天
然ガスだったことは世界中のエネルギー関係者に衝撃を
与えた。
図2に非在来型天然ガス資源の賦存環境例を示す。ア
メリカ合衆国のテネシー州とアラバマ州にまたがるチャ
タヌーガ堆積盆地では、非在来型天然ガスの3点セット
であるタイトガス、コールベッドメタン、シェールガス
が確認されている。
②どういった経緯で登場したのか?
非在来型天然ガスの登場は、「1980年以降のアメリカ
合衆国内ガス供給の動き」を時間軸で追うとわかる。産
業用へのガス使用拡大をめざし、連邦政府や州税の控除
対象として80年代から注目された砂岩からのタイトガス
の開発には、垂直井に水圧破砕を施しガスを産出してい
たが、最近の対象は炭酸塩岩・火山岩・石炭層・シェー
ルに広がりをみせており、水平坑井�3や多段階の水圧破
砕�4が適用されるようになってきた。北アメリカを中心
に90年代初頭にはコールベッドメタンにも注目が集まっ
た。その効果があって生産余力は1986年に日量160億立
方フィート/日まで膨らみ、1985年から2000年までガス
バブルの時代を迎えたのだ。バブル期の1995年にはガス
価は$1.58/MMBtu[1MMBtu(英国熱量単位、メート
ル法によらない熱量単位)=25.2万kcal]まで下がって
需要が伸び、生産余力は40億立方フィート/日まで落ち
込んで、アメリカ合衆国の天然ガス消費の伸びをどう支
えるかが課題となった。2000年に入ると、LNG輸入も
念頭に入れつつも、その救世主としてシェールガスに注
目が集まったのである。
③技術的回収可能資源量の増加
技術の飛躍的な進歩により、世界中に眠っている膨大
な量の天然ガスの存在が明らかとなり、非在来型ガスの
技術的回収可能量は230.3兆m3と試算され、少なく見積
もっても、残された在来型(404.4兆m3)の60%弱も存
在することが明らかとなった(図3)。「技術的回収可能
量」の半分が経済合理的に地下から取り出せるとすると、
図1 天然ガスの資源量トライアングル
在来型ガス
資源量に限界
地下から取り出しやすい
資源量が豊富
地下から取り出しにくい
1,000md(ミリダルシー)
10md
0.1md
.001md
技術の進歩
非在来型ガス
メタンハイドレート
タイトガス
コールベッドメタン
シェールガス
出所:米国地質調査所シェールガス
タイトガス
在来型ガス田
コールベッドメタン
図2 非在来型天然ガス資源の賦存環境(アメリカ合衆国のチャタヌーガ堆積盆地)
*1タイトガス:浸透率0.1ミリダルシー未満の砂岩に含まれる天然ガス1ミリダルシー(1md)=9.87×10−16m2 ※「浸透率」の単位(岩石中のガスの流れやすさを示す)コールベッドメタン:石炭層に吸着したメタンシェールガス:タイトガスよりも浸透率が2桁以上低い(0.001ミリダルシー未満)泥岩の一種である頁岩(シェール)に含まれる天然ガス
*21兆立方フィート=283.2億m3 1フィート=0.3048m
-
8
世界の天然ガスの可採年数は在来型ガスの残存確認可採
埋蔵量をベースとした60年から、少なくとも160年を超
えるのは確実になったといえよう。
④環境への影響
シェールガスの開発業者にとって、ガス井掘削活動の
維持拡大のため、水圧破砕と帯水層汚染との因果関係の
解明は喫緊の課題となっている。それは、水圧破砕に用
いられる多量の水やポンプ類の移動があるからだ。周辺
環境として人口の密集は開発を妨げる要因となる。天然
ガスの開発・生産活動は、浅部の帯水層や地表の水源を
汚染するリスクをはらんでいる。干ばつ時の掘削やフラ
クチャリング(水圧破砕法)用の水の確保はコスト面か
ら容易ではない。規制や検査、関係機関との連絡調整が
リスク軽減に必要だ。それらをクリアした上でシェール
からのガス生産は可能となるだろう。
⑤今後の課題(非在来型が天然ガスの主役になるか?)
この「シェールガス」という非在来型ガスを開発する
動きは、世界的高まりをみせている。まずは、カナダ・
ヨーロッパ・中国ほかへの開発技術ノウハウの伝播が注
目されるところだ。当地での開発課題となる技術・イン
フラのリスクと、それらがガスの生産コストに及ぼす影
響に注目すると、伝播の速度がみえてくる。世界の非在
来型ガスの生産レベルは、2008年で石油換算400万バレ
ル/日強とLNGの市場規模(8兆立方フィート、世界全
体ガス消費の7.5%)と拮抗しながら上昇を続けている。
シェールガスの登場によって増えた「世界のガスの大供
給余力」は、原油価格にリンクさせているLNGの価格
フォーミュラに変革を与えると思われる。日本もその恩
恵を受け、現在の長期契約の取引形態も変わるかもしれ
ない。
シェールガスの登場により、国内のガス生産が増えた
アメリカ合衆国ではガス価格は$4/MMBtu近辺で低迷
するも、ヨーロッパとアジア圏ではその倍、3倍程度と
高値で推移している。そのため国産ガスをLNG化して、
アメリカ合衆国のメキシコ湾から輸出する計画が現実味
を帯びている(図4)。
*3水平坑井:石油や天然ガスの閉じ込められた岩石の層に沿って掘削される井戸(坑井)のこと。通常の垂直・傾斜井に比べ、岩石との接触体積が多く取れるため、1坑あたりの生産量を数倍に増やすことができ、80年代後半より広く、石油開発に使われるようになった。石油や天然ガスの地下からの回収率を向上させる万能薬ともいわれる。
*4水圧破砕:原油や天然ガスが存在する地層に圧力をかけてつくった人工的なフラクチャー(割れ目)により、原油や天然ガスの流れにくさを改善する技術。坑井を介して、水・酸・合成化合物からなる流体に圧力をかけてつくられた地層の割れ目に、流体に混ぜた砂の粒子を圧入・保持させることで、圧力を除去した後も割れ目が閉じないようにする。1940年代後半に開発され、60年強の歴史がある。その後の技術進歩に伴い、地層に沿って段階的につくったフラクチャーの分布もモニタリングできるようになり、シェールガスといった非在来型天然ガスの生産増に大きく寄与している。
世界全体
404.4
230.3
在来型非在来型
32.258.3
北米
22.424.5
7.7
7.2
28.7
21.3
132.5
136.5
30.8
1.7
38.7
23.7
36.0
32.5
中南米
アフリカ
中東
中東・北アフリカ
サブサハラ・アフリカ
西欧東欧・ユーラシア
ヨーロッパ旧ソ連
中国・中央アジア アジア・
太平洋
東南アジア・太平洋
404.4
230.3
在来型非在来型
32.258.3
22.424.5 アフリカ
中東
中東・北アフリカ
サブサハラ・アフリカ
西欧東欧・ユーラシア
旧ソ連
中国・中央アジア アジア・
太平洋
東南アジア・太平洋
ヨーロッパ
7.7
7.2
28.7
21.3
132.5
136.5
30.8
1.7
38.7
23.7
36.0
32.5
在来型非在来型(単位:兆m3)
(注)「非在来型」は原始埋蔵量の回収率25%と仮定して計算出所:IEA「World Energy Outlook 2009」などを基にJOGMEC作成世界全体
北米
中南米在来型非在来型
図3 世界の天然ガス資源量分布(技術的回収可能量)
出所:各種資料よりJOGMEC作成
アフリカアフリカ
中東中東
ロシアロシア
サハリンサハリン
シェールガスシェールガス
コールベッドメタンコールベッドメタン北西大陸棚北西大陸棚
メキシコ湾メキシコ湾
パナマ運河パナマ運河
アメリカアメリカ
カナダカナダ
日本日本
オーストラリアオーストラリア
パプアニューギニアパプアニューギニア
LNGルート(将来も含む) 図4 日本へのLNG供給ソース
-
9
調査を通じて身近な地域を知る〜ヒートアイランド観測を取り入れた授業実践〜
いきいき授業実践� 平成23年度『新詳地理B 初訂版』平成23年度『新詳高等地図 初訂版』
平成23年度�『新詳地理資料 COMPLETE 2011』
愛媛県立松山北高等学校 谷口治義
これまで科目「地理B」を中心に教科指導を行ってき
たが、近頃思うことがある。それは、デジタルネイティ
ブとよばれる言葉が注目されるように、昨今の高校生は
ネットを利用して情報を収集したりまとめたりするスキ
ルは高いが、その一方で自らの目で観察したり、足を使っ
て情報を集めたりすることがだんだんおろそかになって
いるのではないか、ということだ。与えられた知識を吸
収することは得意であっても、課題をみつけ自ら考えて
判断することが弱いのではないかと感じるのは私だけだ
ろうか。私自身、大学で経験した地域調査は、問題解決
的な学習の原点であり、また主体的で創造的な活動だっ
たように思う。大学入試の小論文出題内容では、統計資
料の分析から地域環境に関する考察、地域発展のための
政策提言など、地理学的な視点に立った問いかけが多い
ように感じる。それゆえに、問題解決的思考を育むため
には地域調査という体験学習が、高校現場においても重
視されなければならないと考える。デジタル化が急速に
進む今日、あえて体力勝負のアナログ的な取り組みの
意義は大きいはず。ただし現実的には地域調査に多くの
時間を割くことは難しい。ここでは簡便な方法で地域の
「ヒートアイランド現象」を観測から実感できる方法に
ついて紹介したい。
まずは、都市気候とヒートアイランド現象とはどうい
うものなのかを『新詳地理資料 COMPLETE 2011』(以
下、資料集)で確認させる。
『新詳地理B
初訂版』(以下、教
科書)p.40の「現
代社会と気候」で
は、「 都 市 気 候 」
の一つの特徴とし
て「ヒートアイラ
ンド現象」が取り
上げられている。
教科書には映像メ
ディアでみる機会
が多くなったサー
モグラフィーによ
る東京23区の人工
熱排出量が紹介さ
れている。赤く高
温域となった地域
がどこにあたるの
か、『新詳高等地
図 初 訂 版 』p.98
を参考に重ね合わせてみると、ターミナル駅を中心とす
る地域(品川・新宿・池袋・渋谷など)が浮かび上がっ
てこよう。なお、再開発が行われた汐留シオサイトでは
林立する高層ビル群により、東京湾からの海風が遮られ
都心の高温化に少なからず影響を及ぼしているといわれ
る。また教科書p.41のトピックにおける「大阪市内にお
ける桜の開花日の分布」もヒートアイランド現象を考え
るうえで興味深い。植物を指標として都心部がなぜ早く
開花するのか考えさせることで、都心部の熱環境を推察
することが可能である。ちなみに地元愛媛県宇和島市は
桜の開花が全国でも一番早いといわれてきたが、近年は
桜前線が西日本から北上ではなく関東地域が早まる傾向
がみられる。また、人間活動の影響が地球規模での温暖
化や都市の気温上昇に及んでおり、開花時期が従来より
も早まってきている。グローバルな観点で気候の変化に
着目させることも重要である。
1.はじめに
2.都市気候とヒートアイランド現象
ヒートアイランド現象
豪雨
ヒートアイランド現象
豪雨
『新詳地理B 初訂版』p.40
『新詳地理資料 COMPLETE 2011』p.39
満開日満開日
27
2526
25
26
23
24
23
2423
22
22
212019
27
2526
25
26
23
24
23
2423
22
22
212019
『新詳地理B 初訂版』p.41
-
10
さて、今回の地域調査はヒートアイランド現象の観測
に限定して、 平成22年10月に実施した。松山市街地の
ヒートアイランド現象はこれまでも調査研究があり、実
態については予測されることではあるが、一般化される
事象を自ら確かめることは大変意義深いと考え、テーマ
として取り上げた。また自然科学において観測(観察)
することが重要であることもねらいとして盛り込みた
かった。
①目的と方法
この授業実践の目的として次の3点をあげ、観測調査
を実施した。
・松山でも「ヒートアイランド現象」の実態があるのか。
・あるとすれば、市街地と郊外の気温差はどのくらいあ
るのか。
・ヒートアイランド現象を生じさせる要因として何が考
えられるか。
観測地点は、3年生理系クラス有志10名からなる定点
観測班と、私自身が車を運転して移動しながら観測する
移動班に分かれて実施した。定点には松山地方気象台
と、松山空港をあわせて12か所、移動観測班は18か所で
実施した。小文字のアルファベットが移動観測地点であ
る(図1)。生徒の出身校区が幸いにも散らばってくれ
たが、今回の観測は松山城が位置する石手川右岸の通称
城北地区が観測
エリアとなった。
地点を補う形で
移動観測ルート
を描いた。観測
方法は、理科の
実験で使用する
デジタル温度計
を借用し実施し
た。観測者は定
時5分前から用
意をし、1.5mの
高さでデジタル
温度計を保持し、
うちわで風を送
りながら、定時に気温を読ませた。
1回目は10月16日(土)の21時と23時。2回目は10月
18日(月)の21時と23時とした。残念ながら1回目は私
の温度計のトラブルから、移動観測は実施できなかった。
幸いこの両日とも天候には恵まれたこともあり、夜間に
かけて放射冷却が進むことが期待されるなか、定点観測
と移動観測を無事に実施できた。なお、移動観測データ
については時間補正は行わなかった。
②分布図作成
観測終了後、
クラスで解析作
業を行った。定
点観測と移動観
測が実施できた
10月18日の気温
データにより作
業を行った(図
2)。まず気温
データをベース
マップにおとし、
気温分布図を作
成した。生徒に
とって、数値を
もとに等値線を
なめらかに描くことは意外と難しく、できあがった分布
図も人によってまちまちの結果であった。普段等値線図
を統計グラフでみることはあっても、実際描いてみると
難しく、戸惑っているようすであった。
続いて取り組
んだのが、土地
利用図の作成で
ある。気温の分
布が土地利用と
関連があるので
はという仮説を
もとに、5万分
の1地形図に作
業を行った。建
物密集地、住宅、
水田、果樹園を
色分けし、塗り
分けた(図3)。
③考察
できあがった観測日の気温分布図を用い、松山市街地
で気温が高くなっている場所や逆に気温が低くなってい
る場所について読みとらせた。そして気温分布の相違を、
土地利用図をもとに考察させた。とくに都市内部で気温
3.授業実践
hg
f
e
d
c
b
a
i
j k
J
l
n
oBp
G
r
D
A
C
m
E
q
F
H
図1 観測地点とルート
1919
1919
2020
20201919
1818
1919
1818
2121
1717
1810
図2 10月18日21時気温分布図
図3 松山市土地利用図(生徒作図)
*図1〜4は、国土地理院発行の5万分の1地形図、『松山南部』『松山北部』『三津浜』『郡中』を使用したものである。
-
11
が上昇する要因について、次の3点を提示し、具体的な
要因については考えさせた。
図4のように土地利用図と気温分布図を重ね合わす作
業を行いながら、生徒はそれぞれ次のような見解を得た。
自動車、高層ビ
ル、工場、エアコ
ンの室外機の影
響がある。地表
面がコンクリー
ト、アスファル
トで覆われてお
り、農地や緑地
が減少している
ことも関連して
い る の で な い
か。松山市街地
では建築物の高
層化が進んでい
る。以上の要因
が関連して高温域が形成されたと結びつけた。
一方、発展課題として、ヒートアイランド現象を緩和
するためにどうすればいいか考えさせた。資料集p.39
の「クローズアップ」は空中写真と熱画像を対比してクー
ルアイランドの実態と緑地の効果を確認でき、考察の大
きなヒントになる。
④まとめ
生徒に考察させながらわかったことを結果としてまと
めさせた。
・松山市街地においてもヒートアイランド現象の実態が
明らかである。
・市内高温域と郊外の気温差は3℃を超える。
・高温域は建物密集地となっており、幹線道路が通って
いるため交通量も多い。建物の高層化も進んでいる。
市中心部は周囲より気温が高くなる傾向が顕著である。
水田景観となる郊外は気温が下がる。
・松山城の近辺で低温域が現れており、クールアイラン
ドとなっている(写真)。
なおヒートアイランド現象を緩和する方法として、地
表面やビルに緑を増やす実例として屋上緑化の取り組み
について紹介した。
今回のヒートアイランド観測について、生徒から以下
のような感想を得た(一部)。
・ヒートアイランド現象はよほどの都会でなければ起こ
らないと思っていたが、自分の町で身近に発生してい
ることがわかり興味深かった。この問題に対する解決
策をより検討していくことが今後の課題だと思った。
・実際に調べた結果を等値線図にして土地利用図と比べ
てみると、ヒートアイランド現象が本当に起こってい
ることを実感できた。ある事実を覚えるのではなく、
自分たちで調査して確認することも大切だと思った。
・松山市内にもヒートアイランド現象が起きていること
が、観測を通じて実感することができた。市内にも建物
の屋上を緑化しているところがあることを初めて知っ
た。
生徒の感想から、観測の実践と思考することの大切さ
を改めて教えてもらった。地道な活動ではあるが、地理
教育のあるべき姿を再認識した次第である。一見大がか
りにみえるこの実践も、このような簡易的な方法を用い
れば今後多くの学校でも実施可能ではないかと考える。
ヒートアイランドの観測調査が高校の授業として実施さ
れている事例はあまりないだけに、この報告が少しでも
役に立てればと思う。
・人工熱排出との関連性。
・地表面は何によって被覆されているのか。
・都市景観にどのような特徴や変化があるか。
図4 土地利用図・気温分布図重ね合わせ図(10月18日21時)
1818
1818
1919
19192020
2020
1919
1919
2121
1717
18
『新詳地理資料 COMPLETE 2011』p.39
写真 クールアイランドを示した堀之内・城山公園(2010年11月1日筆者撮影)
4.おわりに
■参考文献
・深石一夫『愛媛の気候 ふるさとの大気環境を探る』1992 愛媛県文化振興財団
・小泉武栄・原芳生『身近な環境を調べる 東京学芸大学地理学会シリー ズ 増補版』2009 古今書院
-
12
「地理B」で日本をどう教えるか〜センター試験に対応して〜
いきいき授業実践� 平成23年度�『新詳地理B 初訂版』� 平成23年度『新詳高等地図 初訂版』
広島県立福山誠之館高等学校 天野真哉
大学入試センター試験は高校までの学習内容が出題さ
れるのであって、高校の学習内容のみが出題されるわけ
でない。このことは、過去10年間のセンター本試験「地
理B」を振り返ってみても明らかである。高校の「地理
B」の授業では日本地誌に多くの時間をあて
るには困難で、学習の中心は世界地誌となっ
ている。にもかかわらず、センター試験では
日本地誌が必ず出題されている。
教科書も世界の自然環境などテーマ別に構
成され、地誌の内容も世界が中心であって日
本単独のテーマにした内容構成にはなってい
ない。日本の地誌を大きく取り上げない高校
の授業では、これらに直接対応できていない
のが現状である。これらの内容に対応するた
めには、与えられた授業時間のなかでどのよ
うな授業をし、生徒たちに力をつけていくの
か、現場の地理教師の悩むところとなってい
る。
表1に過去10年間のセンター本試験におけ
る日本に関する問題を一覧にした。2005年度
までは大問35問中7〜8問程度であったが、
2010年度では36問中11問と3割も占めている。
2011年度は大問数も35問にもどり日本関連の
問いも8問と減ったが、ここ5年間をみる限
りでは、日本関連の問題の割合は増えている。
問いの内容は特定の地域や都市を取り上
げて、地形図や衛星写真からの読みとりか
ら、地域の産業・人口を問う形が定番となっ
ている。問題中に登場する都市は政令指定都
市や三大都市圏など生徒にとってなじみのあ
る都市が大半である。しかし、2002年度の宝
塚市、2007年度の八王子市や東大阪市、2011
年度の西宮市はこの地域周辺の受験生でなけ
れば、これらの都市の性格を知らない場合も
多く、難問であったと思う。これらの都市ま
で授業で押さえることは与えられた授業時間では難しい。
日本に関する問いがセンター試験で2割以上出題されて
いる現状に対して、実際の授業では全学習時間のうち日
本の事項に2割も確保できていない。
1.はじめに
2.センター試験における日本に関する問題
表1 過去10年間のセンター試験本試験「地理B」において日本国内の地域・都市を取り上げている問題
年度 問題番号 地域 都市 内 容 割合
2011
第3問 問5・問6豊田市 長崎市
西宮市 東京都市圏
各都市の人口構造、都市圏の人口分
布に関する問題 8問/35問
第6問 問1〜問6 佐賀県 佐賀市 市の地形図読図、産業・人口・地域
調査に関する問題
2010
第1問 問4〜問6 東北地方 北海道 気候・地形図読図に関する問題
11問/36問第2問 問1〜問6 山形県最上地域 鳥瞰図・地形図読図、人口に関する
問題
第4問 問3・問4 大都市 日本の村落と都市に関する問題
2009第2問 問1〜問6 山陰地方 境港市
市の地形図読図、産業・人口・観光
に関する問題 9問/36問
第4問 問1
問5・問6
仙台市 千葉市
浜松市
村落、各都市の産業・人口、日本各
地の商業地景観に関する問題
2008
第3問 問4〜問6 東京都市圏 東京都市圏、国内都市に関する問題9問/36問
第6問 問1〜問6 広島市 市の地形図読図・産業・地域調査の
手法に関する問題
2007
第1問 問5 日本列島 東北地方 自然災害に関する問題
9問/36問
第2問 問5 都道府県別 産業出荷額に関する問題
第3問 問5・問6鹿児島市 八王子市
東大阪市 札幌市 各市の人口比較に関する問題
第6問 問1〜問5
八戸市 青森市
十和田市 釧路港
銚子港 八戸港
八戸市の地形図読図、産業に関する
問題
2006
第2問 問1〜問6 函館市 市の地形図読図、産業に関する問題
9問/35問第4問 問2・問6日本全図
都道府県別
日本国内の発電、工業別賃金に関す
る問題
第6問 問2 関東地方 都市気候に関する問題
2005
第1問 問6・問7 日本全国 扇状地・火山地域に関する問題
7問/35問第2問 問6・問7
愛知県 山形県
大阪府 関東地方 人口に関する問題
第5問 問4〜問6愛知県 山形県
大阪府 関東地方
地形図読図、主題図、大都市圏土地
利用読みとりに関する問題
2004 第5問 問1〜問7
松本盆地 松本市
新庄市 奈良市
諏訪湖周辺 霞ヶ浦
琵琶湖 支笏湖
衛星写真の読みとり、各湖比較、各
都市の雨温図比較、松本盆地の地形
図読図に関する問題
7問/35問
2003 第5問 問1〜問7 南西諸島 石垣島 島を取り巻く自然環境、島の地形図
読図、島の人口・産業に関する問題7問/35問
2002
第2問 問6・問7 都道府県別 日本の工業立地の特徴と産業別の金
額に関する問題 8問/35問
第5問 問1〜問6釧路市 宝塚市
大阪市
雨温図の判定、釧路の地形図読図・
産業、釧路と他市との人口比較に関
する問題
-
13
一方で、授業の基本である教科書にはどの程度日本の
内容が取り上げてあるのか。『新詳地理B 初訂版』では、
世界とのかかわりのなかで日本が取り扱われている。大
項目で日本の地誌の扱いはないが、各テーマにおいて日
本を学習することができる。たとえば「第Ⅰ部 自然と
生活」「1章 自然環境と生活」「5節 日本の自然の特
徴と人々の生活」では日本の地体構造(図1)を用いて、
日本列島を形成する四つのプレートや、フォッサマグナ、
中央構造線を学習する。小・中学校で学習した日本アル
プスの飛騨・木曽・赤石山脈も登場する。
さらに、この教科書では表2で示した「技能をみがく」
というコーナーを設けて、その大半で日本の諸地域を取
り上げている。「地形図の利用」の作業や読図を通して、
日本の地形を学習するようになっている。
しかし、残念ながら、日本地誌として扱わないために、
小・中学校で学習したほど、自然地形の代表例や都市の
性格が生徒の印象に残りにくくなっている。
正直、日本の内容は生徒たちが小・中学校で経験し学
習してきた知識や思考力で対応してもらうしかないと感
じることがある。しかし、逆にいえば、小・中学校で学
習してきたことを背景にして、高校の授業で今いちど思
い出させる、あるいは再確認していく作業は必要である。
<授業展開例①>
「第Ⅰ部 自然と生活」「1章 自然環境と生活」「2
節 世界の地形」「2 外的営力によってつくられる小
地形」の単元項目で、意図的に日本の代表例を多く取り
上げるようにしている。表3に示した例は一部である。
表3中 太字で示した地名の位置を必ず地図帳で調べさ
せ、こちらで用意した日本の白地図に記入させている。
3.「地理B」の教科書における日本の内容
北アメリカプレート北アメリカプレート
フォッサマグナフォッサマグナ
太平洋プレート
中央構造線中央構造線
ユーラシアプレート
ユーラシアプレート
フィリピン海プレート
フィリピン海プレート
太平洋プレート
図1 「地理B」の教科書で取り上げられている日本の例~日本の地体構造~ 『新詳地理B 初訂版』p.56 ①
写真の見方①〜地形〜「下しも
総うさ
台地」
地形図の利用①〜地図記号〜「成田」
地形図の利用②〜等高線〜「硫黄島」「大室山」
地形図の利用③〜V字谷と断面図〜「黒部湖」
地形図の利用④〜小地形と土地利用〜「琵琶湖西岸」「沼田」
「阿賀野川下流」
気候のとらえ方「東京」
写真の見方③〜産業〜「南陽市」「福山市」「高崎市」「佐倉市」
地形図の利用⑤〜集落の形態〜「天理市」「砺波市」「三芳町」
「旭川市」
地形図の利用⑥〜新旧比較〜「奈良」
統計資料のグラフ化「奈良市」
表2 「地理B」で取り上げられている日本の内容『新詳地理B 初訂版』「技能をみがく」を例にして
4.日常の授業で日本の内容を学習するには
表3 授業で取り上げている自然地形の代表例(一部省略)分 類 代 表 例
地塁 飛騨山脈 赤石山脈 木曽山脈 テンシャン山脈
傾動地塊 シエラネヴァダ山脈 生駒山地
地溝ライン地溝帯 アフリカ大地溝帯
フォッサマグナ 京都盆地 奈良盆地 上野盆地�
火山
マウナロア 八幡平 富士山 羊蹄山 岩木山
阿蘇山 箱根山 デカン高原 一ノ目潟
男鹿半島 ダイヤモンドヘッド 焼岳
昭和新山
カルデラ湖 十和田湖 田沢湖 洞爺湖 摩周湖
堰止湖 中禅寺湖 富士五湖
三角州
円弧状:ナイル川 太田川 宮川
鳥趾状 : ミシシッピ川
カスプ状(尖状):テヴェレ川
扇状地甲府盆地 松本盆地 近江盆地 鈴鹿山脈東麓
人吉盆地 米沢盆地 山形盆地 新庄盆地
自然堤防 石狩川 上川盆地 信濃川 利根川 木曽川
沿岸流による
砂の堆積の地形
砂嘴:三保松原 野付半島 コッド岬
砂州:天橋立 弓ヶ浜(夜見ヶ浜)
陸繋砂州:函館 潮岬 志賀島 ジブラルタル
ラグーン:サロマ湖 中海 八郎潟 河北潟
海食崖 屏風ヶ浦 遠州灘の沿岸 ドーヴァー海峡両岸
海岸段丘 室戸岬 佐渡島
リアス海岸 三陸海岸 若狭湾 志摩半島 スペイン北西部
おぼれ谷 英あ
虞ご
湾 チェサピーク湾 河岸段丘 沼田盆地 伊那盆地
台地関東平野:相模原 武蔵野下
しも
総うさ
台地 常ひ
陸たち
台地
牧ノ原 三方原
三本木原 十勝平野
カルストカルスト地方 秋吉台 平尾台
鍾乳洞:秋芳洞 龍河洞 龍泉洞注1)太字が日本関係
注2)本来の資料ではすべての地形を記入。今回は「ケスタ」など日本で典型例が見
られない地形を省略
☆以上の代表例を地図帳で位置を確認し、世界地図・日本地図それぞ
れの白地図上に記入しよう。
-
14
作業の注意点として、①分類例ごとに色分けするなど
生徒自身に工夫させながら作業させること、②作業する
白地図は生徒のやる気維持とできあがる日本地図プリン
トを保存できるように、できるだけ上質紙(コピー用の
白いB4用紙)を用意すること、③生徒たちに小・中学
校で学習した地名もあることをつねに投げかけ、今いち
ど思い出させ再確認させること、以上を心がけて授業で
可能な限り作業させ、宿題にしないようにしている。
本校では、作業の結果と内容を生徒に定期テストで問
うことを予告し、実際に出題をしている。このことで、
知識の定着をはかるようにしている。定期テストなどを
実施しない場合は、仕上げた作業プリントを提出させる
のもよい。
<授業展開例②>
「第Ⅰ部 自然と生活」「1章 自然環境と生活」「5
節 日本の自然の特徴と人々の生活」の単元項目で、日
本の気候を学習する。ここでは小・中学校で学習した日
本の気候区分にふれるようにしている。図2で示した学
習プリントを用意して、各地域の代表的な都市とその雨
温図を結びつけさせる。
作業の注意点として、①気候区分の名前を暗記させる
のではなく、特色を理解させること、②手順は雨温図と
都市の結びつけをし、解答するなかで各地域の気候の特
色を説明すること、③したがって雨温図と都市の結びつ
けは、小・中学校までの知識で試みること、ここでも生
徒たちに小・中学校で学習した内容を今いちど思い出さ
せ、再確認させるように心がけている。
この学習内容も、生徒に定期テストで問うことを予告
し出題をしている。
<授業展開例③>
「第Ⅰ部 自然と生活」「2章 資源と産業」「2節
農産物の生産と流通」「4 世界のなかの日本の農業」
の単元項目で日本の主要な漁港を統計資料で確認させ、
同じく「4節 工業製品の生産と流通」「4 世界のな
かの日本の工業」の項目で、日本の工業都市を整理する
ようにしている。また、「第Ⅳ部 地球的な課題」「1章
人口・食料問題」「3節 世界と比べてみた日本の人口
問題」の単元項目で、日本の人口を学習する。日本の人
口ピラミッドや産業別人口割合など基本的なデータを押
さえる。ここで、三大都市圏や政令指定都市を整理する
ようにしている。教科書で取り上げられていない都市に
対しては、『新詳高等地図 初訂版』のp.140「日本の市
と人口」から、各県の人口数上位3都市を確認させる程
度にとどめている。さらに、表2で示した「技能をみが
く」というコーナーの「地形図の利用」で、日本の地形
を学習する。本校では『新編コンターワーク 最新版 地
形図学習の基礎』(帝国書院)を使用して、より多くの
日本の地形図にふれさせ、地理的技能をみがきながら、
ここでも可能な限り日本の地域や市をあげるようにして
いる。
高校で「地理B」を学習する目的は、センター試験で
高得点をとるためではない。その視点にたてば、授業の
目的は、日本を含む世界を学習し地理的見方・考え方を
身につけさせることにつきる。地理を学習することで思
考力や判断力が身につき、新たな発見や達成感から、生
徒が「地理好き」になることをめざしている。その先に
センター試験で結果が出せればと思う。
5.おわりに
【作業】 日本の気候①〜⑧の気候区分名を記入しよう。また、地図中の
都市に該当する気温と降水量のグラフを選択しよう。<指導のポイント>雨温図を生徒が考え、答えさせる→気候(気候区分)の特色も説明する。
①( 北日本・日本海側 )の気候
②( 北日本・太平洋側 )の気候
③(中部日本・日本海側)の気候
④(中部日本・太平洋側)の気候
⑤( 内陸 )の気候
⑥( 瀬戸内 )の気候
⑦( 南日本 )の気候
⑧( 南西諸島 )の気候
<指導のポイント>
なぜ雨温図がその形になるかを
考え、在籍校地域がどの気候区
分にあてはまるのか説明する。
資料:広島県立安古市高等学校、広島県立福山誠之館高等学校授業プリントより作成
( 上越 ) ( 札幌 ) ( 岡山 ) ( 那覇 )( 長野 )
( 宮古 ) ( 鳥取 ) ( 高知 ) ( 長崎 )( 網走 )
図2 作業プリントの例 「地理B」で取り上げられている日本地誌の内容 「日本の気候」を例として
⑦ 高知
オホーツク海
那覇⑧
40°
30°
140°
130°
平
太
洋
日
本
海
③鳥取
②宮古
網走
①札幌①札幌
岡山⑥
⑤
長野
④
上越(高田)
長崎
②宮古
那覇⑧
長野
①札幌
0 500km
松本 淳井上 知栄,ほか
年平均気温10.5℃年降水量1306.4mm
-10
0
10
20
30
℃気温
0
100
200
300
400
mm
3 5 7 91
降水量
11月
年平均気温14.6℃年降水量1897.7mm
-10
0
10
20
30
℃気温
0
100
200
300
400
mm
3 5 7 91
降水量
11月
年平均気温16.6℃年降水量2627.0mm
-10
0
10
20
30
℃気温
0
100
200
300
400
mm
3 5 7 91
降水量
11月
年平均気温6.2℃年降水量801.9mm
-10
0
10
20
30
℃気温
0
100
200
300
400
mm
3 5 7 91
降水量
11月-10
0
10
20
30
℃気温
0
100
200
300
400
年平均気温16.9℃年降水量1959.6mm
3 5 7 9 111
mm降水量
年平均気温13.3℃年降水量2779.0mm
-10
0
10
20
30
℃気温
0
100
200
300
400
mm
3 5 7 91
降水量
11月
年平均気温8.5℃年降水量1127.6mm
-10
0
10
20
30
℃気温
0
100
200
300
400
mm
3 5 7 9 111 月
降水量 年平均気温11.7℃年降水量901.2mm
-10
0
10
20
30
℃気温
0
100
200
300
400
mm
3 5 7 91
降水量
11月
年平均気温22.7℃年降水量2036.9mm
-10
0
10
20
30
℃気温
0
100
200
300
400
mm
3 5 7 91
降水量
11月
年平均気温15.8℃年降水量1141.0mm
-10
0
10
20
30
℃気温
0
100
200
300
400
mm
3 5 7 91
降水量
11月
-
付録の解説
19
地誌を極める! ヨーロッパ編
昭和学院中・高等学校 西岡陽子
ステップアップワークシート⑩
教科書:『高等学校 新地理A 初訂版』地図帳:『新詳高等地図 初訂版』
国連気候変動枠組み条約 第17回締約国会議、通称
COP(Conference of the Parties)17が2011年12月11日
閉幕した。毎年開かれてきたこの会議も、今回は、京都
議定書が12年末で期限を迎えることからとくに注目が集
まった。議定書の延長をめぐって議論は分かれ、「発展
途上国に温室効果ガス削減を義務づけない議定書の延長
反対」の立場をとる日本、カナダ、ロシアと、「議定書
を延長し、条約の全締約国に適応する新たな温暖化対策
のための法的枠組みづくりをめざす」それ以外の国々に
分かれた。15年までには枠組みを決め、20年の発効を
めざすとする。EUや、CO2排出量世界一の中国を始め、
インド、ブラジル、南アフリカ共和国などの新興国・途
上国グループや議定書に不参加であったアメリカ合衆国
もこの案に合意している。日本は議定書発祥の地であり
ながら、「新枠組みまで自主的な対策を実施する」とし
て合意せず、温暖化防止に積極的でないと、環境活動
NPOからカナダ、ロシアとともに「化石賞」を授与さ
れたのは残念なことである。
ヨーロッパの地体構造は、南部、地中海沿岸に新期造
山帯であるアルプス=ヒマラヤ造山帯が横切り、北部に
は平原や丘陵性の安定陸塊が分布している。
ヨーロッパの河川は、日本と違い大小を問わず平原を
ゆったりと蛇行しながら流れている。ライン川を始め、
張りめぐらされた運河は国々を越え、複雑な水路網が道
路網、鉄道網を補っている。いくつもの閘門を設置する
ことで勾配を克服し、小さな川では乗船者が自ら閘門を
開け閉めして通行する。家族で船を何日も貸し切る川旅
は人気のある娯楽の一つである。
地中海地方は、日本とほぼ同緯度にある。地図帳でぜ
ひ確認してほしい。地中海沿岸地方は中緯度高圧帯に位
置し、夏は暑く乾燥する。耐乾性のオリーブ畑の根元は
赤茶けた土で覆われている。紺碧の空と海に白壁の家の
風景が美しい。浜辺は海水浴客でにぎわいをみせるが、
老人の熱中症死も報じられる。一方、北西ヨーロッパは
日本よりかなり北にある。西岸海洋性気候のイギリスや
ドイツの海岸では夏でも泳がず潮風にあたるだけの人も
多い。当然水温はかなり低い。ロンドンの7月の平均気
温17.1℃と東京の10月の平均気温18.2℃を比べれば涼し
さが理解できるであろう。真夏の衣料品店では夏物と冬
物が並んで売られている。夏はさわやかで快適、冷房装
置はない。冬は暖流と偏西風によりスカンディナヴィア
半島西岸は不凍港となり、冬でも漁が可能である。
ヨーロッパ中央部では伝統的に混合農業(家畜の飼育
と組み合わせることで、飼料と肥料を自給する合理的な
農業)が行われてきた。穀物は西部・南部では小麦が栽
培されパンやパスタに加工される。北部ではライ麦が栽
培され黒パンになる。発酵させ酸味のある固い黒パンは
栄養価も高く、ドイツや北欧の人々にはなくてはなら
ないものである。えん麦も広く栽培されているが、これ
はビスケットやオートミールの材料となるほか、主要
な家畜飼料である。大麦も北部ではワインのかわりに
飲むビールの材料であるが、これも主として飼料である。
ドイツ人の食卓に欠かせない じゃがいも も飼料になる。
冷涼なヨーロッパ北西部では、酪農が広く行われ、バラ
エティに富むチーズなど乳製品を生産している。
一時は衰退したヨーロッパの工業も、1960年代の北海
油田、天然ガス田の開発を機に再生した。ヨーロッパの
工業をリードするのは、高品質、高価格で輸出向けを主
とするハイテク産業と工芸品産業である。これらは、重
工業がほとんどなかった地域に立地している。イギリス
(イングランド)、ドイツ、フランスそれぞれの南部は、
これらの国々の北部をしのいで製造業の中心地となった。
ハイテク産業の集中地は、ロンドン西方の「M-4回廊」
や、グラスゴー周辺の「シリコングレン(グレンはスコッ
トランド方言で谷の意)」、パリ南西の「サイエンス・シ
ティ」、フランスの地中海沿岸、オランダの環状都市圏
のほか、ミュンヘン、アウクスブルク、ニュルンベルク
やドイツの南部のいくつかの都市にみられる。なお、ヨー
ロッパのハイテク産業は、アメリカ合衆国に比べかなり
遅れをとっている。
工芸品の製造地域として特筆すべきは「第三のイタリ
ア」(サードイタリー)である。イタリア中央部の田園
地帯に散在する中小都市に発達した地場産業であり、そ
ウォーミングアップ!
地理の授業にあたって
ステップアップ!
-
20
の高い国際競争力が注目を集めている。フェラーリなど
の高級乗用車やコモ産の絹製品、ヴィチェンツァ産宝飾
品などである。ヨーロッパのほかの国にもこの種の工業
が発達してきている。
ヨーロッパの環境問題への意識の高さはつとに知られ、
多くの取り組みがなされてきた。京都議定書のCO2削減
目標も日本はなかなか達成できていないが、ヨーロッパ
では多くの国が削減に成功、EU全体としても目標を達
成している。炭素税も1990年以降各国で導入され、現在
では11か国にのぼる。
福島第一原子力発電所事故以来、世界的に原子力発電
を見直す動きがみられ、EUでも域内14か国にある143基
の原子力発電所を対象にした安全性テスト(ストレステ
スト)の実施計画をまとめた。ドイツでは2022年までに
国内に17基ある原子力発電所を閉鎖すると決定、スイス
でも34年までに5基を全廃することを決めた。なお、ス
ウェーデンは、すでにアメリカ合衆国のスリーマイル島
の事故後に撤退を決めている。原子力発電はドイツで現
在電力供給の23%、スイスでも39%を担っている。温暖
化防止の有力な切り札とされてきただけに、再生可能エ
ネルギーの開発が急がれる。
北欧の福祉の充実ぶりは感嘆に値する。スウェーデン、
デンマークとも生涯、医療も教育もすべて無料、老人
ホームや訪問介護費用も年金で十分まかなえるので老後
の心配もない。ドイツでも大学の授業料はほぼ無料であ
り、また、子ども手当も充実している。第1子、第2子
は各164ユーロ(※)、第3子170ユーロ、第4子以降は
各195ユーロ、子どもが学業終了(最高25歳)まで受給
できる。産休中の所得保障も日本が60%に対し、100%
である。ちなみに消費税は、スウェーデン25%(食料品
は12%)、ドイツ19%(同7%)である。
第二次世界大戦後、アメリカ合衆国、旧ソビエト連邦
の2大勢力に危機感をもち、国境を越えた結びつきが模
索された。当初、小国であるベネルクス3国の関税同盟
から始まり、当時の大国、ドイツ、フランス、イタリア
が加わって、石炭、鉄鋼の共同管理や関税引き下げを目
的に始まった。1960年には、イギリスがEECに対抗し
て、EFTAを結成したもののうまく機能せず、結局解散
して現在のEUに合流することになった。その後も経済
同盟として加盟国間の自由貿易を大きな柱として成長し
たEC(European Community)は、マーストリヒト(オ
ランダにある条約締結地)条約を採択した後、政治統
合にまで踏み出しEU(European Union)に名称変更し
た。英語のUnionはCommunityより強い結びつきを意味
する。「ステップアップワークシート⑩ 12.」のように
統合は進んでいる。食料品、とくに野菜や果物の種類は
豊富になった。隣国への買い物や通勤も可能である。一
方、高学歴者がドイツなど経済状態のよい国に流入する
問題も起きている。他国でも、地方参政権は与えられて
いる。現在欧州憲法を締結するところまできたが、加盟
国間の批准に対する足並みがそろっていない。イギリス
は独自路線をとることが多く、国境でのパスポート審査
を廃止するシェンゲン(Schengen)協定にもアイルラ
ンドとともに参加していないし、ユーロも未使用である。
今回のEU全体を襲った財政危機を乗り切るための解決
策でも、ただ一国条約改正に反対した。
EU加盟国は、かつての東欧諸国にも広がり27か国に
達しているが、さらにクロアチアの加盟が予定されてい
る。今後新条約を各国が批准すれば2013年7月をめどに
実現し、28か国になる。旧ユーゴスラビアの内戦経験国
では初となる。一方で、アイスランド、ノルウェー、ス
イスは加盟を拒否している。スイスは同盟には属さない
ことを国是としているが、ほかの2国は規律に縛られる
ことを懸念したと思われる。
トルコの加盟問題は10年来の懸案事項である。国民の
大部分がムスリムであることが問題の根底にある。また、
周辺諸国からの難民流入も課題である。とくにアラブ諸
国に連鎖する政変のあおりで北アフリカからの難民流入
の増大が問題となっている。一国で国境管理に失敗する
とその後の移動が自由になってしまうため、国境審査相
互撤廃を定めたシェンゲン協定を見直しする動きがある。
ギリシャの巨額財政赤字に端を発した今回のヨーロッパ
の財政危機は、他国の国債利率上昇を招くなど、ヨーロッ
パ全体に大きな影響を及ぼし、加盟国が増えることへの
問題点をうかがわせた。「財政赤字を一定割合に抑える
などの財政規律を各国が法制化し、違反した場合は自動
的に制裁を行う」財政規律強化策でようやく合意をみて
収束に向かったが、加盟国間の経済格差は今後も問題と
なるであろう。
※2011年12月現在、円高が進み、1ユーロ=約100〜110円である。
ジャンプアップ!
■参考文献T.G.ジョーダン=ビチコフ・B.B.ジョーダン共著 山本正三他訳
『ヨーロッパ−文化地域の形成と構造』2005 二宮書店
「特集:北欧の歴史と文化」『歴史地理教育』№725 2008年2月号
歴史教育者協議会
竹﨑孜著『スウェーデンの税金は本当に高いのか』2005 あけび書房
-
21
ちりさんぽ 〜地形図とともに出かけよう〜
1
2
34
5
5
6
STSTSTSTSTSTSTSTSTSTARARARARARARARARARARTTTTTTTTTTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTARARARARARARARARARARTTTTTTTTTT
GOGOGOGOGOGOGOGOGOGOALALALALALALALALALALGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOALALALALALALALALALAL
蔵造りの町並み蔵造りの町並み
1866(慶応2)年ごろの川越城の位置1866(慶応2)年ごろの川越城の位置
写真の方向
さんぽルート
凡 例
第6回のフィールドは、埼玉県川越市中心部をめぐるコースです。川越は、江戸時代に江戸城の北の守りとして重視された川越城の城下町として発展しました。1638(寛永15)年の大火がきっかけとなり、現代の町の基礎がつくられました。翌年、城主となった松平信綱は、川越城の整備と町割りを行い、川越城は大拡張されました。このときの町割りは現在でも色濃く残っています。東武東上線川越駅東口を出て、川越街道を北上していくと、かぎの手に曲がったクランク状の道が2か所みられます。見通しを悪くし、城に敵が侵入しづらいようにするための城下町特有の道です。 川越は、江戸と結ばれた新
しん
河が
岸し
川がわ
の舟しゅう
運うん
で発展してきました。前述の大火で焼け落ちた仙
せん
波ば
東照宮の再建資材を江戸から運ぶために舟運を利用し、さらに新河岸が設けられると新河岸川は重要な水運の役割を果たすようになりました。やがて新河岸の河岸場は、上と下の2か所にわ