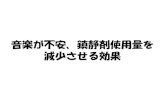群論入門 2lionfan/group2.pdf群論入門 2 -部分群・ 巡回群・ 剰余類- (p443-p449) また会えたね!張り切っていこう!部分群とは何か?ある群Gの
ネフローゼ症候群について - 群馬大学小児...
Transcript of ネフローゼ症候群について - 群馬大学小児...
診断基準小児特発性ネフローゼ症候群診療ガイドライン2013より
1. 高度蛋白尿
夜間蓄尿で40mg/hr/㎡以上または早朝尿で尿蛋白クレアチニン比2.0g/gCre以上
2. 低アルブミン血症
血清アルブミン2.5g/dl以下
1と2を両方満たす
診断基準厚生労働省特定疾患ネフローゼ症候群調査研究班より
• 蛋白尿
1日の蛋白量は3.5g以上ないし0.1g/kg/day、または早朝第一尿で300mg/dl以上の蛋白尿が持続する。
• 低蛋白血症
血清TP:学童・幼児6.0g/dl以下、乳児5.5g/dl以下
血清Alb:学童・幼児3.0g/dl以下、乳児2.5g/dl以下
• 高脂血症血清T-CHO:学童250mg/dl以上、幼児220mg/dl以上、乳児200mg/dl以上
• 浮腫 *蛋白尿、低蛋白血症は必須条件*高脂血症と浮腫は必須条件ではないが、これを認めれば診断はより確実
分類
•特発性ネフローゼ症候群:90%
•その他:10%急性腎炎、慢性腎炎、Alport症候群などの遺伝性腎疾患、HBV・HCV腎症などによる二次性ネフローゼ症候群
微小変化型:MCNS(80-90%)
巣状分節性糸球体硬化症:FSGS(5-10%)
その他膜性腎症、膜性増殖性糸球体腎炎など
組織型分類
言葉の定義
用語 定義
完全寛解 試験紙法で早朝尿蛋白陰性を3日連続して示すもの、または早朝尿で尿蛋白クレアチニン比0.2g/gCr未満を3日連続して示すもの
不完全寛解 試験紙法で早朝尿蛋白1+以上または早朝尿で尿蛋白クレアチニン比0.2g/gCr以上を示し、かつ血清アルブミン2.5g/dlを超えるもの
再発 試験紙法で早朝尿蛋白3+以上を3日連続して示すもの
ステロイド感受性 プレドニゾロン連日投与開始後4週間以内に完全寛解するもの
頻回再発 初回寛解6か月以内に2回以上再発、または任意の12か月以内に4回以上再発したもの
ステロイド依存性 プレドニゾロン減量中またはプレドニゾロン中止後14日以内に2回連続して再発したもの
ステロイド抵抗性 プレドニゾロンを4週間以上連続投与しても、完全寛解しないもの
難治性ネフローゼ症候群
ステロイド感受性のうち、標準的な免疫抑制薬治療では寛解を維持できず、頻回再発型やステロイド依存性のままで、ステロイドから離脱できないものステロイド抵抗性のうち、標準的な免疫抑制薬治療では完全寛解しないもの
体液異常の病態
• Underfilling仮説
尿中へ血漿蛋白が大量喪失することで血清蛋白が低下し、血漿膠質浸透圧が低下して生じる
• Overfilling仮説
遠位尿細管や集合管におけるNa排泄の低下と再吸収亢進が生じ、Na貯留によって血管内容量が増加した結果、静水圧が高まり浮腫が生じる
浮腫出現の成因は単独ではなく、同一症例でも経過中に変化しうると考えられる
浮腫の管理
水分制限
ガイドラインでは不要とされているが、実際はOverfillingの病態であることが多く、「水分摂取量=前日尿量+不感蒸泄量」を大体の目安として行っている。
塩分制限
蛋白尿、高度浮腫を呈している時には、利尿薬の有効性を期待するためにも推奨される。3g/day程度で開始する事が多いが、過度の塩分制限は食欲を減退させ、必要な栄養摂取の妨げになることもあるので注意が必要。実際の摂取量で評価し、浮腫が改善すれば解除する。
利尿薬
• 尿中Na排泄と水排泄を促すために使用
• 7-10%以上の体重増加を伴う浮腫やoverfillingを推定させる持続性浮腫を呈する症例で使用を考慮
• 第一選択薬はループ利尿薬(エビデンスがあるのはフロセミドのみ):副作用は電解質異常、代謝性アルカローシス、腎石灰化、聴力障害
• 持続静注は反復投与による効果減弱を防ぎ、血中濃度が高値にならない投与法だが、ネフローゼ症候群におけるエビデンスはない
フロセミド0.5-1mg/kg/dose 静注または経口
アルブミン製剤
• 低血圧の是正と腎血流増加による利尿を目的
• 適応は有効循環血症量低下によるショックや利尿薬のみでは管理できない難治性浮腫の場合
• 過量投与や急速静注は肺水腫や心不全を引き起こすため、underfillingを評価したうえで使用
高濃度アルブミン(20%, 25%)0.5-1g/kg/dose 2-4時間かけて点滴静注*投与前、30分後、終了時の血圧チェック
その後、フロセミド0.5-1mg/kg/dose 静注
主な降圧薬
<カルシウム拮抗薬>
ニフェジピン徐放 0.25-0.5mg/kg/dayから開始 分1-2 最大3mg/kg/day 60mg/dayまで
アムロジピン 0.06mg/kg/dayから開始 分1 最大5mgまで
ニカルジピン 1-3μg/kg/min 持続静注
<アンジオテンシン受容体拮抗薬>
ロサルタン 0.7mg/kg/dayから開始 分1 最大1.4mg/kg/day 100mg/dayまで
カンデサルタン 0.05-0.4mg/kg/dayから開始 分1-2
<アンジオテンシン変換酵素阻害薬>
エナラプリル 0.08mg/kg/dayから開始 分1 最大10mg/dayまで
カプトプリル 0.9-1.5mg/kg/dayから開始 分2-3 最大6mg/kg/dayまで
*第一選択薬はカルシウム拮抗薬
血栓症の発症頻度
• 9調査研究(総数458症例)での平均発症頻度は25%で多くが静脈血栓。 Kidney Int 1985;28:429-439
• 298症例を10年間追跡した研究では、静脈血栓発症率が1.02%/年、動脈血栓発症率が1.48%/年で一般集団の約8倍。特に発症6か月以内の静脈血栓発症率は9.85%と高率。
*過去、群馬大学及び関連病院でも6例の血栓症あり
血栓症の発症機序• 腎臓からの凝固因子の漏出、とくに分子量の小さい程、尿に漏出しやすく、血漿中AT-Ⅲが低下し、静脈血栓症の危険因子要因と考えられている
Am J Med 1978;65:607-613, Arch Intern Med 1984;144:1802-1803
• 肝臓でのアルブミン合成亢進に付随して、FbgやⅤ因子、Ⅷ因子などの肝臓由来凝固因子が増加し、凝固性が亢進する Thronb Res 2006;118:397-407
• 肝臓でのリポ蛋白合成が亢進し、Ch、LDL-Ch、Lp(a)が増加し、血管内皮の機能不全や動脈硬化が惹起される
N Engl J Med 1990;323:579-584, Kidney Int 1993;44:1116-1123
• 低蛋白や低アルブミンにより、血漿膠質浸透圧の低下が血管内脱水を招き血栓傾向を助長する
感染症• 免疫グロブリンを含む高度の低蛋白血症
• 浮腫による細菌防御能の低下
• 長期のステロイドや免疫抑制薬投与
免疫不全状態
<対応>
・状況によりIgG製剤の投与IgG<200の時に200-400mg/kg/doseで投与
・水痘接触時は抗ウイルス薬の予防投与接触の7-10日後からアシクロビル80mg/kg/day分4またはバラシクロビル
60mg/kg/day分3を7日間
・可能な限り予防接種
食事
•塩分
浮腫改善に対して塩分制限推奨
•タンパク質
腎不全への進行なければ、成長期であることを考慮して年齢に応じた蛋白摂取を推奨
•エネルギー
年齢に応じた摂取を推奨するが、ステロイドによる肥満に注意
運動
•急性期の循環動態が不安定な場合や溢水による高血圧などがみられる場合は安静
•寛解期は骨粗鬆症や肥満の予防のために適度な運動を推奨
•極端な運動制限は小児のQOLを落とし、発育期の体と心の健全な発育を阻害する
検査•血液検査血算、凝固(AT-Ⅲ忘れずに)、生化(TP, Alb, 蛋白分画, トランスフェリン, T-CHO, TG, AST, ALT, LDH, UA, BUN, Cre, Na, K, Cl, Ca, IP, C3, C4, CH50, ASO, ASK, IgG, IgA, IgM, IgE, 抗核抗体, HBVAg, HCVAb)
•尿検査定性、沈査、β2MG、NAG、蛋白定量、Cre、トランスフェリン、IgG
•エコー腹水や器質的腎疾患の有無、循環血症量の評価
•胸部レントゲン胸水の有無
S.I(selective index)=(U IgG×P Tf)/(P IgG×U Tf)
治療 例:身長100cm 体重15kg 体表面積0.64㎡
• 5%Glu(250ml)+Hp 2.4ml 10ml/hr(Hp 154単位/kg/day)
•プレドニン 20-10-10 mg 静注(プレドニン 62.5mg/㎡/day)
•ガスター 20mg 静注
•内服:ビタミンD製剤、ジピリダモール
免疫抑制薬
シクロスポリン
• 寛解維持率が高いが、中止後の再発率も高い
• 2.5mg/kg/day程度から開始(分2 食前)
• 血中濃度をモニタリング:C2 500-600ng/ml程度で管理
• 副作用
①高血圧:PRES(posterior reversible encephalopathy syndrome:可逆性後部白質脳症症候群)に注意
②腎毒性:2年使用したら半年程度休薬し、再開時には腎生検でCsA腎症について評価
シクロフォスファミド• 2-2.5mg/kg/day(最大100mg)で8-12週 分1で投与
• 投与は1クールのみとし、累積投与量は300mg/kgを超えない
• 副作用
①性腺抑制→思春期には使用しない
(男児8歳、女児7歳以下を目安に)
②骨髄抑制
③出血性膀胱炎
④催腫瘍性
ミゾリビン• 安全性が高いが、再発抑制効果は弱い
• ピーク濃度C3:3μg/ml以上で再発予防効果期待
• 副作用:尿酸値上昇
ステロイドパルス療法• mPSL 20mg/kg/dose(最大1g)1日1回 1週間に3日間連続を1クール
•浮腫が強いとき、1クール目はmPSL10→15→20mg/kg/doseと漸増することも
•パルス中は血圧チェックと心電図モニター装着
•シクロスポリンと併用で寛解導入に有効
実際のメニュー(体重10kgの時)①5%Glu(250ml)+Hp 1.5ml 10ml/hr (Hp 96単位/kg)
②ソル・メドロール 300mg+5%Glu(100mg)+Hp 0.75ml(ソル・メドロール20mg/kg、Hp 50単位/kg)
リツキシマブ
• 2014年8月に難治性頻回再発/ステロイド依存性ネフローゼ症候群に対して適応拡大
•寛解期間の延長が課題
•ステロイド抵抗性への応用
•高率なInfusion reaction出現
•長期的な有害事象
好中球減少症、無顆粒球症、進行性多発性白質脳症、肝炎再活性化、肺線維症、炎症性腸疾患など
ステロイドの副作用
• 成長障害:ステロイドの隔日投与は成長障害軽減に有用
• 骨粗鬆症:定期的な骨密度の評価、Vit.D製剤、成人ではビスフォスフォネート製剤
• 緑内障・白内障:早期の眼科受診
• 易感染性
• 胃粘膜障害
• 神経症状
• 食欲亢進
• 中心性肥満、満月様顔貌
腎生検の適応
•発症時に、①1歳未満、②持続的血尿、③高血圧、腎機能障害、④低補体血症、⑤腎外症状(発疹、紫斑など)があり、微小変化型以外の組織型の可能性がある場合
•ステロイド抵抗性の場合
•シクロスポリンを長期に使用する場合