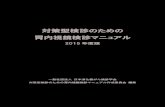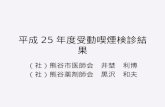ピロリ菌除去 に潜むリスク X線・内視鏡検査の必要 …22...
Transcript of ピロリ菌除去 に潜むリスク X線・内視鏡検査の必要 …22...
20
まずは皆さんに質問があります。がん検診について、どう考えていますか。おそらく、「よく見つかる検診がよい」「検診に害はない」「がん検診はやらないよりやったほうがよい」と考えているのではないでしょうか。じつは、これらの考えは必ずしも正しいとはいえません。なぜなら、検診には、利益と不利益という両方の面があるからです。利益は、いうなればがんの早期発見や罹患の予防、不利益は検査に伴う合併症や過剰診断です。過剰診断とは、放置しても症状が出ることはなく、検査を受けなければ診断されることのないがんを見つけてしまうことです。韓国では、こんな例があります。乳がん検診のついでに甲状腺がんの超音波検査を実施したところ、多く
の人に甲状腺がんが見つかり、数年後には罹患率の 1位になりました。しかしながら、甲状腺がんのほとんどは進行が遅く予後のよいがんであり、もし小さな病変があっても治療が必要ながんに進展しないことが多いのです。実際に韓国では、罹患率が1位でも死亡率は非常に低く、しかも検診の導入前後で死亡率は変わりませんでした。それでも検診でがんが見つかれば、当然、不安な気持ちになり、中には本来は不要だったかもしれない手術を受ける人もいるでしょう。つまり、よく見つかるがん検診がよいとは限らないのです。また、検診施設によっては、がんを見逃してしまうなど、質の悪い検診を行っているところもあります。こうした検診を受けることも不利益となります。がん検診は、利益が多く、不利益が少ないものでなくてはいけません。こうしたことを頭においたうえで、がん検診について理解を深めてほしいと思います。
ピロリ菌と関係しない胃がんは1%弱胃がん検診は、地方自治体が実施する国の対策型検診としては胃のX線検査が行われ、企業検診や人間ドックなどの任意型検診ではX線検査の他に内視鏡検査も実施されています。そうした胃がん検診のシステムに、最近あらたに加わってきたのが、「ヘリコバクターピロリ抗体検査」と「ペプシノゲン検査」です。
がんから身をまもるシリーズ
渋谷大助(しぶや・だいすけ)1979年、東北大学医学部卒。同年、いわき市立総合磐城共立病院内科勤務。82年東北大学大学院医学研究科入学、86年同大学院卒業。同大学附属病院助手、仙台市立病院消化器科医長など経て、99年4月より現職。日本消化器がん検診学会、第24回 有賀記念学会賞受賞。日本消化器がん検診学会役員、胃がん検診精度管理担当。
「ピロリ菌除去」に潜むリスクX線・内視鏡検査の必要性宮城県対がん協会がん検診センター所長
渋谷大助胃がんの発生原因の99%がヘリコバクターピロリ(ピロリ菌)の関与によるものだ。いわゆる中高年層の60%以上が感染しているともいわれ、ピロリ菌除去を含む新しい検診法が登場してきた。しかし、ピロリ菌を除去したからといって、従来のX線検査、内視鏡検査は受けなくてもいいと短絡するのは危険という―。
第3回 胃がん
構成◉藤原ゆみ composition by Yumi Fujiwara
Special Features 2
21
粘膜の表面に炎症を起こします。この状態を「慢性活動性胃炎」といいます。胃粘膜の奥にまで炎症が進むと、粘膜が痩せ衰えて萎縮する、「萎縮性胃炎」という状態になり、胃粘膜の萎縮がさらに進むと、「腸上皮化生」という腸の粘膜に似た細胞が出現してきます。この状態になるとピロリ菌が棲めない環境となり、ピロリ菌は消失していきます。こうした胃粘膜の萎縮が進行してい
く過程で、胃の細胞の遺伝子が傷つけられてしまい、がんの発症へとつながるのです。ただし、ピロリ菌に感染しても必ずがんになるわけではなく、発生率は 1年で0.4%と、わずかな割合です。がんの発症には、ピロリ菌の毒性の強さや胃内の環境、体質、また多量の塩分摂取や野菜不足、喫煙などが関与しているといわれています。このピロリ菌の有無を調べるのが「ヘリコバクターピロリ抗体検査」、胃粘膜の萎縮の進行度をみるのが「ペプシノゲン検査」で、どちらも血液検査です。ペプシノゲンは、胃粘膜で作られる消化酵素ペプシンのもとになる物質で、胃粘膜の萎縮が進むと、このペプシノゲンの産生能が低下し、量が減少していきます。
定期的な胃X線や内視鏡検査は必要これら2つの検査によって、ピロリ菌感染陰性で胃粘膜の萎縮がない健康な胃を「A群」、ピロリ菌感染はあるが萎縮は進んでいない状態を「B群」、ピロリ菌感染があり萎縮が進行した状態を「C群」、ピロリ菌は陰性だが、萎縮が進行した状態、つまりピロリ菌が棲めないほどに荒廃した胃の状態を「D群」と分類します。AからDの順に、胃がんのリスクが高くなります。現実的には、D群の数は非常に少ないため、CとDをま
これらを組み合わせた検査は、「ABC(D)検診」、「胃がんリスク検診」などとよばれ、多くの施設で実施されています。自治体の中でも、胃X線による胃がん検診とともに「ABC検診」を取り入れているところが出てきており、中には「ABC検診」だけを行い、胃X線による検診は任意型検診を勧めるという自治体もあります。ご存じの方も多いと思いますが、近年、胃がん発生の最大の危険因子は、ピロリ菌の感染であることが明らかになっています。胃がんの99%以上はピロリ菌に感染した胃粘膜から発生しており、ピロリ菌と関係のない胃がんは1%弱しかありません。ピロリ菌は胃粘膜の表面に棲み着く細菌で、乳幼児期に感染するといわれています。感染経路は、不衛生な水やピロリ菌感染者の唾液から経口感染するのではないかと推測されています。日本では、年齢が上がるほどピロリ菌の感染率は高く、中高年では60%以上が感染しているといわれています。そのため、将来的には胃がんは少なくなっていくと考えられますが、ピロリ菌感染者が多い団塊の世代が高齢になっていくここ数年は、まだまだ胃がんは増えると予想されます。さて、ピロリ菌感染がどのようにがんの発症へとつながるか説明していきましょう。胃の中に棲み着いたピロリ菌は、胃粘膜細胞にダメージを与え、まずは胃
血清ペプシノゲンを測定することによって、胃の健康度がわかる。ピロリ菌の抗体検査と組み合わせることによって、胃がんのリスクが分類できる。
A群ペプシノゲン 陰性ピロリ菌 陰性
正常粘膜 慢性活動性胃炎 萎縮性胃炎 腸上皮化生(高度萎縮)
胃は健康な状態 ピロリ菌に感染しているが、胃粘膜萎縮は軽い状態
ピロリ菌の感染に伴う萎縮が進行した状態
萎縮が進行して腸上皮化生が現れると、ピロリ菌が棲めなくなる
B群ペプシノゲン 陰性ピロリ菌 陽性
C群ペプシノゲン 陽性ピロリ菌 陽性
D群ペプシノゲン 陽性ピロリ菌 陰性
胃がんの危険度 大小
■ピロリ菌感染による胃粘膜萎縮の進展と胃がん発生リスクの増大
22
とめてC群とする検診施設もあります。しかし、この「ABC検診」には問題点があります。それは、本当にA群の人はがんのリスクが低いのか、がん検診の必要性はないのかということです。実際に、当センターのデータを調べたところ、295の胃がんの発症例のうち、20例、つまり6.8%にA群からの発症がありました。そのうちの2例は、ピロリ菌感染が関係のない胃がんを発症していました。ピロリ菌の感染がなくても発症する胃がんには、食道と胃の境界にできる噴門部がんや胃底腺型胃がん、早期の印環細胞がんがあります。印環細胞がんには悪性度の高いがんと低いがんがありますが、ピロリ菌感染が関係のない胃がんは悪性度が低いがんです。胃底腺型胃がんも悪性度が低く、ピロリ菌感染が関係のない胃がんの中では噴門部がんが要注意です。この2例に関しては、前述したとおり、ピロリ菌感染の関係のない胃がんが1%弱存在するため、予測の範囲内のものです。では、残りの18例はなぜ胃がんになったのか。答えは、偽A群だったからです。ペプシノゲン検査では陰性という結果だったにもかかわらず、胃X線や内視鏡では胃粘膜の萎縮が確認できたのです。ペプシノゲン検査はあくまで血液検査であり、胃の中を直接みているわけではないため、胃粘膜の萎縮があったとしてもピロリ菌抗体価やペプシノゲン値が異常値を示さないとA群と判定されてしまうからです。この人たちを偽A群といいます。原因は、除菌治療によってピロリ菌が消失したか、もしくは風邪などの感染症で抗生物質を服用したことによって知らないうちにピロリ菌が消失したためと推測されます。つまり、ピロリ菌を除菌しても、何年か経過するとピロリ菌由来の胃がんになってしまうのです。なぜなら、一度ピロリ菌に感染すると、除菌するまでに炎症によって胃粘膜の細胞の遺伝子に傷がついている可能性が高く、それががんに発展してしまうことがあるからです。この偽A群の存在は非常に危険です。本当は胃がんのリスクがあるのに、リスクがほとんどないと評価されてしまったら、ほとんどの人が安心して胃がんの検診を受けなくなることでしょう。その結果、がんを見
逃すことになれば、わざわざ検査を受けたにもかかわらず、患者さんに大きな不利益が生じてしまうのです。そもそも、「ABC検診」は、胃の健康度検査であり、胃がん検診ではありません。胃がんの有無をみるには、定期的な胃X線や内視鏡検査といった画像検査が絶対に必要なのです。そのため、「ABC検診」という名称にも問題があると考えます。正しくは、「ABC分類(評価)に基づく胃がん検診」という用語を用いて、胃
X線検査や内視鏡検査とセットで行うべきなのです。
ピロリ菌除菌を過信するのは禁物偽A群の存在がABC分類の大きな問題点であり、しかも今後はこの偽A群が増えていくことが予想されます。なぜなら、ピロリ菌を除菌する人が増えてくるからです。もともとピロリ菌の除菌療法は、胃・十二指腸潰瘍や早期胃がんの治療後など、4種類の疾患で保険適用となっていましたが、去年よりピロリ菌感染による慢性胃炎にも適用になりました。そのため、ピロリ菌に感染し胃に萎縮があることが確認できれば保険適用となり、多くの人が除菌治療を受けやすくなっているのです。そもそも、ピロリ菌を除菌すると、もうがんにかからないと思ってしまいがちです。しかしながら、除菌治療が完了していても、がんのリスクがあることは前述したとおりです。付け加えるならば、慢性胃炎患者において、除菌によるがん予防効果は約 30%といわれています。まずは“除菌したらがんにはならない”という認識を改めることが必要です。これまでの問題点を考えると、ABCにリスクを分類すること自体に意味はあるのでしょうか。私は、真のA群とそれ以外という2つの分類でよいのではないかと考えています。真のA群とは、これまでピロリ菌に感染したことがなく、胃粘膜の萎縮もない健康な胃の状態の人です。この真のA群を見極めるのには、まずは問診が大切です。過去にピロリ菌の除菌をしたかどうかを確認し、もし除菌をしたのであれば、血液検査は行わずに胃X線検査か内視鏡検査を実施します。そして年に1度の胃X線検査か、2年に1回の内視鏡検査を受けてもらうようにします。そして、問診で除菌をした人を除外したうえで、血
23
液検査だけではなく、胃X線または内視鏡検査といった画像検査をあわせて行っていきます。除菌したことを忘れたり、自然とピロリ菌が消失したりするケースを見逃さないためにも、画像検査は重要です。血液検査と画像検査で真のA群と判断されれば、その後は対策型検診としての胃X線・内視鏡検査は不要だと考えます。特に今後は、ピロリ菌未感染者が増えてくるので、不要な検査を行わないほうが、人々の不利益にならず、医療費も抑えることができます。ただし、1%弱のピロリ菌感染に関係しないがんがあるため、家族にそうした胃がん罹患者がいるなど遺伝的素因がある人は任意型検診を受けるとよいでしょう。真のA群以外の人は、胃がんのリスクがあるとして、年に1度の胃X線検査か、2年に1回の内視鏡検査を実施します。
「ABC分類検診」の効果的な活用さらに私が考えていることは、除菌した人の中でもがんにならない人、がんになる人というのを画像検査などから見極めることができるのではないかということです。そうすることで、除菌した人でも真のA群と
同等に扱うことができれば、余計な検診を受けずにすみ、また医療費も抑えることができます。そのために、除菌者を真のA群と同等だと判断するための基準を作りたいと思っています。いずれにせよ、現行の
ABC分類も含めてリスク分類に基づく胃がん検診では、その後複数年にわたり、画像検査による胃がん検診を促し、管理していくことが必要です。しかし、現実にはこうした管理検診は困難であるというのも確かです。とはいえ、今後、ピロリ菌
未感染者が増えてくることを考えると、余計な検診をしないためにもリスク分類は必要であり、胃がん検診のシステムに「ABC分類に基づく胃がん検診」をどう取り入れるかについては、これからも十分な検討が必要だといえるでしょう。他にも胃がん検診においては、さまざまな課題があります。例えば、内視鏡検査の有効性については議論の対象になっていますが、現在では胃X線の有効性には及ばないとし、国の対策型検診では胃X線のほうを用いています。しかしながら、地域によっては胃のX線設備をもたない医療施設もあり、今後は内視鏡検査も対策型検診として認められる必要もあるでしょう。さらに現在、中学生ではピロリ菌に感染している人はたったの5%といわれており、これからはピロリ菌の感染者がどんどん少なくなってきます。そうした状況に合わせて、胃がん検診のあり方は変化していくでしょう。しかし、どの時代にあっても、検診がもたらす利益と不利益を念頭におきながら、がんを見逃さないように、そしてがんで死なないように検診に取り組んでほしいと思います。
Special Features 2がんから身をまもる 第3回 胃がんシリーズ
高齢者早期がん高分化型
若年者進行がん未分化型
検診での発見率は低いが救命価値が高いがんが多い
検診での発見率は低いが診察などで発見される症例数は多い
検診での発見率は高いが過剰診断が増える可能性がある
Hp未感染で萎縮のない健康な胃 A群:Hp-/PG-
A群へのHp既感染者の混入
Hp未感染者の慎重な判定が重要!
胃粘膜萎縮の進行C群:PG+/Hp+B群:PG-/Hp+
Hp……ヘリコバクターピロリPG……ペプシノゲン
D群:PG+/Hp-
検診での胃がん発見率
Hp抗体 PG法
(図版提供:渋谷大助)
未分化型のがんは萎縮のない胃粘膜から発生するといわれている。悪性度が高く、若年者に多い。
■検診で発見した胃がんからみた胃がんリスク評価が抱える問題点