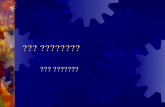参考データ集2000 02 04 06 08 10 12 14 16 18 日本 ドイツ 韓国 英国 米国 中国...
Transcript of 参考データ集2000 02 04 06 08 10 12 14 16 18 日本 ドイツ 韓国 英国 米国 中国...

参考データ集
参考資料4科学技術・学術審議会 学術分科会
研究環境基盤部会(第102回)2019.3.27

目 次
1.我が国の科学技術の現状・・・・・・・・・・・・・・・・・1
2.我が国の研究者を取り巻く状況・・・・・・・・・・・・・・11
3.参考資料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・27

1.我が国の科学技術の現状
1

※日本人受賞者のうち、 2008年南部陽一郎博士、 2014年中村修二博士は、 米国籍で受賞している。
○各国のノーベル賞受賞者数(自然科学系3分野)の推移
○主要国の論文数及びTop10%補正論文数とそのシェアの推移論文数 Top10%補正論文数
○過去の科学技術投資の結果として、2000年以降、我が国のノーベル賞受賞者数(自然科学系)は米国に次いで世界第2位。
○他方、質の高い研究論文数(Top10%補正論文数)について、ここ10年間で中国が2位に躍進する一方、我が国は4位から9位に下降するなど、量的指標となる論文数とともに、シェア及び世界ランクの双方が低下傾向。
1901- 1990年 1991- 2000年 2001-2018年 合計
米国 156 39 70 265
英国 65 3 12 80
ドイツ 58 5 6 69
フランス 22 3 8 33
日本 5 1 17 23
論文数 シェア 順位米国 228,849 25.7 1日本 67,696 7.6 2中国 63,296 7.1 3ドイツ 53,648 6.0 4英国 51,976 5.8 5フランス 38,337 4.3 6イタリア 31,573 3.5 7カナダ 29,676 3.3 8スペイン 23,056 2.6 9韓国 22,584 2.5 10
全分野2004 - 2006年 (PY) (平均)
論文数
国・地域名分数カウント
論文数 シェア 順位米国 273,858 19.3 1中国 246,099 17.4 2ドイツ 65,115 4.6 3日本 63,330 4.5 4英国 59,688 4.2 5インド 52,875 3.7 6韓国 46,522 3.3 7フランス 45,337 3.2 8イタリア 44,450 3.1 9カナダ 39,674 2.8 10
分数カウント
全分野2014 - 2016年 (PY) (平均)
論文数
国・地域名論文数 シェア 順位
米国 34,127 38.4 1英国 6,503 7.3 2ドイツ 5,642 6.4 3日本 4,559 5.1 4中国 4,453 5.0 5フランス 3,833 4.3 6カナダ 3,392 3.8 7イタリア 2,731 3.1 8オランダ 2,146 2.4 9スペイン 2,093 2.4 10
全分野2004 - 2006年 (PY) (平均)
Top10%補正論文数
国・地域名分数カウント
論文数 シェア 順位米国 38,736 27.4 1中国 24,136 17.0 2英国 8,613 6.1 3ドイツ 7,755 5.5 4イタリア 4,912 3.5 5フランス 4,862 3.4 6オーストラリア 4,453 3.1 7カナダ 4,452 3.1 8日本 4,081 2.9 9スペイン 3,609 2.5 10
分数カウント
全分野2014 - 2016年 (PY) (平均)
Top10%補正論文数
国・地域名
我が国の科学技術の現状➀ ~ノーベル賞と論文数~
出典:文部科学省 科学技術・学術政策研究所「科学技術指標2018」(2018年8月、調査資料-274)を基に、文部科学省が加工・作成 2

0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
2000 02 04 06 08 10 12 14 16 18
日本 ドイツ
韓国 英国
米国 中国
年度
科学技術関係予算(指数)
○2000年度を100とした場合の各国の科学技術関係予算の推移
出典:日本:総務省「科学技術研究調査」、他国:OECD, Main Science and Technology Indicators
(年度)
○研究費の政府負担割合の推移
フランス 34.8
ドイツ 28.5英国 28.0
米国 25.1韓国 22.7
中国 20.0
日本 17.4
中国(2016) 1348.3
韓国(2016)510.7
米国(2017)181.0
ドイツ(2017)178.5
英国 (2016)153.2
日本(2018)114.9
○2000年以降、中国、韓国、欧米諸国が科学技術関係予算を伸ばしている一方で、我が国の科学技術関係予算の伸びは低調。
出典:日本:内閣府データ、EU:Eurostat database、中国:科学技術部「中国科技統計数据」、他国:OECD, Main Science and Technology Indicators
15
20
25
30
35
40
45
2000 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
(%)日本 Japan 米国 United States
ドイツ Germany フランス France
英国 United Kingdom 中国 China
韓国 Rep. of Korea
(年度)
3
我が国の科学技術の現状② ~科学技術関係予算と研究費~

1983
1996
2000
2001
2005
2006
2010
2011
2015
2016
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000
40,000(億円)
科学技術関係経費(当初予算額)
○特に、我が国におけるTop10%補正論文数の伸びと科学技術関係予算の伸びが相関しており、近年その伸びは横ばいとなっている。
出典:文部科学省 科学技術・学術政策研究所( NISTEP)調査資料-261「科学技術指標2018」及び文部科学省 科学技術・学術政策研究所(NISTEP)調査資料-262 「科学研究のベンチマーキング2017」を基に文部科学省作成
3,048
799 205 99
90
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
4,500
5,000
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Top1
0%補
正論
文数
(件
) Top10%補正論文数(組織別)
大学等部門 公的機関部門 企業部門 非営利団体部門 それ以外
○Top10%論文数の伸びと科学技術関係予算の伸び
第1期基本計画
第2期基本計画
第3期基本計画
第4期基本計画
第5期基本計画
・国立大学法人化(2004)
4
我が国の科学技術の現状③ ~科学技術関係経費とTop10%補正論文数~

サイエンスマップとは:論文データベース分析により国際的に注目を集めている研究領域を抽出・可視化したもの。世界の研究動向とその中での日本の活動状況を分析している。
○国際的に注目度の高い研究領域が増えているが、我が国は国際的に注目される研究領域に十分に参画できていない。
論文データベース分析により国際的に注目を集めている研究領域を抽出し、当該研究領域を構成するコアペーパ(Top1%論文)に対象国の論文が1件以上含まれている場合、参画領域としてカウントした。
97%90%
38%41%
33%
56%63%
51%56%
12%
51%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
02 16 02 16 02 16 02 16 02 16 02 16
参画
割合
領域
数
領域数 参画割合(右軸)
世界 日本 英国 ドイツ 中国
左からサイエンスマップ2002~2016(2年おき)の値
米国
出典: 科学技術・学術政策研究所: サイエンスマップ2016、科学技術・学術政策研究所 NISTEP REPORT No. 178 (2018年10月9日)
○注目研究領域への参画数・参画割合の推移
我が国の科学技術の現状④ ~注目研究領域への参画状況~
5

カナダ
イタリア
オランダ
インド
ベルギースウェーデン
ロシア
ポーランド
オーストラリア
ブラジル
スペイン
トルコ
イラン
台湾
韓国
英国
中国
ドイツ
スイス
日本
米国
フランス
2005年 2015年
○国際的に科学論文数や国際共著論文数が伸びており、特に中国の増加が目立つが、日本の伸びは鈍い。
日本
注:1.円の大きさ(直径)は当該国又は地域の論文数を示している。2.円の間を結ぶ線は、当該国又は地域を含む国際共著論文数を示しており、線の太さは
国際共著論文数の多さにより太くなる。3.直近3年間分の論文を対象とし、整数カウントにより求めている。
出典:エルゼビア社スコーパスに基づいて科学技術・学術政策研究所作成
カナダ
イタリアオランダ
インド
ベルギースウェーデンポーランド
オーストラリア
ブラジル
スペイン
トルコ
イラン
台湾
韓国
英国
中国
ドイツ
スイス
日本
米国
フランス
ロシア
6
我が国の科学技術の現状⑤ ~論文の国際共著の状況1~

<当該国が関与したTop10%補正論文における共著形態の比較>
英国 ドイツ 日本
国内論文
国際共著論文(2国間)
国際共著論文(多国間)
4,526 4,328 4,542 4,518 3,499 3,516 3,959 4,231 3,718 3,716 3,387 3,008
2,523 2,989
3,988 4,956
2,397 2,894
3,687 4,368
1,250 1,399 1,551 1,725
1,249 2,045
3,973
6,924
1,223
2,022
3,682
6,137
426 706 1,132 1,794
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
16,000
18,0001998
-2000年
2003
-2005年
2008
-2010年
2013
-2015年
1998
-2000年
2003
-2005年
2008
-2010年
2013
-2015年
1998
-2000年
2003
-2005年
2008
-2010年
2013
-2015年
○研究活動の国際化が進む中、日本の存在感が低下。諸外国と質の高い論文数の差が生じているのは、国際共著論文数の差によるところが大きい。
出典: 文部科学省 科学技術・学術政策研究所「科学研究のベンチマーキング2017」(2017年8月、調査資料-262)
7
我が国の科学技術の現状⑥ ~論文の国際共著の状況2~

国A 国B 国A→国B 国B→国A 合計数
英国 米国 12,739 10,323 23,062
米国 中国 8,537 7,978 16,515
ドイツ 米国 8,042 6,210 14,252
日本 米国 5,668 4,039 9,707
フランス 米国 4,913 3,292 8,205
米国 韓国 4,769 2,942 7,711
ドイツ 英国 3,283 2,330 5,613
フランス 英国 2,212 1,698 3,910
日本 中国 2,418 875 3,293 単位(人)
注:矢印の太さは、2国間又は地域の異動研究者数に基づく。異動研究者とは、OECD資料中、「International flows of scientific authors, 1996-2011」の「Number of researchers」を指す。本図は、2国間又は地域の異動研究者数の合計が2,000人以上である矢印のみを抜粋して作成している。
資料:OECD「Science, Technology and Industry Scoreboard 2013」を基に文部科学省作成
8
我が国の科学技術の現状⑦ ~世界の研究者の主な流動~

平成14年度~平成30年度の「科学技術研究調査報告」(総務省統計局)(http://www.stat.go.jp/data/kagaku/index.html)を基に文部科学省作成
基礎研究:特別な応用、用途を直接に考慮することなく、仮説や理論を形成するため又は減少や観察可能な事実に関して新しい知識を得るために行われる理論的又は実験的研究応用研究:特定の目標を定めて実用化の可能性を高める研究や、既に実用化されている方法に関して新たな応用方法を検索する研究
開発研究:基礎研究、応用研究及び実際の経験から得た知識を活用し、付加的な知識を創出して、新しい製品、サービス、システム、装置、材料、工程等の創出又は既存のこれらのものの改良をねらいとする研究
※ここでいう研究費とは、内部で使用した研究費であり、人件費、原材料費、有形固定資産の購入費等を含めたもの
※大学、短期大学、高等専門学校、大学附置研究所、大学共同利用機関、公的機関、非営利団体
〇大学、公的機関等※の性格別研究費(自然科学分野)の推移
42.2% 42.5% 42.9% 40.7% 41.5%39.7% 40.9%40.0% 40.6% 39.5%39.7% 42.1%41.0% 42.0% 42.2% 42.7% 41.7%
0.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
50.0%
0
1
2
3
4
5
2001H13
2002H14
2003H15
2004H16
2005H17
2006H18
2007H19
2008H20
2009H21
2010H22
2011H23
2012H24
2013H25
2014H26
2015H27
2016H28
2017H29
兆円
基礎研究(a) 応用研究(b) 開発研究(c) 基礎研究比率(a)/((a)+(b)+(c))
(百万円)
調査年度2001H13
2002H14
2003H15
2004H16
2005H17
2006H18
2007H19
2008H20
2009H21
2010H22
2011H23
2012H24
2013H25
2014H26
2015H27
2016H28
2017H29
基礎研究(a) 1,545,704 1,612,725 1,614,980 1,528,075 1,552,331 1,503,053 1,537,943 1,525,797 1,587,178 1,486,916 1,505,974 1,601,333 1,671,997 1,688,400 1,632,823 1,597,581 1,617,934
応用研究(b) 1,196,257 1,252,801 1,294,343 1,296,839 1,258,161 1,308,494 1,301,296 1,350,979 1,384,714 1,325,391 1,351,063 1,323,774 1,455,447 1,453,563 1,439,028 1,318,566 1,417,542
開発研究(c) 921,125 927,104 852,583 933,442 933,922 978,567 923,404 938,949 941,777 947,714 937,255 881,893 947,378 873,787 797,453 825,282 844,240
基礎研究比率(a)/((a)+(b)+(c))
42.2% 42.5% 42.9% 40.7% 41.5% 39.7% 40.9% 40.0% 40.6% 39.5% 39.7% 42.1% 41.0% 42.0% 42.2% 42.7% 41.7%
9
我が国の科学技術の現状⑧ ~性格別研究費の推移~

出典:文部科学省作成
政府の科学技術関係経費(※当初予算額)の推移 科研費の予算額(※当初予算額)の推移
2011年度から基金制度導入
2001年度から間接経費を導入
※科学技術基本計画(第1期~第4期)の策定に伴い、1996年度、2001年度、2006年度及び2011年度に対象経費の範囲が見直されている。
※2016年度以降は、行政事業レビューシートの記載内容に基づき予算事業を詳細に分類し、その分類内容に基づく統一的な基準で科学技術関係経費の判定を行う方法に変更されている。
※2018年に既存事業等に科学技術イノベーションの要素を取り入れること(既存事業への先進技術の導入、
先進技術を組み込んだ物品の調達等)により、先進技術の実社会での活用と事業の効率的・効果的な実施等を目指すイノベーション転換を実施した。
※2019年度予算は「科学技術関係予算 平成31年度当初予算案 平成30年度補正予算案の概要について」(2019年1月内閣府政策統括官(科学技術・イノベーション担当))において以下のとおり。
政府全体42,377億円、文部科学省21,876億円
24,657
38,401
0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
35000
40000
45000
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
文部科学省(※2000年度までは文部省の金額) 科学技術庁 その他省庁 政府全体(内訳不明)
(億円)
(年度)
824
924
1,0
18
1,1
22
1,1
79
1,3
14
1,4
19
1,5
80
1,7
03
1,7
65
1,8
30
1,8
80
1,8
95
1,9
13
1,9
32
1,9
70
2,0
00
2,6
33
2,5
66
2,3
81
2,2
76
2,2
73
2,2
73
2,2
84
2,2
86
2,3
72
800
1,000
1,200
1,400
1,600
1,800
2,000
2,200
2,400
2,600
2,800
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
(億円)
(年度)■ 予算額
出典:文部科学省 科学技術・学術政策研究所 「科学技術指標2018」(2018年8月、調査資料-274)を基に、文部科学省が加工・作成
※2019年度は予算額案
10
我が国の科学技術の現状⑨ ~科学技術関係の予算額の推移~

2.我が国の研究者を取り巻く状況
11

68,739
76,954
86,891
99,449
109,649
115,902
119,406
123,255
132,118
142,830
150,797
155,267
159,481
162,712
164,551
165,525
165,219
165,422
167,043
173,831
175,980
168,903
162,693
159,929
158,974
159,114
160,387
163,100
29,911
32,154
35,469
39,303
43,774
48,448
52,141
55,646
59,007
62,481
65,525
68,245
71,363
73,446
74,909
75,365
74,811
74,231
73,565
74,432
74,779
74,316
73,917
73,704
73,877
73,851
73,909
74,367
645
7,866
15,023
20,159
22,083
23,033
23,381
23,191
21,807
20,070
18,776
17,380
16,623
16,623
16,595
16,546
0 50,000 100,000 150,000 200,000 250,000 300,000
H3
H4
H5
H6
H7
H8
H9
H10
H11
H12
H13
H14
H15
H16
H17
H18
H19
H20
H21
H22
H23
H24
H25
H26
H27
H28
H29
H30
修士課程
博士課程
専門職学位課程
(人)98,650
254,013
205,311
※ 在学者数「修士課程」:修士課程,区分制博士課程(前期2年課程)及び5年一貫制博士課程(1,2年次)「博士課程」:区分制博士課程(後期3年課程),医・歯・薬学(4年制),医歯獣医学の博士課程及び5年一貫制博士課程(3~5年次)
通信教育を行う課程を除く 出典:学校基本統計を基に、文部科学省作成
(各年度5月1日現在)・H3→H12で約2.1倍、H3→H30で約2.6倍
12
大学院在学者数の推移

出典:学校基本統計を基に、文部科学省作成
大学院入学者数・在学者数の推移15
,046
14,8
92
14,3
60
14,5
30
14,1
98
13,5
91
13,5
03
13,2
73
13,9
74
13,3
64
12,2
69
11,8
25
11,7
06
11,3
14
10,8
78
10,9
61
10,8
66
45,5
73
47,3
93
48,2
84
48,4
64
48,4
48
49,0
56
49,3
87
50,2
51
53,3
53
51,2
74
48,3
45
47,3
56
47,1
51
46,8
22
46,7
88
47,5
93
48,4
99
13,0
17
13,4
13
14,1
05
14,5
63
15,2
05
14,8
04
14,5
06
14,5
95
14,9
83
14,7
47
14,3
71
14,1
72
13,9
99
13,8
29
14,7
14
14,8
87
14,7
26
0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
70,000
80,000
90,000
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
修士課程入学者数の推移
人文・社会科学 自然科学 その他
3,26
8
3,34
8
3,25
5
3,19
2
3,09
7
3,05
8
2,73
8
2,71
7
2,62
1
2,45
9
2,36
9
2,31
9
2,31
4
2,20
3
2,07
1
1,91
6
1,96
5
11,5
77
12,3
14
12,1
12
11,7
33
11,2
84
11,2
64
10,9
01
10,6
51
11,1
76
10,7
28
10,8
37
10,8
96
10,8
43
10,8
86
10,5
41
10,4
54
10,5
95
2,38
9
2,57
0
2,57
7
2,62
8
2,75
0
2,60
4
2,63
2
2,53
3
2,67
4
2,49
8
2,35
1
2,27
6
2,26
1
2,19
4
2,36
0
2,39
6
2,34
3
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
16,000
18,000
20,000
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
博士課程入学者数の推移
人文・社会科学 自然科学 その他
36,3
73
35,6
56
34,7
18
34,0
38
33,3
74
32,0
95
31,5
68
31,2
75
32,1
04
32,2
83
30,7
85
28,9
36
28,1
01
27,5
17
26,7
97
26,5
90
26,5
92
91,5
15
95,0
92
98,0
57
99,3
34
99,6
95
100,
347
101,
404
103,
228
108,
507
110,
121
105,
217
101,
525
99,9
84
99,8
08
99,8
07
100,
073
102,
387
27,3
79
28,7
33
29,9
37
31,1
78
32,4
56
32,7
77
32,4
50
32,5
40
33,2
20
33,5
76
32,9
01
32,2
32
31,8
44
31,6
49
32,5
10
33,7
24
34,1
39
0
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
140,000
160,000
180,000
200,000
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
修士課程在学者数の推移
人文・社会科学 自然科学 その他
14,3
47
14,8
26
15,0
78
15,2
15
15,2
16
15,1
63
14,8
23
14,4
44
14,0
81
13,6
21
13,1
49
12,7
51
12,5
87
12,2
31
11,9
66
11,6
25
11,3
06
44,9
49
46,6
52
47,7
73
48,6
03
48,5
48
47,8
21
47,3
15
46,9
05
47,8
81
48,5
97
48,7
70
49,1
17
49,4
19
50,1
16
50,1
94
50,1
66
50,5
56
8,94
9
9,88
5
10,5
95
11,0
89
11,6
01
11,8
27
12,0
93
12,2
16
12,4
70
12,5
61
12,3
97
12,0
49
11,6
98
11,5
30
11,6
91
12,1
18
12,5
10
0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
70,000
80,000
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
博士課程在学者数の推移
人文・社会科学 自然科学 その他 (年度)
(年度)
(年度)
(年度)
(人)
(人)
(人)
(人)
13

5,984
12,314
10,595
929
1,786
1,082 1,399
3,571
2,562
580 1,192 680
3,076
6,001 6,271
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
1990
1992
1994
1996
1998
2000
2002
2004
2006
2008
2010
2012
2014
2016
2018
博士課程入学者数の推移(自然科学系4分野)
合計
保健
工学
理学
農学
20,918
50,556
3,067
6,460 4,736 4,315
13,971 12,732
1,742 4,390 3,532
11,794
29,556
0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
1990
1992
1994
1996
1998
2000
2002
2004
2006
2008
2010
2012
2014
2016
2018
博士課程在学者数の推移(自然科学系4分野)
理学
農学
工学
保健
合計
1990(H2)→2017(H29)で2.4倍
博士課程入学者数・在学者数の推移(自然科学系4分野)
(年度) (年度)
(人) (人)
出典:学校基本統計を基に、文部科学省作成 14

14,2
80
13,5
52
12,8
44
11,8
74
11,5
09
10,7
19
10,5
87
11,0
87
10,2
23
9,76
7
9,84
5
9,60
8
9,41
1
8,76
9
8,65
5
8,53
5
3,95
2
4,39
2
4,70
9
5,25
7
5,41
7
5,55
2
5,31
4 5,38
4
5,46
2
5,79
0
5,64
6
5,81
0
5,87
2
6,20
3
6,11
1
6,36
8
2,64
3
2,46
8
2,48
3
2,53
4
2,39
7
2,32
3
2,58
1
2,81
9
2,50
3
2,25
0
2,23
5
2,30
0
2,29
0
2,27
8
2,38
4
2,51
3
18,232 17,944 17,553
17,131 16,926 16,271
15,901 16,471
15,685 15,557 15,491 15,418 15,283 14,972 14,766 14,903
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
16,000
18,000
20,000
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
社会人以外 社会人 留学生
出典:学校基本統計を基に、文部科学省作成
(人)
博士課程入学者における学生の属性別内訳
※留学生の入学者数は社会人以外及び社会人の入学者数の内数
15

9,885 10,288 10,5799,812 10,160
10,937 10,828 10,563 10,541 10,628 10,601 10,603
808 695 636950
1,022855 998 1,019 944 1,026 933 833
16,80116,281 16,463
15,842 15,89216,260 16,445
16,003 15,684 15,773 15,658 15,658
54.0%
56.0%
58.0%
60.0%
62.0%
64.0%
66.0%
68.0%
70.0%
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
16,000
18,000
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
就職者 一時的な仕事に就いた者 その他 就職者・一時的な仕事に就いた者の割合(右軸)
(人)
出典:学校基本統計を基に、文部科学省作成
博士課程修了者の就職状況
16

※ 博士課程修了者及びポスドク等経験者は、博士課程満期退学者を含んでいる。※ 資本金1億円以上で、かつ、社内で研究開発を行っている民間企業を調査対象としており、各年次のデータは、同一
企業を対象として調査した結果ではない。
出典:科学技術・学術政策研究所「民間企業の研究活動に関する調査報告2017」(NISTEP REPORT No.177,2018年5月)等を基に文部科学省作成
○2011~2016年度に研究開発者を採用した民間企業のうち、博士課程修了者(ポストドクター等の経験なし)を採用した民間企業の割合は、2割程度で推移している。
(年度)
52.9%58.4%
53.7%56.1%
60.0% 59.1%
78.3% 77.6% 76.6% 78.3%75.7% 74.6%
20.1%23.1%
20.6% 21.4% 19.3% 18.5%
2.5%6.0%
2.8% 3.6% 2.3% 3.9%
0.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
50.0%
60.0%
70.0%
80.0%
90.0%
2011 2012 2013 2014 2015 2016
学士号取得者を採用した
企業数
修士号取得者を採用した
企業数
博士課程修了者(ポスド
クだった者を除く。)を採
用した企業数
採用時点でポスドクだっ
た者を採用した企業数
研究開発者を採用した企業数 N=448社 N=416社 N=423社 N=471社 N=477社 N=536社
全回答企業のうち研究開発者を採用した企業
割合46.0% 41.5% 41.2% 41.8% 42.4% 45.8%
研究開発者を採用した民間企業における学位別採用状況
17

○ 全職務時間における総研究時間(研究エフォート)割合については減少傾向にある。○ 保健分野においては、研究時間割合が減少しており、診療活動等の社会サービス活動の時間割合
の増加の影響が見られる。また、職種別に見ると助教においてその傾向が最も顕著である。○ 理工農学分野においては、2008年から2013年にかけては研究時間割合は微増している。職位別に
見ると、講師のみ減少傾向にある。
研究時間割合の現状
出典:文部科学省 科学技術・学術政策研究所 「大学等教員の職務活動の変化-『大学等におけるフルタイム換算データに関する調査』による2002年、2008年、2013年調査の3時点比較-」(2015年4月、調査資料-236)
※2002年の『大学等におけるフルタイム換算データに関する調査』においては、総務省統計局が実施している「科学技術研究調査」における大学等の研究本務者のうちの教員を対象とし、無作為抽出を行っている。2008年、2013年調査では、「科学技術研究調査」による教員数を母集団数とし、学問分野別にウェイトバックした母集団推定値を使用した。ただし、職位別の教員数のバランスについては考慮していないため、実際の大学等における職位バランスとは異なっている可能性がある。 18

(出典)文部科学省 科学技術・学術政策研究所 「大学等教員の職務活動の変化-『大学等におけるフルタイム換算データに関する調査』による2002年、2008年、2013年調査の3時点比較-」(2015年4月、調査資料-236)
※2002年の『大学等におけるフルタイム換算データに関する調査』においては、総務省統計局が実施している「科学技術研究調査」における大学等の研究本務者のうちの教員を対象とし、無作為抽出を行っている。2008年、2013年調査では、「科学技術研究調査」による教員数を母集団数とし、学問分野別にウェイトバックした母集団推定値を使用した。
学問分野別大学等教員の職務活動時間割合
研究時間割合の現状
19

出典:山口栄一京都大学教授資料(第2回国立研究開発法人イノベーション戦略会議 2018年1月17日)より抜粋
日本の物理学論文数、物理学博士学生数、日本の大企業の論文数の経年変化
20

出典:総務省「科学技術研究調査」を基に、文部科学省作成
99,925
87,927
23,092 17,750
72,959
52,415
0
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
0
100,000
200,000
300,000
400,000
500,000
600,000
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
総数 理学全体 数学・物理 化学
産業・専門別企業研究者数の推移
21

出典:東京大学の各年度の概要を基に、文部科学省作成
大学教員数と学生数の推移(東京大学の例)
22

出典:「学校教員統計調査」(文部科学省)及び「人口推計」(総務省)に基づき、科学技術・学術政策研究所並びに文部科学省において集計
○ 大学本務教員に占める若手教員の割合は低下傾向。※「第5期科学技術基本計画」(平成28年1月22日閣議決定)において「第5期基本計画期間中に、40歳未満の大学本務教員の数を
1割増加させるとともに、将来的に我が国全体の大学本務教員に占める40歳未満の教員の割合が3割以上となることを目指す」とされている。
39.3%
23.5%
0%10%20%30%40%50%
S61 H1 H4 H7 H10H13H16H19H22H25H28
40歳未満本務教員比率(全大学) 39.9%
24.7%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
S61 H4 H10 H16 H22 H28
国立大学教員の年齢階層構造
39歳以下
40~49歳
50~59歳
60歳以上
39.6%29.2%
0%10%20%30%40%50%
S61 H1 H4 H7 H10 H13 H16 H19 H22 H25 H28
日本の人口の年齢階層別比率(25-69歳)
25-39歳
40-49歳
50-59歳
60-69歳
大学本務教員に占める若手教員の割合
23

※学術研究懇談会(RU11)を構成する11大学における大学教員の雇用状況に関する状況を調査したもの。
○ 研究大学(RU11)においては、任期なし教員ポストのシニア化、若手教員の任期なしポストの減少・任期付ポストの増加が顕著。
若手研究者の任期なしポストの減少
若手研究者の任期付きポストの増加
大学教員の雇用状況(研究大学(RU11))
出典:文部科学省 科学技術・学術政策研究所 「大学教員の雇用状況に関する調査」(2015年9月、 調査資料-241) 24

(人)
出典:平成28年版科学技術白書
トップリサーチャー(各分野における被引用度が上位10%以内の日本の論文の著者)の半数以上が40歳未満であり、トップリサーチャーには若手研究者が多い研究者が最も論文を書いた時期は、キャリア開始から8年以内に最も多く見られるノーベル賞受賞につながる研究を行った年齢の平均は、20代後半から30代にかけての実績が中心(平均37歳)
若手研究者の論文生産性は高い
0
20
40
60
80
100
120
140
0.0%
5.0%
10.0%
15.0%
20.0%
25.0%
30.0%
合計 化学賞 生理学・医学賞 物理学賞
トップリサーチャーの年齢(調査対象論文投稿時点)
注1:「トップリサーチャー」とは、国際的な科学文献データベースである SCI(2001 年版)における被引用度が上位10%以内の論文の著者を指す。調査においては、868件の回答を得た。注2:トップリサーチャーの 7 割以上が大学に所属しており、民間企業と政府・公的研究機関がそれぞれ1割弱を占めている。
Productivity peaks early for most researchers(研究者の生産性のピークは初期に最も多くみられる)
(左:ヒートマップ)2300人以上の計算機科学の教員を勤続年数順に配置し、各教員のキャリアにおいて最も論文を書いた時期(出版した論文数により測定)について表示。
出典:Aaron Clauset, Daniel B. Larremore and Roberta Sinatra, ‘Data-driven Predictions in the science of science,’ Science 355, 477-480(2017) .
(右:ヒストグラム)ヒートマップの行を合計。これによると、研究開始から8年以内に最も論文を書いた時期を迎えている教員が最も多くみられる。
ヒストグラム:主要研究時の年齢(ノーベル賞受賞者 1945-2015)
若手研究者の論文生産性
出典:文部科学省 科学技術政策研究所 「優れた成果をあげた研究活動の特性:トップリサーチャーから見た科学技術政策の効果と研究開発水準に関する調査報告書」(2006年3月、調査資料-122) 25

12,415 10,971
3,263
3,154
3,606 4,274
19,284 [100]
18,399 [95.4]
0
10,000
12,000
14,000
16,000
18,000
20,000
平成16年度 平成30年度
国立大学法人運営費交付金等 私立大学等経常費補助金 競争的資金
+456億円
基盤的経費
(億円)基盤的経費+競争的資金▲885億円(約5%減)
※[]内の数値は、平成16年度の合計額を100とした時の割合。 (文部科学省調べ)
▲1,445億円
▲109億円
+668億円
うち科研費1,830
うち科研費2,286
16,411 [93.7]
17,508 [100]基盤的経費+科研費
▲1,097億円(約6%減)
基盤的経費と競争的資金の推移
26

3.参考資料
27

学術研究・基礎研究の政策的位置づけ
第4章 科学技術イノベーションの基盤的な力の強化(2)知の基盤の強化持続的なイノベーションの創出のためには、イノベーションの源である多様で卓越した知を生み出す基盤の強化が不可欠であり、その際、
従来の慣習や常識にとらわれない柔軟な思考と斬新な発想を持って研究が実施されることが特に重要である。しかし、我が国の論文数、高被引用度論文数は共に伸びが十分でなく、国際的な共著論文の伸びも相対的に低い。そうしたことから、我が国の基礎研究力の低下が懸念される。
このため、研究者の内在的動機に基づく独創的で質の高い多様な成果を生み出す学術研究と政策的な戦略・要請に基づく基礎研究の推進に向けて、両者のバランスに配慮しつつ、その改革と強化に取り組む。さらに、我が国が世界の中で存在感を発揮していくため、学際的・分野融合的な研究や国際共同研究を推進するとともに、国内外から第一線の研究者を引き付ける世界トップレベルの研究拠点を形成する。・・・
このような取組を通じ、知の基盤について、質的・量的双方の観点から強化することを目指す。ただし、論文の質そのものの評価は難しいことから、その代替的な評価指標として普及している高被引用度論文に注目し、我が国の総論文数を増やしつつ、我が国の総論文数に占める被引用回数トップ10%論文数の割合が第5期基本計画期間中に10%となることを目指す。
第5期科学技術基本計画(平成28年1月22日閣議決定)<抄>
学術研究(academic research)
個々の研究者の内在的動機に基づき、自己責任の下で進められ、真理の探究や科学知識の応用展開、さらに課題の発見・解決などに向けた研究。
要請研究(commissioned research)政府からの要請に基づき、定められた研究目的や研究内容の下で、社会的実践効果の確保のために進められる研究。
戦略研究(strategic research)政府が設定する目標や分野に基づき、選択と集中の理念と立案者(政府)と実行者(研究者)の協同による目標管理の下で進めら
れ、課題解決が重視される研究。
基礎研究 応用研究 開発研究
研究者の内在的動機
政策的要請研究の契機
研究の性格
知識の発見 社会実装
28

●基本理念・科学技術イノベーション政策の一体的推進
・人材とそれを支える組織の役割の重視
・社会とともに作り進める政策の実現
●政策の柱・分野別重点化から課題達成型の重点化へ
-震災からの復興・再生-グリーンイノベーションの推進-ライフイノベーションの推進・基礎研究と人材育成の強化・PDCAサイクルの確立やアクションプラン等の改革の徹底・4期総額規模は25兆円(実績:22.9兆円)※対GDP比1%を前提
●基本理念・科学技術イノベーション政策の一体的推進
・人材とそれを支える組織の役割の重視
・社会とともに作り進める政策の実現
●政策の柱・分野別重点化から課題達成型の重点化へ
-震災からの復興・再生-グリーンイノベーションの推進-ライフイノベーションの推進・基礎研究と人材育成の強化・PDCAサイクルの確立やアクションプラン等の改革の徹底・4期総額規模は25兆円(実績:22.9兆円)※対GDP比1%を前提
科学技術基本法
(1995年制定)
第1期基本計画(1996~2000年度)
第2期基本計画(2001~2005年度)
第3期基本計画(2006~2010年度)
第4期基本計画(2011~2015年度)
●政府研究開発投資の拡充
期間内の科学技術関係経費総額の規模は17兆円(実績:17.6兆円)
●新たな研究開発システムの構築
・競争的研究資金の拡充・ポストドクター1万人計画・産学官の人的交流の促進・評価の実施
等
●政府研究開発投資の拡充
期間内の科学技術関係経費総額の規模は17兆円(実績:17.6兆円)
●新たな研究開発システムの構築
・競争的研究資金の拡充・ポストドクター1万人計画・産学官の人的交流の促進・評価の実施
等
●基本理念・新しい知の創造・知による活力の創出・知による豊かな社会の創生
●政策の柱・戦略的重点化-基礎研究の推進-重点分野の設定・科学技術システム改革-競争的研究資金倍増-産学官連携の強化 等
・2期総額規模は24兆円(実績:21.1兆円)
・3期総額規模は25兆円(実績:21.7兆円)
※対GDP比1%を前提
●基本理念・新しい知の創造・知による活力の創出・知による豊かな社会の創生
●政策の柱・戦略的重点化-基礎研究の推進-重点分野の設定・科学技術システム改革-競争的研究資金倍増-産学官連携の強化 等
・2期総額規模は24兆円(実績:21.1兆円)
・3期総額規模は25兆円(実績:21.7兆円)
※対GDP比1%を前提
第5期科学技術基本計画(2016~2020年度)
出典:内閣府作成
●基本方針・「先を見通し戦略的に手を打つ力」、「変化に的確に対応する力」を重視・国際的に開かれたイノベーションシステムの中で競争、協調し、各主体の力を最大限発揮できる仕組みを構築・政府、学界、産業界、国民が共に実行する計画として位置付け●政策の柱ⅰ)未来の産業創造と社会変革・世界に先駆けた「Society 5.0」実現等
ⅱ)経済・社会的な課題への対応ⅲ)基盤的な力の強化・若手活躍、学術・基礎研究推進、大学改革等
ⅳ)人材、知、資金の好循環システム・オープンイノベーション推進、ベンチャー創出等
◆計画の進捗把握のため、目標値と主要指標を設定
◆政府投資の総額規模は26兆円※対GDP比1%を前提
●基本方針・「先を見通し戦略的に手を打つ力」、「変化に的確に対応する力」を重視・国際的に開かれたイノベーションシステムの中で競争、協調し、各主体の力を最大限発揮できる仕組みを構築・政府、学界、産業界、国民が共に実行する計画として位置付け●政策の柱ⅰ)未来の産業創造と社会変革・世界に先駆けた「Society 5.0」実現等
ⅱ)経済・社会的な課題への対応ⅲ)基盤的な力の強化・若手活躍、学術・基礎研究推進、大学改革等
ⅳ)人材、知、資金の好循環システム・オープンイノベーション推進、ベンチャー創出等
◆計画の進捗把握のため、目標値と主要指標を設定
◆政府投資の総額規模は26兆円※対GDP比1%を前提
科学技術基本計画
29