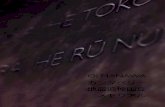戦死者追悼と集合的記憶の間 · 2016. 3. 17. · 戦死者追悼と集合的記憶の間...
Transcript of 戦死者追悼と集合的記憶の間 · 2016. 3. 17. · 戦死者追悼と集合的記憶の間...

戦死者追悼と集合的記憶の間──原爆死した動員学徒を事例として──
直野 章子
� 先行研究と本稿の位置づけ
死者を追悼するとは、死者の生前を偲び悲しみに浸ることだけを指すのではない。その死を受容しようとするなかで、残された者は死者の死と自らの生の意味を問うことになる。とりわけ、寿命を全うすることなく死が訪れた場合には、死に何らかの意味を見出さずして、それを受け容れることは容易ではない。だから、死に因果関係の文脈を与えて物語化するこ
本稿では、死者追悼を死者に関する記憶行為として捉えながら、集合的記憶と死者追悼とがどのように関連しているかを明らかにすることを目的とする。具体的には、多くの犠牲者を出しながら、戦後の早い時期から追悼記集を刊行し続けた広島県立広島第一中学校(一中)と広島市立第一高等女学校(市女)、そして国家による死者顕彰を要求する「広島県動員学徒犠牲者の会」(「学徒犠牲者の会」)が発行した追悼記集に収録された手記を対象として、集団の特徴と追悼における語りの内容との相関性を分析した。戦後日本の戦死者追悼において支配的となった〈平和主義の語り〉〈殉国の語り〉〈平和の礎論〉という3種の語りが、どのように表現されており、それが原爆の集合的記憶との関係で何を意味するのかを検討した結果、以下の点が明らかになった。1)集団によって死者追悼のあり方に違いがみられるが、共通性も確認できる。2)遺族であるか同窓生であるかという死者との関係性の違いが追悼の在り方に影響を与えている。3)日本社会における原爆の集合的記憶が、3つの集団の構成員の死者追悼のあり方に、より大きな文脈を与えている。4)社会の集合的記憶の枠組みでは捉えきれない死者追悼の営みが存在するが、家族や学校という〈記憶の集団〉が解体していくなかで、原爆死者に関する記憶は社会全体の集合的記憶に吸収されていく可能性が高い。
キーワード:戦死者追悼、集合的記憶、動員学徒
�

とが重要となってくる。追悼という死者をめぐる記憶行為は、悲しみや愛情といったきわめて個人的な情動を含むものであると同時に、物
ナラティブ
語という文化資源を活用する社会的な営為でもある1)。つまり、死者追悼・慰霊は社会的な文脈で考察されるべきものなのである2)。なかでも近代の戦死者追悼においては、戦争に関する社会全体の集合的記憶が重要な参照枠となる。死を意味づけるうえでも、生き残った意味を見出すうえでも、戦争が社会の中でどのように記憶されているのかに影響を受けることになるからである。戦死者追悼は、社会における戦争の集合的な表象──集合的記憶──と切り離すことができないのである。 そもそも死者追悼は個人で完結するものではなく、家族や地域共同体のなかで執り行われてきた。死者は社会の諸集団によって想起され、忘却されてきたのである。戦死者の場合、戦勝国においては戦争の大義とともに尊い犠牲として国家的に顕彰され、敗戦国においては社会から忘却されるか否定的に想起される傾向にあるが、いずれの場合も、戦死者は〈国民〉として想起され、戦後の国民統合を促してきた[原田2013;Mosse1991=2002]。こうした戦死者追悼をめぐる政治学を解明するために、記憶という概念を援用する研究が蓄積されている。なかでも、モーリス・アルバックス(MauriceHalbwachs)の「集合的記憶」という概念
[Halbwachs1968=1989]を参照しながら、戦死者追悼をナショナリズムとの関連で分析する研究が多くみられるが、アルバックスが論じたのは、主に家族や学校、村落などの第一次集団や中間集団の記憶であって、それを国民国家のレベルにまで拡大適用したのは、ピエール・ノラ(PierreNora)の「記憶の場」プロジェクトであった[Nora1984=2002]。本稿では、社会全体の集合的記憶だけでなく、アルバックスの議論に立ち戻って家族や学校といった集団にも着目し、個人的記憶と集合的記憶との関係を、戦死者追悼を通して考察してみたい。 記憶研究とは別に、歴史学や民俗学の分野を中心に、地域や家での祭祀や慰霊に焦点を当て、国家ではなく地域や民俗的な実践のなかに戦死者慰霊を位置づける研究が近年増えてきている[一ノ瀬2010;岩田2003;波平2004]。それは、靖国問題に焦点を当てながら国家による戦死者慰霊を批判する従来の研究に対して、生活者としての個人、家族や村落といった共同体の次元から戦死者慰霊を解明しようとする。しかし、田中丸勝彦が示唆するように、家や地域社会での慰霊や祭祀は、個人を国家と結びつける媒体となる可能性が高く[田中丸2002]、国家主義的な戦死者慰霊に代わるとは限らない。同時に、個人の慰霊行為が国家の論理で覆い尽されるわけではない。集合的記憶論が提供する社会学的観点からいえば、個人による慰霊・追悼が、いかに国家や社会(集団)に規定されているかだけでなく、いかに集合的記憶の生成や維持に貢献しているのか、あるいは集合的記憶を変容させる可能性を孕んでいるかを明らかにすることが重要である。 以上の課題と向き合うために、本稿では原爆死した広島の動員学徒を対象として、集合的記憶と個人による死者追悼との関係を考察してみたい。なぜ動員学徒を取り上げるのか。その理由は3つある。 赤澤史朗が明らかにしたように、戦後のあらゆる戦没者追悼は平和主義と無縁ではいられなかったが[赤澤2005:8]、1950年代終盤から60年代初めにかけて〈殉国〉と〈平和〉という2つの潮流に分岐していくことになる[赤澤2005:122-3]。前者の代表が靖国神社や日本遺族会による戦没者追悼であり、後者の代表が平和団体や被爆地自治体による原爆死者追悼で
理論と動態 �

ある。しかし、原爆死した動員学徒に関しては、靖国合祀を要求した運動体が組織され、実際に合祀や「国家補償」の対象となったことからもわかるように、その死が〈殉国の死〉として記憶されてきた文脈が存在する。つまり、動員学徒の追悼・慰霊は〈殉国〉と〈平和〉という2つの潮流が交差する地点に位置しており、それを分析することで、靖国か平和主義かという二者択一的な戦死者追悼の語られ方に再考を促すことができるのである。 動員学徒を分析対象として選択する理由の2つ目に、追悼行為を行う集団の多様性が挙げられる。原爆死した動員学徒の追悼に関する先行研究には、西村[2006]と四條[2012]があるが、西村は長崎医科大学、四條は純心女子学園における追悼を分析しているのに対して、本稿では複数の学校に加えて、国家による死者顕彰を要求する運動体を取り上げる。さらに、遺族と生存学徒という死者との関係性の差異にも注意を払いながら各集団に属する個人の追悼行為を比較検討することで、集団と追悼の関係を考察することができる3)。 最後に、動員学徒に関しては、慰霊・追悼が熱心に行われており、原爆死者の追悼を考えるうえで資料が豊富であることを挙げたい。学徒に関わる集団は他の集団に比べて死者追悼に心を注いできた。宇吹暁によると、原爆後50年の間に刊行された原爆手記のうち、同窓会や遺族会など動員学徒に関係する集団が発行主体となっているものは、全体の10.7%を占めるが、それは、地域被爆者団体の19.5%に次いで多く、官公庁や事業所といった他の被爆当時の組織に比べて突出している[宇吹1999:393-6]。これらの手記を対象として、本稿では集団間における死者追悼のあり方を原爆の集合的記憶との関連のなかで比較検討していく。
� 分析の対象と方法
本稿で扱う資料は、広島県立広島第一中学校(一中)4)および広島市立第一高等女学校(市女)5)の遺族会や同窓会が、原爆死した学徒たちを追悼するために被爆翌年から1995年までの間に発行した手記集に収録された手記計448編と、「広島県動員学徒犠牲者の会」(「学徒犠牲者の会」)が原爆死学徒を追悼するために発行した書籍に収録された手記134編とする6)。一中と市女は、多くの犠牲者を出しながら戦後の早い時期に慰霊碑を建て、追悼記集を刊行し続けており、「学徒犠牲者の会」も1960年代半ば以降、慰霊事業として学徒慰霊塔を建立し、追悼記集を発行してきた。 分析にあたっては、それぞれの手記のなかで死者がどのように記憶されているのかに焦点を当てるが、その際、原爆死をどのように意味づけているかに着目する。原爆死は、50年代初め以降、「人類史上初めての核兵器による犠牲」や「繰り返してはならない悲劇」として語られ、日本における反戦平和および反核兵器の世論を支えるシンボルとして機能してきた[直野2013]。日本社会の集合的記憶においては、原爆死者追悼が平和主義と明確に接合されてきたのである。だからといって、個人的記憶においては、必ずしも平和主義がみられるとは限らず、前述のように、〈殉国の死〉として死者を追悼するものもある。本稿では、戦後日本の戦死者追悼において支配的であった〈平和主義の語り〉(「戦争の悲劇を繰り返さない」など、平和を誓うことで死者を慰めようとする語り)、〈殉国の語り〉(「戦死者はお国のために命を
�

捧げた」と死者を讃える語り)、〈平和の礎論〉(「戦死者の犠牲は日本に平和(と繁栄)をもたらした」と死者に感謝する語り)という3種の語りが、それぞれの手記のなかで、原爆死を意味づけようとするときに、どのように援用されているのかを検討していく。その際、平和への誓いだけでなく、平和を願う言葉や厭戦の思い、核兵器廃止の訴えが含まれるものは〈平和主義の語り〉、「国家のための死」という語りだけでなく、靖国合祀を肯定したり死者を「英霊」と讃えるものは〈殉国の語り〉、原爆死が終戦、つまり〈平和〉をもたらしたと意味づけたり、死者の犠牲が平和の維持や戦争の再発防止に貢献していると謝意を述べるものは〈平和の礎論〉として位置づけていく。 原爆死を意味づけるにおいて、3種の語りのうちのどれか1つだけが援用されるとは限らない。2つ、もしくは3つの語り全てが併用される場合もある。特に〈平和の礎論〉は、〈殉国の語り〉とも〈平和主義の語り〉とも共通点がある。〈平和の礎論〉は〈殉国の語り〉のように戦死を国家への貢献として意味づけることができる。他方、赤澤も指摘するように、〈平和の礎論〉は戦死者の死を無駄にしないために平和を実現するよう生者を促すことにもなり、〈平和主義の語り〉とも共存できる[赤澤2005:160]。さらに、〈殉国の語り〉と〈平和主義の語り〉とが共に用いられることもある。死者が「祖国の平和」を望んでいたとなれば、平和擁護に努めることが〈殉国の死〉を遂げた死者の慰霊になるのである。手記を分析する際には、これら3種の語りがどのように援用されているかをみることで、原爆死にいかなる意味が付与されているかを読み解いていく。手記の分析を通して、本稿では残された者が原爆死した学徒たちをいかに記憶してきたかを、原爆の集合的記憶との関連において考察する。
� 広島県立広島第一中学校
�.� 『泉』 『泉第一集──みたまの前に捧ぐる』(手記数37編)は、被爆翌年という早い時期に発行されたという点に加え、遺族ではなく在学中の生徒が執筆・編集したという点で、異例の追悼記集である。被爆当時に3年生だった一中の生徒たちが、学友の在りし日を追憶しているが、被爆の夏まで同じ工場に動員されていた女学生も「御楯隊」と呼ばれた一中学徒の思い出を綴っている。 戦時下に生を受け、報国精神が強かったとはいえ、まだ中学生だった少年にとって、死は観念的なものであり、学友の死に衝撃を受けたことは間違いない。
東君は日本人と生を享け、御国のために身命を捧ぐを最大の本望とし、御国のため、われこそ防波堤たらんとし、美事に散り逝った。(須郷頼己)
須藤は友が「御国のため」に死んだと強調するが、須藤の他にも「尊い若き一生を国に捧げて倒れた」(太田一男)というように、友の死を顕彰する〈殉国の語り〉が8編ある。 しかし、それは、あまりにも早すぎる死であった。だからこそ、友の霊を慰めようとして学校再建や日本復興の誓いを立てる手記は多く、14編もある。
理論と動態 �

我々は志を遂げずに逝った彼等の分まで働いて、新日本を再興し、平和世界に貢献し以って友の霊に手向けようではないか。(澤村一)
澤村の語りは、50年代以降、原爆死者追悼において支配的になっていく「ノーモア・ヒロシマズ」という〈平和主義の語り〉の萌芽として読める。しかし、沢村は、友の死を「御国の為に殉じて行った」と意味づけており、「敗戦国日本を世界平和の一員として再建」するという慰霊行為は、友人が命を懸けた対象である〈お国〉を護ろうとする意思表示であり、〈殉国の語り〉に該当するといえる。
あの方々の尊い深い祖国愛を心に刻んで、これからの正しい日本を建設しようと思ひます。(波田邦代)
その愛国心を引き継ぐことで死者を慰霊しようとする波田の語りは〈殉国の語り〉に該当するが、「御国の礎とはいえ、余りにも哀しい出来事でございました」というように、死者顕彰よりは慰霊に力点が置かれている。
原子爆弾で亡くなられた方々は世界平和の為の尊い人柱として今は安らかに地下で眠っていられる事でせう。幸か不幸か生き残った私達県女の生徒は、御楯隊の冥福を祈り、その人達の分も頑張って、新日本建設に努力致します。(中西妙子)
中西の語りにある「世界平和の為の尊い人柱」という死者の意味づけは、敗戦直後から被爆地でも繰り返されていた〈原爆平和招来説〉による。原爆によって戦争に終止符が打たれ、平和がもたらされたという解釈である。これは〈平和の礎論〉に融合していくが、終戦を平和の到来と捉える〈原爆平和招来説〉そのものは次第に影をひそめていく。 中西の手記には〈殉国の語り〉もみられ、「国の大事に殉ずるは 我等学徒の面目ぞ」という「学徒動員の歌」を引用しながら「御楯隊」は「花と散りました」とその死を称えている。だからこそ、一中学徒の報国心を引き継いで国家再建に励もうというのである。 波田や中西のように、死者の信念を引き受けることでその霊を慰めようとする者は、降伏という国家による裏切りを受けてもなお、国家護持をうたうのであった。「この方たちや私達の期待を裏切って、祖国日本は悲しい敗戦の憂き目を見ました」と中西は書いているが、国家の責任追及には向かわない。
ああ!この人達は必勝を信じて死んでゆかれたのだ。もっと戦ひたいと思って亡くなられただろうと思ふと、胸が一ぱいになった。必勝の代りに新日本建設を誓ふのだった。
(宍戸信子)
「もっと戦いたい」「敵を討つ」といった死者の願いを叶えて慰霊に代えることは、敗戦後、
�

とりわけ『泉』の原稿が書かれた占領下の日本では不可能であった。しかし、〈平和の礎論〉や〈殉国の語り〉を通して死者の愛国心を称えながら国家再建を誓うことで、生者は死者を裏切っているという事実から目を背けたのである。
�.� 『追憶』 次に見る『追憶』(手記数79編)は、遺族が亡き子を偲んで書いた追悼記をまとめて1954年に刊行したものである。 「戦に出陣し花々しく名誉の戦死をしたと諦め、子供の冥福を祈りつゝ毎日を送つて居ります」(西川誠一)のように〈殉国の語り〉を援用しながら子を亡くした痛みに耐えようとする語りがある一方で、「原子爆弾に斃れた吾が子が世界平和への礎となれば泣いてはならない、悲しんではいけない」(岡田佐美子)と、〈平和の礎論〉を通して自分自身を慰めようとするもある。『追憶』では前者が3編しかないのに対して後者は10編あるが、『泉』と違って国家護持とつなげられた〈平和の礎論〉は1編しかない。戦後10年の間で国家という大義が原爆死者慰霊において存在感を薄くしたことが伺える。他方〈平和主義の語り〉は17編ある。 『追憶』が書かれたのは、広島市が「平和都市」を掲げて復興事業を推進し、市民の間でも原爆禁止運動の萌芽がみられていた時期であり、〈平和主義の語り〉が比較的多くみられる背景となっている。52年には原爆死没者慰霊碑が除幕され、原爆死者慰霊と平和への誓いが明確に結びつけられた。遺族の間でも「再びかゝる悲惨な犠牲者を出すことのないよう、断じて再び戦争の起り得ない平和で幸福な社会と国家を創ることこそ尊い回向であると信ずる」(服部圓)というように、死者慰霊のために平和への努力を誓う者もいる。しかし、そうしたところで、納得できるわけではないのである。 戦死者追悼の3種の語り全てが援用された唯一の手記をみてみよう。筆者の益田美佐子は一人息子を亡くして悲嘆に明け暮れるが、「あなたのような清浄無垢で、国に捧げた生命が、どうして天国に復活しない訳がありませう」と〈殉国の語り〉とキリスト教義を併用して慰めを得ようとする。しかし、「矢張りこの淋しさと歎きとは消すべくもない」のである。さらに、
「信じさせられていた聖戦が、そうではなかったとわかった」ために、悔しさはひとしお大きいと〈殉国の語り〉と相反する心情も吐露する。そして、「広く全世界の人類への尊い犠牲であり、警告でもあった」と〈平和の礎論〉に訴えながら子の早すぎた死に意味を与えて納得しようとする。しかし、「戦争さへなかったら」と、やはりあきらめきれない。ノーモア・ヒロシマズ運動に言及した後「あなた方の捧げた尊い生命を、犠牲を、無駄にしてはなりません。生命のある限り私達も祈り且つ努力致します」と〈平和主義の語り〉で手記を終えているが、そうせざるを得ないのであろう。息子が「尊い生命」を「捧げた」対象は、大義を失くした「聖戦」や大日本帝国であっては、その死が報われないことになる。そうではなく、敗戦後に国家の理想として掲げられた〈平和〉という大義のために犠牲となったと意味づけたならば、「平和を誓う」という行為を通して、その死に報いることも可能となるのである。 しかし、いくら〈平和〉に貢献していると思い込もうとしても、残された親にとって、幼い我が子の死を受容することは容易ではない。
理論と動態 �

平和を斉らした端緒であったかも知れない又現在世界を兎にも角にも熱戦の惨禍より防いでゐるものかも知れない。けれども、私達夫婦に取ってはあの原爆はいくら考へ直しても如何にも憎くそして怨しいものである。(柳武)
7回忌が過ぎても、柳は息子の遺骨を墓に埋める気にはなれず、その一部を肌身離さず持ち歩いているという。「喪の途上」(野田正彰)にある柳にとって、息子の死を「平和のための尊い犠牲」として受け容れることはできない。息子は最後まで「聖戦」を信じて逝ったが、柳はそれを〈殉国の死〉として意味づけることもできない。そして、原爆を憎む気持を吐露しながらも、〈平和主義の語り〉に訴えることもできない。 柳のように、戦死者追悼の3種の語りのいずれも援用していない手記は54編あり、『追憶』の大半を占めている。国家や平和といった大義と結びつけることで死に意味を見出して慰めを得ようとするよりも、最期を看取ることができたことや生前一緒に遊んだ思い出などを心の支えとしようとする親もいる。いずれにしても、圧倒的多数の親たちは、死に意味を付与することができないまま、幼い我が子を失った悲しみと苦しみに、ひたすら耐えているのである。
�.� 『ゆうかりの友』 『追憶』から30年後の1974年、働き盛りとなった生存学徒の手によって『ゆうかりの友』(手記数213編)が刊行された。ほぼ全滅だった1年生のうち、九死に一生を得た生徒が中心となって編集したものである。 収録された「遺族へのアンケート」からは、子どもを失った親の哀切は必ずしも和らいでいないことが伝わってくる。返事を寄せながらも、「何とも口ではいえません。文にも書けません」(乃美巌)と、その胸のうちを言葉にすることに躓いてしまう遺族もいるほどである。しかし、子供の死から20余年の月日が経ち、『追憶』にあった、触れれば火傷しそうなほどの狂おしい嘆きが、親の加齢とともに烈しさを失ったことも伝わってくる。 〈殉国の語り〉や〈平和の礎論〉によって子どもの死を受け容れようとする親たちの姿は『追憶』のなかでもみられたが、そうすることで、耐えきれない悲しみを何とか抱えようとしていた。それに対して、『ゆうかり』では、ある種のあきらめのような感情がみられる。
尊い尊い殉死である。純真な美しい心で、ただ祖国の為に、祖国を救う平和の礎石となって逝った。スコップを手に、銃を持った兵隊と同様な姿で死んだものと思う。(岡野愛子)
建物疎開の作業中に原爆に遭ったということ以外、岡野は、一人息子がいつどのようにして死んだのか、その消息をつかむことは遂に出来なかったという。だからこそ、勤労奉仕に励んだ結果、息子が死に至ったことを「尊い尊い殉死」として納得しようとしているのであろう。 〈殉国の語り〉と〈平和の礎論〉が併用されているのは岡野の手記に限られており、他に〈殉
�

国の語り〉を用いたものが1編、〈平和の礎論〉を用いたものが1編あるが、「仕方がない、これも御国の為だと思います」(三村スエヨ)、「名門校一中で平和の為に死んだ事と思っています」(佐々木初吾・佐々木スギヨ)というように、息子の死は国家や平和のために有意義であったと思うことで、なんとかあきらめようとしている。
このような生き乍らの地獄の形相をくり展げるような原水爆は、絶対に、世界の国々に禁止することを心よりお願いして筆をおきます。(松永繁)
松永のように〈平和主義の語り〉がみられる遺族の手記は5編あるが、アンケートの項目に対する回答であるという理由もあってか、『ゆうかり』には、子供の死を意味づける記述が少なく、『追憶』のように心情を吐露する言葉もあまりない。 親たちの多くがアンケートに応えたのに対して、生き残った生徒の多くは沈黙したままであった。遺族の中にも、息子の死を防ぐことのできなかった自責の念を表現したものがあるが、死者に対する負い目は、生き残った生徒の間でより強烈だったからである。 『ゆうかり』の編集を担当した原邦彦も〈生き残った生徒〉という重荷を背負って生きてきた。校長の求めに応じて46年に書いた手記では、被爆直後の学校の状況や級友たちの惨状に言及しているものの、避難の道中で出会った友人については触れていない。それに対して
『ゆうかり』では、固有名詞を挙げて彼らのことを書いた。そんな原も、友の死に意味を与えることに躓いている。 『ゆうかり』に手記を寄せた5人の生存生徒のうち、「再びこうした惨禍が繰り返されぬよう平和を希求する声を消してはならないと思う」(本田重雄)のように〈平和主義の語り〉を用いながら追悼文を寄せた者は2人いるが、四半世紀が過ぎてもなお心の整理がついていない者もいる。とりわけ、何らかの理由で当日学校を休んだ者は、そうした傾向にある。 『ゆうかり』に手記を寄せた生存生徒は数が少なく、結論めいたことは言えないが、次に見る市女の追悼記集からは、生存生徒による追悼の在り方がより鮮明に浮かび上がってくる。
� 広島市立第一高等女学校
�.� 『流燈』 原爆死者13回忌にあたる1957年に『流燈』(手記数38編)が刊行された。それは、ちょうど日本原水爆被害者団体協議会が結成された時期と重なる。原爆を生き延びた者が自らを「原爆被害者」として捉え返しながら、「ふたたび被爆者をつくらない」運動を始めた頃である[直野2013]。しかし、『流燈』に収められた手記のなかで、平和擁護や原水爆禁止への努力を死者慰霊とつなげる〈平和主義の語り〉が援用されたものは4編にとどまる。〈平和の礎論〉は、さらに少なく2編しかない。
あなたの犠牲によって漸く平和が甦り、国も滅亡から救われお兄さんも弟も妹も夫々平和の裡に立派に生長し今日では毎日朝に夕に仏前にてあなたに感謝報恩の誠心を捧
理論と動態 �

げています。(宮本正一)
女学生の娘を死なせながら軍人だった自分が生き延びたことは「懺愧にたえ」ないと宮本は苦しんでいた。だからこそ、娘の死は有意義なものであったと意味づけようとするのだろう。国家との関係のなかにわが子の死を位置づける語りのなかでは、子を亡くした親の悲哀は影をひそめる。しかし、行方不明のままの娘が「『お父ちやあん』と云って走って来るかもしれない様な気がする」ため、宮本は娘の最後の地を通って毎日勤めに出るという。そこには、国家との関係を介さない父と娘の絆を見ることができる。 「護国の英霊」となることや靖国合祀を支えに子の死を抱きとめようとするなど、〈殉国の語り〉に訴える手記も3編だけある。永田とめは、娘が生前「女でも死んだら靖国神社におまつりして頂けるのよ」と微笑んでいたことを思い起こしながら、娘が合祀される日を「今年は来年はと待ちつづけて」いるという。しかし、靖国合祀が叶ったとしても、悲しみと嘆きが消えるとは思えない。なぜなら、「いか様に慰めの行事をして頂きましても、この母の思いはつきぬ。(中略)宿縁とあきらめるにはあまりにも痛ましい」というのであるから。 まだあどけない顔をした娘を突然原爆で奪われた親にとっては、いかなる大義名分を掲げたところで慰めにはならない。子の13回忌を迎えようとしていた親たちは、悲嘆の中を生きているのである。
何一つとして親らしいことがしてやれなかった。せめて今頃まで、生きていてくれたら、少しは幸にしてやれたろうに。勝つまでは勝つまではだけで、すまなかった。許しておくれ。(澤田いちよ)
澤田のように、死んだ子どもに対して詫びる親は少なくない。動員学徒たちは、戦時中に生を受けて、戦争しか知らずに死んでいった。食べたい盛りの子どもにお腹いっぱい食べさせてやれなかった、不自由な生活しかさせてやれなかったと詫びる親は多い。そして、何よりも、子どもを死なせてしまったことを、すまなく思うのである。
�.� 『流燈 続編』 原爆死者の33回忌にあたる1977年、『流燈続編』(手記数53編)が市女の遺族会と同窓会とによって発行された。そこには、『ゆうかり』と同様、子を失った親の悲哀には日薬さえも効き目がないと思わせる手記がいくつもある。 体調を崩した娘を休むよう説得できなかったことを、宮本操は悔やんでも悔やみきれないという。「お国のために」と作業に出た娘は行方不明のままである。残された親の狂おしい悲哀を何とか抱きかかえるためにも、子どもの死に意義を見出さずにはいられないのであろう。宮本は子供の死を「国のため」に「散っていった」と意味づける。しかし、「運命とは誠に紙一重と申しますが可愛そうで悲しくて、すまなさでこの胸は一杯」なのである。『続編』では〈殉国の語り〉は3編にしかみられないが、宮本の語りが示すように、死を称えるという態度とはかけ離れている。
�0

〈平和の礎論〉も3編と少数である。「戦後三十二年平和の暮しができ、みんなが楽しく、過されるのはあの残酷な原爆で、焼死されたみなさんの貴い犠牲があるからです」と坂本文子は戦死者を忘れて豊かさに浮かれる世の人々に対して死者を忘れないよう訴える。そこには、親亡き後、悲惨な死を遂げた娘を記憶する者がいなくなることへの危惧がみられる。 『続編』には遺族による13編の手記だけでなく同窓生による手記も35編収録されている7)。遺族の手記には〈平和主義の語り〉が2編にしかみられないのに対して、同窓生の手記には20編もみられる。 病気で作業を休んだために助かったという森原シズヱは、生き残ったうしろめたさに苛まれてきた。生き残ったという事実だけでもうしろめたく思うのに、死んだ同級生の親たちに
「横着者が助かって、まじめに作業にいった者があんなめにあって」という言葉を投げつけられたのである。「一緒に死ねなかった事がくやまれて母親がわりの姉をなきながらせめた事」もあったという。しかし、30余年という時が過ぎ、幼くして生を断ち切られた級友たちの悲劇が繰返されないようにとの思いを込めて、「子共達に、戦争で多くの犠牲者のあった事を忘れぬように、平和のありがたさを、大切さを、よく知ってほしいと思っています。合掌」と結んでいる。これも、平和を願う〈平和主義の語り〉といえるであろう。 生存学徒たちは、多くの学友が原爆で死んだなかで生き残ったことに生涯苦しむことになった。とりわけ、原爆から間もない時期においては、森原のように、死んだ生徒の親たちに心ない言葉を投げつけられ、遺族を避けて慰霊祭にも行かなくなったという者は多い。生き残ったとはいえ、生存学徒たちの多くは被爆しており、後遺症や健康不安に苦しむことになったし、なかには後に原爆症で命を落とす者も出た。何よりも、学友が命を落としたのは生き残った生徒のせいではない。それがわかっていても、やはり、生きていることに負い目を感じてしまう。しかし、年月が経ち、うしろめたさと向き合うことで、自分が生き残った意味を見出し、学友たちの最期を記録する行動を起こしていった。その結果、『ゆうかり』や
『流燈続編』など生存学徒の手による手記集が1970年代以降、次々と世に出されていったのである。
�.� 『流燈 第�編』 『流燈続編』から、さらに10年たった1987年に『流燈第3編』(手記数28編)が刊行された。親たちはこの世を去るか、高齢になって活動することもままならなくなったため、『流燈』や
『続編』とは違い、遺族による手記は2編しかなく、同窓生による手記がその大半を占めている。「学徒動員時代の作業内容を書いてください」という依頼に応えた手記が多いため、原爆に言及していないものもあるが、〈平和主義の語り〉が最も多く10編(うち1編は遺族)ある。それに対して、〈殉国の語り〉は1編もなく、〈平和の礎論〉も〈平和主義の語り〉と接合された同窓生による手記が2編あるのみである。被爆40年を過ぎて、死者の記憶は原爆の集合的記憶に統合されてきたことがうかがえる。 原爆当日、作業に行かなかったために、他の場所で被爆しながらも助かったという浅尾早苗は、生き残りとしての責任を平和への努力へとつなげている。
理論と動態 ��

人類史上初めて使用された原子爆弾により多くの犠牲者を出し、残された私達は二度とこんな戦争をしてはならないと、平和に対する使命の重責をいっそう深く認識しております。
浅尾は『続編』にも手記を寄せていたが、そこには、友の命を奪ったものへの怒りと原爆の傷跡の痛みが明確に表現されており、同じ〈平和主義の語り〉であったとしても、『第3編』の抽象的な文章よりも力強さがある。
米国はなぜ戦争の終結に核兵器を使用したのでしようか。この原子爆弾が広島に投下されなかったら皆んな死ななかったはずなのに。(中略)放射能を浴びた体をいたわりながら「核兵器の完全廃絶」を願い、残された余生を大切に、一生懸命生きている昨今です。
浅尾の例にみられるように、『続編』にあった烈しい情動を『第3編』から感じることはない。親たちによる追悼記が少ないことも一つの要因であるが、生き残った生徒にとっても、40余年という年月が経ち、生き残った負い目や苦しみがいくばくかは溶けたことが大きな要因であろう。子の成人や孫の誕生といった節目を迎え、人生に一区切りついたことで、過去に向かっていた記憶のベクトルが、未来へと重心を移していくことになった。そうした傾向は、市女の新制校である舟入高校の同窓会が市女同窓会と共に『第3編』の発行者として名を連ねていることにも現れている。
� 広島県動員学徒犠牲者の会
�.� 会の活動概要 1957年2月に「広島県動員学徒犠牲者の会」が結成された。52年に「戦傷病者戦没者遺族等援護法」が制定されたが、動員学徒に対しては弔慰金が支払われただけであった。そこで、動員学徒の扱いに不満を抱いた遺族や元学徒たちが、会を組織して援護要請運動を開始することになったのである[広島県動員学徒等犠牲者の会1975:67-73]。動員学徒の戦時中の活動は「正に軍人の戦線活動に匹敵する」という理由を掲げて、会は「軍人軍属と同様に」を合言葉に「国家補償」を要求した[結成趣意書]。ほかに、遺族からは死亡した学徒を靖国に合祀するよう強い要望が会の結成当初から出ていたという8)。山口県や大阪府の会などとともに全国組織の「動員学徒援護会」と連携しながら活動を進めたが、運動の成果もあって、63年に靖国合祀が叶い、65年の夏以降、学徒が叙勲されることになった。さらに72年には遺族給与金と障害年金が軍属と同額に引き上げられ「悲願」は達成された[広島県動員学徒等犠牲者の会1975:86-97]。
�.� 会員の語り 会のオフィシャルな語りでは〈殉国の語り〉と〈平和の礎論〉が強調されがちであるが、会員たちが、どのようにして死んだ子どもや学友たちを記憶してきたのかをみるために、「学
��

徒犠牲者の会」の刊行物に載せられた手記を検討してみることにしよう。 1968年に刊行された『動員学徒誌』(手記数44編)にある手記5編に〈平和の礎論〉がみられる。会としてのオフィシャルな立場を反映してか〈殉国の語り〉が10編を数えるところに特徴がある。とりわけ靖国合祀と叙勲受章が実現したことに言及しながら、子の死を顕彰しようとする語りが複数みられる。しかし、戦死したら靖国に合祀されると信じていた子どもは
「満足に思っている」かもしれないが、「掌中の玉を失った気持で胸が一ぱい」(林まつ子)だという母親もいる。林のように、子どもの死を意味づけきれないものも少なくない。 生存学徒の手記には「多くの学友が死没されたのに、私一人が生き残っているのは相済まない気がして思わず涙を呑みました」(柿原蓉子)というように、『ゆうかり』や『流燈続編』でもみられたような〈生き残った負い目〉による苦悩もみられる。 靖国合祀を推進した「学徒犠牲者の会」ではあるが、「原水爆禁示を声を大にして叫びたい」
(朝日輝一)のような〈平和主義の語り〉が11編と最も多くみられる。会員の中には原水禁運動や被爆者運動に関わっている者が複数いることも〈平和主義の語り〉が多用される要因の1つであるが、〈殉国の語り〉と〈平和主義の語り〉が併用されている手記が2編あるように、会として死者を顕彰するからといって、平和擁護や核兵器反対を表明するという、原爆死者追悼において支配的な語りと共存できないわけではない。1950年代半ばに起こった原水爆禁止運動の国民的な広がりが党派ごとに分裂した60年代にあっても、「原水爆禁止と平和擁護」という理想は革新から保守まで広く共有されていたのである。ただし、その具体的内容や方法論に関しては、相容れない対立があった。それが、より明確な形で現れているのが75年に刊行された『戦後30年の歩み』である。 『戦後30年の歩み』(手記数45編)では〈殉国の語り〉が最も多く13編を数える。〈平和の礎論〉は3編しかないが、〈平和主義の語り〉は11編ある。〈殉国の語り〉と〈平和主義の語り〉が数の上では拮抗しているが、〈平和主義の語り〉の多くは〈殉国の語り〉に接近している。革新陣営にみられるような反戦平和の訴えは1編だけであり、〈平和主義の語り〉のうち3編は
〈殉国の語り〉と併用されている。〈殉国の語り〉が見られない場合でも、愛国心や国家主義を唱えつつ核兵器廃絶や平和を訴えている。ここに国家や戦中の道徳観を重んじる「学徒犠牲者の会」という集団における集合的記憶の特徴がみてとれる。 被爆50年に刊行された『動員学徒誌被爆50周年記念』(手記数45編)は、収録された手記の半数近くの23編に〈平和主義の語り〉がみられ、遺族においても生存学徒においても手記の半数を占める。それに対して、〈平和の礎論〉は3編、〈殉国の語り〉は6編と少数であり、それらはすべて遺族によるものである。靖国合祀と叙勲を誇りとしながら娘の死を「世界平和のために無駄ではなかった」と意味づけ、「国民こぞって世界平和を願いたい」というように、3種の語り全てを援用した手記が1編、靖国神社参拝を毎年の行事としながら「戦争は絶対にしたらいけない」と訴えて、〈殉国の語り〉と〈平和主義の語り〉を併用した手記が1編あることからも、全体として〈平和主義の語り〉が主流であることがわかる。
理論と動態 ��

� 追悼と集合的記憶の関係 ここまで、一中、市女、「学徒犠牲者の会」という3つの集団における語りを検討してきたが、ここでは、原爆の集合的記憶と個人による死者追悼との関係について、さらに考察を深めていきたい。
�.� 集団における語りの特徴 『泉』と『戦後30年の歩み』を除く全ての手記集において、〈平和主義の語り〉が最も多くみられ、どの集団においても、死者追悼と平和への願いとは接合される傾向にあることがわかった。『泉』は敗戦翌年に発行されているが、その時期には原爆死者慰霊が平和主義と結び付けられてはいなかった。しかも、手記を寄せた生徒たちは、手記を書く数ヶ月前までは、死をも厭わず「お国のために」勤労奉仕に励んでいたのであり、学友の死を国家という大義との関連で讃えようとするのも頷ける。『戦後30年の歩み』には、靖国合祀、叙勲、軍属と同等の援護獲得という会の目標が実現したことを受けて書かれた手記が多く、「祖国の安泰に努力するため」という趣旨の座談会での発言に〈殉国の語り〉をはじめとする国家主義的な語りが多くみられることになった。一中や市女と比べて「学徒犠牲者の会」には〈殉国の語り〉が多くみられるが、靖国合祀を要求した集団としての特徴が会員の語りに反映されているともいえるし、そうした個々の語りによって会の集合的記憶が形成されているともいえる。しかし、
「学徒犠牲者の会」においても〈平和主義の語り〉が〈殉国の語り〉と並んで多いという点、子どもの死に意味を付与することができず悲しみに沈む親が多いという点は、一中や市女の遺族と共通している。
�.� 死者との関係性 死んだ学徒の遺族であるのか、同級生や同窓生であるのかという、死者との関係性における違いも語りに反映されている。『流燈続編』に手記を寄せた関係者のうち、同窓生の手記で
〈平和主義の語り〉を用いたものは6割にものぼる。それに対して、遺族の手記の6割には、3種の死者追悼の語りのいずれもみられない。『続編』とほぼ同時期に刊行された『ゆうかり』に収められた遺族の手記からも同様の傾向がみられるが、生存生徒の手記が少ないため、『続編』のような比較はできない。「学徒犠牲者の会」の刊行物でいうと、『動員学徒誌』に収められた遺族の手記の29%、『被爆50周年記念』では18%が〈殉国の語り〉を用いているのに対して、生存学徒の手記にはみられないという違いがある。 家族として生活を共にしていたのか、学友として関係があったのかという違いが、『続編』においても「学徒犠牲者の会」の刊行物においても、追悼の語りに反映されているといえる。長い年月を経てもなお、親たちは子どもを家族の一員として記憶しており、だからこそ、幼くして逝った子どもの死を嘆き、いずれの死者追悼の語りをもってしても慰めを得ることは難しい。親子という関係性が子の死後も維持されていることは、「学徒犠牲者の会」の親たちが子どもの靖国合祀を要求したことからも伺える。我が子の死が国家に貢献したと国家に認めてほしいのは、それが子どもの願望だったからである9)。
��

生存学徒の場合、生き残った負い目を感じるために、過去と向き合うことを避けてきた。しかし、自らの加齢に伴い、幼くして死んだ同級生を自分の子どもや周囲の子どもたちの姿と重ね合わせて想起するようになり、平和な未来への願いと死者追悼を結びつけることになった。だから、〈殉国の死〉や〈平和の礎〉という過去を重視する語りよりも、未来志向の〈平和主義の語り〉が『続編』には多くみられることになったのである。また、「学徒犠牲者の会」に集った生存学徒たちは、原爆による障害を持っており、死者の顕彰よりも、軍属と同等の援護を強く求めた。死者追悼を通して同級生という過去の集団を維持することよりも、障害者としての苦しみを和らげることのほうが切実だったのである。
�.� 社会という文脈 学校単位で慰霊のために集った集団と国家による顕彰を要求する集団という性質の違いや、遺族と同窓生という死者との関係性の違いが追悼のあり方に反映されていることがわかった。小規模な集団においても、集合的記憶と個人の死者追悼との間に相関関係があるということである。同時に、集団間にみられる追悼のあり方の共通性を踏まえると、日本社会の集合的記憶が、死者追悼のあり方により
4 4
大きな文脈を与えていると考えられる。 前述のように、近代の戦死者は国民国家の一員として記憶され、死後においても国民統合のために動員されることが多い。しかし、戦争そのものが間違っていたとなれば、戦死は〈無意味な死〉として社会から忘却されていく。小田実が指摘するように、アジア太平洋戦争が侵略戦争として否定されて大義を失ったため、〈日本人〉の戦死全般は〈無意味な死〉となってしまった。この事実は、遺族をはじめとする戦争体験者にとって受け容れがたい。戦争そのものを肯定することで死者を「難死」から救うことはできるが、社会的な孤立を招きかねず、戦死者を社会的に顕彰するという目的を果たせない。だから、戦争を否定してもなお戦死に意義を見出せる論理を探さなければならないのである10)。そこで、戦死を「散華」として救い出すために殉国の美学が持ち出されることになるが[小田1991:9-10]、そうした傾向を『泉』からみることができる。 敗戦を境として、それまで信じていた戦争の大義を喪失したことで、生き残った学徒たちは、学友の死をどう意味づけてよいのか戸惑うことになった。戦争の大義のなかで友の死を意味づけることはできなくなったが、それを無駄死と認めることはできない。なぜなら、生と死に分かたれるまで、友は「お国のため」に命を捨てる覚悟で勤労奉仕に励んだ仲間だったのであり、彼ら・彼女らの死が無意味であるならば、自らの戦中体験も無意味なものとして否定されてしまうことになるからである。こうした「死者との連帯」[作田1981:164-166]意識から、「お国のために散った」と友の死を意味づけて国家再生を誓うのである。 殉国の美学は死を観念的に捉えるため、『泉』に手記を寄せた生徒のような若者ならともかく、子を亡くした遺族の間では、さほどの広がりを持たなかった。その代わり、〈平和の礎論〉や美学を介さない〈殉国の語り〉によって子の死を意味づける遺族は一定数存在した。たとえ大義のない戦争であったとしても、死者の犠牲によって戦争が終結し平和がもたらされたのであれば、その死は国民国家を存亡の危機から救ったことになり、「尊い犠牲」として意味づけることができる。そうした意味において〈平和の礎論〉は、殉国の美学のようなロマン
理論と動態 ��

ティシズムはないにせよ、結果として動員学徒たちを「殉国の士」として記憶することになる。国家という大義は敗戦を受けてもなお生き続けたといえるのである。 ただし、戦死者を「平和の礎」として標榜するためには、戦後日本が平和を維持しなければならない。だから、戦死者に感謝するだけでなく〈平和〉のために努力するよう促されることになる。しかし、ここでいう〈平和〉は、高度経済成長を経た60年代以降、「平和な家庭を守る」という保守的な意味合いを含む場合が多く、だからこそ、〈殉国の語り〉が他の集団より多用されている「学徒犠牲者の会」の手記にも〈平和主義の語り〉が多くみられるのである。 高橋三郎[1988]や新田光子[2005]が論じるように、戦闘員の戦死は戦後日本社会のなかで否定的に扱われたために、生き残った兵士は、自分の過去の体験や戦友の死に対して社会的な認知を求めて、靖国国家護持要求へと向かう傾向にあった11)。それに対して原爆死者の場合は、戦争被害者の代表的存在として認識され、原水爆反対の根拠や平和の尊さの象徴として想起されてきた。原爆死者は平和への誓いを促す道徳的権威として、政治的な立場の如何にかかわらず敬意が払われてきたのである。だから、残された者が原爆死者を追悼する際には、元軍人のように死者を顕彰する必要はなく、〈平和主義の語り〉のなかで死者を慰霊することで多少は慰めを得ることができたのである。それは、本稿で検討した追悼記集全般において〈平和主義の語り〉が占める割合が他の2種の語りに比べてかなり高いことにも表れている。
� 結語に代えて
戦後日本における戦死者追悼の3種の支配的な語りが原爆死者追悼においてどのように表現されているかをみたが、その表れ方は、行為主体が属する集団や社会的な文脈に応じて異なることが明らかになった。同時に、数十年経っても、子どもの死に意義を見出すことができずに悲哀を生きる遺族が多いことも見逃せない。〈平和主義の語り〉をはじめとする戦死者追悼の語りを援用したからといって、悲しみの強度が必ずしも和らぐわけではないことも、手記の分析でみた通りである。生存学徒たちも、生き残った負い目から、長年の間沈黙してきた。こうした遺族や生存学徒の姿から、社会の集合的記憶の枠組みでは捉えきれない死者追悼の営みが確かに存在することがわかる。国家や平和という大義との関連で死に意味を与えたとしても、それで死を納得することはできないのである。しかし、時の流れとともに、家族や学校という死者が属していた集団は解体し、それらの集合的記憶も消え去ることになるため、原爆死者追悼も、より抽象的な社会の集合的記憶や国家の論理のなかに吸収されていく可能性が高い。 1980年代後半から被爆50年にかけては、原爆死者慰霊が年老いた親から兄弟や同窓生へと引き継がれていった時期であるが、ちょうど世界的な反核兵器運動や国内の被爆者運動が広く支持を集めた時期でもあった。こうした背景を受けて、この時期に発行された追悼記集には〈平和主義の語り〉が多くみられることになった。それは、死者の犠牲を「あってはならない悲劇」として社会が記憶し続けるよう求める意思表示でもあった。だがそれは、70年代までの手記──とりわけ初期のもの──にみられた激しい悲哀の情が、型にはまった語りの
��

なかに収まっていくことにもつながった。 他方、社会に加えて国家にも死者を記憶し続けるよう求めたのが「学徒犠牲者の会」である。1978年には「社会福祉の向上」を掲げた財団法人として組織を再編成して会員の裾野を広げ、遺族や同級生ではなく、広く社会が死者顕彰を引き継いでくれることを期待した。同時に、70年代半ばから靖国神社の国家護持を運動方針として掲げるようになった。死者を記憶する主体を有縁者から社会や国家に広げることで、永代供養への道を開こうとしたのである。 柳田国男は若くして死んだ兵士たちが無縁仏となることを危惧したが、動員学徒たちも家において祭祀を行ってくれる子孫を持たずして命を絶たれてしまった。だからこそ遺族たちは、「永遠の命」を持つかにみえる国家や社会に向けて学徒たちを記憶し続けるよう要請するのである。 要請の対象である限り、国家や社会に対して、死をもたらした戦争の責任を問いただすという姿勢は希薄である。本稿で分析した手記の中にも、原爆投下を招いたという理由で日本の指導者に怒りをぶつけるものもあるが、〈平和主義の語り〉のなかにも責任追及の声はきわめて少ない。それが総力戦であったために、戦争責任の追及は自分の身に返ってくることになるからである。だからこそ、少なくない手記のなかに「すまない」という言葉が綴られたのであろう。 死をもたらした構造的な要因を追及する代わりに、「学徒犠牲者の会」に集った親たちは靖国合祀を求めることで「すまなさ」を解消しようとした。死んだ子の望みを叶えようとすることは、親として自然な情なのかもしれない。しかし、そうした慰霊行為を通して個人の記憶は、死者を「英霊」と称えながら国家批判を封じ込める国家の論理に統合されていくのである。 欲しがっていた食べ物を霊前に供えるというようなケースは別として、生前の願いを叶えてやることは、敗戦後の日本においては不可能であった。学徒たちは一億玉砕するまで戦うと信じていたし、「ノーモア・ヒロシマズ」と訴える代わりに「仇を討つ」と誓ったのである。しかし、敗戦を認めて天皇も国家も国民も死者を裏切った。その事実と向き合わないまま、靖国合祀を要求しながら米国に追随したり、「平和を願っていた」と死者の生前の願いを読み替えて平和国家の建設を訴えることは、たとえそれが有縁者によるものであったとしても、欺瞞であるといわざるを得ない。国家による顕彰や平和への誓いを通して死者の願いを叶え、その死に報いることはできないのである。 もしかりに、残された者が死者を裏切ったという事実と向き合っていたならば、戦死者追悼のあり方だけではなく、戦後日本社会も違ったものになっていたであろう。〈平和主義の語り〉はもっと鮮明に国家批判の色を帯びていたであろうし、国家に償いを求める声や国民の戦争責任と向き合う動きが、もっと広がっていたであろう。個人レベルにおける記憶行為が社会全体の集合的記憶を変容させ、新たな社会を創造する契機となりえたのである。しかし、幼い我が子に先立たれた親や生き延びた負い目を背負ってきた生存学徒にそれを求めるのは、酷すぎるのかもしれない。戦後日本の集合的記憶を形成してきたのは、戦後を生きる者である。つまりそれは〈戦後世代〉こそが引き受けるべき課題なのであろう。
理論と動態 ��

[付記] 本研究は JSPS 科研費23730482の助成を受けたものです。
[注] 1) 記憶は物
ナラティブ
語であると断言する論者もいるが、そこには、語りにならない情動や身体実践も含意されているため[直野2010;Connerton1989=2011]、追悼を考えるうえで記憶という概念は有用であると考える。
2) 本稿では〈追悼〉と〈慰霊〉を区別せずに使用する。追悼においては生者の行為や情動に力点が置かれるのに対して、慰霊は働きかける対象である死者の側により重きを置く場合が多い。しかし、死者を慰めることで、悲しみや怒り、恐れといった生者の情動を鎮めるのであり、追悼も慰霊も、生者が行為体として死者に働きかける営為であることに変わりはなく、ともに死者に関する記憶行為として考察できると考える。
3) 西村[2006]も靖国合祀を求めた長崎医科大生の遺族の語りを分析対象としているが、遺族と同窓生の立場を区別することなく論を進めている。
4) 1年生を中心に353人もの生徒と16人の教職員が原爆死している[『中国新聞』2010.8.14 ;広島県立広島国泰寺高等学校百年史編集委員会編1977:485]。被爆50年までに刊行した手記集の数でいえば、広島と長崎の学校の中で旧長崎医科大学に次いで多い。
5) 1年生277人、2年生264人を含む666人の生徒と教職員10人が原爆で命を落とし、学校の中では最も多くの死者を出した[『中国新聞』1999.2.28;2000.6.22;2000.6.23]。女学校としては、広島女子高等師範学校附属山中高等女学校と並んで最も多くの手記集を発行している。
6) 遺族の手記だけでなく、座談会における発言も検討に加えている。また、追悼記集には詩や短歌、漢詩が若干含まれているが、それらは語りと違う表現形式であることから分析の対象からは除外する。
7) 残り5編は教職員による。 8) 初代会長の寺前妙子による。聞き取りは、2012年2月21日に広島市内で行った。9) 敗戦後、靖国が国家機関でなくなったという制度的な変化は、この際重要ではない。
遺族にとって靖国合祀は戦前の約束を国家に果たさせるという意味を持つのである。10) 近年、アジア太平洋戦争を肯定する勢力が力を増しているため、戦争を肯定的に評価
することで戦死者顕彰を果たすことが容易になるかもしれない。11) 軍人は社会的には否定的な扱いを受けたかもしれないが、国家補償や叙勲の対象とな
ることで国家からは謝意を獲得している。
[文献]赤澤史朗,2005,『靖国神社──せめぎあう〈戦没者追悼〉のゆくえ』岩波書店.Connerton,Paul,1989,HowSocietiesRemember,Cambridge:CambridgeUniversityPress.
(=2011,芦刈美紀子訳『社会はいかに記憶するか──個人と社会の関係』新曜社.)Halbwachs,Maurice,[1950]1968,LaMèmoireCollective,Paris:PressesUniversitairesde
��

France.(=1989,小関藤一郎訳『集合的記憶』行路社 .)原田敬一,2013,『兵士はどこへ行った?──軍用墓地と国民国家』有志舎.広島県動員学徒等犠牲者の会,1975,『戦後30年の歩み』広島県動員学徒等犠牲者の会.広島県立広島国泰寺高等学校百年史編集委員会編,1977,『広島一中国泰寺高百年史』母校
創立百周年記念事業会.一ノ瀬俊也,2010,『故郷はなぜ兵士を殺したか』角川学芸出版.岩田重則,2003,『戦死者霊魂のゆくえ──戦争と民俗』吉川弘文館.Mosse,GeorgeL.1991,FallenSoldiers:ReshapingtheMemoryofWorldWars,Oxford:
OxfordUniversityPress.(=2002,宮武実知子訳『英霊──創られた世界大戦の記憶』柏書房.)
西村明,2006,『戦後日本と戦争死者慰霊──シズメとフルイのダイナミズム』有志舎.波平恵美子,2004,『日本人の死のかたち──伝統儀礼から靖国まで』朝日新聞社.直野章子,2010,「ヒロシマの記憶風景──国民の創作と不気味な時空間」『社会学評論』60
(4),pp.500-516.────,2013,「原爆被害者と〈戦後日本〉──被害意識の形成から反原爆へ」安田常雄編『シ
リーズ戦後日本社会の歴史・第四巻社会の境界を生きる人びと──戦後日本の縁』岩波書店 ,pp.220-247.
新田光子,[1983]2005,「慰霊と戦友会」高橋三郎ほか『新装版共同研究戦友会』インパクト出版会 ,pp.213-252.
Nora,Pierre,ed.,1984,LesLieuxdeMémoire,Volume1:LaRépublique,Paris:Gallimard.(=2002,谷川稔監訳『記憶の場1対立』岩波書店)
小田実,1991,『難死の思想』岩波同時代ライブラリー.作田啓一,1981,『恥の文化再考』筑摩書房.四條知恵,2012,「純心女子学園をめぐる原爆の語り──永井隆からローマ教皇へ」『宗教と
社会』18,pp.19-33.高橋三郎,1988,『「戦記もの」を読む──戦争体験と戦後日本社会』アカデミア.田中丸勝彦,2002,『さまよえる英霊たち──国のみたま、家のほとけ』柏書房.宇吹暁,1999,『原爆手記掲載図書・雑誌総目録』日外アソシエーツ.
(なおの・あきこ 九州大学)
理論と動態 ��

【欧文要約】
Work of Mourning and Collective Memory of War: Remembering Hiroshima’s Perished Students
NAONO,AkikoKyushuUniversity
Inanattempttodrawouttherelationshipbetweenanactofmourningthewardeadand thecollectivememoryof thewar, I lookat threegroups thathavecollectivelymemorialized thedeceasedmobilizedstudent-workerswhowerekilledby theatomicbombingofHiroshima:theHiroshimaPrefecturalDaiichiHighSchool,theHiroshimaCityDaiichiWomen’sHighSchool,andtheHiroshimaPrefecturalAssociationoftheVictimizedMobilizedStudent-Workers.Thesethreegroupshavepublishedaccounts inmemoryofperishedstudent-workers fromtheearlypostwaryearstothepresent.Theseaccounts,writtenmostlybystudents’bereavedfamilymembersandthesurvivingstudent-workers,areanalyzed in relation to the threedominantnarrativesof remembering thewar-deadinpostwarJapan:1)the“foundationofpeace”narrative,2)the“martyrdomforthecountry”narrative,and3) the“pacifist”narrative.Analyzingtherelationshipbetweenthesegroups’collectivememoryandtheirmember’swayofcomingtotermswiththestudents’deaths,wecanconcludeas the following.First, threegroupsdiffer in theirmembers’waysofmakingsenseofthestudents’death.Second,one’swayofmourningthedeaddiffersaccordingtoonesrelationshipwiththedead,eitherasafamilymemberoraclassmate.Third,collectivememoryoftheatomicbombinginJapanhavehadagreaterinfluenceonhowonemournsthedeathof thestudent-workersthangroup’scollectivememoryorone’srelationshipwiththedead.Finally,whileindividualactsofmourningarenotentirelydeterminedbythecollectivememory,asthemnemoniccollectivity,suchasfamilyandschool,beginstodisintegrate,memoriesofthedeadstudent-workersarelikelytobesubsumedunderJapan’scollectivememoryofthebombingandthusbecomemoreabstract.
Keywords:mourningthewardead,collectivememory,mobilizedstudent-workers
�0














![クレオパトラⅦの追憶 - [分冊版] クレオパトラⅦの追憶 3/4](https://static.fdocument.pub/doc/165x107/57906feb1a28ab68749b11ee/-57906feb1a28ab68749b11ee.jpg)