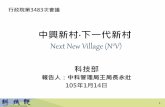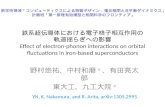放送業界 - fseminar.com放送業界~日テレ・TBS・フジテレビ・テレ朝~...
Transcript of 放送業界 - fseminar.com放送業界~日テレ・TBS・フジテレビ・テレ朝~...

放送業界 ~日テレ・TBS・フジテレビ・テレ朝~
福田哲也ゼミナール
経済学部八期生
池田 泰輔
中井 茜
中村 圭介

放送業界~日テレ・TBS・フジテレビ・テレ朝~ (池田・中井・中村)
2
目次 1.はじめに 4 2.業界及び企業の概要 5 2-1.業界概要 5 2-1-1.放送事業とは .5 2-1-2.経営基盤と収入形態 5 2-1-3.広告収入の仕組み 6
(1)テレビ広告の種類 6 (2)視聴率と広告費の関係 7
2-1-4.放送業界の現状 8 2-2.企業概要 11 2-2-1.企業概要 12 2-2-2.企業のあゆみ 12 (1)日本テレビ 13 (2)TBS 13 (3)フジテレビ 14 (4)テレビ朝日 15 3.経営戦略分析 16 3-1.財務分析 16 3-1-1.成長性分析 16 3-1-2.収益性分析 24 3-1-3.安全性分析 47 3-1-4.キャッシュフロー分析 54 3-2.企業分析 59 3-2-1.企業の特徴と経営戦略 59 (1)日本テレビ 59 (2)TBS 61 (3)フジテレビ 62 (4)テレビ朝日 64 4.戦略課題と展望 65 4-1.戦略課題 65 (1)日本テレビ 65 (2)TBS 66 (3)フジテレビ 66 (4)日本テレビ 67 4-2. 展望 .67 5.終わりに 67 参考資料 69

放送業界~日テレ・TBS・フジテレビ・テレ朝~ (池田・中井・中村)
3
参考文献 83

放送業界~日テレ・TBS・フジテレビ・テレ朝~ (池田・中井・中村)
4
1.はじめに
(中村圭介)
1990 年代以降、インターネットや携帯電話の普及に伴い、情報社会や情報化社会という
言葉が広く用いられるようになってきた。財団法人インターネット協会の調査では、2006年 2 月までのインターネットの世帯普及率は 57.3%となっており、新たなメディアである
インターネットは人々の生活にしっかりと根づいてきている。 この時代の変化は、最大最強のメディアと呼ばれているテレビを介して情報発信を行っ
ている放送業界に、どのような影響を与えているのだろうか。CM という広告収入を収入の
主軸としている放送業界にとって、新たなメディアの登場により懸念される視聴者の「テ
レビ離れ」は、深刻なダメージを与えているに違いない。また、2006 年に起きたライブド
ア買収事件、楽天買収事件や、2011 年に開始される地上デジタル放送など、放送業界の企
業態勢や経営方針に大きな影響を与える変化が起きてきている。 このような大きな転換期にさしかかった放送業界は、今後どのように事業を展開してい
き、私たち視聴者にどのようなサービスを提供していくのだろうか。 本論文では、業界売上高 1、2、3、4 位である、フジテレビ、日本テレビ、TBS、テレビ
朝日の 4 社を取り上げる。業界 1 位のフジテレビは、非常にバランスの良い事業展開を行
っており、視聴率、売上高、利益を見てもこれといった「スキ」がなく、放送業界のリー
ディングカンパニーといえる。業界 2 位である日本テレビは、長年、視聴率トップの座に
君臨していたが、近年は視聴率低下に伴い、業績低迷という状況にある。業界 3 位の BS は
ドラマと報道の二枚看板で「民放の雄」と呼ばれた時代もあるが、80 年代以降は万年 3 位
という状況にある。業界 4 位のテレビ朝日は、近年、深夜のバラエティ番組や、スポーツ
中継の好調により、視聴率を順調に伸ばしている。 業界概要では放送業界の現状と動向を明らかにし、企業概要では取り上げる企業の検討
と、特徴を比較していく。そして財務分析では、財務諸表を基に、4 社の強み、弱みを見て
いく。また、財務分析から見えてくる各社の問題点を、業界動向と 4 社の経営戦略を比較
することで明らかにし、今後の経営戦略課題と展望の提案を行う。

放送業界~日テレ・TBS・フジテレビ・テレ朝~ (池田・中井・中村)
5
2.業界及び企業の概要
2-1.業界概要
(中村圭介)
2-1-1.放送事業とは
放送とは、公衆に向けて音声や映像などの情報を電気通信技術を用いて送信することで
ある。つまり、ラジオやテレビを通して情報を発信するということである。これらのメデ
ィアを扱うことは、新聞・雑誌などの他のメディアを扱うことと比較すると、大きな違い
がある。 その違いの 1 つ目は、「電波の有限性」(西正,『図解放送業界ハンドブック』,東洋経済
新報社,1998 年,16 頁)が挙げられる。他メディアとは違い、放送を行う場合は、国ごと
に利用できる電波の周波数が限られているため、日本国内の放送事業者は限られてしまう。 2 つ目は他メディアよりも高い「倫理性」「公共性」が必要とされることである。放送は、
音声・映像で情報を発信するため、視聴者に対して高い影響力と即効性を持ち合わせてい
る。他メディアと比較しても、国民の思想・世論・人格形成などへの影響力が強いとされ
ている。そのため、放送事業者は高い「倫理性」「公共性」が必要になる。 このように、放送事業は他メディアと比較し特殊なメディアを取り扱う事業のため、総
務省(旧郵政省)が規制する許認可事業となっている。規制されていることで、放送事業
に誰もが自由に参入できないようになっているため、掟破りの破壊的な事業者の参入もな
く波風立たない静かな業界であるといえる。
2-1-2.経営基盤と収入形態
次に、放送事業の経営基盤と収入形態について説明をする。 まず、放送事業には、受信料収入、視聴料収入、広告収入という、3 つの経営基盤がある。
受信料収入とは NHK が行っている経営方法で、視聴料収入はケーブルテレビや衛星放送な
どが行っている経営方法である。いずれも視聴者との契約数が重要となってくる経営方法
である。それに対し広告収入は、民間放送局(以下、民放局)が行っている経営方法で、
企業との契約数が重要となってくる。 本論文では、民放局を取り上げるため、民放局の収入形態の仕組みについて説明をする
こととする。 民放局の収入形態は大きく分けて放送関連事業収入と、その他の事業収入の 2 つに分類
することができる。 放送関連事業収入というのは、民放局の収入の主軸である企業からの広告収入と、番組
販売収入である。広告収入とは、民放局の持つ放送時間を企業に CM という形で売ること

放送業界~日テレ・TBS・フジテレビ・テレ朝~ (池田・中井・中村)
6
で得られる収入である。番組販売収入とは、企画制作した番組を他局に販売することで得
られる収入のことである。これらの放送関連事業、特に広告収入が民放局の売上全体の約
70~80%を占めている。 このように放送業界で重要視されている広告収入を増やしていくことが、これまでの各
民放局の動きであった。 しかし、近年その他の事業収入も重要視されるようになってきている。その他の事業収
入は、ビデオ・DVD 販売やイベント開催、映画制作などの収入が含まれている。
2-1-3.広告収入の仕組み
ここでは、テレビ広告の種類と、大半を占める広告収入と視聴率の関係について述べる。
(1) テレビ広告の種類
テレビ広告はタイム(番組 CM)とスポット CM に大別される。 タイム CM(番組 CM)とは、番組枠と一体のものとして扱われるコマーシャル枠、およ
びその枠内で流されるコマーシャルのことである。タイム CM は「番組が分かっているた
め、視聴者層も大体分かるため、その層を狙っての広告を打つことができる」「提供スポン
サーとして番組内容に対して発言権 CM を持つ場合がある」「番組の前後に提供スポンサー
の紹介枠があり、15 秒単位で流れる CM 以外にも企業名などの露出効果がある」などのメ
リットがある。(フリー百科事典『ウィキペディア』http://ja.wikipedia.org/wiki/、2007 年
10 月 10 日)このタイム CM の購入は、原則として、最低 30 秒単位で、契約は 4 月から 9月または 10 月から 3 月の半年間(2 クール)が基本になる。 タイム CM を出稿する場合、スポンサーは番組料金として、電波料、制作費、ネット費
の 3 種類の費用を支払う。電波料とは、放送局が放送時間の一部を広告主に提供し、その
見返りとして得る料金、つまり、放送料である。制作費は提供する番組そのものを制作す
るのにかかる費用で、ネット費はキー局で制作した番組を他局に送り出す際の回線使用料
である。放送局ではこの 3 種類の料金が、タイム CM の収入となる。(中野明 「最新放送
業界の動向とカラクリがよ~くわかる本」日経印刷株式会社) スポット CM とは、テレビやラジオで番組や時間帯の指定なしに放送されるコマーシャ
ルのことである。スポット CM には、番組と番組の間に放送されるステーションブレイク
と、番組の時間内にタイム CM に紛れて放送されるパーティシペーション(PT)がある。
スポット CM の契約では広告主と放送局の間で、番組や時間帯は指定せずに一定期間内に
指定した本数を放送することを契約する。 (フリー百科事典『ウィキペディア』http://ja.wikipedia.org/wiki/、2007 年 10 月 10 日) 広告主は、ビデオリサーチが発行する「テレビ視聴率週報」に掲載される前 4 週分の同じ

放送業界~日テレ・TBS・フジテレビ・テレ朝~ (池田・中井・中村)
7
時間帯の視聴率である前 4 週平均視聴率を、スポット CM の発注のベースとしている。(中
野明 「最新放送業界の動向とカラクリがよ~くわかる本」日経印刷株式会社) このように、タイム CM では時間帯や番組が分かり、ターゲットである視聴者も特定で
きるが、スポット CM ではいつ CM が流れるかも分からない。そのためタイム CM に比べ
てスポット CM は 1 本あたりの単価が格安に設定されている。 しかし、放送局はこれらの CM の収入がすべて利益になるわけではない。なぜなら、放
送局とスポンサーとの価格交渉は通常、広告代理店経由で行われているため、放送局は広
告代理店に対し、CM 収入の一部を料率に従って代理店手数料として支払っているからであ
る。つまり、放送局の CM の利益は広告収入から代理店手数料を差し引いたものになるの
である。 この料率は、タイム CM とスポット CM では異なる。タイム CM は電波料として入る放
送料収入の 20%および、番組収入としての制作費とネット費の 10%あたりを広告代理店に
支払う。一方、スポット CM は電波料しかかからない。そのため電波料として入る放送料
収入の 20%を支払っている。また、料率は視聴率により変動する。高い視聴率であれば、
料率が低くなり利益が多くなる。そのため、放送局は視聴率のとれる番組を制作しようと
するのである。 では、タイム CM とスポット CM ではどちらの利益率が高いのかを考える。
まず、タイム CM では、スポンサーから電波料、制作費、ネット費を支払われる。そこ
から広告代理店に手数料を支払う。それに加え、スポンサーから集めた電波料や制作費は
番組制作費に回されるため、利益として残るものは少ない。 一方、スポット CM では、番組制作に費用がかからない。そのためスポット CM の収入
の 20%程度を広告代理店に支払い、残ったものは放送局の利益となる。 したがって、タイム CM よりもスポット CM の利益率の方が高いと言える。テレビ局は
タイム CM で得る番組制作費で視聴率が取れる番組を作り、それを「広告塔」としてスポ
ット広告を呼び利益率を上げていくというビジネスモデルを作り上げたのである。(週刊ダ
イヤモンド 2007 年 6 月 2 日 「テレビ局崩壊」)
(2) 視聴率と広告費の関係
まず、視聴率は何を意味し、何を表す指標なのかということを説明する。 視聴率とはあるテレビ番組を放送地区内の住民の何%が視聴したかを表す推定値である。
そして、視聴率の調査方法には、放送地区内の何%の世帯がテレビ番組を見ているかとい
う世帯視聴率と、ある年齢や性別などで括られたグループの中で、何%の人がテレビ番組
を見ているかという個人視聴率の 2 つがある。一般的に視聴率と呼ばれているのは、前者
の世帯視聴率である。 現在日本では、民間調査会社のビデオリサーチ(VR)と NHK が定期的に視聴率調査を
行っている。 視聴率はあくまで推定値なので、番組やCMそのものの価値を表すものとは言えないが、

放送業界~日テレ・TBS・フジテレビ・テレ朝~ (池田・中井・中村)
8
はっきりと数字で表れる視聴者からの評価であるためテレビ局は重要視している。 では、次に、視聴率がどのように広告費に反映するのかを説明する。 CM を放送するために広告主が支払う費用には、番組・CM 制作費と媒体費(電波料)の
2 つがある。タイム広告の場合は、番組制作費、CM 制作費、電波料の支払いが必要だが、
スポット広告においては、CM 制作費と電波料の支払いとなる。通常は、制作費よりも電波
料のほうが高い。 電波料金が決定されるときに基準となるのが、GRP(Gross Rating Point)である。これは、
CM を流す時間帯の視聴率を累計したもので、延べ視聴率とも呼ばれている。 例えば、全日平均視聴率 10%のテレビ局に 100 本のスポット CM を流すとすると
1,000GRP となる。この数字は簡単に言うと、一人 10 回は CM を見てくれるということに
なる。もし仮に、全日平均視聴率 5%のテレビ局に 1,000GRP を要求するとなると、200 本
のスポット CM を流さなくてはならない。また、CM は 1 回見ただけでは人々の記憶に残
らないため、最低でも 6 回は見られるのが望ましいとされている。つまり GRP にすると
600GRP ということになる。サントリーやコカコーラなどの有名な CM になると
10,000GRP は超えているといわれている。 このように GRP が高ければ広告効果は高くなる。そして、一日の CM 放送時間には限り
があるため、ただ放送本数を多くするのにも限度がある。高い GRP を望むのであればやは
り、高い視聴率が必要となる。高い視聴率が見込めるテレビ局であれば、GRP も高くなり、
広告効果も高くなるため、CM 枠の単価は高くなると言える。
放送業界の仕組みが分かったところで、放送業界はどのような状況にあるのか明らかに
する。
2-1-4.放送業界の現状
【図 2-1-1】
放送業界平均 成長傾向
0
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
300,000(百万円)
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
(百万円)
総資本 267,094 245,207 254,260 263,086 278,919
売上高 195,916 177,049 179,835 190,459 204,673
営業利益 20,883 12,228 14,446 15,162 14,683
経常利益 21,073 12,471 14,551 15,444 14,712
平成13年度 平成14年度 平成15年度 平成16年度 平成17年度

放送業界~日テレ・TBS・フジテレビ・テレ朝~ (池田・中井・中村)
9
【図 2-1-1】は放送業界の業界平均を表したものである。平成 13 年度から平成 14 年にか
けてすべての項目が大きく減少している。そして、平成 15 年度以降は売上高、総資本は増
加しているものの、営業利益、経常利益が伸び悩んでいる。つまり、放送業界の現状を簡
単に言ってみるならば、雲行きが怪しい状態といえる。 次に、日本の年度別テレビ広告費の推移と業界平均を比較してみる。
【図 2-1-2】
【図 2-1-2】は日本の年度別テレビ広告費の推移を表したものである。【図 2-1-2】と【図
2-1-1】の業界平均の推移とを比較してみると、平成 14 年度のテレビ広告費の減少と、売上
高と営業利益、経常利益が減少していることが共通している。テレビ広告費が平成 14 年度
に減少した大きな要因は、日本経済の景気後退感が広がっていく中で、多くの企業が広告
費を抑制したためである。その影響を受け、放送業界全体の業績が下がったものと考えら
れる。また、業界平均の売上高の約 70~80%をテレビ広告費が占めていることから、放送
業界が広告収入に依存していることがよく分かる。 さらに、平成 14 年度以降、広告費が停滞気味であることからテレビ広告収入が伸び悩ん
でいることが分かる。つまり、放送業界は広告収入の頭打ち状態にあると言える。 【図 2-1-3】
売上高総利益率
31.00%
32.00%
33.00%
34.00%
35.00%
36.00%
37.00%
(%)
売上高総利益率 36.26% 34.45% 33.76% 33.82% 32.91%
平成13年度 平成14年度 平成15年度 平成16年度 平成17年度
日本の年度別テレビ広告費(電通調べ)
1,850
1,900
1,950
2,000
2,050
2,100
(十億円)
テレビ広告費 2,068 1,935 1,948 2,044 2,041 2,016
平成13年度
平成14年度
平成15年度
平成16年度
平成17年度
平成18年

放送業界~日テレ・TBS・フジテレビ・テレ朝~ (池田・中井・中村)
10
【図 2-1-3】は業界平均の売上高総利益率の推移を表したものである。このグラフを見て
みると、年々数値は下がっている。これは、売上原価が増加していることを意味する。こ
の影響を受け、平成 15 年度以降の業界の営業・経常利益が伸び悩んでいることが分かる。 では、売上原価の増加は何を意味しているのだろうか。放送業界の売上原価は番組制作
費を指している。このことから、業界全体の動きとして、番組制作力を向上させる動きが
見えてくる。なぜ、番組制作力を向上させなければならないのか。それはブロードバンド
の急激な普及によって、本格的なネット映像配信時代を迎え、「放送と通信の融合」が現実
となってきたことが原因だと考えられる。通信事業者は番組を配信する「伝送路=コンテ
ナ」は持っているものの、「番組=コンテンツ」をつくる能力は持ち合わせていない。そこ
で、多くの制作会社を抱えているテレビ局は、番組制作力を向上させることで、より多く
の、より質の良い番組を制作し提供していくことが重要となってきた。そのため番組制作
費が年々増加してきているのだ。 さらにブロードバンドの普及は「放送と通信の融合」の実現だけではなく、インターネ
ット利用者を普及させ、視聴者の「テレビ離れ」という現象も引き起こし始めている。そ れを裏付けるデータが【図 2-1-4】である。 【図 2-1-4】
(ネットレイティングス・データクロニクル 2006
http://csp.netratings.co.jp/nnr/PDF/Newsrelease03122007_J.pdf) 【図 2-1-4】はインターネット人口と総利用時間の推移を表したものである。2000 年 4
月のインターネット利用者は 852 万 8 千人で、月間での一人あたりのインターネット利用
時間は 6 時間 54 分となっている。それが、2007 年 1 月になると、インターネット利用者
は 4461 万 9 千人、月間での一人あたりのインターネット利用時間は 17 時間 28 分と急激
な増加を見せている。 この状況は放送業界にとって大きなダメージとなる可能性がある。人々がテレビをあま
り見なくなる「テレビ離れ」という現象が起きることで、企業はテレビ CM に広告費を投
入しなくなり、インターネット広告などの他のメディアへの広告費の投入をする傾向にな

放送業界~日テレ・TBS・フジテレビ・テレ朝~ (池田・中井・中村)
11
ってきている。つまり、放送業界の収入のメインである広告収入が期待できなくなってき
ているということである。 この「放送と通信の融合」の動きが急速に広がったのは、2005 年に起きたライブドア買
収事件と、楽天買収事件によるものだ。 ライブドア買収事件とは、ライブドアが、2005 年 2 月からフジテレビを実質的に支配す
るため、フジテレビの筆頭株主に当たるニッポン放送の株を大量に取得することで、フジ
テレビの株をも手に入れようとした事件である。ライブドアは、フジテレビとニッポン放
送の資本のねじれに目をつけ、フジテレビの持つコンテンツを自社の事業に転用しようと
考えていたのである。しかし、ライブドアとフジテレビは業務提携することとなり、ニッ
ポン放送はフジテレビの完全子会社となった。 ネット企業が放送局に「融合」を迫る動きは、今まで許認可規制という大きな壁で守ら
れていた放送業界にとって、他業界、外部からの刺激に弱いという、企業として軟弱体質
にあることが露呈した。これらの事件から、放送業界は規制に守られているからといって 安閑としていられず、今後は各放送局ともに、グループ連携を強化することで企業として
の土台作りを行っていくことが必要とされる。
業界の現状を見てきたところで、3 つのキーワードが明らかとなり、今後、放送業界が力
を入れていかなければならないひとつの課題が見えてきた。 1 つ目は「広告収入の頭打ち」である。放送業界の収入の主軸である広告収入は、今後、
急激な伸びを期待することが難しい状態である。2 つ目は「放送と通信の融合」である。「放
送と通信の融合」という動きを止めることは難しく、各放送局はネット事業の展開や、コ
ンテンツのネットへの 2 次利用などに力を入れていくことが重要となってきている。3 つ目
は「グループ企業との連携の見直し」である。放送業界の許認可規制という城壁に甘えず、
フジテレビのように資本のねじれの改善など、グループ企業との連携の見直しをしていく
ことが重要である。
これらのキーワードから、放送業界は放送外事業の拡大が重要になってくる!という課
題が見えてきた。
次の章では大きな転換期にさしかかった放送業界の中で、各企業の業界内におけるポジ
ションがどう変化しているのか。そして、取り上げる企業の特徴を詳しく見ていく。
2-2.企業概要
(池田泰輔)
ここでは、それぞれの企業の概要とこれまでの歩みをみていき、比較していく。

放送業界~日テレ・TBS・フジテレビ・テレ朝~ (池田・中井・中村)
12
2-2-1.企業概要
取り上げる4社の事業概要を比較していく。
(平成 19 年 3 月 31 日現在)
会社名 日本テレビ 株式会社 株式会社 株式会社 放送網株式会社 東京放送 フジテレビジョン テレビ朝日
通称 日テレ TBS フジテレビ テレ朝 創立 1952 年 10 月 28 日 1951 年 5 月 10 日 1957 年 11 月 18 日 1957 年 11 月 1 日 開局 1953 年 8 月 28 日 1955 年 4 月 1 日 1959 年 3 月 1 日 1959 年 2 月 1 日
資本金 185 億 7,500 万円 546 億 8,500 万円 1,462 億 35 万円 366 億 4,280 万円 売上高 3,436 億 5,100 万円 3,187 億 0,000 万円 5,826 億 6,000 万円 2,493 億 8,300 万円
社員 2,886 人 3,103 人 4,251 人 3,052 人 事業内容
放送法によるテレビジョンの放送事業、番組の制作・販売、出版物の発行・販売、文化事業、そ
の他一切の事業 売上構成比 放送事業 78% 放送事業 82% 放送事業 62% 放送事業 85%
文化事業 18% 不動産事業 2% 放送関連事業 8% 音楽出版事業 4% その他の事業 4% その他の事業 16% 通信販売事業 10% その他の事業 11% 映像音楽事業 11% その他の事業 9%
取り上げる企業は日本テレビ、TBS、フジテレビ、テレビ朝日の 4 社である。開局の年
を比較すると日本テレビが一番早く、民放初のテレビ局であることが分かる。フジテレビ
よりも先に開局したテレビ朝日だが、教育専門局としてスタートしたため他の民放とは条
件が異なっていた。他の民放局は総合番組局として位置づけられており、テレビ朝日は 1973年に総合番組局として再スタートを切った。 売上高では業界 1 位のフジテレビが他 3 社を大きく引き離しており、安定した事業展開
を行っている。業界概要でも触れたが、今後は放送外事業の収入をいかに拡大していくか
が重要になると述べた。売上構成比に注目すると、放送事業の割合が他社よりも小さい値
を示しており、また放送事業以外の事業の展開を行っていることが分かる。つまり、フジ
テレビは業界の動向を汲み取った動きをしていると考えられる。 売上構成比について見てみると、日本テレビの中に文化事業がある。これは主にイベン
ト開催や映画制作、DVD 販売などを行っている。その一方で、TBS やテレビ朝日ではこの
分野をその他の事業として報告している。
2-2-2.企業のあゆみ
ここでは企業の歩みを見ることで各企業のポジションの変化を見ていくこととする。

放送業界~日テレ・TBS・フジテレビ・テレ朝~ (池田・中井・中村)
13
(1) 日本テレビ
初期 日本テレビは 1951 年、当時読売新聞社長であった正力松太郎氏により設立された。民放
初として開局されたが、開局当初はテレビの無い家庭がほとんどであった。そのため、首
都圏の主要箇所に街頭テレビを設置するなどして、テレビ普及に努めた。1953 年の放送開
始時は、プロ野球やプロレス中継などのスポーツ番組や「なんでもやりまショー」などの
バラエティ番組が強みであった。 中期 ~成長期~ 1966 年には日本ニュースネットワーク(NNN)を発足させ、強力なネットワークの礎を
築いた。しかし、強みであるプロ野球中継(巨人戦)は、シーズンオフの時期になると番
組編成に苦戦を強いられるという問題があった。この問題は帯番組に力を入れることで解
決を図った。朝の「ズームイン朝」(現・ズームイン!SUPER)、昼の「おもいっきりテレ
ビ」、夕方の「ニュースプラス1」(現・NNN News リアルタイム)、そして夜の「NNNきょうの出来事」(現・NEWS ZERO)などの番組である。これらの番組は他局に匹敵ない
し圧倒する視聴率を獲得した。 ~黄金期~ 1994 年放送開始のゴールデン番組である「電波少年」に代表されるバラエティ番組の大
ブレイクや人気の巨人戦中継などにより、日本テレビの勢いは次第に強まっていった。1994年から 2002 年に 9 年連続「年度視聴率四冠王」を達成した。この記録は民放最高記録とな
り、一時代を築き君臨し続けた。 現在 ~衰退期~
2003 年度の視聴率買収事件以降、視聴率が低迷している。今まで人気のあった巨人戦の 視聴率も不振に陥ってしまったため、視聴率四冠王の座を再びフジテレビに明け渡すこと になった。この状況を打開するために、人気番組の打ち切りを決定し、タイムテーブルを
改善した。しかし、その後の番組は必ずしも順調と言えず、未だ苦戦を強いられている。
(2) TBS 初期 ~成長期~ TBS は民放の中で、唯一ラジオ・テレビ両方の放送局を持つ兼営局としてスタートした。
ラジオはテレビに先行して、1951 年に「ラジオ東京」として開局した。テレビの開局は 1955年である。

放送業界~日テレ・TBS・フジテレビ・テレ朝~ (池田・中井・中村)
14
1960 年から 1970 年代にかけて、ドラマ・バラエティ・報道の各分野で高く評価され「民
放の NHK」「ドラマの TBS」「報道の TBS」と称されるほどだった。報道に関しては、JNN協定を結びネットワークを確立させ、ニュースの正確性・速報性を発揮していた。JNN の
テレビニュースネットワークは民放の中で一番初めに誕生した。 中期 ~衰退期~
1980 年代初めにフジテレビに視聴率トップの座を明け渡して以来、低迷状態に陥り、近
年では万年 3 位の座に落ち着いている。1996 年に発覚した「TBS ビデオ事件」をはじめと
した不祥事が相次ぎ、TBS の報道倫理・報道姿勢を厳しく批判され、今まで築き上げてき
た報道の自信や信頼を失うこととなった。 現在 ~革新期~ 近年では 2000 年 4 月以降、他社に先駆けて分社化を断行した。制作部門を 3 社(エンタ
テイメント・ライブ・スポーツ)に分け、2001 年 10 月にはラジオ部門を分割させた。こ
のラジオ部門の分割により、TBS は兼営局からテレビ単営局となった。2004 年には分社化
した制作部門 3 社を統合し、テレビ事業全般を行う子会社「TBS テレビ」を発足させた。
(3) フジテレビ
初期 1957 年 11 月に、「株式会社富士テレビジョン」として設立された。翌年の 1958 年に、
現在の会社名に変更された。1959 年に本社ビルを完成させ、同年 3 月 1 日に放送を開始し
た。 中期 ~成長期~ 視聴率が低迷していた 1970 年代を経て、1981 年にそれまでの「母と子のフジテレビ」
から、「楽しくなければテレビじゃない」というキャッチフレーズを打ち出した。面白い番
組・視聴者の笑いを取れる番組を生み出そうという意識改革のスローガンであった。そこ
から「THE MANZAI」「オレたちひょうきん族」「笑っていいとも!」など数々の人気番組
が生まれていった。この番組編成を「軽チャー路線」と評された。 その結果バラエティ番組中心の編成は結果として視聴者の支持を集め、1982 年に「年間
視聴率三冠王」を獲得し、その後「三冠王」は 12 年間続いた。 ~衰退期~ 1993 年夏頃から「三冠王」のうちのいくつかをバラエティや巨人戦中継などの人気番組を

放送業界~日テレ・TBS・フジテレビ・テレ朝~ (池田・中井・中村)
15
持つ日本テレビに明け渡すようになってくると、その勢いも次第に衰えていった。 現在 ~成長期~
2003 年度においてはプライムタイム(19 時~23 時の時間帯)の視聴率が日本テレビを
上回った。この結果 2004 年には「三冠」を日本テレビから奪還し衰退期から脱した。2004年度においては、「四冠」も獲得した。
2004 年度からはお笑い系のバラエティ番組だけでなく、「IQ サプリ」や「タモリのジャ
ポニカロゴス」、「熱血!平成教育学院」などの教養系なバラエティ番組などを多く制作し始
めた。このような番組でも高い視聴率の獲得に成功している。
(4) テレビ朝日
初期 すでに民放テレビは 2 社開局していたため、テレビ朝日は教育用に開局するという政策
の下、1959 年に、「日本教育テレビ」として設立された。そのため放送内容は、教育・教養
番組を 80%以上、報道番組と広告については若干に限るという厳しい条件下のスタートで
あった。この CM 放送が限定されてしまう経営苦況は 1973 年の総合番組局になるまで続い
た。総合番組局へと移行した際に、社名から教育の文字を外し「全国朝日放送」、略称をテ
レビ朝日として再出発をした。
中期 映画会社の東映が経営に携わったこともあり、その技術を生かしてスタートさせた「日
曜洋画劇場」(1966 年~)は現在も続く長寿番組となり、民放の映画番組の原型となった。
また、ニュース番組を朝の時間帯に編成し、主婦層の視聴者を獲得したことで他の放送局
を刺激した。そのため、現在の朝は他の民放局もニュース番組を編成している。 このような時代を先取った番組編成や番組作りが可能であるのにも関わらず、「万年視聴
率 4 位」、「振り向けばテレビ東京」と視聴率の低い局として業界 4 位に留まっていた。 現在 ~成長期~ 「スーパーJ チャンネル」「報道ステーション」に代表されるニュース番組や「朝まで生
テレビ!」「サンデープロジェクト」などの討論番組の制作を得意としており、報道に強い
局としてのイメージ作りを図っている。 また、2005 年度にはプライムタイムの視聴率が開局以来初の 2 位にとなり、上向きの兆
しを見せている。

放送業界~日テレ・TBS・フジテレビ・テレ朝~ (池田・中井・中村)
16
3.経営戦略分析
この章では、企業が公表している財務諸表を基に、財務分析を行い、その後、各企業が
とっている経営戦略を分析していく。企業の分析では、ひとつの側面からの分析では偏り
が生じるため、成長性、収益性、安全性、キャッシュフローの 4 つの観点から分析を行う。
3-1.財務分析
財務分析では、まず各企業の傾向を見るため、売上高や総資本、経常利益、営業利益に
焦点を当て、各社の成長性を分析する。次に、企業の存続や発展には欠かせない収益力に
焦点を当て、各社の収益性を分析する。これらの分析で、成長性や収益性が優れていると
判断出来る企業でも倒産の可能性がある場合がある。そこで、企業の借金に対する返済能
力を判断するために、各社の安全性を分析する。以上の 3 つの分析を終えた後、現金の流
れを見るキャッシュフロー分析に移る。なお、図では平成 13 年度から平成 18 年度までの
データを用いる。業界平均は平成 18 年度のデータが発表されていないため、空白とする。
3-1-1. 成長性分析
(中村圭介) ここでは、視聴率、総資本、売上高、利益の順に成長傾向を比較、分析する。
【図 3-1-1】
【図 3-1-1】は各社のプライムタイム(19 時~23 時)年間平均視聴率の推移を年度別に
表したものである。日本テレビ、TBS ともに視聴率が下降している。それに対して、フジ
テレビは上昇傾向にあり、テレビ朝日も平成 17 年度までは大きく成長している。視聴率の
変動は、番組の編成の仕方や、視聴者に好まれ支持される番組の内容かによって大きく左
各社プライムタイム視聴率 年度推移
11.0
11.5
12.0
12.5
13.0
13.5
14.0
14.5
15.0
15.5
日本テレビ 15.2 14.9 13.9 13.5 12.9 12.2
TBS 13.9 13.3 12.5 12.9 12.8 12.6
フジテレビ 14.1 13.6 14.2 14.0 14.5 14.3
テレビ朝日 11.4 11.6 12.1 12.3 13.2 12.2
平成13年度 平成14年度 平成15年度 平成16年度 平成17年度 平成18年度
(%)

放送業界~日テレ・TBS・フジテレビ・テレ朝~ (池田・中井・中村)
17
右される。 フジテレビはバラエティを中心とした番組編成を行い高い視聴率を維持している。日本
テレビの視聴率下降の大きな要因となったのは、2003 年 10 月に起こった視聴率買収事件
をきっかけに、日本テレビの信頼性を失ったためであると考えられる。テレビ朝日の視聴
率の上昇の要因は、バラエティ番組が好調であったことから視聴率を伸ばしていった。TBSの視聴率低迷の原因になっているのが、放送倫理に関する不祥事によるものである。 視聴率は広告収入において重要になってくるため、視聴率の推移を把握しながら、成長
性を見ていくこととする。 【図 3-1-2】
各社総資本の推移
0
100,000
200,000
300,000
400,000
500,000
600,000
700,000
800,000(百万円)
日本テレビ 443,798 476,634 513,429 493,557 519,951 529,265
TBS 522,129 443,778 484,605 506,125 555,271 567,722
フジテレビ 485,594 480,913 625,786 681,190 692,357 731,496
テレビ朝日 291,132 294,047 288,967 297,544 316,079 314,466
平成13年度 平成14年度 平成15年度 平成16年度 平成17年度 平成18年度
【図 3-1-2】は、平成 13 年度から平成 18 年度までの、各社の総資本の推移を表したもの
である。日本テレビ、TBS、テレビ朝日の推移は比較的横ばいである中、フジテレビは、
平成 15 年度から他社に比べ総資本が増加していることが分かる。フジテレビは平成 15 年
度に T/Q MUSIC と windswept holdings という音楽事業に関連する連結子会社の増加を
したため、有価証券、投資有価証券合わせて 108,142 百万円の増加と、ニッポン放送株の
取得の際に発生した、信託受益権の 59,781 百万円の増加に伴い総資本も増加している。平
成 16 年度も音楽事業に関する連結子会社を 4 社増加したため、総資本も増加している。平
成 17 年度には、フジテレビの筆頭株主であった株式会社ニッポン放送を、ライブドア買収
事件をきっかけに完全子会社化したことに伴い総資本が増加となった。また、平成 17年度、
平成 18 年度は、平成 19 年 9 月に完成した新スタジオ「湾岸スタジオ」建設に伴う建物仮
勘定の増加も総資本増加の要因である。 総資本の推移から、フジテレビは日本テレビ、TBS、テレビ朝日と比べ子会社を増やし、
事業を拡大していることが分かる。 【図 3-1-3】

放送業界~日テレ・TBS・フジテレビ・テレ朝~ (池田・中井・中村)
18
各社売上高の推移
0
100,000
200,000
300,000
400,000
500,000
600,000
700,000(百万円)
日本テレビ 358,682 336,299 328,374 357,614 346,642 343,651
TBS 291,255 294,839 295,015 301,731 306,041 318,700
フジテレビ 436,902 429,004 455,945 476,733 593,493 582,660
テレビ朝日 219,926 209,035 218,078 242,036 249,383 251,124
平成13年度 平成14年度 平成15年度 平成16年度 平成17年度 平成18年度
【図 3-1-3】は、平成 13 年度から平成 18 年度までの各社の売上高の推移を表したもので
ある。平成 13 年度から平成 18 年度まで売上高の順位は 1 位フジテレビ、2 位日本テレビ、
3 位 TBS、4 位テレビ朝日と、6 年間に亘り変動していないことが分かる。また、日本テレ
ビ、TBS、テレビ朝日の売上高の推移に比べ、フジテレビの売上高の推移は大きな成長を
見せているのがよく分かる。これは、フジテレビの広告収入だけに頼らない、広告外収入
にも力を入れている経営戦略が成功しているからだと言える。 平成 14 年度は、雇用、所得環境の悪化を背景とした個人消費の低迷により、多くの企業
が広告費を抑制したため、広告収入を軸としている放送業界の売上高にも大きく影響が出
ている。この年は、日本テレビ、フジテレビ、テレビ朝日ともに、売上高が減少している。
それに対し、TBS は売上高を増やしている。TBS の売上高増加の要因は、放送外事業の収
入である、「マッスルミュージアム」や「Dynamite!SUMMER NIGHT FEVER in 国立」
等のイベント収入によって、広告収入の減少を、その他事業の収入で補うことができたた
め全体の売上高が増加したのである。このように、広告収入は景気に左右されやすい体質
を持つため、安定した収入源を確保するために、広告外収入に力を入れていくことは重要
だということが分かる。 次に、各企業の売上高の構成を見るために、セグメント別売上高の推移で、売上高の成
長を分析することとする。

放送業界~日テレ・TBS・フジテレビ・テレ朝~ (池田・中井・中村)
19
【図 3-1-4】
日本テレビ セグメント別売上高の推移
0
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
300,000
350,000
400,000
(百万円)
その他事業 8,645 9,903 11,911 13,717 15,082 14,536
文化事業 51,452 37,645 38,859 62,103 62,474 69,411
テレビ放送事業 304,391 294,517 285,015 289,810 277,977 267,903
平成13年度 平成14年度 平成15年度 平成16年度 平成17年度 平成18年度
【図 3-1-4】は平成 13 年度から平成 18 年度までの、日本テレビのセグメント別売上高の
推移を表したものである。全体の売上高は横ばいである中、テレビ放送事業は年々減少傾
向にある。この大きな原因は視聴率の低迷である。CM 価格の判断基準となる視聴率の低迷
は、放送事業収入に大きな影響を及ぼすことが分かる。平成 13 年度にはプライムタイム年
間平均視聴率が 15.2%であったのに対して、平成 18 年度は 12.2%にまで減少しており、
毎年 0.6%の減少が続いている。そのため、テレビ放送事業の売上高が減少している。 テレビ放送事業に対して、文化事業、その他事業の売上高は増加傾向にある。文化事業
の売上高に波があるのが見て取れるが、この要因は、文化事業に含まれている映画事業の
売上高が増加しているためである。前年度と比較し増加の割合が高い年度はジブリ作品な
どのヒットが影響している。 【図 3-1-5】
TBS セグメント別売上高の推移
0
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
300,000
350,000
400,000
(百万)
映像文化事業 60,301
その他事業 28,580 37,695 40,887 46,851 49,553 1,793
不動産事業 10,636 9,311 7,570 7,365 7,517 7,394
テレビ放送事業 266,094 262,743 260,725 262,394 263,891 264,698
平成13年度 平成14年度 平成15年度 平成16年度 平成17年度 平成18年度

放送業界~日テレ・TBS・フジテレビ・テレ朝~ (池田・中井・中村)
20
【図 3-1-5】は平成 13 年度から平成 18 年度までの、TBS のセグメント別売上高の推移
を表したものである。全体の売上高は増加傾向にあり、テレビ放送事業収入は横ばいであ
り、不動産事業収入は低迷している状態にある。それに対し、その他事業収入が年々増加
している。その他事業の増加の大きな要因は、映画出資や DVD 販売などが好調だったため
である。代表的な作品は、「木更津キャッツアイ」シリーズや、「世界の中心で、愛をさけ
ぶ」、「いま、会いにゆきます」などが挙げられ、そのヒット映画の DVD 化によって得てい
る収入が大きい。また、稼働率平均 80%を越えるライブハウス「赤坂 BLITZ」(現、「横浜
BLITZ」)や、「赤坂 ACT シアター」などのイベント施設を利用したイベント事業の収入も
大きな要因である。平成 18 年度には事業体制を改め、その他事業に含まれていた、映画出
資事業、DVD 販売事業、文化事業を合わせて映像文化事業とした。 全体の売上高を伸ばしつつ、放送事業以外での収入の拡大ができている点は業界動向に
合った成長を見せていると言える。 【図 3-1-6】
フジテレビ セグメント別売上高の推移
0
100,000
200,000
300,000
400,000
500,000
600,000
700,000
(百万円)
映像音楽事業 73,566 74,330
その他事業 29,690 29,688 29,997 30,431 60,096 59,116
通信販売事業 60,395 61,504 67,107 68,366 69,739 67,321
放送関連事業 48,492 46,526 46,925 49,683 53,207 52,494
放送事業 339,965 333,729 358,056 376,039 410,003 402,789
平成13年度 平成14年度 平成15年度 平成16年度 平成17年度 平成18年度
【図 3-1-6】は平成 13 年度から平成 18 年度までの、フジテレビのセグメント別売上高の
推移を表したものである。フジテレビは各事業の収入を拡大しつつ、放送事業以外の事業
の売上高構成比率を増やしている。これは、広告収入に頼ることなく、安定した収入を維
持することができるという、フジテレビの大きな強みである。放送事業収入の増加傾向は、
プライムタイム年間平均視聴率が上昇傾向にあることが大きな要因である。また、平成 17年度にはニッポン放送を完全子会社化したことによって、放送事業に今までに無いラジオ
による収入が得られ、売上高を増加させた。そして、CD、DVD 販売などの映像音楽関係
の事業を行っているポニーキャニオンも連結子会社化できたことで、映像音楽事業が増え、
売上高増加の大きな要因となっている。 平成 18 年度には放送事業の売上高構成比は 61%と、業界で売上高トップでありながら、
業界の特徴でもあった放送事業依存体質から抜け出せている。セグメント別売上高を見る

放送業界~日テレ・TBS・フジテレビ・テレ朝~ (池田・中井・中村)
21
ことで、フジテレビの強みが見えた。 【図 3-1-7】
テレビ朝日 セグメント別売上高の推移
0
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
300,000
(百万円)
その他の事業 12,592 14,745 22,572 24,492 25,856 29,156
音楽出版事業 4,166 4,111 7,264 9,122 10,938 9,348
テレビ放送事業 208,202 195,677 196,753 215,302 220,907 221,438
平成13年度 平成14年度 平成15年度 平成16年度 平成17年度 平成18年度
【図 3-1-7】は平成 13 年度から平成 18 年度までの、テレビ朝日のセグメント別売上高の
推移を表したものである。全体の売上高は増加傾向にあり、その他の事業の売上高増加が
特徴的である。テレビ放送事業の平成 16 年度からの増加傾向は、プライムタイム年間平均
視聴率の上昇による影響が大きい。 その他の事業にはビデオ・DVD 販売事業、イベント事業、映画出資事業、テレショップ
事業などがある。ビデオ・DVD 販売事業では「トリック」シリーズや、「座頭市」、「クレ
ヨンしんちゃん」シリーズ、「ドラえもん」シリーズ等の映画と DVD 販売の相乗効果によ
って収入を増加させている。イベント事業では、毎年夏に開催されるロックフェスティバ
ル「SUMMER SONIC」や、美術館展などで収入を増加させている。テレショップ事業で
は「セレクション X」や「いま得!」などのテレビショッピング番組が好調である。 また、音楽出版事業では、J-POP アーティストのケツメイシや湘南乃風、HY などの専
属アーティストが人気を博しているため堅調な成長をみせている。 セグメント別売上高の推移でから各社を比較した結果、各事業ともに大きな増加傾向を
見せているフジテレビが一番安定しており、尚且つ多角的な事業展開ができていることが
分かる。TBS とテレビ朝日も、フジテレビほどの成長はないものの、放送事業を基盤とし
た、放送事業以外の事業拡大を順調に行えている。日本テレビのみ、放送事業以外の事業
収入を増加させているのにも関わらず、放送事業の収入低迷によって全体の売上高の成長
が鈍化している状態に陥っている。 売上高の推移に差が生じているが、各社ともに、業界動向に合った広告外収入を増やし
ていく傾向が見てとれた。 次に、各社の営業利益の推移を比較していくこととする。

放送業界~日テレ・TBS・フジテレビ・テレ朝~ (池田・中井・中村)
22
【図 3-1-8】
各社営業利益の推移
0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
70,000
(百万円)
日本テレビ 63,573 47,406 35,937 34,325 28,551 30,344
TBS 31,242 24,326 25,271 22,510 16,404 25,327
フジテレビ 45,935 37,268 44,065 43,581 50,724 42,325
テレビ朝日 13,477 7,430 6,520 13,606 17,075 13,677
平成13年度 平成14年度 平成15年度 平成16年度 平成17年度 平成18年度
【図 3-1-8】は平成 13 年度から平成 18 年度までの各社の営業利益の推移を表したもので
ある。平成 13 年度から平成 14 年度にかけては日本テレビが営業利益でトップであったの
に対して、平成 15 年度にはフジテレビが営業利益でトップとなった。平成 17 年度にはテ
レビ朝日が TBS の営業利益を抜いたものの、平成 18 年度では 1 位フジテレビ、2 位日本テ
レビ、3 位 TBS、4 位テレビ朝日のという順位になっている。 まず、目につくのは平成 14 年度に各社ともに営業利益が大きく減少している点である。
この原因は、業界全体が影響を受けた企業の広告費抑制に伴う、売上高の減少によるもの
である。平成 14 年度、TBS の売上高が増加したにもかかわらず、営業利益が減少したのは、
販売費及び一般管理費に含まれている、退職給付費用が 2,077 百万円増加したことが原因
である。日本テレビの営業利益の減少要因は、平成 13 年度に上映された「千と千尋の神隠
し」の大ヒットによる反動である。また、平成 14 年度は各社ともに売上高減少を見込みな
がらも、番組制作費をうまく抑えることができず、売上高総利益率が下がってしまったこ
とも大きな原因である。 次に平成 15 年度に日本テレビが大きく営業利益を減少させた原因は、新しく汐留に建設
していた社屋が平成 16 年 2 月の竣工に伴って、水道光熱費などのランニングコストが大幅
に増加したためである。また、フジテレビは放送事業、通信販売事業の売上高が増加した
ことにより営業利益が増加したのである。それにより、日本テレビはフジテレビに営業利
益トップの座を奪われてしまう。 平成 16 年度にはテレビ朝日のみ営業利益で増加を見せている。この年度には、スペシャ
ルドラマ「弟」、スポーツ大型番組「2006FIFA ワールドカップアジア最終予選」の放送が
あり、「2006FIFA ワールドカップアジア最終予選」の「日本×北朝鮮」では、テレビ朝日
の歴代最高視聴率である 47.2%を獲得した。それにより視聴者をはじめ、広告主からも好
評で、売上高を伸ばした。それに加え番組制作費を固定し、計画的かつ効率的な予算配分
とコンテンツ開発ができたため急成長を遂げたのである。この急成長の裏にはテレビ朝日
が取り組んだ全社変革運動が考えられる。この運動は高い視聴率を獲得することで、景気
に左右されない高収益体質の企業を目指していくことを目標に掲げた運動である。それに

放送業界~日テレ・TBS・フジテレビ・テレ朝~ (池田・中井・中村)
23
対し、日本テレビ、TBS、フジテレビの営業利益の減少原因は投入した番組制作費が、売
上高に反映しなかったためである。 平成 17 年度の営業利益は、フジテレビ、テレビ朝日は増加しているが、日本テレビ、TBSは減少している。この原因は、プライムタイム年間平均視聴率の変動によるものと考えら
れる。プライムタイム年間平均視聴率を比較すると、フジテレビは 0.5%、テレビ朝日は
0.9%上昇している。それに対し、日本テレビは 0.6%、TBS は 0.1%下降している。また、
フジテレビはニッポン放送の子会社化によって売上高が増加したことから、営業利益が大
幅に増加したと考えられる。 平成 18 年度の営業利益は、平成 17 年度とは逆に、フジテレビ、テレビ朝日が減少し、
日本テレビ、TBS が増加している。この年、フジテレビの営業利益が減少したのは、映像
音楽事業以外の事業での売上高が減少した結果、全体の売上高も減少したことが大きな原
因である。また番組制作費も抑えることができなかったことも影響している。一方、テレ
ビ朝日の売上高は増加しているものの営業利益が減少している。これは、番組制作力向上
を図るため、番組制作費に費用投資した結果、売上高総利益が下がったため、営業利益も
減少したと考えられる。 日本テレビの営業利益が増加した理由は、番組制作費を中心に費用全般にわたり削減を
行ったためである。その結果、売上高は減少しているものの、前年度よりも営業利益が増
加した。TBS は、売上高、営業利益ともに増加している。売上高が増加した要因は、映像
文化事業で、「日本沈没」、「どろろ」、「木更津キャッツアイ ワールドシリーズ」などの映
画がヒットした影響が大きく、映像文化事業の売上高が増加した。また、売上原価、販売
費及び一般管理費等の費用を抑えたことで営業利益が大幅に増加した。 次に、各社の経常利益の推移を見ることとする。 【図 3-1-9】
各社経常利益の推移
0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
70,000
(百万円)
日本テレビ 62,662 46,332 36,800 35,591 30,014 34,142
TBS 29,339 23,039 23,903 21,981 15,388 26,216
フジテレビ 44,694 37,744 45,564 44,478 50,340 45,995
テレビ朝日 12,753 6,932 5,893 13,592 17,314 14,587
平成13年度 平成14年度 平成15年度 平成16年度 平成17年度 平成18年度
【図 3-1-9】は平成 13 年度から平成 18 年度までの各社の経常利益の推移を表したもので
ある。【図 3-1-8】と比較してみると、ほとんど推移の仕方、金額ともに違いが生じていな

放送業界~日テレ・TBS・フジテレビ・テレ朝~ (池田・中井・中村)
24
広告収入 総利益率
72.00%
74.00%
76.00%
78.00%
80.00%
82.00%
84.00%
日本テレビ 82.38% 82.57% 82.57% 81.70% 81.67% 81.48%
TBS 76.22% 75.77% 76.06% 76.02% 75.73% 75.90%
フジテレビ 81.28% 81.18% 81.10% 81.03% 80.70% 80.75%
テレビ朝日 81.22% 81.10% 80.84% 80.03% 80.16% 80.35%
平成13年度 平成14年度 平成15年度 平成16年度 平成17年度 平成18年度
いことが分かる。年度ごとの減少、増加の理由は、営業利益の推移の原因と同じなので、
ここでの説明は割愛することとする。
4 社の成長性を比較した結果、フジテレビが非常に優れた成長を見せていることが分かる。
フジテレビが優れた成長を遂げるための原動力は、効果的な事業拡大であると考えられる。 テレビ朝日は視聴率上昇をきっかけに、売上高、営業利益、経常利益が平成 16 年度以降、
成長傾向にあり、フジテレビに続き、4 社の中で二番目に良い成長をしている。 TBS は、売上高は 4 社の中で唯一マイナス成長することなく成長を遂げている。また、
営業利益、経常利益は平成 17 年度まで減少傾向にあるが、平成 18 年度には、営業利益で
前年度比 54%、経常利益で前年度比 70%の伸び率を見せている点から、今後の成長に期待
ができる。日本テレビは、売上高は横ばいの成長にあり、収入の柱であるテレビ放送事業
の売上高は減少傾向にある。また、平成 18 年度に営業利益は前年度比 1,793 百万円の増
加と、経常利益は前年度比 4,128 百万円の増加となっている。しかし、平成 13 年度から平
成 17 年度までのマイナス成長により、営業利益で 35,022 百万円の減少をしており、経常
利益で 32,648 百万円の減少をしているため、平成 18 年度のプラス成長だけでは、日本テ
レビに成長性があるとは考え難い。
次に、各社の収益性を詳しく分析、検討し、営業利益、経常利益の推移をさらに深く分
析する。
3-1-2.収益性分析
(中井茜) 収益性分析では、各企業の収益力、またその収益力の増減要因を明らかにし、経営戦略
の特徴について利幅と効率の 2 つの側面から指標を分解し分析を進める。 まず、放送業界の収益力の特徴を見た後で、企業の総合業績、経営効率を見るために総
資本経常利益率を用いる。次に、この総資本経常利益率を利幅を示す売上高経常利益率と
効率を示す総資本回転率の 2 つの比率に分解し、利幅と効率の側面から分析を進める。 それでは放送業界の特徴として、広告収入について見ていく。 【図 3-1-10】

放送業界~日テレ・TBS・フジテレビ・テレ朝~ (池田・中井・中村)
25
タイムCM
0
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
140,000
160,000
180,000(百万円)
日本テレビ 159,350 154,269 148,921 148,699 141,828 138,219
TBS 55,174 54,860 55,378 55,321 57,601 64,588
フジテレビ 156,834 153,751 152,262 155,946 157,682 157,666
テレビ朝日 95,096 89,448 88,720 91,717 93,932 95,444
平成13年度 平成14年度 平成15年度 平成16年度 平成17年度 平成18年度
スポットCM
0
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
140,000
160,000
(百万円)
日本テレビ 128,033 122,033 117,045 120,137 113,619 108,305
TBS 104,195 101,295 103,556 101,110 103,019 103,048
フジテレビ 125,646 121,204 124,116 140,641 138,928 136,062
テレビ朝日 89,422 83,472 84,838 98,359 100,825 99,373
平成13年度 平成14年度 平成15年度 平成16年度 平成17年度 平成18年度
【図 3-1-10】は、各企業の放送事業の中の広告収入における売上高総利益率の過去 6 年
間の推移を示したものである。業界概要で述べたように、広告収入での売上原価は広告代
理店に支払う代理店手数料だけである。そのため、広告収入の利益率は高くなる。グラフ
を見ると TBS が他社に比べて低い。これは広告収入の内訳が影響していると考えられる。
そこで、タイム CM、スポット CM に分けて売上高を比較を行う。 【図 3-1-11】
【図 3-1-12】
【図 3-1-11】【図 3-1-12】はそれぞれ各企業の過去 6 年間のタイム CM、スポット CM に
おける売上高の推移を示したものである。 日本テレビ、フジテレビ、テレビ朝日はスポット CM よりもタイム CM の売上高の方が
高いことが分かる。一方、TBS の、タイム CM の売上高はタイム CM の売上高が 1 位のフ
ジテレビと比べてみると 3 分の 1 程度である。スポット CM における売上高は 3 位であり、
1 位のフジテレビと比べても 300 億円程度の差である。利益率の高いスポット CM の売上
高が 3 位である TBS は【図 3-1-10】の広告収入の利益率を見ると、他社に比べ 5%程度低
い。これはタイム CM での収入が低いため、番組制作費を十分に得ることができない。そ
のため、TBS はタイム CM での収入の多くを費用として使用している。つまり、タイム CMでの利益が少ないため、広告収入の利益率が低いのである。

放送業界~日テレ・TBS・フジテレビ・テレ朝~ (池田・中井・中村)
26
日本テレビ
0.00%
5.00%
10.00%
15.00%
20.00%
0.000.100.200.300.400.500.600.700.800.90
(回)
総資本経常利益率 14.12% 9.72% 7.17% 7.21% 5.77% 6.45%
売上高経常利益率 17.47% 13.78% 11.21% 9.95% 8.66% 9.94%
総資本回転率 0.81 0.71 0.64 0.72 0.67 0.65
平成13年度 平成14年度 平成15年度 平成16年度 平成17年度 平成18年度
【図 3-1-10】【図 3-1-11】【図 3-1-12】より、放送業界の収益性の特徴として、放送事業
における利益率は高いということと、利益率が高いスポット CM の売上高だけが良好でも
利益率は高くならないということが挙げられる。 これを踏まえて収益性分析に移る。まず、企業ごとに総資本経常利益率、売上高経常利
益率、総資本回転率の指標を見ていくこととする。 【図 3-1-13】
【図 3-1-13】は、日本テレビの過去 6 年間の、総資本経常利益率、売上高経常利益率、総
資本回転率の推移を示したものである。左側の縦軸に総資本経常利益率、売上高経常利益
率の数値をとり、右側の縦軸に総資本回転率の数値をとる。 総資本経常利益率を見ると、年々下降傾向にある。日本テレビは視聴率の低迷に伴い、
利益率の高い広告収入が減少したため経常利益の減少しているため比率が下降傾向にある。
売上高経常利益率は平成 16 年度を除けば総資本経常利益率とほぼ同じ推移である。平成 16年度の経常利益の前年度比伸び率マイナス 3.29%に対し、総資本の前年度比伸び率がマイ
ナス 3.87%と、総資本の減少率の方が大きかったため総資本経常利益率は増加した。一方、
売上高の前年度に比べ増加となったため、売上高経常利益率は減少した。総資本回転率は
平成 18 年度を除いて、総資本経常利益率と同じ推移である。 日本テレビの収益力を見ると、売上高経常利益率、総資本回転率ともに総資本経常利益
率と異なる推移を示す年があった。それぞれ増加幅の大きい比率が総資本経常利益率に影
響していた。続いて TBS を見ていくこととする。

放送業界~日テレ・TBS・フジテレビ・テレ朝~ (池田・中井・中村)
27
TBS
0.00%
2.00%
4.00%
6.00%
8.00%
10.00%
12.00%
0.00
0.10
0.20
0.30
0.40
0.50
0.60
0.70
(回)
総資本経常利益率 5.62% 5.19% 4.93% 4.34% 2.77% 4.62%
売上高経常利益率 10.07% 7.81% 8.10% 7.28% 5.03% 8.23%
総資本回転率 0.56 0.66 0.61 0.60 0.55 0.56
平成13年度 平成14年度 平成15年度 平成16年度 平成17年度 平成18年度
フジテレビ
0.00%
2.00%
4.00%
6.00%
8.00%
10.00%
12.00%
0.000.100.200.300.400.500.600.700.800.901.00
(回)
総資本経常利益率 9.20% 7.85% 7.28% 6.53% 7.27% 6.29%
売上高経常利益率 10.23% 8.80% 9.99% 9.33% 8.48% 7.89%
総資本回転率 0.90 0.89 0.73 0.70 0.86 0.80
平成13年度 平成14年度 平成15年度 平成16年度 平成17年度 平成18年度
【図 3-1-14】
【図 3-1-14】は、TBS の過去 6 年間の、総資本経常利益率、売上高経常利益率、総資本
回転率の推移をまとめたグラフである。左側の縦軸に総資本経常利益率、売上高経常利益
率の数値をとり、右側の縦軸に総資本回転率の数値をとる。 総資本経常利益率を見ると平成 17 年度まで下降傾向にあったが、平成 18 年度に改善し
ているのが分かる。成長性で述べたように、映像文化事業が好調であったことに加え、費
用を抑えたことにより営業利益の増加に伴い経常利益が増加したためである。売上高経常
利益率は総資本経常利益率と同じ推移であるのが分かる。一方、総資本回転率の推移は総
資本経常利益率とは異なり、あまり変化がない。 TBS の収益力を見ると、総資本経常利益率には主に利幅を示す売上高経常利益率が影響
していた。続いてフジテレビを見ていくこととする。 【図 3-1-15】 【図 3-1-15】は、フジテレビの過去 6 年間の、総資本経常利益率、売上高経常利益率、
総資本回転率の推移をまとめたグラフである。左側の縦軸に総資本経常利益率、売上高経
常利益率の数値をとり、右側の縦軸に総資本回転率の数値をとる。 総資本経常利益率を見ると、下降傾向であるのが分かる。総資本は増加しているが、経
常利益にあまり変化がないためである。売上高経常利益率は平成 15 年度、平成 17 年度は

放送業界~日テレ・TBS・フジテレビ・テレ朝~ (池田・中井・中村)
28
テレビ朝日
0.00%
2.00%
4.00%
6.00%
8.00%
0.640.660.680.700.720.740.760.780.800.820.84
(回)
総資本経常利益率 4.38% 2.36% 2.04% 4.57% 5.48% 4.64%
売上高経常利益率 5.80% 3.32% 2.70% 5.62% 6.94% 5.81%
総資本回転率 0.76 0.71 0.75 0.81 0.79 0.80
平成13年度 平成14年度 平成15年度 平成16年度 平成17年度 平成18年度
総資本経常利益率と異なる推移を示している。成長性で述べたように、フジテレビは平成
15 年度に音楽事業に関する連結子会社の増加をした。その影響で総資本が 1600 億円ほど
増加したため、総資本経常利益率は下降したと考えられる。一方、売上高経常利益率が増
加したのは、平成 14 年度まであった持分法による投資損失がなくなり、利益となったこと
により、経常利益が売上高よりも増加したためである。平成 17 年度は、総資本、経常利益
の増加に比べて売上高の増加が多かったため、総資本経常利益率が増加したが、営業外費
用が多くかかったことにより、売上高経常利益率は下降している。次に総資本回転率を見
ると、総資本経常利益率の変動の幅は異なるものの、同じ推移を示している。 フジテレビの収益力を見ると、総資本経常利益率には、主に総資本回転率が影響してい
た。また変動の幅を比べてみると、売上高経常利益率も影響していると言える。続いてテ
レビ朝日を見ることとする。 【図 3-4-16】 【図 3-1-16】は、テレビ朝日の過去 6 年間の、総資本経常利益率、売上高経常利益率、
総資本回転率の推移を示したものである。左側の縦軸に総資本経常利益率、売上高経常利
益率の数値をとり、右側の縦軸に総資本回転率の数値をとる。 総資本経常利益率を見ると平成 15 年度まで下降傾向であったが、平成 16 年以降は改善
され、平成 18 年度にまた下降している。特に平成 15 年度から平成 16 年度は比率が倍以上
改善されている。これは成長性で述べたように、広告収入の増加、さらに全社変革運動に
より番組制作費を固定にすることにより、費用を抑えた結果、営業利益・経常利益が大幅
に増加したためである。売上高経常利益率は総資本経常利益率と同じ推移を示している。
一方、総資本回転率は、平成 15 年度、平成 17 年度、平成 18 年度に総資本経常利益率とは
異なる推移を示している。平成 15 年度、平成 18 年度には負債の減少により総資本が減少
したが、売上高が増加したので総資本回転率が上昇した。平成 17 年度には、売上高・総資
本ともに増加しているが、総資本の増加率の方が高かったため回転率は下降した。 テレビ朝日の収益力を見ると、総資本経常利益率には主に売上高経常利益率が影響して
いた。 今まで各企業の収益力について見てきた。日本テレビ、フジテレビの収益力は売上高経
常利益率、総資本回転率の両方に影響されていた。一方、TBS とテレビ朝日は主に売上高

放送業界~日テレ・TBS・フジテレビ・テレ朝~ (池田・中井・中村)
29
総資本経常利益率
0.00%
5.00%
10.00%
15.00%
日本テレビ 14.12% 9.72% 7.17% 7.21% 5.77% 6.45%
TBS 5.62% 5.19% 4.93% 4.34% 2.77% 4.62%
フジテレビ 9.20% 7.85% 7.28% 6.53% 7.27% 6.29%
テレビ朝日 4.38% 2.36% 2.04% 4.57% 5.48% 4.64%
業界平均 8.16% 5.00% 6.01% 5.97% 5.43%
平成13年度 平成14年度 平成15年度 平成16年度 平成17年度 平成18年度
経常利益率に影響されていた。それでは 4 社を比較しやすくするため、総資本経常利益率、
売上高経常利益率、総資本回転率の順に比率ごとに分析を進める。まず、企業の総合業績
を示す総資本経常利益率から見る。 【図 3-1-17】
【図 3-1-17】のグラフは、各企業、業界平均の総資本経常利益率の過去 6 年間の推移を
示したものである。業界平均は、東証一部に上場している放送企業の平均値である。 総資本経常利益率は、経常利益を総資本で除して、算出する。つまり、企業が持ってい
る全ての資本が、どれだけ営業活動および財務・金融活動の成果に結びついているのかを
示す指標である。この比率が高ければ高いほど収益性の高い企業だと判断される。 大きな変化はあるものの、日本テレビ、フジテレビは、業界平均をどの年度も上回って
いるため、資本の使い方がうまく、収益性が高いといえる。視聴率の良い日本テレビ、フ
ジテレビは、広告収入が多い。業界概要や【図 3-1-10】で述べたように広告収入では費用
があまりかからないため収益力が高いという特徴を持っている。そのため比率が高いと考
えられる。また、どの企業を見ても視聴率の上下に伴い比率が上下していることが分かる。
フジテレビが視聴率の変動に比べ、あまり変動していないのは、セグメント別売上高で見
たように、放送事業への依存度が低いため、視聴率の変動に影響されにくいということに
起因している。 次にこの比率を売上高経常利益率、総資本回転率の 2 つの要因に分解し、各企業の戦略
や強み、問題点などを明らかにする。1 つ目の売上高経常利益率が高いと利幅が高く、高付
加価値戦略を行っていると判断できる。一方、2 つ目の総資本回転率が高いと資本運用の効
率が良く、高効率戦略を行っていると判断できる。各比率を見た後で SPM(戦略ポジショ
ニングマップ)を用いて、相対的に各社の戦略の分析を行う。それでは売上高経常利益率
から見る。

放送業界~日テレ・TBS・フジテレビ・テレ朝~ (池田・中井・中村)
30
売上高経常利益率
2.00%4.00%6.00%8.00%
10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%20.00%
日本テレビ 17.47% 13.78% 11.21% 9.95% 8.66% 9.94%
TBS 10.07% 7.81% 8.10% 7.28% 5.03% 8.23%
フジテレビ 10.23% 8.80% 9.99% 9.33% 8.48% 7.89%
テレビ朝日 5.80% 3.32% 2.70% 5.62% 6.94% 5.81%
業界平均 10.76% 7.04% 8.09% 8.11% 7.19%
平成13年度 平成14年度 平成15年度 平成16年度 平成17年度 平成18年度
総資本回転率
0.50
0.60
0.70
0.80
0.90
1.00
日本テレビ 0.81 0.71 0.64 0.72 0.67 0.65
TBS 0.56 0.66 0.61 0.60 0.55 0.56
フジテレビ 0.90 0.89 0.73 0.70 0.86 0.80
テレビ朝日 0.76 0.71 0.75 0.81 0.79 0.80
業界平均 0.76 0.71 0.74 0.74 0.76
平成13年度 平成14年度 平成15年度 平成16年度 平成17年度 平成18年度
【図 3-1-18】
【図 3-1-18】は、各企業、業界平均の売上高経常利益率の過去 6 年間の推移を示したも
のである。業界平均は、東証一部に上場している放送企業の平均値である。 この売上高経常利益率という比率は、経常利益を売上高で除して、算出される。つまり、
事業活動全体を通じて企業が創造した「価値」を意味し、この比率が高ければ価値幅(利
幅)が高いと判断できる。 グラフを見ると、やはり業界概要で述べたように、視聴率つまり広告収入の影響が大き
く現れていることが分かる。日本テレビはこの比率が高く、利幅が高いと判断できる。視
聴率 1 位であるフジテレビが売上高経常利益率を見ると、日本テレビに次いで 2 位である。
平成 18 年度に、フジテレビは TBS に抜かれ 3 位となっている。成長性で述べたようにフ
ジテレビの平成 18 年度の放送事業の売上高構成比は 61%である。それに対し、日本テレビ
は 76%、TBS は 79%、テレビ朝日は 85%である。フジテレビは視聴率が高く広告収入は
多いものの、他の事業の売上高が他社よりも多く、全体の売上高の中に占める広告収入は
他社よりも少なくなる。そのため、この売上高経常利益率は低下しているのだと考えられ
る。 それでは、利幅を示す、売上高経常利益率を見てきたところで、効率を示す総資本回転
率を見る。 【図 3-1-19】

放送業界~日テレ・TBS・フジテレビ・テレ朝~ (池田・中井・中村)
31
【図 3-1-19】は、各企業、業界平均の総資本回転率の過去 6 年間の推移を示したもので
ある。業界平均は、東証一部に上場している放送企業の平均値である。 この総資本回転率という比率は売上高を総資本で除して、算出される。つまり、企業が
調達したすべての資本がどれだけ売上高に結びついているかを示す比率で、「効率」を意味
する。この比率が高ければ、少ない資本で多くの利益を上げており、効率が良いと判断で
きる。 グラフを見ると、TBS の比率が低いのが目立つ。先ほど成長性分析で述べたように、TBSは不動産事業を行っているため売上高に対し、総資本が他社よりも多い。しかし、視聴率
が悪いため広告収入が少ないことに加え、建設中の建物が多く、資本は増加しているもの
の売上高には結びついていないため、比率が低いと考えられる。 ここまで収益力について総資本経常利益率を見た後で、売上高経常利益率と総資本回転
率に分解し分析をしてきた。日本テレビは視聴率の高さを強みとし、利幅を上げ、収益力
を上げていたが年々下降傾向にある。TBS は、放送事業に依存しているため利幅は大きい
が、不動産事業の展開により総資本回転率が抑制され、収益力を下げていた。フジテレビ
は、多事業の展開により利幅が抑制されているものの、効率を上げ、収益力を上げていた。
テレビ朝日は、放送事業に依存し、視聴率の上昇に伴い利幅、効率ともに拡大し、収益力
を高めている。各企業の収益力の特徴が分かったところで、戦略をさらに深く分析するた
めに、売上高経常利益率と総資本回転率の推移をひとつのグラフにまとめた SPM を見る。 【図 3-1-20】
SPM
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1
総資本回転率(回)
売上高経常利益率(%)
日本テレビ
TBS
フジテレビ
テレビ朝日
線形 (系列1)
【図 3-1-20】の SPM のグラフは横軸に総資本回転率、縦軸に売上高経常利益率をとって
いる。各企業の線グラフは総資本回転率と売上高経常利益率の積を示している。そのため、

放送業界~日テレ・TBS・フジテレビ・テレ朝~ (池田・中井・中村)
32
売上高営業利益率
0.00%
5.00%
10.00%
15.00%
20.00%
日本テレビ 17.72% 14.10% 10.94% 9.60% 8.24% 8.83%
TBS 10.73% 8.25% 8.57% 7.46% 5.36% 7.95%
フジテレビ 10.51% 8.69% 9.66% 9.14% 8.55% 7.26%
テレビ朝日 6.13% 3.55% 2.99% 5.62% 6.85% 5.45%
業界平均 10.66% 6.91% 8.03% 7.96% 7.17%
平成13年度 平成14年度 平成15年度 平成16年度 平成17年度 平成18年度
グラフの右上に位置すれば両方の比率が高いので、企業の総合的な業績は良好であると判
断できる。また、グラフ中の点線は、東証一部に上場している放送企業の平均値を回帰分
析によって導き出したものである。この点線より上にあれば高付加価値型戦略、下にあれ
ば高効率型戦略をとっているということが判断できる。 では、各企業の分析を行っていく。まず、日本テレビは高付加価値型戦略であるのが分
かる。しかし年々利幅、効率ともに下がっている。次に TBS は平成 17 年度には高効率型
戦略になったが、平成 18 年度には高付加価値型戦略となっている。そしてフジテレビは高
付加価値型戦略、高効率型戦略をバランスよくとっていたものの、近年では利幅を下げ、
高効率型戦略をとっていることが分かる。最後にテレビ朝日は、過去 6 年間は高効率型戦
略をとっているが徐々に利幅も上げている。SPM のグラフから、どの企業も業界傾向線に
向かう傾向にあることが分かる。つまり、どの企業も同じ戦略をとろうとしている傾向に
あるということである。 これまで企業の収益力の特徴を見てきた。まず企業別の収益力を見た。次に 3 つの比率
で 4 社を比較し、最後に SPM を用いて相対的に各企業の戦略を分析を行った。 【図 3-1-13】、【図 3-1-14】、【図 3-1-15】、【図 3-1-16】より、日本テレビ、フジテレビが
売上高経常利益率、総資本回転率の両方、TBS、テレビ朝日は売上高経常利益率が各社の
収益力の変動に影響していた。 次に、比率ごとに 4 社を比較した。売上高経常利益率は日本テレビ、総資本回転率はフ
ジテレビが最も良好で、この 2 社が総合業績を示す総資本経常利益率も良かった。 【図 3-1-20】の SPM より、日本テレビ、TBS が利幅を重視した高付加価値型戦略、フ
ジテレビ、テレビ朝日が効率を重視した高効率戦略をとっていることが分かった。 全体の収益性について見てきたところで、各社の収益力の特徴や強み、問題点について
分析していく。ここでは、利幅と効率ごとに比率を分解していく。まず、売上高経常利益
率を分解し、その変動要因について分析する。売上高営業利益率、売上高総利益率、売上
高販売費および一般管理費率(以下、「売上高販管費率」)の順で見ていく。では、売上高
営業利益率を見る。 【図 3-1-21】

放送業界~日テレ・TBS・フジテレビ・テレ朝~ (池田・中井・中村)
33
【図 3-1-21】は、各企業、業界平均の売上高営業利益率の過去 6 年間の推移を示したもの
である。業界平均は、東証一部に上場している放送企業の平均値である。 売上高営業利益率という比率は、営業利益を売上高で除して、算出される。つまり、企
業の営業成績の良否、企業の営業力、営業収益力を判断できる。 グラフを見てみると、どの企業も売上高経常利益率とあまり変化がない。そこで、売上
高経常利益率と経常利益率の関係をまとめた表を見る。 【図 3-1-22】
日本テレビ TBS
①経常利益率 ②営業利益率 ①-② ①経常利益率 ②営業利益率 ①-②
平成 13 年度 17.47 17.72 -0.25 10.07 10.73 -0.66
平成 14 年度 13.78 14.1 -0.32 7.81 8.25 -0.44
平成 15 年度 11.21 10.94 0.27 8.1 8.57 -0.47
平成 16 年度 9.95 9.60 0.35 7.28 7.46 -0.18
平成 17 年度 8.66 8.24 0.42 5.03 5.36 -0.33
平成 18 年度 9.94 8.83 1.11 8.23 7.95 0.28
フジテレビ テレビ朝日
①経常利益率 ②営業利益率 ①-② ①経常利益率 ②営業利益率 ①-②
平成 13 年度 10.23 10.51 -0.28 5.8 6.13 -0.33
平成 14 年度 8.82 8.69 0.13 3.32 3.55 -0.23
平成 15 年度 9.99 9.66 0.33 2.7 2.99 -0.29
平成 16 年度 9.33 9.14 0.19 5.62 5.62 0
平成 17 年度 8.48 8.55 -0.07 6.94 6.85 0.09
平成 18 年度 7.89 7.26 0.63 5.81 5.45 0.36
【図 3-1-22】は、4 社の売上高経常利益率・営業利益率と、その差をそれぞれ表したもので
ある。金融収支がプラスであるということは、財務体質が健全で、財テクなどの財務運用
収益を上げていることを示し、マイナスであるということは、財務・金融活動で損失が出
ていることを示す。 日本テレビは平成 14 年度まではマイナスであったが、それ以降は数値を上げ、財務・金
融活動を順調に改善している。これは平成 15 年度に持分法適用関連会社を 1 社除外したこ
とにより、持分法による投資損失が減少したことに起因している。TBS は平成 18 年度以外
マイナスである。平成 18 年度には受取配当金が増加したことに加え、持分法による投資損
失の減少により改善された。フジテレビは平成 13 年度、平成 17 年度を除けばすべてプラ
スである。平成 13 年度では持分法による投資損失が大きく、平成 17 年度では新株発行費、
社債発行費、支払手数料、投資事業組合投資損失の増加により経常利益が減少し、マイナ
スになった。テレビ朝日は平成 15 年度まではマイナス、それ以降は順調に改善している。
テレビ朝日は平成 15 年以降、受取利息、受取配当金が増え、支払利息、持分法による投資
損失の減少により年々改善できている。

放送業界~日テレ・TBS・フジテレビ・テレ朝~ (池田・中井・中村)
34
売上高総利益率
25.00%
30.00%
35.00%
40.00%
日本テレビ 38.97% 36.01% 33.66% 31.46% 30.00% 30.48%
TBS 33.73% 32.85% 31.55% 30.08% 28.55% 30.41%
フジテレビ 38.35% 36.69% 36.53% 36.74% 35.37% 34.88%
テレビ朝日 31.92% 29.67% 28.41% 31.51% 30.96% 29.33%
業界平均 36.26% 34.45% 33.76% 33.82% 32.91%
平成13年度 平成14年度 平成15年度 平成16年度 平成17年度 平成18年度
【図 3-1-22】よりどの企業も財務・金融活動が改善の傾向にある。特に、日本テレビは
経常利益率を伸ばしており、財務・金融活動で収益を上げていることが分かった。 そこで売上高営業利益率の変動の要因が売上高にあるのか、販売費および一般管理費の
営業費用にあるのかを見るために、売上高営業利益率を売上高総利益率と売上高販管費率
に分解する。まず売上高総利益率から見ていく。 【図 3-1-23】 【図 3-1-23】は、各企業、業界平均の売上高総利益率の過去 6 年間の推移を示したもの
である。業界平均は、東証一部に上場している放送企業の平均値である。 売上高総利益率は売上総利益を売上高で除して算出される。売上総利益は売上高から売
上原価を引き算出され、購買活動、製造活動の結果を評価・判断する時に用いられる。つ
まり、この比率が高い企業ほど、売上原価が抑えられ、購買活動、製造活動が優れている
企業だと判断できる。放送業界の売上原価とは主に番組制作費を指す。業界概要で述べた
ようにこの番組制作費はタイム CM 収入から得ている。つまりタイム CM の売上高が高い
企業ほど番組制作費をかけられるのである。【図 3-1-11】で見たようにタイム CM の売上高
は、フジテレビ、日本テレビ、テレビ朝日、TBS の順である。日本テレビは年々減少傾向
にある。TBS、フジテレビは年々増加傾向にある。テレビ朝日は平成 16 年度を除き減少傾
向にある。 各企業を比較すると、フジテレビの比率が高いことが分かる。【図 3-1-11】と【図 3-1-12】を見て分かるとおり、フジテレビはタイム CM の売上高と、利益率の高いスポット CM の
売上高も高いことが分かる。加えて、他企業に比べ、番組制作費があまりかからない長寿
番組や再放送などの 2 次利用が可能な番組が多い。そのため、売上高総利益率は高くなる。
また、比率の変動幅が小さいことが分かる。これは、放送事業以外の事業を積極的に展開
しているため広告市況の影響を受けにくく、安定した売上高を得ていることに起因してい
る。逆に TBS、テレビ朝日は、視聴率を上げようと、番組制作や番組編成に力を入れてい

放送業界~日テレ・TBS・フジテレビ・テレ朝~ (池田・中井・中村)
35
売上高販管費率
20.00%
25.00%
30.00%
35.00%
日本テレビ 21.25% 21.92% 22.72% 21.86% 21.77% 21.65%
TBS 23.00% 24.60% 22.99% 22.62% 23.19% 22.46%
フジテレビ 27.83% 28.00% 26.87% 27.60% 26.82% 27.61%
テレビ朝日 31.92% 29.67% 28.41% 31.51% 30.96% 29.33%
業界平均 25.60% 27.54% 25.73% 25.86% 25.73%
平成13年度 平成14年度 平成15年度 平成16年度 平成17年度 平成18年度
売上高代理店手数料比率
10.00%
12.50%
15.00%
17.50%
20.00%
日本テレビ 14.12% 14.32% 14.12% 13.76% 13.51% 13.28%
TBS 13.01% 12.83% 12.69% 12.63% 12.74% 12.68%
フジテレビ 12.10% 12.06% 11.46% 11.80% 10.33% 10.39%
テレビ朝日 15.76% 15.64% 15.25% 15.68% 15.52% 15.27%
平成13年度 平成14年度 平成15年度 平成16年度 平成17年度 平成18年度
る。そのため、番組制作費が多くかかり利益率が低くなるのである。特に TBS はタイム CMの売上高が低いのにも関わらず、番組制作に力を入れている。つまり、タイム CM 収入の
利益率が低くなるため売上高総利益率も低いのである。続いて売上高販管費率を見る。 【図 3-1-24】 【図 3-1-24】は、各企業、業界平均の売上高販管費率の過去 6 年間の推移を示したもので
ある。業界平均は、東証一部に上場している放送企業の平均値である。 売上高販管費率は、販売費および一般管理費で売上高を除して、算出される。つまり、
この比率が低い企業ほど、少ない販管費で売上高を得ている企業ということとなる。 グラフを見てみると、日本テレビと TBS の比率が低く、フジテレビとテレビ朝日の比率
が高いことが分かる。 この売上高販管費をさらに細かく費用ごとに分け、各企業が何に費用をかけているのか
を分析していく。販管費を構成している費用の中で、代理店手数料と人件費取り上げて分
析をしていく。まず、売上高代理店手数料比率を見る。 【図 3-1-25】

放送業界~日テレ・TBS・フジテレビ・テレ朝~ (池田・中井・中村)
36
売上高人件費率
2.00%
3.00%
4.00%
5.00%
6.00%
日本テレビ 2.88% 3.11% 3.14% 2.72% 2.79% 2.78%
TBS 4.45% 4.13% 3.85% 3.60% 3.61% 3.62%
フジテレビ 3.88% 4.04% 3.89% 3.88% 3.82% 3.76%
テレビ朝日 5.54% 5.54% 5.35% 5.11% 4.01% 3.93%
平成13年度 平成14年度 平成15年度 平成16年度 平成17年度 平成18年度
【図 3-1-25】は、各企業の売上高代理店手数料比率の過去 6 年間の推移を示したもので
ある。 代理店手数料は広告収入に伴う費用である。そのため、広告収入に依存すればこの比率
が高くなる。テレビ朝日の比率が高い。これはセグメント売上高を見てみるとわかるよう
に、テレビ朝日は売上高の約 85%が放送事業収入であり、広告収入に依存している企業で
ある。そのため全体の売上高に対する代理店手数料の比率が高くなる。フジテレビは放送
事業収入の割合が低く、放送外事業の割合が高いので、全体の売上高に対して代理店手数
料は少なくなるのである。TBS は日本テレビよりも放送事業収入の割合は高いものの比率
が低い。放送事業の内訳に、広告収入と番組販売収入がある。TBS は、放送事業に対する、
広告収入の割合は 60%前後である。一方、日本テレビの放送事業に対する広告収入の割合
は、約 90%である。そのため、全体の売上高に占める代理店手数料が少なくなるのである。
続いて売上高人件費率を見る。 【図 3-1-26】
【図 3-1-26】は、各企業の売上高人件費率の過去 6 年間の推移を示したものである。
日本テレビは人件費を抑えられている。これは、ネットワーク協定を結んでいる局の数
が影響している。日本テレビ系列は 30 社からなる Nippon News Network(NNN)、TBS系列は 28 社からなる JNN ネットワーク、フジテレビ系列は 28 社からなるフジネットワー
ク、テレビ朝日系列は 26 社からなる All-Nippon News Network を形成している。 ネットワークを結ぶメリットとして、基本的に放送局のカバーできるエリアは 1 都道府
県ごとになっているが、テレビ局同士が手を結ぶことによって全国放送ができるようにな
ることが挙げられる。また、ニュース協定を結び、ニュースおよび報道番組の共同編成、
共同制作、共同分担を取り決め、地域ニュースを取材するための放送網としての役割を担
っている。そのため、このネットワークの局数が多いほど、無駄な人件費がかからないの
である。 今まで、利幅を示す売上高経常利益率を分解し、利幅の面で収益力を見てきた。日本テ

放送業界~日テレ・TBS・フジテレビ・テレ朝~ (池田・中井・中村)
37
日本テレビ
0.00
0.50
1.00
1.50
2.00
2.50
(回)
総資産回転率 0.81 0.71 0.64 0.72 0.67 0.65
流動資産回転率 1.94 1.62 1.74 2.04 2.04 1.78
固定資産回転率 1.39 1.25 1.01 1.12 0.99 1.02
平成13年度 平成14年度 平成15年度 平成16年度 平成17年度 平成18年度
レビの収益力が高い理由として、ネットワーク協定により費用の削減ができていることが
挙げられる。フジテレビは長寿番組で安定して高い視聴率を得ることで、番組制作費にあ
まり費用をかける必要がなくなるため費用を削減できている。また、テレビ放送事業以外
での売上高の伸びも順調であるため、景気に左右されやすい広告事業の影響を受けにくい
ということが強みである。TBS、テレビ朝日は番組制作に費用をかけている。しかし、業
界概要でも述べたように、広告収入は頭打ち状態であるため、費用をかけてもそれほど利
益に結びついていないのだと考えられる。 次に効率を示す総資産回転率を流動資産回転率と固定資産回転率に分解し、どの資産に
問題があるのかを企業ごとに見ていく。これまで総資本回転率として分析を進めてきたが、
数値上の変動はないため、総資本回転率を総資産回転率として分析を行う。 【図 3-1-27】
【図 3-1-27】は日本テレビの過去 6 年間の、総資産回転率、流動資産回転率、固定資産
回転率の推移を示したグラフである。 総資産回転率を見ると平成 16 年度の上昇を除けば、他の年度はすべて下降している。こ
れは、年々視聴率の低迷により売上高が減少しているためである。平成 16 年度には、アテ
ネ五輪等の大型単発番組があり、スポット広告の売上高が増加したことに加え、平成 16 年
11 月に劇場公開された映画「ハウルの動く城」が記録的な興行収入を上げたため、売上高
が増加し、比率が改善された。 流動資産回転率を見ると平成 15 年度、平成 16 年度は上昇している。一方、固定資産回
転率を見ると、総資産回転率と同じ動きであるのが分かる。しかし、固定資産回転率の方
が大きく下降している。平成 15 年度には固定資産回転率が総資産回転率以上に下降してい
るが、流動資産回転率の伸びにより、総資産回転率はそれほど下降していない。 日本テレビの回転率を見ると、総資産回転率の変動には、流動資産回転率と固定資産回
転率ともに影響していた。続いて TBS を見ることとする。

放送業界~日テレ・TBS・フジテレビ・テレ朝~ (池田・中井・中村)
38
TBS
0.00
0.50
1.00
1.50
2.00
2.50
3.00
(回)
総資産回転率 0.56 0.66 0.61 0.60 0.55 0.56
流動資産回転率 1.82 1.93 2.04 1.73 2.30 2.76
固定資産回転率 0.80 1.01 0.87 0.91 0.73 0.71
平成13年度 平成14年度 平成15年度 平成16年度 平成17年度 平成18年度
フジテレビ
0.00
0.50
1.00
1.50
2.00
2.50
(回)
総資産回転率 0.90 0.89 0.73 0.70 0.86 0.80
流動資産回転率 2.04 1.97 1.36 1.50 2.27 2.06
固定資産回転率 1.61 1.63 1.57 1.32 1.38 1.30
平成13年度 平成14年度 平成15年度 平成16年度 平成17年度 平成18年度
【図 3-1-28】 【図 3-1-28】は TBS の過去 6 年間の、総資産回転率、流動資産回転率、固定資産回転率
の推移を示したものである。 TBS の売上高は少しずつではあるが、年々増加している。しかし、総資産回転率を見る
と平成 14 年度と平成 18 年度が上昇、他の年度が下降していることが分かる。よって総資
産は売上高の増加幅よりも多く増加する傾向がある。流動資産回転率は平成 16 年度を除い
て、すべて上昇している。平成 16 年度に長期借入れによる資金調達により、有価証券が約
190 億円増加したため、比率は下降しているものの、他の年度では流動資産が減少し、比率
は改善している。固定資産回転率を見ると、平成 16 年度の上昇を除けば総資産回転率と同
じ変動であり、総資本回転率と数値が近い。これは TBS の資産の中で固定資産が多いこと
を示している。 TBS の回転率を見ると、平成 16 年度において固定資産回転率は上昇したものの、流動資
産回転率が大幅に下降した。そのため総資産回転率は下降したと考えられる。しかし、他
の年度を見ると、流動資産回転率が大きく上昇しているにも関わらず、総資産回転率にあ
まり変動が見られない。これは固定資産回転率の影響を受けやすいということが分かる。
そのため、総資産回転率も低い数値となっているのが分かる。続いてフジテレビを見る。 【図 3-1-29】

放送業界~日テレ・TBS・フジテレビ・テレ朝~ (池田・中井・中村)
39
テレビ朝日
0.00
0.50
1.00
1.50
2.00
2.50
(回)
総資産回転率 0.76 0.71 0.75 0.81 0.79 0.80
流動資産回転率 1.20 1.22 1.56 1.66 1.66 1.64
固定資産回転率 2.03 1.71 1.46 1.60 1.50 1.56
平成13年度 平成14年度 平成15年度 平成16年度 平成17年度 平成18年度
【図 3-1-29】はフジテレビの過去 6 年間の、総資産回転率、流動資産回転率、固定資産
回転率の推移を示したものである。 フジテレビは、成長性で述べたように、総資本、売上高ともに伸びていた。その中で総
資産回転率は平成 17 年度に上昇し、他の年度は下降している。つまり、事業を拡大してい
るが、うまく売上高に結びついていないのである。流動資産回転率、固定資産回転率とも
に、変動幅に差があるものの、ほぼ同じ推移である。流動資産回転率の変動は激しいが 6年間で見れば、わずかではあるが上昇している。一方、固定資産回転率は 6 年間で 0.3 下降
している。フジテレビの回転率を見ると、推移が同じであることから、総資産回転率には、
流動資産回転率、固定資産回転率ともに影響していると言える。しかし、総資産回転率、
固定資産回転率は、流動資産回転率の変動の影響をあまり受けていないため、特に固定資
産回転率影響し、総資産回転率が下降傾向であると言える。最後にテレビ朝日を見る。 【図 3-1-30】
【図 3-1-30】はテレビ朝日の過去 6 年間の、総資産回転率、流動資産回転率、固定資産
回転率の推移をまとめたグラフである。 総資産回転率は、平成 15 年度、平成 16 年度、平成 18 年度に上昇しているが、大きく変
動はしていない。テレビ朝日は総資産、売上高ともにほぼ横ばい状態であるためである。
流動資産回転率は平成 15 年度から上昇傾向にある。固定資産回転率は平成 16 年度、平成
18 年度は上昇している。平成 15 年度以降はどの回転率も大きな変動がない。 テレビ朝日の回転率を見ると、総資産回転率は流動資産回転率、固定資産回転率の両方
の影響を受けているのが分かる。 【図 3-1-27】【図 3-1-28】【図 3-1-29】【図 3-1-30】を用いて 4 社を比較すると、TBS の回
転率は固定資産回転率の影響を大きく受けているが、他の日本テレビ、フジテレビ、テレ
ビ朝日の 3 社は流動資産、固定資産の両方の回転率に影響を受けていた。 では、4 社を比較しやすくするために比率ごとに見て、分析を行う。まずは流動資産回転
率から見ることとする。

放送業界~日テレ・TBS・フジテレビ・テレ朝~ (池田・中井・中村)
40
流動資産回転率
1.00
1.50
2.00
2.50
3.00
(回)
日本テレビ 1.94 1.62 1.74 2.04 2.04 1.78
TBS 1.82 1.93 2.04 1.73 2.30 2.76
フジテレビ 2.04 1.97 1.36 1.50 2.27 2.06
テレビ朝日 1.20 1.22 1.56 1.66 1.66 1.64
業界平均 1.84 1.67 1.63 1.72 2.08
平成13年度 平成14年度 平成15年度 平成16年度 平成17年度 平成18年度
日本テレビ
0.00
50.00
100.00
150.00
200.00
250.00
(日)
流動資産回転日数 188.35 225.15 209.77 178.71 179.32 205.57
棚卸資産回転日数 1.32 1.15 1.64 1.71 2.10 2.51
売上債権回転日数 83.78 91.06 92.01 85.73 84.94 95.56
平成13年度 平成14年度 平成15年度 平成16年度 平成17年度 平成18年度
【図 3-1-31】 【図 3-1-31】は、各企業、業界平均の流動資産回転率の過去 6 年間の推移を示したもの
である。業界平均は、東証一部に上場している放送企業の平均値である。 【図 3-1-19】の総資産回転率では、TBS が日本テレビ、フジテレビ、テレビ朝日、業界
平均を下回る回転率を示していた。流動資産回転率を見ると、上下変動はあるものの TBSは業界平均を上回り、他社よりも良好な数値を示している。 それでは、流動資産回転率の変動要因を見るために、流動資産を棚卸資産と売上債権に
分解し、売上高との割合を企業別に見ていく。 【図 3-1-32】
【図 3-1-32】は日本テレビの過去 6 年間の流動資産回転日数、棚卸資産回転日数、売上
債権回転日数の推移をまとめたものである。これまでは回転率を見てきたが、ここでは、
日経経営指標に掲載されている業界平均と比較するため、回転日数を用いる。この比率は
資産が 1 回転するまでに要する期間を示すもので、期間が短いほど効率が良いと判断でき

放送業界~日テレ・TBS・フジテレビ・テレ朝~ (池田・中井・中村)
41
TBS
0.00
50.00
100.00
150.00
200.00
250.00
(日)
流動資産回転日数 200.56 188.91 179.24 210.47 158.82 132.48
棚卸資産回転日数 11.89 11.37 14.76 13.81 12.81 11.54
売上債権回転日数 76.45 75.67 77.93 74.85 81.20 49.60
平成13年度 平成14年度 平成15年度 平成16年度 平成17年度 平成18年度
る。 日本テレビの 3 つ回転日数はすべて 6 年間で増加しているのが分かる。各回転日数を見
ると、流動資産回転日数は平成 15 年度、平成 16 年度を除き増加傾向にある。棚卸資産日
数は流動資産回転日数の変動とは異なり平成 15 年度までは増加傾向にあり、平成 16 年度
に減少し、平成 17 年度に 7 日ほど増加している。そして平成 18 年度に再び減少している。
一方、売上債権回転日数の変動は小さいが流動資産回転率とほぼ同じ変動の仕方である。 日本テレビの流動資産回転日数の変動は売上債権回転日数の影響が大きいと考えられる。
しかし、平成 15 年には棚卸資産回転日数、売上債権回転日数が増加しているものの、流動
資産回転日数は減少している。これは、平成 15 年度に有価証券、その他流動資産の減少に
より流動資産が減少したため、棚卸資産回転日数、売上債権回転日数に関係なく、流動資
産回転率が減少した。続いて、TBS を見ることとする。 【図 3-1-33】 【図 3-1-33】は TBS の過去 6 年間の流動資産回転日数、棚卸資産回転日数、売上債権回
転日数の推移をまとめたものである。 TBS の回転日数は 6 年間で見るとすべて減少している。流動資産回転日数は平成 16 年度
の増加以外は減少している。棚卸資産回転日数は平成 15 年度の増加以外は、わずかではあ
るが減少している。売上債権回転日数は平成 15 年度、平成 17 年度に増加以外は減少して
いる。TBS の流動資産回転日数の変動には、平成 18 年度の売上債権回転日数の大幅な減少
が影響しただけで、あまり棚卸資産回転日数、売上債権回転日数が影響していない。平成
16 年度の流動資産回転日数の増加も有価証券の大幅な増加によるものである。続いてフジ
テレビを見ることとする。

放送業界~日テレ・TBS・フジテレビ・テレ朝~ (池田・中井・中村)
42
フジテレビ
0.00
50.00
100.00
150.00
200.00
250.00
300.00
(日)
流動資産回転日数 179.05 185.46 268.51 244.09 160.53 177.30
棚卸資産回転日数 23.98 21.16 16.79 17.27 13.85 14.50
売上債権回転日数 80.09 80.89 77.63 75.13 68.85 75.02
平成13年度 平成14年度 平成15年度 平成16年度 平成17年度 平成18年度
テレビ朝日
0.00
50.00
100.00
150.00
200.00
250.00
300.00
350.00
(日)
流動資産回転日数 303.57 299.56 233.34 220.26 219.80 222.67
棚卸資産回転日数 26.89 31.28 28.96 21.93 20.92 20.53
売上債権回転日数 87.16 93.35 94.92 96.04 92.47 94.23
平成13年度 平成14年度 平成15年度 平成16年度 平成17年度 平成18年度
【図 3-1-34】 【図 3-1-34】はフジテレビの過去 6 年間の流動資産回転日数、棚卸資産回転日数、売上
債権回転日数の推移をまとめたものである。 グラフを見てみると、流動資産回転日数は、平成 15 年度に大幅に増加し、平成 17 年度
に大きく減少し、平成 18 年度に増加している。棚卸資産回転日数は平成 16 年度、平成 18年度にわずかに増加し、他の年度では減少している。売上債権回転日数は平成 14 年度、平
成 18 年度に増加し、他の年度では減少している。平成 15 年度には有価証券、信託受益権
が大幅に増え、流動資産回転日数が増加した。平成 18 年度の流動資産回転日数の増加要因
は、有価証券の増加に加え、棚卸資産回転日数、売上債権回転日数の増加によるものであ
る。 フジテレビの流動資産回転日数の変動は平成 15年度の増加を除けば、棚卸資産回転日数、
売上債権回転日数の変動と同じである。つまり、流動資産回転日数の変動は 2 つの回転率
が影響しているのが分かる。続いて、テレビ朝日を見ることとする。 【図 3-1-35】

放送業界~日テレ・TBS・フジテレビ・テレ朝~ (池田・中井・中村)
43
棚卸資産回転日数
8.00
13.00
18.00
23.00
28.00
33.00
(日)
日本テレビ 8.34 10.57 15.90 13.24 21.36 17.64
TBS 11.89 11.37 14.76 13.81 12.81 11.54
フジテレビ 23.98 21.16 16.79 17.27 13.85 14.50
テレビ朝日 26.89 31.28 28.96 21.93 20.92 20.53
業界平均 15.14 15.45 18.29 17.01 15.73
平成13年度 平成14年度 平成15年度 平成16年度 平成17年度 平成18年度
【図 3-1-35】はテレビ朝日の過去 6 年間の流動資産回転日数、棚卸資産回転日数、売上
債権回転日数の推移をまとめたものである。 グラフを見てみると、流動資産回転日数は平成 18 年度にわずかに増加したが、他の年度
は減少傾向にある。棚卸資産回転日数は平成 14 年度に増加し、平成 15 年度以降は減少傾
向にある。売上債権回転日数は平成 14 年度から平成 16 年度までは増加傾向にあり、平成
17 年度に減少したが、平成 18 年度に再び増加している。平成 15 年度の流動資産回転日数
の大幅な減少は現金及び預金、有価証券の減少によるものである。 テレビ朝日の流動資産回転日数の変動は平成 15 年度を除けば、棚卸資産回転日数が影響
していると考えられる。 以上の各企業の分析により、流動資産回転日数の変動要因は、日本テレビは売上債権回
転日数、フジテレビは棚卸資産回転日数と売上債権回転日数、テレビ朝日は棚卸資産回転
日数が影響していた。TBS は棚卸資産回転日数、売上債権回転日数ともあまり影響してい
なかった。流動資産回転日数の変動要因について企業別に見てきたところで、次は比率ご
とに見て 4 社、業界平均を比較していく。まずは棚卸資産回転日数から見ていく。 【図 3-1-36】 【図 3-1-36】は、各企業、業界平均の棚卸資産回転日数の過去 6 年間の推移を示したも
のである。業界平均は、株式を上場している放送企業の平均値である。 棚卸資産回転日数は、在庫量が 1 日分の売上高の何倍あるかを示す指標で、この回転率
が短いほど、在庫資産が少なく、資金効率が良好であると判断できる。 グラフを見ると TBS の比率が業界平均を下回り、良好だということがわかる。
放送業界の棚卸資産には番組勘定というものが大部分を占めている。この番組勘定とい
うものは、制作中の番組の制作原価、未放送の番組の制作原価、再放送などの 2 次利用の
可能性のある番組の制作原価の一部、番組の放送権が計上される。各企業の棚卸資産の徳 用を捉えやすくするため、番組勘定について見ていく。

放送業界~日テレ・TBS・フジテレビ・テレ朝~ (池田・中井・中村)
44
番組勘定
0
10,000
20,000
30,000(百万円)
日本テレビ 5,605 7,609 11,524 9,529 16,156 13,209
TBS 7,461 7,833 9,614 8,308 7,149 6,328
フジテレビ 24,063 21,195 16,628 17,426 15,842 15,047
テレビ朝日 15,390 16,855 16,252 13,551 13,455 13,166
平成13年度 平成14年度 平成15年度 平成16年度 平成17年度 平成18年度
売上債権回転日数
40.00
50.00
60.00
70.00
80.00
90.00
100.00
(日)
日本テレビ 83.78 91.06 92.01 85.73 84.94 95.56
TBS 76.45 75.67 77.93 74.85 81.20 49.60
フジテレビ 80.09 80.89 77.63 75.13 68.85 75.02
テレビ朝日 87.16 93.35 94.92 96.04 92.47 94.23
業界平均 81.04 79.77 79.44 76.52 73.68
平成13年度 平成14年度 平成15年度 平成16年度 平成17年度 平成18年度
【図 3-1-37】 【図 3-1-37】は、各企業の番組勘定高の過去 6 年間の推移を示したものである。【図 3-1-36】の棚卸資産回転率と比べると変動が同じであることが分かる。 各企業を比較すると、テレビ朝日は番組勘定が多いことが分かる。これは番組制作に力
を入れていたことが大きく影響している。また、テレビ朝日はスポーツ中継の放送権を多
く持っている。番組勘定にはこの放送権が含まれているため、番組勘定が多くなっている。
フジテレビはタイム CM の収入が多く、番組制作費を多くかけられたことと、BS フジへの
番組販売や、再放送、DVD 化などの番組の 2 次利用を積極的に行っていることにより、番
組勘定が高いと考えられる。以上の TBS、フジテレビ、テレビ朝日の 3 社は年々減少傾向
にある。一方、日本テレビの番組勘定は増加傾向にある。これは、「第 2 日本テレビ」の開
始に伴うコンテンツの増加、また 2 次利用ができる番組制作に力を入れ始めたことにより、
番組勘定が増加傾向にあると考えられる。 【図 3-1-36】【図 3-1-37】より、日本テレビは企業の戦略により棚卸資産である番組勘定を
増やしているが、売上高に結びついておらず、回転日数の数値が高くなってきている。TBSは数値が低く、効率が良いと判断できる。フジテレビ、テレビ朝日は数値を改善させてい
る。 流動資産項目の最後に売上債権回転日数を見る。 【図 3-1-38】

放送業界~日テレ・TBS・フジテレビ・テレ朝~ (池田・中井・中村)
45
固定資産回転率
0.50
1.00
1.50
2.00
2.50
(回)
日本テレビ 1.39 1.25 1.01 1.12 0.99 1.02
TBS 0.80 1.01 0.87 0.91 0.73 0.71
フジテレビ 1.61 1.63 1.57 1.32 1.38 1.30
テレビ朝日 2.03 1.71 1.46 1.60 1.50 1.56
業界平均 1.22 1.27 1.25 1.25 1.14
平成13年度 平成14年度 平成15年度 平成16年度 平成17年度 平成18年度
【図 3-1-38】は、各企業、業界平均の売上債権回転日数の過去 6 年間の推移を示したも
のである。業界平均は、東証一部に上場している放送企業の平均値である。 この比率は売上債権の回収状況を示す指標である。比率が高いほど、貸倒の増加、仕入
代金や諸費用の支払の遅延、資本コストの増加が生じ、安全性が害される。 グラフを見ると、フジテレビ、TBS の比率が低く、日本テレビ、テレビ朝日の比率が高
いのが分かる。TBS は平成 18 年度に大幅な売上債権の流動化により比率を改善している。 【図 3-1-36】と【図 3-1-38】のグラフを見ると両方テレビ朝日の日数が長く、流動資産
回転率の悪化原因となっていたのが分かる。 これまで、流動資産回転率を見てきたところで、次に固定資産回転率を見ていく。 【図 3-1-39】 【図 3-1-39】は、各企業、業界平均の売上債権回転日数の過去 6 年間の推移をグラフに
したものである。業界平均は、東証一部に上場している放送企業の平均値である。 この比率は、固定資産への過大投資や遊休資産の有無を示す指標である。比率が高いほ
ど固定資産をうまく運用し、過大投資や遊休資産が少ないことを示している。 グラフを見ると、不動産業を展開している TBS は土地や機械装置が多く、回転率が悪い。
フジテレビ、テレビ朝日は業界平均を越え比率は良好であると判断できる。日本テレビは
平成 15 年度の汐留の新社屋の竣工に伴い、建物や、地上デジタル放送に向けた機械装置が
増え減少した。 これまで、資産回転率を見てきた。日本テレビの流動資産回転率は業界平均を上回って
いたが、固定資産回転率は下回っていた。また、比率は下降傾向にあった。TBS は流動資
産回転率では業界平均も上回り、改善の傾向にあった。一方、固定資産回転率では、不動
産業を行っているということから回転率が低くなっている。この固定資産回転率が大きく
影響し、総資産回転率も他社に比べて低い。フジテレビは流動資産回転率の上下変動が著

放送業界~日テレ・TBS・フジテレビ・テレ朝~ (池田・中井・中村)
46
しいが、固定資産回転率は業界平均を上回っている。流動資産回転率の影響は少なく、総
資本回転率も上下変動あまりない。他社と比較すると平成 15 年度、平成 16 年度を除けば、
1 位である。テレビ朝日は、番組制作に力をいれているものの、売上に結びつかず流動資産
回転率は他社に比べると低い。しかし、固定資産回転率が高く、総資産回転率を見ると平
成 14 年度以降は 2 位をキープしている。 以上、収益性分析を行ってきた。企業の総合業績を示す総資本経常利益率では変動があ
るものの平成 18 年度を見ると、創業業績は日本テレビ、フジテレビ、テレビ朝日、TBS の
順番であり、日本テレビ、フジテレビはどの年度も業界平均を上回っていた。次に、利幅
と効率の側面から企業の戦略や強み・問題点を分析するため、総資本経常利益率を売上高
経常利益率と総資本回転率に分解した。さらに各企業の戦略を視覚的に捉えるため、SPMを使用した。SPM より、日本テレビ、TBS が利幅を重視した高付加価値型戦略、フジテレ
ビ、テレビ朝日が効率を重視した高効率戦略をとっていることが分かった。 さらに、各指標の変動要因を見るため、売上高経常利益率と総資本回転率をそれぞれ分
解し、分析を進めた。まず売上高経常利益率の変動要因を見るため、売上高営業利益率、
率売上高総利益、売上高販管費率の順に分析を行った。売上高経常利益率・営業利益率に
あまり差はなく、利益率の高い順からの日本テレビ、TBS、フジテレビ、テレビ朝日とな
っていた。売上高総利益率を見ると、フジテレビが日本テレビ、TBS を抜き 1 位になって
いた。これは、フジテレビが他事業を展開し、広告市況の影響を受けず、安定した売上高
を得ていることに加え、長寿番組が多く、2 次利用できる番組制作を行っているため、番組
制作費を抑えることができるという強みが影響していた。一方、TBS、テレビ朝日は番組
制作に注力していることから、比率が低く、業界平均を下回っていた。売上高販管費率を
分析した結果、数値の低い順に日本テレビ、TBS、フジテレビ、テレビ朝日であった。こ
の販管費の中で人件費と代理店手数料に注目し各企業の比率を見た。売上高人件費率を見
ると日本テレビがネットワーク協定というものを強みに人件費を削減していた。売上高代
理店手数料比率を見ると、テレビ朝日がテレビ放送事業に依存していることにより、比率
が高くなっていることが明らかとなった。 次に、総資本回転率の変動要因を見るため、流動資産回転率、固定資産回転率に分解し
た。総資本回転率では回転率が高い順に、フジテレビ・テレビ朝日、日本テレビ、TBS あ
った。流動資産回転率を見ると、順位が大きく変わり TBS、フジテレビ、日本テレビ、テ
レビ朝日となった。TBS は平成 18 年度に売上債権の流動化により比率を改善していた。一
方、総資本回転率で 1 位であったテレビ朝日は、棚卸資産である番組勘定が多い。番組制
作に注力しているテレビ朝日であるが売上高に結びついていないことが分かった。最後に
固定資産回転率では回転率の高い順に、テレビ朝日、フジテレビ、日本テレビ、TBS ので
あった。ここでは TBS が展開している不動産事業が大きく影響していた。TBS は建設中の
建物が多く、まだ売上高に結びついていないため回転率を下げていた。 以上の分析より、日本テレビの強みはネットワーク協定による人件費の削減であり、利
幅を上げていた。TBS は効率が悪いのが問題点である。不動産事業において、建設中の建

放送業界~日テレ・TBS・フジテレビ・テレ朝~ (池田・中井・中村)
47
日本テレビ
0.00%
50.00%
100.00%
150.00%
200.00%
250.00%
流動比率 219.59% 184.04% 159.90% 206.73% 229.96% 235.83%
当座比率 198.07% 156.29% 136.54% 180.70% 191.81% 201.44%
現金比率 52.06% 48.28% 50.69% 57.91% 55.95% 57.47%
平成13年度 平成14年度 平成15年度 平成16年度 平成17年度 平成18年度
物が竣工した後、しっかり売上高に結び付けられるかが課題となる。フジテレビは多事業
展開により安定した売上高の確保や、長寿番組、2 次利用の可能な番組を強みに利幅、効率
ともに上げていた。テレビ朝日は広告市況が低迷する中、番組制作に注力し、売上高に結
びついておらず、利幅を下げていた。 これまで収益力においての強み、弱みを挙げてきた。次に、各企業の資金繰りについて
見ることとする。
3-1-3.安全性分析
(中井 茜)
企業が継続することができるかを判断するため安全性分析を行う。ここではその資金繰
りが安全であるかを 2 つの観点から分析を行う。 1 つ目に短期的な支払能力の観点から分析を行うために、流動比率、当座比率、現金比率
を用いて分析を行う。2 つ目に設備投資は健全であるかどうかなどの長期的な安全性の観点
から分析を行うために、自己資本比率、固定比率、固定長期適合率を用いて分析を行う。 まず、短期的な支払能力があるかを見ていく。ここでは流動比率、またその良否要因を
つかむために、流動資産から現金化されにくい棚卸資産を差し引いた当座資産、現金の順
に見ていく。始めに企業ごとに流動比率、当座比率、現金比率の 3 つの指標をみていく。 【図 3-1-40】 【図 3-1-40】は日本テレビの過去 6 年間の流動比率、当座比率、現金比率の推移をまと
めたものである。 グラフを見ると、当座比率と流動比率の上下変動が同じであることが分かる。当座比率
と流動比率の値が近いことから、日本テレビは棚卸資産が少ないと言える。流動比率、当

放送業界~日テレ・TBS・フジテレビ・テレ朝~ (池田・中井・中村)
48
TBS
0.00%
50.00%
100.00%
150.00%
200.00%
250.00%
流動比率 197.74% 208.20% 203.36% 206.07% 161.84% 151.35%
当座比率 168.23% 172.94% 170.76% 159.41% 129.97% 120.70%
現金比率 77.04% 89.54% 80.94% 62.44% 47.23% 64.04%
平成13年度 平成14年度 平成15年度 平成16年度 平成17年度 平成18年度
フジテレビ
0.00%
50.00%
100.00%
150.00%
200.00%
250.00%
300.00%
350.00%
400.00%
450.00%
流動比率 257.99% 266.71% 401.22% 324.81% 246.87% 188.00%
当座比率 202.09% 214.68% 285.75% 278.00% 181.54% 149.34%
現金比率 30.09% 33.27% 31.90% 39.59% 47.27% 30.80%
平成13年度 平成14年度 平成15年度 平成16年度 平成17年度 平成18年度
座比率に差が出てきたのは、比率が、棚卸資産回転日数で述べたように、2 次利用ができる
番組制作に力を入れ始めたことにより、番組勘定である棚卸資産が増加したためである。
一方、現金比率の比率、変動ともに小さく現金の収支が少ないことがわかる。続いて TBSを見ることとする。 【図 3-1-41】 【図 3-1-41】は TBS の過去 6 年間の流動比率、当座比率、現金比率の推移をまとめたも
のである。 グラフを見ると、3 つの比率の変動はほぼ同じである。平成 16 年度に当座比率、現金比
率が減少しているが、流動比率が上がっている。これは、未収入金の増加によりその他の
流動資産が増加したためである。続いてフジテレビを見ることとする。 【図 3-1-42】 【図 3-1-42】はフジテレビの過去 6 年間の流動比率、当座比率、現金比率の推移をまと
めたものである。

放送業界~日テレ・TBS・フジテレビ・テレ朝~ (池田・中井・中村)
49
流動比率
100.00%
200.00%
300.00%
400.00%
日本テレビ 219.59% 184.04% 159.90% 206.73% 229.96% 235.83%
TBS 197.74% 208.20% 203.36% 206.07% 161.84% 151.35%
フジテレビ 257.99% 266.71% 401.22% 324.81% 246.87% 188.00%
テレビ朝日 338.22% 295.85% 286.52% 281.31% 296.47% 325.25%
業界平均 238.59% 230.92% 251.61% 255.26% 225.92%
平成13年度 平成14年度 平成15年度 平成16年度 平成17年度 平成18年度
テレビ朝日
0.00%
50.00%
100.00%
150.00%
200.00%
250.00%
300.00%
350.00%
400.00%
流動比率 338.22% 295.85% 286.52% 281.31% 296.47% 325.25%
当座比率 298.29% 255.76% 234.04% 219.33% 254.73% 274.93%
現金比率 117.11% 85.10% 64.05% 61.18% 55.22% 34.43%
平成13年度 平成14年度 平成15年度 平成16年度 平成17年度 平成18年度
グラフを見ると、流動比率、当座比率はほぼ同じ変動を見せているが、現金比率は低い
値で推移している。フジテレビは現金が少ないため、流動比率に対する現金比率の影響力
は小さい。次にテレビ朝日を見ることとする。 【図 3-1-43】 【図 3-1-43】はテレビ朝日の過去 6 年間の流動比率、当座比率、現金比率の推移をまと
めたものである。 グラフを見ると、現金比率は年々減少している。一方、流動比率、当座比率は同じ変動
で、平成 16 年度より増加傾向にある。平成 16 年度以降は現金が減少傾向にあるが、有価
証券や受取手形及び売掛金が増加傾向にあることから、流動比率、当座比率は上昇した。 各企業の流動性について見てきたが、どの企業も現金比率よりも当座比率が流動比率に
影響していることが分かった。これは現金が少なく売上債権や有価証券が多いことを示す。
では、比率ごとに各社の比較を行う。 【図 3-1-44】

放送業界~日テレ・TBS・フジテレビ・テレ朝~ (池田・中井・中村)
50
当座比率
0.00%
100.00%
200.00%
300.00%
400.00%
日本テレビ 198.07% 156.29% 136.54% 180.70% 191.81% 201.44%
TBS 168.23% 172.94% 170.76% 159.41% 129.97% 120.70%
フジテレビ 202.09% 214.68% 285.75% 278.00% 181.54% 149.34%
テレビ朝日 298.29% 255.76% 234.04% 219.33% 254.73% 274.93%
平成13年度 平成14年度 平成15年度 平成16年度 平成17年度 平成18年度
【図 3-1-44】は、各企業、業界平均の流動比率の過去 6 年間の推移を示したものである。
業界平均は、東証一部に上場している放送企業の平均値である。 この比率は流動資産を流動負債で除して、算出される。この比率は、短期的に現金化さ
れる流動資産が、短期的な現金支払義務のある流動負債と比べてどの程度あるかを見る指
標である。流動負債より流動資産が多いことが望ましいので、この比率が 100%以上である
と安全だと判断ができる。逆にこの比率が 100%以下であると短期的な支払い能力がないと
判断される。また 200%が理想的な水準であるといわれている。上場企業の場合は平均 130~140%程度である。
グラフを見てみると、業界平均が 200%を越え、短期的な支払い能力は良好の業界だと判
断できる。放送業界は負債の少ないため、この比率が高くなる。負債が少ない要因は後述
することとする。 日本テレビ、TBS は業界平均を下回っているものの、比率は高いので問題はない。フジ
テレビは平成 15 年度に 135%程度比率を改善させたが、平成 16 年度以降年々下降傾向に
ある。平成 15 年度の増加要因は、連結子会社を増やし、有価証券が増加したことに加え、
ニッポン放送株として信託受益権の購入に伴い、流動資産が増加したためである。平成 16年度には新株予約権付社債の発行で負債が増え、前年度に購入した信託受益権を売却した
ことにより、流動資産が減少したため比率が下降している。 次にこの流動比率の変動要因を見るために、流動資産の中ですぐに現金化できる現金預
金、売上債権、有価証券などの当座資産と短期的な支払期限が到来する流動負債を比較す
る当座資産を見ることとする。 【図 3-1-45】 【図 3-1-45】は、各企業、業界平均の流動比率の過去 6 年間の推移を示したものである。
業界平均は、東証一部に上場している放送企業の平均値である この比率は当座資産を流動負債で除して、算出される。つまり、短期的に現金化される
流動資産の中の現金化されにくい棚卸資産を除いた当座資産が、短期的な現金支払義務の
ある流動負債と比べてどの程度あるかを見る指標である。この比率も流動比率と同様 100%

放送業界~日テレ・TBS・フジテレビ・テレ朝~ (池田・中井・中村)
51
現金比率
25.00%
45.00%
65.00%
85.00%
105.00%
125.00%
日本テレビ 52.06% 48.28% 50.69% 57.91% 55.95% 57.47%
TBS 77.04% 89.54% 80.94% 62.44% 47.23% 64.04%
フジテレビ 30.09% 33.27% 31.90% 39.59% 47.27% 30.80%
テレビ朝日 117.11% 85.10% 64.05% 61.18% 55.22% 34.43%
平成13年度 平成14年度 平成15年度 平成16年度 平成17年度 平成18年度
以上であると安全だと判断ができる。逆にこの比率が 100%以下であると短期的な支払い能
力がないと判断できる。 グラフを見ると、日本テレビ、TBS、テレビ朝日は流動比率とあまり変わりはない。フ
ジテレビは平成 16 年度に流動比率は大幅に減少したが、当座比率ではわずかに減少してい
る。これは、流動比率の減少原因が信託受益権の減少であったため、当座比率に影響がな
かったのだと考えられる。 どの企業を見ても、比率は 100%を越えているので安全であると判断できる。 では、短期的な支払能力を測る最後に、預金現金と流動負債との比率を見ていく。
【図 3-1-46】 【図 3-1-46】は、各企業、業界平均の流動比率の過去 6 年間の推移を示したものである。
業界平均は、東証一部に上場している放送企業の平均値である この比率は現金預金を流動負債で除して、算出される。つまり、企業の即時的な支払能
力を示す指標である。この比率は 20%以上であると即時的な支払能力が良好だと判断がで
きる。 どの企業も 20%以上であるため、安全であると判断できる。テレビ朝日は年々減少傾向
であることが見てとれるが、これは番組制作や代理店手数料の増加によるものである。 これまで、3 つの比率を用いて短期的な支払能力について見てきた。どの企業も高い比率
で、短期的な支払能力はあると判断できた。また、4 社とも現金が少なく、比率が低く、流
動比率に影響がなかった。日本テレビはどの比率も変動が小さく安定していた。また現金
比率に変動がなく、収支が少ないと言える。TBS は現金比率以外においては比率を下げて
いた。フジテレビも現金比率は低いものの当座資産が多く、問題はない。テレビ朝日は現
金比率が減少傾向ではあるが、流動比率、当座比率ともに高い比率であるので問題はない。 では次に長期的な支払能力の分析を行う。ここでは、自己資本比率、固定比率、固定長
期適合率の 3 つの指標を用いて分析を行う。 企業は負債よりも返済義務のない自己資本で資本を構成している方が安全である。そこ

放送業界~日テレ・TBS・フジテレビ・テレ朝~ (池田・中井・中村)
52
自己資本比率
60.00%
65.00%
70.00%
75.00%
80.00%
85.00%
日本テレビ 72.85% 68.63% 68.96% 74.29% 76.55% 73.71%
TBS 63.38% 67.22% 67.29% 64.16% 68.08% 67.87%
フジテレビ 77.01% 76.48% 80.20% 70.33% 66.86% 64.20%
テレビ朝日 74.37% 73.40% 76.31% 76.20% 76.83% 79.32%
業界平均 70.12% 70.46% 71.43% 69.14% 69.68%
平成13年度 平成14年度 平成15年度 平成16年度 平成17年度 平成18年度
で企業の資本構成を見るために自己資本比率を用いる。 【図 3-1-47】 【3-1-47】は、各企業、業界平均の自己資本比率の過去 6 年間の推移を示したものである。
業界平均は、東証一部に上場している放送企業の平均値である。 この比率は、自己資本を総資本で除して、算出される。つまり、企業が集めた資金がど
れだけ返済義務のない自己資本でまかなわれているかを見る指標で、財務面での長期的な
安全性が判断できる。この比率が高ければ高いほど安全度は高いと判断され、不況時の耐
久性が強いと判断される。日本の上場企業の平均値は 40%程度である。 この比率の業界平均は 70%前後で放送業界は安全度が高く、不況時の耐久性が強いと判
断できる。流動比率で述べたように、放送業界は負債が少ない。これは放送業界が許認可
事業だということが大きく影響していると考えられる。許認可事業で規制に守られている
ため、会社の倒産の心配が少なく、株主が安心して投資ができるため、この比率が高い。 各社を比較すると、日本テレビは平成 16 年度に短期借入金を返済したために総資本が減
少したが、自己資本に変化がなかったため、比率が上昇した。TBS は他企業と比べると比
率は低いものの、安全性には問題はない。フジテレビは平成 16 年度に比率が大幅に減少し
ている。これは、新株予約権付社債の発行により負債が増加したためである。テレビ朝日
はとても高い比率で、年々上昇している。 では、放送業界は借金体質でないと分かったところで、固定資産投資に対する資金調達
が安全であるかを見るため、固定比率、固定長期適合率の順に分析を行う。

放送業界~日テレ・TBS・フジテレビ・テレ朝~ (池田・中井・中村)
53
固定比率
40.00%
60.00%
80.00%
100.00%
120.00%
140.00%
日本テレビ 80.02% 82.29% 91.71% 86.86% 87.85% 86.05%
TBS 109.41% 97.62% 104.18% 102.28% 111.66% 117.32%
フジテレビ 72.54% 71.49% 57.86% 75.64% 93.17% 95.50%
テレビ朝日 49.98% 56.75% 67.82% 66.81% 68.32% 64.65%
業界平均 85.65% 80.69% 79.29% 83.88% 92.76%
平成13年度 平成14年度 平成15年度 平成16年度 平成17年度 平成18年度
固定長期適合率
40.00%
60.00%
80.00%
100.00%
日本テレビ 72.31% 74.43% 82.80% 78.89% 79.66% 78.93%
TBS 83.13% 78.96% 82.53% 79.07% 89.56% 92.01%
フジテレビ 68.18% 66.71% 54.33% 63.25% 74.66% 77.20%
テレビ朝日 45.90% 52.20% 62.60% 62.03% 62.90% 60.32%
業界平均 72.96% 69.12% 70.59% 70.26% 77.62%
平成13年度 平成14年度 平成15年度 平成16年度 平成17年度 平成18年度
【図 3-1-48】 【図 3-1-48】は、各企業、業界平均の固定比率の過去 6 年間の推移を示したものである。
業界平均は、東証一部に上場している放送企業の平均値である。 この比率は、固定資産を自己資本で除して、算出される。企業の固定資産投資に対する
資金調達の安全性を判断する指標である。この比率が低いほど安全であると判断できる。
比率が低いということは、長期間に渡り資金が拘束される固定資産投資の資金調達が返済
義務のない自己資本を中心にまかなわれていることとなる。もし、この資金調達が負債中
心でまかなわれているならば、負債を返済しなければいけない時に、資金が拘束されてい
るため返済できなくなるので危険だと判断できる。そのため、この比率は 100%以下が安全
であるといえる。 【図 3-1-48】から、TBS は比率が高く危険であるということが分かる。TBS は不動産事
業を展開しているため固定資産が多い。そのため、比率が他社よりも高いと考えられる。
日本テレビ、フジテレビ、テレビ朝日はどの年度も 100%以下で長期的にも安全だと判断で
きる。フジテレビの平成 15 年度に約 14%減少し、平成 16 年度以降は比率を改善させてい
る。平成 15 年度には成長性でも述べたように、音楽関連事業の連結子会社の増加により資
本金、資本剰余金、その他有価証券評価差額金の増加により大幅に自己資本が増えたため
である。 しかし、この比率が 100%以上であっても、必ずしも経営上の安全性が損なわれていると
判断できない。そこで固定比率を発展させ、固定長期適合率という指標を用いて分析する。 【図 3-1-49】

放送業界~日テレ・TBS・フジテレビ・テレ朝~ (池田・中井・中村)
54
【図 3-1-49】は、各企業、業界平均の固定長期適合率の過去 6 年間の推移をグラフにし
たものである。業界平均は、株式を上場している放送企業の平均値である。 この比率は、固定資産を自己資本と固定負債の和で除して、算出される。先ほどの固定
比率では固定資産投資は自己資本でまかなわれているのが理想だといったが、長期的に返
済が許される固定負債を含めてまかなわれていれば、安全といっても良い。そのため、固
定長期適合率が 100%以下であれば、長期的に安全だと判断できる。 グラフを見ると、固定比率の値が 100%を超え危険だと判断できた TBS も 100%を下回
り安全であると判断できる。 これまで長期的な安全性を見るため、自己資本比率、固定比率、固定長期適合率を用い
て分析を進めてきた。許認可事業である放送業界は負債が少なく、自己資本の多い業界で
あるため、日本テレビ、フジテレビ、テレビ朝日には問題はなかった。不動産事業を展開
しており、固定資産が多い TBS は固定比率が 100%以上であり、危険だと判断できたが、
固定長期適合率で見ると 100%以下の数値を示し問題がないと判断できた。 以上、安全性を長期と短期の 2 つの観点から分析してきた。短期的な支払い能力では流
動比率、当座比率、現金比率を用いて分析した。4 社ともに問題はなかった。フジテレビは
平成 16 年度以降、負債の増加により比率が下降傾向であったが、数値に問題はない。長期
的な安全性でも、TBS の固定比率を除けば 4 社とも安全性には問題がないといえる。TBSは固定長期適合率で見れば安全であるため、どの企業も安全である。短期・長期の観点で
見ても 4 社とも問題がなく、安全であると判断できた。特にテレビ朝日はどの比率を見て
も、他社よりも優れていると判断できる。 安全性についての分析を終えたところで、キャッシュフロー分析に移る。
3-1-4.キャッシュフロー分析
(池田 泰輔)
これまでは貸借対照表と損益計算書をもとに成長性、収益性、安全性の分析を進めてい
た。しかし、黒字倒産という言葉があるように、企業が存続していくためには利益だけで
なく、営業活動によって生み出される現金が重要になってくる。そのため、キャッシュフ
ロー計算書を用いてキャッシュフロー分析を行う。キャッシュフローとは、お金の流れを
意味し、企業活動によって実際に得られた収入から外部への支出を差し引いて手元に残る
資金の流れのことをいう。つまり、資金収支である。キャッシュフロー分析では、資金収
支に特化した分析が可能であることから、企業の現金創出能力や将来の発展可能性を見る
ことができるのである。

放送業界~日テレ・TBS・フジテレビ・テレ朝~ (池田・中井・中村)
55
まず、キャッシュフロー計算書において 3 つに区分される、営業キャッシュフロー、投
資キャッシュフロー、財務キャッシュフロー、フリーキャッシュフローを企業ごとに分析
する。 営業キャッシュフローは、売上や仕入などの営業活動によって生じた資金収支のことを
いう。本業でしっかりと資金を稼ぐことができるかは、企業を判断する上で非常に重要に
なるのでプラスであることが望ましい。マイナスだと事業継続のために借金を増やすこと
になり、設備投資ができないなどの影響がある。投資キャッシュフローは、営業活動を行
っていくために、土地や建物といった長期的に使うことを目的とした投資支出のことをい
う。財務キャッシュフローは、株式の発行や融資による資金調達や配当金の支払などによ
りもたらされる収支を表している。フリーキャッシュフローは、営業キャッシュフローか
ら投資キャッシュフローを控除して求められ、企業の資金創出能力を表している。プラス
であれば、積極的な事業展開や企業の安定性の向上が計れる。マイナスになると事業展開
に影響し、財務キャッシュフローによる資金調達の必要が出てくるなどして、資金繰りが
厳しくなることもある。 【図 3-2-1】
日本テレビ
-60,000
-40,000
-20,000
0
20,000
40,000
60,000
百万円
営業キャッシュフロー 38,891 25,981 30,519 49,286 32,683 31,457
投資キャッシュフロー -48,773 -37,394 -41,596 -23,406 -24,358 -24,596
フリーキャッシュフロー -9,882 -11,413 -11,077 25,880 8,325 6,861
財務キャッシュフロー -3,164 22,464 7,131 -37,275 -15,920 -4,713
平成13年度 平成14年度 平成15年度 平成16年度 平成17年度 平成18年度
【図 3-2-1】は日本テレビの過去 6 年間における営業キャッシュフロー、投資キャッシュ
フロー、フリーキャッシュフロー、財務キャッシュフローの推移を表したものである。 営業キャッシュフローは当期純利益を減少させながらも、安定させている。平成 13 年度
から平成 15 年度にかけて、デジタル化に向けた設備投資や汐留新社屋建設の費用の支出が
増加したため、フリーキャッシュフローがマイナスとなった。フリーキャッシュフローの
マイナス分を補うために短期借入金によって資金調達したことから、財務キャッシュフロ
ーがプラスとなっている。 平成 16 年度以降は、営業キャッシュフローが減少傾向となっているが、継続して投資活
動に資金の投下を行い、財務体質の強化を図ったものの再び借入を行っている状況にある。

放送業界~日テレ・TBS・フジテレビ・テレ朝~ (池田・中井・中村)
56
【図 3-2-2】
TBS
-80,000
-60,000
-40,000
-20,000
0
20,000
40,000
60,000
(百万円)
営業キャッシュフロー 18,884 23,368 19,075 26,178 23,261 50,886
投資キャッシュフロー 27,171 -7,192 -20,412 -40,466 -49,817 -55,543
フリーキャッシュフロー 46,055 16,176 -1,337 -14,288 -26,556 -4,657
財務キャッシュフロー -3,737 -11,624 -6,563 9,346 12,619 14,490
平成13年度 平成14年度 平成15年度 平成16年度 平成17年度 平成18年度
【図 3-2-2】は TBS の過去 6 年間における営業キャッシュフロー、投資キャッシュフロ
ー、フリーキャッシュフロー、財務キャッシュフローの推移を表したものである。 営業キャッシュフローは平成 13 年度から 18 年度にかけて増加傾向にある。投資キャッ
シュフローは平成 15 年度以降、営業キャッシュフロー以上の投資活動を行っており、その
ためフリーキャッシュフローがマイナスとなっている。マイナスとなった分を社債の償還
になどにより財務キャッシュフローでまかなっていることが分かる。平成 13 年度に営業キ
ャッシュフローを上回っているのは、公社債投資信託等の売却による収入によるためであ
る。平成 14 年度からマイナスを示しており、将来のための投資を行っているといえる。 【図 3-2-3】
フジテレビ
-150,000
-100,000
-50,000
0
50,000
100,000
150,000
(百万円)
営業キャッシュフロー 30,876 33,458 45,256 44,673 45,786 60,718
投資キャッシュフロー -25,001 -32,245 -68,067 -135,516 -69,748 -18,206
フリーキャッシュフロー 5,875 1,213 -22,811 -90,843 -23,962 42,512
財務キャッシュフロー -2,707 -11,566 92,956 76,731 -28,642 -9,013
平成13年度 平成14年度 平成15年度 平成16年度 平成17年度 平成18年度
【図 3-2-3】はフジテレビの過去 6 年間における営業キャッシュフロー、投資キャッシュ
フロー、フリーキャッシュフロー、財務キャッシュフローの推移を表したものである。

放送業界~日テレ・TBS・フジテレビ・テレ朝~ (池田・中井・中村)
57
営業キャッシュフローは平成 13 年度から平成 18 年度にかけて増加傾向にあり、安定し
ていることが分かる。 平成 15 年度において財務キャッシュフローが増加しているのは、増資による資金調達を
行ったからである。平成 16 年の投資キャッシュフローの増加は、前年度の資金調達を新ス
タジオ建設用地の取得に充てられたことやライブドア事件によるニッポン放送株式を始め
とする投資有価証券を取得したためである。投資キャッシュフローの増加によりフリーキ
ャッシュフローは大きくマイナスとなった。その分を補うため、社債を発行したことによ
って財務キャッシュフローは大きいまま推移した。 【図 3-2-4】
テレビ朝日
-30,000
-20,000
-10,000
0
10,000
20,000
30,000
(百万円)
営業キャッシュフロー 5,610 10,555 6,474 24,808 19,518 13,688
投資キャッシュフロー -5,906 -14,078 -23,751 -19,437 -21,354 -18,748
フリーキャッシュフロー -296 -3,523 -17,277 5,371 -1,836 -5,060
財務キャッシュフロー -7,855 -8,203 -3,064 -2,183 -1,521 -1,419
平成13年度 平成14年度 平成15年度 平成16年度 平成17年度 平成18年度
【図 3-2-4】はテレビ朝日の過去 6 年間における営業キャッシュフロー、投資キャッシュ
フロー、フリーキャッシュフロー、財務キャッシュフローの推移を表したものである。 営業キャッシュフローは平成 13 年度から平成 16 年度にかけて増加傾向にあり、平成 16年度から平成 18 年度にかけては減少傾向にある。投資キャッシュフローが平成 14 年度、
平成 15 年度に増加したのは、六本木ヒルズ移転に伴う有形・無形固定資産の取得によるも
のである。フリーキャッシュフローは、投資キャッシュフローの増額により平成 16 年度以
外はマイナスである。財務キャッシュフローは年々減少傾向にあるのは、平成 17 年度に借
入金の返済が終了したためである。 ここまで 4 社の過去 6 年間における営業キャッシュフロー、投資キャッシュフロー、フ
リーキャッシュフロー、財務キャッシュフローの推移を見てきた。 日本テレビは営業キャッシュフローが減少傾向にあるが、順調に推移しているといえる。
TBS は営業キャッシュフローが増加傾向にあるものの、赤坂再開発に伴う投資キャッシュ
フローの増大により、フリーキャッシュフローがマイナスとなっている。フジテレビは設
備投資やライブドア事件の影響により一時期不安定であったが、今の段階では 4 社の中で
一番安定していると言える。テレビ朝日は営業キャッシュフローが減少傾向にあることが
らフリーキャッシュフローがマイナスとなっている。

放送業界~日テレ・TBS・フジテレビ・テレ朝~ (池田・中井・中村)
58
営業利益と営業キャッシュフロー
0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
70,000
(百万円)
日本テレビ営業利益 63,573 47,406 35,937 34,325 28,551 30,344
TBS営業利益 31,242 24,326 25,271 22,510 16,404 25,327
フジテレビ営業利益 45,935 37,268 44,065 43,581 50,724 42,325
テレビ朝日営業利益 13,477 7,430 6,520 13,606 17,075 13,677
日本テレビキャッシュフロー 38,891 25,981 30,519 49,286 32,683 31,457
TBSキャッシュフロー 18,884 23,368 19,075 26,178 23,261 50,886
フジテレビキャッシュフロー 30,876 33,458 45,256 44,673 45,786 60,718
テレビ朝日キャッシュフロー 5,610 10,555 6,474 24,808 19,518 13,688
平成13年度 平成14年度 平成15年度 平成16年度 平成17年度 平成18年度
【図 3-2-6】 【図 3-2-6】は各社の営業利益・営業キャッシュフローの過去 6 年間の推移をまとめたも
のである。営業キャッシュフローは営業活動により生み出されたキャッシュフローである
ため、これがマイナスであれば、存続するために借入金や財務活動などにより資金を調達
しなければならない。つまりプラスであれば、健全な企業経営ができるということである。
またこの営業キャッシュフローは営業利益の額と近ければより良好だと判断できる。そこ
で、各社の営業利益と営業キャッシュフローを比較してみる。 日本テレビの営業利益は平成 13 年度から平成 18 年度まで減少傾向にある。営業キャッ
シュフローは平成 13 年度から平成 15 年度まで減少傾向にあり、再び平成 17 年度から平成
18 年度に減少している。平成 15 年度から平成 16 年度の増加は、仕入債務が減少したこと
や汐留新社屋への移転完了に伴う減価償却費が増加したことなどによるものである。 TBS の営業利益は平成 13 年度から平成 17 年度まで減少傾向にあるが、平成 18 年度に
増加している。営業キャッシュフローは営業利益との推移と異なり、平成 13 年度から平成
18 年度にかけて増加傾向にある。平成 17 年度から平成 18 年度の増加は、売上債権の流動
化を実施した影響によって売上債権が減少したためである。 フジテレビの営業利益は多少の変動があるものの平成 13 年度から平成 18 年度にかけて
安定した推移を見せている。営業キャッシュフローは平成 13 年度から平成 18 年度まで増
加傾向にある。平成 14 年度から平成 15 年度の増加は、主力であるテレビ放送事業が増収
増益になり、通信販売事業、放送関連事業も増収増益基調となったためである。また、平
成 17 年度から平成 18 年度の増加は前年度法人税等が還付となったためである。 テレビ朝日の営業利益は平成 13 年度から平成 15 年度まで減少傾向にあり、平成 16 年度
から平成 18 年度までは増加傾向にある。営業キャッシュフローは平成 13 年度から平成 16年度まで増加傾向にあり、平成 17 年度から平成 18 年度にかけては減少傾向にある。平成
15 年度から平成 16 年度の増加は、消費税関連の資金の増加などによるものである。

放送業界~日テレ・TBS・フジテレビ・テレ朝~ (池田・中井・中村)
59
4 社を比較すると、フジテレビ、TBS の営業キャッシュフローが年々上昇し、営業利益
を超えている。フジテレビの現金比率は下がっていたが、キャッシュフローは上昇してい
る。これは現金での支出が減ってきていることを示す。また、日本テレビ、テレビ朝日と
もに上下変動はあるものの近年では営業利益を超え健全な企業経営ができていると言える。 ここまで、成長性、収益性、安全性、キャッシュフロー分析の 4 つの観点から財務分析
を行ってきた。 成長性分析では、日本テレビを除く 3 社が成長傾向にあることが分かった。その中でも
特にフジテレビは優れた成長を見せていた。他の 3 社には見られない放送事業以外の展開
を上手く行えているからである。 収益性分析では、総資本経常利益率の推移から日本テレビとフジテレビの収益性が高い
ことが分かった。日本テレビはネットワーク協定により、人件費を削減できたことが収益
力に繋がっている。フジテレビは放送事業以外の事業による売上高の確保に成功したこと
などから、利幅も効率も上げていた。TBS はタイム CM の売上高が低い中、視聴率を上げ
るために番組制作費を多くかけていることに加え、不動産事業の運用効率が良くないため
に固定資産回転率が悪くなり、収益性が低くなっている。テレビ朝日は番組制作費を固定
させたことにより、営業利益・経常利益が増加し、また視聴率上昇により売上高が増加し
たことが総資本経常利益率に影響している。 安全性分析では、短期と長期の観点から見たが、4 社に問題はなく安全であることが分か
った。その中でもテレビ朝日は特に優れていることが分かった。 キャッシュフロー分析では、4 社とも健全な企業経営ができているが、一番安定している
のはフジテレビであることが分かった。 これらを踏まえた上で、企業分析を行っていく。
3-3.企業分析
(中村圭介)
3-3-1.企業の特徴と経営戦略
ここでは、各企業の特徴と経営戦略を明らかにし、各企業の現状を理解する。
(1) 日本テレビ
企業の特徴 日本テレビは 1951 年、民放初のテレビ放送局として当時読売新聞社長であった正力松太
郎氏により設立された。日本テレビは正力松太郎氏の日本全国をテレビ網で覆うという正
力構想の精神のもと、電波の重要性を主張し、ネットワーク構築に専念した。その結果、

放送業界~日テレ・TBS・フジテレビ・テレ朝~ (池田・中井・中村)
60
1966 年には日本ニュースネットワーク(NNN)を発足させ、強力なネットワークの礎を築
き、現在でも、民放キー局トップのネットワーク数を誇っている。 また、力道山のプロレス中継に始まるスポーツ番組は日本テレビの得意分野といえる。
親会社の読売グループ参加の巨人戦の中継は、日本テレビの視聴率のバックボーンを担っ
てきたといっても過言ではない。 さらに、番組編成の特徴として、朝の「ズームイン朝」(現「ズームイン!!SUPER」)、
昼の「おもいっきりテレビ」(現「おもいッきりイイ!!テレビ」)、夕方の「ニュースプラ
ス1」(現「NNN News リアルタイム」)、夜の「NNN 今日の出来事」(現「NEWS ZERO」)
などのベルト番組と呼ばれる、月~金曜日の毎日の同時刻の放送に力を入れている。バラ
エティ番組では「電波少年」を始めとした、「エンタの神様」、「ザ!鉄腕!DASH!!」、「行
列の出来る法律相談所」などの番組が人気を博している。スポーツ番組、ベルト番組、バ
ラエティ番組の成功から、1994~2002 年まで視聴率 9 年連続首位の栄冠を獲得した。常に
視聴率トップの座に君臨していた日本テレビは「視聴率至上主義」(河本久廣,『よくわか
る放送業界』,株式会社 日本実業出版社,2006 年,28 頁)をとり始めた。 日本テレビは「視聴率至上主義」(河本久廣,『よくわかる放送業界』,株式会社 日本実
業出版社,2006 年,28 頁)を推し進めた結果、10 年連続視聴率トップを目前にした 2003年 10 月に、ビデオリサーチ社のモニターとなっている 4 世帯に対し、日本テレビのプロデ
ューサーは自分が制作した特番、計 6 番組を見るように依頼した。その際 5000~10000 円
の謝礼を渡していたとされる。 この視聴率買収事件をきっかけに、日本テレビの「視聴率至上主義」(河本久廣,『よく
わかる放送業界』,株式会社 日本実業出版社,2006 年,28 頁)が非難され始め、10 年連
続視聴率トップを逃し、以降、視聴率低迷に陥る。
経営戦略 日本テレビは「No.1 のコンテンツ供給会社」と、「コンテンツの 2 次利用・多角的配信を
目指す」の二つの経営方針を掲げている。 日本テレビが、この二つの経営方針を基に打ち出している経営戦略は、「コンテンツ制作
力の強化」、「マルチコンタクトポイント戦略の採用」、「放送外収入の拡大」、「視聴者層を
若年層にシフトする」の 4つである。
日本テレビは「No.1 のコンテンツ供給会社」を目指すために、コンテンツ制作に関わる
人材を育成するための「人材育成センター」の新設と、個性的なコンテンツ企画を採用す
る新基準の導入を行うことで、コンテンツ制作力の強化を図る。
そして、マルチコンタクトポイント戦略によって「コンテンツの 2次利用・多角的配信」
の実現を目指していく。マルチコンタクトポイント戦略とは、いつでも・どこでも日テレ
のコンテンツに触れられるということを意味しており、モバイルコンテンツ・インターネ
ットによるコンテンツ配信、地上波放送、衛星放送、通信放送などの伝送路に、日テレの
コンテンツを積極的に配給していくというものである。また、この経営計画は、放送外収
入を拡大していくという要素も含んでおり、通信販売事業とインターネットや、テレビ番

放送業界~日テレ・TBS・フジテレビ・テレ朝~ (池田・中井・中村)
61
組を連動させた事業展開や、「第 2 日本テレビ」のオリジナルコンテンツの充実を目指して
いる。他にも、アニメなどの映画を地上波と連動させて放送を行うことで放送外収入を拡
大する動きがある。最近の例でいえば、「DEATH NOTE 」を地上波と映画で連動させて放
送したのは記憶に新しい。他にも、「ハウルの動く城」や「ゲド戦記」などのジブリ作品の
特番を地上波で放送し、映画の集客数増加を促すなど、積極的に映画と地上波の連携を図
っている。
さらに、日本テレビは番組の質的評価の向上を目指している。質的評価とは、番組の社
会的評価のことを意味するが、日本テレビが考える質的評価とは、広告主に対する CM 広告
の費用対効果が高い企業を目指すということである。日本テレビの視聴者層はフジテレビ
などに比べると高年層の視聴者が多のだが、企業が重視している視聴者ターゲットは消費
活動が活発な若年層である。そのため、視聴者層を若年層にシフトさせていくための番組
編成の改善が行われ始めている。
日本テレビは、これらの計画を実行することにより、「No.1 のコンテンツ供給会社」と、
「コンテンツの 2次利用・多角的配信」の実現を目指している。
(2) TBS 企業の特徴 TBS の特徴として、1960 年から 1970 年代にかけて、ドラマ・バラエティ・報道の各分
野で高く評価されていた点が挙げられる。「民放の NHK」「ドラマの TBS」「報道の TBS」と称されるほどだった。また、報道に関しては、JNN 協定を結びネットワークを確立させ、
ニュースの正確性・速報性を発揮していた。しかし、1980 年代初めにフジテレビに視聴率
トップの座を明け渡して以来、低迷状態に陥り、近年では万年 3 位の座に落ち着いている。 低迷状態に拍車をかけたのが、1996 年に発覚した「TBS ビデオ事件」を始めとした不祥
事が相次いだことである。TBS の報道倫理・報道姿勢を厳しく批判され、今まで築き上げ
てきた報道の自信や信頼を失うことになった。 近年では 2000 年 4 月以降、他社に先駆けて分社化を断行した。制作部門を 3 社(エンタ
テイメント・ライブ・スポーツ)に分け、2001 年 10 月にはラジオ部門を分割させた。こ
のラジオ部門の分割により、TBS は兼営局からテレビ単営局となった。2004 年には分社化
した制作部門 3 社を統合し、テレビ事業全般を行う子会社「TBS テレビ」を発足させた。 2002 年には不動産事業が赤坂再開発に参加している。既存施設の解体作業に入り、業務
棟・文化施設棟・住宅棟を平成 20 年 1 月には竣工する計画となっている。この事業規模・
資金調達方法などについて検討を重ね、将来の収入源の確保に努めていく。 経営戦略
TBSの経営戦略で一番重要なポイントは赤坂再開発事業による不動産事業の拡大である。
赤坂再開発事業とは、TBS旧社屋跡地の再開発を目的に、土地所有者であるTBSとディベ

放送業界~日テレ・TBS・フジテレビ・テレ朝~ (池田・中井・中村)
62
ロッパーである 三井不動産によって行われた計画である。TBS旧社屋跡地に 2008 年 3 月
にグランドオープンが予定されている「赤坂サカス」によって、TBS放送センター周辺の
オフィス・商業棟および住居棟の充実を図り、2010 年度までに売上高 130 億円、営業利益
70 億円を達成するという事業計画を立てているのだ。台場の フジテレビ、汐留の 日テレ、
六本木の テレビ朝日に続き、「赤坂サカス」を完成させることで、放送局を中心とした「街」
を作り、東京の新名所とすることが目的である。このようにして、TBSは「赤坂サカス」
をオープンすることで、放送事業以外の収入の拡大を目指しているのだ。
また、TBS は全日平均視聴率を 9%台にすることを目標に掲げている。そのために、番
組編成の見直しや、プロデューサー研修制度の確立により、視聴者が飽きない番組・番組
編成を行っていくのである。コンテンツ制作力をあげ、コンテンツのマルチユースにも力
を入れていく。
(3) フジテレビ
企業の特徴 フジテレビは、すでに 1954 年に開局していたラジオのニッポン放送を母体として、1959
年 3 月に開局した。当時、フジテレビは、テレビ・ラジオ・新聞の三大メディアを中心と
したグループ形勢によって相互の企業力向上を図ったのである。このメディアの相互作用
のノウハウを生かし、現在、放送・映画・ビデオ・出版・イベントなどの複合的メディア
体制を築き上げてきたのだ。 フジテレビの一般的なイメージと言えば、バラエティ番組が多い放送局というイメージ
が挙げられる。この傾向は、1980 年代から「楽しくなければフジじゃない」というキャッ
チフレーズを打ち出し、面白い番組・視聴者の笑いを誘う番組を制作するという意識が生
まれたことで、今のバラエティのフジテレビが確立された。当時の代表的な番組は、「おれ
たちひょうきん族」や「笑っていいとも」などが挙げられる。 その結果、フジテレビは消費活動が活発な若年層の視聴率が高い番組が多いことから、
広告の費用対効果を考えた上で広告主からの評価が高い企業である。しかし、フジテレビ
の番組はバラエティやトレンディードラマが中心となっており、報道・教養・ドキュメン
タリーなどの番組が充実していないため、「軽チャー路線」と社会的モラルの低下を促すと
批判される側面も持っているのである。ここまでで挙げた特徴は、放送局としての特徴で
ある。 フジテレビは企業としても大きな特徴を持っている。それは、ラジオ放送局である「小」
のニッポン放送に、「大」のフジテレビが所有されていたという、資本のねじれ現象が起き
ていたということである。フジテレビが、この資本のねじれ現象を改善するために、ニッ
ポン放送を完全子会社化しようとした際に起きたのが、ライブドア買収事件である。 2005 年 2 月から起きたライブドア買収事件は、ライブドアがフジテレビを実質的に支配
するため、フジテレビの筆頭株主に当たるニッポン放送の株を大量に取得することで、ニ

放送業界~日テレ・TBS・フジテレビ・テレ朝~ (池田・中井・中村)
63
ッポン放送の持つフジテレビの株をも取得し、フジテレビの筆頭株主になろうとしたので
ある。ライブドアはフジテレビを支配することで、フジテレビの持つコンテンツを自社の
事業に転用しようと考えていたのである。しかし、結果的に、ライブドアとフジテレビは
業務提携することとなり、ニッポン放送はフジテレビの完全子会社となったのだ。 フジテレビはこの事件で、ニッポン放送完全子会社化に成功したことで、大幅な事業拡
大が可能となったのだ。 また、この事件は、近年 M&A が活発化している中で、資本のねじれ現象は企業にとっ
て大きな弱点となることを浮彫りにし、放送業界は今までのように、規制に守られている
からといって安閑としていられないことを明らかにしたのである。 経営戦略 フジテレビの経営方針は「メディア・コンプレックス」の展開と、「デジタル・コンテン
ツ・ファクトリー」の構築という二つを掲げている。 「メディア・コンプレックス」の展開とは、放送・映画・ビデオ・出版・イベントなど
のメディアの連携がとれるよう、複合的メディア体制を目指すということである。「メディ
ア・コンプレックス」を展開することで、イベントや権利ビジネスといった事業を拡大し、
収益の多元化を実現することが可能となってくるのだ。 「メディア・コンプレックス」という土台を最大限活用するための、2 次利用、3 次利用
が可能なデジタルコンテンツの制作が必要になるため、「デジタル・コンテンツ・ファクト
リー」の構築を目指している。「デジタル・コンテンツ・ファクトリー」の構築については、
2007 年 9 月 14 日に完成した新スタジオ「湾岸スタジオ」によって実現を目指している。
また、「湾岸スタジオ」では、実際に映画の撮影で使用された衣装や小道具のほか、レアな
制作物の数々を展示し、一般見学者の入場も可能にしているため、お台場のランドマーク
化による集客効果の向上も見込めるのである。 しかし、なぜフジテレビは、デジタルのコンテンツにこだわっているのかというと、コ
ンテンツをデジタル化することで、企画から収録・編集までのコンテンツ制作一貫体制を
とることができ、創造性・作業効率・費用効率の向上、コンテンツの質の向上を図ること
が可能だからである。さらに、従来のテープによる収録や編集ではなく、制作段階にデジ
タル技術を導入することで、人件費の削減を柱として大幅なコストダウンが図れることが
大きなメリットである。また、デジタルコンテンツは 2 次利用、3 次利用する際に、アナロ
グコンテンツよりも、データ転送が容易なため効率が上がるため、「メディア・コンプレッ
クス」を最大限利用することに力を入れているフジテレビにとって、コンテンツのデジタ
ル化は必要不可欠なのである。 このように、フジテレビは広告収入が落ち込む中、効率のよいコンテンツ制作を可能に
することでコストを抑え、高収益体質を維持しようとしているのである。 経営計画から、フジテレビは、放送業界で何が一番必要となってくるのかを、逸早く感
じ取り、業界の動向に合った経営戦略をとっていると言える。

放送業界~日テレ・TBS・フジテレビ・テレ朝~ (池田・中井・中村)
64
(4) テレビ朝日
企業の特徴 教育用に開放するという政策の下、テレビ朝日は 1959 年に、「日本教育テレビ」として
設立された。そのため放送内容は、教育・教養番組を 80%以上、報道番組と広告について
は若干に限るという厳しい条件下のスタートであった。この CM 放送が限定されてしまう
経営苦況は 1973 年の総合番組局になるまで続いた。総合番組局へと移行した際に、社名か
ら教育の文字を外し「全国朝日放送」、略称をテレビ朝日として再出発をした。 テレビ朝日は、映画会社の東映が経営に携わったこともあり、その技術を生かしてスタ
ートさせた「日曜洋画劇場」(1966 年~)は現在も続く長寿番組となり、民放の映画番組の
原型となった。また、ニュース番組を朝の時間帯に編成し、主婦層を獲得したことで他の
放送局を刺激した。 1985 年にはプライムタイムに、大型ニュース番組「ニュースステーション」を開始した。
現在でも「スーパーJ チャンネル」「報道ステーション」に代表されるニュース番組や「朝
まで生テレビ!」「サンデープロジェクト」などの討論番組の制作を得意としており、報道
に強い局としてのイメージ作りを図っている。 このような時代を先取った番組編成や番組作りが可能であるのにも関わらず、「万年視聴
率 4 位」、「振り向けばテレビ東京」と視聴率の低い局として業界 4 位に留まっていた。そ
こで 1990 年代後半から 2000 年代初期まではそれほど多くなかったプライムタイムのバラ
エティ番組を、2004 年 10 月の改編以降、大幅に増やした。その結果、2005 年度には 23時以降のバラエティ番組が高視聴率となり、プライムタイムの視聴率が開局以来初の 2 位
となった。それに加え、スポーツのビッグイベント中継が強みとなり、2006 年には世界水
泳、サッカーW 杯アジア予選(2008 年までの独占放送権獲得)などでプライムタイムの視
聴率を上げてきている。 経営戦略 テレビ朝日は、コンテンツ力の強化を最優先事項としている。なぜなら、売上高に最も
大きく関係する視聴率の向上を目指すとともに、費用の更なる効率的運用に注力すること
で、利益の拡大を図り、企業価値を高めていくことを最重要視しているため、まずは、コ
ンテンツ力の強化が必要不可欠となっているのである。主に番組制作費の集中投下をする
ことでコンテンツ力の強化を図っている。具体的に言うと、現場への人員投入、制作会社
やアーティスト・マネージメント会社との関係強化、スポーツコンテンツへの継続的な投
資を行うことである。 また、平成 16 年度、平成 17 年度にかけて、プライムタイムの視聴率が向上した背景に
は、番組編成において他局とは違った 2 つの手法をとっていることがうかがえる。1 つ目は
強い相手局の時間帯・視聴ターゲット層を避け、「空き」のあるところを狙う「カウンター
戦略」である。2 つ目に自局の番組の流れを意識して、同一ターゲットを逃がさない番組を
挿入する「フロー戦略」である。今後も、この 2 つの戦略を推し進めていくのである。

放送業界~日テレ・TBS・フジテレビ・テレ朝~ (池田・中井・中村)
65
さらに、景気に左右されにくい高収益体質へと脱皮するために、放送事業以外の収入拡
大を目指している。主に、テレビドラマ、映画上映、DVD 販売の 3 つによるシナジー効果
を生み出すことを鍵としているのだ。他にも、テレショップ事業、音楽出版事業と強化を
図っている。 以上のように、企業の特徴と経営戦略の分析を行うことで、各企業が現在どのような状
況にあり、どのように経営しているかが把握できた。 最後に今までの分析を基に、戦略課題と展望を述べ、本論文を締めくくりとする。
4.戦略課題と展望
(中村圭介) 今までの、業界概要、経営戦略の分析を行うことで、業界と各企業の動向が明らかとな
った。これらを比較することで、今後の各企業の戦略課題と展望の提案を行う。
4-1. 戦略課題
(1) 日本テレビ
日本テレビはコンテンツ制作力を強化し、マルチコンタクトポイント戦略により、コ
ンテンツの 2 次利用・多角的配信を行うという戦略をとっている。コンテンツの 2 次利用・
多角的配信を行うということは、コンテンツを活かし放送外事業の収入も増やすことを目
的としているため、業界動向にマッチした戦略であると言える。 しかし、成長性を分析することで、放送外事業の収入は増加傾向にあるものの、視聴率
低迷により、放送事業収入の減少傾向により、全体の業績が悪くなっていっていることが
分かった。日本テレビにとって視聴率低迷が、業績不振の大きな要因となっている。よっ
て、日本テレビの最優先事項といえる戦略課題は放送事業収入減少傾向を阻止することで
ある。 視聴率の低迷を阻止するためには、経営戦略で挙げているように、コンテンツ制作力の
強化と、若年層の視聴者獲得に注力することが重要である。そのためには、無駄なコスト
を削減し、番組制作費へ回すことが重要である。、 また、収益性分析から総資本回転率の低下を改善しなければならない課題が出てくる。
日本テレビは、総資本は増加しているのにも関わらず、売上高に反映されていないのであ
る。これは、マルチコンタクトポイント戦略を推し進めるばかりで、収入につながる事業
展開が出来ていないことに起因している。各事業の体制を見直す必要があると言える。 現状を改善しない限り、業界 2 位というポジションを、TBS やテレビ朝日に脅かされる
日はそう遠くないであろう。

放送業界~日テレ・TBS・フジテレビ・テレ朝~ (池田・中井・中村)
66
(2) TBS TBS は収益性での分析で分かるように、4 社の中で総資本回転率が一番低い。赤坂再開
発事業を行っているため、現在は回転率が低いとも言えるが、それ以上に広告収入を思う
ように伸ばすことが出来ていないことが原因である。【図 3-1-11】を見て分かるように、タ
イム CM 収入が少ない。タイム CM 収入を増やしていくためには、番組の企画力・制作力
の向上を図り、スポンサーに対する営業力の強化が必要である。TBS はプロデューサー研
修制度を設ける動きを見せている。これにより、どこまで番組の質を向上させられるかが
鍵となってくるであろう。 また、赤坂再開発事業による「赤坂サカス」が、今後どのような結果となるかも大きな
鍵となる。「赤坂サカス」を最大限に活かすために、積極的な広報活動を行うことが重要に
なるであろう。 さらに、安全性を分析した際に明らかとなった、4 社で唯一 100%を超えていた固定比率
を、今後、不動産事業の改善により、下げていくことも必要である。 TBS は「赤坂サカス」を中心とした不動産事業が、今後どのような業績となるかによっ
て放送業界でのポジションが大きく変わってくるであろう。
(3) フジテレビ
フジテレビは「メディア・コンプレックス」の展開と、「デジタル・コンテンツ・ファク
トリー」の構築を実現することを戦略としている。これは業界動向にもマッチした戦略で
あり、実際に業界の動向をしっかりと押さえ、最も業績を伸ばしているのは 4 社の中でフ
ジテレビである。フジテレビが行っている経営戦略は業界動向にマッチし、理にかなった
戦略である。 しかし、これといった「スキ」がない企業であるように思えたが、収益性を分析するこ
とで課題が明らかとなった。総資本回転率が少しずつではあるが減少傾向にある。それに
より、総資本経常利益率も減少傾向にある。事業を拡大するため積極的に連結子会社を増
やしだした平成 15 年度から、総資本回転率は下降の傾向を見せている。つまり、事業拡大
に注力しすぎることで、資本の運用効率が悪くなっている。「メディア・コンプレックス」
の展開や、放送外事業の拡大に囚われすぎず、企業の経営効率を上げることも意識しなけ
ればならない。 また、放送業界のリーディングカンパニーと位置づけられているフジテレビではあるが、
「放送と通信の融合」を意識したネット配信事業への取り組みは、日本テレビよりも劣っ
ている。 真のリーディングカンパニーとなるためには、今後、ネット配信事業への取り組み強化
も必要になってくると考えられる。

放送業界~日テレ・TBS・フジテレビ・テレ朝~ (池田・中井・中村)
67
(4) テレビ朝日
テレビ朝日は、コンテンツ力の強化と視聴率の向上を戦略としている。テレビ朝日は、
今後も視聴率にこだわり、依然、広告収入への依存度の高い戦略をとっていると言える。
現在、放送業界の広告収入は頭打ち状態にあるにもかかわらず、広告収入の拡大を狙って
いるため、業界動向にマッチした戦略とは言い難い。 しかし、業界 3 位のポジションにいるテレビ朝日が、ポジションを上げるための最短ル
ートを考えると、利益率も高く、今までのノウハウを最も活かすことが可能な広告収入の
拡大を行うことが最適であると考えることが出来る。そのため、一概にテレビ朝日の戦略
が間違っているとは言い難い。今は、この戦略でも問題がないかもしれないが、今後、業
界動向から完全に反れた戦略を行ってしまわないよう注意が必要だ。 また、収益性分析の結果、人件費、番組制作費を多くかけてしまうことで、他社に比べ
利益率が低いことが明らかとなった。人員配置の見直しや、無駄に番組制作費を掛けすぎ
ていないかを見直す必要がある。
4-2. 展望
放送業界はテレビという最大最強のメディアに絶対の自信を持っていた。しかし、近年
ではインターネット等の新たなメディアの登場により、テレビというメディアだけを信用
し事業を展開していくことに不安を抱く傾向が現れた。その結果、放送業界の最も重要な
キーワードとして、放送外事業の拡大が重要になってきた。経営戦略分析を行った結果、
各企業とも、放送外事業の拡大を行う上で最重要視するポイントは、コンテンツ制作力を
向上させることであることが分かった。本論文で取り上げた 4 社に共通していることは、
今までのコンテンツ制作のノウハウを活かし、様々なメディアへのコンテンツ配信を行う
ことでメディアシナジー効果を高めていく傾向が強いということだ。つまり、今までのテ
レビ局というイメージからトータルメディア企業へと進化し始めているのである。 この変化により、今後、視聴者は様々なメディアでテレビ局のコンテンツを視聴するこ
ととなり、日本のメディアに供給されるコンテンツのほとんどがテレビ局によって行われ
ていくであろう。
5.終わりに
(池田泰輔) 私たちは新たなメディアの登場により、大きな転換期に差し掛かった放送業界は縮小す
る傾向になると考え、本論文に取り組んだ。実際に業界を分析した結果、広告収入の頭打
ちにより放送業界は縮小傾向にあった。そのため、放送外事業の収入を増やしていくこと

放送業界~日テレ・TBS・フジテレビ・テレ朝~ (池田・中井・中村)
68
で縮小傾向に歯止めをかけなくてはならなかった。放送外事業を拡大していくことで新た
なコンテンツを創出し、放送業界にとって今まで脅威となっていたメディアを活用する必
要が生じてきた。つまり、2 次利用、3 時利用が可能なコンテンツを様々なメディアに活用
していくことが重要視されている。 現在、この動きを見せているのはフジテレビである。フジテレビは置かれている業界の
現状をいち早く察知し、リーディングカンパニーとして放送業界をリードしてきた。もし
仮に、フジテレビに追いつく可能性がある企業を本論文で比較した 3 社の中から挙げると
するならば、TBS であると考えられる。その理由は TBS が現在進めている赤坂再開発にあ
る。再開発が竣工した後、そこで行われる不動産事業によって安定的な収益を確保する可
能性があるからである。しかし、TBS の不動産事業が開始するのは、まだ先であるため、
今後も業界の動きや動向に注目していきたいと思う。

放送業界~日テレ・TBS・フジテレビ・テレ朝~ (池田・中井・中村)
69
参考資料
日本テレビ 貸借対照表 (百万円)
平成 13 年度 平成 14 年度 平成 15 年度 平成 16 年度 平成 17 年度 平成 18 年度
(資産の部)
Ⅰ.流動資産 185,088 207,445 188,717 175,096 170,305 193,543
1.現金及び預金 43,880 54,422 59,829 49,045 41,434 47,163
2.受取手形及び売掛金 82,329 83,904 82,779 83,996 80,667 89,970
3.有価証券 40,743 37,838 18,530 20,007 19,951 28,186
4.棚卸資産 1,052 929 1,324 1,412 1,757 2,192
5.番組勘定 5,605 7,609 11,524 9,529 16,156 13,209
6.繰延税金資産 7,276 7,300 5,980 5,231 4,547 4,798
7.その他の流動資産 4,817 16,331 9,494 6,630 5,656 8,801
8.貸倒引当金 △ 617 △ 891 △ 746 △ 757 △ 774 △ 778
Ⅱ.固定資産 258,709 269,189 324,712 318,461 349,646 335,721
(Ⅰ)有形固定資産 175,002 199,162 231,368 218,590 206,134 197,301
1.建物及び構築物 12,279 11,688 66,213 63,966 59,751 56,437
2.機械設備及び運搬具 11,540 10,809 45,620 35,300 27,612 22,712
3.器具備品 1,917 1,803 4,146 3,902 3,488 2,966
4.土地 115,014 115,112 115,120 114,936 114,858 114,849
5.建物仮勘定 34,250 59,747 268 484 424 335
(2)無形固定資産 3,046 2,858 5,787 5,057 4,675 4,150
(3)投資その他の資産 80,660 67,168 87,556 94,814 138,836 134,269
1.投資有価証券 64,386 55,774 79,350 84,770 121,976 111,773
2.長期貸付金 67 68 57 5,554 5,001 4,554
3.繰延税金資産 852 6,292 312 552 746 1,039
4.長期預金 257 7 7,100 8,100
5.長期未収入金 11,739
6.その他の投資その他の資産 3,745 5,273 8,004 4,068 4,127 8,917
7.貸倒引当金 △ 387 △ 246 △ 168 △ 130 △ 116 △ 114
資産合計 443,798 476,634 513,429 493,557 349,646 529,265
(負債の部)
Ⅰ.流動負債 84,288 112,716 118,019 84,699 74,060 82,070
1.支払手形及び買掛金 12,280 6,937 7,186 7,160 6,408 8,117
2.短期借入金 900 35,764 45,902 11,500 103
3.未払金 9,487 5,768 2,306 6,924 3,425 4,497

放送業界~日テレ・TBS・フジテレビ・テレ朝~ (池田・中井・中村)
70
4.未払費用 44,584 49,086 52,482 48,078 54,778 54,932
5.未払法人税等 12,858 12,191 2,255 6,640 5,119 8,520
6.役員賞与引当金 50
7.返品調整引当金 145 95 99 45 50 120
8.設備関係支払手形 2,049 544 5,118 1,374 1,659 1,530
9.その他の流動負債 1,982 2,325 2,666 2,976 2,618 4,198
Ⅱ.固定負債 34,465 34,542 38,099 37,046 40,902 35,199
1.繰延税金負債 1,031 4,545 4,964 12,756 7,760
2.退職給付引当金 13,576 14,253 12,541 9,355 4,523 5,280
3.役員退職慰労引当金 845 939 965 1,082 1,019 1,149
4.長期預り保証金 19,000 19,344 20,046 20,126 20,143 20,155
5.その他 12 5 1,517 2,460 853
負債合計 118,753 147,258 156,118 121,746 114,962 117,270
(少数株主持分)
少数株主持分 1,725 2,259 3,264 5,165 6,971 7,820
(資本の部)
Ⅰ.資本金 18,575 18,575 18,575 18,575 18,575 18,575
Ⅱ.資本準備金 17,928 17,928 17,928 17,928 17,928 17,928
Ⅲ.連結剰余金 282,364 299,476 316,418 330,170 350,025 363,525
Ⅳ.その他有価証券評価差額金 4,718 774 10,834 9,666 21,084 14,028
Ⅴ.為替換算調整勘定 △ 101 △ 109 △ 179 △ 159 △ 56 12
Ⅵ.自己株式 △ 166 △ 9,529 △ 9,531 △ 9,535 △ 9,540 △ 9,896
資本合計 323,319 327,116 354,046 366,645 398,017 411,994
負債、少数株主持分及び資本合計 443,798 476,634 513,429 493,557 519,951 529,265
日本テレビ 損益計算書 (百万円)
平成 13 年度 平成 14 年度 平成 15 年度 平成 16 年度 平成 17 年度 平成 18 年度
Ⅰ.売上高 358,682 336,299 328,374 357,614 346,642 343,651
Ⅱ.売上原価 218,888 215,180 217,844 245,109 242,643 238,913
売上総利益 139,793 121,118 110,530 112,505 103,999 104,738
Ⅲ.販管費及び一般管理費 76,220 73,712 74,593 78,179 75,448 74,393
1.代理店手数料 50,629 48,150 46,365 49,192 46,821 45,654
2.人件費 10,347 10,454 10,299 9,710 9,686 9,557
3.退職給付費用 528 798 232 312 329 524

放送業界~日テレ・TBS・フジテレビ・テレ朝~ (池田・中井・中村)
71
4.役員賞与引当金繰入額 50
5.役員退職慰労引当金繰入額 149 153 153 171 174 193
6.業務委託・外注要員費 726 817 1,099 890 1,002 1,228
7.水道光熱費 600 543 1,432 1,361 1,205 1,233
8.租税公課 1,271 1,962 2,213 2,370 2,551 2,614
9.減価償却費 840 848 1,452 1,637 1,531 1,402
10.諸経費 11,125 9,982 11,345 12,533 12,144 11,935
営業利益 63,573 47,406 35,937 34,325 28,551 30,344
Ⅳ.営業外収益 1,114 1,002 1,472 1,470 1,949 3,907
1.受取利息 442 338 221 205 285 205
2.受取配当金 250 340 487 579 763 822
3.持分法による投資利益 715
4.為替差益 83
5.投資事業組合運用益 232 464 1,217
6.その他の営業外収益 421 324 763 453 436 562
Ⅴ.営業外費用 2,025 2,076 629 205 485 109
1.支払利息 9 58 133 69 10 1
2.投資有価証券売却損 463
3.持分法による投資損失 1,412 1,638 430 88 182
4.投資事業組合運用損 80 253 58
5.為替差損 62
6.有価証券償還損 186
7.その他の営業外費用 59 125 45 46 42 49
経常利益 62,662 46,332 36,800 35,591 30,014 34,142
Ⅵ.特別利益 352 312 1,043 83 772 590
1.固定資産売却益 42 9 935 5 1 57
2.投資有価証券売却益 212 1 5 64 34 75
3.退職給付制度一部終了益 686
4.保険解約金収入 429
5.貸倒引当金戻入額 97 186 102 13
6.持分変動益 115
7.その他の特別利益 28
Ⅶ.特別損失 647 8,680 3,290 3,888 4,411 2,320
1.固定資産除却損 124 228 796 1,164 443 36
2.固定資産売却損 18 10 475 309 115 372
3.投資有価証券評価損 341 6,679 557 145 3,799 1,416
4.投資有価証券売却損 110 8 4 2

放送業界~日テレ・TBS・フジテレビ・テレ朝~ (池田・中井・中村)
72
5.遺跡調査関連費用 1226
6.新社屋移転関連費用 673
7.開局 50 周年記念事業費用 771
8.退職給付制度移行損失 2,268 374
9.その他の特別損失 52 526 12 50 120
税金等調整前当期純利益 62,367 37,965 34,553 31,787 26,325 32,413
法人税、住民税及び事業税 27,332 20,714 9,247 11,415 10,429 13,183
法人税等調整額 △ 105 △ 3,588 4,941 1,726 385 △ 510
少数株主利益 492 544 1,005 1,797 1,810 1,408
当期純利益 34,648 20,295 19,359 16,847 13,700 18,331
TBS 貸借対照表
(百万円) 平成 13 年度 平成 14 年度 平成 15 年度 平成 16 年度 平成 17 年度 平成 18 年度
(資産の部)
Ⅰ.流動資産 160,042 152,596 144,874 173,990 133,165 115,679
1.現金及び預金 62,351 65,626 57,661 52,724 38,859 48,946
2.受取手形及び売掛金 61,001 61,127 62,988 61,872 68,084 43,309
3.有価証券 12,808 2,381 1,003 19,999
4.棚卸資産 9,489 9,181 11,930 11,419 10,741 10,079
5.前払費用 7,460 8,181 4,831 6,694 6,707 4,276
6.繰延税金資産 2,968 3,079 3,343 5,696 5,271 5,346
7.その他の流動資産 4,007 3,130 3,333 15,719 3,664 3,851
8.貸倒引当金 △ 4 △ 44 △ 217 △ 137 △ 162 △ 130
Ⅱ.固定資産 362,087 291,181 339,730 332,135 422,106 452,042
(Ⅰ)有形固定資産 172,185 174,094 178,862 180,446 189,212 199,200
1.建物及び構築物 79,745 77,031 72,150 70,245 67,772 64,623
2.機械設備及び運搬具 12,374 12,829 15,827 19,915 18,691 17,361
3.工具器具備品 1,842 1,920 1,909 2,806 2,843 2,671
4.土地 76,222 76,138 76,156 76,479 76,292 76,286
5.建物仮勘定 2,000 6,173 12,817 11,000 23,613 38,257
(2)無形固定資産 5,710 4,155 5,366 7,374 7,746 7,065
1.連結調整勘定 2,326 411 654 898
2.ソフトウェア 3,041 3,101 3,167 5,807 5,886 5,639
3.ソフトフェア仮勘定 33 356 1,241 396 315 14
4.その他の無形固定資産 308 287 303 272 1,544 1,411

放送業界~日テレ・TBS・フジテレビ・テレ朝~ (池田・中井・中村)
73
(3)投資その他の資産 184,191 112,931 155,502 144,313 225,146 245,775
1.投資有価証券 165,878 95,949 142,509 131,644 213,624 233,800
2.出資金 213 147 204
3.長期貸付金 244 562 515 392 548 505
4.繰延税金資産 1,223 1,392 860 1,197 1,238 1,366
5.長期前払費用 7,902 6,551 4,682 3,326 849 1,033
6.その他の投資その他の資産 9,190 8,862 7,307 8,188 9,438 9,679
7.貸倒引当金 △ 460 △ 535 △ 577 △ 435 △ 552 △ 610
資産合計 522,129 443,778 484,605 506,125 555,271 567,722
(負債の部)
Ⅰ.流動負債 80,935 73,294 71,241 84,433 82,282 76,433
1.支払手形及び買掛金 28,640 28,416 26,731 26,290 32,164 33,243
2.一年内償却予定社債 10,000 10,000 10,000
3.一年内償還予定転換社債 12,040
4.短期借入金 13,768 9,091 5,759 3,289 1,606
5.一年内返済予定長期借入金 72 72 5,472 72 72 10,040
6.未払金 14,916 14,104 17,185 22,663 20,441 17,452
7.未払法人税等 4,996 6,809 4,180 8,734 6,059 3,552
8.未払消費税等 791 1,366 776 586 949 1,070
9.未払費用 4,950 4,455 4,672 5,848 4,465 4,735
10.役員賞与引当金 322
11.その他の流動負債 4,557 4,300 3,131 4,479 4,839 4,410
Ⅱ.固定負債 104,633 70,464 85,544 95,328 93,303 105,990
1.社債 20,000 20,000 20,000 10,000 30,000
2.長期借入金 15,779 15,657 10,184 30,112 30,040 20,000
3.退職給付引当金 5,975 5,193 13,259 8,160 9,196 9,293
4.役員退職慰労引当金 1,271 1,477 1,274 641
5.繰延税金負債 57,264 24,656 38,030 28,943 41,244 39,253
6.連結調整勘定 719
7.負ののれん 332
5.その他の固定負債 4,341 3,479 2,796 17,470 93,303 7,110
負債合計 185,569 143,758 156,786 179,761 175,585 105,990
(少数株主持分)
少数株主持分 5,614 1,732 1,711 1,639 1,659 2,411
(資本の部)
Ⅰ.資本金 44,162 44,163 44,163 44,163 54,685 54,857
Ⅱ.資本準備金 41,429 42,561

放送業界~日テレ・TBS・フジテレビ・テレ朝~ (池田・中井・中村)
74
Ⅲ.連結剰余金 165,259 172,896
Ⅳ.資本剰余金 42,561 42,561 59,953 60,125
Ⅴ.利益剰余金 174,970 182,924 192,297 202,094
Ⅵ.その他有価証券評価差額金 80,069 39,065 64,863 55,529 71,116 65,154
Ⅶ.為替換算調整勘定 79 24 △ 40 △ 32 13 16
Ⅷ.自己株式 △ 15 △ 424 △ 410 △ 422 △ 39 △ 63
Ⅸ.子会社の所有する親会社株式 △ 39
Ⅹ.繰延ヘッジ損益 700
資本合計 330,946 298,287 326,107 324,724 278,026 385,298
負債、少数株主持分及び資本合計 522,129 443,778 484,605 506,125 555,271 567,722
TBS 損益計算書
(百万円) 平成 13 年度 平成 14 年度 平成 15 年度 平成 16 年度 平成 17 年度 平成 18 年度
Ⅰ.売上高 291,255 294,839 301,731 301,731 306,041 318,700
Ⅱ.売上原価 193,027 197,991 210,956 210,956 218,658 221,798
売上総利益 98,227 96,847 90,774 90,774 87,382 96,901
Ⅲ.販管費及び一般管理費 66,985 72,521 67,820 68,264 70,977 71,573
1.人件費 12,956 12,164 11,355 10,854 11,053 11,533
2.代理店手数料 37,905 37,829 37,499 38,115 38,983 40,398
3.広告宣伝費 1,797 2,030 2,024 1,999 1,918 1,800
4.業務委託費 3,120 3,370 2,845 2,614 2,650 3,798
5.退職給付費用 1,129 3,206 860 763 1,680 631
6.役員退職慰労引当金繰入額 126 139 123 154 136 322
7.減価償却費 1,790 1,835 1,766 1,779 1,771 1,608
8.連結調整勘定償却額 116
9.その他の経費 8,158 11,828 11,348 11,986 12,786 11,483
営業利益 31,242 24,326 25,271 22,510 16,404 25,327
Ⅳ.営業外収益 2,005 1,264 1,120 2,094 1,874 3,104
1.受取利息 214 277 60 47 52 207
2.受取配当金 840 247 356 1,086 1,076 1,945
3.有価証券売却益 6 0
4.為替差益 27 113 2
5.連結調整勘定償却額 243 281 230
6.負ののれん調整勘定 344

放送業界~日テレ・TBS・フジテレビ・テレ朝~ (池田・中井・中村)
75
7.消費税等差額 468 95
8.保険金収入 262 160 249 98 261
9.その他の営業外収益 476 380 300 401 302 342
Ⅴ.営業外費用 3,908 2,551 2,488 2,623 2,890 2,215
1.支払利息 854 469 199 123 95 634
2.為替差損 136
3.社債償還損 682
4.持分法による投資損失 2,122 1,358 1,845 1,459 1,808 705
5.固定資産除却損 152 390 263 767 536 353
6.その他の営業外費用 97 332 43 273 449 521
経常利益 29,339 23,039 23,903 21,981 15,388 26,216
Ⅵ.特別利益 3,067 3,803 949 5,509 16,945 210
1.投資有価証券売却益 212 360 904 371 16,945 168
2.退職給付信託設定益 2,830 2,001 5,026
3.持分変動益 915
4.営業権譲渡益 505
5.関係会社清算益 80
6.抱合せ株式消滅差益 28
7.その他の特別利益 24 19 44 30 12
Ⅶ.特別損失 4,157 3,112 14,547 10,289 4,719 2,616
1.退職給付費用 3,497 10,443
2.投資有価証券評価損 582 1,627 788 517 144 185
3.割増退職金 302 126 23 15
4.前渡金償却 340
5.固定資産除却損 2665 464 389 472
6.退職給付制度終了損失 8,485
7.過年度人件費 743 443 31
8.減損損失 285 5
9.長期前払費用償却額 1,203
10.連結調整勘定償却額 1,861
11.環境特別対策費 267
12.年金訴訟和解金 990
13.年金制度移行解決金 860
8.その他の特別損失 77 843 523 55 107 70
税金等調整前当期純利益 28,248 23,729 10,305 17,201 27,615 23,810
法人税、住民税及び事業税 12,860 14,021 10,527 12,802 121,326 8,376
法人税等調整額 283 △ 1,068 △ 4205 △ 5324 2,001 1,455

放送業界~日テレ・TBS・フジテレビ・テレ朝~ (池田・中井・中村)
76
少数株主利益(控除) 452 177 △ 93 △ 167 △ 37 678
当期純利益 14,651 10,599 4,076 9,890 13,513 13,299
フジテレビ 貸借対照表
(百万円) 平成 13 年度 平成 14 年度 平成 15 年度 平成 16 年度 平成 17 年度 平成 18 年度
(資産の部)
Ⅰ.流動資産 214,317 217,978 335,416 318,810 261,031 283,029
1.現金及び預金 24,998 27,188 26,665 38,855 49,986 46,368
2.受取手形及び売掛金 95,872 95,071 96,978 98,127 111,958 119,763
3.有価証券 47,014 53,196 115,240 135,881 30,008 58,697
4.棚卸資産 28,704 24,867 20,968 22,557 22,517 23,152
5.繰延税金資産 4,536 4,159 4,840 6,256 5,424 7,173
6.信託受益権 59,781
7.その他の流動資産 13,538 13,966 11,211 17,311 41,591 28,245
8.貸倒引当金 △ 347 △ 471 △ 270 △ 179 △ 454 △ 372
Ⅱ.固定資産 271,277 262,935 290,370 362,380 431,308 448,467
(Ⅰ)有形固定資産 132,523 130,019 113,232 127,626 154,342 179,893
1.建物及び構築物 104,847 100,512 93,685 89,484 89,898 84,957
2.機械設備及び運搬具 8,129 9,678 10,549 13,302 16,372 17,451
3.土地 15,563 15,415 4,388 20,340 27,079 27,080
4.建物仮勘定 846 1,396 1,405 1,287 11,439 41,090
5.その他有形固定資産 3,136 3,016 3,204 3,211 9,550 9,314
(2)無形固定資産 19,653 21,846 33,069 43,598 45,461 53,881
1.営業権 1,674
2.のれん 8,616
3.借地権 14,403 14,395 14,393 14,393 15,356 15,356
4.ソフトウェア 4,314 6,592 10,080 12,839 15,521 17,333
5.連結調整勘定 269 180 1,578 3,774
6.その他の無形固定資産 665 678 7,016 12,590 12,908 12,575
(3)投資その他の資産 119,100 111,069 144,068 191,155 231,504 214,691
1.投資有価証券 98,196 85,916 132,014 176,097 211,197 192,027
2.長期貸付金 95 68 65 102 920 1,231
3.繰延税金資産 10,765 16,381 3,321 3,614 3,873 3,584
4.その他の投資 11,239 9,813 9,778 15,317 20,277 20,307
5.貸倒引当金 △ 1197 △ 1109 △ 1,112 △ 3,975 △ 4,763 △ 2,459

放送業界~日テレ・TBS・フジテレビ・テレ朝~ (池田・中井・中村)
77
資産合計 485,594 480,913 625,786 681,190 692,357 731,496
(負債の部)
Ⅰ.流動負債 83,072 81,730 83,600 98,152 105,738 150,545
1.支払手形及び買掛金 44,245 43,402 43,637 45,540 51,330 58,905
2.短期借入金 2,654 2,349 2,072 2,015 5,989 5,490
3.未払法人税等 8,179 4,744 5,849 14,668 2,373 16,535
4.返品調整引当金 198 147 131 138 839 917
5.契約解除損失引当金 16
6.役員賞与引当金 401
7.その他の流動負債 27,794 31,087 31,908 35,772 45,206 68,295
Ⅱ.固定負債 23,893 26,342 32,635 93,864 114,793 111,364
1.社債 50,000 49,984
2.新株予約権付社債 332 63223 366 369
3.長期借入金 227 293 1,904 2,091
4.繰延税金負債 6,158 3,219 22,077 12,283
5.退職給付引当金 20,087 23,437 23,232 23,863 30,794 31,683
6.役員退職慰労引当金 2,038 2,349 2,123 2,880 3,327 3,441
7.連結調整勘定 5,439
8.負ののれん 10,598
7.その他固定負債 1,541 575 788 383 885 911
負債合計 106,966 108,072 116,235 192,017 220,532 291,909
(少数株主持分)
少数株主持分 4,655 5,043 7,680 10,084 8,921 6,645
(資本の部)
Ⅰ.資本金 59,764 59,764 106,200 114,750 146,200 146,200
Ⅱ.資本準備金 87,228
Ⅲ.再評価差額金 2,075
Ⅳ.連結剰余金 217,716
Ⅴ.資本剰余金 87,228 133,664 142,214 175,275 173,664
Ⅵ.利益剰余金 230,167 252,821 272,090 269,855 141,364
Ⅶ.土地再評価差額金 2,111 2,108 2,103 △ 435 △ 454
Ⅷ.その他有価証券評価差額金 12,558 4,586 24,199 18,545 32,621 17,448
Ⅸ.為替換算調整勘定 491 77 △ 985 △ 1,236 237 223
Ⅹ.自己株式 △ 5,862 △ 16,139 △ 16,139 △ 69,380 △ 160,851 △ 15,505
資本合計 373,973 367,796 501,870 479,088 462,903 469,586
負債、少数株主持分及び資本合計 485,594 480,913 625,786 681,190 682,357 731,496

放送業界~日テレ・TBS・フジテレビ・テレ朝~ (池田・中井・中村)
78
フジテレビ 損益計算書 (百万円)
平成 13 年度 平成 14 年度 平成 15 年度 平成 16 年度 平成 17 年度 平成 18 年度
Ⅰ.売上高 436,902 429,004 455,945 476,733 593,493 582,660
Ⅱ.売上原価 269,356 271,605 289,371 301,561 383,592 379,444
売上総利益 167,545 157,398 166,574 175,172 209,901 203,215
Ⅲ.販管費及び一般管理費 121,610 120,130 122,509 131,591 159,176 160,889
1.代理店手数料 52,875 51,759 52,242 56,271 61,300 60,510
2.宣伝広告費 15,685 16,315 17,120 18,878 21,413 23,269
3.人件費 16,954 17,338 17,744 18,488 22,644 21,904
4.役員退職慰労引当金繰入額 378 359 316 362 483 401
5.連結調整勘定償却額 84 307 547 407 554
6.のれん償却額 1,426
7.貸倒引当金繰入額 28 149 5 302
8.研究開発費 320 427 474 341 358 372
営業利益 45,935 37,268 44,065 43,581 50,724 42,325
Ⅳ.営業外収益 3,367 3,722 4,065 3,036 4,998 7,473
1.受取利息 207 257 264 352 294 393
2.受取配当金 350 368 341 723 1,073 1,894
3.連結調整勘定償却額 26
4.受取賃貸料 2,540 2,444 2,399 1,064 1,155 1,124
5.持分法による投資利益 597 657 1,312 2,536
6.有価証券売却益 14 23 14
7.貸株に係る品貸料 402
8.その他の営業外収益 242 651 462 224 737 1,509
Ⅴ.営業外費用 4,609 3,247 2,566 2,138 5,383 3,803
1.支払利息 192 147 126 123 404 921
2.持分法による投資損失 2,210 1,336
3.賃貸費用 1,311 1,263 1,164 851 857 837
4.パートナーシップ投資損失 648 594
5.新株発行費 474 94 532
6.社債発行費 68 215
7.公開買付費用 188
9.投資事業組合投資損失 1,948 1,535
10.支払手数料 356
11.その他の営業外費用 894 498 152 218 1,067 508
経常利益 44,694 37,744 45,564 44,478 50,340 45,995

放送業界~日テレ・TBS・フジテレビ・テレ朝~ (池田・中井・中村)
79
Ⅵ.特別利益 2,474 1,289 590 88 11,922 230
1.固定資産売却益 35 125 304 8 7 46
2.投資有価証券売却益 26 12 0 69 11,647 71
3.レバレッジドリース利益金 1,950 1,035 173
4.貸倒引当金戻入益 124 63 98
5.役員退職慰労引当金戻入益 97
6.契約解除損失引当金戻入益 7
7.会員権売却益 31
8.会員権預託金貸倒引当金戻入益 33
9.その他の特別利益 337 116 48 10 64 48
Ⅶ.特別損失 13,405 8,370 3,767 4,837 36,147 803
1.固定資産売却損 473 20 3,012 281 203 19
2.固定資産除却損 397 159 120 434 284 200
3.投資有価証券売却損 0 9 46 34,885 0
4.投資有価証券評価損 8,887 4,798 286 206 342
5.関係会社株式評価損 119 179
6.会員権等評価損 97 43 23 45 19 2
7.退職給付会計基準変更時差異償却
額 3,062 3,062
8.会員権預託金貸倒引当金繰入額 224 168 54 47 16
9.退職給付費用 351
10.貸倒引当金繰入額 2,503
11.契約解除損失引当金繰入額 16
12.契約解除損失 631
13.会員権売却損 6 1 0
14.特別退職金 70
15.その他の特別損失 263 109 86 301 318 151
税金等調整前当期純利益 33,763 30,663 42,387 39,730 26,115 45,422
法人税、住民税及び事業税 20,543 15,022 13,435 19,475 9,607 20,858
法人税等調整額 △ 4,390 358 3,339 △ 1,456 3,769 △ 1,036
少数株主利益 307 465 897 △ 1,134 1,392 753
当期純利益 17,303 14,816 24,714 22,845 11,345 24,846

放送業界~日テレ・TBS・フジテレビ・テレ朝~ (池田・中井・中村)
80
テレビ朝日 貸借対照表 (百万円)
平成 13 年度 平成 14 年度 平成 15 年度 平成 16 年度 平成 17 年度 平成 18 年度
(資産の部)
Ⅰ.流動資産 182,914 171,558 139,416 146,059 150,177 153,199
1.現金及び預金 63,332 49,351 31,164 31,766 27,971 16,215
2.受取手形及び売掛金 52,515 53,460 56,715 63,686 63,182 64,829
3.有価証券 45,469 45,500 26,001 30,621 37,882 48,453
4.棚卸資産 16,200 17,916 17,302 14,542 14,283 14,127
5.繰延税金資産 1,089 1,672 1,854 1,984 1,906 1,561
6.その他の流動資産 4,432 3,734 6,563 3,565 5,013 8,083
7.貸倒引当金 △ 124 △ 78 △ 185 △ 106 △ 73 △ 70
Ⅱ.固定資産 108,218 122,489 149,551 151,484 165,902 161,266
(Ⅰ)有形固定資産 52,216 67,844 68,808 65,898 63,060 21,896
1.建物及び構築物 11,219 10,349 23,777 23,419 22,642 21896
2.機械設備及び運搬具 12,932 9,904 25,315 23,483 21,418 19,038
3.土地 11,669 11,667 16,699 16,694 16,694 16,694
4.建物仮勘定 15,633 35,194 1,041 214 296 26
5.その他有形固定資産 762 728 1,974 2,086 2,008 2,010
(2)無形固定資産 3,900 5,069 7,049 7,132 6,256 5,779
1.ソフトウェア 3,572 4,777 6,703 6,790 5,930 5,468
2.その他無形固定資産 327 292 346 342 325 310
(3)投資その他の資産 52,100 49,575 73,693 78,453 96,585 95,819
1.投資有価証券 36,789 31,861 46,054 52,751 74,473 75,280
2.繰延税金資産 2,643 4,957 2,924 3,029 1,109 987
3.その他の投資その他の資産 13,452 13,325 25,121 23,147 21,367 19,734
4.貸倒引当金 △ 783 △ 568 △ 407 △ 475 △ 365 △ 182
資産合計 291,132 294,047 288,967 297,544 316,079 314,466
(負債の部)
Ⅰ.流動負債 54,081 57,989 48,659 51,921 50,655 47,102
1.支払手形及び買掛金 15,861 17,519 14,172 13,904 15,341 14,671
2.短期借入金 9,160 2,878 862
3.未払金 11,243 18,186 12,492 14,008 12,715 13,202
4.未払費用 12,063 11,791 13,591 15,336 15,317 16,713
5.未払法人税等 1,200 2,172 1,552 4,884 4,740 393
6.役員賞与引当金 218
9.その他の流動負債 4,550 5,442 5,988 3,786 2,541 1,902

放送業界~日テレ・TBS・フジテレビ・テレ朝~ (池田・中井・中村)
81
Ⅱ.固定負債 19,271 18,796 18,400 17,484 20,911 17,920
1.長期借入金 1,538 333
2.繰延税金負債 3,497 839
3.退職給付引当金 17,219 17,431 17,333 16,326 16,300 15,876
4.役員退職慰労引当金 430 929 964 980 935 1,020
5.その他 82 101 102 177 177 183
負債合計 73,353 76,786 67,060 69,405 71,566 17,920
(少数株主持分)
少数株主持分 1,264 1,418 1,399 1,409 1,664 2,292
(資本の部)
Ⅰ.資本金 36,642 36,642 36,642 36,642 36,642 36,642
Ⅱ.資本準備金 55,342
Ⅲ.連結剰余金 118,912
Ⅳ.資本剰余金 55,342 55,342 55,342 55,342 55,342
Ⅴ.利益剰余金 119,999 120,870 126,828 134,649 143,355
Ⅵ.その他有価証券評価差額金 5,538 3,830 7,984 7,961 16,185 11,776
Ⅶ.為替換算調整勘定 78 26 △ 32 △ 46 27 33
資本合計 216,515 215,842 220,508 226,729 242,848 249,443
負債、少数株主持分及び資本合計 291,132 294,047 288,967 294,544 316,079 314,466
テレビ朝日 損益計算書
(百万円) 平成 13 年度 平成 14 年度 平成 15 年度 平成 16 年度 平成 17 年度 平成 18 年度
Ⅰ.売上高 219,926 209,035 218,078 242,036 249,383 251,124
Ⅱ.売上原価 149,732 147,006 156,124 165,774 172,179 177,475
売上総利益 70,193 62,028 61,954 76,262 77,204 73,648
Ⅲ.販管費及び一般管理費 56,715 54,598 55,433 62,655 60,128 59,970
1.人件費 12,188 11,583 11,677 12,380 9,990 9,876
2.退職給付費用 531 544 587 622 474 440
3.代理店手数料 34,660 32,688 33,249 37,954 38,699 38,356
4.広告宣伝費 2,128 2,262 1,796 2,507 2,186 2,276
5.その他 7,206 7,521 8,122 9,191 8,777 9,020
営業利益 13,477 7,430 6,520 13,606 17,075 13,677
Ⅳ.営業外収益 854 727 780 1,010 1,126 1,383
1.受取利息 197 88 30 126 245 427
2.受取配当金 194 208 223 290 394 520

放送業界~日テレ・TBS・フジテレビ・テレ朝~ (池田・中井・中村)
82
3.その他の営業外収益 462 430 527 593 486 434
Ⅴ.営業外費用 1,578 1,225 1,408 1,023 887 473
1.支払利息 200 114 38 2 0
2.持分法による投資損失 971 905 1,222 901 688 205
3.固定資産廃棄損 136 111 75 61 164 68
4.その他の営業外費用 270 94 71 58 33 200
経常利益 12,753 6,932 5,893 13,592 17,314 14,587
Ⅵ.特別利益 794 793 659 300
1.六本木再開発受取補償金 781 780 659 300
2.固定資産売却益 12 12
Ⅶ.特別損失 1,566 2,656 2,756 961 85 18
1.六本木再開発関連損失 954 957 2,200 565
2.投資有価証券評価損 504 1,605 129 131 54 18
3.会員権評価損 90 31 1
4.貸倒引当金繰入額 17 61 31 11
5.その他の特別損失 393 281 31
税金等調整前当期純利益 11,981 5,069 3,796 12,931 7,228 14,568
法人税、住民税及び事業税 5,601 4,440 2,845 5,886 7,640 3,113
法人税等調整額 173 △ 1,482 △ 782 △ 440 △ 156 837
少数株主利益 267 203 45 103 278 313
当期純利益 5,939 1,907 1,687 7,382 9,466 10,303

放送業界~日テレ・TBS・フジテレビ・テレ朝~ (池田・中井・中村)
83
参考文献
小田正佳,『新 経営分析の卵-入門書を読む前に読む本-』株式会社税務経理協会 2005年 倉田三郎・藤永弘・石崎忠司・坂下紀彦,『入門 経営分析 三訂版』同文舘出版株式会
社 2005 年 河本久廣,『よくわかる放送業界』株式会社日本実業出版社 2006 年 西正,『図解放送業界ハンドブック』東洋経済新報社 1998 年 高橋香,『決定版 キャッシュフロー計算書の基本がよくわかる本』株式会社かんき出版
2007 年 中野明,『最新放送業界の動向とカラクリがよ~くわかる本』日経印刷株式会社 2005 年 『週刊ダイヤモンド』2007 年 6 月 2 日号 p28~58 電通 資料室 (http://www.dentsu.co.jp/marketing/index.html) ネットレイティングス・データクロニクス 2006 (http://csp.netratings.co.jp/nnr/PDF/Newsrelease03122007_J.pdf) フリー百科事典『ウィキペディア』
(http://ja.wikipedia.org/wiki) 日本テレビ 決算短信 2001 年~2006 年 (http://www.ntv.co.jp/ir/library/result/index.html)
TBS 決算短信 2001 年~2006 年 (http://www.tbs.co.jp/ir/ir_tansin.html) フジテレビ 決算短信 2001 年~2006 年 (http://www.fujitv.co.jp/index.html) テレビ朝日 決算短信 2001 年~2006 年 (http://company.tv-asahi.co.jp/contents/setnote/index.html) 日本テレビホームページ (http://www.ntv.co.jp/) TBS ホームページ (http://www.tbs.co.jp/) フジテレビホームページ (http://www.fujitv.co.jp/index.html) テレビ朝日ホームページ
(http://www.tv-asahi.co.jp/) 日経経営指標(2001~2005 年)