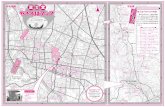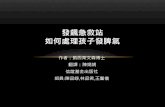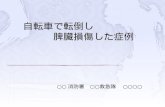宝 在 平民视角国家叙事, 山 线钢 《山海情》于质朴中抵达人 …dzb.whb.cn/imgPath/2021-01-17/10117.pdf里有一群各有脾性的人: 识大局却又暴脾
養生訓を考える - npoany.org ·...
Transcript of 養生訓を考える - npoany.org ·...

平成27年2月1日/毎月1日発行 NPO法人全日本薬膳食医情報協会 情報紙Any 第142号 《1》
~今月の目次~ 1頁「巻頭言」 2頁「セミナー日程」 「Any協会薬膳講座便り」
3頁「薬膳に使う中薬と料理」「薬膳最前線」 4頁「弁証施膳道しるべ」
NPO法人全日本薬膳食医情報協会 〒113‐0033東京都文京区本郷2丁目18番13号イシダビル3F Tel 03(5684)5661 Fax 03(5684)5669 Mail to [email protected] HP www.npoany.org
※このAny紙は、上記サイトからカラーでご覧頂けます。 サイトの 「Anyパートナー」→「会員ページ」から、 パスワード「shokui」でログインできます。
発行人 岡本清孝 編集人 谷口ももよ 第142号(Feb.2015)
薬膳を研究する上で日本の先駆者の存在を見落としてはならない、と思いませんか。 薬膳と云う言葉ではなくても、「食養生」に関する書物は数多くあります。 代表的な文献と作者を挙げると『医心方』丹波康頼編著、『本朝食鑑』人見(小野)必大編著、『大和本草』貝原益軒編著などが有名です。 ところで貝原益軒と聞けば、中学生の頃の教科書に出てくる「養生訓」をご記憶でしょうか。この著作は、江戸時代の健康的な暮し方についての解説書であり、儒学者でもあった彼の著作の中でもっとも著名で、写本も増刷されたほどの評判を博しております。 これは益軒が83歳(正徳2年・1712年)の時、実体験に基づいて書かれた書物であり、長寿を全うする為の身体の養生、心の養生を説いています。 モデルは『孟子』の君子の三楽にちなみ、養生の視点からの「三楽」を題材として挙げています。
養生訓は全8巻から構成されており、特に巻三と巻四は「飲食上・下」にわたって述べられています。各巻はそれぞれ70項目以上あり、その内容に幾つかは今日でも参考になるものがあり、ここでその中から数点取り上げてみましょう。
「禍は口から出、病は口から入る」 「淡薄なる物を食べよ、肉は少量が良い」
「飲食とも控え目にせよ、飽食を避けよ」 これらは今日でも十分理解できますが、肉は牛豚
文献の補足
貝原益軒像
ではなく、野生の猪や鹿などを示しています。 「五味偏勝は不可」はこの時代の人々は理解していたのでしょう。因みに内容をみると「一味を多く食いすぎる事。甘多は腹脹痛む、辛多きは気上りて気減り瘡生じ眼悪し、鹹多ければ血渇き咽喉乾く、湯水を多飲せば湿生じ脾胃傷る、苦多食せば脾胃生気損ず、酸多ければ気縮む。 五味を備えて少食せば病 生ぜず、諸肉・諸菜同続 食せば滞りて害あり。」 とあります。 脾胃の好む十一種目の 物、脾胃の嫌う十三種目 の物。これらは「脾胃」 が日常の言葉であったと 見る事が出来ます。 第四巻の中に次のよう な言葉が出ております。 「日本は中華人より体気 弱し、中華・朝鮮の人は 脾胃強し。飯多く食し、 六畜の肉を食っても毒害 なし、日本人は是に異な り、多く穀肉を食すれば やぶられ易し」とありま す。 まさにこの通りであり、 薬膳も本場の調理法に頼 り過ぎると、決して日本 人の消化力は追いつかないと考えるべきでしょう。 これら先人の教えも心して薬膳の研究を進めましょう。
中華人と称していた 正徳2年(1712年)と 云えば、我が国では徳川七代将軍家綱の時代で 中国は清国が支配していました。しかし、貝原は清国と云わず「中華人」と称している。尤も中華と云う言葉は4千年前「夏国」の時代に使われ、2千年後、秦の始皇帝が咸陽(長安)を都と定めその繁栄を中原華夏と称していた。(K.O)
(理事長 岡本清孝)
養生訓を考える
君子の「三楽」とは 1.道を行い、善を積むことを楽しむ 2.病にかかることの無い健康な生活を快く楽しむ 3.長寿を楽しむ これを基に貝原益軒は養生訓を編纂している。

~協会主催講習会日程のお知らせ~ ※各セミナー6名以上にて催行 ○案内同封
《2》
【初級向け講座】1月20日報告担当:吉野甘草 ◇基礎理論を学ぶ【発病・病機】 発病の原則: ①「正気」と「邪気」の勝負 ②「外環境」と「内環境」 外環境:①気候②土地(地域)③住居、仕事場 内環境:①体質②精神状態 病機: 病機とは? 病機を表現する視点: ①正気と邪気 ②陰陽 ③臓腑 ④気血津液 内生五邪: ①内寒、内熱、内湿 ②内風 ③内燥 病機の具体例:医案を使っての説明
【中級向け講座】1月20日報告担当:吉野甘草
処方箋(recipe)からひも解く薬膳(16)
半夏瀉心湯:適応症:寒熱錯雑証
組成:半夏、黄連、黄芩、乾姜、人参、大棗、炙甘草
逍遥散:適応症:肝気不和証
組成:柴胡、薄荷、当帰、白芍、白朮、茯苓、炙甘草、
炮姜
後半、吉野甘草により薬材⇒食材に置き換えて実習
半夏瀉心湯:
①(治療編)半夏瀉心湯スープ (スープ)
②(養生編)浅利の春野菜炒めカシューナッツソース
(副菜)
逍遥散:
③ (治療編)逍遥散粥(主食)
④ (養生編)サーモンの大根ソース(主菜)
※ ポイント 備考:外部資料より
◆半夏瀉心湯:
心下とは胃脘のことである。 痞は気不昇降、満だが不痛、押して濡である。 寒熱混雑、気不昇降なので上には乾嘔、嘔吐、下には腹痛腸鳴、下痢がみられる。このような方には除寒熱、復昇降をして脾胃を補する法を用いる。七薬は配伍して寒熱併用、苦降辛開で補気和中を果たす。 邪が除かれ、正が復元し、気が昇降でき、諸証は治る。
◆逍遥散:
四逆散の肝気鬱血の病態にさらに血虚、脾虚が考慮されている。消化機能の低下と栄養状態の不良、内分泌系の不調が基礎になり、自律神経の失調が加わったものに用いる。憂鬱、いらいら、易怒、頭痛、胸脇苦満、眼精疲労、四肢のしびれ、動悸、不眠、食欲不振、腹痛、
腹鳴、易疲労、倦怠、浮腫、下痢または便秘、月経痛、無月経などの症状が見られる。
日時 セミナー名 講師 受講料 他
①難易度 (レベル1) ◇◇◇◇◆
2月17日(火) 10:00~12:00
内生五邪
小金井信宏
会員 3,500円 非会員4,000円
○
②難易度 (レベル3) ◇◇◆◆◆
2月17日(火) 13:00~16:30
処方箋(recipe)から ひも解く薬膳(17)治燥剤 (麦門冬湯/瓊玉膏)
小金井信宏 吉野甘草
会員 7,000円 非会員7,500円
○
③難易度 (レベル1) ◇◇◇◇◆
3月17日(火) 10:00~12:00
防治原則 小金井信宏
会員 3,500円 非会員4,000円
○
④難易度 (レベル3) ◇◇◆◆◆
3月17日(火) 13:00~16:30
処方箋(recipe)から ひも解く薬膳 (18)辛涼解表剤(銀翹散/麻杏甘石湯)
小金井信宏 吉野甘草
会員 7,000円 非会員7,500円
○
【Any協会薬膳講座便り】
中級講座
逍遥散養生編レシピより

《3》
薬 膳 最 前 線
薬膳に使う中薬と料理
料理:ホテルクラウンパレス浜松 料理長 岡部 悟
当帰 当帰は、女性の要薬として知られている中薬である。
名前に由来があることで有名で、当帰は「まさに帰る」「当然帰るべき」などと訳すことができ、出て行った夫が当帰を飲んで美しく元気になった妻の元へ帰ってきた。産後の回復を助け、体を元の状態に戻す。などの謂れがあり、女性疾患の良薬とされてきた。 効能は補血活血・調経止痛・潤燥滑腸などで、下痢中は禁忌とされる。
種類は、唐当帰、北海当帰、大深当帰、大和当帰などがあり、ヨーロッパ原産の西洋当帰はアンゼリカともいわれ、茎を砂糖漬けした製菓材料はなじみ深い。 セリ科に属し、医薬品の根もセロリに似た芳香があり、独特な香りをもつ。適した調理法は、煎服・薬酒・スープ・粥などであり、肉と一緒にも調理される。葉はハーブ・スパイスに使用可能である。 ~レシピ~
◆当帰鹿水餃(当帰入り鹿肉の水ギョーザ) テーマ: 補五臓 調血脈 補血活血
鹿肉は温腎補陽・通乳・月経不順によく、女性は注目の食材の一つである。玫瑰花は活血散瘀で補佐的に働く。 《作り方》47個分
1.薄力粉200g 強力粉200gを合わせ熱湯260g加えて混ぜる。 2.鹿挽肉(赤身)200gと調味料(砂糖12g塩3g酒10g醤油24g ピーナッツ油24gたまり醤油5g葱姜水64g卵1個黒胡椒4g ニンニクみじん切り4g)を混ぜ、よく練る。 3.2と玉葱100g冬菇30g当帰5g玫瑰花1g(水で戻し30分蒸し、 みじん切りにしたもの)を混ぜ合わせ、1個12gにする。 4.1の生地を1個14gに切り伸ばす。中央に3の生地をのせ、 月形に包み成形する。 5.熱湯で5分茹で、茹でた青菜と共に器に盛る。 6.好みで、甜醤油・醤油・芝麻醤・辣油・酢のタレでいた だく。
解説:国際中医師・国際薬膳調理師 長島由枝
今月は2月11日のステップアップセミナー で、講師を務めてくださる李玉棟先生にご登場 いただきました
「明白に食べて愉快に生きる」とは、 食の本質を探ること 世界中に食に関わる健康問題が表面化して久しい。近年は益々この問題が増加する傾向が強くなっています。食についてどう捉えるべきか、国地域はもちろん個々人も考えなくてはいけない切実な問題です。 現在の食に対する混乱現象は、食を栄養素として科学分析する事と、食の文化意味の捉え方の違い角度から食問題を解決しようとする事、との食い違いが大きな原因ではないかと考えます。 食を扱って専門にされている皆さんを前にして、その専門ではない自分が僭越ではありますが、敢えてその食についてはっきりさせていくように簡単に纏めました。 食の概念の混乱は東・西洋の文化の違いの反映でも有り、「生きる為に食べよ、食べる為に生きるな」というソクラテスの名言にもあるように、西洋的な食事は個々の栄養を重視し、生命維持に主な意味があると考えます。(図1・①より)
それに対して、「衣食足りて礼節を知る」という東洋的な考えでは、食は文化でもあり、作法でもあり、食の心理文化面との総合作用を重視します。(図1・③より) この総合的食の本質から考えれば、現代栄養学分野の「フィンランドショック」は、個の栄養素であるβカロチンを重視するあまり、その栄養素の総合作用を見落としたことによる誤りであると言えます。 自分が臨床で悩まされた鉄欠乏性貧血に対して、鉄剤の処方使用に効果があまり期待できなかった事からも、病気の個の因素を重視して治療にも個の栄養素を補強するだけでは誤りがあるのではないかと考えました。 これから皆さんは総合的に食を考えて、幸せに生
きて行きましょう。 (李玉棟)
【図1】

肝腎陰虚の薬膳: 症状: 腰膝酸軟、頭目眩暈、耳鳴、耳が遠い、寝汗、遺精、泉門閉合不良、骨蒸潮熱、手足心熱、消渇、虚火歯痛、口燥咽乾、舌紅少苔、脈細数。 弁証:滋陰補肝腎 施膳方針:滋陰補肝腎 施膳: ◇ 鶏肉と山芋炒め (主菜) (食材)4人前 • 鶏胸肉400g(そぎ切りして酒20㏄と揉んでおく) • 皮付山芋200g(5㎝×1・5㎝角) • 長葱100g(2㎝斜め切り) • 生姜8g(みじん切り) • 【A:茯苓3g、牡丹皮3g、を200㏄の水で20分煮出して出来上がり
を50㏄にする】 合わせ調味料:熟地黄6g(みじん切り)、酒30㏄、(A50㏄)、 赤味噌40g、酢20㏄、胡椒少々、片栗粉少々、胡麻油適量 鶏肉 甘/温 脾胃 温中益気 補精填髄 降逆 適:虚労衰弱 気短 倦怠 山薬 甘/平 肺脾腎 健脾益気 滋陰潤肺 益精固腎 止瀉 治:脾虚食少 咳嗽 忌痰湿者 長葱 辛/温 肺胃 解表通陽 散寒健脾 散結 発汗煩 生姜 辛/温 脾胃肺 化痰止咳 解表散寒 健脾解毒 温中止嘔 治:風寒感冒 作り方 1、フライパンに胡麻油で鶏肉に両面焼き色を付け鶏肉に火を入れて取り出しておく。フライパンに胡麻油、生姜で香りをだし皮付長芋、長葱を入れ炒めて、合わせ調味料、①を加え味を確認してとろみが足りなかったら水溶き片栗粉で調節する。
◇鶏肉と山芋炒め◇
弁証施膳道しるべ
《4》
―弁証施膳の学習の進め方について 弁証施膳を考える時必要な“望診・舌診” について学びます。 症状⇒弁証⇒施膳方針⇒ 肝腎陰虚の弁証施膳と 繋ぎます。 【望診とは】 視覚によって得られる情報収集方法。 体格や姿勢、歩く姿、顔色や皮膚の状態、表情などを診る。虚実の判別や陰虚、気虚、血虚などを判断する材料に成る。 【顔や皮膚の色】 色は五臓とも関連している。 青【肝】・赤【心】・黄【脾】・白【肺】・ 黒【腎】色から対応する臓の状態が推測できる。 例えば、顔色が黄色っぽいと脾が弱い、白っぽいと肺が弱い。 【舌診とは】 舌の形や色、苔の付き方、苔の様子を事で全身の状態を診る事が出来る。 舌診は、望診に含まれるが、診断するうえで非常に重要視される。 実際に診断する場合、通常問診の後に主に行われる。 ※ポイント 舌の大きさ、形は舌苔の様子から主に陰の状態 を診る。舌の色から主に陽の状態を診る。 【中医学舌診の参考図】外部資料より
◆治療のポイント:舌と臓腑の関係 舌先は、心(小腸)・肺(大腸)・舌の淵は、 肝(胆)・舌の中央は脾(胃)・舌根は腎(膀胱)の状態を反映している。
担当:
吉野甘草
寒/熱 舌色 淡白舌―淡紅舌―紅舌―深紅舌 苔色 白苔―薄白苔―黄苔―褐色苔
水湿(痰飲)/陰虚 舌形 胖大舌(歯痕)―痩白舌(裂紋) 苔状 厚苔(潤)―薄苔―少苔(乾燥)―無苔
血虚/瘀血 舌色 淡白舌―瘀点 瘀斑 紫舌
今年の恵方は西南西やや西とされています。 今は豆撒きよりも恵方巻きの方がポピュラーになってきましたね。 そもそも恵方とは陰陽道でその年の福徳をつかさどる歳徳神の在する方位をさし、万事に吉といわれているそうです。 巻きずしも本来5色の食材を揃えたもので、陰陽五行にちなみ、ハレの日に食べるめでたい食べ物だということですが、節分の時に食べる太巻きは商売繁盛や無病息災を願って七福神にちなんで7種の具を使うそうです。 日本の五節句も実は陰陽五行の考えが昔からねづいているのですね。 最近このあたりの本を読むのがマイブームとなっています。 M.T