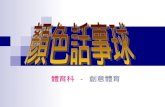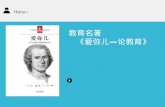〈体育〉...
Transcript of 〈体育〉...

沖縄県立総合教育センター 前期長期研修員 第56集 研究集録 2014年9月
〈体育〉
思考力・判断力を高め合う指導の工夫ー「動きのチェックカード」と運動の楽しさや面白さを積み重ねる協同の学びを通して
(第2学年)ー
名護市立名護小学校教諭 目取眞 堤
Ⅰ テーマ設定の理由
近年、知識基盤社会、グローバル化が進むなかで、各学校においては、児童(生徒)に「生きる力」を
はぐくむことが求められている。また、生きる力をはぐくむとともに、「創意工夫を生かした特色ある教
育活動を展開する中で基礎的・基本的な知識及び技能を確実に習得させる必要がある」とされている。そ
して、これらを活用して課題を解決するために必要となるのが思考力・判断力・表現力なのである。
しかし、昨年度行われた全国学力・学習状況調査の県内結果では、学んだ知識を活用し筋道を立てて考
えたり、説明したりする思考力・判断力に課題があるとの指摘があった。本校においても多くの言語活動
を取り入れているが、体育科においての言語活動はまだ不十分だと感じていた。自分のこれまでの指導を
ふり返っても、思考力・判断力の育成には課題があり、特に、中学年の「友達の良い動き見付けて自分の
動きに取り入れる」では、見付けた良い動きを習得することに時間がかかった。つまり、グループ活動で
の伝え合い活動が充実していなかったと考えられる。このようになった原因として、見付けた良い動きを
習得する場面で、動きを見る視点が多数あり、習得しにくかったと考えられる。以上のことから、見付け
た良い動きを習得する場面で、チェック項目をしぼり、グループで協力して効果的に技能を身に付けてい
くような言語活動の工夫を研究したいと強く感じた。
このような課題を解決するために二つの取り組みを行う。一つは、体育の言語活動(動きのポイントの
焦点化、動きの言語化、情報の発信と共有化)を経て作成する「動きのチェックカード」をつくること。
もう一つは、この言語活動を効果的にするものとして「協同の学び」を行うことである。「動きのチェッ
クカード」づくりは、友達の良い動きを焦点化して言語化し、カードにすることである。言語化する言葉
は、学習指導要領で示されている「例示」を簡潔にし、児童にわかりやすい短い言葉とする。もう一つの
「協同の学び」は、仲間とともに運動し、課題に対して思考していく学びである。今回は小学 2年生の障害物リレー遊びなので、走ったり跳んだりして楽しみながら遊ぶなかで思考をこらし、技能を高められる
ようにしたい。協同の学びでは、動きにつながる言葉で応援する児童、バトンを受ける姿勢ができている
かを見る児童、タイムを測る児童など、全員が割り当てられた役をこなしていく。そこでは、「個人や友
達と一緒に走ったり、跳んだり、バトンパス、障害物跳びなどの技能に挑戦する楽しさ」と「いかに速さ
をつないでタイムを縮めるかという面白さ」を味わわせたい。このように、友達と関わりながら言語活動
を進め、遊びのなかから運動の楽しさや面白さを味わい、友達の良い動きを見付け、自分の運動に取り入
れることができる児童を目指したい。
そこで本研究では、児童の良い動きを習得する場において、動きのポイントを焦点化して言語化したチ
ェックカードを活用し、グループで協同の学びを行うことにより、思考力・判断力が高まり、技能も向上
し、運動の楽しさや面白さを味わうことができると考え、本テーマを設定した。
〈研究仮説〉
児童の良い動きを習得する場において、動きのポイントを焦点化して言語化したチェックカードを活
用し、グループで共同の学びを行うことにより、思考力・判断力が高まり、バトンパスと障害物跳びの
技能が向上し、運動の楽しさや面白さを味わうことができるであろう。
Ⅱ 研究内容
1 思考力・判断力を高め合う指導について
(1) 体育における思考力・判断力と意欲のとらえ方

細江文利(2010)によると、「各運動領域における学習すべき内容は、技能、態度及び思考・
判断のトライアングルで表現されており、この3つが関わり合う中で育成される身体経験こそが
生涯にわたって運動に親しむ資質や能力とな
る。また、その思考力・判断力は技能との関係
性の中で育成される」(図1)。また、「単元に
おける運動学習の流れにおいて、運動の特性と
魅力に触れさせながら楽しさを味わわせれば、
知識・技能、思考・判断、態度面は伸びていく」
と述べている。つまり、思考・判断を高めるこ
とが技能の高まりにもつながるのである。
よって、体育の思考力・判断力は技能の高ま
りと運動の特性と魅力を味わいながら得られる
身体経験の積み重ねの課程で育成されるととら
えていく。 図1 技能、態度、思考・判断のトライアングル
(2) 思考・判断を高めるため三つの言語活動について
現在、思考・判断をはぐくむ観点から言語活動の充実を図ることが大切だとされている。体育
においても、課題を解決するためには思考力・判断力の育成が重要となる。体育おける言語指導
の例として「動きのポイントの焦点化」「動きの言語化」「情報の発信と共有化」の三つの取り組
みがある(図2)。
➀ 「動きのポイントの焦点化」
動きのポイントの焦点化とは、運動の技能を向上させるためにポイントをしぼらせる活動で
ある。今回は、動きのチェックカード作成時この言語活動を行う。つまり、バトンを受ける姿
勢を考えさせる場面で、見る視点が多くならないように「頭、おへそ、手」に視点ををしぼり、
良い動きを探していく。
② 「動きの言語化」
動きの言語化とは、先ほど友達の良い動き
を焦点化して探したあと、その動きを言語化
していくことである。今回は速さをおとさな
いバトンの受け方、障害物の跳び方をしてい
る児童を探し、その動きを言語化して動きの
カードにしていく。そのカードを「動きのチ
ェックカード」として活用していく。
③「情報の発信と共有化」
情報の発信と共有化とは、自分が活動を通
して学んだり、気付いたことをみんなで共有 図2 体育における言語活動
することである。今回、「グループでの協同の学びの場」と授業の終わりに位置付けている「今
日のMVP発表の場」で情報の発信させ、共有化させていきたい。
今回は「動きのチェックカード作り」と「グループでの協同の学びの場」の活動に必要とな
っていくる3つの言語活動を取り入れ、児童の思考力・判断力が高めていく。
(3) 思考力・判断力が高まった姿について
上記に示しているように、細江文利(2010)は「思考力・判断力の高まりは技能の高まりにも
つながる」と述べている。今回は、児童からでた課題や疑問を解決するなかで、思考力・判断力
を育成していく。友達の良い動きを探し、その動きに関しての思考力・判断力が高まれば、それ
が自分の技能の向上にもつながると考えられる。つまり、技能を高めるために友達の良い動きと
は何かを試行錯誤し、自分の動きとの共通点や相違点に気付かせる。そして、その動きを一人で
身に付けることは難しいので、グループで協力して伝え合いながら技能を高めていくことが必要
となってくる。また、活動の場が広い運動場であり、児童の活動も多いため、どのような姿が思

考力・判断力を育成させているのかも提示する必要がある。
よって、本研究では、検証がしやすいように、「テーマに迫る児童の姿」を以下のように示し
たい。また、そこから技能の高まりが授業記録や観察、ワークシートで確認できれば思考力、判
断力が高まったとしてとらえていく。
【テーマに迫る児童の姿】
①動きを身に付けるために、仲間と身体活動や言語を通して試行錯誤する姿。
②自分や仲間の体の動かし方に目を向け、動きの共通点や相違点に気付く姿。
③多様な思いや考えを伝え合い、お互いの動きを高め合う姿。
2 思考力・判断力を高める二つの手立てについて
(1) 動きのチェックカードについて
児童には、各学年の発達段階に応じた力を付ける必要がある。体育の指導要領でも具体的な例
示が示されている。しかし、今までの赴任校を振り返ると、担任の体育の得意・不得意によって
クラスに技能の差が出ることもあった。このような現状から、
経験年数に限らず、動きのポイントと運動に必要な語彙を示
したカードを活用すれば、どの教師もある程度同じレベルの
指導ができるだろうと考えていた。今回の研究を通して、技
能だけでなく、思考・判断・態度をバランスよく育成できる
一つの材料としたい(図3)。
しかし、このカードは全学年共通ではなく、各学年の発達
段階に応じて変化させる必要がある。例えば、チェック項目
を減らしたり、カードでなく、児童が使いやすいような形に
変化させることもある。作成時の留意点は以下の三つである。
ア 学習指導要領の例示をより具体的に示す
イ ポイントは1~2項目とする
ウ 写真や絵を入れる
このカードを使えば、お互いの良い動きが確認でき、書か
れている語彙をつかってみんなに説明やアドバイスもでき
る。つまり、このチェックカードは思考・判断、技能の向上 図3 高学年用チェックカード
の手助けにもなると考える。
(2) 運動の楽しさや面白さを積み重ねる協同の学びについて
➀ 運動の楽しさや面白さを積み重ねるとは
今回の学習指導要領改善の基本方針には、「運動が有する特性や魅力の応じて,基礎的な身
体能力や知識を身に付けることがで
きるようにする」と記されている。
運動の特性は「効果的特性」「機能
的特性」「構造的特性」の3種類あ
ると言われている。効果的特性は、
基礎運動能力を高める特性、機能的
特性はスピードにのって走る感覚や
チームや自分の記録に挑戦できるこ
となどである。そして、構造的特性
が運動の魅力とされている。構造的
特性は、その運動ならではの形式や技 図4 走・跳運動遊びの特性と魅力
術が特性として示されている(図4)。よって、今回は運動の「楽しさ」と「面白さ」を以下
のようにとらえたい。

ア 運動の楽しさ
個人や友達と一緒に走ったり、跳んだり、バトンパス、障害物跳びなどの技能に挑戦する
ことを運動の楽しさととらえる。(機能的特性・構造的特性)
イ 運動の面白さ
「相手の速さをつないでバトンパスができるか」「障害物を跳び越えながら、スピードを
落とさずに最後まで走りきることができるか」を運動の面白さととらえていく。
また、児童の発達段階にあわせ、バトンパスと障害物跳びを同時に行わずに、まずはバトン
パスを習得させたい。その後、障害物跳びに取り組み、最後は障害物リレーにつなげていく。
これを「運動の楽しさや面白さを積み重ねる」として研究を進めていく。
② 協同の学びとは
眞榮里耕太(2012)によると、「体育授業は、協同の学びと個の学びを常に繰り返すなかで児童に学習内容を身に付けさせている。体育授業では、とりわけ仲間と共に学ぶ協同の学びが
意図的に取り入れられいる」と述べている。協同の学びとは、仲間と共に運動したり、動きに
ついて思考したりすることであり、個の学びとは、一人一人が運動技能の習得、向上を目指し
て取り組む場である。今回の研究では、特に協同の学びという言語活動を通して、児童の思考
力・判断力を高め合う指導を工夫していきたい。活動内容として、まず、足が速い児童と遅い
児童のペアをつくる。同じ速さの児童同士よりも、速さが違う方が多くの学び合いにつながる
と考えたからである。次に、30mのバトンコースの場を使い、グループで協力してペアのタイ
ムを計っていく。ペアのタイムを計る際、受け手が走り出す合図を出す児童、バトンを受ける
姿勢ができているか見る児童、タイムを計る児童、記録する児童など、全員に役を与えたい。
活動はグループ同士の対戦ではなく、自分たちのタイムを少しでも縮めることを目的とする。
よって、タイムを縮めるために協同の学びが求められていく。その中でタイムが縮まっていく
楽しさや相手と速さとつなぐ面白さなどを味わわせていきたい。また、協同の学びをより効果
的にするために、「円形リレー」「赤白帽子の色での評価」「とりやすいバトンリングの活用」「運
動に必要な語彙の紹介」などの教材・教具の工夫も取り入れる。
(3) 体育における意図的な発問について
米村耕平(2010)によると、「課題提示が終了し、学習者が課題解決の活動に入る前に、学習者の課題に対する理解度をどのように確認するかという方略を立て、意図的な発問を発すべきであ
る。」と述べている。つまり、課題の確認や活動後の理解度をチェックするために短い一連の発
問をあらかじめ用意しておく必要があると述べているのである。本研究では「バトンをとる姿勢
で三つの大事なことについて先生に話せますか?」や「障害物をあまり遠くから跳んではいけな
いのはなぜでしょう?」など、意図的な発問をしていく。また、クラス全体を巻き込んで思考錯
誤できるように、「ABCDの四つの場所があります。どこから走り出せば良いですか?」など、
児童が思考しやすいような発問も工夫していく。動く場所や位置に関しての発問と動きに関して
まわりと相談させる発問を通して、児童を試行錯誤させ、どの動きが良いのかに気付かせていく。
Ⅲ 指導の実際
1 単元名 「障害物リレー遊び」
2 単元目標
(1) 前方や上方に跳んだり、連続して跳んだりすることができる。(技能)
(2) 運動に進んで取り組み、きまりを守り仲よく運動したり、勝敗を受け入れたり、場の安全に気
をつけたりすることができる。(態度)
(3) 走ったり跳んだりする動き方を知り、友達のよい動きを見付けることができる。(思考・判断)

3 単元の評価規準と具体的評価規準
運動への関心・意欲・態度 運動についての思考・判断 運動の技能
単
元 ○走・跳の運動遊びに進んで取り組むとともに、順 ○走ったり、跳んだりする運動遊び ○走・跳の運動遊び
の 番やきまりを守り勝敗を受け入れて仲良く運動を の行い方を工夫している。 を楽しく行うため
評 しようとしたり、運動をする場面の安全に気をつ の基本的な動きや
価 けようとしたりしている。 各種の運動の基本
規 となる動きを身に
準 付けている。
具 ①走・跳の運動遊びに進んで取り組もうとしている。 ①走・跳の運動遊び
体 ②運動の順番やきまりを守り、勝敗の結果を受け入 ①走ったり跳んだりする動き方を知 では、前方や上方
的 れて、友達と仲よく運動しようとしている。 るとともに、友達のよい動きを見 に跳んだり、連続
な ③友達と協力して、用具の準備や片付けをしようと 付けている。 して跳ぶことがで
評 している。 きる。
価 ④運動をする場や用具の使い方などの安全に気を付
規 けようとしている。
準
4 指導及び評価計画
時 学習のねらいと活動 指導上の留意点 評価 評価方法
○学習計画会をしよう ・交流活動では、副キャプテンが
(1)学習のねらいや通すじ 、進め方を知る。 ファシリテーターとなり、みん 行動観察
1 (2)障害物リレーの動きの特性と運動や思考に なの意見を聞く。まとめはキャ 関心①
つながる語彙を知る。 プテンとする。 学習カード
(3)道具の準備や片付けの役割分担やマナーを ・準備、片付けは一人一役でとす
知る。 る。
○2人ペアでバトンパスの記録会をしよう。 ・記録会のストップウオッチは担 行動観察
2 ・6人で協力して記録係、応援係、ストップウオ 任も補助する。 技能①
ッチ係をつけて記録を計ることができる。 ・安全に気を付けて跳ばせる。 学習カード
・リングバトンの引き継ぎ方を知る。
○友達の良い動きを見付けてみよう。 ・相手と同じ速さでバトンを受け 行動観察
3 ・バトンを取るときの動きを見合い、頭、おへそ、 るためには、すぐに走り出せる 思判①
手に着目して、良いバトンポーズを見付けるこ 姿勢で待つ必要があることに気 学習カード
とができる。 付かせる。
○みんなで見付けたバトンポーズでバトンを受け ・グループで協力し、バトンポー
て走ってみよう。 ズの声かけ、アドバイスなど、
・バトンポーズ(頭低く、おへそは前、手はパー) 交流活動をしっかりさせる。 技能① 行動観察
4 を合い言葉にしてバトンを取ることができる。 ・低い障害物を跳ぶときは安全に
・棒つきポンポンを使ってグループで声かけ、チ 気を付けさせる。 学習カード
ェックをすることができる。 ・まとめのMVP発表は発表の仕方
・低い障害物跳びに挑戦することができる。 の例示を活用する。
○障害物を跳び越すときの友達の良い動きを見付 ・友達の良い動きを見合う場面で
けてみよう。 は、見るポイントを頭と足にし 行動観察
5 ・障害物を跳び越える動きを見合い、頭、足に着 ぼり、良い動きに気付かせるよ 思考①
目して、速くきれいに跳び越す姿勢を見付ける うにする。 学習カード
ことができる。
○バトンパス記録会と障害物リレー大会をしよう。・ストップウオッチ係には補助を
6 ・記録係、応援係、ストップウオッチ係をつけて 付ける。 行動観察
記録を計ることができる。 ・バトンパスや障害物を跳ぶと 関心
7 ・みんなで見付けた姿勢(頭低く、足の裏をゴー き、学んだことが生かせるよう ②③④ 学習カード
ルに向ける)を合い言葉にして、障害物を跳び に声をかける人を決める
越えることができる。

5 学習過程と時間計画
6 本時の指導(3/6)
(1) 目標
相手と同じ速さで走ってバトンを受けるなど、友達の良い動きを見付けることができる。
(2) 授業仮説
お互いの動きを見合う場面で、バトンを受ける友達の姿勢を見るとき、見る視点を「頭、おへそ、
手」にしぼることにより、すぐに動きだせる姿勢は、頭は低く、手は相手に向け、おへそは進行方
向に向けることであることに気付き、その動きをしている友達を見付けることができるであろう。
【テーマに迫る児童の姿】
①動きを身に付けるために、仲間と身体活動や言語を通して試行錯誤する姿。
②自分や仲間の体の動かし方に目を向け、動きの共通点や相違点に気付く姿。
③多様な思いや考えを伝え合い、お互いの動きを高め合う姿。
(3) 展開 (にぬふぁ星プラン、わかる授業、テーマに迫る児童の姿)
学習活動(○教師の発問,●予想される児童の反応) ☆指導上の留意点 ★評価
始 1.準備運動をする。 ☆学習の準備、ベルを意識させる。
め 2.はじめの挨拶をする。 【学習規律】
五 3.前時のふりかえりをする。(前時の感想のはてなを取り上げる) 【学ぶ意義】
分
4.今日の学習とめあてを確認する。 【目標を示す】
(今日のめあて)
バトンをわたすとき、スピードを落とさずにバトンをわたすためにはど ☆聞く姿勢の重視【学習規律】
うしたらいいのかを知る。(思考・判断)
・バトンを受けるときのポーズを探そう
○「バトンをとるのが難しいとはどういうこと?」
・(場所、位置、動きなど)わからないという意見を取り上げ,バトンを取る側が走り出す位置の違いに気付かせる。
・走る速さが違うので、走り出す場所がちがうことに気付かせる。
○「バトンをわたすとき、スピードを落とさずにわたすためには、バトン
をとる人ははどんな速さではしって取ればいいの?近くの人と相談しま 【テーマに迫る児童の姿】
しょう。」(1分30秒程度)→(実際にさせてみる) ①試行錯誤
な ○「今やった動きから考えるとどんな速さで走ればいいの?」
か ●「相手と同じ速さ!」
○「バトンをとる人はパッとはしって相手と同じ速さにしなければいけ
時間 1 2 3 4 5 6 7
0
10
20
30
40
45
(関心・意欲・態度)
○障害物リレーのめあて
○学習の流れ
○学習に使う語彙の説明
○準備片付け、役割分担
○チーム決め、役割分担
準備運動 めあての確認 学習の流れの確認
(技能)
○バトンパスの練習を
して、ペアでバトンパ
スの記録会をする。
↓
○バトンパスリレーを
する。
↓
○相手と同じはやさで
バトンパスをするため
には、バトンを受ける
姿勢が大事になること
に気づかせる。
(思考・判断)
○良いバトンパスの渡
し方、受け方を友達の
動きから探す。
↓
○頭、おへそ、手の動
きに焦点をしぼり、は
やくバトンパスができ
る姿勢に気付かせる。
↓
○見つけたポイントを
お互いで見合いながら
練習する。
(技能)
○前回見つけたバトン
パスの姿勢を自分の動
きにするためにチーム
で練習する。
↓
○バトンパスを生かし
て障害物リレーに挑戦
する。
↓
○障害物をはやく跳び
越えるには、跳ぶ姿勢
が大事になることに気
付かせる。
(思考・判断)
○はやく障害物を跳
び越せる姿勢を友だ
ちの動きから探す。
↓
○頭と足にポイント
を絞り、はやく障害
物を跳び越せる姿勢
に気づかせる。
↓
○見つけたポイント
をお互いで見合いな
がら練習する。
(関心・意欲・態度)
○ペアでバトンパスの
記録会をする。
↓
○バトンパスの仕方、
障害物の跳び越し方に
気をつけて、障害物リ
レーを楽しむ。
(円形リレー)
今日のめあてにそったMVP発表 授業のまとめ

三 ないね。パッと動くんだよ。今日は相手と同じ速さで走ってバトンをと
十 ることをがんばってみましょう。」
五 ・スピードを落とさずにバトンを渡すには相手と同じ速さで走ってバト
分 ンを受けることの必要性に気付かせる。
5.お互いの動きを見合う活動
○「(全員を高い場所にあげて)今から同じスピードで相手にタッチするゲ
ームをします。先生の笛は魔法の笛です。一回笛がなるとその場で動け
なくなるんだよ。2回吹くと動いてよい合図です。笛と同時に止まれる
速さではしってね。見ている人は、同じスピードでバトンを取れそうな 【テーマに迫る児童の姿】
人を見付けてください。見付けることができるかな?」 ②共通点や相違点
「ようい、スタート! 今の見た? 誰の動きが良かった? せーの」 ★友達の良い動きを見付けることが
●「○○くん!」 できる。
○「つまりどこの動きがよかった?」(ポイントの焦点化)
●「頭をひくくしている。」「おへそが前を向いている。」「手を大きくひら
いている。」
○「合い言葉にするなら?」頭ひく! おへそ前! 手はパー!を合い言
葉にする。 【テーマに迫る児童の姿】
6.バトンをとる姿勢を意識しながら走ってみる。 ③伝え合い
・待っている児童は合い言葉を伝えながら応援する。
終 7.今日のMVPとその理由をグループ ☆話す姿勢、聞く姿勢の重視
わ で発表する。 【学習規律】
り (めあてに戻り、良い動きをしていた人をM ★友達の良い動きに気付いたか
五 VPとする) (思・判)
分 8.次回の報告をする。
7 仮説の検証
障害物リレー遊びの場において、運動のポイントを入れた「動きのチェックカード」と「運動の
楽しさや面白さを積み重ねる協同の学び」という二つの手立てが有効であったか。また、その手立
てを通して「テーマに迫る児童の姿」が見られたか。そして、研究内容で示したように「技能が高
まっていれば、児童の思考力・判断力も高まったととらえる」についての検証を行う。検証方法と
して、児童のワークシート、資料画像、アンケート結果などを材料に仮説の検証を行う。
(1) 二つの手立ての有効性について
今回、思考力・判断力を高め合い、技能を向上させるため「動きのチェックカード」と「協同
の学び」の二つの手立てを取り入れた。その手立ての有効性と児童が運動の楽しさや面白さを味
わうことができたかを以下に述べる。
① 運動のポイントを入れた「動きのチェックカード」の検証
今回の指導では、用意していたバトンチェッ
クカードの代わりに、棒付きポンポンを活用し
た。その理由として、2年生では、カードが持
ちにくく使いずらかったからである。そこで、
チェックカードを児童の発達段階に応じて変化
させ、棒付きポンポンにチェックカードを小さ
く貼り付けることにした。(図5)。棒付きポン
ポンについてのアンケートの結果から「ポンポ
ンをつかった授業は楽しかった」「やることが棒
に書かれているのでわかりやすかった」「おもし
ろかったし、応援もしやすかった」など、「今後 図5 学年に応じて変化したチェックカード

も棒付きポンポンを使うことに賛成」と答え
た児童が93%いた(図6)。残りの児童は「ポ
ンポンがなくても口で言えばいい」などの意
見もあった。今回は、2年生でも使いやすい
ように、チェックを1項目にしぼったことが
大きな特徴である。また、運動が苦手な児童
も棒付きポンポンを持って活動に参加し、全
員が楽しく学習ができたと答えていた。この
ように児童の言語活動(動きのポイントの焦
点化、動きの言語化)を通して作成したチェ
ックカードを使い、お互いの動きを高め合う
場をつくることで、運動の楽しさや面白さを
味わわすことができた。 図6 教具の有効性
② 協同の学びからの検証
授業修了後、児童から、「グループ
で練習して、チームワークも高まっ
た。」「はじめはできなかったけど、練
習したらバトンのポーズでバトンがと
れるようになった。」などの感想が多
く出た。6人グループで棒付きポンポ
ンを使い、声かけしたり応援したり、
記録を計ったりした。毎回、合格した
ら帽子を赤にしていく。特に有効だっ
たのが、ポンポンを持っている児童と
応援する児童の声かけである。「ここ
に来たら走って取ってね。」「頭低くね。」 図7 協同の学びの前と後の違い
など、具体的な声かけができていた。
その結果、はじめはバトンパスの合格
者が2割しかいなかったが、協同の学
びを取り入れ「頭低く」「おへそ前」「手
はパー」を合い言葉にして練習させる
と、単元終了後には9割の児童ができ
るようになっていた(図7)。障害物
跳びでも、はじめはほとんどの児童が
上に跳んで走るスピードが落ちてい
た。しかし、協同の学びを取り入れ、
「足の裏を見せて」「頭はひくく」を合 図8 バトンパスの記録の伸び
い言葉にして練習させると、全員が前に跳びながら障害物を跳び越えることができるようにな
った。最後の30mバトンパス記録会でもほどんどのペアのタイムが縮まり、協同の学びの有効
性を感じることができた(図8)。
子ども達は、相手のスピードを落とさずにバトンパスを受けたり、最後まで同じスピードで
障害物を跳ぶことに挑戦し、時にはチームで競争して楽しむことができた。「うまくできるよ
うになった」「走ったり跳ぶのが速くなった」など、競争して遊ぶなかでも技能の高まりを感
じ、喜んでいる児童が多かった。授業後のアンケートでも協同の学びをした日は全員が楽しく
学習できたと答えていた。また、仲間と協力して運動することやバトンパス、障害物跳びに挑
戦していく身体経験を楽しんでいる感想が多かった。グループでポンポンを使った「動きのチ

ェック」で合格して帽子の色が変わることに喜ぶ児童も多かった(図9)。
図9 協同の学びと授業後の感想
(2) テーマに迫る三つの児童の姿からの検証
今回、研究の検証がしやすいように、テーマに迫る三つの児童の姿を示した。毎時間三つの姿
が見られる場を設けるのではなく、学習内容に合わせて思考する場を設けた。思考させる場をを
重ねるごとに、取り組みも速くなり、見通しをもって学習に望むことができた。以下に三つの姿
からの検証を行う。
① 「動きを身に付けるために、仲間と身体活動や言語を通して試行錯誤する姿」からの検証
思考力・判断力を高める手立てとして「動きの位置や場所に関する発問」「良い動きについ
ての発問」を中心に行った(図10)。動きの位置や場所に関する発問では、全体が参加しやす
いようにABCDの四つの選択肢をあげて考えさせた。第3時の発問では、バトンを受ける際、
相手の足の速さに合わせて走り出す位置を変える
必要があることに気付くことが出来た。障害物跳
びの場合は、障害物を跳び越える場所について考
えさせた。安全に跳び越すためには遠くから跳ん
でも近すぎても危ないことに気付かせた。良い動
きについては、友達の動きを高い場所から見なが
ら見るポイントをしぼって考えさせた。個人で考
え、全体発表でその理由を考えていく。どちらも
時間とポイントを与えることで思考錯誤する場面
が多くみられた。 図10 思考錯誤させる図の例
② 「自分や仲間の体の動かし方に目を向け、動きの共通点や相違点に気付く姿」からの検証
お互いの動きを見合う場の中で、全員が「一番○○くんのバトンの取り方がいい。」との声
がでた。良い動きに気付きやすいような
場の工夫を四つ取り入れた。
ア 数人の動きが同時に見れる場を工夫
イ 頭、おへそ、手に注目させたこと
ウ 教師の合図で一時的に動きを止め、
児童が見やすいようにしたこと
エ 高い場所から観察させたこと 写真1 全員で動きを見合う場
この四つの工夫をした結果、ほとんど
の児童が速くバトンパスをしている子の
共通点、相違点に気付くことができた(写
真1)。また、見る視点を「頭、おへそ、
手」にしぼることで2年生でも集中して
動きを見ることができた。その良い動き
を言語化し、児童がなじみやすい言葉で
「頭低く、おへそ前、手はパー」として
まとめることができた(写真2)。 写真2 共通点や相違点に気付かせる場
③ 「多様な思いや考えを伝え合い、お互いの動きを高め合う姿」からの検証

30mバトンパスの記録会をする場面で、「○
○さんがここにきたら『走って』と言ってね。」
「バトンのポーズは頭低く、おへそ前、手はパ
ーだよ。」などの具体的な応援が多く聞こえた
(写真3)。地面に線を引いて走り出す位置を
確認するなど、工夫する児童もいた。運動に必
要な語彙は授業のはじめで確認しているため、
応援のときにその語彙を遣っている児童も多か
った(図11)。また、学習のまとめの場におい
て、「○○くんは足が速いから、このあたりから 写真3 協同の学びの様子
走ったほうがいいよとアドバイスをもらいました。」「○○くんのアドバイスのおかげで障害物
跳びがうまくできるようになりました。」など
の意見があった。グループでの協同の学びとM
VP発表の場をつくることで、児童同士が伝え
合い、高め合う姿が多くみられた。
また、今回の学習の中に見られた児童同士の
伝え合いやお互いの動きを高め合う姿から、関
心・意欲の向上や、技能の高まりも感じること
ができた。評価でも9割以上の児童が「関心・
意欲・態度」「技能」「思考・判断」どちらも高 図11 オリエンテーションで説明した語彙
い評価を得ることができた(図12)。28人中2人は、教師や友達からの声かけで走りながらの
バトンパスや障害物跳びができるようになった。また、全7時間の学習を楽しく活動できたと
答えた児童が9割以上に達することができた(図13)
図12 障害物リレーの評価結果 図13 楽しく学習ができたかアンケート
Ⅳ 成果と課題
1 成果
(1) 思考錯誤して動きの共通点を探すなどの言語活動を通して作成した「動きのチェックカード」
とリレー遊びのなかでもお互いを高め合う姿が見られた「協同の学び」を通して、楽しく学習が
進められた。
(2) 意図的な発問と三つの言語活動の取り組みから、テーマに迫るような「思考を高め合う活動の
場」をつくることができた。
(3) 走る・跳ぶなどの楽しさを実感させるために教材・教具を工夫し、できなかったことができる
ようになったという身体経験を積み重ねるなかで、技能を高めることができた。
2 課題
(1) 思考・判断中心の学習の場において、運動量がしっかり確保できるような学習活動の工夫
(2) 各学年の発達段階にあわせた教材・教具の工夫

〈主な参考文献〉
文部科学省生涯スポーツ課 2014 『運動に親しむ資質や能力をはぐくむ教育の充実』 初等教育資料2月号
岩崎大輔 淺井仁美 佐藤雅彰 2013 『体育科教育』 2013年12月号 大修館書店
眞榮里耕太 2012 『体育科における協同の学びと個の学び』 「教育研究」2012年5月号 金子書房
横浜市教育委員会 2012 『言語活動サポートブック』 時事通信社
文部科学省 2011 言語活動の充実に関する指導事例集 教育出版
高橋健夫 岡出美則 友添秀則 岩田靖 2010 『新版 体育科教育入門』 大修館書店
斉藤草子 2010 『秋田大学付属小学校 授業改革への挑戦』 一莖書房
細江文利・池田延行・村田芳子 2009 『小学校体育における習得・活用・探求の学習』 光文書院
佐藤学 2006 『学校の挑戦 学びの共同体を創る』 小学館
高橋健夫 1988 『体育の教授技術』大修館書店