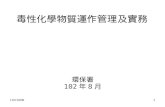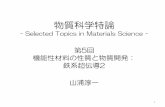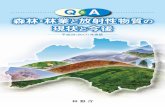石器や土器の物質性、からだの物質性、見えな い …...ない物質...
Transcript of 石器や土器の物質性、からだの物質性、見えな い …...ない物質...

民博通信 No. 14218
器物の素材の物質性人がモノを作るとき、素材の物質性はどのように重要なの
か。過去の遺物を手掛かりに人間と物質の関わりを読み解く考古学の知見には、本共同研究にとって傾聴すべき点が多々ある。松本直子の「考古学からみた物質性:象徴的人工物と物質
性」(2012.11.10)では、縄文土偶の表情を現代人がどのように認知するのかについての実験の話に先立って、石器などの人工物からヒトの心の進化を解明する試みについて報告があった。単純化して言えば、ネアンデルタール人は、石材の性質を深く理解し、剥片を活用するなど、石器を計画的に製作していたが、石器の形態は 20万年間ほとんど変わらず、骨角器はきわめて稀で、石器一辺倒だった。それに対して後期旧石器時代以降のホモ・サピエンスになると、石器の種類も豊富で複雑化し、骨や角や象牙も活用し、装身具を作り、具象的写実的な「芸術」を生み出し、人と物質の関わり方が急激に変化する。文化のこの大爆発の背後に、考古学者マイズン(Steven Mithen)は「領域固有の知能」間の流動性の高まりを指摘する。パソコンへの移行を頑として拒否するワープロ専用機愛好者のようなネアンデルタール人に対して、ホモ・サピエンスの知能は色々なタスクをこなすパソコン的な可塑性へと開かれ、同時に物質も、人間にとって(たんなる条件ではなく)素材としての重要性を増し、様々なモノになりうる可塑性を増大させてきた。溝口孝司の「物質性と考古学:社会
性の変容との関連から」(2012.11.10)によれば、縄文時代には、社会におけるコミュニケーションの再生産が生活世界の再生産によって保証されていて、それが言語や概念によって媒介されない「モノの融即性」にもとづいていたらしい。それが弥生時代になると、コミュニケーションの再生産が抽象性・言説化をともなう儀礼に頼らざるをえなくなる。要素に分割できない一体の表現としての縄文土器と、記号としての絵を描くキャンバスとしての弥生土器の違いにもそうした変化を看取できるという。おそらく縄文時代には、物質・
環境から象徴・概念が剥がれていないために媒体と意味が表裏一体で切り離しがたいのに対して、弥生のデザインは、物質との一体性が薄まり、そこにはすでに、文字さえ到来すればそれで代替できるような抽象性が備わっていたということだろう。
様々なからだの様々な物質性人間のからだが物質から成り立っていることは明らかだが、
どのような物質から構成されているどのような性質のものなのか、それは見えないものも含んでいるのか、死後の人間のからだの場合はどうなのかとなると、問題は急に難しくなる。さらにキリストや聖母や高僧や王など常人を超えた存在となれば、その「からだ」もまた、かなり非凡である。
秋山聰の「西欧中近世におけるキリスト像の生動性をめぐって」(2012.7.28)の主題は、復活・昇天後のキリストそして聖母のからだであるが、少なくともそれには 3種類ある。まず昇天したはずなので存在じたいが稀だが、遺骸つまり霊験あらたかな「聖遺物」。そして「聖像」。さらにキリストの場合は「聖体」。聖像は公式の教義によれば似姿にすぎず、崇拝対象ではない。しかし聖像が「生けるがごとく動いて人間と相互作用する」という現象が中近世では稀ではなかった。のちには、キリスト像が教会内で実際に埋葬されたり、吊上げられて昇天したりして、信者向けの上演に一役買うようにもなる。聖体とはさらに不思議なモノで、「全質変化」(transubstantiation)によってキリストの血と肉と化した葡萄酒とパンであり、聖体拝領で信者が経口摂取する。「からだ」が生の有機物で構成されているとは限らないのである。出口顯の「エンバーミングと記号
化する身体」(2012.7.28)が扱うのは、死体に生ずる腐敗と分解という物質的プロセスと、個人が故人になる社会的プロセスとの間で折り合いをつけるために、死体に加工を施して遺体へと変化させる様式のひとつ、「エンバーミング」である。これはリンカーンの葬儀などを契機に米国で開発されたものだが、1980年代以
昇天儀式用キリスト像(フリブール美術歴史博物館蔵)(Skulptur des Mittelalters: Funktion und Gestalt, Hg.v. Friedrich Möbius/Ernst Schubert, Weimar 1987, p.280)。儀式の際には像を吊上げて教会天井の穴から昇天できるようなつくりになっている。
石器や土器の物質性、からだの物質性、見えないものの物質性
文
古谷嘉章
共同研究 ● 物質性の人類学(物性・感覚性・存在論を焦点として)(2011-2014)

No. 142 民博通信 19
降日本にも導入されつつある。出口によれば、その目的は防腐防疫と修復であるが、日本では長持ちさせるというより、「失われた面影を回復し、あたかも生きている、湯上がりのようなきれいな状態」にすることが望まれているという。エンバーミング以外にも、死体を素材として別のモノへと変化させる営みは多々ある。素材を入れ替えて不死のサイボーグに加工するエジプトのミイラも、自力でからだの物質的変化を成し遂げて成仏する即身仏も、その一例である。野林厚志の「触感という観点からの展示物の解釈」(2012.
11.10)では、国立民族学博物館における触展示に即しての「触ってわかること」についての問題提起と並んで、唐招提寺で鑑真没後 1250年法要での開眼をめざして製作された国宝鑑真和上座像の「お身代わり」について報告があった。まず興味深いことに、国宝の鑑真像(秘仏だが 2013年の 10月 8
日~ 10日に特別公開予定)は、鑑真本人と同じように扱われて、僧侶たちは代々「生けるがごとく、おわすがごとく」お仕えしてきたという。この像は脱活乾漆像(基体として塑像を作り、その上に漆に浸した麻布を貼り重ね、乾いて固まったのち塑像を抜き取る)なので言わば外皮・外殻だけであり、触感もまるで違うだろうし、エンバーミングやミイラの場合以上に、生身の肉体とはまったく別の物質である。しかし野林によれば「僧侶たちの言では、鑑真和上は死んだのではなく、和上像になっている」。となれば、それは追慕のよすがとしての似姿というよりは、鑑真の分身、人類学の術語で言えば distributed personと考えるべきである。また、たんなるレプリカではなく、本物と同一の技法を用いて製作された模像である「お身代わり」も、鑑真本人の諸身体のひとつである(になる)と解すべきであろう。ここでキリスト像や聖母像の生動性も視野に入れれば、人間のような形姿をもつ「からだ」が「生きている」様態は、実に多彩であることがわかる。武井秀夫の「からだを形作ることば」(2012.7.28)が取
り上げるのは、北西アマゾンの先住民トゥユカ社会で、人間のからだと本質的に同一とされるマロカ(住居)やシャーマンの床几などのモノが、いつどのようにして「生きたからだ」になるのかという問いであるが、その変化を実現するのは「正しく操られたことばとしての呪文」である。武井によれば、ことばは「本質的で固有なものである不可視のからだ」に働きかけて、その働きかけの効果が「からだの可視的部分においても発現する」のであり、「からだはものであり、かつことばでもあり、ことばがからだを形にする」。私なりに言い直せば、呪文は物質を活性化して、自らが何であるのかを思い出させるのである。つまり物質はすべからく、活性化されれば発現する様々なものから成り立っていると考えるべ
きだろう。この考え方は、モノとは質料に形相が付与された所産であるとする長く西洋で支配的だったアリストテレスの「質料形相論」(hylomorphism) とは正反対に見える。しかし彼の言う「可能態」とは意外なところでつながるのかもしれない。
チャージされる見えない物質
川田順造の「モノとケガレ:物質が内包する不可触性と不可視性」(2013.2.2)が俎上に載せるのは、「モノに付随する、見たり触れたりできない性質(ケガレや聖性など)」である。西アフリカのバンバラ社会では鍛冶師や土器つくり、ライオンや象やそれを仕留めた狩人、戦で多数の人を殺す王などが「ニャマ」をもち、モシ諸王国でも、鍛冶師や狩人や王などは強い「デグド」をもつ。ここで言う「ニャマ」や「デグド」は、触ると危険な強力かつ不可視の力であるが、これを物質性という観点から捉え直せば、ある種のモノにチャージされる見えない物質であり、それが本来あるべきではないところに溜まっている場合はディスチャージしないと危ないという点で、電気のようでもある。川田発表のもうひとつのテーマである日本の「付喪神」は、捨てられた古器物が生動性を獲得した妖怪であり、供養する必要があるが、この場合も、長年の使用をつうじて道具にチャージされた見えない物質の作用と見ることができる。「見えない物質」というテーマは、武井発表の「不可視のからだ」ともつながるが、物質のエコノミーは、可視と不可視の両方の領域にまたがっていると考えるべきである。そもそも可視・不可視とはたんに人間という生物の性能の関数であるにすぎず、物質の側の本質的属性ではない。
液体の物質性:血とか水とか直近の研究会(2013.6.20)では、Journal of the Royal Anthro-
pological Instituteの血をテーマとする特集号を材料にして、血の物質性について議論した(Carsten (ed.) 2013)。あちこちに溢血・出血・流血したその顛末については、また別の機会に瀉血(=報告)することにしたい。
【参考文献】Carsten, Janet (ed.) 2013. Special Issue: Blood will out: essays on liquid
transfers and flows. Journal of the Royal Anthropological Institute, vol.19, Issue Supplement S1.
ふるや よしあき
九州大学大学院比較社会文化研究院教授。専門は文化人類学。ブラジル・アマゾンを主なフィールドとして、憑依、土器、芸術、モダニズムなどについて考えてきた。著書に『異種混淆の近代と人類学』(人文書院 2001 年)、『憑依と語り』(九州大学出版会 2003 年)など。共訳書に、J. クリフォード『文化の窮状』(人文書院 2003 年)など。
鑑真和上お身代わり像(写真提供:唐招提寺)。
![2016.1.26 藤原忍 [互換モード]nsg-zaidan.or.jp/presentation/2016/pdf/4fujiwara.pdf7 物理的性質 蛍光体 化学的性質 構造制御による物理的・化学的性質の変化と機能創製](https://static.fdocument.pub/doc/165x107/5fd0c1ce252b2a26631bf139/2016126-e-fffnsg-7-ccce-e-oece.jpg)