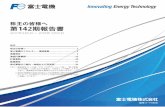病院のための 経営分析入門 - jiho.co.jp · 病院のための 経営分析入門 石井...
Transcript of 病院のための 経営分析入門 - jiho.co.jp · 病院のための 経営分析入門 石井...

病院のための経営分析入門
第2版石井 孝宜公認会計士
西田 大介公認会計士

30
Ⅱ 病院における経営分析のための基礎知識
病院経営分析の基本1
1 非財務情報や社会的情報が経営分析のカギ
①非財務情報の意味を理解する病院経営分析を始める際に最初に理解しておきたいことは,財務データの分析結果だけでは何も見えないということです。一般の企業経営を分析する場合,必要に応じて非財務情報や社会的情報を取り入れていきますが,病院の経営分析においては非財務情報や社会的情報をより積極的に加味しなければ何も見えず,経営評価そのものを間違えてしまいます(図2-1)。誤った分析結果は,全く説得力のない経営情報ということになってしまい,分析そのものの価値をないものとしてしまいます。病院経営分析の結果を用いて経営の問題点を改善しようとする場合,分析結果や問題点は診療部門や病棟,検査部門などの現場で働いている医師や看護師,その他の医療職種などに問題点や改善方法などを説明し,理解を得ることになります。したがって,極力,医療現場の現実に適合し,医療の現場スタッフが理解できる分析データを作成することが肝心です。経営体としての病院の最終目的は,病気に苦しんでいる患者さんに対して良質な医療サービスを提供することです。設備の装備率も決して低くはありませんが,医療サービス提供の中心は“人”であり,極めて労働集約的で高度なサービスを提供していることを前提としなければなりません。そういう意味では,病院経営分析は形式として行うことはできても実質的にその目的を達成することはなかなか困難かもしれません。
●社会的情報に関する知識を習得する
●非財務情報の重要性と情報の所在を理解する
●適切な財務情報を入手し,非財務情報と統合した分析を行う
●分析事業に関連する社会的情報を勘案し分析結果を出す
図2-1 病院経営分析を理解する

1 病院経営分析の基本
31
「病院経営管理指標」では,平成16年の調査開始から「収益性」と「安全性」の指標に関する項目に変化はありませんが,「機能性」の指標に関しては,当初の13項目から平成25年度においては21項目に増加しています。病院経営の「機能性」評価とは,病院が持っている診療上の機能特性を評価し,併せてその機能がどの程度有効に活用されているかを見るものです。このように「機能性」の指標が充実してきているのも一般の企業経営評価にとって大切な収益性や財務安全性,あるいは成長性よりも,病院経営評価においては非財務情報中心の「機能性」が重視される指標だからです。
②社会的情報の重要性を理解する病院経営分析を行う場合,社会的情報を十分に理解することも大変重要です(図2-2)。病院経営における社会的情報とは社会経済情勢,医療や社会保障に関する制度改革,患者ニーズの変化や技術革新といったことです。例えば,病床利用率が低い病院がある場合,収益性の側面からはいかに病床利用率(=稼働率)を高くするかが問題となります。病床利用率を上げる一番簡単な方法は,患者さんの退院を1日でも遅らせることで空き病床を減らすことです。これは,患者さんの平均的な在院期間を延ばすことになりますが,自動的に病床利用率が上がり収益性が改善することになります。しかし,これでは本質的な問題解決になりません。なぜなら,わが国の入院医療における平均在院日数は,一般病院の場合,欧米に比べ2~4倍の長さとなっており,それ自体がわが国の医療制度の重要な課題の1つで,平均在院日数の短縮が医療制度改革の中心的なテーマとなっているからです。また,患者さんの立場から考えた場合,入院期間が延びると経済
経済情勢の変化-経済財政の破綻
社会情勢の変化-少子高齢化
医療制度・変化の方向 ●医療提供体制の改革 ●診療報酬,薬価基準等の見直し ●医療保険制度の改革 ●その他-保険者との直接契約等 ●高齢者医療制度の改革
患者ニーズの変化 ●患者の権利意識の高まり ●インフォームド・コンセント ●医療の安全性への関心 ●リスク・マネジメントの必要性 ●医療情報提供の必要性(カルテ開示等) ●経営情報の開示
その他の環境変化 ●ICT ●公的医療機関の再編成 ●医療技術革命(遺伝子,再生医療等) ●営利法人の参入問題 ●医療の国際展開(医療ツーリズム,TPP等)
図2-2 病院経営をめぐる社会的情報

32
Ⅱ 病院における経営分析のための基礎知識
的負担が増えますが,最近の円安の影響などによる生活物価の上昇により,その負担感は一層高まっているものと考えられます。したがって,できる限り短期間に入院治療を完了したいと多くの患者さんは考えており,入院期間の長期化は患者さんの満足度を低下させることになります。このように病床利用率を上げるために平均在院日数を延ばすことは,制度の側面からも患者さんからも受け入れられない策となります。病院経営では,制度の変化や患者ニーズ等の社会的情報を理解しなければ経営改善の対応策そのものを立案できないケースがたくさんあるのです。
2 どうしても必要な会計知識
病院経営分析では,社会的情報の重要性を認識することと非財務情報の活用方法を理解することがとても大切であると説明しました。とはいえ,病院経営分析において計算される経営指標の多くは主として財務諸表から得られる財務情報を加工して算出されることに間違いありません。したがって,企業の経営分析同様,病院の経営分析でも「会計の知識」がある程度なければいけません。財務諸表を作成するために経理部門では日々「簿記」の法則に従って伝票や帳簿,試算表などを作成しています。「会計」に関する知識をきちんと得ようとすると何カ月かかけて簿記や会計学の勉強をすることになります。けれども,今ここで習得したいのは経営分析を行ううえで必要な会計の知識ですから,帳簿や試算表をどのように作るかといったことではなく財務諸表をどのように読んでいくかに関する知識です。財務諸表とは一般的には決算書ですが,会計学の立場からは財務諸表と呼び,経営体の経営成績や財政状態,すなわち財務の状況を表す複数の表(諸表)ということになります。そして,企業でも病院でも継続して事業を営みますから,事業期間を人為的に一定期間ごとに区切って経営成績や財政状態を確認しますので財務諸表の作成も一定期間ごとに行われます。この一定期間を一般的に会計期間といい,会計期間は通常1年間とされます。財務諸表は,会計期間ごとに通常は1年単位で作成されるということを最初に覚えてください。
病院の会計の基本と財務諸表の構造2
1 病院会計準則による病院の財務諸表
「病院会計準則」で定められている財務諸表を整理すると図2-3になり,貸借対照表

2 病院の会計の基本と財務諸表の構造
33
と損益計算書がいわゆる「複式簿記」によって作成される財務諸表となります。キャッシュ・フロー計算書は,旧「病院会計準則」では財務諸表の範囲に含まれていませんでしたが,その有用性から新「病院会計準則」においては含まれることとなりました。また,附属明細表は,貸借対照表や損益計算書の各項目に対する説明資料です。病院経営分析で主に活用される財務諸表は企業の経営分析と同様,貸借対照表と損益計算書です。キャッシュ・フロー計算書は,分析対象というより,それ自体が損益計算
キャッシュ・フロー計算書
病院の財務諸表
附属明細表
1.純資産明細表 2. 固定資産明細表3.貸付金明細表 4. 借入金明細表5.引当金明細表 6. 補助金明細表7.資産につき設定している担保権の明細表8.給与費明細表 9. 本部費明細表
損益計算書
貸借対照表
図2-3 病院の財務諸表
会 計 期 間( 1 年 間 )
●損益計算書(P/ L):一会計期間の運営状況を明らかにする財務表
●貸借対照表(B/ S):一定時点の財政状態を明らかにする財務表
●キャッシュ・フロー計算書(C/F):一会計期間の資金の増減の状況を明らかにする財務表
損益計算書自 平成 26年4月 1 日至 平成 27年3月 31日
キャッシュ・フロー計算書自 平成 26年4月 1 日至 平成 27年3月 31日
貸借対照表平成 26年3月 31日
貸借対照表平成 26年3月 31日
図2-4 財務諸表に書かれていること

70
Ⅲ 病院の経営分析
病院における一般的な経営指標の特徴1
企業経営を評価する視点としては,一般的に「成長性」,「収益性」,「生産性」,「安全性」の4つが代表的なものです(図3-1)。これに対して病院経営で着目する経営評価の視点は,企業経営の場合と少し異なります。具体的には「機能性」,「収益性」,「生産性」,「安全性」の4つです。営利企業にとっては常に成長を目指して利益を最大化することが重要な目的の1つなので,「成長性」は経営を評価するうえで重要な要素となります。しかし,病院の目的は良質な医療を適切にかつ効率的に提供することであり,財務的な経営数値が成長する必要は必ずしもありません。それよりも,その病院が医療的にどのような機能を果たしているかの方が重要であり,その際,いかに効率的に運営されているかが評価されるべき内容となります。このため,病院の経営指標としては「成長性」は一般的に重要視されず,「機能性」を評価する項目が中心にあげられるのです。ここで病院経営における「成長性」について考えてみたいと思います。確かに「成長性」は病院にとって本質的な目的ではなく,医療計画などにより病床に関する規制があるため,営利企業のように規模の拡大を追求することはできません。また,各病院がむやみに収益の拡大を目指した場合,第1章で示したようにわが国全体という視点から考えると,国民医療費の増加を通じて国の財政状態を必要以上に悪化させてしまう可能性
病院経営を評価する視点
病院経営の「機能性」評価
病院経営の「収益性」評価
病院経営の「生産性」評価
病院経営の「安全性」評価
企業経営を評価する視点
経営の「成長性」評価
経営の「収益性」評価
経営の「生産性」評価
経営の「安全性」評価
図3-1 病院を評価する4つの視点

1 病院における一般的な経営指標の特徴
71
があります。このように規模の拡大を追求することが難しいという病院経営の特徴は,病院経営の難しさにもつながっています。営利企業にとって,規模の拡大の追及は利益の最大化のためですが,規模の拡大は,規模の経済を働かせて収益性を向上させたり,昇進の機会を増やすことで職員のモチベーションを高めることにも非常に役に立ちます。わが国の政策においても「経済成長」は非常に重要視され,社会保障制度を含めた国の課題を解決する手段の1つとして「経済成長」を利用しようとしています。確かに「成長」または「規模の拡大」は,国,組織にかかわらず,課題の解決手段として有効な手段といえますが,病院経営ではこの手段が十分に活用できないのが実情です。そのため営利企業の経営に比べて,病院経営には「知恵」と「工夫」がより一層求められるのではないでしょうか。病院経営における「機能性」については,平成7年12月に大蔵省財政制度審議会がまとめた「歳出の削減合理化の方策に関する報告」で,増大する医療費抑制のために,①病院経営の近代化・効率化,②費用の無駄の排除,③有限である医療資源の有効活用が提唱されました(図3-2)。病院経営評価における機能性の評価は,まさしく病院がどのような機能を持っているか,自らに与えられた機能をどのように果たしているか,有限な医療資源を効率的に活用しているかどうかという観点から取り上げられた経営指標
Ⅰ 病院経営の「機能性」評価 フロー情報
病院が持っている医療機能を数値化した指標によって把握し,機能の状況やレベル・活用度合・医療施設資源の利用状況等を評価する
Ⅱ 病院経営の「収益性」評価 フロー情報
医業活動によって獲得した収益とそのために費消された人的・物的費用等の対応関係を明らかにすることで一定期間の経営成績を評価する
Ⅲ 病院経営の「生産性」評価 フロー情報
医療サービスの中心である人的資源に着目し,人的資源の稼働状況・単位コスト・労働生産性などを分析することによりその活用状況を評価する
Ⅳ 病院経営の「安全性」評価 主にストック情報
投下資本や保有資産の状況を調達と運用のバランスとともに収益性に基づく返済能力について評価する
図3-2 病院経営評価視点の説明

72
Ⅲ 病院の経営分析
です。そして,「収益性」は医業活動によって獲得した収益と費用の関係を見ることで一定期間の経営成績を明らかにし,「生産性」は特に人的資源の投入と産出の関係を明らかにし,医業経営の中心的な資源である“人材”の活用度合いを評価します。これら「機能性」,「収益性」,「生産性」の3つの評価視点は,一定期間の数値に着目したフロー・データからのものですが,最後の「安全性」は一定時点のストック情報が中心となっています。「安全性」評価は,投下総資本や保有資産の観点から機能性や収益性を見るとともに財務の安全性を確認するものです。
「病院経営管理指標」のポイント2
1 「病院経営管理指標」の概要
「病院経営管理指標」において示されている指標は表3-1の通りです。「病院経営管理指標」では「生産性」の視点について,病院の事業の性格上,生産性を一般産業のよう
表3-1 病院経営管理指標一覧「 機 能 性 」 の 指 標
① 平均在院日数③ 1床当たり1日平均入院患者数⑤ 患者1人1日当たり入院収益⑦ 外来患者1人1日当たり外来収益⑨ 医師・看護師・職員1人当たり外来患者数⑪ 紹介率⑬ 看護必要度の高い患者割合(一般病床用)
⑮ 2次医療圏内(外)からの在院患者割合
② 外来/入院比④ 1床当たり1日平均外来患者数⑥ 患者1人1日当たり入院収益(室料差額除く)⑧ 医師・看護師・職員1人当たり入院患者数⑩ ケアカンファレンス実施率⑫ 逆紹介率⑭ 看護必要度の高い患者割合(回復期リハビ
リテーション病棟用)⑯ 2次医療圏外からの外来患者割合
「 収 益 性 」 の 指 標
① 病床利用率③ 経常利益率⑤ 各種医業費用比率(材料費・医薬品費・人件
費・委託費・設備関係費・減価償却費・経費)⑦ 固定費比率⑨ 職員1人当たり医業収益⑪ 総資本医業利益率⑬ 固定資産回転率
② 医業利益率④ 償却前医業利益率⑥ 常勤(非常勤)医師・看護師・その他職員
人件費比率⑧ 常勤医師・看護師・職員1人当たり人件費⑩ 金利負担率⑫ 総資本回転率
「 安 全 性 」 の 指 標
① 自己資本比率③ 流動比率⑤ 償還期間⑦ 1床当たり固定資産額
② 固定長期適合率④ 借入金比率⑥ 償却金利前経常利益率

2 「病院経営管理指標」のポイント
73
に徹底して追及する産業ではないと考えています。つまり,例えば医師1人当り入院患者数は生産性の面からは多いほどよいといえますが,機能性の面からは少ないほどよいといえ,「生産性」の指標を取り上げることは病院の評価をミスリードする可能性を考慮し,「生産性」は「収益性」の補助的位置づけで,「収益性」に内包されることから独立した指標として取り上げていません。したがって,「病院経営管理指標」で取り上げられている指標は,「機能性」,「収益性」,「安全性」の3つです。ここからは,それぞれの指標の内容と基本的な指標についてポイントなどを解説していきます。
2 「機能性」分析で見るもの
「病院経営管理指標」における「機能性」の指標と内容は表3-2の通りです。⑩~⑫の指標は,機能分化と連携が政策上も経営上も重視されていることから,連携に関わる機能性指標として平成23年度から追加され,⑬~⑯の指標は,高機能性,急性期性を
表3-2 「機能性」の経営指標指 標 内 容
① 平均在院日数 入院患者の入院日数の平均を表す指標② 1床当り1日平均入院患者数 病床の稼働状況を表す指標③ 1床当り1日平均外来患者数 病床数に対して診療している外来患者数を表す指標④ 外来/入院比 入院患者数に対する外来患者数を表す指標⑤ 患者1人1日当り入院収益 患者1人が1日入院した場合の室料差額を含めた入院収益の
平均を表す指標⑥ 患者1人1日当り入院収益 (室料差額除く)
患者1人が1日入院した場合の室料差額を除く入院収益の平均を表す指標
⑦ 外来患者1人1日当り外来収益 患者1人が外来診療を受けた場合の1日当りの外来収益の平均を表す指標
⑧ 医師・看護師・職員1人当り入院患者数 医師・看護師・職員1人に対する入院患者の平均数を表す指標
⑨ 医師・看護師・職員1人当り外来患者数 医師・看護師・職員1人に対する1日の外来患者の平均数を表す指標
⑩ ケアカンファレンス実施率 退院患者のうち外部機関を交えたカンファレンスを実施した患者の割合を表す指標
⑪ 紹介率 初診患者に対する他の医療機関の紹介状を持参した患者と救急車で搬入された患者の割合を表す指標
⑫ 逆紹介率 初診患者に対する,他の医療機関に紹介し診療情報提供料を算定した患者の割合を表す指標
⑬ 看護必要度の高い患者割合 (一般病床用)
入院患者のうち一般病棟用の重症度・医療看護必要度を満たす患者数の割合を示す指標(一般病棟)
⑭ 看護必要度の高い患者割合 (回復期リハビリテーション病棟用)
入院患者のうち入院時日常生活機能指標が10点以上の患者数を表す指標(回復期リハビリテーション病棟)
⑮ 2次医療圏内(外)からの在院患者割合 入院患者に対する病院所在地の2次医療圏内(外)の入院患者の割合を示す指標
⑯ 2次医療圏外からの外来患者割合 外来患者に対する病院所在地の2次医療圏外からの外来患者の割合を示す指標

74
Ⅲ 病院の経営分析
示す指標として平成25年度から追加されました。
①平均在院日数在院日数は,患者が入院してから退院するまでの期間をいいます。その平均が「平均在院日数」です。「病院経営管理指標」での具体的な算式は以下の通りです。少しわかりづらい算式ですが覚えてください。
平均在院日数 = 在院患者延数
(新入院患者数+退院患者数)×1/2
平均在院日数の計算法にはいろいろな考え方があり,退院患者の在院期間を平均したり,ある時点の在院患者の入院日数を平均したりする方法もあります。しかし,どちらもたまたま長期間入院していた患者が退院したり,入院していたりすると大きく変動する可能性があることから「病院経営管理指標」では採用されていません。また,他の統計資料や診療報酬の施設基準で使用する平均在院日数は,異なる算式により計算されていたり一部の患者を除外して計算されていたりすることがあるため,それらの平均在院日数と比較する際は,それぞれの算式を確認したうえで比較することが大切です。平均在院日数は別の見方をすると病床の回転率とも考えられます。つまり,平均在院日数が30日の病棟は,病床が平均的に1カ月に1度回転したことになります。15日では2回転,60日では1/2回転です。平均在院日数は,同じ疾病をどれだけ短い期間で対応できているかという指標のため,まさに病院機能の代表的な指標と考えられ,診療報酬算定上でも一定の要件に加えられています。ただし単に短くすれば良いというものでもなく,診療結果とのバランスを見ながらなるべく短くすべき指標であると考えられます。平成25年の「病院報告」によればわが国の平均在院日数は総数30.6日,一般病床17.2日,療養病床168.3日,精神病床284.7日となっており,この10年間で総数は約16%短縮してきています。今後もこの傾向は確実に続くと思われますので,全体としての平均在院日数だけではなく,複数病棟・複数診療科の病院では病棟別・診療科別数値を算定するとともに,患者1人ひとりの個別の「在院日数管理」を経常的に行う必要が生じてきています。
②1床当り1日平均入院患者数病院が保有している入院病床1床に1日平均どのくらいの患者が入院しているかを表示するものが「1床当り1日平均入院患者数」です。内部の管理目的としては,「1床当り1日平均入院患者数」ではなく,単純に「1日平均入院患者数」を用いていることが

2 「病院経営管理指標」のポイント
75
多いと思いますが,「病院経営管理指標」においては病床規模の影響を排除し病院間の比較可能性を確保するために「1床当り」となっています。具体的な算式は以下の通りです。
1床当り1日平均入院患者数 = 在院患者延数
365日×許可病床数
分母になる病床には2つの考え方があります。1つは法律上使用することが認められている「許可病床数」,もう1つは「稼働(可能)病床数」です。「1床当り1日平均入院患者数」は医療機能の活用度合を評価する「機能性」の指標のため,本来稼働すべき病床である「許可病床数」で計算しています。病院は,入院治療を目的とする医療施設ですからその資源の大部分を入院部門に投入しています。このため,その資源が十分に活用されているかどうかは大変重要な経営上の要素となります。
③1床当り1日平均外来患者数「1床当り1日平均外来患者数」の算式は,以下の算式となります。
1床当り1日平均外来患者数 = 外来患者延数
365日×許可病床数
分母を365日としていますが,これは,統計上のデータ集計の都合から全病院を一律的に365日として計算するためです。つまり,土曜日の外来診療をしている病院としていない病院,している病院でも午前中のみの病院と夕方まで診療している病院など外来診療の日数や時間は各病院によってさまざまであることから,一律365日で計算するという考え方です。そして「1床当り1日平均入院患者数」と同様に,「病院経営管理指標」においては病院の規模の影響を排除した指標とするため,「1床当り」となっています。内部の管理目的で使用する際には,一般的に「1床当り」とせず,さらに,実際の外来診療日数(実外来日数ともいいます)を用いることで診療日数の増減による影響を排除した「1日平均外来患者数」を利用することが多いと思いますが,その際の算式は以下の通りです。