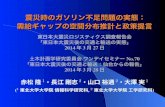就業規則例...中番 午前9 時30分 午後7 時00分 午後1時から2時 まで 午後5時から5時 30分まで 遅番 午前11 時00分 午後8 時30分 午後2時から3時
研究主題と分科会 - 公益財団法人三重県 ... · 研究主題と分科会 11...
Transcript of 研究主題と分科会 - 公益財団法人三重県 ... · 研究主題と分科会 11...

研究主題と分科会
11 月24日(木)
16 時 20 分~17 時 20 分
11 月25日(金)
9 時 00 分~10 時 10 分
研究主題
「青少年の意欲をはぐくむ
効果的な青少年教育施設の運営を目指して」
各分科会テーマ
第 1 分科会
「青少年の意欲をはぐくむための事業の展開について」
青少年教育施設が持つ資源を活かした体験活動を通して、意欲をはぐくむことができた事業の展開事例より、
評価法を踏まえながら研究協議を行う
第 2 分科会
「指定管理者制度と民間施設、団体との連携の在り方について」
指定管理者制度の持つ具体的な課題を通して、民間施設・団体等のノウハウの活用法や民間施設・団体との連
携の在り方を研究協議する

第1分科会
会場:プレイホール
11 月24日(木)
16 時 20 分~17 時 20 分
11 月25日(金)
9 時 00 分~10 時 10 分
第 1 分科会
「青少年の意欲をはぐくむための事業の展開について」
青少年教育施設が持つ資源を活かした体験活動を通して、意欲をはぐくむことができた事業の展開事例より、
評価法を踏まえながら研究協議を行う
司 会 者 国立立山青少年自然の家 主任企画指導専門職 坂川 智幸
発 表 者 三重県立熊野少年自然の家 指導主事 西村 道登
記 録 者 富山県砺波青少年自然の家 社会教育主事 江田 邦彦
会場担当 三重県立鈴鹿青少年センター 専門員 高野 瑞希

第1分科会 研究発表要旨
長期宿泊体験学習「真夏のロングキャンプ」の取り組みから
三重県立熊野尐年自然の家
指導主事 西村 道登
Ⅰ はじめに
熊野市南部の金山町にある三重県立熊野尐年自然の家(海抜約180m)は、青尐年の健全育成に加え、地域の芸術文化、スポーツ活動、地域住民の交流を図る多目的宿泊研修施設として、昭和52年1月15日に創設され、平成22年度から指定管理者制度により(有)熊野市観光公社が管理・運営しています。 三重県立熊野尐年自然の家では、年間約 30 の事業を展開しており、どの事業も好評をいただいています。特に、夏
休みに行われる長期宿泊体験学習「真夏のロングキャンプ」は、当施設としても最も力を注いでいる事業の一つです。
Ⅱ 研究内容
1 事業名
「真夏のロングキャンプ(小学4~6年生)」 2 事業の趣旨
4泊5日の自然体験活動、集団体験活動を通じて、規律、協調、奉仕等の尊さを体験的に学習させるとともに、豊かな情操を培い、心身ともに健全な尐年の育成を図る。
3 取り組みの概要 7月に4泊5日の日程で、児童 18名、ボランティア 6名で実施しました。 1日目は竹細工作りをし、それを使って野外炊事で作った料理をおいしくいただきました。 2日目はシーカヤック、砂アートと海での活動を行いました。夜はきもだめしをして楽しみました。 3日目はいかだを作り、それを使って競争をしておおいに楽しみました。 4日目は山歩きとアマゴのつかみ取りを体験しました。 最終日は自然の家でのフィールドアスレチックとグランドゴルフを楽しみました。
Ⅲ 成果と課題
1 取組の成果
(1) 箸やコップ作り、野外炊事を通して生活に必要なことを自分ですることによって、意欲が芽生えた。 (2) きもだめしやスイカ割りをすることによって、仲間意識が高まり協調性が養われた。 (3) 砂アートで創造力を引き出すことで、豊かな感性が育まれた。 (4) シーカヤック、いかだ競争、山歩き及びアマゴつかみ取りをすることで、自然とのふれあいが体験できた。
2 今後の課題 (1) 募集方法の改善の一つとして、チラシのレイアウト等を工夫する。 (2) プログラムを充実させるため、新メニューの開発をしていく。 (3) 大学生等、ボランティアの確保は、早い時期から募集をしていく。

記 録
(1)発表
① 熊野尐年自然の家の概要
熊野灘が一望でき、海抜は180m。昭和52年1月15日開所。平成22年4月1日指定管理
となる。特徴のある活動として、スターウォッチングを年に10回など30事業を行っている。
他に31種目あるフィールドサーキットなどもある。マスコットは〝タヌゾー〟
② 真夏のロングキャンプについて
4泊5日の自然体験活動、集団体験活動を通じて〝規律、協調、奉仕〟の尊さを体験的に学習
させ、豊かな情操を培い、心身ともに健全な尐年の育成を図る。小学4~6年生の児童18名(県
外から3名)とボランティア6名で実施。宿泊は家と四季の里(車で30分)。
≪日程≫
1日目:アイスブレイク、自己紹介、クラフト真竹コップスプーン作り、小刀の作業(指導はボ
ランティア)、野外炊さん(カレー、飯ごうでご飯、かまどは一斗缶、作ったコップと
スプーンで食べる。)
2日目:シーカヤック(指導は熊野マリンスポーツ推進協会)、砂アート(花、城、亀、象など、
後から投票し展覧会)、すいかわり、きもだめし(日光庵。飛鳥神社をまわり、札を取
ってまわってくる)
3日目:筏作り(コンテナに発砲スチロール)川遊びで川のきれいさや森について学ぶ、竹笛作
り(四季の里工房)、ユニカール(晴の場合は天体観測)
4日目:リバートレッキング 紀州鉱山トロッコ乗り(観光用で使用、自然のクーラー)&山歩
き、B&G 海洋センタープール、アマゴのつかみ取り
(アカグラにアマゴ養殖)、チキン、アマゴでバーベキューパーティー、キャンドル
サービス(自分の言葉で伝える場面)
5日目:フィールドサーキット(7番目のムササビスライダーが人気)、グラウンドゴルフ
≪成果と課題≫
成果・自分でやることでやる気
・肝だめし、スイカ割りで仲間意識や協調性
・砂アートで創造力オリジナリティ豊かな感性
・自然とのふれあい
課題・募集方法の改善チラシのレイアウト
・新メニューの開発
・ボランティアの確保
③ 熊野尐年自然の家の利用状況について
今年度の4月~10月の利用状況、主催事業の内容と参加状況について
④ 広報活動について
年間チラシは主催事業一覧を小学生全員と中学校のクラスに1部ずつ配布している。主催事
業は、その都度チラシを作成し、配布している。(6,000枚)他に平成22年度よりホー
ムページの公開、ローカルテレビやローカル紙等の報道関係へ取材依頼を行っている。

⑤ サービス向上について
食時メニューを A~Cの3つのコースに拡張している。(スタンダード、ボリューム、デラック
ス)
(2)発表についての質疑等
質問:楽しいプログラムが目白押しで、写真の笑顔からわかる。成果課題の評価は何でとらえたの
か教えてほしい。
回答:作り上げている姿や雰囲気などから評価している。
意見:現場の観察、読み取り、アンケート(安易なもの、深まりのあるもの)などは、ある意味自
己満足になってしまい、われわれが陥りやすいことがある。
「生きる力」を育むため、家や地域に戻ってできるのか検証することが大切である。これは、
家の価値になるのではないか。
国立で使用しているもので数値化(合宿に入る前、終了後にアンケート)1ヶ月後に親御さ
んに変化を見てもらっている。生かされているのかを検証 学校にも協力を求める。高学年、
低学年それぞれの工夫は参考になるのではないか?
(静岡県立観音山尐年自然の家 下石所長)
質問:活動フィールドを家の他に活用しているが、移動はどのようにしているのか教えてほしい。
(国立若狭湾青尐年自然の家 増川所長)
回答:熊野市観光公社のマイクロバスを使用し、運転手を雇っている。
質問:参加費と参加者の定員を教えてほしい。(富山県砺波青尐年自然の家 藤崎指導主任)
回答:参加費は16,000円、定員は30名(マイクロバスの人数)
質問:全て指定管理の職員なのか教えてほしい。(福井県立青尐年センター 熊田主任)
回答:全て熊野市観光公社の職員である。
※各自の質問等を記入し、初日の分科会終了。
(3)発表に対しての回答・協議
※初日の質問等を5つの項目に絞り回答しながら協議を行う。
① プログラムの企画について
質問:施設の持つ資源を有機的に活用しているが、プログラム作成上の意図(ねらい)は?
回答:山川海を頭に入れて考えている。OBにも依頼し、いろいろな体験をさせてやりたい。
距離もあるので、活動を充実させるために移動はバスで行っている。
アイスブレイク後、竹でコップや箸を作り、その後の食事にずっと使う
(自分の物として愛着をもつ)。
最後にキャンドルサービスで振り返る場面を設定している。
自然に合わせて柔軟に対応できるように荒天時のメニューも組んでいる。
質問:参加者の定員と班編制のねらいと異年齢集団での社会性の育ちは?
回答:バス移動のため、バスの乗車定員で募集している。高学年をリーダーにしている。
水泳等はアンケートをとって班編制をしている。
質問:経費で参加者負担の軽減について工夫をしているか?
回答:食費を抑えるようにしている。
質問:意欲を育むためのキーワードは?「失敗」体験と「成功」体験など

回答:意欲の面では、何事もぎりぎりまで待つようにした。
尐しのアドバイスで質問することが増えてきた。野外炊さんでは、自分たちで作ったカレー
でまとまりがでてきた。活動メニューを重ねるにつれ、時間を守ったり、自由時間を作った
りとチームワークがよくなった。
② キャンプの運営について ボランティアについて
司会:活動上のねらいを考えると、プログラムの順番や4泊5日の日が必要。また、男女混じって
の異年齢で行うことや、保守点検などが必要となるが。
回答:現場を見て確認したり、地元の人の意見を聞き協力してもらったりしている。使用箇所や用
具等の整備や避難場所の確保を行っている。過去の先輩がボランティアとして協力してもら
っている。
司会:地域に根ざした活動は大事だが、ボランティアについては?
回答:近くに大学がなく、早く動かないと行けない。高校生や大学生も確保したい。
地元の技術や技能を持った人の(OB)の協力がある。打ち合わせは、前日と当日行っている。
司会:謝金は?
回答:1回5,000円程度。
③ 評価について
司会:事前アンケート調査があって班編制があるが、評価はどのようにしているのか?
回答:どう評価していいかわからないが、目に見えた変化、観察で行っている。「楽しかった。」「次
に参加したい。」という声から。
司会:また来てくれるのがうれしい。昨年のキャンプの様子から改善点は?
回答:歩くのはハードにし、テント泊やつりでは夏の暑さを体験するように、移動は距離もあり疲
れるのでバス移動にした。
司会:子供たちの負荷については、子供たちの声から?スタッフの思いから?
回答:アンケートからも両方もある。
司会:職員数が尐ない中、30本事業があり大変だと思うが、見直し改良点について。
回答:指定管理は3年間の2年目である。100項目ぐらいで評価しているが 全て3~4以上
という努力をしている。利用者数を増やすのがプレッシャーでもある。
質問:利用団体への指導や指導力の向上対策として取り組んでいることは?
回答:職員6人のうち指導は3人である。夏場にはボランティアにも協力してもらっている。
質問:おすすめの活動は?
回答:ハイキングや野外炊さん、スターウォッチングなどが挙げられるが、もっと開発したいと思
っている。
④ 広報について
質問:広報はどのようにしているのか?
回答:事業毎にパンフレットを配布している。6,000枚印刷し、全小学生に配布している。ま
た、道の駅などにも掲示している。その他 HPに掲載、チラシ配布、地元のテレビや新聞な
どに取材依頼などを行っている。
質問:チラシのレイアウトで工夫していることは?
回答:一見見にくいという話も聞き、レイアウト等の工夫が必要である。

司会:開催要項の HPでの UPについて、作る上での工夫やいいものは取り入れるようにしている。
⑤ その他
質問:〝意欲を育む〟ことを考えた時に、資源の尐ない中で求められるかどうかを企画する時に
考える。直接指導する場合、どう接するかが大切だが、トラブルがあったときにどう対応
しているか?また、指導力をつけるために何か工夫していることは?
(富山県呉羽尐年自然の家 六渡社会教育主事)
回答:同じ目線で一緒に一生懸命取り組むことが大切だと感じている。要所では OB に協力して
もらったりしている。
質問:〝趣旨にそったプログラムの実施をして評価〟という一連の流れについて定期的に整理し
たらいい。オープンにしていくと目に見えてくる。また、 施設・組織全体のレベルアッ
プにつながっていく。(国立若狭湾青尐年自然の家:増川所長)
回答:評価については、難しいと感じているので、また教えてほしい。
司会:評価の取り組みについては?
意見:意欲を大切にした取り組みの中で、子どもから「次、なにする?」という言葉が出た時
は見通しをもっていないことになる。
そこで、それぞれの日にテーマを〝住む、歩く、燃やす〟と設定し取り組んでいる。
また、観点を示して一日ずつ日記を書かせている。生の声を聞き、次の機会につなげ、
生かすように努力している。ふりかえりは最終日に30分設け、繰り返しながら成長を待
つ。職員、ボランティア、指導者にもアンケート等でふりかえり、次に生かすようにして
いる。(富山市野外教育活動センター:森田指導係長)
意見:所の我々に対する客観的評価(外部評価)なども大切。自然の中では、楽しさばかりでは
なく鍛えるという学校でできない体験ができる。そのために指導力を UPしたり、研修を積
んだりしていくことが課題である。(静岡県立観音山尐年自然の家:下石所長)
意見:施設のアンケートとして、接遇もあるが、事業に対しても評価している。評価目標があっ
て定期的に点検するといい。(国立若狭湾青尐年自然の家 増川所長)
司会:指導の場面で子どもたちに気づいてほしいということがあるが、その場面の蓄積が大切だ
と思うが、何かいい方法はないか?
意見:満足、やや満足、やや不満、不満の4段階で評価をしている。
(三重県立熊野尐年自然の家:大崎副所長)
意見:評価には地域性があり、違いが出ると思う。客観評価なので受け止める必要がある。
(国立若狭湾青尐年自然の家:増川所長)
意見:「施設は人なり」と言われるが、人が最大の課題となる。職員がスキルアップして変わっ
ていくようなればいい。(国立立山青尐年自然の家:澤井次長)
司会:施設、活動プログラム、指導などこれから情報共有をして、悩み事などを相談できる環境
を作っていきたい。

第2分科会
会場:多目的ホール101
11 月24日(木)
16 時 20 分~17 時 20 分
11 月25日(金)
9 時 00 分~10 時 10 分
第 2 分科会
「指定管理者制度と民間施設、団体との連携の在り方について」
指定管理者制度の持つ具体的な課題を通して、民間施設・団体等のノウハウの活用法や民間施設・団体との連
携の在り方を研究協議する
司 会 者 愛知県青年の家 副所長 金子 一元
発 表 者 石川県立白山ろく少年自然の家 所長 北濃 松喜
記 録 者 高岡市二上まなび交流館 指導主任 栗山 満
会場担当 三重県立鈴鹿青少年センター 専門員 加藤 拓史

第 2分科会 研究発表要旨
本所における指定管理者制度導入のメリット
(地域資源を生かした経営の始まり)
石川県立白山ろく尐年自然の家
所長 北 濃 松 喜
Ⅰ.はじめに
白山ろく尐年自然の家は、昭和48年に県内最初にできた県立の青尐年教育施設であり、石川の子ども達の宿泊訓練を伴う
野外体験活動をリードしてきた感がある。その施設も老朽化には勝てず、近年の利用団体のアンケートでは、「活動内容はとて
も良いが、施設の建て替えができるといいですね。」といった意見が多く寄せられるようになった。
本県の自然というと、雪深く「霊峰」と詩歌に詠われた白山連峰を中心とした南加賀の自然と、日本海の荒々しい自然のな
かで培われた人々の優しさや人情を含めた奥能登の自然がある。
本所は、白山のふもとの手取川とその支流に挟まれた河岸段丘に位置し、白山ろく特有の動植物に恵まれた標高 300か
ら 1700 メートル地形を生かし、登山、谷川遊び、スキー等の野外活動をしている。また、近隣には、白山自然保護センター、
恐竜化石産地、手取川ダム、白山スーパー林道などがあり、これらの施設等を利用した活動を取り組むことができる。
指定管理に移管したのは平成 19年度であり、昨年で三年間の一区切りを終え、本年度から引き続き「白山市地域振興公
社」が指定管理者になっている。
どの県のどの施設も違わず、人不足、物不足、予算削減等の課題を抱えているのではないか。このことについては、本所も
同様な悩みがあるが、今回の発表では深く触れることはせず、指定管理者制度に移行し、良くなったと思われる面もあるので、
そのことについて、状況をお知らせしたい。
Ⅱ.研究内容
(1) 指定管理者制度になり、良くなったと思われること
① 手続きが簡素になり、早く決済できる。
・ 県に比べ、手続きが簡単。決済のはんこの数が尐ない。
・ 距離も近い。(県庁まで41キロ。今、20キロ。)書類の移動時間が半分。
・ 制約が尐なく、所の意向をつたえやすい。決済も所の意向をくんでくれる。
・ 臨時職員の採用が容易。シルバー人材、地域の人を採用しやすい。
(キーワードは、地域振興。公社の最終目的は、地域産業の振興、へき地での就労先の確保等)
② 予算執行が、迅速に行える。
・ 小口現金(10万円)が持てるようになった。後決済でよい。→量販店が使える。
③ 地域の人とのつながりが密になった
・ 振興公社職員は地域の人であるので、地域の人のことや地域の中のことが隅々までわかる。
・ 書類なしのお願いが通る。
④ 地域の施設が使いやすくなった。
公社の管理施設数は44施設
(温泉・保養施設、体育館・プール、教育・展示施設、地場産業施設、白山管理施設 等)
・ 連携することで減免、無料が可能。
・ 無理な使用形態のお願いができる。
⑤ 公社備品が使える
・ 県立の時の機動力は、所バス1台、4輪駆動車1台であったが、他に公社の 2台の軽トラックが使えるほか、公社
各施設が保管するバス、除雪機等の利用が可能。
→公社バスの利用は、利用団体の負担を軽減し、要望に広範囲に対応できるようになった。
⑥ その他
・ 公社他施設と連携したプログラムの開発が容易。
(2)課題になっていること
① 老朽化した施設の修繕と改修
② 公社職員と県派遣職員(県からの指導担当教員)との関係のさらなる改善
③ 地域振興を兼ねた「地産地消」の推進

Ⅲ.成果と課題
三年間の指定管理が終わり、振り返れば、初年度は多くの問題を抱えながら、解決に苦労したという話も伝え聞く。
とくに、派遣職員(県からの指導担当教員)と指定管理者職員との関係である。ぎくしゃくした関係は全くないわけではないが、
このことについても3年間の時の流れが多くのことを解決してくれ、互いの領分を理解できるようになってきている。
指定管理になり、本所において一番の成果は、地域とのつながりが密になり活動がしやすくなったことではないか。また、民
間の良さは、目的がしっかりしておれば、足が軽くすぐに対応できることではないか。この利点を生かし、決済の迅速化を図り、
地域人材地域資源の利用、また、公社他施設との連携により、機動力の強化とプログラム開発を今後も行いたい。
なお、今後の課題は、施設の老朽化をどのように乗り切るかである。修理費・維持費がかさむが、県からの指定管理料は増
えない。また、予算には毎年シーリングが 20%掛かるなど、所の努力だけではどうにもならないものがある。このような難題は
あるが、指定管理のメリットを生かし、関係機関との連携を図りながら、利用者から「また来たい。」と言われる施設をめざし、
活動の充実を図りたい。
メモ

第2分科会 事例研究発表 記録
司会者 金子
岡崎にある愛知県青尐年の家に勤務している。創立52年目、新築移転17年目、指定管理2期目、6年目の
施設。
指定管理の在り方、様々な問題点を皆さんと話し合っていきたい。
発表者 北濃
学校を退職して、今の所で2年目。
指定管理にはいろいろな形があり、地域の公社、民間がやっている所もある。活動の様子を伝えながら、今回
のテーマに迫っていきたい。
石川県立白山ろく尐年自然の家は、昭和48年創立の38年目である。
指定管理者制度導入のメリットについて話をしていきたい。また、地域資源を生かした経営についても話して
いきたい。
<パワーポイントの資料を使いながらの発表>
※資料参照
司会者 金子
平成15年の地方自治法の改正、16年から本格導入された指定管理制度であるが、管理者は外郭団体、
NPO 団体など様々である。
淡路、能登の研究大会でも、指定管理制度を導入しての問題点を中心にして報告があった。その中では、
お互いに良いところを見習っていこうという話し合いがなされてきた。
今回の発表では指定管理者導入の長所を多く出してもらった。
経費削減とサービス向上の相反するところをどういうふうにすり合わせていくか、利用者満足度を上げ
ていくことが私たちの最大の課題だと毎回話し合っている。
今日の報告内容では、指定管理制度のいいところをたくさん発表していただいたので、みなさんはどの
ように受け止めたのか、自分たちの所と比べてどうかを考えながら、発表された内容で質問してみたい
こと、疑問に思われたことなどを断片的で結構なので、問題提起という形でもよいので出していただき
たい。
<質疑応答>
関口(富・二上)いずれも晴れの時の活動の様子の発表だが、雤の時はどうしているのか。暖冬で雪が尐ない
時はどうされるのか。
北濃 昨年3mの雪が降った。スキー場では4~5m ある。むしろ雪が多すぎて営業ができなくてもったいな
い時が多かった。
雤の時についてだが、白山の場合、里が降っていても山は降っていない時がある。そのような天候を見
極めてやっている。
関口 川は、増水してだめでしょう。
北濃 川は、宿直の職員が川の状況を見て、水量の調節をしている。小雤程度ならやる。
オリエンテーリング、追跡ハイキング、そばとか工作など、みなさんと同じようにやっている。
服部(福・三方)福井県はどこも指定管理者制度を導入していない。公社と民間と競争してよく勝てたなあと

いう感想をもった。給食関係で、特に11,12月利用者が尐ないのに経営が成り立つのか。利用料金、
依然と比べてどれくらい高くなったのか知りたい。
北濃 公社が勝てたのは、県も分かっていたのだと思う。本当に民間だったら教育に弊害が出るであろうと思
われる。教育に携わる人ではなかったので、提出書類で子どもを育てるような文章が書けなかったから
ではないかと思う。
給食については、11,12月は、はっきり言って赤字である。ただ、年間のトータルでやっているの
で11,12月が赤字でも他の時期で補える。昨年は、年間百数十万円の黒字が出て、公社から施設に
入れてもらった。
利用料金は県の規約の中で決められている。
服部 民間だと料金は上がるのか。
北濃 規約に決められているので、それを守らないといけない。
? (だれかは不明)利用料金の収入については、公社のものになるのか県へ納めるものになるのか。
北濃 県には納めない。公社がもらう委託金(白山青年の家と尐年自然の家で3千万円)と利用料金の収入で
やりくりすればよいということになっている。儲かったからといって県に返す必要は無い。
関口 派遣の先生の給料は、委託料の中に入っているのか。
北濃 入っていない。派遣の先生の給料は県教育委員会から支払われる。委託料は、公社職員の給料、施設の
維持費など。
川村(福・市尐年自然の家)耐震工事についてはどのようになっているのか。
北濃 耐震工事はしていない。耐震補強をしていかなくてはならない施設だが、お金がないということででき
ない。
川村 福井市尐年自然の家の場合は、なかなか予算がつかない状況で学校の方が優先されている状況である。
永井(愛・美浜)公社職員13名、所の管理について清掃、食堂、すべて公社がやっていると理解すれば、民
間委託している業務はどんなことか。
北濃 施設のライフラインのメンテナンスに来る業者、ごみを取りに来る業者以外には、民間が関わっている
ことはない。公社の方でやっている。
永井 指定管理者になる前、県の職員が行っていた時は、食堂、清掃は?
北濃 県の嘱託職員がやっていた。
宮崎(石・国能登)指定管理者として参加する場合の条件はあるのか。指定管理者の期間は何年か。
北濃 詳しくわからないが、条件はないと思う。県で公募される。だれでも応募できる。
宮崎 石川県立の4施設の全てで公社が指定管理者になっている。言い方は悪いが、民間が受けるのは非常に
難しいと考えられるが、その点についてはどうか。
北濃 どのように採点しているかは分からないが、教育の場ということを県は考えているのではないかと思う。
選定の段階で、民間は教育の話がうまくできなかったのではないかと思われる。
宮崎 公社が受けたときは、手助けがある。民間だとそれが難しい。今後、もし民間が受けた場合のことにつ
いての検討はしているのか。
北濃 していない。受けてもらいたくない。本当に民間が入ってくるのかなと県は思っている。
指定管理の契約期間は、3年間である。
平井(富・野教活セ)公社が指定管理を受けた経緯の中、もともとの職員は、そのまま公社の職員と入れ替っ
たのか。
北濃 県職 3名の教員は引き続きやっている。一部の公社職員は、前から残った人がいるが、大多数はかわっ
た。県の方針としては県の教員を徐々に減らしていく予定であったが、教育の場であるので子供の扱い
が良い先生を抜くことはできないのではないかと思う。だから、民間には、できないのではないかと思

う。
関口 県民ふれあい公社というものは、いわゆる石川県のふれあい公社なのか。
北濃 石川県がもともと出資してつくった公社である。
関口 そこの理事長は県の副知事などがやっていて、いわゆる県の下部組織のようなものだと思うが、耐震工
事はやっていないのか。やる予定はないのか。
北濃 この先は分からない。
関口 指定管理者制度の必要性がよく分からない。東京や大阪などの都会の民間業者ならノウハウをもってい
るかもしれないが、こんな田舎でそのようなノウハウをもっている業者はいないと思う。とにかく経費
を安くしたい。そして、県はすべて職員を引き上げる。先生の数を尐しずつ減らし、最後はゼロにする。
耐震工事は、白山市で全てやってくださいというふうになるのではないか。
北濃 それはない。基本的に県との協約の中で、50万円を超える修繕は県が検討する。暖房器の修繕は 2年
越しで行う予定である。
司会者 金子
指定管理を受けて、管理運営していく団体にもいろいろあり、公社が管理運営していく時にはこのよう
なことがありますという今日の発表だったかと思う。
閑散期、繁忙期でのつり合いのこと、建物の老朽化に伴う予算や経費について今後どうしていくのかと
いう悩み、職員のこと、指定期間のこと、次に指定管理を受ける時のノウハウなど、たくさん意見をい
ただいたので、発表者と司会者で明日の話し合いの柱を作って、明日の協議を深めていきたい。
第2分科会 研究協議会 記録
司会者 金子
今日の協議会の柱として4つほど考えてみた。
一つ目は、人材育成のこと。職員の指導、優秀な人材を育てていくためには、どのようなことが大事な
のか。実際にどのようなことに取り組んでいるのか。
二つ目は、経費の面。人件費、管理運営費などの経費の面、さらに経費削減に向けてどんな努力をして
いるのか。
三つ目は、今回のサブテーマにも上がっている地域あるいは企業等との連携の在り方、そこでの問題点、
課題、成果、団体のもつノウハウなどについて話し合っていきたい。
時間があれば、みなさんから出された意見をもとにして進めていきたいと思う。
<協議>
人材育成について
赤堀(愛・県青年の家)指定管理者制度で行政が目指しているのは、経費削減である。経費削減で一番大きな
ウェートを占めるのは人件費であると思う。
白山の場合は、指定管理の形としては特殊であると思う。愛知の場合は、指定管理になった時点で、教
員4名は引き揚げられた。人件費を削減して運営をしていく場合、教員が受け持っていた部分をどうす
るかが大きな課題であった。
愛知県青年の家の人件費が7千万円であったのを4千万円にして、3千万円の人件費を浮かした。そし
て、教員 OBと補助する若者を雇い入れる形をとらざるを得ない。我々の場合は、NPO法人が指定管理者

になっており、100%民間である。NPO法人の中にそういった若い人材がいない。契約期間が5年で、
次に指定管理者をとれる保証がないので、新しい人を雇っても継続して働けるかどうかは分からない。
そんな中で、各施設はどのように人材育成をしているのか教えてほしい。
司会者 金子
それぞれの所では、人材育成にどのように取り組んでいるか。
白山ろく尐年自然の家では、どのようにしているのか。
北濃 非常に深刻な話だと思う。5年たったらどこに勤めたらよいのかという話になる。
静岡の三ヶ日の事故の後、民間だけではだめだという話が出たのではないかと思うが、静岡の方の話を
聞いてみたい。
鎌田(静・焼津)三ヶ日の事故後、県が指定管理者制度が良いのか議論をしているところなので、焼津青尐年
の家は今年から指定管理者制度を導入する予定であったが、今後どのようになるのか把握できていない。
人材育成のことで困っているのは、いつ指定管理が来るのか分からない段階なので計画的に人事異動が
できないことである。
北濃 県は先生を残してくれたので助かっている。先生がいなくなった時の問題として、先生の代わりの指導
をだれがどこまでするかという問題が出てくる。引率の教員に任せるのか、所員が全て面倒を見るのか
によって、指導者のレベルをどこまで上げるのかという問題も出てくる。その体制を変えないで今まで
通り先生がやっていたことをそのまま全部するのは無理で、危険な状況が出てくるのではないかと思う。
赤堀 地域の方、大学生に技を伝達しているようであるが、将来的にその人たちが育ってきた場合、いわゆる
先生たちがいなくなっても運営できるのかについて何か見通しをもっているか。
北濃 まず無理ではないかと思う。地域の人もずいぶん活動に入ってもらっているが、それだけでは足りない。
子供の成長を知っているかどうかがものすごく大事だと思う。我々は、指導的な立場の人には先生がよ
いということを県に訴えていこうと考えている。
金子 イベントをプランニングするには、ある程度ノウハウをもった人でないとできない。そういった職員を
育てていかなければならない。どこの施設も頭を悩ませるところではないかと思う。
地域から専門家を呼んでくるというのも1つのプランとしてあり得る。白山の場合はどうか。
北濃 石川県のある施設では、教員が全員引き揚げられた。そこへ自衛隊の職員を入れた。野外活動の能力は
もっているが、そこの施設の人気がなくなった。子供達への指導が、自衛隊員へ指導するのと同じよう
にしてしまったからだと思う。規律が厳しくなっただけで体験がおもしろくないという話が出た。やは
り、教員ができる事との違いがあり、そのことを県に訴えた。
石原(愛・県青年の家)三ヶ日の件が出た時に思ったのは、職員が活動現場の天候について熟知していなかっ
たからではないかと思う。何年か体験して体で分かっているような指導者が育っていかないと、場の安
全確保、魅力ある工夫ができないと思う。
指導者を養成したいと思っているが、補助に入ってくれている大学生は研修の場がなかったり、与えら
れていなかったりするので実力がない。参加者はある程度の楽しみやニーズをもって参加するが、指導
する方は素人に近い。
昨日の発表で思ったのは、これだけのプログラムをやっていく時に、それぞれ所員がつかないと安全確
保ができないのではないか、ある程度のお金と時間をかけて育てなければいけないのではないかという
ことである。
金子 自然の中へ出た時は、事故のことを必ず考えておかねばならない。白山の場合、安全面や専門的な指導、
参加者に与える満足についてどう考えているのか。
北濃 相当高いレベルの先生がいて、山のことなど熟知している。所長は、安全確保にあたる。優秀な先生が
出て行った場合はどうするかに頭を悩ませている。また、平均年齢は50歳を超えているので、肉体的

にきつい。いかに、20代、30代で若返らせていくか、引き継いでいくかについても大きな問題であ
る。
金子 人材育成、経費削減などで意見はないか。
石原 地域の人材をどのように募集したり、情報を集めたりしているのか。
北濃 公社職員は地元の人が多い。地元の人から情報を集めている。情報が入ってくることでつながりができ
る。
金子 経費について各所で取り組んでいる工夫などはないか。
赤堀 地域の方への謝礼、ボランティアに対しての経費は、白山の場合はどうしているのか。
北濃 地域の方への謝礼については県の規定に基づいて行っている。ボランティアに対しては無いに等しいが、
申し訳ないので図書券を出している。
小林(静・国立中央)ボランティアの交通費は支払わないのか。
北濃 図書券の中に含めてある。大学の方からは、それでよいと言われている。
小林 指定管理者制度の具体的な中身について知りたい。
企画提案の時に、年間の管理費や人件費を含めた金額が提示されていて、内容で審査されるのか。いろ
いろな仕様があって金額までも含めた提案で審査されるのか。
年度途中で経費が足りなくなったときは、追加申請が認められるのか。
食堂での儲けがもらえたという話のなかで、儲けとはどういうものか。どういう扱いをするのか。
赤堀 昨年度、指定管理の提案書を書いた立場から話をする。総額いくらという形で全て提案する。経費の部
分は大きなウェートを占めている。うまく計算しないと他の団体に負けてしまう。
途中でお金が無くなった場合、補助は一切ない。全て、赤字部分は法人で受け持つ。台風などの災害に
よる時は、協議事項としている。
儲けについては、どれだけ儲けても良い。利用料金収入のアップに営業努力をする。
自分としては、青尐年教育施設の指定管理者制度の導入は反対である。
小林 施設の利用料金、食事の価格、主催事業の参加費などは、全て所が単独で決められるのか。
赤堀 利用料金については、県の規則で決まっているので変えられない。主催事業の参加費は所で決められる。
宣伝を兼ねて赤字覚悟でやらないと人が集まらない。
金子 青尐年教育施設は指定管理者制度にそぐわないという意見があったが、詳しく話を聞きたい。
赤堀 教育はお金がかかる。予算を見ても大きなウェートを占めている。教育で金儲けをするのはあまりした
くないが、せざるを得ないという状況の中で、青尐年の健全育成という県の方針があるので、県が指導
権をもってきちんとやるべきである。
指定管理を勝ち抜くためにいろんな提案をするが、利用客増が大きなポイントとなる。利用客増にする
にはそれなりの営業をしなければいけない。そして、ある程度の収入増を図らなければならない。
10,11月の学校行事の多い時に、青尐年を平日に集めることができるのかどうかという問題がある。
県ともそのことで話し合い、難しいということを認識している。
そこで、我が施設で行っているのは、施設の有効利用である。企業に話をもっていき、若手を育成する
研修を入れてもらうようにお願いする形で取り組んでいる。
金子 各施設は、利用料金収入のアップでどのような努力をしているのか。
赤堀 いろんなイベントを行う。いろいろな発想を活発にすることが利用料金収入増にもつながっていき、施
設の活性化にもつながっていく。活性化させるために、人材の育成や経費削減にどう取り組んでいくの
か、みなさんに教えてもらいたい。
藤原(富・砺波)我が所は、県の職員3名、残り10名が指定管理の職員。所長、所長代理、社会教育主事が
県から派遣されていて、主に指導業務を行っている。指定管理の方は管理業務を中心に、指導業務も行

っている。
営業の方針は、リピーターの確保と新規開拓である。学校では、利用する施設や時期が落ち着いており、
子供達も減っているので各施設で取り合う形になる。そこで、それ以外の所、幼稚園児、大学生、企業
を呼ぶといった方法がある。
営業活動については、能登青尐年交流の家のように幅広くまわっていきたいと考えている。
松岡(石・国能登)北陸三県を中心に岐阜県、京都市の小中学校の校長宛に、2千通ぐらいリーフレットを配
っている。活動の選択肢が多いということを売りにしている。また、石川では七尾まで出向いて、校長
会や教育委員会で紹介している。
小林 来ていない層をいかに増やしていくか、来ている層を1泊から2泊にして増やしていくかということだ
と思う。限られた利用者を取り合うという形ではなくて、いかに底辺を増やしていくかが重要だと思う。
国としては、長期の宿泊学習を推進しており、それを踏まえてプログラム開発や指導者養成事業を行っ
ているが、それがなかなか効力を発揮していない。
いかに宿泊数を増やしていくか、今まで来てなかった層を増やしていくのか、という観点でうまくいっ
た事例を紹介してほしい。
鎌田 主催事業を行うときに、どういうものだったら参加しやすいのかを地域に問いかけるようにしている。
地域の人を巻き込み、所の運営について意見を求めるという方向で利用者増を図ろうとしている。
加藤(岐・乗鞍)高地のメリットを生かした高地トレーニングでの利用促進を口コミで広めるようにしかけた。
利用者も関東、大阪からの大学生が多く集まるようになった。逆に通常の利用者がはみ出されるように
なった。口コミはかなり効果があった。
9月終わりから12月の中ごろは利用者がぐっと減る。閑散期の取り組みとして、学校から来てもらう
ことをあきらめ、出ていこうと考えるようになった。そこで、学童保育の子供たちの所へ行こうという
ことになった。また、NPO の大会にブースを出し、尐しでも知ってもらおうとした。
藤原 冬は利用者が尐ない。そこで、指定管理者は県に申請して許可をもらい、利用料金を半額にした。利用
料金ではなく、どこか他のところで儲けようという考えである。
利用料金は指定管理者に入るという条件なので県は損をしない。
関口 二上まなび交流館は、平成19年度に県から高岡市に移管された。耐震補強工事をして存続させるか、
更地にするかを高岡市の判断に任せられた。高岡市は耐震補強工事をして、平成20年に名前を二上青
尐年の家から二上まなび交流館に変えて、運営をしている。利用料金については、条例によって決めら
れている。
岐阜と愛知に PRに行き、教育委員会の方を40名程、高岡に招待した。高岡には、売りとなるものがあ
まりないことが問題である。現在に至っては PRの効果が皆無ではないかと思う。
金子 公社関連施設、地域、民間団体、民間施設との連携についての意見はないか。
平井 立山青尐年自然の家と野外教育活動センターが連携して、幼児の自然体験活動を行うというものである。
立山の方で募集をしてもらい、両方の施設で受け入れるというやり方である。コースの開発や指導のノ
ウハウについて職員が研修を受けて行う。また、富山短大保育学科の学生に子供の面倒を見てもらいな
がら、親には子育て論議ということで子育てアドバイーザーの方に講義をしてもらうというものもあっ
た。大変好評であった。保育士の卵の学生なので、将来保育園の先生になった時には、リピーターとし
て施設を使ってもらいたいという思いがある。
幼児の自然体験は大変重要だと思っており、ターゲットを中学校から幼児に向けていきたい。
藤原 国立の施設は、運営委員会という組織をもっている。運営委員の方が責任をもって、所を支えてくれる
お客を連れてきてくれるのだと思う。それぞれの所が、所を支えてくれる運営委員会という組織をもつ
必要がある。その組織の方がプログラムや活動内容等にいろんな提言をしてもらえばありがたい。