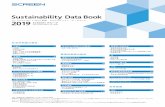ModuleX Filter lighting® オプションフィルター 取扱説 … Sharpener 光源側 フード側 フード側 (平らな側) (凹凸のある側) 光源側 フード側 Full
社会福祉援助技術論1第3講係を「社会関係」として、そこには主体的側面と客体的側面があると考えます。...
Transcript of 社会福祉援助技術論1第3講係を「社会関係」として、そこには主体的側面と客体的側面があると考えます。...

この章では、ソーシャルワークの基本的枠組みを学びます。
社会福祉援助技術論1 第3講
19

第1章で、ソーシャルワークの特性としてもお話ししましたが、ソーシャルワークの対象、つまり働き
かけの対象は何かを整理しておきます。
ソーシャルワークは、個(あるいは人)と環境との相互作用(あるいは交互作用)の接点に介入する
ものです。これは、ソーシャルワーク固有の対象領域だと考えられ、個と環境が相互に作用しあって
いる状況全体に着目することがソーシャルワークの大きな特徴です。
これは、さまざまな研究者によっても説明されています。例えば、ホリスは「人と状況の全体関連性」
に着目しましたし、ピンカスとミナハンは「人びとと彼らの社会環境にあるシステムとの相互作用」に
焦点を当てました。バートレットは、「人びとと環境の相互作用」のなかで人の生活を捉えることを提
唱し、ジャーメインとギッターマンは、人びとのもつニーズ等と環境のもつ特性との「人と環境の適
合」を図るということを考えました。
こうしたシステム論やそれを基盤とする生態学からソーシャルワークの理論的枠組みが作られてき
たことがわかります。
社会福祉援助技術論1 第3講
20

日本では、岡村重夫の「社会福祉の固有の視点」でも、関係に焦点が当たります。
岡村理論では、個人が生活上のニーズを充足させるために利用する社会制度との間に取り結ぶ関
係を「社会関係」として、そこには主体的側面と客体的側面があると考えます。
社会制度が個人のニーズを充足しようとするのが「社会関係の客体的側面」で、個人が主体的・自
発的に制度とかかわって自分のニーズを充足しようとすることを「社会関係の主体的側面」としてい
ます。このうち、「社会関係の主体的側面」にかかわることが、社会福祉、あるいはソーシャルワーク
の固有の対象領域だというのです。
社会福祉援助技術論1 第3講
21

岡村によれば、固有の対象領域である「社会関係の主体的側面」には3つの要素があります。
1つは「社会関係の不調和」で、主体的側面からみて、個人の福祉の社会関係が相互に矛盾してい
る状態をさします。
2つ目は「社会関係の欠損」で、個人が社会生活の基本的要求を満たすのに必要な社会関係を失
い、社会制度を利用できない状態です。
3つ目は「社会関係の欠陥」で、社会制度と利用者の間で意思疎通を欠き、社会制度と利用者間が
断絶状態になったり、制度改善の弾力を失った状態をさします。
こうした状況において、社会関係の主体的な側面に関わる、つまり制度との関わりで利用者の生活
上の要求を充足させるための社会福祉実践がソーシャルワークであるという捉えです。
社会福祉援助技術論1 第3講
22

さて、ソーシャルワークは、何らかの生活上の問題を抱えた人びとが、それを解決することができる
ように、 人と環境の相互に影響しあう接点に介入する実践です。
そこで、ソーシャルワークを構成する要素は、大きく4つに整理することができます。 (1)クライエント
システム、(2)ニーズ、(3)ソーシャルワーカー、(4)社会資源、です。
社会福祉援助技術論1 第3講
23

ソーシャルワークは、個人や家族、グループなどが抱える生活上の課題に対して、問題の解決や軽
減の働きかけをします。したがって、ソーシャルワークが成り立つためには、その支援の対象となる
クライエントの存在が前提となります。
そして、先に学んだソーシャルワークの定義からもわかるよう に、クライエントを単なる個人としてと
らえるのではなく、周りの環境を含むクライエントシステムとしてとらえます。
クライエントシステムには、家族や近隣住民、地域のサービス提供機関などとの関係が含まれ、ソー
シャルワーカーは、このクライエントシステムへの働きかけを行います。
社会福祉援助技術論1 第3講
24

個人がソーシャルワークの対象、つまりクライエントとなるのは、何らかの解決すべきニーズを持っ
ているからです。ここでのニーズは、ウェルビーイングや自己実現のために求められるもので、身体
的、心理的、経済的、文化的、社会的なものであると考えられます。
これらのニーズは、クライエント自身が明確に表明したり、認識しているとは限りません。ソーシャル
ワークの専門職から見て、何らかの援助やサービスの利用が必要であると考えられる場合もありま
す。
何らかのニーズを持つクライエントの存在を認め、そのニーズの充足や問題解決のためにソーシャ
ルワーク実践を担うのがソーシャルワーカーです。
社会福祉援助技術論1 第3講
25

ソーシャルワークの構成要素の3つ目です。
ソーシャルワーカーは、ニーズを持ったクライエントと専門的な援助関係、つまりソーシャルワーク関
係を結び、クライエントシステムに働きかけます。専門的な援助関係ですから、ソーシャルワーカー
は専門職として、ソーシャルワークの価値を基盤としながら、専門知識と専門的な技術を活用して実
践に取り組みます。
もちろん、ソーシャルワーカーは、単独の個人として実践しているわけではなく、多くの場合、社会福
祉の機関や施設などに所属していますから、ワーカー側もソーシャルワーカーシステムの中にある
と考えてよいでしょう。
社会福祉援助技術論1 第3講
26

次に、システム論の立場から、ピンカスとミナハンが整理したソーシャルワークの4つのシステムにつ
いてです。
ソーシャルワークはシステムとしてなり立っていて、それは、「クライエント・システム」「チェンジ・エー
ジェント・システム」「ターゲット・システム」「アクション・システム」です。
クライエント・システムは、社会福祉サービスを利用している人や利用を要する人で、援助活動を通
して問題解決に取り組もうとする個人または家族から構成される小集団のことです。
チェンジ・エージェント・システムは、援助を担当する援助者、施設、機関、それらを構成する職員全
体をさし、ワーカー・システムといってもいいかもしれません。
ターゲット・システムは、問題解決のために変革・影響を与えていく標的、つまり働きかけの対象とな
る人や組織のことをいいます。
アクション・システムは、ターゲット・システムに用いられる人々や資源全体をさし、これらがチーム
ワークを構成します。
社会福祉援助技術論1 第3講
27

最後にソーシャルワークの機能についてです。
社会福祉学の辞書的には、ソーシャルワークの機能は「ソーシャルワーカーが自らを意識的に活用
しながら、目的の達成に向け利用者とともに織りなす『働きかけ』を指す」ものだと説明できます。
先ほどから取り上げている岡村重夫は、「社会福祉の機能とは、『社会福祉固有の対象』の『生活困
難を修復するはたらき』」だと定義しています。
社会福祉援助技術論1 第3講
28

岡村重夫は、社会福祉の機能を5つに整理しています。
「評価的機能」は、アセスメントと呼ばれる事前評価で社会関係の困難などを見つけ、解決の計画を
立て、援助の終わりにはフィードバックと呼ばれる事後評価によって取り組みをふりかえり、次への
改善点を見出す機能です。
「調整的機能」は、個人のもつ複数の社会関係が相互に矛盾すること、つまり「社会関係の不調和」
によって起こる生活困難を修復する機能です。
「送致的機能」は、欠損した社会関係を回復させたり、それに代わる新しい社会関係を見出すように
援助する機能です。新しい社会制度の利用なども含まれます。
「開発的機能」は、すでにある資源では、欠損した社会関係の回復ができない場合に、社会関係の
回復を容易にするような社会資源をつくりだす機能です。
「保護的機能」は、これらの機能によっても、社会関係の調和を実現できないときや、実現までの間
に、特別のサービスを提供する機能です。
この章では、ソーシャルワークが、人と環境との相互作用や、社会関係といった「関係」に着目しな
がら、システムとして働いていることがおわかりいただけたと思います。
社会福祉援助技術論1 第3講
29