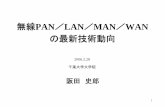無線PAN LAN MAN WAN - ITS情報通信システム推進 …„¡線PAN/LAN/MAN/WAN の最新技術動向 2 全体動向 短距離無線 無線PAN 無線LAN 無線MAN 無線WAN
第3回: 無線LAN標準化の変遷とIEEE802.11今後の展開...1...
Transcript of 第3回: 無線LAN標準化の変遷とIEEE802.11今後の展開...1...

1
解説:ユビキタス無線ネットワーク体系
第3回: 無線 LAN 標準化の変遷と IEEE802.11 今後の展開 執筆:千葉大学 工学部情報画像工学科 教授 工学博士 阪田 史郎 氏 無線 LAN・Bluetooth[更新:2004.11.5]
IEEE802.11規格(各タスクグループ)の概要と、QoS制御、ローミング、セキュリティ、超高速無線LAN、メッシュネットワークにつ
いて解説する。
1.無線 LAN 標準化の変遷と IEEE802.11 今後の展開 図1に無線 LAN に関する標準化の経緯、図2に無線 LAN の標準化を進めている IEEE802.11 委員会
の構成を示す。表1に無線 LAN と無線 PAN を含めた一覧を示す。
無線 LAN は、1990 年代初頭に米国の IEEE802.11 委員会と、ヨーロッパの ETSI BRAN(European
Telecommunications Standards Institute Broadband Radio Access Networks)委員会において、国際標
準化が開始された。この検討開始とほぼ同時期に、Motorola が ALTAIR、NCR が WaveLAN の 2 つの
無線 LAN を製品化した。しかし、これらの製品は、アクセスポイントに相当する制御装置のサイズが大きい、
価格が高い割に伝送速度が遅いなどの理由で普及には至らなかった。
図1.IEEE802.11 委員会における標準化の経緯 図2.IEEE802.11 委員会(1990 年~)の構成
表1.無線 LAN と無線 PAN
最大伝送 速度 通信距離 変調方式
アクセス方式
備 考
(周波数帯、消費電力、用途、標準化時期等)
IEEE802.11b 11Mbps 数 10m DS-SS CSMA/CA 2.4GHz, 1999.9
IEEE802.11a 54Mbps 数 10m OFDM CSMA/CA 5GHz, 1999.9
IEEE802.11g 54Mbps 数 10m OFDM CSMA/CA 2.4GHz, 2003.5
無
線
L
A
N IEEE802.11n 100~200Mbps 数 10m CSMA/CA 5GHz, 2006
Zigbee
(IEEE802.15.4) 250kbps 10~75m HomeRF から派生
2.4GHz/868MHz/915MHz,
<60mW, ホームオートメーション、センサ制御,2003
Bluetooth
(IEEE802.15.1) 1Mbps 10m FH-SS TDD
2.4GHz,120mW/4.2mW
USB の無線版 2001.2 (V1.1)
無
線
P
A
N UWB
(IEEE802.15.3a)
100Mbps 以上
(480Mbps)
10m(110Mbps)
4m(200Mbps)
MB-OFDM,
DS-CDMA 等
3.1 - 10.6GHz,
<100mWUSB2.0 の無線版 2005 年

2
1990年代半ばまでは、ETSI BRANで規格化されたHiperLAN(High performance LAN)が国際標準と
して有力視されることもあったが、1997 年の IEEE802.11、1999 年の IEEE802.11b、802.11a の仕様標準
化に続いて、2000 年以降の IEEE802.11b の製品化とその急速な低価格化、普及に伴い、両者間の調
整を経て、世界の無線 LAN は、IEEE802.11 仕様(物理レイヤに相当するインフラとしての無線 LAN は、
IEEE802.11b、a、g)に一本化された。
2001年には、IEEE802.11bとの互換性を保持しながら高速化するため、IEEE 802.11bと同一周波数の
2.4GHz、IEEE802.11a と同じ OFDM 方式を採用した IEEE802.11g が標準化された。表2に IEEE802.11b、
a、および g の比較を示す。
さらに、2003 年9月には 100Mbps 以上の高速無線 LAN の開発を目指した IEEE 802.11n が発足し、
5GHz の利用をベースに 2006 年の標準化に向けた活動が活発化している。
表2.無線 LAN IEEE802.11b, a, g の比較
IEEE802.11b IEEE802.11a IEEE802.11g
リンク速度 △ ◎ ○
電波距離 ◎ △ ○
同時使用チャネル(国内) 4 4 3
屋外仕様 ○ × ○
電波干渉 △ ◎ △
利用環境 ・低速での利用 ・屋内
・端末数が多い
・2.4GHz のノイズ源
(Bluetooth, 電子レンジ等)
・遮蔽物が少ない
・屋内外
・端末数が少なく特に
高速を必要としない
・802.11b の端末と共存
・遮蔽物が多い
備考 安価で最も普及 将来的に高速化(802.11n)と
屋外利用が可能に
802.11b の上位互換
IEEE802.11 仕様の無線 LAN に対しては、1999 年に発足した業界団体 WECA(Wireless Ethernet
Compatibility Alliance)を改称した Wi-Fi Alliance (Wireless LAN Fidelity Alliance)が各業界へのプロ
モーションとともに、相互接続検証、仕様準拠製品認定を行っている。
なお、無線 LAN と呼ばれることはほとんどないが、IEEE802.11 においても検討がなされた赤外線を用
いた無線通信については、1993 年に業界団体として発足した IrDA(Infrared Data Association)が標準
化を進めてきた。IrDA は、波長 850~900mの赤外線による無線インタフェースのデファクト標準化を目指すコン
ソーシアムとして設立された。
この IrDA によって標準化された方式が、当初の IEEE802.11 の PHY(物理層)規格の 1 つになった。
IrDA 方式には、最低 1m の通信距離で、最大 4Mbps の伝送速度を目標とし、部品コストが安いというメ
リットがある。しかし、光の伝送の特徴である強い直進性(遮蔽物があるとシャドウイングにより通信できな
い)があり、送信側と受信側の軸調整が必要とされるなどの課題がある。このため、赤外線を用いた無線
通信は、直進性の問題が大きな障害とならない、限定された場面での利用に留まっている。
表3に IEEE802.11 委員会における各 TG(Technology Group)とその活動内容を示す。この中で、ユー
ザサービスを実現するための MAC レイヤ以上のミドルウェアとして機能するのは、これまでは IEEE802.11e の
QoS 制御、IEEE802.11f のローミング、IEEE802.11i のセキュリティ(認証については IEE802.1X)であり、これら

3
の活動は、2004 年初頭にはほぼ終結した(IEEE802.11f については 2002 年に終結)。
その後 DSRC ( Designated Short Range Communications )技術をベースに車対象の移動制御用途の
IEEE802.11p、’04/6に、高速ローミングを扱う IEEE802.11r、メッシュネットワーク検討の IEEE802.11s が発足。
IEEE802.11b、a、g の普及を経て、IEEE802.11n による高速化とともに、新たな展開に向け、サービス
に直結するミドルウェア部分の拡張が開始された。
表3.IEEE802.11 における各タスクグループの活動
a 5GHz 帯、最大 54Mbps の無線 LAN (OFDM)
b 2.4GHz 帯、最大 11Mbps の無線 LAN (DS-SS)
c MAC ブリッジ(802.1d)に無線 LAN の MAC 仕様を追加
d 2.4GHz 帯、5GHz 帯が利用できない地域向けの MAC、物理レイヤ仕様
e QoS 制御 (AV 通信向け。優先制御の Prioritized QoS と品質保証の Parameterized QoS。)
f ローミング (アクセスポント/基地局間)
g 2.4GHz 帯、最大 54Mbps の無線 LAN (OFDM)
h 11a に省電力管理と動的チャネルを追加(欧州向け仕様)
i セキュリティレベルの高度化(802.11e から分離)
j 日本における 4.9GHz ミ 5GHz 利用のための仕様策定
k 無線資源の有効活用の研究(Radio Resource Measurement)
m 802.11a と 802.11b 仕様の修正等
n 次世代無線 LAN(100~200Mbps、ターゲットは 2006 年頃、802.11a/b/g と何らかの下位互換
性)。これまで HT SG(High Throughput Study Group)で活動。
p 車などの移動体環境における無線アクセス。ITS への応用をめざす。
r 高速ローミング
s メッシュネットワーク
■:無線 LAN そのものの仕様 ■:ミドルウェアに相当する部分
IEEE802.11p については、具体的な進展はこれからであるが、今後同じ目的の無線 MAN に移動制御
に関する標準化を目指している IEEE802.16e との整合が必要となる。
IEEE802.11r における高速ローミングでは、オフィスや病院、大学キャンパス等における VoIP(Voice over
IP)による IP 電話をはじめとするリアルタイムアプリケーションに対して、通信品質の劣化を抑えることを
目的として、アクセスポイント間での高速なハンドオーバを実現するための MAC レイヤの拡張を行う。
IEEE802.11s におけるメッシュネットワークは、アクセスポイント間をマルチホップで通信するもので、インターネットの
標準化機関である IETF(Internet Engineering Task Force)ではアドホックネットワークと呼ばれ、MANET
(Mobile Ad hoc NETwork) WG で、ルーティングプロトコルの標準化が 1990 年代末より進められている。
IEEE802.15s のメッシュネットワークでは、MAC レイヤにおける隠れ端末・さらされ端末問題、ネットワークレイヤに
おける MANET WG の検討も含め、レイヤ 1~3を通したマルチホップの LAN 接続の研究が本格化しつつある。
IEEE802.11s の活動は、アドホックネットワーク/メッシュネットワークにおける IETF と IEEE との間の初めての連携
である。IP 以上を対象とする IETF と MAC 以下を対象とする IEEE との連携によって、下位から上位まで
の一貫した通信制御インタフェースが共通化されることになり、ユビキタスシステムの基盤アーキテクチャ構築の上で
極めて重要かつ大きいインパクトとなる。

4
(1).QoS 制御
約3年の検討を経て、2003 年夏に大枠を仕様化した。2002 年以前の仕様で不足していた機能を追加
するとともに、全体を再体系化し主要な用語も一新している。自律分散制御に基づき優先制御を行う
EDCA(Enhanced Distributed Channel Access)と、アクセスポイントによるポーリングを用いた集中制御により
品質を保証する HCCA(Hybrid Coordination Function Controlled Channel Access)の 2 つの方式を規
定している。
EDCA は従来の DCF(Distributed Coordination Function)に相当し、データの種別ごとにチャネルアク
セス頻度に対する優先順位付けができるようになっている。サービス品質の差をつけるには、バックオ
フ・アルゴリズムで発生する乱数の範囲をアクセスカテゴリ(Access Category、優先順位に相当)毎に変
えればよい、すなわち、優先度が高いカテゴリのフレームは、乱数発生範囲が小さく短い待機時間で送
信することができる。
HCCA は従来の PCF(Point Coordination Function)に相当し、端末の優先度を考慮したスケジューリ
ングを行い、送信を許可した端末に許可するチャネル使用時間が書かれたポーリングフレームを送信する。
送信を許可された端末が送信中は、他の端末はアクセスを抑制され、QoS が保証される。HCCA は
EDCA よりも常に優先的にチャネルアクセス権を獲得し、各データストリームの種々の伝送遅延要求を
満足するきめ細かなポーリングを行うことが可能になっている。
また、新たに、特定局に対して一定時間のパケット送信権を割り当てるための TXOP (Transmission
Opportunity)の概念を導入している。一旦送信権を獲得したアクセスカテゴリは、TXOP Limit[AC]と呼
ばれる時間だけはパケット送信を継続することができる。 この他にも、
・DLP(Direct Link Protocol):アクセスポイントを介さず、局(通信ノード)間で直接通信するための仕組み。
DLP を設定した局間ではパワーセーブモードに入ることができない。
・Block ACK:複数のデータに対して ACK を一括して返送する仕組み。
データ送信側からの Block ACKRequest パケット(ACK 状況を返送してほしい先頭フレームの ID 情
報を含む)に対し、データ受信側は Block ACK パケットを返送する。
・上位層同期:上位層が共有している時計の任意の精度での時報情報をマルチキャストフレームとして
送受信するための仕組み。
・APSD(Automatic Power Save Delivery):ビーコン単位より短い周期でパワーセーブを行う仕組み。
――などのオプション機能が利用可能となっている。
図3に 802.11e 機器を含むネットワークの構成例 、図4に EDCA の実装モデルを示す。
図3.802.11e 機器を含むネットワーク構成例
QBSS:
QAP(QoS Access Point)を中心
に形成される Infrastructure BSS
QIBSS:
QSTA(QoS Station)を含む
Independent BSS
BSS:Basic Service Set

5
図4.EDCA の実装モデル
(2).ローミング
ローミングは、特にホットスポットシステムのように、事業者が異なる無線 LAN 間を携帯端末をもって移
動する時に、サービスを継続する機能として重要となる。
IEEE802.11f では、アクセスポイント間でのローミングを実現するための IAPP(Inter-Access Point Protocol)
が検討されたが、2001 年には活動を終了している。携帯端末の情報を用いて認証を最初からやり直さ
なくてもすむシングルサインオン(SSO: Single Sign-On)の検討もなされている。この場合、RADIUS
(Remote Authentication Dial-In User Service:ダイアルアップ接続の際に使うユーザ認証の仕組み)サー
バの認証も含まれる。
IEEE802.11r は 2004 年 6 月に発足したが、ほぼ同時期に、無線 LAN に限らず無線 PAN、MAN も含
めた無線ネットワーク間におけるハンドオーバ(サービス継続からシームレス・ローミング)に関する委員
会として、IEEE802.21 が発足した。今後、IEEE802.11f と IEEE802.11r における検討をベースに、
IEEE802.21 における異種無線ネットワーク間におけるシームレス連携の議論が活発化することが期待さ
れる。
(3).セキュリティ
主に MAC レイヤにおける暗号化と認証の機能であり、認証部分については IEEE802.1x(※1)、暗号と
認証を含めたセキュリティ全体は IEEE802.11i において、既に標準化されている。
※1 IEEE802.1x:認証については、もともと有線 LAN でのスイッチなどのポート単位で認証を実現す
る仕組みとして検討されてきたため、11x ではなく 1x になっている。
暗号化については、1998 年に IEEE802.11 委員会において、暗号方式の標準として WEP(Wired
Equivalent Privacy)方式が提案された。 しかし、その後 WEP に対し、
・暗号鍵長が 40bit/104bit*
・暗号アルゴリズムは低強度の RC(Rivest Cipher)4
・暗号鍵は 1 つのアクセスポイント に接続された PC ですべて同一
・暗号鍵はユーザが ASCII コードで入力するが覚えやすい文字列になりがち
――などによる脆弱性が指摘された。このため、2001 年に WEP を置換える新しい方式に検討に

6
着手し、秘密鍵の長さを 40 ビットから 128 ビットへ、初期ベクトルも 24 ビットから 48 ビットへ、などの変
更も含め、3 年後の 2004 年にセキュリティ全体の標準を、IEEE802.11i として規定した。
セキュリティに関しては、業界団体の Wi-Fi Alliance が採用のガイドラインとして、認証部分も含む形で
WPA(Wi-Fi Protected Access)を策定している。暗号に関しては、WEP は WPA に変更され、
IEEE802.11i に相当するフル仕様は WPAv2 として推奨されている。
IEEE802.11i の暗号化に関する規定内容は以下に要約される。
・次世代無線 LAN 暗号化プロトコル:TKIP(Temporal Key Integrity Protocol)
・高強度暗号アルゴリズム:AES(※2)(Advanced Encryption Standard)
※2 Rijndael 方式とも呼ばれ、ベルギーの暗号学者 Joan Daemen 氏と Vincent Rijmen 氏によって
発明された 128 ビットブロック暗号。
TKIP は、パケット毎/一定時間毎に暗号鍵の変更が可能でメッセージ改ざん防止機能を有する。
AES アルゴリズムを用いた CCMP(Counter mode with Cipher block chaining Message authentication
code Protocol。データの改ざんを検出することが可能)、WRAP(Wireless Robust Authenticated
Protocol)を使用することが可能となっている。図5に TKIP による暗号解読への対処、図6に TKIP に
よる成りすましへの対処のしくみを示す。
図5.TKIP における暗号
解読への対処
PML:
Physical Markup Language
ONS:
Object Name System
図6.TKIP におけるなり
すましへの対処

7
AES は、米国が、1970 年代から標準方式して採用してきた従来の DES(Data Encryption Standard)に
代わるより高い強度の標準暗号方式として、2000 年に採用したアルゴリズムである。
認証については、2001 年末に、IEEE802.1x として標準化された。IEEE802.1x では、図7に示す EAP
(Extensible Authentication Protocol)と呼ぶ認証用のプロトコルを規定している。EAP には、ユーザ ID と
パスワードに基づく簡易な EAP-MD(Message Digest)5、PKI(Public Key Infrastructure)の仕組みを用
いて第三者機関 CA(Certification Authority)によるサーバとクライアントの相互認証を行う高強度な
EAP-TLS(Transport Layer security)、および強度的にはその中間に位置するいくつかのプロトコルが
提案されている。 図7.IEEE802.1x を用いた認証プロセス
表4に、主な EAP を示す。参考例として、最も高強度な EAP-TLS におけるメッセージの交信例を図8・
9に示す。IEEE802.11i としては、IETF において RFC(Request For Comments)化された EAP-TLS を推
奨しているが、実装が重く処理負荷が大きいため、他のより簡易なプロトコルの使用も認めている。
表4.802.1x 認証方式の種類
種類 概要 長所 短所
EAP-MD5
ユーザ ID とパスワードによるクライアント認証。アクセスポイントから送られて
くるビット列(チャレンジ)と、自身のパスワードを元に算出したハッシ
ュ値を認証に利用する。
実装が容易 サーバ認証がないた
め、他方式に比べセ
キュリティ強度が劣
EAP-TLS
(RFC2716)
電子証明書を利用した PKI による、クライアント認証とサーバ認証の相
互認証方式。認証によって、認証サーバはユーザの公開鍵を確認
し、これを暗号鍵の配信に用いて認証サーバと端末の間でユーザの
暗号鍵を共有する。その後にアクセスポイントに端末と共有した暗号
鍵を配送する。EAP-TLS では、RADIUS 相当の認証サーバと CA
(Certification Authority: 証明機関) が存在し、ユ認証サーバと各
クライアントに、CA が証明書を前もって発行しておく。
電子証明書を利
用するため、セキュ
リティを強固にでき
る
サーバ側での電子
証明書、およびクラ
イアントと配布する電
子証明書の管理が
必要
EAP-TTLS
EAP-TLS によるサーバ認証を実施した後、さらにユーザ ID、パスワー
ドなど別の方法(RADIUS サーバでの認証)でクライアントを認証する。
FunkSoftware などが提案。EAP-TLS は端末に対して CA が証明
書を発行しなければならかったが、EAP-TTLS では証明書が不
要でパスワード方式を組合せて鍵配送する。パスワードを暗号化し
て、認証を行う相手に送信する。この方式ではサーバ側にしか証明
クライアント認証方
式 に は PAP や
CHAP などの既
存の認証方式が
利用可能
サーバ側での電子
証明書の管理が必
要

8
書がいらないので、個々のユーザに対して証明書を発行する必要
がない。その際、認証サーバと端末間がトンネル化される。鍵配送
に関しては仕組みが似ている PEAP は、トンネル化される区間が
異なり、TLS サーバまでしかトンネル化しない。
EAP-FAST Cisco が開発した独自の認証方式.クライアント認証とサーバ認証の相
互認証。 AirMac(Apple)で実現。
実装済みの製品
が既に出荷
Cisco 以外の製品
と互換性がない
EAP-PEAP
EAP-TLS 認証で認証後、EAP 自体をカプセル化して安全性を高
めた上で認証。Microsoftが提案。EAP-TTLSと非常に似ていて、
パスワードを暗号化して、認証を行う相手に送信する。EAP-TTLS
と同様個々のユーザに対して証明書を発行する必要がない。しか
し、その際 TLS サーバまでしかトンネル化しない。
アクセスポイント間で
のローミング機能が
ある
MD5: Message Digest algorithm 5 TLS: Transport Layer Security
TTLS: Tunneled TLS FAST(Flexible Authentication via Secure Tunneling)
PEAP: Protected EAP PAP: Password Authentication Protocol
CHAT: Challenge Handshake Authentication Protocol
図8.EAP-TLS を用いた
認証プロセス(1)
図9.EAP-TLS を用い
た認証プロセス(2)
また、IEEE802.11i で

9
は、認証と鍵配送については、IEEE802.1x を使用する RSN(Robust Security Network)を規定している。
RSN 内には認証サーバが存在し、802.11i 規格に準拠したアクセスポイントと端末は、IEEE802.1x を用いた認
証と、アクセスポイントと端末の組合せごとに固有な暗号鍵の使用およびその更新が可能になっている。
業界団体の Wi-Fi Alliance が、セキュリティ全般に関して勧告している WPA の仕様を表5示す。
表5.WPA と WPAv2
WPA WPAv2(=IEEE802.11i)
Wi-Fi アライアンスによ
る人体作業開始時期
2002 年 2 月
(2003 年 8 月から Wi-Fi 認定の必須項目に) 2004 年 6 月
概要 IEEE802.11i のドラフト v3 の一部 IEEE802.11i と同じ
データの暗号化方式 TKIP TKIP, CCMP, WRAP
ユーザ認証 IEEE802.1x/EAP
対象ユーザ 一般企業、個人 政府機関、一般企業で特に高度
なセキュリティが必要な部署等
既存の製品の更新方法 ソフトウェアで更新可能 性能維持のためハードウェアの交
換が必要
対応していない利用形態 アドホックモード、 ハンドオーバ 特になし
その他の特徴
・WEP との下位互換性も規定
・家庭等では IEEE802.1x を使わないホームモ
ードも利用可能
・CCMP やWRAP の暗号化アルゴ
リズムには AES を用いる
(4).超高速無線 LAN
2002 年 5 月に HT-SG (High Throughput - Study Group) 発足が発足し、2003 年 9 月に
IEEE802.11n が設置されている。 要求条件としては、
・PHY、MAC の仕様検討により、MAC-SAP(Service Access Point:アプリケーションレベルでの実行伝送)のデータ
速度が 100Mbps 以上(物理レイヤの変調方式による高速化は限界とされ、MAC レイヤ変更が必須)
・IEEE802.11b,g への下位互換性(バックワードコンパティビリティ、OFDM ベース)をもつ
・高周波数利用効率(1Hz あたり 3 ビット以上)
・5GHz 帯の利用が有力 ――が挙げられている。
これらの要求条件を満たすための高速化に向けた変復調技術については、
・複数バンド技術:2つ以上のバンドを束ね高速化(IEEE802.11a、802.11b では 20MNz 帯域が基本バンド)
・空間多重技術: MIMO(Multi Input Multi Output)すなわち、複数のアンテナを用いて複数のデー
タを同時に送受信し、信号処理によってデータを復調
・新誤り訂正技術: 現在(IEEE802.11a、802.11g では拘束長 7 の畳み込み符号)よりも訂正能力の高
い誤り訂正符号。第3世代携帯電話網で用いられているターボ符号や LDPC(Low Density Parity
Check code、低密度パリティ検査符号)が候補 ――の各技術の適用が検討されている。
なお、IEEE802.11n 準拠の超高速無線 LAN に関し、2003 年から 2004 年にかけて米国のベンダを中
心に、WWiSE(World Wide Spectrum Efficiency)、TGn Sync の2つの業界団体が相次いで設立され、
ともに MIMO をベースとする技術仕様の提案を行っている。

10
(5).メッシュネットワーク
アクセスポイント間をメッシュ状に接続しマルチホップで通信する方式を検討するための IEEE802.11s が
2004 年 6 月に発足した。メッシュネットワークは、アドホックネットワークとほぼ同義で用いられる。
メッシュネットワークの利点として、以下が挙げられる。
・通信距離を短くすることにより通信による電力消費を削減(消費電力は通信距離の 2 乗に比例)
・通信頻度低減による省電力化
・迂回経路による信頼性向上
・アクセスポイントやサーバノードへの処理集中を防ぐことによる信頼性向上、負荷分散による性能向上
・電波出力を上げることなく通信範囲の拡大が可能
現在、主に以下の項目について議論が開始されている。今後、シングルホップ、すなわち 1 つの LAN の
中で標準化された IEEE802.11e をベースにマルチホップにした環境での QoS の検討も重要となる。
・MAC 拡張…ビーコン(自端末の存在や状態を他の端末に知らせるためのフレーム)の衝突制御、
QoS 制御、隠れ端末/さらされ端末問題(図10)など
・ルーティング/フォワーディング…IETF の MANET WG において検討され標準化(RFC 発行)された
ルーティングプロトコル(※3)の比較評価、適用可能性
・セキュリティ…IEEE802.11i、IEEE802.1x はともにシングルホップにおけるセキュリティ機能に閉じており、マルチ
ホップ特有の問題を扱う
・ネットワークの状態監視…周囲の状況を確認しながら、電波の強さやチャネルなどを調整
※3 IETF MANET WG で標準化されたアドホックネットワークのルーティングプロトコルは、Reactive protocol
の AODV(Ad hoc On-demand Distance Vector algorithm)、DSR(Dynamic Source Routing)、および
Proactive protocolの OLSR(Optimized Link State Routing protocol)、TBRPF(Topology Broadcast based on
Reverse Path Forwarding routing protocol)の 4 つである。
図10.隠れ端末問題とさらされ端末問題

11
2.ホットスポットサービス
携帯端末(ノート PC や PDA)をもって移動する利用者に対し、無線 LAN を通して各種サービスの提供
をする公共の場そのものは'ホットスポット'、そのサービスを提供するシステムはホットスポットシステム、
提供されるサービスはホットスポットサービスと呼ばれ、2000 年に米国においてサービスが開始された。
ホットスポットには無線 LAN のアクセスポイントが設置される。アクセスポイントは、通常バックエンドの ADSL や
FTTH、T1 回線(米国)等のブロードバンドアクセス網と接続され、利用者にメール処理や Web アクセス
等の高速インターネットアクセスサービスを提供する。
現在までに、空港、駅、大学、ホテル、カフェ、レストラン、ファストフード、ガソリンスタンド、書店などの各種店舗等が
ホットスポットとして利用されている。今後、電車や乗用車、新幹線等の移動体におけるホットスポットサ
ービスへの期待も高まっている。
しかし、未だホットスポット事業者や通信キャリア、各種のサービスプロバイダなどの各プレイヤ間で
Win-Win 関係となるようなビジネスモデルは成立っていない。ホットスポットの数は急速に増加しているも
のの、今後のサービスの拡大、ビジネス展開には未だ課題が多く残されている。
図11.無線 LAN ホットス
ポットシステムのイメージ
図12.想定されるビジネ
スモデル

12
図13.世界のホットスポット数の予想
2004 年末現在既に米国で約 3 万、日本で約 5 千、全世界では 6 万強のホットスポットが設置されて
いる。ホットスポットにおけるキラーアプリの 1 つは VoIP による IP 電話と考えられており、メッシュネットワーク
の実現はこの面からも期待される。携帯電話によるデータ通信が普及している日本では、今後 PC に置き
換わって、携帯電話と無線 LAN の両方のインタフェースをもつデュアルモードの端末がホットスポットで利用
されていくことが考えられる。