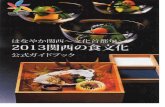第2編 体育活動における 頭頚部外傷の傾向 - 日本スポーツ振興セ … ·...
Transcript of 第2編 体育活動における 頭頚部外傷の傾向 - 日本スポーツ振興セ … ·...

9
第2編
体育活動における
頭頚部外傷の傾向
8 9
第2編

10
第2編 体育活動における頭頚部外傷の傾向
独立行政法人日本スポーツ振興センターでは、学校の管理下で発生した児童生徒等の災害に
ついて医療費、障害見舞金及び死亡見舞金を支給する災害共済給付業務を行っている。この制
度には全国の児童生徒等の約 97%が加入し、義務教育諸学校ではほぼ 100%、高等学校では 98%
が加入している。また、平成 17 年度から災害共済給付オンライン請求システム(以下「システ
ム」。)を導入し、全国の学校・設置者約 7 万 5 千か所とネットワークで結んでいる。
今回、このシステムに蓄積されたデータを使い、調査研究に際して「学校の管理下の体育活
動による頭頚部外傷の現状」を把握し、体育活動における頭頚部外傷の傾向の分析を次のとお
り試みた。
第1章では災害共済給付の医療費(負傷・疾病)のデータ、第2章では死亡見舞金、障害見
舞金(1 級~3 級)のデータを使い分析を試みた。第3章では更に詳しい事故の要因を把握する
ため、平成 24 年度に医療費の請求があった事故事例について実地調査を行った。また、第4章
はスポーツ事故に係る判例の分析である。
第1章 体育活動における頭頚部外傷の基礎データ(負傷・疾病)
平成 17 年度から平成 23 年度に災害共済給付(医療費)を行った、中学校及び高等学校の体
育活動(保健体育の授業及び運動部活動)による頭頚部の外傷事例のうち、被災当初月給付額
3 万円以上の 4,396 件※を抽出し行った。
なお、本分析におけるデータは次による。
※H17~H23 の中・高の体育活動の頭部及び頚部の負傷・疾病 17 万 4 千件の約 2.5%
[部位]
システムでは部位を頭部、前額部、眼部、頬部、耳部、鼻部、口部、歯部、顎部、頚部、肩
部、胸部、腹部、背部、腰部、臀部、上腕部、肘部、前腕部、手関節、手・手指部、大腿部・
股関節、膝部、下腿部、足関節、足・足指部、その他の 27 部位で分けている。本分析において
は、このうち「頭部」及び「頚部」のデータを使用した。
[負傷・疾病の程度]
災害共済給付の対象となる負傷・疾病は医療費の総額が 5 千円以上となっており、その程度
は様々であるが、重篤な事故の防止の視点から、重症例を分析することとした。
[医師データ・柔道整復師データの別]
災害共済給付の医療費は健康保険の対象となるものを対象としている。このため医師のデー
タと柔道整復師のデータがあるが、本分析については「被災当初月給付額 3 万円以上」で抽出
しているため、全て医師のデータである。
※平成 24年 3 月に給付した 195,209 件のうち、柔道整復師分は 17,820 件(9.1%)、はり師・きゅ
う師分 48 件(0.02%)、他の 177,341 件(90.8%)は医師・歯科医師分
10 11
第2編
第1章

11
[診断名]
診断名について、医師が付した診断名は様々であり、また、一つの事故について複数の診断
名が付される場合もある。このため、本資料では集約可能な診断名は集約し、また、表 2-1-6
では特徴的(診断名が 2 以上ある場合は「打撲」、「挫傷」、「外傷」等の一般的な診断名以外)
な診断名を一つ抽出した。
Ⅰ 活動別・競技別・頭頚部別発生件数
活動別では体育の授業で 756 件(17.2%)、運動部活動で 3,640 件(82.8%)と運動部活動で約 8
割が発生していた。部位別では頭部 3,492 件(79.4%)、頚部 904 件(20.6%)と約 8 割が頭部で
あった。(表 2-1-1)
競技別では野球 902 件、サッカー837 件、ラグビー577 件、柔道 449 件、バスケットボール
334 件等の競技で発生していた。
また、運動部活動での部員 1,000 人当たりの頻度ではラグビー2.33 人、自転車 1.71 人、相
撲0.85人、ボクシング0.76人、柔道0.61人と対人接触のある競技や自転車競技で頻度が高かっ
た。(表 2-1-2)
表 2-1-1 活動別・競技別・頭頚部別(平成 17 年度~23 年度 3万円以上、件数)
体育の授業 運動部活動 合計
頭部 頚部 計 頭部 頚部 計 頭部 頚部 計
サッカー 122 9 131 634 72 706 756 81 837
バスケットボール 45 11 56 231 47 278 276 58 334
ハンドボール 9 2 11 58 19 77 67 21 88
ラグビー 17 0 17 387 173 560 404 173 577
テニス 2 0 2 62 6 68 64 6 70
バレーボール 28 5 33 82 19 101 110 24 134
卓球 1 1 2 10 2 12 11 3 14
バドミントン 0 0 0 15 1 16 15 1 16
ソフトボール 43 3 46 43 8 51 86 11 97
野球 4 0 4 790 108 898 794 108 902
水泳 8 16 24 13 22 35 21 38 59
体操 39 78 117 10 7 17 49 85 134
陸上競技 58 14 72 72 10 82 130 24 154
柔道 99 29 128 214 107 321 313 136 449
剣道 1 0 1 76 24 100 77 24 101
相撲 0 0 0 9 6 15 9 6 15
ボクシング 0 0 0 14 0 14 14 0 14
スキー 7 3 10 5 2 7 12 5 17
自転車 0 0 0 16 3 19 16 3 19
その他 79 23 102 189 74 263 268 97 365
計 562 194 756 2,930 710 3,640 3,492 904 4,396
※競技名は N≧10 を表記し N<10 はその他に含む。(以下表 2-1-1 の競技を表記)
10 11
第2編
第1章

12
表 2-1-2 運動部活動 発生頻度(対 1,000 人)
競技種目 件数(件) 対 1,000 人
(人)
サッカー 706 0.26
バスケットボール 278 0.08
ハンドボール 77 0.15
ラグビー 560 2.33
テニス 68 0.02
バレーボール 101 0.04
卓球 12 0.01
バドミントン 16 0.01
ソフトボール 51 0.08
野球 898 0.27
水泳 35 0.07
体操 17 0.12
陸上競技 82 0.04
柔道 321 0.61
剣道 100 0.09
相撲 15 0.85
ボクシング 14 0.76
スキー 7 0.17
自転車 19 1.71
その他 263 0.28
計 3,640 0.14
※ 発生頻度(対 1,000 人)は件数÷部員数×1,000 で算出した。
なお、部員数は中学校体育連盟、高等学校体育連盟、高等学校野球連
盟の H17~H23 の登録数の合計
12 13
第2編
第1章

13
Ⅱ 学年別・競技別発生件数
体育活動全体の学年別・競技別では高 1 が 1,077 件、高 2 が 1,171 件と、この 2 学年で約半
数を占めた。(表 2-1-3)
表 2-1-3 学年別・競技別 発生件数
中 1 中 2 中 3 高 1 高 2 高 3 計
サッカー 87 152 112 149 216 121 837
バスケットボール 46 90 53 61 51 33 334
ハンドボール 5 11 8 25 29 10 88
ラグビー 10 25 21 170 226 125 577
テニス 19 16 11 9 11 4 70
バレーボール 27 29 21 17 31 9 134
卓球 6 5 2 1 0 0 14
バドミントン 5 3 0 5 2 1 16
ソフトボール 10 18 9 17 21 22 97
野球 51 72 44 332 302 101 902
水泳 8 15 13 10 8 5 59
体操 31 34 26 18 15 10 134
陸上競技 21 33 42 17 34 7 154
柔道 56 94 64 106 91 38 449
剣道 16 20 16 17 23 9 101
相撲 0 2 0 5 5 3 15
ボクシング 0 0 0 9 4 1 14
スキー 2 4 0 5 5 1 17
自転車 0 0 0 7 6 6 19
その他 35 40 48 97 91 54 365
計 435 663 490 1,077 1,171 560 4,396
12 13
第2編
第1章

14
体育の授業における発生件数では、学年別にみると中 2 が 137 件、中 3 が 171 件と、この 2
学年で約 41%を占め、学校種別でみても中学校が約 52 %と高等学校より多かった。
これは体操、陸上競技で多く発生していることによる。(表 2-1-4)
表 2-1-4 体育の授業 学年別・競技別 発生件数
中 1 中 2 中 3 高 1 高 2 高 3 計
サッカー 7 18 28 15 24 39 131
バスケットボール 8 9 10 13 4 12 56
ハンドボール 1 3 4 1 0 2 11
ラグビー 0 0 0 7 7 3 17
テニス 0 0 0 1 0 1 2
バレーボール 5 5 6 8 4 5 33
卓球 0 1 0 1 0 0 2
バドミントン 0 0 0 0 0 0 0
ソフトボール 5 5 7 5 6 18 46
野球 0 0 0 2 0 2 4
水泳 1 2 10 3 4 4 24
体操 27 34 26 13 10 7 117
陸上競技 9 17 26 7 9 4 72
柔道 9 21 25 31 28 14 128
剣道 0 0 1 0 0 0 1
相撲 0 0 0 0 0 0 0
ボクシング 0 0 0 0 0 0 0
スキー 1 2 0 3 3 1 10
自転車 0 0 0 0 0 0 0
その他 14 20 28 10 16 14 102
計 87 137 171 120 115 126 756
14 15
第2編
第1章

15
運動部活動における発生件数では野球 898 件、サッカー706 件、ラグビー560 件、柔道 321
件、バスケットボール 278 件の順で、型で見ると、野球型、ゴール型、対人競技型の競技で発
生が多かった。また、学校種別で見ると高等学校が多く、学年別でみると高 1 が 957 件、高 2
が 1,056 件と、この 2 学年で約 55%を占め、特に野球の高 1、サッカー、ラグビーの高 2 が多
かった。(表 2-1-5)
表 2-1-5 運動部活動 学年別・競技別 発生件数
中 1 中 2 中 3 高 1 高 2 高 3 合計
サッカー 80 134 84 134 192 82 706
バスケットボール 38 81 43 48 47 21 278
ハンドボール 4 8 4 24 29 8 77
ラグビー 10 25 21 163 219 122 560
テニス 19 16 11 8 11 3 68
バレーボール 22 24 15 9 27 4 101
卓球 6 4 2 0 0 0 12
バドミントン 5 3 0 5 2 1 16
ソフトボール 5 13 2 12 15 4 51
野球 51 72 44 330 302 99 898
水泳 7 13 3 7 4 1 35
体操 4 0 0 5 5 3 17
陸上競技 12 16 16 10 25 3 82
柔道 47 73 39 75 63 24 321
剣道 16 20 15 17 23 9 100
相撲 0 2 0 5 5 3 15
ボクシング 0 0 0 9 4 1 14
スキー 1 2 0 2 2 0 7
自転車 0 0 0 7 6 6 19
その他 21 20 20 87 75 40 263
合計 348 526 319 957 1,056 434 3,640
Ⅲ 傷病別・競技別発生件数
4,396件の事故別に特徴的な傷病名をテキスト分析の手法により1つ抽出し、分析を行った。
その結果、傷病別では頭部打撲 1,240 件、脳振盪 855 件、頚髄損傷 390 件の順で多く、その
うち脳振盪では競技別で、サッカー、ラグビー、野球、柔道、バスケットボールの順で多く発
生していた。
脳振盪以外の脳の傷病名(脳挫傷、急性硬膜下血腫、外傷性クモ膜下出血、急性硬膜外血腫)
を競技別にみると、野球では脳挫傷、外傷性クモ膜下出血、急性硬膜外血腫が多い傾向にある
が、ラグビー、柔道では急性硬膜下血腫が多いといった傾向がみられた。
また、頚髄損傷、頚椎捻挫、頚椎骨折はラグビー、柔道、サッカーなど、対人競技や対人
接触がある競技で多かった。(表 2-1-6)
急性硬膜下血腫、脳挫傷、頚髄損傷などは重篤な後遺症を残す可能性のある傷病である。
14 15
第2編
第1章

16
表 2-1-6 競技別・傷病別 発生件数
頭部
打撲
脳振
盪
頭蓋
骨骨
折
急性
硬膜
下血
腫
脳挫
傷
外傷
性ク
モ膜
下出
血
急性
硬膜
外血
腫
頚髄
損傷
頚椎
捻挫
頚椎
骨折
その
他 合計
サッカー 297 235 59 32 29 30 18 36 55 2 44 837
バスケットボール 135 68 13 5 12 8 8 27 22 4 32 334
ハンドボール 31 19 3 1 2 1 2 9 5 0 15 88
ラグビー 141 138 10 33 15 17 7 86 60 20 50 577
テニス 29 12 5 1 5 3 3 2 2 0 8 70
バレーボール 45 29 6 5 3 3 3 8 14 2 16 134
卓球 5 2 1 1 0 1 0 1 1 0 2 14
バドミントン 8 1 2 0 1 0 0 0 2 0 2 16
ソフトボール 26 22 9 3 7 2 2 5 2 2 17 97
野球 196 123 132 54 99 86 66 27 32 3 84 902
水泳 8 3 2 0 0 0 0 15 3 24 4 59
体操 21 10 3 4 3 0 1 19 34 8 31 134
陸上競技 45 26 12 8 6 9 8 6 15 0 19 154
柔道 112 79 2 61 10 5 2 82 49 7 40 449
剣道 40 20 4 2 1 1 1 9 5 0 18 101
相撲 1 4 0 0 1 0 0 7 0 0 2 15
ボクシング 1 1 0 11 0 0 1 0 0 0 0 14
スキー 3 2 0 1 3 1 0 1 3 2 1 17
自転車 7 4 1 0 1 3 1 1 1 0 0 19
その他 89 57 21 24 12 18 11 49 35 13 36 365
合計 1,240 855 285 246 210 188 134 390 340 87 421 4,396
※ 傷病名については、災害共済給付の医療費に係る資料からテキスト分析ソフトにより抽出した。
また、1件に複数の傷病名がある場合は数が少ない方を特徴的とみなし抽出した。
[クラスター分析]
発生件数 50件以上の 13競技につ
いて、競技毎の各傷病の発生割合を
変数としクラスター分析を行うと
次のとおりであった。
大きな分類としては、水泳・体
操・柔道・ラグビーの頚部の傷病も
多いグループと、その他の頭部の傷
病が多いグループに分類された。
また、ラグビーと柔道、ハンド
ボール、剣道、バレーボールとバス
ケットボール、ソフトボールと陸上
競技が、それぞれ発生傾向が近かっ
た。(図 2-1-1)
図 2-1-1 13 競技種目のクラスター分析
(傷病別割合を変数)
N>
16 17
第2編
第1章

17
Ⅳ 発生の原因
発生の原因では、「人と接触」が最も多く、「ボールや設備と接触」、「転倒等」、「技をかけら
れる等」の順であった。
競技別にみるとサッカーでは「人と接触」が約 70%を占め、ボールに当たるなどの「ボール
や設備と接触」が約 17%あった。特に、ヘディングの際の相手選手との頭部の接触や、ボール
の衝撃によるものなどがあった。バスケットボールでは「人と接触」が約 71%を占め、「転倒
等」が約 10%、「ボールや設備と接触」が約 10%であり、設備では壁が多かった。ラグビーで
は「人と接触」が約 93%を占めており、タックルを受けたときや、入ったときに多かった。ま
た、柔道では約 91%が技をかけられるであり、技では大外刈り、背負い投げ、内股の順で多く、
「受け身」や「乱取り」に係わるものが多かった。
以上のように「人と接触」が全体的に多いが、競技種目により異なる傾向もみられた。(表
2-1-7)
表 2-1-7 競技別・原因別 発生件数
人と接触
ボールや
設備と接
触
転倒等 技をかけ
られる等 その他 合計
サッカー 584 145 51 0 57 837
バスケットボール 236 34 32 0 32 334
ハンドボール 58 15 8 0 7 88
ラグビー 537 6 9 0 25 577
テニス 8 20 24 0 18 70
バレーボール 39 50 24 0 21 134
卓球 3 2 7 0 2 14
バドミントン 0 4 7 0 5 16
ソフトボール 29 56 4 0 8 97
野球 167 655 43 0 37 902
水泳 0 43 7 0 9 59
体操 8 1 112 0 13 134
陸上競技 12 20 100 0 22 154
柔道 22 0 6 407 14 449
剣道 48 9 10 23 11 101
相撲 10 0 0 2 3 15
ボクシング 2 0 0 11 1 14
スキー 1 0 11 0 5 17
自転車 7 1 7 0 4 19
その他 105 41 147 17 55 365
合計 1,876 1,102 609 460 349 4,396
16 17
第2編
第1章

18
Ⅴ まとめ
体育活動における頭頚部の外傷(負傷・疾病)について、中学校・高等学校での現状をまと
めると次のとおりであった。
活動別では体育の授業で約 2 割、運動部活動で約 8 割と運動部活動で多く発生している。部
位別では約 8 割が頭部であった。
競技別では野球、サッカー、ラグビー、柔道等で多く発生していた。
また、運動部活動での部員 1,000 人当たりの頻度ではラグビー(2.33 人)、自転車(1.71 人)、
相撲(0.85 人)、ボクシング (0.76 人)、柔道(0.61 人)などで頻度が高かった。
体育活動全体の学年別・競技別では高 1、高 2 の 2 学年で約半数を占めた。
体育の授業における発生件数では中 1 から高 3 の 6 年間のうち中 2、中 3 の 2 学年で約 4 割
を占め、学校種でみても中学校が約 52%と高等学校より多い。これは体操、陸上競技で多く発
生していることによるものであった。
運動部活動では野球、サッカー、ラグビー、柔道、バスケットボール等の競技で発生が多い。
また、学年をみると高 1、高 2 の 2 学年で約 55%を占め、特に野球の高 1、サッカー、ラグビー
の高 2 が多かった。
傷病別では頭部打撲、脳振盪、頚髄損傷の順で多い。脳振盪はサッカー、ラグビー、野球、
柔道の順で多く発生していた。
また、脳振盪以外の脳の傷病名(脳挫傷、急性硬膜下血腫、外傷性クモ膜下出血、急性硬膜
外血腫)を競技別にみると、野球、バスケットボールでは脳挫傷、外傷性クモ膜下出血、急性
硬膜外血腫が多い傾向にあるが、ラグビー、柔道では急性硬膜下血腫が多いといった傾向がみ
られた。
頚髄損傷、頚椎捻挫、頚椎骨折はラグビー、柔道、サッカーなど、対人競技や対人接触があ
る競技で多かった。
発生の原因では、「人と接触」が最も多く、「ボールや設備と接触」、「転倒等」、「技をかけら
れる等」の順であった。
競技別をみるとサッカーでは「人と接触」が多く、ボールに当たるなどの「ボールや設備と
接触」が続き、特にヘディングの際の相手選手との接触やボール自体の衝撃によるものなどが
あった。バスケットボールでは「人と接触」が多く、「ボールや設備と接触」、「転倒等」の順で
あった。ラグビーでは「人と接触」が約 9 割をしめていた。また、柔道では約 9 割が「技をか
けられる」であった。
以上のように「人と衝突・接触」が全体的に多いが、競技により異なる傾向もみられた。
以上を踏まえ、指導者、教師、生徒等の誤った行為、ルール違反、故意、不注意、技術不足、
過信、疲労等の人的要因、競技自体の危険要因である活動要因について分析を進め、有効な事
故防止策を検討する必要がある。
18 19
第2編
第1章

19
第2章 体育活動における頭頚部外傷の基礎データ(死亡・障害)
平成 10 年度~平成 23 年度に災害共済給付として死亡見舞金、障害見舞金(1 級~3 級)を給
付したもののうち、当該期間に発生した体育活動による頭頚部の事例 167 例(死亡 57 例、障害
110 例)の傾向の分析をした。
なお、本分析におけるデータは次による。
[方法] 小学校、中学校、高等学校の災害共済給付の事例のうち、頭頚部の死亡・重度の障害事故の
事例を対象に、年度別、傷病別、学年別、性別、教育活動別、競技別等の観点から分析を行っ
た。
[重度の障害の程度]
障害等級(1 級~14 級)の 3 級以上は労働能力 100%喪失であり、死亡見舞金と同水準のた
め、1 級~3 級の障害を「重度の障害」とした。
[「陸上競技」、「体操」および「その他」]
競技別の「陸上競技」には、「短距離走」などの本来の陸上競技の他に、体育祭のリレー、
学校行事のマラソン大会等を含めた。また、「体操」には「跳馬」などの本来の体操競技の他
に、体育の授業での跳び箱、マット運動等を含めた。
競技別の「その他」には、「ダンス」、「ボート」などの競技の他に、体育祭の騎馬戦や体育
の授業時の準備運動などを含めた。
※ なお、統計上、必要に応じて原則として 3 件以上(n≧3)あったものを中心に表記し、そ
れ以外(n<3)は「その他」として一括した。
18 19
第2編
第2章

20
Ⅰ 体育活動による頭頚部の死亡・重度の障害事故の概要
平成10年度~平成 23年度の 14年間で、167例(死亡 57例、障害 110例)であった(図2-2-1)。
死亡事故では、頭部外傷が約 90%を占めており、頚部外傷は約 10%であった。
死亡事故の原因となった競技は、頭部外傷について体育授業等では陸上競技等、運動部活動
では柔道等であった。頚部外傷について体育授業等では水泳等、運動部活動ではラグビー等で
あった。
重度の障害では頚部外傷が約 66%、頭部外傷が約 34%であった。原因となった競技は、頚部
外傷について体育授業等では水泳等、運動部活動ではラグビー等であった。頭部外傷について
は体育授業等、運動部活動とも柔道等であった。
図 2-2-1 体育活動による頭頚部の死亡・重度の障害事故の概要
※「頭部外傷」は「脳挫傷」、「急性硬膜下血腫」などの傷病名を総称したもの。
※「頚部外傷」は「頚椎損傷」、「頚髄損傷」「頚椎脱臼骨折」などの傷病名を総称したもの。
※「体育授業等」は体育の授業、特別活動、クラブ活動などの運動部活動以外の活動の総称。
頭部外傷 51 件
(89.5%)
頚部外傷 6件
(10.5%)
頭部外傷 37 件
(33.6%)
頚部外傷 73 件
(66.4%)
運動 部活動 45 件
(88.2%) 柔道
(21 件) ラグビー (7件) ボクシング
(4件) 野球
(3件) その他
(10 件)
体育 授業等 6件
(11.8%) 陸上
(3件) その他 (3件)
運動 部活動 4件
(66.7%) ラグビー (2件) 水泳
(1件) その他 (1件)
体育 授業等 2件
(33.3%) 水泳
(1件) 体操
(1件)
運動 部活動 34 件
(91.9%) 柔道
(17 件) ボクシング
(4 件) 水泳 (3 件)
ラグビー (3 件) その他 (7件)
体育 授業等 3件
(8.1%) 柔道
(2件) その他 (1件)
体育 授業等 25 件
(34.2%) 水泳
(11 件) 体操
(8件) 柔道
(3件) その他 (3件)
運動 部活動 48 件
(65.8%) ラグビー (13 件)
柔道 (11 件)
体操 (9件) 水泳 (5 件) その他
(10 件)
死亡・重度の障害 167 件(100%)
死亡 57 件(34.1%)
重度の障害 110 件(65.9%)
20 21
第2編
第2章

21
Ⅱ 事故件数の年度別推移
事故件数は、年度による増減はあるが、減少傾向にある(図 2-2-2)。事故の発生頻度を 14
年間について前半(H10~H16)の 7 年間と後半(H17~H23)の 7 年間に分け、生徒 10 万人当た
りでみると、前半は 0.10 件であったが、後半は 0.06 に減少している。
なお、前半と後半の発生頻度について検定すると 5%で有意であり、後半は前半に比較し減少
している。
表 2-2-1 体育活動による頭頚部の死亡・重度の障害事故
-年度別発生件数・頻度-
年度 H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23
件数(件) 15 17 19 13 14 16 12 12 9 7 10 11 8 4
頻度 (対 10万人)
0.09 0.11 0.12 0.08 0.09 0.11 0.08 0.08 0.06 0.05 0.07 0.08 0.06 0.03
※ 発生頻度は生徒 10万人当たりの件数とし、年度毎に事故件数/小・中・高の災害共済給付制度加入児童
生徒数(小・中・高)×10万で算出した。
図 2-2-2 体育活動による頭頚部の死亡・重度の障害事故
-年度別発生件数・頻度-
表 2-2-2 体育活動による頭頚部の死亡・重度の障害事故
-競技別・発生年度別件数(件)- H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 合計
柔道 4 9 4 3 5 7 1 5 1 1 2 4 6 2 54
ラグビー 1 2 3 3 3 2 3 2 2 1 0 2 0 1 25
水泳 1 3 1 3 1 0 3 2 1 1 2 1 1 1 21
体操 4 0 4 2 2 0 1 2 1 1 1 2 0 0 20
ボクシング 0 2 1 0 2 1 0 1 0 0 0 1 0 0 8
陸上競技 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 5
バスケットボール 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 4
野球 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 4
バレーボール 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 3
サッカー 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3
その他 1 1 3 2 1 4 2 0 3 2 1 0 0 0 20
合計 15 17 19 13 14 16 12 12 9 7 10 11 8 4 167
※ 競技種目は原則 3件以上(n≧3)あったものを表記し、それ以外(n<3)は「その他」で一括した。
0
0.05
0.1
0.15
0
5
10
15
20
H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23
件数
頻度
20 21
第2編
第2章

22
Ⅲ 傷病別にみた事故件数
頭部外傷が全体の 53%を占めており、頚部外傷は 47%を占めている。頭部及び頚部の外傷は
ほぼ同程度発生していた。
表 2-2-3 体育活動による頭頚部の死亡・重度の障害事故
-傷病別発生件数-
傷病 度数(件) %
頭部外傷 88 52.7
頚部外傷 79 47.3
合計 167 100.0
図 2-2-3 体育活動による頭頚部の死亡・重度の障害事故
-傷病別割合-
傷病別に事故件数の年度別推移をみてみると、全体的に減少傾向にあった(表 2-2-4)。また、
頭部外傷と頚部外傷のそれぞれの推移を前半 7 年と後半 7 年に分けてみると、頭部外傷は前半
52 件、後半 36 件、頚部外傷は前半 54 件、後半 25 件とそれぞれ減少していた。
表 2-2-4 体育活動による頭頚部の死亡・重度の障害事故
-傷病別・発生年度別件数(件)- H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 合計
頭部外傷 9 9 10 6 6 9 3 7 5 3 4 9 4 4 88
頚部外傷 6 8 9 7 8 7 9 5 4 4 6 2 4 0 79
合計 15 17 19 13 14 16 12 12 9 7 10 11 8 4 167
頭部
外傷
53%
頚部
外傷
47%
22 23
第2編
第2章

23
Ⅳ 学校種・学年別にみた事故件数
小学校約 5%、中学校約 30%、高等学校約 67%と、上級の学校となるほど事故が増え、小学校
では 5 年生、6 年生、中学校、高等学校では 1 年生、2 年生に多く、特に高等学校では 1 年生に
多く発生していた(表 2-2-5、図 2-2-4、5)。これには体格の発育や運動能力の向上に伴い、受
傷に関わる外力の大きさが増加することが大きな要因と考えられる。さらに中高生では低学年
に多くみられていることにより、競技経験の浅い初心者を中心に事故が起こっている可能性が
ある。
表 2-2-5 体育活動による頭頚部の死亡・重度の障害事故
-学校種・学年別件数(件)- 小 1 小 2 小 3 小 4 小 5 小 6 中 1 中 2 中 3 高 1 高 2 高 3 合計
頭部外傷 0 1 0 0 1 1 13 8 4 34 16 10 88
頚部外傷 0 0 0 0 1 1 6 8 11 8 24 20 79
合計 0 1 0 0 2 2 19 16 15 42 40 30 167
図 2-2-4 体育活動による頭頚部の死亡・重度の障害事故
-学校種別割合-
図 2-2-5 体育活動による頭頚部の死亡・重度の障害事故
-学年別発生件数(件)-
0 1 0 02 2
1916 15
4240
30
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
小1 小2 小3 小4 小5 小6 中1 中2 中3 高1 高2 高3
小学校
3%
中学校
30%高等学校
67%
22 23
第2編
第2章

24
Ⅴ 男女別にみた事故件数
全体としては、男子 91%、女子 9%であり、男女比は約 9 対 1 であった。学校種別にみると、
男子の割合は、小学校 60%、中学校 90%、高等学校 93%と、上級の学校となるにつれ男子の割合
が増えていた(表 2-2-6、図 2-2-6、7)。これは前項と同様、男子では体格の発育や運動能力の
向上に伴い、受傷に関わる外力の大きさが増加することが大きな要因と考えられる。
表 2-2-6 体育活動による頭頚部の死亡・重度の障害事故
-男女別・学校種別件数(件)と割合(%)-
小学校 中学校 高等学校 合計
男 3(60) 45(90) 104(93) 152(91)
女 2(40) 5(10) 8( 7) 15( 9)
合計 5 50 112 167
※ ( )内は%
図 2-2-6 体育活動による頭頚部の死亡・重度の障害事故
-男女別割合-
図 2-2-7 体育活動による頭頚部の死亡・重度の障害事故
-学校種別・男女別割合-
男
60%
女
40%
男
90%
女
10%
男
93%
女
7%
男
91%
女
9%
小学校 中学校 高等学校
24 25
第2編
第2章

25
Ⅵ 教育活動別にみた事故件数
小学校では体育の授業中の事故が 40.0%、水泳指導等の「その他課外指導」が 40.0%を占めて
いた。
一方、中学校では運動部活動が 74.0%、体育の授業 20.0%、特別活動 2.0%等、また高等学校
では運動部活動 83.9%、体育の授業 11.6%、特別活動 4.5%等と、運動部活動の割合がほぼ 3/4
を超えていた(表 2-2-7、8、図 2-2-8)。
したがって、これ以降の統計については、小学校と、中学校・高等学校とを分けて検討する
必要があるものと思われた。すなわち、小学校では 5 例の活動内容別に検討し、中学・高等学
校では、「運動部活動」(131 例)と、体育の授業を含めたその他の活動を「体育の授業等」(31
例)として扱い、比較検討することとした。
表 2-2-7 体育活動による頭頚部の死亡・重度の障害事故
-教育活動別・学校種別発生件数(件)-
体育の授業 運動部活動 特別活動 クラブ活動 その他課外 合計
小学校 2 0 0 1 2 5
中学校 10 37 1 0 2 50
高等学校 13 94 5 0 0 112
合計 25 131 6 1 4 167
表 2-2-8 体育活動による頭頚部の死亡・重度の障害事故
-学校種別・教育活動別割合(%) 体育の授業 運動部活動 特別活動 クラブ活動 その他課外 合計
小学校 40.0 0.0 0.0 20.0 40.0 100.0
中学校 20.0 74.0 2.0 0.0 4.0 100.0
高等学校 11.6 83.9 4.5 0.0 0.0 100.0
合計 15.0 78.4 3.6 0.6 2.4 100.0
※ 「%」は、学校種毎に各教育活動の事故件数/各学校種の事故総数×100 で算出した。
図 2-2-8 体育活動による頭頚部の死亡・重度の障害事故
-学校種別・教育活動別割合-
体育
の授
業
40%
クラ
ブ活
動
20%
その
他課
外
40%
体育
の授
業
20%
運動
部活
動
74%
特別
活動
2%
その
他課
外
4%
体育
の授
業
12%
運動
部活
動
84%
特別
活動
4%
小学校 中学校 高等学校
24 25
第2編
第2章

26
Ⅶ 小学校での体育活動による頭頚部の死亡・重度の障害事故
小学校では、Ⅵで述べたように、「体育の授業等」における死亡・重度の障害事故を中心とし
て、全体で 5 件起きていた(「体育授業等」は運動部活動以外の教育活動)。
これを傷病別にみると、頭部外傷3件、頚部外傷2件であり、高学年で多くみられた(表2-2-9、
図 2-2-9)。
表 2-2-9 小学校での体育活動による頭頚部の死亡・重度の障害事故
―学年・傷病別件数(件)―
小 1 小 2 小 3 小 4 小 5 小 6 合計
頭部外傷 0 1 0 0 1 1 3
頚部外傷 0 0 0 0 1 1 2
合計 0 1 0 0 2 2 5
図 2-2-9 小学校での体育活動による頭頚部の死亡・重度の障害事故
―傷病別割合―
また競技別(授業内容)にみると、水泳、体操、卓球がそれぞれ 1 件でその他が 2 件となっ
ていた(表 2-2-10、図 2-2-10)。水泳は飛び込みによる頚椎損傷であり、体操は倒立技の失敗
による頚髄損傷であり、卓球は卓球台が頭部にぶつかったものである。その他は登山時の転落、
体育授業でバランス感覚を培うため自転車に乗りハンドルを切った際の転倒によるものである。
表 2-2-10 小学校での体育活動による頭頚部の死亡・重度の障害事故
―学年・競技別(件)―
頭部外傷
60%
頚部外傷
40%
小 1 小 2 小 3 小 4 小 5 小 6 合計
水泳 0 0 0 0 1 0 1
体操 0 0 0 0 0 1 1
卓球 0 0 0 0 1 0 1
その他 0 1 0 0 0 1 2
合計 0 1 0 0 2 2 5
26 27
第2編
第2章

27
図 2-2-10 小学校での体育活動による頭頚部の死亡・重度の障害事故
―競技別割合―
男女差については、男子 3 名、女子 2 名と、男子が多かったが、発生頻度でみると、10 万人
当たり男子 0.006 件、女子 0.004 件と、それほど差はなかった(表 2-2-11:児童数は文部科学
省学校基本調査の平成 10 年度~平成 23 年度の合計数とした。)。
表 2-2-11 小学校での体育活動による頭頚部の男女別件数と発生頻度
(10 万人あたり発生件数)
Ⅷ 中学・高等学校での体育活動による死亡・重度の障害事故
中学・高等学校では、Ⅵで述べたように、「体育の授業等」における死亡・重度の障害事故は
31 件、「運動部活動」では 131 件起きていた。
1 「体育の授業等」
31 例を傷病別にみると、頚部外傷が 8 割を超えており、頭部外傷は 2 割であった(表 2-2-12、
図 2-2-11)。
表 2-2-12 中学・高等学校での体育の授業等における頭頚部の死亡・重度の障害事故
-学年・傷病別件数(件)-
中 1 中 2 中 3 高 1 高 2 高 3 合計
頭部外傷 1 0 2 2 0 1 6
頚部外傷 3 1 6 2 6 7 25
合計 4 1 8 4 6 8 31
発生件数 頻度
(対 10 万人)
男 3 0.006
女 2 0.004
合計 5 0.005
水泳
20%
体操
20%
卓球
20%
その他
40%
26 27
第2編
第2章

28
図 2-2-11 中学・高等学校での体育の授業等における頭頚部の死亡・重度の障害事故
-傷病別割合-
また競技別(授業内容)で発生件数をみると、水泳が 35%(11 件)を占め、次いで体操が約
26%(8 件)であった。それぞれプールへの飛び込みの時、回転を伴う運動の時に発生している(表
2-2-13)。
表 2-2-13 中学・高等学校での体育の授業等における頭頚部の死亡・重度の障害事故
-競技別・学年別発生件数(件)- 中 1 中 2 中 3 高 1 高 2 高 3 合計
水泳 0 1 2 2 1 5 11
体操 2 0 3 0 3 0 8
柔道 2 0 0 1 1 1 5
陸上競技 0 0 2 1 0 0 3
その他 0 0 1 0 1 2 4
合計 4 1 8 4 6 8 31
図 2-2-12 中学・高等学校での体育の授業等における頭頚部の死亡・重度の障害事故
-競技別割合-
※簡素化のため n<3 の種目は省略してある。
頭部外傷
19%
頚部外傷
81%
水泳
35%
体操
26%
柔道
16%
陸上競技
10%
その他
13%
28 29
第2編
第2章

29
男女差での発生件数については、やはり男子に多く、中学校では 12 倍、高等学校では 8 倍の
発生件数となっていた。これは発生頻度(10 万人あたり発生件数)でも同様であり、また小学
校に比べて、男子の発生頻度は 7 倍から 10 倍の高い頻度であった(表 2-2-14、図 2-2-13)。
表 2-2-14 中学・高等学校での体育の授業等における頭頚部の死亡・重度の障害事故
―男女別発生件数・頻度(件)-
件数 中学校 高等学校 合計 頻度 中学校
(対10万人)
高等学校 (対 10 万人)
性別 (対 10 万人)
男 12 16 28 男 0.044 0.061 0.052
女 1 2 3 女 0.004 0.008 0.006
合計 13 18 31 学校別 0.024 0.035 0.029
図 2-2-13 体育の授業等における頭頚部の死亡・重度の障害事故
-学校別・男女別発生頻度(対 10 万人)-
※「体育の授業等」とは運動部活動以外の教育活動を示す。
2 「運動部活動」
中学・高等学校での「運動部活動」による死亡・重度の障害事故 131 例を傷病別にみると、
頭部外傷が 79 件、頚部外傷が 52 件であり、「体育の授業等」に比べ、頭部外傷の割合が増えて
いた(表 2-2-15、図 2-2-14)。
表 2-2-15 中学・高等学校での運動部活動における頭頚部の死亡・重度の障害事故
-傷病別・学年別発生件数(件)-
中 1 中 2 中 3 高 1 高 2 高 3 合計
頭部外傷 12 8 2 32 16 9 79
頚部外傷 3 7 5 6 18 13 52
合計 15 15 7 38 34 22 131
男
0.006
男
0.044
男
0.061
女
0.004
女
0.004
女
0.008
0
0.01
0.02
0.03
0.04
0.05
0.06
0.07
小学校 中学校 高等学校
28 29
第2編
第2章

30
図 2-2-14 中学・高等学校での運動部活動における頭頚部の死亡・重度の障害事故
-傷病別割合-
また「運動部活動」による死亡・重度の障害事故を競技別にみると、柔道が 49 件(38%)が
最も多く、ラグビー、体操、水泳の割合が多くなっていた(表 2-2-16、図 2-2-15)。
表 2-2-16 中学・高等学校での運動部活動における頭頚部の死亡・重度の障害事故
-競技別・学年別発生件数(件)-
図 2-2-15 中学・高等学校での運動部活動における頭頚部の死亡・重度の障害事故
-競技別割合-
*簡素化のため N<3の競技は省略してある。
頭部外傷
60%
頚部外傷
40%
中 1 中 2 中 3 高 1 高 2 高 3 合計
柔道 13 7 4 17 3 5 49
ラグビー 0 0 0 3 13 9 25
体操 0 1 2 2 5 1 11
水泳 2 3 1 2 1 0 9
ボクシング 0 0 0 3 5 0 8
野球 0 0 0 1 1 2 4
バスケットボール 0 0 0 1 1 1 3
バレーボール 0 2 0 1 0 0 3
サッカー 0 0 0 1 1 1 3
その他 0 2 0 7 4 3 16
合計 15 15 7 38 34 22 131
柔道
38%
ラグビー
19%
体操
9%
水泳
7%
ボクシング
6%
野球
3%
バスケット
ボール
2%
バレー
ボール
2%
サッカー
2%その他
12%
30 31
第2編
第2章

31
さらに、これを競技別の発生頻度(10 万人当たり発生件数)でみるとボクシング(18.43)、
ラグビー(5.11)、柔道(4.18)の順で高かった(表 2-2-17、図 2-2-16)。
表 2-2-17 中学・高等学校での運動部活動における頭頚部の死亡・重度の障害事故
-対 10 万人競技別頻度(件)-
※ 発生頻度(対 10万人)は、件数÷部員数×10万で算出。 なお、部員数は中学校体育連盟、高等学校体育連盟、高等学校
野球連盟の H10~H23 の登録数の合計
図 2-2-16 中学・高等学校での運動部活動における頭頚部の死亡・重度の障害事故
-対 10 万人競技別頻度-
男女差については、中学校では男子は女子の約 8 倍、高等学校で約 15 倍と男子の割合が多く
なっていた。発生頻度(10 万人あたり発生件数)でみると、男女共「体育の授業等」の 8 倍で
あったが、男女差の比率はほぼ同様であった(表 2-2-18、図 2-2-17)。
競技 発生頻度 (対 10 万人)
ボクシング 18.43
ラグビー 5.11
柔道 4.18
体操 3.24
水泳 0.83
野球 0.06
バレーボール 0.06
サッカー 0.06
バスケットボール 0.04
その他 0.06
合計 0.24
18.43
5.114.18
3.24
0.83 0.06 0.06 0.06 0.04 0.0602468101214161820
30 31
第2編
第2章

32
表 2-2-18 中学・高等学校での運動部活動における死亡・重度の障害事故
-男女別発生件数・対 10万人頻度-
件数 中学校 高等学校 合計 頻度 中学校
(対 10 万人)
高等学校 (対 10 万人)
性別 (対 10 万人)
男 33 88 121 男 0.16 0.67 0.36
女 4 6 10 女 0.03 0.09 0.05
合計 37 94 131 学校別 0.10 0.48 0.24
※ なお全体の部員数は、中学校体育連盟、高等学校体育連盟及び高等学校野球連盟登録部員数(平成 10年度 ~平成 23 年度)とした。ただし、中学校の平成 10年度~平成 13年度については未調査のため、平成 14年度の登録数を利用した。
図 2-2-17 中学・高等学校での運動部活動における死亡・重度の障害事故
-男女別発生頻度(対 10 万人)-
また発生件数、発生頻度(10 万人あたり発生件数)を学年別にみると、高校 1 年生が最も多
く、この年代への対応が急務であると思われた。
表 2-2-19 中学・高等学校での運動部活動における死亡・重度の障害事故
-学年別発生件数(件)-
図 2-2-18 中学・高等学校での運動部活動における死亡・重度の障害事故
-学年別発生件数(件)-
男
0.16
男
0.67
女
0.03
女
0.09
0.00
0.10
0.20
0.30
0.40
0.50
0.60
0.70
0.80
中学校 高等学校
15 15
7
38
34
22
0
5
10
15
20
25
30
35
40
中1 中2 中3 高1 高2 高3
学年 中 1 中 2 中 3 高 1 高 2 高 3 合計
件数 15 15 7 38 34 22 131
32 33
第2編
第2章

33
表 2-2-20 中学・高等学校での運動部活動における死亡・重度の障害事故
-学年別発生頻度(対 10 万人)-
中 1 中 2 中 3 高 1 高 2 高 3
発生頻度 0.12 0.13 0.06 0.54 0.52 0.36
※ 学年別部員数については、中体連、高体連の資料がないため、高野連の平成 23年度学年別人数比 1年 35.7%、2年 33.1%、3年 31.1%を使って運動種目毎に案分して算定
図 2-2-19 中学・高等学校での運動部活動における死亡・重度の障害事故
-学年別発生頻度(対 10 万人)-
Ⅸ 頭頚部事故発生原因
体育活動による頭頚部の死亡・重度の障害事故の原因としては、「他の人に投げられる・打た
れる等」が 57 件で最も多く、続いて「人との衝突・接触」32 件、「施設・設備等と衝突」32 件
となっており、この 3 項目で全体の約 3/4 を占める。
他は「技の失敗」、「転倒・転落」、「ボールなど体育用具と衝突」などであった。
これらをみると生徒自身が競技の初心者などの個体の要因、技が不完全などの方法の要因、
プールなどの環境の要因、指導・管理の要因が複合して起きていると思われる。
表 2-2-21 体育活動による頭頚部の死亡・重度の障害事故の原因一覧
競技名
他の人に投げられ
る・打たれる等
人との衝突・接
触
施設・設備等と衝突
技の失敗
転倒・転落
ボールなど体育用具と衝突
その他 合計
柔道 44 0 0 10 0 0 0 54
ラグビー 0 24 0 0 0 1 0 25
水泳 0 0 21 0 0 0 0 21
体操 0 0 1 18 1 0 0 20
ボクシング 8 0 0 0 0 0 0 8
陸上競技 0 2 1 1 0 0 1 5
バスケットボール 0 1 2 0 1 0 0 4
野球 0 1 0 0 0 3 0 4
バレーボール 0 0 1 0 2 0 0 3
サッカー 0 2 1 0 0 0 0 3
その他 5 2 5 0 7 1 0 20
合計 57 32 32 29 11 5 1 167
0.12 0.13
0.06
0.54 0.52
0.36
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
中1 中2 中3 高1 高2 高3
32 33
第2編
第2章

34
Ⅹ まとめ
体育活動における頭頚部の外傷による死亡・重度の障害事故は、平成 10 年度~平成 23 年度
の 14 年間で 167 例(死亡 57 例、障害 110 例)あった。
事故件数は減少傾向にあるが、依然として頭頚部の死亡・重度の障害事故は起きている。
死亡事故では、頭部外傷が約 90%を占めており、その原因の約 40%を柔道が占めていた。続
いてラグビー、ボクシング、陸上、野球などで起きていた。頚部外傷ではラグビーと水泳がそ
れぞれ 1/3 を占めていた。また、重度の障害では頚部外傷が約 70%を占め、その原因となった
主なスポーツ種目は、ラグビー、体操、水泳、柔道などであった。
学校種・学年別にみると、上級学校となるほど事故件数が増え、小学校では 5 年生、6 年生
で、中学校、高等学校では 1 年生、2 年生に多く、特に高等学校では 1 年生に多く発生してい
た。これは死亡・重度の障害事故が、運動レベルの低い初心者を中心に起こりやすいことを示
している。
性別では、男子の児童生徒に多くみられ(男女比は約 9 対 1)、上級学校となるにつれ男子の
割合が増えている。これには身体接触のある競技に男子が多いことや、身体が大きくなるに従っ
てより強い衝撃が加わりやすいことが関係しているものと思われる。
教育活動別にみると、小学校では体育の授業中の事故が 40%で、それ以外では「その他課外
指導」や「クラブ活動」で起きていた。一方、中学校では運動部活動が 74%、また高等学校で
は 84%と、運動部活動中の割合がほぼ 3/4 を超えている。
小学校での死亡・重度の障害事故では、頭部外傷が 60%を占めており、高学年で多くみられ
る。競技別にみると、水泳、体操、卓球がそれぞれ 1 件で、その他が 2 件となっている。水泳
は飛び込み、体操は倒立技の失敗、卓球は卓球台が頭部にぶつかったことが主な原因として挙
げられる。
中学・高等学校における頭頚部の死亡・重度の障害事故では、まず「体育の授業等」でみる
と、傷病別で頚部外傷が 80%を超えており、頭部外傷は約 19%であった。また競技別(授業内
容)では、水泳と体操が多く、それぞれ飛び込みと回転運動の失敗が主な原因として挙げられ
る。
次に「運動部活動」でみると、傷病別では、頭部外傷が約 60%を占め、頚部外傷は約 40%であっ
た。競技別では柔道、ラグビーや体操の割合が多くなっている。それぞれ投げ技、対人接触プ
レーや回転運動の失敗が主な原因として挙げられる。
運動部活動中の事故では、学年別の発生件数は中学校 1 年生、高校 1 年生が多く、この時期
への対応が急務であると思われる。
以上、学校の管理下における体育活動による頭頚部の死亡・重度の障害事故に対しては、こ
れらの傾向を踏まえ、個体の要因、方法の要因、環境の要因及び指導・管理の要因について原
因を分析し危険要因を見極め、早急に対策を講じていく必要があると思われる。
34 35
第2編
第2章

35
第3章 災害実地調査結果からみる頭頚部外傷の状況
本章では事故の発生要因を更に探るため、第1章の負傷事故に見られる傾向や第 2 章の死
亡・重度障害事故に見られる発生傾向を踏まえ、更に詳しい事故の要因を把握するため、平成
24 年度に災害共済給付の医療費の請求があった事案のうち中学校又は高等学校の体育活動(保
健体育の授業、運動部活動)に伴う頭頚部の事故で、次の条件に該当する案件を 48 例抽出し、
本センター職員が学校に赴き体育科教諭、運動部活動顧問教諭等から聞き取り調査を行った。
【抽出条件】
○ 競技はセンターの統計(P11 表 2-1-1「活動別・競技別・頭頚部別」参照)において
頭頚部の負傷が多いラグビー、柔道、野球、サッカーの 4 競技
○ 頭頚部外傷の発生状況を把握するため各競技 10 例以上の調査
○ 比較的重症(原則、被災当初月の給付額が 3 万円以上)の事案
○ 調査事案は災害共済給付システムから「競技名」、「キーワード(タックル等)」等によ
り抽出
○ 事例はセンターの地域の事務所の業務分担毎に全国 6 ブロックから均等に収集
また、本調査は事故の要因を本委員会アドバイザーである武藤氏らの分類方法に従って「個
体の要因」、「方法の要因」、「環境の要因」、「指導・管理の要因」の 4 つに分類して行った。
なお、ここで言う各要因は次のとおりである。
分類項目 説 明
個体の要因 スポーツを実践している人の要因で、体格、体力・運動能力、技術レベル、誤っ
た行為、ルール違反、故意、不注意、過信、疲労等々、選手、児童生徒等々、係
わる人の身体的、精神・心理的要因
方法の要因 スポーツの方法・内容・仕方等の要因で、走、跳、投、蹴、泳等の各動作、パフォー
マンスが不適切な方法による要因
環境の要因
スポーツの施設、設備、用具、自然条件、社会環境等の要因で、体育館、グラウ
ンド、道場、コート、プール等の体育施設をはじめ、野外活動では気象、天候、
地理・地形等の自然環境、また高温、多湿、炎天下といった運動環境の他にも、
人的環境、社会環境等、周辺状況の不備・不適切等の要因 指導・管理の
要因 スポーツの指導方法・内容、管理体制等の要因で指導者、教師、コーチ、管理者
の資質、指導方法及び安全管理の要因
今回の調査事例について個々の調査結果を示すとともに、事故発生の要因について競技別に
まとめると次のとおりである。
34 35
第2編
第3章

36
Ⅰ ラグビー
東京都市大学共通教育部 教授 渡辺 一郎
ラグビーについて、平成 10 年度~平成 23 年度の死亡・重度の障害事故は 25 件であるが、発
生の状況を第2編第2章の表 2-2-21 「体育活動による頭頚部の死亡・重度の障害事故の原因
一覧」でみると「人との衝突・接触」が多い。
さらに、発生時の動作の内訳をみると、タックル 13 件、スクラム 6 件、ラック 4 件、モール
1 件、タックルの練習 1 件の計 25 件であり、半数以上がタックルに絡む事故である。
また、ラグビーによる頭頚部のけがの 97%は運動部活動で起きている(P11 表 2-1-1 「活動
別・競技別・頭頚部別」参照)。
このため、最近の運動部活動のラグビーによる負傷事例から「タックル」に係る案件を抽出
し、調査を行った。
[調査結果一覧]
1.タックルを受ける
練習/試合グランド
状況指導歴 指導内容
経験年数
傷病名 受傷状況 受傷要因
事例1 試合 芝 10年ウエイトトレーニングタックルを受けた時は左右にいなす。
1年以上 頚髄損傷
若干後方にそれたパスを受けた瞬間にタックルに入られ後方に倒れ頚部を地面に強打。
やや後方でボールをキャッチしたため上体が伸び無防備状態となり咄嗟の対応ができなかった。
事例2 試合形式土
良好24年
頭部の怪我の時は3週間安静
1年 脳振盪タックルを受け後方に倒れ後頭部を地面に強打。
痩せ型の選手であり、相手タックルもやや高く(腰付近)受け身姿勢(顎を引きおへそを見る)がとれなかった。
事例3 練習土
良好0年
タックル練習は顧問立会いのもと
初心者脳振盪脊髄振盪
タックルを受け右側頭部を地面に強打。
耐えられると思いタックルの強さの見当が外れた。
事例4 練習土
良好29年
コンタクト練習は顧問立会いのもと
1年以上頭部打撲頚椎挫傷
タックルを受け後方に倒れ後頭部を地面に強打。
相手タックルが高かったのとタックルを受けた時の姿勢(重心)が高かった。
事例5 練習土
良好5年
首のトレーニングから練習に入る。
3年以上外傷性くも膜下出血脳振盪
タックルを受け左側方に倒れ左側頭部を地面に強打。
倒れた選手に乗りかかるように転倒したため受け身姿勢が取れず頭から転倒。
事例6 試合整備され
た芝37年
倒れた時の受け身、頭部を打ちにくい倒れ方の練習
2年以上 頭部外傷Ⅰ型タックルを受け後方に倒れ後頭部を地面に強打。
タックルを受けた時の姿勢(重心)が高かった。
36 37
第2編
第3章

37
[事故発生の要因]
実地調査事例を見ると、事故はすべて運動部活動中に発生し、受傷者は全員高校生でその内
訳は 1 年生 3 名、2 年生 9 名、3 年生1名の計 13 名であった。ラグビー経験年数は初心者 2 名、
1 年以上が 8 名、2 年以上が 2 名、3 年以上が 1 名であった。受傷起点は「タックルを受ける」
6 例、「タックルに入る」7 例であった。受傷原因は「地面に強打」7 例、「味方の頭同士の衝突」
2 例、「相手の膝、大腿部に強打」2 例、「相手の頭と衝突」2 例であった。受傷部位は右側頭部
4 例、右前頭部 2 例、後頭部 4 例、頚部 2 例、左側頭部 1 例であった。傷病名は脳振盪 6 例(重
複傷病名 4 例を含む)、頚髄損傷、脊髄振盪(重複傷病名 2 例を含む)、頭部打撲(重複傷病名
2 例を含む)が 3 例、急性硬膜下血腫、脳挫傷、外傷性くも膜下出血、外傷性硬膜外血腫、頭
部外傷Ⅰ型、外傷性頭痛、頚椎損傷、頚椎挫傷、各 1 例であった。
「調査結果一覧」から判るとおり、各事例とも 10 年以上の指導経験を持つ指導者がほとんど
であり、その多くが日々の練習に頚部周辺の筋力トレーニングを取り入れ、正しいタックルの
入り方やタックルを受けた際の転び方も指導していることがわかった。また 2 人の初心者以外
は皆 1 年以上の経験者であり、グラウンド状況も良好であった。このような状況でも事故が発
生するのは、指導者や生徒の注意だけでは防ぎきれない不可抗力による事例もある一方、生徒
の技術理解度や習得度にも問題があることが伺えた。コンタクト時の姿勢やタックルの入り方、
倒れ方の習得にはさらに時間をかけて指導することが重要である。特に逆ヘッドタックルは頭
頚部への外傷の危険性が高いため、指導者は練習、試合を通して逆ヘッドタックルをさせない
よう厳しく指導する必要がある。
2.タックルに入る
練習/試合グランド
状況指導歴 指導内容
経験年数
傷病名 受傷状況 受傷要因
事例7 練習試合 人工芝 5年日頃から首のトレーニング
2年脳挫傷脳振盪
タックルに入った際相手に弾き飛ばされ後頭部を地面に強打。
タックル姿勢が高かったのとしっかりしたバインドができなかった 倒れた際受け身姿勢がとれなかった。
事例8 試合 良好35年12年
1年8ヶ月
頭と首を守るような転び方の練習
1年以上急性硬膜下血腫頭部打撲
2人で同じ相手にタックルに入り味方の頭部が右前頭部に衝突。
お互いに気付かなかった。
事例9 ミニゲーム 土21年1年
コンタクト練習(タックル、スクラム)は指導者立会いのもと
初心者 脳振盪タックルに入り相手大腿部が右側頭部を強打。
逆ヘッドタックル(頭部が臀部ではなく相手進行方向前方に来るタックル)
事例10 試合整備され
た土27年
日常的に首、体幹トレーニング、タックル、転び方の練習
1年以上脳振盪頭部打撲外傷性頭痛
タックルに入り相手膝が右側頭部を強打。
逆ヘッドタックル(頭部が臀部ではなく相手進行方向前方に来るタックル)
事例11 試合整備され
た芝
25年
9年
頭を下げない、胸を張る、腕を前に出す、飛
び込まない等に気を付けタックル指導
1年以上 頚椎損傷
右肩でタックルに入り右前
方より来た相手の頭と右側頭部が衝突。
タックル姿勢が高いうえ逆
ヘッドタックルになった。
事例12 試合 人工芝 18年1人1日1試合と決めて無理をさせない。
1年以上脊髄振盪頚髄損傷
相手選手にタックルに入ったところ、別の相手選手がタックルに入り首、肩付近を強打。
相手選手がタックルを剥がそうとした行為によるものでラック形成時やモール形成時に起こる衝突。
事例13 試合 人工芝 10年以上
ウエイトトレーニング、準備運動、整理運動時に首のトレーニング首が太くなったら試合に出させる。
1年以上 外傷性硬膜外血腫2人でタックルに入り味方の頭部が右前頭部に衝突。
お互いに気付かなかった。
36 37
第2編
第3章

38
Ⅱ 柔道
東京都教職員研修センター 教授 佐藤 幸夫
東京都立井草高等学校 教諭 柳浦 康宏
柔道については、平成 10 年度~平成 23 年度の死亡・重度の障害事故は 54 件であるが、P33
表 2-2-21「体育活動による頭頚部の死亡・重度の障害事故の原因一覧」をみると「投げられる」
が 44 件、投げの動作の途中に自ら体勢を崩すなど「動作が不完全」が 10 件と投げに係る事故
が多い。
さらに、発生時の動作・技の内訳をみると、大外刈り 12 件、払い腰 7 件、背負い投げ 6 件、
受け身練習 4 件、寝技 2 件、その他投げ技 13 件、乱取り 10 件で投げによるものが多い。
また、投げられた際に安全に身を処するためには, 相手の投げ技と結び付け場面に対応して
受け身がとれるようにすることが大切である。
このため、最近の柔道による負傷事例から「受け身」に係る案件を抽出し、調査を行った。
[調査結果一覧]
1 投げられたとき安全な受身をとれなかった(とらなかった)ために負傷した例
【高等学校】
授業/部活動受傷者
経験・身体能力等相手
経験・身体能力等傷病名 受傷状況 受傷要因
事例1 授業
初心者
(授業30時間目)(57.4kg・1年男)
初心者
(同程度の身体能力)
頸椎捻挫
練習試合中、背負い投げで投げら
れ、前回り受け身がとれず頭から落ちた。
・「取」が投げた時、引き手を引かず投
げっぱなしになった。・「受」は、前回り受け身が十分身に付
いていないため受け身をとれなかった。
事例2 授業
初心者(中高での授業経
験)(51kg・2年男)
柔道部員
(5年)(92.5kg)
頸椎損傷
技のテスト中、体落としで投げられ受け身をとろうとしたが、技の
スピードに追い付けず首、肩から落ちた。
・体格や体力、技能に優る「取」が、「受」の力量に配慮せずに投げた。
・「受」は、相手の技のスピードが速く、体が硬直し受け身が遅れた。
事例3 部活動
有段者(6年)
インターハイベスト16
(52kg・3年女)
有段者レギュラー選手
(61kg)
右後頭部打撲傷後頭部外傷
頸椎捻挫
払い腰の約束練習で、投げられるタイミングがずれて右後頭部から
落ち、首をひねった。
・「取」が不十分な崩しで深く技に入
り、技の掛け方を失敗してしまったのに、投げの動作を止めず、そのまま投げた。
事例4 部活動
初段
(3年)(58kg・1年女)
初段(58kg)
頭部打撲
脳震盪見当識障害
県大会(個人戦)で右払い腰をかけられ、そのまま巻き込まれて右肩から右側頭部にかけて畳に打っ
た。
・「取」が、崩し、体さばきが不十分なまま巻き込みに連絡し同体で倒れた。・「受」が、試合での勝敗にこだわり、
受け身を正しくとらなかった。
【中学校】
事例5 授業
初心者
(身体能力低)(授業3時間目)
(51kg・1年男)
初心者(身体能力高)
急性硬膜外血腫背負い投げの約束練習で投げられる途中、一瞬くらっとして受身が
とれず頭を打った。
・「取」は、相手の力量に応じた技のか
け方ができなかった。・「受」は、前回り受け身が十分身に付
いていないため受け身をとれなかった。
事例6 部活動
無段者
(1年以上)(46.6kg・2年男)
高段者
(6段以上)(90kg)
頭部打撲外傷性健忘
頸部挫傷胸腰部挫傷
過換気症候群
自由練習(乱取り)で、小内巻き
込みをかけたところを返され、頭と背中から落ちた。
・体格や体力、技能に優る「取」が、「受」の力量に配慮せずに投げた。・「受」は、相手の技の変化に対応する
受身ができなかった。
事例7 部活動
初心者
(1ヶ月半)(43kg・1年男)
無段者
(2年)(78kg)
頭部打撲脳挫傷疑い
自由練習(乱取り)で大内刈りを
かけられ、そのまま押し倒され同体で倒れ頭を打った。
・お互いに柔道衣を持ったまま、同体で倒れたため受け身が取れなかった。
・技のスピードはそれほどなかったが、体格差のある大きな者が体を浴びせて同
体で倒れた。
事例8 部活動初心者
(2ヶ月弱)
(46.5kg・1年男)
初心者(2ヶ月弱)
(59.6kg)
頭部外傷自由練習(乱取り)で巴投げをかけられ、正しい対応や受身ができ
なかった。
・まだ指導されていなかった巴投げを、興味本位に突発的に掛けた。・両者共に正しい投げ方、受け身の仕方
を知らず、「取」は両腕を掴んだまま投げ、「受」は手を打つことも受け身の体
勢をとることもできなかった。
38 39
第2編
第3章

39
[事故発生の要因] 1 柔道競技における頭頚部外傷事故発生の要因(調査結果のまとめ)
柔道の負傷には、投げられたとき「受」が安全な受け身をとれなかった場合、「取」が正しい
技を施せなかったり相手の変化する技や体さばきに対応できず自ら負傷する場合、他の練習者や
周囲との衝突による場合などがある。いずれも、発生要因の強度や頻度が限界を超えたときは単
一の要因でも起こり得るが、要因が重なりあい複雑に絡み合ったときはその可能性がより高くな
る。
(1)投げられたとき、安全な受け身をとれなかった(とらなかった)ために負傷するケース
頭頚部の負傷で最も多く、頭部打撲による硬膜下血腫の発症など、死亡や重度障害事故に
つながりやすい(P33 表2-2-21)。その要因は受け身の未熟や技の失敗によるが、体格や体
力、技能に優る「取」が「受」の力量に配慮せず投げたときが多い。特に、体さばきや崩し
が不十分なまま強引に巻き込むなどの技をかけたとき、受け身をとれずに負傷することが多
い。また、投げられまいとして腰を引き、腕を突っ張るなどの極端な防御姿勢や投げられた
とき潔く受け身をとらないで相手にしがみついたり、ぶら下がったりして負傷する場合など
がある。
(2)正しい技を施せなかったり、相手の変化する技や体さばきに対応できずに自ら負傷するケー
ス
試合や自由練習(乱取り)では、攻撃と防御を一体として行う。互いに攻防する中で、「取」
が技のかけ方に失敗して自ら負傷したり、相手の返し技などの変化に対応できずに負傷する
こともある。
(3)他の練習者や周囲との衝突によるケース
大勢が同時に練習するとき、十分なスペースを確保しなかったり、周囲への配慮を怠ると、
練習者同士による衝突によって負傷することがある。その際、投げられた練習者の足が他に
【高等学校】
授業/部活動受傷者
経験・身体能力等相手
経験・身体能力等傷病名 受傷状況 受傷要因
事例9 授業
初心者
(授業6時間目)(58.5kg・1年男)
初心者(61kg)
頭部外傷
固め技の自由練習中、片膝立ち姿
勢から抑え込みに入ろうとして相手の膝で頭を打った。
・抑え込みに入る手順を踏まず、相手をよく見ないまま抑え込もうとした。
【中学校】
事例10 授業
初心者
(陸上部員)(授業3時間目)
(49.4kg・1年女)
単独練習のため相手はいない
頸椎捻挫頭部打撲
3回目の授業で、後ろ受け身の単
独練習を何度か行ったあとで(この日は数十回練習)左後頭部に痛
みを感じた。
・受け身の際、手を打つタイミングが若
干遅かった。・後ろに倒れるときのあごの引き方が十
分でなかった。
【高等学校】
事例11 部活動
有段者
(4年)(66.2kg・1年男)
柔道部員(69.3kg)
頭部打撲脳震盪
投げ技の自由練習(乱取り)中、投げられて受け身をしたところに、別のペアで投げられた部員の
後頭部が衝突した。
・複数が同時練習するために必要なスペースが不足していた。・投げられ倒れている部員に向かって、
投げてしまった。
【中学校】
事例12 授業初心者
(身体能力高)
(48kg・1年女)
同程度の体格頸椎捻挫頭部打撲
膝たち状態で組み合い、崩して抑
え込み技へ移る簡易な試合をしていた時、後方に倒され、別のペア
の頭(頭頂部)と衝突した。
・複数が同時練習するために必要なスペースが不足していた。
2 正しい技を施せなかったり、相手の変化する技や体さばきに対応できず自ら負傷した例
3 他の練習者や周囲との衝突により負傷した例
38 39
第2編
第3章

40
当たるいわゆる「投げ足」がもっとも危険である。また、壁や柱など周囲の突起物との衝突
も考えられる。
2 活動別の発生要因について
(1)授業における発生要因
柔道はほとんどの生徒が中学校で初めて学習する種目であり、指導時間も限られているの
で、基本動作や基本的な技を用いた初歩的な攻防を主とした学習が多い。こうした学習活動
では、とかくケガや事故は起きにくいと考えがちだが、それでも重度の障害事故は5件発生し
ている(P28 表2-2-13)。
生徒の多くはこれまでの運動経験から、受け身につながる安全な倒れ方が身に付いていな
い。また、授業では、極端な体力不足や運動の苦手な生徒、初めての種目に期待をしている
生徒や柔道経験のある生徒など、体力や技能差だけでなく、学習意欲の異なる生徒が一緒に
学習する。授業では、こうした生徒の実態に配慮した段階的指導および、体格や運動能力の
違いへの配慮が欠かせない。
(2)部活動における発生要因
死亡や重度の障害事故のほとんどが部活動中に発生し、中でも、中学1年と高校1年の初心
者の受傷が多い(P28 表2-2-13、P29 表2-2-15)。部活動は、学年やクラスの枠を越えて同
好の士が集い、互いに教え合い学び合うことに意義がある。一方部活動の練習では、対外試
合を目指すなど高度な技能レベルで激しい練習が行われることが多い。その際、体格や体力、
技能に優る者が相手への配慮を忘れた激しい練習を行うことが最大の要因であると考えら
れる。
3 まとめ
柔道における負傷は、崩しや体さばきが不十分なまま強引な技をかけたり、受け身が未熟な
場合に起きやすく、その原因は投げる側、投げられる側双方にある。特に、頭頚部負傷による
死亡や重度の障害事故は、中学校や高等学校における部活動において発生頻度が高く、その対
策が重要になる。
40 41
第2編
第3章

41
Ⅲ 野球
公益財団法人日本高等学校野球連盟 理事 田名部 和裕
野球については、平成 10 年度~平成 23 年度の死亡・重度の障害事故は 4 件であるが、表 9
-1「体育活動による頭頚部の死亡・重度の障害事故の原因一覧」(P33 表 2-2-21「体育活動に
よる頭頚部の死亡・重度の障害事故の原因一覧」参照)をみると「ボールと衝突」が 3 件、「人
と衝突・接触」が 1 件と「ボールと衝突」が多く、ボールが当たる事故が多い。
さらに、発生時の動作の内訳をみると、内野手がボールに当たる 2 件、投手がボールに当た
る 1 件、ヘッドスライディングで野手と衝突 1 件であった。
また、死亡・重度の障害事故には至らないケガの発生原因をみると、「ボールと接触」が約
3/4 を占めており(P17 表 2-1-7「競技別・原因別 発生件数」参照)、頭頚部のけがの 99%以
上が運動部活動で起きている(P11 表 2-1-1「活動別・競技別・頭頚部別」参照)。このため、
最近の運動部活動の野球による負傷事例から「ボール・当たる」に係る案件を抽出し、調査を
行った。
[調査結果一覧]
1 打球による事故
【高等学校(硬式球)】
練習/試合 指導歴 受傷者 経験年数 傷病名 受傷状況 受傷要因
事例1 練習15年20年
打撃投手
軟式3年硬式7ヵ月
頭部打撲、脳挫傷、顔面骨骨折、眼球打撲傷、嘔吐症、急性呼吸不全、頭蓋骨多発骨折、右眼瞼外傷性腫脹、頭蓋内に達する創合併、気脳症、右眼球打撲傷、右虹彩炎、右眼瞼炎
3ヵ所の打撃練習で、隣の打者の打球が投手の顔面を直撃した。ヘッドギアは装着していた。
防護ネットの不備と時間差打撃の徹底が不十分。
事例2 練習12年14年
打撃投手
4年以上外傷性脳出血頭蓋骨骨折脳挫傷
短い距離から投げていた打撃投手が着用していた打者用ヘルメットがずれて、右側頭部に打球が当たる。
防護用具(投手用ヘッドギア)の未使用と投球後ネットに隠れる動作が不十分。
事例3 練習 5年打撃投手
6年以上急性硬膜外血腫頭蓋骨骨折
打撃投手が打者の打球を頭部に受ける。ヘッドギアは装着。
投球後ネットに隠れる動作が不十分。
事例4 練習 3年打撃投手
4年以上外傷性くも膜下出血前頭骨陥没骨折
打球が防護ネットの端に当たり方向が変わり投手のヘルメットの下方から額に当たった。
打球が防護ネットの端に当たって方向が急変化したもので不可避の事故と思われる。投手用ヘッドギア未使用。
事例5 練習 31年マシン補球者
5年以上外傷性くも膜下出血頭蓋骨陥没骨折
打球がマシン用ネットの送球穴から飛び込みバッティングマシンの補球者の額に当たった。
捕球者は投手用ヘッドギアをしていたが、キャッチャー面の装着はなかった。
事例6 試合 12年ベンチの
選手2年以上
外傷性脳挫傷頭蓋骨骨折左片麻痺
練習試合で3塁側ベンチで応援をしていた部員の右側頭部にファウルボールが当たった。
ベンチ前にはネットが設置されていたが、ネットの外側に座っていたため打球がよけられなかった。
事例7 自由時間 10年 投手 2年以上頭蓋骨陥没骨折硬膜外血腫脳挫傷
練習後、室内練習場で打撃のまねごとをしていたところ、誤って投手役の部員にライナーを打ち返し側頭部に当たった。
投手用ヘッドギアの装着もなく、緩慢なプレイで発生したと思われる。
事例8 練習 30年ボールひろい
2年以上
左側頭部打撲傷慢性硬膜血腫の疑い脳挫傷頭蓋骨骨折
打撃練習で外野を守っていた部員がネット脇のボールを拾っていたところ打球がこめかみに当たった。
打撃練習中で、次の打球が飛んでくることに注意ができなかった。
事例9 練習 10年 一塁手 7年脳振盪後頭部打撲傷
守備練習で1塁手が、ノックの打球がイレギュラーし、避けられず後頭部に当たった。
グラウンドが整備されていなかったことによるが、常に整備するのは難しい。
40 41
第2編
第3章

42
[事故発生の要因]
今回報告された野球の部活動における事故例は、12例中 10例が高校で、2 例が中学校で
発生していた。高校はすべて硬式野球で、中学校では軟式と準硬式が 1例ずつだった。
事故例の内 10例は練習中で、試合中及び試合前の守備練習が 2例だった。試合ではボー
ルが一つでプレーされるため全員が注視していることから事故は少ない。今回、試合中の
ファールボールがベンチにいた生徒に当たった事故では、ベンチの位置が打者から余り離
れておらず、しかも防護ネットがない場所で当たっている。近年ではコーチャーズボック
スにいるコーチャーもヘルメットを義務付けていることから、打者との距離がない場合は
グラブを持たせるなど、十分な注意が必要であろう。
次に試合前のノック中の送球がそれて、水撒きをしていた生徒に当たったケースでは、
当然送球がそれることは往々にしてあることから、ヘルメットを着用させるなり、1塁手
の後ろに補助員を配置するなどの対策が必要である。
一方、練習中の事故は、7例が打撃練習中で、6例が打撃投手ないしマシンのボール捕球
担当者だった。一般にも打撃練習中の事故発生が顕著であることから、防護ネットの設置
だけでなく練習方法の工夫も必要となる。
このうち 1例は打撃投手が着用していた打者用ヘルメットがずれて打球を頭部に受けた
ケースだが、投手用ヘッドギアを使用しなかった誤使用が要因とされる。投手用ヘッドギ
アは装着ベルトで絞めつけ、固定するようになっているので、このような事故にはならな
い。また、投球後、打球を捕球しようとせず、しっかりL字型ネットの陰に隠れる習慣を
つける指導が望まれる。
このほか打撃投手が隣の打者の打球を受けた事故例が報告されているが、複数個所で打
撃練習を実施する場合は、防護ネットの設置に留意するとともに、すべての打球に注視す
るため、時間差を設けて打撃する工夫が必要である。
マシンにボールを補給していた部員に、ネットの打ち出し穴から打球が打ち返されてき
た事例は、常々起こりうる。補給者をネットで囲うマシン用ネットが市販されているので
活用して欲しい。しかし、専用ネットがなければ、報告された事後措置のようにマスクを
装着させるなどの指導が必要となろう。
2 送球による事故
【高等学校(硬式球)】
練習/試合 指導歴 受傷者 経験年数 傷病名 受傷状況 受傷要因
事例10 試合前11年2年3年
水撒き 5年以上外傷性硬膜外血腫脳挫傷
試合前にファウルテリトリーで水撒きをしていた部員に1塁への送球がそれて右側頭部に当たった。
グラウンドで行われているプレイを見ていなかったこともあるが、ヘルメットの着用や補助員を配置していなかった。
【中学校(準硬式球)】
事例11 練習5年2年6年
遊撃手 初心者 前頭骨陥没骨折
守備練習で遊撃手が外野手からの送球を中継するときに送球を見失い、前頭部に送球を受けた。
次の送球を考え、投げられた送球から目を切ってしまったことによると思われる。
3 投球による事故
【中学校(軟式球)】
事例12 練習 20年 捕手 2年以上頭部外傷右頚部血腫右外傷性血腫
投球練習の捕手が、手前でバウンドした投球を右頚部に受ける。
捕手の捕球技術の不足。
※ 全て部活動の事例
42 43
第2編
第3章

43
一方、守備練習中の事故例で、内野手がノックの打球がイレギュラーしたため、頭部に
打球を受け、脳振盪を起こしたケースでは、グラウンドの整備不良が要因となっているが、
守備練習前や可能な限りその合間でもグラウンドを整備する注意を喚起したい。
もう一つの守備練習中の事故で、外野からの中継プレーで送球を見失ったケースは、次
のプレーを焦る余り送球から目を切ってしまい負傷するケースで、しっかり捕球してから
次のプレーに移るよう指導をして欲しい。
以上の事故例で、高校 1年生が 7例、2 年生が 2例、3 年生が 1例報告されているが、1、
2 年生の役割り作業中起きた事例と思われる。不慣れというよりその役割をこなすのに夢
中で、周囲に対する警戒が十分ではない状況下で起きたと思われる。いずれの場合もチー
ム全体でこうした生徒への配慮をする習慣を身につけて欲しい。
42 43
第2編
第3章

44
Ⅳ サッカー
東京慈恵会医科大学附属病院脳神経外科 医局長 大橋 洋輝
サッカーについては、平成 10 年度~平成 23 年度の死亡・重度の障害事故は 3 件であるが、
「体育活動による頭頚部の死亡・重度の障害事故の原因一覧」(P33 表 2-2-21)をみると「人
と衝突・接触」2 件、「施設と衝突」1 件があり、生徒同士がぶつかる事故が多い。
さらに、発生の動作の内訳をみるとボールの取り合いで相手と衝突 2 件で、他の 1 件は活動
終了時のクールダウンをプールで行った際の事故である。
また、死亡・重度の障害事故には至らないケガの発生原因は「人と衝突・接触」に続いて「ボー
ルや設備と接触」が多い(P17 表 2-1-7「競技別・要因別」参照)。
このため、最近のサッカーによる負傷事例から「ボールの取り合い・ヘディング・シュート・
ゴール」に係る案件を抽出し、調査を行った。
[調査結果一覧]
1 相手との直接の衝突により受傷
【高等学校】
授業/部活動練習/試合
フイールド状況
指導歴 経験年数 傷病名 受傷状況 受傷要因
事例1部活動
練習試合乾いて固い
30年 4年以上頭部外傷脳振盪
練習試合中、FWで相手ゴール向きに体を反らすように後ろ向きにヘディングをしようと、ハイボールに対し飛び込んだところ相手の頭頂部が後頭部に当たった。
本人も相手もボールを見ているため、お互いの正確な位置を把握していない。
事例2部活動
練習試合人工芝
24年13年33年
10年
外傷性健忘頭部外傷外傷性頚部症候群脳振盪
ヘディングの競り合いをし、相手選手の肘が側頭部にぶつかり、転倒、意識を失い痙攣を起こす。
本人も相手もボールを見ているため、お互いの正確な位置を把握していない。
事例3体育授業
試合
土(整備され
ている)
31年 6年以上脳振盪側頭部打撲
ゲーム中、ドリブルでゴールに向かっている生徒にボールを奪いに後方から接触した際、相手が振り払おうとした肘が顎と胸付近に当たる。
相手の動作を把握できず防御姿勢をとれない。
事例4部活動練習
土(整備され
ている)
10年 2年以上 側頭部打撲傷
ゴール5m手前あたりで1対1の競り合いの中、止まっていた状態からダッシュした途端に地面につまづき、バランスを崩して相手と接触。
相手の動作を把握できず防御姿勢をとれない。
【中学校】
事例5部活動
練習試合
土(整備され
ている)
3年1ヶ月不明
2年以上頭部打撲頭部外傷2型頚椎捻挫
キーパーの本生徒がペナルティエリア外で、ヘディングでクリアしようとした瞬間相手方付近と前頭部が衝突。
相手の動作を把握できず防御姿勢をとれない。
事例6部活動練習
降雨後でぬかるんでいた
9年 5年 脳挫傷
コーナーキックからのセットプレーの練習中、ヘディング時に左斜め後方からのヘディングとぶつかる。
相手の動作を把握できず防御姿勢をとれない。
事例7部活動
練習試合
土(整備され
ている)
9年 1年以上左側頭部打撲傷頚椎捻挫
キーパーをしていてシュートを止めて横になったとき、こぼれ球をシュートしようとした選手の足が頭に当たる。
お互いの正確な位置を把握していない。
44 45
第2編
第3章

45
[事故発生の要因]
サッカーはボールを頭で打ち返すヘディングというプレーが可能であるため、ボールによる
直達の衝撃で受傷することもみられる。しかしそれよりもコンタクトスポーツであるが故に、
ボールを相手と競って奪う場面で接触し受傷する場合や、相手と接触後転倒して地面に頭部を
打撲する場合が多い。第1章の P17 表 2-1-7 によると「人と衝突・接触」だけで事故原因の約
7 割に達することが分かる。これらのことから調査結果をもとに事故発生要因をまとめた。
1 相手との直接の衝突により受傷
事例として多いのはヘディングをする際に相手と衝突して受傷する場合である。調査結果一
覧の表の内、事例 1、2、5、6 がこれに該当する。本人はボールをヘディングしようと、ボール
に対して頭から飛び込んでいる状態であり、同様にほぼ同じタイミングで競ってきた相手と頭
同士で衝突する場合や肘などの他の部位が衝突する場合がみられる。ヘディングでの衝突は 3
つの理由で大きな事故の原因となる可能性がある。まず 1 つはボールをなるべく高い地点で強
く打ち返そうとするため、勢いをつけて飛ぼうとし、衝突の際のエネルギーが高いことが考え
られる。2 つめには本人も相手もボールを見ているため、お互いの正確な位置を把握していな
い場合が多い。特に受傷する側はやや先に飛んでいて、相手の動作を把握できず防御姿勢をと
れないこともあり得る。3 つめには空中での衝突であり、一旦勢いよく飛んでしまうと姿勢制
御できないことにある。
ヘディングの場面以外では、ゴール前で相手の膝が頭部に当たることや、ゴールキーパーが
シュートを止めて横になった際に、こぼれ球をシュートしようとした相手に頭を蹴られるなど、
ゴールに絡む場面での受傷がみられる。その他では、ドリブル中に競り合い相手の肘が頭部に
入って受傷する、ややラフプレーとも考えられる状況で受傷する場合もみられる。
2 相手との接触後、転倒して地面に衝突し受傷
表の事例 10 のようにヘディング時に空中で相手と接触したため、バランスを崩して転倒し地
面に衝突するケースがみられる。これもヘディング時の衝突として、先に述べた理由から受傷
要因として起こりうる。また同様にゴール前の激しいプレーでゴールキーパーが相手と接触後
2 相手との接触後、転倒して地面に衝突し受傷
【高等学校】
授業/部活動練習/試合
フイールド状況
指導歴 経験年数 傷病名 受傷状況 受傷要因
事例8部活動練習
乾いた土(整備され
ていて固く
ない)
30年以上 5年頭部外傷2型意識障害脳振盪
ボールの取り合いで激しく接触後、後ろ向きに転倒し地面で後頭部を強打。
相手の動作を把握できず防御姿勢をとれない。
【中学校】
事例9体育授業
試合
土(整備され
ている)
30年 初心者脳振盪頭部打撲
ゴールキーパーでディフェンダーとの間に出されたクロスボールをカットするために飛び出し、相手と衝突・転倒、頭部を打つ。
相手の動作を把握できず防御姿勢をとれない。
事例10部活動試合
学校運動場(固め)
20年以上 7年脳振盪頭蓋内に達する開放創合併なし
ロングボールを相手選手とヘディングで競り合い、バランスを崩し、肩・後頭部から落下。
相手の動作を把握できず防御姿勢をとれない。
事例11体育授業
試合
土(整備され
ている)
7年 2年以上頭部外傷2型脳振盪
(ゴール前での攻防)ドリブルからシュートをしようとして接触、地面に転倒。
お互いの正確な位置を把握していない。
44 45
第2編
第3章

46
転倒することや、ボールの取り合い、シュートの場面で相手ともつれ合い転倒して受傷する場
合が多い。得点に絡む場面は攻撃側も守備側も特に激しくなるため、衝突するエネルギーが高
く、バランスを崩して頭部を受傷してしまうことが多いと思われる。
3 まとめ
今回抽出した事例の中では環境の要因や指導・管理の要因はほとんどみられず、サッカー競
技の特性上みられる方法の要因が多かった。技術不足やラフプレーなどの個体の要因もみられ
るが、やはりゴール前やヘディングにかかわるプレーで直接衝突し受傷する場合と、競って転
倒し地面に頭部を打撲し受傷する場合が特に多いことが分かった。
46 47
第2編
第3章

47
第4章 判例から見る体育活動中の事故の特徴と予防の課題 日本スポーツ法学会事故判例研究専門委員会 委員長 望月 浩一郎
平成 23 年までに公刊集に判例が掲載されたスポーツ事故は 527 (一部未掲載を含む)件であ
る。1 つの事故が上級審でも審理されているケースもあり、527 の一審判決件以外に 74 の高裁
判決、20 の最高裁判決があり、判決の総数は 621 となる。
スポーツ事故判例の内、競技スポーツでの事故は 436 件ある。競技別の事故数は、野球が 36
件(第 3 位)、柔道が 21 件(第 6 位)、サッカーが 17 件(第 10 位)、ラグビーが 14 件(第 12 位)
となっている(グラフ)。
この 4 競技のスポーツ事故判例の中で頭頚部外傷の事故が占める割合は表のとおりである。
野球とサッカーは、頚部外傷の判例はないが、頭部外傷は野球が 20 件(56%)、サッカーが 6
件(35%)である。この 2 競技の頭部外傷の特徴は、その約半数が眼の負傷であり、ボールが眼に
当たったことが原因となっている。
柔道とラグビーは、頭部外傷と頚部外傷が共に生じているが、柔道で頭部外傷が 14 件と全体
の 3 分の 2 を占め、一方ラグビーでは頚部外傷が 8 件と全体の約 6 割を占めているのが特徴で
ある。
野球での頭部外傷事故の要因は、①バットが当たった事故が 3 件、②投球が当たった事故が
3 件、③打球が当たった事故が 13 件、④捕球をしようとした野手どうしの衝突事故が 1 件であ
る。
バットが当たった 3 件の事故は、周囲に人がいる場所でのスイング、バットの放てきが要因
となっている。バットを振る時には、周囲の安全性を確認し、バットの放てきという危険性の
ある行為を行わないことが必要である。
投球が当たった 3 件の事故は、いずれも練習中の事故である。被災者は、遊んでいた幼児、
他の練習メニューに参加していた野球部員、捕球体制を整えていない捕手(ピッチングマシンの
ボール)であり、当該ボールを注視していない者にボールが当たった事故である。ボールを投げ
水泳, 88, 20%
ウインタースポー
ツ, 37, 8%
野球外, 36, 8%
ゴルフ, 34, 8%
登山外, 30, 7%柔道, 21, 5%
陸上, 20, 5%
スキューバ・ダイ
ビング外, 20, 5%
運動会等, 18, 4%
サッカー, 17, 4%
ボート外, 16, 4%
ラグビー, 14, 3%
その他, 85, 19%
図 2-4-1 競技スポーツ事故判例
46 47
第2編
第4章

48
る場合には、捕球する者の用意ができていることを確認し、ボールが届くところに当該ボール
を注視していない者がいないことを確認することが必要である。
表 2-4-1 競技別スポーツ事故判決
野球 柔道 サッカー ラグビー
全判決 36 件 21 件 17 件 14 件
頭部負傷事故 20 件 56% 14 件 67% 6 件 35% 1 件 7%
(眼の負傷) (12 件 33%) (0件 0%) (3件 18%) (1件 7%)
頚部負傷事故 0件 0% 4 件 19% 0 件 0% 8 件 57%
頭頚部以外 16 件 44% 3 件 14% 11 件 65% 5 件 36%
打球が当たった 13 件の事故は、①他のクラブ活動に参加していた生徒やスタンドで試合を観
戦していた者などのボールに注視していない者に打球が当たった事故が 5 件、②トスバッティ
ング(ティーバッティング)でバッターに斜め前方からボールをあげる者(トサー)に打球があ
たった事故が 3 件、③ピッチングマシンでボールを入れる者に打球が当たった事故(防球ネット
の損傷箇所を打球が通過)が 1 件、④ハーフバッティング練習で投手に打球が当たった事故が 2
件、⑤マスクを着用しないキャッチャーや審判の事故が 2 件となっている。
マスクの着用、防球ネットの補修など、安全のための用具の整備と使用を徹底することが必
要である。
バッティング練習においては、打球が届くところに、当該ボールを注視していない者がいな
いことを確認する必要がある。
複数のバッティング練習を同時に行う場合には、投手を守るために、
① 投手がいる場所には、他の打者からの打球が 100%止めることができる位置に防球ネット
を設置すること
② 投手が対面している打者の打球が、投球を終えた投手に当たらないように防球ネットを
設置しなければならない。打球が、防球ネットのポールなどに当たってコースを変えた場
合でも投手が投球を終えた位置にはボールがこないように防球ネットを配置すること
が必要である。
トスバッティングでは、トサーに打球が当たらないようにトスを上げることや防球ネットの
使用が必要である。
野手同士の衝突を防ぐためには、打球を捕球する者を特定するために、必ず声かけを行うこ
ととする必要がある。
柔道の頭部外傷の 14 事故の要因は、全件において技量の高い者(指導者、段位を有する上級
生、柔道部員)が、技量の低い者(初心者、柔道の授業に参加している一般生徒など)を投げて生
じており、投げ技をかける者とかけられた者との技量の差が要因となっている。さらに、連続
して投げられていること、投げられる者が意識障害が生じても投げ続けていること、投げ技の
種類が危険性の高い技であったことも要因となっている。
頚部損傷の 4 件の内 3 件も技量の差が要因となっている。1 件は上級者どうしであったが、
負傷した者は柔道からしばらく離れていたという要因があった。
技量の差がある場合で、技量の高い者が投げ技をかける場合には、投げられる者が十分な受
け身を取れる配慮が必要である。頭を打たなくても、頭部に回転加速度が加わることでも頭部
外傷は生じるため、スピードのある切れの良い投げ技の危険性を知っておくことも重要である。
48 49
第2編
第4章

49
サッカーでの頭部外傷 6 件の内 3 件は、小学校におけるサッカーボールが眼にあたっての負
傷である。小学校でのボールゲームには柔らかいボールで必ずしも空気圧が高い状態でないも
のが用いられていることが少なくないが、このような柔らかいボールが事故の原因であると指
摘する意見もある。事故の予防という点から、小学校で用いるのに適切なボールのありかたに
ついての検証が期待される。その他の 3 件は、いずれもゴールポストやクロスバーに衝突した
事故であり、内 2 件はゴールが倒れての事故である。サッカーやハンドボールのゴール、野球
における防球ネットや移動式バックネットが倒れて生じている事故は繰り返し生じており、事
故の予防の視点から、�倒の��性がある用�の使用�������を事�に��ておくことが
必要である。国際サッカー連盟は、競技規則において「ゴールポストとクロスバーは、木材、
金属またはその他の承認された材質」であることを要求している。しかし、学校教育において
使用されるサッカーゴールでは、安全性を重視し、バスの車内の鉄柱に緩衝材が巻かれている
ように、ゴールポストに衝突した際の事故を防ぐ配慮も検討する必要がある。
ラグビーでの頭部外傷 1 事故は、中学校の授業でのトライボールで生徒どうしが衝突して眼
を負傷したものである。頚部外傷 8 事故は、いずれも高校における事故であり、2 件が体育の
授業中、6 件がクラブ活動中である。スクラムを組む時の事故が 2 件、タックルでの事故が 2
件、モールでの事故が 3 件、1 件が事故態様不明となっている。
モール事故のようにすでにルール改正により予防措置が講じられているものもあるが、個々
の事故要因を分析して予防の措置を講じることが必要である。
48 49
第2編
第4章

50
50 51