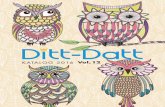民間教育訓練機関の役割と職業訓練 サービスの質の確保・向 …平成30年度は129,761人に訓練を実施。約75%は民間教育訓練機関により実施。6
第2版 - 練上手・練り込み陶芸入門1 はじめに (第2版 序)...
Transcript of 第2版 - 練上手・練り込み陶芸入門1 はじめに (第2版 序)...

1白根開善学校 美術同好会
練り込み
陶芸入門
第2版

2
練り込み陶芸入門 CONTENTS
はじめに(第 2版 序)
1. 陶芸の基礎知識
1-1 やきものができるまで
1-2 粘土について
1-3 道 具
1-4 土練り
荒練り
菊練り
1-5 成形について
手びねり
ひもづくり
タタラづくり
ロクロ成形
1-6 釉薬について
1-7 窯について
2. 練込み基本テクニック
2-1 色粘土をつくる
2-2 色見本をつくろう
2-3 マーブル模様
2-4 ストライプ模様
3. 練込み応用テクニック
3-1 ストライプ模様の花入れ
3-2 市松模様の角皿
3-3 クマの顔をつくる
3-4 「嘯裂文」の壺をつくる
3-5 オリジナル模様の角瓶
3-6 くず粘土の利用
3-7 練り込み作品集
編集後記
‥‥‥‥‥ 1
‥‥‥‥‥ 2
‥‥‥‥‥ 3
‥‥‥‥‥ 4
‥‥‥‥‥ 6
‥‥‥‥‥ 8
‥‥‥‥‥ 8
‥‥‥‥‥ 9
‥‥‥‥‥ 10
‥‥‥‥‥ 10
‥‥‥‥‥ 11
‥‥‥‥‥ 12
‥‥‥‥‥ 14
‥‥‥‥‥ 16
‥‥‥‥‥ 19
‥‥‥‥‥ 20
‥‥‥‥‥ 21
‥‥‥‥‥ 24
‥‥‥‥‥ 27
‥‥‥‥‥ 30
‥‥‥‥‥ 32
‥‥‥‥‥ 33
‥‥‥‥‥ 35
‥‥‥‥‥ 37
‥‥‥‥‥ 40
‥‥‥‥‥ 42
‥‥‥‥‥ 45
‥‥‥‥‥ 46
‥‥‥‥‥ 47

1
はじめに ( 第2版 序 )
「練り込み」とは、陶芸の装飾技法の一つで、色や濃淡の異なる土を練り合わせたり、貼り合
わせたり、交互に積み上げるなどして作った模様の土を使いやきものを成形することです。「練
上手」とも呼ばれ、中国では8世紀の唐時代からはじまり、ヨーロッパでは 18世紀にマーブル・
ウェアの名で呼ばれる伝統技法です。
思えば 15年前、赴任した学校に陶芸の窯があったのがきっかけで陶芸をはじめました。最
初は失敗の連続でしたが、2年・3年と続けることでなんとか作品らしいものが焼けるように
なりました。「練り込み」との出会いもその頃で、人間国宝・松井康成(1927-2003)の作品で
した。片手にのる細かなストライプ模様の小さな「水滴」で、流れるような模様の美しさとその
繊細さに驚き、小品ながら迫力と存在感に圧倒されました。
それから「練り込み」への挑戦が始まりました。書籍やビデオ等を参考に、見よう見まね、試
行錯誤の連続でした。その後、大学に戻り卒業制作で「陶芸テキスト(拙書)」を編集する機会を得、
松井康成の作品を多数所蔵する茨城県立陶芸美術館へ取材に伺うこともできました。
あれからすでに4年が経過してしまいましたが、ようやく第2版の準備が整ったところです。
今回も作業しているのは中学生と高校生で、作例の作品もほとんどが生徒の作品です。実際に
作り始めると想像以上に大変な作業で、思うような模様ができない、亀裂が入る等失敗もよく
あります。しかし、材料と道具をそろえ、基本をしっかり守れば、確実に作品は仕上がります。
「練り込み」の作品を手に持ってみると、絵付け等にはない、温かい味わいと素朴な感動があ
ります。失敗をおそれず、ぜひ挑戦して下さい。
白根開善学校 美術同好会 顧問 関口 正人

2
陶芸の
基礎知識1
「酒 器」 Y . H

3
1 土練り
2 成 形
3 乾 燥
4 素焼き
5 釉掛け
6 本焼き
7 完 成
① 荒練り
粘土を混ぜる、硬さを均一にします。
② 菊練り
粘土の中に残っている空気の粒を抜きます。
手びねり、ひもづくり、タタラづくり、ろくろ成形など形をつくる
作業。「練り込み」は、成形の時におこなう素地の粘土の組み合わ
せによる装飾技法です。
乾燥・素焼き・本焼きと完成までに 12~15%程度縮みます。
700~800℃で焼く。粘土が焼き締まり、強度と吸水性が増し、釉
掛けや絵付けがしやすくなります。
釉薬は焼成するとガラス質のうすい皮膜になります。
1,230~ 1,300℃で焼く。釉薬の特性により、酸化炎焼成、還元炎
焼成に分け、目標温度を決めます。
本焼き後に金彩・銀彩、上絵付けもできます。
作品の完成です。
1-1 やきものができるまで やきものができあがるまでの工程を簡単に説明します。
やきものができるまで
陶芸の基礎知識

4
陶芸の窯は小さな火山陶芸用の粘土の多くは岩石などが雨や風などで削られ小さくなり、流され堆積してできたも
のです。この粘土を陶芸の窯で 1,200 - 1,300 度で焼くと、粘土は熱で熔けて焼き締まり、
冷めると石のようになります。やきものは人間がつくった火成岩といわれ、風化して堆積し
た粘土を窯の中で石に戻したものといえます。日本は火山が多く、噴火等、火山活動がニュー
スになりますが、あの噴火口から噴き出すマグマも 1,300 度以上といわれ、陶芸の窯はたと
えればまさに小さな火山です。
粘土について粘土のいちばんの特徴は可塑性で、つまんだりくっつけたり、のばしたり、自由にかたちを
つくることができることです。粘土の粒子を拡大してみると、粒子には平らなガラスのよう
な面があり、表面に水の皮膜があるので、水の表面張力によって粒子が互いに強く引きつけ
られています。濡れたガラスの板同士を張り合わせるとくっついてしまい、はがしにくくな
るのも同じことでこれも水の表面張力によるものです。
また、粘土を繰り返し使っているとひび割れやすくなりますが、これは粘土の粒の表面の水
の皮膜がなくなってしまったからで、水を加えて練り直し、しばらく寝かせておくと戻ります。
粘土はさわっているだけで、手のぬくもりで表面が乾いてきます。作品を手早くつくるのも
可塑性を失わないポイントです。
水簸(すいひ)で粘土を集める
身近にある山や空き地の粘土質の土を集め、水を加えてよくかき混ぜます。しばらく経つと、
礫や砂は沈殿し、草木片、腐葉土などが浮かび、にごり水ができます。このにごりの正体は
粘土です。このにごり水だけを他の容器に移し、さらに放置するとにごりの中の粘土はほと
んど沈殿し、上ずみ液はきれいになっています。この上ずみ液を流すことで、沈殿した粘土
を集めることができます。この方法は水簸といわれ、非常に細かい粘土を精製するのに利用
します。土の成分にもよりますが、工夫次第でほとんどの場合、やきものの原料として利用
できます。実際にやってみると、苦労する割に集まる粘土は少ない大変な作業です。良質な
粘土を探すのは大変ですが、原料からからやきものづくりに取り組むこともできます。
今回の「練り込み」で使う粘土は、窯業の専門店でブレンドされた「白水簸」で、信楽の粘
土がベースの焼き上がりの白い粘土です。
薪窯の焚き口(大戸窯:群馬県吾妻郡東吾妻町)
1-2 粘土について
粘土について
陶芸の基礎知識

5
粘土の収縮粘土は、乾燥するときと、焼成されるときに12~15%程度収縮します。
乾燥するときは、粘土の粒子をとりまいている水分が蒸発し、粒子が互いに接近するためです。
焼成による収縮は、粘土に含まれる珪酸分が、媒熔原料と結合してガラス化し浸透するため
です。
もう少し専門的に粘土について土のなかの粒のうちで、大きさ(粒径)が2mm以上のものを礫(小石)、それ以下のものを
土粒子といいます。土粒子はさらに 2~0.2mmのものを粗砂、0.2~0.02mmを細砂、0.02~
0.002mmをシルト、0.002mm以下のものを粘土と区分されています。
ですから粘土の粒子を見るためには、電子顕微鏡が必要で、さらに小さい粘土粒子は 0.002 μ
(ミクロン=1千分の1mm ) のものもあります。タバコの煙のなかの粒子が 0.1 ~ 0.01 μと
いわれていますので、粘土粒子がいかに小さいかが分かります。
またやきもので使う粘土の化学成分については、簡単に言えばアルミナ*と珪酸と水で、いわ
ゆるこのような化学成分の粘土(粘土鉱物)を多く含んだ土がやきものに適しています。
*アルミナ(Alumina) 酸化アルミニウム。アルミニウムを強く熱して得る白色の粉。
さらに粘土鉱物についてやきもの(窯業原料)で使う粘土鉱物の代表的なものは、珪酸塩鉱物のカオリナイト
(Kaolinite:Al4Si4O10(OH)8)です。外観は白色の塊状~土状ですが、電子顕微鏡で見ると六角
板状の結晶になっているそうです。
長野県の真田町にかつてろう石を採掘していた鉱山があります。そこにカオリナイトがある
と聞き、原料からやきものづくりに挑戦しようと、生徒と採集に出かけたことがあります。
採集した一部を国立科学博物館に送り、鉱石の鑑定と分析を依頼したところ、「石英を多く含
むカオリナイト」との回答があり、さらに「窯業原料として使えるとは思われますが、恐ら
く可塑性に乏しく成形に苦労すると思います。粉砕など処理法に工夫が必要でしょう。」とア
ドバイスもいただきました。鉱石をハンマーでたたき粉砕、精製しましたが、粘りがなくヒ
ビが入りやすいもので粘土らしくはなりませんでした。それでもなんとか成形し、透明釉を
かけて焼くと、純白の磁器のようになりました。
カオリナイト(長野県小県郡真田町 信陽鉱山)と作品
粘土について
陶芸の基礎知識

6
1-10 木ゴテ・ヘラ各種 おもに皿や鉢などの形を広げて整えたり、表面をなめらかに 仕上げるのに使用。 4・5 細工ヘラ 細かな部分の作業に使う。作品に合わせて使い分ける。 8 柄ゴテ① 壺、徳利などの袋物の内側をふくらますなど、成形するときに使用。 9・10 柄ゴテ② 作業台やロクロに貼りついている粘土をはがすのに便利。 11 なめし皮 成形時、器の口縁をなめらかに仕上げるときに使う。粘土を挟むように なでるとあっという間に仕上がるスグレモノ。 12 スポンジ 主にロクロ成形の時に作品の中に溜まった水を吸い取るのに使う。
13 クレイカッター(ワイヤー) 粘土を切りはなすのに使う。30cm、50cmと2種類 の長さがある。 14 糸 主にロクロ成形の時に作品を切り離すのに使う。 15 剣先(ナイフ) 粘土板をカットしたり、作業工程ではば広く使える。 16 針 あたりをつけたり、粘土をカットするのに使う。 17-18 弓 器の口縁の高さをそろえたい時などに切るために使う。 18は糸鋸の刃を針金に変え、大きな弓として使用している。 19-20 削りカンナ 高台を削り出す時などに使う。
21-25 タタラ板(タタラづくり用) 粘土を同じ厚さにスライスしたり、のばしたりするときに使う。2枚を組として 使う。 21は1mm厚、22は3mm厚、23は5mm厚、24は7mm厚、25は 8mm厚。
26-28 紙筒(タタラづくり用) 心材として粘土を巻きつける時に使う。
29-30 のべ棒(タタラづくり用) のばし棒、粘土を均一ににのばすときに使う。
31 曲尺(さしがね) 直角定規
1-3 道 具
3
456 7 8
910
11 12
1314
15
16
17
18
19
20
21 22 23 24 25
26 27 28
29
30
31
1
2
道
具
陶芸の基礎知識

7
32
33
3435
36
38
39
41
40
37
32 電球型(タタラづくり用) 茶碗や小鉢づくり用の型。粘土がこびりつかないように電球に靴下をかぶせてい る。
33-35 木型各種(タタラづくり用) 角長皿、四角中皿と小皿用の型、丸皿用の型。
36 スポンジ(タタラづくり用) 木型を使った皿づくりの時、縁を一気に持ち上げることができるすぐれもの。座布 団のクッションとして、100 円ショップでも手に入る。
37 手ロクロ(径 22cm) 机の上で使う回転台。さまざまな工程で使う。
38 手ロクロ(径 45cm) ひもづくり、タタラづくりはもちろん、ロクロ成形もできる。 トルクが強く、慣れるととても使い易い 。
39 カメ板 作品をロクロの上に置いて使用。
40-42 はかり各種 顔料や粘土の重さをはかるので練込みでは必需品。
43 乳鉢と乳棒 顔料を擂るのに使用。
42
43
道
具
手は清潔に !?粘土には、土壌菌というバクテリアがいます。粘土の可塑性にも貢献しているありがたい微生物ですが、バイキンです。作業が終わったら、石鹸で手を洗いましょう。
コラム
陶芸の基礎知識

8
長くのびた粘土を、互い違いに折り畳み 90 度回転させ、①から繰り返す。
前から見たところ。前方に押し込むように、腕に体重をのせると楽に練れる。
粘土を起こして、折り畳むうように、身体を乗り出し、やや前方に押し込む。
両手をそろえ、奥から粘土を回転させる。
荒練り(荒もみ)は、粘土のかたさにむらがないように、均質にすることが目的です。粘土をのばして、たたみこみ、再びのばすことをくり返す練り方です。
1-4 土練り
(1) 荒練り
この部分をやや前に押し込む
この部分で押し込んでいる
種類の違う粘土を合わせること
もあります。
羊の顔のようです。
眼
つの
① ② ③ ④
土練り
陶芸の基礎知識

9
5㎏弱の粘土で練習するとやりやすい。慣れてくると 10㎏以上でもできるようになる。
(2) 菊練り粘土の回転軸
左手で押し込む部分。
回転方向
粘土が回転して動くので、菊の花びらのような模様ができる。
① ② ③ ④
手の親指を重ねるように構え、右手で粘土を起こす。矢印は前方に押し込む部分。
左手の手のひらで粘土の上半分を前方に押し込む。力を入れすぎると粘土がつぶれてしまう。
右手を 45 度回転させて、粘土を持ち換え起こす。手を回し起こすことで粘土が回る。
②③の繰り返し。粘土が回転し、菊の花びらのような模様ができる。
菊練り(ねじりもみ)は、粘土の中に残っている空気の粒を抜くのが目的です。空気の粒が粘土の中にあると焼いた時に膨張して、作品が壊れてしまうからです。菊練りを 70 回繰り返し、最後に手の間隔を広げるようにしながら砲弾の形に粘土をまるめます。上下を逆にして、さらに 70回練ります。
うまく練れると、空気の粒がつぶれる音が聞こえます。
土練り
右手は粘土を起こす、左手で粘土の上半分を前方に押し込む。
1
2
陶芸の基礎知識

10
コラム
1-5 成形について
(1) 手びねり
最初に粘土の団子を用意します。この粘土の団子の大きさで作品の大きさが決まります。200~300g 位で湯飲みや茶碗、400~500g位で中鉢になります。実際に手びねりで粘土をのばすと、最初のうちは横へと広がってしまうことが多く、背を高く、上にのびるように意識しながら作るように心がけます。
茶碗各部の名称を覚えよう。
作り始めは手の上で回しながらのばす
腰の部分をしっかりのばす
横に広げるだけでなく、上に上に背が高くなるように
親指と中指・薬指で粘土をはさんでのばす。
粘土を均一の厚みにのばす。腰の部分が厚くなりやすい。
形が完成、すこし乾燥(生乾き)させ、ひっくり返してひも状の粘土を底につけ、高台をつくる。
カンナで削り仕上げをして、成形終了。
口縁
胴
腰高台
見込
成形について
陶芸の基礎知識

11
(2) ひもづくり
粘土のひもをつくり、一段一段積みあげ、自由な発想で形をつくることができます。ひもの粘土の色を変えながら積み上げることで「練り込み」に応用することも可能です。
粘土を手の中でころがすようにひも状にする。
高く積み上げる時は、少し乾かしてから積み上げる。
ひもをねじりながら積む。
底の粘土を用意する。 粘土のひもは、一回りごとにちぎり、積み上げるのが基本。
親指と人差し指で外側、内側の粘土をよくのばし密着させる。
角瓶の成形終了。
成形について
陶芸の基礎知識
作業台の上で転がしながら、さらにのばす。① ②
③ ④

12
(3) タタラづくり
タタラづくりとは、粘土を薄くスライスしたり、のべ棒で押しつぶし板状にし、曲げたり、くっつけたりしながらつくる方法です。また、粘土はすこし乾かす(生乾き)と、木工の板のように組んだり貼り合わせてつくることもできます。
縁の仕上げをすれば成形終了。粘土の両脇に5mmのタタラ板を積み、ワイヤーでスライスし、5mmの粘土板をつくる。
円形の外型を用意し、まわりを切り抜く。粘土が作業台にくっつかないように布を敷いておく。
スポンジの上に内型を置き、押しこむ。スポンジの弾力で、縁が持ち上がり、丸皿ができる。
スライスはタタラ板を両側に積み重ねて置き、クレイカッター(ワイヤー)を使い、①②③の3つの動作を同時に行う。
成形について
丸皿をつくる
陶芸の基礎知識
①①
②②
③
①親指でタタラ板とワイヤーを押さえる。②ワイヤーを横に強く引っ張る。③手前に引いて粘土をスライスする。
布で粘土はさむ。粘土の向きを変え繰り返す。

13
タタラづくりで湯呑みをつくります。 今回使用している心材の円周は 220mmなので、スライスした粘土はそれ以上の長さが必要です。
紙筒に新聞紙を巻き、その上に粘土の板を巻きつけています。貼り合わせるところに、接着剤として、ドベ(泥状の粘土)や水をぬります。
底の粘土を貼り合わせ、剣先(ナイフ)で切り取ります。
貼り合わせたつなぎ目を指やヘラなどでしっかりくっつけます。
取っ手をつければ、コーヒーカップが完成です。「練り込み」は成形する前の段階で模様を組んでおきます。練習しコツをつかんでください。
①
② ③
底の粘土と本体(ボディ)の粘土を用意します。本体の高さは好みで決めます。
220mm以上
底用 本体 ( ボディ ) 用
成形について
湯呑みをつくる陶芸の基礎知識
コラム
スライスした粘土にはワイヤーの跡が残るので、模様として利用することもできます。厚めにスライスし、のべ棒でつぶすと、跡が消え、土もしまります。はさむ布を濡らすと、粘土が水分を吸い込み、柔らかくなります。

14
(4) ロクロ成形
電動ロクロで作品をつくると、みるみるうちに粘土が伸びて、作品ができます。しかし実際やってみると、イメージ通りにはならなくて難しさを実感します。やきものは「土錬り3年、ロクロ 10 年」といわれ、成形の中でも難しい技術で、ねらい通りの作品が作れるようになるには少し時間がかかります。ロクロ成形後、乾燥させます。さわっても形がゆがまない程度(生乾き)になったら、作品の裏を削ります。削りは、できるだけ削る量が少なくなるように、ろくろ挽きのときにしっかりと粘土をのばし、一削り分を残して切り離すのがベストです。何度も練習してコツをつかんで下さい。
ロクロ挽きでできるのは上のボディだけなので、底の高台は少し乾かして(生乾き)から削りだします。
粘土をターンテーブル ( 右回転 )の上に置き、中心に入れる。
親指で粘土を広げ、次に指をかえて、親指と中指・薬指で粘土をはさみ、上にのばす。
口の仕上げ。高さを揃えて切る時は弓を使う。
なめし皮をあてて、口をなめらかに仕上げる。
成形について
陶芸の基礎知識

15
糸で切り離し、作品を移動し、乾燥(生乾き)させる。
作品をロクロの上に伏せて置き、粘土で固定する。針で削り出す高台の線(あたり)をつけている。
削りカンナの角をうまく利用しながら、高台の外側と内側を削りだす。
成形終了
徳利は、背の高い湯呑みをつくり、底の部分を仕上げ、口をすぼめます。
ふくらみをつける時は、柄ゴテを使います。柄ゴテの位置を感覚的につかめるまで練習が必要です。
徳利など袋物がねらい通りにできれば、風船挽き・ドーナツ挽き・蓋ものから急須まで、さまざまな形に挑戦できます。
成形について
陶芸の基礎知識

16
1-6 釉薬について
釉薬とは、やきものの表面をおおっている薄いガラス状の皮膜で、やきものに光沢や色彩を与え、水の浸透をさまたげ、よごれの付着を防ぎます。また、釉薬は美しく見せる美的働きをもち、原料の選択と配合により、組成をかえることによって、透明釉、艶消し釉、色釉、結晶釉等いろいろな種類のものをつくることができます。「練り込み」で利用する釉薬は、素地の色土で模様を組んでいるので、透明釉がメインです。
代表的な透明釉の調合例(熔融温度 1,200 度)
長石…36.0%石灰石…17.8%亜鉛華…6.6%カオリン…8.4%珪石…31.2%
組成珪酸…64.2%アルミナ…10.9%酸化カルシウム…11.0%酸化カリ…7.0%酸化亜鉛…7.3%
釉薬の組成釉薬にふくまれている最も重要な成分は珪酸で、これを酸性成分といいます。またアルミナも、釉薬には欠かせない大切な成分で、これを中性成分とよびます。さらに、この二つの成分のほかに、鉛、ソーダ、カリ、マグネシウム、亜鉛、バリウム、カルシウムなど媒熔の働きをする成分があり、これを塩基成分といいます。どの塩基成分を調合するかにより熔融する温度が変わります。釉薬はこれら酸性成分(珪酸)と中性成分(アルミナ)と塩基成分の三つが結びついてできた、ガラスの一種であるといえます。
釉がけ(流し掛け)
信楽水ひ土
(丸二)
耐熱耐急冷土
(丸二)
半磁土
(赤津貫入土)
磁土
(有田上石)
石灰系透明釉(三合) 酸化焼成
釉薬について
陶芸の基礎知識

17
釉掛け釉掛けをするまえに、作品にほこりなどがついていると釉薬をはじいてしまうことがあるので、絞ったスポンジ等で拭いておきます。
湯呑みや碗ものの釉掛けは、釉薬を湯飲みの3分の1位流し込む。器をかたむけてながら釉薬をこぼさないように器の中をめぐらせ釉薬を付ける。
そっと持ち上げて、湯呑みの釉掛けが終了。
釉ばさみをつかったお皿などの釉掛けでは、まず作品をしっかりとはさむ。
静かに持ち上げる、釉薬のしずくが残らないように注意する。
中の釉薬をこぼし、器を下向きに持ち換え、底の部分に釉薬が付かないように注意しながら浸す。
静かに釉薬に沈める。
釉薬について
陶芸の基礎知識

18
釉薬が作品の裏に付くと本焼きの際、釉薬が熔けて窯の中で棚板にくっついてしまうので、底の部分に付いた釉薬は、ブラシでこすり落としておきます。
同様に硬くしぼったスポンジで拭き取っています。
底の部分に、あらかじめ撥水剤をぬり、釉薬がつかないようにすることもできます。施釉後に作品を触ると釉薬がはがれやすいこともあり、大きな作品やお皿等には事前に撥水剤をぬって施釉します。
本焼きのあと、作品を実際に使い始めると、ジワジワと水漏れすることがあります。もともと陶器は吸水性があるので、使い始める前に、米のとぎ汁で煮沸しておくと水漏れしにくくなります。それでも水漏れするときは、食器用シリコンがあります。器の中にシリコンを流し込み、3日乾かせば大丈夫ですが、窯で 300℃で焼くと安心です。
釉薬について
釉掛けの仕上げ
コラム
水モレにシリコン !?
陶芸の基礎知識

19
1-7 窯について
電気窯
古くは薪を燃料に使い「登り窯」等で焼いていましたが、現在では灯油窯、ガス窯、電気窯が中心です。学校では電気窯を使用しています。
電気窯電熱線を使用した窯で、煙やガスが発生しないこと、温度調節が容易なこと、完全な酸化焼成になるなどの利点があり、「練り込み」には最適です。また、ガスバーナーによる補助焚きもできるので、弱い還元をかけることもできます。還元焼成は、窯の内部を酸素不足状態にして焼くことで、酸化された金属を酸素を奪うことで元へ戻します。焼き方の違いで、釉薬や顔料の発色が変わってきます。「練り込み」で還元焼成をすると、青系の色はよく発色しますが、赤や黄色は色がとびやすく、注意が必要です。
本焼きの窯詰め。棚板には、釉薬が熔けて熔着しないように、コーティング剤が塗ってあります。
素焼きの窯詰め。約 8時間かけて 700 ~ 800℃まで温度を上げます。
本焼きが終わり、まる一日経ちました。作品の裏がざらざらしていたり、尖っているようであれば、砥石ややすりで削り、作品完成です。
窯について
陶芸の基礎知識

20
練り込み
基本テクニック2

21
練込み用顔料の種類
練り込み顔料は、現在多くの種類が販売されています。顔料は酸化金
属で、粘土に混ぜる割合でほぼ計算通りの色をつくることが可能です。
また、絵の具のように青と黄で黄緑の色をつくることもできます。
他にも、練り込み用の顔料を固めて陶芸用のクレパスをつくったり、
白絵土に混ぜて色化粧土に使用します。
練込み用粘土について陶芸用の粘土は大きく分けると、白土と赤土の2種類ですが、窯業の専門店では業者がブ
レンドした様々な粘土が販売されています。
「練り込み」で使う粘土は顔料を混ぜていろいろな色土をつくるので、細かい目の白土を用
意します。顔料を使用せずに、白土と赤土を組み合わせて練り込みができます。またより
白く細かい磁器土でもできますが、陶土に比べやや扱いづらいです。この本では信楽の「白
水簸」という粘土を使っています。
2-1 色粘土をつくる
練り込み基本テクニック
色粘土をつくる
「白水簸」山中陶土
「練り込み用顔料」福島釉薬

22
顔料(陶試紅)を10%含む色粘土を5kgつくる
練り込み用の顔料(陶試紅)を500g 用意する
水を加えて乳鉢でする。マヨネーズぐらいの柔らかさ。
粘土(白水ヒ)4.5kg を用意する。
粘土に顔料を付ける。粘土をちぎって、乳鉢のまわりの顔料もきれいにとる。
なじむまでよく練る。 粘土が柔らかい時は、アーチ型にして乾かす。
粘土をスライスし、顔料を混ぜる
顔料が柔らかく扱いにくい。
練り込み基本テクニック
色粘土をつくる

23
顔料(陶試紅)を10%含む色粘土から、顔料を5%、3%、1%含む色粘土を各2kg つくる。
(1)10%の色土から5%の色土を2kg つくる。 10%の粘土を 900g に、白土を 1,100g 追加し練る。 計算式(900+n):100=100:5
(2)10%の色土から3%の色土を2kg つくる。 10%の粘土を 540g に、白土を 1,460g 追加し練る。 計算式(540 +n):60=100:3
(3)10%の色土から1%の色土を2kg つくる。 10%の粘土を 180g に、白土を 1,820g 追加し練る。 計算式(180 +n):20=100:1
粘土を用意。 それぞれを薄くスライスしに重ねる。
荒練り 菊練り
奥から、10%、5%、3%、1% の粘土。
粘土は、乾かないようにビ ニール袋にしまい、ラベル を貼っておく。
練り込み基本テクニック
色粘土をつくる

24
2-2 色見本をつくろう
練込みの作品をつくる前に、10%、5%、3%、1%の顔料を含んだの色見本をつくってみましょう。黒い色土のドベ(ドロドロにした粘土)を使います。接着と色土の境に黒い筋をつけるのが目的です。
色粘土(陶試紅)10%、5%、3%、1%、と白粘土を用意する。
右から色粘土 10%、5%、3%、1%、白粘土で 10cm程度のひも状にのばす。
ひも状の粘土の両側にタタラ板8mmをおき、粘土のばし棒をころがし、粘土をのばす。
8mmの厚さにのびた粘土。
練り込み基本テクニック
色見本をつくろう

25
黒い色土のドベ(ドロドロにした粘土)を用意、乳鉢ですっておく。
黒ドベを筆で粘土にぬる。接着剤にもなる。
順番に積み重ねる。
すべて積み終わったところ。 タタラ板を使い、7mmにスライスする。 スライスした粘土をはがす。
形を整え成形終了。 素焼き後に、透明釉をかけたところ。 1250℃で本焼き、完成。
練り込み基本テクニック
色見本をつくろう

26
M460 ピンク P40 黄 M120 黄
M6000 トルコ青 T505 濃々青 T9赤茶
M55グリーン T500 ピーコック M700 黒
色見本
白い土にするために、白の顔料(ジルコン)を混ぜて色見本をつくりましたが、色はほとん
ど変わりません。白色は “白水ひ” の粘土をそのまま使っていますが、顔料を多く含ませる
時は、収縮率を合わせるために白の顔料を混ぜた方が歪みやひび割れは少ないです。
練り込み基本テクニック
色見本をつくろう
裏技、レンジでチン !?
作品は自然乾燥が原則ですが、時間が足りないとドライヤーを使い乾燥させること
があります。さらに急ぐときは電子レンジを使います。短時間(30 ~ 60 秒)温める
と作品から湯気があがるので、冷まして様子をみながら繰り返します。電波(電磁波)
で水の分子の振動させることで熱を持たせるので、壊れることもありますよ。
コラム

27
2-3 マーブル模様
2色の粘土を使いマーブル模様をつくります。菊練りがうまくできないときれいなマーブル模様になりません。しっかりと菊練りの練習をしましょう。
まずしっかりと粘土を密着させます。
とりあえず、菊練りを10 回したところです。表面はこんな感じですが、切ってみると中にはしっかりとマーブル模様ができています。
菊練り 10回でスライスしたところです。マーブルケーキのような感じです。菊練りはすごい威力と感動します。
菊練り 20回でスライスしたところです。マーブルも細かくなっています。
菊練り 30回でスライスしたところです。マーブルも細かくなりすぎてしまいました。
練り込み基本テクニック
マーブル模様
コラム
人間国宝・松井康成は、マーブル模様をつくる時は菊練りは 21 回と決めていたそうです。理由は 20 回だと模様にムラがありすぎる、22 回だと模様が細かくなりすぎるからだそうです。フムフム。

28
型を使い、マーブル模様の角皿をつくります。
5mmのタタラ板を粘土の両側に置いて、ワイヤーを外に引っ張りながら、親指でタタラ板を押さえ、手前に引く。
スライスした粘土をはがす。 粘土の板は汚れたり、くっついたりしないように、布の上に置く。
外型を使いナイフで回りを切り取る。
外型をはずす。 内型を中心に置く。
スポンジの上に移動。 内型を押し込むと、角皿の縁が一気に持ち上がる。
スポンジの上から移動し、内型をはずす。
成形終了
① マーブル模様の角皿をつくる
練り込み基本テクニック
マーブル模様

29
マーブル模様の粘土を使い小鉢をつくります。
電球の型を用意する(電球には靴下をはかせてある)。
マーブル模様の粘土の板を電球の型にかぶせる。
少しずつ、丁寧に押さえる。 電球型の合わせて丸くなった。
針で切り取り線をつけ、切り離す。
余分な粘土を切っているところ。 そっと型からはずす。 底と口の部分を仕上げて、成形終了。
② マーブル模様の小鉢をつくる
練り込み基本テクニック
マーブル模様

30
2-5 ストライプ模様
2色の粘土を用意する。 5㎜のタタラ板を両側に積み重ねて置く。
ワイヤーを外に引っ張っぱり、親指でタタラ板を押さえながら、手前に引いて粘土をスライスする。
スライスした粘土に接着剤としてドベや水をぬり、2色の粘土を交互に積み重ねる。重しをのせ2~3日ねかす。
積み重ねた粘土を横に置き、再びスライスすると、ストライプ模様の粘土の板ができる。
スライスした粘土をはがす。粘土がやわらかく、模様が壊れないように、粘土を板にはさんで移動。
粘土の縁を指で押持ち上げて、角皿の成形が終了。
型を使って角皿をつくる。
マーブル模様の角皿と手順は同じ。
角皿の完成。スポンジの上で粘土を押し込み、弾力を利用し縁を一気に持ち上げる。
① ストライプ模様の角皿をつくる練り込み基本テクニック
ストライプ模様

31
② ストライプ模様のコップ・湯呑みをつくる
5mmのタタラ板でスライスした粘土を用意し、曲尺をつかい、粘土を切り取る。
曲尺の向きを変え、切る。長さは約 250mm、高さは好みで、70-100mm 位が使い易いサイズ。
底に使う 5mmの粘土板を用意 sする。
心材に新聞紙を巻き、粘土を巻きつける。粘土に直接ふれないように布を持っている。
粘土が長いので、針で余分な粘土を切り取り、粘土がやわらかいのでそのまま接着する。
貼り合わせた部分をしっかりつける。
底の粘土の上にのせる。
ナイフで余分な粘土を切り取る。 紙筒を先ずぬき、新聞紙を丁寧にはがす。
周囲や口、中をコテで仕上げ成形終了。
練り込み基本テクニック
ストライプ模様

32
練り込み
応用テクニック
3
「角皿(市松模様)」 Y . H

33
3-1 ストライプ模様の花入れをつくる(タタラづくり~ロクロ成形)
タタラづくりでストライプ模様の長めコップをつくり、ロクロの上で胴をふく
らませ花入れをつくります。ロクロが回転しているので、模様も自然に流れます。
背の高いストライプ模様のコップをつくる。
ロクロ挽きしやすいように筆に水を含ませ、外と内側をなでる。
内側に水がたまってしまったときには、コテの先にスポンジをつけて吸いとる。
一度、全体を絞るようにしめてから、口のすぼめる部分にあたりをつけます。
柄ゴテを使用し。胴のふくらみをつける。
ストライプ模様はとくにタテ割れしやすいので、広げる時には注意が必要です。
練り込み応用テクニック
ストライプ模様の花入れ

34
ロクロ挽きが終わったところ、回りに手ドロ(ドベ)がついて模様は隠れている。
急ぐ時はドライヤーを使い、表面を乾燥させる。(自然乾燥の方がベスト)
表面がしっとりと乾いて(生乾き)になったら、削りカンナで手ドロを削る。
うっすら模様がみえてきたら削りをやめ、作品を完全に乾燥させる。
削りの仕上げは、ヤスリ掛け。スチールウールを使い模様を削りだす。
最後に削ったカスがのこらないように、刷毛や筆できれいにはらい、成形終了。
「練り込み」の失敗で意外と多いのが、削りの時です。粘土は乾いたときがいちばんもろく、欠いてしまったり、削りながらつい手をすべらせ、落としてしまうこともあります。注意しましょう。
練り込み応用テクニック
ストライプ模様の花入れ
コラム
粘土を円柱状にし、より球形にふくらますためには粘土の厚みの調整が必要です。底の部分、口の部分は薄く、ボディの中央になるほど厚みをつけた粘土を用意します。模様が流れないようにするには、ロクロを逆回転にします。右回りで 10 回転挽いたら、左回りで 10 回転挽いて、流れた分を元に戻します。理論的には可能ですが…。

35
練り込み応用テクニック
市松模様の角皿をつくる
3-2 市松模様の角皿をつくる
ストライプ模様を組んだものをスライスし、市
松模様を組むことができます。
作品の大きさに応じて、合板で型を用意してお
くと便利です。
黄と緑のマーブル模様の土と白土のストライプ模様で組んだ粘土。
タタラ板を使いスライスする。
スライスした粘土を市松模様になるようにずらしながら組む。
組んだ模様の周りに緑の粘土で縁をつける。
圧着。重石を置いて乾かないようにビニールで包み、2~3日ねかせる。
制作: N . M

36
練り込み応用テクニック
市松模様の角皿をつくる
組みあがった粘土。 タタラ板を使い粘土をスライスする。
スライスした粘土を布の上に置いて、スポンジの上に移動。
模様の大きさに合わせて用意した合板の型を使い、押し込む。
布ごと移動し、型を外す。 成形終了
タタラづくりは歪む !?成形が終了しても安心できないのがタタラづくりです。乾燥中に歪んだり、割れてしまうことがよくあります。成形中に、粘土をしっかり叩いて締めておく、乾燥はビニールをかぶせてゆっくり時間をかけて乾かすなど工夫しても焼くと歪んでしまうことはあります。あとは火の神様に祈るだけ…。
コラム

37
練り込み応用テクニック
クマの顔をつくる
3-3 クマの顔をつくる
金太郎飴の金太郎の顔をつくるように、動物の
顔を組み、ベースになる粘土に埋め込んで湯呑
みや角皿、小鉢づくりに挑戦です。
日本では飴細工ですが、古代ローマではガラス
のトンボ玉の技法で人面モザイクがあり、工程
も似ているので参考になります。
瞳用に黒土のひもをつくる。
切断には弓が便利。 白眼の厚さを 2mmにするためにタタラ板を用意。
のべ棒を使い 2mm にのばす。
のばした白土の上に黒土のひもをおき、巻く。
制作: Y . H

38
練り込み応用テクニック
クマの顔をつくる
黒土のひもが一周巻いたところで、余分な白土は切る。
2等分に切断する。 両眼ができた。 鼻用の黒土のひもを用意する。
鼻を埋め込むために切り込みを入れる。
口の部分の黄色の土を用意し、粘土と水平に弓をあてる。
顔用の青い土を用意する。 口の部分の形に合わせ、弓で切り抜く。
鼻の向きを確認し埋め込み、接着する。
眼の部分を切り抜く。 眼を埋め込む。 反対の眼も同様に切り抜き、埋め込む。

39
練り込み応用テクニック
クマの顔をつくる
顔らしくなってきた。 弓で切って確認。 それぞれのパーツが透き間なく埋め込まれた。
耳用に黄色の土でひもをつくる。
耳のひもを接着し、クマの顔が完成。
湯呑み用に白土のベースの粘土に埋め込む。
スライスし、紙筒に巻きつける。内側と外側に顔があるのが練り込みの特徴。こちらが内側。
角皿や小鉢にもクマの顔を使う。
底をつける。 クマの湯飲みが完成。

40
3-4 「嘯しょうれつもん
裂文」(象裂文)の壺をつくる
人間国宝・松井康成の嘯裂文にチャレンジです。
練り込みでつくった素地の表面につけるマチエールです。櫛目を入れ、ロクロでふくらませることで、亀裂をいれます。
表面の粘土のみ可塑性をなくし、内側からひろげることで、亀裂ができます。
珪酸ソーダ(水ガラス:Na2O・nSiO2・mH2O)は石鹸の添加剤として使われるなど、粒子を分散させる特性があります。鋳込みなど、液状粘土をつくるときにも使うので、陶芸材料店で手に入ります。
練り込み応用テクニック
「嘯裂文」の壺をつくる
表面の可塑性がなくなる !?コラム

41
表面に亀裂を入れる方法は、珪酸ソーダ以外にも、ガスバーナーでできます。櫛目を入れた後、バーナーの炎を1~2秒あてると表面が乾き、ふくらますと嘯裂文になります。より球形にする場合は、タマゴ型に挽き、クシ目を入れます。表面にロクロ目が残っている時は、ヘラなどで消しておきます。
練り込み応用テクニック
「嘯裂文」の壺をつくる
粘土を用意。丸くふくらませるために中心部分に厚みをもたせる。
ロクロの中心に入れる。 心材に巻きつける
表面にはふれずに仕上げる。柄ゴテをつかい、ふくらますと表面に亀裂が入る。
針を使い、櫛目模様をつけ始めたところ。
写真では針を使用していますが、櫛を使い模様をつけることもできる。
霧吹きを使い「珪酸ソーダ」の水溶液をふきつける。

42
3-5 オリジナル模様の角瓶をつくる
黄、白、グレーの3色の色粘土を用意。 5mmのタタラ板を重ね、スライスする。
グレー、白、黄の順で重ねる。 重ねた粘土を立てて(90度回転)、2分割し、ストライプ模様の幅を広げる。
ガラスの角瓶を心材に使い、面ごとに組み立て、貼り合わせることで、成形する。オリジナル文様。
板で両側から、圧着する。
練り込み応用テクニック
オリジナル模様の角瓶をつくる
制作: M . K

43
余分な粘土をスライスして取る . 切断した面の粘土が流れるように、幅の広いタタラ板(2-3mm)を使い、粘土を切断する。
3色の縦縞文様。
互い違いに接着させる。(同方向の場合は鶉手になる)
スライスしたところ。
寸法に合わせて、パーツをそろえる。 接着する。 形をそろえる。
練り込み応用テクニック
オリジナル模様の角瓶をつくる

44
逆さにして組み立て。心材にガラスの角瓶を使用。
慎重に、貼り合わせる。
最後に口の部分に白い粘土のパーツを接着する。
成形終了
内側は、心材をはずしてから、コテ等で仕上げる。
練り込み応用テクニック
オリジナル模様の角瓶をつくる
「鶉手の醤油注しと小皿」
コツのコツタタラづくりは、イメージした作品の形に合わせた道具を用意します。型に合わせてつくる時は心材や木型、紙型、石膏型、発泡スチロールなど、ロクロを使う時は球形に合わせ膨らみをもたせた柄ゴテなど、自分でつくったり、身近にあるもので代用するなど工夫しましょう。
コラム

45
3-6 クズ粘土の利用
① 角瓶のクズ粘土を利用しながら、練込みの丸皿をつくる
パーツを並べ、黒い粘土をすき間にはめ込む。
金属のボールを台にして、布をかけ、パーツを接着する。パーツは特に乾きやすいので、タオルに包んだり、ビニール袋に入れ管理する。
縁の粘土をつける。 成形終了
② クッキーや和菓子の型をつかい、箸休めをつくる
嘯裂文の壺で残った粘土を使いつくったもの。
余った粘土を寄せ集めて、1cmの厚さにのばす。模様を選び、型でくりぬく。
箸が転がらないように、くぼみをつける。
成形終了
練り込み応用テクニック
くず粘土の利用

46
「不思議な生物」ひもづくり Y . M 「練り込みの角瓶」タタラづくり Y . H 「練り込みの壺」ロクロ成形 Y . H
3-7 練り込み作品集
「星座のランプシェード」ひもづくり M . K
練り込み応用テクニック
練り込み作品集
「練り込みの花入れ」タタラづくり M . K

47
編集後記
テキストとしてはふさわしくない作品以上に派手な柄の布をなんとかしたかったのです
が、ありのままの活動記録とあえて繕うことはしませんでした。 相変わらず雑然とした陶芸
室では、これまでと同じように生徒が作業をしています。卒業した生徒たちも、この教室に
居場所を見つけてひたむきに制作に打ち込んでいました。この子どもたちのおかげで自分
もここで仕事ができるのだと改めて感謝しています。(ま)
陶芸材料店
福島釉薬(株)東京出張所埼玉県比企郡玉川村五明 321-2 TEL 0493-65-1498
山中陶土 滋賀県甲賀郡信楽町江田 257-1 TEL 0748-82-0356
練り込み陶芸入門 第 2 版
企画・著・撮影・編集・印刷・製本 関口 正人撮影協力 白根開善学校 美術同好会
発行 白根開善学校平成 21年7月7日
非売品
群馬県吾妻郡六合村大字入山 1 - 1学校法人 白根開善学校白根開善学校中等部白根開善学校高等部TEL 0279-95-5311FAX 0279-95-5315
URL http://www.shirane.ac.jp/

48
練り込み
陶芸入門