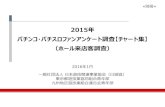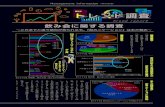10-11月期 調査結果概要報告書】早 期 景 気 観 測 調 査 【10-11月期 調査結果概要報告書】 平成29年12月 甲 府 商 工 会 議 所 1 調査要領
Ⅱ 商品開発・事業化可能性調査 1.調査実施の概要 ·...
Transcript of Ⅱ 商品開発・事業化可能性調査 1.調査実施の概要 ·...

47
Ⅱ 商品開発・事業化可能性調査
1.調査実施の概要
1-1 調査の目的
本調査は、「企業商品開発実態調査(以下、「事前アンケート調査」。)」の調査結果を基に、管内
食料品製造事業所・企業の「研究開発技術ニーズ」を把握し、大学や研究機関とのマッチングの
可能性や商品開発までの技術的課題、生産や流通面での課題等を踏まえた事業化の可能性を探る
ことを目的としました。
また、ヒアリング調査結果を基に、商品化の可能性の高い開発構想について、「商品開発支援パ
ッケージモデル」としてとりまとめ、関係機関と連携した商品開発の実現に向けた基礎的な資料
とすることも調査の目的としています。
1-2 調査の項目
調査項目は、7月1日開催のINO運営会議打ち合わせにおいて、メンバーからの意見を踏ま
え、以下のとおり設定しました。
なお、設計したヒアリング調査票は別添資料としました。
A.「研究開発技術ニーズ調査」……ヒアリング調査の実施
(1) 改良・開発構想に関する確認項目
(2) 改良・開発構想を進めて行く上での課題の項目
1) 生産工程上など技術的な課題
2) 製品化のコスト上での課題
3) 研究開発上や試作品段階での課題
4) 資金等・販促・流通対策上での課題
5) 改良・開発構想スケジュール
6) 地域に対する貢献性や発展性
(3) 事業化に向けての判断項目
1) 新しいものづくりへのこだわり
2) 安心・安全・美味しさ・オホーツクらしさ
3) コスト意識や商品化の工夫
4) 資金調達の具体性
5) 希望する支援内容
(4) 経営上の観点からの強みと弱み(非公開)
(5) 企業の業況把握(非公開)
B.「事業化可能性調査」……商品開発支援パッケージモデル作成の条件設定調査
(1) 改良・商品開発構想の内容・課題等の把握(一部補完調査の実施)
(2) 商品開発支援パッケージモデルの検討
1) 商品開発のコンセプト及び地域貢献・地域活性化へのポイント
2) 事業化に向けた現状・課題
3) 連携支援の方向性
4) 連携支援スキーム案
5) 事業化スケジュール
6) 事業化検討事項

48
1-3 調査の実施状況
(1)調査対象企業
調査対象の抽出は「事前アンケート調査」において、主に商品の改良・開発構想を有し、着
手時期や希望する連携内容が明確と考えられた企業 44 社について「企業カルテ」(別冊)を作
成し、これを「ヒアリング調査対象候補リスト」としました。INO運営会議においては、前
章節Ⅰの9.の(3)「絞込みの手順~その2」に基づき、調査対象企業として 32 社を選定し
ました。
また、ヒアリング調査対象企業とは別に、「事前アンケート調査」の自由記述への回答を寄せ
た企業のうち、加工技術について具体的な課題を有していると考えられた企業として5社を選
定し、回答内容のフォローアップとして同様のヒアリング調査を行うこととしました。
前述の 32 社のうち、調査を進める過程でサンプルデータが得られなかった企業が3社あった
ことから、これらを除く計 34 社が最終的な調査対象企業となりました。
図表1-1 調査対象企業リスト
企業 NO 事業分類 構想商品内容 開発構想上での主な課題 開発予定時期
1- 26 野菜缶詰等製造業 道外工場から道内工場に発注移動 労務コストが掛かり採算が厳しい 平成23年3月から着手済
1- 31 畜産食品製造業 大豆主原料の菓子製品 設備の老朽化。運転資金不足 平成14年~16年着手済
1- 38 水産食料品製造業 全ての商品の見直し(原点に帰る) 原材料費が価格上昇で利幅減少 即時~2年以内
1- 50 その他食料品製造業 地元産米粉使用の菓子 粗利30%を予定している 平成23年3月から1年予定
1- 65 パン・菓子製造業 地元産原料を多く使用の練り菓子 施設の老朽化、販売量の確保 平成24年~着手予定
1- 76 パン・菓子製造業 地元産野菜使用の焼菓子 原材料費高騰、デンプン質含有量均一化 平成23年4月から着手済
2- 81 水産食料品製造業 地元産野菜使用の練り製品開発 特になし 平成22年からサンプル完成
2- 90 水産食料品製造業 地元産未・低利用資源利用の複合食品 味付け方法が確立していない 平成23年4月から25年4月まで
2- 93 水産食料品製造業 農産物活用の加工品 特になし 定まっていない
2- 94 水産食料品製造業 網走湖産魚種利用の新商品開発 味・色を変えずに硬さを柔らかくしたい 平成24年から着手予定
2- 110 パン・菓子製造業 地元産野菜使用の菓子 機械設備・製造ノウハウ・資金繰り 平成24年から着手予定
2- 119 水産食料品製造業 地元産魚種の高次加工 原料が獲れないため製品化中止 22年開発中止
3- 126 その他食料品製造業 地元産野菜を100%使用の製品 資金繰り・生産量の減少 開発の計画なし
3- 142 水産食料品製造業 地元産ほたてとチーズ加工食品 新製品に使う材質の選定 平成23年年内発売予定
3- 171 水産食料品製造業 魚醤を活用した高次加工食品 化合物添加量の調整 平成23年2月から年内完成
3- 178 水産食料品製造業 ホタテみみ使用の製品 味付け方法、煮ても硬くならない製造 具体的に決まってない
4- 195 野菜缶詰等製造業 野菜等使用した加工品開発 本社主導の経営のため特になし 平成23年4月から製品完成
4- 196 野菜缶詰等製造業 じゃが芋とマヨネーズを混ぜた製品化 特になし 平成24年から1年程度予定
4- 198 その他食料品製造業 地元産野菜使用農産加工品の商品化 搬入量のわりに処理能力が低い 平成25年頃から着手予定
4- 208 その他食料品製造業 畜産加工品 特になし 平成23年10月頃着手予定
6- 259 畜産食料品製造業 豚肉使用生ハム製品 工場が手狭のため衛生面で課題 平成20年~着手済
7- 265 その他食料品製造業 漬物への農産加工製品 乳酸菌発酵が課題。 平成22年9月~着手済
13- 292 水産食料品製造業 パッケージングの向上 特になし 食品での開発はなし
14- 306 調味料製造業 地産品使用の無添加調味料の開発 運転資金・販路拡大 平成23年10月から1年程度
14- 309 野菜缶詰等製造業 地元産ハッカ使用加工食品開発 特になし 定まっていない
15- 325 畜産食料品製造業 ドリンクタイプ乳製品開発 機械が旧式で製造能力が低い。 平成23年4月から着手済
15- 333 畜産食料品製造業 チーズ乳製品開発 加工粉砕機がなく、資金不足、コスト高 平成23年3月頃から着手済
18- 241 畜産食料品製造業 野菜を使った菓子開発 フリーズドライ設備導入への資金不足 平成23年3月頃から着手
18- 242 その他食料品製造業 オホーツク産秋鮭使用加工品 特になし 商品開発は毎日行う
2- 95 水産食料品製造業 蟹殻有効活用による製品化 販路が未定 平成23年1月頃から着手済
2- 108 調味料製造業 道産原料使用の醤油製造 試作品製造中なので加工技術の指導 平成23年7月から着手済
2- 117 その他食料品製造業 大豆加工品の開発 味の均一化等技術上全般 平成23年4月から着手済
2- 120 水産食料品製造業 海産物・農産物活用食品構想 商品構想・試作品製作など 平成23年4月から着手済
9- 275 その他食料品製造業 蜂蜜利用の加工品製造 試作品製造・人手不足 平成23年頃から着手済

49
(2)調査方法
調査票は、前節1-2において設定された項目に即して設計しました。
調査方法は「研究開発技術ニーズ調査」と「事業化可能性調査」の双方とも、調査員が調査
票を基に直接企業訪問し、ヒアリング(面談聞取り法)を行いましました。
また、調査結果の精査や連携支援可能性企業の選定に向けて、再度、重点的な企業訪問を行
い、補足・補完調査を行いました。
(3)調査スケジュール
7月中旬から下旬にかけて、32 社に対する網羅的なヒアリング調査及び補完事項調査を行い、
事業化に関する判断項目の回答を精査し、商品開発構想が具体的で事業化に向けた意欲が高い
と考えられた企業を 10 社選定するとともに、資料調査による産学官連携の事例収集を行いま
した。
さらに、この 10 社に対する重点的なヒアリング調査及びフォローアップ調査の5社に対する
ヒアリング調査、関係機関訪問による情報収集を8月~9月中旬にかけて行い、特に、開発構
想の内容や各種支援機関等とのマッチングの可能性などの情報収集を進め、主に以下の観点か
ら、商品開発支援パッケージモデルをとりまとめました。
a.INO運営会議との連携に非常に高い関心がある
b.開発構想内容と課題が非常に明確となっている
c.連携支援のニーズとシーズが合致している
d.企業業況に安定感がある
<スケジュール>
調査項目 期 間 本文章立て
・INO運営会議における調査対象企業の抽出
・調査の計画準備
・ヒアリング調査実施及びデータ収集
7月1日
7月2~10 日
7月 11 日~30 日
2.章
3.章
・個票の整理及び補足・補完事項の調査
・事業化進展判断重点調査[15 社]
・関係機関訪問及び事業化可能性検討調査
8月1日~22 日
8月 23 日~30 日
9月1日~16 日
4.章

50
2.研究開発技術ニーズ調査
2-1 調査対象企業の属性と類型
(1)調査対象企業の属性
調査対象とした 34 社の属性は、図表2-1のとおりとなりました。エリア別では「網走エリ
ア」が 16 社と最も多く、次いで「紋別エリア」9社、「北見エリア」7社、「斜里エリア」2社
の順となりました。従業員規模では「5~9人規模」が 11 社と最も多く、「10~19 人規模」と「30
人以上規模」が同じく8社となりました。事業分類は「水産食料品製造業」が 12 社と最も多く、
次いで「その他食料品製造業」が8社、「畜産食料品製造業」5社の順になりました。
エリア別と事業分類の属性は、事前アンケート調査結果とほぼ同様の傾向となりましたが、
従業員規模については、事前アンケート調査では「30 人以上規模」の中小企業者が最も多かっ
たものが、本調査では「5~9 人規模」の 11 社を筆頭に、「1 人~4 人規模」5社、「10 人~19
人規模」8社とを合わせて、全体の約 70%が小規模企業者となりました。
開発構想上の商品分類は、13 品目にわたり構想が練られていましたが、中でも多いのは「加
工水産」の8品目、次いで、「菓子類」6品目と「練り製品」4品目等の順となりました。
(2)調査対象企業の類型
構想発想のきっかけからは、差別化型・資源活用 図表 2-2 開発構想内容の類型
型・ターゲット型等に分けることができますが、調 査結果では 34 社中 29 社が“地元にこだわり、地元
産原料使用”と答えているなど、「地域資源活用型」
の傾向が窺えました。 開発構想内容を類型化してみると、図表2-2に示
すように、他社・他商品との「差別化型」が 22 社と、
最も多く、次に、取引先や消費者からの「開発要望
型」は 13 社、素材や品質に係る「安心安全対応型」
と「消費者満足志向型」が同じく 10 社の多い順と
なりました。
類 型 数差別化型 22安心安全対応型 10開発要望型 13消費者満足志向型 10新技術導入型 7利益増大型 6製造効率性型 5ネーミング型 4社内企画提案型 3パッケージデザイン型 3ノウハウ継承型 3その他 2 計(n=34 複数回答) 88
図表2-1 調査対象企業の属性エリア別 数 従業員規模 数 事業分類 数 開発構想商品分類 数網走エリア 16 1~4人 5 畜産食料品製造業 5 調味料 1北見エリア 7 5~9人 11 水産食料品製造業 12 乳製品 1斜里エリア 2 10~19人 8 野菜缶詰等食料品製造業 4 冷凍食品 3紋別エリア 9 20~29人 1 調味料製造業 3 粉類 1計(n=34) 34 30人以上 8 糖類製造業 1 加工肉類 2
無回答 1 パン・菓子製造業 4 練り製品 4計(n=34) 34 その他食料品製造業 8 漬物・佃煮 3
清涼飲料製造業 1 加工水産 8茶・コーヒー製造業 1 菓子類 6計(n=34 ※1) 34 デザート・ヨーグルト 1
アイスクリーム類 3※1.複数事業を営む企業5社あり アルコール飲料 1※2.原材料から複数商品化構想する企業2社あり その他食品以外 1
無回答 2 計(n=34 ※2) 37

51
2-2 改良・開発構想における課題の把握
□ ヒアリング調査項目
〇 INO運営会議からの質問事項
〇 改良・開発構想を進めていく上での課題
1. 生産工程上など技術的な課題 2. 製品化コスト上の課題
3. 研究開発上及び試作段階での課題 4. 資金等及び販促・流通対策上の課題
各企業の商品開発構想に関する技術的課題、生産や流通面での課題等を調査することにより、
オホーツク地域での食料品開発構想におけるニーズを把握するとともに、大学や研究機関シー
ズとのマッチング可能性の検討材料となる情報収集を行いました。
(1)生産工程上など技術的な課題
〇 生産工程上の技術的課題について、「課題がある」と答えた 12 社のうち、その理由が“古
くなったので更新したい”などの「機械設備上の課題」が7社、“加工方法が社内対応できな
い”など「加工技術(者)上の課題」が4社となりました。
「課題はない」と答えた 15 社の理由は、「機械設備上は問題ない」と「技術者対応により
問題ない」が同じく6社となりました。
〇 機械設備上の課題内容では、“開発構想を有していても製品化の機械設備がない”、あるい
は“旧式で生産能力が低く、技術的には確立しているが設備がない”などの事業化への課題
を抱えている傾向にありました。
加工技術(者)上の課題内容は、主に、味付けなどの加工調整が必要との状況にありました。
<主な課題のコメント>
【機械設備上】
・昭和 63 年以来、設備更新していないので、生産性は低いものと思う。(畜産)
・機械設備はなく、ノウハウもまだ決まっていない。(パン・菓子)
・搬入量のわりに機械の性能が良くないので、処理能力が低い。(その他)
・製造機械が旧式で製造能力が低い。(畜産)
・海草を粉末化する粉砕機がない。(畜産)
・製品化は技術的には確立しているが、設備がないため製造ができない。(畜産)
・手作業で 300 品目生産しているので、生産効率のため機械化を図りたい。(水産)
【加工技術(者)上】
・味付処理の仕方が確立していない。(水産) ・味・色を変えずに硬さだけ軟らかくしたい。(水産) ・乳製品発酵技術に課題が残る。(その他) ・試作品段階で生産ラインに乗せるには人手が足りない。(その他)
図表 2-3 生産工程上の技術的課題
回答項目 回答数・% 回答項目 回答数・%
「課題がある」 12 44 「課題はない」 15 56
理 由 理 由
1.機械設備上の課題 7 58 1.機械設備上は問題ない 6 40
2.加工技術(者)上の課題 4 33 2.技術者対応により問題ない 6 40
3.品質管理上の課題 1 8 3.開発構想が中止 3 20
母数(n=34 回答数 27 無回答 7)

52
(2)製品化コスト上の課題
〇 製品化コスト上の課題を整理すると、「課題がある」と答えた 12 社の理由は「原材料コス
ト上の課題」が5社と最も多く、次に、「生産量コスト上の課題」が4社の順になりました。
「課題はない」と答えた 16 社の理由は、「販売段階でコスト吸収」が9社と最も多く、「原
材料段階でコスト吸収」が5社の順になりました。
〇 原材料コスト上の課題内容は、“原材料の値上がりや確保に不安定さがあるため、製品・販
売価格に転嫁せざるを得ない”との回答が多く見られました。
生産量コスト上の課題内容は、“少量であるため、多くが価格で吸収せざるを得ない”との
状況にあることがわかりました。
<主な課題のコメント>
【原材料コスト上】
・原材料が割高で一般的な製品より高く、売り値も高いと思われる。(畜産)
・原料が少しずつ値上がりし、製品価格も市場動向で決まるため、利幅は薄くなっている。(水産)
・7月から小麦値上がりの影響があり、何らかのコストを抑えなくてはならない。(パン・菓子)
・原材料の好不漁があるので営業ベースでの採算は合わない。(水産)
・美味しさにこだわるため、原料高は商品に転嫁せざるを得ない。(その他)
【生産量コスト上】
・生産量が減少してコストは相対的に割高となる。(その他)
・現状の生産規模ではやや割高となる。(水産)
・マーケティングから価格は設定していないので、少量での製品化は仕方がない。(調味料)
・生産販売量が少ない事から、コストは高くなると思われる。(畜産)
(3)研究開発上及び試作段階での課題
〇 研究開発上・試作段階において「課題がある」と答えた理由は、「品質の改良」が4社、「パ
ッケージが決まっていない」が2社となりました。
「課題はない」と答えた理由は、「販売段階に移行している」と「試作段階で問題ない」が
同じく4社となりました。
〇 品質改良における課題内容は、“味付けの加工調整が上手く行かない”との回答が多く見ら
れました。
また、パッケージの素材やデザインが決まらず、商品化段階に進めない状況もありました。
図表 2-4 製品化コスト上の課題
回答項目 回答数・% 回答項目 回答数・%
「課題がある」 12 43 「課題はない」 16 57
理 由 理 由
1.原材料コスト上の課題 5 42 1.販売段階でコスト吸収 9 56
2.生産量コスト上の課題 4 33 2.原材料段階でコスト吸収 5 31
3.人件費コスト上の課題 2 17 3.人件費段階でコスト吸収 2 13
4.機械設備コスト上の課題 1 8
母数(n=34 回答数 28 無回答 6)

53
<主な課題のコメント>
【品質の改良】
・製品化はやや臭みがあり改良支援を希望する。(畜産) ・試作品がべとつくため、添加化合物の数量が決まらないことから完成にはいたらない。(水産)
・味付けの仕方、煮ても硬くならない煮方が確立していない。(水産)
・凝固剤の関係で味が疎らとなり、試作段階では更に改良を要する。(その他) 【パッケージ等未定】
・製品使用のシリコンカップの材質を決めかねている。(水産) ・パッケージデザインが、まだ決まっていない。(その他)
(4)資金及び販促・流通対策等における課題
〇 資金上の課題としては、「課題がある」とした4社全てが必要な資金の調達を理由に上げま
した。「課題がない」と答えた 24 社では、「自己資金で賄う」が最も多く 18 社となりました。
〇 販促・流通対策等のマーケット上の課題としては、「販路が未定」が4社と少なく、「課題
はない」とした回答では、半数以上の5社が「既存の取引先で対応」との答えでした。
【販促・流通対策等】
図表 2-5 研究開発上及び試作品段階での課題
回答項目 回答数・% 回答項目 回答数・%
「課題がある」 6 38 「課題はない」 10 63
理 由 理 由
1.品質の改良 4 67 1.販売段階に移行している 4 40
2.パッケージが決まっていない 2 33 2.試作品段階で問題ない 4 40
3.何も決まっていない 2 20
母数(n=34 回答数 16 無回答 18)
図表 2-6 資金及び販促・流通対策における課題
【資金】 回答項目 回答数・% 回答項目 回答数・%
「課題がある」 4 14 「課題はない」 24 86
理 由 理 由
1.資金調達が必要 4 100 1.自己資金で賄う 18 75
2.知人・親類からの支援受け 3 13
3.提携先・取引先の支援受け 2 8
4.制度資金で手当 1 4
母数(n=34 記入回答数 28 無回答 6)
回答項目 回答数・% 回答項目 回答数・%
「課題がある」 4 31 「課題はない」 9 69
理 由 理 由
1.販路が未定 4 100 1.既存の取引先で対応 5 56
2.大手量販店を予定 2 22
3.販売提携で行う 2 22
母数(n=34 記入回答数 13 無回答 21)

54
<主な課題のコメント>
【資金等】
・新製品開発によって当面の資金繰りに傾注している。(パン・菓子)
・資金繰りは厳しく、販売が縮小している。(その他食料品)
・運転資金がなく、販路もない。(調味料)
・資金・販売先ともに脆弱。(畜産)

55
2-3 事業化に向けての判断項目の把握
前節では、ヒアリング調査対象企業 34 社について、改良・開発構想を進めていく上での生産技
術に関する課題を中心とした、「研究開発技術ニーズ」が浮き彫りになりました。
一方、生産・加工から市場に商品提供を行うまでの過程において、人・物・金を投入しながら
持続性的に展開を図るためには、「ビジョン(あるべき姿や確固たる意志、事業の展望)」と「ド
メイン(目指すべき事業領域、満たすべき顧客のニーズ)」をある程度明確にして取り組む必要が
あります。そのため、ヒアリング調査では、ビジョンに関する項目として、「新しいものづくりへ
のこだわり」と「安全・安心・美味しさ・オホーツクらしさ」、ドメインに関する項目として、「コ
スト意識や商品化の工夫」と「資金調達の具体性」、加えて「希望する支援内容」は連携の意志を
再確認するための項目として設定し、「商品開発支援パッケージモデル」の事例案を検討しました。
また、併せて、「改良・開発構想がアイディアの域を脱しているのか」といった構想内容の具体
性についても確認し、事業化進展の途上にある企業については、内容の仔細を把握する補完調査
も行いました。
調査の結果は、別冊の「企業カルテ」にまとめましたが、企業の経営業況や診断内容も含まれ
ていることから非公開としています。
(1)ビジョンに関する事業化判断項目
① 新しいものづくりへのこだわり
○ 商品開発コンセプトが明確に示されているか、あるいは、構想内容が具体的であるかを
確認したところ、13 社が「商品開発への意欲はあるが、現状、具体性がまだ見えていない」
状況にありました。
○ 開発構想が明らかで、試作段階に向けて取り組んでいる「意欲的な企業」は7社あり、
事業化への可能性を帯びていると判断されました。この7社の支援希望の内訳は、生産工
程上の加工技術が3社、販売先・パッケージング等が4社となりました。
② 安心・安全・美味しさ・オホーツクらしさ
○ “高くとも美味しく、産地(生産者)の場所(顔)が見え、安全・安心なものを購入したい”
という消費者トレンドを意識した開発構想から、「地元産原材料使用により安心・安全性を
追求」が 12 社と最も多く、次いで「製品の品質において安心・安全性を追求」が 10 社と
なりました。
○ また、オホーツクらしさを意識したものづくりであるかを確認したところ、「商品化にお
いて一貫性を持ってオホーツクらしさを意識」している企業が7社となりました。この7
社の支援希望の内訳は、加工技術支援・資金支援が1社、販売方法支援が1社、他5社は
「支援を希望していない」となりました。
図表2-7 新しいものづくりへのこだわり回答内容 数
1.商品開発段階での意欲はあるが具体性が見えてこない 132.経常的に取組んではいないが開発意欲が窺える 93.新商品完成に向けて意欲的である 74.新分野・業態転換のために取組んでいる 5 計(n=34) 34
図表2-8 安心・安全・美味しさ・オホーツクらしさ回答内容 数
1.地元産原材料において安心・安全性の追求 122.製品の品質において安心・安全性の追求 103.商品化の一貫性においてオホーツクらしさを意識 74.特に見当たらない 5 計(n=34) 34

56
(2)ドメインに関する事業化判断項目
① コスト意識や商品化への工夫
○ 事業化を図る上でコストについてはどの段階で意識しているのか、また、商品化段階を
想定した“売れる商品づくり”への工夫が見られるか確認したところ、「ものづくりの工夫
は見られるがコスト意識は高くない」企業が 13 社となり、一方、「商品化へのコストバラ
ンスを意識している」企業は 12 社ありました。
○ コスト意識は高くないと見られた 13 社のうち、8社が支援希望を有し、内訳は加工技術
が1社、パッケージデザイン等が1社、販売先が2社、資金手当てが4社となりました。
コストバランスを意識して商品化を工夫していると見られた企業 12 社のうち、半数の6
社は、「自社単独あるいは既取引先と開発等可能であり支援を希望しない」状況にありまし
た。
② 資金調達の具体性
○ 事業化に必須の資金の手当てについて具体的に再確認したところ、「自己資金で賄う」企
業が 15 社と最も多くなりました。そのうち、支援を希望しない企業は8社、支援を希望す
る企業は8社となり、その内訳は、加工技術が5社、販路拡大が2社、品質管理が1社と
なりました。
○ 特に、「自己資金で賄う」とした8社のうち、5社が加工技術の支援を希望し、販路拡大
は2社、品質管理が1社となりました。また、企業8社のうち5社が「商品化へのコスト
バランスを意識」していることが窺えました。
<自己資金で賄う企業(8社)の支援希望内容>
・商品メニューは沢山あるので販路拡大に支援を願いたい。(加工水産)→販路拡大[■]
・ペーストづくりのアドバイスが欲しい。(菓子)→加工技術
・未利用水産資源の製品化において生産工程上でのアドバイス。(加工水産)→加工技術[■]
・豚肉加工上での品質管理のノウハウを求めたい。(加工肉類)→品質管理
・乳酸菌発酵のアドバイス。(漬物・佃煮)→加工技術[■]
・健康食品向け商品の薬理効果と販売先支援。(加工水産)→加工技術[■]
・味が全体にまわるようにする製品開発の助言とネーミング等の助言。(水物)→加工技術
・フェアや物産展出展の助言。(調理品)→販路拡大[■]
※[■]は商品化へのコストバランスを意識していることがが伺える企業
図表2-9 コスト意識や商品化への工夫回答内容 数
1.アイディア・構想段階でとどまっている 32.ものづくりの工夫は見受けられるがコスト意識は低い 133.商品化へのコストバランスを意識している 124.原材料調達と品質のこだわりでコスト高となっている 35.特に見当たらない 3 計(n=34) 34
図表2-10 資金調達の具体性回答内容 数
1.自己資金で賄う 152.制度資金を導入する予定にある 23.金融機関から調達する予定にある 24.本社サイド・恩借による 35.資金計画は具体化していない 46.資金調達の充てはない 6 計(n=34) 34

57
3.産学官連携の取組動向
3-1 オホーツク地域の商品開発の動向
オホーツク地域企業の産学官連携及び企業間連携による商品開発の動向について、過去3年間
のニュースソース(北海道新聞地方版)から調べ、主なものを図表3-1のとおり整理しました。
(詳細は別冊資料4)
これによると、オホーツク地域では、幅広い商品分類にわたり商品開発の意欲が高いことが窺
われると同時に、多くの事例で地元産原材料使用した構想を基に商品開発が行われ、その販売も
地元で主に展開されている傾向にありました。
取組の体制として多く見られたのは、網走市やオホーツク食科技等との産・官連携、企業共同
グループや酒造メーカー等との産・産連携による加工技術分野での事例でした。また、こうした
取組を通じて、未利用の地元産原材料の利活用が進み、それがオホーツクらしい商品開発に繋が
っているという特徴が浮き彫りとなりました。
今後の課題として上げられていたものを下記に示しましたが、生産加工上の課題が 10 件、販路
開拓上の課題が9件とほぼ同数ありました。
特筆すべき販路開拓の方法としては、首都圏市場拡大を目指して大手スーパー(流通部門)と
の連携を目指す取組や、デパート物産展販売実績から通販市場へ販路拡大した取組、札幌圏アン
テナショップへのブース出品などの取組が見られました。
<今後の課題のコメント(詳細は別冊資料4)> ・ホテル用として新商品を開発中(つべつチーズ工房風の丘)[〇]
・ワインの生産も検討し地域の名産品に育てる予定。(佐藤建設管理)[〇]
・試作段階(試食会用)であるので商品化を目指す(リスの森・横山蒲鉾店)[〇]
・設備と人材を充実させ、農業や水産加工のサポートにも取組みたい。(オホーツク農業研究センター)[〇]
・社長職を譲っても卵麺の開発を極めたい(北見麺業)[〇]
・商品開発により“受賞”したが、今後は技術向上に努める(ノースプレインファーム)[〇]
・通信販売を検討中(マルキタ・香遊生活)[□]
・JR 北見駅前パラボが今後店頭販売展開するかを検討中。(シーニックカフェ帽子岩)[□]
・オホーツクサーモンの通信販売を検討中。(農業法人香遊生活、販売先:関東デパートでの物産展)[□]
・商品展開でホタテ加工品の差別化を図りたい。(竹本水産)[□]
・ペーストの価格が高いので製品価格設定が課題(しんや)[□]
・JR北見駅前パラボでの店頭販売検討中(置戸町商工会特産品開発委員会)[□]
・マヨネーズ風ドレッシングの商品開発(乳食研)[〇]
・追加生産したので、ポスフール北見店等やオンラインショップでも扱う予定(きたみらい農協)[□]
・地産地消にこだわる安価な商品作りを目指す(ベーカリー&カフェ捏)[〇]
・オーガニック牛乳や有機牛肉増産し、首都圏での販売を目標(津別有機農研究会、販売先:コープ札幌)[□]
・有機肥料で育てた唐辛子を今後は業務用として販促したい。(つべつべ GROW)[□]
・網走は食材の宝庫なので今後も地元の素晴らしさを伝える商品開発を続ける(ダニエル・ドゥ・ノウ)[〇]
・リピーターが多いので、これまで以上に味の美味い焼酎をつくりたい。(西興部酒店会)[〇]
※課題分類=[〇]生産加工上の課題 [□]販路開拓上の課題

58
図表3‐1 地域商品開発の動向
企業名
相手方
商品名(商品分類)
製 法
オホーツクらしさ(特徴)
販売方法
課 題
東京農大バイオインダストリー
網走市
エミューオイル
(食用油)
エミューオイルにビタミンEを加えソフトカプセルにつめた
網走市内で繁殖しているエミューから抽出した油を使
用東京農大バイオインダストリーにて販売
不明
みるくVACCA
網走農業改良普及センター
さけるチーズ、アイス、生キャラメル
(乳製品・菓子類)
食品衛生法の基準が厳しいため試作段階、販売には至らず
自家製牛乳を材料に温根湯地区酪農家女性が活動販売していない
不明
スコッチバー・ジアス
網走市
網走産マタタビ入り生チョコ
(菓子類)
生チョコにマタタビのドライフルーツの実を砕いて混入。隠し味にコニャック
と紅茶のリキュール。
網走産のマタタビを活用
自店のみ提供
不明
KITAMIブランドの会
道立オホーツク圏地域食品加工技
術センター
オホーツクビールde酢です
(アルコール飲料)
ビネガーファーメンタにて原材料を醸造
原材料が北見の地ビール・オホーツクビール
北見市内まちきたパラボ食品売り場などで販売不明
銀河の里ベリー園
道立オホーツク圏地域食品加工技
術センター
フルーツソース
(デザート・ヨーグルト)
自家栽培の果実を果実酢に加工、道産のグラニュー糖と寒天を加えて
ソースに
自家栽培の果実(ブラックベリー、ハスカップ、カシス)を使
用北見市内まちきたパラボと札幌・東京でも販売不明
オホーツク農業研究センター
農協婦人部
おこっぺアイス
(アイスクリーム類)
記載なし
地元の材料で製造
現在は店舗を構えるまで成長
設備と人材を充実させ、農業や水産加工のサ
ポートにも取組みたい
佐藤建設管理
道立林業試験場
ジャム
(スプレッド類)
佐藤建設がジャムに加工
自社農園で栽培・加工している
不明
ワインの生産も検討し地域の名産品に育てる予
定
つべつべGROW
構成メンバー
朱乃一振
(農産乾物)
有機肥料で育てた唐辛子を乾燥させ粉末化
地元産材料。ラベルのデザインも地元イラストレーターに依
頼。
つべつ西洋軒(GROEメンバー店舗)
今後は業務用としても販促したい
津別町有機酪農研究会
北海道三富屋
津別有機牛コロッケ
(調理品)
同会飼育の乳牛で乳の出の悪くなった経産肉用牛肉と栗山のジャ
ガイモを合わせコロッケにした
管内で有機飼料で飼育されている牛を活用
コープさっぽろの宅配便
オーガニック牛乳や有機牛肉増産し首都圏で販売目
標
端野町商工会
会員
オホーツク玉ねぎふりかけ
(調理品)
玉ねぎをスライスして炒めかつお節やいりごま、りんご酢などを加え
たオホーツク産の玉ねぎ
市内ホテルでも朝食に活用している
不明
北見ブランドの会
会員
きた味おにおんスパイス
(調理品)
みじん切りにした玉ねぎに海洋深層水と塩を混ぜてフリーズドライ後、
粉砕
オホーツク産の玉ねぎ
不明
不明
蝦夷農園
ソラチ(芦別)
蝦夷農園のたまねぎドレッシンク ゙
(食用油)
すりおろした玉ねぎがたっぷり入り和風に仕上げた
オホーツク産の玉ねぎ
不明
不明
シーニックカフェ帽子岩
大谷蒲鉾店
流氷たまご
(加工肉類)
1個80gで皮のすり身にはニンジンと玉ねぎが入り、おにぎりの具
はシソとサケの2種類
地元産業を取入れ、ネーミングにもオホーツクらしさあり
流氷硝子館内でのカフェで販売
不明
置戸町商工会特産品開発委員会
北海道麦酒醸造(小樽)
ヤーコンサイダー
(清涼飲料)
ヤーコンをすりつぶしたペーストを原料にして色は透明ですっき
りした甘み
町の特産品のヤーコンを使用している
町内の食料品店や勝山温泉ゆうゆなどで販売
JR北見駅前パラボが今後店頭販売展開するか
を検討中
ユートピア知床
①知床ジャーニー
②シャンボールベーカリー
シカ肉バーガー
(加工肉類)
シカ肉特有の臭みを消す処理後ハンバーグに。バンズは斜里産小麦
「春よ恋」使用。野菜は道内産レタスなどを季節によって使用。
原材料を地元産にこだわり使用。なにより食害対
策を有効活用している。
道の駅ウトロ・シリエトク、知床五湖レストハウスで
販売
不明
ホテル・マウレ山荘
石狩市の製粉会社と共同開発
①韃靼そばな
②韃靼そば香 (麺類)
①そば粉にバターやバニラを練り込むクッキー。②生クリームや
ラム酒で仕上げたパウンドケーキ。保存料無添加で甘さ控えめ。地元産の素材を使用。韃靼そばなの包装はソバの
花をモチーフにしている。
当面は春~秋の期間限定、ホテル売店で扱う
不明
びほろ酒倶楽部
田中酒造(小樽)
純米吟醸びほろ
(アルコール飲料)
管内農家で収穫したきらら397を田中酒造に委託して醸造
管内で収穫した米で醸造した日本酒
筒井酒販店、道の駅「ぐるっとパノラマ美幌
峠」の売店
不明
金田牧場
東京の卸売業者と商品化
流氷牛 和牛ジャーキー
(加工肉類)
1頭から10キロしか取れないスネ肉を薄く切った後、醤油や日本酒を
混ぜ特製タレに3日間漬け込むことで柔らかく仕上げた
管内で生産された流氷牛を使用
セブンイレブン津別共和店、ランプの宿森つべつ、
柿崎商店
不明
しんや
北海道バイオインダストリー
いきいき帆立オニオンスープ
(調理品)
DPTSを多く含むペーストを使用して商品を開発
オホーツク管内で栽培された玉ねぎを使用
道外生協から共同購入の引き合い、記憶障害改善作
用が認知症改善の可能性あり、高齢者介護食や病院
食使用の販売戦略
ペーストの価格が一般と比べ5,6倍高く、製品が高
価になるため価格設定が課題
①マルキタ
②農業法人香遊生活
丸加水産
オホーツクサーモン
(加工水産)
カットして塩水に漬けた紋別産オホーツクサーモンにフェンネルなど4種類のオーガ
ニックハーブを加えて密封
オホーツクサーモンや地元で採れたハーブを使用している
関東デパートでの北海道物産展
通信販売を検討(価格未定)
グリーンヒル905
網走ビール
流氷ソフトクリーム
(アイスクリーム類)
市内卯原内産牛乳使用、色は藻類のスピルリナ色素を加え青色再
現地元産原料を使用し流氷をイメージした商品
流氷街道網走にて販売
不明
竹本水産
道立網走水産試験場
ホタテのいずし
(加工水産)
米こうじ、人参と紋別産ホタテを漬け込む
紋別産ホタテを使用
2年目だが約500キロを生産、好評完売状態
商品展開で差別化を図りたい
置戸町特産品開発委員会
北海道麦酒醸造釧路工場
ヤーコンドラフト
(アルコール飲料)
原料は「北のクリーン農産物」承認を受けの町内産ヤーコンを使
用町内産ヤーコンを使用。ラベルには生産者の写真を入れ
る。
町内の小売店や飲食店で販売・提供する他、道
の駅、おんねゆ温泉でも販売
不明
ダニエル・ドゥ・ノウ
オホーツクすり身活用委員会
①ホッケバーガー
②クッキー (調理品)
①ホッケフィレをフライにし道産小麦などで作ったパンに特製ソースをかける
②乾燥後の砕いた人参やサケフレークを生地に練りこみ味を再現管内でとれた雪ぼっけ(重さ150g以下)を使用
店頭販売
網走は食材の宝庫なので今後も地元の素晴らし
さを伝えられる商品を開発
①ガトー・ロバ
②本田菓子舗
①花田養蜂園
②網走桂陽高校生徒
①みつばちぶんぶん
②ねこチーズ (乳製品)
①天然はちみつに道産牛乳やバター、生クリームを加えて煮込む
②生クリームやゼラチンの量を調節し、ねこチーズを商品化
両方とも地場の原材料を使用している
①本支店と丸瀬布温泉ホテル「マウレ山荘」て
に販売。②本田菓子舗にて冬期限定販売
不明
西興部酒店会
二世古酒造
マツタケ焼酎
(アルコール飲料)
地元の山でとれたマツタケを原料にした米焼酎。
村特産品のマツタケで製造
店頭販売
リピーターが多いからこれまで以上に味の良い
焼酎を造りたい
NPO法人 北福人
サン・グリーン
たまシュー 大地の真珠
(菓子類)
玉ねぎを皮生地に混ぜて焼いたシュークリーム
北見産タマネギを使用
JR札幌駅のどさんこプラザや北見駅前パラ
ボ、北福人のホームページで販売中
不明
土里夢(どりーむ)
酪農家3戸
①とろーりプリン②しろーいプリン③
抹茶プリン(デザート・ヨーグルト)
搾り立ての牛乳を使い改良を重ねて現在の味にたどりついた
丸瀬布酪農家三戸が共同製作、地元産牛乳原料
道の駅まるせっぷ内の木芸館
不明

59
3-2 都府県の産学官連携の動向
インターネット検索により、近年の全国の産学官連携事業の中から「フード分野」の実施状況
について調べ、図表3-2のとおりまとめました。連携支援内容の概要から類型化を行ったとこ
ろ、試験研究機関のシーズとマッチした「技術支援・研究支援」ニーズが高い傾向が見られまし
た。
それぞれの具体的な連携内容については、図表3-3に概要をまとめました。群馬県や宮崎県
の例のように、行政がコーディネート機能を発揮しながら、制度資金の活用に向けた情報提供、
販売チャンネル開拓のためのマッチング支援等によって、企業の弱みである資金面やマーケティ
ングへの側面支援を行い、課題解決に繋がった事例が見られました。中には大阪府のように、自
治体と大手企業等が連携し、地産地消の啓発運動から始まった継続的な取組として、環境保全を
重視し、地元産野菜を活用した商品開発の事例もありました。
<その他の主な支援内容>
【販売PR支援】 ・群馬県=日本アプリコット㈱「商品名:サミトールデリシャス」、県インキュベーター制度採択、ファンド獲
得・販売支援受け、商品化加速し、売上が拡大した。
・宮崎県=道本食品㈱「商品名:(かける食物繊維)干大根ドレッシング」、県クラスター協議会を窓口に農水省
食料産業クラスター事業採択及び県内外への販路拡大を支援。
【商品化・事業化調査協力】
・青森県=NAgene㈱「商品名:(遺伝子組替)海草石鹸他」、地域イノベーションプログラム採択、消費者モニタ
ー試験を実施、モニター結果の支持が高いことを受けて商品化。
【パッケージ支援】
・茨城県=(有)菊水食品「商品名:黒大豆納豆」、県工業技術センターがデザイナーの協力を得て、商品差別化・
顧客ターゲットに対応したネーミングとパッケージングの企業支援を行う。
・愛媛県=西南開発㈱「商品名:(元祖)魚肉ソーセージ」、中小企業支援制度ファンド事業活用、専門家による
パッケージデザイン開発、販売経費支援を行う。
【情報提供支援】
・沖縄県=勝連漁業協同組合「商品名:(モズク入り)ゴーヤー餃子」、商品開発に際して、開発アイデア支援か
ら商品化テスト販売・流通・店頭小売段階等 12 の組織が情報ノウハウを持ち寄り連携する。
【コーディネーター(マッチング)支援】
・大阪府=東大阪市農業啓発協議会(エコほうれん草栽培農家・市・JA 参画)「商品名:グリーンシチュー」、
ハウス食品工業が共同開発・商品化・販売することにより、事業化展開が進む。
図表3‐2 都府県産学官連携実施の状況
連携支援内容 数
1.技術支援・研究支援 272.資金支援 23.人材派遣・受入支援 04.販路・PR支援 75.コーディネーター機能 46.臨床試験実施、評価・分析 57.商品・事業化調査協力 18.パッケージ等の支援 29.その他(情報提供等) 10
計(n=43) 58

60
図表3‐3 都府県の産学官連携の動向
都府県名 商品開発名 連携支援内容
岩手県 岩手県(食産業アドバイザー) 「コンにく」(コンにく煮込みハンバーグ、コンにく餃子など)
岩手県中小企業団体中央会
※株式会社マーマ食品
宮城県 宮城県産業技術センター 抗活性酸素ゼリー「ぷちぷちゼリーの実」
※㈱フードユニテク
秋田県 秋田県総合食品研究所
JF秋田県
※八峰白神自然食品㈱〔代表企業)
㈱鈴木水産
山形県 県工業技術センター ラ・フランスパウダー
「むらやま食品加工推進部グループ」下記5社で設立
※日東ベスト㈱(㈱杵屋本店、㈱マーケティング・トレジャー、
㈱ハイスタッフ、大沼)
群馬県 財団法人群馬県産業支援機構 梅の実エキスを使った食品
群馬大学医学部 「ミサトール」「梅の実エキス」「ミサトールデリシャス」
昭和薬科大学
※日本アプリコット㈱
千葉県 千葉県産業技術研究所 レトルトゆで落花生「千葉のかほり」
東京都 東京都島嶼農林水産総合センター 魚のマリネ
※伊豆大島漁業協同組合波浮港女性部 明日葉ところてん
大島町学校給食センター(「魚のマリネ」)
石川県 石川県工業試験場 町の花木「椿」の酵母菌を使用した野々市町ブランド酒
㈶石川県産業創出支援機構 「ichi椿」
野々市町(産業振興課)
福井県 福井県農林水産部食品加工研究所 発芽玄米健康おかき「ギャバプラス」
※株式会社吉村甘露堂
福井県 福井県農林水産部食品加工研究所 健康ドリンク「米と梅のジュース」
※力泉酒造 糀亭
福井県 福井県農林水産部食品加工研究所 生きた乳酸菌が豊富な新たな漬物「コメヨーグル漬(大根、
※株式会社 越前漬物本舗 白菜、キムチ)」
長野県 長野県上伊那地方事務所 信州飯島唐辛子チェリーボムを使ったビネガー調味料
「すっぱ辛の素」
長野県商工労働部ものづくり振興課生活産業係
※内堀醸造株式会社、株式会社田切農産
信州大学
岐阜県 岐阜県(飛騨地域農業改良普及センター、農業技術課) 飛騨地域特産作物エゴマの品種選抜および
岐阜県農政部中山間農業研究所 省力機械化栽培体系の確立と新商品開発
※アルプス薬品工業株式会社
(バイオテクノロジー分野の産学官連携を推進・支援する
NPO法人東海地域生物系先端技術研究会も連携)
愛知県 愛知県産業技術研究所食品工業技術センター 酵母「五条川桜」を利用した純米酒「おおぐち」
大口町商工会
※勲碧酒造㈱
京都府 京都府立茶業研究所 てん茶の茎入りクッキー「流れ橋クッキー」
※特定非営利活動法人京・流れ橋食彩の会
和歌山県 県工業技術センター 紀州産南校梅使用「カラダにおいしい梅 とろり梅」
近畿大学先端技術総合研究所
近畿大学生物理工学部
※サッポロ飲料株式会社
鳥取県 鳥取県産業技術センター応用技術部応用生物科 海洋性フィッシュコラーゲン
鳥取県広報課
※㈲カンダ技工
島根県 連携参加者:県産業技術センター エゴマの葉の用途拡大に向けた産学官連携による機能性玉品
県農業技術センター 島根大学 の開発・販売
サポート機関等:県商工会連合会、地域活性化支援事務局
※農林漁業者:㈱オーサン(建設業)
※中小企業者:㈱山海(食料品製造業)
広島県 県食品工業技術センター
広島大学
㈱岩井商会
※㈱丸福商会
山口県 県農林総合技術センター
県産業技術センター
山口大学
※ヤマカ醤油
香川県 県産業技術センター食品研究所
※株式会社 高橋商店
香川県 香川大学
※宝食品㈱
福岡県 県新産業・技術振興課
県工業技術センター
九州産業大学
※福徳長種類株式会社
長崎県 長崎県工業技術センター (長崎県産物由来の植物性乳酸菌及び酵母を活用した加工
(長崎県内の大学) 食品の開発)
※㈱バイオジェノミクス ほか県内の食品製造業者
宮崎県 県食品開発センター 「かける食物繊維~干し大根ドレッシング」の開発
宮崎県食料産業クラスター協議会
※道本食品
※ヤマエ食品工業株式会社
大分県 大分県産業科学技術センター食品工業部 大分県の鮎を用いた魚醤「鮎魚醤」
※合名会社まるはら 原次郎左衛門
沖縄県 県工業技術センター 健康食品「モモタマナ茶」の開発
※㈱琉球バイオリソース開発
琉球大学
天然塩・白神こだま酵母による自然食品調味料を用いたハタハタ加工商品の開発・販売秋田県商工会連合会、㈶あきた企業活性化センター、地域活
性化支援事務局
千葉県レトルト落花生製造連絡協議会が中心となって開発を行い、千葉県公設試が技術支援を行った。
※野々市ブランド酒検討会参加企業・生産者(中村酒造をはじめとする酒造会社、酒米生産者)
山形県村山総合支庁の支援を受けて「むらやま食品加工推進グループ」が異業種5社で設立された。以前にラ・フランスパウダーの開発で芳香を保持したまま粉末化する技術を確立していた。これに日東ベストのパウダー化のノウハウが加わり独特の芳香を保持したパウダーが生まれた。
「2010国際ツバキ会議久留米大会:第20回全国椿サミット」の盛り上げ事業の一環で、久留米ツバキを代表する品種「正義(まさよし)」から分離した酵母と久留米産米「ヒノヒカリ」を使った焼酎の開発に取り組み、製品化に成功。
「健康長寿」推進の取組みの一つである。公募に基づいて民間活力を取り入れるという趣旨で、試験研究機関と民間と共同で健康長寿食品の研究成果を生み出すというもの。吉村甘露堂と県食品加工研究所とで、県の特産物である米を利用した健康長寿食品の開発について共同研究を行った。
越前漬物本舗と県食品加工研究所とで、地場産野菜と米乳酸発酵食品を活用した健康長寿食品について共同研究を行った。
力泉酒造有限会社と県食品加工研究所とで、県の特産物である梅を利用した健康長寿食品の開発について共同研究を行った。
桜の花から新規清酒酵母を分離することに成功。分離酵母の生理特性、安全性、醸造特性に関する検討を行った。勲碧酒造とセンターとで桜酵母による酒を共同開発し地域ブランド純米酒「おおぐち」が完成した。
島根県が進める機能性食品産業化プロジェクトにおいて、エゴマの葉がα―リノレン酸等の機能性成分を含有することが確認された。県産業技術センターはプロジェクトの中核として、㈱オーサンと㈱山海とのマッチングを行い、両者が連携するに至った。
京都府立茶業研究所が、特定非営利活動法人 京・流れ橋食彩の会と連携して開発、試作。八幡市「四季彩館」で販売。
地元の醤油メーカーであるまるはら原次郎左衛門と大分県産業科学技術センターで約4年の歳月をかけ共同開発。
平成13年度沖縄産学官共同研究推進事業の一環として、県工業技術センター、㈱琉球バイオリソース開発、琉球大学と共同で、モモタマナの葉の抽出エキスの小夜を研究。また、共同研究により、機能性評価を実施。有効成分がタンニン類であることを明らかにした。
群馬大学、昭和薬科大学との共同研究に取り組み、梅エキスに抗腫瘍効果があることを確認。①インキュベータに入居し健康補助食品を商品化。②商品PRや資金調達資金を調達し商品化を加速。③販路開拓や資金調達に成功。売り上げを拡大。
「久留米ツバキ正義(まさよし)酵母」で使った焼酎
過熱水蒸気・輻射熱の併用加熱による①「広島牡蠣」加工品の販路拡大②地場産品を活用した特産品の加工 〔受託加工)
「そら豆で作ったみそ」
県オリジナルかんきつ「せとみ」を使い産学公の連携で開発した半固形状のポン酢「かほりのジュレポン」
海藻から抽出したオリゴ糖を付加した「創健シリーズ」(「だし醤油しいたけ」他)
たくあん商品の販路は、旧来、関東圏限定的であったが、この連携では、県やセンター、クラスター協議会の協力により、宮崎空港他、地元宮崎県内への販売展開を中心としている。
相手先 (※印:支援対象企業)
宮城県などが設立した「高活性酸素食品等開発研究会」にフードユニテクが加わり、ゼリーの開発に成功し、県産業技術総合センターで、高い活性酸素機能が証明された。
鈴木水産は素材のよさを活かしつつ保存性に富んだ商品開発を目指していたが、八峰白神自然食品の天然食品調味料の開発、県総合食品研究所の天然食品調味料の最適化及び品質管理手法の確立のための指導のおかげで、連携開発がなされた。
農林水産省の競争的資金の中核機関・研究総括者として、岐阜県農政部中山間農業研究所が採択された。共同研究機関としては、同研究所とアルプス薬品工業株式会社、岐阜県(飛騨地域農業改良普及センター、農業技術課)。
千葉県レトルト落花生製造連絡協議会(※有限会社フクヤ商店)
長野県地域資源製品開発支援センター(工業技術総合センター 環境・情報技術部門)
マーマ食品は商品拡充のため「岩手県中小企業団体中央会」に支援要請した。県の食産業アドバイザー等による専門化指導を実施、施策開発を続けた結果、「コンにく」という新ブランドで販売を開始した。
町の花木である椿からとった酵母を使った日本酒を開発。
オリジナル商品の開発を考えていた内堀醸造が、唐辛子研究者である信州大学農学部准教授に相談し、唐辛子を活用した酢の開発を着想。支援機関が連携して試作を重ね、商品が完成した。
①ゴマサバなどの魚肉すり身について、製造指導、情報提供などを行った。②サメ一斉駆除で捕獲したサメ類の加工利用法について技術開発し、得られた成果を学校給食センターへ情報提供した。
サッポロ飲料株式会社から「カラダにおいしい梅 とろり梅」が発売された。パッケージにはロゴマーク(和歌山県章と和歌山県協力商品の文字)が付されて販売される。
高橋商店と県産業技術センター食品研究所は、既に「そら豆醤油」を商品化し、食物アレルギー患者に好評を博していた。その際の発酵管理技術を元に、同社が食品研究所の技術支援を受けて開発、販売。
県農林総合技術センター、県産業技術センター、山口大学、ヤマカしょうゆが連携し、「県産かんきつ類を活用した香味豊かな半固形状の食酢加工品」をテーマにポン酢を開発。
農林水産省の産学官連携開発補助事業に参画し、「過熱水蒸気と輻射熱併用加熱」による新たな加熱方法を確立。
長崎県工業技術センター平成21年度~23年度戦略プロジェクト研究。
香川県から宝食品へ、糖質バイオ研究を進めている香川大学との共同研究の紹介があり、県の支援を受けて技術開発に取組み、オリゴ糖を付加した食品を「創健シリーズ」として商品化する。
魚の鱗の有効利用を目指し、カンダ技工と県産業技術センターとで共同研究を行い、魚の鱗からコラーゲンを効率的に抽出する技術を開発し、特許出願した。

61
4.事業化可能性調査
4-1 事業化可能性の高い構想プランの抽出
開発構想段階において事業化進展の可能性が高いと考えられた企業の絞り込みについては、前
章1の1-3のとおり抽出を行い、各企業の構想内容と連携希望事項を再確認するため補足調査
を更に実施しました。
その調査結果をもとに、INO運営会議構成機関や想定される外部連携機関が有するシーズや
ソリューション等とのマッチング、また、他府県の産学官連携の取組動向を参考に検討し、その
結果を図表4-1にまとめました。
本図表に示したとおり、前章2における「事前アンケート調査」結果及び連携支援事項の検討
経過から、最終的には「商品開発支援パッケージモデル」の対象として、4事例(4社)を抽出
しました。
また、上記4事例のほか、「ワンポイントでの技術支援等が可能」、「今後とも連携希望事項に沿
い密に情報共有すべき」と考えられた 11 事例(11 社)についても、併せて類型化し、INO運営
会議において共通認識を深めるための検討原案としました。
<連携シーズマッチング判定> 連携支援判定事項 抽出数 支援のパターン
◎ 商品開発支援パッケージモデル 4社 支援パッケージモデル案を基に支援 ○ 技術指導・マッチング支援 7社 ワンポイントでの支援が可能 ◆ 情報共有・連携検討 4社 今後とも連携希望事項に沿い情報共有
図表4‐1 連携支援可能な企業の検討
商品分類 商品構想名 連携希望分野 開発時期・期間連携マッチング判定案
1-38加工水産
地元産野菜を活用したスープ 品質管理技術分野(連携あり)
着手中1年半~2年半 ◆
1-76菓子類
地元産野菜を活用したを活用した焼菓子
加工技術(餡子づくりの原料確保)
23年4月~不明 〇
2-90加工水産
地元産未利用資源を活用した複合食品
加工技術・販路拡大(味付け)
22年~3年以内◎
2-94漬物・佃煮
地元産水産資源を活用した新商品開発
加工技術(佃煮の煮方:連携あり)
24年~半年~1年未満 ○
2-119加工水産
地元産水産資源を活用したミンチ 技術指導を受けて行いたい 現在中止◆
3-171調味料
水産加工品を高次加工 加工技術(加工形態や技術)
23年~1年~2年未満 ◎
3-178加工水産
地元産水産資源を活用した水産加工品
加工技術(煮方)
23年~予定不明〇
4-198冷凍食品
地元産野菜を活用した農産加工品 加工技術(加工形態や技術)
25年~1年半~2年半未満 ◎
6-259加工肉類
地元産酪農産品を活用した生ハム製造
加工技術・機械設備導入(加工技術等:連携あり)
今後検討◆
15-325乳製品
乳製品の改良等によるチーズ製品 加工技術・制度資金等(連携あり)
23年~1年~2年未満 〇
2-95加工水産
蟹殻の有効利用 加工技術の概況把握(情報収集)
今後検討〇
2-108酒類製造
道産小麦を使用した新たな加工品の製造
加工技術・技術者派遣(加工技術等:連携あり)
23年~予定不明○
2-117水物
農産加工品の試作 加工技術(味付け)
23年~1ヶ月~半年未満 ○
2-120冷凍食品
ITを活用したアンテナショップ運用
商材マッチング 今後検討◆
9-275その他食品
地元産農産品を活用したアルコール飲料製造
試作品製造・技術者派遣 23年~1年~2年未満 ◎

62
4-2 商品開発支援パッケージモデルの提示
図表4-1における整理を基に、商品開発支援パッケージモデルについては、次の4事例を取
りあげることとしました。
<商品開発支援パッケージモデル案とする4事例>
○「5種類の魚貝類を凝縮した魚醤を活用した“オホーツク独自の調味料・調理品”
の商品化」
○「オホーツク産の未利用資源を活かした新たな水産加工品の商品化」
○「6次産業化の取組によりオホーツク産野菜を有効活用した農産加工品の商品化」
○「オホーツク産のこだわり天然蜂蜜を活用したアルコール飲料の商品化」
上記4事例について、支援の方向性を浮かび上がらせるため、次の観点から連携支援策を検討
し、それぞれの支援パッケージモデル案を提示しました。
<パッケージモデル案の検討事項>
1. 商品開発コンセプト
2. 地域貢献・地域活性化へのポイント
3. 事業化に向けた現状・課題
① 製造及び販路の課題
② 商品開発の課題
③ 開発構想上の優位性[強み]・課題[弱み]
4. 商品開発支援パッケージモデル
① 連携支援の方向性(骨子)
② 開発支援スキーム案
③ 連携支援スケジュール
④ 事業化検討事項

63
商品開発名:5種類の魚貝類を凝縮した魚醤を活用した「オホーツク独自の調味料・調理品」の商品化
1 【商品開発コンセプト】
・水産品や加工時の副産物を原料とする魚醤は、内臓や肉に含まれている酵素により動物性タンパク質等が自然発酵し造られる。
特にS社の魚醤は、原材料にオホーツクの5種類の水産品を使用し、化学調味料を一切使わず、3年仕込みで完成した旨味を売り
にしており、発酵の過程で精製される18種類のアミノ酸が含まれていることが特徴。
・身近な隠し味として様々な調理に使用されている魚醤であるが、さらに高次加工を行い、新たな水産加工品として活用の幅を広
げ、一層の普及を図ろうとするもの。
魚醤特有の臭みを改善した製法を確立することに
より水産品や加工時の副産物の活用促進が図られ
る。地域貢献・地域活性化へのポイント
【事業化に向けた現状・課題】
○製造及び販路等の課題
・原材料の調達ルートは、加工
副産物の有効活用ということ
で、充分な量を確保。
・魚醤の既存生産能力は潤沢で
あるが、製造にあたり追加的量
産ラインを必要に応じ導入する
こと。
・販路は既存の取引先のほか、
新たに学校や老人施設等での給
食需要を開拓すること。
○商品開発の課題
・新たな加工形態・方法の検
討・確立。
・自社の既存品との統一感のあ
るパッケージングの検討・作
製。
・魚醤以外の具材へのオホーツ
ク水産品の活用検討及び総合的
な商品評価。
・加工工程に応じた生産体制の
検討・設備導入対策。
■商品開発に関する技術支援 ■パッケージデザイン検討支援
連携支援の方向性(骨子)
商品開発支援パッケージモデル①
H23 H24 H25
技術検討
試作・試食
モニタリング
パッケージング
検討
販路拡大
事業化検討事項
■魚醤の顆粒化などの高次加工技術確立 ■商品タイプ及び製造工程の検討
■メジャーブランドとの差別化・購買層の検討 ■モニタリング評価を踏まえた消費者ニーズ把
握 ■販路拡大・PR等へのマッチング支援 ■他の地域食品メーカーとのコラボレーション
■評価を踏まえたオホーツクらしいパッケージ
デザイン検討
[オホーツク圏地域食品加工技
術センター]
■加工技術開発・指導等支援
[東京農業大学]
■加工技術開発・指導等支援
[日赤北海道看護大学]
■商品評価モニタリング等支援
[北見市工業技術センター]
■パッケージデザイン支援
[オホーツク総合振興局]
■関係機関マッチング
■販路拡大・PR支援
(商談会等)
S社
他の調味料
メーカー
日赤
看護大
オホーツク
総合振興局
東京農業
大学
商品開発・販売
研究開発・技術支援
連携
パッケージ支援
マッチング支援
販路拡大PR支援
コラボ商品検討
商品評価モニタリング
連携
北見工技
センター
オホーツ
ク食加技
センター
優位性[強み]
課題[弱み]
〇原材料
〇研究開発
・水産資源の有効活用
・新たな加工工程の検討
・地元産品活用と仕込みにこだ
・ブランド力のあるパッケージ
わり
〇製造
〇流通販売
・機械設備導入コスト
・安定した一定量のルートを確立
・揚げ物の開発で受賞
〇流通販売
・新たなルートの開拓

64
商品開発名:オホーツク産の未利用資源を活用した新たな水産加工品の商品化
2 【商品開発コンセプト】
・A社は、地元自治体や支援機関と連携しながら、魚醤開発等、地域資源を活用した価格向上に意欲的。資源量は未把握ながら、
これまで未利用であった地元で獲れる大型の未利用魚種に着目し、従前の一夜干し等の乾物と違った加工法に取組み、新たな付加
価値を付けることにより販路拡大を図ろうとするもの。
・当該未利用魚種は、地元では有用な水産資源を捕食する一種の害魚であり、市場単価も安く、一夜干し等の干物の原料として利
用されている。
・道内では安価な雑魚のイメージがあるので、まるごとソフトな味付けをし、道外の外食企業等への売込により需要拡大を目指
す。
地元産未利用魚種を活用した新しい商品開発を行うもので
あり、有用水産資源を捕食する害魚をオホーツク独自の地
域素材として用いるなど、未利用資源を活用した商品化モ
デルの展開が図られる。
地域貢献・地域活性化へのポイント
【事業化に向けた現状・課題】
○製造及び販路等の課題
・資源量が不安定であるため、
自社で急速冷凍した原材料を使
用しており、品質管理の検討が
課題。
・当該未利用魚種はおなかの肉
が薄く、開きにすると商品の見
栄えが良くないので、まるごと
加工する方向。
・現状、社内で試作している
が、味付け方法を検討中であ
り、地域の特性を活かした味付
け方法を詰めるのが課題。
○商品開発の課題
・味付け方法や試食モニタリン
グを反映した味の確定。
・販路は既存の取引中で、首都
圏の外食企業(居酒屋等)に流
すルートがあるので、試作品を
ベースに売込、来年度中にルー
トとして確保。
■商品開発に関する技術支援 ■販路拡大に向けたマッチング支援
連携支援の方向性(骨子)
商品開発支援パッケージモデル②
H23 H24 H25
加工技術検討・
技術支援
試作・試食
モニタリング
事業化検討事項
■味付けの方向性及び製法の検討 ■モニタリング評価を踏まえた味やパッ
ケージ検討
■ターゲットに対応した価格設定 ■販路拡大・PR等へのマッチング支援
■道外企業との連携(モニタリング等)
[オホーツク圏地域食品加工技術
センター]
■加工技術支援
[網走水試]
■加工技術支援
[地元自治体]
■商品開発制度資金支援
■道外姉妹都市での物産販売
[オホーツク総合振興局]
■関係機関マッチング
■販路拡大・PR支援(商談会等)
販路拡大
A社
地元自治体
道外の外食企業網走
水試
オホーツク
総合振興局
商品開発・販路拡大
(既存ルート)
加工技術支援
連携
制度資金支援
マッチング支援
販路拡大PR支援
商品評価モニタリング
オホーツ
ク食加技
センター
販路拡大・モニタリングの総合的な支援(連携)
優位性[強み]
課題[弱み]
○研究開発
〇研究開発
・魚醤等食品加工に実績
・味付け等製法の確立
・試食等による味の確定
〇原材料
・未利用水産資源の有効活用
○流通販売
・急速冷凍による鮮度保持
・価格確定
・道外への販路拡大
○製造
・既存の加工設備で対応
〇流通販売
・外食企業への販売ルート

65
商品開発名:6次産業化の取組によりオホーツク産野菜を有効活用した農産加工品の商品化
商品コンセプ
トの検討
3 【商品開発コンセプト】
・地元食品製造業からの野菜等の一次加工受託を主体としたU社は、経営基盤の強化に向けて、未利用の規格外野菜や関連農業法
人が生産する野菜の有効活用を検討している。
・取引先の食品製造企業が新しく導入した加工機械による低コストな野菜等の高次加工技術をヒントに、自社加工時に未利用と
なっている規格外野菜やU社関連農業法人のこだわりの農産物を活用し、6次産業化の取組として新たな商品開発を目指すもの。
・開発する農産加工品は、介護給食用の既存加工技術を応用したもので、U社は外食・菓子製造業等の業務需要をメインとしつ
つ、一部消費者市場向けの商品開発も検討しながら、新たな販路確立を目指している。
地元農産物を原料にした農産加工品の商品化に、
関連企業・支援機関等が連携して商品開発に取組
むモデル的な6次産業化の取組事例となる。
地域貢献・地域活性化へのポイント
【事業化に向けた現状・課題】
○製造及び販路等の課題
・商品化に向けた加工技術は、
取引先の食品製造企業の低コス
トな高次加工技術であり、商品
開発・製造段階における協力・
連携関係の構築が必要。
・業務用をメインとするため、
ユーザーの満足度やニーズを踏
まえた商品開発、衛生管理、レ
シピ提供等が新たな販路確立が
必要。
○商品開発の課題
・商品企画をコーディネートす
る支援機関や経営アドバイザー
等との連携。
・ターゲットの絞込み等、商品
開発コンセプトの設定。
・加工技術の支援と受託生産企
業との連携。
・想定ユーザーを対象とした商
品評価モニタリング。
・業務ルート確立後の消費者市
場向け商品の開発。
■商品開発に関するコーディネート ■ユーザーニーズに応じた商品開発支援
連携支援の方向性(骨子)
商品開発支援パッケージモデル③
H23 H24 H25
技術検討
試作・試食評価
サンプル
出荷
事業化検討事項
■商品コンセプトの検討 ■製造委託等提携企業(本社道外)・司厨士協会
■モニタリング評価を踏まえた加工技術 ・菓子協会との連携確立、試作検討
・ラインナップ検討 ■ターゲットに対応した量目・価格の検討
■販路拡大・PR等へのマッチング支援
U社
日赤
看護大
オホーツク
総合振興局
商品開発・販売
商品開発コーディネート
・技術支援
商品評価モニタリング
関係機関マッチング
販路拡大PR支援
製造委託等提携
商品流通開始
消費者向け商品検討
[オホーツク圏地域食品加工技
術 センター]
■商品開発コーディネート
■加工技術検討支援
[日赤北海道看護大学]
■商品評価モニタリング等支援
[農水省北海道農政事務所]
■S農業法人の農作物高付加価値
化に向けた取組に対し支援
[オホーツク総合振興局]
■関係機関マッチング
■販路拡大・PR支援
(商談会等)
司厨士協会
菓子協会
オホーツ
ク食加技
センター
北海道農政
事務所
商品化検討参画
・モニタリング
連携
食品製造企業
(本社道外)
S農業法人
促進事業者
として連携 自社農作物の高付加価
値化対策へ支援
6次産業化支援
優位性[強み]
課題[弱み]
〇原材料
〇研究開発
・加工時に発生する未利用資源
・商品コンセプトの設定
・関連農業法人のこだわりの農産物・製造委託等提携企業との連携確立
・ユーザーニーズに応じた商品開発
○研究開発
・安定した経営基盤
〇製造
・製造委託等提携企業との連携に下地・製造委託等提携企業との生産体制
の確立
〇流通販売
・自社ネットショップを運営
○流通販売
・試用評価による量目・価格設定
・消費者市場向け商品ニーズの把握

66
商品開発名:オホーツク産のこだわり天然蜂蜜を活用したアルコール飲料の商品化
4 【商品開発コンセプト】
・養蜂業者であるK社は、従前、生産量の大半を大手取引先へ出荷していたが、「花の種類によって異なる蜂蜜の本当の美味しさ
を伝えたい」との思いから個人向けネット販売や小売向けの出荷をはじめ数量を伸ばしてきており、中でも、K社の蜂蜜は、地域
ブランド認証も取得するなど「良品」との評価を確立している。
・こうした自社ブランドの蜂蜜の高次加工のアイディアとして、蜂蜜をアルコール発酵させて造る醸造酒に着目。オホーツク産の
こだわりの蜂蜜の持つブランド力を活かした加工品として、試作・市場開拓を目指している。
良質な産品への「こだわり」と醸造酒の「ストーリー
性」を前面に、ブランド力の高いオホーツク産品の
新たな蜂蜜製品の商品開発・市場開拓を目指す。
地域貢献・地域活性化へのポイント
【事業化に向けた現状・課題】
○製造及び販路等の課題
・K社は養蜂業及び蜂蜜の小売
販売を業としているため、酒類
製造及び販売に関してはノウハ
ウがなく、醸造免許も有してい
ない。
・商品コンセプトのコーディ
ネーターや製品試作・製造販売
を協働で行う連携先とのマッチ
ングの構築が必要。
・自社の既存取引先への売り込
みや製造販売企業との連携によ
る新たな販路が必要。
○商品開発の課題
・商品企画をコーディネートす
る支援機関との連携。
・ターゲットの絞り込みなど、
商品開発コンセプトの設定。
・試験醸造への支援と受託生産
企業とのマッチング。
・想定ユーザーを対象とした商
品評価モニタリング。
■商品開発に関するコーディネート ■開発・製造企業とのマッチング支援
連携支援の方向性(骨子)
商品開発支援パッケージモデル④
H23 H24 H25
試験醸造
サンプル醸造
商品モニタリング
事業化検討事項
■商品コンセプト及びパッケージデザイン検討 ■販路拡大・PR等へのマッチング支援
■醸造免許を有する酒類製造・販売企業との ■モニタリング評価を踏まえた商品開発
共同体制確立、試作検討
■外食企業・ホテル等の業務用ユーザーや司厨士
協会との連携確立
[東京農業大学]
■商品開発コーディネート
■試験醸造支援
[北見市工業技術センター]
■パッケージデザイン支援
[オホーツク総合振興局]
■関係機関マッチング
■販路拡大・PR支援
(商談会等)
販路開拓
商品出荷開始
K社
司厨士協会
オホーツク
総合振興局
東京農業
大学
商品開発・販売
(既存取引先)
商品開発コーディネート
試験醸造支援
関係機関マッチング
販路拡大・PR支援(商談会等)
商品販路拡大
北見工技
センター
アドバイス
酒類製造・
販売企業
外食企業・ホ
テル等の業務
用ユーザー
商品開発
モニタリング
サンプル醸造
製造委託等
パッケージ
デザイン支援
優位性[強み]
課題[弱み]
〇原材料
〇研究開発
・個性的で良質な天然蜂蜜を製造・商品コンセプトの確立
・試作・製造企業との連携確立
○研究開発
・開発品目が明確化
○製造
・受託製造企業との生産体制確立
〇流通販売
・ブランド認証がある個人向け商品○流通販売
に実績
・試用評価による商品評価
・醸造酒のストーリー性
・新たな販路確立

67
5.オホーツク地域の商品開発に期待される取組や方向性
5-1 企業側に期待される取組の方向性
(1)マーケットインを高める取組
調査結果によると、オホーツク地域では、商品開発において「地元産原材料使用による新た
な商品開発」にこだわる一方、「市場関係者や消費者のニーズ」に対する関心は低く、プロダク
トアウト(技術や思い入れなどを優先した商品開発)が高い傾向が見られました。
図表5-1は、一般的な商品開発のプロセスを示したものですが、事業化に向けた成功要因
としては、プロダクトアウトとマーケットイン(販売検討)の双方が有効な手立てとされてお
り、一方に偏らずに、双方の視点で商品開発をスタートすることが重要と考えられています。
このことから、企業側におけるマーケットインの取組について、流通事業者や消費者による
商品モニタリング等を通じ、十分な検討が行われていくことが期待されます。
具体的には、a.原材料と販売量を安定的に確保する見通しを立てること、b.ターゲットを
明確にして売り方やこだわりをまっとうすること、c.消費者が求めるボリュームやサイズでの
商品提供を心がけ、それに応じた品質保持やパッケージデザインを検討すること等のほか、d.
域外の流通事業者や大手食品メーカー等との協力によって、販売流通ルートを確保する等の検
討も必要と考えられます。
(2)商品化にストーリー性を持たせる取組
調査結果を見ると、オホーツク地域の小規模企業者の多くは、商品開発の期間が短く、マー
ケットインにコストを掛ける余裕がない実情にあり、この分野の支援を希望する企業が多くあ
りました。
消費者側において、嗜好や購買ニーズが多様化している中で、同じ商品でも特定の産地にこ
だわるなど、商品にストーリー性を求める商品選択のトレンドがあります。地域特性の“強み
(優位性)”を活かした地域資源活用型の商品開発の場合、販売段階の検討に当たっては、他地
域との差別化を一層明確にする必要があり、その商品自体にどのようなストーリー性を付加し、
アピールしていくかが重要となります。
また、地元原材料使用や商品パッケージ、ネーミングを基に「オホーツクらしさ」を訴えて
いく傾向が強いことからも、例えば、a.原料由来型、b.製法由来型、c.農法・漁法由来型、
d.伝統食・料理(法)由来型、e.自然環境・健康由来型、f.文化・歴史由来型など、生産から
販売まで一貫した商品ストーリー性を持って付加価値を確立し、商品の“強み(優位性)”に繋
がっていくことが期待されます。
図表5‐1 商品開発のプロセス
(「商品開発支援サービス業の成長戦略」大阪府立産業開発研究所(平成2年)P20~34より図表化)
①開発テーマ検討 ②商品化検討
原材料調達計画
④販売検討③生産検討
資金調達計画
マーケットニーズの把握生活志向・消費者ニーズ把握商品特性・ライフスタイル分析開発テーマ・ストーリー性設定
対象市場の明確化商品イメージの具体化商品の基本仕様設定
基本仕様・開発評価試作・実験・品質調整生産工程設計試作品テスト(販売)量産準備
販売先・市場供給計画パッケージ・ネーミング等デザイン販促・販売方法
商品テスト(評価)ユーザー反応・モニタリング物産展・商談会・アンテナショップ

68
5-2 行政側に期待される取組の方向性
(1)マーケット分野へのフォローアップの取組
他都府県における産学連携取組事例を見ると、加工技術に関する支援ニーズは、本調査にお
ける回答傾向とも概ね同様となっていました。また、こうした連携事業の中には、開発段階か
ら並行してマーケティング分野への支援を図ることにより成功に繋がっている事例も見受けら
れました。 ヒアリング調査の結果を見ると、販促・流通対策上の課題がないとした理由の背景として、
既存の取引先に加え「大手量販店を予定・販売提携で行う」として、独自の新たなマーケット
開拓にはあまり余裕のない実情が窺われました。 オホーツク地域の食料品製造業企業は、開発構想に意欲がありながらも、新たなマーケット
を切り拓く力は弱い面があると見られるため、行政サイドとしても販売チャンネルや商談会開
催等の情報提供、マーケットリサーチ・試食等商品モニタリング等の支援を進めるとともに、
各種支援事業に関する情報提供やその採択にむけたソフト面の支援を推し進めることが、商品
開発構想の事業化を一層進展させる手立てとして期待されます。 (2)地域商品の一元的情報発信支援への取組
オホーツク地域の商品開発の調査では、情報発信が新聞社地方版扱いのインソースとなりが
ちで、最大市場の札幌圏にまでは伝わりにくい状況にありました。 そのため、自治体HP等の公共媒体を活用して、観光情報・食関連イベント情報とオホーツ
ク地域の食材情報等とを結び付けて情報発信を行うなどの支援が必要と思われます。 また、行政が発信する情報は、マーケットにとっても信頼感を持って受け入れられ易いこと
から、「商品開発支援パッケージモデル」の普及促進も含め、オホーツク地域のフード関連情報
を一元的に発信することをはじめ、地域開発商品の認知度を高めるためのさまざまな情報発信
が期待されるものと考えられます。
(3)企業の商品開発意欲を支える取組
今回の調査では、フード分野におけるものづくりに対して、オホーツク地域の多くの企業が
関心を寄せ、新商品の開発意欲が高い状況にあることがわかりました。また、INO運営会議
構成機関と連携を希望する企業も多く、連携の橋渡しにより付加価値の高い商品づくりの機運
が高まる可能性が窺われました。
今後も地域における商品開発意欲を支えるため、企業訪問等の機会を活かした商品開発ニー
ズ把握や事業化相談会の開催を図るほか、企業側からの問い合わせや提案に対する技術的なア
ドバイス・商品化ノウハウの提供等に、より一層、取り組む必要があると考えられます。 こうした企業側から提示される課題や今後の事業展開に係る商品企画や技術開発等に関する
多様なニーズに答えるためには、それらのニーズ等を大学や試験研究機関等に的確に伝える場
を設けることや、産学官連携の機会を創出するためのマッチングフォーラム開催等が必要な支
援として期待されます。

69
5-3 地域の関係者に期待される取組の方向性
(1)販路拡大等への連携した取組
事前アンケート調査では、回答を寄せた企業等の半数近くが「最近3年~5年の間に改良・
開発した商品がある」と答えました。また、代表的な商品としては、地域資源を活用した「加
工水産・菓子類」が半数を占め、改良・開発構想を有する企業が 60 社に及ぶなど、オホーツク
地域では商品開発に対する企業等の意欲が高いことが窺われました。 こうした意欲の高い企業が開発した商品を、自治体等が取りまとめて地域発の商品としてP
Rに取組む例もあり、物産展の開催や出品企画支援、展示会へのブース出展、アンテナショッ
プへの出品等も活発化してきています。 最近では、札幌大通公園の「さっぽろオータムフェスト」や「札幌駅前通地下歩行空間」を
はじめ、「商業施設のイベント広場」・「大手スーパーのフェア」などが、新しい開発商品のPR
及び商品評価の場になってきています。また、これらのイベント会場には、新たな商品発掘の
ため、道外の流通バイヤーが数多く訪れることから、特に札幌圏においては、産地間競争・流
通業者間競争が一層活発化しています。 厳しさを増す産地間競争を乗り越えるためには、オホーツク地域が市町村の枠を超えて、生
産・商工・観光の各主体と共に、住民やNPO・研究機関・メディア・金融機関・行政といっ
た多様な主体によって連携・協力するネットワークを形成し、一層、企業の商品開発意欲を高
めていくこと等が重要と考えられます。また、ターゲットとする消費者市場に確実に商品提供
を行うためには、大手スーパー・コンビニ等の物流システムとの協力、百貨店バイヤーや地元
大手食品メーカーとの提携など、流通分野での連携した取組も一層必要と考えられます。 (2)地域ブランド確立に向けた取組
「食」関連産業を取り巻く環境が厳しくなる中で、オホーツク地域や市場における存在感を、
今後も維持し増大させていくためには、オホーツク地域のブランド力を高めていくことが鍵と
なります。全国的にも評価の高い豊かな「食」資源の活用と高付加価値化、その両輪となる「オ
ホーツク地域のイメージ」の確立・浸透が不可欠となっています。 地産地消意識の高まりもあって、地元の優れた食材を使用し地元のみで販売する例も数多く
見られます。こうしたこだわりの商品を、オホーツク地域に暮らす人々が、自らその価値を認
め、積極的に域外にも発信していくことで、域内にヒト・モノ・カネを呼び込み、地域経済を
持続的に活性化していく効果に繋がります。
図表 5‐2 地域ブランド形成ネットワーク
オホーツク『食』の地域ブランド形成ネットワーク
東京農大
道立総合研究機構
北見工大
日赤看護大 各省出先機関
(ハローワーク等)
市町村
消費者団体等
域外の生活者
企業・生産者
建設業関係団体
林業関係団体
生産者団体(農協・漁協)
網走開発建設部
オホーツク総合振興局
産北見工技センター
オホーツク財団(食加技センター)
金融機関等商工・観光関係団体
官学
NPO・団体等

70
また、商品開発における技術的な課題のほか、流通事業者や消費者が求めている的確な商品
情報の把握、メディアを活用した地域の食材と観光イベント等を組み合わせた効果的なPR、
市場ニーズや流通の現状を踏まえた品揃えなど、商品開発上の課題が山積していますが、ブラ
ンド化への取組は、これらの課題解決に向けたプロセスの一つ一つにおいて、消費者・流通関
係者からの認知度を高め、商品に対する信頼感を持続的に高めていくことによって確立してい
くものと考えられます。
このため、図表5-2に示すように、地域ブランドの形成・確立に向けた「オホーツク『食』
の地域ブランド形成ネットワーク」の中で、INO運営会議の取組を「産学官連携による食づ
くり産業の育成強化」の動きとして位置づけ(前図の赤字部分)ながら、地域の食関連産業に関
わる多様な主体によるネットワークづくりに地域全体で戦略的に取組んでいくことが必要と考
えられます。
(3)連携支援機能の拡充と継続化への取組
INO運営会議においては、今後の展開として「アクションプラン」を掲げ、図表5-3に
示すように、平成 24 年度以降、今回発掘されたオホーツクにおける新商品開発支援モデルの展
開と中長期的な地域のフード分野への技術的な支援等を予定しています。 地域における食料品製造企業の連携ニーズに応えていくためには、本調査における支援パッ
ケージモデルの具体化を契機として、INO運営会議構成機関を中心としたコーディネート活
動を活発化するとともに、今後とも、商品開発事例の掘り起こしや連携のきっかけづくり等の
側面的な支援を継続的に進めていくことが求められていくものと考えられます。
地域全体としては、INO運営会議の取組内容の充実とともに、今後、次のような取組が期
待されるものと考えられます。
① 地域の関係機関が連携した取組
商品開発支援パッケージモデルの事業化を加速するため、地域のネットワークを活用し
た商品評価モニタリングやストーリー性の高い商品PRの検討、物産展・商談会等の販路
拡大事業の実施など、商品化に向けて、地域一体となったバックアップが期待されます。
② 新たな事業化に繋がる取組
INO運営会議の取組事例を契機として、地域内外の資源を結び付けた多様な商品開発
コンソーシアムの形成が進められるよう、産学が連携した開発技術の応用など、新たな事
業化に結びつける取組が進められることが期待されます。
③ リーディング商品の発掘と地域外発信の取組
支援パッケージモデルの商品やオホーツク地域でつくられている既存商品については、
新しいPR手法の導入やストーリー性を構築するなどして、札幌圏・首都圏等に発信する
ことによって「売れるリーディング商品」となる可能性を秘めています。
例えば、「食」関連情報のデータベース化やサイト開設、ネット上のアンテナショップ開
設等によりさまざまな機会を通じてマーケットに積極的にPRするほか、関連イベントを
通じて幅広く情報発信に努めることが期待されます。
図表 5-3 アクションプラン・ロードマップ H23 H24 H25
新商品開発モデル
「オホーツク食創出モデル」
商品開発・事業化ニーズ調査
(4月~9月)
タイアップ企業発掘・連携
出前新商品開発室の実施
(局独自事業)
商品コンセプト検討
企業個別訪問
技術的課題の
洗い出し等
シーズ&ニーズ・マッチ
ングフォーラム(局独自
事業)
商品開発コンセプト(機軸)の設定
プレイヤー・推進体制の明確化
競争的研究資金応募支援制度要請等
支援プロジェクトの検討・予算要求
試作品発表会・試食会
(局独自事業)
製品完成!
(
試作品ベース
)
プロジェクト推進事業パッケージ
機能性分析・評価
安全性確保
生産技術開発
資金対策
流通対策
新商品事業展開・普及PR事業・物産展参加・販路拡大事業 など
Ⅰ・N・オホーツクを核としたコンソーシアムによる新たな事業展開を検討(応用技術活用等)
企業個別訪問