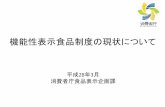ジョイナス保育園 12月給食献立表 · 2020. 11. 28. · 日 曜 行事 朝間食 昼食 おやつ ジョイナス保育園 12月給食献立表 牛乳 ポテトサンド
食事のマナー発表
Click here to load reader
-
Upload
eiji-tomida -
Category
Education
-
view
470 -
download
4
Transcript of 食事のマナー発表

・教師の人柄について
論文①
【調査方法】
112 名の大学生と 157 名の現職教師に小学校、中学校、高校の理想的な教師の特性に関す
る自由記述を求めた。
【結果】
大学生は教師の人間性に関する特徴を理想的教師像において重視しているのに対して、現
職教師は、
児童・生徒の理解を最も重視していることが示された。
大学生においては「干渉しすぎない」「対等に付き合う」「やさしい」「おもしろい」などの
生徒への対忚及び人間性に関する特徴を重視しているのに対して、
現職教師は、生徒指導・学習指導全般に関わる特徴(「生徒との信頼関係がもてる」「指導力
がある」「教科専門の知識がある」「教育への情熱がある」)を重視している。
この結果から、両者の理想の教師像にはズレが生じており、教師は生徒が教師に最も求め
ていることを十分に認識できていない可能性があることがわかった。
論文②
本論文では、学生による授業評価と達成動機の関連について書かれている。
【調査方法】
大学生に授業評価をアンケート形式で求めた。なお、授業評価の際、学生は試験結果など
成績については知らされていなかった。
アンケートでは授業評価、自己評価、授業に対しての満足度、授業担当教員の人柄の良さ、
達成動機について聞いており、授業担当教員の人柄についての主な項目は以下の4つであ
る。
・この授業の担当教員は友好的である
・この授業の担当教員は熱意がある
・この授業の担当教員には親しみが持てる
・この授業の担当教員にはユーモアが感じられる
これ項目の得点が高いほど、授業担当教員の人柄についての評価が高いことを示す。
【結果】
教員の人柄についての得点が高いほど、満足度、自己評価、授業評価の得点も高かった。
授業評価において学生は教員の人柄の良さを重視する傾向がある。

【結論】
教師の人柄の良さは、授業評価、自己評価による学習内容の理解と関連がある。
論文③
【調査方法】
小学5年生・中学2年生・小中学校教師を対象に,児童生徒の学校生活全体にかかわる教
師影響力の認知について,分析を行った。また,学習場面に限定された教師影響力の認知
についても分析を行った。さらに,主観的・客観的意欲の高さによるタイプ別の学習場面
影響についても検討した。調査用紙は各担任から児童・生徒に配られ,授業時間内に回答・
回収した。
【結果】
学校生活全体への影響において,現在の小学生は,教師としての信頼や親しみやすさに影
響を受けやすく,中学生は罰を感じさせる教師の影響を強く受けやすいことを見出した。
学習場面の影響については,小学生は,親しみを感じる教師であると意欲的に学習ができ
ると感じ,中学生は,信頼感があり親しみを感じる教師であると意欲的に学習ができると
感じていた。また,学習意欲の低い児童・生徒には,教師との良い人間関係を構築するこ
とが学習意欲を高めるために特に重要である。
【結論】
児童・生徒は,「快くない」罰や厳しさの影響を除けば,学校生活全体においても,
学習場面においても,「信頼感」や「親しみ」といった,人間関係の影響を強く受ける。つ
まり,教師が大切にしなければならないものは,子ども一人一人と触れ合いよい関係を構
築することであり,この良好な人間関係がひいては,学校生活を能動的に送ることができ
る児童・生徒,さらには学習を意欲的に行うことができる児童・生徒の育成につながる。
子どものためを思い,教材や授業形態を工夫してもよい関係が構築されていなければ,せ
っかくの努力も無駄になる可能性が高い。多忙な日常の中でも,教師は子どもたちとのよ
い関係の構築が重要であることに目を向け,そのために費やす時間を作り出す努力をすべ
きであろう。ただし,よい関係の構築において,子どもたちが求めるからといって,子ど
もの言うなりになるのではいけないことを忘れてはならない。現在の学級崩壊は「馴れ合
い」の中から,発生しているとも言われている。親しみと馴れ合いを混同しないよう,悪
いことに関しては毅然とした態度で接することは当然である。
論文④
本論文では「興味」と「努力」の関係について書かれている。

【事例】
積み木で遊んでいる尐年がいる。彼の興味は「積み木の城をつくること」に向いている。
そして彼は目的を達成するには遭遇した困難を乗り越えなければならないことや、
そのためには技術が必要だということにも気づいている。だから彼は目的のみならず、そ
の手段にも興味を持ちうる。
【結論】
「興味」を持たないのならば、「努力」にも「興味」を持たない。
【考察】
生徒がある科目の授業担当教員に興味を持ち、目的を「授業担当教員に好かれる」とした
場合、生徒はその教科に対しての努力にも興味を持つだろう。





![農産物等の食品分類表 厚生労働省食品安全部 …...農産物等の食品分類表 厚生労働省食品安全部 [2015.8版] 食品名 食品分類 あおうり しろうり](https://static.fdocument.pub/doc/165x107/5e28e49034b5f41845388afd/eccceee-cfcoeeef-eccceee.jpg)