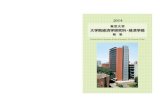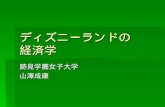2013 年度 上智大学経済学部経営学科 網倉ゼミナー...
Transcript of 2013 年度 上智大学経済学部経営学科 網倉ゼミナー...
2
<はじめに>
2013年のシリーズを制覇したのは創設からわずか 9年の楽天ゴールデンイーグルスであった。
同シリーズ第 7戦の平均視聴率は仙台地区 44.0%、関東地区 27.8%、関西地区で 32.0%であり、
東日本大震災の復興のシンボルとしての役割も担う楽天の優勝という結果をさし抜いてもその
注目度の高さは際立っていた。ワールド・ベースボール・クラシック(WBC)においても高い
注目を集めており、いまだに野球人気は根強いように思われる。しかしその一方で、日本の W
杯初出場や日韓ワールドカップの開催以来サッカーの人気向上、プロ野球の人気低迷が叫ばれて
久しい。(ex. http://chosa.nifty.com/cs/catalog/chosa_report/catalog_120816000916_1.htm
)幼少の頃より、野球を愛してきた筆者にとってはこの上なく寂しいものであるが、自分の感覚
とは少々異なるところもある。一チームレベルの人気低迷がリーグ全体の人気低迷に拡大解釈さ
れているのではないかなど、様々思うところがある。このことが、私がこのテーマを選んだきっ
かけである。
本論文の目的は、「プロ野球人気の低迷」の認識に繋がっていると考えられる諸要因を一つず
つ検証することでプロ野球の人気に関する現状を正しく把握することである。その際、客観的か
つより多面的に捉えていきたい。
3
目次
はじめに P.2
仮説 P.4
1章 テレビ中継 P.5
<1-1>巨人戦
<1-2>地上波以外のチャネルによる放送
<1-3>ローカル局でのプロ野球中継
2章 観客動員数 P.13
3章 若年層の野球人気 P.15
4章 結論 P.18
5章 おわりに P.19
参考文献 P.20
4
仮説
本論文の目的は、プロ野球人気の現状について客観的に把握することである。また、それを通し
て見えてきた課題等を整理することによって、本論文が 00今後のプロ野球界の発展の一助とな
ることが出来たら幸いである。
本論文は、二つの仮説を中心に進めていく。
① 「地上波巨人戦の視聴率低下=プロ野球人気の低下」の構図が成り立っている。(1章)
② 観客動員数は減少傾向にあり、球場での観戦も減ってきている。(2章)
5
1章. テレビ中継
この卒業論文を進めていくうえで、「人気」とは何かということに最初に触れておきたい。
辞書によると「人気」について 1.人々の気受け。世間一般の評判。2.その土地の人々の気風。と
いう二つの意味が主にあげられている。本論文では、この二つの中でも 1 の方の意味で人気を
捉えていくが、気受けは定性的な側面が強い。よって今回は「気受け」を「どれだけ多くの人が
プロ野球を見た(観た)か」として考える。気受けが良ければ、より多くの人がプロ野球を見る
(観る)はずであるということを前提とする。
プロ野球人気を考えていくうえで、必要な要素の一つが 1 章のテレビ中継である。プロ野球人
気が論じられる際、視聴率はその根拠として頻繁に用いられる。プロ野球の視聴率と一口に言っ
てもメディアや対戦カードによってその意味合いは変わってくる。ここではプロ野球の視聴率を
単に一括りでとらえるのではなく、より細分化して考察していきたい。
<1-1>巨人戦
地上波、BS、CS などを含めて最も放送されているのが巨人戦である。戦後期には、「巨人、大
鵬、卵焼き」と言われ国民的人気を誇った読売巨人軍(以下、巨人と表記)は、その後の V9時
代を経て人気・実力ともに球界を代表する球団となった。巨人は、球団の創設者であり初代オー
ナーであった正力松太郎氏が日本テレビ放送網の代表取締役社長だったこともあり、他球団より
はるかに多くテレビ中継されてきた。実際、幼少期から巨人のファンであった私は毎日のように
その中継を見て育った。しかし、その巨人戦のテレビ中継も地上波から姿を消しつつある。
図 1.地上波ゴールデンタイムにおける巨人戦の放送試合数
(http://www.my-favorite-giants.net/giants_data/audience-rating.htmを基に作成)
0
20
40
60
80
100
120
140
試合数
6
図 1は過去 10年間の巨人戦の地上波放送(ゴールデンタイムにおける)の試合数の推移を示し
ている。年間の試合数は若干の多少はあるがおよそ 140試合前後である。2004年は全 138試合
中 133試合がゴールデンタイムに地上波で放送されている。しかしその後は減少の一途を辿り、
2013年の放送は 144試合中わずか 7試合にとどまった。デーゲームが増えたことを考慮しても、
この減少率は際立っている。では視聴率はどうか。
図 2.巨人戦の年間平均視聴率
(http://www.videor.co.jp/data/ratedata/b_index.htm を基に作成)
図 2 は 1965 年~2009 年の巨人戦の年間平均視聴率の推移を示している。放送される試合数の
顕著な減少から察しが付くかもしれないが、巨人戦の視聴率は 2000 年以降減少の傾向にある。
ピーク時の 1983 年には年間平均視聴率が 27.1%を記録したものの、近年は 10%前後にとどま
っている。他媒体の優位性が向上してきたことによって顕著になった「テレビ離れ」によって視
聴率自体が低下の傾向にあることを加味しても、低い数字のように思える。図 1 と図 2 が示す
変化をそのままの形で読み取れば、確かにプロ野球人気は低迷していると言えるだろう。
0.0%
5.0%
10.0%
15.0%
20.0%
25.0%
30.0%
1965年
1968年
1971年
1974年
1977年
1980年
1983年
1986年
1989年
1992年
1995年
1998年
2001年
2004年
2007年
視聴率
7
<1-2>地上波以外のチャネルによる視聴
1-1 ではメディアに頻繁に取り上げられる地上波放送について考察してきたが、視聴するチャ
ネルが多様化している今、それだけでは不十分である。次は BSや CSなどの衛星放送やネット
中継について考察する。今回はプロ野球を比較的多く扱っている BSとスカパーについてみてい
きたい。
図 3.BS放送の受信普及数の推移
(http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/eisei/eisei.pdf より引用)
グラフの青部分は BSアナログ、緑部分は BSデジタルを表している。
8
図 4.スカパーの加入者件数の推移
(http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/eisei/eisei.pdf より引用)
記述の通り、図 3 は「BS 放送の受信普及数の推移」を図 4 は「スカパーの加入者件数の推移」
を示したものである。この図 3,4 の推移はプロ野球中継と直接的な関係があるわけではないが、
地上波以外でプロ野球を視聴する環境が徐々に広まりつつあることを意味している。BSとスカ
パーについて考察していくうえで、先ずは地上波放送・BS・スカパーのプロ野球中継の特徴を
それぞれ整理する。
地上波放送
・民放を中心に放送開始時間が試合開始時間より遅い。
・予定時間を過ぎた際、延長の措置が取られることもあるがゲームセットまで放送されないこと
も多々ある。
・他の番組宣伝の為に、タレント等がゲストとして解説に加わることなどがある。
・CMが多い。
BS放送
・試合開始時間から視聴できることが多い。
・試合が長引いても、ほとんどの場合ゲームセットまで放送される。
・CMが少ない。
スカパー
・有料のコンテンツである。
・公式戦の全試合が放送される。
・全試合徹底放送で試合開始からゲームセットまで必ず見ることができる。
・試合中継に加え、プロ野球関連番組も見ることできる。
0
50
100
150
200
2502002年
2003年
2004年
2005年
2006年
2007年
2008年
2009年
2010年
2011年
2012年
2013年
個人契約数(万件)
9
以上に挙げた特徴を簡単にまとめると、
地上波放送→BS放送→スカパーの順にサービスの充実が図られているということである。地上
波放送を視聴する比較的ライトな層からスカパーに加入するようなコアな層まで各々が棲み分
けられている。図 2を参照すると、地上波の巨人戦の視聴率の減少率が高いのは 2000年前後で
ある。そしてそれとほぼ同時期に BSデジタル受信やスカパーの導入が始まっている。これらの
ことを考慮すると、地上波の巨人戦における視聴率低下は短絡的にプロ野球人気の低迷に繋げて
はいけないものであり、それが本来的に意味するものは BSやスカパーへの視聴者の分散ではな
いだろうかと思える。
図 3.4では BS放送の受信件数とスカパーの加入件数の増加傾向を示したのみだったため、次で
はそれをプロ野球中継というところに落とし込んでいきたい。まずは BS放送から見ていく。視
聴率を調べることができればそれが最も良いのだが、衛星放送では番組個別の視聴率が出ていな
いため、放送試合数からアプローチする。(図 1.2 より視聴率の低下→中継試合数の減少が読み
取れることから放送試合数は視聴率の代替となりうる有効な指標として採用する)
巨人の主催試合を放送する BS日テレでは 2005年は 4試合のみの放送だったが、その後増え続
け、2012 年には 61 試合の放送となった。その他にも BS-TBS では 2013 年に開局以来最多の
47試合が放送され、2008 年から開始した twellv では毎年 60試合前後の放送がある。以上のよ
うに BS放送でのプロ野球中継は軒並み増加傾向にある。
では次にスカパーを見ていく。スカパーではプロ野球に特化したパックがある。残念ながらプロ
野球パック契約者の推移を示すデータは部分的にしか得られなかったが、2006 年から 2007 年
にかけてプロ野球パック契約者は 30%増加している。(2007/11/05日経新聞より)
母数がわからないのでこの 30%の増加率がどれほどの意味を持つかについては明らかにできな
いが、スカパーがプロ野球視聴の選択肢として確実に普及してきていることは示せていると考え
る。
1-2 では地上波放送以外のチャネルとして BS 放送とスカパーについて考察した。どちらも視
聴率や契約者数を調べられずに正確な数字として把握することはできなかったが、BS放送もス
カパーもプロ野球視聴のチャネルとしての環境が整ってきていることはわかる。少なくとも、地
上波の視聴率だけを見て人気の有無を判断していい時代ではなくなっていることは明白である。
10
<1-3>ローカル局でのプロ野球中継
1-3 では地上波でもキー局でなくローカル局の方について見ていきたい。プロ野球球団が本拠
地を置く都市のローカル局のほとんどは、自社制作によるプロ野球中継を行っている。
その例として、
・マリーンズナイター(千葉テレビ)
・横浜 DeNAベイスターズ熱烈 LIVE(テレビ神奈川)
・TVSライオンズアワー(テレビ埼玉)
・TVQ スーパースタジアム(TVQ九州放送)
などが挙げられるほかにも、各地で地元球団のプロ野球中継がなされている。ローカル局の自主
制作で放送されるプロ野球中継は、地元球団に偏重している点が特徴であり、キー局のそれとは
多少異なる。好みや趣向も関係してくるが、地方の地元球団を応援しているファンにとってはロ
ーカル局の中継は非常に魅力的のように思える。ファンからしたら魅力的でも、果たして放映権
を払って放送するテレビ局側にとってはコンテンツとしての魅力があるのだろうか。当然のこと
ながらテレビ局にとっては視聴するだろう人(あるいは世帯)が多ければ多いほど魅力が高い。
そこで地域別の好きな球団ランキングを参照する。
11
図 5.地域別好きな球団ランキング
順位 北海道 東北
1 北海道日本ハムファイターズ 75% 東北楽天ゴールデンイーグルス 42%
2 読売ジャイアンツ 6% 読売ジャイアンツ 21%
3 阪神タイガース 3% 東京ヤクルトスワローズ 5%
順
位 関東 北陸・甲信越
1 読売ジャイアンツ 29% 読売ジャイアンツ 23%
2 阪神タイガース 9% 東北楽天ゴールデンイーグルス 6%
3 横浜 DeNA 5% 中日ドラゴンズ 6%
順位 東海 関西
1 中日ドラゴンズ 42% 阪神タイガース 46%
2 読売ジャイアンツ 19% 読売ジャイアンツ 15%
3 阪神タイガース 9% オリックスバファローズ 3%
順位 中国・四国 九州
1 広島東洋カープ 27% 福岡ソフトバンクホークス 44%
2 読売ジャイアンツ 21% 読売ジャイアンツ 15%
3 阪神タイガース 14% 阪神タイガース 7%
(http://chosa.nifty.com/cs/catalog/chosa_report/catalog_120816000914_1.htm より引用)
12
図 5 を見ると、プロ野球球団が本拠地を構えていない北陸・甲信越地域以外はすべて地元球団
がランキングの 1 位になっていることがわかる。全地域において高い人気を誇る巨人はやはり
全国放送に最も適していると言えるが、殊ローカルの放送においてはその地元球団の方がコンテ
ンツとしての魅力は高いと言える。実際、コンテンツの有力さを示す根拠もある。テレビ札幌で
は 2012 年 4 月の視聴率ランキングの TOP10 を北海道日本ハムファイターズ戦が独占した。1
位の 4月 13日「日本ハム×楽天」は 30.8%を記録している。その他にも名古屋テレビでの中日
戦、広島テレビでの広島戦、KBC 九州朝日放送でのソフトバンク戦などはいずれも安定して二
桁以上の視聴率を獲得しており、広島テレビが昨年放送したクライマックスシリーズ「広島×巨
人」は平均視聴率 40.2%を記録した。
1-3 をまとめて言えることは、プロ野球中継はローカルソフト化してきているということであ
る。「アンチ巨人というファン(野村、2006)」という表現もあるほど未だ球界の盟主として存
在している巨人であるが、巨人戦だけを放送していればいいという時代はとうに終わっているの
である。地域に細分化し、ミクロな視点で捉えていけばまだまだプロ野球は魅力的なコンテンツ
である。
1章まとめ
1章では主にメディアで用いられる「地上波の巨人戦の視聴率低下=プロ野球人気の低下」とい
う構図に対しての疑問を検証してきた。1-1 より地上波の巨人戦の視聴率低下は確かである。
しかし、
①「テレビ離れ」が進んでおり、そもそも視聴率自体低下の傾向にあること。
③ BSやスカパー等のチャネルの拡大により、プロ野球視聴の選択肢が広がっていること。
④ ローカル局による地元球団の試合中継では高い視聴率を記録していること。
これらを加味すると「地上波の巨人戦の視聴率低下=プロ野球人気の低下」という構図はあまり
にも短絡的に思える。
以上より、「地上波巨人戦の視聴率低下=プロ野球人気の低下」の構図が成り立っているとする
仮説①は棄却された。
13
2章. 観客動員数
1章で扱ったテレビ中継に対して、2章では直接球場に足を運んで試合観戦した人の数である観
客動員数について見ていきたい。
図 6.セントラル・リーグ 1試合平均入場者数の推移
(http://www.npb.or.jp/statistics/attendance_yearly_cl.pdf を基に作成)
図 7.パシフィック・リーグ 1試合平均入場者数の推移
(http://www.npb.or.jp/statistics/attendance_yearly_pl.pdf を基に作成)
25,000
25,500
26,000
26,500
27,000
27,500
28,000
28,500
29,000
29,500
30,000
1試合平均入場者数
18,500
19,000
19,500
20,000
20,500
21,000
21,500
22,000
22,500
23,000
1試合平均入場者数
14
図 6,7 は各リーグの 1 試合平均入場者数の推移を示している。2004 年以前は水増ししたデータ
が発表されているため、実数発表されている 2005年以降のデータを採用している。
図を参照すると分かるように多少の増減はあるものの、2005 年と 2013 年を比較するといずれ
のリーグにおいても数字は伸びている。とりわけパシフィック・リーグ(以下パリーグと表記)
は昨年の観客動員数が過去最高であり、人気が高まっていることが顕著に表れている。巨人や阪
神タイガース(以下、阪神と表記)といった人気球団を抱えるセントラル・リーグ(以下セリー
グと表記)とはまだまだ差があるが、各チームが地域密着型の経営を推し進めると同時に、リー
グ単位でもパリーグ主催の全試合のライブ動画を配信する「パリーグ TV」等の独自のコンテン
ツを行っている。今ではかつての「人気のセ・実力のパ」から「人気のパ・実力もパ」になって
きているという意見も多い。
図 8.「人気のセ、実力のパ」現在は?
(http://number.bunshun.jp/articles/-/127721/feedbacks?per_page=10 より引用)
以上の通り、観客動員数は決して減少しているとは言えない。2005年と 2013年を比較すると、
いずれのリーグでもむしろ増加している。パリーグに至っては、過去最高となっており観客動員
数の推移からプロ野球人気の低迷を導き出すことはできないと判断する。よって、観客動員数は
減少傾向にあり、球場での観戦も減ってきているとする仮説②は棄却された。
31.7%
6.7% 61.7%
「人気のセ・実力のパ」
「人気のセ・実力もセ」
「人気のパ・実力もパ」
15
3章. 若年層の野球人気
1.2章における仮説の検証を通して、現状としてプロ野球人気低迷を決定づけることはできない
と判断した。しかし、果たしてプロ野球人気は盤石なのだろうか。今後について述べることはで
きないが、3章では現状における課題を自分なりに考えて考察していきたい。
図 9,小学生のよくやるスポーツトップ 5(男女各 618人、回答人数 1236人、複数回答可)
順位 よくやるスポーツ 全体
人 %
1 なわとび 408 33.0%
2 かけっこ 387 31.3%
3 水泳 309 25.0%
4 ドッジボール 297 24.0%
5 サッカー 295 23.9%
図 10,小学生の一番好きなスポーツトップ 5(男女各 618人、回答人数 1236人)
順位 一番好きなスポーツ 全体
人 %
1 サッカー 201 16.3%
2 水泳 152 12.3%
3 なわとび 105 8.5%
4 ドッジボール 100 8.1%
5 野球 90 7.3%
(http://www.gakken.co.jp/kyouikusouken/whitepaper/201112/chapter3/01.html より引用)
図 9.10ではそれぞれ小学生のよくやるスポーツと一番好きなスポーツのトップ 5を示した表で
ある。かけっこを除いて、よくやるスポーツのトップ 5 が一番好きなスポーツの 1 位から 4 位
を占めており、二つの変数の間に一定程度の相関関係が見受けられる。野球を見てみると、好き
なスポーツトップ 5 にはかろうじて入っているものの、よくやるスポーツには入っていない。
よくやるスポーツトップ 5 は体育の授業において扱われる機会が多いように感じるが、野球は
どうだろうか。現行の学習指導要領では中学年でハンドベースなどのベースボール型ゲームを、
高学年ではソフトボールを指導することとしている。しかし、技能の個人差が顕在化しやすく、
個々の技能がある程度に達していないとゲームが停滞し、楽しさが損なわれてしまうなど導入へ
の障壁は高い。実施状況は学校によって異なるものの、小学校における野球またはそれに類似し
たスポーツに触れる機会はサッカーをはじめとする他のスポーツと比較して限られているよう
に思える。では学校以外ではどうだろうか。学校以外考えられる場所として、公園を考えてみる。
16
図 11,公園におけるキャッチボールの使用状況(回答 21都市)
図 12,公園におけるバットの使用制限状況(回答 24都市)
(http://www.posa.or.jp/catchball/purpose04.html より引用)
52%
8%
40% 全面禁止
日時・場所により禁止
禁止していない
58%
7%
35% 全面禁止
日時・場所により禁止
禁止していない
17
図 11,12 を見るとおよそ半分以上の公園でキャッチボールとバットの使用が禁止されているこ
とがわかる。学校でも公園でも、野球と接触する機会はほとんどないのが現状である。
図 13、小学生の将来就きたい職業(男子、プロサッカー選手とプロ野球選手の比較)
(http://www.gakken.co.jp/kyouikusouken/whitepaper/201009/chapter2/12.html を基に作成)
小学生の将来就きたい仕事において、プロサッカー選手とプロ野球選手は 1,2位を独占した。高
学年においてはプロ野球選手がプロサッカー選手を上回ったが、それ以下では大きく水をあけら
れている。やはり年齢が低くなればなるほど野球人気は下がっているようである。図 9,10 で示
したように頻度と人気度には一定の相関関係がみられる。よって、学校にしても公園にしても子
供たちが野球に接する機会を今以上に増やしていかないと今後の野球人気、プロ野球人気は危う
い。プロ野球のコンテンツとしての魅力を高めていく努力は勿論不可欠だが、野球を出来る環境
をより整えていくという異なる視点も交えて考えていかなければならない。
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
1年生 2年生 3年生 4年生 5年生 6年生
プロサッカー選手
プロ野球選手
18
4章. 結論
1 章と 2 章ではテレビ中継と観客動員数からプロ野球の人気を比較的興行的な面から考察した。
結論から言うと、仮説①②は棄却されたためプロ野球人気低迷を断言することはできないという
ことである。地上波や巨人といったミクロな部分での問題を、プロ野球全体の話に拡大して解釈
しているため、「プロ野球人気の低迷」という言葉だけが独り歩きしてしまっているのである。
よりマクロな視点で捉えると、地上波→衛星放送、巨人→他球団という風に“分散”が起こって
いることはわかるだろう。セリーグはまだまだ人気球団への依存体質が強く改革が進んでいる印
象が薄いが、パリーグは地域密着型経営の推進や独自コンテンツの配信などの改革を行い、着実
に人気を伸ばしている。このことが示しているのは、プロ野球がまだまだ伸びしろのあるコンテ
ンツであるということだ。しかし、プロ野球人気が低迷していることはないと言っても、その基
盤は必ずしも安定しているとは言えない。そのことを示したのが 3 章である。地上波放送の減
少によりライト層の取り込みが難しくなっていることに加えて、公園等での球技の禁止等で小学
生などが野球に接する機会も限られてきている。小学生の将来就きたい仕事で 1 位の座をプロ
サッカー選手に譲ってしまったところにも、その影響の一端を見ることはできる。これらの課題
を整理し、解決策を模索していくことが求められる。
19
5章. おわりに
筆者は幼少の頃より野球大好き少年であり、プロ野球とともに育ったといっても過言ではない。
そんな筆者にとって、たびたび目にする「プロ野球人気の低迷」という文言は非常に辛いもので
あった。今回、卒業論文で本テーマを扱い、その論を棄却できたことに筆者自身ある種の安堵感
を得られたのは間違いない。しかし、常日頃から網倉先生がおっしゃっている“面白さ”という
観点から見ると、随分不十分なものになってしまったと感じている。卒業論文の作成に当たり『ヤ
バい経済学』を一読した。まさしく“面白い”ものがそこには詰まっていた。そこを究極の目標
として掲げて臨んだが、事象を批判的に捉える目や自らの仮説を検証するための知識・技術が自
分には圧倒的に欠けていることを痛感した。面白さ以外にも、必要としていたデータを集められ
ずに遠回しの表現をせざるを得ない場所が数か所あったのは反省点として挙げられる。本来なら
スカパーの野球パック契約者数のデータを示さなければならないところで、スカパー全体の加入
者数の推移しか示すことが出来なかったところがその一例である。
反省点は非常に多いが、今回の卒論執筆で得られた経験は非常に大きいと感じる。これを無駄に
しないためにも、再度課題等を整理し今後に生かしていきたい。
20
<参考文献>
スティーブン・D・レヴィット/スティーブン・J・ダブナー
『ヤバい経済学』東洋経済新報社 2013/4/23
並木裕太『日本プロ野球改造論―日本プロ野球は、日本産業の縮図である!』
ディスカバー携書 2013/4/5
大坪正則『パ・リーグがプロ野球を変える―6球団に学ぶ経営戦略』朝日新書
2011/3/30
野村克也『巨人軍論―組織とは、人間とは、伝統とは』角川 Oneテーマ 21
2006/3/10
野村克也『読売巨人軍黄金時代再び』宝島社新書 2013/6/24
<参考 URL>
ビデオリサーチ http://www.videor.co.jp/data/ratedata/b_index.htm
衛星放送の現状 http://www.videor.co.jp/data/ratedata/b_index.htm
Nifty何でも調査団
http://chosa.nifty.com/cs/catalog/chosa_report/catalog_120816000914_1.htm
日本野球機構オフィシャルサイト http://www.npb.or.jp/
Number Web http://number.bunshun.jp/articles/-/127721/feedbacks?per_page=10
学研教育総合研究所
http://www.gakken.co.jp/kyouikusouken/whitepaper/201112/chapter3/01.html
キャッチボールのできる公園づくり http://www.posa.or.jp/catchball/purpose04.html