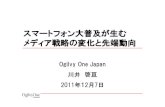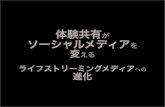《アフィリエイトの最終兵器》 SMO(ソーシャルメディア最適 … · 2016-01-07 · smo(ソーシャルメディア最適化)の定義 SMO(Social Media
2...
Transcript of 2...

ソーシャルメディアの普及がもたらす変化 第 2節
ソーシャルメディアの普及がもたらす変化第2節
第1節では新たなICT端末のインパクトについて述べたが、アプリケーションにおいて近年普及が著しいものとしては「ソーシャルメディア」が挙げられよう。ソーシャルメディアとは、インターネットを利用して誰でも手軽に情報を発信し、相互のやりとりができる双方向のメディアであり、代表的なものとして、ブログ、FacebookやTwitter等のSNS(ソーシャルネットワーキングサービス)、YouTubeやニコニコ動画等の動画共有サイト、LINE等のメッセージングアプリがある
(図表4-2-1-1)。ソーシャルメディアには利用者同士のつながりを促進
する様々なしかけが用意されており、互いの関係を視覚的に把握できることが特徴である。2000年代以降、世界的に普及し、インターネットの活用において重要な存在となった。たとえば、Facebookのアクティブユーザー数は2015年3月時点で全世界14億人に達している(図表4-2-1-2)。更に2000年代末以降のスマートフォンの普及は、生活の中でソーシャルメディアをいつでもどこでも利用可能にし、位置情報等のスマートフォンの様々な機能と連携して、その活用の幅を広げた。
図表4-2-1-2 Facebook、Twitterのユーザー数の推移
02004006008001,0001,2001,4001,600(百万ユーザー)
3億200万ユーザー
14億4,100万ユーザー
Twitter Facebook
2011年3月
2011年6月
2011年9月
2011年12月
2012年3月
2012年6月
2012年9月
2012年12月
2013年3月
2013年6月
2013年9月
2013年12月
2014年3月
2015年3月
2014年6月
2014年9月
2014年12月
(出典)各社公表資料より作成
ソーシャルメディアの普及が進み、生活に密着した情報交換が行われるにつれて、情報交換だけではなくモノの貸し借りに活用されることも出てきた。多数の利用者が参加することで多様な交換の可能性が広がってきたのである。このような貸し借りを仲介する様々なサービスも出現してきており、新たな経済活動として「シェアリング・エコノミー」と呼ばれている。本節ではソーシャルメディアの普及がもたらす変化の1つとして、「シェアリング・エコノミー」の動向を把握するとともに、アンケート調査によってユーザー側の利用意向や普及に向けた課題を分析することとする。
また、ソーシャルメディアが広く普及したことで、問題投稿が広範囲に瞬時に拡散し、投稿者が思わぬ社会的な非難にさらされる可能性が出てきている。この「拡散」と「炎上」の問題についてもソーシャルメディアの普及がもたらす変化の1つとして、その動向を把握するとともに、アンケート調査によってユーザー側の意識を把握し、今後に向けた課題を分析する。
図表4-2-1-1 ソーシャルメディアの種類と代表的なサービス例
種類 サービス例
ブログ アメーバブログ、ココログ、Seesaa ブログ、ライブドアブログ
SNS(ソーシャルネットワーキングサービス)
Facebook、Twitter、mixi、Instagram、LinkedIn
動画共有サイト YouTube、ニコニコ動画、ツイキャス、Vineメッセージングアプリ LINE、WhatsApp、Viber、WeChat情報共有サイト 価格コム、食べログ、クックパッドソーシャルブックマーク はてなブックマーク
(出典)総務省「社会課題解決のための新たなICTサービス・技術への人 の々意識に関する調査研究」(平成27年)
平成27年版 情報通信白書 第2部 199
暮らしの未来とICT
第4章

ソーシャルメディアの普及がもたらす変化第 2節
シェアリング・エコノミー―ソーシャルメディアを活用した新たな経済1
1 シェアリング・エコノミーとは
「シェアリング・エコノミー」とは、典型的には個人が保有する遊休資産(スキルのような無形のものも含む)の貸出しを仲介するサービスであり、貸主は遊休資産の活用による収入、借主は所有することなく利用ができるというメリットがある。貸し借りが成立するためには信頼関係の担保が必要であるが、そのためにソーシャルメディアの特性である情報交換に基づく緩やかなコミュニティの機能を活用することができる。シェアリング・エコノミーはシリコンバレーを起点にグローバルに成長してきた。PwCによると、2013年に約150億ドルの市場規模が2025年には約3,350億ドル規模に成長する見込みである(図表4-2-1-3)。
シェアリング・エコノミーの嚆矢は2008年に開始された「Airbnb」であるが、その後様々なものを対象としたサービスが登場している。以下に主なサービスを示す*1(図表4-2-1-4)。
図表4-2-1-4 海外におけるシェアリング・エコノミー型サービスの例
事例名称 実施主体 時期 概要
Airbnb Airbnb(米国) 2008年8月開始 保有する住宅や物件を宿泊施設として登録し、貸し出しできるプラットフォームを提供するWEBサービス。190か国超の34,000超の都市で100万超の宿が登録されている*2。
Uber Uber(米国) 2010年6月開始スマートフォンやGPSなどのICTを活用し、移動ニーズのある利用者とドライバーをマッチングさせるサービス。高級ハイヤーを配車するUber、低価格タクシーを配車するuberX、既存のタクシーを配車するUberTAXIなどのサービスを提供。
Lyft Lyft(米国) 2012年8月開始スマートフォンアプリによって移動希望者とドライバーをマッチングするサービス。Facebookのアカウントか電話番号でログインして利用する。移動希望者とドライバーがお互いに評価を確認してから、乗車が成立する*3。
DogVacay DogVacay(米国) 2012年開始 ペットホテルの代替となるペットシッターの登録・利用が可能なプラットフォームを提供するWEBサービス。
RelayRides RelayRides(米国) 2012年開始 使用されていない車を、オーナーからスマートフォンアプリを通じて借りることができるサービス。米国内の2,100以上の都市及び300以上の空港で利用できる。
TaskRabbit TaskRabbit(米国) 2011年7月開始 家事や日曜大工等の作業をアウトソーシングするためのウェブサービス。Prove Trust Prove Trust(米国) 2014年開始 シェアリング・エコノミーにおける貸主と借主の信頼関係を一括で管理できるウェブサービス。
(出典)総務省「社会課題解決のための新たなICTサービス・技術への人 の々意識に関する調査研究」(平成27年)
ア AirbnbAirbnbは、空き部屋や不動産等の貸借をマッチング
するオンラインプラットフォームである。個人・法人を問わずに利用でき、共用スペースから戸建て住宅、アパート、個室から個人が所有する島まで幅広い物件が登録されている(図表4-2-1-5)。
また、ユーザー間の信頼性を高めるために、過去の利用者による「レビュー評価制度」、写真入り身分証明書などから本人確認を行う「ID認証」、Facebook等の外部のソーシャルメディアの認証情報を利用する「SNSコネクト」、利用者に起因する損害を補償する「ホスト保証制度」等の機能が導入されている。なお、利用者による評価は双方向であり、ホストからゲストへの評価も行われる。
図表4-2-1-3 シェアリング・エコノミーの市場規模
15
335
0
100
200
300
400(10億ドル)
2013年 2025年※金融、人材、宿泊施設、自動車、音楽・ビデオ配信の5分野におけるシェア
リングを対象(出典)PwC「The sharing economy - sizing the revenue opportunity」
*1 各社ホームページより作成。*2 Airbnb社ホームページ、https://www.airbnb.jp/about/about-us*3 高橋陽一「ライドシェアリングのジレンマ」(KDDI総研R&A、2013年7月号)
図表4-2-1-5 Airbnbのサービスイメージ
ホスト(貸したいユーザ)
ゲスト(借りたいユーザ)部屋情報閲覧部屋情報登録
予約リクエスト
ホスト手数料(宿泊料金の3%)
ゲスト手数料(宿泊料金の6~12%)
宿泊料金部屋
Airbnb
(出典)総務省「社会課題解決のための新たなICTサービス・技術への人 の々意識に関する調査研究」(平成27年)
平成27年版 情報通信白書 第2部200
第4章
暮らしの未来とICT

ソーシャルメディアの普及がもたらす変化 第 2節
Airbnbは2008年に設立され、2015年 時 点 で190か 国 以 上 の34,000を超える都市で100万以上の宿が提供されている*4。
Airbnb社によるとAirbnbの効果は地域経済にも影響を与えている。図表4-2-1-6は、Airbnbの扱う物件と民間ホテルの立地の比較である。同社の研究によると、ホテルのないところに物件があり、一般の旅行者が訪れない地域企業などにお金が落ちる効果が創出されている。具体的には、サンフランシスコで年間約56億円、シドニーで年間約214億円の地域経済効果が見込まれている*5。イ Uber
Uberは、スマートフォンやGPSなどのICTを活用し、移動ニーズのある利用者とドライバーをマッチングさせるサービスである(図表4-2-1-7)。
各地域のタクシー会社、ハイヤー会社に加えて、個人のドライバーとも提携をしており、利用者はスマートフォンから配車の依頼をすることができる。現在、57か国の都市でサービスが提供されている*6。
移動の目的や人数によって、サービスを「uberX(エコカー)」「uberTAXI(タクシー)」「UberBLACK(ハイヤー)」「UberSUV(ミニバン)」「UberLUX(最高級車)」等から選択することができる。なお、都市によって利用できるサービス及び料金が異なり、例えば東京であれば、uberTAXI、UberBLACK、UberLUXの3種類から選択することになる。
uberXは、エコカーを利用して個人で開業しているドライバーが多く、自家用車によるライドシェアリングが行われている。同社によると、uberXのドライバーは1時間20ドル以上の収入を得ることができ*7、年間平均収入はニューヨークで約90,000ドル、サンフランシスコで約74,000ドルである*8。そのため、米国等では、ドライバー登録をして収入を得る個人ドライバーが増えている。
同サービスでは、ユーザーが安心かつ便利に利用できるように「過去の利用者による運転手の評価確認」、「事前に登録したクレジットカードからの運賃の電子決済」、「同乗者との割り勘決済」などの機能を提供している。ウ Prove Trust
シェアリング・エコノミー型サービスでは個人と個人との信頼関係が鍵となる。このため各サービスでは、Facebook等の既存ソーシャルメディアと連携したり、サービス独自に利用者間のレビュー評価制度を導入したりして、信頼性の確保に努めているが、一歩進んで、オンライン上の様々な活動履歴からユーザーの信頼度を総合的にスコア化するサービスも提供され始めている。その一つであるProve Trustでは、ユーザーの信頼度を、Facebook、地域情報コミュニティサイト「Craigslist」、
図表4-2-1-7 Uberのサービスイメージ
ドライバータクシー会社等 利用者
ユーザ登録ドライバー登録
配車依頼配車依頼
報酬 サービス料(手数料含む)
輸送サービス(目的地までの送迎)
Uber(スマホアプリ)
(出典)総務省「社会課題解決のための新たなICTサービス・技術への人 の々意識に関する調査研究」(平成27年)
*4 Airbnb社ホームページ、https://www.airbnb.com/economic-impact/*5 Airbnb社ホームページ、https://www.airbnb.com/economic-impact/*6 Uber社ホームページ、https://www.uber.com/cities*7 Uber社公式ブログ、http://blog.uber.com/getgenne*8 Uber社公式ブログ、http://blog.uber.com/uberimpact*9 ProveTrustホームページ、https://www.provetrust.com/#!/p/example
図表4-2-1-8 Prove Trustによる信頼度のスコア化のイメージ
(出典)Prove Trust ホームページ*9
図表4-2-1-6 Airbnbとホテルの位置(ロサンゼルスの例)
(出典):Airbnb社ホームページ
平成27年版 情報通信白書 第2部 201
暮らしの未来とICT
第4章

ソーシャルメディアの普及がもたらす変化第 2節
Airbnb、ビットコイン、結婚恋愛サイトの利用状況等に基づき、総合的にスコア化するサービスを提供している。評価の内容は、ユーザーが実在する人物かどうかを評価する「Real Score」、ソーシャルネットワーク上での活動の活発さを評価する「Social Score」、他のユーザーからの評判を評価する「Feedback Score」により構成され、これらのスコアを集計して最終的な信頼度がスコア化される(図表4-2-1-8)。類似のサービスとして、TrustCloudがある。
2 シェアリング・エコノミー型サービスへのニーズ
このように海外では、様々なシェアリング・エコノミー型サービスが登場し、普及しつつある。それでは、このようなサービスに対し、日本の消費者はどのような利用意向をもっているのだろうか。以下、アンケート調査*10の結果に基づき分析する。ア 海外シェアリング・エコノミー型サービスの利用意向
海外で普及しつつある以上のようなシェアリング・エコノミー型サービスについて、サービス種類別に日本の消費者の利用意向を尋ねた。その結果をみると、「一般のドライバーの自家用車に乗って目的地まで移動できるサービス」について「利用したい」あるいは「利用を検討してもよい」と答えた人は22.9%、「旅行先で個人宅の空き部屋などに宿泊できるサービス」について「利用したい」あるいは「利用を検討してもよい」と答えた人は26.4%となり、いずれも「利用したくない」あるいは「あまり利用したくない」と答えた人を下回った(図表4-2-1-9)。現段階では日本の消費者の多くはこれらのサービスの利用に対して慎重であることがわかる。
利用意向を年代別に見ると、「一般のドライバーの自家用車に乗って目的地まで移動できるサービス」と「旅行先で個人宅の空き部屋などに宿泊できるサービス」のいずれについても、20代以下の利用意向が最も高く、年代が上がるにつれて利用意向が低くなる傾向がある。(図表4-2-1-10)。
図表4-2-1-10 海外シェアリング・エコノミー型サービスの利用意向(年代別)
8.8
7.5
4.8
4.8
3.3
23.5
21.5
23.0
19.8
15.0
24.3
29.0
31.8
32.8
30.5
43.5
42.0
40.5
42.8
51.3
0 20 40 60 80 100
20代以下
30代
40代
50代
60代以上
(%)
n
400
400
400
400
400
旅行先で個人宅の空き部屋などに宿泊できるサービス
0 20 40 60 80 100
20代以下
30代
40代
50代
60代以上
(%)
利用したい 利用を検討してもよい あまり利用したくない 利用したくない
n
400
400
400
400
400
一般のドライバーの自家用車に乗って目的地まで移動できるサービス
5.0
5.0
3.5
4.0
3.0
23.3
20.8
19.8
19.3
10.8
27.3
33.5
35.0
35.8
34.0
44.5
40.8
41.8
41.0
52.3
(出典)総務省「社会課題解決のための新たなICTサービス・技術への人 の々意識に関する調査研究」(平成27年)
*10調査仕様の詳細は巻末の付注5を参照されたい。
図表4-2-1-9 海外シェアリング・エコノミー型サービスの利用意向
5.8
4.1
20.6
18.8
29.7
33.1
44.0
44.1
0 50 100
旅行先で個人宅の空き部屋などに宿泊できるサービス
一般のドライバーの自家用車に乗って目的地まで移動できるサービス
(%)
利用したい 利用を検討してもよいあまり利用したくない 利用したくない
n=2,00026.4
22.9
(出典)総務省「社会課題解決のための新たなICTサービス・技術への人 の々意識に関する調査研究」(平成27年)
平成27年版 情報通信白書 第2部202
第4章
暮らしの未来とICT

ソーシャルメディアの普及がもたらす変化 第 2節
イ 海外シェアリング・エコノミー型サービスを利用したくない理由シェアリング・エコノミー型サービスを利用したくな
いと回答した人(「あまり利用したくない」又は「利用したくない」と回答した人)にその理由を尋ねたところ、「事故やトラブル時の対応に不安があるから」を挙げた人が約6割で最も多かった。未知のサービスであるため、事故やトラブル時の対応に漠然とした不安を感じる人が多く、信頼性の向上が課題となっていることがわかる。他方、「利用者の口コミによるサービス評価には限界があるから」や「企業が責任をもって提供するサービスの方が信頼できるから」を理由に挙げた人はそれぞれ1割、2割程度にとどまり、必ずしも多くない(図表4-2-1-11)。C2Cサービスの品質を口コミ評価によって担保するというシェアリング・エコノミー型サービスの基本的な仕組み自体は、広く受け入れられる余地があることがうかがえる。
利用したくない理由を年代別にみると、両サービスとも「事故やトラブル時の対応に不安があるから」が各年代で共通に高く、「利用者の口コミによるサービス評価には限界があるから」が各年代共通で低い。利用したくない理由には年代によって大きな違いがないことがわかる。ただし、「企業が責任をもって提供するサービスの方が信頼できるから」を理由に挙げた人は20代以下が他の年代に比べてやや多い(図表4-2-1-12)。
図表4-2-1-12 海外シェアリング・エコノミー型サービスを利用したくない理由(年代別)
企業が責任をもって提供するサービスの方が信頼できるから
利用者の口コミによるサービス評価には
限界があると思うから事故やトラブル時の対応に不安があるから
サービスの内容や使い方がわかりにくそう
だから
個人情報の事前登録などの手続がわずらわしいから
20代以下(n=271) 29.5 10.0 59.8 20.7 26.630代(n=284) 15.8 9.9 59.2 19.0 33.540代(n=289) 20.1 8.0 61.6 19.4 33.250代(n=302) 22.5 7.3 59.3 20.9 31.860代以上(n=327) 27.5 10.7 65.1 20.8 28.4
0
20
40
60
80(%) 旅行先で個人宅の空き部屋などに宿泊できるサービス
企業が責任をもって提供するサービスの方が信頼できるから
利用者の口コミによるサービス評価には
限界があると思うから事故やトラブル時の対応に不安があるから
サービスの内容や使い方がわかりにくそう
だから
個人情報の事前登録などの手続がわずらわしいから
20代以下(n=287)30代(n=297)40代(n=307)50代(n=307)60代以上(n=345)
0
20
40
60
80(%) 一般のドライバーの自家用車に乗って目的地まで移動できるサービス
27.9 11.5 61.7 20.2 25.816.2 9.1 60.3 17.5 32.318.2 8.1 65.1 16.3 28.718.6 6.5 64.8 14.3 29.024.6 10.4 67.2 19.4 24.1
(出典)総務省「社会課題解決のための新たなICTサービス・技術への人 の々意識に関する調査研究」(平成27年)
ウ 国内におけるシェアリング・エコノミー型サービスの例海外におけるシェアリング・エコノミー型サービスの急速な普及に触発され、国内でもシェアリング・エコノ
図表4-2-1-11 海外シェアリング・エコノミー型サービスを利用したくない理由
1.7
1.6
30.7
27.9
20.2
17.6
61.1
64.0
9.2
9.1
23.2
21.1
0 10 20 30 40 50 60 70
旅行先で個人宅の空き部屋などに宿泊できるサービス
n=1,473
一般のドライバーの自家用車に乗って目的地まで移動できる
サービスn=1,543
企業が責任をもって提供するサービスの方が信頼できるから利用者の口コミによるサービス評価には限界があると思うから事故やトラブル時の対応に不安があるからサービスの内容や使い方がわかりにくそうだから個人情報の事前登録などの手続がわずらわしいからその他
(%)
(出典)総務省「社会課題解決のための新たなICTサービス・技術への人 の々意識に関する調査研究」(平成27年)
平成27年版 情報通信白書 第2部 203
暮らしの未来とICT
第4章

ソーシャルメディアの普及がもたらす変化第 2節
ミー型と位置付け得るサービスが提供され始めている。以下、そのいくつかを紹介する。(ア)駐車場シェアリング・エコノミー型サービス「akippa」
「akippa」は、契約の埋まっていない月極駐車場や使っていない自宅の駐車スペースを持っている人と、外出先で一時的に駐車場を利用したい人とをインターネット上で仲介するサービスである。akippa株式会社が2014年4月からサービスを提供している(図表4-2-1-13、図表4-2-1-14)。駐車場の利用者は、同社が提供するスマートフォンの専用アプリを利用して、どこからでも簡単に空き駐車場の検索や予約を行うことができる。
駐車場の貸し借りは、現在のところ、1日単位で行っている。同社によると、料金は駐車スペースの貸主が自由に設定できるが、おおむね周囲のコインパーキングの7割程度の金額に設定されており、1日あたり500円から1,000円程度となっている。利用料金の6割程度が貸主への報酬として支払われる。現在は東京都と大阪府を中心に駐車場を4.7万台分確保しており、同社では、2016年末までに10万台以上確保することを目標としている。利用者は20代から40代が多く、利用目的は通勤、イベント、旅行の際の利用など多岐にわたっている。2014年2~8月期と2014年9月~2015年3月期の登録ユーザー数を比較すると約11倍に伸びており、本サービスへの注目度が上がっていることがうかがえる。
知らない人同士をつなぐというシェアリング・エコノミー型サービスの特性を踏まえ、同社では、利用者が安心してサービスを利用できるよう、様々な工夫を行っている。例えば、駐車スペースの持ち主が新たに駐車場を登録する際には、同社が事前審査を行い、登録内容に間違いがないかを確認している。また、利用者が間違えた場所に駐車しないよう、Googleマップ上での駐車場の表示位置にずれがないかも確認している。さらに、トラブル発生時に利用者や貸主が同社とすぐに連絡が取れるよう、24時間対応の電話窓口を設置している。
図表4-2-1-13 akippaの仕組み、及び駐車場予約画面
(出典)akippa株式会社提供資料
図表4-2-1-14 利用風景
(出典)akippa株式会社提供資料
(イ)家事代行仲介サービス「Any+Times」「Any+Times」は、部屋や水回りの掃除、難しい家
具の組立て、忙しい時のペットの世話などを、他人に依頼できるウェブ上のサービスである。株式会社エニタイムズが2013年9月からサービス提供を開始した。
日常生活に関わる課題を抱える依頼者が、依頼内容と価格をAny+Timesのサイトに記載すると、該当するスキルを有する登録者(同社では、依頼者の課題を解決する登録者のことを「サポーター」と呼んでいる)が依頼者に見積りや交渉を行う。登録者と依頼者の交渉がまとまると、依頼者は、Any+Timesに支払を行う。その後、登録者が仕事を行い、依頼者はその仕事の結果に対して評価を行う。Any+Timesは登録者に手数料を除いた額の支払を行う(図表4-2-1-15)。
家事代行が主要なサービスのため登録者は40代から60代の主婦であることが多いが、サービスの新規性に着目した比較的感度の高い20代の女性や大学生も登録しているケースがある。家事以外の依頼についても登録可能であり、依頼内容によって登録者の属性は異なる。
図表4-2-1-15 Any+Timesの仕組み
(出典)株式会社エニタイムズ提供資料
平成27年版 情報通信白書 第2部204
第4章
暮らしの未来とICT

ソーシャルメディアの普及がもたらす変化 第 2節
同社では、他の家事代行サービスと比較した場合の本サービスの強みとして、C2Cサービスであるため比較的安い価格でサービスを提供できることを挙げている。同社ではまた、C2Cサービスがまだ世の中に浸透していないため初回利用時のハードルは高いが、一度利用されれば費用対効果の高さからリピート利用につながっていると分析している。
同社では本サービスを、隠れていた個人の多様なスキルを顕在化させるものと考えており、今後、本サービスを個人の様々なスキルをシェアするプラットフォームに発展させたいと考えている。同社ではまた、近所の課題を解決するという本サービスの利用を通じ、地域内での個人と個人のネットワークが可視化されれば、地域活性化にもつながると期待している。
(ウ)その他その他、国内でも様々なシェアリング・エコノミー型サービスが提供され始めている*11。
図表4-2-1-16 その他の国内におけるシェアリング・エコノミー型サービスの例
事例名称 実施主体 時期 概要
AsMama AsMama 2009年設立
実生活での友達・知人を検索したり、FacebookやTwitterから友達・知人を誘って、同じ幼稚園、保育園、学校等に通う保護者や友人と子どもの送迎や託児を行うSNSサービス。基本的には顔見知りの知り合いに子どもを預け、その対価として500円を支払う仕組みとなっている。人とのつながりを作ったり、子どもを預ける場合の依頼、対価の支払はSNS上で行うことが可能。
hakobito RAWHIDE 2006年設立 同社ではソーシャルメディアを活用した新たな物流サービスと位置づけている。例えば出張等の機会を利用して「もの」を運ぶことができる方と運搬を希望している方(企業)の「もの」をマッチングするサービス。
モノシー セイビー 2013年設立
ふだん使っていない持ち物等をサイト上に登録し、借りたい人に貸すことができるサービス。貸主はレンタルによる収入を得ることができる。様々な物が貸し借りされており、海外の部屋・家、国内の空きスペース、乗り物、衣料品、PC・電化製品、ロボット、インテリア用品、スポーツ用品等が登録されている。また、優れた能力を持った人を探すことも可能である。
RoomStay(ルームステイ)
みんなのマーケット 2011年設立
ホスト(部屋を貸したい人)とゲスト(借りたい人)をオンライン上でマッチングするサービス。部屋だけではなく、家、キャンピングカー、ボートも登録することができる。世界37か国、239件の部屋が登録されている。ソーシャルメディア認証、クレジットカード決済システムを導入して、安全に利用できる工夫を施している。
とまりーな とまれる 2013年設立 ユーザーが自分の好みに合った日本全国の農家民宿等を、ネットを通じて予約、宿泊することができるサービス。農業体験、漁業体験、古民家での田舎暮らし等の体験目的別に、宿泊先を探すことができる。
軒先.com 軒先 2009年設立
様々な空きスペースを貸し出して、スペースを使いたい人が物販やイベント、撮影、教室等に活用できるマッチングサービス。ふだん使用していないスペースを貸し出し、有効利用することができる。特定の時間や期間での貸し借りもできる。貸し出すことができるスペースは、住宅やビルの軒先、商業ビルの公開空地や空きスペース、レジ脇等の、営業中の店舗の屋内外にある空きスペース等である。
(出典)総務省「社会課題解決のための新たなICTサービス・技術への人 の々意識に関する調査研究」(平成27年)
エ 国内シェアリング・エコノミー型サービスの利用意向以上のような国内で提供されているシェアリング・エコノミー型サービスを念頭に置いて、アンケート調査で
消費者の利用意向等を尋ねた。その結果をみると、「車で外出した際に、空いている月極駐車場や個人所有の駐車スペースに一時的に駐車できるサービス」(駐車サービス)について「利用したい」あるいは「利用を検討してもよい」と答えた人は5割を超えた*12。一方、「インターネットを通じて、他人の使っていないモノ(楽器、自転車等)をレンタルできるサービス」(レンタルサービス)について「利用したい」あるいは「利用を検討してもよい」と答えた人は3割強、「インターネットを通じて、家事やペットの世話などの仕事を個人に直接依頼できるサービス」(家事依頼サービス)について「利用したい」あるいは「利用を検討してもよい」と答えた人は26.5%となった(図表4-2-1-17)。
年代別に利用意向をみると、各サービス共通して60代以上の利用意向が他の年代に比べて低い(図表4-2-1-18)。海外のシェアリング・エコノミー型サービスの場合と同様、シニア層に受け入れられにくい結果となった。
*11各社ホームページより作成。*12「車で外出した際に、空いている月極駐車場や個人所有の駐車スペースに一時的に駐車できるサービス」については、「自動車免許を現在持っ
ておらず、将来持つ予定もない」と答えた人を集計対象から除いている。
図表4-2-1-17 国内におけるシェアリング・エコノミー型サービスの利用意向
12.9
5.1
4.3
43.6
26.1
22.2
23.3
38.5
37.4
20.1
30.4
36.2
0 50 100
車で外出した際に、空いている月極駐車場や個人所有の駐車スペースに
一時的に駐車できるサービス(n=1,752)
インターネットを通じて、他人の使っていないモノ(楽器、自転車等)
をレンタルできるサービス(n=2,000)
インターネットを通じて、家事やペットの世話などの仕事を個人に直接依頼できるサービス
(n=2,000)(%)
利用したい 利用を検討してもよい あまり利用したくない 利用したくない
(出典)総務省「社会課題解決のための新たなICTサービス・技術への人 の々意識に関する調査研究」(平成27年)
平成27年版 情報通信白書 第2部 205
暮らしの未来とICT
第4章

ソーシャルメディアの普及がもたらす変化第 2節
図表4-2-1-18 国内におけるシェアリング・エコノミー型サービスの利用意向(年代別)インターネットを通じて、他人の使っていないモノ(楽器、自転車等)をレンタルできるサービス
6.5
6.0
5.0
4.5
3.3
27.8
31.0
30.8
24.0
16.8
32.5
36.0
36.0
43.3
44.8
33.3
27.0
28.3
28.3
35.3
0 20 40 60 80 100
20代以下
30代
40代
50代
60代以上
(%)
n400
400
400
400
400
0 20 40 60 80 100
20代以下
30代
40代
50代
60代以上
(%)
利用したい 利用を検討してもよい あまり利用したくない 利用したくない
n400
400
400
400
400
5.8
4.5
4.3
3.3
3.8
22.8
25.0
25.8
21.8
15.5
32.8
38.3
38.0
37.8
40.0
38.8
32.3
32.0
37.3
40.8
インターネットを通じて、家事やペットの世話などの仕事を個人に直接依頼できるサービス
0 20 40 60 80 100
20代以下
30代
40代
50代
60代以上
(%)
n332
373
368
309
370
車で外出した際に、空いている月極駐車場や個人所有の駐車スペースに一時的に駐車できるサービス
15.4
12.1
11.9
14.1
11.0
41.6
46.6
45.4
42.4
41.4
20.5
23.3
21.6
25.5
25.9
22.6
18.0
21.1
17.9
21.7
(出典)総務省「社会課題解決のための新たなICTサービス・技術への人 の々意識に関する調査研究」(平成27年)
オ 国内シェアリング・エコノミー型サービスを利用したくない理由以上のシェアリング・エコノミー型サービスについ
て、「あまり利用したくない」あるいは「利用したくない」と答えた人にその理由を尋ねた。
利用したくない理由は各サービスともに「事故やトラブル時の対応に不安があるから」が5割から6割で最も高く、次に「個人情報の事前登録などの手続がわずらわしいから」が約3割で続く。他方、「利用者の口コミによるサービス評価には限界があるから」や「企業が責任をもって提供するサービスの方が信頼できるから」を理由に挙げた人はそれぞれ1割未満、2割程度にとどまり、必ずしも多くない(図表4-2-1-19)。海外のサービスの場合と同様、C2Cサービスの品質を口コミ評価によって担保するというシェアリング・エコノミー型サービスの基本的な仕組み自体に抵抗を感じる人は少なく、サービスを実装していく上での信頼性の確保や利便性の向上が課題であることがわかる。
利用したくない理由を年代別にみると、海外のサービスの場合と同様、年代によって大きな違いがないことがわかる。ただし、「企業が責任をもって提供するサービスの方が信頼できるから」を理由に挙げた人は20代以下が他の年代に比べてやや多い(図表4-2-1-20)。
図表4-2-1-19 国内におけるシェアリング・エコノミー型サービスを利用したくない理由
1.8
1.4
1.9
36.5
30.3
29.4
20.9
19.7
17.9
54.1
61.7
62.7
5.5
7.1
9.0
14.6
15.8
17.0
0 10 20 30 40 50 60 70
車で外出した際に、空いている月極駐車場や個人所有の駐車スペースに
一時的に駐車できるサービスn=762
インターネットを通じて、他人の使っていないモノ(楽器、自転車等)を
レンタルできるサービスn=1,378
インターネットを通じて、家事やペットの世話などの仕事を個人に直接依頼
できるサービスn=1,471
企業が責任をもって提供するサービスの方が信頼できるから利用者の口コミによるサービス評価には限界があると思うから事故やトラブル時の対応に不安があるからサービスの内容や使い方がわかりにくそうだから個人情報の事前登録などの手続がわずらわしいからその他
(%)
(出典)総務省「社会課題解決のための新たなICTサービス・技術への人 の々意識に関する調査研究」(平成27年)
平成27年版 情報通信白書 第2部206
第4章
暮らしの未来とICT

ソーシャルメディアの普及がもたらす変化 第 2節
図表4-2-1-20 国内におけるシェアリング・エコノミー型サービスを利用したくない理由(年代別)
企業が責任をもって提供するサービスの方が信頼できるから
利用者の口コミによるサービス評価には
限界があると思うから事故やトラブル時の対応に不安があるから
サービスの内容や使い方がわかりにくそうだから
個人情報の事前登録などの手続がわずらわしいから
20代以下(n=143) 24.5 6.3 55.2 27.3 30.830代(n=154) 14.9 6.5 48.1 25.3 39.640代(n=158) 11.4 3.8 57.6 14.6 39.950代(n=160) 8.8 4.4 46.9 20.0 43.160代以上(n=147) 14.3 6.8 63.3 17.7 27.9
0
20
40
60
80(%) 車で外出した際に、空いている月極駐車場や個人所有の駐車スペースに一時的に駐車できるサービス
企業が責任をもって提供するサービスの方が信頼できるから
利用者の口コミによるサービス評価には
限界があると思うから
利用者の口コミによるサービス評価には
限界があると思うから
事故やトラブル時の対応に不安があるから
サービスの内容や使い方がわかりにくそうだから
個人情報の事前登録などの手続がわずらわしいから
20代以下(n=263)30代(n=252)40代(n=257)50代(n=286)60代以上(n=320)
0
20
40
60
80(%)
22.4 6.5 60.8 25.5 25.915.1 7.1 60.3 15.5 32.913.6 6.2 61.5 17.9 34.213.6 8.0 58.7 22.0 32.514.7 7.5 66.3 17.5 26.9
インターネットを通じて、他人の使っていないモノ(楽器、自転車等)をレンタルできるサービス
企業が責任をもって提供するサービスの方が信頼できるから
事故やトラブル時の対応に不安があるから
サービスの内容や使い方がわかりにくそうだから
個人情報の事前登録などの手続がわずらわしいから
20代以下(n=286)30代(n=282)40代(n=280)50代(n=300)60代以上(n=323)
0
20
40
60
80(%)
23.8 10.8 61.2 20.6 24.515.6 8.2 61.0 16.3 29.815.7 7.5 65.4 13.9 34.614.0 7.3 62.7 17.7 31.716.1 10.8 63.2 20.7 26.9
インターネットを通じて、家事やペットの世話などの仕事を個人に直接依頼できるサービス
(出典)総務省「社会課題解決のための新たなICTサービス・技術への人 の々意識に関する調査研究」(平成27年)
3 シェアリング・エコノミーの普及に向けて
以上、海外と国内のシェアリング・エコノミー型サービスについて、代表的なサービスを紹介するとともに、消費者の利用意向等をみてきた。シェアリング・エコノミー型サービスは我が国では黎明期にあると考えられ、一部に利用意向の高いサービスもあるものの、全体として現状では企業が提供する従来型のサービスと同程度の支持を得ているとは言い難い。しかしながら、C2Cサービスの品質をインターネットでの口コミ評価によって担保するというシェアリング・エコノミー型サービスの基本的な構造自体に抵抗を感じる消費者は少なく、サービスを実装していく上での信頼性の確保や利便性の向上が課題となっている。既に各企業で取り組まれているような、信頼性の確保や利便性の向上に向けた取組が更に進めば、我が国でも利用が広がっていくと想定され、将来的には企業が従業員を通じて消費者にサービスを提供するという現在の経済活動の仕組み自体が変わっていく可能性もあるだろう。
平成27年版 情報通信白書 第2部 207
暮らしの未来とICT
第4章

ソーシャルメディアの普及がもたらす変化第 2節
SNSでの「拡散」と「炎上」21 問題の背景
近時、TwitterやFacebookなどのSNSでの不用意な投稿が原因となって投稿者本人が非難に晒されたり、これらのSNSでの消費者の投稿を契機として企業が予期せぬ非難に晒されたりする、いわゆる「炎上」が注目されており、大手メディアでも頻繁に取り上げられるようになっている。実際、新聞記事データベースで関連する記事を検索*13すると、2010年頃から顕著に増加している(図表4-2-2-1)。
また、Googleにおける「Twitter 炎上」「Facebook 炎上」というキーワードでの検索頻度をみても、2010年頃から徐々に増加している*14(図表4-2-2-2)。
インターネット上の自分や他人の書き込みが原因で個人や企業がトラブルに巻き込まれる現象自体はインターネット黎明期から存在したが、このようにSNSでの「炎上」が近時特に注目されるようになった背景には、TwitterやFacebookなどのSNSが持つ機能上の特性がある。すなわち、これらのSNSは自分が気に入った他人の投稿を知人と簡単に共有する機能を備えており、連鎖的に投稿の共有が行なわれた結果、投稿が瞬く間に広範囲へと「拡散」していくという特徴がある。また、これらのSNSではスマートフォンで撮影した写真を簡単に投稿でき、インパクトのある写真が掲載されやすい点も、「炎上」を誘発する一因となっている。
なお、ソーシャルメディアのリスク対応コンサルティングを手掛けるアディッシュ社(ガイアックス社)の調査結果によると、炎上のきっかけとなったSNSの約4割がTwitterである(図表4-2-2-3)。
以下では、アンケート調査の結果を基に、SNSでの「拡散」と「炎上」を巡る現状と課題を探っていくことにする。
2 SNSの利用率
まず、代表的なSNS*16の利用状況を確認する。最近約1年以内に利用した経験のあるSNSを尋ねたところ、LINE(37.5%) 、Facebook(35.3%)、Twitter(31.0%)の順となった。それぞれ実名(本名又はこれに準ずる氏名)、匿名(実名以外)のどちらで利用しているかを尋ねたところ、実名利用率(全利用者数に対する実名利用者数の比率)が高かったのはFacebook(84.8%)、LINE(62.8%)であり、低かったのはmixi(21.6%)、Twitter(23.5%)であった(図表4-2-2-4)。
図表4-2-2-1 新聞記事データベースにおけるSNS炎上関連記事件数の推移
0 113
4 6 7 13
38 45
112
71
0
20
40
60
80
100
120
04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14(年度)
(件数)
(出典)日経テレコンより総務省作成
*13日経テレコンで「SNS 炎上」を検索ワードとして記事を検索。日経各紙、その他全国紙(朝日、毎日、読売、産経、共同通信、時事通信)及びNHKが対象。
*14GoogleTrendsでそれぞれ「Twitter炎上」、「Facebook炎上」を検索ワードに設定して検索。2015年3月分までが対象。*15「学生・生徒のツイートを見守る「セーフティプログラムforTwitter」を提供開始~大学・高校生のTwitterでの炎上トラブル増に対応~」
(2014年6月24日公表)http://www.gaiax.co.jp/news/press/2014/0624/*16LINEは一般にメッセージングアプリや通話アプリと分類されることが多いが、本節では、その利用の広がりに鑑み、LINEをSNSに含めて
いる。
図表4-2-2-2Google検索における検索キーワード
「Facebook炎上」「Twitter炎上」の検索動向
■ Twitter ■ Facebook
2005 2007 2009 2011 2013 2015
(出典) Google Trendsより総務省作成
図表4-2-2-3 炎上のきっかけとなったサイト
2010(年)
2011
2012
2013
0 50 100 150 200 250 300 350 400 450(件)
twitter 2ch SNS公式ページ 動画共有サイト ブログ
(出典)アディッシュ株式会社(株式会社ガイアックス)調べ*15
平成27年版 情報通信白書 第2部208
第4章
暮らしの未来とICT

ソーシャルメディアの普及がもたらす変化 第 2節
図表4-2-2-4 SNSの利用率及び実名利用率
84.8
23.5
31.9
21.6
62.8
15.2
76.5
68.1
78.4
37.2
0 20 40 60 80 100
mixi
LINE
実名利用 匿名利用
〈実名利用・匿名利用〉〈利用率〉
n
620
(%)
706
119
329
749
35.3
31.0
6.0
16.5
37.5
0 20 40 60 80
mixi
LINE
(n=2,000)
(%)
(出典)総務省「社会課題解決のための新たなICTサービス・技術への人 の々意識に関する調査研究」(平成27年)
年代別に利用率をみると、全般に年代が高くなるほど利用率が下がる傾向にあるが、Facebookについては20代以下で約5割、30代と40代で4割弱、60代以上でも2割以上の人が利用しており、年代を問わず浸透している。これに対し、LINEの利用率は年代によって大きな差があり、20代以下では6割以上の人が利用しているのに対し、60代以上で1割未満の人しか利用していない(図表4-2-2-5)。実名・匿名の別をみると、年代によってそれほど大きな違いはみられないものの、60代以上ではLINE、Twitterについては他の年代に比べて実名利用率が高くなっている。
図表4-2-2-5 SNSの年代別利用率(カッコ内は実名利用率)
38.3
33.0
7.8
22.5
47.0
49.3
52.8
16.0
27.5
62.8
0 20 40 60 80
mixi
LINE
〈20代以下〉
(83.2)
(18.0)
(34.4)
(20.0)
(66.9)
(%)
(n=400)
0 20 40 60 80
mixi
LINE
〈30代〉
(86.9)
(20.5)
(29.0)
(22.2)
(63.8)
(%)
(n=400)
0 20 40 60 80
mixi
LINE
〈50代〉
(83.7)
(30.9)
(25.0)
(31.4)
(62.2)
(%)
(n=400)
0 20 40 60 80
mixi
LINE
〈60代以上〉
(79.1)
(45.2)
(0.0)
(26.1)
(81.3)
(%)
(n=400)
0 20 40 60 80
mixi
LINE
〈40代〉
(89.1)
(19.5)
(35.7)
(16.9)
(52.1)
(%)
(n=400)36.8
29.5
3.5
17.8
41.8
30.8
24.3
2.0
8.8
27.8
21.5
15.5
0.5
5.8
8.0
(出典)総務省「社会課題解決のための新たなICTサービス・技術への人 の々意識に関する調査研究」(平成27年)
3 SNS上でのトラブル経験
次に、SNSを利用していて何らかのトラブルにあったことがあるかどうかを尋ねたところ、SNS利用者全体の8割以上が「トラブルにあったことはない」と回答している。年代別にみると、おおむね年代が下がるほどトラブルにあった人が増える傾向にあり、20代以下ではSNS利用者のうちの26.0%が何らかのトラブルにあった経験をもっている(図表4-2-2-6)。
経験したトラブルの内容をみると、「自分は軽い冗談のつもりで書き込んだが、他人を傷つけてしまった」、「自分の発言が自分の意図とは異なる意味で他人に受け取られてしまった(誤解)」、「ネット上で他人と言い合いになったことがある(けんか)」、「自分の意思とは関係なく、自分について(個人情報、写真など)他人に公開されてしまった(暴露)」が比較的高くなった(図表4-2-2-7)。
平成27年版 情報通信白書 第2部 209
暮らしの未来とICT
第4章

ソーシャルメディアの普及がもたらす変化第 2節
図表4-2-2-6 SNS上でのトラブル経験の有無(年代別)
93.5
90.4
85.9
87.9
74.0
84.6
6.5
9.6
14.1
12.1
26.0
15.4
0 20 40 60 80 100
60代以上(n=124)
50代(n=198)
40代(n=256)
30代(n=273)
20代以下(n=327)
全体(n=1,178)
トラブルにあったことはない トラブルにあったことがある
(%)
(出典)総務省「社会課題解決のための新たなICTサービス・技術への人 の々意識に関する調査研究」(平成27年)
図表4-2-2-7 SNS上でのトラブル経験の内容
4.77.4
4.42.7
4.21.4 1.6 1.4 0.5
0
5
10
15
20(%)
(n=1,178)
その他
自分のアカウントが乗っ取られた結果、入金や商品の
購入を促す不審なメッセージを他人に送ってしまった
自分の書いた内容に対して複数の人から批判的な
書き込みをされた(炎上)
他人が自分になりすまして書き込みをした
(なりすまし)
自分の意思とは関係なく、自分について(個人情報、
写真など)他人に公開されてしまった(暴露)
自分は匿名のつもりで投稿したが、他人から自分の
名前等を公開されてしまった(特定)
ネット上で他人と言い合いになったことがある
(けんか)
自分の発言が自分の意図とは異なる意味で他人に
受け取られてしまった(誤解)
自分は軽い冗談のつもりで書き込んだが、
他人を傷つけてしまった
(出典)総務省「社会課題解決のための新たなICTサービス・技術への人 の々意識に関する調査研究」(平成27年)
4 SNSでの情報発信経験
次に、SNSでの情報発信の状況について尋ねたところ、「SNSを利用しているが、自ら情報発信することよりも他人の書き込み等を閲覧することの方が多い」又は
「SNSを利用しているが、自らはほとんど情報発信せず、他人の書き込み等の閲覧しか行わない」と回答した人が、SNS利用者全体の65%以上を占めた。これに対し、
「SNSを利用して自ら情報発信を積極的に行っている」と回答した人は1割程度にとどまった。年代別にみると、20代以下は「SNSを利用して自ら情報発信を積極的に行っている」と回答した人が17.4%と他の年代よりも高くなっている(図表4-2-2-8)。
5 SNSでの情報拡散の状況
ア SNSでの情報拡散経験上でみたように、SNS利用者の中でも自ら積極的に
情報発信を行っている層は少数にとどまる。これに対し、他人の投稿を知人と共有する情報の「拡散」
(Facebookの「いいね!」機能やTwitterのリツイート機能等を利用して情報を広めること)は、SNS利用者の5割以上が実施しており、約17%はほぼ毎日実施している。年代別にみると、20代以下でやや多いが、30代以上は大きな差はなく、年代を問わず活発な情報拡散が行われていることがわかる(図表4-2-2-9)。
図表4-2-2-8 SNSでの情報発信経験(年代別)
11.8
17.4
9.9
8.2
11.6
8.9
33.3
38.8
29.7
31.6
30.8
33.9
31.9
28.4
36.3
30.9
33.8
30.6
23.0
15.3
24.2
29.3
23.7
26.60 20 40 60 80 100
全体
20代以下
30代
40代
50代
60代以上(%)
SNSを利用して自ら情報発信を積極的に行っているSNSを利用しているが、自ら情報発信することよりも他人の書き込み等を閲覧することの方が多いSNSを利用しているが、自らはほとんど情報発信せず、他人の書き込み等の閲覧しか行わないSNSをほとんど利用していない
n1,178
327
273
256
198
124
65.2
(出典)総務省「社会課題解決のための新たなICTサービス・技術への人 の々意識に関する調査研究」(平成27年)
図表4-2-2-9 SNSでの情報拡散経験(年代別)
17.1
21.7
16.5
13.3
18.7
11.3
13.6
17.4
11.4
12.5
13.6
10.5
24.6
22.0
23.1
26.6
24.2
31.5
44.7
38.8
49.1
47.7
43.4
46.8
0 20 40 60 80 100
全体
20代以下
30代
40代
50代
60代以上
(%)
ほぼ毎日 週1~ 2回程度 週1~ 2回未満 ない
n1,178
327
273
256
198
124
(出典)総務省「社会課題解決のための新たなICTサービス・技術への人 の々意識に関する調査研究」(平成27年)
平成27年版 情報通信白書 第2部210
第4章
暮らしの未来とICT

ソーシャルメディアの普及がもたらす変化 第 2節
イ 情報拡散の基準それではSNS利用者は、どのような基準で拡散する情報を選んでいるのだろうか。SNS利用者に拡散する情
報の基準を尋ねたところ、「内容に共感したかどうか」が46.2%で最も多く、「内容が面白いかどうか」が40.4%でこれに続く。これに対し、「情報の信憑性が高いかどうか」は23.5%と相対的に低い(図表4-2-2-10)。SNSで拡散される情報は、事実かどうかよりも、共感できるかどうかや、面白いかどうかを基準にして選ばれる傾向があることがうかがえる。
図表4-2-2-10 情報拡散の基準
1.80 10 20 30 40 50
その他6.8運営事業者が本人確認を行って認証している公式アカウントかどうか
3.4発信者が有名人かどうか3.1発信者が政府機関や大企業かどうか
13.7発信者が自分の知人や友人かどうか12.7発信者が拡散を希望しているかどうか
23.5情報の信憑性が高いかどうか
46.2内容に共感したかどうか40.4内容が面白いかどうか
30.4生活に役立つ内容かどうか26.9社会的に重要な内容かどうか
n=651
(%)(出典)総務省「社会課題解決のための新たなICTサービス・技術への人 の々意識に関する調査研究」(平成27年)
情報拡散の基準を年代別にみると、「内容に共感したかどうか」を基準とする人の割合は全ての年代に共通して高いが、「内容が面白いかどうか」を基準とする人の割合は年代が下がるほど高くなり、反対に「情報の信憑性が高いかどうか」を基準とする人の割合は年代が上がるほど高くなる傾向がある(図表4-2-2-11)。年代によって、情報拡散の基準に違いがあることがわかる。
図表4-2-2-11 情報拡散の基準(年代別)
12.1
3.0
4.5
18.2
13.6
25.8
33.3
37.9
18.2
47.0
7.1
2.7
5.4
20.5
17.0
37.5
26.8
25.0
27.7
48.2
7.5
2.2
0.0
10.4
11.9
26.9
22.4
22.4
30.6
44.0
7.2
1.4
4.3
12.2
12.9
28.1
26.6
23.0
45.3
41.7
4.0
6.0
2.5
11.5
10.5
32.0
28.0
19.0
58.0
49.5
0 10 20 30 40 50 60 70
運営事業者が本人確認を行って認証している公式アカウントかどうか
発信者が有名人かどうか
発信者が政府機関や大企業かどうか
発信者が自分の知人や友人かどうか
発信者が拡散を希望しているかどうか
生活に役立つ内容かどうか
社会的に重要な内容かどうか
情報の信憑性が高いかどうか
内容が面白いかどうか
内容に共感したかどうか
20代以下(n=200) 30代(n=139) 40代(n=134)50代(n=112) 60代以上(n=66)
(%)
(出典)総務省「社会課題解決のための新たなICTサービス・技術への人 の々意識に関する調査研究」(平成27年)
平成27年版 情報通信白書 第2部 211
暮らしの未来とICT
第4章

ソーシャルメディアの普及がもたらす変化第 2節
6 SNS利用における課題
ア SNSを利用する際の注意事項の実施状況次に、SNSを利用する際に、「本人の許可なく他人の個人情報やプライバシーに関する情報を書かない」など
の一般的な注意事項にどの程度気をつけているかを尋ねた。その結果をみると、「非常に気をつけている」と答えた人と「気をつけている」と答えた人を合わせると、例示した注意事項については、SNS利用者の約9割が気をつけていると回答している。
年代別にみると、60代以上は「非常に気をつけている」と回答した人の比率が他の年代よりも多く、慎重に利用していることがうかがわれる。他方、20代以下は「あまり気をつけていない」や「気をつけていない」と回答した人の比率が他の年代に比べてやや高い(図表4-2-2-12)。
図表4-2-2-12 SNSを利用する際の注意事項の実施状況(年代別)
43.9
40.1
43.642.2
43.9
58.1
45.8
45.0
46.250.8
48.5
32.3
5.8
10.1
5.92.7
3.5
4.0
4.6
4.9
4.44.3
4.0
5.60 20 40 60 80 100
全体
20代以下
30代
40代
50代
60代以上(%)
n1,178
327
273
256
198
124
本人の許可なく他人の個人情報やプライバシーに関わる情報を書かない
0 20 40 60 80 100
全体
20代以下
30代
40代
50代
60代以上(%)
n1,178
327
273
256
198
124
仕事の具体的な内容など守秘義務のある情報を書かない
48.2
45.3
47.6
46.5
49.0
59.7
41.1
40.1
42.1
46.1
42.4
29.0
6.1
9.8
6.6
3.1
4.0
4.8
4.6
4.9
3.7
4.3
4.5
6.5
0 20 40 60 80 100
全体
20代以下
30代
40代
50代
60代以上(%)
n1,178
327
273
256
198
124
他人への誹謗中傷と受け止められるような内容を書かない
0 20 40 60 80 100
全体
20代以下
30代
40代
50代
60代以上(%)
n1,178
327
273
256
198
124
匿名で利用している場合は、実名の特定に繋がるような内容を書かない
43.4
37.0
44.3
43.0
44.4
57.3
45.4
46.8
44.0
48.4
49.0
33.1
6.9
11.3
8.1
4.3
3.0
4.0
4.3
4.9
3.7
4.3
3.5
5.6
41.3
37.9
41.0
44.1
38.9
48.4
44.9
41.0
45.4
47.3
52.0
37.9
8.7
15.6
8.8
4.3
4.0
6.5
5.2
5.5
4.8
4.3
5.1
7.3
0 20 40 60 80 100
全体
20代以下
30代
40代
50代
60代以上(%)
n1,178
327
273
256
198
124
特定の人種や民族、集団への差別や偏見と受け止められるような内容を書かない
0 20 40 60 80 100
全体
20代以下
30代
40代
50代
60代以上(%)
n1,178
327
273
256
198
124
無暗に他人を挑発するような内容を書かない
38.5
33.3
38.1
39.8
36.9
52.4
47.4
45.3
48.0
50.0
54.0
35.5
9.8
16.5
10.3
5.9
5.1
6.5
4.4
4.9
3.7
4.3
4.0
5.6
39.8
36.1
39.9
38.3
38.9
54.0
47.6
45.0
46.9
53.5
52.5
36.3
8.2
14.1
9.5
3.9
5.1
4.0
4.3
4.9
3.7
4.33.5
5.6
0 20 40 60 80 100
全体
20代以下
30代
40代
50代
60代以上(%)
n1,178
327
273
256
198
124
著作権などの知的財産権を侵害する内容を書かない
0 20 40 60 80 100
全体
20代以下
30代
40代
50代
60代以上(%)
n1,178
327
273
256
198
124
非常に気をつけている 気をつけているあまり気をつけていない 気をつけていない
事実と異なる内容や事実関係があやふやな内容を書かない
36.2
31.2
35.2
38.7
34.3
49.2
49.2
45.3
49.1
53.9
55.6
39.5
10.4
18.7
12.1
3.1
6.1
6.5
4.3
4.9
3.7
4.3
4.0
4.8
0 20 40 60 80 100
全体
20代以下
30代
40代
50代
60代以上(%)
n1,178
327
273
256
198
124
他人からの批判的なコメントには冷静に対応する
35.6
29.1
35.2
36.3
35.9
51.6
51.4
50.8
50.9
54.7
56.1
39.5
8.8
15.3
10.3
5.1
4.5
3.2
4.2
4.9
3.7
3.9
3.5
5.6
32.3
28.1
31.5
32.8
32.8
43.5
54.1
53.8
53.1
57.0
58.1
44.4
9.2
13.1
11.4
5.9
5.6
6.5
4.4
4.9
4.0
4.3
3.5
5.6
(出典)総務省「社会課題解決のための新たなICTサービス・技術への人 の々意識に関する調査研究」(平成27年)
平成27年版 情報通信白書 第2部212
第4章
暮らしの未来とICT

ソーシャルメディアの普及がもたらす変化 第 2節
イ SNSの不適切な利用方法に対する意識「若者等がアルバイト先の店舗の冷蔵庫に入っている
様子や飲食店で悪ふざけをした様子などを撮影した写真をTwitterなどのソーシャルメディアに投稿し、マスメディアに取り上げられているケース」に対して、アンケート対象者がどのような意見を持っているかを尋ねた*17。
全体に「このようなケースが起きるのは、モラルが低下していることの表れだ」との意見や、「ネット社会の変化に対応して、よりしっかりした情報モラル教育が必要だ」との意見を持つ人が多かった(図表4-2-2-13)。年代別にみると、年代が上がるほどこうした意見を持つ人の比率が高くなる傾向にある(図表4-2-2-14)。
図表4-2-2-14 SNSの利用方法に対する意見(年代別)
そもそも仲間内だけに
伝えようとした投稿であり、
社会全体が騒ぎ立てる
必要はない
犯罪行為でない限り
大騒ぎすることではない
このようなケースが
起きるのは、モラルが
低下していることの表れだ
このような行為を行った
人に対しては、退学や
解雇等、厳罰で臨むべきだ
マスメディアが、そのような
ケースを取り上げること
自体が問題を拡大する
原因になっている
ネット社会の変化に対応
して、よりしっかりした
情報モラル教育が必要だ
このようなケースを
防止するために、法律で
罰則を定めるべきだ
自分もノリで気軽に投稿する
ので、一歩間違うと
自分にも起こりうる話である
自分が投稿した内容を削除
したら、周囲から見られない
ようになるべきだ
(例:アプリの機能、削除申請)
このようなことにあまり
関心が無い
20代以下(n=400) 7.0 5.5 42.5 34.5 20.0 37.3 21.8 6.8 8.5 24.030代(n=400) 7.5 4.5 49.5 30.5 18.5 37.3 21.5 3.8 5.5 22.540代(n=400)50代(n=400)60代以上(n=400)
4.5 5.3 57.5 33.8 18.5 41.8 23.3 3.5 7.8 19.55.5 4.3 56.5 35.0 18.3 49.5 26.8 3.3 8.0 16.33.5 6.0 66.5 41.8 21.5 58.5 33.0 2.8 8.5 17.3
0
20
40
60
80(%)
(出典)総務省「社会課題解決のための新たなICTサービス・技術への人 の々意識に関する調査研究」(平成27年)
ウ 留意すべきSNSの特性への認知度最後に、「SNSによっては投稿に位置情報が付くことがある」ことや「SNSによっては投稿の公開範囲を設定
できる機能がある」ことなどの、一般に必ずしも広く知られているとは言えないSNSの特性について、アンケート対象者の認知度を尋ねた。「知っている」と答えた人の比率は年代が上がるほど低くなる傾向があり、60代以上では3割程度の認知度にとどまっている(図表4-2-2-15)。
図表4-2-2-13 SNSの利用方法に対する意見
5.6 5.1
54.5
35.1
19.4
44.9
25.3
4.0 7.7
このようなことにあまり関心が無い
自分が投稿した内容を削除したら、
周囲から見られないようになるべきだ
(例:アプリの機能、削除申請)
自分もノリで気軽に投稿するので、一歩間違う
と自分にも起こりうる話である
このようなケースを防止するために、法律で
罰則を定めるべきだ
ネット社会の変化に対応して、よりしっかりした
情報モラル教育が必要だ
マスメディアが、そのようなケースを取り上げる
こと自体が問題を拡大する原因になっている
このような行為を行った人に対しては、退学や
解雇等、厳罰で臨むべきだ
このようなケースが起きるのは、モラルが低下
していることの表れだ
犯罪行為でない限り大騒ぎすることではない
そもそも仲間内だけに伝えようとした投稿で
あり、社会全体が騒ぎ立てる必要はない
19.9
0
20
40
60
80(n=2,000)
(%)
(出典)総務省「社会課題解決のための新たなICTサービス・技術への人 の々意識に関する調査研究」(平成27年)
*17本設問及び次の設問の作成に当たっては、橋元良明他「誰がネットで情報漏洩するのか?−企業従業員に対するTwitter利用調査−」(『東京大学大学院情報学環紀要情報学研究・調査研究編』No.30(2014年4月)所収)を参考にした。
平成27年版 情報通信白書 第2部 213
暮らしの未来とICT
第4章

ソーシャルメディアの普及がもたらす変化第 2節
図表4-2-2-15 留意すべきSNSの特性への認知度(年代別)
SNSによっては投稿に位置情報が付くことがある
20代以下(n=400) 76.030代(n=400) 60.540代(n=400) 60.550代(n=400) 51.860代以上(n=400) 29.0
020406080100(%)
SNSによっては、他人がメールアドレスで自分のアカウントを
検索できる
20代以下(n=400) 66.530代(n=400) 52.540代(n=400) 52.550代(n=400) 40.360代以上(n=400) 23.8
020406080100(%)
SNSによっては、投稿の公開範囲を設定できる機能がある
20代以下(n=400) 75.030代(n=400) 58.040代(n=400) 57.350代(n=400) 45.060代以上(n=400) 27.5
020406080100(%)
SNSでの発言は、匿名で行っていても本人が特定されることが
ある
20代以下(n=400) 69.530代(n=400) 56.840代(n=400) 57.050代(n=400) 45.060代以上(n=400) 33.0
020406080100(%)
SNSでは他人の投稿に自分の名前がタグ付けされると、そこから自分のプロフィール情報等を確認される場合がある
20代以下(n=400) 65.030代(n=400) 52.040代(n=400) 51.050代(n=400) 39.560代以上(n=400) 28.0
020406080100(%)
SNSによっては設定変更しないと、プロフィールに登録した情報等が全てのユーザーに公開される場合がある
20代以下(n=400) 71.330代(n=400) 58.540代(n=400) 53.350代(n=400) 46.360代以上(n=400) 29.3
020406080100(%)
SNSでは、過去の発言を遡ることで趣味や嗜好などが知られて
しまうことがある
20代以下(n=400) 74.330代(n=400) 59.540代(n=400) 59.050代(n=400) 50.360代以上(n=400) 32.0
020406080100(%)
SNSでは、自分の発言を限定公開していても他人に共有(リツイート等)されると公開される場合がある
20代以下(n=400) 66.330代(n=400) 52.040代(n=400) 49.550代(n=400) 41.860代以上(n=400) 27.5
020406080100(%)
SNSで一度発言した内容は、インターネット上から削除されないことがある
20代以下(n=400) 68.830代(n=400) 58.040代(n=400) 60.050代(n=400) 47.560代以上(n=400) 34.3
020406080100(%)
(出典)総務省「社会課題解決のための新たなICTサービス・技術への人 の々意識に関する調査研究」(平成27年)
7 今後のSNS利用に向けて
以上、アンケート調査の結果を基に、SNSでの「拡散」と「炎上」を巡る現状と課題を探ってきた。プライバシーや知的財産権への配慮など、SNSで自ら情報発信をする際の一般的な注意事項はSNS利用者の間で広く意識されている。しかし、SNS利用者が他人の情報を拡散する際は、情報の信憑性よりも内容への共感や内容の面白さが基準とされる傾向にあり、これがSNSでの炎上が多発する一因となっている可能性がある。
また年代別にみると、若年層はSNS利用率が高く、SNSの各種特性への認知度も高いが、情報拡散時に情報の信憑性よりも面白さを重視する傾向が強く、トラブルに巻き込まれる利用者の割合も高い。一方、シニア層は総じてSNS利用者のモラルが高く、情報の信憑性にも注意しつつ慎重にSNSを利用している様子がうかがえるが、SNSの利用率自体やSNSの各種特性への認知度が低い。
SNSはコミュニケーションのツールとしてだけでなく、様々なサービスのプラットフォームとしても活用されるようになっており、その重要性は今後ますます高まっていくと予想される。全ての人がトラブルに巻き込まれず安心してSNSを利用できるようにするためには、以上のような各年代の利用特性を踏まえて教育や周知啓発を行っていくことが必要だろう。
平成27年版 情報通信白書 第2部214
第4章
暮らしの未来とICT