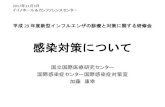結核感染対策マニュアル - pref.shiga.lg.jp · PDF...
Transcript of 結核感染対策マニュアル - pref.shiga.lg.jp · PDF...

湖北地域感染症予防検討会
平成 25 年 3月
結核感染対策マニュアル

1
目次
Ⅰ.結核の基本
1.結核について
(1)結核とは・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3
(2)結核の罹患者数と病院感染・・・・・・・・・・・・・・・・・・3
(3)感染経路・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3
2.結核の症状と発症の高リスク患者
(1)結核の発病・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4
(2)症状・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4
(3)結核発病のリスクが高い患者・・・・・・・・・・・・・・・・・5
3.結核の検査
(1)ツベルクリン反応検査・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5
(2)クォンティフェロン(QFT)検査・・・・・・・・・・・・・・・6
(3)細菌学的検査とその意義・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7
4.結核の治療
(1)肺結核の標準的な治療法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9
(2)結核の治療薬・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10
(3)規則的な服薬が治療の大原則・・・・・・・・・・・・・・・・・11
(4)DOTS・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11
5.結核の医療費
(1)一般医療・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12
(2)入院医療(結核病床入院の場合)・・・・・・・・・・・・・・・・12
Ⅱ.病院編
1.病院における感染対策
(1)外来での対策・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13
(2)入院患者の対策・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14
(3)放射線科テレビ室での対策・・・・・・・・・・・・・・・・・・15
(4)細菌検査質での対策・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15
(5)病理検査室、解剖室での対策・・・・・・・・・・・・・・・・・16
(6)手術室での対策・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・17

2
Ⅲ.施設編
1.高齢者施設での対策
(1)入所時および通所サービス利用開始時の健康診断・・・・・・・・17
(2)入所後および通所サービス利用開始後の定期健康診断・・・・・・18
(3)症状がある入所者および通所者・職員への対応・・・・・・・・・18
(4)結核疑い患者が発生した場合・・・・・・・・・・・・・・・・・19
Ⅳ.共通編
1.結核の届出・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・21
2.結核患者の搬送・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・21
3.接触者健診
(1)接触者健診の概要・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・22
(2)結核患者の感染性の評価・・・・・・・・・・・・・・・・・・・22
(3)結核患者との接触者の区分について・・・・・・・・・・・・・・24
(4)接触者健診の優先度の決定について・・・・・・・・・・・・・・24
(5)接触者健診の実際・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・25
4.職員が結核を発症した場合の対応・・・・・・・・・・・・・・・・・25
5.潜在性結核患者の治療について・・・・・・・・・・・・・・・・・・26

3
Ⅰ.結核の基本
1.結核について
(1)結核とは
結核とは結核菌を原因とする、人から人に伝染する感染
症である。結核菌は長さ1~4ミクロン(ミクロンは1,000
分の1mm)、幅0.3ミクロンの細長い細菌である。ろうの膜に覆われた抵抗力
の強い菌で、1回の分裂に10~15時間を要し、菌の培養検査には長い時間が
かかる。
結核菌は加熱や直射日光(紫外線)には比較的弱いが、冷暗所では3~4
か月間生存可能である。
人に感染した場合、肺結核の頻度が最も多いが、感染した部位によりリン
パ節結核、腎結核、脊椎カリエス、腸結核、結核性髄膜炎などが時として認
められる。
(2)結核の罹患者数と病院感染
結核は日本では、毎年3万人を超える患者が発生しており、このうちおよ
そ12,000人は他人に結核を感染させるおそれのある、塗沫陽性の患者である。
これらの患者の80%以上は、医療機関で発見されている。特に60 歳以上
の高齢者で高率である。
結核の病院集団感染(1人の患者が20人以上に感染させた場合)は全国で
毎年10件程度報告されており、小規模感染はさらにこの数倍に上るといわれ
ている。
(3)感染経路
肺結核の感染経路は空気感染であり、排菌患者の咳などで飛散した、結
核菌を含む飛沫核を吸入することによって起こる。吸入した結核菌が肺胞に
到達し、そこで増殖し
感染が成立する。吸入
した人の80~90%は
免疫が働き発病しない
が、栄養状態が悪く、
抵抗力が落ちている場
合に発病しやすい。ま
た、喀痰中の排菌量が
多いほど、咳の持続期
間が長いほど感染性が
高くなる。

4
2.結核の症状と発症の高リスク患者
(1)結核の発病
感染しても多くは発病に至らず、肺組織やリンパ節内で保菌状態が保た
れる。菌を吸い込んでも発病するのは10人に1~2人程度である。
発病には、感染してから早い時期(6か月から2年くらい)に病気が進む初
感染発病と、感染してから長期間たって発病する既感染発病がある。初感染
発病は大量の菌を吸い込んだときや感染した人の抵抗力が弱いときに起こ
る。既感染発病は昔感染した(そのときは発病していなかった)結核菌が肺
のどこかでじっと眠っていて、何十年もして何らかの理由で目を覚まし再び
活動を始めるもので、体力や抵抗力の低下した高齢者に多くみられる。
(2)症状
肺結核を発病すると、咳(せき)、痰(たん)、微熱、だる
さなど風邪のような症状から始まる。放置しておくと、症状は
だんだん悪化し、痰に血が混じったり、喀血(真っ赤な血を吐
く)、呼吸困難(息苦しさ)を起こすようになる。早期に適切
な治療を行わないと、死に至る場合もある。
初めはふつうの風邪に似ている症状だが、咳などの症状が2
週間以上続いているときは、結核を疑ってみる必要がある。なお、高齢者で
は、全身衰弱や食欲不振、体重減少などの症状が主で、咳、痰、発熱などの
症状を示さない場合もある。そのため、高齢者施設においては全身状態の注
意深い観察が特に重要となる。
(3)結核発病のリスクが高い患者
<結核患者早期発見のための日々の健康観察ポイント>
○全体の印象
・何となく元気がない
・活気がない
○全身症状
・37.5度以上の発熱は続いている
・体重の減少
・食欲がない
・全身の倦怠感(全身のだるさ)
○呼吸器系の症状
・2週間以上続く咳
・痰や血痰(痰に血が混じる)
・胸痛
・頻回な呼吸や呼吸困難(呼吸のえらさ)

5
(3)結核発病のリスクが高い患者
① 糖尿病患者
② 抗癌剤・免疫抑制剤または副腎皮質ホルモンによる治療中
③ 悪性腫瘍、塵肺(珪肺など)
④ 胃切除や空腸回腸バイパス手術後
⑤ 慢性腎不全(人工透析)免疫不全に関連した病気
⑥ 極端な低栄養状態
⑦ 大量飲酒者
3.結核の検査
(1)ツベルクリン反応検査
①ツベルクリン反応検査とは
ア.結核菌感染の有無を診断する検査である。
イ.BCGを受けていない人では結核菌による感染の既往(免疫的な記
憶)を示し、過去に有効な治療や化学予防を受けていなければ生
きた結核菌が体内に潜んでいることを意味する。
ウ.BCGを受けている人は、結核菌による感染を示すのか、BCG接種
の影響を示すのかはわからない。また、免疫の記憶は、しばらく抗
原に曝露されてなければ眠っていることがあるため、BCG接種者は、
ツ反接種後1~3 週間後に再接種(二段階法)したときの反応が正
しいツ反の値である。
②ツベルクリン反応成績の記載様式 【感染・発病の診断 結核予防会 より引用】
判定 略符号 ツベルクリン反応の判定基準
陰性 - 発赤長径9mm以下の者
弱陽性 + 発赤の長径の10mm以上で硬結を触れず二重発赤
のない者
中等度陽性 ++ 発赤の長径の10mm以上で硬結を触れ、あるいは
計測できる者
強陽性 +++ 発赤の長径の10mm以上で硬結を触れるほか、二
重発赤あるいは壊死などを伴う者

③ツベツクリン反応測定方法
(
a1:発赤の長径
a2:発赤の短径
2)クォン
近年、
の白血球
査が開発
分離され
試験管の
この反応
性」、即
しなけれ
化学物質
といえる
BCG 接種
わろうと
ツベル
題が全く
するには
核患者さ
から 2 ヶ
近の感染
ついてま
c1 a1
a1 ×
b1 ×
ティフェ
ツベルク
(T リン
された。
た白血球
中で反応
で白血球
ち「過去
ば「陰性
を産生し
。これを
の影響を
している
クリン皮
ないわけ
、少なく
んと接触
月以上待
の区別が
だ十分に
b1:硬結の長径
b2:硬結の短径
c1:二重発赤の長径
c2:二重発赤の短径
b1
a2
b2
a2
b2(
パ
に
Q
と
6
ロン(QFT)検査
リン反応検査にかわって血液中
球)の反応を用いた新しい検
この検査は、採血した血液から
と、結核菌の 2 種類の蛋白質を
させる。
がインターフェロン γという化学物質を産生すれば「陽
結核菌に感染した」ことがある、逆に化学物質を産生
」、即ち「結核菌に感染していない」と判断する。
た白血球の持ち主は、結核菌に感染した(ことがある)
FT 検査(クオンティーフェロン TB-3G 検査)といい、
ほとんど受けないことからツベルクリン皮内検査に変
。
内検査に比べ、画期的かつ正確な検査といえるが、問
ではない。結核菌に感染してから QFT 検査が「陽転」
も 8~10 週間かかるといわれている。このことから結
があった場合、この検査を受けるには最後に接触した日
つ必要がある。なお、「陽性」を示した場合、過去と最
できない。また、5 才未満の子供は、検査結果の判断に
検討されていないため検査はできない。
c2
c1 × c2 )(他の副反応があれば記入)

7
「陽性」の場合は過去と最近の区別はできないが、結核菌に感染して
いることが疑われるため、胸部X線検査等の健診や発病予防のための治療
を行うことになる。
「陰性」の場合は、「結核菌の感染はない」と判断する。
(3)細菌学的検査とその意義
結核症の診断は、患者の基礎疾患、臨床症状、画像診断などの臨床的な
所見などからある程度は可能だが、最終的には細菌学的検査で確定する。
塗抹検査(顕微鏡検査)、培養検査、核酸増幅検査(PCR法)を実施する。
① 検体採取について
ア. 膿性痰の採取に努める。
イ. 3日間連続して喀痰を採取する。
ウ. 採取容器は専用容器を用いる。
エ. 結核菌は病巣部から採取された膿性痰から検出される。唾液の
混入が多く膿性痰の少ない材料は検出感度が低く、検査材料とし
ては不適切である。
(4)検査の意義
①塗抹検査(チールネールゼン法)
ア.迅速に結果が判明する。
イ.検出感度は培養検査や核酸増幅検査に劣る。
ウ.結核菌と非結核性抗酸菌との鑑別はできない。
【QFT 採血時の注意事項】
特に次の 2 点には注意する
1.採血管は室内温度(22±5℃)に戻してから使用する。
2.1 検体に付き、3 本の専用採血管に各 1ml(全 3ml)採血し、採血後上下
に 5 秒間または 10 回振って、十分に混合する。採血管の内表面全体が血
液で覆われていることを確認する。(強く振りすぎると誤った結果になる
ことがあるため注意する)

8
②培養検査
ア.陽性結果を得るのに数週間を要する。
イ.検出感度が高い。(核酸増幅検査よりやや高い)
③核酸増幅検査(PCR法)
ア. 1~2日で結果が得られる。
イ.検出感度は高い。
ウ.抗結核薬で治療中の患者においては、喀痰中に死滅、あるいは増
殖能を失った結核菌が存在するため、増殖陰性でも核酸増幅検査が
陽性となることがある。
④塗抹、PCR、培養検査結果の解釈
塗抹 PCR 培養 検査結果の解釈
- - - 陰性
- - + 微量排菌
- + + 微量排菌
+ + + 陽性
+ + - 死菌の可能性あり
+ - + 非結核性抗酸菌(結核菌以外の抗酸菌)
+ - - 抗酸性のある汚染菌が染色された

9
4.結核の治療
結核の治療は、化学療法によることを原則とする。化学療法によっては治療
の目的を十分に達することができない場合には、外科療法等を行う場合もある。
化学療法は、患者の結核菌に感受性を有する抗結核薬を 3 剤又は 4 剤使用す
ること原則とする。
(1)肺結核の標準的な治療法
①標準治療法(A)
(EB)
INHRFPPZA
SM(EB)
0 2 4 6 9 12ヶ月
②(標準治療法(B)
(EB)
INHRFP
SM(EB)
0 2 4 6 9 12ヶ月
※過去に結核の治療をされた方は、結核菌が薬剤耐性(薬が効かなくなるこ
と)になっている可能性がある。
医療機関で、薬剤感受性試験(薬の効果の度合いを調べる検査)を行い、治
療に有効な薬が選ばれ治療が始まります。薬の種類や治療期間が標準的な治
療と異なることもある。

10
(2)結核の治療薬
※ 薬剤耐性(薬が効かなくなること)の発生を防ぐため、複数の異なる薬を組み合わせて治療する。
薬
(くすり)
形
(かたち)
副作用
(ふくさよう)備考
I N H
(イソニコチン酸ヒドラジド)
<製品名>
イスコチン、イソニアジ
ド、ヒドラなど
白い錠剤 指先のしびれ
食欲不振
肝障害
結核菌を殺す力の強
い薬です。治療の主
力となります。
末梢神経障害の防止
のためビタミン剤を
併用することがあり
ます。
R F P
(リファンピシン)
<製品名>リマクタン など
赤または
青と赤のカ
プセル
胃腸障害(むかつき、腹痛、下痢、
食欲不振)
肝障害
アレルギー症状(発疹・かゆみ)
この薬は、尿、涙汗などに排泄さ
れ赤い色が付きますが異常では
ありません。
INHと同様に結核
菌を殺す力の強い薬
です。
結核治療のために特
に大切な薬です。短
期化学療法の中核的
なお薬です。
E B
(エタンブトール)
<製品名>エサンフトール、エブトール など
黄色の錠剤 視力低下
視野狭窄
下肢のしびれ
他の抗結核薬と一緒
に飲むことで結核菌
の増殖を抑える力を
高めます。
P Z A
(ピラジナミド)
<製品名>
ピラマイド など
白い粉末 肝障害(吐き気・食欲不振・黄疸)
高尿酸血症、関節痛を伴うことも
あります。
治療期間の短縮に有
用な薬です。
S M
(ストレプトマイシン)
注射薬 口が渇く、めまい、耳鳴り、難聴 結核菌を殺す力があ
ります。

11
(3)規則的な服薬が治療の大原則
結核は、指示された期間、薬をきちんと飲めば治癒する。
薬を飲み始めてしばらくすると、咳や微熱等の症状は治まるが、ここで「治
った」と早合点して薬をやめると、症状がぶり返したり、あわてて薬を飲み
始めても耐性菌ができて薬が効かなくなっていることがある。
症状もないのに毎日薬を飲む・・これは人間の能力の限界を超えたこと
であると言われている。症状が消えても、結核菌が弱っているだけのため、
薬をやめると、菌は再び増殖を始める。
(4)DOTS
「DOTS」とは直接服薬確認療法のことである。患者
本人以外の人が、患者の服薬を継続的に確認し、支援す
るサービスのことをいい、結核治療の中断防止に効果的
とされている。
退院前には、退院後確実に服薬が継続できる方法について、患者、家族、
病棟看護師、ケアマネージャー、保健所保健師等で確認している。
一人暮らしの老人などの治療を確実にするために、服薬を支援する
DOTS の推進が強化されており、保健所においても結核患者の状況に応じ
た服薬確認の支援、毎日飲み続けられるための工夫等を一緒に考えて結核
患者の療養を支援している。

12
5.結核の医療費(結核医療費公費負担制度)
(1)一般医療
人に結核を感染させるおそれのない結核患者(一般患者)の医療費は、
感染症法第 37 条の 2 で定められた治療(主に治療薬)の 5%が自己負担と
なる。
病院で受ける全ての治療・検査が対象にはならない。
総医療費を健康保険本人の例で示すと次のようになる。
公費負担対象外医療
公費負担対象医療
(2)入院医療(結核病床入院の場合)
人に結核を感染させるおそれのある結核患者は、感染症法第 37 条に基づ
き、感染のおそれがなくなるまでの期間、結核病床に入院となる。
その間の医療費は、原則として自己負担を生じない。年間の税額 147 万
円を超える人は、公費対象医療費の 5%の負担となる。
合計税額
147 万円以下の場合
合計税額
147 万円超の場合
加入保険(70%)
自己負担(30%)
加入保険(70%)
公費(25%)
加入保険(70%)
公費負担(30%)
加入保険(70%)
公費(25%)
自己負担:公費対象医療費の5%
自己負担:公費対象医療費の 5%

13
Ⅱ.病院編
1. 病院における感染防止対策
結核の成立には、感染源患者の排菌量、空気中の結核菌密度、感受性宿主が
吸い込む結核菌の量が影響する。
結核の病院感染を防止するために、以下の対策を組み合わせ総合的に実施する。
患者の早期発見、他の患者との分離、早期治療
空気感染予防策
「感染経路別予防策:空気感染予防策」を参照
化学予防投与、定期健診、有症時の受診
(1)外来での対策
①問診及びサージカルマスクの着用
受付担当者は、患者が記載した問診票を確認し、咳・痰の症状があり
結核の既往や接触歴などがあれば担当看護師に知らせる。また、咳症
状のある患者にはサージカルマスクを着用するように指導し、飛沫の
拡散を防ぐ。
②空気感染対策
ア.診察にて結核が疑われた場合には、医師がN95マスクの装着を職
員に指示する。医師・看護師ともにN95マスクを装着し対応する。
イ.患者を専用診察室または個室に案内し、呼吸苦がない限りサージ
カ ルマスクを装着してもらう。ドアは閉鎖する。
<N95マスク着用方法>
①マスクの上下を確認
する
②グレーのノーズフォ
ーム部分が鼻に当たる
部分
③マスクの中央を持
ち、鼻当て部を広げな
がら開く
④マスクを顔に当て、
上のゴムバンドを頭頂
部にかける
⑤下のゴムバンドを首
回りにかける
⑥鼻当て部、顎当て部
を引っ張り整える
⑦両手の指で鼻当て部
が鼻に密着するように
押し当てる
⑧両手でマスクを覆
い、空気の漏れがない
か確認する

14
③ 喀痰採取方法
ア.患者にサージカルマスクを着用してもらい、採痰ブースに誘導する。
採痰ブースがない場合は、他の患者がいない場所や屋外で採痰して
もらう。
イ.吸入器はディスポーザブルを使用するか、使用後は次亜塩素酸ナト
リウム液で消毒する。
ウ.誘発する必要がある場合の吸入などの誘発方法は、呼吸器科医師の
指示を受ける。
エ.検査結果が判明するまで、個室か離れた場所で待機してもらう。
オ.家族が同伴の場合には、廊下で待機してもらう。やむを得ず同席す
る場合は、N95マスクを着用してもらう。
④ 喀痰塗抹陽性、PCR陽性であった場合
ア.原則として外来で診断し、結核病床を有する病院へ紹介する。
イ.患者退室後は、2時間密閉放置し、換気が終了するまで使用しない。
ウ.清掃は通常の方法でよいが、湿性生体物質が付着した環境は、消毒
用アルコールで清拭する。
(2)入院患者の対策
①喀痰塗抹検査陽性:
結核菌の可能性あり、排菌のおそれあり。ただし、非結核抗酸菌
の可能性もある。
ア.患者に以下のことを説明する。
(ア)結核の疑いがあり、排菌しているおそれがある。
(イ)感染予防について説明する。
・痰や咳が出るときの対処:
痰は必ずティッシュにとり、ビニール袋に密閉して捨
てる。
くしゃみ・咳の出るときは、ティッシュや手で覆う。
・面会について:
家族の面会は出来るだけ控えてもらう。
(特に、小さな子ども・風邪をひいているなど体力が落
ちている方は面会を避けてもらう)
面会される場合は、専用のマスク(N95)を装着しても
らう。(面会者にN95マスクの装着方法を指導する)
イ.トイレのある個室へ移床する。
(陰圧空調設備がある個室がある場合は、優先的に使用する)

15
ウ.空気予防策実施。「感染経路別予防策:空気予防策」を参照
エ.咳のある結核患者の場合、可能な限り、病室内においてもサージ
カルマスクを装着する。また、咳嗽時にはハンカチやティッシュ
ペーパーで口元を多い、飛沫の拡散を防ぐよう指導する。
オ.患者退室後、2時間は密閉放置し換気が終了するまで次の入室を避
ける。換気が終了後に通常の清掃を行う。
カ.2類感染症のため、使用したリネンは一般リネンの取り扱いとは別
扱いとする。
②喀痰塗抹検査陽性・PCR検査陽性:
結核菌確定、排菌の可能性が高いと判断する。
ア.原則結核病床を有する病院に転院する。
③喀痰塗抹陽性・PCR陰性:
非結核性の抗酸菌である可能性が高く、対策は不要。
④喀痰塗抹陰性・PCR陽性
微量排菌の可能性がある。
①と同様の対策を実施
(3)放射線テレビ室での対策
① 結核が疑われる患者に気管支内視鏡検査を行う場合は、術
者も介助者も、N95マスクとディスポガウンを装着する。
② 順番は最後にし、検査終了45分~2時間はドアを閉鎖し換気が終了す
るまで、他の患者に使用しない。
(4)細菌検査室での対策
① 喀痰など下気道由来材料のすべて、また、結核が疑われる材料はバイ
オハザード用安全キャビネットの中で作業を行う。
② 培養された結核菌は、無菌室のバイオハザードキャビネットの中で
作業を行う。
③ 培養された結核菌の付着したディスポ器具、器材は、バイオハザー
ドキャビネット内で、ビニール袋などに密閉してから取り出し、感染
性廃棄物処理容器へ廃棄する。
④ 作業時はN95マスクを装着する。

16
(5)病理検査室、解剖室での対策
①検体の取り扱いについて
結核が疑われる材料は、バイオハザードキャビネットの中で作業を
行う。
②検体の取り扱いについて
検体の種類 検体の処理方法 感染防護
細胞診検体 ・アルコールなどで固定さ
れた検体は感染源とな
る可能性は低い。
・風乾された検体は感染源
となりうるので注意が
必要。
手袋
サージカルマスク
生検組織検体 ・小さく割を入れる必要の
ない未固定検体
・割を入れる必要のある未
固定検体
手袋、サージカルマ
スクを装着し速やか
に固定操作をする
術中迅速検体 ・検体処理(割入れ、凍結、
薄切)
N95マスク
手袋
クライオトー
ム
汚染は避けられない
ため、定期的な消毒
をする。
③解剖時の注意
ア.解剖時は、できる限りN95マスクを着用する。
イ.特に結核が疑われる症例に対しては、解剖室内の全員が着用する。
ウ.部外からの入室者は、N95マスクの他、ディスポガウンも装着す
る。
エ.粟粒結核が疑われる症例は、摘出する臓器を必要最小限とし、摘
出の際には飛沫の飛散を防ぐ操作を行う。また、原則として臓器
の割入れは固定後に行う。
オ.電動鋸には、覆いを掛けて広範な飛沫の飛散を防ぐ。
カ. 使用した器材は感染性廃棄物処理容器へ廃棄、再生機器は部署内
または中央材料室に依頼し適切に処理する。

17
(6)手術室での対策
結核と診断された患者、疑いある患者の手術では、以下の対応を行う。
①手術の順番
可能であれば最後とし、手術室ホール・廊下での他患
者や医療従事者との交差に配慮する。
②部屋の使用
手術中の入退室は最小限とする。手術が終了し患者が退室した後は
30分間、閉鎖・換気を行う。その後通常の清掃を実施する。
③マスクの装着
結核病巣の切開、粟粒結核患者の手術では医療従事者は、N95マス
クを装着する。
喀痰から結核菌が検出されている患者は、サージカルマスクを装着し
入室する。
④麻酔器
通常の清掃を行う。
Ⅲ.施設編
1.高齢者施設での感染対策
結核感染対策の基本となる要素は、①結核菌の除去、②結核菌の密度の低下、
③吸入結核菌数の減少、④発病の予防、⑤発病の早期発見だが、高齢者施設で
は、特に発病の予防と早期発見が重要と考えられる。
(1)入所時および通所サービス利用開始時の健康診断
入所時および通所開始時には、判定用として提出されている健康診断書
等に加え、胸部エックス線写真による結核発病の有無を健康診断書で確認す
ることが望まれる。
最低限必要な項目は以下の通り。
①問診
結核を疑う症状があるかどうか(咳、痰、発熱、胸痛など)
②過去に結核の既往があるかどうか(結核性胸膜炎、じん肺、肋膜な
どを含む)
③過去に結核患者との接触があるかどうか(家族や親族、
親しい友人 など)
④免疫力の低下する基礎疾患があるかどうか(糖尿病、悪性腫瘍、腎
透析を必要とする腎疾患、胃切除後、リウマチや喘息などに対する
ステロイド治療中など)

18
⑤胸部エックス線検査
定期健康診断や有症時のエックス線検査と比べるため、検査所見
は必ず記録に残す。
胸部エックス線写真に異常所見があるときは、以前のエックス線写
真との比較や、呼吸器症状の有無、喀痰検査結果などから、総合的
に判断する必要がある。
また、肺結核で外来治療中の患者でも、治療が順調に進み、結核
菌の排菌がないと確認されれば入所や通所は可能であるため、主治医
と相談する。
(2)入所後および通所サービス利用開始後の定期健康診断
結核に関しては,社会福祉施設の従事者及び入所者に定
期の健康診断が法律によって義務づけられており、入所
者は年1回実施することになっている。また、法律で義
務づけられていない施設(老人保健施設、デイサービス
センター等の通所施設)においても、利用者の健康管理
及び施設職員への感染防止の観点から、定期的な健康診
断を行うことが望まれる。
定期健康診断においては、胸部エックス線検査のみならず、結核症状の有
無(咳、痰、発熱、胸痛など)を確認することも重要である。立位での胸部エ
ックス線検査が困難な入所者に対しては、寝たままの状態でも胸部エックス
線検査ができる施設で検査を行うか、ポータブルの撮影装置を使うことによ
り、検査が可能となる。胸部エックス線検査ができなかった場合や、検査の
結果が経過観察となっている場合は、呼吸器症状の有無に関係なく喀痰検査
を行うことを考慮する。健康診断の結果、精密検査が必要と診断された場合
は、確実に精密検査を実施することが望ましい。
(3)症状がある入所者および通所者・職員への対応
結核の症状には、咳、痰、発熱、胸痛などがあり、これらの症状が2週間
以上続く時は注意を要する。中でも咳は見落としてはならない、最も重要な
サインである。それは、咳が結核の症状として最も頻繁に現れることと、も
し排菌している結核であった場合、咳により結核菌が飛散し、周囲の人を感
染させる危険性が高くなるからである。なお、咳がある場合でも、咳をして
いる人がマスクを着用することで、周囲への感染の危険性を減らすことがで
きる。

19
施設長は、入所者および通所者の健康管理に際しては、常に
呼吸器症状 の有無に気をつけ、2週間以上症状が続く時は、
医師の診察を受けるよう手配し、必要に応じて胸部エックス線
検査や喀痰検査を行う。職員も同様に、呼吸器症状が続く場合
は必ず医師の診察を受けるようにする。現在結核は、高齢者の
発症者が多く、若年者ほど感染しやすい傾向にあることから、高齢者施設で
は、入所者や通所者から若い職員への結核感染が起こりやすい状況にあるた
め、常に結核の症状を念頭において、早期受診を心がけることが大切である。
①咳が出る入所者および通所者には
ア.サージカルマスクを着用してもらう
イ.早期に受診させる
②咳症状があり、診察の結果精密検査が必要な入所者の場合
ア.サージカルマスクを着用してもらう
イ.できれば個室にうつす
ウ.部屋の換気を十分におこなう
エ.他の入所者との接触を制限する
オ.結核患者への接触の際はN95マスクを使用する
③咳症状があり、診察の結果精密検査が必要な通所者の場合
ア.診断が確定するまではサービス利用を控えるよう本人および家族
と相談する。
イ.自宅ではできれば個室で過ごすことが望ましい
(4)結核疑い患者が発生した場合
①入所者の場合
ア.有症状者の受診
多くの高齢者福祉施設では、通常、胸部エックス線撮影装置や
結核菌検査を行う設備がないため、施設長は2週間以上呼吸器症状
の続いている入所者について、これらの検査がで
きる医療機関を受診する。この場合、入所者にか
かりつけの医療機関があれば、以前の結果と比較
できるため診断の参考になる。
イ.結核の診断
医療機関では、結核を発病しているかどうか調べるために胸部
エックス線検査や喀痰検査が行われる。喀痰から結核菌が発見さ
れれば診断は確定するが、結核菌が見つからなくても症状や胸部
エックス線写真、血液検査などから総合的に診断されることもあ

20
る。
喀痰検査は周囲への感染の危険性を判断する上で重要な検査の
ため、本人もしくは職員が、確実で正しい採痰方法についてきち
んと指導を受けることが必要である。他の人にうつす可能性のあ
る患者は、結核専門病院での入院治療が基本となる。病院受診・
入院までの間は個室対応とする。またケアをする職員は、N95マ
スクを適切に装着する。患者にはサージカルマスクを着用しても
らい、必要最低限を除いて個室の外には出ないようにしてもらう。
ウ.保健所と対応方針協議
保健所は結核を診断した医師からの届出を受理する
と登録を行い、患者の生活状況等の調査を行う。この届
出とは別に施設から保健所に患者発生の報告を速やか
に行い、その後の対応方法について保健所と協議を行う。
エ.結核病院への患者搬送あるいは通院治療
結核菌陽性の患者は高齢者福祉施設では入所さ
せたまま治療することはできないため、結核病床
を有する病院に搬送することになる。職員はN95
マスクを着用し、車内の空気は常に入れ替わるよう配慮する。
結核菌陰性の患者については通院治療を行う。この場合、結核感
染への過度の心配から、患者が不当な処遇を受けないよう関係者は
配慮するとともに、同室者の理解を得る必要がある。
オ.施設内感染対策委員会へ報告
施設長は、患者の発生情報を施設内感染対策委員会へ報告する。
委員会は保健所と連携をとりながら、他の入所者、職員の健康状態
の把握、過去の健康診断受診状況およびその結果などの情報収集に
努めるとともに、入所者や職員の間に不安が広がらないよう適切な
情報提供と教育を行う。
カ.事後措置の要否の検討
患者の情報(既往歴、家族歴、発病からの生活状況、症状の出現
状況、診断時の検査所見など)と、他の入所者、職員の健康状態、
過去の健康診断受診状況及びその結果などの情報をもとに、保健所
と事後措置の必要性について検討する。
キ.接触者健診が必要になった場合
周囲への感染が懸念される場合、接触の頻度が高いほど感染を受
けた可能性が高いため、健診対象者としては同室者や長時間行動を
共にした人たちを濃厚接触者として、優先的に健診を行う。濃厚接

21
触者の中から患者、感染者が発見されなければ、その人たちより接
触頻度の低い人たちへの感染の可能性は低く、これ以上健診を行う
必要はない。しかし、濃厚接触者の中から患者、感染者が発見され
た場合には、次の接触頻度の人たちへ健診対象を拡大する。このよ
うに接触者健診の対象者は接触の頻度をもとに同心円状に考え、感
染の有無を見ながら健診を進める。そのため、必要に応じて接触者
名簿などを保健所へ提出する。
②通所者(ショートステイやデイサービス利用者など)の場合
ショートステイやデイサービス利用者といった通所
者の場合も、結核発生時の対応手順は入所者と同様に行
う。通所者が結核と診断された場合には、感染性の判断
が明確になるまでは他の利用者や職員への感染拡大予
防のために、通所サービスの利用を控えていただくよう
家族およびケアマネージャーと話し合う。加えて、保健所との連携の
必要性を家族に説明し、保健所への情報提供の了解を得る。
主治医より検査の結果、感染性がないと判断されれば、服薬治療中
であっても通所サービスを利用再開していただくことは可能である。施
設として、サービス利用再開にあたって不安な点があれば、保健所に相
談する。
③保健所との連携
入所者または職員が結核と判断された場合、もしくは結核の発症が
疑われる場合には、速やかに保健所に連絡する。
Ⅳ.共通編
1.結核の届出
届出書類 届出期間
結核発生届 診断後直ちに
入(退)院結核患者届出票 7日以内
結核医療費公費負担申請書 治療開始後(時)直ちに
2.結核患者の搬送
<排菌のある患者を、結核感染症指定医療機関に移送する方法>
-外来・入院患者共通-
救急車での搬送は原則行なわれていない。よって自家用車や民間の寝台車で

22
の搬送が困難な重篤な病状の患者は移送しない。各施設の基準に応じて、施設
が所有する救急車を使用することは問題ない。
また、症状が軽微でも排菌が判明した患者は、公共交通機関を利用した移動
は避けるよう指導する。
酸素吸入が必要な患者を移送する場合は、医療者がN95マスクを装着し同乗
する。
(1)搬送方法
優先順位 搬送手段 搬送時の感染対策
① 自家用車を準備する
車の窓をあけて、患者にサージカルマ
スクを装着する。
同乗者はN95マスクを装着する。
(同乗者にマスク着用方法を指導)
② 自家用車がない場合
施設の基準に準じて、施設所有の救急
車等で搬送する。
患者はサージカルマスク、同乗者はN
95マスクを装着する。
3.接触者健診
(1)接触者健診の概要
①塗抹陽性患者との至近距離での接触者は、接触者健診の対象となる。
②接触者の範囲については、保健所と患者の感染性を協議した上で決定
する。また、各施設で決定している基準に沿って決定する。
③検診の結果、予防内服の適応となった患者は、各施設の基準に従って
対応を行うか、呼吸器内科を受診し専門医に相談する。
(2)結核患者の感染性の評価
健診対象者の調査の前に、接触者健診の必要性を判断しなければなら
ない。保健所に届けた結核患者について、「感染性」の評価を行う必要が
ある。「感染性」の評価は保健所の指導の元で行うが、そのフローチャー
ト(感染症法に基づく結核の接触者健康診断の手引き)を紹介する。

23
(※1)肺実質病変を伴い、喀痰検査で結核菌が検出された場合(小児では稀)。
(※2)3回行われていない場合には、喀痰検査の追加依頼などを含めて慎重に
対応する。
(※3)小児結核及び若年者の一次結核症(結核性胸膜炎等)の患者では、そ
の感染源の探求を目的とした接触者調査と健診が必要。
(※4)連続検痰の結果がすべて塗抹陰性(核酸増幅法検査でも陰性)で、培
養検査でもすべて陰性と判明した場合には、「高感染性」の評価を撤
回してよい。核酸増幅法検査または培養検査で「非結核性抗酸菌」に
よる病変と判明した場合は、「接触者健診は不要」と判断する。
(※5)喀痰塗抹陽性例(高感染性)に比べて相対的に感染性が低いという意
味。喀痰塗抹(-)でも、その核酸増幅法検査でTB(+)の場合は、
塗抹(-)培養(+)と同様に、「低感染性」とみなしてよい。
(※6)例えば,接触者の中に乳幼児(特にBCG 接種歴なし)や免疫低下者等
がいた場合。
初発患者の診断名(結核罹患部位)
肺結核、喉頭結核(結核性胸膜炎、粟粒結核)(※1)
排外結核(肺結核の合併なし)
喀痰塗抹(+) 塗抹(-)(原則 3回)(※2)
接触者検診は不要(※3)
PCR 検査 or培養検査で(+)
PCR 検査と培養検査共に(-)
結核に特徴的 な 空 洞(+)
空洞(-)かつ
培養(+)
空洞(-)かつ
培養(-)
高感染性綿密な接触者の把握と健診が必要
接触者健診は不要
高感染性(※4)
綿密な接触者の把握と健診が必要
低感染性(※5)
ハイリス接触者・濃厚接触者の把握と健診が必要
限られた状況(※6)にお い て のみ、接触者健診を実施(※3)

24
(3)結核患者との接触者の区分について
対策の発端となった結核患者が結核を感染させる可能性のある期間に
おいて、その患者と同じ空間にいた者を「接触者」と定義し、感染・発病
の危険度に応じて以下の4種類に区分する。
①ハイリスク接触者
感染した場合に発病リスクが高い、または重症型結核が発症しやすい
接触者。
ア.乳幼児(特に、BCG接種歴のない場合)
イ.免疫不全疾患(HIV感染など)、治療管理不良の糖尿病患者、免疫
抑制剤や副腎皮質ホルモン等の結核発病のリスクを高める薬剤治
療を受けている者、臓器移植例、透析患者など
②濃厚接触者
結核患者が感染性であったと思われる時期(感染性期間)に濃密な、
高頻度の、または長期間(注)の接触があった者を「濃厚接触者」と定
義する。
ア.患者の同居家族、あるいは生活や仕事で毎日のように部屋を共有し
ていた者
イ.患者と同じ車に週に数回以上同乗していた者
ウ.換気の乏しい狭隘な空間を共有していた者などが相当する。
エ.結核菌飛沫核を吸引しやすい医療行為(感染結核患者に対する不十
分な感染防護下での気管支内視鏡検査、呼吸機能検査、痰の吸引、
解剖、結核菌検査等)に従事した者
オ.集団生活施設の入所者(免疫の低下した高齢者が多く入所する施設、
あるいは刑務所等で感染性結核患者が発生した場合)
③非濃厚(通常)接触者
濃厚接触者ほどではないが、接触のあった者(結核患者を数回訪ねて
いた、週に一回程度短い時間会っていたなど)
④非接触者
初発患者と同じ空間を共有したことが確認できない者(原則とし て
接触者健診の対象外)
(4)接触者健診の優先度の決定について
結核患者の家族、同室の患者および患者家族、排菌患者に関わった医
療従事者・清掃業者などの曝露者のリストの作成を行ったうえで、感染担
当者は病棟、診療科及び保健所の担当者と相談しながら、どこまでを健診
の対象者に含めるかを決定する。

25
具体的には、優先度の高い方から①最優先接触者、②優先接触者、③低
優先接触者の3つに区分する。接触者健診は、優先度の高い対象集団から
低い対象集団へと「同心円状」に段階的に対象者を拡大する方法が基本と
なる。
第一同心円(最優先接触者及び優先接触者)の健診で患者が発見され
ず、感染疑い例もない場合は、接触者健診の範囲をそれ以上拡大する必要
はない。第一同心円の健診で新たな患者が発見(または複数の潜在性結核
感染者が発見)された場合は、第二同心円(低優先接触者)にも健診の範
囲を拡大する。
(5)接触者健診の実際
接触者健診では、適切な時期に結核感染の有無を確認することが重要
で、対象者には基本的に「クォンティフェロン(QFT)検査」を実施する。
QFT検査の実施時期は、潜在性結核感染症の過剰な治療を防ぐために、
原則として①結核患者との接触直後、②最終接触から10週間経過した後に
実施することが望ましい。結核患者と接触してから2週間以上経過した場
合には、「前値」としてのQFT検査の意義が少なくなるため、①を省略す
ることも可能である。ただし,患者との接触期間(結核菌への曝露期間)
が長い、または既に二次患者が発生しているような場合、あるいは対象者
が「最優先接触者」(その中でもハイリスク接触者)である場合には、(結
核患者と接触してから2週間以上経過していた場合であっても)初発患者
発生直後のQFT検査を行い、「陰性」の場合は最終接触から2~3ヶ月(8
~12週)経過後に再度QFT検査を行う。
4.職員が結核と診断された場合の対応
(1)感染者のスクリーニングとフォロー
① 職員が結核を発病した場合は、その感染性(排菌の有無)を迅速に
判断する。
② 感染性の否定ができない間は、医療等用務に従事しない。
③ 潜在性結核感染症、非感染性の肺結核と診断された場合は、治療を
受けながらの勤務は可能である。
(2)職場復帰について
① 非感染性が証明されるまで職場復帰はできない。

26
5.潜在性結核患者の治療について
定期外検診(接触者健診)、並びに採用時定期健診で、QFT検査陽性者は呼
吸器科を受診し、結核発病の有無について精査をする。発病していない(排菌
していない)場合は、潜在性結核と診断される。
潜在性結核感染症の治療を行なう場合は、通常の結核の届出を行なうことに
なる。結核菌は感染が成立しても、臨床的に明らかな結核を発病する人は、生
涯のうちで10%といわれている。そのうちの半数は感染成立後1年以内に発症す
る。潜在性結核感染症とは、結核菌による感染は成立しているが、臨床的に発
病していない人をいい、抗結核薬による治療は、体内に潜んでいる結核菌を殺
し、発病を予防する目的で行なわれる。
治療にかかる費用は、公務(労務)災害や結核医療費公費負担の対象となる。