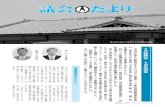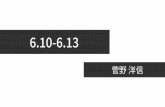地方議会のあり方と議員の政策立案 - WordPress.com · 2010-11-21 · 地方議会は,住民の直接公選による議員によって構成される合議制の機関であり,間接民主主義におい
はじめに - Ministry of Internal Affairs and Communications · はじめに...
Transcript of はじめに - Ministry of Internal Affairs and Communications · はじめに...


はじめに
非常通信協議会(以下「協議会」という。)は、昭和26年7月に電波法第74条
に規定する通信(非常の場合の無線通信)の円滑な実施を図ることを目的に設立され、
その主な活動として、非常の場合における通信計画の作成、通信訓練の実施及びその
他の必要な措置を行っている。
また、協議会は発足以来50余年間にわたり、非常時における非常通信の円滑な実
施の確保に向けて積極的に通信体制の整備に取り組み、防災活動に多大な貢献を果た
し、被害の拡大の防止、軽減の一翼を担ってきた。
一方、近年の情報通信技術の進展により、無線通信ネットワークは、国民ニーズの
多様化等に対応し構築されてきていることを踏まえ、被災状況の即時把握、各種防災
情報の伝達など国・地方公共団体間、住民等の間の情報共有のために、施設整備の状
況に応じ絶えず見直しを行い、地域の実情に即した実践的な計画とするとともに、社
会情勢にあった非常通信の円滑な実施体制の確立を検討すべき時期に来ているものと
考える。
このため、平成14年4月の第51回中央非常通信協議会の総会決定を踏まえ、「非
常時の通信確保の在り方に関する調査検討会」を設置し、計7回にわたり調査検討を
行った。
本報告書は、本調査検討会における調査検討結果を取りまとめたものである。
本報告書の「地方通信ルート策定のための指針」を有効に活用し、非常時に強い地
域社会の形成のためにお役立ていただければ幸いである。


1 調査検討の目的
電波法第74条第 1 項に規定する通信及びその他非常時において用いられる必要な
通信(以下「非常通信」という。)の円滑な運用を図るため、近年の通信技術の発達
や通信機器の機能向上を踏まえ、現状にあった非常通信ルートの計画、非常通信訓練
の方法や協議会組織の見直しなど、非常時における通信確保の在り方について調査検
討を行うことを目的とする。
2 調査検討項目
近年の通信事情にあった非常通信の円滑な確保を図るため、今までの協議会の活動
の中から課題や問題を整理し、下記の項目について検討を行った。
(1)非常時における活動体制について
・要請会議の位置付けと必要性の再確認
・地方非常通信協議会(以下「地方協議会」という。)と都道府県との連携強化につ
いて
(2)通信計画について
・中央通信ルートの新規開拓
・地方通信ルートの確立
・新技術を利用した通信計画
(3)訓練について
・実践的な訓練方法
・市町村・民間機関等の訓練参加促進(自治体等主催の防災訓練との連携実施)
(4)周知・啓発について
・過去の周知・啓発効果の検証と問題把握
・新たな周知・啓発活動
・構成員増強による組織強化
1

3 調査検討会の構成
中央非常通信協議会(以下「中央協議会」という。)の構成員とオブザーバーによっ
て構成。事務局は、中央協議会の事務局(総務省総合通信基盤局電波部基幹通信課)。
「非常時の通信確保の在り方に関する調査検討会」構成員名簿
(敬称略)
構 成 機 関 の 名 称 構 成 員
1 消防庁 防災情報室 課長補佐 市川 麻里
2 内閣府(防災担当)政策統括官付参事官付参事官補佐(通信担当) 則武 潔
警察庁 情報通信局 情報通信企画課 理事官 降簱 喜和男 ※13
情報通信局 情報通信企画課 課長補佐(指導) 中島 五郎 ※2
防衛庁 長官官房情報通信課 基盤班長 坂本 大祐 ※34
同上 林 美都子 ※4
水産庁 資源管理部 管理課 課長補佐 平野 智巳 ※55
同上 矢野 京次 ※6
6 国土交通省 大臣官房技術調査課 電気通信室 課長補佐 小野寺 次雄
気象庁 予報部通信課 無線通信室調査官 櫻庭 喜男 ※77
同上 佐藤 博 ※8
8 海上保安庁 警備救難部 救難課 運用司令室 上席運用官 古堅 慶太
宇宙通信株式会社 運用本部 通信サービス運用部 顧客グループリーダー 高橋 信一 ※99
宇宙通信株式会社 運用本部 サービス部 カスタマサポートグループリーダー 田村 知子 ※10
10 KDDI株式会社 運用管理部長 杉田 信男
JSAT株式会社 ネットワーク本部サービス部長 馬場 俊明 ※1111
JSAT株式会社 技術企画本部企画・調整部 ネットワーク企画担当部長 早坂 裕一 ※12
自治体衛星通信機構 事務局長 今福 應 ※1312
自治体衛星通信機構 総務部長 三木 哲夫 ※14
全国移動無線センター協議会 技術部長 有馬 正人 ※1513
全国移動無線センター協議会 管理部長 臺 俊男 ※16
社団法人 全国漁業無線協会 業務部長代理 大竹 三郎 ※17
社団法人 全国漁業無線協会 業務部長 藤村 政弘 ※18
14
同上 井坂 一夫 ※19
15 中央電力協議会 中央給電連絡指令所 系統グループリーダー 金子 隆
電源開発株式会社 水力流通事業部中央通信指令所運用グループリーダー 大塚 寿生 ※2016
同上 宮崎 正之 ※21
社団法人 日本アマチュア無線連盟 事務局長 北垣 重夫 ※2217
社団法人 日本アマチュア無線連盟 会員部長 日野岳 充 ※23
18 社団法人 日本ガス協会 技術部 情報企画グループマネージャー 岡野 晴人
19 日本赤十字社 事業局 救護福祉部 救護課長 竹下 修
日本電信電話株式会社 第二部門ネットワークビジョン担当 担当部長 神野 公秀 ※2420
日本電信電話株式会社 第二部門ネットワーク調整担当 担当部長 高野 雅希 ※25
21 社団法人 日本農村情報システム協会 参与 芦田 隆敏
日本放送協会 放送技術局報道技術センター ニュース・回線副部長 古川 雅之 ※2622
日本放送協会 中継技術部 担当部長 山北 淳 ※27
23 社団法人 日本民間放送連盟 総務部 村沢 イズミ
24 NTT東日本㈱ サービス運営部 災害対策室担当部長 田中 啓行
25 水資源開発公団 第一工務部 電気通信課補佐 河合 建喜
26 社団法人 全国自動車無線連合会 専務理事 池田 司
2

(オブザーバー)
1 関東地方非常通信協議会(関東総合通信局 私設第一課) 菊地 孝和
2 東京都 総務局 災害対策部 応急対策課 防災設備係長 平柳 茂
総務局 IT推進室 情報通信担当課 無線管理係長 村山 孝之 ※28
3 横浜市 危機管理対策室 情報・技術課 係長 能條 嘉幸
事務局長:総務省電波部基幹通信課 課長補佐 太田 清喜 ※29
同上 川浪 久則 ※30
事務局 :総務省電波部基幹通信課 防災通信係長 本田 定良 ※31
:同上 柄澤 佳徳 ※32
:総務省電波部基幹通信課 防災通信係 主査 宮山 浩一
:総務省電波部基幹通信課 防災通信係 則座 勝久 ※33
:総務省電波部基幹通信課 防災通信係 黒澤 孝 ※34
:総務省電波部基幹通信課 防災通信係 福原 章博 ※35
:総務省電波部基幹通信課 防災通信係 川原 洋平 ※36
構成員変更: ※1 平成14年11月~平成15年5月 ※2 平成15年5月~
※3 平成14年11月~平成15年7月 ※4 平成15年7月~
※5 平成14年11月~平成15年5月 ※6 平成15年5月~
※7 平成14年11月~平成15年5月 ※8 平成15年5月~
※9 平成14年11月~平成15年5月 ※10 平成15年5月~
※11 平成14年11月~平成15年5月 ※12 平成15年5月~
※13 平成14年11月~平成15年5月 ※14 平成15年5月~
※15 平成14年11月~平成15年5月 ※16 平成15年5月~
※17 平成14年11月~平成15年5月 ※18 平成15年5月~平成16年1月
※19 平成16年1月~
※20 平成14年11月~平成15年5月 ※21 平成15年5月~
※22 平成14年11月~平成15年5月 ※23 平成15年5月~
※24 平成14年11月~平成15年5月 ※25 平成15年5月~
※26 平成14年11月~平成15年5月 ※27 平成15年5月~
※28 平成14年11月~平成15年5月
※29 平成14年11月~平成15年9月 ※30 平成15年9月~
※31 平成14年11月~平成15年9月 ※32 平成15年9月~
※33 平成14年11月~平成16年1月 ※34 平成14年11月~平成15年5月
※35 平成15年5月~ ※36 平成16年1月~
機関名称変更:組織変更に伴い、水資源開発公団は平成15年10月に独立行政法人水資源機構に名称を変更
4 調査検討会の審議過程
「非常時の通信確保の在り方に関する調査検討会」は、平成14年4月の第51回
中央協議会総会における設置・開催決定を踏まえ、平成14年11月29日の第1回
会合から計7回の会合を開催し、非常時における通信確保の在り方について調査検討
を行った。
3

本検討会が検討を行った非常通信ルートは、次に示す防災無線システムの構成図に
おいて、災害時に国と都道府県及び都道府県と市町村を結ぶ通信ルートである。
防災用無線システムの全体構成
内閣府
災害対策本部
総理官邸
その他機関
国土交通省
気象庁
防衛庁
総務省
警察庁
東京電力
NHK
NTT
総務省消防庁
他関係行政・公共機関
海上保安部等
工事事務所等
地方気象台等
駐屯地・師団
県警察本部
都道府県庁
他の自治体警察署
防災関係機関
消防署
防災関係機関
中央防災無線
海上保安庁
固定系 移動系
市町村役場
地域衛星通信ネットワーク
消防防災無線
消防・救急無線
市町村防災行政無線 地域防災無線
屋外拡声器戸別受信機
車載型無線機携帯型無線機
(県内・全国共通波)
防災相互通信用無線
消防署
都道府県防災行政無線
通信衛星
地域防災無線
防災用無線システム
その他防災に関係の深い自営通信システム
防災用無線システム
その他防災に関係の深い自営通信システム
生活関連機関病院、学校金融機関等
4

開催日 検 討 内 容
第1回 H14.11.29 1)本検討会開催趣旨説明
2)協議会の現状及び検討項目の説明・提案
3)今後の検討会の進め方とスケジュール説明 第2回 H15.2.28 1)検討会の検討項目
2)本検討会における検討課題について
3)非常時における活動体制の検討について 第3回 H15.5.29 1)第2回会合における検討項目についての経過報告
① 要請会議の設置について
② 地方協議会と都道府県との連携強化について
2)通信計画
① 中央通信ルートの新規開拓
② 地方通信ルートの確立
③ 新技術を利用した通信計画
3)通信訓練 第4回 H15.7.17 1)周知・啓発活動に関する検討について
①周知・啓発効果の検証、問題把握
②新たな周知・啓発活動の検討
③構成員増強による組織強化
2)これまでの検討・決定内容の再確認 第5回 H15.9.25 ・通信計画に関する検討について
①全市町村と都道府県の間のルート構築
②新しい通信形態
第6回 H16.1.30 ・「地方通信ルート策定のための指針(素案)」の検討について
第7回 H16.3.10 ・本検討会の最終報告案について
5

5 検討結果
本調査検討会により得られた結果は、下記のとおりである。
(1)非常時における活動体制について
ア 要請会議の設置
要請会議は、非常時における通信確保の取り扱い要請をする協議会内部の合議
機関であり、通信事業者等である協議会構成員より要請会議議員を指名するため、
適切な取り扱い要請が実施できると同時に、協議会構成員間の協力も得やすいと
いう利点がある。
要請会議は、大半の地方協議会において設置されている。
なお、要請会議を設置していない地方協議会については、「協議する時間的余裕
がない場合は議長が自ら要請を行うことができる」との規定をしていることから、
非常時においても対応が可能となっている。
地方協議会における要請会議の設置の現状については、以下のとおり。
地方協における要請会議の現状について
地方協議会名 設置の
有 無 構 成 員
要請会議に
関する規程
北海道 ○ 議 長:議員の中から会長が指名。
副議長:議員の中から会長が指名。
議 員:協議会委員の中から会長が
指名(部長クラスで6名)。
任期は次期総会まで(1年)
となっているが、そのまま再
任している。
北海道地方非常通信
協議会非常通信要請
会議規程で規定。
東 北 ○ 議長:東北総合通信局無線通信部長
議員:協議会構成員のうち若干名。
東北地方非常通信協
議会会則で規定。
関 東 ○ 議長:会長が委員の中から指名。
議員:議長が委員の中から指名。
(任期は1年)
関東地方非常通信協
議会会則で規定。
6

信 越 ○ 議長:会長が委員の中から指名。
議員:議長が委員の中から指名(4)
(構成団体の部長程度・任期なし)
信越地方非常通信協
議会会則で規定。
北 陸 ○ 議長:北陸地方協議会会長
議員:各県協議会会長(3)
任期:なし
北陸地方非常通信協
議会会則で規定。
東 海 ○ 議長:東海総合通信局無線通信部長
議員:議長が委員の中から指名(6)
議員の選出基準:
災害時に徒歩により会議参加
が可能な中央非常通信ルートを
所有する機関、電気通信事業者、
放送事業者の代表(任期1年)。
東海地方非常通信協
議会会則で規定。
近 畿 ○ 議 長:議員の中から会長が委嘱
副議長:議員の中から会長が委嘱
議 員:20 名(任期 1年)10 年度か
ら同メンバーで再任。
近畿地方非常通信協
議会非常通信要請規
程で規定。
中 国 ×
(規程
のみ)
議長:中国地方協議会会長
議員:委員の中から議長が指名。
中国地方非常通信協
議会会則で規定。
四 国 ○ 議長:四国地方協議会会長
議員:協議会委員の中から議長が若
干名を指名。(4)
四国地方非常通信協
議会会則で規定。
九 州 ×
(規程
のみ)
議長:九州総合通信局無線通信部長
議員:委員の中から議長が指名。
九州地方非常通信協
議会会則で規定。
沖 縄 × - -
※要請会議を設置していない事由について
1)九州・・・会則において「(要請会議において)協議する時間的余裕がない場合
は議長(九州総合通信局無線通信部長)が自ら要請を行うことができ
る」との規定があり、非常通信を要請すべき非常時も対応可能である
ため。
2)中国・・・九州地方協と同一理由による。
3)沖縄・・・設置していない経緯については不明である。
7

要請会議の設置については、非常通信規約*1第5条の2において「協議会は、そ
の内部に要請会議を設置する。」こと、「要請会議は、協議会からの委任を受け、非
常通信の取扱い要請を行う。」ことと規定されており、構成員からも、非常時に迅速
な対応ができるよう、あらかじめ要請会議の議長・議員について選出し、常設機関
としておく必要があるとの意見があったことから、本検討会において要請会議設置
の必要性を確認した後、第52回中央協議会総会(平成15年4月24日開催)に
おいて要請会議の設置を提案し承認を得た。
なお、要請会議議長については、総会時に中央非常通信協議会会則*2第8条の2
(1)の規定により、中央協議会会長から総務省総合通信基盤局電波部長が指名さ
れた。
また、要請会議議員については、中央非常通信協議会会則第8条の2(2)の規
定により、要請会議議長によって指名された。
第52回中央協議会総会資料(抜粋)は、以下のとおり。
8

第52回総会資料(抜粋)
要請会議の設置について
非常時において迅速・的確な非常通信の取扱い要請が出来るように、非常通信規約
第5条の2及び中央非常通信協議会(以下「中央協議会」という。)会則第8条の2
から第8条の4の規定に基づき、協議会の内部に要請会議を設置する。
なお、非常時に迅速な対応が行えるよう、あらかじめ要請会議の議長を会長の指名
により総会時に決定しておくこととしたい。
議長については、中央非常通信協議会委員長(総務省総合通信基盤局電波部長)と
し、議員については、議長の指名により要請会議設置時に決定することとする。
<参考> 要請会議に関する規定
○非常通信規約(*1) 第5条の2 協議会はその内部に要請会議を設置する。 2 要請会議は、協議会からの委任を受け、非常通信の取扱い要請を行う。
○中央非常通信協議会会則(*2)
(要請会議) 第8条の2 中央協議会に規約第5条の2に定める要請会議を設け、議長及び若干名
の議員を置く。 (1)議長は、委員の中から会長が指名する。 (2)議員は、委員の中から議長が指名する。
第8条の3 議長及び議員は、次の任務を行うものとする。 (1)議長は、要請会議を代表し、会務を統括する。 (2)議長は、非常通信の取扱い要請を行う。 (3)議員は、非常通信の取扱い要請に関する協議を行う。
第8条の4 非常通信の取扱い要請については、要請会議で協議し行う。ただし、協
議する時間的余裕がない場合は、議長自ら要請を行うことができる。 (1)会議は、議長が招集する。 (2)要請会議は、非常通信の取扱い要請を行う時期及び機関等について審議する。
9

イ 地方協議会と地方公共団体との連携強化
平成13年1月の協議会組織の再編により、全国に54あった多くの地区非常
通信協議会(以下「地区協議会」という。)が解散等したため、地方協議会事務局
が、非常通信訓練を実施する際の通信ルート設定などにおいて、各地域の実情を
踏まえた対応が困難な状況にあるなど、各地域で都道府県との協力体制が円滑に
行われていない地方協議会が見受けられるようになった。
本検討会の資料として、地方協議会と都道府県との協力関係に関するアンケー
ト結果については、以下のとおり。
地 方 協 議 会 名
(地区協議会数)
都道府県防災担当部署
との協力関係の現状
良好な関係保持の為に実施
している施策等
北海道
良 好 特に実施している施策等はないが、担当者レ
ベルでの意思疎通が大事と考えます。
東 北 良 好 最近は特に実施している施策等はないが、地
区協議会を解散した13年度は、解散に伴う各
県の当地方協議会への協力体制の認識の温度差
が有った為、県の担当者に対し
①災対法等関係においての県としての役割(位
置付け)を指導
②ささいな照会においても懇切丁寧に応対す
ると共に意思疎通を密にするよう心がけた。
関 東
(7)
どちらかというと良好
ではない。
特になし
信 越 概ね良好 特になし
北 陸
(3)
良 好 特にないが、連絡を密に取るようにしている。
東 海 良 好 日常的に実施していることはない。
非常通信訓練実施の約1ヶ月程の期間は、密
接な連絡を取っています。
近 畿 府県によっては良好で
ない。
特になし
10

中 国 協力関係については、概
ね良好だが、非常通信ルー
トの設定については、県が
連絡しやすいルートを設
定する事が多く、当方から
他のルート設定をお願い
している例がある。
今後は、市町村⇔県間は
県にお願いするものの、県
⇔内閣府間の通信設定は
当方で行うことを考えて
いる。
特にないが、強いて言えば、無線局の許認可
等において県との良好な関係を保つよう努力し
ている。
四 国
(4)
良 好 協議会の会議等の機会を捉えて県防災担当
者との意思疎通を図る。
今年度は、市町村防災行政無線の高度利用の
検討会を通じて、4県係長(補佐)には各分科
会の部長をしてもらい、かつ4県課長と当局課
長の話し合いの場を持つなど、協力関係を深め
ている。
各県の協議会関連会議等への要請の積極的
な対応や、業務レベルで無線局の置局等に関す
る相談にのっている。
九 州
(7)
良 好
※協議会活動について、積
極的とはいえないが、一応
協力的である。
各県に協議会の役員に就任してもらってお
り、年4回~6回程度の会議出席をお願いして
いる。これらの会議の際に、協議会関係の打合
せだけでなく、なるべく許認可関係の打合せ・
情報提供等を行う事により「意義ある会議出席」
となるよう配慮している。
沖 縄 良 好 特別な施策等はないが、沖縄地方協議会は管
轄が沖縄県のみということから、連絡等が行い
やすい環境にある。
※各地方非常通信協議会事務局担当者にアンケートを実施。
11

非常通信の円滑な実施を確保するためには地方公共団体の協力が不可欠である
ため、本検討会において連携強化の方策が検討されることとなった。
検討会において、地方協議会と都道府県との連携に関して各地方協議会に対し
アンケートを行った結果、都道府県と良好な関係を維持している地方協議会につ
いては、以下のような取り組みを行っている。
① 各地方協議会が、都道府県、市町村及び市長会・町村会等の開催する各種
防災関連の会合に参加し、協議会の活動に理解を求める。
② 各都道府県防災担当者の協議会役職就任等を通じて、協議会活動への認識
強化を図る
③ 都道府県からの相談・照会に対する対応、情報提供など各都道府県の防災
担当部署と協力関係の維持・強化を図っている。
今後、都道府県と良好な関係を維持している地方協議会(地区協議会を含む。)
の実施方策を全地方協議会においてさらに推進することとした。
また、中央協議会から地方協議会主催の講演会等への参加の機会を捉えて、都
道府県防災担当者への協力要請を強化するなど、中央協議会と地方協議会(地区
協議会を含む。)の更なる連携を通じて、地方公共団体との関係強化を図ることと
なった。
(2)通信計画について
ア 中央通信ルートの新規開拓
中央通信ルート(災害時に国と都道府県を結ぶ通信ルート)については、都道
府県毎に「①通常通信ルート」、「②非常通信ルート」併せて4ルート以上が既
に策定され、策定されたルートが機能するかの検証を定期的に実施し、毎年度、
中央協議会総会時に再検討・見直しが行われていることから、現状のルートで十
分であり、これ以上ルートの開拓は不要との結論となった。
12

中央通信ルートの都道府県別設定数一覧は以下のとおり。
都道府県別ルート設定数一覧管 内 都道府県 合計 ①通常通信ルート ②非常通信ルート
消防 地星 その他 小計 警察 防衛 海保 建設 電力 その他 小計
北海道 北海道 4 1 1 2 1 1 2
東 北 青森県 4 1 1 2 1 1
岩手県 5 1 1 2 1 1 1
宮城県 4 1 1 2 1 1
秋田県 5 1 1 2 1 1 1
山形県 4 1 1 2 1 1
福島県 4 1 1 2 1 1 2
関 東 茨城県 5 1 1 2 1 1 1
栃木県 4 1 1 2 1 1
群馬県 6 1 1 2 1 1 1 1 4
埼玉県 5 1 1 2 3
千葉県 8 1 1 2 1 1 4 6
東京都 6 1 1 1 3 3 3
神奈川県 5 1 1 2 1 1 1 3
山梨県 5 1 1 2 1 1 1 3
信 越 新潟県 5 1 1 2 1 1 1長野県 5 1 1 2 1 1 1
北 陸 富山県 6 1 1 2 1 1 2
石川県 5 1 1 2 1 1 1
福井県 5 1 1 2 1 1 1
東 海 岐阜県 5 1 1 2 1 1 1
静岡県 6 1 1 2 1 1 1 1 4
愛知県 6 1 1 2 1 1 1 1
三重県 6 1 1 2 1 1 1 1 4
近 畿 滋賀県 6 1 1 2 1 1 1 1 4
京都府 8 1 1 1 1 1 2 2
大阪府 6 1 1 2 2 2
兵庫県 5 1 1 2 1 1 1
奈良県 6 1 1 2 1 1 1 1 4
和歌山県 6 1 1 1 1 1 1 1 5
中 国 鳥取県 5 1 1 2 1 1 1 3
島根県 7 1 1 2 1 1 1 1 1 5
岡山県 8 1 1 2 1 1 1 1 1 1 6
広島県 7 1 1 2 1 1 1 1 1 5
山口県 5 1 1 2 1 1 1 3
四 国 徳島県 6 1 1 2 1 1 1 1
香川県 5 1 1 2 1 1 1 3
愛媛県 5 1 1 2 1 1 1 3
高知県 6 1 1 2 1 1 1 1 4
九 州 福岡県 7 1 1 2 1 2 1 1
佐賀県 6 1 1 2 1 1 1 1
長崎県 5 1 1 2 1 1 1
熊本県 8 1 1 2 1 2 1 1 1
大分県 7 1 1 2 1 1 1 1 1
宮崎県 7 1 1 2 1 1 1 1 1
鹿児島県 6 1 1 2 1 1 1 1
沖 縄 沖縄県 6 1 1 2 1 1 1 1 4
合 計 266 47 45 1 93 46 17 24 33 34 19 17
2
3
2
3
2
3
2
3
3
3
4
3
3
3
4
7
4
3
4
5
4
3
6
5
5
4
3
13

イ 地方通信ルートの確立
地方通信ルート(市町村⇔都道府県)は、非常時に住民の人命の救助、災害の
救援、交通通信の確保又は秩序の維持のために必要不可欠な被災状況の即時把握、
各種防災情報の伝達など市町村と住民等の間の情報共有のために直結する通信経
路であり重要性が高いものである。
このように、非常時において迅速かつ的確な災害情報等を収集・伝達し、円滑
な通信を確保するためには、被災市町村から都道府県まで、中央通信ルートに準
じた地方通信ルートを予め策定しておくことが必要であると確認され、②の「非
常通信ルート」の策定を主な目的として「地方通信ルート策定のための指針(案)」
について検討を行った。
①「通常通信ルート」:公衆回線の途絶又は輻輳の発生により公衆網による通信が
困難な場合を想定した通信ルート
②「非常通信ルート」:通常通信ルートが使用できない場合を想定し、他団体・他
機関(隣接する市町村など)の自営通信システムを利用す
る通信ルート
また、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(案)に
おいて都道府県及び市町村等が実施する避難、救援等の国民の保護のための措置
を実施するために必要な通信についても、非常通信規約第1条に規定する目的に
合致することや現在の活動の延長として対応が可能であることから、住民等に対
する通信の円滑な実施の確保についても配慮することが適当であるとされた。
地方協議会での地方通信ルートの策定の取組状況については、平成15年9月
現在では、近畿地方協議会のみが策定していたところであるが、その後、東北及
び中国地方協議会において、地方協議会事務局と国の地方機関及び地方公共団体
等が連携調整し、平成16年3月に策定したところである。一方、他の地方協議
会では、非常通信訓練の際にその都度策定しているのが現状である。
前述した3地方協議会のルート実例の一部を資料2(東北地方非常通信ルート)、
資料3(近畿地方協議会非常通信事務必携)及び資料4(中国地方非常通信ルー
ト)に示す。
14

地方通信ルート策定のための指針
1 はじめに
我が国は地震・台風・火山噴火等災害に見舞われやすい自然環境下にあるが、これら
災害の被害を最小限に食い止めるには、災害発生後の迅速かつ的確な情報収集・伝達が
大変重要になる。
これまで非常通信協議会を中心に、通信計画の作成や通信訓練等を通じて通信ルート
の策定に取り組んできたが、非常時の情報伝達ルートとして国と都道府県を結ぶ通信ル
ート(以下「中央通信ルート」という。)は策定されているものの、都道府県と市町村
を結ぶ通信ルート(以下「地方通信ルート」という。)は未だ多くの地域で未策定であ
り、通信訓練時の地方通信ルートもその都度設定しているのが現状である。さらには、
地方通信ルートが非常時、住民に直結するものであることを考えると、早急に策定する
ことが望まれる。
2 地方通信ルート策定の目的・根拠について
(1)策定の目的
中央通信ルートに併せ地方通信ルートを策定し、被災市町村から都道府県、国まで
の通信経路を確立した上で、非常通信協議会の作成する非常通信計画等に掲載し、非
常時において国及び地方公共団体が迅速かつ的確に災害情報等の収集・伝達を行うこ
とを目的とする。
なお、地方通信ルートには、公衆回線の途絶又は輻輳の発生により公衆網による通
信が困難な場合を想定した通信ルート(以下「通常通信ルート」という。)と、通常
通信ルートが使用できない場合を想定し、他団体・他機関(隣接する市町村など)の
自営通信システムを利用する通信ルート(以下「非常通信ルート」という。)がある
が、本指針においては「非常通信ルート」の策定を主な目的とする。
15

(2)策定の根拠
都道府県及び市町村は、災害対策基本法第40条及び第42条に基づき、地域防災
計画の中で「情報の収集及び伝達、災害に関する予報又は警報の発令及び伝達」に関
する計画を定めなければならない。
また、防災基本計画(平成7年7月中央防災会議決定)の中には災害時の情報収集・
連絡体制の整備として、「国、公共機関及び地方公共団体は、市町村、都道府県、国
その他防災機関との連絡が、相互の迅速かつ確実に行えるよう情報伝達ルートの多重
化及び情報交換のための収集・連絡体制の明確化など体制の確立に努めるものとす
る」とあり、国及び地方公共団体等が災害時の重要通信の確保に関する対策の推進を
図る場合、電波法74条の2の規定により非常通信の確保を目的に活動する「非常通
信協議会との連携にも十分配慮すること」とある。
なお、本指針において策定を求めている「非常通信ルート」とは、電波法第74条
第1項に規定する通信及びその他非常時において用いられる必要な通信を円滑に実
施するためのものである。
さらに、近年の国際情勢の緊張の度合の高まりや武装した不審船の出現、大規模な
テロリズムの発生等の取り巻く諸情勢の変化を踏まえ、武力攻撃災害及び緊急対処事
態における災害への対応も想定した計画作成等の必要性も求められております。この
ことから、策定に当たっては自主防災組織や災害発生地域以外の要避難地域及び避難
先地域の避難拠点など地域・住民等に対する警報の伝達等が的確かつ迅速に行われる
よう、非常通信の円滑な実施の確保についても十分な配慮が必要と考える。
以上のことから、非常時の通信の円滑な実施を確保するための体制の整備に備え、
各機関は相互に協力して通信ルートの策定に努める必要がある。
3 地方通信ルートの策定方法について
地方通信ルートは都道府県、市町村及び地方非常通信協議会が連携し、以下の条件等
により策定する。
16

(1)策定における条件
① 無線局等の選定に当たっては、商用電源の停電を想定して非常用電源の運用許容
時間等を考慮すること。
② 自主防災組織や避難拠点など地域・住民と市町村役場間の情報収集・伝達手段に
ついて考慮すること。
③ 地域防災計画における通信ルート等との整合性を図ること。
■地方通信ルート想定例(非常通信事務必携<平成15年3月近畿版>抜粋)
宇
治
市
宇治市 ①――京都府(消防防災課)
役所 ②――宇治警察署――府警察本部――京都府(消防防災課)
③……JR宇治駅~~JR二条駅……京都府(消防防災課)
④……関電宇治営業所~~関電京都支店――京都府(消防防災課)
⑤(宇治市消防本部)――京都市消防局――京都府(消防防災課)
⑥――国土交通省天ヶ瀬ダム管理支所――京都府(消防防災課)
◇記号 ――無線区間 ~~有線区間 ……使走区間
①は通常通信ルート ②~⑥は非常通信ルート
(2)策定の手順
策定手順の一例として、以下の様な手順が考えられる。
① 地域防災計画等で設定している既存の通信ルートのうち、都道府県防災行政無線
などの自営の通信ルート(公衆回線を除く)を通常通信ルートとして設定する。
② 既存の通常通信ルートの使用不可に備えて、他団体・他機関の自営通信システム
を利用する非常通信ルートを選定する。
③ 非常通信ルートを選定できない場合、地方非常通信協議会に当該地域の自営通信
システムの保有団体・機関についての情報提供を求める。
④ 提供された情報をもとに、市町村から自営通信システムの保有団体・機関までの
距離等を考慮して、非常通信ルートを選定する。
17

⑤ 自営通信システムの保有団体・機関との調整等については、必要に応じ地方非常
通信協議会に協力を要請し、非常通信ルートとして設定する。
⑥ 策定した非常通信ルートを地域防災計画等に反映させる。
⑦ 防災・通信訓練等を通じて非常通信ルートの確認や機器の点検を定期的に実施す
る。
(3)策定における体制等について
① 都道府県、市町村及び地方非常通信協議会は実務担当者会議等を開催するなど
連携して、地方通信ルート策定のための体制整備に努めること。
② 地域の特性や実情等に応じた地方通信ルートの策定計画を立て、実施すること。
③ 都道府県と地方非常通信協議会は円滑なルート策定を図るために、各市町村と
自営通信システムを保有する団体・機関との間の調整を積極的に行うこと。
④ 地方通信ルート策定後は、各地方非常通信協議会が作成する非常通信事務必携
等に通信ルートを掲載し、都道府県、市町村及び地方非常通信協議会との間で定
期的な情報交換を行うなど、情報の共有化を行い、密接な連携に努めること。
⑤ 中央非常通信協議会構成員は、本指針に基づく地方通信ルート策定に関してそ
れぞれの支社・出先機関等に対し指示又は助言を行うこと。
18

通 常 通 信 ル ー ト 非 常 通 信 ル ー ト
無 線 局 情 報 の 協 力 依 頼
・
新 た な 通 信 ル ー ト の 可 能 性
地 域 防 災 計 画 へ の 反 映
・
新 た な 地 方 通 信 ル ー ト の 策 定
情報提供・積極的な調整
「 非 常 通 信 事 務 必 携 」 等 に お い て 情 報 を 共 有 化
訓 練 ・ 検 証
避難所等との情報収集・
伝達手段を考慮
地 域 防 災 計 画 の 確 認 ・ 整 理
地方非常通信協議会
市 町 村
検証の結果通信ルートの見直し
地方通信ルート
地方通信ルート策定のフローチャート
都 道 府 県
策 定 計 画 の 作 成 ・ 体 制 整 備
19

これにより、現在策定されていない地域についても、「地方通信ルート策定のた
めの指針(案)」を基に、活動体制を整えた上で、地方通信ルートの策定に向け、
一つ一つ着実に実行し、具現するよう地方協議会において取り組むこととした。
なお、地方通信ルートの策定については、多大な作業量となるものであり、国・
地方公共団体及び協議会の構成員との連携・調整が欠かせないことから、各地方
協議会と地方公共団体は地域における防災担当者の実務担当者会議などを開催し、
地方通信ルートの必要性等について相互に十分理解した上で、地域の実情、特性
等を考慮しながら計画的に策定していくことが重要である。
また、地方通信ルート策定後は各地方協議会が発行する非常通信事務必携等に
掲載し情報の共有化を図ると共に、防災・通信訓練等を通じて通信ルートの確認
や通信機器の点検を定期的に実施することとした。
20

ウ 新技術を利用した通信計画
近年における情報通信技術の進展から、防災分野においてもインターネットや
衛星通信設備、携帯端末等の新技術を導入し、音声だけでなく、映像やデータに
よる災害情報の収集・伝達機能を拡大することが提案された。
新しい通信形態を利用した通信システムのイメージについては図1のとおり。
これまで地方協議会が非常通信訓練において新しい通信形態を通信訓練に導
入・実施している例としては、衛星通信設備、地域公共ネットワークを使用した
市町村役場から県庁までの画像伝送、無線 LAN 及び eメールの利用が上げられて
いる。
インターネットの使用については、被災地の情報をリアルタイムに配信する場
合には有効な手段であるが、通信手段により輻輳もありえること、着信の確認が
必要となるなどの課題があり、非常通信ルートとしては、現状において補完的な
通信として取り扱うことが望ましいとされた。
災害発生時に複数の通信ルートを確保することは極めて重要であるが、MCA シス
テムは、全国の主要地域をカバーし広い範囲での利用が可能で通信の輻輳もない
ことから災害時の利用に適している。また、衛星通信設備については、地上系の
無線局の通信途絶に有効であるが、構成員保有の衛星通信設備は、それぞれ仕様
が異なること、可搬型衛星通信設備は、衛星捕捉に長時間要する場合があるため
日頃の訓練が重要であり、 構成員の配備状況を踏まえ通信ルートに組み入れる必
要があるとされた。
また、通信手段については非常時においても機能する可能性が高い現状の通信
形態を基本とし、新技術の導入は現状の通信形態の補完的手段として通信訓練等
を通じ随時検討していくこととなった。
21

22
図1

(3)訓練について
訓練については、毎年度、春と秋の全国非常通信訓練、内閣府主催総合防災訓練
(9月1日)における非常通信訓練、各地方協議会主催の非常通信訓練等を実施し
ているが、本検討会における意見の、「訓練が実践的なものになっておらず、訓練に
関わる各機関のルート確認作業となっている」、「隣接する自治体間、事業者間での
協力要請による非常通信や国の機関を介して指定公共機関への伝送も想定する必要
がある」、「訓練のルートは状況に応じて選定することが実践的であるが、訓練の連
度をあげることも必要」などにみられるように、訓練参加機関や訓練使用ルートの
固定化、訓練方法の形式化等が問題となっている。
地方協議会が実施している通信計画・通信訓練の現状については下記のとおり。
23

各地方協議会における通信計画・通信訓練の現状 地方協議会 地方ルート
設定の現状
地方協議会
主催通信訓
練の実施
都道府県主
催防災訓練
等との連携
実施
防災相互通信
波を活用した
訓練実施
新技術等を活用
した訓練の実施
北海道 × ○ × ○
(感度交換訓練)
東 北 × ○ × ○
関 東 × ○ × ×
信 越 × ○ × ○
北 陸 × ○ × ○
東 海 × ○ × ○ 映像(画像)によ
る情報伝達。
災害の広域化を
想定し、対中央非
常通信ルートの
迂回経路の検討
を実施中。
近 畿 ○
○ ○(防災の
日の訓練、
近畿2府7
県訓練につ
いて、連携
実施。)
○ 近畿2府7県非常
通信訓練(広域災
害を想定した府県
間の応援要請等
を伝達する横断
的な訓練)
府県と近畿協議
会事務局間で、通
信機器の手配要
請及びその応諾
情報を府県防災
行政無線(衛星系
を含む)を使用し
て伝達する訓練
24

中 国 ×(但し、
本年度作成
する事で総
会に提案予
定)
○ × ×
四 国 ×(県協議
会で作成し
ているが、
地方協議会
としては作
成していな
い。)
○ × ○ 3年前から衛星
による通信訓練
を実施しており、
その際にパソコ
ン通信にも挑戦
している。
九 州 × ○ × ○ 現状では特段な
いが、今後eメー
ルを利用した訓
練にも取り組ん
でいきたいと考
えている。
沖 縄 × ○ ×(地方協
議会主催の
分 は 今 年
度、実施し
たいと考え
ている。)
×
この現状から、実践的な訓練方法の検討、非常通信伝達時間の短縮、市町村・民
間機関等の訓練参加促進(自治体等主催の防災訓練との連携実施)、訓練実施結果の
検証等を通じて、現行の訓練の見直し・改善方策等について検討した。
その結果、構成員からの提出意見の中にあった150MHz帯、400MHz帯
の「防災相互通信波」を活用した訓練について、8地域の地方協議会で既に実施し
ているが、実施していない地方協議会についても、訓練の一形態として実施するよ
う中央協議会事務局として指導していくこととなった。
25

また、都道府県等主催の防災訓練と協議会の非常通信訓練との連携実施について
も、都道府県の協議会への訓練参加意識を高めていく有効な手段であるため、今後
も中央協議会事務局として連携実施を図っていく方向で地方協議会を指導していく
こととした。
(4)周知・啓発について
ア 周知・啓発効果の検証、問題把握
現在、無線局免許人・防災関係機関等への協議会の活動に対する理解・協力を
促進するため、中央協議会及び地方協議会において、防災関係の講演会や集会の
開催、パンフレット・リーフレットの作成配布等において周知・広報活動を行っ
ているが、現在の周知・啓発活動が効果的であるかを検証する必要がある。
地方協議会が実施している周知・啓発活動の現状については以下のとおり。
地方非常通信協議会における周知・啓発活動の現状 地 方
協議会名
周知・啓発活動の現状
(今後の実施予定を含む)組 織 強 化 方 策
周知・啓発活動に関して
日頃苦労している事等
北海道 非常通信協議会の活動
状況、情報提供を重点に会
報を発行している。(年1
回)
春・秋期の全国訓練、北
海道地方協主催の道内訓
練実施の前に報道発表を
行っている。
この1年間、加入促
進を 14 年度の重点施
策として取り組んでき
た結果、235 組織から
311 組織に増加した。
現在も未加入となっ
ている市町村(30)・消
防組合(2)・コミュニ
ティ放送局(6)に対し、
文書による加入要請の
ほか、他の業務で現地
訪問した際、直接加入
要請を行っている。
地区協議会があった時
は、各地区協議会とも活発
な活動が行われ、地方の実
態が把握できていたが、当
局が一括所管するように
なってから、地方との意見
交換や情報収集が疎遠に
なりがちである。
26

東 北 ①会報の発行の実施
発行は毎年度1回。
送付先は、地方協構成員
の他、東北の全市町村あて
とし、周知・啓発を図って
いる。
②訓練実施時の報道発表
市町村については、
青森県のみ「市長会」・
「町村会」として加入。
その他の県について
は、各市町村毎に加入。
現在、未加入市町村
については、特段加入
促進の取組み等は行っ
ていない。
電気通信事業者関係
でいうならば、今年度
「ジェイフォン株式会
社東北技術部」が新加
入し、一定加入は終了
したものと思われる。
関 東 年度の事業計画には周
知・啓発を掲げているが、
具体的方策は未了。
市町村については、
各県(地区)協議会に
「市長会」・「町村会」
は加入している。
信 越 会員向けに会報を発行
していたが、平成14年度
は発行しなかった。
非常通信の重要性の認
識を深めて頂くため、例年
防災相互通信用周波数に
よる感度交換訓練の実施、
平成14年度には全市町
村参加の地域衛星通信ネ
ットワークを利用して県
に非常通信文を伝達する
訓練を実施し、これら訓練
を通して協議会の会員と
しての意識高揚を図って
いる。
市町村及び消防機関
については、市長会、
町村会、消防長会の加
入をもって間接的に加
入して頂いている。
各種訓練等を通じて、参
加機関においては非常通
信の認識を深めて頂いて
いるが、自営通信網を持た
ない機関や訓練等に参加
しない機関を如何に非常
通信協議会に目を向けて
頂くよう活動してゆくか
苦慮している。
27

北 陸 会報の発行、訓練時の報
道発表等は未実施。講演会
は、各県非常通信協議会と
共催で実施。また、地方協
総会時には、会員を対象と
した講演会を実施。
市町村(市長会、町
村会を含む)は、未加
入。市町村の加入につ
いては、問題意識を持
っており、今後各県協
との関係等整理してい
こうと考えている。
東 海 総会及び講演会開催時
の報道発表。
非常通信事務必携(東海
地方協作成)を全ての市町
村・消防本部及び警察署あ
て配布し、非常災害時の通
信の重要性について、理解
を深めて頂くよう取り組
んでいる。
電気通信事業者は、
主要な全社加入済。
市町村については、
特段加入の取組みは実
施していない。全国非
常通信訓練参加の市町
村に対して、訓練を依
頼する際に中央作成の
パンフレット、「非常通
信確保のためのガイ
ド・マニュアル」等を
配布し、非常通信訓練
参加の理解を深めるよ
う取り組んでいる。
東海地方協議会におい
ては、殆どの事項が円滑に
取り組まれており、苦労す
る事はほとんどない。
近 畿 (1)訓練時の報道発表
(2)講演会の開催及びその
報道発表
地区協議会解散後、
各地区内での非常通信
の中心となる府県警本
部が地方協議会に未加
入であったため、昨年
度から加入要請を実施
し、現在、京都府警察
本部以外は加入済み。
周知・啓発として講演会
を開催しているが、講師の
選定に毎度苦労している。
各地方協でも同じだと思
うので、講師の情報のデー
タベースを作ってはどう
か。周知・啓発としては、
広報誌を作成・配布するの
が一番効果があると思う。
中央協で全国版の広報誌
を作成してはどうか。作成
に当たっては、各地方協の
ページを作る等して、作業
を分散してはどうか。
28

中 国 (1)講演会の開催
(2)防災行政無線未整備
市町村への指導・啓発
未加入の一般放送事
業者、コミュニティ放送事業
者、市町村、消防機関
に加入して頂くべく、
本年度事業として加入
促進活動を行うことと
している。
講演会等を開催する場
合、講師の謝金及び交通費
が必要だが、謝金は中央協
議会へ要求すること等に
より賄えるものの、交通費
が支出できないことから、
情報通信月間行事として
認められなければ開催が
困難です。
四 国 定期総会・四国地方非常
通信訓練時等を捉えて、報
道発表をしている。
市町村合併時の会合や
県・市町村の会議に参加
し、周知・啓発に努めてい
る。協議会構成員に対し
て、協議会の会議等で、無
線設備環境の見直し(整
備)や市町村との連携につ
いて協力を求めている。
四国地方協議会に
は、市町村はいずれも
加入していない。
四県が代表して加入
しており、市町村とは、
各県との結びつきで全
国訓練等連携してい
る。
九 州 局のHPに協議会とし
て掲載。
一般市民等を対象とし
たセミナー等の開催
訓練実施時の報道発表
市町村は一括して町
村会や市長会として加
入し、訓練等に参加し
ている。
平成 13 年度の協議会の
組織見直しにより独自予
算を持たなくなったため、
予算的に制約を受けるこ
ととなった。
沖 縄 訓練実施時に報道発表
を行っている。
沖縄県が主宰する沖縄
県防災行政運営協議会の
講演会に講師を派遣し、協
議会の活動等を紹介して
いる。
市町村については、
一括して町村会や市長
会として加入してい
る。
管内を5ブロックに分
けて、地方協主催の訓練を
5年周期で実施しており、
その際に市町村の防災担
当者を対象に講演会を開
催しているが、都道府県・
市町村が訓練参加機関を
選定する際、会員の中から
通信スタッフが充実した
機関を訓練参加機関とし
29

て選定するため、訓練参加
する会員が特定されやす
い。
訓練に参加する機関は
認識が高いが、その他の会
員は認識が薄い。
検討会における意見では、「構成員に関しては非常通信訓練への参加等を通じ
て非常通信の重要性が十分理解されているが、未加入の市町村等への周知・啓発
が必要」、「マスメディアの使用は効果的だが、費用について考慮する必要があ
る、平常時のPRは人間の心理・意識から効果的ではないが、防災の日、阪神・
淡路大震災の日などに実施していくのが良い」などがあった。
イ 新たな周知・啓発活動
現在、中央協議会、地方協議会が行っている周知・啓発には、①広く社会に向
けた広報活動と、②非常通信協議会内部(構成員相互間)における周知・啓発活
動の二つがある。協議会構成員以外に対しては、テレビ・ラジオ等マスメディア
を活用した広報活動等が考えられ、協議会構成員相互は会報の発行による情報共
有、構成員相互の交流の場の提供がある。
協議会がこれに取り組むべき事項として、協議会内部(構成員相互間)の周知・
啓発活動(情報共有・情報交換)に重点を置き、非常通信及び協議会に対する構
成員の意識高揚を図ること。その一環として、防災週間(毎年8月30日~9月
5日)、防災とボランティア週間(毎年1月15日~21日)等の時期に合わせて
非常通信セミナーや防災関連施設の見学会等を開催する。そのほか、非常通信訓
練時において訓練に直接参加しない構成員への訓練情報の提供及び報告を行って
いくこととした。
30

ウ 構成員増強による組織強化
地方協議会の構成員の加入に関しては、市町村については市長会、町村会とし
て一括加入している場合と、市町村が個別に加入している場合がある。
地方協議会の構成員の中で、市町村は災害時に住民と直結する重要な構成員で
あるが、災害時に市町村と地方協議会がどのように機能するのか、市町村に十分
理解されていない実情がある。
市町村に対しての周知・啓発においては、地方協議会が都道府県・市町村の開
催する防災担当者会議等に積極的に参加し、協議会の活動内容や非常通信ルート
についての必要性を説明し、より一層の理解を求めるほか、アンケート及びその
他の手段により防災に関するニーズを把握、災害時における市町村と協議会がど
のように機能するかについてのパンフレット作成等により、市町村に対しての周
知・啓発を強化していくこととした。
31

6 今後必要な取組
本検討結果を基に、今後中央協議会、地方協議会(地区協議会を含む。)は以下
項目について取り組んでいくこととする。
なお、協議会構成員は地方通信ルートの策定に関して、それぞれの支社・出先機
関等に対し必要な周知・指導を行うこととする。また、非常時において、協議会構
成員相互間の協力により、通信の確保について、要請会議との連携を図るものとす
る。
(1)地方協議会と地方公共団体との連携強化
・都道府県、市町村及び市長会・町村会等の開催する各種防災関連の会合に参加
・各都道府県防災担当者の協議会役職者就任
(2)通信計画について
・地方協議会(地区協議会を含む。)と地方公共団体は地域における防災担当者
の実務担当者会議などを開催し、地方通信ルートの必要性について相互に十分理
解した上で、地域の実情、特性等を考慮しながら計画的に地方通信ルートを策定
する。
・インターネット、衛星通信、携帯端末等を利用した非常通信訓練について地方
協議会が非常通信訓練において現状の通信形態の補完的手段として検証してい
く。
(3)訓練について
・地方協議会(地区協議会を含む。)において、防災相互通信波を活用した非常
通信訓練を実施していく。
・都道府県等主催の防災訓練と地方協議会の非常通信訓練の連携実施を図る。
(4)周知・啓発について
・協議会構成員の情報共有・情報交換に重点を置き、非常通信セミナー、防災施
設見学会等の開催により意識高揚を図る。
・非常通信訓練に直接参加しない構成員への訓練情報の提供、報告を行う。
・都道府県、市町村が開催する防災担当者会議に積極的に参加し、協議会の活動
内容、非常通信ルートの理解を求める。
32

おわりに
本検討会は、平成14年11月29日の第1回会合から計7回にわたり、非常時に
おける円滑な通信確保を目的に活動する協議会の今後の在り方について、調査検討し
てきた。その間にも熊本県水俣市における水害、宮城県沖・宮城県北部地震や十勝沖
地震とそれに伴う苫小牧石油コンビナート火災等、多くの災害が発生し尊い人命、財
産が失われることとなった。また、国際情勢の緊張の度合いが高まりテロ等の発生も
懸念されており、改めて非常時における迅速かつ的確な情報収集・伝達のための体制
整備の必要性について認識するところである。
災害に強い社会を作るためには、社会環境の変化、地域の実情に即した実践的な計
画とするとともに、被災状況の即時把握、各種防災情報の伝達など国・地方公共団体
間、住民等の間の情報共有のための情報の収集・伝達体制や初動・応援体制など緊急
を要する措置すべき事項を踏まえ、施設整備の強化等に応じ、絶えず見直しを行い、
実態に即したものとしておかなければならない。
このような状況を鑑みると、協議会が果たすべき役割はこれまで以上に増しており、
通信計画の策定、非常通信訓練、周知活動など協議会の活動をより一層有効なものに
していく必要があり、そのためには、国・地方公共団体及び協議会の構成員との連携・
調整が欠かせないものとなっている。
こうした活動体制の整備を図った上で、本検討会における検討結果の一つ一つを着
実に実行し、具現していくことが最も重要であると考える。
33