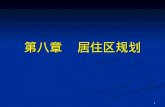日本酒ラベルの用語事典 日本語版 第4版Title 日本酒ラベルの用語事典 日本語版 第4版 Author 独立行政法人 酒類総合研究所 Created Date 12/3/2019
歴史・世界から見た日本の居酒屋kuroken/html/16ishikou.pdf · 第三節...
-
Upload
vuongkhanh -
Category
Documents
-
view
252 -
download
0
Transcript of 歴史・世界から見た日本の居酒屋kuroken/html/16ishikou.pdf · 第三節...

歴史・世界から見た日本の居酒屋
4 年 14 組 4 番 1710130082 石塚皓太郎
2017/01/12

1
目次
第一章 はじめに
第一節 研究の背景・動機・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2
第二節 研究の目的・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2
第三節 本論文の構成・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3
第二章 日本の居酒屋の現状
第一節 データから見た現状・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3
第二節 過労死事件の二つの事例・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6
第三章 日本の居酒屋の歴史
第一節 戦前の居酒屋・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8
第二節 戦後の居酒屋・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9
第三節 高度経済成長期の居酒屋(飯田保の功績)・・・・・・・・・・・・・・・・9
第四節 高度経済成長期の居酒屋(木下藤吉郎の功績)・・・・・・・・・・・・・10
第五節 新興居酒屋チェーンの台頭・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11
第六節 現代の居酒屋・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12
第四章 世界の居酒屋の成り立ち・現状
第一節 アメリカの居酒屋・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13
第二節 中国の居酒屋・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15
第三節 韓国の居酒屋・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15
第五章 改善提案
第一節 問題提起・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・16
第二節 改善提案と課題・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・17
第六章 まとめ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・19
参考文献および参考 URL・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・20
あとがき・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・21

2
第一章 はじめに
第一節 研究の背景・動機
本論文を通して、私は「歴史・世界から見た日本の居酒屋」というテーマを掲げ、現代
社会における日本の居酒屋の雇用問題を解決する糸口を見つけるために考察していきたい
と思う。
なぜこのテーマ選択をし、研究しようと思ったかというと、一つ目に、2015 年 11 月の
経営学部ゼミ対抗プレゼンテーション大会(以下、ゼミプレと略)で私が所属する B 班が飲食
業界を対象に、過重労働問題について着手したことがある。その中で、様々な形態がある
飲食サービス業界の中でも「和民」や「庄や」といった居酒屋で、長時間労働による過労
死などの雇用問題が特に目立ったことから、卒業論文では居酒屋だけに焦点を絞ってさら
に深く研究したいと考えた。
二つ目に、私自身が御茶ノ水にある個人経営の居酒屋で約二年間アルバイトをしていた
ということがある。私が在籍した二年間の間にも多くの社員が入社しては辞め、店長も過
多な労働時間を強いられているといった現状を目の当たりにした。このような状況は、居
酒屋でアルバイトしている友人からもよく聞く話であり、居酒屋において日常茶飯事にな
っていることは確かな事実である。私が客として新宿や池袋で居酒屋を利用する時も、毎
夜毎夜朝まで営業している店は無数に立ち並び、誰が見ても店員の数が足りなかったりな
ど杜撰な経営状況を目にすることは多くある。
こういった身近な経験が、居酒屋の雇用問題に着手し、解決策を見つけたいと強く思う
きっかけになった。
第二節 研究の目的
本論文の最終目的は、日本の居酒屋の雇用問題に対する解決策を創出することである。
昨年のゼミ対抗プレゼンテーション大会において、私たち B 班は完全週休二日制、変形労
働時間制フレックスタイムを導入し、正社員の長時間労働を防ぐ、これによって高離職か
ら生まれていると考えられる負のサイクルを打破することで、飲食サービス業界の雇用状
況を良い方向に導けると考えた。この解決策を前提に踏まえたうえで、さらに飲食サービ
ス業界の中でも居酒屋に突出した、労働者たちの過酷な労働環境を救済できるような策を
創出したいと考えている。
その糸口を見つけるために、本論文では日本の居酒屋の歴史を辿る、世界の居酒屋、居
酒屋形態の店の環境を参考にするなど多角的な方向から調査を進めて、問題の根底から探
り、良い解決策を作り上げたいと思う。

3
第三節 本論文の構成
第ニ章では、日本の居酒屋の給与や残業などの雇用環境、居酒屋の店舗数や居酒屋チェ
ーンの経営状況などの現状を述べ、特に何が問題であるのかを具体的に浮彫にしていく。
第三章では、日本の居酒屋を歴史の観点から見ていく。どのような経緯で現在のような
街に居酒屋が溢れる状態になり、居酒屋チェーンや 24 時間営業の店などが増えたのか、営
業形態の変化、飲食業界の居酒屋の位置付けなど、変わり巡る居酒屋を研究する。
第四章では、世界ではどのように居酒屋は成り立ち、現在そこではどのような経営・雇
用が行われているのか、参考となるものを紹介する。
そして第五章の改善提案では、第四章までの研究を踏まえたうえで、今後の日本の居酒
屋の雇用を良い方向へ導ける提案を述べる。第六章では、本論文のまとめ、総括をする。
第二章 日本の居酒屋の現状
第一節 データから見た現状
本章では、日本の居酒屋の現状を分析し、問題点を見直していきたい。初めに、飲食業
界という枠組みでのデータを発表する。
先ずここでブラック企業について、説明したいと思う。ブラック企業とは、労働基準法
を守らず、利益追求のために従業員を過度に働かせる企業のことを指す。ブラック企業の
第一の特徴は、入社したら死ぬまで働かさせられることである。これは比喩での意味では
なく、過労による突然死や自殺、あるいはほかの労災事故など、文字通り命を落としかね
ないという余りにも残酷な意味である。後に述べるが、過労による飛び降り自殺が起きた
ワタミでは、2008 年の新入社員研修で配られた「新入社員激励文」には、「入社おめでとう。
グループ 1000 店のために死ぬ気で働け」と記載されていたほどだ。また、賃金を搾取する
ことも一つの大きな特徴である。その典型例としては、サービス残業の強制がある。社員
に対して過多な業務を押し付ける一方で、残業時間には上限を設け、上限を超えた分の労
働に対しては賃金を支払わないということだ1。
飲食業界には、そんなブラック企業と呼ばれる企業が多く存在し、業界自体がブラック
と言っても過言ではないかもしれない。低賃金、長時間労働という過酷な業界なのである。
1 古川琢也著『ブラック企業完全対策マニュアル』普遊舎、2013 年、12 ページ以下。

4
図表—1
厚生労働省大臣官房統計情報部雇用・賃金福祉統計課「毎月勤労統計調査年報(全国調査)」
これは昨年のゼミプレで使用したパワーポイントの一部である。この図を見ても分かるよ
うに、飲食業界は他の業界に比べて低賃金、そして圧倒的に労働時間が長いことが伺える。

5
図表-2
http://food-doctor.jp/?p=4968 より引用(給与の単位は千円)アクセス日 2017/01/07
また、図表2は大手居酒屋チェーンの平均年齢、平均勤続年数、平均給与(年収)がまとめら
れたものである。差はあるものの、平均勤続年数の低さ、そして平均給与の低さは一目瞭
然だろう。これが大手の表であるのだから、これよりも待遇の悪い店が多くあることは言
うまでもない。
厚生労働省の統計によると、飲食業界の平均給与は 23 万 3000 円と他業界よりもかなり
低い。平均労働時間は 100.7 時間、出勤日数 15.6 日と一見少ないように見えるが、実際に
はサービス残業が蔓延しているのが実態である。離職率は、厚生労働省の統計によると、
大学卒業 3 年後は 2009 年度で 48.5%。直近 7 年の数値も 45.7~54.4%の範囲で推移して
おり、同年度における全業界の平均値が 28.8%であることからも、あらゆる業界の中でも
かなり高い。平均勤続年数が 6.8 年であることも、労働状況の劣悪さがうかがえる。店舗数
は、飲食市場規模自体が縮小しているにも関わらず、以前よりも増えている。市場全体の
売上高は 1997 年の約 29 兆円、店舗数は 91 年の 85 万店がピークで、その後 10 年でそれ
ぞれ 20%近く減少している。しかしその間も、居酒屋業態の店舗数は 10%増加、同業態に
従事する労働者数は 386 万人から 440 万人へと 14%増加している。
次の章で述べる、ワタミ株式会社と株式会社大庄のデータを、2016 年度版就職四季報か
らも見てみよう。ワタミ株式会社は、大卒初任給 19 万円(外食)、平均年収 591 万円と、
飲食業界においては賃金は低くはないと、データを見る限り言えるかもしれない。しかし、

6
三年後離職率が 42.3 パーセントとかなり高いことが目立つ。それに付随し、私が特に気に
なったところは休暇の部分だ。夏季休暇、年末年始休暇ともになし、有休消化年平均はノ
ーアンサーとなっている。次に株式会社大庄は、まず平均年収が 400 万円(平均 41 歳)で
ることに驚きを隠せない。会社自体は東証一部上場であるのに、飲食業界の厳しさが垣間
見える。大庄もワタミと同様に、ノーアンサーの多さが目立つ。離職率、有休消化年平均
ともにノーアンサーとなっている2。
第二節 過労死事件の二つの事例
このように過酷な飲食業界、そして居酒屋業界において、過多な長時間労働が実際に従
業員の命までを奪った痛ましい事件は実際に起こってしまった。ここでは代表的な二つの
事件を紹介させていただきたいと思う。
まず一つ目に、余りにも有名な事件として私たちもゼミプレで取り上げた、居酒屋チェ
ーン大手の「ワタミフードサービス株式会社」の事例だ。2008 年 6 月、和民の 26 歳女性
社員だった森美菜さんが入社してわずか 2 ヵ月で、過労の末に自宅近くのビルから飛び降
り自殺したという事件である。亡くなる 1 ヵ月前に森さんが書いた日記には、「体が痛いで
す。体が辛いです。気持ちが沈みます。早く動けません。どうか助けて下さい。誰か助け
て下さい」と綴られており、すでに心身の限界に達していたことは明白である。ワタミフ
ードサービスでも社員の労働時間は、午後四時から翌日午前一時までと就業規則で定めら
れていた。しかし、実際の労働環境が、以下の図表である。
図表-3
図表3も、セミプレで使用したパワーポイントの一枚の図である。この表の赤い部分が仕
2 東洋経済新報社編、山縣裕一郎発『就職四季報 2016年版』東洋経済新報社、2014
年、655 ページ。

7
事の日である。遺族が死後に入手した勤務実態資料によれば、森さんはほぼ毎日開店の二,
三時間前には出勤して、退勤時間も平日で午前三時、週末は午前六時というパターンが常
習化していた。平日も午前三時など電車が走っているはずがなく、朝まで店舗に居残る状
態だった。さらに、最長で連続7日間の深夜勤務を含む長時間労働や、連日午前4~6時
まで調理業務などに就いたほか、休日も午前7時からの早朝研修会や障碍者施設でのボラ
ンティア活動、リポート執筆が課されたりと、森さんの労働には過酷きわまる実態があっ
た。完全な休養に充てられたのは勤務していた二か月のうちたったの六日のみである。5 月
中旬の時点で 1 ヵ月の時間外労働が約 140 時間に上り、森さんはそのときすでに抑うつ状
態に陥っていた。遺族は労災の認定を申請したが、平成 21 年に横須賀労働基準監督署は仕
事が原因とは認めず、遺族が神奈川労働局に審査を求めた。神奈川労働局の審査官は、「残
業が 1 か月あたり 100 時間を超え、朝 5 時までの勤務が 1 週間続くなどしていた。休日や
休憩時間も十分に取れる状況ではなかったうえ、不慣れな調理業務の担当となり、強い心
理的負担を受けたことが主な原因となった」として、2012 年にようやく労災と認定された3。
また、居酒屋チェーン「日本海庄や」「やるき茶屋」、そしてカラオケチェーンの「歌う
んだ村」などを展開している大手の「株式会社大庄」でも痛ましい事件があった。大学を
卒業して新卒で入社した 24 歳男性社員吹上元康さんが、働き始めてからわずか 4 カ月で、
急性心不全により亡くなった事件である。吹上さんは、大学卒業後の 2007 年 4 月に日本海
庄や・石山駅店に配属され、入社後は朝 9 時ごろに出勤し、夜 11 時まで働くという生活を
送っていた。そして 8 月に急性左心機能不全で就寝中に自宅で亡くなった。4 ヵ月間の彼の
残業時間は平均して 1 カ月あたり 112 時間だった。これは過労死ラインと定められている
80 時間をはるかに超える労働時間である。このような長時間労働が、健康な若者を過労死
させたと言える。また、会社は極めてわかりづらい制度で募集、採用していた。そもそも
長時間労働を前提としたような給料体系を使用していたということだ。当時、求人情報に
は新卒者の最低支給額として 19 万 4500 円と記載されていたが、実はそのうちの 7 万 1300
円は時間外手当であり、会社は最低支給額に時間外労働 80 時間分を組み込んでいたのだ。
実際に大庄の「給与体系一覧表」には最低支給額は月 19 万 4500 円と記載されていたが、
但し書きに「時間外(労働が)80 時間に満たない場合、不足分を控除するため、本来の最
低支給額は 12 万 3200 円」との記載があった。これが詳しく説明されたのは、入社後の研
修であり、吹上さんを含む新卒者はそれまで事実に気づかないでいたのだ。つまり、80 時
間の時間外労働をしないと、満額の 19 万 4500 円は受け取れないことになっていたのだ。
厚生労働省が定めた月 80時間以上の時間外労働があると過労死の危険性が高いという過労
死ラインを、大庄は当然の前提として契約にしていたのである。吹上さんが過多な長時間
労働していた事実が認められ、2008 年 12 月に労働基準監督署から労災が認定された4。
二人はまだ年も若く、これから輝かしい未来があり、これからの日本を担っていくはず
3 http://www.mynewsjapan.com/reports/1585 アクセス日 2017/01/23 4 http://www.mynewsjapan.com/reports/1277 アクセス日 2017/01/23

8
だった。それが会社の杜撰な経営状況、行き過ぎた働かせ方のせいで命を落としてしまっ
たのだ。この問題は、居酒屋の雇用が変化しない限りまた起きてしまう過ちであると私は
考え、この二方の命を無駄にしないためにも、居酒屋業界には経営を考え直してほしいと
強く考えるに至った。
第三章 日本の居酒屋の歴史
第一節 戦前の居酒屋
本章では、戦前から現代に至るまでの日本の居酒屋の立ち位置や普及を振り返り、どの
ような経緯を通して現代の居酒屋の姿になったのかを考察していきたい。
日本では居酒屋というものは、最初は上流階級のものであり、庶民が活用できるような
居酒屋が成立するのは 15 世紀頃、本格的に居酒屋文化が発展したのは江戸時代である。江
戸時代は 260 年余りも続いた一つの大きな時代であり、これが現代社会の原点とも言える
だろう。江戸では、飲食店や居酒屋が最も発展したことは多くの文献からも分かっており、
新興都市であった江戸には地方から多くの単身の男が上京してきて、江戸時代初期から飲
食店や居酒屋は多かった。この時代には全国の街道が整備され、宿場町が繁盛した。この
頃の宿屋は居酒屋でもあり、この宿屋兼居酒屋は飯、酒、そして売春を提供していた。し
かし江戸中期には茶屋という酒と茶を提供する形態の居酒屋が発達し、この茶屋は料理茶
屋、芝居茶屋、相撲茶屋など様々なエンターテイメントを提供し客を楽しませる形態へと
発展した。
そんな江戸時代が終わり、明治維新とともに西洋から洋酒が参入してきた。ビールとビヤ
ホールはその代表ともいえるものである。しかし当時は洋酒は高価なものであり、都市部
の富裕層しか手の出せないものだった。洋酒とともに洋風居酒屋も入ってきたが、後に述
べる海外で見られた多機能性は日本の居酒屋には現れなかった。ちなみに、それまで日本
人が飲んでいた清酒と、今日多くの人に飲まれているビールの消費量は 1960 年に逆転をし
ている5。
私は、戦前の居酒屋はまだ外国の文化が参入していなかったことや、茶屋という形態で
人々が楽しみを求めに行く場所であったこと、そしてもちろん居酒屋チェーンなど存在し
ていなかったことなどから、現代の居酒屋とは雰囲気が大きく異なるのは明らかである。
この頃は、まだ今日のような営業形態でもないし、雇用の面でも大きな差を感じる。
5下田淳著『居酒屋の世界史』講談社現代新書、2011 年、158 ページ以下。

9
第二節 戦後の居酒屋
戦中から戦後のある時期まで多くの人にとって、酒は贅沢品であった。なぜなら、そも
そも戦中戦後は食料不足であったからだ。それでも酒を求める人々は、バクダンと呼ばれ
る燃料用アルコールを水で割ったものなど、毒物を含む粗悪な酒を飲み、亡くなる人も多
くいた。そんな日本で第二次世界大戦後、現代の居酒屋の起源となった大きな一つの要因
はヤミ市である。
終戦直後の日本では物資の流通は厳しい規制がされていたが、極端な物資不足のうえに
配給は滞っていたことから、人々はヤミ市に頼るしかなかったのだ。ヤミ市は都市部の駅
前にでき、日用品や農産物、加工品など様々なものが売られたが、飲食店も多く立ち並び、
その大半は飲み屋であったという。しかし元々露天商は戦前の代表的な職業のひとつであ
り、それが戦後配給制度によって流通が規制されたことによってヤミ市となったのだ。終
戦直後は混乱期にあり、身分も国籍も学歴も関係なく店を開き、そこに酒を求めて多くの
人が集まった6。
その時代のヤミ市が当時のまま形を残している場所が東京にもある。その代表格として
知られるのが新宿西口の思い出横丁である。約 80 メートルの細い路地に、焼き鳥屋、料理
屋、ラーメン屋、バーなどが所狭しと立ち並んでいる。酒好きには一度は足を運んでほし
い場所だ。この時代の居酒屋は、民衆たちが貧しい生活を強いられていた戦後の、憩いの
場として活用されていたように思える。憩いの場という意味では現代と変わらないかもし
れないが、それよりももっと切羽詰まった生活、民衆たちの苦労が見える。本当の意味で、
酔いたかったという当時の日本人の思いを感じた。
経済復興が軌道に乗って物資の流通が豊富になると、ヤミ市の露天は役割を終えて撤去
された。酒の出荷量としては、終戦直後の一時期の落ち込みから次第に回復してきた。
第三節 高度経済成長期の居酒屋(飯田保の功績)
高度経済成長期には、チェーン居酒屋が花盛りになった。バブル崩壊以降は居酒屋店舗
数、売り上げともに減少傾向が続いているが、チェーン居酒屋はわずかながら増加傾向に
ある。居酒屋市場の半分前後をチェーン居酒屋が占めていると思われる。そんなチェーン
居酒屋のビジネスモデルを確立した立役者には、三人の名前が挙げられる。「ニュートーキ
ョー」創業者の森新太郎、「養老乃瀧」創業者の木下藤吉郎(本名、矢満田富勝)、「天狗」
創業者の飯田保の三人である。その中でも飯田保の役割は大きく、今日のチェーン居酒屋
の原形を確立したのは天狗であると言える。
飯田は 1969 年に創業し、池袋に一号店を出した。(1977 年にテンアライドに社名変更。)
しかし一号店ではトラブルが多発した。当時は板前を外部から呼んでくることが常識だっ
6橋本健二著『居酒屋の戦後史』祥伝書、2015 年、20 ページ以下。

10
たのだが、その板前が営業中に酒を飲んだりと言うことをまったく聞かず、そこで飯田は
従来の板前制度を廃止した。そして自前の料理人を育成するとともに、セントラルキッチ
ンを開設した。セントラルキッチンとは、店内での調理作業を簡素化するためのものであ
る。これは養老乃瀧でも一部採用はされていたが、全面的に取り入れたのは天狗が初めて
の試みであった。また、飯田は積極的に海外視察に出かけ、新しい業態のヒントを見つけ
に行った。そうして英国のパブやドイツのビヤホールを参考に、1972 年に天狗神田二号店
の二階に洋風店をオープンした。初めは一階と二階は内装だけでなく、料理や酒も違うも
のを提供していたのだが、これを一階と二階のメニューを共通にしたところ大評判となっ
た。ここに幅広い酒と和洋中様々な料理を提供する、今日の居酒屋チェーンの原形がここ
に出来上がったのである。
会社はその後も急成長を続けて、1986 年には居酒屋業界で初めての株式を店頭公開した。
バブル崩壊後も勢いは止まらず、そして 1995 年には東証一部上場した。その後はワタミや
モンテローザ、コロワイドなどの新興のチェーンに押され苦戦はしているものの、日本の
居酒屋業界のビジネスモデルを確立した功績は称えられるべきものである。
ただ、現代の居酒屋と違うところがある。それは、「天狗」は営業時間が 23 時 30 分まで
で、週末にも深夜営業をしない。その理由は採用ページに記載されている。「『次の日に疲
れを残さないように』との配慮から」「基本深夜営業なし。店舗閉店は 23 時 30 分。終電で
帰宅でき、リズムある生活が遅れます」と記載されており、過多な長時間労働でブラック
企業と噂される飲食サービス業界の中で、見習われるべき姿勢であるといえるだろう。ま
た、テンアライドは組織率の高い労働組合があることも見習うべきポイントである。2014
年の有価証券取引報告書によれば、組合員数はおそらく、管理職を除く正社員の九割を超
え、パートも短期を除くと八割くらいいるといえる。今日では非正規労働者の増加によっ
て組織率が低下する一方の労働組合にとって、この点も模範となるであろう7。
第四節 高度経済成長期の居酒屋(木下藤吉郎の功績)
木下藤吉郎(本名、矢満田富勝)は、1938 年に妹とともに富士食堂を開業した。戦時中
にはヤミ物資が原因で全財産を失うなどしたものの、戦後には食堂経営が波に乗り、1951
年に株式会社富士養老の滝を設立した。直営と暖簾分けの両方で長野県下に店舗を増やし、
ピーク時には 110 店舗を超えたという。しかしその後、製菓業や金融業、新聞社など多角
的に経営を広げたことで経営不振に陥り、首都圏でやり直すことを決める。1956 年に横浜
市に養老乃瀧一号店を誕生させ、この一号店はたちまち評判になる。その後横浜市内に店
舗を展開、翌年には東京に進出、さらには関西にも進出を果たし、1965 年には 100 店舗を
達成する。
今から見ると異様ではあるが当時、精神主義と軍隊的な規律、合理主義で学歴、性別な
7 橋本健二著『居酒屋の戦後史』祥伝社、2015 年、156 ページ以下。

11
ど無関係の実力主義が木下藤吉郎のやり方だった。また、当時は飲み屋はツケが普通の時
代だったが、養老乃瀧は食券制であり、客は現金前払いであることで、酔った勢いで過大
な注文をせず安心して飲むことができた。さらに現金前払いであるということは、店には
常に現金があり、取引業者に歓迎されやすく納入してくれるようになった。
また当時、本社に入ると、「この会社は日本一給料が良く日本一早く出世ができます。/
この会社は、親孝行と勤勉の修養道場です。」という文字が掲げられ、その言葉通り、社員
の初任給は中卒で二万円、高卒で二万三〇〇〇円だった。これは高卒の銀行員の初任給が
一万七〇〇〇円、国家公務員上級の初任給が二万一六〇〇円だったことから高給だったこ
とがいえるだろう。1966 年からは直営店だけでなく、フランチャイズ方式を開始し、当時
はまだ珍しかったフランチャイズシステムだが、わずか八年後の 1973 年には 1000 店舗を
突破する快挙だった。フランチャイズには、予想に反して希望者が殺到した。応募したの
は飲食店関係者だけでなく、会社員や繊維関係、小売店、公務員など幅広い職種の人であ
った。この頃にはセントラルキッチン方式を採用しており、板前が必要なく、短期間の研
修で開業することができた。当時の日本は自営業者が増加を続け、分厚い自営業セクター
が維持されていたこと、多くの人々が独立して一国一城の主となるルートを求めていた。
養老乃瀧は高度経済成長期の独立を求める人々に、比較的容易に参入できるルートを提
供したのであった。現在会社は、やはり新興居酒屋チェーンに押され気味ではあるものの、
新業態をいくつも展開して、その存在感は依然としている。8
第五節 新興居酒屋チェーンの台頭
私がこれまで歴史の観点から居酒屋を振り返ってきて、本節では新興居酒屋チェーンの
台頭について話す。このことから何を述べたいか簡潔にいうと、日本の居酒屋は進化し、
良い方向へと繁栄を続けてきたが、本節のころから行き過ぎた経営が生まれてしまったと
いうことなのだ。
前節で述べたように、「天狗」と「養老乃瀧」はチェーン居酒屋の先駆者として業界を引
っ張っていたが、1990 年前後からは新興居酒屋チェーンが台頭し、天狗や養老乃瀧を追い
越す勢いで繁栄した。その原点には、札幌で小さな居酒屋を開店した石井誠二という男の
登場がある。石井は 1973 年、三十歳の時に札幌で雑居ビルの二階につぼ八を開店した。タ
ーゲット層を若いサラリーマンと女性に絞り、メニューは一律一五〇円にして新鮮なもの
を格安で提供した。たちまち店は評判を呼び、順調に店舗を拡大していき、1981 年には 50
店舗を超えた。そんな時に中堅商社の伊藤萬(後イトマンに改名)から提携の話を受けた
石井はこれに乗り、1982 年にはつぼ八東京本社を設立、つぼ八は全国に店舗を順調に増や
すこととなった。
その時期に、ワタミ創業者の渡邊美樹とモンテローザ創業者の大神輝博がつぼ八傘下に
8橋本健二著『居酒屋の戦後史』祥伝社、2015 年、162 ページ以下。

12
入った。渡邊美樹は子供のころから自分は社長になると公言していたほどの野心家で、元々
横浜でライブハウスを開こうとしていたところ、石井につぼ八のフランチャイジーとして
経営のノウハウを身に付けることを勧められ、石井の気迫に押されて提案を受け入れた。
そして 1984 年渡美商事を設立し、つぼ八とフランチャイズ契約を結んで高円寺北口店のオ
ーナーとなった。渡邊は経営不振の店を立て直して収益を上げ、店舗を増やした。さらに
つぼ八とは別にお好み焼き店を立ち上げて軌道に乗せた。そんな時、石井がイトマンにつ
ぼ八から追放され、また渡邊が経営するつぼ八は格段に業績が好調だったことから、他店
のフランチャイジーの反感と嫉妬を買い、石井を追放した経営陣からワタミのこれ以上の
出店を禁止される。そこで渡邊はつぼ八からの離脱を決め、1992 年に「居食屋 和民」を
オープンさせた。和民が“居食屋”と名乗るのは、居酒屋とファミリーレストランの中間
業態を目指したからであり、メニューの構成や店員のトレーニングなど石井のバックアッ
プもあり、誰もが知る快進撃を遂げた9。
モンテローザ創業者である大神は、歌舞伎町の高級クラブの客引きで桁外れの成績を上
げ、総支配人となった後、独立してパブレストラン「モンテローザ」を開業するが経営に
行き詰まり、事業を売却してつぼ八の傘下となった。1983 年に中野店をオープンした後、
株式会社モンテローザを設立し、次々と出店するもののやはり本社と対立関係となり、つ
ぼ八各店舗を「白木屋」に切り替え、カクテルメニューを充実させることで若い女性客に
評判を呼んだ。そして次々に新業態を展開し、店舗を増やした。2002 年には 1000 店舗を
達成し、現在ではその業態は三十五種類にも上る10。
このように、三人が常に新しい市場を的確に発見して開拓したことで、新興チェーンの
基礎を築いた。こうした新興居酒屋チェーンの台頭は、それまでの居酒屋の概念を覆した
と言えるだろう。現在では当たり前になっている飲み放題や、低価格帯、酒の飲み方自体
が変わることになった。しかし私は、この新興チェーンの目まぐるしい発展と繁栄が、現
代の居酒屋の問題を生むきっかけになってしまったと考える。利益を考える余り営業時間
を伸ばし、客が入る場所にはことごとく店舗を増やす。会社を経営するという立場からす
れば、利益の追求は欠かせないものであるし、理解できないことでもないが、もう少し原
点に返り、利益の追求と従業員の幸せを考えられる経営をする必要があるのではないだろ
うか。この話は第五章で改めて述べる。
第六節 現代の居酒屋
1990 年代後半から日本では経済的格差の拡大が進行し、これにより居酒屋の異変が始ま
った。日本のジニ係数はかなり高い方であり、OECD 加盟国の中で米国、英国などに次ぐ
六番目の高さである。ジニ係数とは、社会における所得分配の不 平等さを測る指標である。
9橋本健二著『居酒屋の戦後史』祥伝社、2015 年、169 ページ以下。 10 同上書、173 ページ。

13
貧困率は更に上位にあり、16 パーセント、人数に換算すると2000万人以上の貧困層が
いることになる。日本は国際的にみても、かなり経済格差の大きい国であり、貧困率も高
いのである。
こうした状況になって、客単価が五千円を超えるような居酒屋へは客が来なくなり閉店
が相次いだ。これに代替するように格安の居酒屋に多くの客が足を運ぶようになった。格
安の居酒屋にはサラリーマンやワーキングウーマンが集まるようになり、それまで格安の
居酒屋に集まっていた労働者や年金生活者の姿は消えていったのだ。居酒屋、ビヤホール
などの売り上げは、1992 年の 1 兆 4629 億円をピークとして減少の一途を辿り、2013 年に
は 1 兆 96 億円と七割以下にまで減っている。外食産業自体が低迷しているが、その中でも
居酒屋、ビヤホールなどの落ち込みは特に激しく、外食産業市場におけるシェア率は 4,2%
にまで減少をしている。
居酒屋の店舗数も減少の一途を辿り、経済センサスの調査によると、2004 年には 15 万
719店だった居酒屋は、2014年には 12万 5281店にまで減少している。比率に換算すると、
16,9%も減っていることになる。また、居酒屋の問題として事業者の高齢化と後継者難が挙
げられる。2014 年個人企業経済調査によると、飲食サービス業の事業主の 38,8%が 60 歳
以上で 27,3%は 70 歳以上となっている。後継者がいる店はたった 14,7%しかおらず、廃業
したいと考えている主は 15、8%となっている11。
第四章 世界の居酒屋の成り立ち・現状
第一節 アメリカの居酒屋
アメリカの居酒屋は、イギリスの植民地であった時代からタヴァンと呼ばれており、宿
泊施設が併設されていた。町のコミュニティセンターとしての多機能性を備えており、19
世紀中葉以降には北部の大都市ではホテルも現れ、フランス語でサルーンと呼ばれるよう
になった。19 世紀末にはアメリカには約 30 万軒もの居酒屋が存在したと言われ、多くは北
部の工業都市に集中していたという。サルーンは工場労働者の憩いの場であり、また情報
収集の場でもあった。こういった点からアメリカにおいての居酒屋は、単に酒を飲み酔う
という目的よりも、多機能的に楽しむ場として親しまれていたことが読み取れる。
しかしその後、1919 年にアメリカ連邦議会で採択されて禁酒法は、各州で成立され、1920
年には発効された。飲酒そのものを禁止するものではなく、酒の醸造、販売、輸送を禁じ
たものである。しかし禁酒法は逆にギャングたちの密造、密売を誘発させ、1931 年には全
11橋本健二著『居酒屋の戦後史』祥伝社、2015 年、250 ページ以下。

14
国にもぐり居酒屋が 22 万軒以上も存在したと言われている。こうして禁酒法は失敗に終わ
り、1933 年には撤廃されることとなった12。
アメリカではこうした禁酒法時代に、人々が居酒屋以外の憩いの場、余暇を見つけるし
かなく、野球観戦や映画館など、多方面の楽しみ方が発展した13。結果として、元々は多機
能的な役割は果たしていたアメリカの居酒屋は、その多機能性がそれぞれ棲み分けされた
ことにより、結果として人々の飲酒の減少、居酒屋通いの減少をもたらしたと言えるだろ
う。
ここで興味深い文献を紹介したいと思う。冷泉彰彦氏が書いた「アメリカの外食産業に
過労死がない理由とは?」というウェブの記事である。冷泉氏によると、その理由は、ま
ず大前提としてサービスの水準が低いことだという。客も店も細かいことは気にしない、
期待値が低いことでストレスが生まれにくいということだ。細かく理由を述べると、第一
に役割分担がはっきりわかれていること、第二に仕事は契約書で明確になっており、双方
が履行しなくてはならないため記載されてあることだけやればいいこと、第三に他人の仕
事をやってあげることは、その仕事を奪ってしまうことになり法律違反にもなるので禁じ
られていること、第四に低賃金の仕事に皆それぞれ目的をもち腰掛けと割り切って働いて
おり、長く勤めるつもりの人は皆無である、ストレスが溜まるならすぐに転職すること、
第五に本部など経営層やマーケティング専門職など管理職になるには MBA などの学歴が
必要で、現場から叩き上げで昇格できる可能性はゼロであることから、将来の出世を人質
に無理な働き方を強制されることはないこと、第六に店長は業績に応じた歩合制でノルマ
未達成なら解雇という処遇で上司から終身雇用と出世を人質にネチネチと詰められること
もないこと、第七に店員も営業職としてチップ制によってモチベーションを高めて収入を
稼ぐ方式なので、固定給を前提にノルマ達成を迫られることがないこと、第八にサービス
水準が低く、客を待たせても、注文の料理が遅くても、冷めていても、謝罪を求められる
ことがないためストレスが溜まらないこと、そして最後に多くの州で会社は従業員控え室
に労働法規の一覧と最低賃金額を記載したポスターを掲示する義務が法律で定められてお
り、労働法規違反があれば労働者が弁護士を雇って訴訟に持ち込み巨額の賠償を求められ
る恐れがあるため、法令順守のプレッシャーとなっていることが挙げられる14。日本でも、
過労死にまで追いやられてしまうのは正社員であり、そういった点でアメリカと異なると
ころはまず、店長が目標未達成で解雇されたとしても、また他の店にいけばいいという流
動性の高い環境が備わっており、雇用の長期継続や出世と引き換えに身を削ってまでも会
社に奉仕するという考えにはならないのだろう。また、アメリカは訴訟社会であり、もし
も会社が違法行為を行えば従業員から簡単に訴えられるということが企業の違法行為の抑
止力になっていると思われる。日本の場合の労働規制は、多くの小売・サービス業、外食
12下田淳著『居酒屋の世界史』講談社現代新書、2011 年、99 ページ。 13同上書、106 ページ。 14 http://www.newsweekjapan.jp/reizei/2012/03/post-407.php (2017/01/11 アクセス)

15
産業、中小企業においては実質無法地帯であり、サービス残業やクビ切りがやりたい放題
になっているという現実が少なからずある。これは不十分な監督行政に起因する部分もあ
るが、訴訟行為に出た場合の労働者の負担の大きさが最大の原因であると考えさせられる。
第二節 中国の居酒屋
中国の居酒屋は、歴史として居酒屋とともに茶館が大きな役割を担った。ここでいう茶
館とは、単に茶を提供する場であるだけでなく、酒を提供する場でもあった。中国におけ
る茶館は、先に述べたアメリカのサルーンのように多機能性を備えており、商談、取引、
仕事場、職業外線、民事法廷などコミュニティセンターとしての役割を併設して持ってい
た。また、賭博、売春、人身売買の場としても利用されていた。居酒屋は都市の道路沿い
に宿屋を兼ねて成立した。しかし茶館も居酒屋も都市の文化であり、農村のものではなか
った。農村に住む人々は、現物経済であったこともあり、酒や茶を自宅で飲み、宴会も自
宅にて行われた15。ちなみに、現代中国語で「酒家」という言葉はレストランのことを表す。
「居酒屋」という言葉は日本からの逆輸入語で、そのまま居酒屋のことを指す。
第三節 韓国の居酒屋
韓国の居酒屋が本格的に成立したのは 1900 年前後であったようで、それは都市であるソ
ウルやピョンヤンに限定されたものであった。しかし韓国でも居酒屋のようなチュマクと
いう形態の店が存在した。チュマクは都市や街道沿いの宿屋兼居酒屋であり、酒を飲み食
事が提供されるような場所であった。韓国は無償接待の精神が強くて貨幣経済の浸透が遅
かったこともあり、チュマクにおいても宿代は無料で飲食代だけ取っていたとされている。
しかし韓国も植民地時代に貨幣経済が本格的に浸透して、こういった無償接待の精神は薄
れていき、現在では居酒屋も日本よりも盛況となっている16。
15下田淳著『居酒屋の世界史』講談社現代新書、2011 年、137 ページ以下。 16 同上書、143 ページ以下。

16
第五章 改善提案
第一節 問題提起
これまで述べてきた日本の居酒屋の現状、歴史、そして海外の居酒屋事情を振り返って、
改めて現代の日本の居酒屋の問題とは何かを自分なりに考えてみた。
一つ目に、日本の居酒屋は高度経済成長期から、良くも悪くも成長しすぎてしまったと
私は強く感じた。第三章でも述べたように、戦中そして戦後のある時期までは、ヤミ市な
どが栄え、現在のような街並みとはまったく違ったことがわかった。それが、日本の居酒
屋は高度経済成長期に、飯田保や木下藤吉郎らによって、大きく成長し、居酒屋業界に革
新をもたらした。居酒屋チェーンが本格的に頭角をあらわしたと言えるだろう。しかし私
がここで注目したいのは、先駆者である「天狗」はあくまでも従業員に配慮し、営業時間
は原則 23 時 30 分までと定めていたことである。これが、その後の新興チェーンであるワ
タミやモンテローザなどの台頭により、さらに全国に居酒屋チェーンが大量に軒を連ねる
こととなった。そうして誰もが知るように街の居酒屋チェーンの営業時間は朝までが当た
り前になり、結果として社員への負担が増えた。確かに、営業時間の延長も、顧客のニー
ズに応え続けた結果なのかもしれない。先にも述べたが、会社として利益の追求をするこ
とは正しいし、創業者たちがやり手の経営者であることは間違いないだろう。
しかし、こういったサービス競争が過ぎている気が、私はしてならない。営業時間にし
ろ、価格帯にしろ、店舗数にしろ、行き過ぎた現状だと感じる。更に、高度経済成長期に
は、分厚い自営業セクターが維持されており、企業セクターと共存共栄し、高度成長を支
えていたが、現在の日本では自営業セクターが急速に縮小していることも起因すると考え
る。
二つ目に、雇用の直接的な原因として、低賃金長時間労働と言われているインショクサ
ービスだが、やはり低賃金よりも長時間労働に焦点を当てなければいけないと改めて感じ
た。第二章で述べた労働問題の痛ましい事件は、二つとも過多な長時間労働が原因であっ
たことは明白である。確かに賃金の面でも、時間外手当が基本給に含まれていたり、ボラ
ンティアや研修と称したサービス出勤のようなものが課されていたりと問題は多くあるが、
命を落としてしまっては賃金など意味をなさないものであると私は考える。そして長時間
労働を防ぐには、就業規則を定めたりすることではなく、店自体の営業時間を見直さなけ
ればいけないと思う。このことは次節で述べる。
三つ目に、アメリカと比較して日本の居酒屋で働くには、従業員側が不利な立場に置か
れ過ぎていると私は感じた。これは日本人の気質も大きく関与しているように思えるが、
勤勉で真面目な国民性がサービス水準を引き上げ、従業員を苦しめている。流動性も備わ
っていないはずではないと思うが、その真面目さが耐えることを促してしまっている気が

17
してならない。そして日本では訴訟を起こすにも、金銭面でも大きな負担があり中々切り
出せない。結果として飲食サービス業は無法地帯とも言える状態になっている。
次章では、これらの問題点を踏まえたうえで、私が考える現代の居酒屋問題の改善策を
詳しく述べる。
第二章 改善提案
私が改善提案として掲げたい一つ目の案は、飲食店の一日の「営業時間」に制限を設
ける法律を制定することである。というのも、従業員の就業時間を定めたり、三六協定に
則り残業時間に規定を作るというのは、現代の居酒屋において行われてはいるものの全く
機能をしていないと感じたからである。ワタミの森さんにしても、労働時間は午後四時か
ら翌日午前一までと就業規則で定められていたにも関わらず、実際はサービス残業や不適
当な出勤によって過度な長時間労働を強いられていた。このように、就業規則や法律で縛
ったところで、サービス残業というものは防ぐことができないのだ。しかし、営業時間そ
のものに制限を設けることは、私は出来ると考える。そうすれば、必然的に従業員の労働
時間の短縮にもつながる。ここで、深夜営業する店が街から消えるのかと考える人もいる
だろうが、そこで居酒屋チェーンの力を発揮してほしいと思う。あれだけ沢山の店舗を構
えている居酒屋チェーンだったら、例えば、同じ街に 16 時~24 時までが営業時間の店と
22 時~6 時までの店と構えて、客を逃さない方法はあると考える。
しかし私は、そもそもあそこまで多くの店が深夜営業すること自体に疑問を抱いている。
自身が客として深夜に居酒屋に訪れるとき、だいたい店はがらがらで、むやみやたらに深
夜営業するのは非効率的であると思う。今や新宿、渋谷、池袋など繁華街に限らず、住宅
街の素朴な駅前の居酒屋ですら朝まで営業している。この提案は具体的には、深夜営業を
するかしないかで、営業時間の規定を分けるという法律だ。深夜(24 時から朝にかけて)
営業をしたい店は開店できる時間を 8 時間まで、深夜ではない時間に営業する店は 13 時間
までと定める。こうすることで従業員にとっても無理のない生活を送る手助けになると思
うし、これだけ居酒屋が多い現代では客も困ることはないと考える。一つ、営業時間を短
縮することによって店の売り上げが減少してしまうという問題が発生するが、これもそも
そも居酒屋チェーンが格安になり過ぎている気が私にはする。この解決策は、一つは店の
営業時間が短くなることで、店自体にかかっている経費や人件費は削減できる。そして居
酒屋業界全体で規定を設けたりして、商品の最低賃金なるものを決めるべきであると考え
る。
この営業時間の短縮は、実際に近年の日本で見直されている事象だ。電通の社員が過労
自殺したことなど過重労働は今や社会問題であり、営業時間短縮をする企業が増え始めて
いる。例えば、ファミリーレストラン「ロイヤルホスト」を運営するロイヤルホールディ
ングスが 24 時間営業の店舗を 2017 年 1 月までに廃止することを決定している。さらに、

18
業界で異例の定休日を設ける検討も始めていると言われている。このような営業時間短縮
の動きは数年前から始まっている。24 時間営業によって業績を伸ばした「マクドナルド」
も営業時間短縮を始めている。2012 年には、24 時間営業の店舗は 1857 店にまで拡大した
が、2016 年 9 月時点で 809 店舗まで縮小した。「24 時間営業に必要な人材や光熱費にかか
る投資を昼の時間帯のサービス強化にあてたほうが、お客さまのご希望に沿うことができ
るという店舗が多くなってきた結果です」というのが、日本マクドナルド PR 部担当者の意
見である。また、営業時間の短縮には企業ばかりでなく、消費者の意識改革も必要である。
少しは不便になるかもしれないが、このサービスは無理な環境によって生まれたものであ
るという視点を持つことが大切だ。企業が 24 時間営業や年中無休に代表される過剰品質を
見直すことを「プラス」のこととして受け止めることが必要となる。消費者は少しだけ我
慢を、企業は少しだけ損をすることが、社会を大きく変える17。ファミリーレストラン最大
手のすかいらーくも、深夜営業店舗を大幅に縮小すると 2016年 12月 15日に発表している。
早朝 5 時まで営業を行っている 987 店舗のうち、約 8 割にあたる 750 店舗を、17 年の 4 月
1 日までに原則深夜 2 時閉店にするとしている18。今述べた例は、ファーストフード、ファ
ミリーレストランの例だったが、これは居酒屋業界にも浸透していかなければならない風
潮だと思う。
二つ目は、これは具体的な提案というよりも、意識的な問題にはなってしまうが、アメ
リカの飲食店社員の意識を見習うべきであると私は考える。まず、アメリカでは流動性が
高く、ほかの店に行けばいいというが、居酒屋業界に限定していえば、これは日本でも可
能であると私は考える。実際に、私がアルバイトしていた社員の方々も居酒屋を転々とし
ている方は多くいたし、私のアルバイト先に転職してきたのも、前の会社よりも待遇がい
いからだと言っていた。現代の日本の飲食業界は人手不足であることからも、自身がその
気になれば転職することは可能であると私は考える。
しかし提案以前に、飲食業界に勤めることは、ある種肉体労働的な面があることは事実
であると私はアルバイトをしていて感じた。これは居酒屋でアルバイト経験がある学生な
ら理解できると思う。ただ単に料理が好きで、お酒が好きで、という理由で就職するとこ
ろではないと思う。居酒屋チェーンの店長になるということはどういうことかをもっと理
解し、そのうえでなりたいと思う人間が就職するべきだと思う。これは飲食業界に限った
ことではないが、ミスマッチが起きていると私には感じ取れたというのが事実である。
17 http://toyokeizai.net/articles/-/147155(2017 年 1 月 12 日アクセス) 18 http://www.j-cast.com/2016/12/15286226.html(2017 年 1 月 12 日アクセス)

19
第六章 まとめ
第二章で述べたように日本の居酒屋の現状は厳しいものである。他業界に比べて、低賃
金、長時間労働、そして平均勤続年数の低さ、すなわち高離職率という厳しい条件がそろ
っている。飲食業界自体は縮小しつつあるものの、居酒屋業態の店舗数は増加している。
そして実際に長時間労働が原因で痛ましい事件が起き、死者が出ているが、現状は変わっ
ていないのが事実である。社員として働くには、相当な覚悟のある人間でないと押しつぶ
されてしまうこともあるだろう。
そんな日本の居酒屋は、第三章でも述べたように江戸時代から、しいてはもっと古い時
代から続いてきた日本の文化の一つであることを理解できた。人々は酒を求め、そして憩
いを求め、そして居酒屋はエンターテイメントを提供したりして、古くから居酒屋に足を
運んでいた。戦中戦後の苦しい時期にも、人々を助けた一つに居酒屋があっただろう。ヤ
ミ市で粗悪な酒であるにも関わらず、多くの店が開き、人々が集まった。そういった意味
で、居酒屋とは素晴らしい文化であると私は思う。人々が談笑し、楽しい時間を共有する
ということは現代も変わらないところで、これからも居酒屋には酒を飲み語らう場であり
続けてほしいと素直に思う。
だが、高度経済成長期を経て飯田や木下らによって居酒屋チェーンが繁栄し、その後も
ワタミやモンテローザの台頭があり、現代では少し行き過ぎた営業形態になっているのは
事実であろう。アメリカなど他国に比べても、日本の居酒屋は顧客のニーズに応えようと、
利益を追求しようとするあまり、従業員の生活を蔑ろにしている。私には、経営のバラン
スが崩れてしまっている気がする。もっと客と、従業員を大事にできるような経営をしな
くてはならない。そんな行き過ぎた現代の居酒屋チェーンには、第五章で述べたように営
業時間の短縮を強く提案したい。他の業態の飲食チェーンでは実施され始めているからこ
そ、居酒屋チェーン大手にも是非この波に乗ってほしい。それでなくてもなにか他の形で
も良いから、居酒屋の雇用形態がもっと良いものになればいいと、私は強く願う。私たち
日本人がこれからも居酒屋を楽しむためにも、この問題は解決されなければいけない。

20
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
参考文献および参考 URL
・橋本健二著『居酒屋の戦後史』祥伝社新書、2015 年。
・下田淳著『居酒屋の世界史』講談社現代新書、2011 年。
・古川琢也著『ブラック企業完全対策マニュアル』普遊舎新書、2013 年。
・河岸博一著『激安食品が 30 年後の日本を滅ぼす!』辰巳出版、2015 年。
・柏野満著『飲食店の店長の実務がわかる本』旭屋出版、2009 年。
・いずみ朔庵著『財布でひも解く江戸あんない』誠文堂新光者、2016 年。
・東洋経済新報社編・山縣裕一郎発『就職四季報 2016 年版』東洋経済新報社、2014 年。
・飲食ドクター「【保存版】飲食業界・外食産業の平均給与を丸ごと公開」2016/10/28、ア
クセス日 2017/01/10。http://food-doctor.jp/?p=4968
・ニューズウィークス日本版「アメリカの外食産業に過労死がない理由とは?」2012/03/05、
アクセス日 2017/01/11。http://www.newsweekjapan.jp/reizei/2012/03/post-407.php
・東洋経済 ONLINE「24 時間営業をやめる、企業や飲食店の本音「あって当たり前」ではま
ったくない」2016/11/29、アクセス日 2017/01/12。http://toyokeizai.net/articles/-/147155
・JCAST ニュース「すかいらーく、深夜営業を約 8 割縮小 外食産業の営業時間短縮進む」
2016/12/15、アクセス日 2017/01/12。http://www.j-cast.com/2016/12/15286226.html/
・Business Journal「外食産業、なぜ離職率高い?低賃金、長時間残業が横行する構造的
問 題 と 経 営 側 の マ イ ン ド 」 2014/01/22 、 ア ク セ ス 日 2017/01/12 。
http://biz-journal.jp/2014/01/post_3918.html
・田中成省著『ワタミの経営理念』日経 BP 企画、2010 年。
・坂口勤一郎著『日本の酒』岩波文庫、2007 年。
・渡邊美樹著『渡邊美樹のシゴト進化論』日経 BP 社、2008 年。
・今野春貴著『ブラック企業 日本を食いつぶす妖怪』文藝春秋、2012 年。
・渡邊美樹著『きみはなぜ働くか』日経ビジネス人文庫、2010 年。
・一般社団法人日本フードサービス協会「外食産業データ」2014、アクセス日 2017/01/07
http://www.jfnet.or.jp/data/y/data_c_y2012_reki.html
・My News Japan「15時間労働で休憩わずか30分! 入社2カ月で過労自殺するワタミ
社員のスタンダードな働き方」2012、アクセス日 2017/01/23
http://www.mynewsjapan.com/reports/1585
・My News Japan「入社4カ月で過労死した「日本海庄や」社員の給与明細とタイムカー
ド公開」2010、アクセス日 2017/01/23
http://www.mynewsjapan.com/reports/1277

21
あとがき
まず一言目に、大変でした。大学に入ってからレポートを書くことは増えましたが、こ
れだけ分量の多い論文を書いたのは、この卒業論文が初めてです。内容としては、一昨年
前に班の仲間と研究した内容をさらに深堀りする感じで、自分自身が居酒屋でバイトして
いたこともあって興味を持って取り組むことが出来ました。反省点としては、自分の計画
力がなかったので、ゼミプレの時のように足を使った情報収集が出来なかったことです。
でも、達成感を得ることはできました。ありがとうございました。