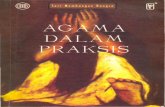Y2381E ISBN4-906165-77-X C3040for Hardwood Identification with an Appendix on non-anatomical...
Transcript of Y2381E ISBN4-906165-77-X C3040for Hardwood Identification with an Appendix on non-anatomical...
-
広葉樹材の識別 IAWAによる光学顕微鏡的特徴リスト
附属資料:解剖学以外の情報
編 集 IAWA(国際木材解剖学者連合)委員会 E. A. Wheeler, P. Baas & P. E. Gasson
日本語版監修 日本木材学会 組織と材質研究会 伊 東 隆 夫・藤 井 智 之・佐 伯 浩
定価[本体2,381円+税]
ISBN4-906165-77-X C3040 -Y2381E
広葉樹材の識別IAWA による光学顕微鏡的特徴リスト
海青社 海 青 社
■ カバー写真
● 表紙(表)、
A. ブナ Fa B. ケヤキ Z C. アカガシ
● 表紙(裏)、
D.アケビ Ak E.ウワミズ
F.ガジュマ
写真撮影
A, C ~ F
B 藤井智
海青社
伊東
隆夫
・
藤井
智之
・
佐伯 浩 日本語版監修
E. A. Wheeler, P
. Baas &
P. E. Gasso
n 編集
広葉樹材の識別
-
広葉樹材の識別IAWAによる光学顕微鏡的特徴リスト
附属資料:解剖学以外の情報
編 集
IAWA (国際木材解剖学者連合)委員会
E. A. Wheeler, P. Baas & P. E. Gasson
日本語版監修
日本木材学会 組織と材質研究会
伊 東 隆 夫 ・ 藤 井 智 之 ・ 佐 伯 浩
日本語版編集委員
伊 東 隆 夫 岩 田 和 佳 大 山 幹 成 岡 本 和 巳
景 守 紀 子 木 村 聡 杉 山 淳 司 鈴 木 潔
馬 場 啓 一 藤 井 智 之 藤 野 猛 史 松 前 智 之
海青社
-
IAWA List of Microscopic Features for Hardwood Identification
with an Appendix on non-anatomical information
IAWA Committee
Veronica Angyalossy Alfonso- São Paulo, BrazilPieter Baas- Leiden,TheNetherlands
Sherwin Carlquist -Claremont, California, USAJoao Peres Chimelo - São Paulo, BrazilVera T. Rauber Coradin -Brasilia,Brazil
Pierre Détienne -Norgent-sur-Marne, FrancePeter E. Gasson - Kew, UK
Dietger Grosser -München, FRGJugo Ilic -Highett, Victoria, AustraliaKeiko Kuroda -Kyoto, Japan
Regis B. Miller -Madison, Wisconsin, USAKen Ogata - Tsukuba, Japan
Hans Georg Richter -Hamburg, FRGBen J. H. ter Welle -Utrecht, The Netherlands
Elisabeth A. Wheeler -Raleigh, North Carolina, USA
edited by
E. A. Wheeler, P. Baas & P. E. Gasson
Copyright: 1989 by IAWA Bulletin n.s. 10 (3): 219-332Published for the International Association of Wood Anatomists at the Rijksherbarium,
Leiden The Netherlands
Translated by Takao Itoh, Tomoyuki Fujii and Hiroshi Saikiwith permission of the International Association of Wood Anatomists
-
i
FOREWORD
The publication of the ‘IAWA List of Microscopic Features for Hardwood Identification’ in1989 was a logical step in a long tradition of the International Association of Wood Anatomists to stan-dardize terminology and contribute to the development of effective methods in wood identification. Theimpact of the List has been great, not only as an aid for computer-assisted identification but also indescriptive and comparative wood anatomy in general, and as a teaching aid. A wood anatomical de-scription in coded form, following the IAWA List is often more precise and informative than many writ-ten descriptions in the literature.
It is very gratifying that the List is now also available in Japanese. Among the 61 countries repre-sented in the IAWA, Japan plays a leading role in all aspects of wood anatomical research, especially inthe identification of commercial timbers from all over the world and of prehistoric artefacts and fossilisedwoods from Japan. We sincerely hope that this version will be used by many students of Wood Science,Forestry and Botany in Japan, and are grateful to the translators of making the work of the IAWA Com-mittee accessible to a wider audience.
日本語版出版によせて
1989年の「IAWA List of Microscopic Features for Hardwood Identification」の出版は木材解剖学用語を統一することにより、さらに木材識別方法の発達に寄与することにより、長い伝統をもつ国際木材解剖学者連合(IAWA : The International Association of Wood Anatomists)を一歩前進させた。 この「IAWA List」は、コンピューターによる木材識別に役立つのみならず、比較木材解剖学や木材解剖学的記載の全般において、さらには教材としても利用価値があり、これが出版された効果は大きい。「IAWA List」 に従ってコード化された木材解剖学的記載は、既往の文献において記述されている記載内容よりも、正確でかつ情報量に富むことがあり得る。 この「IAWA List」が日本語版でも利用できるようになることは大変喜ばしいことである。IAWA の61カ国の中で日本は、木材解剖学のすべての分野、特に全世界からの商業木材の識別の分野や日本の有史前の木製品および化石木材の樹種識別の分野において指導的立場にある。私たち編者は、この日本語版が日本の木材科学、森林学、植物学の数多くの学生ならびに研究者に利用されることを希望するものであり、IAWA 委員会の成果がより多くの人々に受け入れられることを喜びとしています。 1997年 3月
The Editors Elisabeth A. Wheeler Pieter Baas Peter E. Gasson
-
ii
日本語版序文
本書は、IAWA Bulletin n.s. 10 (3): 219-332(1989)に掲載された E. A. Wheeler, P. Baas & P. E.Gasson 編「IAWA List of Microscopic Features for Hardwood Identification with an Appendix on non-anatomical information」の日本語版である。 木材識別のための顕微鏡的特徴のコードは、Oxford Keysや日本産材を対象とした須藤彰司(1956)でそれぞれのコードがそれぞれのカード式検索に用いられてきたが、1981 年の R. B. Miller の「Standard List」に象徴されるように、パーソナル・コンピューターの発達に伴って顕微鏡的特徴コードによるデータ化が進行した。そして、コンピューターによる木材識別は、NCSU のE.A.Wheelerらの「GUESS」や CSIRO の J. Ilic の「CSIROID」、日本国内では、利用範囲が限られていたが、市販データベース・ソフトを用いた日本産広葉樹材の識別データベース(島地謙:d-CARD、長谷川益夫・塚本英子:MS-Access)が、それぞれに相互の互換性が不十分なままに開発されてきた。 日本木材学会「組織と材質研究会」では、日本産広葉樹材の識別に対する需要の増大を背景に、1995年 8 月に「コンピューター識別のための日本産広葉樹材の解剖学的記載とデータベース化」を主題としてワークショップを開催した。このワークショップでは、日本産広葉樹材の統一的データベースの必要性、樹種識別の作業過程からのデータベースへの要求、顕微鏡画像を取り込んだデータベースの必要性、などについて討論された。その結果として、日本産広葉樹材の木材解剖学的記載とそのコンピューター識別のためのデータベース構築の作業を進めていく際に、世界的に共通かつ統一性のあるデータとするために、基本的な内容や構造などを「IAWA List」に準拠した形式とする必要があることが確認された。 「組織と材質研究会」のワークショップで確認された方針と作業方向に基づいて、日本産広葉樹材の「IAWA List」に準拠したコード化の作業が進められている。最近では、E.A.Wheelerらの「GUESS」や CSIRO の J.Ilic の「CSIROID」も、コンピューター識別のためのデータベースを「IAWA List」に準拠した形式に修正しており、これらとは別に Hamburg の Richter も CSIRO が提供している植物学的記載と識別のためのソフトウェア DELTAINTKEYS を用いて「IAWA List」に準拠した形式でデータベースを構築し始めている。韓国では既に「IAWA List」に準拠した形式で韓国産広葉樹材の記載とコード表が公表されている。さらに、東南アジア産植物の既存の情報を整理統合することを目的とした PROSEA(Plant Resources of South-East Asia)のプロジェクトでも、そのVol. 5 に樹木を扱っており、東南アジア~パプアニューギニア地域産広葉樹材の解剖学的記載を「IAWA List」に準拠した形式でデータベース化し、Vol.5 No.3では特徴がコード化されて、木材組織の記載に用いられている。 このような現状では、日本国内におけるデータベース構築と識別作業を共通的かつ統一的なものとすること、それと同時に、世界各国で進行している広葉樹材の顕微鏡的特徴のコード化の成果を正確に理解することが必要とされる。その基盤となる「IAWA List」の理解を助けることを目的として、このたび日本語版を刊行した。従って、和訳にあたっては原文の構文や用語を尊重したが、分かりやすい文章とするために、説明のための言葉を補ったり、意訳した箇所がある。また、原文には委員会の見解不統一による記述の矛盾や、「緩衝された蒸留水」のような直訳が残されているが、これらについては「IAWA List」の編者たちが原文を尊重することを希望したので、読者の誤解を招かないと思われる範囲で、原文を尊重した。
1998 年 6 月伊 東 隆 夫 藤 井 智 之
-
iii
日本語版注釈
科名:科名の日本語表記は、原則として『学術用語集 植物学編』(増訂版1990)の一覧表に従った。 Leguminosae(広義のマメ科)は、しばしば下記のように3亜科に分けられるが、それぞれが独立した科として扱われることもある。原文においては、Leguminosae(広義のマメ科)とそれを細分化した3科:Papilionaceae(マメ科)、Mimosaceae(ネムノキ科)、Caesalpiniaceae(ジャケツイバラ科)の両方が用いられている。日本語版では、Papilionaceae = Leguminosae Subfamily Papilionoideae(マメ科 - マメ亜科)、Mimosaceae = Leguminosae Subfamily Mimosoideae(マメ科 - ネムノキ亜科)、Caesalpiniaceae = Leguminosae Subfamily Caesalpinioideae(マメ科 - ジャケツイバラ亜科)と表記した。また、BetulaceaeとColylaceaeが用いられているが、これらについても、Betulaceae = BetulaceaeTrib. Betuleae(カバノキ科 - カバノキ連)と Colylaceae = Betulaceae Trib. Colyeae(カバノキ科 - ハシバミ連)と表記した。
属名、種名:原文に例示されている樹種の一部は、日本産広葉樹材や唐木などのよく知られた外国産木材であるが、多くは標準和名を持たない樹種である。読者の理解を助ける意味で和名を訳注とするならば、外国産樹種については、一般名(英語名または現地名の英語表記)を記した方が、一般的でない和名を入れるより有効であろう。―例えば、Laurus nobilisゲッケイジュ(Lauraceaeクスノキ科)は一般的に受け入れられるが、Ulmus procera ヨーロッパニレ(Ulmaceae ニレ科)は「ヨーロッパを代表するニレ属の樹種」を意味する程度の和名であり、この和名がUlmus proceraを示すことは一般的に受け入れられていない。この様に、一般的でない属名や種名については日本語表記を加えなかった。
木材解剖学用語:木材解剖学用語の和訳は、原則として『国際木材解剖学用語集』(1975:日本木材学会組織と材質研究会編)および『学術用語集 植物学編』(増訂版 1990)に従ったが、両者で訳語が不一致の場合には後者を優先した。また、「せん(穿)孔」のように、漢字表記とひらがな表記の両方が選択可能な用語については、「穿孔」のように、漢字表記を採用した。 「fiber」は学術用語集植物学編では「繊維」であるが、「IAWA List」の原文中で「fiber」は常に「wood fiber」を意味し、繊維を説明する「wood」が省略されている。この日本語版では、読者が理解しやすいように、「繊維」と直訳しないで「wood fiber」と理解して「木部繊維」の用語を用いている。 「foraminate perforation」は、学術用語集植物学編では「多孔穿孔」としているが、一方では 「IAWAList」の原文の「multiple perforation」は「多孔穿孔」または「多孔型穿孔」と訳さざるを得ない。この様に「多孔穿孔」と表記することは誤解を招きかねないので、「IAWA List」における「foraminateperforation」の定義を解釈して、「ふるい状穿孔」と和訳した。
特徴項目:個々の特徴は、概ね記載文で記述されている。しかし、一部の特徴項目は複数の項目をひとまとめにして記述しているので、個々の項目の記述が不完全である。例えば、「道管内腔の平均接線径」に関する特徴 40 ~ 44 のように、「道管内腔の平均接線径:特徴 40. 50μm 以下;41. 50~100µm」などであるが、個々の特徴項目を引用する際に不都合である。この様な不完全な特徴項目については、対象となる特徴を補って「道管内腔の平均接線径:40. 道管内腔の平均接線径は50μm 以下;41. 道管内腔の平均接線径は 50 ~ 100μm」などと記述した。
同義語 : 特徴項目の定義において同義語(synonym)が示されていることがある。例えば、「Helicalthickening」に関する特徴 36 ~ 39 では「Synonym: spiral thickening」と記述されているが、和訳で
-
iv
は「らせん肥厚」が両者に用いられている。この様に、同義語については和訳する意味がないので、原文通りとした。
訳注:「IAWA List」の原文の表現では分かりにくい記述については、訳者の注釈を付した。例えば、特徴9「道管は孤立のみ(90%以上)」の場合、孤立道管の比率の求め方は定義にもコメントにも記述されていないので、「手順:孤立道管の比率=(孤立道管の数/道管の総数)× 100%」と訳注を加えた。
コード化:特徴項目は、観察した試料のすべてにおいて同じように適用できるとは限らない。特徴の記載に際して、その特徴が供試試料のすべてに共通しない場合、「feature variable(特徴に変異がある)」とする。例えば、成長輪界に関する特徴 1&2 の例示(Fig. 4.)には明瞭な成長輪界(特徴 1)と不明瞭な成長輪界(特徴 2)が観察され、写真の説明文には「features 1 and 2 variable(特徴1と2に変異あり)」と記述されている。複数の切片を観察した結果、その特徴が認められたり認められなかったりした場合にも、「features 1 and 2 variable(特徴 1 と 2 に変異あり)」、または、例えば孤立道管の特徴のように独立した特徴項目の場合には「feature 4(特徴4)に変異あり」と記録する。コード番号を用いる場合には、例えば; 1v, 2v, 4v とする。 例えば、穿孔板の階段数に関する項目(特徴 15 ~ 18)の場合には、25 個以上の道管要素について観察した結果、階段数が 8 ~ 18 本であったら、特徴 15 と特徴 16 を記録する。このとき、階段数12 ~ 15 の階段穿孔板(特徴 15)が普通で、階段数 8 ~ 10 本の階段穿孔板(特徴 16)が観察されることが稀であったら、コード番号は 15,(16)とする。
日本語版謝辞
本書は、京都大学木質科学研究所 木質細胞構造・機能学研究室の1995年度の輪読会で「IAWA Listof Microscopic Features for Hardwood Identification、1989」を通読した成果をもとにしている。 また、緒方健博士、大谷諄博士には原稿を査読していただき、貴重なご助言を頂いた。 日本語版出版にあたっては、坂巻育子女史に割り付け編集を手伝って頂いた。
-
v
原 著 序 文
「IAWA List of Microscopic Features for Hardwood Identification、1989」は、R. B. Miller によるコード化法に関する解説と共に 1981 年(IAWA Bull. n. s. 2: 99-145)に発表された「Standard List of Char-acters Suitable for Computerized Hardwood Identification(コンピューターによる広葉樹材の識別に適した性質の標準リスト)」を継承している。この 1981 年の出版によって、広葉樹材の識別に適した特徴に関して情報および経験の交換が国際的に著しく促進された。その結果、1987年7月にベルリンで開催された XIV International Botanical Congress(第 16 回国際植物科学会議)の期間中に催されたIAWAの会合において、1981年の「Standard List(標準リスト)」の改訂が決定された。コンピューター自体とそのためのプログラムが発達したので、新たなリストの内容を、コード化法に重点を置くよりも、定義および解説と例示に限定することで合意した。 新しいリスト作成に向けて、IAWAのCouncil(評議会)により新たに委員会が設置された。USDACompetitive Research Grant(アメリカ合衆国農商務省、競争的研究補助金)から多大の補助金(WoodUtilization Program(Grant No. 88-33541-4081)(木材有効利用計画:(補助金番号 88-33541-4081))を頂き、委員会によるワークショップが 1988 年 10 月 2 ~ 7 日 North Carolina State University(Raleigh,NC, USA)において、IAWA と IUFRO Division 5 との共催によって開催された。このワークショップの期間中にリストの原案が作成された。この原案に対してIAWA会員の意見が求められ、新しいリストの仕上げ作業に役立てられた。ここに提示したリストは、その後、委員会による校正と委員会内部の広範にわたる協議の結果了承されたものである。 本リストには163項目の木材解剖学的特徴とその他の雑多な58の特徴が採用されているが、広葉樹材に現れるすべての内部構造を包含するような完全なものではない。むしろ、識別を目的とした場合に有用な特徴をまとめて、簡潔なリストとすることを目的とした。また、個々の特徴につけられた番号はコンピューター・プログラムのためのコード番号として用いられることを期待したものではなく、特徴を参照する場合に作業を容易にすることを目的としており、かつまた、あるプログラム/データ・ベースから別のプログラム/データ・ベースへコード化されたデータを変換する場合に役立てられることを期待している。 木材および木材を構成する細胞は生物学的な構成要素であり、生理的もしくは機械的な機能を果たすために、高木、低木、つる性植物によって形成されたものである。木材の構造には植物体の他の部分よりも個々に独立的な多様性があるが、しかし、連続的な変異の方がはるかに多く、このような多様性を明確な特徴として分類すること自体が不自然な要素を含んでいる。とはいえ、この特徴のリストでは記載内容の不明瞭性が最小限におさえられていると自負するところであり、現時点ならびに将来において、木材識別ならびに木材解剖学的記載に携わる人々にとって貴重な案内書であり参考書となることを希望する。
The IAWA Committee:
Veronica Angyalossy AlfonsoDivisão de Madeiras, I.P.T. Cidade Universitária, São Paulo, Brazil
Pieter BaasRijksherbarium, Leiden, The Netherlands
Sherwin CarlquistRancho Santa Ana Botanic Garden, Claremont, California ,U.S.A.
-
vi
Joao Peres ChimeloDivisao de Madeiras, I.P.T. Didade Universitária, São Paulo, Brazil
Vera T. Rauber CoradinInstituo Brasiliero de Desenvolvimento Florestal, Departomento de Pasquista, Brasilia, Brazil
Pierre DétienneDivision d’Anatomie de Bois, Centre Technique Forestier Tropical, Norgent-sur-Marne, France
Peter E. GassonJodrell Laboratory, Royal Botanic Gardens, Kew, U.K.
Dietger GrosserInstitut für Holzfroschyng und Holztechnik der Universität Müchen, Müchen, F.R.G.
Jugo IlicCSIRO, Wood Science & Technology, Highett, Victoria, Australia
Keiko KurodaForestry & Forest Products Research Institute, Kansai Branch, Kyoto, Japan
Regis B. MillerCenter for Wood Anatomy Research, Forest Products Laboratory, Madison, Wisconsin, U.S.A.
Ken OgataForestry & Forest Products Research Institute, Tsukuba, Japan
Hans Georg RichterInstitut für Holzbiologie und Holzschuz, Bundesforschungstalt für Forst- und Holzwirtschaft, Hamburg,F.R.G.
Ben J. H. ter WelleRijksuniversiteit Utrecht, Institut voor Systematische Plantkunde, Utrecht, The Netherlands
Elisabeth A. WheelerDepartment of Wood & Paper Science, North Carolina State University, Raleigh, North Carolina, U.S.A.
-
vii
原 著 謝 辞
The IAWA Committee (IAWA 委員会)は下記の機関ならびに個人に対して負うところが多大である。 The USDA Competitive Research Grant-Wood Utilization Program (Grant No. 88-33541-4081)(アメリカ合衆国農商務省、競争的研究補助金)によって、ノースカロライナ州 Raleigh における IAWA/IUFRO ワークショップ開催およびその後の London と Leiden における P. Baas、P. E. Gasson、E.A. Wheeler の会合の開催経費が援助された。 The Department of Wood & Paper Science、NCSU には IAWA/IUFRO ワークショップ開催を快諾され、施設などを提供して頂いた。特に、Dr. C. A. La Pasha、Ms. Vann Moora には各段階での原稿作成を手伝って頂いた。そして、Ms. Mille Sullivan にもお世話になった。 The Forest Products Laboratory, Madison, Wisconsin, USA にはこの特別号の印刷経費に対する経費援助を頂いた。 The Jodrell Laboratory, Royal Botanical Gardens Kew, U. K. には写真原稿作成および顕微鏡写真選定のための 1989 年 3 月に開催された会合の際に施設を提供して頂きかつ歓待して頂いた。 The Bailey-Wetmore Laboratory of Plant Anatomy and Morphology, Harvard University ならびにDr. P. B. Tomlinson, Dr. D. Pfister, Dr. A. Knoll には Bailey のネガフィルムを調べさせて頂き、暗室を使用させて頂いた。 The Rijksherbarium には種々の便宜をはかって頂いた。特に、Ms. Emma E. van Nieuwkoop には図版の作成と割り付け編集をして頂いた。 最終稿に至る過程では、本リストの原稿に対して下記の IAWA 会員からコメントを頂いた:
K. M. Bhat, IndiaLim Seng Choon, Kepong, MalaysiaD. F. Cutler, Kew, UKW. C. Dickison, Chapel Hill, NC, USAT. Fujii, Tsukuba, JapanH. Gottwald, Hamburg, FRGMary Gregory, Kew, UK
Yvonne Hemberger, Hamburg, FRGAlberta M. W. Mennega, Utrecht, The NetherlandsC. A. La Pasha, Raleigh, NC, USAA. Londono, ColumbiaPaula Rudall, Kew, UKM. Seth, India
-
viii
図版提供者
図版は下記の方々の御好意による。
I. W. Bailey, Bailey - Wetmore Laboratory of Plant Anatomy and Morphology, Harvard University : 10, 11,16, 18, 39, 57, 58, 64, 65, 148.
Blumea: 38, 44, 73, 74 (Baas 1973), 174 (Van Vliet 1981).P. Détienne: 129.P. E. Gasson: 2, 4, 7, 8, 12, 19, 21, 26, 28, 30-34, 36, 37, 40, 45-54, 63, 66, 75, 78-82, 84-86, 88, 90- 93, 95-99,
102-106, 111, 114-116, 118, 120, 122, 126-128, 130-135, 137-144, 151, 153, 154, 156,157, 159, 161, 163-168, 171, 172, 176, 178, 180-182, 188.
D. Grosser: 15, 27, 29, 55, 68, 71, 72, 112, 113, 146, 158, 170, 173, 177.IAWA Bulletin: 3 (Bridgwater & Baas 1982), 35 (Vidal Gomes et al. 1988), 70 & 123 (Bridgwater &
Baas 1982), 155 (Topper & Koek - Noorman 1980), 175 (Baas et al. 1988), 184 (Gottwald 1983), 185(Ter Welle 1980).
J. Ilic: 56.C. A. La Pasha: 190.R. B. Miller: 160, 186, 187, 189.K. Ogata: 1, 5, 9, 13, 14, 20, 22, 24, 25, 41, 42, 61, 62, 76, 77, 83, 89, 94, 101, 107-109, 117, 119, 124, 125, 136,
145, 147, 149, 150, 152, 162, 179.E. A. Wheeler: 6, 17, 23, 43, 59, 60, 67, 87, 100, 110, 121, 169, 183.H. P. Wilkinson: 69.
原 著 注 釈
定量的特徴:一般的に適用可能な定量的特徴(例:道管分布密度、道管内腔の接線径、道管要素長、ならびに木部繊維長)に関しては、本リストでは未知試料の識別を目的とした場合に使いやすいように各階級の範囲を広く区切り、同時に精度の高い定量的記載(平均値、範囲、標準偏差)を採用している。データベースを作成する際には測定対象の試料数と同時に試料毎の測定数をも記録すること。記録可能な情報量(例:全測定値または単に平均値、範囲、標準偏差のみ)はコンピューター・プログラムに依存しており、なおかつ定量的特徴の一致を検索するアルゴリズムも異なる。ここでは、定量的データの蓄積および取り出しに関するプログラムとして特定のものを推奨するものではなく、それらのデータを得るための方法についての手引きをするものである。
変異のある特徴ならびに相対量:木材固有の変異性のために、ある特徴が同一種においても試料によっては明確であったり不明確または存在しなかったりすることが必然的に生じてくる。検索表を作成する際には、そのような変異をどう扱うかが常に問題となっている。ある特徴、例えば菱形結晶、の相対量の記載にも問題があり、相対的頻度の記述を記載またはデータベースに書き加えておかなければならない。本リストでは、ある種の特徴はそれが普通に認められる場合にのみ適用されるように記述している。その場合、例として示した顕微鏡写真や説明によって「普通」の解釈を補完できるように配慮した。数多くの検索表で、ある種の特徴が「普通」に見られることを用いているが、これまでに何%出現すれば「普通」と言えるかについて体系的な解析はなされてきていない。従って、本リストでは「普通」に対する量的な基準を提示していない。
-
ix
広葉樹材の識別
IAWA による光学顕微鏡的特徴リスト
附属資料:解剖学以外の情報
目 次
-
目 次x
FOREWORD ....................................................................................................................................... i日本語版出版によせて ...................................................................................................................... i日本語版序文 ...................................................................................................................................... ii日本語版注釈 ...................................................................................................................................... iii日本語版謝辞 ...................................................................................................................................... iv原 著 序 文 ........................................................................................................................................... v原 著 謝 辞 ........................................................................................................................................... vii図版提供者 .......................................................................................................................................... viii原 著 注 釈 ........................................................................................................................................... viii解剖学的特徴リスト .......................................................................................................................... xiii
名前(科、属、種、命名者).............................................................................................................. 1
解剖学的特徴 ................................................................................................................................. 2
成長輪 .................................................................................................................................................. 2道 管 .................................................................................................................................................. 4管孔性 .................................................................................................................................................. 4道管の配列 .......................................................................................................................................... 6道管の複合 .......................................................................................................................................... 10孤立道管の外形 .................................................................................................................................. 12穿孔板 .................................................................................................................................................. 14道管相互壁孔:配列と大きさ .......................................................................................................... 18道管相互壁孔の大きさ(交互壁孔と対列壁孔).............................................................................. 18ベスチャード壁孔 .............................................................................................................................. 20道管放射組織間壁孔(存在と配列).................................................................................................. 21らせん肥厚 .......................................................................................................................................... 24道管内腔の平均接線径 ...................................................................................................................... 261mm2 あたりの道管数 ..................................................................................................................... 27平均道管要素長 .................................................................................................................................. 27チロースおよび道管中の堆積物 ...................................................................................................... 27木材は無道管 ...................................................................................................................................... 30仮道管と木部繊維 .............................................................................................................................. 30基本組織の木部繊維 .......................................................................................................................... 32隔壁木繊維と柔組織様木部繊維の帯 .............................................................................................. 34木部繊維の壁厚 .................................................................................................................................. 36木部繊維の平均長 .............................................................................................................................. 37軸方向柔組織 ...................................................................................................................................... 38独立柔組織 .......................................................................................................................................... 38
-
目 次 xi
随伴柔組織 .......................................................................................................................................... 40帯状柔組織 .......................................................................................................................................... 44軸方向柔組織の細胞型と柔組織ストランド長 .............................................................................. 48放射組織 .............................................................................................................................................. 50放射組織の幅 ...................................................................................................................................... 50集合放射組織 ...................................................................................................................................... 52放射組織の高さ .................................................................................................................................. 52放射組織の大きさは明らかに 2 階級に分類される ..................................................................... 54放射組織:細胞構成 .......................................................................................................................... 56鞘細胞 .................................................................................................................................................. 60タイル細胞 .......................................................................................................................................... 60穿孔を有する放射組織細胞 .............................................................................................................. 62離接放射柔細胞壁 .............................................................................................................................. 621mm あたりの放射組織の数 ............................................................................................................ 64木材は放射組織を持たない .............................................................................................................. 65層階状構造 .......................................................................................................................................... 66分泌要素と形成層活動による変異 .................................................................................................. 68油細胞と粘液細胞 .............................................................................................................................. 68細胞間道 .............................................................................................................................................. 70管および小管 ...................................................................................................................................... 74形成層活動による変異 ...................................................................................................................... 76無機含有物 .......................................................................................................................................... 78菱形結晶 .............................................................................................................................................. 78集 晶 .................................................................................................................................................. 81その他の結晶形 .................................................................................................................................. 81結晶についてのその他の識別上の特徴 .......................................................................................... 82シリカ .................................................................................................................................................. 86
附属資料 ―解剖学以外の情報 .............................................................................. 89
地理的区分 .......................................................................................................................................... 89生 態 .................................................................................................................................................. 90商業用材 .............................................................................................................................................. 90比 重 .................................................................................................................................................. 90心材の色 .............................................................................................................................................. 91木の匂い .............................................................................................................................................. 93心材の蛍光 .......................................................................................................................................... 94水とエタノールの抽出液:蛍光と色 .............................................................................................. 94
-
目 次xii
発泡試験 .............................................................................................................................................. 96クロムアズロール - S試験............................................................................................................... 97軸片燃焼試験 ...................................................................................................................................... 97
引用文献 .............................................................................................................................................. 99
用語および索引
英和対照木材解剖学用語 .................................................................................................................. 104樹種名索引 .......................................................................................................................................... 109用語索引 .............................................................................................................................................. 117
-
xiii
解剖学的特徴リスト
● 名前(科、属、種、命名者)― p. 1
解剖学的特徴
● 成長輪 ― p. 2
1. 成長輪界が明瞭 2. 成長輪界が不明瞭または欠如
● 道管 ― p. 4
管孔性 ― p. 4 3. 木材は環孔性 4. 木材は半環孔性 5. 木材は散孔性
道管の配列 ― p. 6 6. 道管は接線状に配列 7. 道管は斜線状あるいは放射状に配列 8. 道管は火炎状に配列
道管の複合 ― p. 10 9. 道管は孤立のみ(90% 以上)10. 4 個以上の放射複合道管が普通11. 集団道管が普通
孤立道管の外形 ― p. 1212. 孤立道管の外形が角張る
穿孔板 ― p. 1413. 単穿孔板14. 階段穿孔板 15. 階段穿孔板の階段数が 10 以下(≦ 10) 16. 階段穿孔板の階段数が 10 ~ 20(10 ~ 20) 17. 階段穿孔板の階段数が 20 ~ 40(20 ~ 40) 18. 階段穿孔板の階段数が 40 以上(≧ 40)19. 網状、ふるい状、あるいは他の型の多孔穿孔板
道管相互壁孔:配列と大きさ ― p. 1820. 道管相互壁孔は階段状21. 道管相互壁孔は対列状22. 道管相互壁孔は交互状23. 交互壁孔の形が多角形
-
解剖学的特徴リストxiv
道管相互壁孔の大きさ(交互壁孔と対列壁孔) ― p. 18 24. 道管相互壁孔の大きさは微小:4μm 以下(≦ 4μm) 25. 道管相互壁孔の大きさは小 :4 ~ 7 μm(4 ~ 7μm) 26. 道管相互壁孔の大きさは中 :7 ~ 10μm(7 ~ 10μm) 27. 道管相互壁孔の大きさは大 :10μm 以上(≧ 10μm)28. 道管相互壁孔の大きさの範囲 (μm)
ベスチャード壁孔 ― p.2029. ベスチャード壁孔
道管放射組織間壁孔(存在と配列) ― p. 21 30. 道管放射組織間壁孔には明瞭な壁孔縁がある: 個々の放射組織細胞において、壁孔のすべてが 大きさおよび形ともに道管相互壁孔に類似する
31. 道管放射組織間壁孔は壁孔縁が狭くて見かけ上単壁孔:壁孔は円形または角張る32. 道管放射組織間壁孔は壁孔縁が狭くて見かけ上単壁孔: 壁孔は水平(階段状、裂け目状)から垂直(栅状)
33. 同一の放射組織細胞の中に、明らかに大きさあるいはタイプが異なる2種類の道管放射組織間壁孔がある
34. 道管放射組織間壁孔は片複壁孔であって、径が大きい(10μm 以上)35. 道管放射組織間壁孔が放射組織の縁辺の細胞列に限定されている
らせん肥厚 ― p. 2436. 道管要素にらせん肥厚がある 37. 道管要素全体にらせん肥厚がある 38. 道管要素尾部にのみらせん肥厚がある 39. 小径道管要素にのみらせん肥厚がある
道管内腔の接線径 ― p. 26 40. 道管内腔の接線径は 50μm 以下(≦ 50μm) 41. 道管内腔の接線径は 50 ~ 100μm(50 ~ 100μm) 42. 道管内腔の接線径は 100 ~ 200μm(100 ~ 200μm) 43. 道管内腔の接線径は 200μm 以上(≧ 200μm)44. 平均、標準偏差(+、-)、範囲、測定個数 n=x45. 道管の直径が明らかに 2 階級に分類される非環孔材
1 mm2 あたりの道管数 ― p. 2746. 1mm2 あたりの道管数は 5 個以下(≦ 5/mm2) 47. 1mm2 あたりの道管数は 5 ~ 20 個(5 ~ 20/mm2)48. 1mm2 あたりの道管数は 20 ~ 40 個(20 ~ 40/mm2)49. 1mm2 あたりの道管数は 40 ~ 100 個(40 ~ 100/mm2)50. 1mm2 あたりの道管数は 100 個以上(≧ 100/mm2)51. 平均、標準偏差(+、-)、範囲、測定個数 n =x
平均道管要素長 ― p. 2752. 平均道管要素長は 350μm 以下(≦ 350μm)
-
解剖学的特徴リスト xv
53. 平均道管要素長は 350 ~ 800μm(350 ~ 800μm)54. 平均道管要素長は 800 μm 以上(≧ 800 μm)55. 平均、標準偏差(+、-)、範囲、測定個数 n =x
チロースおよび道管中の堆積物 ― p. 2756. チロースが普通にある57. チロースは厚壁58. 心材道管中にゴム質およびその他の堆積物がある
木材は無道管 ― p. 3059. 木材は無道管
● 仮道管と木部繊維 ― p. 30
60. 道管状仮道管または周囲仮道管がある
基本組織の木部繊維 ― p. 3261. 木部繊維は単壁孔または壁孔縁の狭い有縁壁孔をもつ62. 木部繊維は明瞭な有縁壁孔をもつ63. 木部繊維の壁孔が放射壁と接線壁の両方に普通に認められる64. 基本組織の木部繊維にらせん肥厚がある
隔壁木繊維と柔組織様木部繊維の帯 ― p. 3465. 隔壁木繊維がある66. 無隔壁木繊維がある67. 柔組織様木部繊維の帯が通常の木部繊維と交互に配列する
木部繊維の壁厚 ― p. 3668. 木部繊維はきわめて薄壁69. 木部繊維は薄壁ないし厚壁70. 木部繊維はきわめて厚壁
木部繊維の平均長 ― p.3771. 木部繊維の平均長は 900 μm 以下(≦ 900 μm)72. 木部繊維の平均長は 900 ~ 1600 μm (900 ~ 1600 μm)73. 木部繊維の平均長は 1600 μm 以上(≧ 1600 μm)74. 平均、標準偏差(+、-)、範囲、測定個数 n=x
● 軸方向柔組織 ― p. 38
75. 軸方向柔組織が欠如あるいはきわめて稀
独立柔組織 ― p. 3876. 軸方向柔組織は独立散在77. 軸方向柔組織は短接線状
-
解剖学的特徴リストxvi
随伴柔組織 ― p. 4078. 軸方向柔組織は随伴散在79. 軸方向柔組織は周囲状80. 軸方向柔組織は翼状 81. 軸方向柔組織はまぶた型-翼状 82. 軸方向柔組織はかもめ型-翼状83. 軸方向柔組織は連合翼状84. 軸方向柔組織は帽状
帯状柔組織 ― p. 4485. 軸方向柔組織の帯の幅は 4 細胞幅以上86. 軸方向柔組織の帯の幅は 3 細胞幅以下の狭い帯または線状87. 軸方向柔組織は網状88. 軸方向柔組織は階段状89. 軸方向柔組織は成長輪界状あるいは擬成長輪界状
軸方向柔組織の細胞型と柔組織ストランド長 ― p. 4890. 紡錘形柔細胞91. 柔組織ストランドは 2 個の柔細胞で構成される92. 柔組織ストランドは 3 ~ 4 個の柔細胞で構成される93. 柔組織ストランドは 5 ~ 8 個の柔細胞で構成される94. 柔組織ストランドは 9 個以上の柔細胞で構成される95. 未木化の柔組織
● 放射組織 ― p. 50
放射組織の幅 ― p. 50 96. 放射組織は単列のみ 97. 放射組織は 1 ~ 3 列 98. 大きな放射組織は普通 4 ~ 10 列 99. 大きな放射組織は普通 11 列以上100. 多列部の幅が単列部と同じ
集合放射組織 ― p. 52101. 集合放射組織
放射組織の高さ ― p. 52102. 放射組織の高さが 1mm 以上
放射組織の大きさは明らかに 2 階級に分類される ― p. 54103. 放射組織の大きさは明らかに 2 階級に分類される
放射組織:細胞構成 ― p. 56104. 放射組織を構成する細胞がすべて平伏細胞105. 放射組織を構成する細胞がすべて直立 / 方形細胞
-
解剖学的特徴リスト xvii
106. 放射組織多列部は平伏細胞で構成され、1細胞高の直立 / 方形細胞の縁辺部をもつ107. 放射組織多列部は平伏細胞で構成され、たいていは 2 ~ 4 細胞高の直立 / 方形細胞の縁辺部をもつ
108. 放射組織多列部は平伏細胞で構成され、5細胞高以上の直立/方形細胞の縁辺部をもつ109. 放射組織全体に平伏、方形、直立細胞が混在する
鞘細胞 ― p. 60110. 鞘細胞
タイル細胞 ― p. 60111. タイル細胞
穿孔を有する放射組織細胞 ― p. 62112. 穿孔を有する放射組織細胞
離接放射柔細胞壁 ― p. 62113. 離接放射柔細胞壁
1mm あたりの放射組織の数 ― p. 64114. 1mm あたりの放射組織の数は 4 個以下 (≦ 4/mm)115. 1mm あたりの放射組織の数は 4 ~ 12 個(4 ~ 12/mm)116. 1mm あたりの放射組織の数は 12 個以上(≧ 12/mm)
木材は放射組織を持たない ― p. 65117. 木材は放射組織を持たない
● 層階状構造 ― p. 66
118. 放射組織がすべて層階状119. 低い放射組織は層階状で、高い放射組織は非層階状120. 軸方向柔細胞 / 道管要素が層階状121. 木部繊維が層階状122. 放射組織 / 軸方向要素が不規則に層階状123. 軸方向 1mm あたりの放射組織の段数
● 分泌要素と形成層活動による変異 ― p. 68
油細胞と粘液細胞 ― p. 68124. 油細胞と粘液細胞の一方または両方が放射柔組織に随伴する125. 油細胞と粘液細胞の一方または両方が軸方向柔組織に随伴する126. 油細胞と粘液細胞の一方または両方が木部繊維間に存在する
細胞間道 ― p. 70127. 軸方向細胞間道は長接線状配列128. 軸方向細胞間道は短接線状配列
-
解剖学的特徴リストxviii
129. 軸方向細胞間道は散在130. 放射(水平)細胞間道131. 傷害細胞間道
管および小管 ― p. 74132. 乳管またはタンニン管
形成層活動による変異 ― p. 76133. 同心円型材内師部134. 散在型材内師部135. その他の形成層活動による変異
● 無機含有物 ― p.78
菱形結晶 ― p.78136. 菱形結晶がある 137. 菱形結晶が直立および方形細胞の一方または両方にある 138. 菱形結晶が平伏細胞中にある 139. 菱形結晶が平伏細胞中にあり、放射方向に並んでいる 140. 菱形結晶が多室の直立および方形細胞の一方または両方にある 141. 菱形結晶が非多室の軸方向柔細胞中にある 142. 菱形結晶が多室の軸方向柔細胞中にある 143. 菱形結晶が木部繊維中にある
集晶 ― p. 81144. 集晶がある 145. 集晶が放射柔細胞中にある 146. 集晶が軸方向柔細胞中にある 147. 集晶が木部繊維中にある 148. 集晶が多室細胞中にある
その他の結晶形 ― p. 81149. 束晶150. 針晶151. 柱晶 / 細長い結晶152. 他の形の結晶(大抵は小さい)153. 砂晶
結晶についてのその他の識別上の特徴 ― p. 82154. 1つの細胞または室中に同程度の大きさの結晶が 2 つ以上ある155. 1つの細胞または室中に明らかに大きさの異なる結晶がある156. 結晶が膨らんだ細胞中にある157. 結晶がチロース中にある158. シストリス(鐘乳体)
-
解剖学的特徴リスト xix
シリカ ― p. 86159. 粒状シリカがある 160. 粒状シリカが放射柔細胞中にある 161. 粒状シリカが軸方向柔細胞中にある 162. 粒状シリカが木部繊維中にある163. ガラス状シリカ(ガラス状ケイ酸体)
附属資料 ―解剖学以外の情報 ― p. 89
地理的区分 ― p. 89164. ヨーロッパと温帯アジア (Brazier & Franklin 74 区) 165. 地中海地方を除くヨーロッパ 166. アフリカ北部と中東を含む地中海地方 167. 温帯アジア(中国)、日本、旧ソ連168. 中央南アジア (Brazier & Franklin 75 区) 169. インド、パキスタン、スリランカ 170. ビルマ171. 東南アジアと太平洋地域 (Brazier & Franklin 76 区) 172. タイ、ラオス、ベトナム、カンボジア(インドシナ) 173. インドマレイシア :インドネシア、フィリピン、マレイシア、ブルネイ、シンガポー
ル、パプアニューギニア、ソロモン諸島 174. 太平洋諸島(ニューカレドニア、サモア、ハワイ、フィジーを含む)175. オーストラリアとニュージーランド (Brazier & Franklin 77 区) 176. オーストラリア 177. ニュージーランド178. 熱帯アフリカ本土と近隣諸島 (Brazier & Franklin 78 区) 179. 熱帯アフリカ 180. マダガスカルとモーリシャス、レユニオンとコモロ181. アフリカ南部(南回帰線以南) (Brazier & Franklin 79 区)182. 北アメリカとメキシコの北部 (Brazier & Franklin 80 区)183. 新熱帯および温帯ブラジル (Brazier & Franklin 81 区) 184. メキシコと中央アメリカ 185. カリブ海地方 186. 熱帯南アメリカ 187. ブラジル南部188. 温帯南アメリカ:アルゼンチン、チリ、ウルグアイ、パラグアイを含む (Brazier & Franklin 82 区)
生態 ― p. 90189. 高木190. 低木191. つる(性)植物
商業用材 ― p. 90192. 商業用材
-
解剖学的特徴リストxx
比重 ― p. 90193. 比重が小さい、0. 40 以下194. 比重が中程度、0. 40 ~ 0. 75195. 比重が大きい、0. 75 以上
心材の色― p. 91196. 心材の色が辺材の色より濃い197. 心材が茶色を基調とするかまたは茶色味を帯びている198. 心材が赤色を基調とするかまたは赤味を帯びている199. 心材が黄色を基調とするかまたは黄色味を帯びている200. 心材が白色ないし灰色を基調とする201. 心材に縞がある202. 心材が上記以外の色
木の匂い― P. 93203. 特徴的な匂い
心材の蛍光 ― p. 94204. 心材は蛍光性である
水とエタノールの抽出液:蛍光と色― p. 94 205. 水抽出液に蛍光がある206. 水抽出液が無色から褐色または褐色味を帯びている207. 水抽出液が赤または赤味を帯びている208. 水抽出液が黄色または黄色味を帯びている209. 水抽出液が上記以外の色210. エタノール抽出液に蛍光がある211. エタノール抽出液が無色から褐色または褐色味を帯びている212. エタノール抽出液が赤または赤味を帯びている213. エタノール抽出液が黄色または黄色味を帯びている214. エタノール抽出液が上記以外の色
発泡試験― p. 96215. 発泡試験で陽性
クロムアズロール-S試験― p.97216. クロムアズロール-S試験が陽性
軸片燃焼試験― p. 97217. 軸片が燃えて炭化する218. 軸片が燃えて完全な灰になる:灰は明るい白色219. 軸片が燃えて完全な灰になる:灰は黄褐色220. 軸片が燃えて完全な灰になる:灰は上記と異なる221. 軸片が燃えて部分的に灰になる
-
解剖学的特徴(ANATOMICAL FEATURES) 1
名前 (NAME)
科、属、種、命名者 (Family, genus, species, authority)
データーベースを作成する際、標本について充分な分類学上の情報を記録すること、すなわち、科、属、種、命名者名を記録することは本質的なことである。命名者名については、省略形を用いる場合には、一般的に用いられている省略法を用いること (Mabberley (1987) に一覧表がある)。種々の属について類縁関係を調べたり、適切な科名を決めたりする際には “Willis's Dictionary of Flow-ering Plants and Ferns (顕花植物およびシダ植物辞典) (Willis 1973)”や Mabberley (1987) を参考にすることを推奨する。データベースを準備する時、科の決定についてどの分類体系を用いたかということも明示しておくべきである (例:Takhtajan 1980, 1987;Cronquist 1981, 1988;Thorne 1976)。 特定の科の木材解剖学的情報を検索したり、未知の材の同定のためには特定の科あるいはいくつかの科に絞って調べることは有効である。従って、特徴の1つとして科名を記録することは賢明である。科名についてはデーターベースの注に明瞭に説明してある限りは、どんなコード方法が使われていようと問題ではない。例えば、科名は3つの頭文字 (Weber 1982) で示すこともできるし、数字のコード (Miller 1981 の p. 144ー155 を参照) で示すこともできる。
-
解剖学的特徴(ANATOMICAL FEATURES)2
解剖学的特徴 (ANATOMICAL FEATURES)
成長輪(GROWTH RING)
1. 成長輪界が明瞭 (Growth ring boundaries distinct)2. 成長輪界が不明瞭または欠如 (Growth ring boundaries indistinct or absent)
定義: 成長輪界が明瞭:成長輪の境界部において急激な木材構造の変化が認められ、通常、木部繊維の壁厚 / 放射径の変化を伴う。Figs. 1 & 2。
成長輪界が不明瞭または欠如:成長輪は不明瞭で、境界部では木材構造の変化は多少とも緩やか、または、成長輪界が認められない。Fig. 3。
コメント: 成長輪界は、以下の木材構造の変化のうち、一つあるいは複数の項目によって決定される。a . 晩材の厚壁で偏平な木部繊維あるいは仮道管に対して早材の薄壁の木部繊維あるいは仮道管。Fig. 1、Weinmannia trichosperma (Cunoniaceae クノニア科)、Laurus nobilis ゲッケイジュ(Lauraceae クスノキ科)。b. 半環孔材や環孔材のように、晩材(latewood)と次年輪の早材(earlywood)との間の道管径の明確な相違があること。Figs. 5~8、Juglans regiaペルシャクルミ (Juglandaceae クルミ科)、Ulmus procera(Ulmaceae ニレ科)。c. 成長輪界柔組織(ターミナルあるいはイニシアル柔組織)。Fig. 2、Xylopia nitida (Annonaceae バンレイシ科)、Brachystegia laurentii (Leguminosae Subfamily Caesalpinioideae マメ科 - ジャケツイバラ亜科)、Juglans regia ペルシャクルミ (Juglandaceae クルミ科)、Liriodendron tulipifera ユリノキ (Magnoliaceae モクレン科)。木部繊維の径や壁厚の急激な変化を伴わない非周期的な帯状 の柔組織は成長輪界柔組織とはみなされず、明確な成長輪界を表すものではない。
例:Eschweilera subglandulosa (Lecythidaceae サガリバナ科)、Irvingia excelsa (Simaroubaceae ニガキ科)。
d. 道管状仮道管と非常に小径の道管要素が晩材に数多く存在するか、または、基本組織を構成し、早材にはそれらが存在しない。例:Sambucus nigra (Caprifoliaceae スイカズラ科)。
e. 晩材に向かうにつれて帯状柔組織の出現頻度が減少し、結果として、明瞭な木部繊維の領域ができあがる。例:Lecythis pisonis (Lecythidaceae サガリバナ科)、Donella pruniformis(Sapotaceae アカテツ科)。
f. 広がった放射組織。例:Fagus spp. ブナ属 (Fagaceae ブナ科)。g. 成長輪界の他のタイプと、通常、上の特徴のいくつかの組み合わせで起こるものについては Carlquist (1980, 1988) を参照のこと。
「成長輪界の欠如」は十分に明確な記述であるが、「不明瞭」と「明瞭」との違いはいくぶん任意のものであり、中間的なものもある (Fig. 4)。成長輪は、肉眼で観察して明瞭に見えても、光学顕微鏡観察では境界が不明瞭な場合がある。不明瞭な成長輪界は熱帯の樹木ではごく一般的である(Fig. 3、例:Spondias mombin(Anacardiaceae ウルシ科)、Parkia nitida(Leguminosae Subfamily Mimosoideae(マメ科 - ネムノキ亜科))、Coelocaryon preussii(Myristicaceae ニクズク科)、Xanthophyllumphilippinense(Polygalaceae ヒメハギ科) )。 非周期的で散発的な成長輪界が、極端に異常な気候状態あるいは傷害により生じている場合は、成長輪が存在しないかあるいは境界が不明瞭として、記録されるべきである。
-
解剖学的特徴(ANATOMICAL FEATURES) 3
Figs. 1 & 2. 成長輪界が明瞭(特徴 1)。 - 1:Weinmannia trichosperma、成長輪界は木部繊維および道管の直径の違いで区切られる、× 80。- 2:Xylopia nitida、成長輪界は厚壁の晩材木部繊維と成長輪界柔組織によって区切られる、× 48。Fig. 3. 成長輪界が不明瞭あるいは欠如(特徴 2)、Xanthophyllum philippinense、× 22。Fig. 4. 成長輪界が明瞭と不明瞭の中間(特徴 1 と 2 のいずれにも変異しやすい)、Jacaranda copaia、× 48。
-
解剖学的特徴(ANATOMICAL FEATURES)4
道管(VESSELS)
管孔性 (POROSITY)
3. 木材は環孔性 (Wood ring-porous)4. 木材は半環孔性 (Wood semi-ring-porous)5. 木材は散孔性 (Wood diffuse-porous)
定義: 木材は環孔性:早材の道管が、前年輪および同じ年輪内の晩材の道管より明らかに大きくて明瞭に区分された領域あるいは孔圏を形成する木材。同じ年輪内において、晩材への移行が急激。Fig. 5。例:Quercus robur (Fagaceae ブナ科)、Fraxinus excelsior (Oleaceae モクセイ科)、Phellodendronamurense キハダ (Rutaceae ミカン科)、Bumelia lanuginosa (Sapotaceae アカテツ科)、Ulmusamericana (Ulmaceae ニレ科)。
木材は半環孔性:1) 早材における道管は前年輪の晩材道管より明らかに大径であるが、同じ年輪内の中間部から晩材では、より小径の道管へ徐々に変化していくような木材。または、2) 早材道管は密に配列して明確な孔圏(pore zone)を形成するが、それらの孔圏道管が前年輪あるいは同年輪における晩材の道管に比べて特に大径でない木材。別の定義:環孔材と散孔材の中間的状態。Figs. 6 &7、例:Cordia trichotoma (Boraginaceae ムラサキ科)、Juglans nigra (Juglandaceae クルミ科)、Lagerstroemia floribunda (Lythraceae ミソハギ科)、Cedrela odorata (Meliaceae センダン科)、Pterocarpus indicus (Leguminosae Subfamily Papilionoideae(マメ科 - マメ亜科))、Prunus amygdalusアーモンド (Rosaceae バラ科)、Paulownia tomentosa キリ (Scrophulariaceae ゴマノハグサ科)。
木材は散孔性:道管径が同一成長輪内で多少とも均一な木材。Figs. 9 & 10、例:Acer spp. カエデ属 (Aceraceae カエデ科)、Rhododendron wadanum トウゴクミツバツツジ (Ericaceae ツツジ科)、Cercidiphyllum japonicum カツラ (Cercidiphyllaceae カツラ科)、Swietenia spp. マホガニー属(Meliaceae センダン科)、Enterolobium spp. (Leguminosae Subfamily Mimosoideae(マメ科 - ネムノキ亜科));大多数の熱帯材と多くの温帯産材。
コメント: 管孔性についての3つの特徴は、それらの中間的段階が存在するために、連続的なものであり、多くの種の木材では、散孔材(diffuse-porous wood)から半環孔材(semi-ring-porous wood)、あるいは環孔材(ring-porous wood)から半環孔材までの変異がある。管孔性(特徴 3 ~ 5)は、道管配列(特徴 6~ 8)とは独立して番号が付けられている。このことは、道管径がほぼ均一であるならば、特徴的な道管配列(特徴 6 ~ 8)をもつ木材であっても、道管が均等に分布した木材と同様に、散孔材であるということを示している。 ある種の温帯産散孔材の中には(例:Fagus spp. ブナ属 (Fagaceae ブナ科)、Platanus spp. スズカケノキ属 (Platanaceae スズカケノキ科))、晩材の最後に形成される道管が、次年輪の早材道管よりかなり小径ものがあるが、道管径は成長輪のほとんどの部分でほぼ一様である (Fig. 10)。 記載では、環孔材の早材の孔圏の特徴、すなわち、その孔圏道管が何列であるかということを記述すべきである。須藤 (Sudo 1959) の検索表では、その特徴を「孔圏:単列」と「孔圏:多列」として用いている。そのような特徴は、種を識別するのに有効であろう。例えば、Ulmus americana アメリカニレは、基本的に単列の早材をもつが、Ulmus rubra は、2 列以上の早材をもつ。(訳注:日本産広葉樹材では Zelkova serrata ケヤキ (Ulmaceae ニレ科) および Kalopanax septemlobus ハリギリ(Araliaceae ウコギ科)では孔圏道管が単列となる傾向が強い。)
-
解剖学的特徴(ANATOMICAL FEATURES) 5
注意:成長の遅い環孔材では、成長輪は狭く、ほとんど晩材が無くなる (Fig. 8)。また、成長の遅い環孔材では複数の年輪の早材部が相互に近接しているので、これを接線状配列と混同したり、散孔材と解釈しないように注意する必要がある。
Fig. 5. 木材は環孔性(特徴 3)、Phellodendron amurense キハダ、× 28。Figs. 6 & 7. 木材は半環孔性(特徴4)。-6: Prunus sp. サクラ属の一種、×25。-7: Paulownia tomentosaキリ、× 18。Fig. 8. 木材は環孔性(特徴3)であるが、年輪が狭いため、散孔材あるいは半環孔材であるかのような誤った印象を与える、Catalpa bignonioides アメリカキササゲ、× 30。
表紙本扉英語奥付
FOREWORD日本語版出版によせて日本語版序文日本語版注釈日本語版謝辞原著序文原著謝辞図版提供者原著注釈目 次解剖学的特徴リスト名前(科、属、種、命名者)解剖学的特徴成長輪1.成長輪界が明瞭2.成長輪界が不明瞭または欠如
道管管孔性3.木材は環孔性4.木材は半環孔性5.木材は散孔性
道管の配列6.道管は接線状に配列7.道管は斜線状あるいは放射状に配列8.道管は火炎状に配列
道管の複合9.道管は孤立のみ(90%以上)10.4 個以上の放射複合道管が普通11.集団道管が普通
孤立道管の外形12.孤立道管の外形が角張る
穿孔板13.単穿孔板14.階段穿孔板15.階段穿孔板の階段数が10 以下(≦10 )16.階段穿孔板の階段数が10 〜20 (10 〜20 )17.階段穿孔板の階段数が20 〜40 (20 〜40 )18.階段穿孔板の階段数が40 以上(≧40 )19.網状、ふるい状、あるいは他の型の多孔穿孔板
道管相互壁孔:配列と大きさ20.道管相互壁孔は階段状21.道管相互壁孔は対列状22.道管相互壁孔は交互状23.交互壁孔の形が多角形
道管相互壁孔の大きさ(交互壁孔と対列壁孔)24.道管相互壁孔の大きさは微小:4 μm 以下(≦4 μm )25.道管相互壁孔の大きさは小 :4 〜7 μm (4 〜7 μm )26.道管相互壁孔の大きさは中 :7 〜10 μm (7 〜10 μm )27.道管相互壁孔の大きさは大 :10 μm 以上(≧10 μm )28.道管相互壁孔の大きさの範囲(μm )
ベスチャード壁孔29.ベスチャード壁孔
道管放射組織間壁孔(存在と配列)30.道管放射組織間壁孔には明瞭な壁孔縁がある31.道管放射組織間壁孔は壁孔縁が狭くて見かけ上単壁孔:壁孔は円形または角張る32.道管放射組織間壁孔は壁孔縁が狭くて見かけ上単壁孔:壁孔は水平(階段状、裂け目状)から垂直(柵状)33.同一の放射組織細胞の中に、明らかに大きさあるいはタイプが異なる2 種類の道管放射組織間壁孔がある34.道管放射組織間壁孔は片複壁孔であって、径が大きい(10 μm 以上)35.道管放射組織間壁孔が放射組織の縁辺の細胞列に限定されている
らせん肥厚36.道管要素にらせん肥厚がある37.道管要素全体にらせん肥厚がある38.道管要素尾部にのみらせん肥厚がある39.小径道管要素にのみらせん肥厚がある
道管内腔の平均接線径40.道管内腔の接線径は50 μm 以下(≦50 μm )41.道管内腔の接線径は50 〜100 μm (50 〜100 μm )42.道管内腔の接線径は100 〜200 μm (100 〜200 μm )43.道管内腔の接線径は200 μm 以上(≧200 μm )44.平均、標準偏差(+、−)、範囲、測定個数 n=x45.道管の直径が明らかに2 階級に分類される非環孔材
1mm 2 あたりの道管数46.1mm 2 あたりの道管数は5 個以下(≦5/mm 2 )47.1mm 2 あたりの道管数は5 〜20 個(5 〜20/mm 2 )48.1mm 2 あたりの道管数は20 〜40 個(20 〜40/mm 2 )49.1mm 2 あたりの道管数は40 〜100 個(40 〜100/mm 2 )50.1mm 2 あたりの道管数は100 個以上(≧100/mm 2 )51.平均、標準偏差(+、−)、範囲、測定個数 n =x
平均道管要素長52.平均道管要素長は350 μm 以下(≦350 μm )53.平均道管要素長は350 〜800 μm (350 〜800 μm )54.平均道管要素長は800 μm 以上(≧800 μm )55.平均、標準偏差(+、−)、範囲、測定個数 n =x
チロースおよび道管中の堆積物56.チロースが普通にある57.チロースは厚壁58.心材道管中にゴム質およびその他の堆積物がある
木材は無道管59.木材は無道管
仮道管と木部繊維60.道管状仮道管または周囲仮道管がある基本組織の木部繊維61.木部繊維は単壁孔または壁孔縁の狭い有縁壁孔をもつ62.木部繊維は明瞭な有縁壁孔をもつ63.木部繊維の壁孔が放射壁と接線壁の両方に普通に認められる64.基本組織の木部繊維にらせん肥厚がある
隔壁木繊維と柔組織様木部繊維の帯65.隔壁木繊維がある66.無隔壁木繊維がある67.柔組織様木部繊維の帯が通常の木部繊維と交互に配列する
木部繊維の壁厚68.木部繊維はきわめて薄壁69.木部繊維は薄壁ないし厚壁70.木部繊維はきわめて厚壁
木部繊維の平均長71.木部繊維の平均長は900 μm 以下(≦900 μm )72.木部繊維の平均長は900 〜1600 μm (900 〜1600 μm )73.木部繊維の平均長は1600 μm 以上(≧1600 μm )74.平均、標準偏差(+、−)、範囲、測定個数 n=x
軸方向柔組織75.軸方向柔組織が欠如あるいはきわめて稀独立柔組織76.軸方向柔組織は独立散在77.軸方向柔組織は短接線状
随伴柔組織78.軸方向柔組織は随伴散在79.軸方向柔組織は周囲状80.軸方向柔組織は翼状81.軸方向柔組織はまぶた型−翼状82.軸方向柔組織はかもめ型−翼状83.軸方向柔組織は連合翼状84.軸方向柔組織は帽状
帯状柔組織85.軸方向柔組織の帯の幅は4 細胞幅以上86.軸方向柔組織の帯の幅は3 細胞幅以下の狭い帯または線状87.軸方向柔組織は網状88.軸方向柔組織は階段状89.軸方向柔組織は成長輪界状あるいは擬成長輪界状
軸方向柔組織の細胞型と柔組織ストランド長90.紡錘形柔細胞91.柔組織ストランドは2 個の柔細胞で構成される92.柔組織ストランドは3 〜4 個の柔細胞で構成される93.柔組織ストランドは5 〜8 個の柔細胞で構成される94.柔組織ストランドは9 個以上の柔細胞で構成される95.未木化の柔組織
放射組織放射組織の幅96.放射組織は単列のみ97.放射組織は1 〜3 列98.大きな放射組織は普通4 〜10 列99.大きな放射組織は普通11 列以上100.多列部の幅が単列部と同じ
集合放射組織101.集合放射組織
放射組織の高さ102.放射組織の高さが1mm 以上
放射組織の大きさは明らかに2 階級に分類される103.放射組織の大きさは明らかに2 階級に分類される
放射組織:細胞構成104.放射組織を構成する細胞がすべて平伏細胞105.放射組織を構成する細胞がすべて直立/方形細胞106.放射組織多列部は平伏細胞で構成され、1 細胞高の直立/方形細胞の縁辺部をもつ107.放射組織多列部は平伏細胞で構成され、たいていは2 〜4 細胞高の直立/方形細胞の縁辺部をもつ108.放射組織多列部は平伏細胞で構成され、5 細胞高以上の直立/方形細胞の縁辺部をもつ109.放射組織全体に平伏、方形、直立細胞が混在する
鞘細胞110.鞘細胞
タイル細胞111.タイル細胞
穿孔を有する放射組織細胞112.穿孔を有する放射組織細胞
離接放射柔細胞壁113.離接放射柔細胞壁
1mm あたりの放射組織の数114.1mm あたりの放射組織の数は4 個以下 (≦4/mm )115.1mm あたりの放射組織の数は4 〜12 個(4 〜12/mm )116.1mm あたりの放射組織の数は12 個以上(≧12/mm )
木材は放射組織を持たない117.木材は放射組織を持たない
層階状構造118.放射組織がすべて層階状119.低い放射組織は層階状で、高い放射組織は非層階状120.軸方向柔細胞/道管要素が層階状121.木部繊維が層階状122.放射組織/軸方向要素が不規則に層階状123.軸方向1mm あたりの放射組織の段数
分泌要素と形成層活動による変異油細胞と粘液細胞124.油細胞と粘液細胞の一方または両方が放射柔組織に随伴する125.油細胞と粘液細胞の一方または両方が軸方向柔組織に随伴する126.油細胞と粘液細胞の一方または両方が木部繊維間に存在する
細胞間道127.軸方向細胞間道は長接線状配列128.軸方向細胞間道は短接線状配列129.軸方向細胞間道は散在130.放射(水平)細胞間道131.傷害細胞間道
管および小管132.乳管またはタンニン管
形成層活動による変異133.同心円型材内師部134.散在型材内師部135.その他の形成層活動による変異
無機含有物菱形結晶136.菱形結晶がある137.菱形結晶が直立および方形細胞の一方または両方にある138.菱形結晶が平伏細胞中にある139.菱形結晶が平伏細胞中にあり、放射方向に並んでいる140.菱形結晶が多室の直立および方形細胞の一方または両方にある141.菱形結晶が非多室の軸方向柔細胞中にある142.菱形結晶が多室の軸方向柔細胞中にある143.菱形結晶が木部繊維中にある
集晶144.集晶がある145.集晶が放射柔細胞中にある146.集晶が軸方向柔細胞中にある147.集晶が木部繊維中にある148.集晶が多室細胞中にある
その他の結晶形149.束晶150.針晶151.柱晶/細長い結晶152.他の形の結晶(大抵は小さい)153.砂晶
結晶についてのその他の識別上の特徴154.1 つの細胞または室中に同程度の大きさの結晶が2 つ以上ある155.1 つの細胞または室中に明らかに大きさの異なる結晶がある156.結晶が膨らんだ細胞中にある157.結晶がチロース中にある158.シストリス(鐘乳体)
シリカ159.粒状シリカがある160.粒状シリカが放射柔細胞中にある161.粒状シリカが軸方向柔細胞中にある162.粒状シリカが木部繊維中にある163.ガラス状シリカ(ガラス状ケイ酸体)
附属資料解剖学以外の情報地理的区分164.ヨーロッパと温帯アジア (Brazier &Franklin 74 区)165.地中海地方を除くヨーロッパ166.アフリカ北部と中東を含む地中海地方167.温帯アジア(中国)、日本、旧ソ連168.中央南アジア(Brazier &Franklin 75 区)169.インド、パキスタン、スリランカ170.ビルマ171.東南アジアと太平洋地域 (Brazier &Franklin 76 区)172.タイ、ラオス、ベトナム、カンボジア(インドシナ)173.インドマレイシア :インドネシア、フィリピン、マレイシア、ブルネイ、シンガポール、パプアニューギニア、ソロモン諸島174.太平洋諸島(ニューカレドニア、サモア、ハワイ、フィジーを含む)175.オーストラリアとニュージーランド (Brazier &Franklin 77 区)176.オーストラリア177.ニュージーランド178.熱帯アフリカ本土と近隣諸島(Brazier &Franklin 78 区)179.熱帯アフリカ180.マダガスカルとモーリシャス、レユニオンとコモロ181.アフリカ南部(南回帰線以南) (Brazier &Franklin 79 区)182.北アメリカとメキシコの北部(Brazier &Franklin 80 区)183.新熱帯および温帯ブラジル(Brazier &Franklin 81 区)184.メキシコと中央アメリカ185.カリブ海地方186.熱帯南アメリカ187.ブラジル南部188.温帯南アメリカ:アルゼンチン、チリ、ウルグアイ、パラグアイを含む(Brazier &Franklin 82 区)
生態189.高木190.低木191.つる(性)植物
商業用材192.商業用材
比重193.比重が小さい、0.40 以下194.比重が中程度、0.40 〜0.75195.比重が大きい、0.75 以上
心材の色196.心材の色が辺材の色より濃い197.心材が茶色を基調とするかまたは茶色味を帯びている198.心材が赤色を基調とするかまたは赤味を帯びている199.心材が黄色を基調とするかまたは黄色味を帯びている200.心材が白色ないし灰色を基調とする201.心材に縞がある202.心材が上記以外の色
木の匂い203.特徴的な匂い
心材の蛍光204.心材は蛍光性である
水とエタノールの抽出液:蛍光と色205.水抽出液に蛍光がある206.水抽出液が無色から褐色または褐色味を帯びている207.水抽出液が赤または赤味を帯びている208.水抽出液が黄色または黄色味を帯びている209.水抽出液が上記以外の色210.エタノール抽出液に蛍光がある211.エタノール抽出液が無色から褐色または褐色味を帯びている212.エタノール抽出液が赤または赤味を帯びている213.エタノール抽出液が黄色または黄色味を帯びている214.エタノール抽出液が上記以外の色
発泡試験215.発泡試験で陽性
クロムアズロール‐ S 試験216.クロムアズロール−S 試験が陽性
軸片燃焼試験217.軸片が燃えて炭化する218.軸片が燃えて完全な灰になる:灰は明るい白色219.軸片が燃えて完全な灰になる:灰は黄褐色220.軸片が燃えて完全な灰になる:灰は上記と異なる221.軸片が燃えて部分的に灰になる
引用文献用語および索引英和対照木材解剖学用語樹種名索引用語索引
奥付付録:図一覧Fig.1 成長輪界が明瞭(特徴1)。Weinmannia trichosperma、成長輪界は木部繊維および道管の直径の違いで区切られる、× 80。Fig.2 成長輪界が明瞭(特徴1)。Xylopia nitida、成長輪界は厚壁の晩材木部繊維と成長輪界柔組織によって区切られる、× 48。Fig.3 成長輪界が不明瞭あるいは欠如(特徴2)、Xanthophyllum philippinense、× 22。Fig.4 成長輪界が明瞭と不明瞭の中間(特徴1 と2 のいずれにも変異しやすい)、Jacaranda copaia、× 48。Fig.5 木材は環孔性(特徴3)、Phellodendron amurense キハダ、× 28。Fig.6 木材は半環孔性(特徴4)。Prunus sp. サクラ属の一種、×25。Fig.7 木材は半環孔性(特徴4)。Paulownia tomentosaキリ、× 18。Fig.8 木材は環孔性(特徴3)であるが、年輪が狭いため、散孔材あるいは半環孔材であるかのような誤った印象を与える、Catalpa bignonioides アメリカキササゲ、× 30。Fig.9 木材は散孔性(特徴5)。Rhododendron wadanum トウゴクミツバツツジ、× 75。Fig.10 木材は散孔性(特徴5)。Cercidiphyllum japonicum カツラ、最後に形成される晩材の道管径と早材の道管径が相違するが、散孔材に区分される。× 30。Fig.11 道管は接線状に配列する(特徴6)。晩材道管が接線状に配列する(特徴3: 木材は環孔性であることにも注意)、Kalopanax septemlobus ハリギリ、× 80。Fig.12 道管は接線状に配列する(特徴6)。道管と柔組織は花綱状(festooned )、Cardwellia sublimis、×30。Fig.13 道管は接線状に配列する(特徴6)。すべての道管が接線方向の帯状に配列する、Enkianthuscernuus チチブドウダン、× 75。Fig.14 道管は斜線状に配列(特徴7)、Calophyllum papuanum、× 29。Fig.15 道管は火炎状に配列(特徴8)。Rhamnus cathartica クロウメモドキ属(特徴5: 木材は散孔性であることにも注意)、× 60。Fig.16 道管は火炎状に配列(特徴8)。Rhus aromatica ウルシ属、道管の火炎状配列は晩材にのみ限定される(特徴3:木材は環孔性であることにも注意)。Fig.17 道管は放射状に配列(特徴7)、Amyris sylvatica、× 18。Fig.18 小径道管は接線状ないし斜線状に配列(特徴6 および7)、Kalopanax septemlobus ハリギリ、× 80(特徴3:木材は環孔性であることにも注意)。Fig.19 道管は斜線状あるいは火炎状に配列(特徴7 および8)、Bumelia obtusifolia (特徴5:木材は散孔性であることにも注意)、× 45。Fig.20 道管は斜線状あるいは放射状に配列(特徴7)、Lithocarpus edulis マテバシイ、× 29。Fig.21 道管は孤立のみ(特徴9)、Aspidosperma quebracho、× 45。Fig.22 4 個以上の放射複合道管が普通(特徴10)、Elaeocarpus hookerianus、× 29。Fig.23 集団道管が普通(特徴11)、Gymnocladus dioica、晩材部、× 140。Fig.24 道管の一部は孤立し、その他は2~4個の放射複合道管あるいは構成道管数の少ない集団道管、(特徴9、10、11 を欠く)、Drypetes gerrardii 、× 75。Fig.25 立道管の外形が角張る(特徴12)、Stemonurus luzoniensis、× 75。Fig.26 丸みを帯びた道管の外形(特徴12 を欠く)、Banara regia、× 45。Fig.27 単穿孔板(特徴13)、Aesculus hippocastanum、× 105。Fig.28 単穿孔板および階段(bar) 数が2 本の階段穿孔板(特徴13、14、15)、Didymopanax morototoni、× 115。Fig.29 階段穿孔板の階段(bar)数が20~ 40 (特徴14、17)、Staphylea pinnata、× 220。Fig.30 網状穿孔板(特徴19)、Didymopanax morototoni、× 115。Fig.31 ふるい状穿孔板(特徴19)、Oroxylum indicum、× 115。Fig.32 網状に分岐した階段をもつ階段穿孔が斜めに複合した穿孔板(特徴14、19)、Iryanthera paraensis、× 290。Fig.33 規則正しい網状穿孔板(特徴19、しばしば特徴14 の階段穿孔板と共に生じる)、Iryantherajuruensis、× 290。Fig.34 階段と網状の複合した穿孔板(特徴14、19)、Iryanthera elliptica、× 290。Fig.35 放射状穿孔板(特徴19)、Cytharexylum myrianthum、× 300 (SEM)。Fig.36 階段壁孔(特徴20)、Michelia compressa オガタマノキ、× 115。Fig.37 対列壁孔(特徴21)、Liriodendron tulipifera ユリノキ、× 115。Fig.38 階段壁孔から対列壁孔(特徴20 と21)、Ilex laurina、× 350。Fig.39 交互壁孔(特徴22)、Mappia racemosa、× 112。Fig.40 交互壁孔の形が多角形(特徴23)、Salix sp. ヤナギ属、特徴22(交互壁孔)と26、27(壁孔の大きさは中から大)でもあることに注意。Fig.41 道管相互壁孔の形は円形から楕円形(特徴23 が欠如)、対列壁孔(特徴21)にも留意、Nothofagusmoorei、× 300。Fig.42 道管相互壁孔は微小、4μm以下(特徴24)、Polyalthia oblongifolia. 交互壁孔(特徴22)にも留意、×300。Fig.43 ベスチャード壁孔(特徴29)、Terminalia sp. コバテイシ属の1 種× 825。Fig.44 可溶性の堆積物のためにベスチャード壁孔のように見える壁孔(特徴29 のベスチャード壁孔が存在しない)、対列壁孔(特徴21)にも留意、Ilex cymosa、× 800。Fig.45 道管放射組織間壁孔には道管相互壁孔と同様に明瞭な壁孔縁がある(特徴30)。Couratari cf. oblongifolia × 290。Fig.46 道管放射組織間壁孔には道管相互壁孔と同様に明瞭な壁孔縁がある(特徴30)。Camptostemon philippinense × 75。Fig.47 道管放射組織間壁孔は壁孔縁が狭くて見かけ上単壁孔:壁孔は円形(特徴31)。Salixs p . (ヤナギ科)。特徴3 5(道管放射組織間壁孔が縁辺部に限られている) も注目、× 290。Fig.48 道管放射組織間壁孔は壁孔縁が狭くて見かけ上単壁孔:壁孔は円形(特徴31)。Elaeocarpus calomala × 290。Fig.49 道管放射組織間壁孔は壁孔縁が狭くて見かけ上単壁孔:水平な壁孔(階段状、裂け目状)か ら垂直な壁孔(.状)(特徴32)。水平な壁孔、Atherosperma moschata、× 450。Fig.50 道管放射組織間壁孔は壁孔縁が狭くて見かけ上単壁孔:水平な壁孔(階段状、裂け目状)か ら垂直な壁孔(.状)(特徴32)。垂直な壁孔、Trigonobalanus verticillata × 290。Fig.51 道管放射組織間壁孔の一部は壁孔縁が狭くて見かけ上単壁孔、かつ同一の放射組織細胞の中に、明らかに大きさあるいはタイプの異なる2 種類の道管放射組織間壁孔がある(特徴32 と33)。Horsfieldiasubglobosa、× 115。Fig.52 同一の放射組織細胞の中に、明らかに大きさあるいはタイプの異なる2 種類の道管放射組織間壁孔がある(特徴33):大きい壁孔(矢印)は穿孔に類似している、Chaunochiton breviflorum、× 290。Fig.53 道管放射組織間壁孔は片複壁孔であって、径が大きい(特徴34)、Ceriops tagal (微分干渉コントラスト)、× 450。Fig.54 道管要素全体にらせん肥厚がある(特徴36 と37)。Prunus spinosa、× 290。Fig.55 道管要素全体にらせん肥厚がある(特徴36 と37)。Cytisus scoparius、× 220。Fig.56 道管要素尾部にのみらせん肥厚がある(特徴36 と38)、Cercidiphyllum japonicum カツラ。× 150。Fig.57 道管要素尾部にのみらせん肥厚がある(特徴36 と38)、Cercidiphyllum japonicum カツラ。× 240。Fig.58 道管が明らかに2 階級に分類される非環孔材(特徴45)、Serjania subdentata、× 35。Fig.59 チロースが普通にある(特徴56)。木口面、Anacardium occidentalis、× 220。Fig.60 チロースが普通にある(特徴56)。接線面、Robinia pseudoacacia ハリエンジュ、× 140。Fig.61 チロースは厚壁(特徴56 と57)、Cantleya corniculata。木口面、× 75。Fig.62 チロースは厚壁(特徴56 と57)、Cantleya corniculata。板目面、× 75。Fig.63 心材道管中にゴム質およびその他の堆積物がある(特徴58)。Physocalymma scaberrimum、×110。Fi