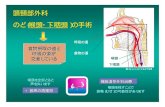暮らしの税情報 税の基礎知識...税の基礎知識 2 所得税のしくみ 所得税は どのように 計算するの?所得税の算出のしくみ 所得税は、個人の所得に対してかかる税金で、1年間の全ての所得から所得
Title 漢代人頭税の崩壞過程 : 特に算賦を中心として 東洋史研 …546 頭 税...
Transcript of Title 漢代人頭税の崩壞過程 : 特に算賦を中心として 東洋史研 …546 頭 税...

Title 漢代人頭税の崩壞過程 : 特に算賦を中心として
Author(s) 永田, 英正
Citation 東洋史研究 (1960), 18(4): 546-568
Issue Date 1960-03-31
URL https://doi.org/10.14989/148167
Right
Type Journal Article
Textversion publisher
Kyoto University

546
頭
税
の
鼠
壊
過
程
漢
代
人
|
|
特
算
賦
を
中
六 五四三二一
は
し
が
き
渓代の郷里制と人頭税
人頭税の負猪と流民の渡生
後漢の流民と郷里制の崩援
貨幣経済の衰退
結語にかえて
周知の如く漢代には、算賦(口算)及び口賦(口銭)の二
種類の人頭税があった。算賦は、十五歳以上五十六歳以下
の男女から、毎歳
一人あたり百二十鏡、即ち一算の課徴を
行い、それで以て武庫の兵器或は軍事用の車馬をととのえ
司令、
いわゆる軍事費にあてられたものであった。この算賦
'L,'
と
し
刀え
英
正
田
が成丁に課せられた人頭税であるのに射し、口賦は未成丁
に諜せられた人頭税で、
それは七歳以上十四歳以下の未成
- 50ー
丁の男女より、毎歳一人あたり二十三銭を徴収し、
うち二
十銭は天子の奉養費に、
残りの三銭は武帝以後、車騎の馬
を補う費用にあてられたものであった。
ところで、
この算賦、
ロ賦と呼ばれる人頭税は、前漢の
みならず後漢時代にも縫績して施行されたが、興味深いこ
ぞれが後漢帝園没落の寸前まで徴収されたのにも拘
とは、
らず、帝園が没落して三園時代になると消滅し、以後あら
たに戸を客桂とした課税方法||
それは均田制によって代
表される課税方法であるが|
|に出炭化して来る事寅である。
思うに、賦税は格役とともに、
園家成立の必要上から園民

に課せられた一つの大きな義務である。従って、賦税の賓
馳胞を明らかにすることは、その園家を究明する上に於て、
また必須の篠件でもある。漢の人頭税もこの例外ではない。
しかし、就中この税制が、
漢帝園の没落と運命を共にして
いる事賓を考える時、人頭税の賓健を究明することは、秦
と並んで中闘史上最初の統一園家である漢帝園の歴史的性
格を、
一層明確ならしむる
一つ
の手掛りを得るものと云え
るであろう。かかる意味から本稿では、算賦を中心に漢代
人頭税の退化し、崩壊していく過程を考察し、併せて漢帝
園の歴史的性格の一端に燭れんと試みたもので、その貼多
少なりとも得るところがあれば、また筆者の幸とするとこ
ろである。
向、卒中苓次氏は
『居延漢簡と漢代の財産税』に於て、
従来、漢代成丁の人頭税の名稿として使用されて来た算賦
は、人頭税のみならず財産税(賞算)も含むものであると
いう有力な意見を提示した。しかし、算賦が賞算を含めて
向日算を意味する以上、算賦を従来通り成丁の人頭税の名
総として使用することは許されるものと思う。本稿で使用
547
する算賦は、全て人頭税の調である。あらかじめ記して諒
解を得ておきたい。
人頭税は如何にして徴収されたか。先ず順序として、そ
の徴収の手績から考える。
漢書百官公卿表、績漢書百官志によれば、徴税の任に蛍
ったのは、郷の有秩、車問夫及びその属僚である、郷佐であ
つわ。しかし、初めにも述べたように、算賦は十五歳から
五十六歳までの男女成丁を、
口賦は七歳から十四歳までの
- 51ー
未成了を各々針象とした人頭税である以上、徴税に先立ち、
先ず課税の針象となる適齢者の調査、いわゆる戸口調査を
行う必要があったことは言うまでもない。漢代の戸口調査
は、案比と呼ばれていた。案比とは毎年仲秋の八月に行わ
れた「案戸比民」のことで、その賓際は、年齢などのごま
かしを防ぐために、地方官吏(豚・郷の吏)が一々首貧検
を行ったものであった
Q
そして、周蔵小司徒の「及三年則
大比。大比則受邦園之比要」の賀公彦の疏に
漢時。八月案比。而造籍書。
とあるように、案比の結果、人民は名籍(戸籍)
の上に登

548
載されたのである。漢書巻
一下高帝紀五年五月(前二
O二)
の詔によると
不書名敏。酬前日一VM今天下己定。
令各蹄其間柄。復故爵回宅。吏以文法教訓排告。勿答厚。
民前或相緊保山津。
とあり、故郷を離れ、名籍に登載されていない避難民の整
理を命じているところから見るに、漢の案比は、高祖の天
下統一と同時に、賢施されたようである。このような案比
111名籍にもとづいて揺役
・成役の徴用などとともに、ま
た人頭税が課徴された。たとえば、後漢書一
O后紀の序に
漢法。常因八月算人。
とあり、李賢はこれに注して
漠儀注目。八月初矯算賦。故日算人。
と言っている。ここでいう
「算人L
であるが、この解樟に
かぞ
は問題があり、従来は「人を算える」の意味にとられてい
た。しかし、
これは
「人を算える」ではなく、むしろ卒中
苓次氏の説くように「人に算する」の意司、毎年八月に案
比して戸口を調べ、それによって作成された名籍に照して
「適齢者に算賦を課した」というのが適切な解線であろう。
では、
一櫨漢の名籍と郷里制とは、
どのような閥係にあ
ったのか。この貼を明らかにしておく必要がある。これに
ついては近年、
日比野丈夫、宮崎市定の雨氏が注目すべき
見解を護表している。先ず日比野氏は
『郷亭皇についV
ての
研究』
(東洋史研究
一四の一・一一)に於て、居延漢筒研究
の成果にもとづき、嘗時の名籍は
「名勝欝里」といわれる
ように行政単位としては必ず里を記入せねばならなかった
里は漢代の地方制度の一連としてみるかぎり人
ことから、
借用的に編成されたある戸数の組み合せであったとし、皇は
戸籍、亭部は地籍編成の単位で、いくつかの亭部が集って
郷をなし、その中に含まれる人戸が適宜に分けられて里と
- 52ー
なったと推測した。この日比野氏の読を更に護展させたの
が、宮崎氏の『中園における緊落形態の襲遷について||
邑
・園と郷
・亭と村とに劃する考察』(大谷史皐六)であ
る。氏は、中園古代は都市園家であったという前提から出
護し、臨
・郷・
亭
・緊といわれるものもこの都市園家の系
統をひくもので、
それらはいずれも大小の城郭をもった同
性質の緊落であると考え、
里はそれら城郭をも
その場合、
った緊落中にある民居の匡劃であるとした。この二つの論
考は、
里を以て自然緊落とする従来の遁設を否定した貼注

1
」味a
目されるが、同時に漢代郷里制の解穆として、受賞な設と
考える。これらを綜合するに、漢の褒落は大小の城郭に園
まれでおり、人民はこの城内の匡劃された里に従って居住
していた。また、
星には里魁、
里正、父老といった、
わ
ば皇の代表者が存在した。彼らは里を主宰し、
里民の指導
に嘗ることを主としたが、同時に毎年八月の案比の時、地
方官が戸口調査を行って名籍を作成したり、或は賦税を徴
収する場合に於ても、
里の内部事情に明るい彼らが立禽い、
協力したものであった。また、漢の名籍について、前記日
比野氏の次のような護言がある。即ち「名籍は算賦(人頭
税一般)徴収のもとであって、
田租徴収の資料ではなかっ
たことに注意しなければならない。従って名籍が人頭税徴
収の蓋帳である以上、何人もこれから脱することはできな
いはずである。すなわち、何人もいずれかの里に属すべき
であって、そのものが不動産を所有しているかいないかは
問題にならない」と。このように漢の名籍が地籍と蓋帳を
異にし、専ら人頭税徴収の蓋帳であったという事賓は、特
に重要なことである。漢の名籍は、戸籍のほかに戸版とか
549
名数、或は単に数といった言葉で呼ばれていた。たとえば、
漢書巻八一孔光俸に
元帝即位。徴〔孔〕覇。以師賜欝閥内侯。食邑八百戸
0
・
・加賜黄金二百斤。第一臣。徒名数子長安。側一町駅VW咽
とあるほか、また漢書巻一
OO上班固の叙俸に租宗班況の
ことを-記して、
成帝之初。:::〔況〕致仕就第。貨累千金。徒昌陵。昌陵
後罷。大臣名家。皆占数子長安。棚訪日
yh白一軒F制一噌
とあるのが、それである。そして、この二例でもわかるよ
うに、
しも庶民は勿論のこと、
かみは関内侯、大臣といっ
- 53ー
た高位高官のものまでも全て名籍に登載されていた。そし
て、この名籍に登載されている以上、彼らといえども人頭
税の課徴から逃れることの出来なかったことは、
日比野氏
の読く通りである。漢代の民が「編戸の民」或は
「編戸の
湾民」と呼ばれ、漢代、特に前漢の戸口統計が信用のおけ
るものであると言われるゆえんも、
おのずと明らかであろ
、「ノ。漢の郷里制と名籍とは、人頭税徴収の上に於て不可分の
保件であった。

550
前節に於て人頭税徴収の手績の概略を述べて来たが、
は、
この人頭税が質際に課徴される人民にどのような影響
を興えたのか、次に嘗時、人口の大多数を占める農民の生
活からその貼を考えてみたい。
先ず、算賦一算百二十銭という金額であるが、漢代の穀
一一桝の卒債を限りに七十銭とすると、
一算の徴収額は穀に
換算して約一
・七斜。嘗時丁男一人一月の食糧は約三凡で
あるから、これはまた丁男一人の約牢月強の食糧に相嘗す
る。この計算の上からのみ見るに、人頭税の徴収額は決し
て高くはないように思われる。しかし、ここにあらわれて
いる数字は、穀一一桝の債格を七十銭として計算したもので
ある。漢の穀債は非常に獲動が激しく、水早などによる凶
作の年には一餅数百、数千、更には省内銭といった騰阜県を示
凶
す一方、逆に盟作の年には数十鏡、宣帝即位の年などは一
餅五銭といった場合もあっゎ。凶作の時は、穀慣に比較し
て、算賦一算の金績は非常に安,いという印象をうけるが、
しかし、農民自身の食糧にさえも事欠き、時には餓死する
といった状態であれ尚、貴重な食糧を買って人頭税の支梯
をするということは、到底不可能である。では逆に、
盟作
で
などによって穀債が下落した時はどうか。いま回収りに一一斜
の債を十銭として考えてみよう。この場合、
一算の金額は
穀に換算して十二斜、即ち丁男
一人の四月分のA良糧に相嘗
する。嘗時豊作といっても、今日にくらべて農業技術の幼
稚な時代であれば、卒年作を多少上回る程度のものであっ
たであろう。このような時代に、
一人四月分の主食費に相
嘗する人頭税を納めることもさることながら、また人頭税
- 54-
が銭納制である以上、穀物で納入することも出来ず、穀物
を買って金にかえなければならない。しかも盟作であれば
買手もなく、それを無理にも買って金にかえようとすれば、
買手は嘗然、値切れるだけ値切り、その結果、賓際に農民
の受取る金は蛍時の下落した穀債を更に大きく下回ったで
あろう。これは容易に想像し得るところである。そうなれ
ば、四月分はおろか、現賓には五月分、六月分の主食費に
も相嘗する結果になったであろう。いくら豊作とはいえ、
これはやはり大きな負権であったに違いない。大盟作で一
餅五銭にまで穀債が下落したと俸えられる、先の宣帝即位

-創刊ゐ川、
N
Av
j
の年(前七四)
たとえば漢書巻七昭帝紀・
の前後のこと、
元鳳六年夏(前七五)の詔山に
夫穀賎傷農。今三輔太常穀減賎。其令以叔粟嘗今年賦。
師古田。鵬畑多而銭
少。是骨周傷也。
とあり、穀債の下落により農民の貨幣収入が少いため、嘗
年の賦ー
I人頭税も含む銭納税一般ーーーに限り特別に叔粟
闘
で以て賦銭に代納することを許可しているほか、また漢書
品位
λ宣帝紀・甘露二年正月(前五二)の詔に
鳳皇甘露降集。黄龍登輿。:::威受禎群。其赦天下。減
民算三十。側一昨ヨドト官
と言い、算賦一算につき三十鎮の減税が行われているのも、
恐らく以上のような事情に劃する一種の針策であったと思
われる。漢代、貨幣で納める税制には、算賦・口賦などの
人頭税以外に更賦或は賀算といったものがあり、これらを
帥山
総稽して賦欽という言葉で呼ばれていた。そして、この支
排に醸ずるために、貧しい者は日用生活の必需品である衣
服、履物、鍋釜類は勿論のこLH、文帝の時(前一七九l前
551
の晃錯の上言(漢書巻二十四上金貨志)に
ω
念政暴虐。賦数不時。朝令暮嘗具。有者学曹而貰。亡者
一五七)
取倍稿之息。於是有賀回宅。君子孫。以償責者失。
とあるように、彼らの最後の財産である、土地更には子供ま
でも買ったり、
入賞したりして金にかえなければならずー
極端な例では、これを逃れるために子供を殺すといったこ
とも行われてい向。これよりしても結局、凶作、豊作の加
何にかかわらず、人頭税も含めた漢代の銭納税は、農民に
仰
とって寅に大きな負携であったと考えなければならぬ。
土地は彼ら農民の唯一最後の財産であり、
いわば生命で
もある。しかし、晃錯の一言葉にもあるように、賦放に醸ず
-55ー
るためにこれを手放すということは、彼らの生活手段を放
棄したにも等しい。では、これら無一文になった農民は一
桂どうなるのか。ぞれは先ず、故郷を離れ食を求めて他郷
を放浪する流民のコースへとつながるのである。
しかし、農民が流亡するのは、何も賦数の負携のみが原
因ではなかった。前漢末の人、組宣は、農民が流離する原
因として水早などの天災による飢僅、苛酷な賦税の取立て、
貧吏の搾取、豪強大姓の兼併、各役の煩重、内凱或は兵媛、
そして盗賊の略奪などをあげている。これらはいずれも農
民の流亡に関係するものばかりで、
その質例は史書に多く

552
あらわれて来るが、
しかしこの中にも、租税賦倣の負擦が
その一因として含まれていることは
やはり見逃し難い。
それゆえ、盟鍛論巻七執務篇の賢良の言に
賦礼服省而農不失時。則百姓足。流入締其田塁。
といった謹言も出て来るのである。
四
農民の流亡は前漢以来しばしば史書に見えるが、特に後
漢になると一層願著になり、
その記事は枚撃にいとまない。
では更に、
かかる流民の状況を人口推移の面から考察して
みよう。
前漢の戸口統計で今日残っているのは卒帝元始二年のも
のだけであるが、後漢になると数回に亘る統計が残ってい
る。今それらを表にすると、下の遁りであ針。
卒帝以前の統計がないため、前漢の人口推移は不明であ
るが、しかし或る程度これを推測することは可能である。
即ち漢
輿。:::時大城名都。民人散亡。戸口可得而徴。裁什
二三。:::逮文景四五世間。流民既障問。戸口亦息。
桓質帝 1中順安和 章明 光卒 帝帝 帝永帝帝帝帝帝武帝 帝永本 建延元章永 元 王蕎初嘉康光 興 和 卒 中 始二元元元四 元 二 一 元 二 年年年年年年年年八二年
年年 紀
西
一一一一一一豆プ王て フZ可E ヨZ三9 IZ区Eヨ ニヨエ三 ζヨコ王 ノ/11 4EEご ヨ4三コ 二二 紀
ヨC王〉、 立耳 E耳 IZY IZ耳 ヨ三三王 位耳 三三 二二 ヨプ王L 口→ゴ、 プL、 プL、 ノ1、 、 三三、 区E、 一一、 、
Cフフコ可可 主フ主可 ヨZ一王Eー 三C→三コゴ フCプコ可L、 ヨフー王可ー 三ヨフ三王可、 ニ主ニ主、 ζι4コ二Z〉 豆プELE 王、 "7・・品開、F、、- 、 、 、 、 、
ヨプ/ヨ1て: ペ七ーZーご 三/三1 ヨ三ζEコ王t ぺノアス=L ブ一一一Lー 三プ4三ゴて Cー〉・ Cニ/コ1ニ ーブ/ヒし'( 数
- 56ー
(漢書巻一六高葱高后文功臣表)
孝昭。:::承孝武脊修品開敵師旗之後。海内虚耗。戸口減
牢。〔塞〕光知時務之要。軽怒薄賦。輿民休息。至始元元
鳳之問。勾奴和親。百姓充賓。
(同書巻七昭帝紀賛)
至孝宣。:::輿子間閤。:::属精爵治。:::稿中輿駕。
(同書巻八九循吏博序)
とあり、更に哀帝卒帝の時のことを述べて
百姓替富。雄不及文景。然天下戸口最盛笑。
(同書巻二
十四上食貨志)

とある。これより見るに、前漢時代の口数は武帝の時、
時的な減少はあっても、以後は漸次増加したものと考えて
よいだろう。また前漢末、卒帝の時の口数に劃し、光武帝
のそれは約H¥ω
に激減している。しかし、章帝和帝の頃に
なると大陸回復して来ていることからして、これは賓在人
口の減少というよりも、
る戸口調査の不徹底が、その主な原因であろう。ところで、
むしろ前漢末、避難民の増加によ
後漢の統計を見るに、和帝の時を境としてそれ以前は増加
一方それ以後は停滞乃至はやや減少の傾向を示してい
る。そして、後漢で最も多い和帝の時でさえ、前漢の口数
しに比較すると約一割の減少となっている。漢代の戸口調査
は、人頭税徴収の必要上、巌重に行われた答である。しか
るに、後漢書巻四和鶴帝紀・晴樹帝延卒元年七月(一
O六)
の訪問に
問者郡園或有水災。妨害秋稼。朝廷惟答。憂悔悼懐。而
郡園欲獲豊穣虚飾之島官。逮覆蔽災害。多張墾因。不端流
亡。競増戸口。
553
とあるように、後漢も中期以降になると、綱紀の弛緩とと
凶
もに地方官吏の虚構も加っていることからして、中期以後
の統計に見える口敏は、賓際よりも多かったことを認めな
ければならぬ。即ち、和帝以後の口数が統計の上で停滞乃
至はやや減少しているということは、現貨に帝園が把握し
得た人口はむしろ減少の一途を辿ったものと考えなければ
ならない。
そこで、
いままで見て来た爾漢の人口推移からして、凡
そ次のようなことが言えるであろう。それは、前漢の人口
は一時的な減少があって漸次増加の傾向にあったと考えら
れる以上、
たとえ前漢時代に流民が袈生しても、
彼らはま
- 57-
だ、かなり安定性があったということである。即ち、
たと
えば天災・飢鍾・兵第などのために、流民となって郷里を
離れた者の場合にしても、
それが落着けば再びもとの郷里
に踊って来る可能性のある者が、まだかなり多かったと思
われる。
しかし、それが後漢になると一時的ではなく、永
久的に郷里を放棄することに、大きな特徴があった。たと
えば、岡崎文夫氏によれば、前漢時代に中園南部
(漢水・
揚子江流域)と北部(黄河・堆水流域)との人口比率が
一割
五であったのに封し、後漢になるとこれが一針二になった
ということである。このように後漢時代、大量の人口が南

554
方に移動しつつあったことから見ても、後漢の流民が決し
て一時的に郷里を去ったものではないことが理解されるで
あろう。
では、後漢の流民が再び自己の郷里に蹄ることを望まず、
永久に郷星を放棄せざるを得なかった原因は何か。それに
は、いろいろと多くの原因が考えられるであろう。たとえ
ば、後漢時代願著になって来る北方異民族の侵入、内観な
どもその一つであった。しかし、今それを人頭税との関連
に於て考えるならば、人頭税の課徴がまた、
その大きな原
因の一つであったと言わねばならぬ。前漠以来、人頭税が
農民の大きな負携であったことは既に述べたが、
一般農民
は勿論のこと、
たとえば彼らが土地を失い、豪族大地主の
土地を耕す小作人になったとしても、彼らが自己の郷里に
残留している以上、人頭税は徴収された。何故なれば、漢
代の里の制度は、本人が不動産を所有しているかいないか
は、全く問題ではなかったからであ向。即ち、観りに農民
が土地を失って小作人になったとしても、彼らが皇の組織
で把揮されている限り、人頭税を逃れる理由は何もなかっ
たからである。前漢以来このように巌しく取立てられて来
た人頭税であったが、前漢ではまだ、減兎されることもし・
田租の減兎に比較
しばてし人ば頭あ税つのたそれとはこ
ろ非 が常 後に漢少にし、ωな。 る
といや少いどころか、後
漢も中期以降になると政治は腐敗し
地方官吏は自己の賓
績をあげんがために凶年でも盟年と偽稽し、更には不正に
聞
墾田
・戸口を増加して虚偽の報告をなし、その埋合わせと
して農民に定額以上の苛酷な課税を強制したのであった。
そのことは、
たとえば順帝から桓帝に至る問、外戚として
専横のかぎりを悲した梁翼に針し、彼を練めた朱穆の言葉
-.58ー
(後漢書巻七三本俸)
に
京師諸官。費用増多。詔書護調。或至十倍。各言官無見
財。皆嘗出民。携掠割剥。張令充足。公賦既重。私数文
深。牧守長吏。多非徳選。貧爽無厭。遇人如虜。或絶命
於筆楚之下。或自賊於迫切之求。又掠奪百姓。皆託之骨骨
府とあるほか、順帝に封する左雄の上疏の一節(同書巻九
本体)にも
現民如冠響。税之如材虎。
と、嘗時の官吏を評していることなどからも窺うことが一出

来る。かかる官吏の苛数議求は、そのまま農民の上に大き
な座力となってのしかかり、彼らの経済的負携、更には貧
困、
没落をますます増大せしめるばかりであった。しかじ、
これは何もひとり農民ばかりに加之られた摩迫ではなかっ
た。たと之ば二世紀前牢の人、
王符の潜夫論巻五賞過篇に
よれば、嘗時の外征による出費の塘加を述べた中に
放散銭穀。嘩泰府庫。乃復従民懐貸。彊奪財貨。千高之
家。制身無除。高民匿唱。因随以死亡者。皆吏所餓殺也。
と言い、政府の財貨強奪の前には、千寓の財産を有する富
裕な民といえども、忽ちにして破産するとい
った有様であ
ったことを俸えている。彼らにして既に、このような朕態
であれば、零細な農民の負携たるや、まさに想像に繰りあ
るものがある。まして、人頭税が、農民の最も不利とする
銭納税であれば、尚更のことである。彼ら農民じとって、
この歴迫を兎れるためには、奴隷(奴稗)となって豪族大
ω
地主に隷属するか、さもなければ自己の郷里を棄てて他郷
へと逃亡するか、この二つより以外に、
方法はなか
った。
そこで、この奴隷となるのを嫌って彼らが逃亡を始めるの
555
は勿,論のこと、また同じ奴隷になるにしても、借金などの
負擦をそのままに自己の故郷で賎しい身分に代るよりは、
むしろ見知らぬ他郷で生きることに、まだしも一抹の希望
を抱いたものに違いない。後漢時代の流民が、永久に郷里
を放棄して南下しでいった原因の一つは、ここにあったと
田山、っ。
」れら郷里を棄てた流民の行方は、
たとえば潜夫論巻
浮修篇に
今奉世舎島民桑。趨商買。牛馬車輿。填塞道路。務手潟巧。
充畳都邑。治本者少。浮A民者衆。
:::今察洛陽。浮末者
- 59-
什於農夫。虚偽瀞手者什於浮末。
:::天下百郡千勝。
市
邑寓致。類皆如此。
とあるように、都市に集って遊民となり、また中仁は盗賊
凶
となる者もあったが、大部分は豪族大地主の下に吸収され
ていった。
後漢書の中に奴隷、
小作人の記
このことは、
回
載が多く見られるほか、後漢末の人である仲長統が、
昌言
(後漢書巻七九本俸所引)
の中で
漢輿以来。相輿同篤編戸斉民。而以財力相君長者。世無
数駕。
:::豪人之室。漣棟数百。菅田浦野。奴蝉千輩。
徒附蔦計。船事官版。周於四方。

556
と言い、大土地所有と農民の奴隷・小作化が大規模に行わ
れるようになったことを述べてい
ることからも窺われる。
即ち、前漢以来護展しつつあった土地の兼併と農民の奴隷
j
小作化の傾向は、後漢未になると、既に普遍的な現象と
なって来ているのである。後漢中期以降の人口の減少は、
このような豪族大地主の下に吸収されていく農民ーーー園家
の権力の及ぶところを離れ、
豪族大地主の勢力の下に再組
織されていく奴隷、小作階級|
|の増加に起因するものと
言わねばならない。
かかる農民の流亡、設落は、帝闘の政治的、経済的基礎
を大きくゆさぶり、
ひいては帝園を解睦に導く危険を苧ん
だものであった。そこで中央でも、何とかして彼らを園家
権力の下に把握しておこうとする努力が、
いろいろと矯さ
れている。たとえば、災害に遭遇した民の田租を減兎した
り、糧食を賑給したり、また貧民
・流民などに田苑を懐輿
それである。
して農業生産に従事せしめたりしているのが、
しかし、このほかに、民或は流民に欝を賜うことが、頻繁
に行われてい
るoat一一一の例をあげてみると、即ち
建初四年四月。立皇子慶篇皇太子。賜霞。人二級
0
・
民無名数及流人欲自占者。人一級。(後漢書巻三章帝紀)
元初元年正月。改元元初。賜民団酎。人二級。:::民脱無
名数及流民欲占者。人一級。
(同書巻五安帝紀)
永建四年正月。帝加元服。::・賜男子霞。及流民欲占者。
(同書巻六順帝紀)
人一級。
陽嘉元年正月。立皇后梁氏。賜欝。人二級。:::民無名
数及流民欲占著者。人一級。
(同右)
本初元年六月。大赦天下。賜民健及粟白m。各有差。
同
書巻六質帝紀)
- 60ー
等、がある。これを見てもわかるように、民に霞を賜うのは
いずれも園家の慶事の場合に於てであった。しかし、それ
が名籍(戸籍)に登載されていない流民をも劃象としてい
る事賞を考える時、民に震を賜うのも
一種の流民針策であ
ったと思われる。というのは、居延漢簡などの例からも既
に明らかなように、漢代の名籍が
「名勝欝里L
といわれ、
有霞者は霞とともに行政単位として必ず自己の所属する皇
を記さねばならなかった。そこで、名籍から脱漏している
流民に霞を輿えるということは、彼らを或る
一定の地の名
籍に編入せしめようとしたのに、
ほかならなかったからで

ある。即ち、民或は流民に欝を賜うことは、郷里を棄てて
まさに逃亡せんとする農民、或は現に名籍の上から脱漏し
ている流民などを、強制的に名籍の上に留めることによっ
て彼らの流亡を防、ぎ、あくまでも編戸の民として園家権力
の下に把握しようとしたものであった。名籍に登載された
以上、彼らは人頭税の課徴を逃れることは出来ない。しか
し、それが彼らの負措であり、彼らが流亡する大きな原因
の一つであったことは、もはや繰返すまでもない。そのた
め、農民はまずまず他郷へと流亡して闘家権力から離脱す
ることを徐儀なくされ、逆に豪族大地主に劃する隷属閥係
をより強固にし、奴隷・貧農小作民などのいわゆる賎民階
より康範閤に構成されていくという、悪循環を生む
級は、
結果となった。
一方では園家権力の下に把握しようとする
努力も、他方では彼らを
一層窮地に追込み
ますます園家
権力から離脱せしめる結果となったかかる政策的矛盾は、
そのまま漢代人頭税のもつ矛盾でもあり、
ひいては後漢帝
園の矛盾、幾質でもあった。
かくして農民が流亡、波落すると、嘗ては編戸の民とし
557
て、彼らがその一員となって構成していた郷塁の制度が破
壊されたことは、言うまでもない。そして、こ
の郷里制が
破壊すると同時に、
皇を単位として名籍を編成し、それに
もとづいて徴収されていた人頭税の制度もまた嘗然のこと
ながら、崩壊せざるを得なかったのである。
五
前節では、漢代人頭税の崩壊の原因を、専ら郷里制の尉
壊の中に求めて来た。しかし、これほどまでに農民を苦し
めた人頭税が銭納税である以上、次にはどうしても嘗時の
- 61 -
貨幣経済の面から一言しなくてはならぬ。
漢の貨幣は初期に於ては撒英銭(高租)、
八銑銭
(呂后)、
四銑銭
(文帝)、三銑銭(武帝建元元年)などが用いられて
いた。しかし、武帝の元狩五年
(前
一一八)に五銭銭が鋳
造されるに及び、以後一時王葬の貨幣濫造があったほか、
前後漢を通じて、
五銑銭が標準貨幣として使用された。そ
して、この五銑銭を中心に漢代の貨幣経済が展開されるわ
けであるが、これはその後の政治、経済、社舎の上に多大
な影響を興え、
やがて貨幣膿止論も登場するようになって
来る。たとえば、
そのはしりとして、早くも前漢元帝の時

558
ω
(前四八|前三三)、貢掲の腰止論が登場するに至る。しか
し、彼の主張||これは
「交易待銭。布用不可尺寸分裂」
という反射論にあって結局中止されたーーーは、主として貨
幣経済の進展に伴って困音楽業する農民を
その経済的負
機から救済し、彼らをして本来の農業に専念せしめんとし
た、いわば一種の重農政策にもとづくものであった。これ
に劃して後漢の貨幣腰止論になると、貨幣の数量もしくは
貨幣債値の観恥から、主としてそれが論じられるようにな
って来る。即ち、後漢書巻七三朱陣俸によると、章帝の元
和年間(八四|八六)、穀慣が高く、閣の財政が不足した時
のこと、備蓄張林が上書して
穀所以貴。由銭賎故也。可壷封鎖。
一取布白巾矯租。以逼
天下之用。
ω
と主張したのに封し、朱陣は「布白巾矯租。則吏多姦盗」と
言って反劃し、途にこの議が中止されたことを述べている。
また同書巻八七劉陶俸には、桓帝の時(一四六l一六七)
人以貨騒銭薄。故致貧困。宜改鋳大銭。
という意見が出たのに針し
「蛍今之憂。不在於貨。在乎
民飢」という劉陶の反針にあって中止されたことが出て
い
る
ところで、今この後漢書の二つの記載を見るに、後漢時
代には一種の貨幣過剰とでも言うべき現象があったらしい。
この現象について、牧野巽氏は
『中園古代貨幣経済の衰頚
過程』
収、
(一橋大息一証禽撃部論文集「祉舎と文化の諸相」所
「これは貨幣の紹封量が増加した
一九五三)
の中で、
からではなく、恐らく貨幣の流通する範囲が非常に縮少し
たために生ずる相針的な過剰現象で、貨幣の組制到量は後漢
時代を遁じて寧ろ減少していった」という推測を下した。
- 62ー
これはまことに安嘗な見解で、後漢の史料にあらわれる貨
幣過剰の現象は、恐らくどこか特定の場所に、大量に貨幣
が蓄積された結果生じた現象であったと思う。では、この
特定の場所とは一躍どこかれそれは貴族、商人も含む豪族
大地主など、首時の一部特権階級の手中である。
漢代を通じ、彼ら豪族の土地と農民に劃する麗食は、護
展の一途を辿る祉禽現象であった。たとえば、早くも前漢
武帝の時、葦仲併が限回論、奴碑底止論を主張するように
なるのも、一哀を返せば嘗時かかる政策を議論せねばならぬ
程、いかに大規模な兼併が行われつつあったかを物語るも
t

のであろう。しかしこの場合、彼が問題として取上げた大
土地所有者は、主として武帝の臨鍛専頁制賓施以後、それ
ω
以前の商人に代って拍頭して来た農村地主であった。しか
るに、これが前漢末から後漢時代になると、
たとえば南陽
の豪族礎氏の如く、彼らは農村地主として本来の農業経営
に従事すると同時に、また一方では商業とか高利貸しを管
関
む商人へと繁貌して来るのである。前節で引用した仲長統
の昌言に描く豪人も、まさにこれと向性質のものである。
かくして、後漢時代になると、豪族大地主は二業を兼務す
るようになり、その結果、彼らは莫大な財産を築くに至つ
た。即ち、史記貨殖列停、漢書貨殖俸によると、前漢時代
の長者といわれる者の財産は、貨幣に換算して一たかだか一
ω
憶であった。ところが後漢になると、たとえば扶風の土孫
奮は一億七千絵高、梁葉の如きは、寅に一人で三十数億の
的
財産を所有していた。これは前漢時代にくらべて、ほぽ倍
から数十倍に及ぶものであり、そこに集中した貨幣の量は、
また前漢に匹敵、もしくはそれを凌駕する多額なものであ
ったと思われる。事賞、後漢の中期から末期になると、中
559
失では通貨の不足をきたし、その劃策として官吏の減俸、
ω
買官などによって銭を吸収したほか、また富裕な民から借
ω
金することもしばしば行われ、既に安帝の永初四年
(一一ω
その負債は数十億の
E額に達していたといわれる。
O)頃、
またそのほかに、霊帝の時(一六八l一八九)、銭五百高を
あかがねくさ
入れて司徒の位を買い、世間から
「銅臭いL
と言われて疎
ω
んぜられた葉州の名士l
髪室の従兄|雀烈。或は、梁翼か
ら銭五千蔦を要求され、それに劃して銭三千蔦を輿えたた留
めに糞の怒にふれ、途に蒐罪で獄死したという前記土孫奮。
甚だしきは、先代垣帝の私蔵なぎを歎き、
西国に高金堂を
- 63-
建て、大司農
(園庫)
の金銭の横流し或は買官などによっ
て貨幣の蓄積に専念した、霊帝自身など。これらの諸例か
らしても、
嘗時彼らが、
いかに大量な貨幣を所有していた
かが理解されるであろう。今日、後漢の貨幣鋳造の様子を
窺う史料は見嘗らない。しかし、前記牧野氏によると、後
漢末でも王葬の貨泉が流通していたこと、また董卓の悪銭
濫造ののち曹操が五銑銭を復活したのは、もともと貨幣の
鋳造が久しく結えていたため貨幣が少く、
ために穀債が下
落して困るという理由であったこと其の他からして、後漢
の貨鰐鋳造は盛んでなく、貨幣は増加しなかった||貨幣

560
の絶劉量は寧ろ減少していったーーであろうと推測してい
向。若し氏の推測が可能であるとするならば、貨幣の紹針
量が漸次減少を辿る後漢時代に於て、大量の貨幣が
一部特
機階級のうちに
一方的に集中していくということは、もは
や貨幣は、彼らの聞のみで通用する、
いわば彼らの完全な
私有物と化し、逆に農民などにとっては、無縁の存在とな
りつつあったと言わねばならぬ。後漢後期の人である緩室
が、政論(遁典倉一食貨所引)
の中で
上家累鈍億之ば。
斥地伴封君之土。行琶立。以鋭執政。
養籾客。以威斡首。専殺不事。:::放下戸時踊。無所時
足。乃父子低首。奴事富人。弟帥妻李。震之服役。故富
者席徐而日織。貧者協短而歳蹴。歴代篤虜。猶不贈於衣
流離溝
メ弘、
及。
死有暴骨之憂。
歳小不登。
生有終身之動。
盤。嫁妻貰子。其所以傷心腐蔽。失生人之紫者。蓋不可
勝陳。
と言い、短億の財産を所有する豪族大地主と、彼らに隷属
し、
・また隷属を除儀なくされていく農民との針象的な生活
を術開えているが、これほどまでに爾極端な二者の生活を生
じたのも、結局は、後漢の貨幣鰹済の賀状が、恐らく以上
のようなものであったことに原因するものであろう。
かかる現象||貨幣のアンバランスーーは嘗然、貨幣鰹
減伺を衰退せしめ、同時に銭納を建前とする人頭税は、
く
ら戸口調査だけを充分に行つでも、もはや徴収不可能にし
たことは言うまでもない。しかし、
それにも拘らず政府は
貨幣経済を強行し、貨幣収入源として人頭税の徴収を強行
畑幽
した。その結果は、豪族大地へのより一方的な貨幣の集中と、
それを背景とした彼らの横暴に拍車をかけ、農民の借金の
負鎗と窮乏、波落を一層激化するばかりであった。帝園の
- 64-
矛盾と挺質は、ここにもあらわれて来る。後漢帝園崩壊の
致命傷となった彼の黄巾の範は、このような帝閣の矛盾に
劃する農民の不満の一大爆震であったと言わねばならない。
後漢末の戦凱と董卓の悪銭濫迭とは、漢の貨幣経済を一
問
事に崩壊せしめることになるが、結局人頭税は、貨幣経済
の上からもまた、溺壊せざるを得なかったのである。
では、このように人頭税の徴収が帝園の溺援を招くとい
うことも顧みず、後漢帝国崩援の寸前まで執勘に徴収した、
また徴収しなければならなかった理由は、
一般何か。問題
は、帝闘の歴史的な性格に開漣して来る。

...... ,、
例の漢書刑法志、食貨志などによると、先王の世に賦と
税との匝別があり、賦はいわゆる軍賦であったことを述べ
ω
ている。そして、漢代でも筒、かなり明確にこの匪別が存
在し、漢代に賦と呼ばれた算賦、口賦、更賦の三種は、いず
れも大なり小なり軍事税、軍賦としての性格をもっていた
ω
ということは、既に宮崎市定氏の読くところである。しか
しながら、往々、賦の一字で以て算賦を意味している場合
回
がある。このことは、漢代、算賦が田租と並んだ園家の二
大財源の一つであり、その収入の莫大なことにも起因する
ものであろうが、むしろ算賦を以て刑法志、食貨志などに
見える古来の停統的な賦l軍賦の系統をひく典型として考
問
えられていたからにほかならない。
思うに、春秋末から職園にかけて開始される識製農具
牛耕法の使用は、農業生産力を高め、やがて農村社禽の分
解が促進されるようになる。即ち、従来の血縁的大集圏に
よって維持されていた農村生活は、もはや必要なくなり、
561
小家族による生活も可能ならしめる祉舎が作られるように
なった。そして、それと同時に、農村駐禽に於ける階級の
分化もあらわれ始めるが、しかし全鰻的には、彼らの政治
的世曾的勢力はまだ弱かった。そこで、新しい富の生産開
係による彼らの階級分化に先んじて、
かかる農村枇禽を再
編成し、それを基盤として強大な王権、帝王権を構成する
ことに成功したのが、邑制園家以来の貴族の有力者、即ち
秦によって代表される職園の諸園家であった。そして、そ
の園家は強大な王権乃至は帝王権によって秩序づけられる
とともに、園家の民、中でも大多致を占める農民層は全て
- 65ー
卒等な自由農民として王様、帝王権の下に把握されたので
ある。秦漢帝闘はまさに、このような園家の到達し得る最
関
後の段階であった。ところで、この秦漢帝国の強大な帝王
権の下に於て、園家の民を全て自由卒等な民として把握す
る一種の卒等主義が、最も強くうち出されたのは、税制に
於ける古来の軍賦としての人頭税にほかならなかった。そ
れは、秦では商験以来の賦であり、漢では賞に、算賦その
ものであった。
軍賦は本来兵役であり、兵役の義務は蔦民共有の義務で
ω
あった。従って、人頭税は全ての民に、また民の男女、貧

562
富に聞係なく、
一律卒等に課せられたものであった。そし
て、この税制施行のために郷里制||従来の自然爽落を再
編成し、劃一的な郡腺制を行う過程に於て成立して来た|
ーを活用し、こ
の組織にもとづいて人民を編戸の民として
把握するとともに、戸口調査と人頭税の徴収とを徹底せし
めたのであった。
漢の戸口調査は毎年八月に行われ、それによって人頭税
が徴収されたのであるが、少くとも帝園がこの戸口調査を
行い得るかぎり、漢の大きな園庫収入の一つである人頭税
の徴収は、
一腰確保されたと考えてよいであろう。しかし
ながら一方、現賓の祉舎では、このような帝園の性格を否
定する現象が、除々に形成されつつあった。それは帝園が
把握していた、或は把握していると考えていた自由農民の
流亡・波落、
そして豪族大地主の下に吸収されていく貧農
小作民乃至は奴隷などのいわゆる賎民階級の増大であった。
その主な原因には貨幣経済の惨透による貧富の差の激化な
どがあげられるが、同時に銭納の人頭税の負猪がそれに拍
車をかける結果になったことは、注意しなければならない。
そして、更に後漢時代、大量の貨幣が豪族大地主のうちに
一方的に集中するようになると、事態はますます深刻とな
り、もはや戸口調査だけを行つでも、現賓には人頭税の徴
収を不可能ならしめていった。漢帝園はその園家の性格の
上からも、また帝園を維持していく上に於ても、この税制
を強行していかねばならなかった。しかし、帝園が強行す
ればするほど||現貨には後漢中期以後徴収不可能となり、
それを補うために、多くの不法な農民に劃する座迫が加え
られるようになるがーーー一層農民は国家権力から離れて豪
族大地主の勢力の下に隷属せしめられていくという、皮肉
- 66-
な結果を生じたのである。帝圏内部に於て、園家権力の下
を去って豪族大地主に隷属し、彼らの下であらたな秩序を
構成していくかかる賎民階級の増加は、嘗ては自由農民と
して、彼らがその一員となって構成、組織していた郷里制
を破壊せしめるとともに、この郷里制を基礎として徴収さ
れて来た人頭税の制度も崩壊せしめることになったのであ
る。このことは、もとより帝園がそれを基盤として成立し
ていた政治的、祉舎的、経済的基礎そのものの愛質であり、
それは同時に帝園の解鰻を意味するものであった。
算賦(人頭税)は古代園家の歴史的産物であり、古代帝

園の崩壊と運命を共にすべく宿命づけられていたのである。
後世、内容的に賦と税との完全な混同が生じるのも、結局
に違いない。
は、かかる算賦の崩壊によってもたらされた結果であった
註ω算賦については、漢書巻一上高帝紀四年八月の僚の「初鋳算
賦」の如淳の注に
漢儀注。民年十五以上至五十六。出賦銭。人百二十篤
一算。信同
治庫兵車馬。
とあり、また街宏漢蓄儀巻下にも
令民男女年中ι五以上至主十六。出賦銭。人百二十第一算。以給
車馬。
とある。またロ賦については、漢書巻七昭帝紀元鳳四年正月の
脇陣の「母収四年五年口賦L
の如淳の注に
漢儀注。民年七歳至十四。出口賦銭。人二十コ一。二
十銭以食天
子。其三銭者。武帝加口銭。以補事騎馬。
とある。
出問、算賦、口賦についての研究警には、次のようなものがある。
加藤繁「漢代に於ける鴎家財政と帝室財政との匪別並に帝室
財政一斑」同「支那経済史考讃」上所収
同
「
算
賦
に
就
い
て
の
小
研
究
」
同
右
宮崎市定「古代中園賦税制度」同「アジア史研究」一所収
吉田虎雄「漢の箔役と人頭税」同「爾漢租殺の研究」所収
563
馬非百「秦漢経済史資料(七)租税制度」食貨三の九
卒中苓次「居延漢簡と漢代の財産税」立命館大暴人文科事研究
所紀要一
同「漢代の馬口銭と口銭に就いて」東方皐報、京都二七
倒
注
ωを参照。
ω漢書巻一九百官公卿表上。郷有三老有秩車問失激徴。:::育夫
職聴訟収賦税。
績漢書百官志。本注目。有秩郡所署。:::其郷小者。師肺置車間夫
一人。皆主知民善悪。盛岡役先後。知民貧富。潟賦多少。:::又
有郷佐。属郷主民。収賦殺。
ω績漢書砲儀志。仲秋之月。豚道皆案戸比民。
伺後漢書巻六九江草停の「毎至歳時。耐鵬首案比」の李賢の注に
案験以比之。猶今貌閑也。
とある。
- 67ー
制加藤繁「算賦に就いての小研究」
開卒中苓次「居延漢簡と漢代,の
財産税」
川
W
周雄官伯の「掌王宮之庶子凡在版者」の郷注に
版名籍也。以版第之。今時郷戸籍。世謂之戸版。
とある。これと同文は大菅の注にも見える。
制史記巻二一九貨殖列俸。夫千乗之王。高家之侯。百室之君。
向猶患貧。而況匹夫編戸之民乎。
後漢書巻七九仲長統惇。漠輿以来。相輿同第編戸湾民。而以財
力相君長者。世~無数鷲。
州側宇都宮清士口「績漢志百官受奉例考」、「同再論」(向「漢代批曾

564
経済史研究」所収)によると、淡代の米一餅は約七十一銭という
推定である。
叫
醐m織論巻六散不足柄刷。
川判
決山川谷二
四上食貨志。元帝即位。
天下大水。閥東部十
一尤甚。
二年。湾地飢。穀石コ一百除。民多餓死。瑛邪那人相食。
後mHH巻七三朱廊問問。〔章-MW〕建初中。南陽大飢。米石千除。
同市川は径八一腕胤昔前問。〔安帝永初四年〕連年不担当
穀石柑削除。
問書倉一
O六第五訪跡。〔順帝時〕第五訪:・
・溢張披太守。放機。
粟石数千。
とあるのが、その例である。
帥たとえば、
出
3径二四上食貨志。宣帝即位。用吏多選賢良。百姓安土。歳
倣盟副情。穀歪石五銭。幾人少利。
後波書径二明。清紀
・永卒十二年。歳比笠稔。
百姓股官。来餅三
十。
帥
什広岡を参照。
同
昭怖の時の世相、及び決民の生活を述べたものに、次のよう
なものがある。
模台二四上食貨志。至昭帝時。流民梢還。回野盆闘。頗有蓄積。
同川谷八九循変体序。孝昭幼川内。密光乗政。承高官服伊師放之後。
指川内雌耗。光因循守職。無所改作。至於始元元鳳之問。旬奴郷
化。百姓金寓。
MW
宮崎市定「古代中園賦税制度」を参照。向、更賦については
演口霊協「践更と過更|如淳設の批判」(東洋皐報一九の一一)
を参照。
間
後
波
書巻四和帝紀・永元五年二月認。:・:住者郡図上。貧民
以衣絞盆所岬間賞。而豪右得其鋭利。向、注川仰を参照。
同開
百納本には「朝令而悲改品市兵」とあるが、
いま加藤肺訴評註
「淡
者食貨志」
(岩波書席)に従って改めた。
MW
未成丁の人頭税である日賦
(口銭)は、元来七歳より十四歳
まで
の者を料開象としたも
のであった。しかし、
一時武帝より元
帝に至る問、三歳以上の者にも課せられたことがあ
った。元帝
に糾問する貢再の上書(波書径七二本俸)に、そ
のことを述べて
起武帝征伐四夷。重賦於民。民産子三歳。則出口銭。故民重悶。
至於生子机殺。甚可悲筋。
と言ってい
る。
邸
側
算賦
一算百二十銭という定額が何を根擦に定められたものか、一
勿論わからない。しかし、ここで想像を逗しくするならば、こ
れは古来の
田租の基準であった十一之税にもとづいて、定めら
れたものではなかろうか。即ち、政代、田租の税率は十五分の
一或は三十分の一と減税されたのであるが、こ
の十分の
一と漢
代の回租との差額が人頭税であり、換言すれば、淡代の田租と
人頭税とを合計して、古来の十一之税に則ったものではなかろ
うかと思う。これについては更に考察を必要とし、今後の研究
にまたねばならないが、若し限りに、このような推測が今後質
経されるとするならば、十
一之税は天下の中正と一吉田われる如く、
この中に人頭税が含まれたとしても、決して負搬にはならなか
ったであろう。しかし、それが銭納であり、穀物を貰って金に

換えねばならなかったという駄にこそ問題があったと思われる
が、これらのことに就いては稿を改めて詳述する考えである。
帥漢書巻七二飽宣傍。倫、農民の流亡については馬非百「秦漢
経済史資料宝乙幾業」(食貨三の一)を参照。
凶
漢書巻二八下地理志。綴漢書郡園士山注。
MW
後漢紀巻二
O質帝紀に朱穆が梁葉を諌めた言葉があり、その
一節にも
京師之費。十倍於前。河内一郡。嘗調機素締穀。縫八蔦徐匹。
今乃十五寓匹。官無見銭。皆出於民。民多流亡。皆虚張戸口。
戸門山既少。而無響者多。
とある。
帥間肌崎文夫「江域被化小記」支那皐五の四。
このほか、第聡「爾漢郡園面積之佑計及口敏増減之推測」(中
央研究院歴史語言研究所集刊五)には、後漢に於ける地域別の
人口の増減を、百分率であらわした表をあげている。
鈎日比野前掲論文、及び本稿第二節を参照。
抽脚漢代、正史(本紀)に見える賦・設の減苑回数を表にすると、
凡そ次の遁りである。
後 前漢 漢
田租
租税 16 34
国税
租賦 14 2
ロ算算 6 6 賦
ロ賦3 6
ロ銭
更賦 1 I 11
馬口銭 1
毒事 藁 14
田租 30 36
人頭税 23 14
565
租賦は租と賦である。いまこの表から、田租と人頭税に分けて
各々合計すると、下段の如くなる。街ここで一雷同しておくが、
後漢の史料に見える口賦が、果して前漢と同様に未成丁の人頭
税を意味したものかどうか、貨のところわからない。しかし、
後漢にも未成丁の人頭税があったことは確貨で、そのことは、。
たとえば後漢の人、玉充の論衡巻一二謝短篇にも
十五賦。七歳頭銭二
十三。
とあり、孫訟譲(札乏巻九)は漠蓄儀を引用して
算民年七歳以至十四歳。出口銭。人二十三。二十銭以食天子。
三銭者。武帝加
口銭。以補車騎馬。叉令民男女年十五以上至五
十六。出賦銭。百二十震一算。以給車馬。
即此云十五賦七歳頭
銭二
十三也。
と設明していることからもわかる。また後漢書巻一下光武帝紀
の建武二十二年九月の篠に「戊辰。地震裂。制詔日。:::其口
賦遁税。而庭宅尤破援者。勿収責」とあり、李賢はこれに注し、
漢儀注目。人年十五至五十六。
出賦銭。人百二十篤一算。又七
歳至十四歳。出口銭。人二
十。以供天子0
・・
と一記しているが、これを見ると、李賢は口賦を、算賦も含めた
庚毅の人頭税の意味に解四押している。思うに後漢の口賦は、特
定名詞としての未成丁の人頭税とするよりも、算賦も含めた普
通名詞としての人頭税と考えた方がよさそうである。
同制
日本文訂頁に引用した後漢書和蕩帝紀及び注闘を参照。
MW
奴縛に糾問しては、算賦は課徴されなかった。漢書巻二恵帝紀、
六年十月の「(令)女子年十五以上至三十不嫁五算」の態初の注
に、漠律。人出一算。算百二十銭。唯買人輿奴抑倍算。
- 69ー

566
とあるように、商人と奴仰には一人に射して二人分の算賦が課
せられたが、奴仰の場合はその所有者が負檎した。加藤繁「算
賦に就いての小研究」を参照。
M同大淵忍爾「中園における民族的宗教の成立制」(歴史事研究
一八ニ
の注側によると、紫州、強州等の、後に賀巾の賊の猛
威をふるった地方に流民が多かったことを指摘している。向、
馬非百「秦漢経済史資料(五)人口及土地」(食貨三の一二)を参
問山。
側たとえば、次のようなものがある。
後間関蓄倉六二焚宏停。〔宏〕父重。・:・世善農稼。好貨殖0
・:・
其管理産業。物無所来。課役童殺。各得其宜。故能土下数力。
財利歳倍。至乃関康国土三百除頃。:::貸至
E高。
同書巻七二曜阿南安王康停。〔章帝〕建初八年。・:康途多殖財貨。
大修宮室。奴御至千四百人。厩馬千二百匹。私回八百頃。
同書巻五四馬援俸附防俸。防兄弟貴盛。奴鱒各千人己上。資産
E億。皆貿京師膏腕美因。
同盤巻一一一一上折像体。〔折〕園有貨財二億。家償八百人
同蓄倉六四梁統停附業停。葉乃・・・取良人悉盛岡奴紳。至数千人。
名目白賢人。
倒西村元佑「漢代の働農政策|財政機構の改傘に関連して|」
(史林四二の一一一)を参照。
倒漢書巻七二本体。古者不以金銭信用幣。専意於嫌。故一夫不耕。
必有受其飢者。:・・自五妹銭起己来。七十除年。民坐盗鋳銭。
被刑者衆。宮人積銭満室。猶亡厭足。民心機動。商買求利。東
(33) 西南北。各周智巧。好衣美食。歳有十二之利。:::貧民雄賜之
因。猶間間賞以賀。窮則起第盗賊。何者。末利深而惑於銭也。是
以姦邪不可禁。其原皆起於銭也。疾其末者。紹其本。宜罷採珠
玉金銀時間銭之官。亡復以銭幣。市井勿得販問H
。除租鉱之律。租
税蔽賜。皆以布吊及穀。使百姓萱蹄於曲演。
晋書巻二六食貨志には
今非但穀貴也。百物皆貴。此銭賎故爾。宜令天下悉以布吊篤租。
市買皆用之。封銭勿出。如此則銭少。物皆賎失。
ル」怠叩
40
。
帥宇都宮消吉「史記貨殖列停研究」
所収)を参照。
倒同「償約研究」(同「漢代社禽経済史研究」所収)、及び注帥を
参照。また注MWに引く奨宏俸を参照。
側宮崎市定「讃史街記二、漢書の貨殖家番付」(同「アジア史
研究」一所収)の一覧表を参照。
制後漢書巻六四梁統俸附葉停。向、このほかに康漢の折園には
二億、積陽侯馬防の兄弟には互億の貸震があったといわれる。
注側を参照。
側二、三の例をあげると、次のようなものがある。
後漢書巻五安帝紀・永初三年四月。三公以園用不足。奏令吏人
入銭穀。得策関内侯・虎賞・羽林郎・五大夫・官府吏・緑騎・
替士。各有差。
.
問書巻六順帝紀・漢安二年十月。滅百官奉Oi---又貸王侯圏租
一歳。
(同「漢代社曾経済史研究」
- 70ー

567
同書巻七桓帝紀・延蕪四年七月。京師写。減公卿以下奉。貸王
侯牢租。占頁閥内侯・虎賞・羽林・綾融制・営士・五大夫。銭各
有差。
,倒後漢書巻六順帝紀・永和六年七月。詔俵民有賞者。戸銭一千。
帥後漢書巻八一瞬参俸。永初四年Oi---参奏記於郵勝目。比年
・発泡。特図閥右。供筏賦役。唖帥損日滋。官負入賞。激十億薦。
今復募褒百姓。調取穀鳥。街賀什物。以藤吏求。
ω後漢書巻八二律姻俸附寒停。
脚注帥に同じ。
帥後漢書巻八霊帝紀。問書巻一
O八呂強停、張譲俸。向、西国
に多額の銭が蓄積されていたことを示す一例に、
後漢書一
O八曹騰俸。〔曹〕樹。霊帝時。貨賂中官。及輪西国銭
一億薦。故位至大尉。
との記載がある。
制因に、武帝の時に五鉢銭が鍛造されてより前漢末卒帝の元始
年間に至る問、貨幣の年間鋳造額は、卒均して約二億であった
(漢書巻二四下食貨志)。いま綴りにこの数字を後漢時代にあて
はめると、先の安帝の時の歎十億という負債は数年間もしくは
十敏年間分の銭銭額に相賞するものであり、また、梁葉が支梯
可能と見込んで士孫奮に要求した五千高は、年間鋳銭額の四分
の一に相蛍する金額となる。
帥臨世信威「中園貨幣史」第二章、第一節によると、前漢では、
帝王の賞賜とか服罪には黄金、銅銭が用いられていたのに射し、
後漢になると布白巾、線白mが代って用いられるようになったこと
などを指摘し、後漢時代の黄金不足の原因として、刑判外貿易の
盛行による黄金の流出、玉奔の黄金園有政策による一部特権階
級への集中、工裏方面に於ける需用の増加などをあげている。
筒、このほかに後漢時代の貨幣減少の一因として、随葬品とし
て墓中に埋められた貨幣の盆も、些少ではあるがやはり無視出
来ないと思う。漢代、貨幣が隠葬口聞として盛んに用いられたこ
とは、玉仲殊「墓葬略説」(考古遜訊、一九五五年創刊披)も
指摘しているが、事賞、最近の中閣の褒掘を見ても、漢墓から
多数の貨幣(五鉢銭、王宜伸銭など)が我見されている。判明し
た一墓中の枚敏は凡そ歎枚から敏百枚前後であるが、中には、
たとえば安徽省合肥市近郊の漢末と推定される碍墓の如く、千
枚に近い五妹銭が渡見された例もある(「安徽合肥東郊古碍墓
清理簡報」同一九五七の一)。
帥脚容媛「故漢毅城長蕩陰令張遜表須集標」(燕京準報三一)に
よると、霊帝中卒三年(一八六)にも向、戸口調査が行われ、
算賦が課徴されている。
制牧野、多信威前掲論文を参照。
糊漢書巻二三刑法志。畿方千里。有税有賦。税以足食。賦以足
兵。
-71ー
同書巻二四上食貨志。有税有賦。税謂公周什一及工商衡虞之入
也。賦共車馬甲兵土徒之役。充貧府庫。賜予之用。税給郊社宗
廟百紳之記。天子奉差。百官緑食。庶事之費。
働問「古代中園賦税制度」
制加藤肺訴「算賦に就いての小研究」を参照。

568
向、一例をあげると
波書径六四下賀摘之停0
4
ヰ女皇帝。
・:・民賦四十。
同書巻九六下西域市博・
渠惣閣僚。征和中
0
・::前有司奏。欲盆
民賦三十助溢用。
とある賦がそれである。また周礎太宰の九賦の鄭注にも
賦日本出泉也。今之算泉。或謂之賦。此其沓名輿。
と言っている。
制いま絞りに漢代の人口を五千寓人とし、十五歳以上五十六歳
以下の者がその五分の三を占めるとすれば、彼らから納める百
二十銭の算賦の総計、即ち大司臨時(園庫)に収まる算賦の総計
は銭三十六億となる。太卒御賀谷六二七に引用された恒読の新
論によると、前漢時代、大司農の歳入は銭四十除億ということ
であるから、算賦の総計はまた園家財政の大部分を占めたこと
になる。粗雑な計算ではあるが、これで大般の見蛍はつくであ
ろう。
脚
注
側
を
参
照。
倒宇都宮消士ロ「古代帝園史概論」(悶「漢代社合経済史研究」所
収)。
制賦の沿革については注側、及び松本光雄「中園古代社禽にお
ける分邑と宗と賦について」(山梨大皐事護翠部研究報告四)
を参照。
昭和三十四年度京大東洋史卒業論文題目
修士論文
ジ
ャ
フ
パ
ズ
に
つ
い
て
の
一
考
察
岡
崎
||十世紀イスラム帝園の金融業者の研究||
明代江南に於ける官回の性格
事土論文
高句麗諸城の起源と護達
明代の軍戸制について
唐宋の出皮革と使職
||特に三司使の成立について||
北宋時代に於ける宋と西涼府及び青麿族との開係
中
山
俺答汗とその時代
||明代蒙古祉舎の一考察||
森谷
上
村
硝
波
若
松
正孝
-72ー
正
夫仲男治護費寛

which they had previously taken from the peasants, who were the taxpa-
yers, by the system of the cadastral. tax in money (misa}J,a). But the
middle class, consisting of merchants, proprietors (tunna)), and others who
wielded economic power, gradually came to occupy an important position
in the society and to have a severe antagonism against the bureaucratic
State which was working to complete its internal expansion. The an-
tagonism, nevertheless, found' a compromise in the one-step retreat on
the part of the State. This retreat meant in fact the farming out of .tax
man包gements(4aman) and the fosterage of the rank of purveyors through
the business of public grain of the Sawad. lt was indeed the presence
of the complicated mechanism of the fiscal administration and the super'
vision by a centralized authority that permitted this excessive concession
to.those who, though favoured by financial capacity, were lacking in profes-
sional knowledge relative to the public fiscal economy. On the other hand,
since this compromise between the St~te and the middle class imposed a
consequent economic oppression upon the lower classes, the (Abbasid State
was doomed to be alienated from them, and this must be regarded as one
of the fundamental causes. of the internal disintegration of the Sta主e.
On the Decay of the Poll Ta玄 inthe Han漢 Dynasty
Hidemasa Nagata
lt is well known that the tax system of the Han dynasty had a poll
tax or capitation called suan-fu算賦 Thistax derived from the ch伽 -fu寧賦, a tax which was paid in lieu of military service. All those, includ-
ing women, who were recognized to be fifteen years old by the census
periodically taken in every August through the rural organization system
(hsiang-li郷里), were required to pay 120 ch'ien銭 ayear for suan-fu
until the time they reached the age of fifty-six. But this capitation system
disappeared with the fall of' the Han dynasty, and a new system, levying
a tax on each house, appeared in the Three Kingdoms period.
The author inquires why the suan-fu tax vanished, and finds an
answer in the abandonment of the rural organization system and the
- 2ー

decay of the money economy. The former became impracticable be-
cause of the appearance of wanderers and the increase of slaves and
tenant farmers among the lower orders. The decay of the latter was
brought about by the decrease of the amount of currency and the tenden-
cy of currency to become concentrated in the hands of the privileged
c1asses. The author concludes that the suan-fu vanished because of these
conditions.
On the Appearance of Villages in China
一一一AnAspect of the Ruin of the Ancient Empire--
Ichisada Miyazaki
China had its period of city-states in antiquity, and something of this
system remained in the Han漢 dynasty.Therefore, in the Han the hsien
瞬,hsiang郷 andt'ing亭 wereall cities, each with a wall around it, and
held some arrondissement (li畏)in it. The peasants living in the cities
tended the farms nearby outside the wall every day, and the lands farther
away were left uncultivated. In the Han dynasty, there were few vi1lages
to be. found like those of later times.
When the centralization policy adopted by the government brought
about the ruin of the hsiang and t'ing, the peasants moved to the hsien to
seek employment, and therefore more and more‘fields were left uncultiva-
ted. These deserted areas were then occupied by the nomad-invaders from
the north or west, who established vi1lages there. On the other hand the
Chinese government alloted the deserted areas to its soldiers, after aban-
doning attempts to reconstruct the hsiang and t'ing. These al10ted fields,
cal1ed t'un-t'ien屯田, were established by Ts'ao Ts'ao曹操 ofthe Wei魂
dynasty in the north. The t'un-t'ien needed the establishment of vi11ages
as well. Sometime later, in the Yangtze River basin in the south, there
tlourished the manors of the powerful c1ans, who gave refuge to those
who tled from north China, and vi11ages consequently appeared there also.
The ρaoωu保伍 system,though original1y designed for the military, was
later used by the government to gain control of the dwel1ers of the new
vil1ages.
-3-