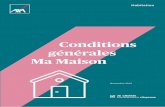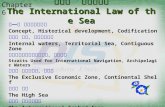The Founding of the Republic of Singapore The...
Transcript of The Founding of the Republic of Singapore The...
Journal of Asian and African Studies, No.95, 2018論 文
シンガポール共和国の建国について*
人民行動党政府とイギリス帝国 1963–1966
鈴 木 陽 一
The Founding of the Republic of SingaporeThe People’s Action Party Government and the British Empire, 1963–1966
SUZUKI, Yoichi
The objective of this study is to re-examine the reasons Singapore pursued its independence from Malaysia and followed its own path. On September 16, 1963, Malaysia was formed by the independent Federation of Malaya, along with Sarawak and North Borneo, which were ruled by the British. Singapore, which was a British protectorate, also voluntarily joined this group. However, the State of Singapore had an ethnic Chinese majority and was not able to come to terms with the Malay-led federal government for various reasons; this caused serious interethnic riots between Malay and non-Malay groups.
This study concludes with the following findings: (1) The Singapore government arrived at the decision to form an independent state. The main reason that the People’s Action Party was forced to comply with this was because the British Empire, the rear-guard of the party, refrained from giving support to the party in the federal politics during the following critical phases. In the early 1960s, the People’s Action Party tried and failed in creating a multi-ethnic Malaysian federation in cooperation with the British Empire with the objective of participating in the federal government. Therefore, as the relationship between the federal government and the Singapore state government worsened, both sides tried to find a compromise and the State of Singapore attempted to reconcile by loosening its relationship with the federal government. The British government, nevertheless, strongly opposed this policy of compromise which appeared to imply the division and defeat of Malaysia, since, at that time, Indonesia had implemented a ‘confrontation policy’ in an attempt to destroy Malaysia. The People’s Action Party, caught in a dilemma, went on the offensive against the federal government to liberate itself from the oppressive rule and achieved it through the formation of the Republic of Singapore.
(2) Although the Republic remained open to reunification with Malaysia for some time, this never came to fruition. After Singapore gained its independence,
Keywords: Singapore, Malaysia, British Empire, Decolonisation, Lee Kuan Yewキーワード : シンガポール,マレーシア,イギリス帝国,脱植民地化,リー・クアンユウ* 本稿の執筆にあたっては,東京外国語大学の左右田直規准教授,広島市立大学の板谷大世准教授から貴重なコメントを頂いた。また,2名の査読者からは的確なご助言を頂いた。記して感謝いたします。
66 アジア・アフリカ言語文化研究 95
はじめに
冷戦後に繁栄を極めるようになったシンガポールであるが,その背景には苦々しいとも言い得る建国をめぐる歴史がある。シンガポール共和国は予期せざる国 unexpected nationとも評され,1965年のマレーシアからの分離独立とその後の歩みは人々の想定を大きく覆す事件であったのである。戦後,シンガポールはイギリスの直轄植民地として再出発を果たしたが,小さな島が単独で独立を果たすというシナリオは誰も予期するところではなかった。確かに,独立には,当時,世界各地でナショナリズムの機運が高まっていたという背景もあった。ただ,マレー半島もシンガポールもその構成比率こそ違うもののともにマレー人,華人などからなる複合社会を形成し,両地域は歴史的・社会的な一体性を醸成していた。それゆえ,シンガポールが独立するとすれば半島との再合同を通しての独立となろうことがほとんど自明の道理と当時は考えられていた。実際,1963年,すでに独立を果たしていたマラヤ連邦がイギリス支配下にあったサラワク,北ボルネオと合同して―これに伴い北ボルネオはサバと改称―マレーシアを結成するにあたり,同じくイギリス保護下にあったシンガポールもこれに加わることで最初の独立を果たすことに
なった。確かに,マレーシア成立後,華人が多数派を占めるシンガポール州はマレー系が主導する連邦政府と折り合いがあわず,これと対立を繰り返した。同州は 2年足らずでマレーシアから分離独立することになった。しかし,この分離はほとんどのシンガポール人にとって極めて不本意なものであった。分離の直後,リー・クアンユウ Lee Kuan Yew首相が記者会見を開き,その経緯を涙ながらに語ったのは有名な話である。その後,リーたち率いる人民行動党 PAP:
People’s Action Party政府は,同国が置かれた苦境を克服して生き残るべく,強力なリーダーシップをもって人々を導くことになった。同国は半島という後背地を失ったが,外国資本を率先して迎え入れて世界に市場を求め,徐々に産業を高度化させていく大胆な経済政策を進めた。また,マレーシア参加の経験から特定エスニック集団が支配的になることの危険性を学んだとして,公の場では,華語でもマレー語でもなく,共通言語とされた英語の使用が推奨された。こうして,英語を共通語とするシンガポール人のナショナル・アイデンティティが形成された。現在の繁栄はこれらの政策の帰結である。予期せざる分離独立が予期せざる繁栄をもたらしたようにも見えるのである。本稿の目的は,なぜシンガポールがマレー
the Malaysian federal government established Muslim-oriented governments in Borneo, which ended any hopes for reunification. When Singapore was part of Malaysia, non-Muslims led the governments in the two Borneo states and were potential partners of the People’s Action Party government in Singapore. After the federal government intervened, these non-Muslims met with their downfall.
はじめに第 1章 マレーシア創設のエスノポリティクス第 2章 連邦・シンガポール州関係の展開 1
早々の対立から暴動発生へ第 3章 連邦・シンガポール州関係の展開 2
連邦関係希薄化の試みとその挫折第 4章 分離独立の後おわりに参考資料
67鈴木陽一:シンガポール共和国の建国について
シアから分離独立を果たし,自らの道を進むことになったのか,共和国建国の理由を再検証することにある。こうした問いを探求することは,同国が半島とは異なるナショナル・アイデンティティを築き上げ,抜きん出た繁栄を謳歌することになった背景を理解することにも繋がろう。
共有されて来た言説とその難点シンガポール独立の経緯については,これまで,うえにもその片鱗を記したとおり,ある支配的な言説がマレーシア・シンガポール両国の人々に共有されてきた。「分離独立は,マレー系住民と非マレー系住民―主に華人系住民―のあいだのエスニック集団間の対立感情が高まるなか,連邦首相トゥンク・アブドゥル・ラーマン Tunku Abdul Rahmanが流血の惨事を避けるために行った苦渋の決断であった」というのがその言説である1)。人々が望んだマレーシアは成立したものの,先住人であるマレー系住民が主導する連邦政府と華人が多数派を形成するシンガポールとの折り合いは悪く,エスニック集団間の対立感情がすぐに頭をもたげ出した。1964年,半島で行われた連邦議会下院議員選挙以降,連邦政府与党・統一マレー国民組織UMNO: United Malays National Organization内のマレー急進派がシンガポール州政府与党・PAPの対マレー人政策への批判を強め,これが契機となって,シンガポールでは二度に渡って大きなエスニック
暴動が起きた2)。さらに,その翌年,PAPが半島などを本拠とするほかの野党と強力な野党連合を形成して連邦政府への全面対決姿勢をとると,マレーシア政治は混乱の極みに達した。連邦政府にとってはリー・クアンユウを逮捕して与党の政権基盤を固めようとすることも選択肢であり,そうした声も上がっていた。が,そうなればより大きなエスニック衝突が起こることも予想された。それゆえ,流血の事態を避けるため,ひどい苦痛を伴うものであるけれども,そのことは分かりつつ, トゥンクは分離の決断を下したのであった。彼がこの決断を行ったのは,対立が絶頂を迎えるなか,帯状疱疹を患って 1月以上入院したそのベッドのなかでのことであった。1970 年代に出版された回想録において,彼はそのときの様子を次のように記している。
(引用者注:病気の)苦しみがひどくなればなるほど,私は彼(同:リー・クアンユウ)が憎らしくなり,自ら巻き起こした問題とは言え,シンガポールが可哀そうに思えてきました。心は乱れましたが,たどり着く結論は一つでした。それはシンガポールを残りのマレーシアから切り離してしまうということでした。
その後,シンガポール切り離しの準備作業が不測の事態を避けるため秘密裏に進められた。最終局面において,連邦を緩やかにするなどほかの方法はないか,リーはトゥンクに
1) ほかに平和への道がないゆえ,トゥンクが自らの決断でシンガポール分離を決断したことは分離当日の彼の会見でもリーの会見でも強調された。The Straits Times, 10 August 1965. トゥンクが病床において苦渋の決断を行った詳しい経緯については,その後,当時のストレイツ・タイムズ記者によって広く伝えられた。The Straits Times, 15 August 1965. シンガポールがマレーシアから追放されたことについてはリー・クアンユウ死去時のリー・シェンロン Lee Hsien Loong首相の弔辞でも強調されている。The Straits Times, 30 March 2015. なお,シンガポールの歴史教科書では,分離の原因を①経済的理由(共同市場問題,財政負担問題)②政治的理由(異なった人種の扱いについての不合意,国をどう統治するかについての見解の相違,二度の選挙における PAPと連盟党の争い,暴動,「マレーシア人のマレーシア」運動)などが高じて分離に至ったとしている(Ministry of Education 2007 : 195)。
2) 政党名の日本語訳はいろいろありうるが,混乱を避けるため,本稿では原則として鷲田の表記(鷲田 2008)に統一することにした。
68 アジア・アフリカ言語文化研究 95
迫ったものの,トゥンクはこれを拒絶した。このように,分離はトゥンクの英断であったが,人々,とくに連邦から放り出されたシンガポールの人々にとって極めて不本意なものであった3)。まことに印象的な話である。共存を求めて努力したにもかかわらず,ままならず,流血の惨事直前にまで追い詰められた。忸怩たる思いのなか分離の決断が下され,追放された人々は生き残りを賭けた国づくりを進めることになった。ただ,冷静になって振り返ると,こうした言説には次のようないくつかの重大な難点があることに気づかされることになる。まず,第一に,分離の主要な原因をエスニック集団―とくにマレー人と華人―のあいだの対立に求めるのは全くの誤りではないにしろ,そればかりを強調した言説は,現実の政治過程から乖離した議論に陥りがちになる,という難点を持つ。確かに,連邦政府与党であるUMNOが PAPの対マレー人政策を厳しく批判したことは二度に渡るシンガポール暴動の背景となったし,また,高まったマレー人と華人のあいだのエスニック対立感情は連邦・州関係をさらに悪化させもした。しかし,以上のことから「連邦を統治するマレー人政党UMNOとシンガポール州を統治する華人政党 PAPとがエスニック問題をめぐって互いに譲れない対立を繰り返して結局は分離に至った」と対立を図式化するならば,それは大きな誤りであると言わざるを得ないのである4)。まずもって,そのような議論では連邦政府がマレー人たちによって
壟断されていたことが前提となっているが,これは正確さを欠いている。当時,連邦政府はUMNOのほかマラヤ華人協会MCA: Malayan Chinese Association,マラヤ・インド人会議MIC: Malayan Indian Congressの三党から構成されるマラヤ連盟党 Alliance Party(Malaya)によって運営されていたからである。しかもそうしたなか,華人政党MCAは連邦の経済財政政策を握り,連邦政府・州政府間の関係を考えるうえでも決して軽視できない存在であった。本論でも見るように,両政府の対立も元はと言えばこのMCAと PAPとの対立に端を発してのものであった。また,さらに言えば,そのような議論はシンガポール州政府与党 PAPが華人政党であるかのような前提のうえに理解されがちになるが,そのような前提ともなると,これはまったくの誤りと言わざるをえない。確かに PAPは華人を中心に構成されていたが,同党は結党当時から非種族主義的non-communalであることを党是として掲げており,華人政党ではなかったからである。PAPは特定エスニック集団を偏重しないという方針の下,公的な場における英語の使用を奨励し,また,積極的に進めていた都市の再開発にあたっては特定エスニック集団が集住しないよう心がけたりもしていた。それゆえ,PAPは彼らの言うマレー急進派Malay Ultrasと対立したが,英語を解さない人々が多数派を占める中華総商会とも相当に緊張した関係にあった。本稿結論において詳説するが,分離独立後のシンガポールではその傾向がより顕著なものとなり,PAP政権はい
3) トゥンクは回想録で分離に至る政治過程を記している。本文はほぼこれに沿って構成した言説である(Abdul Rahman 1977: 118-124)。分離に至る政治過程については竹下秀邦の詳細な研究もある。同様の物語を主にシンガポール側の視点から詳細に追ったもので,マレーシアが非種族主義を採らなかったことに分離独立の原因を見ており,PAP側の主張にほぼ沿ったものとなっている(竹下1995: 245-257)。
4) 最も優れたマレーシア史の教科書とされるアンダヤ夫妻の『マレーシア史』では,シンガポール分離について次の趣旨の説明が施されている。PAPが主に華人たちからなる野党連合をつくったため,対立はマレー人と非マレー人との対立の色彩を帯び,このため人種暴動の脅威が生まれた。そのことは分離の決定的要因となった(Andaya and Andaya 2001: 288)。
69鈴木陽一:シンガポール共和国の建国について
わゆる華語派の抑え込みを続け,結局,同国を英語の島につくりかえることで問題の解決を見ている。マレー人と華人とのエスニック対立が分離を促したのだとするならば,両政府ともマレーシア設立を強く望んだマルチエスニック政党によって統治されていたにもかかわらず,なぜ両政府が深刻な対立を起こし,またその結果,なぜエスニック対立が激化し,両政府ともこれを制御できぬまま国家分裂へと突き進んだのか,そうした疑問に答え得る必要がある。また,第二に,こうした言説は分離の過程におけるクアラルンプール側のイニシアティブを強調するあまり,その間のシンガポール側の動きを軽視し過ぎている,という難点を持つ。確かに,分離はトゥンクの類稀な指導力に拠るところが大きかったと断言できる。当時のマレーシア国内の混乱を連邦からシンガポールを切り離すことで解決するなどという荒技は彼以外の人物をしてはなし難かったであろうし,また,分離がなければ混乱は収拾がつかなくなっていた可能性は極めて高く,そうとすれば,その功績は極めて大きかったとしか言いようがない。分離の決断がトゥンクの固い意志に拠るものであったことは,分離の数日後のリーの記者会見でも強調されている。そうした語りは分離が連邦政府の一方的な決定であって,シンガポール政府の意に反するものであったことを印象付けてきた5)。しかしながら,分離のイニシアティブについては,実に驚くべきことに,これまでかような言説とは異なる響きを持つ話がときおり語られて来たのも事実であり,そうとすれば,これをそのまま受け入れることは問題も多いと言えるのである。たとえば,秘密保持を理由にシンガポールのマレーシアからの
分離を定めた協定(参考資料。以下,分離協定と記す。)がシンガポール側で起草されたことは以前から知られたところであった6)。分離協定は簡易明瞭に記された協定ではあるがその適用には争いの余地があり,とくにシンガポールがこれによって保障されたと主張するジョホール州からの水の供給は,今なお両国のあいだの争いの火種になっていることは知られているとおりである。協定起草という重要な作業がシンガポール側に任されていたことは,支配的な言説とは大きく異なり,分離作業が両国の合意の下で進められ,シンガポール側も大きな役割を担っていたことを示唆している。さらに,第三に,従来の言説は現在のような両国の分立のあり方を当然視し,分離協定第 5章,第 6章の内容,あるいはその精神を軽視している,という難点を持つと言える。実のところ,マレーシアとシンガポールとのあいだで結ばれた分離協定は単純に後者の前者からの分離を定めた協定と言うよりも,両者がある種の国家連合を設立することを定めた協定として読まれるべき文書と言える。第5章では防衛援助条約の締結が謳われ,両国が防衛及び援助のために統合防衛委員会を設立し,マレーシア軍が引き続きシンガポールに駐留することが明記されている。また第 6章では経済分野での協力が謳われ,その実現のために統合委員会の設立も選択肢の一つとなることが明記されている。分離協定を素直に読めば,国家安全保障を中心とした国家存立の基盤を両国が共有しようとする精神が見えてくる。実際,分離当時,両国分離の状態は一時的なもので両者はいずれ何らかのかたちで再統合される,との見方を採る者は決して少数派ではなかった(竹下 1995: 289-
5) 本文でも記したように,分離直前の 8月 7日,リーはトゥンクと会談し,中央・州の関係を緩くして連邦を維持するよう懇願したが拒否された,とされている。Press Conference of the Singapore Prime Minister, Mr Lee Kuan Yew, with Malay Journalists, 11 August 1965, lky 19650811a, National Archives of Singapore.
6) Asiaweek, 27 March 1992.
70 アジア・アフリカ言語文化研究 95
290)。結局,こうした国家連合の枠組みは何らかの理由で実現されなかったわけであるが,ただそうとすれば,分離の政治史を語るのに 1965年の協定成立をもって両国の分立が確定したとするのは極めて不十分な話であると言える。分離後,何ゆえ協定の精神が放棄され,現在のようなかたちでの分立に至ったのか,その説明に欠けているのである。
シンガポール共和国の独立過程に関する先行研究以上,共有されて来た言説の難点を並べてきたが,共和国の建国を考えるにあたってここで留意したいのは,ここ十数年余り,公文書の公開,関係者の回顧録の出版などに伴って一次史料に基づく研究が進み,マレーシア・シンガポールの脱植民地化について旧来の言説を覆す研究がすでに現れるようになっていることである7)。代表的な研究としては,アントニー・ストックウェル Anthony Stockwell,マシュー・ジョーンズMatthew
Jones,タン・タイヨン Tan Tai Yongのマレーシア形成の研究などがあげられる(Stockwell 1998, Jones 2002, Tan 2008)8)。従来の研究がマレーシア脱植民地化を当然のごとく現地ナショナリストが主導した現象として描いてきたところ,これらの研究はその背後にあった宗主国イギリスの帝国主義的動機を強調することで新しい視座を提供するものとなっている。1960年代初頭,イギリスはアメリカ合衆国とのパートナーシップを梃子に地球規模の勢力であり続けることを望んでいたが,そのためにはアメリカの望む東南アジア関与の継続が必要であった。それゆえ,イギリスは現地ナショナリストと協力しながら植民地の脱植民地化を進めてこれをいわばジュニア・パートナー国家につくりかえること―帝国史研究の言葉を用いれば帝国を非公式化すること―で地球規模の勢力としての地位を維持しようとした。すでに 1957年,マラヤ連邦はイギリス帝国を後ろ盾とした反共国家として独立を果たしていたが,マレー
7) 史料公開全般の状況について言えば,旧宗主国であるイギリスの公文書が 30年ルールに則って次々に公開されて来たのに対し,マレーシア,シンガポールの公文書の公開はほとんど進んでいないことを指摘できる。このため,最近の脱植民地化研究は主に旧宗主国であるイギリスの史料に基づいて行われる傾向にある。宗主国側から見たときのバイアスを克服できるのかという問題もあるが,これが現状である。以下,研究に使われている史料の状況について敷衍しよう。イギリス側の史料は主にイギリス国立文書館NAUK: National Archives of the United Kingdomに保管・公開されており,非常に使いやすく,実際にもよく使われている。さらに,イギリス帝国脱植民地化についてはこれらの史料から史料集が編まれている。British Documents on the End of Empire(BDEE)がそれである。マレーシア脱植民地化については,The Conservative Government and the End of Empire, 1951-1957, Series A, Vol. 3, (London: HMSO, 1994). The Conservative Government and the End of Empire, 1957-1964, Series A, Vol. 4, (London: The Stationary Office, 2000). East of Suez and the Commonwealth, 1964-1971, Series A, Vol. 5, (London: The Stationary Office, 2004). Malaya, Series B, Vol. 3, (London: HMSO, 1995). Malaysia, Series B, Vol. 8, (London: The Sta-tionary Office, 2004). に関連する史料がある。他方,マレーシア,シンガポール側の史料については,公文書の公開が進まないなか,研究者は回想録,インタビュー,さらに新聞記事,演説原稿など既存の公開史料に頼ることが多い。うち回想録については,リー・クアンユウ,ガザリ・シャーフィーによる三冊が最も重要である(Lee Kuan Yew 1998, 2000, Muhammad Ghazali 1998)。インタビューでは,シンガポール国立文書館National Archives of Singaporeのオーラル・ヒストリー・プロジェクトがきわめて有用である。そのほか,21世紀に入り,インタビューを中心に PAPの歴史を再構成するプロジェクトが政府系出版社によって実施されて出版されており,これも有用である(Yap et al. 2009)。新聞記事,演説原稿については,シンガポール国立図書館,シンガポール国立文書館がそれぞれインターネット上にデータベースを公開している。
8) 邦語の研究としては鈴木,木畑の研究がある(鈴木 1998,2001,木畑 2008,2011)。なお,マレーシア形成に対して,インドネシアは「対決政策」をとった。これについての研究も進んだ。代表的な研究としてジョン・サブリツキー,デイヴィッド・イースターの研究がある(Subritzky 2000, Easter 2004)。
71鈴木陽一:シンガポール共和国の建国について
シア形成はこの連邦にシンガポールなどほかのイギリス保護領・植民地をも編入しようというものであった。これによって植民地主義批判をかわし,さらにあわよくば防衛負担も一部現地持ちとしたうえで関与を継続しようとしたのであった。これらの研究においては,大まかに言えば,そうした見解が提出されている9)。さらに注目すべき研究がある。こうした研究の流れのなか,シンガポールの分離独立についても一次史料に基づく研究が出されているのである。うえに見たジョーンズの研究などにおいても分離過程の記述はあるが,アルバート・ラウ Albert Lauの研究は詳細かつ分析も鋭い。分離過程におけるシンガポール側の主導権という新しい視座を提供している点で決定的に優れた先行研究となっている。同書は 1964年 12月から翌年 2月にかけて連邦政府とシンガポール州政府とのあいだで衝突を回避するため両者の関係をより緩やかなものにするよう国制見直し(連邦関係希薄化)の秘密交渉があったことを明らかにした。さらに,同書は,両政府の対立の頂点となった野党連合・マレーシア連帯会議MSC: Malaysia Solidarity Conventionの形成について,これが連邦側の消極姿勢にあって停滞しつつあった連邦関係希薄化の議論の再開をめざすシンガポール側の戦術であったとも言いうることを指摘している(Lau 1998)。上に記した言説の問題点の第二の点について一定の新しい見識を示しているのである。ただ,これら近年の研究については,前述の共有されて来た言説の難点を克服する視座を必ずしも十分に提供していないという限界もあり,さらにまた,新しく見出された知見が今度は新しい疑問を生んでいるとの指摘もありうる。ラウの研究は分離の過程におけるシンガポール側の主導性を明らかにしたが,
そのほかの点については従来の言説を広い意味で踏襲している。たとえば,PAPの連邦議会選挙参入の理由について,リーたちはMCAにとって替ろうとしただけであって,マレー人指導者のリーダーシップに挑戦する意図はなかったのだとしている。PAP政府は特定のエスニック集団に肩入れする政策をとらなかったにもかかわらず,半島の一部マレー人たちがエスニック感情を煽り,結局,分離の道を選択せざるをえなかったというのである。同書はシンガポール側が提示してきた主張をそのまま繰り返したものとも言え,その意味では一方的な説明と言える。また,ラウの研究の本論記述は分離時のリーの記者会見で終わっている。分離協定が両国の密接な協力関係の構築を約したにもかかわらず,なぜこれが実現しなかったのか,その経緯については言及がない。さらに,うえに紹介した近年の研究の動向を咀嚼しようとすれば,シンガポールの分離独立については次のような新たな疑問も湧いてこよう。マレーシア形成がイギリス帝国非公式化の作業であったのだとすれば,それに続くシンガポール分離の過程においてイギリス帝国は一体何をしていたのか,結局,なぜその帝国再編はエスニック対立による瓦解などという無残な結末を迎えることになってしまったのか,と。
本稿の視点本稿では,これら先行研究を受けつつ,シンガポールがマレーシアの一州であったときからこれが分離して共和国の運営を軌道に乗せていくまでの過程について,十分な注意が払われて来なかった次の二つの点に着目しながら明らかにする。そのことを通してシンガポール分離独立の原因を再考していきたい。すなわち,本稿がまず第一に着目する点は,PAP政府が展開したエスノポリティクスの
9) イギリスでは,脱植民地化全般に関する史料公開が進むなか,脱植民地化における帝国主義的要素を強調する研究が盛んに出されるようになった。これを指摘した代表的論文として「脱植民地化の帝国主義」がある(Louis and Robinson 1994)。見解はこうした研究の流れに沿ったものと言える。
72 アジア・アフリカ言語文化研究 95
起源とその展開である。PAP政府は「半島との合同を通しての独立」とともに「非種族主義的であること」を政策として掲げていたが,実のところ,両政策には密接な関係があった。華人が多数派を形成するシンガポールがそのまま華人国家として単独独立することを掲げず,半島と合同したうえで独立することを掲げたことの前提には,シンガポールを華人文化から解き放とうとする非種族主義のエスノ政策があったと言い得るからである。それでは,PAP政府は具体的にはどのような見通しを持ってかかる―見方によっては不自然とも見える―非種族主義というエスノ政策を進めようとしたのか。また,PAP政府は非種族主義を採用したにもかかわらず,なぜマラヤ連盟党率いる連邦政府と対立し,さらにマレーシア国内のエスニック対立が惹起されることになったのか。本稿では,PAP主流を構成した集団がプラナカンperanakanと呼ばれる帰化系の流れを背景にした人々であったことに留意しながらこれらの問いを探求し,分離独立の原因を考える。プラナカンとは生物学的な出自をマレー世界(語の意味については第 1章で述べる。)以外のアジアに持ちながら現地化した人々を意味し,一般にはそのなかでも華人系住民を指すことが多い10)。本稿においては現地化した人々のなかでも英語を自由に操ることになった人々―英語を操るプラナカン―に注目する。PAPを率いた人々がある種のエスニック集団の性格を帯びていたこと,彼らがマレーシア創設を通して自らの活躍の場と権力基盤を回復しようとしていたことに光を当て,非種族主義的とされてきた彼らのエスノポリティクスへの理解を深める。さらに,本稿が第二に着目しようとする点は,この間のイギリス帝国の動向である。すでに述べたように,史料公開以降の研究ではマレーシア脱植民地化の背景にイギリス帝国
の帝国再編への意図があったことが強調されるようになっている。イギリス帝国はその植民地をジュニア・パートナー国家につくりかえることを通して地球規模の勢力であり続けようとしたというのである。重要な指摘であるが,それでは,その後,イギリス帝国はマレーシアの設立からシンガポールの分離独立に至る過程においてどのような政策をとったのだろうか。本稿では,脱植民地化の過程を通してイギリス帝国と PAP政府のあいだに密接な協力関係が築かれていたことに留意しながらこうした問いを探求し,分離独立の原因を考える。上記プラナカンはイギリス帝国史研究において帝国支配の現地協力者と位置付けられているエスニック集団でもあった。その流れを背景にした人々が主導した PAP政府はイギリス帝国ときわめて密接な協力関係を構築し,マレーシア創設において大きな役割を果たした。そうした協力関係がその後どのような展開を見せたのかを見ていく。本論では,以上のような点に着目しつつ,シンガポール共和国建国の過程を順を追いながら明らかにしていく。(1)まず初めに,マレーシア形成の政治過程を振り返る。そもそもなぜ PAP政府がマレーシアへの参入を果たそうとしたのかについてエスノポリティクスの観点から再考する。(2)次に,マレーシア成立以降,連邦政府とシンガポール州政府とが深刻に対立するようになっていった過程を明らかにする。二度に渡ってシンガポール暴動が起こった時期までを見る。(3)その次に,連邦政府とシンガポール州政府とが新たな国のあり方を模索しつつも結局後者が分離独立する決断を下していった過程を明らかにする。イギリス帝国とシンガポール PAP政府の協力関係の変容が分離にどのような影響を与えたかについてはとくに注意を払って考える。(4)最後に,その後,マレーシア・シンガポール両国が分離協定の企図したとこ
10) プラナカンはマレー語の原義で子孫,末裔を意味する。
73鈴木陽一:シンガポール共和国の建国について
ろから離れて別々の国家へと完全に分立していった過程を明らかにする。インドネシアの「対決政策」が終了する頃までを見る。研究にあたっては公開されたイギリス史料,出版された回想録などを用いる11)。
第 1章 マレーシア創設のエスノポリティクス
1960年代前半,シンガポールの人々は自らの意志でマレーシアに加わることで最初の独立を果たした。しかし,その後,シンガポール州は連邦と衝突し,結局これから離脱して自らの道を進むことになった。なぜそのような帰結に至ることになったのか。この問題を考えていくにあたっては,ある一つの疑問を改めて追求することが必要であると考えられる。PAP政府はそもそもどのようなエスノ政策上の見通しを持ってシンガポールとエスニック構成が大きく違う半島・ボルネオとの合同を望み,実際,マレーシアに加わったのだろうか,という疑問である。もちろん,この問いに対しては,シンガポールの人々は半島とのあいだで歴史的に築き上げてきた社会的一体性から半島と合同することを自然の成り行きと見ていたからである,と答えることは可能である。そうした言説が支配的であったことはすでに述べたとおりである。ただ,たとえそうであったのだとしても,華人が多数派を占めるシンガポールがマレー人の多い地域と合同するとはやはり大胆な話と言える。エスニック構成が大きく異なる地域との合同がそれまでにない事態を惹起
することは予想されていたはずだ。それゆえ,シンガポールがマレーシア内の一州となってからの連邦・州両政府間関係の展開を見ていくに先立ち,本章においては,シンガポールがマレーシア参加に至った経緯について見直すことにする。合同が進められるにあたっては,異なったエスニック集団が共存することについてエスノ政策の見地からこれを肯定する議論が展開されたはずであるが,どのような理由付けがなされていたのだろうか。PAP政府は,本当のところ,どのような見通しを持ってこれを推進したのだろうか。合同をめぐる政治は新しく生まれる連邦にどのような影響を及ぼしたのだろうか。そういった論点について考えていく。
「多人種が融和するマレーシア」という理由付け
PAP政府は,マレーシア発足前,エスニック構成が大きく違う半島・ボルネオと合同して独立するべきとの考えについて,それら地域の歴史的・社会的一体性の議論を進め,エスノ政策の見地からある理由付けをシンガポール住民に示した。東南アジア社会が本来的に様々なエスニック集団が共存する複合社会であるとの前提のうえに立ち,シンガポール市民はそれら多様なエスニック集団が融和するマレーシアをつくり出し,そのなかに自分たちの安住の地をつくることこそが独立への自然の流れとなる,という楽観的とも言える見通しがその理由付けであった12)。確かに,東南アジア社会は大陸部,島嶼部ともに複合
11) イギリス史料についていえば,機密性が高かった公文書が 40年,50年を経てさらに公開されたため,それらも用いることができた。他方,シンガポール,マレーシアの公文書の多くは依然として非公開のため用いることができなかった。
12) エスニック集団とは「周囲のほかの集団と自分たちを隔てる文化的アイデンティティを自分たちが共有しているという明確な認識を成員がともにする集団」(Giddens and Sutton 2013)とされ,1970年代以降,研究者たちのあいだで民族,部族などという言葉に替わってこれを指す語として広く使われることになった。他方,マレーシア・シンガポールにおいては,いわゆる民族集団をエスニック集団と呼ぶ呼び方は定着せず,昔からこれを「人種 race」と呼ぶことが一般的である。もちろん,一般的に人種による分類は生物学的要素が基礎となるため,婚姻・出産などによってグループ間の移動が生じているマレーシア・シンガポールではこうした用法を用いるのは不適切なはずであるが,今も使用されている。このようなマレーシア・シンガポールの言語状況に鑑みて, ↗
74 アジア・アフリカ言語文化研究 95
社会と評されてきた。島嶼部について言えば,その主要な言語集団は 5000年ほど前に台湾から島伝いに南下して定住することになったオーストロネシア語族―広い意味でのマレー系集団の人々―であるが,さらにその後,中国本土,インド亜大陸などからその他の言語集団の人々もその地に流れ込み,現在のような状況がつくり出された。東南アジア島嶼部はマレー世界とも呼ばれるが,それは様々なエスニック集団に属する人々が共存して暮らして来た地域でもあるのだ。構想されたマレーシアは主要エスニック集団―マレー人,華人,インド人,イバン人,カダザン人ほか―から構成される複合社会となる見通しであった。これら多人種が融和する社会こそがその本来の姿であって,シンガポールの人々が半島などとの合同に躊躇すべき理由はなく,むしろシンガポールの華人たちが固まって孤立することのほうが危険である,というのが議論の趣旨であった。1961年 12月,リー・クアンユウは第 2回マレーシア連帯諮問委員会MSCC: Malaysia Solidarity Consultative Committee―委員会の役割については後述―出席のためサラワクを訪れたが,このとき,彼は次のように述べてマレーシアの設立を訴えた13)。
もし私たちがばらばらで孤立し続けていれば,我々の生き残りは確実に危ういものになるでしょう。しかし,ダヤク人,ドゥスン人,ムルトゥ人,マレー人,華人,インド人,その他の人々のあいだで道理をわきまえて寛容にやってきたという実績のうえに立ち,強力なマレーシア連邦を設立すれば,多人種のあいだに安定と幸福をもたら
している私たちの多人種社会が生き残り繁栄し続ける可能性は十分にあるのです。
明快で説得力のある議論と言える。かなりのシンガポール市民がこうした議論に納得して合同を支持したと言ってよいように思われる。ただ,このような議論を受け入れるにあたっては慎重な吟味も必要であろう。議論の前提となるマレーシアがかような主要エスニック集団から構成されることになるであろうという見解については,エスニック集団がつねに構築過程にあることを考えれば本質主義的に過ぎる粗い議論であり,以下のような問題点があるからである。すなわちまず第一に,かかる見解はそもそも上記主要エスニック集団それぞれ自体が複合的な存在であり,かつそのアイデンティティが常に変容の過程にある存在であることを見逃している点で問題があると言える。上記オーストロネシア語族の人々も長いあいだに分化と統合を繰り広げてきた。マレー人概念がそうしたなか王権を中心に長い構築過程を経て確立されてきたものであることについては研究の積み重ねがある(Roff 1967, Ariffin Omar 1993, Milner 1995, Barnard 2004)。また,華人系集団には出身方言ごとに分かれた集団が存在していた。彼らの主要な出自は福建,広東,客家,潮州,海南などで,華人としての意識は辛亥革命以降に高まりつつあったが,こうした出自意識は強く残されたままであった。さらに,インド系集団においては,出身地による違いのほか宗教,カーストによる分裂もあり,インド系としてのアイデンティティはかなり希薄であった。インド亜大陸南部出身のタミル系の移民が最大多数で,彼らはゴム農園など
↗ 筆者が主体的にエスニック集団について記述する際にはエスニック集団の語を用いるが,引用・準引用などの理由から人種・民族などの語を用いることになったときは,そのままの語を用いることにした。
13) Prime Minister’s Broadcast Speech over Radio Sarawak, 19 December 1961, lky 19611219, National Archives of Singapore. リーは半島との再合同をシンガポールにとってあるべき当然の姿,自然の摂理のようなものと考えていたように読める。
75鈴木陽一:シンガポール共和国の建国について
で働いていたが,そのほかの地域からイギリス帝国によって特定職業に従事するために招かれた人々もいたし,また,イギリスが来る以前からグジャラートなどからのムスリム商人も棲んでいた14)。かように状況を注意深く見るならば,上記見解において言及された主要エスニック集団は植民地支配下において初めて現在に近いかたちを成すようになったものであることがわかるし,住民のエスニック・アイデンティティが依然として変容の過程にあること,したがって,そうした変容のうえにナショナル・アイデンティティも形成されていくであろうことも推測され得る。主要エスニック集団が確定的に存在し,マレーシア成立後もそのまま存在し続けるかのような語りは誤解を生みやすい15)。さらに第二にかかる本質主義的な見解は主要エスニック集団の構図で説明することが困難な人々―主要集団に本来的に属さない小集団や越境的な立場にある人々―の存在を
見過ごしかねない点で問題があると言える。半島にもボルネオにも主要エスニック集団に属さない小規模のエスニック集団は多々存在した。半島のオラン・アスリOrang Asliなどはその典型である。さらにこのような類型では,長く複合社会において媒介者として支柱的な役割を担い,今また現に脱植民地化を担おうとしている(と本稿が注目する)リーら帰化者の存在もなぜか無視されている。マレー世界においては,生物学的な出自をマレー世界以外のアジアに持ちながら現地化したプラナカンたち―言わばアジア系クレオールの人々―が重要な役割を担ってきていた16)。東と西を繋ぎ外来者が集うこのエンポリウムにおいて,長らく彼らプラナカンたちはムラユ王権が支配する内世界と自らの出自である外世界とを結ぶことで社会をリードしていたのである。彼らプラナカンたちは現地化しつつも,広い意味での外来系エスニック集団―アラブ系集団と華人系集団など
14) イギリス帝国から招かれ,専門職として働くインド系住民も多かった。彼らは少数者ではあったが,職業柄,タミル系より社会的影響力があった。鉄道などで働いたセイロン系の人々,英語学校などで働いた人々などである。また,インド系移民は単純にインド系とは言えない側面もあった。現在のインド出身者のほか,パキスタン,バングラディッシュ,スリランカ出身者もいた。うち,セイロン系はインド系というよりセイロン系としての集まりを重視していたふしがあるし,インド系ムスリムは,ムスリム・コミュニティに身を置くことが多かった。独立期に至るインド系移民の状況については先行研究がある(Sandhu 1969)。
15) 植民地支配の結果,エスニック集団が構築された,という議論が盛んであるが,マラヤ主要三集団の分類もまた植民地支配に由来する,と言いうる。チャールズ・ハーシュマンも指摘するとおり,時系列に沿って海峡植民地センサスを並べると,カテゴリーとしての三大種族が形成されてきたことがわかる(Hirschman 1987)。当初,イギリス人はその被治者を見るのにマレー人というカテゴリーを狭く考えていた。それが,19世紀末以降,半島への介入を進めるにつれ,ミナンカバウ人なども含むかたちで被治者としてのマレー人を広く考えるようになった。「マレー人」の創出は,イギリス人が「弱い人種」である「マレー人」への庇護者としての役割を意識するようになった結果であった,とも考えられる。
16) 本稿におけるプラナカンはアイデンティティそのものよりもむしろその集団の置かれた社会構造に注目してエスニック集団を規定した概念になる。通常,エスニック集団はエスニック・アイデンティティによって定義されるが,そのエスニック・アイデンティティは集団の置かれた社会構造のなか構築される。本稿はそのことに注目した。プラナカンを構築主義的に理解した研究にルドルフの研究がある(Rudolph 1998)。今日のマレーシアにおいては,プラナカンというと,「マラッカあたりに今なお暮らしているらしいけれど,基本的にはその独特の衣装とともに博物館に入った過去の人々である」というイメージを浮かべる人が多い。これには「華人独自の文化を失った根なし草の人々」というネガティブなニュアンスも伴う。もちろん,こうした理解は本質主義の典型的な陥穽に陥っている。彼らがいつも冠婚葬祭の服を着て暮らしているなどということはあり得ない。そして,かように壮麗な衣装は彼らが相当な資産を持った上流階層にあったこと―単純なエスニック集団ではなく,その社会階層性に拠っても規定される集団であったこと―を強く示唆しているのである。
76 アジア・アフリカ言語文化研究 95
―にも所属し,そこで内世界と外世界とを繋ぐ宗教,文化,経済などのチャネルを握り,そのことを通して集団の内外で強力な発言力を確保していた17)。ムスリム移民は帰化すると,マレー・ムスリム系住民集団の構成員となったが,彼らはそのコミュニティと域外のイスラム世界とを繋ぐ役割を果たした。マレー社会の先進者集団は彼らムスリム移民との混血者によって形成された,というのはマレーシアにおいて広き行き渡った言説とさえなっている18)。また,同様のことは華人系帰化者たちについても言えた。彼らは華人系集団を地場権力へ結びつけ,また,内世界には外来の文化や豊かな富をもたらし,媒介者としてそこに高い社会的地位を築いていた。ムラカ王国の繁栄は彼ら華人系集団が政府機構の一翼を担ってのものであったし,マレー語新聞の走りも彼らの資本や技術によるところが大であった(Anderson 2006: 133)。
イギリス帝国とプラナカン実のところ,シンガポール脱植民地化の背景をエスニシティの観点から理解しようとするならば,次のことは前提として押さえておく必要がある。19世紀以降,その地の新たな支配者となったイギリス人たちもまたかなりの数のアジア系帰化者をその体制に組み込み,帝国支配を支える新たな帰化者層―本稿が着目する英語を操るプラナカン―がつくりあげられていたということ,さらに脱植
民地化が進むなか,イギリス人がますます彼らを頼むようになっていたということである。実に,イギリス帝国支配の下,帰化者の少なからぬ者たちがイギリス帝国との特別の関係―英語の受容,帝国臣民としての地位の獲得など―を通して海峡植民地を中心としたイギリス支配地域に主導的階層を形成することに成功した。これが本稿の注目する英語を操るプラナカンである。彼らの多くは主に海峡植民地に暮らし,植民地の発展に伴ってその勢力を拡大させた。植民地経済の運営に貢献することが期待され,欧州系企業に従業員として仕えたり,植民地政府の信任を得て外来者を動員した事業を行ったりもした。そして,彼らプラナカンにはインド系,アラブ系などの人々も含まれたが,なかでも帝国が最も重用し,最大の人員を擁していたのは華人系帰化人であるババ Babasあるいは海峡華人 Straits Chineseと呼ばれる人々であった。もともとババと呼ばれる華人系帰化人の人々には何代にも渡ってマレー世界に暮らしたため祖先の母語である中国系諸語を解さなくなった人々も多かったとされる。また,彼らの多くはムラカに集住し,独自の料理,服装などの文化を発達させていた。ところが, 19世紀以降,イギリスの海峡支配が確立する と,イギリス支配に仕える者が増加し,彼ら は本拠地をシンガポールに移したのである19)。 帰化者である彼らは広い意味での華人系集団に身を置きつつも,清朝臣民ではなく,イギ
17) 彼らは後の主要エスニック集団で多数派を構成する人々―農村に暮らすマレー人,年季奉公で来たまま留まっている華人など―とは随分と違ったエスニック・アイデンティティを持っていた。主要集団から独立していたという表現も可能かもしれない。
18) 1981年から 22年余りに渡って首相を務めたマハティール・ビン・モハンマドは論争を巻き起こしたその著書『マレー・ジレンマ』のなかで,マレー人の社会が都市の外来者との混血(を含む)マレー人と農村の純血なマレー人とに分かたれており,前者が進んだ存在,後者が遅れた存在であり,イギリス人の到来以降,その差はますます拡大した旨を記している(Mahathir 1970: 16-31)。
19) 海峡華人とババとは類似した概念であるが,同一の概念ではない。ともに定義することが困難な語であるが,ここではそれぞれを次のように説明しよう。海峡華人とは,政治学的な概念で,海峡植民地やその周辺を自らの本拠とし,往々にしてその市民権を取得していた華人系帰化人を指す。ババとは,文化人類学的な概念で,何代にもわたって南洋に暮して帰化し,往々にして華語を話さなくなった華人系帰化人を指す。ババについては,クラマーの研究(Clammer 1980),ルドルフ(Rudolph 1998)の研究が最重要である。
77鈴木陽一:シンガポール共和国の建国について
リス帝国臣民であることを主張する者が多かった。イギリス帝国に忠誠を誓う者たちは結束し,1900年には,海峡英籍華人公会SCBA: Straits Chinese British Association を結成した。その後,彼らは植民地の立法評議 会Legislative Councilや執行評議会Executive Councilに代々議員を送り込んだ(Rudolph 1998, 93-156)20)。その意味で,戦後,世界規模で進行しつつあった脱植民地化の流れがこの地に波及する過程において,帝国がそれまで長く協力関係にあった彼ら英語を操るプラナカンたち―そのなかでもとくに海峡華人たち―にこうした指導的役割をますます与えるようになり,彼らが政治の世界へめざましい進出を果たすようになっていったことは当然の成り 行きであると言えた。当時,アメリカが主導する国際連合などの安全保障枠組みと地球規模の単一市場が成立し,さらに冷戦の勃発と波及を見て,公式帝国は宗主国の重荷となりつつあった。そうしたなか,各地植民地では様々な立場の人々が市民的自由を求め,ナ ショナリズムを唱えることで権力奪取をはか り出した。そして,帝国支配の協力者層には こうした動きに恐怖した者たちもいたが,自 らナショナリズム運動の指導者となり,帝国 から権力移譲を受ける者も多かったのだ。1948 年,シンガポールに立法評議会が設置されると,進歩党 Progressive Partyが選挙に勝利した。同党は SCBA人脈と欧州人の商業的利益を代表したシンガポール協会 Singapore Associationの人脈によって 1947年に成立した政党であった。創設者は SCBA政治小委員会委員にあった CCタン C. C. Tan,イギリス人で弁護士事務所を構えていたジョン・レイコック John Laycockらであった。英語を唯一の公用語とし,自由貿易港の地位を維持する,などといった植民地政府の施策
を支持した。この進歩党は 1955年選挙で大敗を喫するまで政府と協調しながら立法議会をリードした(Yoe 1973: 98-105)。重要なことは,リー・クアンユウ率いる
PAPが台頭し,マラヤ全域に影響力を伸ばそうとし出したこともまたこうした流れを受けたものと位置付けられるということである。当時,左派勢力として売り出されていたPAPであったが,これは,実のところ,リーら主流派の英語教育を受けた帰化者たちが左派イメージを出すことで華語を母語とする華人たち(以下,華語集団と呼ぶ。)を支持基盤に取り込むことで成立した政党であった。リーたちは結党にあたってリム・チンシオンLim Chin Sionら労働組合指導者たちを党のメンバーに迎え入れた。彼らには華語集団に圧倒的な支持があり,これによって党勢拡大を図ろうとしたのである。実際,この戦略は奏功した。1959年 5月,新憲法の施行に先立つ立法会議 Legislative Assembly(立法評議会に替わり,1955年に設置。)総選挙では,リー率いる PAPは過半数の得票を得て圧倒的多数の第一党の地位を獲得することに成功し,6月,新たな憲法の下に自治政府(外交・防衛以外の事務を掌理)が成立すると,彼ら英語教育組がその権力を掌握した。しかも,このとき,リーは組閣に先立ち政府によって拘束されていたリムら PAP左派指導者たちの釈放を求め,これを実現したものの,彼らが力を揮うことには制限をかけた。左派指導者には閑職を宛がったに過ぎなかったのである(竹下 1995: 126-132)21)。リー・クアンユウは裕福な海峡華人の家系に育ちながら,青年期を戦中戦後の混乱期に過ごすことで政治的自覚を発展させた人物であった。崩れることがないとされていたイギリスの支配が瞬く間に崩れ去るのを目撃し,いつまでも帝国に頼ることができないこと,
20) SCBA創設の経緯については篠崎の研究を参照(篠崎 2001)。21) このときの選挙は新憲法の導入によるもので,立法評議会は立法会議に改組され,その権限は強化
された。
78 アジア・アフリカ言語文化研究 95
英語を操るプラナカンたちが率先して自立をめざしていかなければならないことを自覚したと考えられる22)。実際,政権発足後,リーは現地ジャーナリスト向けの演説で英語教育を受けた者たちの役割について印象的なことを述べている。マラヤ(ここでは,マラヤ連邦ではなく歴史的マラヤを意味。)で英語教育を受けた者たちはある特定の特徴を身に着けている―たとえばマラヤで英語教育を受けた華人は中国で英語教育を受けた華人たちよりもマラヤで英語教育を受けたほかのエスニック集団の者たちにより共通のものを見出す―としたうえで次のように述べているのである23)。
「英語教育を受けた人」という言葉の意味をはっきりさせたところで,その特徴をあげてみましょう。長所の第一は,同質であるということです。第二は,基本的に自分たちのことを華人,マレー人,あるいはインド人とは考えなくなっていることです。植民地当局に従順すぎるところもあるものの,彼らはこの社会に忠実であり,正直であり,また良く振舞うのです。……
この階層の未来はどこにあるのでしょう。……イギリス帝国領すべての植民地革命において,イギリス支配から独立が勝ち取られたとき,権力は英語教育を受けた現地ナショナリストへと手渡されました。インド,パキスタン,ビルマ,セイロン,ガーナ,マラヤ(引用者注:この場合,マラヤ連邦を意味)またしかりです。……シンガポールとマラヤにおいて英語教育を受けた者の役割はインドにおいて担われたものと同じであると私は考えています。イギリスから勝ち取ってきた権利と特権を大衆―その多くは英語教育を受けていない人々―へとさらに拡大することで彼らは社会革命を達成したのです。
演説は,英語教育を受けた自分たちこそがマラヤの独立と社会革命をリードすべき存在である,そうした趣旨のものであった。強い政治的な意志を感じさせる演説であるが,ただ,その真意を正確に理解するためにはさらにその言説の背景で起きていた出来事にも注目する必要があるだろう。演説は自分たちのアイ
22) リー・クアンユウは 1923年にシンガポールで生まれた。リー家はシンガポールに 19世紀以来続く客家の家系であるとされる。両親とは英語を話し,祖父母とは華語が混じったマレー語を話して育ったとされる。シンガポールで英語教育を受け,戦後,渡英してケンブリッジ大学を卒業,弁護士試験に合格した。帰国後,海峡華人の大立者で華僑銀行経営者の陳振傳 Tan Chin Tuanの姪に当たる柯玉芝Kwa Geok Chooと結婚。また SCBAの事務局長も務めた。職場はレイコックが経営するレイコック・アンド・オン Laycock and Ongで,弁護士として頭角を現したとされている。彼は,こうした進歩党人脈にあって 1951年の立法議会選挙では進歩党の運動を支援していたが,これに飽き足らず,1954年,仲間とともに PAPを結成した。華人コミュニティ主流からの支持がなければ自分たちの支持基盤は弱まることを察知し,華語世界の取り込みに奔走したのであった。なお,1955年選挙では進歩党は大敗を喫しており,以降,彼とレイコックとの関係は悪化した。結局,リーは弟や妻とともに自分たちの法律事務所を開設している。
23) Text of an Address by the Prime Minister, Mr. Lee Kuan Yew, at the Singapore Union of Journalists, 16 August 1959, lky 19590816, National Archives of Singapore. 当初,英語教育を受けた者のあいだには PAP政権への根強い不満があった。PAP政権は主流派が自分たちと同じ英語教育組によって構成されているとはいえ,自分たちとは相容れない親共の華語集団の支持で成立したことが明らかであったからである。演説は自分たちが英語を話すジャーナリストたちとともにあることを訴え,彼らの支持を確保するためになされたものとも考えられる。リー回想録参照(Lee 1998: 319-320)。なお,このような英語教育による同胞意識形成の議論はアンダーソンの示した植民地支配下の青年のあいだの国民意識の醸成の図式に似通っている。英語を共通語としたマラヤン・ナショナリズムの主張と評することもできよう。アンダーソン著『想像の共同体』参照(Anderson 2006: 120-122)。
79鈴木陽一:シンガポール共和国の建国について
デンティティーを確認するだけではなく,逆境を越えてマラヤをリードしていこうという扇動の目的も込められたものであった。一見すると,プラナカン主導による脱植民地化は現実味を帯び出したものの,その実,次段落以下のように現実を冷徹に見るならば,彼らがマラヤを主導する立場にあるというかような言説はその足元において急速に妥当性を失いつつあったのである。すなわち,まず,かような言説の背景にあって英語を操るプラナカンたちの指導的地位に深刻な影響を与えつつあったことの第一に,1948年にマラヤ連邦がシンガポールを切り離したかたちで半島に成立しさらに 1957年には独立を果たしたため,実のところ,彼らの主張する歴史的マラヤの一体性は薄れ,シンガポールの孤立化が進みつつあった,という事実があった。確かに,脱植民地化の過程にあってシンガポールの住民大多数はマラヤ連邦との合同を通しての独立を「本来そうあるべきこと」,ほとんど自明の道理と考えていたふしがあった24)。さらに,それを裏付けるような両者の結びつきがイギリス帝国によって維持されてもいた25)。ただそれにもかかわらず,肝心の半島の人々はマラヤ連邦の独立によって自足の傾向を強めていた。とくにマレーナショナリズムは自らの起源である
旧海峡植民地から勢力を退潮させ,マレー人たちはシンガポールを華人の島とみなすようになりつつあった26)。半島華人たちの少なからぬ人々も連盟党を支持することで市民権を得て,独立の恩恵に浴しているただなかにあった。そうした傍ら,シンガポールの人々は直轄植民地の自由貿易港として未曾有の繁栄を謳歌していたが,客観的に見れば,同島はますます多島海のなかの孤島の島になりつつあり,彼らは拠って立ってきた後背地を失おうとしていた。イギリス帝国の東南アジア政策によって両者は辛うじて繋ぎとめられていたが,脱植民地化が進むなか,何もしなければプラナカンたちが活躍の場としてきた旧海峡植民地と半島諸邦からなる歴史的マラヤが瓦解するのは時間の問題であるかのようであった27)。さらに,英語を操るプラナカンたちの指導的地位に深刻な影響を与えつつあったことの第二に,マラヤ連邦においてマレー人優位の体制が固まりつつある傍ら,シンガポールでは市民権の拡大が進み,プラナカンならぬ華語集団が政治的発言力を増大させつつあったという事実があった。当時,シンガポールの人口の四分の三は華人たちであったが,その多くは中国に戻ることを前提に仕事に来たものの内戦による本国荒廃などの理由からそこ
24) シンガポール政治においてはほとんど全ての政党がマラヤ連邦との再合同を条件の違いこそあれ政策に掲げていた。各政党の主張などについてはヨーの研究に詳しい(Yoe 1973)。
25) マラヤ連邦は依然として英馬防衛協定 Anglo-Malayan Defence Agreementによってシンガポールを拠点とするイギリス帝国の極東軍事戦略のなかに組み込まれていた。同協定は本旨としてはマラヤ連邦防衛のための条約であったため,イギリスはその他の目的のためにそこに駐留する自国軍を動かすことができなかった。そのため,その他の目的のためにこれを動かすときは,一旦シンガポール基地に軍隊を動かすという煩雑な措置がとられもしていた。他方,シンガポール政府の治安評議会 Internal Security Councilにはイギリスと並んでマラヤ連邦からも委員が送り込まれていた。治安評議会はシンガポールから 3名,イギリスから 3名,マラヤ連邦から 1名,計 7名の委員から構成され,シンガポールの治安の方針を決定した。
26) 1950年代,シンガポールは依然としてマレー文化の中心地であったが,マラヤ連邦の独立に伴い,それまでマレー文化をリードしてきた人々の多くがクアラルンプールに活動の本拠を移しつつあった。50年代世代 Asas ‘50の作家たちがそうであり,さらにマレー語紙ウトゥサン・ムラユが本拠をクアラルンプールに移したのもこの頃である。
27) マラヤ連邦独立への動きが進むなか,連邦に組み込まれた旧海峡植民地では,SCBAなどを中心に連邦からの分離運動,さらにシンガポールとの再統合の運動も起こった。しかし,こうした運動は受け入れられず,ペナン,マラッカは連邦に留まり,シンガポールのみが植民地として残された(Mohamed Noordin 1974: 71-80)。
80 アジア・アフリカ言語文化研究 95
に留まった大陸各地の方言を母語とする華語集団の人々であった。確かに,もともと彼らの多くは中国への帰属意識が強く,そのため,マラヤへの忠誠心が疑われていた。市民権を得た者も少数者に留まっていた。しかし,時が経つにつれて彼らの定住志向も強まっていたのも事実であり,彼らへの市民権の拡大は止めようもない流れとなっていた。そして,そうとすれば,そうしたなか,数的に劣るプラナカンたちの発言力が相対的に弱まり,数的に圧倒する華語集団の発言力が増すことは火を見るよりも明らかであった。1955年選挙において進歩党は没落を見たが,これは華語集団へ市民権の大幅な開放が実施されたことに大きな原因があった。リーたちが PAPを立ち上げてこれに華語集団を取り込んだのも,かような事態を見越してのことであった。しかも,ここで問題であったのは,華語集団のなかの少なからぬ者たちが共産主義・中国に共感を抱いており,イギリスとの特別の関係に権力基盤を置くプラナカンたちとはその点で相容れない立場にあった,ということであった。実際,この頃のシンガポールにおいては非合法な共産党が彼ら華人のあいだに勢力を浸透させ,イギリスからの自立を煽っていた。それゆえ,新憲法施行前まで首席大臣Chief Ministerを務めたリム・ユウホックLim Yew Hockは島内の共産主義者を一斉検挙したものの,彼は共産主義に共感を抱く人々の支持を失って失脚することになった。PAP英語教育組は同じ轍は踏みたくないはずであった。指導的地位を維持するためには,華語集団の機嫌をとり続けるか,あるいは逆にこれをうまくコントロールする方法を手に入れるか,いずれかが必要となっていたはずであった。
新連邦創設のエスノポリティックスリー・クアンユウ率いる PAP政府が新連邦創設というエスノポリティクスに邁進し出したのは,そうしたなかでのことであった。
PAPは半島との合同を唱えて 1959年の選挙に勝利し,さらに 1960年代に入るとイギリス帝国の意向も受けながら半島だけではなくボルネオも含めた合同を追求するようになっていったのである。先に見たように,多様なエスニック集団が融和する新連邦をつくり出し,そのなかに自分たちの安住の地をつくることこそが独立への自然の流れとなるというのが彼らの主張であった。ただ,新連邦創設は,こうしてエスノ政策上の観点から見れば,英語を操るプラナカンたちの活躍の場とその権力基盤とを大きく回復させ,そのリーダーシップの下,より巨大な国家を建設していくことに繋がるものでもあった。リーたちは以下のような見通しを持って合同を推進した,と解することができるのである。すなわちまず第一に,PAP政府は自らの活躍の場であった歴史的マラヤを回復してシンガポールの孤立を回避し,さらにその経済基盤を強化するという見通しを持って半島・ボルネオとの統合を推進した。前節で見たように,このまま行けば,その体制のいかんにかかわらず,同島が遠からず多島海のなかの孤島になるのは明らかであった。もちろんかような危険な状態は避けられるべきであり,そうとすればシンガポールの人々は―とりわけその地域において指導的地位にあった英語を操るプラナカンたちは―活躍の場として来た後背地を合同によって回復すべきであった。そして,合同の必要性は経済的な見地からは以前より高まっていたとも言いえた。当時,シンガポール経済は自由貿易港としての地位を生かして中継貿易を主要な生業にして繁栄を続けていたものの,人口の流入・増大も続き慢性的に高い失業率を抱える状態にあった。工業化はそのような苦境を打開するために不可欠な戦略であったが,その実施のためには,市場となるべき後背地・マラヤ連邦との共同市場の創設が必要と考えられたのであった28)。さらに第二に,PAP政府はそこに自らが
81鈴木陽一:シンガポール共和国の建国について
主導する複合社会を再生して新たな仕様のナショナル・アイデンティティを構築し,そこに彼らが公正と考える社会を実現するという見通しを持って半島・ボルネオとの合同を推進した。総じて言えば,複合社会こそは媒介者であるプラナカンたちが長く拠って立ってきた権力基盤であった。ところが,その複合社会は変容が進み,華語集団がその力を伸長させる傍ら,プラナカンたちの足場は揺れつつあった。それゆえ,当時,PAP政府は独自の言語政策,都市再開発政策などを実施することで特定のエスニック集団が強大化することを阻止し,新たな市民意識を創出することに着手していた。言語政策としては多言語政策をとり,国語をマレー語とし,公用語をマレー語,華語,タミル語,英語の四言語として現状を維持しつつも,華語校,マレー語校,タミル語校に英語学習の時間を設けた。また,都市再開発政策としては,慢性的な住宅不足を解決することを理由に,エスニック集団ごとに集住する地区を立ち退かせ,そこに公営集合住宅をつくり,特定エスニック集団が集住しないよう人々をランダムに入居させた。事実上,市民が英語を唯一の共通語とせざるを得なくなる政策を採ったのである。ただこうした政策には中華総商会なども含めた華語社会からの強い反発もあった。市民意識の創出を確実に実現するためには,半島などとの合同を通して本来あるべき複合社会を再生させ,各エスニック集団の力を相対化させることが得策であったのだ。マラヤ連邦はマレー人人口と非マレー人人口とが拮抗した複合社会の状態にあり,政府は英語を公用語
とする政策を採っていたのだ。そして,合同の必要性は PAP党内の事情によってさらに高まることになった。前述のように PAPはリーら英語を操るプラナカンと左派勢力との連携のうえに成立していたが,政権獲得後,閑職に置かれた左派指導者たちに状況への不満が高まり,その関係は徐々に悪化していた。華語集団に支持のある左派が内閣に反乱を起こせば,倒閣される可能性も高かった。そうしたなか,リーたちにすれば,複合社会の回復によって華語集団に支持された左派に対抗する別の勢力を創出するというシナリオは絶大な効果を有するシナリオと言えた。マレー人政党UMNOが主導するマラヤ連邦政府は共産主義勢力を武力で鎮圧するなどこれに対して非常に厳しい態度で臨んでいた。シンガポールが合同によって連邦の傘下に入れば,自分たちが表立つことなく連邦政府が左派の行き過ぎを牽制するであろうと考えられたのである29)。そうした意味で,新連邦の創設はリーたち英語を操るプラナカンたちの活躍の場となる巨大な国家を創出し,その文化そのものを彼らの仕様に変革する道を開くものとも言い得た。確かに,エスニック構成の違う半島やボルネオと合同すれば,数の上で拮抗するマレー人と非マレー人とが隣り合わせで暮らすことになり,深刻な問題が出て来る懸念もなくはなかった。しかし,かような状況こそはマレー人,華人,インド人といったエスニック集団を越えた存在であるプラナカンたちが指導的地位に立つ場であった。彼らは英語教育によって特定エスニック集団の利益に偏ら
28) 実際,1955年,世界銀行はシンガポールの工業化を促すレポートをまとめており,1959年,PAPも工業化とマラヤ連邦との合同をバックボーンとしたマニフェストを掲げて選挙戦を勝ち抜いていた(Rodan 1989: 47, 61-62)。なお,PAP政権におけるその構想の推進者はゴー・ケンスイ財務相であった。
29) 当初,リーたちは密室の治安委員会の席では治安維持令によって拘束された活動家たちの解放に消極的な姿勢を採り続けつつも,表向きはイギリスに抵抗する姿勢を見せて市民からの歓心を買おうとしていた。もちろん,こうしたスキームはいつまでも続くはずもなかった。現地のイギリス人官僚たちは PAP内の華語集団に対して一定の理解を示しており,事態は複雑であったのである(Harper 2001: 31-39)。
82 アジア・アフリカ言語文化研究 95
ない公正な社会をつくりあげるための文化的基盤を身につけているとしていたのだ。
イギリス帝国と新連邦の構想シンガポール PAP政府の目論見は,本稿序章でも述べたとおり,庇護者であるイギリス帝国の強い支持を得て推進されることになった。1960年代初頭,イギリスは同盟国アメリカ合衆国とのパートナーシップを梃子として地球規模の勢力であり続けることを志向しており,それゆえ,アメリカが望む東南アジアへの関与の継続は重い課題となっていた。当時,東南アジアは冷戦の最前線となろうとしていた。インドシナでは内戦が続き,東南アジア条約機構 SEATO: South East Asia Treaty Organizationが様々な戦争のシナリオを検討していた。イギリス本国はインドシナに軍隊を派遣していなかったが,その背後のシンガポールにコモンウェルス軍を駐留させてこれに備えていた。同地は東西交通の要衝であり,帝国の極東の拠点であった。イギリス帝国はアメリカとの協力関係を維持し地球規模の勢力であり続けるためにこのシンガポール基地を維持し続けたのであった30)。ただもっとも,イギリスにすればそうした状態は長く続き得るというのにほど遠いものでもあった。第 1章で見たように,イギリス帝国はシンガポールに内政自治を付与していた。さらに,自立を求める同島民衆の要求を容れ,帝国は次の段階に移るべく 1963
年に次の憲法の見直しに入ることも約束していた。ところが,シンガポールには華語集団の勢力拡大,非合法共産党の彼らへの浸透といった事情があった。そのまま行けば同島が単独で独立して共産化し,イギリス帝国はその基地を失いかねないとも考えられた。そのような状況下,とりあえず,イギリス帝国の庇護下にあるマラヤ連邦がシンガポールとより強い連携を結んでいくのが望ましい,イギリスはそのように考え出したのである31)。この構想を推進するにあたっては障害もあり,当初,それは克服不能とさえ考えられうるものでもあった。マラヤ連邦はシンガポールと同様イギリス帝国を後ろ盾とした反共国 家でありかつ英語を公用語とする国家であった が,政府与党・連盟党がシンガポールとの合同にきわめて消極的であったのである。序章で述べたように,連盟党はUMNO,MCA,MICの三党から構成された政党であったが,その盟主は先住人であるマレー人の地位を守ることを掲げたUMNOであった。UMNOは国語であるマレー語が政府などにおける公用語となるべきことを主張していた。そうしたUMNO主導のマラヤ連邦政府には単純に半島と同島が合同するというシナリオは次のような理由から受け入れられるものではなかった。1960年当時,マラヤ連邦の人口は,概数で八百万人。その内訳はマレー人四百万人,華人三百万人,その他百万人とされ,人口的にはマレー人と非マレー人とが拮抗して
30) 当時,イギリス政府は内閣に委員会を設けて東南アジア関与のあり方について議論を行っていた。焦点の一つとなったのは東南アジア関与の意味であった。シンガポール基地の駐留費用はイギリス海外軍事支出の約半分にまで達していた。東南アジアにこれ以上支出を増やすことは経済的な見地から見て正当化しえないが,中国に対する核抑止力に貢献することは,アメリカやコモンウェルス諸国への影響力,共産主義を阻止する大国としての地位の見地からして肯定できる,というのが最終的な考え方であった。Final Report, Committee on Future Developments in South East Asia, DSE(60)30(Final), 3 November 1960, CAB134/1645, NAUK. シンガポール基地は核抑止力の要であり,この考えからすると,絶対に譲れない極東の拠点であった。
31) イギリスは半島とシンガポールの政治統合を究極的には最も望ましいと考えていた。ただ,シンガポールがマラヤ連邦に併合された場合にはイギリス軍基地の利用の制限が予想されるため,早急な政治統合そのものには懸念があった。“Possibility of an association of the British Borneo territories with the Federation of Malaya, and Singapore,” Memorandum by Mr. Macleod for Cabinet Colonial Policy Committee, CPC(60)17, 15 July 1960, CAB134/1559, NAUK, BDEE, Series B, Vol. 8, No. 25.
83鈴木陽一:シンガポール共和国の建国について
いた。当初,PAP政府は単純な馬新合同を志 向していたが,そうなれば,新連邦においては華人がマレー人を人口で上回る多数派を形成し,連盟党の掲げる国家像とその支持基盤が大きく揺らぐことが予想されたのである32)。さらに言えば,当時のUMNO指導部がシンガポールとの合同とは異なる連邦拡大の思惑を抱いていたという事情もあった。1959年,連邦議会下院議員・各州議会議員総選挙が実施されたが,連盟党はマレー人の集住率の高いクランタン州とトレンガンヌ州の二州―これら半島東岸地域はムラユのハートランドとも呼ばれる―で敗北し,両州政府のコントロールを失った。勝利を収めたのは汎マラヤ・イスラム党 PMIP: Pan-Malayan Islamic Partyであった。彼らはマレー文化とイスラム教を重んじるとともに同じ言葉bahasaを共有するインドネシアへの強い親近感を露にした政党であった(Means 1976: 229-230)33)。この頃のマレーナショナリズム全体の状況については次章で詳しく述べるが,PMIPに対抗するため,UMNOにはより広い支持層を開拓しなければならないという状況にあったことは重要である。実際,当時,UMNO指導部が強く望んだのは,イギリス領ボルネオと合同することでその先住人
―言語的にはその多くが広い意味でマレー系であった―の支持を取り込んで政権基盤を強化しようというシナリオであった34)。早くは 1958年 12月,トゥンクは彼がボルネオとの統合について強い関心があることを前東南アジア総弁務官であるマルコム・マクドナルドMalcolm MacDonaldに打ち明け,さらに 1960年 6月にも彼は同件についてイギリス側に打診したのであった35)。いわゆるグランド・デザイン grand design がイギリス政府内に浮上し,これが推進されていくことになったのは,まさにそうしたなかのことであった。このグランド・デザインとはマラヤ連邦,シンガポールにイギリス領ボルネオ植民地も加えた政治的連合体であった。これならばマラヤ連邦にも受け入れられやすいと考えられた。ボルネオの広い意味でのマレー系住民も加わることで,新連邦の人口において広い意味でのマレー系住民が過半数を占めることが予想された。そうとなれば,UMNO率いる連盟党は政権基盤を強化できるはずであった(Jones 2002: 61-64)。1961年 4月 18日,植民地相から出されたグランド・デザインの提案にイギリス政府内閣植民地政策委員会は次のような結論を出した36)。
32) UMNOが連盟党内において優越的な地位を獲得し得たのは,マレー人の人口が非マレー人の人口を上回っていたことのほか,マラヤ連邦が選挙制度として小選挙区制を採用していたことも大きい。連盟党は共通のマニフェストを掲げ,各選挙区に一名の候補者を立てて戦った。マレー人が多く暮らす選挙区においてはUMNOの候補,華人が多く暮らす選挙区においてはMCAの候補,インド人が多く暮らす選挙区においてはMICの候補が立てられた。一見すると三党は対等のように見えたが,重要なことは,そうしたなか,MCAやMICの候補は最大エスニック集団であるマレー人の支持を背景としたUMNOの後ろ盾がなければ,多くの場合,当選しづらい―しかしその逆はそれ程ではなかった―ということであった。こうした力学は 1959年の下院議員総選挙の過程において明らかになった。
33) インドネシアではマレー語が共通語として使われ,これがインドネシア語となった。34) 現在のマレーシアでは,半島のマレー人ほか先住人も含め,これら先住人はブミプトラ
Bumiputera(土地の子)という呼称で呼ばれるようになっている。35) Note by Malcolm MacDonald of his talk with Tunku Abdul Rahman on 20 December, 22 December
1958, DO35/10019, NAUK, BDEE, Series B, Vol. 8, No. 7. Memorandum by Lord Perth recording Tunku Abdul Rahman’s proposal for closer association of independent Malaya and British dependencies in Southeast Asia, 10 June 1960, CO1030/1126, NAUK, BDEE, Series B, Vol. 8, No. 22. マラヤ連邦のボルネオ進出への渇望がマレーシア構想の起源にあったことを強調する研究は 1970年代から存在する(Mohamed Noordin 1973)。
84 アジア・アフリカ言語文化研究 95
提案についてはおおよその合意を見ることになった。提案は防衛の観点から見て受け入れられるし,この地域における将来の防衛枠組みと部隊の配備について考える際に考慮に入れる必要があるものと言えるだろう。また,提案は長期的に見た場合にマラヤの利益にもなる。しかし,マラヤの首相は北ボルネオ諸邦への影響拡大を望んでおり,目下のところ,シンガポールを含む連邦の拡大には反対である。華人が多数派を占めることでマラヤの政治的安定が脅かされると感じているのである。しかしながら,この点については,どのようなかたちの政治結合をめざすかということで随分違ってくるはずである。
帝国史研究の言葉を用いれば,イギリス帝国はここで自らを非公式化してマラッカ海峡地域に新たなジュニア・パートナーたるマルチエスニックな新連邦を創設し,そこに東南アジア有数の軍事力を駐留させることでアメリカの外交政策を支援し,そのことを梃子として地球規模の勢力としての地位を維持しようとした,と言い得るだろう。帝国領の現地協力者としては,新連邦を指導することになるであろう連盟党―マレー人政党UMNOが主導―と引き続きシンガポールに堅固な基盤を保持し続けるであろう PAP―英語を操るプラナカンが主導―とが想定され
た。グランド・デザインとはそのようにも解釈され得るものであった37)。グランド・デザインの実現に向けて,マラヤ連邦側への説得にあたったのはリー・クアンユウその人であった。トゥンクが単純な馬新合同をかたくなに拒否したため,1961年初頭までにグランド・デザインでも実現できるならそれがよいと考えるようになり,これに熱心に取り組むようになっていたのだ38)。リーはイギリスの意を受けて具体的な統合案を文書で提案した。同案はマラヤ連邦市民,シンガポール州市民はそれぞれの地のみで投票できるとすることを提案するなど,後のマレーシア憲法の骨格を含むものでもあった39)。そのうえで,シンガポールを放置し続ければ,華語集団の増長が続き,親共政府の樹立が避けられないこと,早急な連邦,シンガポール,ボルネオの合同こそが連邦の利益にかなうことをトゥンクに説いたのであった。もちろん,マラヤ連邦政府にとってマラヤ共産党は仇敵であり,一衣帯水のシンガポールに親共政府が成立することは国家の存亡に関わる脅威とも言い得るものであった。トゥンクはその場で説得されたわけではなかったが,結局はこれを受け入れる意向を固め,5月 27日,自らの構想としてこれを公表した。このときの様子について,その前日,在クアラルンプール・イギリス高等弁務官は本国に次のような報告を行っている40)。
36) “Possibility of an Association of the British Borneo Territories with the Federation of Malaya and the State of Singapore,” Memorandum by the Secretary of States for the Colonies, CPC(61)9, 14 April 1961, CAB134/1560, NAUK, BDEE, Series B, Vol. 8, No. 34. Minute of a Meeting, Cabinet Colonial Policy Committee CPC4(61)1, 18 April 1961, NAUK, BDEE, Series B, Vol. 8, No. 35.
37) イースターの研究参照(Easter 2004: 5-12)。38) Letter from Lord Selkirk to Ian Macleod, 30 January 1961, CO1030/978, NAUK. リーはその前
年からグランド・デザインに関心を持っており,ボルネオへの訪問も行っていた。シンガポールとボルネオとは貿易上の結びつきが強く,そのことには強い関心があったようである。“Forthcoming visit of Mr. Lee Kuan Yew to the Borneo territories,” Note by H. T. Bourdillon, 14 September 1960, CO1030/977, NAUK.
39) “Paper on the Future of the Federation of Malaya, Singapore and the Borneo Territories,” Memorandum by Lee Kuan Yew for the Government of the Federation of Malaya, 9 May 1961, NAUK, BDEE, Series B, Vol. 8, No. 37.
85鈴木陽一:シンガポール共和国の建国について
ご存知のことと思われますが,リー・クアンユウは最近クアラルンプールを何度か訪ね,グランド・デザインをトゥンクに勧めてきました。一九六三年春にシンガポール憲法が見直しを迎える前に憲政発展のための手掛かりを提案する必要があることに鑑みてのことです。……5月 27日,明日午後,シンガポールにおいて行われる国際記者団との昼食会において次のような文言を含んだ記者クラブ演説を行うつもりであることを,午前中,トゥンクから知らされました。以下がその文言: マラヤ(引用者注:この場合,マラヤ連邦を意味)は一国で孤立していくことはできません。遅かれ早かれ,マラヤはシンガポール,北ボルネオ,ブルネイ,サラワクとある了解を持たねばなりません。……シンガポールを安全かつ建設的に吸収する方法を見出すことがマラヤのためになる,トゥンクはそう理解するようになりました。グランド・デザインはこれを可能にする唯一の方法なのです。
マレーシア構想―グランド・デザインは公表後そのように呼ばれるようになっていった―はこうして現実に動き出したのである。リーたちはその後も新連邦発足に向けた政治の過程において重要な役割を果たした。全体の流れのなか,シンガポールの利益を守ることだけに専念するのではなく,イギ
リス政府やマラヤ連邦政府と連携をとりながら,新連邦が実現するよう全体的な調整に関わった。そのなかでもとくに顕著な功績は,ボルネオの連邦参加への世論を高めるために一役を買ったことであった。本章初めで若干ふれたように,マレーシア形成に先んじ,マラヤ連邦,シンガポール,サラワク,北ボルネオの様々なエスニック集団を背景にした現地政治家たちがマレーシア連帯諮問委員会MSCCと称する会議を四度に渡って開催した。リーはこれに積極的に協力し,会議は大きな成功を収めた。当初,ボルネオ住民の多くはマレーシア構想に必ずしも積極的ではなかった。ボルネオ住民の過半数は広い意味でマレー系に属する人々であったが,必ずしもムスリムではなかった。数だけから言えば,ボルネオ住民のうちムスリムは少数派と言えた。それゆえ,多くのボルネオ住民にムスリム国家と合同することへの躊躇があったのだ。オンキリ James P. Ongkiliの研究が示すように,そうしたなか,この委員会が打ち出したマレーシア構想への肯定的な姿勢はその民意を示したものとして構想を推し進める力となった(Ongkili 1967)41)。その後,紆余曲折を経ながらも提唱から 2年あまりほどの後,ブルネイを除く当事者たちが新連邦の形成で合意し,マレーシアが発足したのは知られての通りである42)。
新連邦が抱えた矛盾以上,PAP政府が半島・シンガポールの
40) Telegram from Kuala Lumpur to Commonwealth Relations Office, 26 May 1961, PREM11/3418, NAUK, BDEE, Series B, Vol. 8, No. 39. なお,その前月,シンガポールでは立法議会のホンリム選挙区補欠選挙が実施され,オン・エングアンOng Eng Guan元市長が左派勢力の支持を得ることで PAP候補を楽々と下していた。このことがマラヤ連邦に危機感を抱かせ,統合を急がせる直接のきっかけとなった(鈴木 1998)。
41) MSCCの経緯についてはガザリの回想録に詳しい。MSCC設立の提案は,長くマレーシア設立に反対してきたステファンが突然に提案したものとされてきた。しかし,これは正確ではなく,イニシアティブはガザリやリーにあったようである。ステファンによる提案はガザリがリーの助けを得てステファンに会議を設立するよう説得した結果であるとされている(Muhammad Ghazali 1998: 56-57)。
42) イギリス公文書公開以降,マレーシア形成過程に関する研究が多数出された。序章を参照されたい。なお,独自の首長制を発展させつつあったブルネイはこれに加わらなかった(鈴木 2015)。
86 アジア・アフリカ言語文化研究 95
歴史的・社会的一体性の感覚に訴えながらもある種のエスノポリティクスを展開し,マレーシアを実現するに至った経緯について見て来た。以下の章では,シンガポールがマレーシアの一州となって以降の連邦・州両政府関係の展開を見ていくことになるが,その前に,ここで一つ,以上を精査して改めて気づかされることについて指摘しておこう。それは,実現した新連邦構想は実のところその参加者の見通しのあいだに微妙な矛盾を抱えていた,ということである。マレーシア構想はイギリス帝国,マラヤ連邦政府,シンガポール政府の三者の思惑が大まかに一致したことで推進された。そこでは,マレーシアが様々なエスニック集団の共存する場となることについては了解があった。ただ,参加者の思惑のあいだには微妙な亀裂もあったのである。マラヤ連邦政府はもともとマレーナショナリズムを補完する勢力をボルネオに確保したいという一念から連邦拡大に着手していたが,シ ンガポール政府は,上に見てきたように,英語教育を受けた者たちが連邦全体を指導する 新国家像を描いていた。マレーシアとは「ムラユの多島海」を意味する語であったが,PAP政府が目指したのは事実上「プラナカン 国家」ともいうべき,様々なエスニック集団が混在するなか,英語を操るプラナカンが国政における主導的地位(ないしその一角)を占め,彼らの文化が支配的な国家であったのである43)。こうした参加者のあいだの矛盾はその後の新連邦の国内政治に深刻な影響を及ぼしていったように思われる。実際,マラヤ連邦政府(マレーシア成立後,
同連邦政府を実質的に引き継ぐ)とシンガポール政府とのあいだの亀裂は―当初はエ スノ政策をめぐってではなかったが―マレー
シアの発足が迫る頃から徐々に目立つようになり,その後,拡大することになった。新連邦の成立に先立つ 1963年 2月,シンガポール政府は外部からの圧力を示唆しながら,リム・チンシオンを含む親共左派を一斉拘束し,これによって島内における権力基盤の強化に成功した。マレーシア構想が進行する過程において,PAP左派は党を割ってバリサン・ソシアリス(社会主義戦線)Barisan Sosialisを結成し,新連邦形成に激しい抵抗を試みていた。シンガポール政府はこれら左派指導者・運動員百名以上を拘束したのだ。しかし,そのことは両政府共通の敵であるシンガポールにおける共産主義勢力が退潮したことを意味し,連邦とすれば同州を自らに留め置く―あるいは州政府との友好関係を維持する―動機づけを低下させるものでもあった44)。実際,これ以降,両政府の関係は対立のトーンを強めていくことになった。新連邦設立へ向けた詰めの経済交渉は難航し, 連邦・州のあいだの財政分担・共同市場スキー ムづくりをめぐる攻防は未決のまま連邦成立後へと持ち越されることになったのである。さらに言えば,マレーシアの設立はプラナカンたちに皮肉な帰結ももたらした。新連邦の成立は PAP政府にすればそれまで自らの庇護者となっていたイギリス帝国との関係を弱めるように働くものでもあったのである。確かに,マレーシアはイギリス帝国と PAP政府との協力関係の産物とも言い得るものであった。しかし,その設立以降,それまでいかなる事情があったにしろ,新連邦におけるイギリス帝国の一義的なパートナーはマレーシア連邦政府となり,シンガポール州政府は二義的なパートナーでしかありえなくなった。新連邦の安寧こそはイギリス帝国が最も
43) もともとマレーシアMalaysiaとは,マレーMalay―マレー語ではムラユMelyu―にネーソスnesos―ギリシア語で島嶼の意―を加えてつくられた造語で,ムラユの島嶼―島々,あるいは多島海―を意味する。
44) 一連の措置を受け,シンガポールにおけるマラヤ共産党の勢力は退潮することになった。現地の責任者であった方壮壁は,1961年,共産党地下組織は安全を期して引き上げを開始し,1964年までに 50名が同島からの脱出に成功したとしている(Fong 2008: 172)。
87鈴木陽一:シンガポール共和国の建国について
重視するところとなったのである。さらに言えば,いったん身を引きだしたイギリスがいつまでも東南アジア関与を続ける保証はないという問題もあった。厳しい財政問題を抱え,イギリスはそうした余裕を失いつつあったのである。PAP政府が弱まりつつあったイギリスとの特別の関係を利用して「プラナカン国家」をつくりあげるのだとしても,彼らに残された力,それに時間的余裕はそれほど多くはなかった。
第 2章 連邦・シンガポール州関係の展開 1 早々の対立から暴動発生へ
1963年 9月 16日,マレーシアは祝祭ムードのなか成立したが,知られているとおり,新連邦は発足当初から政治的に不安定な状態に置かれることになった。まずもって,周辺国であるインドネシア,フィリピンがボルネオのマレーシアへの編入を認めようとしなかった。インドネシアは編入が島民の自決権に反すると主張し,フィリピンは自らのサバ領有を主張した。周辺諸国にとっては,イギリス帝国が後ろ盾となった強大な国家の誕生は脅威ともとらえることができた。簡単に許容されるべきものではなかったのだろう。すでに 1950年代後半,イギリス・アメリカは左傾化を続けるインドネシア・スカルノSukarno政権へ反旗を翻そうとした反乱勢力への支援を行い,さらにマラヤ連邦自体も1957年の独立以来イギリス帝国の軍事的な後ろ盾を得てインドネシアと鞘当てを続けていたという経緯もあった(Jones 1999, Liow 2005)。それゆえ,マレーシア構想は周辺国,
とくにインドネシアから強い反発を呼んだ。同国は「対決政策」を実施し,武力紛争を起こすに至った45)。加えてさらに,マレーシアの存立基盤をより深刻に揺るがし続けたのは,マラヤ連盟党率いる連邦政府とシンガポール,サラワク,サバの新参諸州の政府との関係の不安定さから来る絶えざる軋轢であった。新参諸州は住民のエスニック構成も社会経済発展の程度も旧来の連邦構成諸州と大きく異なっていた。そうした事情を背景に,旧マラヤ連邦政府が実質的に引き継いだ連邦政府と新参諸州政府とのあいだには政治的な抗争が生じることになった。本章では,マレーシアが発足前後から内外の困難に遭遇して揺れるなか,連邦政府とシンガポール州政府とのあいだに深刻な対立が発生し,これが先鋭化していく過程について見る。
連邦と新参諸州マレーシア設立後の連邦とシンガポール州との関係の展開を見ていく前に説明しておくべきことがある。連邦政府と新参州政府とのあいだに何らかの軋轢が現れるであろうことは,連邦の設立交渉時からある程度予想されており,そのため,当事者は関係を調整するための仕組みをつくることで合意していたということである。連邦憲法は新参諸州それぞれの固有の利益を保護し,また互いのあいだのハンディを補うため,在来諸州にない特別の権限を新参諸州に与えるとともに,新参諸州住民の連邦政治へのアクセスのあり方に工夫を凝らしたのであった。こうして,発足当
45) 「対決政策」については,これまで長く,その主要な起源をインドネシアに求める言説が強かった。1960年代前半,スカルノ政権は二大勢力である国軍とインドネシア共産党との微妙なバランスの上に立っていた。そうしたなか,外からの脅威は両者の関心を外に振り向けて国内で表立った対立を自重させるうってつけの捌け口でもあったとされる。長く定番とされて来たマッキーの研究などでもこうした点が強調されている(Mackie 1974)。ただ,最近は史料公開も進み,インドネシア側からの要因のみならず,英米側のインドネシア側への敵意が大きな要因となったことも強調されるようになっている。「対決政策」の起源について英米側の問題を強調した研究としては,若干論理に飛躍したところがあるが,ポールグレインの研究がある(Poulgrain 1998)。
88 アジア・アフリカ言語文化研究 95
時,連邦は三種類の州から構成されることになった。第一の種類は従来の連邦構成州,第二の種類は第一の種類の州にない特別の権限―宗教,言語などの事項に関する権限―を享受した上に連邦議会下院に代表を人口に比して過剰に送るボルネオ二州,第三の種類は他州にないより高度な自治を享受した上に連邦議会下院に代表を人口に比して過少に送るシンガポール州であった。社会経済上の発展が遅れていたボルネオ諸州には特別の権限のみならず連邦議会において割り増しされた発言力が与えられた。他方,頭抜けて発展していたシンガポール州には高度な自治が与えられたものの連邦議会においては割り引かれた発言力しか与えられなかった。そうすることで,公平で安定した連邦の運営が可能になると考えられたのであろう。ただ現実には,こうした当事者の努力にもかかわらず,連邦政府と新参州政府とのあいだの関係は想像を遥かにこえる程度に不安定なものとなった。それでは,なぜ用意された仕組みがうまく機能せず連邦と新参諸州とのあいだに軋轢が続くことになったのか。理由はいくつかあったと考えられるが,一つには,新参諸州に与えられた当の特別の地位のあり方についてマラヤ連邦政府(マレーシア成立後,同連邦政府を担った)と当該諸州政府とのあいだで十分な合意が成立していなかったことが指摘できるだろう。連邦とボルネオ二州との関係においては,連邦政府がボルネオ二州が特別の権限を保持し続けることへ強い不満を抱えていた。とくにボルネオ二州が英語を公用語にし続けようとしたことには連邦政府内に不満が強く,そのことは後に両者のあいだの争点
となっていった46)。連邦とシンガポール州との関係においては,前章で若干述べたように,設立交渉において重要な点で話がまとまらず,連邦・州関係のスキームは流動的な状態のままとなっていた。マレーシア設立を定めたマレーシア協定付属文書ではシンガポール州の連邦政府への財政貢献は 1965年以降に見直しがされるとされた。また,共同市場形成も漸進的に進めるとされた47)。連邦は骨格分野の設計図に合意がないまま出発していたのである。さらに,用意された仕組みがうまく機能せず軋轢が続いた理由,いま一つ,より根深い問題として,連邦の拡大にあわせて代議政体の制度が拡大されたものの,これを実際に運用する政治の過程がうまく整備されていなかったことも指摘できるだろう。マレーシアには,前章で述べたように,マラヤ連盟党率いるマラヤ連邦政府がマレーナショナリズムを補完する勢力を新参諸州―とくにボルネオ二州―に確保したいという思いから連邦拡大をはかってつくられたという経緯があった。実際,マレーシア連邦政府は最大勢力にして半島諸州に支持基盤を持つマラヤ連盟党が担うことになった。しかし,マラヤ連盟党が確保できたのはそこまでで,彼らはその当初の思惑に反して新参諸州にほとんど支持基盤を築くことができなかったのである。ボルネオやシンガポールでは,マレーシア設立に先立ち,現地指導者たちがそれぞれ独自の政党を発足させていた。シンガポールの状況についてはすでに概要を述べたとおりであるが,ボルネオ二州においても半島から自立した現地政党の設立が進んだ48)。それら諸政党
46) マレーシア発足後,連邦政府は残留して州政府を支えるボルネオ旧植民地官僚の動きに神経質になる局面もあった。イギリス人植民地官僚たちの一部は,引き続き,ボルネオの政党指導者らを影ながら支援し,結果としてボルネオへの連邦政府の介入に抵抗する立場に立った。そのことについては第 4章でみる。
47) Annex J: Agreement between the Governments of the Federation of Malaya and Singapore on Common and Financial Arrangements, Agreement Relating to Malaysia, 9 July 1963, United Nations Treaty Series, no 10760-10761.
89鈴木陽一:シンガポール共和国の建国について
の指導者のなかには連邦設立過程において植民地政府構成員としてマラヤ連邦政府と対等な立場から交渉を行った者も多く,彼らは重みのある政治家たちであった。しかも,ボルネオ二州選出の議席数が割増しされた結果,連邦議会下院議員の半数近くがボルネオ,シンガポール出身議員で占められることになっていた。このことは新参諸州の政治家たちが団結して旧マラヤ連邦の野党勢力をうまく取り込めば連邦政府を奪取しうることをも意味していた。そうとすれば,連邦政府としては混乱を避けるべく,これら新参諸州の政治的意思を連邦に入れて政府を運営する仕組み―逆の言い方をすれば,連邦政府が新参諸州にその支持基盤を広げる仕組み―をつくりあげる必要があるはずであった。しかし,ことはそう簡単に運ばなかったのだ。もちろん,連邦政府の政権運営についてはマラヤ連盟党と新参諸州の現地政党とのあいだに何らかの枠組みをつくろうという動きがないわけではなかった。グランド・アライアンス grand alliance構想があったのである。マレーシア形成の過程において,マラヤ連盟党はこれに積極的に関わった現地有力政党がバンドワゴンし,各州に連盟党を形成することを促していた。実際,ボルネオにはサラワク連盟党 Alliance Party(Sarawak),サバ連盟党 Alliance Party(Sabah)が形成され,これらが各州政府を担う見込みとなった。グランド・アライアンスとはこれら各地の連盟党がさらに合同して形成する連盟で,それは
将来的にはより高度な融合をめざす意図も秘めた連合体でもあった。1963年 3月 30日から 31日にかけてマラヤ連盟党はこれら諸政党を招待してグランド・アライアンス大会を開催した。会議の目的はすべての政党が加盟するマレーシア連盟党―すなわちグランド・アライアンス―の創設の可能性を探ることにあった。さらにこのとき,トゥンクはUMNOのメンバーシップをボルネオの非マレー先住人に開放することも提案した49)。もしこれが実現されればUMNOが不動の最大与党の座を確保し,政権基盤が強化されるのは確実であった。ただしかし,この構想は実現に時間がかかることが予想された。すでに見たように新参諸州の現地政党はそこに独自の基盤を築いており,その地位を容易に放棄するとは考えづらかった。ボルネオ先住人政党はムスリム系政党と非ムスリム系政党とに分かれており,それをどう統合するのかという問題もあった。そうした状態のなか,連邦からの無用な刺激によって連邦・州関係が険悪なものになることは避けられるべきであった。さらに,UMNO側においてはメンバーシップを非マレー人に開放することに抵抗が発生することが予想された。同党の名称変更が要求される可能性もあり,そうとなれば,それは同党支持者のアイデンティティにもかかわるきわめて論争的な問題に発展するに違いなかった50)。それゆえマラヤ連盟党とこれら新参諸州の現地有力政党―とくにサラワク連盟党,サ
48) 1963年 9月時点において,サラワクにサラワク人民連合党 SUPP: Sarawak United People’s Par-ty,サラワク国家党 PANAS: Parti Negara Sarawak,サラワク国民党 SNAP: Sarawak National Party,サラワク民衆党 BARJASA: Barisan Rakyat Jati Sarawak,サラワク華人協会 SCA: Sarawak Chinese Association,サラワク保守党 PESAKA: Parti Pesaka Sarawak,サバに統一全国カダザン人組織UNKO: United National Kadazan Organization,統一サバ国民組織USNO: United Sabah National Organization,サバ国民党 SANAP: Sabah National Partyなどの諸政党が活動していた。
49) The Straits Times, 31 March, 1 April 1963. エドウィン・リーの研究(Lee 1976: 194-197)。50) 名称変更は 1964年のUMNO大会において議題に上る予定であった。党名をUnited Malays and
Native Organizationに変更しようとしたのである。しかし,これはその名称からマレー人こそが国民であるという含意を取り去るものであり,抵抗が強く議題にも出せなかった。Letter from R.R.G. Watts to P. Jenkins, 22 October 1964, DO169/356, NAUK.
90 アジア・アフリカ言語文化研究 95
バ連盟党―が当面のあいだ甘んじることになったのは互いの領分を守る,という棲み分けの枠組みであった。すなわち,一方で,連邦政府は引き続きマラヤ連盟党が担うこととされ,他方で,州政府はこれら現地政党が担うこととされた。連邦政府の運営について言えば,連邦発足当時,マラヤ連盟党だけでは議会の過半数を制し得なかったため,サラワク連盟党,サバ連盟党には連邦議会でマラヤ連盟党がつくる連邦政府を全面的に支持することが期待された。PAPの立場は不明確であったが,最初の連邦議会ではクロスベンチが宛がわれ,準与党の立場が期待された。また,新参諸州の政府の運営については,マラヤ連盟党は現地政党との友誼を重んじ,各州政府の運営に口を出すことを自重した。とくにサラワク連盟党,サバ連盟党との友好関係は重んじられ,マラヤ連盟党はボルネオに進出しようとさえしなかった。原則,かつて対等な立場で話し合った政治家たちの政府をそのまま連邦のなかに温存しようとしたのであった。しかしながら,こうした棲み分けの枠組みは一見すると理にかなった仕組みのように見えたものの,よくよく考えれば,当面維持することさえ困難な原則と言えた。州政府が連邦政府とのつき合いを断って州を運営することは,連邦政府が様々な管轄権,予算を握っていることに鑑みれば不可能であることは明らかであった。さらに,同様なことは連邦の運営についても言えた。連邦政府も新参諸州(直接にはその選出議員)からの安定的な支持が確保できなければ自らの運営ができなかった。しかし,それにもかかわらず,棲み分けの原則の下,連邦政府がその支持を新参諸州に広げる仕組みをつくりあげることは非常に微妙な問題となっていた。それゆえ,マ
ラヤ連盟党率いる連邦政府はマレーシア発足後徐々に政権基盤の脆弱さを露呈していくことになったのである51)。とくに問題であったのは,頼りにしていたサラワク連盟党,サバ連盟党の先住人主導政党がムスリム政党と非ムスリム政党とに分かれて内部抗争を始めた,ということであった。何度も述べるように,マレー人主導のマラヤ連盟党が華人の多いシンガポールの参入を許容してまで連邦を拡大したのは,それと同時に広い意味でのマレー系住民である先住人の多いボルネオ二州も参入することで連邦政府の政権基盤が補強されると考えたからであった。その先住人がムスリムと非ムスリムとに分かれて抗争を始めたのだから,そうした事態はまったくの本末転倒と言えた。マラヤ連盟党政府はマレーシア形成でむしろ政権基盤を弱めることになってしまったのであった。連邦・ボルネオ関係において最初に表面化した問題はサラワク州政府人事の問題であった。マレーシア発足に先立って,サラワクでは州議会議員が選出され,その結果,非ムスリム先住人主導の二政党が与党第一党,同第二党の地位を占めることになった。ここで,非ムスリムのトゥメンゴン・ジュガ Temenggong Jugahが州元首Yang di Per-Tua Negriに就こうとしたところ,連邦政府がこれに反対したのであった。やはり非ムスリムのステファン・カロン・ニンカン Stephen Kalong Ningkanが首席大臣に就くことになっていた。連邦政府は非ムスリムが二つの重要ポジションを独占してしまうことを好まなかったのである。結局,これは連邦政府がジュガを連邦政府閣僚であるサラワク問題担当大臣に招くことで妥協が図られたが,このときに顕在化した先住人間の亀裂は,その後の 1965年,土地法改正をめぐる州政治に連
51) 後述のように,連邦発足時,またその後,サラワク連盟党,サバ連盟党それぞれが連邦政府にサラワク問題担当大臣,サバ問題担当大臣を送り込むことになった。ただ,これは,連邦政府がボルネオ二州の政治的意思を汲んで政権運営をする仕組みとしては不足感が否めないものであった。2人だけで閣議の決定に影響を与えることは困難であった。
91鈴木陽一:シンガポール共和国の建国について
邦からの介入を招く伏線となった52)。他方,サバにおいては,1964年 6月,首席
大臣を務めるドナルド・ステファン Donald Stephensが非ムスリム先住人を糾合した統一全国パソ・モモグン=カダザン人組織UPKO: United National Pasok-Momogun Kadazan Organizationを結成してサバ連盟党のなかでムスリムや華人との対立を深め,そのことは連邦の介入を招くきっかけになった53)。UPKOは非ムスリム先住人がリーダーシップを握った政党ではあったが,彼らはメンバーシップをムスリムや華人にまで開放して党勢の拡大を目指した。このため,ムスリムや華人は連邦政府と緊密な関係を築くことでこれに対抗しようとしたのであった。同年 11月には,ステファンの推す官房長人事についてムスリム主導政党や華人主導政党が反対し,これを任命できなくなる異常事態も発生した(Luping 1994: 134-143)。この危機もステファンの連邦政府への入閣によってひとまず収まることになったが,これでサバ連盟党内の対立が治まったというわけではなかった。
マレーシア発足直後の連邦・シンガポール州関係連邦政府とシンガポール州政府とは,連邦政府が自らの安定の基盤と期待していたボルネオ二州との友好関係がかように揺らぎ続ける傍ら,1963年 9月のシンガポール州議会選挙をきっかけに潜在的な対立を表面化させていくことになった。同月,マレーシア発足を前に選挙が公示されると,PAPはマレー
シア形成に激しく抵抗した野党バリサン・ソシアリスのみならず同島に本格進出をめざしてきた連盟党とも選挙戦で激しく争うことになったのである。以上のことについては,これを詳しく見ていく前に説明しておいたほうがよいことがある。すでにマレーシア設立までの過程において,PAPと連盟党―とくにこれを構成するMCA―とは互いのあいだに御し難い利害対立があることを確認しつつあった,ということである。もともとシンガポールにおけるMCA,UMNOの活動の歴史は PAPよりも古く,両党と PAPとはそれまでの二度の選挙戦で相見えた間柄であったという経緯もあった。とくに PAPとMCAとはともに華人を主要な支持基盤としており,両立し難い関係にあったと言い得た。1959年選挙においてはそのことが顕著に現れ,PAPが大勝する傍ら,MCAは議席を失っていた54)。さらにマレーシア設立への詰めの政府間交渉において,MCA総裁で財務相のタン・シュウシン Tan Siew Sinが連邦政府の経済財政政策を優先し,シンガポール政府に厳しい姿勢で臨むと,対立は白日の下に曝されることになった。そもそも第一次産業を主たる産業としていた連邦が豊かな自由貿易植民地を取り込むこと自体が困難な作業であったが,対立にはそれ以上の含意もあった。タンの強硬姿勢は自分たちMCAが連邦の経済運営を担っていること,シンガポール華人が引き続き繁栄を享受したければ自分たちに協力すべきことをシンガポール華人たちに知らしめようとしているようなものであったからであ
52) 州政府人事問題についてはレイの研究,ガザリ・シャーフィー回想録を参照(Leigh 1974: 82-83, Muhammad Ghazali 1998: 439-445)。1965年 5月,ニンカンが土地法の修正案を州議会に提出すると,ムスリム勢力などはこれに強く反発した。同法はそれまで制限されていた先住人の土地の取引を緩和するものであった。ニンカンたちが主に利益を得ると考えられたのである。このとき,連邦は州政治に介入の姿勢を示した(Leigh 1974: 86-88)。
53) UPKOはUNKOと統一全国パソ・モモグン党 PM: United National Pasok Momogun Partyの合併によって結成された。
54) ただし,1959年から内政自治を担っていた PAP自治政府の下,UMNO及びその友党である SPAはマレーシア設立支持の立場から要所要所で政府の議会運営を助けたという実績は持っていた。
92 アジア・アフリカ言語文化研究 95
る55)。結局,シンガポール州の連邦財政への貢献の問題,共同市場形成の問題などで折り合いが会わず,問題解決が先送りされたことは前章末に記したとおりである56)。
MCAは選挙戦を前にシンガポール支部への梃入れをはかり,MCA,UMNO,MICそれぞれの支部とリム元首席大臣率いるシンガポール人民連盟 SPA: Singapore People’s Allianceの四党をもってシンガポール連盟Singapore Allianceを結成した(Lau 1998: 21-22)57)。このシンガポール連盟が全 51選挙区中 42選挙区に候補者を立てて PAPに挑むことになった。もちろん,当時のマラヤ連盟党の方針はマレーシア形成に積極的であった政党が集ってグランド・アライアンスを形成しようというものであり,トゥンクとすれば,本来最も望ましい選択肢は PAP,MCAを始めとする政党が共同戦線を組むことであった。しかし,それまでの 4年間の実績を考えれば,PAPとしては基盤の弱い諸政党にわざわざ議席を宛がうなどという一方的な
譲歩は受け入れ難かった。リーはグランド・アライアンスへの参加を拒み,独自の道を歩むことにしていたのである58)。激しい選挙戦が戦われたが,結果は PAPが 37議席,バリサンが 13議席を獲得する傍ら,シンガポール連盟が全敗で,そのことはマラヤ連盟党を大いに刺激することとなった。MCAはひどく傷ついたが,UMNOのショックも大きかった。UMNOはマレー人が多く居住する選挙区に参戦したものの,そこで PAPに敗北したのであった。UMNO書記長サイード・ジャファール・アルバールSyed Ja’afar bin Hassan Albarは PAP政権がシンガポールのマレー人を抑圧している旨を非難し出し,対立は PAP対UMNOの様相も帯び出すことになった(Lau 1998: 48-53, Lee 1998: 552)59)。ただし,このときの諍いはそれ以上拡大することなく,その後しばらくのあいだ,連邦政府とシンガポール政府は気を取り直したかのごとく平穏な関係に立ち戻ることになっ
55) 当時のマラヤ連邦においては,政治全般の主導権はUMNOが握りつつも,経済運営はMCAが責任を持つという大まかな了解があった(金子 2001: 150-162)。それゆえ,トゥンクはマレーシア設立にあたってもタンに経済交渉を任せ,それに介入しようとはしなかった。Telegram from Kuala Lumpur to Commonwealth Relations Office, 2 May 1963, DO169/261, NAUK.
56) タンの研究参照(Tan 2008: 123-150)。MCAと PAPとは経済財政政策のあり方をめぐって激しく対立した。MCAは連邦の経済財政を担当してその利益拡大を狙ったが,PAPはシンガポールの経済財政の利益を守ろうとした。
57) もともとMCAはその設立の経緯からして汎マラヤの政党であった。初期においてはシンガポールにおいて度々会議を開催していた。しかし,シンガポールにおける政治基盤自体は弱かった。
58) リーはグランド・アライアンス大会へのオブザーバー派遣の招待を断った。グランド・アライアンスの目的がマレーシアにおける選挙で共同で戦おうというものであるとすれば,これに参加することはできない,と言うのがその理由であった。The Straits Times, 12 September 1963. 連盟党はこのほかにも何度か PAPの懐柔を試みた模様である(Lau 1998: 23-24)。
59) マレーシア発足直前,マラヤ連邦政府とシンガポール政府は新連邦の発足直前においても抜き差しならぬ対立を起こした。マレーシア設立をめぐってはインドネシア,フィリピンが強く異を唱えたため,マラヤ連邦は新連邦発足を延期することで妥協を図ったが,シンガポールやボルネオ二州は頭越しに発足延期が決められたことに反発した。そこで,シンガポールはマレーシア設立予定日にイギリスからの独立を宣言し,新連邦の設立を急ぐようマラヤ連邦政府に圧力をかけたのであった。しかもこの対立は不安定な状況を利用してシンガポール政府がイギリス政府を通してマラヤ連邦政府にあることを強要したことでさらに深刻なものとなった。この頃,マレーシア協定について合意はされたものの未だ法的拘束力のある文書となっていない部分―しかし,シンガポール政府としてはどうしても文書化しておきたい部分―があった。そこで,シンガポールはマラヤ連邦がこれを文書化するよう,さもなくばシンガポール単独で独立するとイギリスを脅し,イギリスからマラヤ連邦に圧力をかけさせたのである。マラヤ連邦はこれを容れざるを得なくなったが,以降,リーは,彼自身の言葉で言うと,「扱いにくい人間だとはっきり認識」されるようになったのであった(Lee 1998: 497-503)。
93鈴木陽一:シンガポール共和国の建国について
た。インドネシアが「対決政策」を続ける傍ら,双方ともマレーシアの団結を乱す行為を慎んだのであった。連邦議会が招集されると,PAPにはクロスベンチが宛がわれた。さらに,1964年 1月,マレーシア設立の正当性を訴えるため,リーはマレーシア政府使節団を率いてエジプト,ナイジェリアなどアフリカ十七カ国訪問の旅に出た。リーのほかサラワク,サバの政治家たちも使節団に加わり,自分たちが進んでマレーシアをつくり出したことを国際社会に宣伝して回ったのであった。これによって,リーは国際的な政治家としての名声を獲得することになったが,隣国からの不承認で広がっていたマレーシアへの疑念も大きく解消され,トゥンクもこれを喜んだ(Lee 1998: 525-539)。束の間であったが,連邦・シンガポール州関係は協調的に推移したのである。
連邦議会下院議員選挙(旧マラヤ連邦)1964年 2月,PAPが来るべき半島での連邦議会下院議員選挙に若干の候補者を擁立する方針を公表して連邦政治へのより積極的なコミットメントの姿勢を示すと,連邦政府とシンガポール州政府との関係は急速な悪化を見ることになった。最後の旧マラヤ連邦議会下院議員選挙からすでに 5年が経過しようとしており,下院議員選挙が半島で行われることが予定されていた。ただ,それまで PAPはこれに参入しないで連邦政府と協力関係を築いていきたい旨を公言(あるいは約束)していた60)。連盟党はリーたちの前言撤回に激しく反発したのであった。
確かに,連盟党の反発に対しては,PAPは連盟党政府そのものに挑戦しようとしたわけではなかった(PAPは選挙参入をもって UMNOを支えるという姿勢を採っていた。)にもかかわらず,連盟党が過剰反応したため両者の関係が悪化した,とする PAP擁護論も成り立つだろう。まずもって,PAPの選挙参入の表向きの目的は連盟党本体への攻撃ではなく,仇敵となりつつあったMCAを牽制することでシンガポール政府の活路を見出すことにあり,その意味で選挙参入はきわめて防御的なものであった,とも言い得た。すでに述べたように,シンガポール州の連邦財政への貢献問題,共同市場の形成の問題などが先送りとなっていた。MCAが連邦政府の経済運営を握り続ける限り,選挙に参入しようとしまいと,両者の再衝突は避けられないことであったのだ61)。さらに言えば,選挙戦における最大の争点はマレーシア形成の是非であり,PAPは自らの主要な敵をこれに反対してきた左翼野党連合・社会主義戦線Socialist Frontと見定めていた,という事情もあった62)。1959年にMCAが華語教育の政策をめぐってUMNOと対立するも妥協して(連盟危機)以降,華人のMCAへの支 持は全般的に低下の傾向にあり,マレー人主導の政治に不満を持つ華人たちのあいだには社会主義戦線の支持が広がっていた(金子2001: 139-140, 189)。それゆえ,PAPは人気の落ちたMCAに取って替わってUMNOを支える立場に立ち,これに対抗したいことを主張した。PAPは連盟党がMCA候補を立てた九の選挙区のみに候補者を擁立し,社
60) PAPはもともと汎マラヤを基盤とする政党として構想されており,連邦政治への参入自体は既定の方針と言えた。しかし,1964年の選挙についてはこれを見合わせると公言していた。ストレイツ・タイムズ紙はリーの言葉として次のことを伝えている。「私は連邦における 1964年の選挙に参加しない」The Straits Times, 29 September 1963. なお,この部分の発言は,現在,シンガポール国立文書館のリー・クアンユウ演説文書に収録されていない。
61) ラウによる先行研究もまた PAPの半島進出についてMCA要因を強調した解釈を採っている(Lau 1998: 95-97)。
62) 社会主義戦線は主に非マレー人に支持層を持つマラヤ労働党 Labour Party of Malayaと主にマレー人に支持層を持つ人民党 Parti Rakyatから構成されていた。
94 アジア・アフリカ言語文化研究 95
会主義戦線の票を切り崩して議席を獲得する姿勢をとった63)。そのうえで,連邦与党におけるUMNOのパートナーとなる姿勢をとったのである64)。しかしながら,こうした擁護論は次のように容易に論駁され得る。PAPはシンガポールにおける教育,雇用,住宅などの政策の成果を強調し,マレーシア全体にエスニック集団の枠組みに囚われないシンガポール型の社会経済政策を導入したいとしていた。そのために半島に暮らす人々の票(とくに社会主義戦線に向かうであろう人々の票)を取り込んで,そこに権力分有のための橋頭保を築こうとした。
PAPの連邦政治への参入はシンガポール政府の利益の防御やUMNOのリーダーシップへの支援以上の意図を持っていた。そうしたことは当時の報道を注意深く分析すればよくわかる。3月 1日,連邦議会が解散され実質的な選挙戦が始まるなか,3月 22日,リーは告示後初の選挙演説において次のようなことを述べている65)。
PAPがマラヤで 9人を当選させれば,シンガポールの 12人も加わって,合計 21人のUMNO以外で最大の単一政党となります。……変革が 1964年に始まれば,1969年に始まるよりも大変動 upheavalは激しくないものですみます。今年の選挙が1969年選挙への準備となっていることはだれもが知っています。今年変革の風を穏
やかに吹かすことができれば,1969年の転覆 upsetはずっと軽減されます。
ここで言う 1969年選挙とは次の連邦議会下院総選挙のことであった。次に下院解散が行われるのは任期満了の年になる 1969年であろうという観測が当時人々に共有されていたのだ。そして,なぜそのときに「大変動」が起こるかと言えば,おそらくはその間に決定的な年である 1967年を迎えるからであった。1957年のマラヤ連邦独立時の取り決めで,独立から 10年を経た 1967年,マレーシア憲法が定めた英語の公用語としての地位は見直し可能となる予定になっていた66)。そして,そのときマレー語が唯一の公用語となって,マレーシアは大きく変わる,と,当時のマレーシア人―とくにマレー人―のあいだにそのように考える向きもあったのである。演説の意は,もしそのときまでに自分たちの主張する社会経済変革が進んでいなければ,人々の不満も爆発し,1969年選挙では大変な変動―もっと言えば大変な社会不安―が起こる,というきわめて煽情的なものであったと解することができる67)。しかも,このときの PAPの選挙への参入を名ばかりのものと見る見方もあったが,この演説を見れば,その目標は連邦議会においてMCAを超える議 席数(シンガポールから送り込まれた議員も含む)を獲得することにあったこともわかる。また留意すべきことは PAPは自らを特定
63) リーは,PAPは 11選挙区に候補を立てたものの,うち 2選挙区にUMNO候補が対立候補として立ったため,これを引き揚げたとしている(Lee 1998: 541-542)。ただ,実際には,引き揚げたのではなく応援のみを止めたようである。2選挙区で PAP候補は若干の票を得たうえで落選した。
64) UMNOはMCAとともにやっていくつもりであり,PAPは必要ない,とトゥンクは公言した。これに対し,マレーシア成功のため,トゥンクのリーダーシップは必要不可欠であるが,MCAのリーダーシップは取って替わられ得る,リーはそうした旨を公言した。The Straits Times, 15 March 1964, 16 March 1964.
65) The Straits Times, 23 March 1964.66) Constitution of Malaysia, Article 152.67) 翌年になってからのことになるが,リーは後述する有名な議会演説において 1967年の「奇跡」へ
の懸念をより明確に述べている。本文の解釈はこのときの演説を参考にしておこなった。Speech by the Prime Minister, Mr. Lee Kuan Yew, During the Debate in the Federal Parliament, on the Motion of Thanks to the Yang di-Pertuan Agong for his Speech from the Throne, 27 May 1965, lky19650527, National Archives of Singapore.
95鈴木陽一:シンガポール共和国の建国について
エスニック集団ではなく都市を基盤としたマルチエスニック政党と位置付けていたということである。リーは 4月 6日の選挙演説において次のようなことも述べている68)。
PAPが支持を集めようとしているのは都市部の華人だけで都市部のインド人,マレー人などはその対象外であるなどと言ったことは一度もありません……都市部人口のおよそ 70パーセントは華人であるけれども,30パーセントはインド人,セイロン人,ユーラシアン,マレー人から成っています……我々が提供しようとしているのはマレーシア都市部すべての人種のための指導者なのです。
PAPは都市を基盤とする政党であることを鮮明にして,都市部のマレー人票をも掘り起こそうとした。PAPはUMNOを支えるというよりは,その支持基盤を切り崩し,これと対等に渡り合える政党となろうとしたのであった69)。選挙は 4月 25日に実施され,今回の選挙の圧倒的勝者はマラヤ連盟党であることが判明した。同党は改選議席 104議席中 89議席を獲得した(図表 1)。この議席数は連邦議会下院議 159議席の過半数にあたり,この結果,理論上,マラヤ連盟党はボルネオ二州, シンガポール州の政党からの支援を得なくとも連邦政府を運営できるようになった(図表2)。選挙戦中野党の社会主義戦線やPMIPは
連盟党主導によるマレーシア設立を非難し, インドネシアとの和解を訴えた。が,その支持は思うほどには広がらなかった。社会主義戦線は大きく票を伸ばしたものの,PMIPはこれを減らし,結果として両党とも議席を大きく減らしたのであった。この選挙において特筆すべきことは,
UMNO主導のマレーナショナリズムが「対決政策」に対抗する過程を通してナショナリズムとしての正統性を確立し,半島における連盟党の支持基盤の強化が進むことになったということであった。実のところ,マレーナショナリズムは東南アジアのナショナリズムのなかでは後発のナショナリズムにあたり,インドネシアナショナリズムから強い影響を受けて発展してきたという歴史を持っていた70)。それゆえ,半島においても 1960年代初頭までインドネシアナショナリズム指導者のスカルノ大統領の人気は大変に強かった。前章でも若干述べたように,PMIPなどはインドネシアへの強い親近感―半島のマレー人は大インドネシアを構成する一員とも位置付けられた―を表明し,彼らはマレー人のあいだで一定の支持を得ていた。さらに,こうした事情に加え,UMNOが華人たちとの妥協のうえに政府を維持している点には不満を持つ者も多かった。マレーシア形成前,同党はマレー人のあいだにおいて盤石な支持を集めているとは言い難かったのである。ところが,こうした状況は「対決政策」によって一変することになった。スカルノは同国内の共産党を頼り,さらに中国の支持を得たうえ
68) Text of Mr. Lee Kuan Yew’s Speech at a Rally at Serdang Batu, Kuala Lumpur, 6 April 1964, lky 19640406, National Archives of Singapore.
69) リーは 4月 23日の演説において必要とされているのはUMNOと対等にやっていける政党であると述べている。Some Points from Mr. Lee Kuan Yew’s Speech at a Rally in Kuala Lumpur, 23 April 1964, lky 19640423, National Archives of Singapore. また,UMNOは現実に華人を代表しない華人政党とは取引をしようとしないという趣旨の発言をリーはイギリス側にしている。“Note of Conversation between Lee Kuan Yew and Moore,” 9 April 1964, DO169/365, NAUK.
70) 20世紀初頭,インドネシアで発展したナショナリズムがマレー半島に流入し,これはマレーナショナリズムの起源の一つとなった。マレーナショナリズムの起源についてはウィリアム・ロフの研究が依然として最も重要である(Roff 1967)。
96 アジア・アフリカ言語文化研究 95
で,マレーシアへの武力攻撃を仕掛けた。そして,これに対してUMNO指導者たちは譲らぬ姿勢で立ち向かい,マレーシアがインドネシアの植民地にならないことを訴え,国民―とくにマレー人―の支持を集めたのである。こうしてインドネシアとの統合を長く持論として掲げてきた野党 PMIP指導者ブルハヌディン・ヘルミ Burhanuddin Al-Helmyは面目を失った。選挙戦終盤,PMIPとインドネシアとの秘密の協力関係が指摘され,これは同党にとってとくに大きな痛手となった(Ratnam and Milne 1967: 110-119)71)。「対決政策」の下,UMNO主導のマレーナショナリズムはインドネシアナショナリズムから完全に自立し,マレー人の特別の地位をより強調する人々のあいだにも広い支持基盤をつくりあげることに成功した。選挙における各党の得票率を見ると,連盟党の得票が伸びているが,華人に厚い支持層を持つと考えられる野党の社会主義戦線や統一民主党UDP: United Democratic Party
もこれを伸ばしたと読むことができ,連盟党の支持は非マレー人のあいだでは伸び悩んだとも言いえた。そうとすれば,連盟党の勝利はUMNOがこうしてマレー人のあいだで支持を伸ばしたことに拠るところが大きかったと考えられるのである。そうした傍ら,PAPはと言うと,これは彼らにとってまったく予想外の大惨敗を喫することになった。リーの選挙演説は連日の大入りで大変な盛況であり,彼らは 6議席か 7議席は獲得できると踏んでいたところ,PAPが獲得した議席はわずか 1議席であった(Lee 1998: 542-546)。これは PAP創設メンバーの一人でもあるデヴァン・ナイアDevan Nairがインド系市民の多く暮らすクアラルンプール市バンサ地区に赴いての当選であった。PAPは得票数でも大いに伸び悩み,社会主義戦線の八分の一にも届かない結果となった。供託金没収が相次ぐことになった。PAPは社会主義戦線の票をとりに出たものの,その壁は厚かった。PAPはシンガ
71) 1965年 1月 28日,ブルハヌディン・ヘルミはインドネシア後援の亡命政府を樹立しようとしたとの嫌疑で逮捕・拘留された。The Straits Times, 30 January 1965.
図表 1 1959年マラヤ連邦議会下院議員選挙及び 1964年マレーシア連邦議会下院議員選挙(旧マラヤ連邦)の結果
政党1959年 1964年
得票数 得票率 獲得議席数 得票数 得票率 獲得議席数連盟党 800,944 51.8 74 1,204,340 58.5 89 統一マレー国民組織(UMNO) 52 58 マラヤ華人協会(MCA) 19 27 マラヤ・インド人会議(MIC) 3 3汎マラヤ・イスラム党(PMIP) 329,070 21.3 13 301,187 14.6 9社会主義戦線 199,688 12.9 8 330,898 16.1 2 マラヤ労働党 6 2 人民党 2 0人民進歩党(PPP) 97,391 6.3 4 69,898 3.4 2統一民主党(UDP) ― ― 88,223 4.3 1人民行動党(PAP) ― ― 42,130 2 1その他 120,176 7.7 5 20,828 1.1 0無効票 17,306 ― 89,104 ―
計 1,564,575 104 2,146,608 104
出典:Nohlen 2001
97鈴木陽一:シンガポール共和国の建国について
図表 2 マレーシア第二議会下院各党議席数(1964年 4月現在)
政党 議席数【旧マラヤ連邦】 【104議席】 連盟党(マラヤ)* 89 統一マレー国民組織(UMNO) 58 マラヤ華人協会(MCA) 27 マラヤ・インド人会議(MIC) 3 汎マラヤ・イスラム党(PMIP) 9 社会主義戦線 2 マラヤ労働党 2 人民進歩党(PPP) 2 統一民主党(UDP) 1 人民行動党(PAP) 1【シンガポール州】 【15議席】 人民行動党(PAP) 12 バリサン・ソシアリス 3【サラワク州】 【24議席】 連盟党(サラワク)* 18 サラワク保守党(PESAKA) 6 サラワク国民党(SNAP) 4 サラワク華人協会(SCA) 4 サラワク民衆党(BARJASA) 4 サラワク人民連合党(SUPP) 4 サラワク国家党(PANAS) 2【サバ州】 【16議席】 連盟党(サバ)* 16 統一サバ国民組織(USNO) 6 統一全国カダザン組織(UNKO) 5 サバ国民党(SANAP) 4 統一全国パソ・モモグン党(PM) 1計 159
注:1) シンガーポール州,サラクワ州,サバ州の各州は,各政党に州議会議席数に応じた議席数を改めて割り当て,各州議会が下院議員を選出した
:2)連邦政府与党には *を付した出典: Leigh 1974 p. 96, Ratnam and Milne 1967 pp. 292-294, pp. 307-309, マ
レーシア連邦議会サイトより筆者作成
98 アジア・アフリカ言語文化研究 95
ポールにおける実績を強調したが,社会主義戦線は PAPがシンガポールで華語教育に抑圧的である旨を主張して支持層を固めたのであった(Ratnam and Milne 1967: 130-131)。PAPは主に非マレー人の票を取りに出ながらもUMNOのリーダーシップは支持するという中途半端な立場に立ち,結局,連盟党と社会主義戦線という二大勢力のあいだに埋没してしまったとも言い得る(Lau 1998: 118-120, Lee 1998: 542-547)。PAPは連邦政治の主要政党となるための足掛かりを確保することに失敗することになった。さらに,PAPの半島への進出は選挙における敗北以上に深刻な帰結を彼らにもたらした。選挙はそれまで必ずしも焦点となっていなかったマルチエスニック政党である PAPとマレー人政党であるUMNOとのあいだの深刻な矛盾を浮かび上がらせ,勢い付いていたUMNOが PAPに対して激しい敵愾心を剥き出しにするようになったのである。直接の標的にされたMCAが敵対的態度を強めたのは当然であったが,PAPの半島進出はUMNOをも強く刺激した。確かに,今回の選挙戦で PAP候補が争った相手はMCA候補であり,UMNO候補ではなかった。そうした意味において,UMNOは実害を被らなかったようにも見えた。しかし,小選挙区制の下,PAP候補は連盟党候補(この場合,MCA候補。)の後ろ盾となったUMNO組織とマレー人票の獲得をめぐって争いを展開した。さらに,選挙が終わると,PAPはそれぞれの選挙区に支部を設け,その原則に則ってムスリムの入党手続きを許容した72)。PAPは自らを都市部を基盤とする政党と位置付け,都市部のマレー人(UMNOが票田としていた。)に浸透しようとしていることを隠そうとしなかったのである。PAPの半島進出はエスニック集団別政党の連合である連盟党全体―さらにはその仕組みのな
かで盟主であり続けようとするUMNO―への明白な挑戦であることは明らかであった。さらに言えば,前述のように,この頃,UMNOはマレー人の特別の地位をより強調する人々にも支持基盤を広げるようになっており,同党指導部は彼らの期待にとくに敏感になっていたという事情もあった。UMNOは PAPの半島進出を許すことのできない裏切りとしたのである。
シンガポール暴動への道選挙以降,アルバールら一部のマレー人政治家たち(リーたちはマレー急進派と呼んでいた。)から PAPへの反撃が先鋭化し,これは PAPの本拠地・シンガポールにおけるエスニック集団間の対立感情に火をつけることになった。アルバールらと緊密な関係にあるマレー語紙ウトゥサン・ムラユ Utusan Melayuなどにおいて PAP政権がシンガポールのマレー人を差別的に扱おうとしている旨の記事の掲載が相次ぎ,マレー人の感情が刺激され出したのである。5月末以降,とくに争点として取り上げられることになったのは,前章でも紹介したシンガポール州政府が進めていた都市再開発・再定住政策の問題であった。州政府は慢性的な住宅不足を解消することを理由に再開発による公共住宅供給を進め,幾つかのマレー人の集住していた地区においても再開発のための住民の立退きが進められることになった。そのことがマレー人たちへの差別に当たるとされたのであった。7月 12日,UMNOはマレー人団体を招請した会議をシンガポールで開催し,ここでアルバールはリーたちがマレー人を虐げ,マレー人と華人との諍いを煽っていると非難し,さらに,リーは平和な環境では生きていけない男,共産主義者で悪魔であると述べ,リーを中傷した。会場はリーを逮捕しろとの声で溢れたとされている(Lau 1998: 138-
72) The Straits Times, 29 April 1964. 竹下の研究(竹下 1995: 230)。
99鈴木陽一:シンガポール共和国の建国について
150)73)。アルバールらの非難は基本的にはリーらシンガポール政府に向けられており,華人たちに向けられたものではなかった。ただ,そうは言っても,彼らの言説はマレー人たちのエスニック感情を煽るものであり,エスニック集団間の緊張が極めて高くなったことは明らかであった。エスニック集団が集住する地区の人々を立退かせることはいずれの国においても難しい問題となるが,ここで見過ごしてはならないことはシンガポールにおいてはこの問題が PAP政府の存立基盤に直結していたということである。前章において述べたように,都市再開発・再定住政策は PAPがめざすマルチエスニック社会の基盤の創出に直接繋がるものであった。再定住は実質的に既存のコミュニティを解体し,様々なエスニック的背景を持つ人々が英語を共通語として共存する新たなコミュニティの生成を促すものであった。それゆえ,これには華人たちからも強い反発が出されたが,既存のエスニック集団の凝集力を削ごうとしている PAP政府は譲ろうとしなかったという経緯があった。さらに言えば,都市再開発・再定住政策は,当然のことながら,各政党の選挙の際の有利不利にも影響を与えるものでもあった。エスニック集団の集住の解消は,小選挙区制の下,エスニック集団を基盤とした政党の連合である連盟党には不利に働き,エスニック集団を基盤としないPAPに有利に働いた。州政府によって指定されたマレー人が集住する地区は, UMNOがシンガポールにおける支持基盤をつくろうとしていた地区であった。再開発はそうした努力を実質的に台無しにするものであり,これがUMNOを刺激したのは当然の
ことであった。再開発計画については,19日, 州政府もマレー人団体に招請して政府の政策に理解を求めるべく説明会を実施した。このとき,リーは教育・社会・経済上の純粋な問題を政治対立から切り離すことが必要であることを訴え,そのうえで,いわゆるマレー人問題がエスニック集団間の不均等発展に起因していることを指摘し,教育,雇用,住宅の三点の問題の解決が必要であることを強調した74)。ただ,住宅不足のためたまたま当該地 区が今回の再開発地区に指定されただけであっ たのだとしても,客観的に見れば,それはきわめて政治的インパクトの強い争点であった。
7月21日―この年の預言者ムハンマドの 生誕記念日―シンガポールでエスニック集団間に暴動が発生したのはそうしたなかのことであった75)。夕刻,これを祝うイスラム教徒たちの行進がカラン通りにさしかかったとき,警備の警官とのあいだで起こったちょっとした言争いがきっかけで乱闘が始まった。これが数時間以内に全島規模でのマレー人と華人とのエスニック間暴動へと発展したのだった。夜間外出禁止令が政府によって出されたが,翌朝,再び衝突が各所で発生し,午前 11時半には再び外出禁止令が出された。こうして数日間緊張が続き,外出禁止令が解除されたのは 8月 2日以降のこととなった。死者 23名,負傷者 454名。戦後の混乱以降, 最悪の惨事であった(竹下 1995: 232,Lau 1998: 161-175,Lee 1998: 558)。しかも,シンガポール政府には治安維持の最終権限がないため,連邦閣僚がシンガポールを訪れての事態の収拾となった。あろうことか,外出禁止令が出されているあいだにもマレー語メディアはリーへの攻撃を続けた。PAP政府への信
73) インドネシアからの「対決」が続くなか,連邦政府はマレーナショナリズムに訴える姿勢をとっていた。それゆえ,アルバールのようなマレーナショナリズムを強調する人々を抑え込むことは政治的リスクが高かった。トゥンク自身はアルバールを苦々しく見ていたと考えられるが,これを止めようとしなかった。
74) The Straits Times, 20 July 1964. 出席したのは政党を除いたマレー人団体であった。75) リーは,アルバールらが当該民族間衝突を抑制しようとせず,むしろ利用しようとした,と主張し
ている(Lee 1998: 551-569)。
100 アジア・アフリカ言語文化研究 95
認は大きく揺らいだ(Lau 1998: 175-185)。さらに 9月 2日,シンガポールで再びエ
スニック間暴動が起こった。マレー人地区における殺人事件に端を発したもので,ゲイランなどを中心に暴力沙汰が続き,4日から11日まで外出禁止令が出された。死者 13名,負傷者 109名。前回は偶発的要素が強かったのに比べて今回は仕組まれたものであるとされ,インドネシアの関与が取り沙汰された。同日,インドネシアが半島にコマンド部隊 30名ほどを落下傘降下させていた(竹下1995: 234,Lau 1998: 195-199,Lee 1998: 567)。ただ,たとえ同国の工作活動があったのだとしても,衝突の素地が依然として国内に残存していたことは事実であった。彼らはそれを利用しただけのことであった。9月20日,トゥンクはシンガポールにおいて講演し,暴動の原因はインドネシアにあるとしつつも,それを許すような雰囲気をつくった幾ばくかのシンガポールの政治家たちは非難を免れることができないとした76)。以上見たように,新連邦発足後,マレーシア連邦政府とシンガポール州政府とのあいだの矛盾が表面化し,両者は深刻な衝突を起こすことになった。PAPはエスニック集団に囚われない社会の創出をめざそうとして連邦政治における権力分有をはかろうとしたが,UMNOは連邦政治はマレー人が主導するものと考えた。PAPの野望は一旦阻まれ,シンガポールでは暴動が発生することになった。ここで留意すべきは,かような事態は PAP指導者たちのみならずその庇護者であったイギリスにとっても望んでいたところから大きく離れた帰結であった,ということである。PAPが没落するとすれば,そうした事態はイギリス人たちにとっても大きな打撃のはずであった。PAP政府は彼らに忠実
に振舞ってきたパートナーであったし,依然としてイギリス極東軍の最大拠点を統治していたからである。そして,そうとすれば,かの事態にあって,イギリス人がリーたちを庇護しようと動く可能性はあったし,PAP政府とすればそのことは大いに期待するところであった。イギリスの手元には連邦政府と州政府との対立を調整するための様々な手段が残されており,彼らはそれを行使できるはずであった。が,問題は,事はそう容易には運ばない,ということであった。
第 3章 連邦・シンガポール州関係の展開 2 連邦関係希薄化の試みとその挫折
1960年代半ば,東南アジアは冷戦の最前線になっていた。大陸部ではベトナム戦争の本格化が進行していた。1965年 3月以降,アメリカが軍事介入を拡大させ,この年の末,駐ベトナム・アメリカ軍は 18万にまで膨れあがった。その南,島嶼部においても,インドネシア・マレーシア紛争が世界規模な冷戦と連動しながら対立を激化させていた。一方,インドネシアは中国からの強い外交的支援を受け,他方,マレーシア防衛の最前線にはイギリスを始めとするコモンウェルス軍が立った。前章末でみたようにマレー半島もまたインドネシアからの攻勢に曝されたが,主要な戦場はボルネオの両国国境地帯であった。インドネシアが「義勇兵」を送り込み,これを迎えるコモンウェルス軍とのあいだで激しいゲリラ戦が展開された77)。インドネシアの行動に国際社会の非難が高まると,1964年 12月 31日,同国は国連脱退を宣言した。中国とともに第二国連をつくるとのことであった。アメリカとイギリスは協力関係を発展させながら東南アジアにおける冷戦に対処した。
76) The Straits Times, 21 September 1964.77) イギリス史料公開後の研究ではコモンウェルス側はゲリラ兵を迎え撃つだけではなく,国境を越え
て戦闘のイニシアティブをとる赤ワイン作戦Operation Claretを展開し,インドネシア側を消耗させていたことが明らかになっている(Easter 2005)。
101鈴木陽一:シンガポール共和国の建国について
米英の東南アジア政策は重点の置き方で異なるところもあったが,1964年 2月,両国首脳 会談において政策の調整がほどこされた。アメリカの対ベトナム政策,イギリスの対インドネシア政策を互いに尊重し,協力するとしたのである(Jones 2002: 258-262)。加えてその後,アメリカとイギリスは東南アジア政策をめぐって両国のあいだにさらなる取引があることを意識しながらこれに当たることになった。当時,イギリス・ポンドは売り圧力に曝されがちであったが,アメリカはこれを支える立場に立った。そして,イギリスが極東に関与し続けることがアメリカからの金融支援の対価であると考えられるようになっていったのである78)。そうした傍ら,当のマレーシアは内在させていた不安定さを増幅させていくことになった。1964年連邦議会選挙を契機に連盟党とPAPとは関係を悪化させ,これはシンガポール暴動を惹起したのみならず,連邦全体におけるエスニック集団間の感情をもひどく険悪なものにした。それゆえ,連邦・シンガポール州両政府は関係をより緩やかにすることによって事態の収拾を図ろうとしたが,交渉は難航した。両者の後ろ盾のはずであったイギリス政府がそうした解決策に強く反対した のだ。本章では,連邦政府とシンガポール州政府とが関係の調整に失敗して対立を深刻化させ,結局,後者が連邦から離脱を果たす過程について見る。
イギリス帝国とマレーシア連邦議会選挙以降,リー率いる PAP政府はおそらく彼らが想像していた以上に困難な状況に追い込まれていった。なぜそのような事態に陥ることになったのか。この点,その背景としてまず指摘されなければならないことは,第 1章末でも若干述べたように,PAP政府の後ろ盾のはずであったイギリス帝国が連邦成立以降はマレーナショナリズムへの依存を強める連邦政府を究極的には支持していかざるを得ない―両政府のあいだに二律背反な問題が起きた場合,最終的には PAP政府側を見捨てざるを得ない―立場に置かれることになっていたということであろう。1960年代初頭,イギリスはシンガポールのプラナカンたちと協力してマレーシア形成を推進したが,同国の成立以降,そうした協力関係をどこまで維持できるかは不明なところがあった。確かに,イギリス帝国はマレーシアを極東の拠点として重視し,その複雑な事情に相応の配慮を払っていた。マレーシア成立にあたっては新任の高等弁務官に防衛大臣など閣僚経験のある大物政治家アントニー・ヘッド Antony Headを派遣した。彼はナイジェリアでも初代の高等弁務官を務めた経験があり,独立したばかりの新興国の抱える困難に熟知した人物と言えた。実際,連邦政府との軋轢に悩むリーたちの立場を理解し,数々の支援を行った。リー自身も彼の能力を非常に高く評価し,彼の支援が大きな力となったことを率直に認めていた79)。しかし,ここで重要なことは,たとえそうであったと
78) ウィルソン政権発足の頃から,イギリスの極東関与とアメリカのポンド支援は両国の政策決定者のあいだで取引として認識されるようになっていたと考えられる(Dumbrell 1996, Dockrill 2002: 119, Pham 2010: 53-56)。
79) ヘッドは旧植民地官僚,外交官などに比して格段に強い影響力を持つ人物であった。マレーシア形成に携わって 1963年 10月までその任にあったハロルド・マクミランHarold Macmillan首相とはアンソニー・イーデン Anthony Eden内閣で同僚を務めるなど旧知の間柄であった。また,彼はシンガポールの困難な立場に理解を示していた。リーが自らの名声を世界に広げることになったアフリカ諸国訪問はもともとヘッドの案であったようである。リーは「彼がいなければ,マレーシアとシンガポールの歴史はかなり違ったものになっていたに違いない」と述べている(Lee 1998: 519-522)。シンガポール暴動においても,連邦と州とが衝突しないよう両者のあいだにたって動いた(Lau 1998: 182-185)。
102 アジア・アフリカ言語文化研究 95
しても,イギリス人にとって一番重要なパートナーはこの期に至ってはやはり連邦政府となっていた,ということであった。ヘッドはかつて帝国を支えたシンガポールやボルネオの人々の立場に共感を持って事態の推移を眺め,また彼らとのチャネルを大切にし続けたものの,ヘッドが究極的に心配していたのは連邦政府の行方であった。連邦政府と彼らのあいだに対立が起きたとき,そこに不公正を思わせる事柄があるからと言って,連邦政府との関係を大きく損なってまで彼らを守り続けるようなことはできなかった。そもそも,イギリス人は主権移譲を終えており,マレーシアに統治権を持っているわけではないという当然の前提もあった。イギリスは依然としてマレーシアに軍を駐留させてその安全保障に関わっており,同国に影響力を行使する様々な手段を残してはいたが,それらの効果には限界があったのだ。世論の反発を予想すれば,連邦の運営に正面切った影響力の行使をするわけにもいかなかった。さらにまた,PAP政府が困難な状況に追い込まれていく背景としては,こうした事情に加えて,インドネシアからの想定を超えた強い反発―「対決政策」―が起きたことによってイギリス帝国が採ることのできる政策の選択肢の幅に大きな制約が加えられるようになってしまっていた,ということも注目されなければならないだろう。すでに述べたように,イギリス帝国が描いたグランド・デザインは,自らの東南アジア植民地帝国を非公式化して安定したジュニア・パートナー国家を創設し,そこに東南アジア有数の軍事力を駐留させることでアメリカの外交政策を支援し,そのことを通して地球規模の勢力としての地位を維持しようというものであった。それゆえ,インドネシアからマレーシアへの攻撃にあって,イギリスは軍事力を動員して
後者の防衛に当たった。その成果は明白のように思える。マレーシアは持ちこたえることができた。イギリスの支援がなければ,そうすることはより困難であったと言える。ただ,この時期のマレーシアの状況を考えようとするならば,イギリスによるマレーシア防衛への関与がそのほかにも顕著な帰結をもたらしたことは留意されなければならないだろう。関与はその対マレーシア政策全般に一定の作用をもたらし,そのことはマレーシアの内政に大きな影響を与えた。端的に言えば,「対決政策」が続くなか,イギリス政府内においてはマレーシア連邦のあり方そのものについて現状維持を望む強いインセンティブが生まれることになったのである。同国とすれば,自らが守るマレーシアが実は帝国主義の産物でまともに機能するような代物ではなかった,といった印象を内外に与えることはどうしても避けたいところであった。それゆえ,最初につくりあげた連邦政治の仕組みの改変を促すことで対立の緩和を図る,あるいはそうした現地の動きを支援する,といった連邦の正統性に疑念が生じかねない大胆な対応が採れなくなったのであった。この点,イギリスが最も憂慮したのはマレーシアに起こった内紛がアメリカの姿勢に影響を与えることであった。「対決政策」が拡大するなか,オーストラリア,ニュージーランドなどのコモンウェルス諸国はイギリスの方針に堅固な支持を寄せたものの,イギリスの最も重要なパートナーであるはずのアメリカが微妙な姿勢を採り続けていたのである。その就任以来,アメリカ大統領ジョン・F・ケネディ John F. Kennedyは東南アジア最大の国家であるインドネシアとの関係を重視し,西イリアン問題などにおいてインドネシアに有利とも見られる仲介工作などを試みていた80)。こうした流れを受け,当初,アメ
80) インドネシアは西イリアン(西ニューギニア)の帰属をめぐってオランダと争っていた。西イリアン紛争についてオランダ語も駆使した研究としてはペンダースの研究が優れている(Penders 2002)。
103鈴木陽一:シンガポール共和国の建国について
リカはマレーシアとインドネシアの争いにおいても中立的とも見られる曖昧な姿勢を採った(Jones 1998: 136-139)。インドネシアがボルネオ,半島,シンガポールなどに小規模な武力攻撃を仕掛けても,アメリカはなかなかこれに強い非難を出さなかったのである。イギリス人たちにすれば,それは本末転倒とも言える状況であったし,かようなアメリカ人の姿勢を改めなければ紛争解決への道が開けないように思われた81)。先に述べたように,1964年 2月,両国首脳は互いの東南アジア政策を尊重することで合意したが,姿勢の違いはそれでも潜在的なかたちで残ることになった。それゆえ,連邦政府の正当性を傷つけかねない―とくにマレーシア形成が無理な作業であったとアメリカ人に印象付けてしまうような―危険はいかなるものであれ避けたいところとなっていたのである。そうしたなか,イギリス帝国はボルネオの状況,さらにシンガポール暴動を深く憂慮し,事態の収拾に向けて動き出した。帝国はマレーシアの防衛に努めており,当然のことながら,同国の安定はイギリスの政策の前提条件であったからである。7月 22日,第一次シンガポール暴動発生の翌日,ヘッドはマレーシアが極めて不本意な状況にあることを認めるとともにある進言を記した電信を本国
に送った。連邦政府が一貫性をもって如才なく,非党派的に振舞えば,こうした事態は避けることができたはずであり,イギリスはこれを放置すべきではない,というのが,ヘッドの観察であった。実は,この間,トゥンクはアメリカ訪問に出ており,近々,その帰りにロンドンに立ち寄ることになっていた。そこで,この機会を利用して首相かコモンウェルス関係相が彼に直接に考えるところをしっかり話すべきである,と彼は主張したのであった82)。ヘッドに限らず,イギリス人が考えたマレーシアの大きな誤りは連邦政府がシンガポール,サラワク,サバからほとんど閣僚を迎えず,彼らからの支持を得ようとしていないことであった83)。この点,ヘッドは首相不在のマレーシア政府に直接の働きかけも行った。トゥン・ラザク Tun Razak副首相に暴動の原因をめぐって非難し合ったりしないことが肝要であると意見を述べるとともに,PAP閣僚も入れた挙国一致政府National Governmentをつくってみてはどうかと働きかけたのであった84)。しかし,ラザクはいったんこれに積極的な姿勢を示したものの,数日後には消極な姿勢へと転じることになった85)。こうして,イギリスがマレーシアをよいように変えていくためには,高等弁務官の働き掛けでは足りないことが明らか
81) イギリス帝国としては,マレーシアを形成することでアメリカとの共同作戦能力を維持しようとしていたのだから,これは本末転倒の事態とも言えた。研究者はそのように指摘している(Easter 2004: 84-85)。アメリカの動きの影響については,リー自身も計算外であったこと,自分がおめでかったことを認めている(Lee 1998: 519-522)。
82) Telegram from Kuala Lumpur to Commonwealth Relations Office, 22 July 1964, DO169/527, NAUK.
83) こうした考えは首相へのブリーフにも記されている。Brief for the Prime Minister’s Talk with the Tunku on 6 August 1964, 31 July 1964, PREM11/4909, NAUK.
84) Telegram from Kuala Lumpur to Commonwealth Relations Office, 24 July 1964, DO169/527, NAUK.
85) 7月 28日,ラザクは二つの提案をゴー・ケンスイに示した。次の(a)(b)いずれかのうち一つをとってみてはどうかというものであった。(a)リー・クアンユウが首相を退き,駐国連大使などに転出し,連邦政府が PAP閣僚を受け入れる。(b)PAPがマレー人とやりとりするときはキハール・ジョハリKhir Johariを通してのみとすることで互いにプロパガンダを止め,政治休戦をする。リーは(a)については条件付きで受け入れ可能として乗り気であった。Telegram from Kuala Lumpur to Commonwealth Relations Office, 28 July 1964, DO169/527, NAUK. しかし,8月 1日,リーがラザクと会談を行う段となると,ラザクはこの提案を撤回させていたのであった。Telegram from Kuala Lumpur to Commonwealth Relations Office, 3 August 1964, DO169/527, NAUK.
104 アジア・アフリカ言語文化研究 95
になり,首相アレク・ダグラス=ヒュームAlec Douglas-Home自らが働き掛けることになったのであった。
8月 6日,ロンドンにおいて英馬首脳会談が行われた。両首脳は正式な会談を前に私的な会談も行った。ダグラス=ヒュームによるとそこでは次のようなやり取りがなされた86)。
「マレーシアが団結していると感じられるよう,首相の揺るぎない権威を発揮してサラワク,サバ,シンガポールからさらに代表を政府に迎え入れてみてはどうか。」と私はトゥンクに聞いてみました。「この問題はよく理解しており,できることはしたいと切に思っている。しかし,この問題は政治的に難しいところがある。リー・クアンユウは狡猾な紳士であり,マラヤの内政への干渉に反対せず,実際に干渉した。それは前回の選挙において交わされた了解を破るものであった。しかし,マラヤに帰ったらリーと取引するつもりである。リーはマレー人,華人などに非常に不人気であるため,彼を内閣に迎えることはできないけれども,防衛委員会 Defence Councilなどを通してシンガポールの代表を迎え入れたい。」と彼は述べました。
ダグラス=ヒュームは挙国一致内閣の設立を勧めたものの,結局,トゥンクは忠告を聞くような素振りを見せつつ重要なところでは譲ろうとしなかった。UMNOの足元を侵食し,対等なパートナーとなろうとした PAPから閣僚を迎えることは不可能であったのだろう。また,ここで注目すべきは,イギリスは控えめな提案に終始し,トゥンクをそれ以上追い込もうとしなかった,という事実である。
コモンウェルス関係省が首脳会談のために用意した首相へのブリーフには,騒動における連邦政府の非が長々と述べられていたが,トゥンクが内政事項への介入に態度を硬化させて事態が全く動かなくなる危険性も強調されていた87)。ダグラス=ヒュームの穏やかな物言いはこうした事情に配慮して予め練られたものであったと考えられる。また,このとき,首相には外相からの覚書も届けられていた。外相が表明したのは,インドネシア対決政策が続くなかでの今回の騒動が国際世論に及ぼす悪影響への懸念であった。暴動が起きたため国際社会からマレーシアへの支持を集めることが難しくなっており,事態が悪化すればそれがより困難になること,とくにアメリカとの関係においてより困難になることの危険性が訴えられていた88)。イギリスはトゥンクの機嫌をとり,国際世論にも十分に配慮する必要があった。たとえ非が連邦にあるのだとしても,シンガポールやボルネオの肩を持って騒ぎ立て,マレーシア連邦政府の正当性を傷つけることはできなかった。イギリスと PAP政府との協力関係はかつてほどには機能しえなくなりつつあった。後ろ盾であるイギリスがマレーシア国内政治への大々的な介入を控える傍ら,連邦政府とシンガポール州政府は事態の悪化を受けて,局面の打開を探ることになった。9月 25日,両者は 2年間の政治休戦を結ぶことにしたのであった。内容は,双方ともエスニック集団の地位に関する感情問題を取り上げない,双方の食い違いを 2年間棚上げにしてマレーシアの利益を第一にする,インドネシアからの攻撃と破壊活動に対して国民を動員するよう最大の努力を払う,というものであったとされる89)。ただしかし,この政治休
86) Note by the Prime Minister of His Private Conversation with the Tunku Abdul Rahman at No. 10 Downing Street, 6 August 1964, PREM11/4909, NAUK.
87) Brief for the Prime Minister’s Talk with the Tunku on 6 August 1964, 31 July 1964, PREM11/ 4909, NAUK.
88) “Malaysia,” Memorandum by the Secretary of State for Foreign Affairs, 5 August 1964, PM64/86, PREM11/4909, NAUK.
105鈴木陽一:シンガポール共和国の建国について
戦は,翌月,連盟党がシンガポール連盟の再建に着手したことですぐに曖昧なものとなった。シンガポール側からの非難にもかかわらず,トゥンクは政治休戦の趣旨はエスニック集団間の問題を政党が取り上げないことにあり,「連盟の再建を禁ずるものではない」としてこれを許容したからである90)。先に述べたように,PAPと連盟党の対立の主要な原因は双方の支持基盤が重なろうとしていたことにあった。双方が相手方の本拠地に入って党勢を拡大しようとすることをそのまま放置すれば,再び激しい舌戦が再開されることは必至であった。安寧を確保するためには政治休戦のうえにこれを保証するさらなる対策が必要であった。
連邦関係希薄化の試みと帝国の介入結局,連邦・シンガポール州両政府がここで行き着いたのは,両政府の関係をより緩やかなものにすること―連邦関係希薄化disengagement―で対立の緩和を図ろうとの構想であった。もちろん,政治休戦を保証するためにはほかにもいくつかの採りうる選択肢がありえた。おそらく最も有力な案はリーを駐国際連合マレーシア大使に転出させるというものであったように思われる。「対決政策」が続くなか,リーには一旦マレーシア国内の政治から身を引かせることで国内の
安寧を確保し,そのうえで弁の立つ彼に国連でマレーシア擁護の論陣を張らせるというもので,内外政治で一石二鳥を図ろうとの考えと言えた。7月末になるが,連邦側はこうした案を州側にいったん提出した。ただ,この案はリーの国際的名声を高めて彼の国際政治上の立場―翻って彼の国内政治上の立場―を強化するだけになる可能性もあった。連邦政府内に異論もあったのだろう。提案は8月初めにいったん撤回されていた91)。転出案はその後も温存されたが,10月,連邦政府内でこれが再び検討されると,トゥンクがこれに反対し,彼は連邦関係希薄化を主張したのである92)。こうして,12月 19日,トゥンクがこれをリーに内々に提案し,秘密交渉が進められることになった93)。翌年 1月 22日に連邦政府側から出された内容は,シンガポール州選出議員が連邦議会から退出するかわりに同州が外交・防衛を除くほぼ完全な自治を享受するというものであった94)。それは連邦というよりはもはや国家連合に近いものと言いえた。トゥンクはこのときの交渉について回想録で次のように述べている(Abdul Rahman 1977: 116)。
マレーシア内の平和と落ち着きを保つために,私は新しい提案を行いました。……内容としてはシンガポール政府は州内の財
89) The Straits Times, 27 September 1964. リーの回想録に拠る(Lee 1998: 576-577)。90) The Straits Times, 29 October 1964. リーの回想録に拠る(Lee 1998: 578)。91) 注 85参照。この話はジョセーの著書でも言及されている(Josey 1980: 288)。92) 現地の史料公開が進んでないため確定的なことは言えないが,関係希薄化案自体が話題になり出し
たのは,10月下旬,政治休戦の成立の後しばらくしてのことであったと推測される。すでにこの頃,「シンガポールが分離を考えている」との噂が広まり,リーが否定するという事態が発生していた。The Straits Times, 19 October 1964. 実際,イギリスも連邦政府でそうした考えが真剣に考慮されているとの情報を得ていたようである。ラザク副首相ほかはリーの国連大使転出に賛成であるが,トゥンクが反対しており,彼は連邦を緩やかにすることを考えているというのである。 “Malaysia: Internal,” Note of an Informal Discussion between Lord Head, Sir N. Prichard, Mr. Chadwik, Mr. Brown, Mr. Turner and Mr. Jenkins, 22 October, DO169/356, NAUK. また,同月下旬,エディ・バーカー Eddie Barkerシンガポール州政府法務相が連邦下院議員就任の宣誓をクアラルンプールで行った際,旧知のラザク副首相から連邦政府が関係希薄化を考えている旨を内々に告げられたとの証言もある。Asiaweek, 27 March 1992.
93) 12月 19日に提案があったというのはリーの回想録に拠る(Lee 1998: 581-582)。94) Letter from Antony Head to Saville Garner, 28 January 1965, DO169/528, NAUK.
106 アジア・アフリカ言語文化研究 95
政,経済,社会の事項に責任を持ち,中央政府は防衛,治安の事項に最終的な権力を保持するというものでした。この提案が効果を発揮すれば,シンガポールは引き続きマレーシアの共同市場から恩恵を受けることができ,この恩恵と引き換えにシンガポールの各政党は自州以外での政治活動を差し控えるだろう,と私は考えました。私は憲法改正を行いたくありませんでした。そのようなことをすれば,諸外国からマレーシアで分裂が生じ始めたと解釈される恐れがあったからです。その代案として,議会への選出代表者数を変更―憲法はそうした事態を許容していました―し,防衛と国内治安以外の,中央政府管轄下にある省庁を州政府の管理下に置くことも考えました。詳細については,この案が公表された後,連邦および州政府の担当官の合同委員会をつくって協議すればよいことでした。
統合のために積み重ねてきた努力を思い起こせば,納得できないところもある提案ではあったが,現実に鑑みれば,シンガポール政府としてももはや決して悪いスキームとは言えないものとなっていたと言えた。当時,両者のあいだの政争は上記のような政党間の諍いの領域に留まらなくなっていた。シンガポール州政府が強く求めていた共同市場設立交渉は遅々として進まず,逆に,1964年 11月,タン財務相は増税を要求して物議を醸していた。連邦政府から州政府への財政的な締め付けが発生したのである95)。そうとすれば,連邦・州の結びつきをいったん国家連合の程度に緩めることで激しい政争を沈静化させ,そのうえで共同市場を求めていくというのは
一つの考え方であったのである。リーたちとすれば,その後,自州の社会経済政策を成功させれば,連邦政治の主導権獲得へ今一度挑 戦する道もあり得た。それゆえ,とりあえずイギリスに秘密としながら,両政府はその話を進め,新しい結びつきのあり方を考えることになった。リーの回想録に従えば,1月 25日,リーは話し合いの方向性をまとめる覚書を完成させたという。その内容は,シンガポール政府は統合前の権限を回復し,中央政府はシンガポール政府と協議のうえで外交・防衛の責任を負い,両政府は治安評議会において治安責任を共有する,また,シンガポール市民はシンガポール以外で政党政治活動を行わず,その逆もしかり,すなわち,シンガポールは統合前の地位に立ち戻る,というものであった(Lee 1998: 584)96)。このように連邦・シンガポール州両政府は関係の希薄化によって対立が決定的な事態に陥ることを回避しようと努力した。ただしかしながら,それまでの経緯に鑑みれば,双方が描く構想に簡単には相容れない相違が出てきたとしてもそれは不思議なことではなかった。論点は幾つかあったが,なかでも相違が際立ったのは連邦議会におけるシンガポール州選出議員の扱いの問題と治安事務の所轄の問題においてであった。シンガポール州が連邦議会から完全に退出するというトゥンクの原案についてはリーらが反対であった。連邦の政治に何ら発言できないということになれば,代表なければ課税なしの原則に反し,植民地扱いも同然であった(Lee 1998: 586-587)。連邦が州の防衛を所轄する以上,州政府に防衛費の請求が来ることもありえた。その額が納得できるものならよいかもしれないが,そうではない可能性も十分にあった。全議員が退出するという案は適切ではなく,や
95) 1964年 11月 25日,タン財務相は来年度予算案を議会に提出したが,これはシンガポールには厳しい課税強化予算であった。The Straits Times, 26 November 1964.
96) イギリス側文書でも,リーがこれにほぼ同じ提案を行ったことが記されている。Letter from Antony Head to Saville Garner, 28 January 1965, DO169/528, NAUK.
107鈴木陽一:シンガポール共和国の建国について
はり財政負担の妥当性を担保する仕組みは必要と考えられた。他方,警察機構を州政府に委ねることについては連邦内務省の強い反対があった。治安事務の所轄については連邦・州共同で国内治安委員会を開催して警察をその下に置くというかつてのスキームへの復帰もあり得たが,やはり不安は残された。警察庁長官クロード・フェナー Claude Fennerらが反対することになった97)。連邦に都合のよいことはシンガポール州には都合が悪く,シンガポール州に都合がよいことは連邦には都合が悪かった。双方とも年月をかけて築き上げてきた政治的立場を捨てて後戻りすることはすでにきわめて困難となっていたのであった。イギリスがこうした関係希薄化交渉に強く反対し,帝国の東南アジア支配を支え続けてきた基軸の一つであるイギリス本国と英語を操るプラナカンたちとの協力関係が崩れ出そうとしたのは,そうしたなかにおいてのことであった。イギリス人たちは秘密の情報筋―フェナー警察庁長官―から話を聞きつけ,両政府に関係希薄化をやめるよう圧力をかけ出したのである98)。すでに述べたように,彼らとすれば,それまでシンガポールを包含するマレーシアをつくるために努力し,現にこれをインドネシアから守るために軍隊を展開し続けている最中にあった。平和裏にであれマレーシアが連邦の絆を緩め,結果としてマレーシア構想の失敗を世界の世論に印
象付けるようなことは,彼らの闘争に壊滅的な打撃を与えることになると考えられた。たとえ内政自治が与えられるのだとしてもシンガポール人が連邦議会から退出するのは非常に印象が悪いことであった。さらに,こうした動きはボルネオにも飛び火する可能性もあった99)。それゆえ,2月 11日から 12日にかけ,ヘッドは折からマレーシアを訪れていたイギリス軍参謀総長マウントバッテン伯爵The Earl Mountbatten of Burmaとともにラザク,トゥンク,リーと相次いで会談して関係希薄化に懸念を表明し,とくにシンガポールが連邦議会から引揚げないよう圧力を掛けたのであった100)。さらに,その後,イギリス本国は内閣に首相ハロルド・ウィルソンHarold Wilson―1964年 10月,イギリスでは総選挙が実施され,ウィルソン率いる労働党がこれに勝利していた―を委員長とする関係閣僚委員会を設けてこの問題に関する検討を行った。委員会に提出された官僚たちの報告書の結論は連邦側の案も州側からの対案もいずれも受け入れられないというものであった。マウントバッテンらとの会見時,リーは大きな憲法改正を行わずに行政事務の再分配を行うとの妥協案をイギリスに提示したが,それもシンガポールの治安維持の問題,ボルネオへの波及の問題などに鑑みれば支持できるものではなかった。閣僚たちも関係希薄化をさせないよう両者の説得に出ようとの結論に達した101)。
97) Letter from Antony Head to Saville Garner, 28 January 1965, DO169/528, Telegram from Kuala Lumpur to Commonwealth Relations Office, 18 February 1965, DO169/528, NAUK.
98) リーは情報源はフェナーであったと推測した(Lee 1998: 635)。実際,12月 20日,フェナーはトゥンクが本気でシンガポールを連邦から追放しようとしている話をイギリス側に漏らしている。 Letter from J. R. A. Bottomley to Sir Neil Pritchard, 23 December 1964, DO169/528, NAUK.
99) Telegram from Commonwealth Relations Office to Kuala Lumpur, 30 January 1965, DO169/528, NAUK.
100) Telegram from Singapore to Commonwealth Relations Office, 12 February 1965, DO169/528, NAUK.
101) 大きな憲法改正を行うことなく,シンガポール選出議員が連邦議会において連邦政府批判をすることない旨の文書を差し入れ,替りに連邦がシンガポールに行政事務を移管する,という関係希薄化についての妥協案をリーはマウントバッテンらに示していた。Telegram from Singapore to Commonwealth Relations Office, 12 February 1965, DO169/528, NAUK. しかし,イギリス ↗
108 アジア・アフリカ言語文化研究 95
結局,このマウントバッテンらによる説得は数日の内に奏功し出した。リーの回想録に従えば,トゥンクはシンガポールを連邦議会から退出させるアイディアを捨て,さらに関係希薄化の道はゆっくり模索したい,という姿勢をとるようになったという(Lee 1998: 587-588)102)。さらに,トゥンクはウィルソンには親書を送り,マレーシアの分裂はないことを確約もした103)。イギリス人たちの勝利 であった104)。連邦議会からシンガポール選出議員が退出するという案が葬り去られたことはリーたちにとってはよい話ではあったが, 交渉が進展しないままシンガポール政府が圧迫を受け続けるということになればそれはそれできわめて危険なことであった。この点,リーは状況について州政府内閣に次のような 評価書を提出したとしている(Lee 1998: 590)。
マウントバッテンやヘッドがマレーシアのリーダーに圧力をかけるだけでなく,警察のフェナーや連邦財務のグールドGouldら連盟党閣僚に信頼されているイギリス人官僚も加わって連邦のあり方を見直すことをやめるようトゥンクに一所懸命働きかけている。イギリスは「対決」が継続してい
る以上は,いかなる変化も望まず,変化があるとしても最小限でなければならないと考えている。……もし,我々がヘッドの忠告を聞かなければ,トゥンクが連邦全域で我々の挑戦を一掃することをイギリスが黙認する準備があることを彼がトゥンクに伝える可能性は排除できない。
ここにおいて,リーたちは自分たちが活躍するためにつくった国家が自分たちの棺桶にな ろうとしていることに気付かされたのであった。
PAPの反撃とその失敗イギリスからの介入を受け,雲行きは急速に怪しくなった。だが,もちろん,リーたちはこのような状況に直面して大人しく引き下がる輩ではなかった。PAPは,秘密交渉の傍ら,すでに次の手を打ちつつあった。2月12日,PAPは半島,さらにボルネオを基盤とする野党を秘密裏にシンガポールに招き,与党に対抗し得る勢力の結集を図っていたのである。PAP,ペナン州を基盤とする統一民主党,ペラ州を基盤とする人民進歩党 PPP: People’s Progressive Party,サラワク州を基盤とする SUPPなどがこれに加わった105)。
↗ 政府はこうした案も受け入れようとはしなかった。Minutes of a Meeting of Ministers held at 10 Downing Street, 19 February 1965, MISC 39/1st, “Malaysia,” Note by the Secretary of the Cabinet, 18 February 1965, MISC 39/1, CAB130/225, NAUK.
102) Telegram no. 255 from Kuala Lumpur to Commonwealth Relations Office, 18 February 1965, DO169/528, NAUK 参照。トゥンクにとって関係希薄化の本来の意図はシンガポール人を連邦議会から追放することにあったように思われる。これを放棄せざるを得なくなれば,関係希薄化交渉への熱意が急速に萎むのは必然のことと言えたように思われる。
103) Letter from Tunku Abdul Rahman to Harold Wilson, 2 March 1965, PREM13/430, NAUK. リーの回想録に拠れば,リーが原文を書いたとされる(Lee 1998: 588)。
104) また,交渉が遅滞したのは,このほか,シンガポールに財政自治を与えることにタン財務相が強硬に反対したという理由もあった。Telegram no. 254 from Kuala Lumpur to Commonwealth Relations Office, 18 February 1965, DO169/528, NAUK.
105) 特務部の報告書によればUPKO,汎マラヤ・イスラム党もこのときの会議に出席したとされている。Report by Director of Special Branch, Royal Malaysia Police, 22 February 1965, DO169/529. リーの回想録においても,ステファンはMSCの公表直前まで大野党連合の動きに加わっていたとされる(Lee 1998: 603-605)。それでは,なぜこの情報が流れ出たのか。右記報告書はクチン発のもので,SUPP中央工作委員会においてオン・キーフイOng Kee Huiが行った報告の内容が書かれている。オンは同党指導者であり,シンガポールでの会合に自ら出席してその内容を同僚に報告した。その記録なのである。そうとすれば,その委員に特務部のエージェントがいたと考えるのが妥当である。
109鈴木陽一:シンガポール共和国の建国について
こうして野党連合―のちに多人種主義運動と評されるマレーシア連帯会議の前身―の形成が進められることになった。ボルネオ住民の過半数は先住人であったが,同島とシンガポールとは後者を中心とするイギリス帝国の東南アジア支配にあって長く強く結ばれていた。そうしたなか,各州政府を主導する非ムスリム(非ムスリム先住人も含む)たちにとって,PAPは連邦政治における潜在的な同盟相手であった106)。そして,ここで重要なことは,これがその傍らで進められていた関係希薄化交渉の梃子としても働くものであった,ということであった。この点,確かに,中心となってこれを推進した PAP幹部トー・チンチャイ Toh Chin Chye,ラジャラトナム Rajaratnamらはもともと半島出身者で,彼らはシンガポールというよりはマレーシアという国をつくるために政治に参画してきたとも言える人物たちであった。彼らが本気でマレーシア全体の変革のために対抗勢力の結集を図ったことは紛れもない事実であろう。ただ,近年公開された史料などに鑑みれば,勢力結集が関係希薄化交渉への梃子としても利用されたことは否めない。3月,リーはニュージーランド,オーストラリア両政府から招待を受けて両国への外遊に発つが,その直前,ヘッドは彼から次のような要求を受けることになった。連邦政府が交渉に入る姿勢を明らかにしない限り,野党連合の動きは止まることがなく,それゆえイギリスはトゥンクにそう動くよう圧力を掛けるべきである,というのである107)。
リーが(引用者注:UMNOの)ショービニズムを非難するボルネオやマラヤの野党とシンガポールで会談したことにトゥンクが大変に困惑していた旨,私はリーに述べました。トゥンクが交渉に入り,何らかの合意に達するよう,リーが意図的に自分に留め針を突き刺しているのではないかという印象をトゥンクは持っており,リーがそうしたことをすればトゥンクはますます交渉に消極的になる,とも述べました。……リーの反応は,トゥンクが交渉にすぐに入るということについて暫定声明を出したり,明らかに示さない限り,自分がオーストラリアにいるあいだ,リーの支持者たちがUMNOやトゥンクを攻撃することを止めることはできない,というものでした。トゥンクは自分に会う予定がないので,そのことをトゥンクに伝えてほしいとのことでした。
しかし,結果として言えば,こうしたリーの戦略は燃えあがろうとしていた火に油を注ぐだけのものにすぎなかった。連邦政府内では,このような危険なゲームを行うリーにシンガポールの治安の責任を渡すわけにはいかない,との考えが強まるようになった108)。さらに,リーのニュージーランド,オーストラリアへの訪問も連邦・州関係を悪化させるように働いた。リーは両国国民に「対決政策」に圧迫されるマレーシアへの支援を要請したうえで,さらにマレーシア国内の困難な状況の説明も展開し,人々に好印象を与えた。リーがこうして築いた海外メディアとの良好な関
106) MSCはシンガポールとボルネオとの潜在的な利益共同関係が顕在化したものであったとも言い得る。サラワク最大の政党である SUPPがこれに参加したことについては本文で述べたとおりである。また,当初,UPKOがこの野党連合に加わっていたことについては前注に記した。リーはステファンがUPKOと PAPとの合併を持ちかけたとさえ述べている(Lee 1998: 603)。UPKOの多人種主義についてはMSCの文書においても大きく取り上げられている(Lee 1965b: 48-50)。
107) Telegram from Kuala Lumpur to Commonwealth Relations Office, 4 March 1965, DO169/529, NAUK.
108) “Relation between Kuala Lumpur and Singapore,” Memorandum by N. Pritchard, 5 March 1965, DO169/529, NAUK.
110 アジア・アフリカ言語文化研究 95
係はクアラルンプールを神経質にするばかりであったのだ。4月初旬,ニュージーランド,オーストラリアから帰国すると,彼は連邦政府などから激しい非難を受けることになった(Abdul Rahman 1977: 119, Lee 1998: 594-599)。事態が悪化したにもかかわらず,イギリス政府は動かなかった。帰国後の 4月 14日,リーはまたしてもヘッドを訪ね,関係希薄化の許容を求めたものの,ヘッドはこれを受け付けなかった。彼はこのときのことを次のように本国に報告している109)。
(引用者注:リーとゴー・ケンスイGoh Keng Sweeは次のように述べました)
シンガポールとクアラルンプールとの政治的な関係希薄化がなければ,両者は衝突に向かうでしょう。衝突は人種暴動を起こして多分マラヤに広がり,連邦全体が消失するでしょう。ですから,関係希薄化は必要不可欠です,と。彼らの考えに拠れば,関係希薄化への唯一かつ実質的な障害は私であるそうです。彼らの主張に拠れば,関係希薄化の輪郭が浮かび上がったとき,私がトゥンクをひどく脅してすべてを駄目にしてしまったというのです。ですから,連邦が消失するか成功するかはイギリスの手に委ねられているというのです。私は歪曲と極端な単純化に満ちた話を受け入れることを完全に拒否しました。
イギリスが動かないと見ると,4月29日,リー
はヘッドにさらに次のようなことも述べた。政治的圧力が最終的にトゥンクをして関係希薄化へと向かわせるであろう,と110)。
5月 9日,大野党連合が正式に旗揚げされた。PAP,UDP,PPP,SUPP,マチンダMachinda五党の代表者がシンガポールで会議を開催し,トー副首相らが共同宣言を発表した111)。会議は自らをマレーシア連帯会議MSCと呼び,「マレーシア人のマレーシア」といういわば多人種主義を求める連合体と位置付けた。マレーシアはシンガポール,ボルネオも包含したマルチエスニック国家であること,そうしたなか,特定エスニック集団に依存しない―と自らが主張する―PAPこそが連邦政治において主導権を握る立場にあることを PAPは印象付けようとし,マレー人の優位に正面から挑んだと言える。宣言の内容は次のようなものであった112)。
インドネシアからの対決や親共主義者による破壊活動ではなく,これら(引用者注:建国時の)基本原則からの逸脱がこの国へのより大きな危険となっています。……マレーシア人のマレーシアとは,特定の集団や人種のみが優越し,幸福,利益を享受するわけではない,そうした国民や国家のことを意味しています。マレーシア人のマレーシアとは,マレー人のマレーシア,華人のマレーシア,ダヤク人のマレーシア,インド人のマレーシア,カダザン人のマレーシアといったものへの反対命題なの です。
109) Telegram from Kuala Lumpur to Commonwealth Relations Office, 15 April 1965, DO169/529, NAUK.
110) Telegram from Kuala Lumpur to Commonwealth Relations Office, 30 April 1965, DO169/529, NAUK.
111) マチンダはサラワク州の小政党(野党)であった。州議会に一議席を有していた。112) The Straits Times, 10 May 1965. 1990年代,シンガポールの情報通信技術政策 IT2000に対抗して,
マレーシアのマハティール政権は同様のマルチメディア・スーパー・コリドーMSC:Multimedia Super Corridorを打ち出した。現在,マレーシアでMSCと言えばこの構想をさす。マハティールはこのときのリーの政敵であった。この命名はマレーシアの歴史からリーたちのMSCを葬り去る試みであったとも言えよう。
111鈴木陽一:シンガポール共和国の建国について
当然,リーたちはさらに激しい非難にさらされることになった。5月 15日に開催されたUMNO党大会では,リーを拘束するよう要求が相次いだ113)。連邦政府のあいだにもこれを真剣に検討する動きも出た114)。抜き差しならぬ状況のなか,リー自身は 5月 6日からインドで行われる会議に出席するため再び外遊に出発し,その間,マレーシアを不在にした115)。前回の外遊同様,MSCの動きから距離をとって交渉のためのフリーハンドを保とうとした行動とも見えるが,国際社会に自らをさらに売って出る行動であったと解することもできる。リーはさらにその足で東南アジア諸国を訪問した。PAPはカンボジアに亡命政権をつくることも考えていたとも言われている116)。
シンガポール共和国建国への道リーたちは関係希薄化をめざして強硬姿勢を貫いたものの,こうして 5月半ば,連邦政府とシンガポール政府とのあいだの対立は先鋭化して制御不能となり,双方妥協による関係希薄化という軟着陸の解決は遠のくことになったと言えるだろう。そうとすれば,リーたちの前には,事実上,二つの帰結しか残されていなかったように思われる。リーが治安維持法で逮捕されるか,シンガポールがいったんは連邦から追放されるかである117)。前者は後でも見るように連邦政府が本気で検討した措置であったが,それに続くエスニック間暴動の事態も予想された。また,それがなかったとしても,「対決政策」が続くなか,どう考えても,国際世論―とくに同盟国アメリカの心証―へのダメージを恐れるイギ
リス政府が絶対に許さないシナリオであった。そうとすれば,リーたちがさらに突き進めば,後者のシナリオが展開される可能性が高かった。リーにも迷いや逡巡があったかもしれないが,このとき,MSC運動をそのまま続ければどこに向かうことになるのか彼にはっきりとした見通しがあったと考えてもおかしくはない。5月 21日,リーは帰国するが,そのとき,彼はそうした理解を示唆する次のような発言を行っている118)。
問題があるなら,今処理しましょう。5年, 10年と待つことはありません。もし現在マ レーシアがうまく機能していないのだとす れば,替りの枠組みalternative arrangement をつくることもできます。
実際,PAP政府は事態をより深刻化させながら,自らの道を切り開くことを選択することになった。激しい言葉の応酬が増していった背景には,連邦に留まり続けることの経済的な負担の深刻化もあった。共同市場の設立は望むべくもない状況に陥り,さらに州政府による外資への優遇措置が連邦政府によって骨抜きにされるなど経済財政上の締め付けが進んでいたのである。リーの右腕ゴー・ケンスイ財務相もすっかり幻滅していたのであった(Lee 1998: 600-601)。
5月 27日,リーは連邦議会下院で正面切って連盟党政府を否定する演説を行った。彼がマレー急進派と呼ぶマハティールMahathir bin Mohamadらを非難したうえで,連盟党政府の下では一部マレー人・華人のみしか豊かになれないであろうこと,1967年にマレー
113) The Straits Times, 16 May 1965. リー回想録(Lee 1998: 607)。114) 警察庁長官フェナーもリーの逮捕を許容する考えを持つに至ったのである。Minutes of a Meeting,
19 May 1965, DO169/529, NAUK.115) The Straits Times, 7 May 1965.116) 独立後にリーの秘書を務めるアレクス・ジョシーの著書参照(Josey 1980: 287-288)。117) トゥンクは分離時の発言でそうしたことを述べている。これについて,リーはその回想録で的を射
ていたと評している(Lee 1998: 649)。118) The Straits Times, 22 May 1965.
112 アジア・アフリカ言語文化研究 95
語が唯一の公用語になっても多くのマレー人の貧困は解消しないこと,PAPの政策こそがマレー人の貧困の解消に繋がること等を主張したのである。リーは次のように述べた119)。
華人には豪邸と大きな車を持つ億万長者がいます。似たように豪邸と大きな車を持つほんの一握りの億万長者を生みだすというのが連盟党の救済策ですが,それで根本問題の解決になるのでしょうか。……非マレー人にはあなたが貧しいのはマレー人のように特権がないからだと言い,マレー人にはあなたが貧しいのは野党がマレー人の特権に反対しているからだと言って国民を騙しても行く着く先がありません。村落部のマレー人が自分たちが貧しいのは私たちがマレー語を話さないからだ,あるいは政府がマレー語で文書を書かないからだと思い込まされたとすれば,彼らは 1967年に奇跡が起こることと期待するでしょう。すべての人々がマレー語で話し始めるとき,村人の生活水準は上がることと信じているでしょう。しかし,そんなことが起きなかったらどうなるんでしょう。……私たちを窒息させようとするのではなく,私たちが代替策を実行する機会を与えてください。私たちは機能する代替策を持っています。それはシンガポールで機能して来
たし,今後も実を結びつづけることでしょう。10年のうちに教育された心を持ち,反啓蒙主義的ではなく,科学技術と現代産業管理を理解したマレー人の世代を発展させることができます。
演説は途中からマレー語で行われ,マレー人たちを切り崩そうとしていることは明らかであった。後に,トゥンクはこの演説をラクダの背を折る麦藁 the straw that broke the camel’s backと表現し,これで決裂が決定的となったことを示唆している(Abdul Rahman 1977: 120)120)。これを受け,トゥンクはリーを逮捕する決断を下したが,ヘッドに止められ,おそらくはそれをもってやむなく自制した121)。現在公開されている史料を総合すると,分離への最終局面の進展は次のようなものであった,と考えられる122)。
6月 6日,MSC大会がシンガポール国立劇場で開催。三千人が集結した。「マレーシア人のマレーシア」を掲げて熱気溢れる集会となった123)。6月 11日,トゥンク,コモンウェルス首相会議に出席のためイギリスへ出発。しかし,彼は現地で帯状疱疹を発症して入院し,ほぼ 2カ月に渡ってマレーシアを不在にすることになった。彼はこの間に思索を巡
119) Speech by the Prime Minister, Mr. Lee Kuan Yew, During the Debate in the Federal Parliament, on the Motion of Thanks to the Yang di-Pertuan Agong for his Speech from the Throne, 27 May 1965, lky19650527, National Archives of Singapore. リーは連邦関係希薄化といった軟着陸を諦めて攻勢を強めたと考えることも可能である。6月 19日,リーは連邦政府への攻撃の主要な目的は関係希薄化交渉打開であったため,自らは直接関与しないよう注意を払ってきたが,当面,関係希薄化は考えていかない旨,イギリス側に伝えている。“Note of Conversation between Lee Kuan Yew and Moore,” 19 June 1965, DO169/530, NAUK.
120) リーもまた自分が行ったこの演説が決定的な意味を持っていたとしている(Lee 1998: 610-615)。121) 6月 1日,トゥンクはヘッドと会談を持ち,彼に「自らの義務を果たすことに躊躇しない」と述べ,
リー逮捕を実施する姿勢を示した。これに対し,ヘッドはリーを逮捕することは国際世論に大きなダメージを与えるため,絶対にしてはならない旨,強い警告をトゥンクに発した。Telegram from Kuala Lumpur to Commonwealth Relations Office, 1 June 1965, DO169/529, NAUK.
122) 分離はイギリス側に秘密にして進められたため,この間の詳細はどうしてもリー回想録やトゥンク回想録に頼るところが大きくなったが,なるべくその他史料も加えて構成した。
123) The Straits Times, 7 June 1965. リー回想録(Lee 1998: 616-621)。
113鈴木陽一:シンガポール共和国の建国について
らし,シンガポールの完全分離を決断124)。見舞いに訪れたリム・キンサン Lim Kim San開発相(新)にその旨を示唆した(Lee 1998: 628-629)125)。6月 29日,リーとラザクとのあいだで会談が持たれたが,話は全くかみ合わず,極めて不快な会談となった(Lee 1998: 624-626)126)。7月1日,トゥンク,病床からラザクに書簡。完全分離の方向を指示(Abdul Rahman 1977: 123)。7月 10日,シンガポール州立法集会ホンリム選挙区補欠選挙。PAPはバリサンと対決。結果は六割の票を得て PAPの勝利。シンガポール華人社会が PAPの英語教育組への支持で固まりつつあったことを示した127)。7月 20日,ゴー・ケンスイとラザクが会談。完全分離の方向で話を進めることで合意(Lee 1998: 629-631)128)。ゴーからの申し出であったという(Chew 1996: 147)。
8月 6日,前日,トゥンクが療養先のヨーロッパから帰国。ゴー,ラザク,イスマイル Ismail Abdul Rahman内相らが会談。分離法案,完成129)。8月 7日,リー,トゥンクと会談。リーは完全分離ではなく,国家連合という解決策はないものかと持ちかけるも,トゥンクが拒絶。リーはシンガポール主要閣僚であるトー,ラジャラトナムに合意書への署名を要請。両者は渋るも,最終的に署名(Lee 1998: 640-643, Chew 1996: 132-133)。8月 8日,日曜日。シンガポール政府閣僚,招集される。合意書に署名(Lee 1998: 644-645)。この日,ヘッドは連邦政府のある閣僚から分離の決定を知らされる130)。ウィルソンは分離声明を出さないようトゥンクにメッセージを発信131)。8月 9日,午前 10時,シンガポール政府,独立を宣言。連邦議会上下両院が憲法・マレーシア(シンガポール修正)法案を可決。国王,即日裁可。
124) The Straits Times, 12 June 1965. トゥンク回想録(Abdul Rahman 1977: 122-123)。125) The Straits Times, 15 August 1965. リムは実業家で多芸な人であった。開発相として住宅建設で名
をあげ,シンガポールをつくりあげた人物として知られる。老後はシンガポール出版持株会社の代表を務めた。リーからの信頼が篤かったが,トゥンクとの関係も良好であった(Asad-Ul Iqbal Latif 2009)。筆者がガザリ・シャーフィーから聞いたところに拠れば,裕福なリムはトゥンクとは競馬の馬主仲間であった。しかし,このとき,リムはトゥンクの真意を測りかねていたようである。
126) The Straits Times, 15 August 1965. 7月 22日,ラザクはリーやゴーとの会談の内容をトゥンクに報告した(Abdul Rahman 1977: 123)。
127) 6月 16日,オン・エングアンが再び議員を辞し,このための補欠選挙が実施された。辞任の理由については依然として明らかではないが,連邦政府の差し金があった―PAPの支持率を測るため,オンと話をつけた―とする説が有力である(Lee 1998: 622-624, Yap et al. 2009: 291-294)。
128) この 7月 20日の会談が決定的であったことを考えると,分離にあってはゴーの役割が非常に大きかったことに気づかされる(Yap et al. 2009: 297-299)。ただ,だからと言って,ゴー・ケンスイがリーの意向に反して独走したとは考えづらい。リーの回顧録に拠れば,会談後,リーは分離も含めた交渉の権限をゴーに与えた(Lee 1998: 629-630)。また,エディには分離協定の起草も命じた(Lee 1998: 631)。ゴーが交渉を進めれば,分離(あるいはよくてより緩やかな連邦の形成)などに至るであろうとの未必の故意の下,リー自らは前面に出ないで交渉をゴーに任せたというのが正しい解釈のように思える。分離におけるゴーの役割は大きいが,流れをつくったのはリーと言える。
129) The Straits Times, 6 August 1965. リー回想録(Lee 1998: 638-639)。チュウによるインタビュー(Chew 1996: 132)。
130) それが誰なのかは電信のうえでははっきりしない。Telegram from Kuala Lumpur to Common-wealth Relations Office, 8 August 1965, DO169/532, NAUK. これをステファンであったとする見方もある(Luping 1994: 146)。
131) Telegram from Commonwealth Relations Office to Kuala Lumpur, 8 August 1965, DO169/532, NAUK.
114 アジア・アフリカ言語文化研究 95
分離交渉はすべて秘密裏に進められた。完全分離の提案は連邦政府側から出されたが,協定案はシンガポール側でつくられた。本稿序論でも述べたように,協定では第 5章で分離後に両国が防衛援助条約を締結すること,第 6章で同じく経済協力することが謳われ,両国が秘密交渉では結実できなかった事実上の国家連合をめざしていくことが定められた132)。機密にされたのはイギリスの介入を避けるためであった。リーはこれを関係希薄化交渉の妨害に出たヘッドに対するクーデターであると述べている(Lee 1998: 639)。
8月 9日,シンガポールが独立した。このとき,リーはテレビ会見で涙ながらにシンガポールの分離独立を説明し,次のように述べた後,会見を途中で打ち切ったことは本稿冒頭でも記した通り有名である。半島・シンガポールの歴史的・社会的一体性に沿って統一国家をつくりあげたものの,自分たちの力は至らなかった。リーはその苦悩を語った133)。
マレーシアからシンガポールが切り離す協定に署名したときのことを思い出すとき,誰もが苦悩のときを噛み締めることになるでしょう。私にとっても苦悩のときです。人生のすべて,成人になってからのすべて,二つの地の統合と統一を信じていたのですから。私たちは地理に拠って,経済に拠って,親族関係に拠って繋がっているのですから。
リーにとっては忙しい日であったが,最後の客人はヘッドであった。その晩,クアラルン
プールから飛んで来たのである。このとき,リーはヘッドにシンガポールを承認する訓令を本国から得ているかを問い質したという(Lee 1998: 651)。
第 4章 分離独立の後
シンガポールの独立は早々に多くの国々によって承認され,9月,同国は国際連合への加盟も果たした。同月 21日,マレーシアのイスマイル内相らが総会で演説し,加盟国にシンガポールの加盟承認を求めたのであった134)。ただし,インドネシアはシンガポールの独立を認めようとせず,「対決政策」は1966年まで続いた。その間,1965年 10月 1日未明,インドネシアでは共産党によるクーデター未遂事件が発生し,その後,陸軍が徐々に国政の主導権をとるようになった。彼らのなかには「対決政策」の継続に消極的な者たちもいた。が,これを推進して来たスカルノ大統領はしばらくその地位にとどまり,インドネシアの政情不安定は回りの国々の不安の種となった135)。「対決政策」の終結には日を要したのである。イギリスは再び PAP政府の直接の庇護者となった。マレーシアからの分離を振り返り,リーはそのときの感慨について,後に次のように述べている136)。
自分たちが,後背地もなきまま,東南アジアにおけるイギリス帝国の中心にあることに気づかされました。
132) 協定は法務相であったエディ・バーカーが起草した。また,リーはこれを妻の柯玉芝に見せ,柯はこれにジョホール州からの水の供給を確保する条項を加えたとされる(Lee 1998: 631-632)。
133) Transcript of a Press Conference by the Prime Minister, Mr Lee Kuan Yew, at the Broadcasting House, Singapore, 09 August 1965, lky 19650809b, National Archives of Singapore. 現在,8月 9日は独立記念日であり,会見は国民の重要な記憶となっている。記者会見の様子はインターネットの動画サイトなどでも見ることができる。
134) The Straits Times, 23 September 1965.135) リーはこの事件で困惑が深まったと回想している(Lee 2000: 25)。136) The Straits Times Weekly, 5 July 2003.
115鈴木陽一:シンガポール共和国の建国について
英語を操るプラナカンたちは今また帝国の支援をあてにした。シンガポールはイギリス軍の極東の拠点であった。基地が存続する限りイギリスとの特別関係は続き得た。ただ,ここで重要なことは,第 1章末でも若干述べたように,そうした関係がいつまでも続くという保証はどこにもない,ということであった。逼迫していた財政事情に鑑みれば,アメリカの引き留めを振り切って,イギリスがシンガポールから撤退する日も遠くないという観測も出された。シンガポールはムラユの多島海のなかの孤島となりかねなかった。イギリス人の撤退までにシンガポールの人々は自らの生きる場を確保しなければならなかった。そうしたなか,シンガポール政府はマレーシア政府との関係の再構築をめざしたものの,ことは思うように進まなかった。分離時,両政府はその後の協力関係の大枠を約して円満に別れたはずであった。防衛援助条約を締結し,経済分野で協力し,事実上の国家連合をめざそうとしたのであった。しかし,両者は「対決政策」終結などをめぐって関係を悪化させ,さらにマレーシアの連邦のあり方も変容するなか,分離協定に謳われていた関係の構築は困難をきわめた。本章では,シンガポール分離後,マレーシアが変容する過程について概観した後,シンガポール政府とマレーシア政府が協力関係の構築を模索しつつも,緩やかな再合同への展望を消滅させていった過程について見る。
連邦とボルネオシンガポール分離の衝撃はその直後からボルネオを襲った。ボルネオの非ムスリムを中心とした野党勢力が PAPの誘いに乗って連邦政府に対抗しようとしていたことについては前章で述べたとおりである。彼らにすれば,PAPの離脱は深刻な痛手であった。そもそも,連邦からシンガポールの華人たちが抜け 出れば,連邦全体の人口における非ムスリム人口の比率は低下することになり,そうなれば,ボルネオの非ムスリムの地位も相対的に低下することは目に見えていた。それにもかかわらず―あるいはおそらくそれゆえに―分離の手続きはボルネオの人々には知らされずに進められた。両州の首席大臣に知らされたのは分離の前日であった137)。以降しばらく,連邦政府・ボルネオ州政府関係は不安定な状態に置かれることになった。まず動きを起こしたのはステファンであった。8月 16日,UPKOはサバ州のマレーシア編入のあり方の見直し re-examinationを決議し,ほかのサバ州連立与党にも見直しに同調するよう働きかけたのであった。見直しという言葉は多義的で様々な解釈が可能であった。連邦をより緩やかな関係に変えていくという見直しもありえた。ただ,当時,ステファンが強く意識していたのは最も急進的な分離独立の構想であった。こうした考えの背景には,シンガポール抜きのマレーシアという状況は連邦協定の前提を欠いたものである,という主張があった138)。これを受け,8
137) Telegram from Kuala Lumpur to Commonwealth Relations Office, no.1369, 11 August 1965, DO169/534, NAUK. リー回想録(Lee 1998: 637)。
138) Telegram from Kuala Lumpur to Commonwealth Relations Office, no.1411, 17 August 1965, DO169/364, NAUK. Telegram from Kuala Lumpur to Commonwealth Relations Office, no.1414, 17 August 1965, DO169/364, NAUK. これまでの研究においては,このときのサバの動きはマレーシアへの編入の条件の見直しという曖昧な言葉で語られてきた(Luping 1994: 147-148)。しかし,その内容は連邦離脱も辞さない過激なものであった。
ステファンが模索した「独立」の真意については解釈が分かれる。彼の主要な目的は混乱に乗じての首席大臣の地位回復であった,というのが現地の政治の見方であった。Telegram from Kuala Lumpur to Commonwealth Relations Office, no.1431, 18 August 1965, DO169/364, NAUK. ただ,見直しという言葉が出された以上,独立ほどではないにしろ,サバ州が自治権を大幅に拡充する案をUPKOが練ろうとしたということは考えられる。ステファンは自らを首席大臣とする権限が強化されたサバ州を着地点として考えていたとも考えられる。
116 アジア・アフリカ言語文化研究 95
月 17日,サバ連盟党国民評議会は連邦のあり方について見直しを検討する委員会を設置することを決したのであった139)。しかし,こうしたサバ分離独立への動きはイギリス政府と連邦政府の連携によって封じられることになった。イギリス副高等弁務官はフェナー警察庁長官から情報を受け,これを本国に伝えた。ここでコモンウェルス関係相はボルネオの連邦離脱となればその防衛責任を負わないという趣旨の指針を示したのであった140)。イギリスとしては,ここまでして守り続けてきたマレーシアが自壊するなど論外であったし,ボルネオの小国を将来に渡って守る余裕もなかった。連邦政府ももちろんサバ州の分離阻止に動いていた。連邦はイギリスの方針を歓迎し,サバ州主席大臣ピーター・ロー Peter Loと連絡をとりながらその対処にあたった141)。この間,ステファ
ンはイギリス側に離脱を支援してくれるよう依頼したが,イギリスは分離はありえないとの姿勢を示した。彼はイギリスの後ろ盾を得られないことを悟ると意気消沈した142)。結局,こうした流れのなか,サバ連盟党はマレーシア編入のあり方の見直しについては話を先送りとしたのである(Luping 1994: 148-149)。さらに 20日,トゥンクがジェッセルトンを訪問し,サバ州の分離を図る者は反逆者であると強い調子でスピーチを行うと,以降,州政治の形勢は完全に反転し出した143)。サバ連盟党はステファンとUPKOへの攻撃を強め,10月,ステファンを民族融和を侵したかどで党から追放する手続きに入った。こうした圧力の下,ステファンはUPKO総裁を辞任することを余儀なくされ,UPKOは「見直し」の主張を取り下げた(Luping 1994: 153-159)144)。この後,紆余曲折しなが
139) Telegram from Kuala Lumpur to Commonwealth Relations Office, no.1431, 18 August 1965, DO169/364, NAUK. なお,ルピンはこの間の政治過程について,本論文とは詳細において異なった記述を行っている(Luping 1994: 144-149)。
140) UPKOの決議について,フェナーはイスマイル内相に告げる前にイギリス側に告げていたようである。Telegram from Kuala Lumpur to Commonwealth Relations Office, no.1411, 17 August 1965, DO169/364, NAUK. コモンウェルス関係相はヘッドと相談のうえで次のような指針を示した。“If the Borneo territories go, ... it would be unwise for the Borneo territories to make any assumptions about where they would stand in relation to Britain.” Telegram from Commonwealth Relations Office to Kuala Lumpur, no. 2127, 17 August 1965, DO169/364, NAUK.
141) Telegram from Kuala Lumpur to Commonwealth Relations Office, no. 1423, 18 August 1965, DO169/364, NAUK.
142) Telegram from Kuala Lumpur to Commonwealth Relations Office, no. 1414, 17 August 1965, DO169/364, NAUK. Telegram from Kuala Lumpur to Commonwealth Relations Office, no. 1431, 18 August 1965, DO169/364, NAUK. ヘッドはステファンにイギリスのスタンスを示した書簡も送った。Telegram from Kuala Lumpur to Commonwealth Relations Office, no. 1433, 19 August 1965, DO169/364, NAUK.
143) The Straits Times, 22 August 1965. その翌日,トゥンクはステファンとゴルフを共にしたようである。ステファンが首席大臣になりたい旨申し出ると,トゥンクはこれを断るとともに,連邦州関係の変化を求めることのないよう説得に入り,さらに駐イタリア大使への転出を提案したようである。“Sabah: The Retirement of Dato Donald Stephens,” Memorandum, December 1965, attached to a letter from R. R. G. Watt to A. K. Mason, 14 January 1966, DO169/364, NAUK. このときのトゥンクによるボルネオ訪問については様々な評価があり得る。新聞報道を読む限り,恫喝染みたトーンは否定できない。ボルネオに憤激をもたらしたとの評価もある。Telegram from Kuala Lumpur to Commonwealth Relations Office, no. 1454, 21 August 1965, DO169/364, NAUK.
144) ステファン辞任の顛末を記したイギリス人の書簡には,ステファンが辞任に追い込まれた理由は「彼が本当のハード・コアを得なかった」ことにあったとする記述がある。シンガポール分離の際,その機会を利用して―本当にそうするかどうかは別として―サバの分離を主張し,そのことをもって自分の地位を回復しようとはしゃいだものの強く賛同する人々を得られなかった,との解釈である。同書簡には,USNO側からテープの証拠がある旨の主張があってステファンが弱さを見せるようになったこと,また,ステファンがシンガポールのリー・クアンユウへ電話を掛けた ↗
117鈴木陽一:シンガポール共和国の建国について
らも,サバ人は自らの手で建国の父を失脚させ,ムスリムがリーダーシップを取るマラヤ化の道を進んだ145)。1967年,連立与党はとうとうUPKOの解散を求めた。ステファンは連邦がサバを植民地の如く扱っていると非難したが,UPKOは自らを解散せざるを得なかった(Luping 1994: 239-250)146)。他方,サラワクにおいては,同年の土地法危機の後,しばらく表立った政治危機は起きなかったものの,州政府を主宰するニンカン への風当たりは次第に強まることになった147)。
サラワク州政治においてムスリムが相応の発言権を得ていないことは連邦政府の不満の種であった。1966年 2月,トゥンクがサラワクを訪問して分裂していたムスリム政党の合同に動くと,これは州政府を刺激した148)。こうして,両者のあいだで舌戦が始まった。いくつかのことが言争われたが,最も激しい争点は言語政策であった。連邦政府は翌年1967年からマレー語を唯一の公用語とすることを考えていたが,サラワク州政府はこれにきわめて消極的であった。英語を引き続き
↗ ことを連邦政府は察知していたことなどについての記述もある。ただし,シンガポールとの連携を図ったのか,書簡では定かではない。Letter from R. R. G. Watts to P. Jenkins, 5 November 1965, DO169/364, NAUK. なお,ステファンが辞任を迫られた理由について,ルピンは(1)リー・クアンユウとの電話テープ問題,(2)イギリス側にシンガポール分離を事前に漏らした問題の二つを挙げている(Luping 1994: 146)。
当初ステファンが分離を排除しない姿勢をとったことは彼にとって大きな仇になったということは言えるであろう。本文でも記したとおり,当初,ステファンはイギリスに分離独立への理解を求めたものの,これに失敗した。そのためか,UPKOの決議は表向きはマレーシアへの編入条件の見直しを求めるという表現に留められた。しかも,事態が紛糾していく過程において,ステファンは自分は分離などということは口にしていないとして自分の立場を公に弁明するようになった。Letter from J. T. Masefield to P. Jenkins, 8 September 1965, DO169/364, NAUK. 見直しへの支持が広がらないなか,分離の主張はまったくのタブーとなったのである。さらに問題であったのは,分離の主張を主導したのはおそらくステファンその人であったろうということである。UPKOは一枚岩ではなかった。ジャヤスリヤ Jayasuriya自然資源相のようにその阻止に動いた者もいた。Telegram from Kuala Lumpur to Commonwealth Relations Office, no. 1431, 18 August 1965, DO169/364, NAUK. ステファンは煽り行為に出ていたとも言えるのである。
145) 田村慶子は先駆的な研究でマラヤ化―文化的にマレー文化が支配的になること―という概念を用いた。政治的に連邦のコントロール下に置かれることまでは意味しないと解される。ここではほぼその定義に従ってこの語を用いた(田村 1988)。
146) この後,サバはムスタファの時代を迎える。連邦州関係の安定が期待されたが,連邦政府は強力になり過ぎたUSNOに手を焼くことになる。国民戦線がそのなかにボルネオ諸政党を迎え,セーフガードに守られたボルネオが連邦与党の牙城となるのはこれよりずっと後のこととなる。
147) サバが揺れる傍らにあって,ニンカンたちはサラワクがマレーシアに留まる旨を公言していた。The Straits Times, 13 August 1965. サバ州で動きがあることは注視していたものの,ステファンの真意は連邦からの離脱ではないと読んでいたようである。サバ州が連邦から譲歩を勝ち取れば,サラワク州も同様のものを得られるというのが彼らの目算であった。ただ,本当にサバ州が分離してしまえば,彼らは政権維持できず,同様に分離しなければならなくなると自覚していたようである。Telegram from Kuala Lumpur to Commonwealth Relations Office, no. 1422, 18 August 1965, DO169/364, NAUK. Letter from J. T. Masefield toP. Jenkins, 7 September 1965, DO169/364, NAUK.
ニンカンはイバン人と華人のあいだに生れたとされる。シェルの従業員として働き,その後,SNAPの形成に関わった。イバンの支持と華人の財力を背景に台頭したと言える。ただ,彼は有能であったものの,敵も多く,この頃までに多くの問題を抱えるようになっていた。イギリスの公文書では,私生活上の問題として,ムスリムでないにもかかわらず 4名の妻を持っていたこと,酩酊して警察沙汰の喧嘩を起こしたことなどが記録されている。さらに華人政商への土地取引に腐敗があったとされ,同じ非ムスリムにも不満が高まっていたとされる。Letter from R. R. G. Watts to A. K. Mason, 14 February 1966, DO169/369, NAUK. Dispatch from F. W. Marten to Michael Walker, 28 June 1966, DO169/369, NAUK.
148) このとき,連邦政府は寄付を行ったが,その大半はムスリムに向けられた。当然,そのことも刺激となった。Telegram from Kuching to Kuala Lumpur, 1 March 1966, DO169/369, NAUK.
118 アジア・アフリカ言語文化研究 95
公用語とし続けようとしたのである。もともと,マレーシア憲法をつくる過程において,英語は,同連邦設立後 10年間,ボルネオ各州の公用語であり続け,各州の承認がない限り,その後も公用語であり続けることになっていた。それゆえ,ニンカンは 1973年以降も英語が公用語であり続けるべきことを示唆したが,これは物議を醸すだけとなった149)。かくして,6月,連邦政府の支持を背景
に事態は州議会議員 21名がニンカンの首席大臣辞任を求める願書を出す事態へと発展した150)。議会が開かれたとは言えなかったし,21名では議席のうえで過半数にも達しなかったが,連邦政府は彼に辞任を強く求め,同月 17日,州元首は新しい首班を任命し,新しい内閣が形成された。その後,法廷闘争において高等裁判所はこれを無効とし,9月 7日,ニンカンは職務を再開したが,同月 15日,連邦は共産主義勢力の脅威を理由
にサラワクに非常事態宣言を出し,24日,ニンカンは再び職を追われた。連邦政府に協調姿勢をとるタウィ・スリ Tawi Sliが後任に着いた151)。この間,イギリス政府はニンカンたちの動きを同情的に見守ってはいたものの,彼らを助けようとはしなかった。非常事態宣言には相応の根拠がないと見ていたものの,そうしたことを主張しなかった152)。イギリス政府は自分たちに争いの火の粉が飛んで来ないようにすることで手一杯となり,それどころではなかったのである。トゥンクは,サラワクにおいては英語が使い続けられているだけではなく,イギリス人官僚がその政府を切り盛りしていることも指摘し,同州が依然としてイギリスの影響下にあることを問題視した発言を行った153)。さらに,ニンカン再解任に至る過程では,在クチン一等書記官の発言が内政干渉にあたると連邦議会で問題視される
149) これには多くのイバン人たちがマレー語よりも英語の読み書きに慣れていたという事情もあったとされる(Leigh 1974: 88-91)。
150) 連邦政府内にはニンカンを追い落とそうとする一派があったものの,当初,連邦指導部はそれほど強硬ではなかったと推察される。Letter from R. R. G. Watts to A. K. Mason, 11 May 1966, DO169/369, NAUK. しかし,「対決政策」が終結に近づく頃になると,連邦政府はニンカンの解任に打って出た。トゥンク自身がイギリス側に語ったところに拠ると,その第一の理由は,ニンカンが土地・木材に関する許認可権を用いて多額の賄賂を華人たちから受け取り,これを半ば吹聴していたことにあった。Telegram from Kuala Lumpur to Commonwealth Relations Office, 15 June 1966, DO169/369, NAUK. ただ,史料を見ると,当時,もっと抜き差しならないことが起こっていたこともわかる。5月,ニンカンはサラワクがマレーシアから離れ,シンガポールと一緒になる構想を吹聴していたらしい。Letter from R. R. G. Watts to A. K. Mason, 7 June 1966, DO169/369, NAUK. ただし,そのことがニンカンの解任にどれほど影響したか,これにリーの関与があったのかは不明である。7月,浪人中のニンカンはシンガポールを訪れ,リー・クアンユウと会談を行った。しかし,リーの対応はつれないものであった。ニンカンは選挙の専門家を派遣してほしい旨要請したが,リーはこれを断った。さらに,リーは会談がニンカンの要請で開かれたことを文書にしてニンカンに署名させた。The Straits Times, 16 July 1966. Letter from J. W. Maslen to A. K. Mason, 23 July 1966, DO169/369, NAUK.
151) 非常事態宣言を受け,連邦議会は州議会に代わって州憲法の改正を行い,州元首が州議会を招集できるようにしてこれを開催させた。こうして,9月 23日,抗議するニンカンたちが欠席するなか,州議会は首席大臣への不信任を決議し,翌日,州元首がこれを解任したのである。The Straits Times, 18 June, 8, 24, 25 September 1966. レイの研究(Leigh 1974: 102-111)。
152) このとき連邦政府が発表した「サラワクへの共産主義の脅威」はその前年の「対決政策」の最絶頂につくられたもので,実情にそぐわないものであった。Dispatch from F. W. Marten to Michael Walker, 27 September 1966, DO169/370, NAUK.
153) 連邦政府はサラワク州においてイギリス人官僚が居座り続けるだけではなく,権勢を握っていることに苛立ちを募らせていた(Leigh 1974: 99-102)。確かに,当時,政策決定はまず最初にニンカンとイギリス人官僚らが話し合い,次に主要閣僚らが話し合って,その次に閣議が行われる,というかたちをとっていたようで,彼らの役割は極めて大きかったようである(Leigh 1974: 83)。
119鈴木陽一:シンガポール共和国の建国について
局面もあった154)。発言を問題視した本当の目的はニンカン一派の追い落としであったと考えられるが,事件はラザク副首相からの当該書記官退去の要請にまで発展した155)。また加えて問題であったのは,ニンカン自身がそうしたイギリスからの支援を示唆するような発言をしていたことであった。ニンカンはサラワクが独立すればイギリスがこれを守るだろうと吹聴し,連邦政府内にもこれを疑う者が出たのである156)。独立国サラワクの防衛など考えたくもない重荷であった。イギリス政府はその意図が微塵もないことを明らかにすることに躍起となった157)。
シンガポールとマレーシア 最初期の関係こうした傍ら,マレーシア・シンガポール両国政府は秘密交渉では成しえなかった関係の再構築を探ることになった。重要なことは両国とも互いを必要であると考えていたということであった。分離の日の記者会見においてリーは次のように述べているのである158)。
トゥンクは私に次のように述べました。あなた方がマレーシアの一員でなくなれば,
議会や選挙区で争うことがなくなる。再び友人に戻れるし,互いに相手を必要とし,協力できる,と。そうなることは私(引用者注:リー)の心からの願いです。
何度も強調するように,分離協定第 5章では防衛援助条約の締結,第 6章では経済分野での協力が謳われていた。大雑把に言えば,マレーシアは統合防衛委員会 joint defence councilを設立することでシンガポールの治安・安全保障に関与することを望み,シンガポールは共同市場を設立することでマレーシア市場を確保することを狙っており,双方が協力しながら事実上の国家連合を構築していくことが協定に明記されていたのである。実際,インドネシアとの対立が続いていたため,8月早々,両国は暫定的なかたちで防衛協力に合意した。マレーシア政府内にすでに設置されていた国防委員会は合同防衛委員会Combined Defence Councilと改称され,シンガポール側からは新設の内務防衛相に就いたゴー・ケンスイが引き続きこれに出席することになった159)。ただ,両政府は分離後も緊密に協力してい
154) Telegram from Kuala Lumpur to Commonwealth Office, no. 1308, 21 September 1966, DO169/370, NAUK.
155) Telegram from Kuala Lumpur to Commonwealth Office, no. 1307, 21 September 1966, DO169/370, NAUK. Telegram from Kuala Lumpur to Commonwealth Office, no. 1323, 22 September 1966, DO169/370, NAUK.
156) Telegram from Kuala Lumpur to Commonwealth Office, no. 1438, 21 October 1966, DO169/371, NAUK.
157) コモンウェルス省官僚はサラワクが独立して共産主義の手に落ちたとしてもこれは単独で介入する ことはできないとさえ考えており,サラワクの内紛に関与することは選択肢になかった。Letter from J. O. Moreton to J. R. A. Bottomley, 21 November 1966, DO169/371, NAUK. 問題はイギリスの意図をどう表明するかであったが,高等弁務官が直接トゥンクにイギリスはサラワク,サバの責任 を再び負うことを考えていないこと,内政に干渉しようとしていないことが告げられた。Saving Telegram from Kuala Lumpur to Commonwealth Office, 25 November 1966, DO169/371, NAUK.
158) Transcript of a Press Conference by the Prime Minister, Mr. Lee Kuan Yew, at Broadcasting House, 9 August 1965, lky 19650809b, National Archives of Singapore.
159) シンガポール軍の創設に大きな役割を果たしたのはゴー・ケンスイとジョージ・ボガーズGeorge Bogaarsであった。分離直後,防衛のみならず,治安も担当する行政組織として内務防衛省MID:Ministry of Interior and Defenceが新設された。警察組織から特務部が切り離されてこれに加 えられた。財務相であったゴーが大臣,特務部長であったボガーズが次官を務めた(Huxley 2000: 9)。コンフロンテーションが続くなか,ラザクとゴーは(1)軍事作戦のために取り決めたことをなるべく動かさないこと,(2)両国の防衛が一体であることの証としてシンガポール第二大隊をボルネオでの任務に派遣することなどで合意した。Telegram from Singapore to Commonwealth Relations Office, 11 August 1965, DO169/450. 委員会の名称変更はこの合意の後になされた。
120 アジア・アフリカ言語文化研究 95
くことを約し合ってはいたものの,実際の両国関係は苦渋の過去を反映してきわめて不安定なものとなった。舌戦がすぐに始まることになった。マレーシア側から政府関係者の不用意な発言が繰り返されると,シンガポール側からはリー・クアンユウ自らが挑発的発言で応酬した160)。両国は正式に抗議の文書を突き付けあった。政府の責任ある地位にあるものが対岸の隣国の政治について下手にコメントすれば内政干渉になることは明らかであったが,そうした事実が実感を伴って人々に共有されるには年月が必要であった。両国民のメディアは従来通り共有されており,同じメディアの上に載る互いの記事を無視すること自体が不自然であったとも言える。メディアの側も両国が別個の国家であることへの配慮は少なかったし,多くの読者もまたそうであったかもしれない161)。さらに,対決政策を続けるインドネシアとの関係のあり方も両国のあいだの重要な争点となった。インドネシアにおいては,共産党によるクーデター未遂事件を経て,陸軍が権力を掌握しつつあったが,彼らも依然としてマレーシア粉砕を唱える状態にあった。そう
した傍ら,10月下旬,シンガポール政府が同国とのバーター貿易を再開したい旨を明らかにすると,マレーシア政府は緊急の閣議を開催して声明を出し,そのことについて公式には何ら相談がなかったとしてシンガポール政府を強く牽制した。再開は対決政策始まって以来の最も深刻な安全保障上の脅威をもたらすというのである162)。事件の背景にはシンガポールがインドネシアと結んで仕返しを行おうとしているのではないかとのマレーシア政府の懸念があった。26日,ヘッドはトゥンクに呼び出されて事情の説明を受けた。リー・クアンユウが弟のデニス・リー Denis Leeをインドネシアに派遣し,そのための話し合いが行われたというのである。シンガポールがコーズウェイの水パイプラインを自ら破壊してこれをマレーシアの仕業として非難することを計画しており,これを受けてマレーシア政府は実際にコーズウェイに警備態勢を敷くことにした,との説明であった163)。両国間の関係は疑心暗鬼の状態にあったのである。すでに互いに進出し合っていた政党の清算,とりわけ PAPがマレーシアに残した支
160) リーは「サバ,サラワクの人々はマレーシア人のマレーシアを持つべきである」といった発言もしている。Telegram from Singapore to Commonwealth Relations Office, 17 September 1965, DO169/537, NAUK. マレーシア政府が神経を擦り減らすような発言であった。
161) すでに分離前,代表的英字紙ストレイツ・タイムズはクアラルンプール版とシンガポール版とに分けて発行されるようになっていたが,この後,これらは別々の新聞となった。両国政府・与党がそれぞれのメディアを完全に掌握するのはそれよりさらに後のことである。
162) この頃,インドネシアとのバーター貿易は禁止するとの馬新合意が存在していた。The Straits Times, 25, 26 October 1965.
163) 情報源は警察機構からのものではなかった。ヘッドはフェナーに確認したが,トゥンク自身の非公式な情報源からのものであるとのことであった。Telegram from Kuala Lumpur to Commonwealth Relations Office, no. 1771, 26 October 1965, DO169/537, NAUK.
シンガポールとインドネシアとのあいだでこうしたことについて話し合いが行われていたのかどうかは定かではない。前月,リーはインドネシアから貿易について密使を受けたことをイギリス側に漏らしている。リーはインドネシアを信頼できないとして暫く交渉を断つと述べたが,交渉再開の可能性は否定しなかった。Telegram from Singapore to Commonwealth Relations Office, no. 432, 17 September 1965, DO169/537, NAUK. ただ,たとえ話し合いが持たれていたのだとしても,このようなことが話題になったとは考えづらい。インドネシアによる情報操作であった可能性は否定できない。重要なことは,マレーシアがこのような不確かな情報を真に受け実際に警備態勢を敷いたことであった。
ヘッドは困惑し,両国にイギリス軍の引き揚げを示唆して圧力を掛けてみてはどうかとの進言を コモンウェルス関係省に行っている。Telegram from Commonwealth Relations Office to Salisbury, 27 October 1965, DO169/537, NAUK.
121鈴木陽一:シンガポール共和国の建国について
部の扱いも困難な問題であった。PAP本体はMSCから早急に離脱したが,同党は活動を共にした党員たちをマレーシアに残していた。先の連邦議会下院議員選挙ではナイアが当選を果たしており,彼の扱いも一つの論点となった。PAP本部としては彼らに活動を停止せよなどと言える立場にはなかった。それゆえ,結局,政党登録は非常に手間取ったものの,彼らは党名を変更して民主行動党 DAP: Democratic Action Partyとして政党登録し,別の政党として活動を継続することになった。ナイアは書記長として草創期のDAPをリードすることになった164)。確かに,両国のあいだのこうした困難さは両者が分かち難く結びついている証拠とも言い得た。分離協定の内容に照らして考えても,いずれは何らかのかたちで再合同があるというのは当時の共通の見方であった。「対決政策」が終わってひと段落を迎えれば,ゆるやかな連合のかたちで関係が再生するだろうとも考えられた。この頃,表向きには口にしなかったものの,リーは次のような楽観的な見方をイギリス側に述べた165)。
決定的なときは対決が終わるときに来ます。……イギリスが軍隊を引き揚げます。そうするとすぐに,トゥンクはサバとサラワクで問題を抱えることになります。両州がトゥンクに従順であったのは,イギリス軍がいて安全が確保されたからなのです。そのときこそがトゥンクにシンガポールとの争いについて解決をつけるよう促す心理的に最も適切な瞬間となります。理想的な解決策はシンガポールの連邦への復帰,ただしシンガポールに受け入れられる共同市場を伴った緩やかな国家連合の形でです。
イギリスがボルネオから軍隊を引き揚げれば,サラワク,サバの不満を抑えるために連邦は緩やかなものとならざるをえず,さらに言えば,そうした枠組みならばシンガポールが連邦に再加入することも可能と考えたのである。交渉で実現できなかった緩やかな結合のマレーシアを実現し,そのうえで自州の社会経済政策を成功させることで連邦政治への復帰を目論んだとも考えられる。しかし,ここで留意すべきは,シンガポール・インドネシア間の対話の噂がマレーシアを強く刺激したことに見られるように,馬新両国が協力に向けて曲がりなりにも前向きに努力しえたのは実はインドネシアという共通の敵がいればこそでもあった,ということであった。分離後,両者がそれなりに関係の再構築を模索していた背景には,第三国からの武力行使が両国にいやがおうにも協力せざるを得ない強い誘因として働いていたのである。そして,そうとすれば,対決が終わればそうした誘因は確実に低下するだろうし,また,終わろうとする瞬間こそはリーの期待に反して最も危険なときであった。そして,実際,1966年初頭以降,インドネシア国内の権力闘争においてスカルノが追い詰められ,「対決政策」が終わろうとするなか,両国のあいだにはいくつかの問題をめぐって強い緊張が走ることになったのであった。
コーズウェイ危機まず浮上したのはシンガポール第二大隊の帰還をめぐる問題であった。分離に伴い,シンガポール政府はマレーシア軍から二個大隊を引き継いだが,「対決政策」が続くなか,両大隊を引き続きマレーシア軍の指揮下に置き,しかもうち第二大隊を両国の連帯の
164) 分離のとき,リーからの帰国要請にもかかわらず,ナイアはマレーシアに留まった。しかし,1967年末ごろ,馬新関係に鑑みてほしいとのリーの説得を受けて彼はシンガポールに帰ることにした。 Devan, Janamitra, “Remembrance,” http://dapmalaysia.org/english/2006/june06/bul/bul3032.htm, 2016年 3月 20日閲覧。彼は後に第三代シンガポール共和国大統領となる。
165) Telegram from Singapore to Commonwealth Relations Office, 12 January 1966, DO169/537, NAUK.
122 アジア・アフリカ言語文化研究 95
証としてボルネオでの任務に派遣していた。そこで翌年 2月,紛争の鎮静化が見られるようになったなか,この大隊が任務を終えてシンガポールに帰還しようとしたところ,驚くべきことに,その間にシンガポールの基地に陣取っていたマレーシア軍がそのまま居座りを続け,当該基地への大隊の帰還を拒否しようとしたのであった166)。確かに,両国の分離協定第 5章では,両国は共同防衛のため,統合防衛委員会を設けるだけではなく,シンガポールがマレーシア軍の駐留を認めるものとされており,マレーシア軍の国内駐留には国際法上それなりの裏付けがあった。マレーシアとすれば,前記分離協定の趣旨は,シンガポールの意向も踏まえながらマレーシアが同国の防衛を受け持つ―さらに言えば同国を庇護下に置く―というものに近かった。しかし,シンガポールとすれば分離協定第 5章は未だ話が進んでいない同第6章(経済分野での協力)の実現をもっての み有効なものであった167)。さらに,彼らは駐留を「対決政策」終結までの暫定措置と位置付け,マレーシア軍は退去すべきと考えた。シンガポールとすれば,マレーシアとシンガポールとは安全保障においてもあくまで対等なのであった168)。その意味で,第二大
隊の帰還問題は分離協定では曖昧になっていた分離後の国家間関係のあり方について双方の思惑の違いがここに至ってあからさまなかたちで噴出したものとも言えた。結局,こうした状況のなか,シンガポール側はそれまで参加してきた合同防衛委員会,合同作戦委員会 Combined Operations Committee,合同諜報委員会 Combined Intelligence Staff Committeeへの出席を停止することにした169)。 これに並行し,3月 1日,マレーシア側は分離協定に定められた防衛条約の締結に向けた話し合いを正式に申し出て,シンガポール側もこれを受け入れることになった170)。さらに,「対決政策」が本格的に終わりを告げようとすると,こうして高まりつつあった両国間の緊張はさらに高い水準にまで高められることになった。インドネシアによるシンガポールの国家承認が問題とされるようになったのであった。4月,インドネシアによるシンガポールの国家承認への動きが明らかになると,マレーシアは紛争を激化させるものとしてこれを公に非難した171)。一見するとインドネシアによるシンガポールの国家承認は「対決政策」終結への一歩のようにも見えて,マレーシアにとっても悪い話ではないようにも見えた。また,国家承認はインドネ
166) 居座りはラザク防衛相の意向とされる。結局,イギリス軍が動くことで第二大隊は帰還できた(Lee 2000: 32)。
167) Telegram from Singapore to Commonwealth Relations Office, 21 February 1966, DO169/449, NAUK.
168) シンガポール軍への指揮権の所在などについて,シンガポール側が分離協定起草の過程であえて言及しなかったため問題を残したことをリーは率直に認めている(Lee 2000: 633, 637)。
169) なお,これを受け,合同防衛員会は名称を元の国防委員会に戻すことにした。Minute of the 37th Meeting of Combined Defence Council, 15 March 1966, DO169/449, NAUK. このとき,内務防衛省の組織再編が実施され,特務部は警察から切り離され,内務防衛相の直接の下に置かれることになった模様である。Telegram from Kuala Lumpur to Commonwealth Relations Office, 18 February 1966, DO169/449, NAUK.
170) Letter from the Office of the High Commissioner for Malaysia in Singapore to the Ministry of Foreign Affairs, Singapore, 1 March 1966, DO169/538, NAUK. Letter from the Ministry of Foreign Affairs, Singapore, to the Office of the High Commissioner for Malaysia in Singapore, 3 March 1966, DO169/538, NAUK. 合同防衛委員会への出席停止に伴い,ゴーはラザクと会談を行い,合同防衛委員会のかわりに別の統合防衛委員会を設置することで合意に達した。Telegram from Kuala Lumpur to Commonwealth Relations Office, 9 March 1966, DO169/449, NAUK.
171) The Straits Times, 13 April 1966. Telegram from Kuala Lumpur to Commonwealth Relations Office, 12 April 1966, DO169/423, NAUK.
123鈴木陽一:シンガポール共和国の建国について
シアの一方的な行為であって,シンガポールが非難される筋合いのものでもなかった。しかし,マレーシアとしては,前年 10月のときと同様,シンガポールとインドネシアが共同歩調をとってマレーシアを陥れようとしているように思われたのであった。公にはされなかったが,マレーシアは,承認行為の背後で両者の秘密交渉が行われたと考え,そのことを問題視したのであった172)。
1966年 4月 19日,マレーシア連邦政府が,両国を結ぶコーズウェイにおいて近い将来に出入国管理を開始すると発表し,両国のあいだの緊張が一気に高まったのはそうしたなかのことであった173)。当時のシンガポールは労働力過剰の状態が続いており,毎朝コーズウェイを渡ってジョホールに仕事に行く人も多かった。このため,出入国管理開始はシンガポール側にとって大きな打撃であった。別の国になったのだということを実感させ,大きなショックをもって迎えられることになった,と言われている174)。ただ,実のところ,その当時の両国間の緊張関係の高まりはその程度のものではなかった。この頃のクアラルンプールの様子について,イギリス高等弁務官は次のような報告を行っている175)。
昨晩のディナーで,インドネシアと外交関
係を樹立することでシンガポールがマレーシアの安全保障を脅かすならば,それが何を意味するか,シンガポールに見せるときがきた,とトゥンクは述べました。彼は,予防的措置として,追加の歩兵大隊をシンガポールに移動するよう,ラザクをジョホールに派遣しました。……イスマイル博士(内務大臣)にも,必要があればコーズウェイを閉じるよう準備できているか,確認するようジョホールに行くよう指示を出しました。
こうした動きについて,この直後,イギリスを訪問し,コモンウェルス関係相と会談したリーは次のように述べている176)。
両国が大人の関係を築くにはどうしたらよいのかと質問すると,リーは次のように述べました。シンガポールに軍隊を行進させ,コーズウェイを閉じるなどという考えからトゥンクは解放されるべきだ。シンガポール政府は抑制的な行動を心がけており,人々には事態の危険性を教えている。トゥンクはシンガポールを占領した後それをうまく保持できないことを理解していないのだ。
172) Telegram from Kuala Lumpur (New Zealand High Commission) to Wellington, 19 April 1966, DO169/538, NAUK.
173) The Straits Times, 20 April 1966. “Immigration Control to Be Established at Causeway,” Siaran Akhbar, 19 April 1966, DO169/539, NAUK.
174) 竹下の研究参照(竹下 1995: 302-303)。175) Telegram from Kuala Lumpur to Commonwealth Relations Office, 15 April 1966, DO169/423,
NAUK. マレーシアがシンガポールに軍隊を差し向ける動きについて,このとき,シンガポール側はイギリス側に「クアラルンプールの一部の人々は無責任である」とコメントしている。Telegram from Bangkok to Foreign Office, 16 April 1966, DO169/423, NAUK. なお,前年8月9日午前9時,ヘッドがトゥンクにウィルソンからのメッセージを渡したとき,ヘッドは独立したシンガポールが外交政策でマレーシアを困らせる可能性がないか聞いている。このとき,トゥンクはジョホールからの水の供給を止めることでシンガポールに圧力をかけることができると答えている。Telegram from Kuala Lumpur to Commonwealth Relations Office, 9 August 1965, DO169/532, NAUK. これがマレーシア側の基本的な考え方であった。発言はリー回想録においても言及されている(Lee 1998: 663)。
176) Record of Meeting between the Secretary of State and Mr. Lee Kuan Yew, Prime Minister of Singapore on 20 April, 1966 at the Commonwealth Relations Office, DO169/458, NAUK.
124 アジア・アフリカ言語文化研究 95
結局,この一件はシンガポール側がリーからトゥンクに宛てた書簡一通,電信一通を公表することで決着した。シンガポール側がマレーシア側の利益を害する意図のないことを記した書簡・電信であった177)。マレーシアに忠誠を誓う旨,誓約書を入れさせられたようなものであった。シンガポールはマレーシア側からの圧力に対抗するだけの実力をこのときは有してはいなかったのである。
シンガポールとマレーシア その後の関係翌 5月に入ると,マレーシアとシンガポールとは分離協定第 5章,第 6章に定められた協力関係を構築するため正式に話し合いを開始したが,交渉は進まなかった。マレーシア側が防衛協定の締結を求めると,シンガポール側は経済協力協定の締結を交換条件に持ちだした。これに対して,マレーシア側は第 6 章は経済協力協定の締結まで規定しておらず, 必要な経済協力はすでに進んでいると応じたのであった。交渉は二度行われたが話し合いは噛み合わず,事実上,防衛援助協定,経済協力はともに葬り去られることになった178)。そうした傍ら,シンガポールを取り巻く情勢は大きく変化することになった。「対決政策」がインドネシアとマレーシアの直接交渉を経て終結へと向かった。4月 30日,新
任のインドネシア外相アダム・マリク Adam Malikはマレーシア外務次官ガザリ・シャーフィーMuhammad Ghazali Shafieと秘密会談を行った。このとき,マリクは彼自身は「対決政策」に反対してきたと述べたうえで,サラワク,サバがマレーシアから離脱することにも反対であるとしたのであった179)。その後,マリクはマレーシア副首相ラザクと公式の会談を重ねた。6月 1日,両者は,太古からの歴史と文化によってよって結びつけられた両国民の兄弟的な精神に基づいて意見交換を行った旨を声明で謳ったうえで,平和に向けた協定に署名した180)。もちろん,「対決政策」が終焉へと向かったことは,馬新両国が協力していくことへの誘因を低下させるものであった。さらにこれと並行して,同月以降,サラワクで政変が進んだことはすでに述べたとおりである。マレーシア連邦政府がニンカンの追い落としを図るようになり,9月,サラワクに親連邦の政府が成立した。こうして,サラワク,サバの自立傾向の顕在化を待ってシンガポールも含めた緩やかな連邦を再結成するというリーの思惑は完全に外れることになったのである181)。結局,この年 11月,ゴー内務防衛相は十二大隊の常設,徴兵制の導入を含む大規模な国防計画を固め,翌年 3月には改正ナショ
177) The Straits Times, 26 April 1966. これに対して,トゥンクは「友情の選択は明らかとなった」と答えた。The Straits Times, 27 April 1966.
178) 第一回交渉は 5月 9日に行われた。The Straits Times, 10 May 1966. Telegram from Singapore to Commonwealth Relations Office, 11 May 1966, DO169/538, NAUK. 今一度,19日にも交渉が行われたが,これ以降は行われなかったようである。Telegram from Singapore to Commonwealth Relations Office, 21 May 1966, Telegram from Kuala Lumpur to Commonwealth Relations Office, 21 May 1966, Telegram from Singapore to Commonwealth Relations Office, 16 June 1966, DO169/538, NAUK.
179) Telegram from Kuala Lumpur to Commonwealth Relations Office, 8 May 1966, FO371/187562, NAUK.
180) The Straits Times, 2 June 1966.181) コーズウェイ危機の最中においても,リーはイギリス側に次のような発言を行っていた。「(引用者
注:「対決政策」が終われば,マレーシアに動揺が訪れ)サバ,サラワクを保持するためのより緩やかな連邦の構造が必要になるでしょうし,その種の構造ならば多分最終的にはシンガポールを再び受け入れることもできるでしょう。」Record of Meeting between the Secretary of State and Mr. Lee Kuan Yew, Prime Minister of Singapore on 20 April, 1966 at the Commonwealth Relations Office, DO169/458, NAUK. しかし,こうした可能性はニンカンたちの失脚によって消えることになったと言えるだろう。
125鈴木陽一:シンガポール共和国の建国について
ナル・サービス法が議会を通過した。計画は巨額の出費を伴うものであったが,シンガポールがマレーシアと対等に渡り合うための軍事力を保有するためには致し方ないものと言えた。また,徴兵制の導入は国民に愛国心を植え付け,もって国民創出を図るのにも有用と考えられた182)。独立以降,シンガポールは同じく四方をイスラム教徒に囲まれたイスラエルから軍事顧問を招いていた。彼らの助言を受けながら,政権指導部はこの大規模な国防計画の実施に踏み切ったのである183)。重要なことは―詳しい政策形成過程を明
らかにするためにはシンガポール政府文書の公開を待たねばならないけれども―マレーシア政府との分離後一年のやりとりがシンガポール共和国のその後の安全保障政策にきわめて強い影響を与えたと考えられる,ということである。分離直後,ゴーは,シンガポールの防衛の役割についてどのようなものがありうるのか,自前の陸海空軍を持つ選択肢から全く防衛費を使わず警察力のみに頼る選択肢まであらゆる可能性を検討しているところである,とイギリス側に説明していた184)。結局,この間のうえのような曲折を経て,シンガポール政府は大規模な国防計画を立案することになったのである。リーは回想録のなかで第二大隊の帰還問題の経緯を説明したうえで次のように述べている(Lee 2000: 32-33, 35)185)。
彼ら(引用者注:マレーシア政府)のやり方は理不尽であったので,我々はシンガポール軍をつくりあげる意を強くさせざるをえませんでした。彼らがそうしたやり方で我々を脅すことができないようにするためにです。……マレーシアがシンガポールの管理を回復しようとするならば,シンガポールの軍隊を鎮圧するだけでは足りず,武器や爆発物の扱いによく慣れた全ての人民をも鎮めなければならない,ということをマレーシア側に知らしめることが,そうした計画を最も強く抑えつける力となりました。
建軍の趣旨が建国の指導者によって明快に記されている。分離後,シンガポールは半島との軋轢の拡大を経験し,これに備えるために市民防衛を支柱とする軍事ドクトリンを確立した。ここに至って,PAP政府は半島と一線を画し,これを仮想敵としながら,シンガポール共和国の国民創出に励むことになったのである。
おわりに
1960年代,シンガポール PAP政府はイギリス帝国との協力関係を背景にマルチエスニック国家マレーシアを創り出し,同党は成立した連邦政府への参画をめざしたが,権力共有の試みは失敗に帰した。こうした状況を
182) ハクスレイの研究(Huxley 2000: 12-13)。リー回想録(Lee 2000: 35-36)。The Straits Times, 14 March 1967.
183) リーによれば,イスラエルとの接触は分離の数日後からあったとされる。軍事使節の招聘は周辺国を刺激しないため,秘密裏に進められた(Lee 2000: 30-31)。1966年には参謀総長も訪れた模様である。Note for Record by F. Mills, 15 March 1966, DO169/449, NAUK. イスラエル軍事使節は1965年末から 1974年まで滞在したとされるが,同国との軍事協力関係はその後も続いている。協力は多方面に渡り,サイバー戦争,ミサイル,無人機の共同研究開発,インテリジェンス交流などに及ぶと考えられている(Huxley 2000: 183, 197-198)。
184) Telegram from Singapore to Commonwealth Relations Office, 19 August 1965, DO169/450, NAUK.
185) その後,マレーシア軍は歩兵大隊を引き揚げたものの,1980年代末に至るまでマレーシア海軍の最大の基地はウッドランドにあった。さらにその後も訓練基地を残したが,シンガポール政府がその地代を引き上げようとしたため,これより撤退したとされる(Huxley 2000: 45-46)。
126 アジア・アフリカ言語文化研究 95
受け,シンガポール PAP政府は試行錯誤を経たうえで同国が単独国家の道を歩む決断を下して自らこれを主導していった。このとき,PAP政府がかような道を選ばざるを得なくなっていった主要な原因は,インドネシアがマレーシアへの「対決政策」を続ける傍ら,シンガポール PAP政府の後ろ盾であったイギリス帝国がマレーシア連邦政治において彼らへの支持を重要局面で自重したことにあった。南シナ海をまたぐ巨大な連邦国家の出現は周辺国から予期に反する大きな反発を招いた。とくにインドネシアはマレーシア粉砕を掲げる「対決政策」を実施し,イギリス帝国はその防衛にあたることになった。そうした傍ら,マレーシア国内ではマレー急進派たちがUMNOの権力基盤を切り崩そ うとするPAPに激しい攻勢を加え出した186)。 そのことはエスニック間の対立感情を高め,1964年,シンガポールではエスニック間暴動も発生することになった。それゆえ,ここで両者は妥協をさぐり,シンガポール州が連邦との関係を緩めることで折り合いをつけようとした。ところが,インドネシアが「対決政策」を進めている手前,イギリス帝国がマレーシアの分裂と敗北を暗示するようなこの妥協策に強く反対したのだった。結局,関係希薄化は頓挫し,PAP政府は窮地に追い込まれることになった。それゆえ,これ以降, PAP政府はなりふり構わぬ連邦政府への攻勢 に出て圧政からの脱出を試み,共和国の建国というかたちでそれを成し遂げたのであった。当時においても,少数ながら以上に似た見解をとる人々もいた。ここでは,そのことについて付言しておこう。分離直後の 8月 13日,イギリス政府関係省庁官僚たちが閣僚たちに事情を説明するためまとめあげた報告書には次のような件がある187)。
本年の初め,関係のさらなる悪化を避けるため,トゥンクとリー・クアンユウ氏はシンガポールが連邦との関係を希薄化することについて交渉をしていました。リー・クアンユウ氏が政治活動をシンガポール州内に止めることに同意する見返りに,シンガポールに大幅な内政自治権を認めるというものでした。……このとき,トゥンクは連邦関係希薄化計画を放棄しましたが,イギリス政府の反対は確実にその一因となりました。マレーシアがインドネシアからの対決に直面するなか,連邦の結びつきを弱くすれば,スカルノを利するだけであるとして,イギリス政府がこれに反対したのです。すると,リー・クアンユウ氏は,明らかに二者択一の目的をもって,マレーシア全土で野党の運動を激化させていきました。1969年国政選挙において連盟党を深刻に脅かすだけの幅広い支持を獲得するか,あるいはリー氏の条件に基づく連邦関係希薄化へとマレーシア政府を立ち戻らせるか,いずれかを達成しようとしたのです。
その後,シンガポールはマレーシアとの再合同という選択肢をしばらく温存し続けたが,結局,それが実現することはなかった。以上,見てみると,分離の経緯は共有されてきた支配的言説とは違うことが多いことがわかる。「はじめに」の部分であげた 3つの論点に沿いながら,以下ではどのように違っていたか吟味していこう。
(1) 分離の経緯においてエスニック対立に重点を置く説について
分離の主要な原因をエスニック集団間―とくにマレー人と華人―のあいだのエスニック対立に求めるのは,誤りではないにし
186) 連邦政府首脳はなるべく広い範囲のマレー人の支持を得てインドネシアに立ち向かおうとしていたため,マレー急進派に対して毅然とした態度をとることに躊躇するようになっていたという状況があった。
187) “Singapore,” Report by Officials, 23 August 1965, MISC 75/2, CAB130/239, NAUK.
127鈴木陽一:シンガポール共和国の建国について
ろ,やはりこれを分離の根本原因と考えるのは難しいだろう。たしかに,分離直前のエスニック間対立の緊張は高まっていた。前年のシンガポール暴動とUMNO急進派との関係については分からないことが多いが,暴動が終戦直後を除けば戦後最悪の惨事であることはまぎれもない事実である188)。また,この年 5月以降のエスニック集団間の緊張の高まりは凄まじく,連邦政府においてリーの逮捕が真剣に検討される事態に至ったことも史料から裏付けられた。しかし,このようなエスニック対立が悪化した直接の起源はマレー人と華人の文化的対立にあったわけではなかった。確かに,連盟党側はマレー語公用化などマレー人優位の政策を求めた。また,UMNOは自らが優越権を握る体制の維持を求めた。しかし,シンガポール側は華語文化を前面に出してUMNOに攻勢をかけたわけではなかった。彼らの目的は,マレーシア都市部においてシンガポール型の社会経済政策を導入して英語を基盤とする社会を創出し,そのうえで,UMNOとの権力の分有をはかろうとしたところにあった。あえて言えば,文化上の対立は,マレー文化と華語文化の対立ではなく,マレー文化と英語をまとってエスニック的に中立を装うプラナカン文化との対立であった。そして,重要なことは,連盟党と PAPとは互いの利益を調整するかたちで国制のあり方の改変に大筋で合意したものの,これが先に述べたようにイギリスの介入によって阻止され,PAP政府が窮地に追い込まれること
になったことだった。そうとすれば,長く続いてきた PAP政府に代表されるプラナカンたちとイギリス帝国の協力関係に修復困難な損壊を見たというのが分離の本質的な原因ということになるように思われる。両者の協力関係は PAP政府がマレーシア国内に留まる限り十分には復旧し得ないことが判明し,それを悟った PAP政府が離脱へと舵を切ったのだ。
(2)分離のイニシアティブについてまず,連邦の関係を緩やかにするという話はこれまで出されてきた研究で明らかにされたよりもはるか前から話題にされていたことが分かった。シンガポールでは 1964年 7月9月とエスニック間暴動が起き,9月末に連盟党政府と PAP政府は政治休戦を決するが,10月半ば,これを保証するために早くもトゥンクがこれを連邦内で発案していたというのだ。連邦政治からリー・クアンユウを排除したいという意向があったのだろう。ただし,トゥンクからリーに内々の提案があったのは,時期が遅れて 12月 19日になってからのことだったようである。それでは分離へのイニシアティブは連邦側が握っていたのかというと経緯はそう単純ではない。連邦関係希薄化のスキームは双方の思惑に違いがあったものの,双方にメリットの大きいものであった。ほぼ完全な自治を回復するシンガポール側も積極的に応じたのだ。そして,こうしたなか 2月に起きたのが イギリス帝国の介入による交渉の停滞・停止であった。このとき,「対決政策」の最中にあ
188) トゥンクは二度の暴動についてなかなか原因の調査を行わなかった。この点,リーは一回目の暴動においてUMNOが大きな役割を担ったと主張している(Lee 1998: 565-567)。リーはアルバールたちの手口はそれまでも半島でよく使われてきたと主張し,その概要を次のようなものであると指摘している。「まず,悪漢やヤクザを散らばらせ,悪事を働かせる。警察や軍隊は彼らを贔屓目に見て暴動を傍観する。怒りの熱気が高まって対抗する華人の数が増えると,一般のマレー人も暴動に参加した。華人が殴り返したなら,警察や軍隊に殴り倒された。」(Lee 1998: 602)。問題はならず者たちとUMNO関係者との関係である。独立の翌年,シンガポール政府はマレー急進派数名を逮捕したが,うち一名はUMNO関係者であった模様である。Savingram from Singapore to Commonwealth Relations Office, 28 July 1966, DO169/367, NAUK.
128 アジア・アフリカ言語文化研究 95
る連邦はこれに素直に従ったが,シンガポールはそうではなかった。以降,野党連合を立ち上げ,交渉が進まなければ野党連合による攻撃を強めるという姿勢をとることにした。野党連合のスローガンは「マレーシア人のマレーシア」であり,連邦関係希薄化とはなじみの薄いテーマであったが,シンガポール側は連邦関係希薄化が進まない限りこの運動を強化すると脅しをかけた。2月以降,分離へ向かうイニシアティブは明らかにシンガポール側にあったのである。
(3)8月 9日完全分離説について現在のようにマレーシア・シンガポール両国の完全分離が 1965年 8月 9日に確定したという理解は正しくない。それまで,双方が求めていたのは治安・安全保障,共同市場などの結びつきを残したかたちでの分離で あった。交渉がなかなかまとまらなかったため,完全分離をいったん図って緩やかな連合の回復を図ることにしたというのが素直な理解であろう。分離協定には,安全保障上・経済上恒久的な協力関係を構築していくべきことが明記されていた。さらにシンガポール側は半島とボルネオの確執を注視しており,その分裂の可能性を期待する向きも持っていた。半島,ボルネオ二州,シンガポール州からなる共同市場を伴う緩やかな連合に復帰することを期待していたのである。
ただ,このような緩やかな再合同は成立し得なかった。一つには馬新関係がおそらく当初考えられていたよりも険悪なものとなったこともあったろう。が,決定的であったのは,「対決政策」終結に伴う二つの変容であった。うち一つは,その過程で,シンガポール・インドネシア関係が良好化することについてマレーシア側の警戒が高まり,馬新間に軍事的な緊張関係が高まったことであった。マレーシア側はシンガポール侵攻も辞さないという姿勢をとったようであった。こうして,シンガポールは軍事的な自立への意志を強くすることになった。シンガポールはマレーシアを仮想敵国とする市民防衛を柱とした軍事ドクトリンを確立したのだ。さらに,「対決政策」が実際に終わると,両国の協力への誘因はさらに弱まることになった。その過程においてマレーシア連邦政府がボルネオにムスリム主導の政府を確立したことが決定的な事件となった。シンガポールがマレーシアに参加していた時期,非ムスリムがボルネオ二州の政府を主導し,彼らはシンガポール PAP政府の潜在的なパートナーとなっていたが,その彼らが連邦政府の介入にあって失脚したのだった189)。失脚の過程において,非ムスリムたちはイギリスからの支援をあてにしたが,イギリスはこれに応えることがなかった。分離後 1年ほどの経過を経て,再合同の構想は急速に萎んでいったのである190)。
189) 連邦政府がボルネオのムスリムに手を差し伸べ,ボルネオのムスリムも連邦政府の干渉を頼むという構図が明確化されることになった。ボルネオにおいては,今なお,こうした力学を背景としたムスリム主導の翼賛体制の構図が続いているとも言える。ボルネオには人口に比して過剰な連邦議会議員議席配分がほどこされたこともあり,連邦政府与党は二州政府確保のため注力し続けている。ただ,連邦政府はムスリムをあからさまに一方的に支持する姿勢を採ることは少なく,争いの仲裁というかたちで介入することが多い。ムスリム主導の州政府が独走して翼賛体制が崩れることは連邦政府の利益とは言えないのである。その意味で,ボルネオの特権が骨抜きにされてマラヤの命令で動くようになってしまった,というよくある言説は全く正しいことではない。憲法上の特権は生き,その上に則った政治過程がつくられたと言える。
190) ただし,シンガポール政府は,それ以降半年ほどのあいだ,再合同への希望をわずかながらも依然と して持ち続けていたように思われる。1967年初頭,マレーシアで再合同への希望が高まっている旨 がシンガポール政府からイギリスにもたらされた。Savingram from Singapore to Commonwealth Office, 1 March 1967, FCO24/294, NAUK. しかし,これはイギリスの力を借りて何らかのかたちの再合同を進めようというシンガポール政府による一種の情報操作であったようである。Letter from S. Falle to Sir Neil Pritchard, 21 March 1967, FCO24/294, NAUK. その意味で,シンガ ↗
129鈴木陽一:シンガポール共和国の建国について
シンガポール共和国のその後独立後,PAP政府は―最初,マレーシアとの再合同の機会をうかがいながらも―英語を共通語とするシンガポール人のナショナル・アイデンティティの創出という課題に勤しんだ。リーたちはマレーシア参加失敗の責任をほとんど問われなかった。むしろ彼らはその経験から特定エスニック集団が支配的になることの危険性を学んだとさえ主張するようになった。1965年 12月,リーは第 1議会における大統領演説に対する返礼演説において次のように述べた191)。
私たちがマレーシアで過ごした二年間は簡単には忘れ去れない日々でありました。一部の人々が一つの人種,一つの言語,一つの宗教の下にほかの人々を支配しようとすることで生み出される恐怖,愚かさ,苦々しさをこの地の多数の移民系の人々が学んだ日々でもありました。
経験は自らの政策の正当性を傍証する材料となったのである。
PAPの政権運営において野党そのものは大きな脅威ではなかった。マレーシア発足前の一斉拘束で左派が弱体化してしまったことは第 1章で述べた通りである192)。1964年には,最大野党バリサンは連邦政府が進める兵 役登録をめぐって内紛を起こし,委員長リー・ シュウチョー Lee Siew Chohが脱党するなどして分裂した。翌年 3月,リー・シュウチョーはこれに復帰したが,その後,バリサンは冒険路線を突き進むばかりとなった。独立後,バリサンは議会をボイコットし,議会外での闘争を強化しようとしたが,政府によ
る運動員の大量逮捕にあって勢力を退潮させた。1968年 4月,総選挙が実施され,PAPは全議席を確保した。そうした意味で,PAP政府にとってより困難な課題はやはり華人が人口の 4分の 3を占める社会において英語の共通語化を進めることにあった。まず,1965年 9月,南洋大学課程審査委員会報告書が公表され,これは論争を巻き起こすことになった。報告書はシンガポールがマレーシアに留まっていた時期,同大学がマレーシアの大学であることを前提に州政府が設置した有識者委員会から答申されたものであったが,あえてこの時期に公表されることになった。報告書は,南洋大学がすべての言語別学校卒業生を受け入れ,卒業生が二種の言語に精通することを求めるものであった。華語教育の最高学府である南洋大学にまで英語教育を導入しようとしたのである。華語紙はこれを大いに非難し,学生たちは大規模な授業ボイコットを繰り広げた。これに対し,政府は大学に警察を常駐させ,大学も大量の学生の退学処分をするまでに追い込まれた(田村 2013: 110-119)。PAP政府と華語文化を重んじる人々の支持を背景とした南洋大学との緊張関係は 1980年に南洋大学が消滅するまで続いた。PAP政府は,さらに,初等・中等教育政策の転換も進めた。 1966年,英語校,華語校,マレー語校,タミ ル語校すべてにおいて生徒が英語を第一言語として学ぶとする二言語政策を導入することを発表した。英語校においても生徒は英語にプラスして三つの言語から一つを第二言語として学ぶことになった(田村 2013: 125)。以降,華語集団のあいだでも子どもを英語校に通わせる人々が徐々に増えることになった。
↗ ポールがアメリカの進める地域協力機構の創設に賛同し,同年,ASEANに加盟したことは,シンガポールが独自の道を歩んでいくうえで非常に重要な事件であったと考えられる。
191) Speech Made by the Prime Minister, Mr. Lee Kuan Yew, for His Policy Speech on the Opening of Parliament, 14 December 1965, lky 19651214b, National Archives of Singapore.
192) なお,マラヤ共産党はシンガポールの分離独立を認めようとせず,その後も「ラーマン・リー一派」を非難し続けた。彼らが分離独立を承認するのは,冷戦終結の頃,ハジャイ和平合意のことになる(Chin and Hack 2004: 199)。
130 アジア・アフリカ言語文化研究 95
このように,シンガポールは英語を共通語とする国家としての道を進むことになったが,重要なことは PAPが創出をめざしたシンガポール人のナショナル・アイデンティティは純粋に非エスニックな基盤のうえに立つものとは言い難かったし,シンガポールの分離独立によって突然に発明されたものでもなかった,ということである。それは,以上で見てきたように,英語を操るプラナカンたちが最初より広い地域に活躍の場を求めつつも最終的にはシンガポールのみにおいて国政の主導的地位を占め,その地で彼らの越境的な文化が支配的になっていく環境において構築されてきたものであったのである。
独立したシンガポール共和国の前途にはほかにも様々な課題があった。最後に安全保障関係の問題に焦点を絞ってこれを振り返ってみたい。わずか数年前,リー・クアンユウはマレーシアへの参加がなければシンガポール住民の生き残りは危ういと訴えていたが,分離後,彼らはどうなったのだろうか。この点について,シンガポールにとってまず問題となったのは,やはり,国内の深い部分に影響を残すマレーシアとの関係であった。本論では触れなかった国内治安との関わり,その後の経緯も含めいま少し詳しく述べると次のようにまとめることができる。分離は少数派に陥ったマレー人たちの政府への反感を高め,彼らが暴動を起こす可能性が現実の問題となった。それゆえ,万一に備え,リー一家は数か月のあいだイギリス空軍基地近くの守られた地帯で暮らすことになった(Lee 2000: 20-21)。またこれに絡んで,
シンガポールに駐留するマレーシア軍が深刻な不安の材料となった。12月,これを率いるビン・サイード・アフマッド・アルサゴフSyed Mohamed bin Syed Ahmad Alsagoff准将はリーの下を訪れたが,彼はシンガポールの総司令官のように振舞い,いつでも国の支配を引き受けんばかりの態度をとったらしい(Lee 2000: 26)。さらに,第 4章でも記したとおり,翌年 2月,シンガポール陸軍第二大隊帰還にあたっては馬新両政府のあいだに軋轢が生じた。このとき,リーはアルサゴフによるクーデターに備えて再び居を移したらしい。暴動などを背景にマレーシアの政治家たちが彼をそそのかし,ことに至る可能性が否定しきれなかったというのである(Lee 2000: 31-32)。2月 1日には,不手際からマレー系兵士たちの暴動が実際に起きていた(Lee 2000: 26-29)193)。実のところ,分離協定には秘密了解があり,シンガポールの治安に必要な場合にはマレーシアの警察が投入されうることが定められていたようである194)。その後,コーズウェイ危機などを経て,11月,自らの脆弱性を思い知らされた共和国が大規模な国防計画を固めたことは本論にも記したとおりである。1967年 11月,アメリカ外交使節との会談の際,リーはこのときのことを次のように振り返ったとされる195)。
(引用者注:シンガポールが分離独立を果たしてから後の六か月程度の)時期,マレーシアが―リーが「トゥンクの男」と呼ぶ―アルサゴフ准将に率いられた歩兵旅団をシンガポールに駐留させていたにもかかわらず,シンガポール自身には軍備が
193) このとき,リーはどうしようもなくなった場合,イギリス軍が出動して法と秩序を回復してくれるものか,イギリス側に聞いている。Telegram from Singapore to Commonwealth Relations Office, 1 February 1966, DO169/459, NAUK.
194) Telegram from Singapore to Commonwealth Relations Office, no.1378, 11 August 1965, DO169/450, NAUK. そうとすれば,クーデター後にマレーシアが治安介入するシナリオも考えられないわけではなく,リーの心配は決して杞憂ではなかったと言える。
195) Memorandum of Conversation, 17 November 1967, Lot 72 D 97, RG59, National Archives and Records Administration.
131鈴木陽一:シンガポール共和国の建国について
ありませんでした。イギリス軍の駐留がなかったとすれば,マレーシア軍が行動を起こせば,シンガポールは完全にその思いのままであったでしょう。しかし,今や状況は一変しました。シンガポールにいるマレーシア旅団は「人質」となりました。トラブルが起きれば,マレーシア旅団は取り囲まれ,シンガポール軍の思いのままになるでしょう。
国防計画実施の成果は 1年ほどで現れたということになる。マレーシアの国内政治そのものもシンガポールの大きな関心事となった。トゥンクがいずれ引退し,ラザクがその後に就くことをリーはよく理解していたが,ラザクはマレーナショナリズムの傾向が強い人物として知られていた。トゥンクがいつ引退するかはシンガポール政府にとって気になる問題であったのだ196)。1960年代後半,マレーシアではエスニック集団間の緊張が徐々に高まり,政府への支持率は落ち続けた。1967年,国語法案が議会を通過した。マレー語が国の公用語であることが認められたが,非マレー系住民からの激しい反発にあって制限付きで英語の公用も続き,法案通過は両者の痛み分けを意味した。1969年 5月,マレーシア連邦議会下院総選挙で連盟党が大きく後退すると,かつてリーが警告した通り,マレーシアで大規模なエスニック暴動が起きた。連邦政府は非常事態を宣言し,ラザクが実権を握ることになった。翌年,彼は首相に就くが,彼はリーがかつてマレー急進派と呼んで非難したマハ
ティールを重用することになった。現在,ときに,シンガポールとマレーシアとはともに会
ムシャワラ
議を重んじる ASEANをリードするあいだがらで,統合防空システムと常設の多国籍司令部を持つ五カ国防衛協定FPDA: Five Power Defence Arrangementの当事者であり,いわば安全保障共同体を形成するあいだがらのようにも見られている197)。しかし,統制されたアジア諸国のメディアに流れる ASEAN諸国の協調の様子をそのまま鵜呑みにするならば,見逃すところも大きい。実際,マレーシア・シンガポール関係はあらゆる東南アジア諸国間の関係で最も敏感で不安定な二国間関係であり,シンガポールの軍事力はとりわけマレーシアとの(作戦上はマレーシア国内での)戦争を想定して練られてきた,との主張もあるのである198)。他方,駐留するイギリス軍撤退の可能性もまたシンガポールの死活に関わる深刻な問題であった。第 1章に見たように,イギリス帝国はアメリカとの協力関係を維持し地球規模の勢力であり続けるためにシンガポール基地を維持し続けていた。さらに第 3章でも若干触れたように,1960年代半ば以降,アメリカからの協力を期待する内容には売り圧力に曝されがちとなったポンドの価値を同国に保証してもらうという経済的な側面が強まるようにもなっていた。もちろんこうしたイギリス軍の駐留はシンガポールにとっては安全保障(対インドネシアのみならず,すでに見てきたように,対マレーシアにおいても)の要となっていた。経済的にもイギリス軍基地の貢献は大きく,同国国内総生産の 10パーセ
196) 1966年 3月,リーとトゥンクは会談を持った。トゥンクに拠れば,このときのリーの一番の関心は トゥンクが早々に引退しないとの確証を得ることであったようである。ラザクとはうまく付き合っていけないと考えていた,とのことであった。Telegram from Kuala Lumpur to Commonwealth Relations Office, 24 March 1966, DDO169/538, NAUK.
197) FPDAはイギリス,オーストラリア,ニュージーランド,マレーシア,シンガポールから構成され1971年に締結されたマレーシア・シンガポールの防衛枠組みである(Chin Kin Wah 1983)。東南 アジアを安全保障共同体とする見方はブザンの論文を嚆矢として多数出されてきた(Buzan 1988)。
198) シンガポール軍はマレーシア軍に優位している。戦闘が始まれば,シンガポール側が制空権を握り,ジョホール州に進軍してその占領を続けるとの予想がある(Huxley 2000: 45, 58-67)。このシナリオはイスラエルによるレバノン侵攻(1982年)に酷似していることに気付くべきである。
132 アジア・アフリカ言語文化研究 95
ントを担っているとも試算された。しかし,イギリス軍の極東への展開は前節でも若干述べたように同国経済を蝕む側面もあり,イギリス国内では極東からこれを撤収させるべきであるとの声もあがっていた。欧州大陸諸国が共同市場を成功させる傍ら,イギリスは多額の海外軍事駐留経費と過大とも言えるポンド評価によって国際収支の赤字を拡大させていた。それゆえ,イギリスはアメリカとの関係を見直して地球規模の勢力としての立場を放棄するとともにポンド切り下げを容認して共同市場に加盟して欧州の一員となるべきである,との意見もあったのだ。当然のことながら,シンガポールの分離独立はことがその方向に進む可能性を想起させた。イギリスのサンデー・タイムズは,分離独立の月,早くもイギリス軍撤退の可能性を指摘し,リーはこれに神経質となったのであった(Lee 2000: 20)。実際,イギリス政府官僚たちはシンガポールの分離独立をもってその地に軍を留めることができる期間が著しく短くなったとの見解をとりまとめることになった。PAP政府への国内からの圧力,マレーシアの不安定な内政から考えると,早くインドネシアとの紛争を終結させ,シンガポール基地を撤収すべきである,としたのである。内閣防衛海外政策委員会もこれを議し,基本的にこれを支持する結論に達した199)。この早急な撤退という方針は同盟国であるアメリカ,オーストラリア,ニュージーランドの反対にあっていったん放棄されたが,「対決政策」が終結するとイギリス軍の部分的な撤退が始まることになった。こうして,1967年 4月,イギリス政府はとうとうアジア本土から軍隊を撤退さ
せていくことを決定し,防衛相はその旨を内々に伝えるためにシンガポールを訪れたのであった。このときの様子をイギリス政府の電信は次のように伝えている200)。
イギリス軍が対決前の水準でいつまでもシンガポールに留まることを期待できないことはよくわかっている,とリーは述べました。……10パーセントのGNPの喪失は大変ではあるが,イギリスが十分な経済援助を本当に行うように努め,段階的な人員整理によって秩序だった撤退を保証するならば破滅的なことにはならないかもしれない。しかし,1970年代半ばに撤退すると述べることで信頼感が損なわれるならば,資本は逃避するだろう。そうすれば,多くのイギリス企業が別の場所でビジネスを展開するようになるのではないか。彼はそれを恐れていました。
リーは回想録でも同様の議論を繰り返している。イギリス軍の撤退は,そのこと自体が惹き起す経済的損失もさることながら,シンガポールへの信頼感を喪失させるという点でその政治経済全般に極めて深刻な影響を与え得るものと考えられたのである(Lee 2000: 52-53)。イギリスに替わって地域の空白を埋め,信頼感を醸成してくれる国は,もちろん,アメリカしかなかった。分離直後からリーはアメリカにこの地に関与を続けることを要請していたし,イギリスの駐留軍撤退表明以降,アメリカ海空軍がシンガポール基地を商業利用することを提案しもした201)。こうした要請
199) “Singapore,” Note by Deputy Secretary of the Cabinet, 25 August 1965, OPD(65)123, CAB148/22, NAUK. Minutes of a Meeting, Defence and Oversea Policy Committee, 31 August 1965, OPD(65)37th, CAB148/18, NAUK.
200) Telegram from Singapore to Commonwealth Office, 24 April 1967, FCO24/54, NAUK.201) 分離の後,リーは駐クアラルンプール・アメリカ大使にイギリス軍がシンガポールに留まり続けら
れないかもしれないことについての懸念を表明するとともに,アメリカがこの地域に留まり続けることを要請した。Telegram from Washington to Foreign Office, 18 August 1965, ↗
133鈴木陽一:シンガポール共和国の建国について
は終局的には受け容れられていったし,シンガポールもまたアメリカが求めた地域協力機構への参加を果たした。ただ,アメリカはベトナム戦争に疲弊し,シンガポールの安全保障への関与はとても緩慢にしか進まなかった。フィリピンのスービック海軍基地が閉鎖されるのに伴い,東南アジアにおけるアメリカの軍事拠点がシンガポールに創設され,両国が準軍事同盟の関係に入るのは,冷戦終結後,グローバル化が急加速する前夜になってからのことであった(Huxley 2000: 208-209)。
参考資料 シンガポールがマレーシアから独立した主権国家として分離独立することに関する合意 An agreement relating to the separation of Singapore from Malaysia as an independent and sovereign state(本文)
An Agreement dated the 7th day of August, 1965, and made between the Government of Malaysia of the one part and the Government of Singapore of the other part.
Whereas Malaysia was established on the 16th day of September, 1963, by a federation of the existing states of the Federation of Malaya and the States of Sabah, Sarawak and Singapore into one independent and sovereign nation;
And whereas it has been agreed by the parties hereto that fresh arrangements should be made for the order and good government of the territories comprised in Malaysia by the separation of Singapore from Malaysia upon which Singapore shall become an independent and sovereign state and nation separate from and independent
of Malaysia and so recognised by the Government of Malaysia;
Now therefore it is agreed and declared as follows:
ARTICLE IThis Agreement may be cited as the
Independence of Singapore Agreement, 1965.
ARTICLE IISingapore shall cease to be a State of
Malaysia on the 9th day of August, 1965, (hereinafter referred to as “Singapore Day”) and shall become an independent and sovereign state separate from and independent of Malaysia and recognised as such by the Government of Malaysia; and the Government of Malaysia will proclaim and enact the constitutional instruments annexed to this Agreement in the manner hereinafter appearing.
ARTICLE IIIThe Government of Malaysia will declare
by way of proclamation in the form set out in Annex A to this Agreement that Singapore is an independent and sovereign state separate from and independent of Malaysia and recognised as such by the Government of Malaysia.
ARTICLE IVThe Government of Malaysia will take
such steps as may be appropriate and available to them to secure the enactment by the Parliament of Malaysia of an Act in the form set out in Annex B to this Agreement
↗ DDO169/540, NAUK. その後,リーはシンガポール基地の商業利用を提案するようになった。Memorandum from Secretary of State to President Johnson, 13 October 1967, Central Files 1967-1969, POL7 SINGAPORE, RG59, National Archives and Records Administration, Foreign Relations of the United States, 1964-1968, Vol. XXVI, No. 284.
134 アジア・アフリカ言語文化研究 95
and will ensure that it is made operative as from Singapore Day, providing for the relinquishment of sovereignty and jurisdiction of the Government of Malaysia in respect of Singapore so that the said sovereignty and jurisdiction shall on such relinquishment vest in the Government of Singapore in accordance with this Agreement and the constitutional instruments annexed.
ARTICLE VThe parties hereto will enter into a treaty
on external defence and mutual assistance providing that:(1) the parties hereto will establish a joint defence council for purposes of external defence and mutual assistance;(2) the Government of Malaysia will afford to the Government of Singapore such assistance as may be considered reasonable and adequate for external defence, and in consideration thereof, the Government of Singapore will contribute from its own armed forces such units thereof as may be considered reasonable and adequate for such defence;(3) the Government of Singapore will afford to the Government of Malaysia the right to continue to maintain the bases and other facilities used by its military forces within Singapore and will permit the Government of Malaysia to make such use of these bases and facilities as the Government of Malaysia may consider necessary for the purpose of external defence;(4) each party will undertake not to enter into any treaty or agreement with a foreign country which may be detrimental to the independence and defence of the territory of the other party.
ARTICLE VIThe parties hereto will on and after
Singapore Day co-operate in economic affairs for their mutual benefit and interest and for this purpose may set up such joint committees or councils as may from time to time be agreed upon.
ARTICLE VIIThe provisions of Annex J and K of the
Agreement relating to Malaysia dated the 9th day of July, 1963 are hereby expressly rescinded as from the date of this Agreement.
ARTICLE VIIIWith regard to any agreement entered
into between the Government of Singapore and any other country or corporate body which has been guaranteed by the Government of Malaysia, the Government of Singapore hereby undertakes to negotiate with such country or coporate body to enter into a fresh agreement releasing the Government of Malaysia of its liabilities and obligations under the said guarantee, and the Government of Singapore hereby undertakes to indemnify the Government of Malaysia fully for any liabilities, obligations or damage which it may suffer as a result of the said guarantee.
In witness whereof, the undersigned, being duly authorised thereto, have signed this Agreement.
Done this 7th day of August, 1965, in two copies of which one shall be deposited with each of the Parties.
For the Government of Malaysia :Y.T.M. TUNKU ABDUL RAHMAN
PUTRA AL-HAJ, K.O.M.Prime Minister
TUN ABDUL RAZAK BIN DATO HUSSEIN, S.M.N.
135鈴木陽一:シンガポール共和国の建国について
Deputy Prime MinisterDATO (Dr.) ISMAIL BIN DATO ABDUL
RAHMAN, P.M.N.Minister of Home Affairs
TAN SIEW SIN, J.P.Minister of Finance
DATO V.T. SAMBANTHAN, P.M.N.Minister of Works, Post and
Telecommunications
For the Government of Singapore :LEE KUAN YEW
Prime MinisterTOH CHIN CHYE
Deputy Prime MinisterGOH KENG SWEEMinister for Finance
E. W. BARKERMinister for Law
S. RAJARATNAMMinister for Culture
INCHE OTHMAN WOKMinister for Social Affairs
ONG PANG BOONMinister for Education
YONG NYUK LINMinister for Health
LIM KIM SANMinister for National Development
JEK YUEN THONGMinister for Labour
出典 United Nations Treaty Series, no 8206.
史料
The National Archives of the United Kingdom(NAUK)所蔵
イギリス帝国の脱植民地化については史料集が編まれている。British Documents on the End of Empire (BDEE). 同史料集に掲載されている史料については,出所の後に史料集掲載場所を明記した。
The United States National Archives and Records
Administration(NARA)所蔵 アメリカの外交については史料集が編まれている。Foreign Relations of the United States (FRUS). 同史料集に掲載されている史料については,出所の後に史料集掲載場所を明記した。
The National Archives of Singapore所蔵The United Nations Treaty Series所蔵
参 考 文 献
Abdul Rahman, Tunku, Putra Al-Haj. 1977. Looking Back: Monday Musings and Memories. Kuala Lumpur: Puskata Antara.(トゥンク・アブドゥル・ラーマン・プトラ著,小野沢純監訳『ラーマン回想録』,勁草書房,1987年).
Andaya, Barbara Watson and Andaya, Leonard Y. 2001. A History of Malaysia, 2nd ed.. Basingstoke: Palgrave.
Anderson, Benedict. 2006. The Imagined Communities, revised ed.. London: Verso.(ベネディクト・アンダーソン著,白石隆,白石さや訳『定本 想像の共同体 ナショナリズムの起源と流行』,書籍工房早山,2007年).
Ariffin Omar. 1993. Bangsa Melayu: Malay Concepts of Democracy and Community, 1945-1950. Kuala Lumpur: Oxford University Press.
Asad-Ul Iqbal Latif. 2009. Lim Kim San: A Builder of Singapore. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies.
Barnard, Timothy P. (ed.). 2004. Contesting Malayness: Malay Identity across Boundaries. Singapore: Singapore University Press.
Buzan, Barry. 1998. “The Southeast Asian Security Complex.” Contemporary Southeast Asia, 10(1): 1-16.
Chew, Melanie. 1996. Leaders of Singapore. Singapore: Resource Press.
Chin, C. C. and Hack, Karl (eds.). 2004. Dialogues with Chin Peng: New Light on the Malayan Communist Party. Singapore: Singapore University Press.
Chin Kin Wah. 1983. The Defence of Malaysia and Singapore: Transformation of a Security System 1957-1971. Cambridge: Cambridge University Press.
Clammer, John R. 1980. Straits Chinese Society: Studies in the Sociology of the Baba Communities of Malaysia and Singapore . Singapore: Singapore University Press.
Dockrill, Saki. 2002. Britain’s Retreat from East of Suez: The Choice between Europe and the World? 1945-1968. Basingstoke: Palgrave Macmillan.
Dumbrell, John. 1996. “The Johnson Administration and the British Labour Government: Vietnam,
136 アジア・アフリカ言語文化研究 95
the Pound and East of Suez.” Journal of American Studies, 30(2): 211-231.
Easter, David. 2004. Britain and the Confrontation with Indonesia, 1960-66. London: Tauris Academic Studies.—. 2005. “‘Keep the Indonesian Pot Boiling’:
Western Covert Intervention in Indonesia, October 1965-March 1966.” Cold War History, 5(1): 55-73.
Fong Chong Pik. 2008. Fong Chong Pik: The Memoirs of a Malayan Communist Revolutionary. Petaling Jaya: Strategic Information and Research Development Centre.
Giddens, Anthony and Sutton, Philip W. 2013. Sociology, 7th ed.. Cambridge: Polity.
Hanna, Willard A. 1964. The Formation of Malaysia: New Factor in World Politics. New York: American Universities Field Staff.
Harper, T. N. 2001. “Lim Chin Siong and the ‘Singapore Story’.” Comet in Our Sky: Lim Chin Siong in History (Tan Jing Quee and Jomo K.S., eds.), 3-55, Petaling Jaya: INSAN.
Hirschman, Charles. 1987. “The Meaning and Measurement of Ethnicity in Malaysia: An Analysis of Census Classifications.” The Journal of Asian Studies, 46(3): 555-582.
Huxley, Tim. 2000. Defending the Lion City: The Armed Forces of Singapore. St Leonards: Allen & Unwin.
Jones, Matthew. 1999. “‘Maximum Disavowable Aid’: Britain, the United States and the Indonesian Rebellion, 1957-58.” The English Historical Review, 114(459): 1179-1216.—. 2002. Conflict and Confrontation in South
East Asia, 1961-1965: Britain, the United States and the Creation of Malaysia. Cambridge: Cambridge University Press.
Josey, Alex. 1980. Lee Kuan Yew: The Crucial Years. Singapore: Times Books International.
Lau, Albert. 1998. A Moment of Anguish: Singapore in Malaysia and the Politics of Disengagement. Singapore: Times Academic Press.
Lee, Edwin. 1976. The Towkays of Sabah: Chinese Leadership and Indigenous Challenge in the Last Phase of British Rule. Singapore: Singapore University Press.
Lee Kuan Yew. 1965a. The Battle for Malaysian Malaysia, Vol. 1. Singapore: Ministry of Culture.—. 1965b. The Battle for Malaysian Malaysia,
Vol. 2. Singapore: Ministry of Culture.—. 1998. The Singapore Story: Memoirs of Lee
Kuan Yew. Singapore: Times Editions.(リー・クアンユー著,小牧利寿訳『リー・クアンユー回顧録 ザ・シンガポールストーリー 上』,日本経済新聞社,2000年).
—. 2000. From Third World to First: The Singapore Story: 1965-2000: Memoirs of Lee Kuan Yew. Singapore: Times Editions.(リー・クアンユー著,小牧利寿訳『リー・クアンユー回顧録 ザ・シンガポールストーリー 下』,日本経済新聞社,2000年).
Leigh, Michael B. 1974. The Rising Moon: Political Change in Sarawak. Sydney: Sydney University Press.
Liow, Joseph Chinyong. 2005. “Tunku Abdul Rahman and Malaya’s Relations with Indonesia, 1957-1960.” Journal of Southeast Asian Studies, 36(1): 87-109.
Louis, WM. Roger and Robinson, Ronald. 1994. “The Imperialism of Decolonization.” The Journal of Imperial and Commonwealth History, 22(3): 462-511.
Luping, Herman J. 1994. Sabah’s Dilemma: The Political History of Sabah, 1960-1994. Kuala Lumpur: Magnus Books.
Mackie, J. A. 1974. Konfrontasi: The Indonesia-Malaysia Dispute, 1963-1966. Kuala Lumpur: Oxford University Press.
Mahathir bin Mohamad. 1970. The Malay Dilemma. Singapore: Times Books International.(マハティール・ビン・モハマド著,高多理吉訳『マレー・ジレンマ』,勁草書房,1983年).
Means, Gordon P. 1976. Malaysian Politics, 2nd ed.. London: Hodder and Stoughton Limited.
Milner, Anthony. 1995. The Invention of Politics in Colonial Malaya: Contesting Nationalism and the Expansion of the Public Sphere. Cambridge: Cambridge University Press.
Ministry of Education (Singapore). 2007. Singapore: From Settlement to Nation Pre-1819 to 1971. Singapore: EPB Pan Pacific.
Mohamed Noordin Sopiee. 1973. “The Advocacy of Malaysia—before 1961.” Modern Asian Studies, 7(4): 717-732.—. 1974. From Malayan Union to Singapore
Separation: Political Unification in the Malaysia Region, 1945-65. Kuala Lumpur: University of Malaya Press.
Muhammad Ghazali Shafie. 1998. Ghazali Shafie’s Memoir on the Formation of Malaysia. Bangi: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia.
Nohlen, Dieter et al. (eds.). 2001. Elections in Asia and the Pacific: A Data Handbook: Volume II: South East Asia, East Asia, and the South Pacific. Oxford: Oxford University Press.
Ongkili, James P. 1967. The Borneo Response to Malaysia, 1961-1965. Singapore: Donald Moore Press.
Penders, C. L. M. 2002. The West New Guinea Debacle: Dutch Decolonisation and Indonesia,
137鈴木陽一:シンガポール共和国の建国について
1945-1962. Leiden: KITLV Press.Pham, P. L. 2010. Ending ‘East of Suez’: The British
Decision to Withdraw from Malaysia and Singapore, 1964-1968. Oxford: Oxford University Press.
Poulgrain, Greg. 1998. The Genesis of Konfrontasi: Malaysia, Brunei and Indonesia, 1945-1965. Bathurst: Crawford House Publishing.
Purushotam, Nirmala. 2012. Negot ia t ing Multiculturalism: Disciplining Difference in Singapore. Berlin: Mouton De Gruyter.
Ratnam, K. J. and Milne R. S. 1967. The Malayan Parliamentary Election of 1964. Singapore: University of Malaya Press.
Rodan, Garry. 1989. The Political Economy of Singapore’s Industrialization: National State and International Capital. London: Macmillan.
Roff, William R. 1967. The Origins of Malay Nationalism. New Haven: Yale University Press.
Rudolph, Jürgen. 1998. Reconstructing Identities: A Social History of the Babas in Singapore. Aldershot: Ashgate.
Sandhu, Kernial Singh. 1969. Indians in Malaya: Some Aspects of Their Immigration and Settlement, 1786-1957. Cambridge: Cambridge University Press.
Stockwell, A. J. 1998. “Malaysia: The Making of a Neo-Colony?” The Journal of Imperial and Commonwealth History, 26(2): 138-156.
Subritzky, John. 2000. Confronting Sukarno: British, American, Australian and New Zealand Diplomacy in the Malaysian-Indonesian Confrontation, 1961-1965. London: Macmillan Press.
Tan Tai Yong. 2008. Creating “Greater Malaysia”: Decolonization and the Politics of Merger. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies.
Yap, Sonny et al. (eds.). 2009. Men in White: The Untold Story of Singapore’s Ruling Political Party. Singapore: Straits Times Press.
Yoe Kim Wah. 1973. Political Development in Singapore, 1945-55. Singapore: Singapore University Press.
金子芳樹 2001『マレーシアの政治とエスニシティ 華人政治と国民統合』晃洋書房.
木畑洋一 2008『イギリス帝国と帝国主義 比較と関係の視座』有志舎.― 2011「アジアにおけるイギリス帝国の終焉」和田春樹ほか編『岩波講座 東アジア近現代通史 第 8巻』,194-211,岩波書店.
篠崎香織 2001「シンガポールの海峡華人と「追放令」 植民地秩序の構築と現地コミュニティの対応に関する一考察」『東南アジア 歴史と文化』30: 72-97.
鈴木陽一 1998「マレーシア構想の起源」『上智アジア学』16: 151-169.― 2001「グレーター・マレーシア,1961-
1967 帝国の黄昏と東南アジア人」『国際政治』126: 132-149.― 2015「スルタン・オマール・アリ・サイフディン 3世と新連邦構想 ブルネイのマレーシア編入問題 1959-1963」『アジア・アフリカ言語文化研究』89: 47-78.
竹下秀邦 1995『シンガポール リー・クアンユウの時代』アジア経済研究所.
田村慶子 1988「マレーシア連邦における国家統一 サバ,サラワクを中心として」『アジア研究』35(1): 1-44.― 2013『多民族国家シンガポールの政治と言語 「消滅」した南洋大学の二五年』明石書店.
鷲田任邦 2008「マレーシアの政党・選挙データ 1955-2008年」山本博之編著『「民族の政治」は終わったのか? 2008年マレーシア総選挙の現地報告と分析』,171-182,日本マレーシア研究会.
採択決定日―2017年 7月 10日