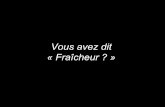Teaching-Support User Interface of Course Management...
Transcript of Teaching-Support User Interface of Course Management...

コース管理システム CEAS の授業支援型ユーザインターフェイス
植木泰博*, 冬木正彦**
Teaching-Support User Interface of Course Management System CEAS
Yasuhiro UEKI *, Masahiko FUYUKI **
Although both commercial and open-source course management systems are having difficulties in acquiring
instructor users, the CEAS (Web-Based Coordinated Education Activation System) has much increased the
number of its users at Kansai University without such efforts as to frequently open workshops for novice
instructor users but with few participants. The CEAS is designed aiming to improve the ‘delivery process’
for the instructor and the learning activities associated with preparation, classroom teaching, grading and
evaluation. The authors abstract the structure and expressions from the user interface of the CEAS, and
propose the Teaching-Support User Interface for the course management system. As an example of the
implementation in our proposal, a BBS function is designed and implemented in our system through
combining a general purpose contents management system with ours. The result of the actual classroom
use of our system indicates the easiness and smoothness during the operation and the usefulness of the
proposed user interface.
キーワード:e-Learning,教育活動,ユーザインターフェイス,支援,CEAS
1.はじめに
情報通信技術を利用して教育を支援する「教育の
情報化」が多くの大学で進んでいる.大学には,教
務管理的な情報を扱う教務情報システムをはじめ,
図書館業務や研究活動を支援する学術情報システム
など各種の情報システムが導入運用されている.
コース管理システム(CMS,Course Management
System)は,大学における授業を中心とする教員の
教育活動と学生の学習を直接的に支援することを目
的として,それらの活動に必要なあらゆるデータを
維持管理するシステムである.CMS は学習管理シス
テム(LMS, Learning Management System)や e ラー
ニングシステムとも呼ばれ,ベンダ製のシステムと
して,ブラックボード,WebCT(1),オープンソース
のシステムとして,Moodle(2),Sakai(3),CEAS(4),
などがあり,各大学で独自開発されてきたシステム
も多い.(5)
CMS の大学への導入が進んでいるが,定型的な業
務を対象とし利用が強制されることが多い教務情報
システムなどとは異なり,教育実施方法に直接関係
する CMS の利用は教員の自主性に任されているこ
とが多く,次のような問題を抱えている.
� 教員がなかなか使ってくれない
� 講習会を企画しても、参加者が少ない
� 機能改善の要望が出ても、すぐに対応できない
� 利用者が少ないので学内での認知度が低い
� システムの運用費用が、利用実績からみて割高
である。(商用)ライセンス料の負担も大きい
� 学内に、システム保守を行える人材がいない
これらの問題点は,いずれもシステムの継続的運
用を目指すには解決しなければならない問題である.
これらの中で,教員の利用者拡大が特に重要な課題
である.利用が拡大すれば,正の連鎖で上記の問題
も解決の方向に向かう可能性が高い.
教員利用者の拡大にとって検討すべき要因として
つぎの三つが重要である.
原著論文
* 関西大学先端科学技術推進機構 Organization for Research and Development of Innovative
Science and Technology, Kansai University, Japan **関西大学環境都市工学部
Faculty of Environmental and Urban Engineering, Kansai University, Japan
教育システム情報学会誌 27 巻 1 号 5-13 頁(2010 年 3 月 31 日)掲載

インターフェイス:利用者が CMS を使う際の使い
やすさを左右するユーザインターフェイスは,教員
がすぐに CMS を使いはじめ,使い続けるのに適切
であること.
機能:利用者が CMS を利用して目的を実行するた
めの機能として,教材作成、問題作成、学習者情報
取得などの必要な機能が備わっていること.
利用環境:教員がすぐに CMS を利用して授業を実
施できるように CMS が整備されていること(教員
の科目担任情報や学生の科目履修情報の登録).教育
での使い方のアドバイスや操作の疑問などへの回答
がタイムリーに得られ,さらに,機能改善の要望が
CMS に反映される体制があること.
CMS に必要な機能は,例えばメディア教育開発セ
ンターの「e ラーニング等の ICT を活用した教育に
関する調査報告書(2008 年度)」の調査報告書(5)に記
載されている.上述のベンダ製やオープンソースの
システムは必要な機能を具備しているので機能の種
類の点では問題はない.
CMS の利用環境は,全学的規模の利用を想定して
CMS を導入する場合には整えられるのが普通であ
るので,利用環境が利用者拡大を困難にしていると
は考えにくい.
ユーザインターフェイスについては,筆者らが開
発保守を行っている授業支援型 e-Learning システム
CEAS のユーザインターフェイスは,2 章以下で説
明するように他の CMS とは,異なっている. CEAS
は,関西大学において積極的な働きかけをすること
なく教員の利用が拡大し、大規模な全学運用を行っ
てきた実績がある.
本論文では,上記の要因の中でユーザインターフ
ェイスに焦点をあて,CMS の使いやすさについて考
察し,CEAS(4)を一つの成功例としてその特徴を論じ
る.さらに,CEAS のユーザインターフェイスの実
装方式を汎用化した「授業支援型ユーザインターフ
ェイス」を提案し,他の CMS 開発者へのデザイン
指針となることを目指す.他の CMS において「授
業支援型ユーザインターフェイス」のデザイン指針
が採用されれば,利用者拡大につながり,上述の
CMS 導入に関する問題解決につながることが期待
できる.
2 章では,CMS を利用する教員の特性とユーザイ
ンターフェイスのあり方を検討する.従来の CMS
について考察したのち,教員の利用者拡大の点で実
績を有する CEAS の特徴を整理する.3 章では,画
面への表現レベルで CEAS が有する特徴を考察し,
そのユーザインターフェイスを汎用化した授業支援
型ユーザインターフェイスを提案する.
4 章では,汎用 CMS(Contents Management System)
のフォーラム機能を,高度な機能を有する電子掲示
板として CEAS に機能追加する実装を具体的に示す
ことにより,CEAS の授業支援型ユーザインターフ
ェイスの具体的なシステム開発への適用例とする.5
章では,その機能を授業で利用した教員の評価を記
載し CEAS の授業支援型ユーザインターフェイスの
有効性を示す.
2.CMS のユーザインターフェイスの考察
本章では,CMS を利用した教育を実施する側のユ
ーザである教員にとって望ましいユーザインターフ
ェイスについて考察する.教員の特性とユーザイン
ターフェイスのあり方を検討し,従来の CMS の問
題点を指摘する.さらに関西大学での利用者拡大の
点で実績を有する CEAS の特徴を論じる.
2.1 CMS 利用者としての教員の特性
大学での教育に携わっている教員のコンピュータ
スキルは,初級者から上級者まで多様である.情報
教育や情報系の専門課程の教員でスキルの高い人は
いるが,大多数の教員は年齢が高いこともありスキ
ルは,一般的には高くない.
情報システムの使い方は,「単発的な使い方」と「対
話的な使い方」を異なるタイプとして想定できる.
利用できる機能が固定的な場合には単発的な使い
方になる.たとえば手持ちのディジタル化された授
業資料を登録する,授業に関する「お知らせ」を掲
載する,アンケート結果の一覧を見る,などがこの
タイプである.それに対し,予習・復習教材を作成
する,出題形式を工夫した問題を作成する,学生の
個人の学習記録を分析する,評価の重みなどを調整
しながら成績表を作成する,などが対話性を必要と

する使い方である.
CMS を利用する教員が,いずれのタイプの使い方
を CMS に期待するかは,授業科目や主として利用
する機能に依存するが,通常,教員の関心は授業の
内容に向いているので,教育方法に(研究的)関心
がある教員を除いては,単発的な利用が容易である
ことを期待している教員が多いと考えられる.
以下では,利用者拡大の視点から,まずは多数を
しめるスキルは特に高くなく単発的な利用を目的と
した教員を利用者像として論じる.
2.2 ユーザインターフェイスのあり方
教育と学習を支援するためには数多くの機能をシ
ステムは備える必要があるが,それらの機能を上記
のような特性をもつユーザに対してどのように提供
するかということは,ユーザインターフェイスの設
計にとって重要である.機能の利用手順やオプショ
ンが限られ,「開放性」が低すぎればユーザは窮屈で
不満に感じ,逆に「開放性」が高すぎると,ユーザ
は次に何をすればよいか分からなくなり,操作を続
けられなくなる.(6)ユーザの特性に合わせて「開放
性」のバランスを取ることが重要である.
また,ユーザが一覧的な情報提供を望んでいるの
か,分析に利用できるような詳細な情報の提供を望
んでいるのかという,粒度の異なる情報提供の仕方
も考慮する必要がある.
さらに,ユーザインターフェイスに用いる用語や
操作手順の選択も重要である.現実の授業実施の中
で当たり前として使われている用語や実施手順(暗
黙の「教育学習環境のドメインモデル」)が,ユーザ
インターフェイスに使われることが望ましいが,開
発技術者と利用者の情報交換が不足する場合には,
情報の専門用語やシステムでの処理手順が十分な検
討なしに用いられる.CMS 利用を始めるにあたり
CMS について別途学習する必要がないことがユー
ザインターフェイスにとって重要である.
2.3 従来の CMS のインターフェイス
大学等に導入され,利用者拡大で問題を抱えてい
る従来の CMS(例えば、WebCT や Moodle)を前節
の視点から考察する.
第一の「開放性」に関しては,従来の CMS は,
具備している機能を自由に使える開放性の高いユー
ザインターフェイスで提供されている.これは,ベ
ンダ製のシステムの場合には,他社製品に対する優
位性を示すためには,機能の多さを表面に出す必要
があること,コミュニティベースで開発されること
が多いオープンソースのシステムでは,機能単位で
モジュール化するのがコミュニティベースでの開発
に適していることが,主な理由と考えられる.さら
に,機能の高度化も差別化や特徴を出すために追及
されてきた結果,利用手順が複雑化し,学習しなけ
ればそれらの機能を使いこなせないレベルになって
いる.
さらに,それぞれの CMS に特有の用語が用いら
れ,暗黙の教育学習環境での用語との対応関係を常
に考えながら利用することが求められる.
以上の考察より,従来の CMS は,大学の教員の
特性や期待,ドメインモデルとの対応において,ミ
スマッチをおこしており,このことが教員の利用者
拡大を困難にしているのではないかと考えられる.
2.4 CEAS のユーザインターフェイス
筆者らは,多人数教育を対象に授業と学習(予習
と復習)のサイクル形成をインターネット技術を用
いて統合的に支援することを目的とした授業支援型
e-Learning システム CEAS を開発し,2002年 11月か
ら保守と運用支援を行ってきた.2004年度に採択さ
れた現代 GP 取組により CEAS の利用環境の整備が
行え,学内の教務システムとのデータ連携ができた.
(7)科目データ,担任者データ,科目履修者データな
ど CMS を利用するのに必要な履修環境データが,
CEAS に自動的に提供され,担任者が CEAS にログ
インするとすぐに授業に使える環境を提供できてい
る.この様な環境下で,CEAS の利用は,利用講習
会などを行うことなしに教員の間に広がり,2008年
度には,年間 760科目で専任教員 238 名,非常勤教
員 104 名,学生 17,770 名が CEAS を利用する状況
になっている.
CEAS は,授業資料の掲載から,レポートやアン
ケート機能の利用,電子掲示板や FAQ などのコミュ
ニケーション機能の利用など,教員の担当科目の教

育方法に応じ多様な形態で利用されている.さらに,
カリキュラムに記載された正課教育以外では,入学
前教育や高大接続教育の取組などにも利用されてい
る.
CEAS は,システム開発の概念モデルとして,図
1 に示した「授業明示モデル」と呼ぶモデルを採用
し,授業と予習・復習のサイクルに出てくる「授業」
を明示的に扱っている.また,授業で利用する授業
資料や小テストなどの教材に対する担任者と学生の
アクセス権限の違いや利用可能期間などを,担任者
が実際の授業で行うことと同様に設定できるように
している.(「教育環境ドメインモデル」との一致を
図っている.)
さらにシステム設計実装にあたっては次の方針を
とった.
●「コンテンツ制作」を前提としない
教員が作成した PowerPointなどで作成されたディ
ジタル教材が利用でき,授業回数の進行に沿って掲
載できる
●教務管理的な負担の軽減に配慮する
出席確認と修正が容易,小テストの一斉実施/学生
による自己採点,採点や自己採点結果の「一括確認」,
など
●多機能化/自動化を避ける
基本機能の洗練を重視し,教員の使い方の「工夫」
も想定する
●画面上に操作に関する説明を記載する
操作によって何が起こるのか,次に何を行えばよ
いかなど,教員の利用者が疑問を持ちそうなことに
関する説明を,きめ細かく記載する
授業明示モデルや上記の設計実装方針により,
CEAS の場合には利用者が使い方として期待してい
ることやドメインモデルの一致という点では適合性
が高くなっていると考えられ,2.3 節で示唆した従
来の CMSが有するミスマッチを解決していると考え
られる.このことが可能であったのは,CEASの開発
過程において,設計・機能改善を,教員と開発者が
十分な意思疎通を図って進めることができたという
要因が大きいと考えられる.
次章では,画面の表現レベルで CMS に求められ
るユーザインターフェイスの要件について考察し,
CEAS を一つの実装例とし,教員利用者にとって適
合性の高い CMS のユーザインターフェイスを提案
する.
3.授業支援型ユーザインターフェイス
CMS には多様な機能の提供が求められるため前
章で述べた「開放性」を保持することは必要である.
しかしながら,必要な機能提供する方式については
検討の余地がある.図 2 は,機能の選択を CMS の
画面構成の階層の上位に置く場合(機能分類メニュ
ー)と,機能を利用する利用者の活動のフローの各
段階(CMS の場合には,授業の準備,実施,評価)
に必要な操作機能の選択を上位に置く場合(操作分
類メニュー)を,小テスト,レポートや授業資料を
扱う場合について模式的に表している.
単発的な使い方の期待にこたえるには,教員の活
動フローの各段階で,その活動段階で必要な機能を
直ちに使えることが重要である.この視点からは,
図 2の,縦軸に沿った操作分類メニュー構成の画面
上で機能の選択が行えることが望ましい.
たとえば,授業後または締め切り後に,提出され
たレポートを採点したい場合には,機能分類メニュ
図 1.授業明示モデル
図 2.2 種類のメニュー構成

ーでは,レポート機能を選択し,さらに「作成」,「採
点/確認」から「採点/確認」を選択するという手順
になるが,操作分類メニューでは,メニューから直
接「レポート管理」を選択することで学生からアッ
プロードされたレポートを確認でき,採点できるの
で単発的な使い方に適している.
さらに,提供する情報の粒度については,粒度の
大きい情報の提供の仕方を工夫することが重要と考
える.CMS 上に掲載する授業資料や各種の小テスト,
アンケートのコンテンツが授業の進行とともに増加
する場合には,授業実施回と連動して掲載されてい
るコンテンツが「連結一覧」できることが望ましい.
また,科目を履修している学生数が大きい場合には,
例えばレポートの提出状況や小テストの結果が一覧
できさらに授業回数毎にまとめて「連結」して学生
全体が一覧表示される機能も必要である.
以上の考察より,教員利用者にとって適合性の高
いユーザインターフェイスの要件を次の二つにまと
める.
(要件 A)各活動段階のユーザの活動と,それに必
要な機能操作の集まりとが,ユーザインターフ
ェイスで分かりやすく提供されていること
(要件 B)一覧的な情報の提示があること
この要件を満たすユーザインターフェイスを「授業
支援型ユーザインターフェイス」と名付ける.「授業
支援型ユーザインターフェイス」は,教員の利用者
に対する CMS のユーザインターフェイスのデザイ
ンの指針を与えるものであり,CMS の具体的な実装
方法を規定するものではない.
以下では,CEAS が実装している各種の画面を,
授業支援型ユーザインターフェイスを実現している
一つの具体例であると位置付け,その画面構成を抽
象化することにより,要件 A と要件 B を満たす授業
支援型ユーザインターフェイスの表現を規定する.
要件 A を満たす表現を与えるため,まず担任者の
教育実施に関する活動フローにおける活動のまとめ
方を図 3に示す.図 3の左側は,学期のサイクルで
繰り返すフローの中での,学期前・学期中・学期末
の諸活動を示し,右側は授業回ごとのサイクルで繰
り返すフローの中での,授業前・授業中・授業後の
諸活動である.これら 2種類のフローでの3つの活
動(段階)の共通名称として,「準備」・「実施」,「評
価」を用いることにする.これらの段階にまとめら
れる活動以外に,担任者や学生に必要が生じた場合
その都度対応が必要となる活動もある.学生へのお
知らせ,学生からの質問とそれに対する対応などが,
その例である.
準備・実施・評価の活動のまとめ方に対応させ,
機能ではなく,機能を実行する「操作」を準備・実
施・評価のくくりでまとめた表現を,要件 Aを満た
す表現とする(図 4参照).表現の実装イメージとし
ては,操作を行うメニュー項目などを,準備・実施・
評価の活動に対応する「操作のカテゴリ」でまとめ
たものを想定するので,この表現を「活動別操作カ
テゴリ表現」呼ぶことにする.操作カテゴリとして
は,教材の作成/登録/割付,授業実施,授業データ
管理を設ける.図 4中の実線の矢印は,活動と操作
カテゴリの対応関係を示している.
図 5は,「活動別操作カテゴリ表現」の実装イメー
ジの例をCEASの担任者のTopページの場合について
示している.左側には,準備と評価の活動で分類し
た操作分類メニューが配置され,画面中央から下部
の区画には,授業実施で利用する各種教材が授業回
図 3.教育実施のフローと諸活動
図 4.授業支援型ユーザインターフェイスの表現

数毎に配置された「授業実施画面」へ遷移するため
の担任科目一覧表(と選択ボタン)が配置されてい
る.なお,お知らせや学生からの質問への回答など
のニーズが発生する都度、その対応に利用するツー
ルの選択メニューグループは左下の破線で囲まれた
区画に,それに関する情報表示は中央上部の破線で
囲まれた区画に配置されている.
要件Bを満たす一覧的な情報の提示の表現につい
ては,準備・実施・評価の活動で操作する機能に応
じた一覧表示・連結表示の表現を用意する.前出の
図 4の中で,破線の矢印の指す表現が要件 B を満た
すための表現である.「」で囲んだ表現は,CEAS の
特徴を与えている授業回数のくくりで教材などを配
置する表現であり,固有名称を与えている.
「授業回数順教材配置一覧表現」は,授業回数順
にそれぞれの授業回数で利用する教材が配置されて
いる表現であり,CEASでの実装例は文献(8)の図 10
に記載されている.「授業回数毎教材割付表現」は,
授業回数ごとに,その授業で利用する教材をまとめ
た表現であり,後出の図 6が CEAS での実装例であ
る.さらに「連結評価一覧表現」は,授業回数毎の
出欠データ,小テスト結果などを特定の科目につい
て授業回数順に連結し,その科目の履修学生につい
て一覧できる表現であり,実装例は文献(4)の図 4
に記載されている.
授業明示モデルをベースに,4 つの設計実装方針
に従い上述の授業支援型ユーザインターフェイスを
CEAS に実現できていることが,利用者特に教員に
とって CEAS が分かりやすく、容易に使いだせ,か
つ使い続けられる理由と考えられる.
次章以降では,授業支援型ユーザインターフェイ
スの要件を順守した CEAS の機能拡張例と担任者の
評価を示し,授業支援型ユーザインターフェイスの
要件を満たすことの有効性を示唆する.
4.授業支援型ユーザインターフェイスを実現した
フォーラム機能
CEAS に新たな機能を追加し,授業支援型ユーザ
インターフェイスでその機能を利用できるようにす
るには,追加機能の特性を考慮して実装の設計を行
う必要がある.ここでは,汎用 CMS(Contents
Management System)である Geeklog(9)のフォーラム
機能を,高度な機能を有する電子掲示板として
CEAS に機能追加した結果(10)から上述の授業支援型
ユーザインターフェイスがどのように実現されてい
るか説明する.
フォーラムは,特定のタイトルのもとでトピック
(話題)が書き込まれ閲覧される Web 上の掲示板で
ある.フォーラムは,各科目に複数設定できるもの
とし,各フォーラムは特定の授業回数に割付けるこ
とにより,その科目を履修する学生が利用できるも
のとしている.
要件 Aを満たすために,教材作成/登録/割付のカ
テゴリに「フォーラム作成」のメニュー項目を,授
業データ管理カテゴリに「フォーラム管理」のメニ
ュー項目を差し込んだ.
教材作成/登録/割付のカテゴリに設けたフォーラ
ム作成の操作方法を以下に述べる.
担任者は,メニューの「教材作成および登録」の
「フォーラム作成」からフォーラムを設定する科目
を選択する.フォーラム作成画面が表示されるので
フォーラムタイトルを設定する.作成されたフォー
ラムは,授業教材の一つとして利用できるようにし,
教材の割付操作により当該科目の特定の授業回数に
割付けられる.割付けられたフォーラムは,当該授
業回でフォーラム名が表示されるので,学生は,そ
れをクリックすることでフォーラム内のトピックに
書き込め,さらに新しいトピックも作成することも
できる.学生が作成したトピックは,他の学生から
図 5.活動別操作カテゴリの配置例.

の書込みも可能となる.
作成されたフォーラムは,授業教材として登録さ
れ,当該授業回に割付けられる.フォーラムが特定
授業回に割付けられた授業実施画面を図 6 に示す.
(これは「授業回数毎教材割付表現」の実装例)
フォーラム管理機能として,当該科目の各授業回
登録したフォーラムに対し学生ごとの集約情報が参
照できるフォーラム連結表と,フォーラムごとに集
約情報(閲覧数,投稿数,トピックの作成数)が参
照できるフォーラム一覧表とトピック連結表機能が
実装されている.
要件 B を満たすために,フォーラムの授業データ
管理の中にフォーラム連結表とトピック連結表が設
けられている.図 7のフォーラム連結表では,授業
回と授業回に割付けられたフォーラムに対する学生
ごとの閲覧数,投稿数,トピックの作成数が連結し
て表示されている.表の縦の列には,担任者と TA
と学生が表示され,横には,授業回全合計の閲覧数,
投稿数,トピック作成数と授業回ごとのフォーラム
への閲覧数,投稿数,トピック作成数が表示されて
いる.
トピック連結表は,各フォーラムのトピックに対
する学生ごとの閲覧数,投稿数,トピックの作成数
が表示されている.図 8は,トピック連結表の例で
ある.表の縦の列には,担任者と TA と学生が表示
され,横の行にはトピックの全合計閲覧数,投稿数,
トピック作成数とトピックごとの閲覧数,投稿数,
トピック作成数が表示されている.これら 2つの連
結表は,CSV 出力可能であり,担任者が CSV 形式
のファイルをダウンロードし,表計算ソフトウェア
上で個別に集計し評価することも想定している.
5.授業支援型ユーザインターフェイスの利用と評
価
前章で具現化した授業支援型ユーザインターフェ
イスのフォーラム機能を,関西大学において 2008
年度秋学期に 7 人の担任者が 14 科目(履修者合計
1361人)で実際に利用した.利用期間終了後のフォ
ーラム機能利用に関するアンケート調査のうち担任
者を対象とした中から授業支援型ユーザインターフ
ェイス部分に関係するアンケート結果を紹介する.
(問 1)「フォーラムを科目に作成/登録→作成したフ
ォーラムを授業回ごとのページに割付→学生に利用
してもらう」という手順はわかりやすかったです
か?という設問に対し 5 名の担任者がわかりやすか
ったと答えた.残りの 2 名の担任者の回答は,授業
回への割付方法の改善提案と毎回科目を選択するこ
とが不便であるという回答であった.
不便さは,手順のわかりにくさを示すものではな
く,同じ作業の繰り返しと一覧表示される科目数の
図 6.フォーラムが割付けられた授業実施画面
図 7.フォーラム連結表
図 8.トピック連結表

多さから選択しにくいという煩わしさに起因し,
CEAS 全体の設計方針に関することであり今後,見
直す予定である.
(問 2)学生の投稿数や閲覧数を参照することができ
る「フォーラム管理」は授業を進行する上で有効で
すか?という設問に対し 6 名の担任者が有効である
と答えた.残りの 1 名の担任者は,アンケート実施
時点でフォーラム管理機能をまだ利用していない.
担任者は,毎回の授業でフォーラム管理の授業デー
タを加工し学生に提示することで学生のモチベーシ
ョン向上に利用することや参加状況の把握に有効で
あるとの回答を得ている.
要件Aである活動別操作カテゴリ表現を実現して
いる教材作成/登録/割付の操作方法がわかりやすく,
要件Bである授業データ管理の一覧表現に関して授
業実施に有効であることがわかった.
以上より,CEAS の授業支援型ユーザインターフ
ェイスは,教員にとって使いやすく,わかりやすい
と言える.
6.おわりに
現状の CMS が抱える問題点の一つである利用者
拡大の解決のために,教員の利用者の使いやすさを
実現できるユーザインターフェイスとして CEAS の
「授業支援型ユーザインターフェイス」を提案し,
実装例と評価を示した.
CMS を学習のプラットフォームとして利用する
学生(学習者)にとって,良いユーザインターフェ
イスのあり方についての検討は本論文で取り上げて
いないが,教育と学習を支援する CMS にとって今
後検討すべき重要な課題である.
さらに CMS の今後の展開にとっての課題として,
� CEAS で実現しているユーザインターフェイス
のデザインや機能は 2002年当時のWeb 技術をベ
ースにしているので,最近のリッチクライアント
技術をベースにした新しい授業支援型ユーザイ
ンターフェイスの作成
� 多機能な CMS の存在を考慮すると「授業支援型
ユーザインターフェイス」を有する CMS のシス
テムを実現するシステムアーキテクチャは一体
的な構成から連携構成まで幅があるので,実現の
ためのアーキテクチャの比較検討
� CMS の利用は今後さらに広がると予想されるの
で,CMS を利用することで蓄積される授業実施
や学習に関する利用記録を,例えば「eポートフ
ォリオ」システムと連携して利用できるような関
連システムとの連携のインターフェイスの検討
などが重要な課題である.
謝辞
本研究に協力いただいた関西大学大学院生の水上
賢治,矢野敏也,岩崎千晶の諸氏に感謝いたします.
参考文献
(1) http://www.blackboard.com/
WebCT は, 2006 年に Blackboard 社に買収され
Blackboard Learning System に変更されているが多く
の大学では WebCTの名称を使用している
(2) http://moodle.org/
(3) http://www.sakaiproject.org/portal/
(4) 辻昌之,植木泰博,冬木正彦,北村裕:”Web 型自発
学習促進クラス授業支援システム CEAS の開発”,教
育システム情報学会論文誌, Vol21, No.4, pp.343-354
(2004)
(5) メディア教育開発センター:”e ラーニング等の ICT
を活用した教育に関する調査報告書(2008 年度) ”,
pp.49-50 (2009)
(6) Tidwell,J.:”Designing interfaces”, O'Reilly, (2005), 浅野
紀予訳:『デザイニング・インターフェース』, オラ
イリージャパン, 東京, pp. 7-9 (2008)
(7) 関西大学現代 GP推進担当者会議:”平成 18年度(最
終年度)関西大学現代 GP成果報告書”,(2007)
(8) 冬木正彦:”教育改善につながる ICT活用の進め方”,
NIME研究報告,45-2008,pp. 32-40(2009)
(9) Geeklog Japanese:”無償 CMS Geeklog導入ガイド”, 技
術評論社, 東京 (2007)
(10) 水上賢治,植木泰博,冬木正彦:”CEAS に連携する
汎用 CMSを用いた授業支援型 BBSの開発”,情報処
理学会研究報告 [教育学習支援情報システム研究グ
ループ]第 9回 CMS研究発表会,pp.91-96 (2008)