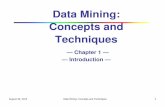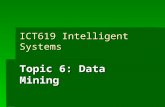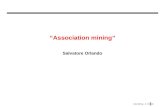Surface Mining & Underground Mining Methods ~...
Transcript of Surface Mining & Underground Mining Methods ~...
1. 露天採掘法露天採掘法において、現在ではベンチ・カット(階
段採掘)法が、世界的にも最も広く採用されている方
式である。この方法は、階段状の切羽を設けて、岩盤
を爆薬によって発破起採し採掘するやり方であるが、
起採された採掘物は大型の油圧ショベルなどによって
積込みされ、立坑やプラントまで、また大型ダンプト
ラックにて運搬されるのが通常の流れである。
昨今、世界的な鉱物資源の需要拡大による生産量増
大とともに、1998 年以降概ね平均的に推移していた銅
価格が、2003 年秋以降急激に上昇し、ついには 2005
年 10 月には史上初めて 4,000$台を突破し、鉱山開発
の気運に拍車を掛ける格好となった。
世界の鉱山に目を向けてみると、生産量増大に伴う
鉱体の深部化や鉱石品位の低下が技術的克服課題とな
っており、銅の主要産出国であるチリにおいては、露
天採掘の鉱山におけるピット深度が、地表下 1,000mに
も迫る勢いである。この事は、二次富化帯のさらに下
位の 0.5 ~ 1 %と銅品位の低い初生鉱化帯へと、採掘
深度が深くなっている事を物語っている。
図1のとおりチリのエスコンディーダ銅鉱山では深
度 600m を超え、鉄鉱石産出で名が知れているスウェ
ーデンのキルナ鉱山では、地表下 200m の露天採掘の
深度から 1957 年からサブレベル・ケービングの手法を
用いた大規模坑内採掘を実施している。
1-1. 露天採掘(ベンチ・カット法)露天採掘におけるベンチ・カット法について、採掘
に関する要点を以下に纏めた。
(1)採掘計画露天採掘の一連の工程は、穿孔→発破→積込→運搬
である。
a.優位で安全な開発道路の設計:露天採掘では、
一番高い標高からベンチを形成しながらスライス
ダウンしていくので、まず最初に一番高い標高地
点に取付く必要がある。また採掘に要する重機類
を山頂に上げるために、開発道路を設定する。道
路が完成すると地表の表土を剥ぎながら処理して
いき、初期剥土岩の処理道路から鉱石の運搬道路
へと、採掘の進展に合わせて開発道路の役割は変
化していく。
道路の勾配は、一般的に7~ 15 %位であるが、
その土地の気候や重機の仕様、投資金額などで道
路は設計されていく。ちなみに高低差 200m で、
勾配 10 %の運搬道路においては、その道路長は
2,000m となる。勾配を 10 %以下にすれば、緩や
かで安全な道路となるが、その分道路が長くなり
コスト増加に繋がる(図 2)。
b.計画的な剥土岩処理の実施:切羽の中には、品
位の高い場所だけあるのではなく、品位の低い箇
所や剥土岩も点在する。品位の高い箇所だけ採掘
しても、ベンチとはならず単なる狸掘りの山とな
り、いずれ採掘が行き詰まることになる。従って
品位の低い箇所も採掘して、スペックが許す限り
品位の高い所とブレンドし、また剥土岩も損益を
横目で睨みながら計画的に処理し、採掘面と長さ
を広げベンチを形成する(図 3)。
c.上段ベンチからの形成:採掘範囲までベンチが
進むと、端縁が出来、その壁を処理して残壁が形
成されていく。残壁を造り上げるまでかなりの手
間を要するが、壁を追込む前に次々と下のベンチ
に手を出すと、採掘面はいずれ狭くなり、収拾が
特 集
Surface
Mining
&Underground
Mining
Methods
〜採鉱技術の動向紹介〜
2007.5 金属資源レポート 9(9)
Surface Mining & UndergroundMining Methods~採鉱技術の動向紹介~
はじめに近年の世界の資源開発の大きな変化としては、BRICs 諸国を中心とした経済発展に追随する金属消費の拡大やそれ
に伴う生産量の増大があげられ、鉱床からいかに効率良くかつ安全に鉱石を掘り出すかという採鉱技術に、今後の焦
点の一つが当てられている。採鉱技術には、地下の浅部や地表に露出した鉱床を採掘する露天掘と地下に埋もれた鉱
床を採掘する坑内掘と大きく分けられる。当機構では開発・製錬技術等調査事業における技術動向調査の一環として、
最新の国内外における採鉱技術の動向調査を実施しており、今回はその成果について報告する。
金属資源技術グループ 生産技術チーム 専門調査員[email protected] 大山 雅嗣
図 1 大規模露天掘鉱山における採掘深度の推移(Brown, 2004)
(2)リクラメーション掘ればなくなるのが鉱山の宿命ではあるが、採掘が最
下低レベルまで下がり、最終残壁が形成されれば終掘と
なる。この露天採掘の掘跡の空間は、空間資産として十
分活用できる容積で、周辺の剥土岩処理などの埋戻し場
として覆土緑化される。リクラメーションの一環として
機能している採掘跡の様子を、写真1、図 4に示す。
つかなくなり切羽が行き詰まることになる。従っ
て、露天採掘においては、必ず上から順々にベン
チを形成しながら下段のベンチへダウンしていく
のが原則である。特 集
Surface
Mining
&Underground
Mining
Methods
〜採鉱技術の動向紹介〜
2007.5 金属資源レポート10(10)
露天掘地質平面図
図 2 露天採掘の道路計画 図 3 露天採掘の平面図
写真1 剥土岩投下(埋戻)処理
図4 埋戻完成予想鳥瞰図
1-2. 発破について(1)発破における孔曲りの問題点穿孔機械の穿孔能力は大きく向上しているが、いか
に打撃出力が大きいドリフターを搭載しても、実際の
現場では破砕帯や岩質の変化のため、また、盤荒れの
ため孔壁が崩れたり孔曲りにより、所定の穿孔能力を
発揮できない場合がある。発破後の穿孔跡で確認され
るが、穿孔機の特性や穿孔中の岩盤の変化等で、程度
の差はあるものの岩盤中で孔曲りが発生しており、計
画された発破規格と異なった状態で発破しているのが
実状である(写真 2、図 5)。
特 集
Surface
Mining
&Underground
Mining
Methods
〜採鉱技術の動向紹介〜
2007.5 金属資源レポート 11(11)
写真2 孔曲りした穿孔の軌跡
図5 孔曲りの模式図
この孔曲りの状態は、穿孔能力や起砕効果の低下を
招くだけでなく、孔曲りにより最小抵抗線が短くなっ
た状態で発破すれば、発破の飛石事故をも起こしかね
ない。また、鉱石の採掘において、穿孔・発破作業は
その良否が発破の安全性やそれ以降の工程の作業効率
を決定することは言うまでもない。特に、近年の発破
においては、その安全性や経済性のみならず、発破振
動低減等の環境に配慮して実行することが求められて
おり、これらを満たす適正な発破を行うためには、穿
孔段階においていかなる岩盤でも、より速く孔曲りの
ない、より精度の高い穿孔規格の発破孔を削孔するこ
とが重要な要素となる。
a.孔曲り量の考え方孔曲りの評価として、穿孔規格等で計画された目標
とされる穿孔線(図 7)と、実際に穿孔した線との
“ずれ”の状態を「孔曲り」と定義し、その“ずれ量”
を「孔曲りの変位量」として評価するのが一般的であ
る。しかし、目標とする穿孔線に対し、穿孔機をセッ
トした段階ですでに方向が狂っている場合は、いくら
真直ぐな穿孔ができたとしても、当然、目標線に対し
“ずれ”が生じるため、結果として孔が曲った状態で仕
上がってしまう。
従って、穿孔の孔曲りの変位量は、図6に示す様に、
ロッド自体の曲り量+穿孔機のセットアップした時点
の位置のずれの総和だと言える。
また、孔曲りの変位量は、穿孔ツールにフレキシブル
なロッドを使用するため、穿孔する長さ(深度)とその
口径とに密な関係がある。当然、穿孔する長さが長くな
れば孔曲りは大きくなり、また口径が大きくなれば、そ
れだけロッドの剛性が高まり孔曲りしなくなる。
図7 計画の穿孔線 図6 孔曲りの変位量
特 集
Surface
Mining
&Underground
Mining
Methods
〜採鉱技術の動向紹介〜
2007.5 金属資源レポート12(12)
b.孔曲り量(変位量)の評価孔曲りの量を変位量として評価するには、穿孔線の
軌跡を X-Y-Z の3次元で捉えなければならない。具体
的には穿孔フロアー面を真上から見た面をセット位置
とし、X-Y の原点は穿孔の口切位置、穿孔のさし角の
目標線は Po-PNN 軸上となる(図8)。
Po-PNN 軸と直交する平面上において、目標となる孔
尻の点を原点としてプロットされた実際の孔尻の位置
は、原点に対する“ずれ”すなわち「孔曲り量(変位
量)」を示している。
この穿孔線の軌跡を Po-PNN 軸と直交する平面のレー
ダー図に投影させると、図9の様になるが、真っ直ぐ
穿孔されれば、(0, 0)の原点を貫く結果となる。こ
のレーダー図は、ある国内露天掘鉱山によるデーター
であるが、穿孔機械をセットしたフロアー真上から穿
孔線の軌跡を投影したものである。穿孔の口径は
80mmで、穿孔深度は 11mであった。この図から孔の
曲り量は、左方向に抵抗が少なくなる方向に約 20 °、
1~2mの間で変位しているのが判る。これは穿孔の
さし角を与える力の向きと穿孔機のロッドの回転が、
反時計廻り(左回転)であることが、影響しているも
のと考えられる。
しかしながら、発破孔の仕上がり精度を左右する要
因となる孔曲りは、穿孔機のセット段階での方向誤差
も無視できないことから、穿孔機を目標穿孔線に対し
てどう正確にセットするかが、国内外を問わず今後の
共通の課題の一つとなるであろう。
(2)露天採掘の発破規格露天掘の発破は、ほとんどが下向きの落とし孔の発
破である。下向穿孔の発破は、切羽自由面までの長さ
である抵抗線(図 10、11 のB)の取り方が重要であり、
穿孔するビット口径と密な関係がある。
抵抗線であるBと穿孔口径の関係を式に表すと、以
下の様な関係式がある。
露天採掘の抵抗:B(m)=18.1 × d0.689
d:口径(m)
坑内採掘の抵抗:B(m)=11.8 × d0.63
d :口径(m)
一般的に言うと、抵抗線Bと込物長であるステミン
グTと同じ長さであり、また根切りの重要な要素とな
るサブ・ドリリング長Jは、抵抗線Bの3割の長さを
取ると良い。この抵抗線の計算式は、現場によって状
況が違うのは言うまでもないが、現場のノウハウとし
て、口径をインチ表示した数値が、抵抗線の取るべき
メートル表示の数値の目安となる(例えば、口径が5
インチであれば、取るべき抵抗線の値は5m)。
発破の起砕の良し悪しの目安として、計算した抵抗
線の剛性効果を考慮すると、図 11 の様にベンチ高さを
柱に見立て、柱を倒すイメージで発破を捕らえると理
解しやすい。
すなわち、ベンチ高さKを抵抗線Bで割った{K/B}
の値から、K/B= 1(爆砕不良)、K/B= 2(爆砕普通)、
K/B= 3(爆砕良)、K/B= 4(爆砕優良)といった判
断材料を得ることができる。また、口径(直径)と最
適穿孔長には、50mm - 10m、80mm - 15m、
100mm- 20m、150mm- 30mの相関関係があり、ベ
ンチ高に対する口径の選択が可能となる(図 12)。
図9 変位量と方位 図8 孔曲り変位概念図
→
→
特 集
Surface
Mining
&Underground
Mining
Methods
〜採鉱技術の動向紹介〜
2007.5 金属資源レポート 13(13)
図12 穿孔径と穿孔長との相関図
図10 露天掘の発破規格 図11 発破の剛性効果
2. 坑内採鉱法金属鉱山における坑内採掘は、主として鉱床の規模、
形態などの鉱体の状態に支配されることが多い。また
坑内採掘技術は、大きく天盤を支持する方法と天盤を
支持しないケービング技術に代表される方法に分けら
れる。図 13 に坑内採掘技術を体系化して示す。
図 13 坑内採鉱技術の体系図
特 集
Surface
Mining
&Underground
Mining
Methods
〜採鉱技術の動向紹介〜
2007.5 金属資源レポート14(14)
(2)Unsupported Methods坑内採掘においては、鉱体の規模、傾斜、形状及び
鉱体、岩盤の強さなどで採掘法が選択されるが、露天
採掘において鉱体の深部化が進み、昨今では露天採掘
から坑内採掘へ移行がなされる中、ケービング技術を
利用した大規模坑内採掘がメジャーになりつつある。
a.Sublevel Stopingサブレベル・ストーピング法は、鉱体が大規模かつ
急傾斜である場合に適用される採掘法である。中段坑
道(サブレベル)から扇形穿孔により発破起砕された
鉱石が、重力により最下底レベルまで落とされ、搬出
レベルに設けられた運搬坑道で抽出される方法である
(図 16)。従って、鉱石を自重で落とせる鉱体の傾斜が
必要となってくる。
この手法は、1902 年米国ミシガン州の鉱山で初めて
試みられ、1960 年代後半より生産量の増大とともに採
用が増えてきた。穿孔時、一気に長孔を掘り長孔発破
しストーピングする手法は Bighole Stoping と呼ばれ、
自由面を開削するため下向穿孔し、下払い(アンダー
カット)するVCR(Vertical Crater Retreat)法と同
様に、サブレベル・ストーピング法の一つのバリエー
ションとして見なされる(図 17)。
地下の鉱床を採掘するには、地表から鉱体に達する
坑道を開き、鉱石を掘り出すための採掘場(切羽)を
設ける必要がある。この坑道は、採掘対象の部分に最
短距離でかつ安全に到達されるべきであって、鉱体の
傾斜や形態によって坑道(斜坑)又は立坑開坑などの
選択肢が選ばれる。坑内採掘では坑道開削による応力
影響を考慮し、適切な支保技術によって採掘が進めら
れるが、現在世界的な大規模露天掘鉱山における採掘
深度の増加により、露天採掘から坑内採掘への移行が
行われつつある。坑内採掘が増加している理由として、
以下の点が理由として挙げられる。
①露天採掘では剥土岩比が上昇し、ズリが増加する。
②鉱山の環境に対する影響を最小にする。
①の解釈として、鉱体の深部化に伴い、露天採掘で
は剥土岩比が高くなり、剥土処理するズリが増加する。
また、鉱石の運搬に係わるコストが深度の増大に伴い
増加する。
②の解釈として、坑内採掘は視覚的影響が小さく、
露天採掘と違って採掘切羽が露出していないので、騒
音振動や発塵問題などの環境への負荷が軽減される。
次の章で代表的な坑内採掘法について紹介する。
2-1. 坑内採掘法(1)Supported Methodsa.Room & Pillar (残柱式採掘法)この採掘法は、ルーム&ピラーと言う様に、鉱石の
一部を採掘せずに鉱柱として残し、その鉱柱で天盤を
支えながら採掘する方法である。古くから石炭の坑内
採掘に採用されており、主に鉱床が水平又は層状の状
況で適用される。ルームとピラーの大きさは、鉱床の
安定性や鉱体の厚さなどを考慮し設計される(図 14)。
b.Cut & Fill (充填採掘法)この採掘法は、採掘跡を廃滓やズリを充填して埋戻
し、天盤の支保と採掘面の安定化を図る採掘法で、採
掘と充填を繰返す手法である。選鉱廃滓を地下で処分
することができ廃滓ダムや堆積場の減量化が図られ、
廃滓処理場やズリ捨場の容量確保のメリットもある
(図 15)。
図15 Cut&Fill Stoping図14 Room&Pillar
特 集
Surface
Mining
&Underground
Mining
Methods
〜採鉱技術の動向紹介〜
2007.5 金属資源レポート 15(15)
b.Sublevel Cavingサブレベル・ケービング法は、鉱体の断面を貫いた
中段坑道(サブレベル)から上向きに扇形に穿孔し、
上盤もしくは鉱体の端から発破してゆく。発破起砕さ
れた鉱石は坑道に充填される形で陥没し、坑道内で鉱
石が積込まれ、運搬坑道までロード&キャリーされ搬
出される(図 18)。
この採掘法は、鉱体の上部から下部へ下がって掘り
進んで行くので、ズリの混入などが多くなると、次の
発破箇所へ移動してゆく。この方法は、1957 年に露天
採掘から坑内採掘へ転換を図ったスウェーデンのキル
ナ鉱山で初めて大規模に用いられ、その後世界的に広
がりを見せた。
c.Block Cavingブロック・ケービング法は、1920 年代から 1930 年
代にかけて巨大で又は脆弱な鉱体を開発するために多
くの鉱山で用いられる様になった採掘法である。サブ
レベル・ケービング法が鉱体の上部から下部へアクセ
スするのとは逆で、鉱体の下部から上部へのアプロー
チである(図 19)。従って、まず鉱体の下部に、鉱石
の抽出口となるドローポイントと鉱石を搬出するため
の運搬坑道を掘削し、そのドローポイントの上部を発
図17 VCR(Vertical Crater Retreat) 図16 Sublevel Stoping
図19 Block Caving図18 Sublevel Caving
(2) 粗鉱生産の発破法露天採掘の発破は主に下向き穿孔のベンチ発破のみ
であるが、坑内採掘の発破法には、下向きの穿孔発破
に加え Sublevel Caving などの採掘法に用いられる坑
道(Sublevel)からの上向きの穿孔発破法がある。
a.上向穿孔(扇形穿孔)について Sublevel Stoping 法や Sublevel Caving 法で用いら
れる穿孔方式では、中段坑道(Sublevel)が鉱体断面
を貫く場合、その坑道から扇形に穿孔発破する。
この扇形穿孔(Fan drilling)は、3本穿孔が基本の
パターンで、垂直線に沿ってセンター孔を決定し、他
の孔は左右対称に展開する(図 21)。4本孔、5本孔
もこの基本パターンの組み合わせで展開する(図 22、
23)。9本孔の場合は、5本孔のパターンに左右2本ず
つ均等展開したものが穿孔デザインとなる。爆薬を装
薬する長さは、V字に発破ゾーンが広がるので、装薬
した穿孔の間を更に穿孔する場合、そこの装薬長は穿
孔線の孔尻間隔と同じ長さ T で留めておく(図 24 :
孔 1 と孔 3 の間で孔 2 を穿孔する場合、孔 2 の装薬長
は両脇より短くする)。
b.下向穿孔(VCR法)についてVCR(Vertical Crater Retreat)法は、坑内採掘で
自由面を開削する下向穿孔の発破を行う方法で、その
発破デザインの基本は、中央に心抜きの Relief Hole
(非装薬)を穿孔し、周辺の装薬孔の Blasthole と抱き
合わせで発破するものである。
破してアンダーカットし、鉱石を自然崩落させる坑内
採掘法である。鉱石を下部から抽出すると崩落が上部
に順次伝わり、やがて地表まで崩落が起き、鉱石全て
と被覆岩盤まで陥没させる。従って、地表面に構築物
がないことが大前提となる。
ブロック・ケービング法は、巨大で脆弱な鉱体を開
発するのに適用されてきたが、最近では国際ケービン
グ研究(ICS : International Caving Study)が盛んに
行われるようになった。硬岩盤への適応や重力フロー
のメカニズム解明、鉱石引き出し法など種々の研究報
告がなされ、今後坑内において鉱石を大量に生産する
ために、広く用いられるであろう採掘法である。
2-2. 発破について(1) 坑道掘進の発破法坑内採掘における発破は、生産のための発破と坑道
を掘進するための発破がある。坑道を掘進する発破は、
ドリルジャンボなどの油圧機械で水平に穿孔される
(図 20、写真 3)。また中心には心抜き孔が掘られ非装
薬で発破され、起砕ズリが中央に集まる発破となる。
水平穿孔長の掘進長は、L = 0.15 + 34.1d - 39.4d2
d :口径(m)で与えられ、点火は中央付近からされ、
周辺孔に影響が及ぶ前に次々と、周辺孔が起爆されて
いく。
特 集
Surface
Mining
&Underground
Mining
Methods
〜採鉱技術の動向紹介〜
2007.5 金属資源レポート16(16)
写真3 坑道掘進の穿孔 図20 坑道掘進穿孔配置断面
図24 実際の装薬線図
図21 基本パターン 図22 4Hole Pattern
図23 5Hole Pattern
おわりに1997 ~ 2004 年の 8年間に国際ケービング研究(ICS)
により、ケービング採鉱法に関する地盤力学が研究され
てきた。取り組まれた主な課題は、次のとおりである。●岩盤の特性評価と、原位置において発生する割れ
目のシミュレーション●ケービングの可能性と破砕の評価の方法について
のレビュー●アンダーカットと引抜き坑道の設計●数値モデル、大規模物理モデル及び鉱山規模での
マーカー試験を用いた破砕岩石の流れ●線形計画法及び混合整数線形計画法を用いた引抜
き制御と計画システムの開発●水圧破砕法を用いた高い強度の岩盤の事前調整●露天採掘からケービング法坑内採掘への移行につ
いての地盤工学的指針の作成●ブロック及びパネル・ケービング法についてのリ
スク評価法の開発●ケービング法の実際と知識及び研究成果とを容易
に利用できる形での照合
以上の様に、今後各露天掘鉱山が坑内採掘へ転換を
図る中、坑内での大規模採掘による低コスト化、自動
化を促すにはケービング技術の確固たる確立が必要で
ある。
また、多くの鉱山現場において生産効率を改善しコ
ストを削減するためには、操業のマネージメント、機
械の自動化や取扱い管理、環境工学、水理管理、情報
通信技術、システム工学など、他の工学分野における
鉱山への技術導入など重要な挑戦課題も残っている。
しかしながら、世界の露天及び坑内掘鉱山の操業の中
で経済性かつ安全性を考慮する時、出発点は鉱山の基
本スタイルを決定する採鉱方法であることを再認識す
る必要があると考える。
(2007.4.4)
特 集
Surface
Mining
&Underground
Mining
Methods
〜採鉱技術の動向紹介〜
2007.5 金属資源レポート 17(17)
〈参考文献〉Australian Center for Geomechanics, 2006,
Proceedings of a seminar on “Development and
Production Blasting in Underground Mines”,
CSIRO/Curtin University/University of Western
Australia Joint Venture, Perth, Australia.
Brown, E. T., 2004, Geomechanics: The critical engi-
neering discipline for mass mining. Proceedings
MassMin2004, Santiago, Chile, 21-36.
金属資源技術グループ・企画調査チーム, 2006, 採鉱技
術を中心とした世界の鉱山技術動向, JOGMEC 金属
資源レポート, Vol. 36, No.3, 414-426.
大山雅嗣, 2004, ドリルチューブ仕様油圧クローラドリ
ルの稼働状況-岩質変化の著しい石灰石の穿孔性・
孔曲り改善-, 資源・素材学会 2004 年秋季大会(盛
岡)講演集.
特 集
Surface
Mining
&Underground
Mining
Methods
〜採鉱技術の動向紹介〜
2007.5 金属資源レポート18(18)