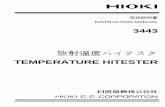SAP16 13 2013 制定appie.or.jp/wordpress/wp-content/uploads/2018/10/sap16...4 SAP 16-13:2013...
Transcript of SAP16 13 2013 制定appie.or.jp/wordpress/wp-content/uploads/2018/10/sap16...4 SAP 16-13:2013...

日本粉体工業技術協会規格
SAP 16-13:2013
明度測定による粉体混合装置の
混合特性評価方法
Evaluation method for mixing characteristics of powder mixer by brightness measurement
2013 年 11 月 27 日 制定
一般社団法人日本粉体工業技術協会

SAP 16-13:2013 白 紙

SAP 16-13:2013
(1)
目 次
ページ
序文 ··································································································································· 1
1 適用範囲 ························································································································ 1
2 引用規格 ························································································································ 1
3 用語及び定義··················································································································· 1
4 記号 ······························································································································ 2
5 試験粉体及び参照混合粉体 ································································································· 3
6 混合試験方法··················································································································· 3
6.1 試験粉体の混合比率 ······································································································· 3
6.2 混合前における試験粉体の調製 ························································································ 3
6.3 仕込み ························································································································· 3
6.4 混合操作条件設定 ·········································································································· 3
6.5 測定時間及び測定間隔 ···································································································· 3
7 混合状態の測定方法·········································································································· 3
7.1 混合物の明度測定装置 ···································································································· 3
7.2 測定装置の設定 ············································································································· 3
7.3 測定サンプル数及びサンプルサイズ ·················································································· 3
7.4 測定方法 ······················································································································ 4
8 測定データの処理及び混合特性の評価 ·················································································· 4
8.1 明度の分散又は標準偏差の変化 ························································································ 4
8.2 到達度の変化 ················································································································ 4
8.3 混合特性曲線 ················································································································ 5
9 測定結果の報告················································································································ 5
附属書 A(規定) 混合試験粉体 ···························································································· 6
A.1 混合試験に使用する試験粉体の要件 ·················································································· 6
A.2 試験粉体 ······················································································································ 6
A.3 試験粉体及び参照混合粉体の物性値 ·················································································· 6
A.4 参照混合粉体の調製方法 ································································································· 6
附属書 B(参考) 明度の測定方法 ························································································· 8
B.1 測定方法 ······················································································································ 8
参考文献 ····························································································································· 9
解説 ································································································································· 10

SAP 16-13:2013
白 紙

日本粉体工業技術協会規格 SAP 16-13:2013
明度測定による粉体混合装置の混合特性評価方法 Evaluation method for mixing characteristics of powder mixer by
brightness measurement
序文
目的に合った混合機の選択及び混合操作条件の設定,並びに,合理的な混合機の設計・開発及び改良
を行うためには,使用者と製造者とが共通の基盤に立って議論できる混合機の特性に関する試験方法及
び評価指標が必要であることからこの規格を制定する。
1 適用範囲
この規格では,回分式混合機による混合操作において,統計的にランダムな混合状態に到達するまで
の“巨視的な混合が支配的な段階”から,凝集体が解砕・分散・展延され“微視的な分散が支配的な段
階”までの混合過程を対象とする。色調及び粒子径の異なる二種類の粉体を用い,この範囲における混
合状態を混合物の明度として測定し,混合・分散状態に対する相対的な指標により混合特性を評価する
方法を規定する。
2 引用規格
次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これら
の引用規格のうちで,西暦年を付記してあるものは,記載の年の版を適用し,その後の改正版(追補を
含む。)は適用しない。西暦年の付記がない引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。 JIS Z 8840:1993 粉体機器―図記号
3 用語及び定義
3.1
統計的にランダムな混合状態
異なる成分の粒子同士が不規則に配列した混合状態で,混合物から任意に採取したサンプル粒子の種
類の出現頻度が組成比に等しい混合状態。
3.2
完全分散状態
混合する各粉体成分が1次粒子のオーダーまで均一に分散した混合状態。
3.3
明度
一定の照明の下に置かれた反射面の明るさ。この規格では,明色成分の粉体と暗色成分の粉体との混
合物からの反射光強度を明度として測定する。
3.4

2
SAP 16-13:2013
明度の分散及び標準偏差
ある混合状態の粉体からサンプリングした試料の組成が,その平均値のまわりにどのようにばらつい
ているかを表す指標。着目成分の組成は明度測定装置の出力値と一定の関係にあるので,この出力値を,
試料中における着目成分の空間的な均一性の指標とする。
3.5
巨視的な混合
着目成分粉体がバルク成分粉体中のいたるところに分散し,統計的にランダムな混合状態に近づく過
程で,転動,及び/又は,かくはんの程度に応じた大きさの凝集体として移動する混合。第Ⅰ段階の混
合ともいう。
3.6
微視的な混合
圧縮・せん断・摩擦などで凝集体が解砕されつつ分散が進行するような混合過程。第Ⅱ段階の混合と
もいう。
3.7
到達度
着目成分の凝集体が混合によって解砕・分散されながら完全分散状態にどの程度到達しているかを表
す指標。到達度が1であることは,着目成分微粒子が完全分散状態であることを示す。
3.8
参照混合粉体
所定の配合比率で各粉体成分を完全分散状態に混合した混合粉体。到達度の基準となるもの。
3.9
混合特性曲線
混合操作の進行に伴う混合状態の変化を混合時間に対して示した図。混合状態を示す指標としては,
組成の空間的な均一性を示す 3.4 の明度の分散又は標準偏差,及び,3.7 の到達度がある。
3.10
サンプルサイズ
混合物の組成を測定するために採取する1試料当りの質量・容積・面積など。光学的な測定では,光
を反射する検査面の面積。サンプリング単位ともいう。
3.11
ワークインデックス
粉砕に費やされたエネルギーに関する指標。付着性の強い微粒子の混合過程を,凝集体を解砕する過
程と見なした場合,到達度がその指標に対応する。
4 記号
N サンプルの数
s2 , s 明度の分散及び標準偏差
t 時間
yj 試料 j に対する測定装置の出力
Yj , Y 試料 j に対する測定装置の出力をその最大及び最小出力によって正規化した値,並びに,その
平均

3
SAP 16-13:2013
yst 参照混合粉体に対する測定装置の出力
j , 試料 j に対する到達度,及びその平均
5 試験粉体及び参照混合粉体
次の炭酸カルシウム及び酸化鉄を試験粉体とする。また,これらを一定比率で均一に混合した混合物
を参照混合粉体とする(各粉体の主な物性は附属書 A(規定)を参照)。
a) 炭酸カルシウム(白色粉体)
b) 酸化鉄(ベンガラ)(赤色顔料)
c) 参照混合粉体:a) の炭酸カルシウムと b) の酸化鉄とを質量比 95:5 で混合し,A.4(規定)に従って
調製した混合物。
6 混合試験方法
6.1 試験粉体の混合比率
炭酸カルシウムと酸化鉄との混合比を,質量比で 95:5 とする。
6.2 混合前における試験粉体の予備調整
用いる試験粉体の流動性は高いことが望ましく,混合試験の前に試験粉体を乾燥することが望ましい。
試験粉体の凝集が著しい場合には,かくはん,ふるい通過等による軽い予備分散をしてもよい。
6.3 仕込み
試験粉体を所定の量,投入順序及び添加方法に従って混合機に仕込む。
6.4 混合操作条件設定
容器,及び/又は,かくはん機の回転速度(主軸回転速度,自転・公転の比率及び速度,補助羽根速
度など),気流速度,温度・湿度・圧力など,混合機の操作条件を設定する。
6.5 測定時間及び測定間隔
混合操作の時間経過に従ってバルク成分である炭酸カルシウム粉体中に酸化鉄が分散し,混合物全体
の明度が変化していく過程を測定する。混合物の明度変化が認められなくなるまで測定することが望ま
れるが,長時間にわたる場合には状況に応じて終了する。
測定間隔は,装置の混合特性に応じて設定する。また,起動/停止のタイムラグなども装置特性を考
慮して設定する。
7 混合状態の測定方法
7.1 混合物の明度測定装置
粉体面に一定強度の光を照射し,そこからの反射光強度を測定する原理の装置を使用する。
光学ファイバープローブ式混合度計,白度計,反射式明度計,光沢度計,色彩色差計など,明度を直
接出力する装置又は反射光強度を電圧値として出力する装置がよい。
7.2 測定装置の設定
任意に感度設定が可能な装置については,暗色成分(酸化鉄)の指示値(明度又は電圧などの出力値)
と明色成分(炭酸カルシウム)との指示値の幅ができるだけ広くなるように調整する。
装置固有の標準光,基準物質又は校正用反射板等がある装置の場合は,それらを基準にして調整する。
7.3 測定サンプル数及びサンプルサイズ
測定は,予め設定した 15~20 の測定位置又はサンプルに対して行う。また,粉体量が少ない場合でも

4
SAP 16-13:2013
最低 10 個所において測定する。
サンプルサイズに対応する測定検査面の大きさは一定とする。測定用のサンプルセル等が測定装置に
附属する場合には,サンプルサイズをそれに対応して決める。
7.4 測定方法
明度の測定はできるだけ粉体が自然充填された状態で行う。
混合容器内の粉体層に測定用のプローブを直接挿入する場合には,所定の位置にプローブ端を静止さ
せ,粉体に観測面を軽く圧着させるようにして測定する(附属書 B(参考)参照)。
採取した粉体については,適当な容器又は専用のセル等に移し,軽くタッピングしながら充填状態を
整える。必要に応じてスクレーパ又は平板などで粉体層表面を平滑にする。
同一サンプルについて 3~5 回測定を行い,計測器からの出力値の平均値を各サンプルに対する測定値
yj とする。
8 測定データの処理及び混合特性の評価
8.1 明度の分散又は標準偏差の変化
組成の空間的な均一性の指標である明度のサンプル分散又は標準偏差を次の様に求める。
時間 t における混合物において,試料 j 又は観測位置 j の明度測定装置の出力値 yj を,試験粉体の炭酸
カルシウム及び酸化鉄の明度測定装置の出力値により, 次の式 (1)で正規化する。
Y j =y j - ymin
ymax - ymin
……………………………………………………………………(1)
ここに,ymax 及び ymin は,それぞれ試験粉体の炭酸カルシウム及び酸化鉄の出力値である。
時間 t における全試料 N 個にわたる Yj の平均値を Y とする。
Y = 1N
Y jj=1
N
å
…………………………………………………………………………(2)
各時間 t におけるサンプル平均基準の明度の分散 s2又は標準偏差 s を求める。
s2 = 1N -1
Y j -Y( )2
j=1
N
å
………………………………………………………………(3)
8.2 到達度の変化
酸化鉄を質量分率 5 %で十分に分散させた参照混合粉体の明度に対して,ある混合時間における混合
物の明度がどの程度近づいたかの評価指標である到達度 を次の様に求める。混合時間 t における試料 j
に対する到達度 ,jを,明度測定装置からの出力値 y,j から式(4) によって求める。
h j =ymax - y j
ymax - yst
………………………………………………………………………(4)
ここに,ystは参照混合粉体の明度である。
混合物全体の平均値を とする(式(5) )。

5
SAP 16-13:2013
h = 1N
h jj=1
N
å
…………………………………………………………………………(5)
ここで定義される は一種のワークインデックスで,その範囲は 0< ≤1 であり, =1 は酸化鉄が完全
分散状態であることを示す。
8.3 混合特性曲線
混合特性曲線は,目的・必要に合わせ a) ,b) のいずれか又は双方を作成し,用いる。
a) 明度の分散 s2 又は標準偏差 s の対数値を混合時間 t に対して点綴した線図。s2 対 t の関係及び s 対 t
の関係は,いずれも着目成分(酸化鉄)の混合機内における空間的な分布(均一性)の経時変化を示
し,主として酸化鉄が凝集体として局在する状態も含めた巨視的な混合の特徴を表現している。
b) 到達度 を混合時間 t の対数値に対して点綴した線図。 対 t の関係は,着目成分が巨視的な混合を
経て,酸化鉄の凝集体が解砕され,分散されていく微視的な混合の過程をも表現している。
9 測定結果の報告
測定結果として次の事項を報告する。
a) 測定機関,測定者
b) 試験日時
c) 試験混合装置の形式及び機種・名称:JIS Z 8840:1993 による分類及び具体的な容器形状等(混合装置
の諸元,有効仕込み容量,所要動力,操作条件の可変範囲等)
d) 予備調整:調整の有無及び調整条件
e) 試験粉体の装入方法:試験粉体の投入順序,酸化鉄の初期添加方法(一括又は分割投入,散布など),
添加位置,仕込み量(質量又は体積)及び粉体装入率
f) 混合操作時の機器運転条件:容器,及び/又は,かくはん機の回転速度(主軸回転速度,自・公転比
率及び速度,補助羽根速度など),気流速度,温度・湿度・圧力など。可能なら消費電力量
g) サンプリング:測定位置,サンプルの数及びサンプルサイズ(測定検査面の大きさなど)
h) 測定結果:次の 1),及び/又は,2)の測定結果
1) 各測定時間におけるサンプル毎の計測器からの出力値及びその平均値,並びに,明度の分散又は
標準偏差
2) 各測定時間における試料 j に対する到達度 j 及びその平均値
i) 混合特性曲線

6
SAP 16-13:2013
附属書 A (規定)
混合試験粉体
A.1 混合試験に使用する試験粉体の要件
試験粉体を次の要件に基づいて選定する。
a) 化学的組成・成分が既知であり,物理・化学特性の経時変化が少ない安定物質であり,取り扱い上安
全である。
b) 混合操作によって一次粒子が粉砕されて微粉化しない。
c) 分散性が良く,外力の程度に応じて凝集体の分散が進行する。
d) 色の変化で容易に混合状態の変化が判別できる組合せができる。
e) 測定が容易で,複数の方法で混合状態が検証できる。
f) 同一規格の粉体が入手可能である。
g) 適度の価格である。
h) 混合の程度として巨視的な混合,及び,微視的な混合が観測できる。
A.2 試験粉体
A.1 の選択基準を満たす試験粉体として次のものを使用する。
a) 炭酸カルシウム
b) 酸化鉄
A.3 試験粉体及び参照混合粉体の物性
試験粉体である A.2 a) 及び A.2 b)の物性値を表 A.1 に示す。
表 A.1―試験粉体及び参照混合粉体の物性値
粉体 質量分布の中位径 ( m)
かさ密度 (kg/m3) 色彩計による明度L
ゆるめ かため
炭酸カルシウム 2 - 4 300-500 700-900 94 以上
酸化鉄 0.5 - 0.8 500-700 800-1000 45 以下
参照混合粉体 - 400-600 1000-1200 65 以下
A.4 参照混合粉体の調製方法
次の手順に従って参照混合粉体を調製する。
1) 炭酸カルシウム A.2 a) と酸化鉄 A.2 b) をそれぞれ質量比 95:5 で精秤し,乳鉢に入れる。

7
SAP 16-13:2013
2) エタノール,イソプロピルアルコール又はその他の揮発性の有機溶媒を粉体に添加し,湿潤した
状態で乳鉢で十分に練り合わせる。
3) 乳棒で,湿潤状態の混合粉体をかくはんしながら溶媒を蒸発させる。
4) 乾燥後,解砕し,参照混合粉体とする。
表 A.1 に,A.3 で示された物性を有する試験粉体を用い,A.4 に従って調製した場合の参照混合粉体の
物性値を示す。

8
SAP 16-13:2013
附属書 B (参考)
明度の測定方法
B.1 測定方法 本文 7.3 の測定方法において,再現性の良い測定方法の例を図 B.1 に示す。
(a) は,混合粉体の所定の位置でサンプリングした試料に対する測定方法である。 (a-1) は,光学プローブ式混合度計による測定で,まず,サンプリングした所定量の試料を測定用
セルに入れ昇降機にセットする。昇降機に固定された明度測定のプローブを,昇降機を上下させる
ことで挿入する。昇降機を使用することで粉体層の圧密状態を一定にすることができる。本操作を
数回繰り返して,明度値を得る。 また,(a-2) に色差計など,所定の測定用セルにサンプリングした粉体を入れ,明度を測定する例
を示す。 (b) は混合粉体試料に直接,光学プローブ又はサンプラーを挿入する方法である。粉体が少量の
場合には図の様に混合機に光学プローブを数カ所挿入することで明度値を求める。
図 B.1―明度の測定方法

9
SAP 16-13:2013
参考文献
[1] Alonso, M., M. SATOH and K.MIYANAMI: “Mechanism of the Combined Coating-Mechanofusion Processing of Powders”, Powder Technol., 59, 45-52 (1989)
[2] 佐藤宗武他:「光学的手法による粉粒体の混合度の連続測定システムの開発」,粉体工学会誌, 22, 79-84 (1985)
[3] 佐藤宗武他:「付着性粉体を用いた粉体混合機の混合特性の評価」,粉体工学会誌, 30, 390-396 (1993)
[4] 佐藤宗武他:「凝集粉体の解砕モデルによる混合過程の評価」,粉体工学会誌, 34, 330-336 (1997)

10
SAP 16-13:2013 解説
SAP 16-13 : 2013
明度測定による粉体混合装置の混合
特性評価方法 解 説
この解説は,規格に規定・記載した事柄を説明するもので,規格の一部ではない。
1 制定の背景及び趣旨
2 種類又はそれ以上の性質の異なる固体粒子を混ぜ合わせ,組成について一様均質な状態を得る粉体
混合は,ほとんどあらゆる産業分野で用いられる重要な単位操作の一つである。
混合状態の評価には,着目成分濃度の不偏分散を基に導かれた様々な“混合度”が用いられている。
これらの混合度はいずれも統計的に基礎づけられた定量的な評価指標として有効であるが,サンプリン
グの方法及び測定方法に影響されやすい。また,装置構造及び操作条件による混合状態の変化及び粉体
に対する機械的作用を加味した特性を評価するには不十分な場合がある。更に,近年の粒子加工技術の
発展に伴い,混合,分散のスケールはより微細化しており,従来の混合度による評価では十分ではない。
混合機の使用者は,製品に対する様々な公的規格に加えて各社各様の品質評価基準に基づいて混合状
態を測定・評価している。一方,混合機製造者は,使用者を限定せず,できるだけ広い分野のニーズに
応えられるように,各社独自の試験粉体の選定及び測定方法で 混合特性,最適条件,スケール効果等
を評価している。このため,混合機製造者と使用者との間では,性能評価の違いに起因したトラブルが
発生することもある。このような問題を防ぐために,使用者と製造者間で混合特性を評価する共通の尺
度が求められた。また,時間と経費を軽減しながら合理的な装置構造・操作条件を含めた実製造プロセ
スを設計するために,混合特性をより把握しやすい試験方法及び評価方法が求められた。
2 制定の経緯
1) 上記の様な混合特性の評価に対するニーズを背景として,旧(社)日本粉体工業技術協会 混合かく
はん分科会は,1991 年 6 月に“混合度評価検討小委員会(以下,小委員会という)”を発足させた。
2) 小委員会では,先ず各種混合機に共通使用する試験粉体を選定するとともに,混合状態の測定方法お
よび表現方法を決めた。その後,小委員会に参加する機関が所有する混合機により混合試験を行い,そ
の評価結果を持ち寄り,混合状態の評価方法の共通化について検討した。その測定結果は,1994 年 11
月に“混合度評価検討小委員会活動報告”としてまとめられ,小委員会として上記のニーズに対応する
ことが可能な評価方法を提案した。
3) 提案された評価方法は,混合かくはん分科会関係者により使用された。更に,2007 年からスタートし
た“中小企業産学連携製造中核人材育成事業”及び“粉体エンジニア早期養成講座”において一般社団
法人日本粉体工業技術協会 混合・成形分科会(以下,混合・成形分科会)が担当した混合・混練操作の
評価方法として当該方法を使用し,混合機の使用者及び製造者に対して当該方法の普及を図ってきた。
解 1

11
SAP 16-13:2013 解説
4) 混合・成形分科会では,こうした活動の中でこの方法の信頼性が確認されたことから,協会規格とし
て制定するに至った。
3 粉体の混合過程及びその評価
解説図 1 に粉体の混合過程の一例を示した。ここでは 2 種類の色の異なる粉体を混合した場合の混合
粉体における明度の時間的変化を示した。こうした混合過程は,概念的に次の様に分類することができ
る。
a) 巨視的な混合(第Ⅰ段階混合)
着目成分粉体がバルク成分粉体中のいたるところに分散され,統計的にランダムな混合状態に近づく
過程。付着性の強い微粒子がある場合には,必ずしも一次粒子まで解砕されずに,転動及びかくはんの
程度に応じたあるサイズの凝集状態を保ったまま動的平衡状態に到達するような混合過程で,第Ⅰ段階
混合とも呼ばれる。
b) 微視的な混合(第Ⅱ段階混合)
圧縮・せん断・摩擦などで微粒子の凝集体が解砕されつつ分散が進行するような混合過程。第Ⅱ段階
混合とも呼ばれる。
c) 第Ⅲ段階混合
圧縮・せん断・摩擦・衝撃などの高エネルギー負荷によって局所的な発熱・軟化・変形・展延・コー
ティング・表面改質・反応・粒子同士の融合・練り込み・複合化・断裂などの複雑な現象が発現するよ
うな過程。
解説図 1―粉体混合プロセス
従来の混合度による混合状態の評価は,a) の段階に対して有効であったが,近年,粉体混合操作では
b) 又は c) の段階が求められ,それに対しては十分に対応できない面がある。
解 2

12
SAP 16-13:2013 解説
4 混合度評価検討小委員会
評価方法の共通化を図るための基礎的な検討及び実験的な検証を行うために組織された小委員会の構
成を次に示す。
氏名 所属
コーディネータ 宮 南 啓 大阪府立大学
遠 藤 茂 寿 工業技術院資源環境技術総合研究所
特別協力 佐 藤 宗 武 大阪府立大学
委員長 井 上 速 男 塩野義製薬株式会社
代表幹事 谷 本 友 秀 株式会社徳寿工作所
幹事 服 部 好 伸 株式会社ダルトン
吉 田 康 一 ホソカワミクロン株式会社
委員 天 野 勝 弘 株式会社ダルトン
池 上 嘉 宏 大平洋機工株式会社
角 田 淳 愛知電機株式会社
神 谷 昌 良 ホソカワミクロン株式会社
小 林 隆 株式会社栗本鉄工所
近 藤 茂 之 愛知電機株式会社
佐 藤 耕 治 塩野義製薬株式会社
竹 内 和 株式会社島津製作所
谷 口 十 一 神鋼パンテック株式会社
寺 田 裕 彰 株式会社ツムラ
堀 合 誠 株式会社徳寿工作所
山 下 敏 夫 不二パウダル株式会社
(委員:五十音順;所属は当時のもの)
5 混合特性の評価に適する試験方法
5.1 概要
混合試験により装置特性が把握できる粉体及び測定方法が求められた。
5.2 評価試験に使用する試験粉体の選択基準
試験粉体に求められる要件として付属書 A.1(規定)に採用された次のものが挙げられた。
a) 化学的組成・成分が分かっており,経時変化の少ない安定物質であり,取り扱い上安全である。
b) 混合操作によって一次粒子が粉砕されて微粉化しない。
c) 分散性が良く,外力の程度に応じて二次凝集体の分散が進行する。
d) 色の変化で容易に混合状態の変化が分かる組合せができる。
e) 測定がしやすく,複数の方法で混合状態が検証できる。
f) 同一規格の粉体が入手可能である。
g) 価格が適度である。
h) 巨視的な混合,及び,微視的な混合程度までの混合状態が観測できる。
解 3

13
SAP 16-13:2013 解説
5.3 評価試験に使用する測定方法
解説図 1 に示す混合過程における粉体の状態は,解説図 2 の様に変化していくと考えることができる。
例えば,5.2 の要件 d) を満たすような赤色の酸化鉄微粒子と白色粉体を混合すると,酸化鉄微粒子の凝
集体が混合に伴い解砕され,混合物の明度が変化する。色の異なる粉体を混合し,その状態を明度又は
色彩の変化として捉えることで,巨視的な混合から微視的な混合まで把握することが可能である。
解説図 2―混合過程における明度及び到達度の変化モデル
6 試験粉体
6.1 試験粉体の検討及び選定
5.2 の選択基準を満たす試験粉体として,次の組み合わせについて検討した。
― 炭酸カルシウム・ベンガラ(酸化鉄)
― ホワイトアランダム・シリコンカーバイド
― ガラスビーズ・ベンガラ(酸化鉄)
― 鋳物砂・ベンガラ(酸化鉄)
その結果,炭酸カルシウム(SUPER1500,丸尾カルシウム株式会社)・酸化鉄(トダカラー140ED,戸
田工業株式会社)が最も妥当な組み合わせであった。それぞれは,5.2 a)を満たすとともに,白色と赤色
の粉体であり 5.2 d) 及び e) を満たす。また,国内製造者の標準的な製品であり,5.2 f) 及び g) を満た
す。
6.2 試験粉体の粒子径分布
SUPER1500 及び トダカラー140ED の粒子径分布(質量基準)を,それぞれ解説図 3 及び解説図 4
に示す。測定は,レーザー回折・散乱式粒子径分布測定装置(SALD-2001,株式会社島津製作所)で行
った。
解 4

14
SAP 16-13:2013 解説
解説図 3―炭酸カルシウム(SUPER1500)の粒子径分布
解説図 4―酸化鉄(トダカラー140ED)の粒子径分布
6.3 試験粉体の流動性
二分割セル法(コヒテスタ,ホソカワミクロン株式会社)による各粉体層の引張強度の測定結果を解
説図 5 に示す。酸化鉄は微粒子で凝集性がより強いため,混合過程ではバルク成分である炭酸カルシウ
ム層中に凝集体として存在し易い。他方,炭酸カルシウムの引張強度は相対的に小さく,混合過程では
バルクとして流動する。
解 5

15
SAP 16-13:2013 解説
解説図 5―試験粉体及び参照混合粉体の引張強度
6.4 混合過程における粒子径の変化
炭酸カルシウムと酸化鉄とを質量比 95:5 で混合した混合物を,スパチュラによる手混合,高速・高せ
ん断型の混合機又は湿式分散機などで処理した後の粒子径分布を解説図 6 に示す。原末粒子(炭酸カル
シウム)の粉砕又は摩耗による顕著な微粒子化は認められず 5.2 b) を満たしている。
解説図 6―炭酸カルシウム・酸化鉄の混合粉体の粒子径分布
7 混合状態の測定方法―光学的な方法による評価
7.1 混合過程における明度変化
先に示した解説図 1 は,個数基準中位径 50 m の PMMA(ポリメチルメタクリレート)球形粒子(白
色)と個数基準中位径 0.17 m の酸化鉄微粒子(黒色)とを混合し,色彩色差計により測定した混合物
の明度値 L の変化である。明度値は,本体 8.1 の式(1) 及び式(2) により求めた混合物における平均値で
ある。解説図 1 のように明度の変化は巨視的な混合から微視的な混合に至る混合状態を表している。ま
た,炭酸カルシウム・酸化鉄以外の系でも明度値による混合過程の評価・記述が可能である。
7.2 混合粉体の組成比及び混合物の明度
6.1 で選定した炭酸カルシウムと酸化鉄の混合物中における,酸化鉄の混合比(質量)と混合物から
の反射光強度の関係を解説図 7 に示す。任意の組成比である混合物は,附属書 A.4(規定)の方法で調
製した。
また,反射光強度は次によって測定した。
(a) 色彩色差計(CL-100,コニカミノルタ株式会社)
(b) 光ファイバープローブ式混合度計(フォトメーター PM-Ⅲ,株式会社ミナミデシステムエンジニアリ
ング)
(c) 照度計(T-10,コニカミノルタ株式会社)
各測定装置の出力値は,混合物中の酸化鉄組成と相関を示し,明度により混合物の組成評価も可能で
ある。
解 6

16
SAP 16-13:2013 解説
解説図 7―炭酸カルシウム・酸化鉄混合物の組成と反射光強度(明度)
7.3 混合過程における明度変化と凝集体サイズの関係
解説図 8 に,6.1 で選定した炭酸カルシウム・酸化鉄混合物(質量比 95:5 で混合)における平均の到
達度 と,酸化鉄の凝集体サイズとの関係を示す。ここで凝集体サイズは画像解析法で求めた個数基準の
中位径である。また,到達度は本体 8.2 に従って求めた。解説図 8 の様に到達度は酸化鉄の凝集体サイ
ズと関係しており,混合の進行とともに酸化鉄の凝集体が解砕・分散される過程は到達度に反映される。
従って,この系は,5.2 c) ,d) ,e) 及び h) を満たす。
到達度は本体 8.2 の式(4) の様に,明度と線形の関係に有る。従って,混合に伴いあるサイズに分散さ
れた酸化鉄凝集体の混合物内における空間的なバラツキは,明度のサンプル分散に対応している。
解説図 8―混合物中の酸化鉄凝集体の個数基準中位径と混合物明度値に基づく到達度との関係
8 参照混合粉体の調製
到達度を評価するためには参照混合粉体を調製する必要がある。そこで,検討小委員会では,完全分
散状態の混合物を次の様に調製した。300 秒間スパチュラを用いて十分な手混合をした混合物を,高速
羽根かくはん型混合機(Blender KB-1,PHOENIX 社)により乾式かくはん混合し,更に,高速せん断摩
砕法(製造者ノフュージョンシステム,ホソカワミクロン株式会社)によって混合した。最後にアセト
ン添加の下で乳鉢によって湿式分散・混合し,アセトンが蒸発するまで分散操作を行った乾燥粉体を調
製した。
このように調製した“手混合粉体”と他の混合方法による混合粉体に対して,光ファイバープローブ
解 7

17
SAP 16-13:2013 解説
式混合度計及び色彩色差計 CL-100 により測定した結果,両者の差が検出可能なことが分かった。また,
手混合粉体は完全分散状態にあり,参照混合粉体として使用可能である。
9 各種混合機による到達度の測定
検討小委員会に参加した混合機製造者及び使用者各機関において所有する混合機における混合過程を,
この規格で規定する試験粉体及び参照混合粉体を用い到達度によって評価した。混合機の操作条件は各
試験機関が独自に設定した。その結果を解説図 9 に示す(図には混合機の概念図を示し,具体的名称は
明記していない)。
解説図 9 の様に各混合機の特徴を良く表現した混合特性曲線が得られた。
解説図 9―各種混合機に対する到達度と時間との関係の点綴例
10 到達度と組成の分散に関して
規格本体では,明度の分散(標準偏差)とともに本体 8.2 で定義する到達度を評価パラメータとして
用いても良いことを規定している。
明度の分散は,組成の分散に対応しており,本体 8.1 のように着目成分の混合物内における均一性を
反映している。巨視的な混合状態の評価に適している。
これに対して到達度は,定義の様に混合物内での着目成分の均一性を反映したものではない。しかし,
全体の着目成分の全体としての混合・分散された状態とともに,解説図 8 に示される様に,到達度は凝
集体が解砕され,より微細な凝集体になり,完全分散状態に近づくプロセスを示すワークインデックス
である。
混合特性を評価するためには,混合操作の目的に応じて評価パラメータを選択することが重要である。
解 8

18
SAP 16-13:2013 解説
11 参考文献
[1] 日本粉体工業技術協会 混合かくはん分科会・混合度評価法検討委員会:「混合度評価法検討委員会
活動報告書」(1993)
[2] 粉体工学会編:「粉体工学便覧 第 2 版」,4.12「混合」,p. 389,日刊工業新聞社 (1998)
[3] 佐藤宗武他:「付着性粉体を用いた粉体混合機の混合特性の評価」,粉体工学会誌,30, 390-396 (1993)
[4] 佐藤宗武他:「光学的手法による粉粒体の混合度の連続測定システムの開発」,粉体工学会誌,22,
79-84 (1985)
[5] Alonso, M., M. SATOH and K.MIYANAMI: “Mechanism of the Combined Coating-Mechanofusion
Processing of Powders”, Powder Technol., 59, 45-52 (1989)
[6] 佐藤宗武他:「凝集粉体の解砕モデルによる混合過程の評価」,粉体工学会誌, 34, 330-336 (1997)
解 9

19
SAP 16-13:2013 解説
12 原案作成委員会の構成表
混合・成形分科会に設置された原案作成委員会の構成表を,次に示す。
明度測定による粉体混合装置の混合特性評価方法 SAP 原案作成委員会 構成表
氏名 所属
委員長 ○ 遠 藤 茂 寿 単層 CNT 融合新材料研究開発機構
副委員長 ○ 鈴 木 道 隆 兵庫県立大学
委員 安 藤 泰 典 株式会社ノリタケカンパニーリミテド
市 川 卓 司 大平洋機工株式会社
○ 小 泉 一 郎 株式会社ダルトン
小 西 孝 信 ホソカワミクロン株式会社
菅 原 一 博 菅原精機株式会社
菅 原 尚 也 菅原精機株式会社
○ 谷 本 友 秀 株式会社徳寿工作所
藤 井 淳 株式会社栗本鐵工所
松 本 和 弘 株式会社ツムラ
○ 六 車 嘉 貢 塩野義製薬株式会社
特別委員 ○ 佐 藤 宗 武
注 ○は原案作成 WG 構成員
(文責 遠藤 茂寿)
解 10

一般社団法人日本粉体工業技術協会 [協 会 本 部] 京都市下京区烏丸通六条上ル北町 181 番地 第 5 キョートビル 7 階(〒600-8176) TEL: 075-354-3581(総務・経理) 075-354-3583(標準粉体専用)
FAX: 075-352-8530 [東京事務所] 東京都文京区本郷 2-26-11
種苗会館 5 階(〒113-0033) TEL: 03-3815-3955 FAX: 03-3815-3126
http://www.appie.or.jp/