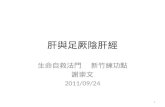Review of - Gastroenterology...El Naggar, J. Rasenack, and N. H. Afdhal 40...
Transcript of Review of - Gastroenterology...El Naggar, J. Rasenack, and N. H. Afdhal 40...


Review of
編集主幹代表菅野 健太郎自治医科大学医学部内科学講座主任教授
編集主幹千葉 勉京都大学大学院医学研究科消化器内科学講座教授
坪内 博仁鹿児島大学大学院医歯学総合研究科消化器疾患・生活習慣病学教授
日比 紀文慶應義塾大学医学部内科学(消化器)教授
編集委員東 健神戸大学医学部消化器内科教授
飯田 三雄九州大学大学院病態機能内科学教授
一瀬 雅夫和歌山県立医科大学第二内科教授
井廻 道夫昭和大学医学部第二内科教授
上村 直実国立国際医療センター内視鏡部長
榎本 信幸山梨大学医学部第一内科教授
太田 慎一埼玉医科大学消化器・肝臓内科教授
岡崎 和一関西医科大学内科学第三講座(消化器肝臓内科)主任教授
岡上 武京都府立医科大学消化器病態制御学教授
恩地 森一愛媛大学大学院医学研究科先端病態制御内科(第三内科)教授
金子 周一金沢大学大学院消化器内科教授
上西 紀夫東京大学大学院消化管外科学教授
河田 純男山形大学消化器病態制御内科学教授
木下 芳一島根大学医学部消化器肝臓内科学教授
熊田 博光国家公務員共済組合連合会虎の門病院副院長
小池 和彦東京大学大学院医学系研究科内科学専攻生体防御感染症学教授
後 裕旭川医科大学消化器・血液腫瘍制御内科学教授
後藤 秀実名古屋大学大学院医学系研究科消化器内科学教授
坂井田 功山口大学大学院医学系研究科消化器病態内科学教授
坂本 長逸日本医科大学消化器内科教授
向坂 彰太郎福岡大学医学部第三内科教授
佐々木 裕熊本大学大学院医学薬学研究部消化器内科学教授
篠村 恭久札幌医科大学医学部内科学第一講座教授
下瀬川 徹東北大学大学院消化器病態学分野教授
白鳥 敬子東京女子医科大学消化器内科教授
杉山 敏郎富山大学医学部内科学第三講座教授
茶山 一彰広島大学大学院医歯薬学総合研究科分子病態制御内科学(旧内科学第一)教授
畠山 勝義新潟大学大学院医歯学総合研究科機能再建医学講座消化器・一般外科学分野教授
林 紀夫大阪大学大学院消化器内科学教授
春間 賢川崎医科大学内科学食道・胃腸科教授
平石 秀幸獨協医科大学消化器内科教授
福土 審東北大学大学院医学系研究科行動医学教授
藤岡 利生大分大学医学部消化器内科教授
藤本 一眞佐賀大学医学部内科学教授
藤山 佳秀滋賀医科大学内科学講座教授
本郷 道夫東北大学病院総合診療部教授
松井 敏幸福岡大学筑紫病院消化器科教授
松本 譽之兵庫医科大学内科下部消化管科教授
三輪 洋人兵庫医科大学内科上部消化管科教授
森 正樹九州大学生体防御医学研究所細胞機能制御学部門分子腫瘍学分野教授
森脇 久隆岐阜大学消化器病態学教授
芳野 純治藤田保健衛生大学坂文種報 會病院内科教授
渡辺 純夫秋田大学消化器内科教授
渡邊 昌彦北里大学医学部外科教授
渡辺 守東京医科歯科大学消化器病態学教授
(五十音順)
© 2006 HESCO International, Ltd.© 2006 American Gastroenterological Association Institute
All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrievalsystem, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying,recording or otherwise, without the prior permission of the copyright owners.
Disclaimer: Statements and opinions expressed in any review article, summary or letter are those of the author only and are not necessarily those of the journal, the editors, theAmerican Gastroenterological Association Institute (AGAI), the publisher or the author of the original article that is being summarized or reviewed, unless specifically stated as such.AGAI had no role in selecting which articles would be summarized or reviewed and is not responsible for the accuracy of the articles. The reader is advised to reference the appropriatemedical literature, to include the original article that appeared in one of the AGAI's official journals, and product information currently provided by the manufacturer of each drug to beadministered to verify the dosage, the method and the duration of administration and contraindications. It is the responsibility of the treating physician or other health care professional,relying on independent experience and knowledge of their patient, to determine drug dosages and the best treatment for the patient. Publication of an advertisement or other productmention in the journal should not be construed as an endorsement of the product or the manufacturer's claim. Neither the AGAI nor the publisher assumes any responsibility for anyinjury and/or damage to persons or property arising out of or related to any use of the material contained in this journal.
編集顧問跡見 裕杏林大学医学部長
藤原 研司独立行政法人労働者健康福祉機構横浜労災病院院長
Anil K. Rustgi, MDGastroenterology 編集長
Michael Camilleri, MDClinical Gastroenterology and Hepatology 編集長
Health Sciences Communications 株式会社ヘスコインターナショナルwww.gastrojournal.orgwww.cghjournal.org
‡
No.2 表2-3 09.9.1 1:56 PM ページ 1

Review of September 2006
Volume 1 • No. 2
CONTENTS
FEATURED ARTICLE 3 消化器病学における新しい概念Lynch症候群(遺伝性非ポリポーシス大腸癌)とミスマッチ修復遺伝子検査に関する最近の知見千葉 勉 京都大学大学院医学研究科消化器内科学講座教授
New Developments in Lynch Syndrome (Hereditary Nonpolyposis ColorectalCancer) and Mismatch Repair Gene Testing
S. B. Gruber
11 平坦・陥凹型大腸腫瘍後藤 秀実 名古屋大学大学院医学系研究科消化器内科学教授 他
Nonpolypoid (Flat and Depressed) Colorectal NeoplasmsR. Soetikno, S. Friedland, T. Kaltenbach, K. Chayama, and S. Tanaka
REVIEW ARTICLE- 14 過敏性腸症候群患者における内臓感覚神経回路の過敏性に関する新たな ALIMENTARY TRACT エビデンス―過敏性腸症候群の内臓感覚過敏をいかに評価するか―
藤本 一眞 佐賀大学医学部内科学教授
Novel Evidence for Hypersensitivity of Visceral Sensory Neural Circuitry inIrritable Bowel Syndrome Patients
A. Lawal, M. Kern, H. Sidhu, C. Hofmann, and R. Shaker
17 クローン病におけるヒト型抗TNFモノクローナル抗体(Adalimumab):CLASSIC-I試験松本 譽之 兵庫医科大学内科下部消化管科教授
Human Anti-Tumor Necrosis Factor Monoclonal Antibody (Adalimumab) inCrohn's Disease: the CLASSIC-I Trial
S. B. Hanauer, W. J. Sandborn, P. Rutgeerts, R. N. Fedorak, M. Lukas, D. MacIntosh, R. Panaccione, D. Wolf,and P. Pollack
21 IFNγ、IL-4両方のsignal cascadeが、SOCS1欠損に伴うTCRααノックアウトマウスでの腸炎を制御する藤山 佳秀 滋賀医科大学内科学講座教授 他
Suppressor of Cytokine Signaling-1 Regulates Inflammatory Bowel Disease inWhich Both IFNγand IL-4 Are Involved
T. Chinen, T. Kobayashi, H. Ogata, G. Takaesu, H. Takaki, M. Hashimoto, H. Yagita, H. Nawata, andA. Yoshimura
24 実験腸炎におけるT細胞および抗原提示細胞機能のCD48による調節後 裕 旭川医科大学消化器・血液腫瘍制御内科学教授 他
CD48 Controls T-Cell and Antigen-Presenting Cell Functions in ExperimentalColitis
A. C. Abadía-Molina, H. Ji, W. A. Faubion, A. Julien, Y. Latchman, H. Yagita, A. Sharpe, A. K. Bhan, and C.Terhorst
28 クローン病の予後予測―予後良好例の予測は可能である―松井 敏幸 福岡大学筑紫病院消化器科教授
Predictors of Crohn's DiseaseL. Beaugerie, P. Seksik, I. Nion-Larmurier, J.-P. Gendre, and J. Cosnes
AGA 02.qxd 09.9.1 11:23 AM ページ 1

REVIEW ARTICLE-LIVER, 32 細胞間競合は移植された胎児幹細胞/前駆細胞による効率的な正常肝再構築PANCREAS, AND BILIARY をもたらすTRACT 河田 純男 山形大学消化器病態制御内科学教授
Cell Competition Leads to a High Level of Normal Liver Reconstitution byTransplanted Fetal Liver Stem/Progenitor Cells
M. Oertel, A. Menthena, M. D. Dabeva, and D. A. Shafritz
36 急性C型肝炎に対するペグインターフェロンアルファ-2b療法:持続的ウイルス陰性化に対する治療開始時期の影響熊田 博光 国家公務員共済組合連合会虎の門病院副院長
Peginterferon Alfa-2b Therapy in Acute Hepatitis C: Impact of Onset of Therapy onSustained Virologic Response
S. M. Kamal, A. E. Fouly, R. R. Kamel, B. Hockenjos, A. Al Tawil, K. E. Khalifa, Q. He, M. J. Koziel, K. M.El Naggar, J. Rasenack, and N. H. Afdhal
40 血中B型肝炎ウイルス量に基づく肝硬変発生リスクの予測榎本 信幸 山梨大学医学部第一内科教授 他
Predicting Cirrhosis Risk Based on the Level of Circulating Hepatitis B ViralLoad
U. H. Iloeje, H.-I. Yang, J. Su, C.-L. Jen, S.-L. You, C.-J. Chen, and The Risk Evaluation of Viral LoadElevation and Associated Liver Disease/Cancer-In HBV (the REVEAL-HBV) Study Group
43 原発性胆汁性肝硬変にウルソデオキシコール酸を投与し肝機能が改善すると長期予後は改善する岡上 武 京都府立医科大学消化器病態制御学教授
Excellent Long-Term Survival in Patients With Primary Biliary Cirrhosis andBiochemical Response to Ursodeoxycholic Acid
A. Parcs, L. Caballería, and J. Rodés
46 Pdx1遺伝子欠損マウスでは十二指腸主乳頭部の欠損により色素系胆道結石を形成する岡崎 和一 関西医科大学内科学第三講座(消化器肝臓内科)主任教授
Loss of the Major Duodenal Papilla Results in Brown Pigment Biliary StoneFormation in Pdx1 Null Mice
A. Fukuda, Y. Kawaguchi, K. Furuyama, S. Kodama, T. Kuhara, M. Horiguchi, M. Koizumi, K. Fujimoto,R. Doi, C. V. E. Wright, and T. Chiba
49 肝細胞癌患者における3種類の腫瘍マーカー同時測定の予後判定における有用性井廻 道夫 昭和大学医学部第二内科教授
Prognostic Significance of Simultaneous Measurement of Three Tumor Markers inPatients With Hepatocellular Carcinoma
H. Toyoda, T. Kumada, S. Kiriyama, Y. Sone, M. Tanikawa, Y. Hisanaga, A. Yamaguchi, M. Isogai,Y. Kaneoka, and J. Washizu
52 編集後記
本誌では原則として国内未承認の薬剤は英語表記としています。
AGA 02.qxd 09.9.1 11:23 AM ページ 2

Review of Gastroenterology & Clinical Gastroenterology and Hepatology Vol. 1, No. 2 3
消化器病学における新しい概念Lynch症候群(遺伝性非ポリポーシス大腸癌)とミスマッチ修復遺伝子検査に関する最近の知見千葉勉 京都大学大学院医学研究科消化器内科学講座教授
New Developments in Lynch Syndrome (Hereditary Nonpolyposis Colorectal Cancer)and Mismatch Repair Gene Testing
STEPHEN B. GRUBERDepartments of Internal Medicine, Epidemiology, and Human Genetics, Division of Molecular Medicine and Genetics, University of Michigan, Ann Arbor,Michigan
Gastroenterology 2006 Feb;130(2):577-587
伝性非ポリポーシス大腸癌(Hereditary Nonpolyposis
Colorectal Cancer:HNPCC)は現在ではLynch症候群
としてより認識されているが、その遺伝子検査はこの症候群が
疑われる患者やそのリスクのある近親者に対する標準的ケアと
なっている 1-5。Lynch症候群とは結腸直腸、子宮内膜、胃、小
腸、肝胆道系、上部尿管、卵巣、まれに脳に悪性腫瘍が多発す
る常染色体優性遺伝性疾患である 6-8。この総説ではLynch症
候群の臨床的知見と遺伝子検査に関する最近の進歩に重点を
置いて述べる。
Lynch症候群における悪性腫瘍発生のパターンや生涯リス
クについては現在では十分に確立されており、そのパターンは
1913年にMichigan大学のAldred Warthinによって初めて
記述されたもの 9 や、約40年前にHenry Lynchの画期的な観
察報告 10,11で示されたものとあまり変わっていない。以前の家系
図では胃癌が多発していたが、1930年代以降、欧米諸国の地域
登録で胃癌の罹患率が減少するのに伴って 12、Lynch症候群家
系での胃癌の罹患率も減少してきた 13。
大腸癌の生涯リスクは82%に上るとみられている14が、最近の
地域研究では男性は68.7%、女性では52.2%と報告されている15。
子宮内膜癌はLynch症候群では大腸癌に次いで多く、生涯リス
クは40~70%と考えられている14,16,17。Hampelらは、その生涯リ
スクは54%、平均発症年齢は62歳と報告した15。また、子宮内膜
癌の生涯リスクは大腸癌の生涯リスクをも凌ぐといういくつかの
研究もある。現在ではLynch症候群家系ではこれらの悪性腫瘍
と比べて胃癌の発生は少なく、その累積リスクは13%である14。
しかし、中国 18や韓国 19では胃癌のリスクはより高い傾向にあ
り、子宮内膜癌をはるかに凌ぐ。卵巣癌の生涯リスクは、
Newfoundlandのある大家系の研究で36%と算定されたが 21、
実際にはおよそ10~12%と考えられる 14,20。
臨床基準HNPCC/Lynch症候群の臨床的基準は当初連鎖解析と
ポジショナルクローニング研究を容易にすることを目的とし
て、1991年に初めて確立された 22。Amsterdamで開催された
International Collaborative Group on Hereditary Nonpolyposis
遺 Colorectal Cancerの会議で最初に提唱されたこれらの診断基準
は、それぞれの家系を誤って分類してしまう可能性を減らすた
めに高い特異度を有するようにデザインされた。この高い特異
度が結果として感度を低くさせ、Lynch症候群の多くの家系が
このオリジナルの「Amsterdam criteria」には当てはまらなくなっ
た。このような限界はあるが、このオリジナルの診断基準
(Amsterdam I)は臨床現場でLynch症候群の家系を同定す
る有用な手段を提供し続けている。時に「3-2 -1 -0方式」と記
述されるが、オリジナルのAmsterdam criteria はHNPCC(とし
て当時は知られていた)を次のように定義している:病理学的に
大腸癌の診断が確立した家族が3人以上おり、そのうちの1人
は他の2人の第一度近親者である。少なくとも連続する2世代
以上で罹患しており、そのうち1人は50歳以前に診断された者
がいる。家族性大腸腺腫症は除外されている。現在ではLynch
症候群の分子的機序が明らかになり、既知の突然変異を有す
る家系を検出するためのAmsterdam I criteriaの感度と特異
度について、最近のメタ解析も含めいくつかの研究がなされて
いる。それによると、Amsterdam I criteriaの感度は54~
91%、特異度は62~84%とされている23。
Amsterdam criteria は1999年に、Lynch症候群に認められる
他の悪性腫瘍(大腸癌以外)をも含む、と改訂された 24。この
Amsterdam II criteriaはAmsterdam I criteriaと基本的には同
じであるが(表1)、唯一の改訂基準は家族内に発生する悪性
腫瘍を大腸癌に限定していないことである。大腸癌に加え、
Amsterdam II criteriaで該当すると考えられるLynch症候群
の悪性腫瘍は子宮内膜、小腸、腎臓、腎盂、尿管の癌である。
Amsterdam II criteriaの集団感度は78%、特異度は46~68%で
ある23。
臨床現場でAmsterdam criteriaに頼り過ぎることはLynch
症候群の見落としにつながりかねないため、該当する家族を同
定する助けとなる他の方法が開発されてきた。家族歴に加え、
若年齢時での診断、多発するLynch症候群関連悪性腫瘍、
Lynch症候群でみられるようなマイクロサテライト不安定性を示
す腫瘍に特徴的な組織学的所見、などの臨床的および病理学
的特徴もまたLynch症候群の同定に利用可能である。Bethesda
Featured Article
AGA 02.qxd 09.9.1 11:23 AM ページ 3

Review of Gastroenterology & Clinical Gastroenterology and Hepatology Vol. 1, No. 2 11
研究の背景
腸癌の多くはポリープの形状から徐々に発育することが
知られている1。近年、非ポリープ型(平坦・陥凹型)の大
腸病変(nonpolypoid colorectal neoplasms:以下NP-CRN)も大
腸癌の原因となることが報告されている(表1)2-7。NP-CRNは周
囲の正常粘膜と比べることにより、表面隆起型、平坦型、陥凹
型に分けられる。特に陥凹型のNP-CRNは、同じサイズのポリ
ープ型病変に比べて高異型度の部分が存在する可能性や、浸
潤傾向の強い癌である可能性が高い(図1)8,9。このレビューで
はNP-CRNについての自然経過、診断、そして治療についての
新しい情報を提供する。
大
早期大腸癌分類、平坦・陥凹型腫瘍、大腸癌発育主経路、
EMR
キーワード
表1.ヨーロッパと北米におけるNP-CRN前向き疫学研究の抜粋
Authors (country) andnumber of patients
studied
Prevalence ofpatients withNP-CRN, %
Number of NP-CRNlesions detected per
100 patients
Number of allCRN with non
polypoidmorphology, %
Number of allNP-CRN withhigh-grade
dysplasia, %
Number of flatNP-CRN withsubmucosal
invasivecarcinoma, %
Number ofdepressed
NP-CRN withsubmucosal
invasivecarcinoma, %
Jaramillo et al (Sweden)N = 232
23.7 47.0 41.7 11.0 2.75 0
Fujii et al (UK)N = 208
Not stated 14.4 42.2 3.3 0 6.7
Rembacken et al (UK)N = 1000
Not stated 12.3 37.6 13 1.6 1.6
Saitoh et al (US)N = 211a
21.8 26.1 39.6 Not stated 1.8 0
Tsuda et al (Sweden)N = 973
6.0 7.0 6.6 16.7 1.5 6.1
Hurlstone et al7
5
6
4
2
3
(UK)N = 850
Not stated 32.4 35.8 20.4 0.7 2.18
この表には抄録のみの報告、200例未満の報告、後向き研究は含まれていない。a 2例の陥凹を伴う平坦病変は固有筋層以深に及ぶ進行癌であり、この表から除外した。
論文の概要
用語(Terminology)
Paris分類(図2)10 は日本の大腸癌分類 11を基にして作られ
た。粘膜下層までにとどまる大腸癌はポリープ型、非ポリープ
型に分けられた上、さらにそれぞれ0-Ip、0-Isと0-IIa、0-IIb、0-
IIcに分類される。陥凹型(0-IIc)と周辺隆起を伴った陥凹型(0-
IIc+IIa)病変は粘膜下層まで浸潤した癌であることが多い。
疫学(Epidemiology)
アジアでは多数例の報告は日本からに限られているが、韓
国、台湾、マレーシア、シンガポールからも報告がある。西欧
諸国からはNP-CRNの存在ならびに重要性が発表されている
(表1)。
自然史(Natural History)
NP-CRNの自然史の多くは不明であるが、報告例から推察す
ると腺腫であってもポリープ病変よりも悪性化傾向の強い病変
と考えられる12。
平坦・陥凹型大腸腫瘍安藤貴文 名古屋大学医学部附属病院消化器内科助手
後藤秀実 名古屋大学大学院医学系研究科消化器内科学教授
Nonpolypoid (Flat and Depressed) Colorectal NeoplasmsROY SOETIKNO, SHAI FRIEDLAND, TONYA KALTENBACH, KAZUAKI CHAYAMA, and SHINJI TANAKAVeterans Affairs Palo Alto Health Care System and Stanford University School of Medicine, Palo Alto, California; and Hiroshima University School ofMedicine, Hiroshima, Japan
Gastroenterology 2006 Feb;130(2):566-576
Featured Article
AGA 02.qxd 09.9.1 11:23 AM ページ 11

14
過敏性腸症候群患者における内臓感覚神経回路の過敏性に関する新たなエビデンス―過敏性腸症候群の内臓感覚過敏をいかに評価するか―藤本一眞 佐賀大学医学部内科学教授
Novel Evidence for Hypersensitivity of Visceral Sensory Neural Circuitry in IrritableBowel Syndrome Patients
ADEYEMI LAWAL, MARK KERN, HARJOT SIDHU, CANDY HOFMANN, and REZA SHAKERDivision of Gastroenterology and Hepatology, Medical College of Wisconsin, Milwaukee, Wisconsin
Gastroenterology 2006 Jan;130(1):26-33
Background & Aims: Visceral hypersensitivity in irritablebowel syndrome (IBS) patients has been documented byevaluation of perceived stimulations that can reflectabnormalities of both sensory neurocircuitry and cognitiveprocesses. The presence of actual neurohypersensitivityin human beings has not been documented separately.Because subliminal stimulations are free from theinfluence of stimulus-related cognitive processes,functional magnetic resonance imaging (fMRI) corticalresponse to these stimuli can be considered a measure ofactivity of the neural circuitry alone. The aim of this studywas to compare quantitatively the cerebral cortical fMRIactivity response to equal subliminal stimulations betweenIBS patients and age-matched controls. Methods: Westudied 10 IBS patients and 10 healthy controls using acomputerized barostat-controlled rectal distention device.fMRI activity volume and percent maximum signalintensity change for equal subliminal distention pressureswere compared between controls and patients. Results:Three levels of subliminal distention pressures (eg, 10, 15,and 20 mm Hg), were represented in both controls andpatients and were analyzed for fMRI response. In all 3distention levels the fMRI activity volume in IBS patientswas significantly larger than age- and sex-matchedcontrols (P < .05). The percent maximum signal intensitychange was similar between IBS patients and controls.Conclusions: The volume of cerebral cortical activityresponse to equal subliminal distention pressures in IBSpatients is significantly larger than in controls,documenting the existence of hypersensitivity of theneural circuitry in this patient group irrespective ofstimulus-related cognitive processes.
研究の背景
敏性腸症候群は上部消化管の機能性ディスペプシア
(functional dyspepsia:以下FD)とともに消化管の機
能性疾患であり、臨床症状が下部消化管中心の場合に診断が
付けられる。実際の臨床現場では、過敏性腸症候群とFDを鑑
別することは必ずしも簡単ではない。これらの疾患は器質的疾
患がない場合が診断の原則となるが、炎症性腸疾患との移行
や感染性腸炎の関係なども考えられており、機能性腸疾患とし
ての過敏性腸症候群と器質的疾患の鑑別も容易ではない。過
敏性腸症候群の原因として末梢組織での受容体反応性 1など
の要因の関与が報告されているが、神経系因子としては求心性
内臓感覚神経回路異常2と大脳皮質を中心とする中枢神経系異
常 3の2つに大別できる。これらの異常によりIBS患者では消化
管の過敏性を生じており、圧刺激や痛みに対する閾値の低下が
起きている 4,5。これらの異常を評価する場合に「認知」は重要
な因子となっており、中枢神経による知覚を介した認知能を利
用した評価法が中心である。「認知」を介した評価が本当に客
観的であるかどうかは疑問の残るところであり、今回の論文で
は直腸伸展に対する中枢神経系の反応を機能性MRIで評価す
ることで、より客観的な評価を試みている。
過
直腸伸展刺激、バロスタット、大脳皮質、認知、知覚
キーワード
Review Article Alimentary Tract
図1.活性化された大脳皮質体積の直腸伸展圧別での評価
(m m H g)
10 1 5 20
activa
ted
co
rtic
al vo
lum
e (
µL
)
0
2000
4000
6000
8000
I B S
controls
n= 7
n= 4
n= 6
n=8
n=1 0
n= 9
* p=0 .001
* p= 0 .00 3
* p= 0 .036
AGA 02.qxd 09.9.1 11:23 AM ページ 14

Review of Gastroenterology & Clinical Gastroenterology and Hepatology Vol. 1, No. 2 17
広く使用されていたが、緩解導入療法には大きな変化がなかっ
た。そのような中で、1990年代に開発された抗TNFα抗体であ
るインフリキシマブ 1は、クローン病の腸管病変と外瘻の両者に
対して、強い緩解導入効果をもたらすことが多施設共同の二重
盲検試験で証明され、1998年には米国でFDAに認可された。
その後、インフリキシマブを8週ごとに長期投与することが、腸
管病変・外瘻の両者に対して極めて高い効果をもつ緩解維持療
法となることも示された(ACCENT-I/II試験)。
しかしながらインフリキシマブはヒト・マウスキメラ型抗体であ
り、このことが抗インフリキシマブ抗体(ATI)産生のきっかけと
なりうること、ATI陽性例では、副作用発現率の増加や効果発
現期間の短縮が認められることも明らかとなり、より抗原性の低
い完全ヒト型抗体の有効性が期待され、いくつかの抗体が開発
された。その中で、IgG1サブクラスのヒト型抗体をポリエチレン
グリコール(PEG)化することにより、皮下注射可能としたものが、
adalimumabである2。本試験は、クローン病(特に活動性の腸管
病変)に対する臨床効果と適正用量を多施設共同試験で検証
したものである。本試験では、Crohn's Disease Activity
Index(以下CDAI)による臨床効果をプライマリエンドポイント
としており、内視鏡的な病変の改善に関しての情報は含まれて
いない。なお、本CLASSIC-I試験では短期の緩解維持効果が
検討されているが、ほぼ同時期に長期効果をみたCLASSIC-II
試験も実施されている。
論文の概要
Tumor necrosis factor(TNF)阻害療法は、クローン病に
対する効果的な治療である。Adalimumabはヒト型抗TNF抗
体でIgG1サブクラスに属している。本研究は、2002年7月から
2003年12月にかけて55施設が参加して行われた、多施設共同
ランダム化二重盲検プラセボ対照比較試験である。
患者選択基準
X線あるいは内視鏡的に診断が確定された18~75歳のクロー
ン病患者で、試験参加前少なくとも4ヵ月以上中等症から重症
クローン病におけるヒト型抗TNFモノクローナル抗体(Adalimumab):CLASSIC-I試験
松本譽之 兵庫医科大学内科下部消化管科教授
Human Anti-Tumor Necrosis Factor Monoclonal Antibody (Adalimumab) in Crohn'sDisease: the CLASSIC-I Trial
STEPHEN B. HANAUER,* WILLIAM J. SANDBORN,‡ PAUL RUTGEERTS,§ RICHARD N. FEDORAK,¶ MILAN LUKAS,‖
DONALD MACINTOSH,♯ REMO PANACCIONE,** DOUGLAS WOLF,‡‡ and PAUL POLLACK§§
*Division of Gastroenterology, University of Chicago Medical Center, Chicago, Illinois; ‡Department of Gastroenterology and Hepatology, Mayo Clinic,Rochester, Minnesota; §Department of Gastroenterology, Universitaire Ziekenhuizen Leuven, UZ Gasthuisberg, Leuven, Belgium; ¶Division ofGastroenterology, University of Alberta, Edmonton, Alberta, Canada; ‖Clinical Department of Gastroenterology and Hepatology, Charles University, Prague,Czech Republic; ♯Department of Medicine, Dalhousie University, Halifax, Nova Scotia, Canada; **Gastroenterology and Hepatology, University of Calgary,Calgary, Alberta, Canada; ‡‡Atlanta Gastroenterology Associates, Atlanta, Georgia; and §§Abbott Laboratories, Parsippany, New Jersey
Gastroenterology 2006 Feb;130(2): 323-333
Background & Aims: Tumor necrosis factor blockade has
been shown to be an effective treatment strategy in
Crohn's disease (CD). Adalimumab is a human
immunoglobulin G1 (IgG1) monoclonal antibody targeting
tumor necrosis factor (TNF). A randomized, double-blind,
placebo-controlled, dose-ranging trial was performed to
evaluate the efficacy of adalimumab induction therapy in
patients with CD. Methods: A total of 299 patients with
moderate to severe CD naive to anti-TNF therapy were
randomized to receive subcutaneous injections at weeks
0 and 2 with adalimumab 40 mg/20 mg, 80 mg/40 mg, or
160 mg/80 mg or placebo. The primary endpoint was
demonstration of a significant difference in the rates of
remission at week 4 (defined as a Crohn's Disease Activity
Index score <150 points) among the 80 mg/40 mg, 160
mg/80 mg, and placebo groups. Results: The rates of
remission at week 4 in the adalimumab 40 mg/20 mg, 80
mg/40 mg, and 160 mg/80 mg groups were 18% (P = .36),
24% (P = .06), and 36% (P = .001), respectively, and 12%
in the placebo group. Adverse events occurred at similar
frequencies in all 4 treatment groups except injection site
reactions, which were more common in adalimumab-
treated patients. Conclusions: Adalimumab was superior
to placebo for induction of remission in patients with
moderate to severe Crohn's disease naive to anti-TNF
therapy. The optimal induction dosing regimen for
adalimumab in this study was 160 mg at week 0 followed
by 80 mg at week 2. Adalimumab was well tolerated.
研究の背景
米におけるクローン病の治療は、ステロイドを中心として
行われていたが、再発率、再手術率など満足できるもの
とはいえなかった。その後、アザチオプリンなどの免疫抑制剤
が緩解維持や肛門部病変の治療に有効であることが示されて
欧
Review Article Alimentary Tract
クローン病、TNF、生物学的製剤、
Adalimumab、インフリキシマブ
キーワード
AGA 02.qxd 09.9.1 11:23 AM ページ 17

Review of Gastroenterology & Clinical Gastroenterology and Hepatology Vol. 1, No. 2 21
IFNγ、IL-4両方のsignal cascadeが、SOCS1欠損に伴うTCRαノックアウトマウスでの腸炎を制御する小川敦弘 滋賀医科大学内科学講座
藤山佳秀 滋賀医科大学内科学講座教授
Suppressor of Cytokine Signaling-1 Regulates Inflammatory Bowel Disease in WhichBoth IFNγ and IL-4 Are Involved
TAKATOSHI CHINEN,*,‡ TAKASHI KOBAYASHI,* HISANOBU OGATA,* GIICHI TAKAESU,* HIROMI TAKAKI,*
MASAYUKI HASHIMOTO,* HIDEO YAGITA,§ HAJIME NAWATA,‡ and AKIHIKO YOSHIMURA*
*Division of Molecular and Cellular Immunology, Medical Institute of Bioregulation, ‡Department of Medicine and Bioregulatory Science, Graduate School ofMedical Sciences, Kyushu University, Fukuoka, Japan; and the §Department of Immunology, Juntendo University School of Medicine, Tokyo, Japan
Gastroenterology 2006 Feb;130(2): 373-388
Background & Aims: The suppressor of cytokine
signaling-1 (SOCS1) is a potent negative regulator of
various cytokines and it has been implicated in the
regulation of immune responses. However, the role of
SOCS1 in inflammatory bowel diseases (IBDs) has not
been clarified. To determine the role of SOCS1 in colitis,
we generated SOCS1/T-cell receptor α (TCRα) double
knockout (DKO) mice. Methods: The depletion of
interferon γ (IFNγ) and IL-4 was achieved by crossing
the DKO mice with IFNγ knockout (KO) mice and by the
administration of anti-IL-4 antibody, respectively. The
activation of cytokine-induced transcription factors was
determined by Western blotting with phosphorylation-
specific antibodies, and the induction of inflammatory
factors was measured by reverse-transcription
polymerase chain reaction. Results: Much more severe
colitis developed in 100% of the DKO mice within 9 weeks
of age than in TCRα-KO mice. Although the proportion
and the activation status of CD4+ TCRα-β+ T cells in
DKO mice were similar to those in TCRα-KO mice, signal
transducer and activator of transcription 1, nuclear factor
κB, and their target genes were hyperactivated in
infiltrated mononuclear cells and colonic epithelial cells in
DKO mice. Cytokine-depletion experiments showed that
exacerbated colitis in the DKO mice was dependent on
both IFNγ and IL-4. SOCS1-deficient cells were
hypersensitive to IFNγ, IL-4, and lipopolysaccharides,
depending on the target genes. Conclusions: SOCS1
plays an important role in preventing murine colitis by
restricting the cytokine signals. SOCS1/TCRα DKO mice
could be a useful model for investigating human IBD.
Review Article Alimentary Tract
IBD、SOCS1、IFNγ/STAT1、IL-4/STAT6、
TCRαノックアウト(KO)マウス
キーワード
研究の背景
ローン病(Crohn's disease:以下CD)や潰瘍性大腸炎
(ulcerative colitis:以下UC)に代表される慢性非特異
性炎症性腸疾患(inflammatory bowel disease:以下IBD)は、
最近の研究によって、遺伝的要因を背景として、腸内細菌に代
表される環境因子に対する腸管粘膜における免疫応答の破綻
がその病態と捉えられている。すなわち、TNFα、IL-12、IFNγ、
IL-4、IL-13に代表される炎症性サイトカインと、IL-10、TGFβ
などの抗炎症性サイトカインとの不均衡が関与すると想定されて
いる1。一般的には、CDはTh1(T helper 1-type)型優位(TNF
α、IL-12、IFNγ)、UCはTh2型優位(IL-4、IL-13)のサイトカイ
ン産生パターンを呈する傾向がある。しかし、実際にはCDにお
けるIL-4産生増加や2、UCにおけるIFNγ/STAT1からのsignal
cascadeの重要性も報告されている3。
サイトカインからの刺激は、特定のJAK/STATシグナル伝達
を介して核内での遺伝子発現を制御しておりIFNγ/STAT1、
IL- 4/STAT6系などが明らかにされている 4。また、同時に
SOCS(suppressor of cytokine signaling)familyによるシグナル
伝達抑制機構の存在も解明されている 5。例えばCDおよびUC
患者の腸管においては、SOCS3の高発現が認められており、IL-6
からSTAT3へのシグナルに対するSOCS3による抑制性機構が
考えられ、粘膜治癒、過形成に寄与していると推測されている6,7。
本論文は、Th2型自然発症腸炎モデルマウスのTCRαノック
アウト(KO)マウスを用いて腸炎惹起におけるSOCS1の役割を
明らかにしようとしたものであり、SOCS1/TCRαダブルノック
アウト(DKO)マウスでの腸炎発症、およびIFNγ、IL-4からの
シグナル抑制の病態への修飾を検討している。
ク
AGA 02.qxd 09.9.1 11:23 AM ページ 21

24
Review Article Alimentary Tract
実験腸炎におけるT細胞および抗原提示細胞機能のCD48による調節蘆田知史 旭川医科大学消化器・血液腫瘍制御内科学講師
後 裕 旭川医科大学消化器・血液腫瘍制御内科学教授
CD48 Controls T-Cell and Antigen-Presenting Cell Functions in Experimental ColitisANA C. ABADÍA-MOLINA,* HONBING JI,* WILLIAM A. FAUBION,* AIMÉE JULIEN,*YVETTE LATCHMAN,‡ HIDEOYAGITA,§ ARLENE SHARPE,¶ ATUL K. BHAN,‖ and COX TERHORST**Division of Immunology, Beth Israel Deaconess Medical Center, Harvard Medical School, Boston, Massachusetts; ‡Puget Sound Blood Center, ResearchDivision, Seattle, Washington; §Department of Immunology, Juntendo University School of Medicine, Tokyo, Japan; ¶Department of Pathology, HarvardMedical School, Boston, Massachusetts; and ‖Department of Pathology, Massachusetts General Hospital, Harvard Medical School, Boston, Massachusetts
Gastroenterology 2006 Feb;130(2): 424-434
炎症性腸疾患、補助刺激分子、制御性T細胞、抗CD48抗体
キーワードBackground & Aims: The cell-surface receptor CD48 is alipid-anchored protein expressed on all antigen-
presenting cells and T cells. CD2 and 2B4 are known
ligands for CD48, which themselves are expressed on the
surface of hematopoietic cells. Here we examine the
effect of CD48 in the development of chronic experimental
colitis and how CD48 affects adaptive and innate immune
functions. Methods: The role of CD48 in experimentalcolitis was first assessed by transferring CD4+CD45RBhi
cells isolated from either wild-type or CD48-/- mice into
either Rag-2-/- or CD48-/- × Rag-2-/- mice. Development
of chronic colitis in these adoptively transferred mice was
assessed by disease activity index, histology, and
production of interferon-γ in mesenteric lymph nodes.
Relevant functions of CD48-/-CD4+ T cells and CD48-/-
macrophages were examined using in vitro assays. In a
second set of experiments, the efficacy of anti-CD48 in
prevention or treatment of chronic colitis was determined.
Results: CD48-/-CD4+ cells induced colitis whentransferred into Rag-2-/- mice, but not when introduced
into CD48-/- × Rag-2-/- recipients. However, both
recipient mouse strains developed colitis upon adoptive
transfer of wild-type CD4+cells. Consistent with a CD4+ T-
cell defect was the observation that in vitro proliferation of
CD48-/-CD4+ T cells was impaired upon stimulation with
CD48-/- macrophages. In vitro evidence for a modest
macrophage functional defect was apparent because
CD48-/- macrophages produced less tumor necrosis
factor α and interleukin 12 than wild-type cells upon
stimulation with l ipopolysaccharide. Peritoneal
macrophages also showed a defect in clearance of gram-
negative bacteria in vitro. Treatment of the CD4+CD45RBhi
→Rag-2-/- mice or the wildtype BM→tgε26 mice with
anti-CD48 (HM48-1) ameliorated development of colitis,
even after its induction. Conclusions: Both CD48-dependent activation of macrophages and CD48-
controlled activation of T cells contribute to maintaining
the inflammatory response. Consequently, T cell-induced
experimental colitis is ameliorated only when CD48 is
absent from both T cells and antigen-presenting cells.
Because anti-CD48 interferes with these processes, anti-
human CD48 antibody treatment may represent a novel
therapy for inflammatory bowel disease patients.
研究の背景
症性腸疾患(inflammatory bowel disease:以下IBD)は腸
内細菌や自己抗原に対する異常な免疫反応がその病因
と考えられている。この疾患に関与する多くの要因を理解する
目的で、多くの実験モデル動物の解析が行われている。これら
の動物モデル、特にCD4+CD45RBhiT細胞をSCIDマウスへ移
植することによって惹起される腸炎モデル 1や、tgε26マウスへ
野生型(wild type:以下wt)マウスの骨髄を移植する腸炎モデ
ル 2では、IFNγ、IL-12、TNFαのサイトカインが炎症局所ある
いは末梢血中に増加するTh1型の反応が腸管管腔内抗原に対
して生じ、これにより炎症が惹起される。抗TNFα抗体やsLT
βRでこのサイトカイン環境を中和すると炎症が抑制されること
も明らかとなっている。これらのモデルにおける炎症発症の主
体はTh1型のCD4+T細胞であるが、wtのマウスでは腸炎惹起
性のCD4+CD45RBhiT細胞はCD4+CD25+の制御性(regulatory)
T細胞(Treg)によって抑制されていることが明らかとなって
いる3。
一方、T細胞の活性化にはNHCと抗原ペプチドの複合体を
T細胞受容体(TCR)が認識するだけでは不十分で、抗原提示
細胞(APC)上のリガンドを認識するcostimulatory molecule
(補助刺激分子)からのシグナル伝達が不可欠である 4。この
costimulatory molecule/リガンドの代表はAPC上のCD80、
CD86とT細胞上のCD28、CTLA-4であり、広く研究が行われ
ている。実験腸炎においては、この他にCD40とCD40L 5、T細
胞に誘導されるICOSとそのリガンドのB7h2の関与 6など新し
いcostimulator分子の解析も報告されている。本研究ではこの
ようなcostimulatory molecule/リガンドのセットであるCD48とそ
のリガンドのCD2とCD244(2B4)分子に着目し、実験腸炎モデ
ルにおける腸炎誘導への関与を明らかにした。CD48はT細胞、
B細胞、NK細胞、およびすべてのAPCに発現するGPI-anchored
proteinである7。CD2はT細胞とAPCに発現する分子、2B4は
NK細胞とCD8+細胞に発現する分子でいずれもCD48と親和性
炎
AGA 02.qxd 09.9.1 11:23 AM ページ 24

28
クローン病の予後予測―予後良好例の予測は可能である―松井敏幸 福岡大学筑紫病院消化器科教授
Predictors of Crohn's DiseaseLAURENT BEAUGERIE, PHILIPPE SEKSIK, ISABELLE NION-LARMURIER, JEAN-PIERRE GENDRE, and JACQUESCOSNESDepartment of Gastroenterology, Saint-Antoine Hospital, and Pierre et Marie Curie University, Paris, France
Gastroenterology 2006 Mar;130(3): 650-656
研究の背景
ローン病(Crohn's disease:以下CD)の自然史は不明の点
が多い。病院例では多くのCD患者が難治であり、それゆ
え一様に治療を考えがちである。しかし、中には易治例もあり、
さらにその中間の経過をたどる例も存在する。これらを初診時
から見極めることができれば、長期経過を考慮に入れ治療法を
選択することができ、患者にとってこれ以上有利なことはない。
Beaugerieらは、極めて長期間の追跡研究により予後を判定し
てこれらの事実に迫った。また、彼らは一部には前向き研究を
併用し、その事実を確認している。この結果は、過去の研究結
果とも矛盾しないことから 1-3、おそらくは、高いエビデンスとして
受け入れられることは間違いない。これまで、CD患者を病態に
より群別する試みはあまりうまくいっていない。過去には、CDの
病態として狭窄型と瘻孔型に分ける試みがあった。もちろん、瘻
孔型の予後が悪いとの理論が主張された。しかし、CD患者の
病態が一定の行動をしないことから、有用な分類とは考えられ
ていない。その理由は、瘻孔型は年々その比率を高め、疾病行
動が一定していないことによる。すなわち、今回の共著者であ
るCosnesによれば、瘻孔型は診断後5年で患者総数の約40%で
あるが、15年後には約60%に増加するという4。したがって、予
後を推測する新たな分類が求められてきた。そこで、Beaugerie
らは、新たなdisabling patternを考え出した。
論文の概要
目的
CDに対する早期の強力な治療が治療困難例(disabling
disease)に推奨されている。そこで、初診から5年間の治療困
難例を初診時に予測することができるか否かを検討する。
Beaugerie自身は以下のように述べている:最近、インフリキ
シマブが広く使用されるようになり、CD患者に長期緩解をもた
らすようになった。特に、step-up治療に代わりインフリキシマブ
を初期から用いるtop-down治療が重要視されるようになった
が、これは最初の再燃時からインフリキシマブを連続使用して
ク
disabling、predictor、クローン病
キーワードBackground & Aims: Early intensive therapy in Crohn's
disease should be considered only in patients with
disabling disease. The aim of our study was to identify at
diagnosis factors predictive of a subsequent 5-year
disabling course. Methods: Among the 1526 patients seen
at our unit with Crohn's disease diagnosed between 1985
and 1998, we excluded patients operated on within the
first month of the disease, patients with inadequate data,
and patients with severe chronic nondigestive disease. In
the 1188 remaining patients, Crohn's disease course
within the first 5 years of the disease was categorized as
disabling when at least 1 of the criteria of clinical severity,
conventionally predefined, was present. Results: Among
the 1123 patients with follow-up data allowing full 5-year
course classification, the rate of disabling disease was
85.2%. Independent factors present at diagnosis and
significantly associated with subsequent 5-year disabling
were the initial requirement for steroid use (OR 3.1 [95%
CI: 2.2- 4.4]), an age below 40 years (OR 2.1 [95% CI: 1.3-
3.6]), and the presence of perianal disease (OR 1.8 [95%
CI: 1.2-2.8]). The positive predictive value of disabling
disease in patients with 2 and 3 predictive factors of
disabling disease was 0.91 and 0.93, respectively. These
values were 0.84 and 0.91, respectively, when tested
prospectively in an independent group of 302 consecutive
patients seen at our institution from 1998. Conclusions: At
diagnosis of Crohn's disease in a referral center, factors
predictive of subsequent 5-year disabling course are an
age below 40 years, the presence of perianal disease, and
the initial requirement for steroids.
Review Article Alimentary Tract
AGA 03.qxd 09.9.1 11:34 AM ページ 28

32
細胞間競合は移植された胎児幹細胞/前駆細胞による効率的な正常肝再構築をもたらす河田純男 山形大学消化器病態制御内科学教授
Cell Competition Leads to a High Level of Normal Liver Reconstitution by TransplantedFetal Liver Stem/Progenitor Cells
MICHAEL OERTEL, ANURADHA MENTHENA, MARIANA D. DABEVA, and DAVID A. SHAFRITZMarion Bessin Liver Research Center, Albert Einstein College of Medicine of Yeshiva University, Bronx, New York
Gastroenterology 2006 Feb;130(2): 507-520
胎児幹細胞、肝再構築、細胞間競合、アポトーシス、
MMP
キーワードBackground & Aims: A critical property of stem cells is
their ability to repopulate an organ or tissue under
nonselective conditions. The aims of this study were to
determine whether we could obtain reproducible, high
levels of liver repopulation by transplanted fetal liver
stem/progenitor cells in normal adult liver and the
mechanism by which liver replacement occurred.
Methods: Wild-type (dipeptidyl peptidase IV [DPPIV+])
embryonic day (ED) 14 fetal l iver cells underwent
transplantation into DPPIV- mutant F344 rats to follow the
fate and differentiation of transplanted cells. To determine
the mechanism for repopulation, proliferation and
apoptosis of transplanted and host liver cells were also
followed. Results: Transplanted ED 14 fetal liver cells
proliferated continuously for 6 months, differentiated into
mature hepatocytes, and replaced 23.5% of total liver
mass. The progeny of transplanted cells were
morphologically and functionally indistinguishable from
host hepatocytes and expressed unique liver-specific
genes commensurate with their location in the hepatic
lobule. Repopulation was based on greater proliferative
activity of transplanted cells and reduced apoptosis of
their progeny compared with host hepatocytes, coupled
with increased apoptosis of host hepatocytes immediately
adjacent to transplanted cells. This process, referred to as
cell-cell competition, has been described previously in
Drosophila during wing development. Conclusions: We
show for the first time that cell-cell competition, a
developmental paradigm, can be used to replace
functional organ tissue in an adult mammalian species
under nonselective conditions and may serve as a
strategy for tissue reconstitution in a wide variety of
metabolic and other disorders involving the liver, as well
as other organs.
Review Article Liver, Pancreas, and Biliary tract
研究の背景
天性代謝疾患や重篤な肝障害の治療法として、再生医療
は最も重要なものとして位置付けられている。その中で
肝幹細胞を用いた細胞療法は障害された実質臓器を修復する
手段として大いに期待されてきた。肝は旺盛な再生能を有する
臓器であることから、組織再生における幹細胞の役割について
検討するにはうってつけの臓器であると考えられている。とはい
え、肝幹細胞の同定は難渋しているのが現実である。その理由
は肝幹細胞に特異的なマーカーが見つかっておらず、かつ急性
の肝細胞脱落による再生は幹細胞の分化・増殖によらず、成熟
した肝細胞の増殖によって賄われるからである。
肝障害がより重篤であり成熟肝細胞が分裂できない条件下で
は肝前駆細胞が活性化され再生を担う。この前駆細胞は卵形
細胞(oval cells)と呼ばれ、ヘリング管上皮に由来し、肝細胞
あるいは胆管上皮細胞への分化能を有する 1。しかし、いくつ
かの実験により、単離された卵形細胞を移植してもその再生能
には限りがあることが報告されて、効率的な移植療法に適した
肝幹細胞の単離が必要とされてきた 2。
そこで著者らは肝幹細胞として野生型すなわち正常dipeptidyl
peptidase IV遺伝子を有するF344ラット(DPPIV+)から胎生14日
目の肝細胞を分離した。このDPPIV+肝幹細胞を変異型ラット
(DPPIV-)に移植し、変異型ラット肝における分化・増殖につ
いて検討を行った。この論文は、宿主肝細胞よりも生存に有利
な肝細胞を移植することにより、すなわち細胞間競合(cell-cell
competition)3によって、成体の正常肝を移植細胞で置換する
ことができた最初の報告である。
論文の概要
(1)胎生14日のDPPIV+F344ラット肝由来細胞の正常肝への
移植
胎生14日のDPPIV+ラット肝から細胞を分離し、成体のDPPIV-
ラットへ門脈を介して1.0×107、2.5×107、4.0×107細胞をそれぞ
先
AGA 03.qxd 09.9.1 11:34 AM ページ 32

36
急性C型肝炎に対するペグインターフェロンアルファ-2b療法:持続的ウイルス陰性化に対する治療開始時期の影響熊田博光 国家公務員共済組合連合会虎の門病院副院長
Peginterferon Alfa-2b Therapy in Acute Hepatitis C: Impact of Onset of Therapy onSustained Virologic Response
SANAA M. KAMAL,*,‡,§ AMR E. FOULY,‡ REFAAT R. KAMEL,‡ BRIDGETTE HOCKENJOS,§ AHMED AL TAWIL,‡
KHALIFA E. KHALIFA,‡ QI HE,* MARGARET J. KOZIEL,* KHAIRY M. EL NAGGAR,‡ JENS RASENACK,§ and NEZAM H.AFDHAL**Division of Gastroenterology and Liver Disease Center, Beth Israel Deaconess Medical Center, Harvard Medical School, Boston, MA; ‡Department ofGastroenterology and Liver Diseases, Ain Shams University, Cairo, Egypt; and §Department of Gastroenterology and Hepatology, University of Freiburg,Freiburg, Germany
Gastroenterology 2006 Mar;130(3): 632-638
研究の背景
が国における新規C型肝炎ウイルス(HCV)感染は今や針
刺し事故など極めて限定的で、急性HCV感染に対する
治療法を大規模に検討できる可能性はほとんどない。しかし欧
米ではいまだにinjection-drug userがかなり存在しており、急
性HCV感染を発症する症例も一定程度存在する。HCVの自然
排除率が低いこともあって肝硬変・肝癌への進展予防という観
点から急性肝炎に対するインターフェロン(IFN)治療法の確立
が急務となっている。特にgenotype 1感染の慢性HCV感染者
においては、ペグインターフェロンアルファ(PEG-IFNα)とリバビ
リン併用療法によりHCV完全排除率が飛躍的に上昇したとはい
え、約半分の症例では無効であり1,2、HCV急性感染の段階で
HCVが完全に排除できれば早期治療の意義は高い。しかしな
がら、急性HCV感染に対するIFN療法の有効性の評価には、治
療開始時期が早すぎれば自然治癒の可能性も排除できず、臨
床的有効性の判定が困難であった。さらに、慢性HCV感染のよ
うに、リバビリン併用療法を行う必要があるのかも不明である。
リバビリン併用の意義については、著者らは先の研究 3におい
て、PEG-IFNα単独投与によるウイルス持続陰性化(sustained
virologic response:以下SVR)率は80%と高率であり、リバビ
リンを上乗せしても有効性の上昇は5%にとどまることからPEG-
IFNα単独投与で十分であることを検証している。
本研究は、HCV急性感染例を対象に、PEG-IFNα-2b単独療
法のHCV感染後からの至適投与開始時期の確立を目指した大
規模ランダム化比較試験として実施された。
論文の概要
本研究の対象となる急性HCV感染の診断は、症候の有無に
かかわらず、ALTが正常上限の5~10倍、HCV-RNA陽性化、
HCV抗体陽性とし、他の原因による急性肝炎例は除外された。
わ
C型肝炎ウイルス、急性肝炎、IFN治療、PEG-IFN、
治療開始時期
キーワード
Review Article Liver, Pancreas, and Biliary tract
Background & Aims: Pegylated interferon therapy has not
been adequately evaluated in acute hepatitis C virus
(HCV) infection. This randomized trial assessed the
efficacy, safety, and timing of pegylated interferon alfa-2b
for treatment of acute hepatitis C. Methods: One hundred
seventy-five patients acutely infected with HCV were
screened. Patients whose infection did not spontaneously
resolve by week 8 were randomized to once weekly
peginterferon alfa-2b monotherapy (1.5 μg/kg per week)
started at weeks 8, 12, or 20 for a duration of 12 weeks.
The primary endpoint was undetectable HCV RNA 24
weeks after the end of treatment (sustained virologic
response [SVR]). All patients were followed for 48 weeks
after cessation of therapy. Results: One hundred twenty-
nine subjects started treatment at week 8 (group A, n =
43), week 12 (group B, n =43), or week 20 (group C, n =
43). By using an intent-to-treat analysis, the overall SVR
rate was 87%. The SVR rates were 95%, 92%, and 76%
with treatment onset at 8, 12, and 20 weeks, respectively.
Overall, SVR rates were better for patients infected with
genotypes 2, 3, and 4 than those infected with genotype 1.
Earlier initiation of therapy improved SVR rates for
patients infected with genotype 1 with high viral load.
Peginterferon alfa-2b was well tolerated. Subjects with
SVR maintained undetectable HCV RNA 48 weeks after
therapy. Conclusions: Peginterferon alfa-2b monotherapy
in acute hepatitis C induces high sustained virologic
response rates, prevents chronic evolution, and is well
tolerated. Initiation of treatment at week 8 or 12 results in
higher sustained virologic rates than initiation at week 20.
AGA 03.qxd 09.9.1 11:34 AM ページ 36

40
血中B型肝炎ウイルス量に基づく肝硬変発生リスクの予測井上泰輔 山梨大学医学部第一内科助手
榎本信幸 山梨大学医学部第一内科教授
Predicting Cirrhosis Risk Based on the Level of Circulating Hepatitis B Viral LoadUCHENNA H. ILOEJE,* HWAI-I YANG,‡ JUN SU,* CHIN-LAN JEN,‡ SAN-LIN YOU,‡ CHIEN-JEN CHEN,‡,** and The RiskEvaluation of Viral Load Elevation and Associated Liver Disease/Cancer-In HBV (the REVEAL-HBV) Study Group*Global Epidemiology and Outcomes Research, Pharmaceutical Research Institute, Bristol-Myers Squibb Company, (Wallingford, Connecticut); the ‡GraduateInstitute of Epidemiology, College of Public Health, National Taiwan University; and the **Genomics Research Center, Academia Sinica, Taipei, Taiwan
Gastroenterology 2006 Mar;130(3): 678-686
Review Article Liver, Pancreas, and Biliary tract
B型慢性肝炎、肝硬変、HBV-DNA量、
住民ベースコホート研究
キーワードBackground & Aims: Cirrhosis develops as a result of
hepatic inflammation and subsequent fibrosis in chronic
hepatitis B infection. We report on the relationship
between hepatitis B viremia and progression to cirrhosis
in chronic hepatitis B infection. Methods: This was a
population-based prospective cohort study of 3582
untreated hepatitis B-infected patients established in
Taiwan from 1991 to 1992. Serum samples were tested for
HBV DNA on cohort entry serum samples and the
diagnosis of cirrhosis was by ultrasound. Results: During
a mean follow-up time of 11 years, the 3582 patients
contributed 40,038 person-years of follow-up evaluation
and 365 patients were newly diagnosed with cirrhosis. The
cumulative incidence of cirrhosis increased with the HBV-
DNA level and ranged from 4.5% to 36.2% for patients
with a hepatitis B viral load of less than 300 copies/mL
and 106 copies/mL or more, respectively (P < .001). In a
Cox proportional hazards model adjusting for hepatitis B
e-antigen status and serum alanine transaminase level
among other variables, hepatitis B viral load was the
strongest predictor of progression to cirrhosis relative risk
[95% confidence interval] was 2.5 [1.6 -3.8]; 5.6 [3.7-8.5];
and 6.5 [4.1-10.2] for HBV-DNA levels >–104 – <105; >–105 –
<106; >–106 copies/mL, respectively. Conclusions: These
data show that progression to cirrhosis in hepatitis B-
infected persons is correlated strongly with the level of
circulating virus. The risk for cirrhosis increases
significantly with increasing HBV-DNA levels and is
independent of hepatitis B e-antigen status and serum
alanine transaminase level.
研究の背景
型肝炎ウイルス(hepatitis B virus:HBV)キャリアは全世
界で約3億5千万人、本邦でも150万人存在し、HBV感染
は肝硬変、肝癌、肝不全の重要な危険因子である1。HBVキャ
リアの自然経過は多様性があり、症例により大きく異なる病態
の把握が必要である。大別すると、HBe抗原陽性無症候性キャ
リアから慢性肝炎を経て、HBe抗体陽性無症候性キャリアへと
落ち着く予後良好な経過(約80%)と、長期間肝炎が持続し肝硬
変へと進行し肝癌や肝不全を合併する予後不良な経過(約20%)
とに二分される。HBVキャリアに合併する肝癌はC型肝炎ウイ
ルス(HCV)キャリアとは異なり肝硬変非進行例でも認められる
が、やはりその大多数は肝硬変進行例においての発生である。
このためHBVキャリアにおける肝硬変の発生率や肝硬変発症
への危険因子の検討は、予後の予測や抗ウイルス治療の適応を
考える上で重要と思われる。これまでの報告の多くは専門医療
機関からのものであり、肝硬変発生率は年率0.7~7%と、報告 2-5
により差がある。肝硬変への危険因子としてはHBV-DNA陽性、
HBe抗原陽性、高齢、アラニントランスアミナーゼ(ALT)値上
昇、D型肝炎の合併などが報告 3,6 -8 されているが、PCR
(polymerase chain reaction)法による高感度HBV-DNA量測定
を用いた検討はいまだ少ない。
今回紹介するIloejeらの論文はHBVキャリアにおける肝硬変
発生危険因子として血中HBV-DNA量に注目し、検討したもの
である。医療機関受診者ではなくHBVに対して無治療の地域
住民を対象にしたバイアスの少ない研究であり、高感度PCR法
によるHBV-DNA量の詳細な検討を行った点に特色がある。
論文の概要
本研究は1991~1992年に登録された23,820人中のHBV陽性
者3582人を対象とした住民ベースの前向きコホート研究である
(図1)。2004年6月まで、平均11年間の観察期間中、超音波検
査により肝硬変への進展が確認された例は365例(10%)であっ
B
AGA 03.qxd 09.9.1 11:34 AM ページ 40

Review of Gastroenterology & Clinical Gastroenterology and Hepatology Vol. 1, No. 2 43
原発性胆汁性肝硬変にウルソデオキシコール酸を投与し肝機能が改善すると長期予後は改善する岡上武 京都府立医科大学消化器病態制御学教授
Excellent Long-Term Survival in Patients With Primary Biliary Cirrhosis andBiochemical Response to Ursodeoxycholic Acid
ALBERT PARÉS, LLORENÇ CABALLERÍA, and JUAN RODÉSLiver Unit, Digestive Diseases Institute, Hospital Clínic, IDIBAPS, Barcelona, Spain
Gastroenterology 2006 Mar;130(3): 715-720
原発性胆汁性肝硬変、ウルソデオキシコール酸、生命予後、
血清ビリルビン、血清アルブミン
キーワード
Review Article Liver, Pancreas, and Biliary tract
Background & Aims: Because the efficacy of UDCA on
long-term outcome of primary biliary cirrhosis (PBC) has
not been completely elucidated, we have assessed the
course and survival of patients with PBC treated with
UDCA and compared with the survival predicted by the
Mayo model and the estimated survival of a standardized
population. Methods: (One hundred ninety-two patients
[181 women] with PBC treated with UDCA [15 mg/kg per
day] for 1.5-14 years.) Response to treatment was defined
by an alkaline phosphatase decrease greater than 40% of
baseline values or normal levels after 1 year of treatment.
The predicted survival was obtained by the Mayo model
and the estimated survival was taken from the
standardized matched Spanish population. Results:
Seventeen patients died or fulfilled criteria for liver
transplantation (8.9%). The observed survival was higher
than that predicted by the Mayo model and lower than
that of the control population (P < .001). One hundred
seventeen patients (61%) responded to treatment. The
survival of responders was significantly higher than that
predicted by the Mayo model and similar to that estimated
for the control population (P = .15). By contrast, the
survival of patients without biochemical response was
lower than that estimated for the Spanish population (P <
.001) although higher than that predicted by the Mayo
model. Conclusions: Biochemical response to UDCA after
1 year is associated with a similar survival to the matched
control population, clearly supporting the favorable
effects of this treatment in PBC. The suboptimal survival
of nonresponders identifies the group for further
treatments.
研究の背景
発性胆汁性肝硬変(primary biliary cirrhosis:PBC)は多
くが進行性で、特に黄疸や掻痒のある、いわゆる症候性
PBCは最終的に肝硬変になり、食道静脈瘤破裂や肝不全で死
に至る。しかし、黄疸や掻痒もない、いわゆる無症候性PBCの中
で血清ALT低値例はほとんど進行せず、予後は良好である。
1987年、PBCに対する治療としてウルソデオキシコール酸
(ursodeoxycholic acid:UDCA)のパイロット研究が行われ、
以後いくつかの大規模臨床試験が実施され、UDCAは生化学
的検査の改善 1,2,3のみならず、対照に比して肝組織進展阻止効
果もあることが報告された 4。UDCAは病期(線維化)のあまり
進展していない症例(Scheuer分類やLudwig分類のI期、II期)
に有効で、黄疸のある例はもとよりIII期、IV期例にはそれほど
有効でないことから、UDCA投与は生命予後を含めた長期予
後を本当に改善するのか否か、十分なデータが揃っているとは
いえない 5,6。
本研究は、UDCA投与例を長期フォローし、Mayo risk
modelを用いての予後予測について、年齢、性をマッチさせた
一般対象者の生命予後予測と比較検討したものである。
論文の概要
検討項目
対象は192人のPBC患者で、診断は血液生化学検査と肝組織
所見に基づいて行われており、13例(6.7%)は肝機能異常がご
く軽度の抗ミトコンドリア抗体(AMA)陽性例である。この13例
中10例は I期、3例はII期である。過去にUDCA、コルヒチン、
コルチコステロイド、アザチオプリンその他免疫抑制剤の投与を
受けている症例は除外されている。事前の検査項目は、年齢、
性、腹水や浮腫の有無、血清ビリルビン、血清アルカリホスファ
ターゼ(ALP)、血清アルブミン、プロトロンビン時間(PT)で、最
初の1年間は3ヵ月ごと、以後は6ヵ月ごとに上記項目を検査
している。Mayo Clinic scoreは年齢、血清ビリルビン、血清アル
原
AGA 03.qxd 09.9.1 11:34 AM ページ 43

46
Pdx1遺伝子欠損マウスでは十二指腸主乳頭部の欠損により色素系胆道結石を形成する岡崎和一 関西医科大学内科学第三講座(消化器肝臓内科)主任教授
Loss of the Major Duodenal Papilla Results in Brown Pigment Biliary Stone Formationin Pdx1 Null Mice
AKIHISA FUKUDA,*,‡,§ YOSHIYA KAWAGUCHI,*,¶ KENICHIRO FURUYAMA,* SOTA KODAMA,* TAKESHI KUHARA,*
MASASHI HORIGUCHI,* MASAYUKI KOIZUMI,* KOJI FUJIMOTO,* RYUICHIRO DOI,* CHRISTOPHER V. E. WRIGHT,‖
and TSUTOMU CHIBA‡
*Department of Surgery and Surgical Basic Science, Kyoto University Graduate School of Medicine, Kyoto; ‡Department of Gastroenterology andHepatology, Kyoto University Graduate School of Medicine, Kyoto; §Japan Society for the Promotion of Science, Tokyo; ¶Precursory Research for EmbryonicScience and Technology, Japan Science and Technology Agency, Kawaguchi, Saitama, Japan; and ‖Vanderbilt Developmental Biology Program, Departmentof Cell and Developmental Biology, Vanderbilt University School of Medicine, Nashville, Tennessee
Gastroenterology 2006 Mar;130(3): 855-867
Pdx1、十二指腸主乳頭部、胆石
キーワード
Review Article Liver, Pancreas, and Biliary tract
Background & Aims: Pdx1 plays a pivotal role in pancreas
organogenesis and specification of some types of cells in
the duodenum and antral stomach. However, its
expression is not restricted to pancreas, duodenum, and
antral stomach but is also found in the common bile duct
during embryogenesis. This study aimed to elucidate the
role of Pdx1 in the development of the common bile duct,
major duodenal papilla, and duodenum. Methods:
Expression pattern of pdx1 during embryogenesis and the
morphology of the common bile duct, major duodenal
papilla, and duodenum in pdx1 null mice were analyzed.
Results: The major duodenal papilla, peribiliary glands,
and mucin-producing cells in the common bile duct were
not formed in pdx1 null mice. Pdx1 null mice had shorter
periampullary duodenal vill i than wildtype mice at
postnatal stages associated with reduced cell proliferation
and increased apoptosis of the duodenal epithelial cells.
Loss of the major duodenal papilla allowed duodeno-
biliary reflux and bile infection, resulting in the formation
of brown pigment biliary stones in pdx1 null mice, and
antibiotics treatment significantly reduced the incidence
of biliary stone formation. Conclusions: Pdx1 is required
for proper development of the major duodenal papilla,
peribiliary glands, and mucin-producing cells in the
common bile duct and for maintenance of the
periampullary duodenal epithelial cells during perinatal
period. Bile infection because of loss of the major
duodenal papilla plays a significant role in the formation of
brown pigment biliary stones in pdx1 null mice.
研究の背景
ancreatic duodenal homeobox gene-1(Pdx1)はインスリン、
グルコキナーゼやグルコーストランスポーター2(GLUT2)
など、糖代謝の恒常性に関わる膵転写制御因子のひとつとして
同定され、その遺伝子異常は膵β細胞の機能異常を来し、先
天性糖尿病、若年性4型糖尿病(MODY4)の原因となることが
明らかにされている1,2。さらに、pdx1欠損マウスでは膵外分泌・
内分泌腺の形成不全を来し、高血糖により生後すぐに死亡する
だけでなく、胃においてはセロトニン産生細胞の増加とガストリ
ン産生細胞の欠損を認め、内分泌系細胞の分化増殖にも関わ
ることが示唆されている 3。一方、Pdx1は胃幽門腺、十二指腸
上皮やBrunner腺に少ないながらも発現しており、胎生期には
総胆管にも発現していることが報告されている4。しかしながら、
Pdx1の総胆管やその末端に連続する十二指腸乳頭部の器官形
成における役割や疾患との関連性については不明である。マ
ウスの十二指腸乳頭部には一応、平滑筋の存在は認めるもの
の、ヒトにおける十二指腸乳頭括約筋(Oddi括約筋)ほど発達
したものではなく、運動生理学的にはヒト乳頭括約筋でみられ
るような収縮拡張運動を認めるとの報告はない。
本論文は総胆管、十二指腸主乳頭、十二指腸の形成におけ
るPdx1の役割を明らかにするとともに、十二指腸主乳頭部の欠
損と逆行性胆管感染が胆管結石形成に関して重要であることを
明らかにしたものである。
論文の概要
Pdx1遺伝子欠損マウスの胎生期におけるPdx1の発現様式と
総胆管、十二指腸主乳頭、十二指腸の形態学的解析を経時的
に行った。
生後3日目における野生型マウスとpdx1欠損マウスにおける
十二指腸主乳頭部の実体顕微鏡像の比較をすると、野生型マ
P
AGA 03.qxd 09.9.1 11:34 AM ページ 46

Review of Gastroenterology & Clinical Gastroenterology and Hepatology Vol. 1, No. 2 49
肝細胞癌患者における3種類の腫瘍マーカー同時測定の予後判定における有用性井廻道夫 昭和大学医学部第二内科教授
Prognostic Significance of Simultaneous Measurement of Three Tumor Markers inPatients With Hepatocellular Carcinoma
HIDENORI TOYODA,* TAKASHI KUMADA,* SEIKI KIRIYAMA,* YASUHIRO SONE,* MAKOTO TANIKAWA,*
YASUHIRO HISANAGA,* AKIHIRO YAMAGUCHI,‡ MASATOSHI ISOGAI,‡ YUJI KANEOKA,‡ and JUNJI WASHIZU‡
*Department of Gastroenterology and ‡Department of Surgery, Ogaki Municipal Hospital, Ogaki, Japan
Clin Gastroenterol Hepatol 2006 Jan;4(1): 111-117
肝細胞癌、腫瘍マーカー、予後
キーワード
Review Article Liver, Pancreas, and Biliary tract
Background & Aims: We conducted a prospective study
to evaluate the significance of simultaneous measurement
of 3 currently used tumor markers in the evaluation of
tumor progression and prognosis of patients with
hepatocellular carcinoma (HCC). Methods: Three tumor
markers for HCC, alpha-fetoprotein (AFP), Lens culinaris
agglutinin A-reactive fraction of AFP (AFP-L3), and
desgamma-carboxy prothrombin (DCP), were measured in
the same serum samples obtained from 685 patients at
the time of initial diagnosis of HCC. Positivity for AFP >20
ng/dL, AFP-L3 >10% of total AFP, and/or DCP >40
mAU/mL was determined. In addition, tumor markers were
measured after treatment of HCC. Results: Of the 685
patients, 337 (55.8%) were positive for AFP, 206 (34.1%)
were positive for AFP-L3, and 371 (54.2%) were positive
for DCP. In a comparison of patients positive for only 1
tumor marker, patients positive for AFP-L3 alone had a
greater number of tumors, whereas patients positive for
DCP alone had larger tumors and a higher prevalence of
portal vein invasion. When patients were compared
according to the number of tumor markers present, the
number of markers present clearly reflected the extent of
HCC and patient outcomes. The number of markers
present significantly decreased after treatment.
Conclusions: Tumor markers AFP-L3 and DCP appear to
represent different features of tumor progression in
patients with HCC. The number of tumor markers present
could be useful for the evaluation of tumor progression,
prediction of patient outcome, and treatment efficacy.
研究の背景
細胞癌は特に南アジアおよび東アジアでは最も多い悪性
腫瘍の一つである。日本においては、肝細胞癌は現在3
番目に多い癌死の原因となっている。種々の画像診断法の開
発、感度・特異性の高い腫瘍マーカーの登場は肝細胞癌の検出
のみならず、肝細胞癌の進展の評価、患者の予後の決定にも貢
献している。日本では現在、AFP、AFP-L3分画、DCP(PIVKA-
II)の3種類の腫瘍マーカーが肝細胞癌に対して臨床的に使用
されている。個々の腫瘍マーカーの肝細胞癌の検出・診断、腫
瘍進展の評価、患者の予後の評価に関する有用性は報告され
ているが 1-4、3種類の腫瘍マーカー同時測定による肝細胞癌の
進展、患者予後の評価に対する有用性の検討はこれまでなさ
れていない。
本研究は、肝細胞癌診断時に3種類の腫瘍マーカーを同時
に測定し、腫瘍の進展、患者の予後の予測に対する同時測定
の意義を検討したものである。
肝
図1.肝細胞癌の腫瘍マーカー陽性の患者分布
AGA 03.qxd 09.9.1 11:34 AM ページ 49