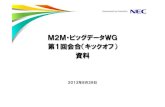PTCAの適応と予後 -...
Transcript of PTCAの適応と予後 -...
-
328 循環制御第17巻第3号(1996)
鑛
PTCAの適応と予後
大島 茂*
はじめに
経皮的冠動脈形成術(Percutaneous Trans・
1uminal Coronary Angioplasty;PTCA)は,器具
の改良や経験の積み重ねのほか,DCA(Directlonal
Coronary Atherectomy),ステントなどのnew de-
viceが併用して使われるようになった結果,成功
率は高くなり,その適応は非常に拡大している1).
しかし,PTCAには急性冠閉塞,再狭窄など問題
点も多いため,長期予後,運動耐用性容能などに
関して,PTCAが薬物治療や冠動脈バイパス術
(Coronary Artery Bypass Graftlng;CABG) より
も有用であると判断された症例に対してのみ施行
されなければならない.
ここでは,①初回冠動脈造影(Coronary
Arteriography;CAG)症例の治療方針,②初回待
機的PTCA症例の成功率,合併症発生率,再狭
窄率など,③PTCA後,結果的にCABGとなっ
た症例の冠動脈病変やCABGとなった原因,④
PTCA後の経過,などからPTCAの適応について検討した.
冠動脈造影後の治療方針
群馬県立循環器病センターでCABGおよび
PTCAが日常的に行われるようになった1990年以
降の初回CAG症例のうち,主要冠動脈に75%以
上の有意狭窄を認めた803例を対象とし,病変枝
数別の治療方針を検討した(Fig.1).なお,左
主幹部病変は50%以上の狭窄を有意とし,二枝
病変に含めた.また,急性心筋梗塞症例は対象か
ら除外した.
その結果,一枝病変例は薬物治療が56.4%
(243/432)ともっとも多く,PTCAは42.5%
(183/432)であった.有意病変であるにも拘わ
らず,半数以上の症例で薬物治療が選択されてい
る.これは,1)灌流域心筋にviabilityがある,
2)灌流域が狭くない,3)発作時あるいは運動
負荷時心電図に有意なST変化がある,4)運動
負荷心筋シンチグラフィ上再分布所見を認める,
5)社会的適応がある,などの条件を満たさない
場合には,有意狭窄であっても通常PTCAを選
択しないことによる.また,一枝病変例で初回
CAGからCABGが選択されたのは5例(1.2%)
のみであった.その内訳は,手術が必要な胸部大
動脈瘤や弁膜症との同時手術が3例,左右幹部と
前下行枝のなす角度が急峻でPTCAではリスク
が高いと考えられた症例が1例,患者のCABG
希望が1例であり,罹患病変はいずれも左前下行
(n=432) (n=238)
團Medial
圏PTGA
口CABG
(n=133)
*群馬県立循環器病センター循環器内科
Fig.1 Management of lst CAG cases
SVD , Single Vessel Disease, DVD . Double Ves-
sel Disease
TVD : Triple Vessel Disease
Presented by Medical*Online
-
枝であった.
二枝病変例はPTCAが42.2%(98/233)と多く,
以下薬物治療が35.8%(83/233),CABGが22.3
%(52/233)であった.CABGが選択された52例
のうち37例(71.2%)は左主幹部病変,あるい
は完全閉塞病変を含む二枝病変例であった.
三枝病変例では,CABGが48.2%(67/139)
ともっとも多く,以下薬物治療31.7%(44/139),
PTCA20.1%(28/139)の順であった.
薬物治療とCABGを比較したECSSGの報告2>
では,三枝病変例,および左前下行枝近位部の有
意狭窄を含む二枝病変例においては,CABGが薬
物治療に比して生命予後は良好である.しかし,
最近は,CABGの良い適応とされるこうした多枝
病変例に対しても積極的にPTCAが行われるよ
うになっている.多枝病変症例に対するPTCA
とCABGを比較したこれまでの成績3”一5)では,
PTCAはCABGに比して再血行再建術の頻度は
高いが,全死亡や心筋梗塞をエンドポイントとし
た分析ではCABGと差はないという結果である.
しかし,現在進行中の試験も多いため,最終的な
結論はまだ出ていない.
PTCAの成績
初回待機的PTCAを施行した627例,721病変
について,標的病変をAHA/ACC Task Forceの
Type A, B, C(Table 1)6)に分け,初期成功率,
『急性冠閉塞の発生率,再狭窄率を検討した,
初期成功率をPTCA施行年代別にみると,単
純病変であるType Aの成功率は各時期とも同様
に高率である.Type B病変の成功率は徐々に高
くなり,Type C病変の成功率は1994年以降で高
くなっている(Fig. 2).このようにType B, C病
変の成功率が高くなっているのは,器具や手技の
進歩,およびステントの使用が関係していると思
われる.また,一時期を通しての初期成功率は
Type Aが97.2%ともっとも高く,以下Type
B87.0%, Type C57.9%の順であり,全体の成
功率は88.3%であった.
急性冠閉塞の発生率はType Aが2.2%ともっ
とも低く,Type Bは4.2%, Type Cは5.1%,
全体では3.6%であった(Fig.3)が,急性冠閉
塞は通常再拡張やステントの挿入により心筋梗塞
に至らずに解決できることが多い,また,初回待
PTCAの適応と予後 329
機的PTCA後に緊急CABGが必要となったのは,
屈曲した(Type B)左前下行枝に急性冠閉塞を
生じた1例(0.16%)のみであった.
Table 1 Characteristics of type A, B, C lesions3)
eType A lesions (minimally eomplex)
Discrete (length 〈10 mm)
Concentric
Readily accessible
Nonangulated segment (〈450)
Smooth contour
Little or no calcification
Less than totally occlllsive
Not os/tial in location
No major side branch involvement
Absence of thrornbus
e Type B lesions (moderately complex)
Tubular(length 10 to 20 mm)
Eccentric
Moderate tortuosity Qf proximal segment
Moderately angulated segment(>450, 〈90e)
Irregular contour
Moderate or heavy calcification
Total occlusions 〈3 mo old
Ostial in location
Bi/furcation lesions req/uiring dou/ble guide wires
Some thrombus present
eType C lesions (severely complex)
’Diffuse (length >2 crn)
Excessive tortuosity of proximal segrnent
Ex/tremely angulated segments >900
Total occluisions 〉 3 mo old and/or bridging collater-
als Inability to protect major side branches
Degenerated vein grafs with friable lesions
N’X1
圏Typo A(n=250)
置 Typo B
(n=415)
nType C(n= 57)
Fig. 2 lnitial success rates of PTCA in lesion types
Presented by Medical*Online
-
330 循環制御第17巻第3号(1996>
次に,PTCAの際に得られた内心拡大の50%
以上の減少を再狭窄とした場合,PTCA施行後3
~6カ月における再狭窄率はType Aが33.5回
目もっとも低く,Type B, Type Cの再狭窄率は
それぞれ46.1%,45%とほぼ同様の割合であっ
た(Fig.4).
PTCA後のCABG
CABG症例のうち, PTCAの施行歴がある57例
について検討した結果,CABGとなった原因とし
てはPTCA不成功(38.6%),繰り返す再狭窄
(33.3%)が多く,以下,PTCA施行病変以外
の病変の進行や新たな有意病変の出現(10.5%),
再狭窄に加えて新たな病変の出現(8.8%),心
筋梗塞急性期にPTCAを施行した症例の慢性期
造影結果によるCABG(8.8%)などであった(Fig.
5).これをPTCA施行時期でみると,1992年以
前はPTCA不成功のためにCABGが選択される
場合が多く62.1%(18/29)を占めていたが,
1993年以降では再狭窄の結果CABGとなる症例
が48.1%(13/27)と多かった.PTCA不成功後
のCABGが減少しているのは, PTCAの成功率
が高くなっているためばかりでなく,難易度の高
い症例には最初からCABGを選択することが多
くなっていることも関係していると思われる.
PTCA不成功後にCABGとなった23症例の病
変枝話は一枝病変8.7%,二枝病変52.2%,三
枝病変39.1%であった.多枝病変例では一枝に
完全ないし亜完全閉塞病変を有し,側副血行を供
給する冠動脈にも有意狭窄のある症例も多い.そ
の場合,側副血行の供給を受ける高度狭窄側の冠
動脈から拡張せざるを得ないため,PTCA不成功
からCABGを選択される症例が多くなった(71.4
%)と思われる.したがって,閉塞期間が長い完
全ないし亜完全閉塞を含む多枝病変例では,
CABGを第一選択にすべきであると思われる.
再狭窄が原因でCABGとなった症例のうち,
89.5%で左前下行枝が標的血管に含まれていた.
また,CABGまでのPTCA施行回数は1回22.7%,
2回50%,3回22.7%,4回4.5%と3回以内
の再狭窄でCABGが選択される症例が多かった.
前述のごとく,Type B, C病変では成功率が低く,
再狭窄率も高いので,二枝病変でも左前下行枝に
Type C病変を有する症例では早期にCABGを考
Type A Type B Type C Total(n=268) (n=433) (n=59) (n=760)
Fig. 3 Rates of acute vessel closure during or after
PTCA in lesion types
%50c
45
40E
35k
30
25k
20
15E
10E
o
100%
75X
50%
25X
O瓢
Type A Type B Type C (n=206) (n=269) (n=20)
Fig.4 Restenosis rates in lesion types
目AMl
wt REST +PROGRESSION
口PROGRESS!ON
-RESTENOSIS
tw PTCA UNSUCCESS
N’X2 93.v TOTAL
Fig. 5 Reasons for CABG after PTCA
AMI : Acute Myocardial lnfarction
REST. Restenosis
Presented by Medical*Online
-
PTCAの適応と予後 331
慮することが必要と思われる.
PTCA施行部以外に生じた新たな狭窄病変の進
行,あるいは新たな狭窄病変の進行+再狭窄から
CABGが選択された10症例のうち6例で左主幹部
病変の進行が関係していた.左主幹部の有意狭窄
ではほとんどの場合CABGが選択されることも,
比率を高くしている原因の一つと思われるが,そ
の進行にPTCAの物理的刺激が影響している可
能性も否定できない.したがって,左四幹部,特
にその入口部に多少でも狭窄病変を認める症例で
は,左主幹部病変が進行する可能性も考慮して左
前下行枝あるいは回旋枝へのPTCAを施行する
ことが必要である.
PTCA後の経過
初回PTCA成功後3~4カ月の確認造影で再
狭窄を認めた215例について,その後の治療経過
をFig.6に示した.再狭窄215下中148例(68.9%)
に2nd PTCAが施行され, CABGは5例(2.3%),
薬物治療は62例(28.8%)であった(Fig.6二2nd).
再狭窄を認めながらも28.8%で薬物治療が選択
されたのは,患者が再PTCAを希望しない場合
もあるが,多くの症例では,造影上は再狭窄に含
まれるが,PTCA施行前よりも狭窄が軽度で,狭
心症状や心筋虚血所見が消失したことが原因であ
った.2nd PTCAを施行した148例中,33例(22.3
%〉 に3rd PTCA,11例 (7.4%) にCABGが:選
択され,104例(70.3%)では薬物治療が選択さ
れた.なお,2nd PTCAの再狭窄率は45.5%で,
初回PTCAの40.8%に比して高率であった.また,
初回再狭窄症例のうち3.3%(7/215)に4th
PTCA,0.5%(1/215)に5th PTCAが施行さ
れた.5th PTCAを施行した79歳の男性は,
CABG後の心機能低下例(左室駆出率;28%)で,
5th PTCA後にも再狭窄を認めたため再CABG
を施行したが,術後早期に死亡した.
PTCAの適応
初回CAG後選択された治療は一枝病変では薬
物治療,二枝病変ではPTCA,三枝病変では
CABGが多かった.一・枝病変は通常PTCAの良
い適応であるが,PTCAの適応決定に際しては,
冠動脈病変の形態学的特徴のみでなく,心筋虚血
の客観的証拠がある,標的冠動脈の灌流域が狭く
ない,社会的適応がある,などの条件を満たして
いることも必要である.また,一枝病変でも左前
下行枝入口部の高度屈曲病変など,重大な合併症
を生じる可能性がある病変では最初からCABG
を選択する場合もある.
Objective Evidence of Myocardial lschemia
SVD Type A,B,(C)
DVD Type A,B
TVD Type A
DVD Type C( 十)
il TVD Type A(一)
CASES250
200
150
100
50
2nd 3rd 4th
画MEDICAL
口CABG一 PTCA
Myocardial lschemia
5th
Fig. 6 Clinical course of patients with restenosis
after successful lst PTCA
2nd, 3rd, 4th, 5th’number of PTCA and
other management after restenosis
[(
PTCA orSTENT
(+)
pt[¢&]
Myocardial lschemia
(一) (+)・
Medical
Fig.7 PTCA strategy
Presented by Medical*Online
-
.332 循環制御第17巻第3号(1996)
多枝病変例ではCABGを選択する割合が高く
なるが,病変が複雑でない場合には,PTCAが
CABGよりも侵襲が少ないことを考慮し,まず
PTCAを施行することも多い.しかし,多枝病.変
例で難易度の高い病変を含む場合には,PTCAは
成功率が低く,合併症や再狭窄の頻度が高くなる
ので,CABGを第一選択としてる.
以上の結果から,われわれの施設における虚血
性心疾患の治療方針をFig.7に示した.
お わ り に
虚血性心疾患治療の目標は長期的には生命予後
の改善,短期的には運動耐容能の改善である.こ
れはPTCAの場合でも同様であり,狭窄病変の
拡張はそれ自体が目標ではなく,目標に至るため
の手段である.したがって,PTCAの施行するか
否かを検討する場合には,冠動脈病変の性状だけ
でなく,心機能,全身状態.患者の活動度.なども
加味して考える必要がある.また,PTCA,
CABGのいずれかを選択する場合,種々の面から
両者を比較する必要があり,患者側の条件だけで
なく,施設側の条件として心臓外科チームの成績
を考慮することも必要である。
文献
1) Myler RK, Stertzer SH : Coronary and Peripheral
angioplasty: Historic Perspective. ln Topol, EJ (ed) :
Textbook of interventional cardiology. ed 2. Saunders,
1994, p. 171-185
2) Vaunauskas E, and the European:Coronary Surgery
Study Group: Survival, myocardial infarction, and em-
p【oy血ent status in a prospective randomized study of
coronary bypass surgery. Circulation 72 (suppl V) :
90一, 1985
3) King SB III, Lembo NJ, Hall EC, for the EAST investi-
gators: The Emory Angioplasty vs Surgery Trial (EAST) : analysis of baseline characteristics. A」n J
Cardiol 75:42-59, 1995
4 ) BARI investigators: Protocol for the bypass angioplas-
ty revascularization investigation. Circulation M(suppl
V):V-1-V-27, 1993
5) Hamptokn JR, Henderson RA, Julian DG, for the RITA
trial partieipants: Coronary angioplasty versus corQn-
ary artery bypass surgery: the Randomized lnterven-
tion Treatment of Angina (RITA) trial. Lancet 341 :
573-580, 1993
6) Ryan TJ, Bauman/ WB, Kennedy W, et al : Guidelines
for Percutaneous Transluminal Coronary Angioplasty.
A Report of the American Heart Association/American
College of Cardiology Task Force on Assessment of Di-
agnostic and The rapeutic Cardiovascular Procedures
(Committee on Percutan eous Translurninal Coronary
An gioplasty) . J Am Coll Cardiol 12 : 529 一545, 19zz
Presented by Medical*Online
03280329033003310332