OLIVE ]ÝY'[f[f S`ÅX10ê0Ý0¸0È0ê 交換経済における貨幣
Transcript of OLIVE ]ÝY'[f[f S`ÅX10ê0Ý0¸0È0ê 交換経済における貨幣
![Page 1: OLIVE ]ÝY'[f[f S`ÅX10ê0Ý0¸0È0ê 交換経済における貨幣](https://reader031.fdocument.pub/reader031/viewer/2022013009/61ce3b3c47e46a36c17b92d4/html5/thumbnails/1.jpg)
交換経済における貨幣
一一J.ニーハシズの貸幣理論を中心にー一一
宮 回 旦朗
l はじめに
かつて, われわれは R・M ・スター並びに N・R・ギブソンの考察を通じ
て,交換経済における取引貨幣の保有動機を分析した。そこで得た結論を要約
すると次のよろである。先ず,物々交換の成立に必要な条件は,価格との一致
性,単調超過需要減少,および超過需要の完全充足の三つである。とのラちる
単調超過需要減少の条件をはずし取引者の欲求に関係なく授受されるような財
を認めるならば,クラワァーのいうすべての財が貨幣となる物々交換が実現す
るか,あるいはある特定の財に裁定機能を与える貨幣交換経済が実現すること
になる。また,交換が円滑に行われるためには異時点閣の橋渡しをなす投機者
の介在を必要とする。そこで,もし第一の条件すなわち価格との一致性をはず
し信用を導入するならば,投機者を含む物々交換が実現する。他方,もし貨幣を
導入しそれに投機者の役割を託すならば,異時点間の橋渡しを行う貨幣交換経
済が実現することになる。したがって,物々交換経済と貨幣交換経済との根本
的差異は,上の三つの条件のラち価格との一致性と単調超過需要減少の二条件
をどのような形ではずすかという点に求められる。次に,その考察の過程で特
(1) 拙稿「貨幣交換経済に関する覚書」香川大学経済論議第54巻第4号昭和56年3月 Starr,R胎 M.The Structure of Exchange in Barter and Monetary Eco・
nomies, Q, .1, E. Vol. .86, no. 2, May 1972; Gibson, N. R., The Case 101 International Money, 1979.
( 2 ) Clower, P., A Reconsideration of the Microfoundations of Monetary Theory, Western Economic .1ournal, V. 8, Dec. 1957
(3) 取引を行う二人の取引者が自己の提供する財に対し直接相手方からそれと等価の財を受取り決済することを意味している。
OLIVE 香川大学学術情報リポジトリ
![Page 2: OLIVE ]ÝY'[f[f S`ÅX10ê0Ý0¸0È0ê 交換経済における貨幣](https://reader031.fdocument.pub/reader031/viewer/2022013009/61ce3b3c47e46a36c17b92d4/html5/thumbnails/2.jpg)
-28ー 第55巻第1号 28
に見落してならなL、点は.,第一にクラヲァーのいうすべての財が貨幣となる物
々交換であろうと特定の財を貨幣とする貨幣交換経済であろうと各取引者は交
換の初めに予め準備として交換を仲介する財(貨幣〉を保有し亡いなければなら
ないこと,すなわち各期の取引の出発点と終了点に一定額の貨幣ストックの保
有な必要とすることであり,第二に月曜日に取引の契約がなされ残るその過に
その履行が生じるとするヒックス流の設定を考え火曜日以降に生起する受取と
支払の異時点聞の橋渡しを円滑に行うとすれば,期首に存在する貨幣ストック
だけでなくその時点までの貨幣の受取と支払の状況が問題となってくること μで
ある。そして,とのうち後者は,期首に存在する貨幣ストック M と,その週の
ある日ちょうど満期となる支払超過およびその日までに満期となる支払超過のh h
合計額L:(m,-l,)並びに期末における貨幣ストック保有 M とが, :E (m,-l,)
十M-M=Qで相互に関係しかっ期首と期末の貨幣ストックが与えられるとき
は 2ムと:Em,のいずれか一方のみで表わしうることになる。かくして,効用
函数は貨幣ストック M 以外に貨幣のフロー Jを導入し
U=U(.x1,一, .xn, M, 1, pl, , pn) (1)
として分析に使用することになる。
この(1)式は,かつて国際通貨の需要を計測するに際し規定した特殊な形
の効用函数 U=U(A,B, M/P,π) と類似のものである。〉ただし, この場合,
A,sは二財,Pは一般物価水準, πは取引に関する主体の安全性である。この
ときの安全性 πは,次のように規定された。いま,火曜日より始まる取引契約h
の履行期閣のある時点での支払超過合計額:E(mτーめを純支払必要額と呼び,
その最高額を確率変数 hで表わせば, ζ のhが期首の貨幣保有額 M を越える
とき,モの取引者は,契約の履行を行えず,支払不能に陥入ることになる。ゆ
えに,lr=P(k:;;'M)は,その支払に対する安全性を現わす指標となるといえ
(4) 拙稿上掲論文で,(1')式に相当するものであるが,貨幣フローlを m と記している。とれは記号の遠いにすぎない。
(5) 拙稿 「国隆通貨の需要とその計測」金融学会報告 No"44. 1977年 9月 およびFujita, M. and N. Miyata, The Demand foI' International Cunencies, Kobe Economic & Bu.sine.s.s Review, 24th Annual Report, 1978"
OLIVE 香川大学学術情報リポジトリ
![Page 3: OLIVE ]ÝY'[f[f S`ÅX10ê0Ý0¸0È0ê 交換経済における貨幣](https://reader031.fdocument.pub/reader031/viewer/2022013009/61ce3b3c47e46a36c17b92d4/html5/thumbnails/3.jpg)
29 交換経済における貨幣 -29.-
る。この πは,期首の M,日々の支払いと受取りの差額 m,ーム,および受取・
支払の時差,によって変動すると考えることができfる。すなわち,M の額が小
さいなら当該期聞に取引者の応じうる支払要求額も小さくなり,またかりに M
が一定であるとしても,日々の収支差額が大となれば,あるいは日々の支払に
対し受取りの時点の遅れが大があれば,kの値が大となりそれだけ支払不能と
なる危険は高められてくる。ところで,月曜日の取引契約の締結は,火曜日以
降の残るその週の各時点の支払いと受取りに関する期待にもとずいて行われ℃
いる。そこで,日々の収支差額m,--/, を二分して,取引者の期待並びに計画が
反映される部分と統計的に独立に生起する部分とにわけ℃考える。前者につい
ては, 前日の収支差額の傾向が γの率で反映するものと仮定する。他方,後
者は収支差額の期待値iとその分散引にわける。いま, σuを一定とすれば,そ
の週の全体問る支出m(=か)の減少が (1=const とする)その期聞に独
立に生起する収支差額の赤字期待を減じ安全性 πに影響を与えると考えること
がでさるから,月曜日に取引契約を締結するに際し経済主体の動かし得るもの
は,その週の間に履行する総額mであるとみることができる。 かくして,こ
れら諸々の仮定の下に安全性を π=π(MjP,σ川 γ,mjP) と規定する。これを
効用函数 U=U(A,B, MjP,π〉に代入すると ,U=U(A, B, MjP, mjP)
となり,上記の(1)式と類似のものを得る。ただし,ここでは, (1)式の f
に代って mを効用菌数に導入している。なお.σu,γは一定である。
以上は,かつてわれわれが用いた効用函数並びに取引貨幣に関する分析の概
要である。そとで,本稿では,これらと対比することによって,ニーハンズの
「貨幣論」第 1$"-'第5章における取引貨幣の取扱いに関してその差異を考察
してみよろと思う。なお,ニーハシズの「貨幣論」第6主主以降は,別の機会に
(6) 予算制約式からして M=givenのとき経済主体の意志により動かしうるものは,M,m, 1のうちこつである。期末スト yクMを決定すると,残るものは,mかJの一方l
のみとなる。ここではmについて廷志決定を行うものとして取扱っている。(7) Niehans, J., The Theory 0/ Money, 1978 (2 nd printing) pp. 1-98.
OLIVE 香川大学学術情報リポジトリ
![Page 4: OLIVE ]ÝY'[f[f S`ÅX10ê0Ý0¸0È0ê 交換経済における貨幣](https://reader031.fdocument.pub/reader031/viewer/2022013009/61ce3b3c47e46a36c17b92d4/html5/thumbnails/4.jpg)
-30ー 第55巻第 1号 30
改めて考察する予定である。
2 ニーハンズの基本モデ/レ
ニーハンズは,新古典派の伝統に立脚しながら一般均衡のプレーム・ワーク
の中で貨幣の保有を取扱い,取引貨幣を含む貨幣交換経済を分析することを試
みる。先ず,貨幣は,直接にはその効用を持たず,それによって購入される財
の効用を反映する形で間接的にのみ効用を持つものとされる。したがって,効
用函数は,上記の(1)式に代って
u = U (.xi, "",吟,…,.xf.) = U (x) (2)
となる。ただし, ,x~孟 O は,第 t 財の第 t 自における消費である (i= 1 ,"",q;
t= 1,…, h)。そして,それは通常の微分可能性と限界代替率逓減および正の
限界効用をもつものと仮定される。各個人は,一定の財の賦存畳ベクトノレ x=(.Xl,…, f;,…,iZ)を持ち,交換を通じ.cそれを一定の消費ベクトノレに交換す
る。もし消費ベクトノレの価値が賦存畳ベクトノレの価値を越えるならば,現金残
高の引出が行われる。したがって,予算制約式は,
q
z ρ: (.x~-.xD = Mt-Mt+l (t= 1,…,h) (3)
となる。いま,第h臼までの財の販売と購入から生じる貨幣の受取と支払をか
りに第 1図のようであるとする。第 t日までの受取総額を R とし,支払総額を
Eとすれば,受取総額と支払総額の差額は, 累積黒字 S=R-E孟Oまたは累
積赤字 D=E-R孟 Oとして示される。そして,この第 1図では,最終日である
第 h日の当期間全体の総受取額は総支払額を越え,したがって期首の現金残高
Moをこえる現金残高 Mhが保有されてくると仮定されている。しかしながら,
期首全体としては黒字であるとしても,当期間の初めの部分で第 1図にあるよ
うに赤字が累積する場合には,もし期首に現金残高 Moを持たないものとすれ
ば,取引を開始してまもなく支払不能の状態に陥入る。また,支払不能は,期
首の Moが最大の累積赤字D悦帥より小さいとまにも生じてくる。それは, 期
首の Moとその日までの貨幣受取総額Rとの合計額 R十 Moがその日までの貨
OLIVE 香川大学学術情報リポジトリ
![Page 5: OLIVE ]ÝY'[f[f S`ÅX10ê0Ý0¸0È0ê 交換経済における貨幣](https://reader031.fdocument.pub/reader031/viewer/2022013009/61ce3b3c47e46a36c17b92d4/html5/thumbnails/5.jpg)
31 交換経済における貨幣 -31-
Dmax
第 1 図
幣支払総額Eを越えるからであ
る。したがって,少くとも R十
Mo孟Eでなければならない。こ
のように,貨幣交換過程が円滑
に遂行されるためには,ある額
の貨幣を期首に保有しているこ
とが必要である。そして,ニ lー
ハンズ?によれば,その大さは,
少くとも五つの要因に依存して
いる。すなわち, (i)受取りと
支払いの不一致, Cii)金融上の発展の程度,(iii)一般物価水準, (iv)商品フロ lー
畳, (v)経済統合の程度である。このうち,最初の受取りと支払いの不一致は,
いわゆる財フローの時間的パターンを意味し,その社会の支払習慣にある程度
依布するものとみることができる。他方,第 2の金融上の発展は,パプター取引
から出発し貨幣化の進むにつれて貨幣に対する需要が増大するこi とを意味し,
また最後の経済競合の程度は, ø'~えばこつの経済主体の市場活動が統合される
場合のように,各個別の取引は以前と同じであるとし℃も統合した主体の合計
された累積赤字はより小さくなるという事実を意味しており,ともに期首に貨
幣保有を必要とする要因であるといえる。なお,一般物価水準並びに取引され
る商品量の増大に関わる第 3と第 4の要因が,取引を円滑に遂行するために必
要な貨幣の保有を増加させることは,改めて述べる必要もないであろう。
かくして, (3)式の予算制約式において,期首と期末の貨幣保有高は,少く
とも正でなければならず,しかも当期間全体に亘ってそれをゼロか正に維持し
ていなければならないということになる。すなわち,Mt孟o(t= 1 ,…, h)で
ある。いま,単純化のために,期首と期末の貨幣残高を外生的に与えられたも
のと考え,Ml=Ml, Mh+l=Mh+lとする。そして,これらの条件の下で, (2)
式の効用函数を極大化するための非線型プログラミシグ問題を設ける。そし
-C,。ラグランジュ方程式
OLIVE 香川大学学術情報リポジトリ
![Page 6: OLIVE ]ÝY'[f[f S`ÅX10ê0Ý0¸0È0ê 交換経済における貨幣](https://reader031.fdocument.pub/reader031/viewer/2022013009/61ce3b3c47e46a36c17b92d4/html5/thumbnails/6.jpg)
-32ー 第55巻 第 1号 32
L=川 ι ,.xZ)一台t[会ld(山 n十 Mt+1-'MtJ (4)
を x~ および貨幣ストックにつき偏微分し, クーン・タッカーの条件
(au)8U/制一一一九tP~ )x;= 0 ,一一----:::;:At,ô.x~ ノ ρ;
,x~孟;0 (5)
および
(入t'-'At山 l)M戸 0,At-At-1三五0,Mt孟o(t=丸山・,h) (6)
を得る。 ラグランジュ乗数h は, (5)式から, 第 t日における所得の限界効
用,いはほ効用のタームで測った貨幣の限界購買力である。そこで, ニーハン
スーは, この h を貨幣の限界フロー効用と名付ける。 (5)式では,財の消費が
正(x;>0)のとき財の加重された限界効用はこの貨幣の限界フロー効用と等
しくなり, また財の消費がゼロ (.x;=0)のとき財の加重された限界効用は貨幣
の限界フロー効用より小さくなることを表している。他方, (6)式では貨幣ス
トックが正 (Mt>0)のとき第 t日と第 t-l日の二時点聞の貨幣の限界フロ
ー効用の差。s一λト 1)はゼロとなり,貨幣ストックがゼロ (Mt= 0)のときそ
の二時点閣の貨幣の限界フロー効用の差は負となることを表している。 この
(6)式の二時点間貨幣の限界フロー効用の差(入t'-At-1)は,消費を差し控え翌
日にのぼすことを意味し,いわば貨幣ストック lドノレの限界効用であるといえ
る。そとで, ニーハンズは, この (-t,.-'¥t-1) を貨幣の限界ストック効用と名
付ける。ゆえに,貨幣ストックの正の保有'(Mt>O)は, この限界ストック効
用が限界コストに等しくなるように決定されてくることになる。 そし"c, この
At'-At-1= 0となるケースは,貨幣の限界ストック効用がゼロの限界コストに
等しくなること,換言すれば貨幣が飽和状態に達するまで保有されたことを表
わしている。
( 8) Auow, K. J. and A. C" Enthoven, Quasiconcave Programming, Econometrica, Vol. 29, no.4, Oct. 1961..
(9) 貨幣ストックの限界効用は,今日の 1ドノレの支出からの利得から,昨日支出を控差えたための犠性を51いた効用上の純利得であるo I¥.tくI¥.t_1は,もはや純利得がなく損となるほど貨幣を保有したことを意味する。
OLIVE 香川大学学術情報リポジトリ
![Page 7: OLIVE ]ÝY'[f[f S`ÅX10ê0Ý0¸0È0ê 交換経済における貨幣](https://reader031.fdocument.pub/reader031/viewer/2022013009/61ce3b3c47e46a36c17b92d4/html5/thumbnails/7.jpg)
33 交換経済における貨幣 -33ー
よ記の体系では期首と期末の貨幣ストックは,外生的に与えられていた。そ乙
で,この仮定をはずし,それに代って無限定常運動(infinitestationary motion)
の概念を導入する。ニーハンズによれば,これは定常状態を作り出すためのも
のである。いま,h日からなる H年を考え,各年の同じ日に同じ賦存量£と趣
好が生起するものと仮定する。すなわち,
.X'CT -1)九十t=X;,M(T-l)h+t=Mt (T= 1, ...., H) (7)
である。にの場合,各年の同じ日には同じ結果が生じてくることになる。モと
で,Hを無限にとり無限の期間に亘り効用を極大にする個人を考える。このと
きその個人の行動は,無限定常運動の仮定からして,ある任意の 1年聞の行動
を無限に繰返すことになり, (2)式の効用函数を極大としてそれを無限に続け
るとみることができる。そこで,以前の期首並びに期末の貨幣ストック所与の
仮定に代えて ,Ml=Mh+lと置き (2)式の効用函数を極大とする。 (5)(6)
式の上に (8)式が加わり,
(BU4 8 U /批;-ÀtP~)← 0 ,一一.一孟川注 O
ax; ρ;
(入8一入トl)M戸 0,At'-'At-l孟 0,Mt孟 O(tロ 2,…,h)
(5)
(6)
(入1一入h)Mt=0, Al'-'X."孟0,Ml孟o (8)
を得る。 (6)式と (8)式から,貨幣の限界ストック効用は,すべての tにつ(11)
いて限界コスト(ゼロ〉に等しくなることが導出される。すなわち, 入t=A.t-l
(t= 1,…, h)である。第2図は,一種類の財のみからなる経済で期間2自に宣
るケースを例にとって描いたものである。同じ財について,その第 1日の消費
量を横軸に,その第 2日の消費量を縦軸にとる。賦存量 fはP点で示されてい
る。予算制約は右下りの直線で儲かれ,その勾配はーρl/PZである。貨幣スト
(10) 一般均衡理論においては,均衡成立時に貨幣を保有する動機が余り見当らない。す
なわち例えば貨幣保有を摩擦の産物と把える限りそラなる。そこで,ユーハシズは,この無限定常運動の概念の導入によって,新古典派の貨幣保有の考えを拡張し一般均衡理論に結びつけようと考える。
(11) 例えばh=3として考えてみると (6)式と (8)式が両立するためには l=λ2=
λ3を必要とすることが容易にわかろう。
OLIVE 香川大学学術情報リポジトリ
![Page 8: OLIVE ]ÝY'[f[f S`ÅX10ê0Ý0¸0È0ê 交換経済における貨幣](https://reader031.fdocument.pub/reader031/viewer/2022013009/61ce3b3c47e46a36c17b92d4/html5/thumbnails/8.jpg)
- 34ー 第55巻第1号 34
ックの期首保有額と期末の保有額は同額vであるから,その予算線はP点を通る
X2
Xl~一一~一一~Mj/Pj
第 2 図
Xl
ことになる。 (5)式と入1=I¥2の関係
から (BU/BX1)/ (BU /Jxz) =ρdρ2が
得られかつ Ml=M2よりしてパ 2)
式を表わす無差別曲線は,極値にお
いてこの予算制約線に接し,かっそ
の接点をR点に位置しなければなら
ない。斜線で固まれた領域は,その
財の賦存量と貨幣ス「ックの保有額
からして第 1日と第 2日に購入可能
な範囲を示したものである。すなわ
ち, {11Jえば第 1日に購入しラる限度は,ふと保有貨幣ストックの実質額Ml/ρl
の合計量で表わされてくる。 したがって,接点 Rは, この領域の右上端にあ
ることになる。とのR点では貨幣ストックの限界効用はゼロとなり飽和状態に
到達している。かくして,ニーハシズは,無限定常運動において貨幣の限界コ
スト(取引コスト〉がゼロであるような場合には,貨幣が存在しながらあたか
も貨幣がないときと同じように,p点を通る予算線上において商品取引を行い
最大満足に達すると結論する:ここに得られた矧の各時点の消費量は,それ
をまとめると,以前の第 1図におけるような財の販売と購入したがって貨幣の
受取りと支払いの時間的パターシを描くことになる。かくして,上記(5)(6)
(8)の体系は,第 i図で暗黙に所与とされていた Rおよび Eの両曲線を内生
的に決定したものであるとみることがでまる。
以上は,エーハシズ・モデlレの基本的部分の骨子である。この基本的モデlレ
は,容易に時間選好や現金残高利子並びにインフレ率を考慮した形に書き改め
ることができる。ニーハンズによれば,先ず時間選好による修正は次のように
なされる。時間選好を考慮するとさ,上記の (5)式の限界効用 JU/B.x;は,
(12) もし M,占<;,M2であるなら, 予算制約線は P点を通らず (M,-M2)/ρ1だけ左右
に平行移動してくることになる。
OLIVE 香川大学学術情報リポジトリ
![Page 9: OLIVE ]ÝY'[f[f S`ÅX10ê0Ý0¸0È0ê 交換経済における貨幣](https://reader031.fdocument.pub/reader031/viewer/2022013009/61ce3b3c47e46a36c17b92d4/html5/thumbnails/9.jpg)
35 交換経済における貨幣 -35 -
すでにそれを含んだものとして解釈される。富保有者の心理的なコストである
時間選好率を,日当り Oであるとすれば,割引かれない限界効用 aV/ax; と割
引かれた限界効用 âU/âx~ との聞にâV/âx;=( 1 +めゆU/iJ,x;の関係があり,ま
た貨幣の限界フロー効用の当1151かれないもの仰と割百|かれたもの~の聞にも
灼=(1十8Y-tの関係があるととになる。そこで, ( 5)式と (6)式にこれらの
関係を代入し整理すると,
。V~' 一一一一主主主μtax~
(5 ')
(1十8)些 71g, llQ O(6つ
を得る。 (6')式の左辺 (1+8)(μs一μト 1)/μtは比率(%)で表わした割目|かれな
い貨幣の限界ストック効用を表わし,他方右辺 0は貨幣の限界コストを表わし
ている。そして, 割51かれない貨幣の限界ストック効用(%)は,貨幣ストッ
クM,が正のとき 8に等しく ,Mtがゼロのとき 0より小となる。そのうえ,貨
幣ストック Mtは,少くとも一度はゼロにならなければならない。もし,すべ
ての時点 (t=l,., h)で正であれば,貨幣の限界フロー効用が常に上昇する
こととなり,無限定常運動の仮定と矛盾することになるからである。さて,次
にρ率の複利で現金残高から収入を得る場合を考えると次のように修正されて
くる。このケースでは,各人の支出可能額がそれに応じて増大し,予算制約式q
をも言 ρ~(x;- ,xD = c1 +ρ)M,-Mt+,としてくる。モこで、, (6)式は CC1+ρ)I¥,t-,
I¥,t-IJMt= 0となる。同時に時間選好率。をも考慮に入れるとすれば, (6つ式は
(1 +(})正子~:s;;,.(}ーρ Mt孟 O (6つ
で表わされてくる。かくして,利子率 pは,時間選好の影響を椙殺するものと
して導入されてくることにな2i最後に,日々 π%の率で・物価水準が上昇する
インフレの場合は次のようになる。このとま,各個人は,各年の実質現金残高
(13) この (6")式から明かであるが,ニーハシズでは利子率は,投機,不確実性,取引コストなどのない場合でも,また貨幣が唯一の資産である経済でも,現金残高への需要に関わっ℃くる。
OLIVE 香川大学学術情報リポジトリ
![Page 10: OLIVE ]ÝY'[f[f S`ÅX10ê0Ý0¸0È0ê 交換経済における貨幣](https://reader031.fdocument.pub/reader031/viewer/2022013009/61ce3b3c47e46a36c17b92d4/html5/thumbnails/10.jpg)
-.36ー 第55巻 第 1号 36
を一定水準に維持する (Mt+k=(1+ir)"Mt)ために, インフレ率に相応した支
出の減少を行わねばならなくなる。 そこで, インフ νは,各人にとって一種の
コストとみなされる。予算制約式はあ(1+π)(.Xt -Xt) = ( 1十p)Mt._.Mt+!,(t
1,・・" h)となる。ただし,単純化のため財は一種類とし,その価格あでー
般物価を代表する。この場合の貨幣ストックに関わるクーン・タツカーの条件
式は
(1十 O)-~す己記 1 + 0)一士号 (6"')
である。時間選好率と利子収入がない (0=ρ=0) とき (6川)式は (1十π〉
(μ8一向ー1)/μt~五π となり,また利子収入を考慮するとき(1 +n) (J"t一向-1)/J"tS
π一ρとなる。ゆえに, インフレ率 πは,(6')式や (6")式における時間選好率:
。と同じように,取引コストの効果を持ち, 貨幣保有を飽和状態に到達させな
いよラに作用する。 しかも, この場合のインフ ν率 πは,利子率 ρによって
(6'/1)式と同じように相殺的な影響を受ける。 したがって,利子率の減少は,イ
シプレ効果を促進するものとなる。 Mt>Oのときは灼一向ー1>0であるから早
急に消費するのが有利となる。なお,第3図は,時間選好率。と利子率 pの影
Xz 事撃を,第 2図と同じよラなー
α 財二時点のケースで描いたも
。 のである。通常,時間選好率
。は,効用函数を変化させ,
無差別曲線の勾配を平担にす
る傾向がある。 しかし, ここ
では無差別曲線を乙/フトさせ
る代りに,予算制約線を乙/ブ
トさせることによってその影
轡を描く方法をとっている。X1
すなわち,初期賦存量を示す
第 3 図 P)点、から出発し"c,今日の財
OLIVE 香川大学学術情報リポジトリ
![Page 11: OLIVE ]ÝY'[f[f S`ÅX10ê0Ý0¸0È0ê 交換経済における貨幣](https://reader031.fdocument.pub/reader031/viewer/2022013009/61ce3b3c47e46a36c17b92d4/html5/thumbnails/11.jpg)
37 交換経済における貨幣 -37ー
.:1:1 の犠牲の下に明日の財 X'2 をより多く消費する場合には以前と同じよラに
予算線上を aに向かつて上昇して行くことになるが, 逆に明日の財.:1:2の犠牲
の下に今日の財 Xlの消費をふやす場合にはPb線上でなく時間選好率(1十 (j)2
によって修正されより険しい Pb'線上を下方に移動することになる。かくし
て,時間選好率。は, aPb'の予算制約折線を作り出してくる。他方, 利子率直
ρの効果は,この臼の影響を相殺するものであるから,a"Pb"のように P点を
中心に右方に回転した予算制約折線をもつことになる。なお,インフレ率 1ての
効果は,時間選好率。と同じであり,上図から推測しうる。
この節を終るに当り,以上考察したニーハシズ・モデノレの基本的部分とわれ
われのモデルを比較し, その問題点を探ってみることにしよう。 (a)先ずわれ
われのモデルでは,各個人は,月礎自に効用函数と予算制約にしたがってその
週全体の取引に関する意志決定を行い,火曜日以降その週の残りでその契約の
履行をなすと仮定された。これに対し,ニーハンズのモデノレでは,このような
契約の締結とその履行の間の区分は行われず,日々の契約はその日のうちに直
ちに履行されるものとされている。したがって,例えばニーハンズの第 1図の
R曲線と E曲線はわれわれのモデルでは,各月曜日に締結され直ちに履行され
るその週全体の総受取額と総支出額の軌跡を示したものとなり,また同じく R
十Mo曲線もその週末の貨幣ストックの需要額の軌跡を示したものとなる。ゆ
えに,われわれの言葉で言えば,ユーハンズ・モデノレの (5)(6)(8)式は,各
週の財の需要総量と貨幣ストックの需要額だけを決定する条件式にすぎないも
のになる。そこには,契約を履行する過程で生じる支払不能の問題は存在しな
い。 (b) したがって,われわれは,エーハシズが主張するように t時点での
貨幣ストック Mtを,支払不能とならないための橋渡しの役割をする貨幣であ
ると解釈することはできなくなる。彼のモデルでは,各時点で連続的に意志、決
定をなす経済を取扱う。したがって,支払不能となる場合には,直ちに意志決
(14) 無差別曲線のνフトは,任意の的に対し (1+1:1)2だけ増大したらの組みとして修正し描かれてくる。したがって,それに代って,無差別線を以前のままにし,予算線の勾配をc1十8)2だけ険しくすることで修正している。
OLIVE 香川大学学術情報リポジトリ
![Page 12: OLIVE ]ÝY'[f[f S`ÅX10ê0Ý0¸0È0ê 交換経済における貨幣](https://reader031.fdocument.pub/reader031/viewer/2022013009/61ce3b3c47e46a36c17b92d4/html5/thumbnails/12.jpg)
-38ー 第55巻 第 1号 38
定の修正を行えばすむことである。かりに初期に所有する貨幣残高が如何に小
額であろうとも,すべての取引はそれに応じ予算制約の下で円滑に遂行されて
くる筈である。換言すれば,彼のモデjレにおい℃は,貨幣残高の減少は,貨幣
以外の任意の財の賦存量が減少した場合と何等本質的な差異はないのである。
(c) また彼のモデルには,財のフローは存在するけれども,その対価として流
れる貨幣のフローは存在しないようである。貨幣のフローがないことは,彼の
規定する貨幣の限界アロー効用の概念の中にも見出し得る。初jえば (5)式の
hを財の対価として流れる貨幣フローの限界効用と解ーすることは,無理である。
それは,貨幣所得の限界効用を表わすものである。すなわち ,t時点における貨
幣所得をIt=I:ρ;均十Mtとし,かりに効用函数 U=U(x:,…,.xy, lt, Mt)とす
るときの極値における貨幣所得の限界効用は, aU/Blt= I'vtとなと一方,この
ときの貨幣フローの限界効用は,BU/白んである。 そしてこれもまたA.tに
等しくなる。そこで,ニーハシズの言うように BU/Blt=BUjoんがなりたつ。
しかし, これは,結果として等しくなったものであり.tが貨幣フローの限界
効用そのものであるということを示してはいない。ちなみに,物々交換経済に
おいて,U =U(.x:,・ .xVとIt=I:ρ;巧とした場合のラグラシジュ乗数 M を
求めてみると,所得の限界効用 BU/Bltは b であるが, しかしながらこの場
合には,貨幣フローの限界効用を規定しえない筈である。くのまたニーハシズ
・モデルは,貨幣所得 Itの変動が貨幣ストック M,の変化によるものか,財の
賦存畳fjの変化によるものかも区別していない。したがって,かつて我々が指
摘したよろに,貨幣ストックの変化と財の賦存霊の変化との,財の需要に与え
る効果は,全く同じになってくる。)それは,彼のモデノレがクラウァーの主張す
るような貨幣で財を買う場合と貨幣に対し財を売却する場合とを,全く区別し
(15) 拙稿 「国際経済理論における社会的無差別曲線と貨幣」 香川|大学経済学部研究令報 21,脚注 (10)
(19) 拙稿「国際通貨の需要に関する研究j 神戸大学経済経営研究所金融研究νリー
ズ第4冊 1976年 47頁。(17) 拙稿「貨幣交換経済に関する覚書」香川大学経済論議第54巻 4号昭 和56年3
月。
OLIVE 香川大学学術情報リポジトリ
![Page 13: OLIVE ]ÝY'[f[f S`ÅX10ê0Ý0¸0È0ê 交換経済における貨幣](https://reader031.fdocument.pub/reader031/viewer/2022013009/61ce3b3c47e46a36c17b92d4/html5/thumbnails/13.jpg)
39 交換経済における貨幣 --39ー
なL、からであるといえよう。 (e)かくして h を貨幣の限界フロー効用と規定し
8U/8It=:>Ct となることからして,貨幣が財の取引の対価として実際に流れたと
考えることは,錯覚以外のものではないということになる。予算制約式2:ρ;
(x~ -.i:) = Mt -Mt+1をみても,各取引者のすべての財の取引が貨幣で支払われ
ているとはいえないことがわかろう。すなわち,第 2図の例でいえば, Ml/ム
が使用された財取引の部分のみが確実に貨幣戸で支払われたといいちるにすぎな
い。その他は物々交換であるかもしれないのである。ゆえに,ニーハンズのモデ
ノレは,貨幣交換経済を全面的に取扱ったモデノレであると言うことはできない。
以上の諸点、からみて, ニーハンズ・モデノレはMt!ρzが使用されるとさのみ,
確実に貨幣交換されたと明言しろるような限られたモデノレであるというにとに
なる。そのうえ,それは,貨幣フローに対する選好を全く考慮に入れていない
とみなければならない。しかしながら,彼のモデノレの特色は,無限定常運動の
仮定の下に,ある期間(t=1 ,…, h)に亘る貨幣;ズトック Mtの需要ノミターン
を描きー出し,その Mtの需要に時間選好,利子率,インフレ等が関わるケース
を分析した点にある。そこで, このニーハンズ・モデノレの貨幣ストック Mtの
需要を次節でより詳細に考察することとしよう。
3 ニーハシズにおける基本モデルの展開
ニーハシズは,上記の基本的モデルを貨幣以外に,利子っき資産があるケー
スと債務を負うことが可能なケースに拡張して分析する。先ず,利子っき資産
として,一定率 3の利札っさ永久コシソノレ債のような債券を考える。いま,前
節の無限定常運動径路のように財・サービスの受取りと支払いの時間的パター
ンが予め決定されているものとし,そこに生じてくる取引資産を貨幣ストック
とこの債券の保有の聞で配分する最適資産構成を問題とする。貨幣と債券との
聞を移転するのに,取引コスト(一種の手数料〉が掛る。その取引コストが債
券1ドルの購入または売却に対してらであるとする。前節の (5つ(6つの条件
式にみるように,この無限定常運動径路上では,取引資産は少くとも年に一度
はゼロでなければならない。したがって,ニーハンズは,初期の取引資産がぞ
OLIVE 香川大学学術情報リポジトリ
![Page 14: OLIVE ]ÝY'[f[f S`ÅX10ê0Ý0¸0È0ê 交換経済における貨幣](https://reader031.fdocument.pub/reader031/viewer/2022013009/61ce3b3c47e46a36c17b92d4/html5/thumbnails/14.jpg)
.-40ー 第55巻第1号 40
ロであるとして出発しても,一般性を失うことなく取扱うことができるという。
そこで,受取りと支払いの時間的ノミターンを第 4図のように描きろるものとす
る。この図で斜線の領域は,貨幣ストックで保有される額を示している。点SI,ポ
…, Snは貨幣ストック蓄積の開始時点を表わし,他方点 Sr,、" S;は支払い
を支弁するための債券売却の開始時点を表わす。これらの転換点、は, A(t)を
所与とするときは取引コスト Cvと利子率tによって決定されてくる。すなわち,
貨幣ストックの保有期間を T とすると,取引資産を債券の形で保持しその後再
びそれを貨幣?と交換して使用に供するため必要となるコストは 2のであり,
その閣の利子収入はムである。ゆえに,債券の形で取引資産を保持するために
は 2活んの条協:成立たねばならない。なお, 不等号が逆転するときは,
取引資産が貨幣の形で保持されることになる。第 4図において, ,*は条件2Cv
豆んが成立する最適保有期間である。さて,財のフロー,すなわち実質で表わ
A,II
10 1, t 2 t3 t ~ t j t6 ti IS '
、~ 、ーー~.---'
τ* τ本
第 4 図
した受取りと支払いが,各時点で同率に上昇するとき ,A(t)は,価格不変で C匂
とtも不変ならば,転換点並びに保有期間 T を不変のままに残し,上方に比例
して乙/プトしてくる。したがって,すべての時点の貨幣残高や債券保有額は,同
率に増加する。また,財のフローが不変ですべての価格の同率に変化する場合
も,Cvとiが一定ならば,上例と閉じよろに貨幣残高と債券保有額を同率に増
(18) 2 cυくんなら取引資産はすべて債券で保持される。 2cv=んでなら,第4図のふ,ふのような点,すなわち一部が貨幣,他が債券となる点になる。
OLIVE 香川大学学術情報リポジトリ
![Page 15: OLIVE ]ÝY'[f[f S`ÅX10ê0Ý0¸0È0ê 交換経済における貨幣](https://reader031.fdocument.pub/reader031/viewer/2022013009/61ce3b3c47e46a36c17b92d4/html5/thumbnails/15.jpg)
41 交換経済における貨幣 -41-
加させる。他方,取引コスト Cvが上昇し利子率不変の場合は,'"を増大させ,
債券保有額を減少(貨幣残高を増加)させる。 これに対して,利子率 tが上昇
しの一定の場合は, '"を短縮させ債券保有額を増大(貨幣残高を減少〉させる。
以よのことを, ボーモノレ・トーピン流の鋸の歯状のケースで考えると,貨幣保
有の最適伎は,周知のように M=2 (Cv/i)2Yη となる。ただし,所得yは年間
均等に n回与えられるものとされている。ゆえに Y=nyである。この特殊ケー
スにおいても, 上述の諸関係はほぼそのまま保持されている。特に, その原因
が財のフローの菱化であろうと価格水準の変化であろうと貨幣所得が比例的に
変化するとさは,債券と貨幣の両保有額を同率で変化させるとし寸関係が成り
立つ。 以上は,取引コストが債券1ドノレ当り一定値 c。のクースである。そこ
で,ユーハシズは,取引一回当り固定コスト Cfが必要となるケースについても
A
第 5 図
一一-k=2-.--k=3
k=4
考える。 この場合,受取りと
支払いのパターンが与えられ
ているので,利子収入を極大
とするような債券保有額が選
択されてくる。第5図に示す
ように.,取引回数hは最低ニ
回であり,利子収入はその取引回数の函数として表わされてくる。そこで, lそ
$
(19) 拙稿
第
k*
6 図
「生産と貨幣に関する覚書(l)J
k
の利子収入を図示すれば,第
6図のR曲線を得る。ただし,
このR曲線は, 限界収入逓減
の法則にしたがうものと仮定
されている。 この場合の第6
図の C直線は,取引コスト総
額を描いたものである。なお,
R曲線は,kが増大するにつ
れて総資産 J~A(切に漸次
香川大学経済学部研究年報 20 を参照。
OLIVE 香川大学学術情報リポジトリ
![Page 16: OLIVE ]ÝY'[f[f S`ÅX10ê0Ý0¸0È0ê 交換経済における貨幣](https://reader031.fdocument.pub/reader031/viewer/2022013009/61ce3b3c47e46a36c17b92d4/html5/thumbnails/16.jpg)
-42- 第55巻 第 1号 42
接近して行く。そこで,債券取引から生じる純利益Pは,k*点で極大になる。す
なわち,この点で限界コストは限界収入に等しくなる。さて,取引コス rCfの上
昇は, C直線の勾配の増加で示され,k*点を左方へ動かし,貨幣保有額の増加
(債券保有額の減少〕を導く。また,利子率の上昇は,R曲線の勾配を急に
し R*点を右方に動かし,貨幣保有額の減少(債券保有の増加)を導く。他
方,実質所得が変化しそれによって資産曲線 A(t)が上方に乙/プ「する場合は,
第5図から想像しうるように,各々の hに対する貨幣と債券の割合を一定に保
つよろに両者の保有額を比例して増大させることになる。したがって,第 6図
のR曲線は,上にνフトする。他方でコスト曲線Cはl不変のままである。ゆえ
に,k*点は右方へ動いてくる。かくしてJ実質所得の増大による A(t)曲線の
比例的増加は,貨幣保有額を実質所得の変化より少な自に増大させる(もし,
F点、が以前の位置にとどまるならば,貨幣の保有額は,実質所得に比例して増大
す27こととなる。そこで,固定コスト Cfの存在は,貨幣の保有に,規模の経
済を生じさせる。なお,A(t)曲線の乙/プトが価格の比例的変化に起因するとき
は,取引コスト Cfもそれに応じ同率の変化をし ,k*点を以前の位置のままに残
すことになる。したがって, 乙の場合,名目貨幣残高は同じ比率;で増大し,貨
幣対所得の比率を不変のままにする。以上のことを,鋸の歯状の特殊モデノレで
考えると,次のようになる。債券の保有から得られる粗収益は,全取引資産を
債券購入にあてるときの利益 (1/2)yiから, 貨幣を保有したために失う利益
(1/2)Mi を差~I いたものであり,他方取引コスト総額は Cfn(y/M)である。ゆ
えに,その差で規定される純益 (1/2)i (y--M)ーの(Y/M)を極大にし,最適貨
幣ス}ツク保有額 M=y石Y沼Jを得る。これは周知のボーモJレの平方根公式
である。そして,この場合も上記の一般形式での議論とほぼ類似した結果を得
る。すなわち,貨幣ストック保有額は,実質所得の平方根に比例し,規模の節
約がある。また,取引コストの変化についても同様である。他方,A(t)のν
ブトが価格の比例の変化に起因する場合は CfとYに同率の上昇をもたらし
(20) しかし, k*)点が右方へ移動するときは,収穫逓減則の仮定のために, 比例以下と
なる。
OLIVE 香川大学学術情報リポジトリ
![Page 17: OLIVE ]ÝY'[f[f S`ÅX10ê0Ý0¸0È0ê 交換経済における貨幣](https://reader031.fdocument.pub/reader031/viewer/2022013009/61ce3b3c47e46a36c17b92d4/html5/thumbnails/17.jpg)
43 交換経済における貨幣 -43--
貨幣保有額に同率の変化を与える乙とになz:次に,ニーハシズは,以上の所与の A(t)の下での貨幣と債券の最適資産構
成の議論を, 前節で考察した最適な A(t)径路の決定の議論と一緒にし,同時
的に決定しうるものとし'C.前節の議論のうちで時間選好を考慮したケースに
ついて一般化することを試みる。単純化のため多数財を一種類にまとめ合成財
を作る。ゆえに,取引資産は,貨幣と債券とこの合成財ストックの三つのいず
れかで保有されることになる。そして,各取引者は,自己の債券の発行を認
められ,ゆえに債務を負うことが可能となる。これらの仮定の下で,効用函数
は,
U =U(.Xl,…, ,X't,…, 'xh) (9)
で与えられる。賦存量ベクトノレは,(.Xl,…, Xt, "" , .Xh)である。各 t時点で財,
債券,貨幣のそれぞれに関わる制約式が存在する。先ず,財に関する制約式は,
t時点から t十 1時点に至る 1期間の財のス fックの増加 Sf+l-.Sfが, 当期閣
の自己保有の財の消費をこえる賦存量の超過量ゐ-'Xtと他人より購入した財の
超過量 zf-y~ の合計量から,財の在庫コスト γS~ および財の取引コスト cg(z~(22)
十YD と債券の取引コスト Cb(Z~十 y~) を差引いたものに等しくなければならぬ
ものとして現わされてくる。ただし,yは売却量 zは購入量, γは財の在庫コ
スト係数 cは取引コスト係数であり,添字gはそれらの値が物量単位で測ら
れていることを示している。そこで
Sf+l-Sf = (Xt-.Xt)+ (Zf -Y~)- 'YSf ーが (z~ 十 .YD-Cb(Z~ 十 y~) (10)
となる。他方,債券に関する制約式は,当期閣の債券保有額の増加がその購入
(21) なお,ユーハシズでは,コシソノレ債の利子収入が不確実であり,その期待値E(i)と
標準偏差引が与えられているケースについて分析を展開している。 しかし, ここでは省略する。
(22) 取引コストは一種のブローカー手数料である。ただし,財の取引コストについては,情報収集,検査,その他不完全市場で考えられるもので,それらの入手によって完全市場により近ずきうるようなコスト全体を考えている。したがって,ブローカ一手数料とみるよりも,財の取引者の負担となるコストと考えている。これら取引コストは,いずれも,財の投入をそれだけ必要としてくる。
OLIVE 香川大学学術情報リポジトリ
![Page 18: OLIVE ]ÝY'[f[f S`ÅX10ê0Ý0¸0È0ê 交換経済における貨幣](https://reader031.fdocument.pub/reader031/viewer/2022013009/61ce3b3c47e46a36c17b92d4/html5/thumbnails/18.jpg)
-44ー 第55巻第1号 44
超過に等しいことを意味する。すなわち,
S~+l- S~ = z~-y~ (11)
である。また,貨幣に関する制約式は,当期閣の貨幣ストックの増加額が,財
と債券の売却受取額封 (y~-zD +対(y~-zD と債券利子収益 rS~ 並びに貨幣
の利子受取額 ρS'(' の合計額から,税の支払額 tt を差51~、た差額に等しいこと
を意味している。すなわち,
S~l-S;'= ρ~ c.y~-z~) + ρ~(y~-- z~) +rS~+ρS'('-t, (12)
である。勿論,)tjや貨幣のストックおよび財や債券のフローはすべて非負(α与
o ;a=x, yU, zY, yb, Zb, sg, Sりである。また,無限定常運動からして qnll+l=
qt (q=.x, yg, zg, yb, Zb, sg, sm, Sbおよび n=0,“", (H-l))でなければな
らない。かくして ,X,t1, tb, t, r, p, 7, Cg, Cbの所与の下で, 一次制約式を
もっ非線型プログラミングを解く問題に帰着する。
消費,交換フロー並びにストックに関するクーン・タッカーの条件は,次の
ラグランジュ方程式から得られる。
L=U(.X1, "', X"川zねωhρ〉一芸三会P〆沖入巧咋f
十何州州c♂州0べ(何十 yD+cb (ヰ十ペ)〕 -Spi[外l-'S~)
、、,〆qs
z
仰
uu'
,旬〆
〆t
、、nMu'
,ιb ν AUA
、.ノ叫
zcu
l
mH
Qu
r't
、
rillB、
mc
入ゐ
訂
問
、tla--d
、、ノbg
mvJW
仇
υebz
〆{、
一 ρ~(y~-zD 一川-pS,,!, 十 ttJ (13)
ただし,乗数λf,λi,λFは財と債券と貨幣の割引かれた限界フロー価値であ
る。それは,割引かれない限界価値に μ~=(1 +8)t;>.,;の関係で変換される。な
お,時間選好率。と貨幣ストックの利率 p並びに財の在庫コスト γの聞には,
O孟p孟 0,8,十'y孟Oの関係が仮定され℃いる。
(23) 債券のストック sfについては,負もあり得る。その場合債務を負っているととを
表す。なお,債券の利札7とすれば市場利子率tはi=r/tbで表わされる。
OLIVE 香川大学学術情報リポジトリ
![Page 19: OLIVE ]ÝY'[f[f S`ÅX10ê0Ý0¸0È0ê 交換経済における貨幣](https://reader031.fdocument.pub/reader031/viewer/2022013009/61ce3b3c47e46a36c17b92d4/html5/thumbnails/19.jpg)
45 交換経済における貨幣 -45-
めに関し (13)式を微分し,消費に関する条件を求めると,
(旦-auv-(18仇 OXt =>"t - ¥ 1十。 )μ1,41)po--豆一一一 Xt孟O (14)
を得る。これは,以前の (5)式と同じものである。そして,oU/o,Xtく刈のと
き財は消費されない (.:~t= 0)。市場への財の販売と購入に関する条件は,販売
に関しては,
[( 1 +CY)^'~-P~^'~J λfμfρf (1十 CY)巧サ~^'~l.Yr = 0 ,一一= 二三一一つ.y~孟 o (15) 」 入批 μm=1 +C
fNt
となり,購入に関しては.,
、、,Jno
噌
i/目、、nu 注一
nwe
,u ヴ亀一が
封一一zi
i一
gs
山
mc
μ
一ーμ
一一
gz一
冗
入一利
nu 一一nu
,“v ,‘ 、tlt
J
叫
S入nwvozU
AU晶
gz
入、、1ノ
nue
、pb
噌'・-ft
、、
phg
,EBE
、
となる。 .Yrおよびzfが正であるとき,入uλア=ρU(1 十 CY) および λ~/λア=ρ:/(1-cりとなる。もし,取引コスト CYがゼロであれば,貨幣と財の限界代替
(24)
率が市場価格比率に等しいという関係を得る。また,もし取引コストが存在す
れば,その限界代替率は,市場価格比率よりも,販売についてより大となり,
購入についてより小となる。他方,問/λア〉民/(1+cりあるいはλ~/λア<ρv
(1 -cりの場合には, 市場での販売またはそとからの購λは, 全く生じない
(.Y~= 0 または z~= 0)ことになる。さて,債券の売買に関する条件を求めてみ
ると,その販売は,
一 入i μ i μ fλ1(^'~十C叫ー封印)Yt= 0 ,-=ー」孟ρ~-Cb一一民-'cb_- , y~孟 o (17)
7包 勿Z 、バ勿,
入rμzμt i
であり,その購入は,
(24) 貨幣残高について飽和状態に達することは, λア=0を意味していなし、。 λ?はλ12
0 のときのみゼロとなる。それは λ~>o で満されない需要がある限り,貨幣の贈与が
喜ばれる筈であるからである。
OLIVE 香川大学学術情報リポジトリ
![Page 20: OLIVE ]ÝY'[f[f S`ÅX10ê0Ý0¸0È0ê 交換経済における貨幣](https://reader031.fdocument.pub/reader031/viewer/2022013009/61ce3b3c47e46a36c17b92d4/html5/thumbnails/20.jpg)
-46ー 第55巻第 1号 46
入?μiμ~ ^'~ (はーのiールア)z~= 0 ,一一一説?十cb一一=ρι十cbー,Z~孟 O
入? μT pT 入ア
(18)
である。これらの条件は,財の販売・購入の条件に類似しているが,その右辺
に fJ-Uμfまたは λUλFを乗じている点で違っている。 それは,すべての取引
コストが仮定によって財の投入として取り扱われているため生じたものであ
る。
次に,ストックに関する条件を求めてみる。先ず,財のストックについて,
[( 1-7) ^,~-^,~-1] 入~-À ~-1 (1ーかi一昨11Sf= 0,一一一-::;:'7.Sr孟OJ 入1
を得る。割引かれ℃いない限界値のタームで置き換えると
μ?ーμf-It一一一一一一三二一ーとー(8+γ〉
〆 一 ( 1 十8)s
(19)
(19a)
となる。 ζの (19a)式から判るように,財のストックが正 (Sr>0)なら,%で
表わされた財ストックの限界価値(左辺)は,割引かれたその財の在庫コスト
(財ストックの機会費用)(8+γ)/(1 +のに等しくならなければならない。当
然のことであるが,財ストックの限界価値がその在庫コストより大であれば,
財ストックの保有は増大してくる。逆に小であれば,財のストックは減じゼロ
となる (Sf=0)。他方,債券ストックの保有に関する条件式は,
入?一入i-1 λア(λi-λ~-1+ 1" λ;") S~= 0 ,一一一一一='-1"一一一一, S~孟 o (20)
入tλ?
b ηz μs一μt-1 μs一一一一一=一一土一一切'-'1"一一一) (20a) μ-(1 +8) 'v I ..b
fNt
となる。これらの式もまた財のストックの条件式に類似している。その左辺は
OLIVE 香川大学学術情報リポジトリ
![Page 21: OLIVE ]ÝY'[f[f S`ÅX10ê0Ý0¸0È0ê 交換経済における貨幣](https://reader031.fdocument.pub/reader031/viewer/2022013009/61ce3b3c47e46a36c17b92d4/html5/thumbnails/21.jpg)
47 交換経済における貨幣 -47ー
債券の保有から得る報酬を表わし,またその右辺は債券の取引コス r(債券の
機会コスト〉を表わしている(負の値をとり,一種の債券の在庫コストであ
る)。右辺に λ;'/巧あるいはμ;'/μ?を乗じているのは,イ責券利子 rを貨幣で支
払うためである。 (20)式と (20a)式は,不等号でなく,等号で表わされ℃いる。
それは,各取引者にとり,債券を買い債権を持つことと債券を売り債務を負ち
ことの両者の選択が可能であり (S~呈 0) , そのため各取引者が等号に達する
まで自由に行動するからである。ゆえに,尽くOのときは,上式の右辺は債務
を負ちことから得る限界利益を表わすと考えるべきである。また,貨幣ストッ
クの保有に関する条件I':l:,
[ 入アーは1
(1 + p)A;'仏]S;'= 0 ,っす一川たo (21) 入c
μt一μt-1
~~~---:s:--;-ームーー ((}-p) (21a) r 一(1+()) t
となる。 (21a)式は (6つ式と同じものである。したがって, (21)と (21a)式の
説明は,既になされている ζ とになる。ただし,ニーハンズは,あたかも土地に
地代とその価格があるように,貨幣にも限界フロー価値と限界ストック価値が
あり,貨幣の価値が価格水準の逆数であるのかあるいは利子率であるのかとい
う古い問題はすでに上記の入?と (21)または (21a)式によって解かれたことに
なっているといい,そして,貨幣ストックの価値は,債券の利子や非貨幣的資
産の利子で表わされているものではなく,時間選好と貨幣の利子の差異によっ
て表わされるものであると附言する。なお,貨幣の限界フロー価値入アがゼロ
となるのは,バ=0でない限りあり得ないことである。しかし,貨幣の限界ス
トック価値は (}=pのときゼロとなることが可能であり,そしてそれはSア>0(2め
すなわち正の貨幣ストック保有の状態と両立し得るものである。
(25) ニーハンズは,取引資産が財ストック,および貨幣と依券の三種で保有されるクースについて,無限定常運動のときの t=hで時間径路図を第4図を複雑にした形で描いている。また,この場合の第3図の拡張した図も附加している。とこでは,紙面の都合上,これらを省く。
OLIVE 香川大学学術情報リポジトリ
![Page 22: OLIVE ]ÝY'[f[f S`ÅX10ê0Ý0¸0È0ê 交換経済における貨幣](https://reader031.fdocument.pub/reader031/viewer/2022013009/61ce3b3c47e46a36c17b92d4/html5/thumbnails/22.jpg)
-48ー 第55巻第 1号 48
いま,かりに t=2のケースを考え, 財が第 1日に売却され,第2日に購入
されるものと仮定する。すなわち, (15)式から河/λ'!'=PUC1十cりを得,(16)
式から沌/λP=封/(1-cりを得て,それらを λ?と入Pにつき解き,(λr-λ'{')
/入Fに代入すれば
入P一入子 bg A.I! 噌 r “ 1十cg 山 A
一一一一一一I¥,:' b~ 1.-cg 、g2 1'1 ん 2
(22)
となる。にの布辺の λ~/立は財の限界代替率を示している。ゆえに,貨幣の限
界ストック効用と財の限界代替率の聞には一次式の関係が成り立っていること
になる。同様に,資産の閣の限界代替率を求めてみると,財ストックと貨幣ス
トックの聞はI
λf-λf-1
入?一ーで一一一一=一てでただし 8~>0 , 8':>0 入了一入;I-I Y
(23)
入F
となり,債券と貨幣の聞は
一一一一一一一=ーと, ただし Sア>0λアーλ主1 ρ v
入i一入?"1(24)
となる。これらの関係は,周知の限界代替率がそのストックの価格比〈ーγ/pま
たはr/p)に等しいという関係の成り立っていることを表わし lている。
なお,ニーハンズは,第 1節でのべたような,効用菌数の中に貨幣ストック
M を導入し,そとから得る限界条件 (DU/δM)/i=入を求める分析を批判して'
上記の (21a)式の単なる変形にすぎないものであると主張する。すなわち,
(21a)式を変形し
/与一
叩一
hμ一 (25)
OLIVE 香川大学学術情報リポジトリ
![Page 23: OLIVE ]ÝY'[f[f S`ÅX10ê0Ý0¸0È0ê 交換経済における貨幣](https://reader031.fdocument.pub/reader031/viewer/2022013009/61ce3b3c47e46a36c17b92d4/html5/thumbnails/23.jpg)
49 交換経済における貨幣 -49-
を導出する。その左辺の分子 μアーμ?と1は8U/θMに相当し,分母 (}-pは(8U
/8M)/i=λの3すなわち貨幣の機会コストに相当しており, そして, 右辺の
μア/(1十のは C8U/8M)/i=λのラグランジュ乗数入に相当しているという。
なお,自明のことであるが,ニーハンズによれば,財および貨幣のストックの
蓄積に関するよ記(19a)式と (20a)式は,その左辺を正とする条件を必要とす
る。すなわち, ()十γ孟Oおよびかず孟Oでなければならない。 また, (21a)
式は,債券の蓄積の場合には (21a)式を正として (18)式を用いて得る封十
cbμ~/μ「孟r/() の条件を,他方負債の場合には (21a) 式を負とし (17) 式を用い
て得る Þ~-CbßYμア豆r/(} の条件を必要!としている。
ニーハンズは,最後に,以上の諸分析を基礎にして,それらを組み込んだ一
般均衡体系を記述する。よ記の最適化条件から各個人の需要因数を導出すれ
~í,
* * 1~ 費 X't=川 (.i,t?,ρb, t, r,ρ, 'Y, C1, Cb) (26)
財ス fック s*i=S9e 1(Z,f,ρb, t, r,ρ,γ, Cg, Cb) (27)
*~ * 債券(含負債) SトS~(i, t1, tb, t, r,ρ,γ, C7, Cb) (28)
貨幣ストック S*Tzt器)';'(i, t1, tb, t, r, p,γ, Cg, Cb) (29)
* * となる。また,同様のものは,財の販売と購入 (z~ , .YDおよび債券の販売と
* * 購入 (z~ , .yわについても得られる。なお,.X, t1, tb, tは,それぞれに時間を
付した要素からなるベクトノレである。そこで,これらの需要函数を各個人につ
いて合計すれば総需要函数を得る。例えば,債券と貨幣のストックについてみ
れば,
n * De=EfsjzDc〔(£), y,r,(t),rよρ,(γ), (Cp) , (C引 (30)
n * Lt =呂志 S~=Lt((i) , tP,ρヘ(t), r,ρ, (γ), (CP) , (cb)) (31)
OLIVE 香川大学学術情報リポジトリ
![Page 24: OLIVE ]ÝY'[f[f S`ÅX10ê0Ý0¸0È0ê 交換経済における貨幣](https://reader031.fdocument.pub/reader031/viewer/2022013009/61ce3b3c47e46a36c17b92d4/html5/thumbnails/24.jpg)
~50 ー 第55巻第1号 50
となる。)ただし・ (f)(t) (γ) (cり(cb)等の記号は,各時点(t=1,…, h)におけ
るすべての個人 (i=1 ,…, n)のそれら変数のベクトノレである。17lJえば (.f)=
a, ・,n.X=l.Xr, ", i.Xt,川引 ,n.f" (ただし,右添字は時点を,左添字は各個人を表
す)である。他方,貨幣と債券の総供給は,政府によって決定されその予算制約式
T=ρM+rB (M>O, Bミ0) ~ID
に依存する。すなわち,租税収入 Tは,政府の貨幣とコンソル債の利子支払に
あてられねばならない。ここでは,政府の財・サービスの売買は無視されて
いる。さらに ρ,M,r,Bは, すべての時点で一定であると仮定される。 した
がって,Tは一定の値をとる。また,債券額Bは,正あるいは負の値をとりラ
る。負の場合には,政府が民聞の債券を保有することになる。租税Tは,
,Tv
nZ伊一一T
(33)
である。この恒等式は,i=l,'"", n'-'l人について自己の賦存置と資産の大
きさを考慮しムを自由に選択できるとするとき,最後に残る第 n番目の人の
nttを決定するために使用される式となる。そこで,一般均衡体系は, (32)(33)
の両式と貨幣並びに債券の需要と供給の均等を表す式,
Lt( J =M (34)
Dt( ) =B (35)
によって表示されてくる。この体系は 4つの方程式と p1,pb, T, nttの末知
数からなっている。同様の等式は, (26)式や (27)式についても成り立つ。 し
たがって,それらは,多期聞に宣る一般均衡体系であるといえる。なお,上記
の体系は,財市場と債券市場で需要の均衡が,すでに (34)式と (35)式と同時
に,背後で成立していることを意味していると解釈されねばならない。すなわ
ち, (11)式の左辺はすべての個人について加えると (35)式からゼロとなり債
券市場での販売と購入が等しくなることを表し,また同様に(12)式の左辺もす
べての個人について加えると (34)式からゼロとなり貨幣市場の均衡を表わす
(26) 上の (28)式は,tY,tb,t,rに関しゼロ次同次であり, (29)式は一次同次である。この性質は (30)および (31)式にもそのままあてはまる。
OLIVE 香川大学学術情報リポジトリ
![Page 25: OLIVE ]ÝY'[f[f S`ÅX10ê0Ý0¸0È0ê 交換経済における貨幣](https://reader031.fdocument.pub/reader031/viewer/2022013009/61ce3b3c47e46a36c17b92d4/html5/thumbnails/25.jpg)
51 交換経済における貨幣 -51--
ことになる。したがって,債券市場と貨幣市場の需給均衡は,既に成り立ってn
いるといえる。しかも他方で (32)式と (33)式から zytS?+ρJ子四め)=0
となることを考えると,財市場での超過需要は,ゼロでなければならないこと
が導かれてくる。¥すなわち,これはワノレラス法則による当然の帰結である。
ニーハンズは,以上のように一般均衡体系を構築してのち,M,rおよび (t)
がすべて等比例的に変化する場合の効果や pの増大する場合の効果について考
察する。前者はすべての価格と貨幣ストックなどの比例的な増大を招来し実質
変数に何の影響も与えないことになり,後者は F とグがある特定の日(t)以
外一定に保たれると想定し貨幣と債券の需給に差が生じたときに政府の均衡基
金のようなもので t+1日の均衡が達成されるよろにカバーするものとし ρの
変化が封と討に与える効果を考えると IS-LM分析と類似の結果が導かれ
るにとになるという。しかしながら,ここでは,にれらの問題に立入らない。
また,ニーハシズの考察した貨幣供給が一定率。で増大するケースのインフレ
の問題についても省略する。
4 むすび
以上,われわれは,第2節と第 3節において,ニーハンズの著書「貨幣論」
の第 1主主~第 5章を中心に彼の貨幣交換経済に関するミクロ分析を考察してき
た。その第 2節で考察したニーハンズの基本的モデノレの特徴は,その終わりで
まとめたよラに, (a)契約の締結とその履行が同時に進行するモデルであるこ
と, (b) したがって初期の貨幣ストック保有額がどのような水準であろうと支
払不能にならないこと, (c)経常の財の取引の対価として流れる貨幣フローが
存在すると認め難いモデノレであり,彼が導出した h を貨幣の限界フロー効用
と解釈し難いこと, (d)財の賦存量、の変化と初期貨幣ストック保有額の変化が
それぞれ財の需要に与える効果の聞に区別をなし得ないこと, (e)確実に貨幣
と交換されたと言いうる取引の部分は, 第2図で示したような MJ/Plの支出
によって取引された部分だけであるとと,の五つの点に見出された。これらの
特徴は,当然上記第3節で示した彼の分析にも現われてくる。すなわち, i皮は,
OLIVE 香川大学学術情報リポジトリ
![Page 26: OLIVE ]ÝY'[f[f S`ÅX10ê0Ý0¸0È0ê 交換経済における貨幣](https://reader031.fdocument.pub/reader031/viewer/2022013009/61ce3b3c47e46a36c17b92d4/html5/thumbnails/26.jpg)
-52ー 第55巻第1号 52
貨幣以外に債券の保有を加えその分析を拡大するけれども,ボーモペ二トーピ
シ流の最適資産構成の考えを一般化するにすぎず,なお大部分の取引を貨幣と
交換されないままに残している。例えば,予算制約を示す (12) 式 S~l-S;"=
民(y~- Z~) →封 c.y7- z~) → rS~ 十 pS;"-tt をみても,財の販売と購入のうち貨幣
に影響するものは,その差額部分対 c.Y~-zりだけである。確かに二人からなる
社会を考え,もし販売と購入の事象が同じ瞬間に生起するものとすれば,貨幣
に関わるのは,その販売抗Y~ と購入封z? の差額だけとなる。 しかしなが
ら,もしこれらの事象が別々に生起するのであれば,その販売と購入のすべて
について貨幣の流れが存在することを明示しなければならないことになろう。
したがって,このような差額部分の貨幣ストック分析だけでなく貨幣フローを
導入した分析を必要とする所以は,ここにあるといえる。ゆえに,ユーハンズ
が示した (9) 式~ (21)式にいたる分析は,単に債券保有を含めた一般化であ
り,貨幣ストック M,を無限定常運動径路上で分析したにすぎないものといえ
る。そこに,取引貨幣として最も重要な橋渡しのために貨幣フローの分析は,
除外されてしまってし、る。貨幣フローの分析を行うとすれば,契約の締結とそ
の履行を分離し,契約の締結時点で,その履行期間内に生起するであろう受取
りと支払いの予測を行い決意する個人を考えに入れなければならな L、。この
考えに立てば,本稿第 1節で述べたように,支払不能の危険を考えながら,取
引の橋渡しを行い,かつ次期以降の取引についても円滑に遂行されるために,
一定額の貨幣ストックを手元に留保しようとする行動を認めなければならない
ことになる。そこで,われわれの分析は,貨幣のフローん(=p~YD と m,(= ρ1
zDを分離した形で導入すると共に各期首に一定額の貨幣ストックを予め保有
することを仮定したのである。さらに,このことは,ニーハシズが無限定常運
動の仮定の下に導いたような t=1,…, hの聞に少くとも一回の M,=Oとな
るケーヌを設けなければならないとする結論と,われわれの分析を相容れない
ものにしてくる。
(2:1) 財の取引だけでなしその他取引も含む。(28) 拙稿上掲論文香川大学経済論援策53巻第4号。
OLIVE 香川大学学術情報リポジトリ
![Page 27: OLIVE ]ÝY'[f[f S`ÅX10ê0Ý0¸0È0ê 交換経済における貨幣](https://reader031.fdocument.pub/reader031/viewer/2022013009/61ce3b3c47e46a36c17b92d4/html5/thumbnails/27.jpg)
53 交換経済における貨幣 -53-
ニーハシズがこのように Mt=Oのケースを導出したのは, (6つ式にみる虫11
しもしすべての時点で Mt>Oとなるならば (μ「仰ー1)c1十())/仰=0並び
に ()>Oの仮定から灼>μト 1というととになり貨幣の限界フロー効用の恒常的
な増加を招くとみたからである。しかしながら,貨幣ストックと貨幣フローを
S,,::, ltと規定し(債券市場はニーハンズの取扱いのままとし21本稿第 1節に
掲げたような効用函数と制約条件 (10)-(12)式を用い't,最適条件を求める
と,ラグランジコ方程式
ゐ r
L=U(Xl,…,X", lt, S~I) 一記入札 (Sf+l- SD 一 (.Xt-Xt) 一 (Z~-Yn 十 γS~
+cク 仲YD川伸対)Jーさ〆(件l-sD一件同)]
-Sy[間 I-S"::)-It+ mtー討小
ただし lt= ρ~'y~, mt =ρiz~
によって,消費に関して,ニーハシズと同じ条件式
(;U1θU/1)t 一一ーバ IXt=0 一一三二λ~=(~) f.L~, ,X't詮 OXt "'j""' v , dXt ='!"t ¥ 1十()/
貨幣の流入(財の販売〕に関して
[au]8UBV(1HO)バ百万一(1+c
g)中川Y;=0 ,百7;=百五孟 一一向
( 1 + cg)λf =一一一一一ーザ,y;孟 O
ρ1
貨幣の流出(財の購入〉に関して
(36)
(14)
(37)
(巧(1-Cl)-P~À"::] z; = 0 ,入fC1ーかバ(1 ー出ρ~fJ,'Z'=附, z注 0
(38)
(29) もし,依券市場についても貨幣の流れがある以上,それを考えに入れると,このラh 〆
グランジュ方程式の(紛の右辺の最後の項は, -EF〔(SEI-m-fz+ms〕とな
る。ただし,lt=ρ;.Yr+ρfyf + rSf + pS;nであり ,mt=Þiz;+ρ~zf+tt 'である。
OLIVE 香川大学学術情報リポジトリ
![Page 28: OLIVE ]ÝY'[f[f S`ÅX10ê0Ý0¸0È0ê 交換経済における貨幣](https://reader031.fdocument.pub/reader031/viewer/2022013009/61ce3b3c47e46a36c17b92d4/html5/thumbnails/28.jpg)
- 54-- 第55巻第1号 54
そして,貨幣のス fックに関して
[au au av ー 十 ( 1 十川一昨付 o. 一 手 (1十川1
asア as;naS;n
一(1十ρ〉山口入?とl一(1十ρ)λ;':1'S,!,主主O (39)
を得る。ここでは,エーハンズの仮定にしたがい一種類の財のみを仮定してお
り,したがって同種の財が同時に販売され購入されることがないと考えられる
から.(37)と(38)式のうちいずれか一方のみが使用される。 そこで Xt>O
で z~>O または y~>O となる。 c?= 0のケースで, (38)式に (14)式を代入す
れば
。U 1 、m
OXt云[ーんt(40)
を得る。また, (37)式に (14)式を代入すれば,
au 1 au 、m
OXt P~ alt叶
(41)
を得る。この両者は,当然異ってくる。一方,S'!'> 0の場合について, (39)式
から
の「1一ザ
何一昨
入
7t
一一入
λ
一(42)
あるいは,時間選好を考慮して
w一昨
十 (43)
を得る。この場合の左辺を貨幣フローの限界効用の比率と解釈することは出来
ない。それは, (41)式にみるようにすでにau/aんによって定義されているか
らである。単純イbのため, 8= 0および ρ=0として考えると,この (42)およ
び(43)の両式は,貨幣ストックの限界効用が, (38)式を用いる場合 1ドノレから
得る消費の限界効用の二時点閣の差異に等しくなること,また (37)式を用い
る場合 1ドルから得る消費の限界効用と貨幣フローの限界効用との閣の違いの
OLIVE 香川大学学術情報リポジトリ
![Page 29: OLIVE ]ÝY'[f[f S`ÅX10ê0Ý0¸0È0ê 交換経済における貨幣](https://reader031.fdocument.pub/reader031/viewer/2022013009/61ce3b3c47e46a36c17b92d4/html5/thumbnails/29.jpg)
55 交換経済における貨幣 -55-
二時点閣の差異に等しくなるにとを,それぞれ均衡の条件としているにすぎな
いものといえる。すなわち,
au au 1 au 1
as;n aXt_lρf-18zzρ?
あるいは,
au / au 1 au¥/ au 1 au ¥ as"(' ¥ axト 1 jうト1 θlt-l J ¥ aXt ρ alt J
(44)
(45)
である。そこから貨幣フローの限界効用が恒常的に増加するという結論は何等
見出し得なし、。以上の (14) 式と (37) 式~ (39)式の体系においては, (36)式
にみる如くにクラクァーが言うよろな貨幣の受取りと支払いについての別個の
制約条件を設定することはしていなしでその意味で,それは不充分なものであ
る。しかし,それでもなお,貨幣のフローを導入しようとするとき,ニーハシ
ズの結論とは異なるものに到達することになる。
(30) 拙稿上掲論文香川大学経済論議第53巻第4号。
OLIVE 香川大学学術情報リポジトリ



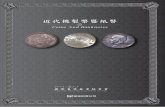







![OLIVE ]ÝY'[f[f S`ÅX10ê0Ý0¸0È0êshark.lib.kagawa-u.ac.jp/kuir/file/3770/20120327035236/... · now understood to be the key point for determination ofthis fundamental biological](https://static.fdocument.pub/doc/165x107/5e78c3abce3267581e147966/olive-yff-sx100000sharklibkagawa-uacjpkuirfile377020120327035236.jpg)







