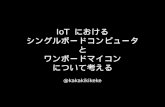行政手続におけるオンラインによる本人確認の手法 に関するガイ … · 行政手続におけるオンラインによる本人確認の手法 に関するガイドライン.
日本におけるオープンエデュケーションの課題 ―大...
Transcript of 日本におけるオープンエデュケーションの課題 ―大...
17
1. TIESの歴史
我々のオープンエデュケーションの活動は、1996年に帝塚山大学1経済学部の教員の、“大学の講義をホームページで公開してみよう”というアイデアから始まった。ようやく、各機関でホームページ開設が開始されたばかりで、eラーニングという言葉すら、まだなかった時代だった。
1998 年に、このアイデアは、大学プロジェクトとして推進されることになり、大学の講義 資 料 を Web サ イ ト で 配 信 す る TIES
(Tezukayama Internet Educat iona l Service)を一般公開した。
その後、TIES を練習問題や学習履歴の記録も可能な e ラーニングシステムに改良し、1999 年には、甲南大学、関西学院大学、武蔵大学、成蹊大学、帝塚山大学の 5 大学連携による講義公開へと発展した。そして、2001年には、高等教育機関へ TIES を ASP 方式にて無償提供することで、その活動をさらに拡大していった。
当時は、MIT による OCW、ユネスコによる OER が開始されていたが、いずれも教材や講義ビデオ、シラバスなど学習リソースの公開に止まっており、TIES に見られる大学の講義を e ラーニングシステムで公開する活動は非常に、革新的であった。
2006 年には、NPO 法人 CCC-TIES2 を設立し、このオープンエデュケーションの活動を支援していくことになった。
2. TIESのビジョン
インターネットの普及が加速した 1999 年当時、我々には教育こそが高密度の情報であ
り、インターネットと融合することで、大学教育のあり方を変えることができるのではないか、という期待感があった。
そこで、我々は、“連携・共有・公開” をキーワードに掲げ、組織を超えた大学教員の教育コミュニティにより、システム・コンテンツ・ノウハウを共有し、そこから生まれた教育を広く公開することで、高等教育の改善・改革ができると考えた。
図 1 設立当時の TIES の Principle
また、我々は、教員が安心して ICT 教育に取り組める環境を “e ティーチング環境”とし、e ティーチング環境の整備には、誰でも無料で利用できる e ラーニングシステムと組織的なシステム運用・支援体制が必要であるとした。
そこで、e ティーチング環境を整備し、教育コミュニティを活性化することにより、教育方法の質、教員の教育力、そして教育の質を高めていく事を活動の基本理念とした(図1)。
TIES のこのようなビジョンに賛同し、参加大学、参加教員は 2011 年度に、83 大学1,275 人にまで増加した。(図 2)
日本におけるオープンエデュケーションの課題―大学コンソーシアム TIES のケースタディ―
堀 真寿美NPO 法人サイバーキャンパスコンソーシアム TIES 企画室長
概要:NPO 法人サイバーキャンパスコンソーシアム TIES は、1998 年より、オープンエデュケーションの先駆けとして大学連携による講義公開を実施してきた。しかし、補助金に頼った資金運営、ボランティアに基づいた事業運営、そして、大学のユニバーサル化への対応などの課題を抱えている。TIES の取組みと日本のオープンエデュケーションについて述べる。
キーワード : オープンエデュケーション
1 http://www.tezukayama-u.ac.jp/2 http://www.cccties.org/
18
図 2 TIES の拡大
3. TIESに見られるオープンエデュケーションの課題
2012 年に TIES のサービスは一時停止することとなった。理由は、十数年間スクラッチで作り続けてきたシステムが肥大化し、システム不良、セキュリティ等、システム上の課題が山積し、また、それに伴い、運用サポート体制が耐えきれなくなったためである。 以下に、2012 年時点での TIES が抱えていた課題を紹介する。
3.1 収支構造の課題
図 3 は、当時の TIES の収益構造である。収益の 6 割が補助事業の助成金である。経費のほとんどが、システム改修・修繕、そして運用サポートに係わる人件費であったため、補助事業に採択され続けなければ、活動が継続できない体制となっている。
その結果、活動の目的がオープンエデュケーションであったにもかかわらず、いつの間にか補助事業に採択されることが、活動の目的に変わって行った。
図 3 TIES の収益構造
3.2 教員のモチベーション
TIES の教育コミュニティは、TIES のビジョンに賛同する教職員のボランティアの活動が中心であった。しかし、そのボランティアによる活動には限界がある。
また、コミュニティメンバーの増加によりコミュニティメンバー間の意識の違いも発生してきた。
図 4 は、e ラーニングシステム TIES に登録された講義と、公開された講義の割合である。2004 年度には登録された講義の 30%近くが公開されているにもかかわらず、2011年度にはその割合が 15%にも落ちている。一方、登録講義数は年々増加し、2011 年度には 1800 件を超えている。多くの教員が、講義を公開せず、無償の e ラーニングシステムを本人の授業のために利用するようになった。
このことは、オープンエデュケーションを拡大できないばかりではなく、運用サポートに係わる経費の圧迫にも繋がった。
図 4 登録講義数と講義公開
3.3 教育市場の変化
図 5 は、教育市場の PPM(プロダクト・ポートフォリオ・マネジメント)である。横軸がシェア、縦軸が成長率である。
ニューヨークタイムスによって、“The Year of the MOOC” と名付けられた2012年、オープンエデュケーションは、まさに成長期にあり今後、拡大、発展が期待できる分野であると考えられた。一方、世界の教育市場は、当時から急速に成長しており、MOOCs は、この世界の教育市場の成長の波に乗る形で出現してきた。また、日本の教育市場は、既に安定期に入り、今後の成長はそれほど見込め
19
ないものの一定の収益は確保できる分野であると考えられる。そして、既にコモディティ化した e ラーニングは所謂、負け犬プロダクトであると考えられる。
そして、オープンエデュケーションとしての活動を拡大できず、事業の中心が e ラーニングとなってしまっていた 2012 年度のTIES は、ここに位置してしまっていた。
図 5 教育市場の PPM
4. CHiLOプロジェクトの開始
我々は、システムを止めていた 1 年間で、スクラッチで独自に作っていた TIES をすべて回収して、オープンソースを利用して、全く新しいシステムとして改修した。
新しいシステムは、従来の TIES を踏襲した TIES V8 と、オープンエデュケーションを意識し従来の TIES とは全く違う発想により設計した CHiLO Book の、異なる二つのプロダクトからなる。
TIES V8 は、在校生の学習支援を目的とした e ラーニングシステムである。Moodle3
をベースに、従来の TIES が持っていた、ライブ機能、オンデマンドビデオ配信機能などの特有な機能を Moodle モジュールをカスタマイズすることで実現した。さらに、ASPで無償提供してきたサービス方式を取りやめ、オープンソースにて提供することとした。また、TIES V8 を導入した大学は、学認4 による統一認証基盤により、互いのシステムを連携できるため、大学間の教材共有、単位互換などのカリキュラム連携を可能とした。
一方、CHiLO Bookは、オープンエデュケーションを目的とした大規模オンラインコース
基盤として設計した。CHiLO Books は、電子書籍を学習のポー
タルとした、新しい形のオンラインコースである。学習者はダウンロードした電子書籍から、学認5 を経由し、教育機関に分散配置された TIES V8 の練習問題やフォーラムなどの学習リソースにアクセスし、学習することができる。電子書籍は、様々な形で手軽に配布ができるため、大規模なシステムがなくても、オンラインコースを提供することが可能である。(図 6)
図 6 CHiLO プロジェクト
5. オープンエデュケーションへの期待
TIES の新しいシステムは、2 つのプロダクトにより在校生に対する学習支援の活動とオープンエデュケーションの活動を分離した。
MOOCs の拡大にも見られるように、オープンエデュケーションは、今後、高等教育におけるキーワードの一つになると思われる。
我々は、2008 年に、新聞社と連携して、新聞広告やサイト広告で広く告知し、大学講義を期間限定で一斉公開する実証実験を行った。
この実証実験では、14 大学 104 本の講義ビデオを 40 日間に渡り配信したが、全国よりユニークユーザー数で 3 万人の人々がサイトを訪れた。日本においても社会人のオープンエデュケーション、特に高等教育に対するニーズは高いと思われる。
従って、我々の今後の活動は、オープンエデュケーション活動で得られたノウハウやコンテンツを、大学の学習支援に還元していくこととし、オープンエデュケーションを推進
3 https://moodle.org/4 http://www.gakunin.jp/ 5 http://www.gakunin.jp/