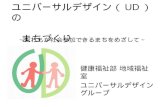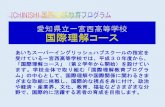令和元年度 杜の都のエコ・スクール活動報告 1 テーマ 「身近な … ·...
Transcript of 令和元年度 杜の都のエコ・スクール活動報告 1 テーマ 「身近な … ·...
-
令和元年度 杜の都のエコ・スクール活動報告
学校番号 011 学校名 仙台市立榴岡小学校 校長名 猪股 亮文
1 テーマ
「身近な物で命を救おう」
2 取組の紹介
ペットボトルキャップ回収
JRC委員会の児童が中心になって行っている活動です。毎月の委員会で回収日を決め,放送
やお便り,ポスターで全校児童に呼び掛けます。当日は,昇降口であいさつをしながら,登校す
る児童からペットボトルキャップを受け取ります。また,全校放送や掲示物を通して,回収した
キャップが世界の子供たちを救うワクチンとして役立っていることを伝え,より多く集められる
ように協力を呼び掛けました。
3 取組の成果(児童の変容) 委員会の子供たちの呼び掛けによって,毎回,かなりの量のキャップが集まります。委員会の
子供たち自身が,自分たちが取り組んでいる活動の意味を知り,エコ活動に対する意識が変わっ
たことで,やりがいを感じながら,より意欲的に活動する姿が見られました。
【児童の感想より】
・私は,JRC委員会に入るまでは,「こんなに小さな物が何になるんだろう?役に立つのかな?」と思
っていました。しかし,委員会に入り,子どもたちの食糧や学習用具,ワクチンなど,様々な物に変
えることができると知りました。今は,私達が集めている小さな物が世界の子供たちを救うことに役
立つことを,誇りに思うようになりました。これからもみんなで協力して,命を救うことに繋がる物
を集め続けていきたいです。
・以前まではペットボトルキャップをどうして回収するのかが分からなかったけれど,JRC委員会に入
って意味が分かり,より一層活動への意欲が高まりました。例えば,ペットボトルキャップを持って
くるのを忘れてしまった人に,「明日も回収やっているよ。」と声を掛けるなどし,少しでも多くの
人の命が救われるように頑張りました。
・早起きすることは苦手でしたが,ペットボトルキャップがどんどん集まっていくのを見て,達成感
を味わうことができました。さらにペットボトルキャップが集まり少しでも多くの人の命を救うため
には,校内のテレビ放送で活動内容を知らせたり,ポスターを作製したりし,より多くの人たちが協
力してくれるようにしたらよいのではないかと考えました。
・実際に活動をしてみると,早起きをしたり声を出し続けたりすることが大変でした。しかし,キャ
ップを持ってきてくれた人がいるととてもうれしく,キャップが増えていくにつれやりがいを感じま
した。これからは,更に多くの人に協力してもらうためにどのように努力していくとよいか,みんな
で考えていきたいです。
-
令和元年度 杜の都のエコ・スクール活動報告
学校番号 012 学校名 仙台市立八幡小学校 校長名 小石 俊聡
《3年生での取組》 総合的な学習の時間 「広瀬川となかよくなろう」 ○取組の紹介
八幡小学校の3年生では,身近にある広瀬川をテーマに,総合の学習に取り組んでいます。9月には,
校外学習で広瀬川に行き,実際に川の中に入って川の流れを感じたり,網を使って水生生物をとって観
察したりする活動をしました。また,より広瀬川を身近に感じることができるように,河川敷の石を拾
って,ペーパーウエイトを作成しました。
さらに,12月からは,サケの成長や広瀬川の環境についての学習をしています。ゲストティーチャー
をお招きし,顕微鏡を使って,サケの卵を観察したり,サケの成長についての講話を聞き,サケについ
ての理解を深めました。
○取組の成果(児童生徒の変容)
・広瀬川での活動を通して,自然と触れ合うことの良さ・楽しさを感じることができました。また,
広瀬川の自然や,そこに生息している生き物について学ぶ活動を通して,自然と共存していくための
基礎知識を学ぶことができました。
・卵から稚魚に孵化する様子を観察することで,命の大切さに触れることができました。孵化した後
も,毎日水槽を見に行き,サケがどのように成長していくのかを見守る児童の姿が多く見られまし
た。また,ゲストティーチャーをお招きしてお話を伺ったことで,サケが戻ってくる広瀬川の環境へ
と視野を広げることができました。
《環境委員会での取組》
○取組の紹介
環境委員会では,春と秋に花壇の植え替え,節電・節水の呼びかけのために環境委員会オリジナル
のエコキャラクターを作成して,ポスターに使用し呼び掛けるなど,よりよい学校環境にするための
啓発活動に取り組みました。
○取組の成果
水やりなどの手入れも自ら行っていたことで,校庭で遊んでいる他の児童も花に興味関心を持って
活動を見ている様子が見られました。また,オリジナルのエコキャラクターを校内のポスターに共通
して使用することで,電気や水を無駄にしないように気を付けている子供の姿を見ることができまし
た。
広瀬川での体験活動 広瀬川の水生生物 サケの卵の観察
-
令和元年度 杜の都のエコ・スクール活動報告
学校番号 013 学校名 仙台市立南小泉小学校 校長名 永井 一也
1 エネルギー環境教育の実践
2 取組の紹介
本校は, 経済産業省資源エネルギー庁より平成28・29年度エネルギー教育モデル校の認定を受け,
エネルギー環境教育を校内研究として取り上げ, 3年目の今年度も実践を重ねてきました。エネルギー
環境教育のねらいは, 「持続可能な社会の構築をめざし, エネルギー・環境にかかわる諸問題を通じて
エネルギー・環境問題に関する理解を深めるとともに, 技能を身に付け, その解決に向けて課題意識を
醸成し, 成長や発達に応じて, 主体的かつ適切に判断し行動できる資質や能力を養う」というねらいで
す。そのねらいは, 仙台自分づくり教育(キャリア教育)で育てたい力と合致しています。
エネルギーは, 全ての子どもたちの身近にあり, 生活をしていくために必要不可欠であり, エネル
ギー・環境について学習することは, 過去を振り返り, 今を知り, 未来を考えること, つまり生きるこ
とを考えることへとつながります。エネルギー環境教育を低学年は生活科の中で, 3年生以上は総合的
な学習の時間を軸に 取り上げたテーマに向けて, 各教科がそれぞれの特性を維持しながらテーマの追
求や課題の解決に向けてつながるクロスカリキュラムによって学習を深めていきました。
3 取組の成果(児童の変容)
1年生は, 学習テーマを「みずであそぼう」とし, 体験的な活動を通して水で遊ぶ楽しさ・面白さ, そ
して水の不思議さに気づくことができました。「電池であそぼう」では, 電池を使ったおもちゃなどで
遊びを通して気づきを自分なりに表現することができました。
2年生は, 「風と遊ぼう」をテーマにしたことから, 日常生活の中で風を意識して過ごすようになり
ました。また, ヨットカーなど風の力を上手に利用しておもちゃを作り遊ぶことで, 風の力に対する
様々な考えを出すことができました。
3年生は, 「太陽の力を使って」をテーマに, ソーラーバルーンやソーラークッカーを用いて学習し
自分たちで課題を見つけ, 情報を集め, 整理し, まとめて表現することができました。また, 昔と今の
エネルギーの使い方を考え, 今の生活が電気のエネルギーで成り立って便利だと理解できました。
4年生は, 3年生での学習を発展させ, 「電気はどこから」をテーマに主体的な活動や学習ができま
した。電気の通り道や電気をためることの難しさを実感しました。また, 東北電力との連携授業でも専
門的な知識を得ました。
5年生は, 「めざせ!省エネマスター」をテーマに, 自らを取り巻く環境問題やエネルギー事情を知
り, 日頃の生活の中で環境を考えながら実践可能な省エネ行動を学びました。
6年生は, 「未来をみつめて~私たちの未来を考えよう」をテーマに, エネルギーと地球環境問題や
これからのエネルギーミックスを考え, 自分たち未来のまちについて学習しました。課題設定・情報収
集・整理・分析し自分の考えを表現することができました。今までの学習を踏まえつつ, 未来への希望
を持ち, 取り組むことができました。自分の考えを持って社会参画しようとする態度を育てるだけでな
く, 生活とエネルギー・環境の関わりの考えも深めることができました。
特別支援学級は, 「太陽の力を知ろう」をテーマに遊びや体験を通して身近な自然や環境・エネルギ
ーに興味を持つことができました。
エネルギー・環境問題を学んだ子どもたちは, エネルギー・環境を身近な問題として捉え, 体験した
り探求学習したりと意欲的に学習し, 自分の考えを伝え合ったりして自己肯定感・自己有用感を育むこ
とができました。
-
令和2年度 杜の都のエコ・スクール活動報告
学校番号 014 学校名 仙台市立原町小学校 校長名 春日 文隆
1 取組のタイトル,テーマ(1行程度)
環境に優しいエコ活動の取り組み
2 取組の紹介
(1) 残食を減らす取り組み 原町小学校では残食を減らし,食への意欲・閑心を高めるために栄養職員が毎日「給食室から」というメニューの
紹介をしています。さらに給食委員会では放送やポスターで給食ができるまでの過程や食材などについて詳しく説
明をしています。その結果昨年4月~現在まで残食が明らかに減りました。給食への感謝の気持ちも高まりまし
た。
(2) ゴミの分別回収
各クラスでごみの分別回収を行っています。教室から出た牛乳のストロー袋等のプラごみを係児童が職員室前の
専用のポリバケツに捨てています。
(3) 社会環境から学ぶ〈4年生〉
原町小学校の4年生では,ごみ処理場やダムを見学し,生活環境について学びました。松森清掃工場では,ごみ
処理の仕方やリサイクルについて理解を深めました。毎日の生活から生じるごみの多さを実感するとともに,捨て
られたごみを処理する際に発生する熱を利用し発電していることも学習しました。
(4) 原町本通り花壇整備活動〈5 年生〉
原町小学校の5 年生は,地域の方と一緒に原町本通りの花壇の整備をしました。きれいな街作りの一端を担うこと
ができました。
3 取組の成果(児童の変容)
これらの日常的な活動や体験的活動を通して,子供たちは,地域や身の回りの環境を見直すことができました。普段からご
みの分別を意識し,食べ物を無駄にしないように残さず食べる児童が増えました。さらに皆が気持ちよく暮らすためにはどう
したらよいか考えるようになりました。
-
令和元年度 杜の都のエコ・スクール活動報告
学校番号 015 学校名 仙台市立長町小学校 校長名 髙橋 洋充
(1) テーマ 長町環境教育活動
(2) 今年度の取組 長町小学校では以下の3点について主に取り組んできました。 ① ゴミの有効活用
今年度も学校全体でゴミの分別やリユースに取り組んでいます。各クラスや職員室ではゴミ箱を
2つ設置して,児童や職員が簡単にゴミを分別できるようにしています。また,職員室では紙ゴミ
を集めたり古紙を再利用したりしています。理科室では,ペットボトルや空き瓶を理科実験に再利
用しています。
理科室でのリユース 教室のゴミの分別
② 委員会の取組 委員会では,ボランティア委員会での「ペットボトルキャップ集め」,四季山の清掃,環境緑化委員
会での「校内花壇の整備や花の苗や球根の植え付け」などを行ってきました。 緑化委員会による花壇の整備 ボランティア委員会で集めたペットボトルキャップ
③ 学校の環境整備 子供たちにとって憩いの場になっていた「築山」に昨年度「四季山」と命名し,本年度,環境緑化
事業の協力を得て,さらに親しみやすい環境に作り上げました。四季折々の景色が,子供たちを和ま
せてくれています。
(3) 成果と課題
・ボランティア委員会では,ペットボトルキャップリサイクル回収に向け,校内放送での呼びかけやポ
スターの掲示など啓蒙活動に力を入れてきました。その結果,たくさんのキャップが集まり,全校児
童のエコに対する意識も高まってきています。今後は,節電・節水などにも力を入れていきたいと思
っています。
-
令和元年度 杜の都のエコ・スクール活動報告
学校番号 016 学校名 仙台市立向山小学校 校長名 三浦 敏光
1 取組のタイトル 「地域の特色を生かした環境活動」~ 地域との連携 ~
2 取組の紹介
(1) どんぐりの森づくりプロジェクト
地域にある野草園と連携した活動で,生活科の学習の中で「環境教育」として行っています。
1,2年生の児童が向山中央公園でどんぐりを拾ってポットに植え,野草園の皆さんの御協力の
もとに苗木を育てる活動です。数年後に育った苗は,希望する児童と保護者が,東日本大震災で
被災した海岸公園などに市民の方々と協力して植栽しています。どんぐりの森をつくる自然の営
みの大切さを学び,震災前の自然豊かな森を取り戻すことを目的としています。
(2) 広瀬川の生き物観察
4年生の総合的な学習と理科を関連させた「環境教育」として,学区に近い広瀬川の生き物観
察の学習を行いました。広瀬川の上流・中流・下流に生息している生き物について教えていただ
き,自然環境に適応しながら生物が生きていることを学びました。その後,講師の方と保護者ボ
ランティアの皆さんの御協力のもとに,実際に広瀬川に入って生き物を見付ける活動を通して,
川の生き物と自然環境が深く関わっていることを自分たちの目で確かめることができました。川
の変化に応じて生き物が生息していることから環境を守る大切さを知り,更に自分で決めた課題
を調べてまとめました。
(3) 大念寺山伊達家歴代御廟落ち葉拾い清掃
ボランティア活動として,学区にある伊達家歴代御廟の清掃活動に参加しています。伊達家の
歴史に触れながら落ち葉清掃を行い,カブト虫の幼虫を発見するなど一年を通じて自然の中で生
き物の命が育まれていることを体験することができました。
3 取組の成果(児童の変容)
野草園,向山中央公園,広瀬川など自然環境に恵まれた地域であることから,地域の方々と連
携して自然の様子に興味・関心を高めることができました。どんぐりを育てている向山中央公園
は児童の遊びの場所ともなっていることから,日常生活の中でどんぐりの成長の様子が分かり,
水やりを手伝う姿も見られます。自分たちが植えたどんぐりが学区から離れた海の近くに植樹さ
れることで自然環境の連鎖に気付くこともできるようになってきました。向山の丘陵地から広瀬
川,海へと地域から環境を考える態度と環境について考えようとする気持ちが育ってきています。
-
令和元年度 杜の都のエコ・スクール活動報告
学校番号 017 学校名 仙台市立北六番丁小学校 校長名 伊藤 敏子
1 取組のタイトル,テーマ
学級,学年,全校と繋がるエコの輪
2 取組の紹介
○グリーンデー活動
グリーンデー活動とは,春と秋の年2回行われる校庭の美化活動です。たてわり班ごとに割り振られ
た場所で,異学年で協力して草取りや落ち葉拾いをします。グリーンデー活動の際には,たくさんの草
や落ち葉を集めようと一生懸命児童が活動しています。
秋のグリーンデー
○ごみの分別の取組
各クラスに「燃えるごみ」と「プラごみ」のごみ箱を1つずつ設置し,児童は捨てるものによって
ごみ箱を使い分けています。低学年など,どちらに捨てて良いか判断できないときには,学級全体で
確認するなど,指導の機会にもなっています。児童が分別の仕方を学び,各クラスがきちんと分別を
行うことで,学校全体でのごみの分別が容易になっています。
○エコ・ハッピーまつり
縦割り活動の一環で,ゴミとして捨ててしまう物を再利用して,みんなで遊ぶという学校行事を行っ
ています。エコ・ハッピー祭りでは,3~6年生の児童がお店を開き,1・2年生の児童を招待したり,
3~6年生の児童がお互いのお店で遊んだりします。
3 取組の成果(児童の変容)
○グリーンデー活動
「自分達の通っている学校をきれいにしよう。」という思いや,「安全に過ごせる校庭にしよう。」と
いう思いが強くなっていると感じます。休み時間に,落ち葉拾いの声掛けをする児童の姿も見られま
す。
○ごみの分別の取組
ストローの袋や,レジ袋が落ちていると,「プラごみだからリサイクルしないと。」と,プラごみ
のゴミ箱に入れている児童の姿が見られ,資源の再利用の意識の高まりを感じています。また,給食
の際に,当番が,「ストローの袋を落とさないでください。」と声掛けしている姿も見られます。
○エコ・ハッピーまつり
新しい物を買わなくても,今ある物で遊ぶことができ,物の再利用・再使用の思いが強くなってい
ると感じます。また,物を大切にする思いを養うことで,ゴミを減らすことにも繋がっているように
感じます。
-
令和元年度 杜の都のエコ・スクール活動報告
学校番号 018 学校名 仙台市立西多賀小学校 校長名 近澤 裕子
(1)取組のタイトル 「環境を大切にするきれいな学校作り」
(2)取組の紹介
① 可燃ごみ・プラスチックごみの分別
各学級で可燃ごみとプラスチックごみの分別に取り組みました。教室でも,可燃ごみとプラスチック
ごみのごみ箱を分けて,分別して捨てることができるようにしています。校内のごみが集まるごみ置き
場に可燃ごみとプラスチックごみの掲示をし,児童は掃除のときなど分別を意識してごみを捨てていま
す。校内のごみ置き場は,大きな文字で表示が分かりやすく,学年を問わず分別しやすい環境が整って
います。可燃ごみのごみ箱の数を増やしたり,近くにほうきやちりとりを置いたりして,校内美化にも
努めています。
② 資源リサイクル運動 ペットボトルキャップの回収
ボランティア委員会が中心となり,ペットボトルキャップの回収
を行いました。ポスターやちらしで全校児童に協力を呼び掛けま
した。毎月,多くのペットボトルキャップが集まり,家庭と連携し
た活動となっています。回収したキャップは,業者の方に引き取っ
ていただき,洋服などの資源に再利用されます。
③ 環境緑化活動 緑化委員会を中心として,花壇の整備,花の苗や球根の植え替え,世話を行いました。今年は春と秋
にPTAと連携して花の苗を植えました。PTAからも多くの方が参加し,学校と地域全体で緑化活動を行
いました。また,今年度も緑化委員会の児童が近隣の中学校で行われた「花いっぱい運動」に参加し,
花の植え替えを行いました。
(3)取組の成果
ゴミの分別や資源のリサイクル活動を行うことで,児童一人一人がエコについて考え,実践するこ
とができていました。環境緑化活動の一つである「花いっぱい運動」では,保護者の方々と協力し,
色とりどりの花や緑で溢れる学校作りをすることができました。
-
令和元年度 杜の都のエコ・スクール活動報告
学校番号 019 学校名 仙台市立中田小学校 校長名 千葉 博久
1 取組のテーマ
身近な環境に興味を持ち,自分にできることを考えて行動しよう
2 取組の紹介
(1)各学年の活動
1年生…生活科の学習でアサガオを育てたり,つるを使ってリースを作ったりしました。また,
どんぐりや松ぼっくりを使っておもちゃを作り,近隣の保育園園児と一緒に遊びまし
た。
2年生…図工で色や形の違う落ち葉を集め,画用紙の上に並べて楽しみながら作品に仕上げまし
た。
3年生…理科でピーマン,ヒマワリ,ワタなどの植物を育て,観察しました。種子から枯れるま
での植物の一生について理解を深めました。
4年生…社会科で茂庭浄水場,葛岡清掃工場で学びました。ゴミ処理,リサイクルの仕組みや資
源を節約することの大切さを学びました。
5年生…総合的な学習の時間では,防災について調べました。自分ができることがないか考え,
模造紙やプレゼンテーションソフトにまとめて発表をしました。
6年生…理科で人の生活と空気・水・植物との関わりを学びました。それらを生かし,これから
も地球で暮らしていくためにどう行動すべきか考え,まとめる予定です。
わか竹…大根や人参などの野菜を植え,毎日水やりを行うなど継続して栽培しました。収穫した
野菜を使って豚汁を作り,「わか竹レストラン」を開き,お世話になっている先生方に
食べてもらいました。
(2)委員会の活動
栽培委員会が学校花壇に植える花を選んで,春から秋まで季節ごとに苗の植え替えと世話を行
っています。また,花の花言葉を調べてポスターにまとめる活動も行いました。福祉委員会は,
全校生徒に使用済みの切手の回収を呼びかけ,再利用してくれる団体に送る活動もしました。
(3)学校園の活用
各学年の花壇に花や理科教材のホウセンカ,ヒマワリ,ヘチマなどを植えています。近隣の保
育園に学校園の一部を貸し,保育園とも協力して,花や緑が豊かな学校になるよう努めました。
3 取組の成果
上記の取り組みに加えて,各教科,総合的な学習の時間,特別活動など様々な教育活動において
自然に親しむ学習活動をしたり,エネルギー資源についての学習をしたりすることで,子供たちに
身近な環境を大切にする気持ちが育っています。
-
令和元年度 杜の都のエコ・スクール活動報告
学校番号 020 学校名 仙台市立六郷小学校 校長名 加藤 徹
1 取組のタイトル,テーマ
「給食を通して,感謝の心,食べ物の大切にする気持ちを持とう!」
2 取組の紹介
六郷小は自校給食校です。給食時間が近付くと,いつも美味しいにおいが食欲を誘います。作る人との距離
が近く直接言葉を交わすことができるのも,自校給食校のよさです。
栄養教諭は,給食の時間に各クラスを回って直接声をかけたり,昼の放送で給食についての話をしたりして
います。また,担任も栄養教諭の言葉を受け,児童の指導にあたっています。児童の素直さと栄養教諭や担任が
食育に力を入れているため,残食率の平均は約6%とそれほど多くはありません。
1月の給食週間では給食委員会を中心とした取組が行われています。給食について理解を深めるだけでなく,
関わる方々に感謝を伝える機会です。今年は,栄養教諭の発案の下,残食を減らすための取組を行いました。栄
養教諭による「残食のゆくえ」を知らせるVTRを見た子供たちは,驚きの声を上げていました。
これらの取組から,給食により感謝し,食べ物を大切にする心を養い,残食をしない意識を持たせたいと考え
ました。
3 取組の成果(児童の変容)
「苦手な食べ物が給食出たとき,あなたはどうしますか」という質問に対し,給食
週間前は,「少しは食べるが残す」「一口も食べずに残す」と答えた児童が51%でし
た。給食週間後のアンケートでは「残さず食べる」が57%と8%増加しました。
残した給食の行方を聞いた質問においては,給食週間前は,知っている児童は24%
しかいませんでした。給食週間後に実施したアンケートでは,「給食週間を通して,
給食を残すことに対する考えは変わりましたか」という質問に,76%の児童が「とて
も変わった」「どちらかというと変わった」と答えました。自由記述からも「ゴミに
なり捨てられてしまうのはもったいないから食べる」や「届けてくれる人,作ってく
れる人に失礼にならないよう残さず食べる」と答える児童が多くいました。
また,給食週間中の残食率は4.3%と,事前に比べて1.7%も減少しました。これら
のことからも,給食週間の取組を通して,残食を少しでも減らそうと意識する児童が
増えたということが言えます。
今回の調査を通して,児童から残食に対し「もったいない」という言葉が聞かれま
した。人の思いを大切にする意識を持って,実際に食べ物を大切にする児童を育てて
いきたいと思います。一週間という限られた期間での実践でしたが,日頃から栄養教
諭や担任の食に関する指導があってこその結果だと考えます。これからも自校給食校
というメリットを生かし,六郷小ならではの取組を続けていきます。
49%44%
7%
残さず食べる少しは食べるが残す一口も食べずに残す
感謝の手紙 テレビ放送を真剣に見入る児童 児童が作成した給食ルーレット 残した給食はどうなるの?スライドより
57%37%
6%
残さず食べる少しは食べるが残す一口も食べずに残す
苦手な食べ物が給食出たとき,
あなたはどうしますか
前
後