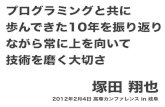「長良川中流域における岐阜」の 地下水と生業空間...
Transcript of 「長良川中流域における岐阜」の 地下水と生業空間...

「長良川中流域における岐阜」の 地下水と生業空間
周 鴻1・出村 嘉史2・神谷 浩二2
1学生会員 岐阜大学大学院工学研究科(〒501-1193 岐阜市柳戸1-1)
2正会員 工博 岐阜大学工学部社会基盤工学科(501-1193 岐阜市柳戸1-1,
E-mail:[email protected])
長良川中流域における岐阜市街地の領域は,2014年に国重要文化的景観に指定されたが,その根
底にある資源として重要であると考えられる地下水は,未だその特性と文化的な影響が確認されて
こなかった.本研究は,長良川の伏流水であるこの領域の地下水の流れと地下水温の分布について,
夏冬の気温の変化と逆行する領域があるという稀有な特徴をもつことを,実測により明らかにした
上で,これを用いた生業者がどのような空間を必然的に作ってきたのかを明らかにするものである.
それぞれの店舗における作業効率の向上を求めた結果,汲み上げた地下水を配水管で作業場まで導
水する仕方のパタンが,それぞれの場所における地下水の特性と適合していた.
キーワード :文化的景観, 長良川, 地下水, 井戸水温, 生業
1.研究の背景と目的
岐阜市の旧市街中心地は,中世の城下町にルーツを持
つ長良川河畔の金華山麓周辺である.このエリアが「長
良川中流域における岐阜の文化的景観」として,2014年
に国重要文化的景観に選定された(図-1)1).文化的景
観とは,「地域における人々の生活又は生業及び当該地
域の風土により形成された景観地で我が国民の生活又は
生業の理解のため欠くことのできないもの(文化財保護
法第二条第1項第五号)」と定義されており,その選定
にあたっては,8つの基準が設けられている2).岐阜の文
化的景観は,そのうち森林の利用,漁ろう,流通・往来,
居住に関する景観地であるとされ,図-2の構造的イメー
ジで捉えられている.しかし,こうした景観上の構成を
支えている基盤的要素のひとつと考えられる地下水を涵
養する地盤については,未だ明確な現象把握がされてお
らず,「長良川扇状地」と表現されるこのエリアの本質
的な理解には至っていないと考えられる.
そこで本研究では,1)未だ解明されていなかった長
良川扇状地における地下水の特性を明らかにした上で,
2)地下水との関わりとして形成される生業空間の特性
を整理し,3)地下の特性分布と地上における生業空間
の関係,あるいはその創成の可能性を探ることを目的と
する.ここで生業空間というのは,汲み上げた地下水を
直接的に用いて食品製造,サービス業などに用いる店舗
の建物の内部空間を指すものとする.
2.研究の方法
(1)対象地域
対象地域は,濃尾平野北部の長良川扇状地に位置する
図-2 長良川中流域における岐阜の文化的景観の構造イメージ図(『保存調査報告書』)
図-1 文化的景観対象地全覧図 (奈良文化財研究所景観研究室作成)
長 良 川
金 華 山

旧城下町の範囲であり,総称して金華地区といわれる
(図-1の長良川の南,左岸側の市街地).この市街地の
道の構成は,中世に山城が建設された当時のものが,ほ
ぼ継承されていると言われている.近世からは尾張藩の
保護を受け,長良川を主要な流通路として川湊をもつ商
業都市へと発達した.そこでの生業を支えた岐阜の町家
には,敷地表の店と奥に配置された土蔵との間の頻繁な
通行を可能にするため,広めの土間を設ける工夫が見ら
れる.町並みは1891(明治24)年の濃尾地震によって壊
滅的な被害を受けたが,ほぼ形を変えずに復興している.
近代には,このエリアと近接して,長良川鵜飼と金華山
登山,岐阜公園が観光の焦点となった.
地下水の状況については,G.L.-60mあたりに粘性土が
介在する部分があるものの,概ね厚い礫質土で構成され
ており,また扇状地範囲の河川堤防の基盤も礫質土で構
成されていることから,長良川の河川水が地下水に涵養
されていることが認められている3).
(2)地下水特性の調査
第一に対象地域における基本的な地下水の特性を明ら
かにするために,以下の調査を実施した.
対象地域内における18地点の既設消防水利井戸(深度
は約30m)を用いて,約3時間内で全地下水位を測定す
る一斉調査を2014年8月から翌年7月までの各月1回の頻
度で12回行った.
同時に,このうち16地点における消防水利井戸を用い
て,地下水温を同じタイミングで測定した.計測は,井
戸にロープ式水温計を投入し,地盤高から25mの深度で
行った.これらの消防井戸(調査地点)は,図-4に示す.
(3)店舗の実見およびヒアリング調査
対象地において地下水を利用している生業者が,どの
ように地下水を使用しているのか,そのための空間はど
のように構成されているのかを把握するため,以下の調
査を実施した.
第一に対象地域において現在営業している生業者の店
舗をできるだけ全エリアから均等に分布するように選定
し,協力の得られた10店舗を対象とした(図-3).
2014年9月から11月の期間に各店舗を訪問し,店主に
ヒアリング調査を行った.事前調査として4軒の店舗に
おいて意見交換と地下水に関する広範な質問をし,共通
項目や視点の整理を行った上で,鑿井の時期・井戸の深
さ・地下水の使い方・地下水の特性についての感覚・地
下水の利点と感じること・その他(地下水にまつわる伝
承など)に項目を絞り全件の調査を行った.
これと同時に,各店舗の地下水使用に関する空間の構
成を実地観察し,平面図に描画して,利用の方法が井戸
から作業場へ至る空間に及ぼす物理的な影響を考察した.
3.地下水の特性
図-4は,2014年8月の地下水位測定値に基づき描いた
地下水位等高線およびこれらに直交する流線を示したも
のである.河川水位は調査時間範囲における平均水位で
あり,その間の変動幅は, 大でも10cmであった.他
の月においても同様に北東から南西へ向かって下がる等
高線分布を描き,月比較では図-4に示した8月が 低水
位,3月が 高水位を示した.これは河川水位と比較す
ると正の相関を示す(図-5).ここで,図中の地点A~
Dは図-4に示した地点における値である.
図-6は,2015年1月と7月の地下水温の測定値を用いて
描いた平面分布を示したものである.図中には各調査日
の日平均気温(℃:岐阜地方気象台)を併記した.
(a)の冬では河川近傍や南部の領域で 15℃程度になる
が中央あたりの山地付近で 18~20℃と高めになる領域
が存在する.対照的に(b)の夏には,河川近傍で15℃
程度になるが中央の山麓(伊奈波神社門前あたり)に
10~12℃と低めになる領域がある.一年間のデータを通
して,この中央の山麓の領域では,夏により低くなり冬
により高くなる傾向にあり,気温と比べると夏冬が逆転
する現象が確認された.
図-7は,長良川の日平均水温(2014年1月~2015年5
月)の値と図-4の地点A~Dのそれぞれについて測定し
た地下水温の値を示したものである.図中の実線は,次
の式(1)による関係4) を描いている.
tTTT tw 365
2sin (1)
図-3 対象領域の商業店舗と調査対象店舗の分布
0 500m
商業店舗
対象店舗
玉井屋
両香堂
公園の湯
湯葉勇
かわらや
かわらや支店
後楽荘
徳広
麩兵
旧麩兵
高松屋伊奈波神社
長 良 川
金華山
N

ここで,T(℃)は河川あるいは地下水の水温,Tw
(℃)は河川あるいは地下水の平均水温,ΔTt(℃)は
河川あるいは地下水の水温変動の振幅,α(日)は河川
あるいは地下水の水温変動の位相である.
地下水温は,河川水温と同様に1年間の周期で変動し,
その平均値は河川の平均水温に対して±1℃程度の近い
値を示す.一方で振幅比は,地点Aで 0.69,地点Bで 0.53,
地点Cで 0.53,地点Dで0.19と南へいくにつれて減衰し,
河川の位相の値からの地下水の位相のずれは,地点Aで
63.4日,地点Bで 142.8日,地点Cで 172.0日,地点Dで201.8
日と大きくなる.
これらの計測により,対象地域の地下水は,長良川よ
り北東地点から流入した伏流水であることが再確認され
た.さらに,流入時の気温が反映された地下水がその温
度を保ちながら約半年かけてエリア中央の山麓へ到達す
るために,気温と地下水の季節逆転が観察される,極め
て特色のある性質を持つことが見出された.
4.生業における地下水特性の認識
本調査を行う上で,1) 地下水と水道水で何らかの使い
分けを意識しているか,2) 地下水に対してどのようなイ
メージを持っているか,さらには地下水を使用する際に
暗黙に従っている何らかのルールが存在するか,3) 店舗
の立地場所毎に地下水の利用特性に異なる特徴が見出せ
るか,という視点に留意した.10 軒(ただし,麩兵お
よび徳広は現在主として店舗に使用していない旧店舗に
ついても対象とした)の店舗に対して実施したヒアリン
グ調査の結果は,表-1の通りである.すなわち,以下の
ことが把握できる.
第一に,地下水は在って当たり前の資源と捉えられて
おり,進んで利用をするものの,地下水環境の保全のた
めに具体的に実施している行為は,ほぼないと言ってよ
い5).それは他地域に見られるような深刻な伝染病の蔓
延などが,少なくとも住人の記憶には存在しておらず,
これまでのところ地下水が豊富かつ安全な資源であり続
けているためと考えられる.しかし持続的な利用を考慮
図-7 長良川および地下水の水温の周期的な変化
図-4 地下水位(T.P.m)等高線(2014年8月)
図-5 河川水位と地下水位の相関性
長良川の
河川水位(T.P.m)
(長良観測所)
地下水位(T.P.m
)
図-6 地下水温(℃)分布(2015年1月14日と7月22日)

表-1 ヒアリング調査の結果
店
舗項
⽬⽟
井屋
公園
の湯
両⾹
堂湯
葉勇
かわ
らや
本店
後楽
荘か
わら
や⽀
店料
理徳
廣料
理徳
広別
館旧
麩兵
麩兵
⾼松
家
井⼾
を掘
った
時期
1980
年代
1930
年代
(×
)20
00年
代18
90年
代19
7519
2419
87(
2本)
1990
年代
(東
)19
60年
代(
南⻄
)19
9719
20年
代20
00年
代19
60年
代18
90年
代19
8519
70年
代19
80年
代(
再掘
)
凡そ
の井
⼾の
深度
(m
)20
m10
(×)
30浅
井⼾
不明
不明
(古
井⼾
)30
(新
井⼾
)10
309(
調理
場)
25(
敷地
奥)
930
9040
(当
初20
)
凡そ
の井
⼾の
⼝径
(cm
)不
明25
2520
30(
古井
⼾)
80(
新井
⼾)
2530
2525
5020
25
建物
の建
築年
代18
90年
代19
91増
設18
90年
代19
75(
改築
)19
24・
1987
(増
改築
)
1898
(中
央の
建物
)19
22(
⻄の
蔵)
1950
(東
の建
物)
1971
(南
⻄の
座敷
)
1965
1997
(改
築)
1920
年代
1960
年代
1890
年代
1985
1980
年代
雑⽤
、飲
⽤、
商業
⽤雑
⽤、
飲⽤
、商
業⽤
雑⽤
、飲
⽤雑
⽤、
飲⽤
、商
業⽤
雑⽤
、飲
⽤、
商業
⽤雑
⽤、
飲⽤
、商
業⽤
雑⽤
、飲
⽤、
商業
⽤雑
⽤、
飲⽤
、商
業雑
⽤、
飲⽤
、(
商業
)雑
⽤、
飲⽤
雑⽤
、飲
⽤、
商業
⽤雑
⽤、
飲⽤
、商
業⽤
・⼩
⾖(
さら
す、
こす
)・
⼀度
タン
クへ
上げ
て使
⽤・
年1度
清掃
・商
業⽤
も⽣
活⽤
も井
⼾⽔
・貯
⽔し
た井
⼾⽔
を蒸
気
ボイ
ラー
で温
める
・年
1回
の⽔
質検
査・
⼤型
軟⽔
器は
塩⽔
で
⽉1
回洗
う・
軟⽔
器を
通す
と⽢
くな
る・
排⽔
前は
温度
をと
り
下⽔
道へ
流す
・洗
濯、
台所
・5
年前
菓⼦
製造
に井
⼾⽔
使
わな
くな
った
・問
題は
ない
(⽔
質検
査)
・⼤
⾖(
もど
す)
・⾖
乳・
料理
、⽔
まき
(⽣
活⽤
)・
商業
⽤30
00L/
⽇を
利⽤
・料
理⽤
(古
井⼾
)・
調理
場は
井⼾
⽔だ
け・
⽣活
⽤、
洗い
場⽤
(
新井
⼾)
・新
井⼾
は屋
上タ
ンク
へ
⼀度
上げ
てか
ら使
⽤・
年1回
の⽔
質検
査・
古井
⼾は
その
まま
使⽤
・抹
茶、
料理
、⼿
洗い
・昔
は各
部屋
に⽔
冷式
ク
ーラ
ー
(湿
度、
⽔滴
が周
り
を
腐ら
せる
)・
⽣活
⽤⽔
は南
⻄の
井⼾
・調
理場
付近
の井
⼾は
お
茶室
、庭
・2
本の
井⼾
はパ
イプ
で
連接
︓冗
⻑性
・微
量の
塩素
で衛
⽣管
理
・う
なぎ
を「
たて
る」
(
餌絶
ち7-
10⽇
井⼾
⽔)
・井
⼾⽔
を冷
やし
て飲
む・
料理
、⽔
まき
(⽣
活⽤
)・
年1
回の
⽔質
検査
・⽔
冷式
の冷
蔵庫
(
使⽤
後は
外部
側溝
へ)
・汚
⽔は
下⽔
へ・
特殊
な浄
⽔器
をつ
けた
・排
⽔は
下⽔
へ流
す・
年1回
の⽔
質検
査・
昔⽔
冷式
クー
ラー
を使
⽤・
だし
は必
ず井
⼾⽔
・タ
ンク
を使
⽤・
配管
の各
箇所
にコ
ック
を
設け
メン
テナ
ンス
し易
く
・年
1回の
⽔質
検査
・2
階に
座敷
を設
ける
時に
厨
房と
して
⽤い
る流
しは
地
下⽔
利⽤
・料
理、
⽔ま
き等
(
⽣活
⽤)
・地
中配
管
・井
⼾・
⽔道
を使
い分
け・
麩(
50%
は⽔
分)
(
原料
およ
び冷
却媒
体)
・製
造⼯
程を
通し
て⽔
に
浸し
てお
かね
ばな
らな
い・
何に
でも
使⽤
・商
業⽤
には
塩素
酸ソ
ーダ
を
⼊れ
る・
地中
配管
・⽔
冷式
クー
ラー
使⽤
・年
2回
の⽔
質検
査・
うど
ん(
こね
、し
める
)・
だし
「井
⼾⽔
のは
最⾼
」・
うど
んに
は⽔
が重
要な
要
素(
⽔+
塩+
粉)
地下
⽔の
特徴
味、
温度
、イ
メー
ジ、
季節
・今
昔の
変化
・⽔
道⽔
より
井⼾
⽔ぬ
るい
⽔
道⽔
が冷
たい
・温
度は
5〜
7⽉
13
℃
10
⽉1
5℃
・⽔
質は
ずっ
と変
わら
ない
・か
つて
浅い
井⼾
だっ
たが
安
定性
が⼼
配で
掘り
直す
・⼤
垣と
⽐べ
て⽔
は少
ない
・⽔
温は
⼀定
のは
ずが
、
夏は
冷た
く冬
は暖
かい
・井
⼾を
使う
際天
気に
留意
・春
先や
夏、
⾬が
少な
いと
井
⼾が
「か
らか
ら」
鳴る
そ
の際
は気
を付
けて
使う
・⾬
の⽇
は出
やす
い
・⾬
が多
いと
⽔質
が悪
い・
冷た
くて
おい
しい
・無
味無
臭
・新
旧井
⼾で
⽔質
同じ
だが
味
が変
わら
ぬよ
う旧
井⼾
を
維持
・夏
は冷
たく
冬は
暖か
い・
⽔が
おい
しい
と⾔
われ
る・
新井
⼾2
本は
道路
側
(施
⼯の
便宜
)
・昔
はよ
くお
いし
いと
⾔
われ
た
(使
⽤頻
度に
よる
)・
温度
は⼀
定の
はず
が、
夏
は冷
たく
、
冬は
暖か
く感
じる
・⽔
の仕
事に
は好
都合
・味
は変
わる
感じ
がな
い・
温度
は季
節の
変化
感じ
る
・井
⼾⽔
の様
⼦は
変化
なし
・⽔
が豊
富、
掘り
すぎ
る
とダ
メ・
おい
しい
、⽔
質が
よい
・炊
飯に
適し
てい
る・
⽔質
を気
にし
ない
・夏
は冷
たく
冬は
暖か
い
・深
さで
⽔質
の変
化な
い・
おい
しい
・濁
った
時期
もあ
る・
⽔質
が地
層で
違う
らし
い・
⽔質
の良
さが
⾃慢
・19
90 六
甲の
おい
しい
⽔
と⽐
較︓
六甲
は臭
くて
飲
めな
い・
無味
無臭
、美
味し
い・
15℃
以下
が理
想
・温
度が
12℃
程度
で⼀
定
のは
ずが
夏は
冷た
く
冬は
暖か
く感
じる
・井
⼾⽔
の様
⼦は
変化
なし
・⽔
質に
変化
はな
いが
、
20m
の井
⼾の
⽔質
の
安定
性が
⼼配
で40
mに
掘
りな
おし
た・
美味
しい
地下
⽔の
メリ
ット
・井
⼾は
常に
おい
しい
・消
毒臭
くな
い
・⽔
は美
味し
い、
枯れ
ない
・⼤
量に
使う
ので
コス
ト
が安
いこ
と・
⽔質
が良
い
・お
いし
い・
夏で
も井
⼾⽔
は⼿
が
痛く
なる
ほど
冷た
い
・⽔
きれ
い、
⽔質
良い
・⽔
質汚
染の
⼼配
は少
ない
・無
味無
臭、
⽣産
に良
い・
⼤⾖
には
⽔質
の影
響が
⼤
きい
・夏
は冷
たく
冬は
暖か
く
作業
に好
都合
・流
しっ
ぱな
しで
もコ
スト
が
かか
らな
い・
おい
しい
・コ
スト
⾯・
冷凍
庫で
早く
凍る
・豊
富に
使え
るこ
と・
冬は
⽔が
温か
くて
作業
に
良い
・お
いし
い
(名
古屋
のは
飲め
ない
)
・⽔
源が
豊富
・温
度が
低い
・低
コス
ト
・こ
こで
作っ
たう
どん
と
⼤阪
で作
った
うど
んは
透
明感
・味
が違
う
地下
⽔の
デメ
リッ
ト・
ない
・か
つて
少し
砂が
混じ
った
・井
⼾枯
れの
⼼配
・モ
ータ
ーの
故障
・ポ
ンプ
の故
障・
困っ
たこ
とが
ない
・周
辺環
境の
変化
が⽔
に
影響
する
⼼配
・20
年前
には
砂が
混
ざっ
たこ
とが
あっ
た・
商業
⽤の
⽔質
管理
必要
・ポ
ンプ
が壊
れる
時。
・⽔
質
(変
化の
可能
性)
地下
⽔に
関す
る伝
承・
慣例
、使
⽤上
のル
ール
・年
1回
掃除
・井
⼾に
対し
て使
⽤ル
ール
や
⽣活
習慣
はな
い・
⻑良
川の
影響
なし
・⽔
が枯
れる
こと
はな
い
・⽔
質検
査で
「最
⾼」
・川
向こ
うの
⽔は
「
にお
う」
・井
⼾に
対し
てお
飾り
する
・⽔
道⽔
は悪
くな
いが
、
井⼾
⽔と
飲む
感じ
が違
う・
⻑良
川の
恩恵
を受
ける
・井
⼾を
あま
り話
題に
は
しな
い
・毎
⽇井
⼾飾
りは
する
が
⼤き
な祀
りは
しな
い・
⽔の
神様
に感
謝の
気持
ち・
ポン
プの
負担
が⼤
きく
空
気が
⼊り
やす
いた
め、
井
⼾か
ら遠
くで
は
使わ
ない
・か
つて
家の
前に
防⽕
⽤
ポン
プ
⽔を
定期
的に
出す
のが
⼦
供の
仕事
・何
にで
も井
⼾⽔
を使
える
・井
⼾は
埋め
ては
いけ
ない
・⽣
活の
中で
井⼾
⽔が
⼤事
・井
⼾の
上に
ふた
が必
要。
・井
⼾を
家の
奥に
置く
のは
縁
起が
いい
・正
⽉井
⼾に
鏡餅
を祭
る・
井⼾
⽔の
話あ
まり
しな
い
⽔が
出る
のは
当た
り前
・⿊
⾖を
炊く
には
井⼾
⽔
・昔
は井
⼾の
位置
を記
録・
井⼾
にお
飾り
はし
ない
・昔
は⽔
をよ
く汲
んだ
・使
うほ
ど出
やす
く
美味
しい
・井
⼾⽔
は⻑
良川
の⽔
・周
辺の
⼈は
井⼾
⽔の
良さ
を
認識
して
井⼾
⽔を
使う
・⽔
を惜
しま
ず仕
事で
きる
・⻑
良川
の伏
流⽔
とい
う
認識
・仕
事全
般に
つい
て祀
る
が、
井⼾
が対
象で
はな
い・
井⼾
位置
は⾃
分に
使い
や
すく
(メ
ンテ
ナン
スの
便宜
上)
・正
⽉飾
りお
供え
物等
の
⾏事
・井
⼾⽔
を使
う量
は減
って
も
、⽔
は出
る・
掘削
時お
酒で
清め
た・
井⼾
を家
の奥
に置
くの
は
縁起
がい
い・
周辺
はか
つて
⾖腐
家な
ど
多く
の店
が井
⼾使
⽤・
井⼾
は⽔
の神
様
⼤事
にす
る・
稲葉
神社
の神
主が
家に
対
して
毎⽉
御祈
祷す
る
・⻑
良川
の流
路の
関係
、
裏⼭
を⽔
道⼭
と呼
んだ
・⼦
供の
頃か
ら井
⼾⽔
を
おい
しく
飲ん
でき
た・
⽔の
渇⽔
の⼼
配が
ない
、
⽔の
冷た
いエ
リア
・掘
れば
⽔が
出て
くる
、
伏流
⽔の
上に
住む
イ
メー
ジ・
使⽤
ルー
ルは
特に
なし
・井
⼾を
家の
中央
に掘
る
のは
よく
ない
・⽔
が良
くて
ここ
を選
択・
⾦華
⼭と
⻑良
川か
らの
⽔・
地下
⽔が
あっ
ての
商売
・地
下⽔
をお
ろそ
かに
で
きな
い
過度
の使
⽤は
戒め
る・
お飾
りは
しな
い・
近所
と井
⼾⽔
の話
しな
い
上⽔
道の
利⽤
状況
・洗
い場
に使
う。
・⽔
道⽔
は補
助⽤
・蒸
気ボ
イラ
の中
は⽔
道⽔
・作
業場
⽤は
全部
⽔道
⽔・
⽣活
⽤(
停電
時)
・成
膜・
湯葉
のひ
きあ
げ・
作業
の終
わり
に作
業場
を
洗う
・あ
るが
ほと
んど
使わ
ない
・普
段あ
まり
使わ
ない
・ポ
ンプ
故障
時の
⾮常
⽤・
⽔道
⽔あ
まり
塩素
感
じな
い
・停
電時
ポン
プが
⽌ま
った
場
合・
作業
場を
洗う
・停
電時
に⽔
道⽔
を使
う・
夏は
渇⽔
時⽔
道⽔
を使
う・
洗い
場に
予備
で⼀
本蛇
⼝
・渇
⽔時
に使
⽤・
店舗
表に
⽔道
蛇⼝
・⽔
道⽔
は使
わな
い・
作業
の終
わり
に作
業場
を
洗う
・補
助⽤
・⽔
道⽔
は⾮
常⽤
・⽔
道⽔
を使
う際
には
う
まく
いか
ない
・⽔
に対
して
危機
感
店の
⽴地
の理
由+
A10A
5:M
13
・も
とは
旅籠
屋だ
った
、
その
井⼾
を使
って
始め
た・
末広
町あ
たり
繁華
町
・⽔
がよ
いか
ら・
もと
は造
り酒
屋・
紙問
屋・
本町
から
移転
︓
稲葉
⼭麓
に⿂
市場
地下
⽔の
使い
⽅
・井
⼾⽔
の様
⼦は
変化
なし
・美
味し
い・
掘れ
ば⽔
が出
る・
夏は
渇⽔
する
こと
もあ
る・
この
地域
は特
に⽔
温が
低い
・⽔
温は
⼀定
のは
ずな
のに
、夏
冷た
く冬
暖か
く感
じる
・⽔
脈は
⻑良
川よ
り下
にあ
って
、ひ
るが
の⾼
原あ
たり
の
雪と
つな
がり
があ
る、
とい
うイ
メー
ジ
・⽔
を無
駄に
使う
なと
⾔わ
れる
・昔
は家
庭に
井⼾
があ
った
・使
⽤ル
ール
なし
・⽔
神様
を祭
って
いる
・地
下⽔
は共
同の
もの
(
周辺
で掘
る時
には
挨拶
があ
る)
・冬
期、
⽔道
より
井⼾
の温
度が
⾼く
、
湯を
沸か
す時
など
の燃
料費
が安
い・
⽔道
より
井⼾
のほ
うが
良い
イメ
ージ
・掘
る深
度は
50m
より
25m
で良
い⽔
が出
た
・渇
⽔時

図-8 空間構成調査の結果一覧(建物内は全て1階平面)
public空間
semipublic空間
semiprivate空間
private空間
地下水を使用する場
導水管(地下埋設)
導水管(地上架空)
鑿井時期
井戸
給水タンク 0 20m

すれば,前章で見たように長良川との連続性を意識して,
川の環境保全とともに意識を高めていく必要がある.
次に,地下水の性質で利点と考えられていることは,
比較的多量の水を利用できる経済性と,夏は冷たく冬は
暖かいという温度であった.地下水の温度は一定である
という一般常識に従って,相対的な感覚であると考えら
れている例が多かったが,実際は前章で明らかにしたよ
うに,この季節と逆行する温度の感覚は絶対的なもので,
さらに活かしていくべき資源であると捉えられよう.い
ずれも水道水との比較によってその感覚が確かめられて
おり,それ故に地下水を主に使用して,水道水を補助利
用に留める店舗が大多数であった.
ただし,玉井屋・両香堂・湯葉勇など,地域内北側に
位置する河川近傍の店舗においては,地下水の味につい
ての優位性を認めながらも水道水を利用する頻度が高く
なっているなど,南北の分布において地下水の利用価値
の認識が異なっていることが見出された.地下水を溜め
る給水タンクの用い方が多様である点は,注目すべきで
ある.
水源に関するイメージとしては,長良川の下を通って
くる別の水脈であるとか,金華山の方からやってくるな
ど,どこか異様なイメージが一部介在していることはあ
ったが,総じて長良川の伏流水であることの認識は根底
にあった.
5.地下水を利用する生業空間の特性
現地における実見調査によって把握した空間構成の内
容を整理すると,図-8のようになる.ここで,地下水を
利用する際の建物内部の空間用途の背景を分かりやすく
するために,調査した店舗空間を「public-private」の秩序
で分類している.すなわち,不特定多数の人が自由に使
用できる外部空間(公有空間)を public空間とし,客と
して立ち入ることのできる空間をsemipublic空間,客に視
覚上は認識されるが立ち入ることのできない空間を
semiprivate空間,そして客に視認できない空間をprivate空
間と定義した.製造業の作業員のみが出入りする場所も
private空間に分類される.
空間の整理をする際に着目したポイントは,井戸の位置,
そこから作業空間までの距離とつながり,必要な場所ま
で地下水を運ぶ工夫であった.調査の結果,全ての店舗
において,地下水は鉄管あるいは塩化ビニル管を用いて,
蛇口あるいは必要な設備まで配管して導水していた.従
って,空間の特性としては,配管の仕方に着目すること
になった.排水については,水冷式クーラーなど熱交換
に使用するだけのものを除いて,作業後に市の下水道へ
図-13 複雑に発達した配水系の例(公園の湯)
図-12 複雑に発達した配水系の例(徳広と徳広別館)
徳広 徳広別館
給水タンク
図-9 井戸水利用設備の例(麩兵)
冷却用水槽(500L) 地下水を流して使用 素早く温度を下げて雑菌の繁殖を防ぐ
水冷式クーラー
作業用流し 市の上水道蛇口と地下水蛇口を併用 上水道は補助として
図-10 井戸水利用設備の例(湯葉勇)
濾過器
戻した大豆を
すり潰す
圧力釜にて加熱
布で漉して取り
出す
濾過
豆乳を取り出す
豆乳の製造 摩砕器・圧力釜・濾過器にそれぞれ地下水が入る
圧力釜
摩砕器
湯葉の製造 成膜・引き上げ こちらは水道水を使用 湯槽が均等に加熱されるように下部に蒸気層が設けられている
図-11 井戸水利用設備の例(かわらや支店)
魚料理の調理台 地下水の蛇口の下に 木のまな板を仮設台 で支えて据える
作業中は蛇口を開放
「うなぎをたてる」 餌を絶ち新鮮な地下水の流れる3層の器の中で生かしておくと旨くなる
うなぎ
うなぎ
うなぎ

流している.
当然ながら井戸水を使用する作業場では,それぞれの
水を用いた作業の必要に応じて設備が配置され,合理化
された作業の工程が空間化されている.とりわけ製造工
場では工程が顕著に表れる.例えば麩の製造においては,
加工の過程で加熱した後は直ちに冷却をして雑菌の繁殖
を防ぐ必要があり,大きめの水槽に地下水が常に供給さ
れるしくみを必要とし,また凝固後は地下水に浸したま
ま作業をしなければ麩同士が互いにくっついてしまう製
品の特性も水の供給する箇所を決定する要因になってい
るものと考えられる(図-9).湯葉の製造においては,
成膜や引き上げの作業で水道水を使用しているが,味の
決め手となる豆乳の製造には専ら地下水を使用し,井戸
に近接する箇所を選択している(図-10).かわらや支
店においては,調理前にうなぎを「たてる」作業に地下
水は欠かすことができず,そのための装置を自作して地
下水の扱いやすい場所に据えている(図-11).他の店
舗においても同様に,衛生上の理由に加えて,製造のた
め,あるいはサービス上の工夫が,作業空間を構成する
原理になっていることが観察された.それ故に,概して
地下水を利用する空間は,不特定多数の侵入を許さない
private空間あるいはsemiprivate空間に位置づけられる.
作業場にまで至る配管は,大きく分けて地上配管と地
下配管に分類できる.食品を扱う殆どの店舗の作業場ま
では,地下数cmのレベルで配管していた.地下配管には,
目につかないために邪魔にならないことの他,外気から
隔絶されて水温保存の利点があるものと考えられる.一
方で,地上配管はメンテナンスがしやすく,改良を加え
やすい利点がある.実際,地上配管の箇所において,分
岐を加えたり,複数の井戸から取水した水をコックで調
節しながら配合して使用するために,複雑な取り回しに
なる傾向があった(図-12,13).
先に確認したように,地下水の使用量とも関連の深い
地下水の給水タンクの使用の仕方にもバリエーションが
あり,これが配管の仕方と併せて観察すれば,3つのタ
イプに分類できる.すなわち,給水タンクを使わない場
合(両香堂・高松屋・徳広別館),ポンプ付近の冷暗所
に給水タンクを設置する場合(湯葉勇・後楽荘・かわら
や支店・麩兵),そして比較的大きな給水タンクを屋上
など高い場所に設置する場合(玉井屋・公園の湯・かわ
らや本店・徳広)である.給水タンクを高い場所へ設置
するのは,広範囲における,あるいは大量の水の効率的
な使用を促進する場合であり,地上の配管が際立つこと
になる.
「public-private」の視点で空間を分類した結果からは,
およそsemiprivate空間あるいはprivate空間に位置する作業
場を核として,周辺空間がどのように構成されており,
その中における井戸の位置付けを読み取ることができる.
第一に確認できるのは,井戸が建物の内部に設けられて
いるものと,外部に設けられているものの区別である.
内部に設けられているものは,建築と同じ時期か早い時
期に鑿井されたものであることは,櫓を建てたり仮設の
水溜めを設けなければならない基本的な鑿井のプロセス
を鑑みれば容易に想像できる.一方で,public空間に分
類できる建物外部の空間に鑿井する場合には,施工作業
上の便宜が得られる公道付近あるいは公道からのアクセ
スのよい場所が選ばれている.
これらのことを確かめるため,対象店舗の建築年代と
鑿井時期を一覧できるようにしたものが図-14である.
ここで,黒実線が現存する建物の存在する期間を,灰実
線が現在と同じ業種で建て替え前の建物の存在した期間
をそれぞれ示し,上記のpublic空間に鑿井したものを白
丸,private空間ではあるが裏の建物外部に鑿井されたも
のを灰丸で示す.店舗名は,概ね北から南へ列記した.
旧麩兵は井戸も作業場の一部も建築南の屋外に位置し
ていたことを例外とすると,1980年代を境にそれ以前は
建物の新築や改築と同時期に鑿井しており,それ以後は
建物を維持したまま井戸を再掘していることが分かる.
すなわち図の右側に現れる白丸や灰丸は,生業の工程上
の改善などによって,地下水供給を強化するがために後
付けされた井戸であり,それがために水を作業場まで導
く過程が複雑なパイプワークを出現させた要因となった.
ここで,3章で明らかにした地下水温の特性と,今回
の調査で対象にした生業の店舗立地を重ねると,図-15
のように表すことができる.ここで,2015年7月と同年1
月の地下水温の差をとり等高線で表した温度差分布図を
下敷きにし,調査対象と同種の生業,すなわち飲食店・
食品加工店・銭湯のうち対象にしなかったものの分布も
示している.同時にこれらの敷地のうち,1935(昭和
10)年頃から変わらず存在していることが確認できるも
の6) もプロットした.
この図から指摘できることは,金華地区に分布してい
●:建物内部の井戸の鑿井時期 ○:建築外部表の井戸の鑿井時期
:敷地奥(建物外部)の井戸の鑿井時期 (全て現存するもの)
図-14 店舗建物の建築年代と鑿井の時期

る地下水を利用する生業を営む店舗は,概ね先に示した
地下水特性と適合していることである.すなわち,季節
と温度が逆転する伊奈波神社門前周辺の地域は,夏に低
温の地下水を得られることを重視しており,井戸と作業
場が比較的近く,汲み上げた水を地下配管を通して作業
場へ運ぶことが顕著にみられる.一方で,水源に近い長
良川近傍では,加工食品のために水を煮炊きする生業や
銭湯など,低温の水を特に必要としない業種では,むし
ろ広く分布した作業場へ多量の水を効率的に運ぶことが
できるよう,高架の給水タンクまで一度水を揚げ,架空
の管を多用していた傾向がみられた.屋上などに設置す
る給水タンク内の水は,日光で温められる.こうした傾
向は,1980年代以降の井戸水環境改善の動きの後に顕著
になっており,それ以前では,原則として井戸と作業場
は比較的近くに配置されていた.
ただし,各店舗がその場所に位置している理由は実際
には様々であり,地下水特性が店舗の立地状況について
因果関係をもつものとはいえない.しかし現状の店舗が
どういうわけか地下水利用において有利な条件をそれぞ
れ備えていることを前提として,大きな資源として確認
された地下水の性質を今後に活かすためのヒントと考え
た方が建設的だろう.
6.結論
対象地域の地下水は,長良川より北東地点から流入し
た伏流水であり,流入時の気温が反映された地下水がそ
の温度を保ちながら約半年かけてエリア中央の伊奈波神
社周辺へ到達するため,気温と地下水の季節逆転が観察
される,極めて特色のある性質を持つことが見出された.
こうした特質は,店舗を網羅的に比較する視点や不可
視な地下の状態の理解がなかなか持たれなかったことか
ら,地域においては未だ正しいイメージが持たれている
とは言えない状態であった.しかしながら,それぞれの
店舗における作業効率の向上を求めた結果,空間構成に
ある程度の特性が現れていた.すなわち,井戸と作業空
間の配置は,少なくともこれらを同時に建設できた場合
には,可能な限り近接していることが求められていた.
この必然性は,地下水の温度に留意する業種で顕著であ
る.一方で,利用する際の温度が高い業種(煮炊きや湯
を使用)は,この傾向に比較的無頓着であり,むしろ質
に価値を認める場合が多い.今回の調査では,比較的地
下水温が気温に近い長良川付近と,気温と逆の特性を示
す伊奈波神社門前付近で,それぞれ業種と地下水温の特
性がよく適合していた.店舗の存続,嗜好性には他の多
くの要因を含むためその因果を説明できないが,現状の
業種の分布は,今後の地下水利用を促進するためのよい
モデルになることが分かった.
謝辞:本研究の資料調査において快くご協力頂いた各店
主の皆様,そして労を惜しまず支援して頂いた岐阜市社
会教育課 高木晃氏には,厚く謝意を表する.
参考文献
1)岐阜市教育委員会:長良川中流域における岐阜の文化的景
観保存調査報告書,2015.3
2)すなわち,水田・畑地などの農耕に関する景観地,茅野・
牧野などの採草・放牧に関する景観地,用材林・防災林など
の森林の利用に関する景観地,養殖いかだ・海苔ひびなどの
漁ろうに関する景観地,ため池・水路・港などの水の利用に
関する景観地,鉱山・採石場・工場群などの採掘・製造に関
する景観地,道・広場などの流通・往来に関する景観地,垣
根・屋敷林などの居住に関する景観地のいずれかに,あるい
は複合的に該当することとされる.(平成17年文部科学省告
示第46号)
3)神谷浩二・真鍋洋・山崎勲:溶存イオンデータの多変量解
析に基づいた広域地下水流動系の評価,地盤工学ジャーナル,
pp.49-54,2015.3
4)岐阜大学:環境省平成19年度クールシティ推進事業報告
書・大型施設での地下水揚水型冷房機器の長期稼働に伴う地
下水・地盤環境への影響評価事業,2008
5)ただし,水量および水質の変化を不安に思い,さらに深い
井戸を掘削した例はあった.
6)金華一二三会:昭和10(1935)年頃の岐阜市金華地区の地図,
わたしたちの子供の頃の金華の町,2010.3,付録により確認
図-15 現在の対象地域における地下水温特性と 飲食店・加工食品店・銭湯の分布
飲食店
加工食品店
昭和初期から立地する飲食店・ 加工食品店・銭湯の店舗
玉井屋
両香堂
公園の湯
湯葉勇 かわらや
かわらや支店
後楽荘
徳広
麩兵
旧麩兵
高松屋
伊奈波神社
長 良 川
0 500m