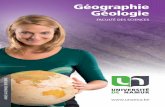地質学雑誌 2第 17 巻 5第 5 7–2 8 Jour. Geol. Soc. …...地質学雑誌 2第 17 巻 5第5...
Transcript of 地質学雑誌 2第 17 巻 5第 5 7–2 8 Jour. Geol. Soc. …...地質学雑誌 2第 17 巻 5第5...

地質学雑誌 第 117巻 第 5号 277–288ページ,2011年 5月 JOI: JST.JSTAGE/geosoc/117.277Jour. Geol. Soc. Japan, Vol. 117, No. 5, p. 277–288, May 2011
A Middle Miocene widespread tephra in the Nanatani Formation of the Niigata sedimentary basin, northeast Japan: Correlation between the Kbi tephra and the Muro Pyroclastic Flow Deposit in Kii Peninsula
新潟堆積盆七谷層中に見つかった中期中新世広域テフラ:Kbiテフラと紀伊半島室生火砕流堆積物の対比
Abstract
The Komadegawa-biotite (Kbi) tephra is a crystal-rich coarse tuff layer (9 cm thick) intercalated in the upper part of the Middle Mio-cene Nanatani Formation in the eastern area of the Niigata sedimen-tary basin, northeast Japan. The Kbi tephra contains plagioclase (oligoclase to labradorite in composition), quartz, sanidine, biotite, trace amounts of garnet, and reddish and colorless zircons. The Kbi tephra is intercalated in the N.9 planktonic foraminiferal zone and the CN4 calcareous nannofossil zone, corresponding to an age of 14.2–14.7 Ma, which is consistent with a newly determined fission track age of 14.6±0.3 Ma (1σ). On the basis of the petrography, fission track age and biostratigraphy, the Kbi tephra is correlated to the Muro Pyroclastic Flow Deposit in Kii Peninsula and the Kn-1 tephra in Boso Peninsula. These tephras are considered as a widespread tephra layer associated with the formation of the Kumano Acidic Rocks in Kii Peninsula. This tephra is expected to be found across large parts of Japan and provides a stratigraphic marker in various sedimentary basins.
Keywords: Middle Miocene, Kbi tephra, Nanatani Formation, Niigata sedimentary basin, biostratigraphy, correlation, widespread tephra, Muro Pyroclastic Flow Deposit, Kii Peninsula
工藤 崇* 檀原 徹** 岩野英樹**
山下 透** 三輪美智子***
平松 力*** 柳沢幸夫*
Takashi Kudo*, Tohru Danhara**,Hideki Iwano**, Tohru Yamashita**, Michiko Miwa***, Chikara Hiramatsu***
and Yukio Yanagisawa*
2010年 6月 25日受付.2011年 2月 22日受理.* 産業技術総合研究所地質情報研究部門 AIST, Institute of Geology and Geoinforma-
tion, Geological Survey of Japan, Central 7, Higashi 1-1-1, Tsukuba, Ibaraki 305-8567, Japan
** (株)京都フィッション・トラック
Kyoto Fission-Track Co., Ltd., 44-4 Minami-tajiri-cho, Omiya Kita-ku, Kyoto 603-8832, Japan
*** 石油資源開発(株)技術研究所
JAPEX Research Center, 1-2-1 Hamada, Mi-hamaku, Chiba 261-0025, Japan
Corresponding author; T. Kudo, [email protected]
©The Geological Society of Japan 2011 277
は じ め に
テフラは地質学的に極めて短時間に堆積するため,同時間
面の指標として重要な役割を果たす.特に,姶あい
良ら
Tn火山灰層(AT)(町田・新井, 1976)に代表されるカルデラ形成に伴った巨大噴火による広域テフラは,日本列島規模で分布
し,各地の時間面をつなぐ重要な鍵層となる.日本列島の第
四紀広域テフラについては,現在までに膨大なデータが記
載・蓄積され(町田・新井, 2003など),年代決定や詳細な地史の復元等に広く活用されている.近年では分析技術の進
展やデータの蓄積に伴い,より古い鮮新世においても日本列
島規模で分布するテフラが見つかりつつある(Kurokawa and Tomita, 1998; 富田・黒川, 1999; 田村ほか , 2005; 黒川ほか , 2008など).第四紀や鮮新世と比較して,中新世の広域テフラに関する
研究は進展が遅れている.新潟堆積盆では後期中新世テフラ
の対比に成功した例があるものの(黒川・大海, 2000; 平中ほか , 2002, 2004, 2009),これらはいずれも隣接する地域での対比にとどまっている.一方,檀原ほか(2007a)は,房総半島の安
あ わ
房層群木の根層に挟在するKn-1テフラ(中嶋ほか , 1981)が紀伊半島の室
むろ
生う
火砕流堆積物(西岡ほか , 1998)に対比されることを示した(Fig. 1).室生火砕流堆積物は,熊野酸性岩(荒牧・羽田, 1965; Fig. 1)の形成に関連したカルデラ群(Miura, 1999; 三浦・和田, 2007; 川上・星, 2007; Kawakami et al., 2007)起源のアウトフロー堆積物と推定されている(星ほか , 2004; 山下ほか , 2007).室生火砕流堆積物は,現存する部分だけでもその体積が 100 km3を越えると見積もられており(西岡ほか , 1998),熊野酸性岩の火成活動による一連の珪長質岩類の侵食・散逸分も含めた総体積は,約 2000 km3と見積もられて
いる(三浦・和田, 2007).このような巨大噴火によって生成されたテフラは,広域に分布する可能性が高く,房総半島

278 工藤 崇ほか 2011―5
に続く各地での新たな発見が期待されていた(檀原ほか , 2007a).著者のうち工藤と柳沢は,産業技術総合研究所の 5万分の 1地質図幅「加茂」(Fig. 1)作成の調査過程で,中部中新統の七
ななたに
谷層上部から黒雲母に富む 1枚のテフラを発見した.このテフラを駒
こま
出で
川がわ
バイオタイト(Kbi)テフラ(新称)と命名する.本テフラについて,フィッション・トラック
(FT)年代測定,記載岩石学的観察,上下層準の泥岩の微化
石分析を行ったところ,本テフラが紀伊半島の室生火砕流堆
積物に対比される可能性があることが判明したので,ここに
報告する.
地 質 概 説
新潟県加茂地域は新潟堆積盆の東縁部に位置する(Fig. 1).本地域では先第三系を不整合に覆って,新第三系が広く分布する.Kbiテフラは,加茂地域南東部,三条市下
した
田だ
北きた い も が わ
五百川の七谷層上部の泥岩中に産する.独自の調査結果に
基づく北五百川付近の地質図を Fig. 2に,駒出川ルートのルートマップを Fig. 3に示す(これらの図では簡略化のため段丘堆積物, 現河床堆積物等を省略した).なお,地層名の区分は津田ほか(1984)に従った.北五百川付近の新第三系は,下部~中部中新統からなり,
下位より大谷川層,七谷層,南みなみいもがわ
五百川層の順に東から西に向
かって累重し,前期~後期中新世の貫入岩がこれらを貫いて
いる(Fig. 2).七谷層は,大村(1928)により命名され,新第三紀における新潟堆積盆地標準層序の 1つとされている(片平, 1974など).本層の模式地は,北五百川の北方約8 kmに位置する加茂市東部(旧七谷村)の大谷付近である(三梨・宮下, 1974; 津田ほか , 1984).北五百川付近での本層は,南北に帯状に分布し,南北~北東方向の走向を示し,
10~40°で西方~北西方に傾斜する(Fig. 2).本地域における七谷層は,下部の暗青灰色~暗紫灰色硬質泥岩・流紋岩
火山砕屑岩互層(Nmt),上部の明灰色~灰色塊状泥岩および弱成層泥岩(Nm),Nm上部に挟在する流紋岩火山砕屑岩(Nt)から構成され,下位の大谷川層の流紋岩火山砕屑岩(Ot)を整合に覆い,上位の南五百川層の黒灰色~暗灰
Fig. 1. Locality map of the Kamo district in Niigata, Kii Peninsula and Boso Peninsula.
Fig. 2. Geological and topographical map of the Kita-imogawa area in the Kamo district, Niigata. The base map is part of 1:25,000 “Awagatake” topographic map published by the Geospatial Information Authority of Japan. Alluvium and terrace deposits are omitted for simplicity.

地質雑 117( 5 ) 新潟堆積盆七谷層中に見つかった中期中新世 Kbiテフラ 279
色泥岩(Mn)に整合に覆われる(Fig. 2).また,これらは前期~中期中新世の流紋岩(Ry1)およびドレライト・玄武岩(Do),後期中新世の流紋岩(Ry2)の貫入を受けている(Fig. 2).なお,本論による七谷層の岩相区分(Nmt, Nm, Nt)は,津田ほか(1984)による asm5,ms5,Tr9にそれ
ぞれ相当する.七谷層の堆積環境は,底生有孔虫化石群集よ
り,近くに浅海域を伴った漸深海と推定されている(加藤ほ
か , 1992).北五百川における七谷層は,駒出川および祓
はらい
川(Fig. 2)沿いに連続した好露出があり,これまでに微化石層序学的研
究(三梨・宮下, 1970, 1974; 菅野・中世古, 1975; 米谷, 1978, 1988; 佐藤, 1982; 佐藤ほか , 1991; 柳沢, 1993; 平松ほか , 1997),アミノ酸類の堆積学的研究(佐々木, 1973),挟在するテフラの記載(黒川ほか , 1998)がなされてきた.このうち微化石層序学的研究によれば,北五百川
における七谷層は,浮遊生有孔虫化石帯区分(Blow, 1969)のN.8からN.10帯に(米谷, 1978; 佐藤, 1982),石灰質ナンノ化石帯区分(Okada and Bukry, 1980)の CN3から CN5a帯(佐藤, 1982; 佐藤ほか , 1991; 平松ほか , 1997)に,底生有孔虫化石帯区分(米谷, 1987)のBF1帯に(三梨・宮下, 1970, 1974; 米谷, 1988)に相当する.
テフラの産状
駒出川バイオタイト(Kbi)テフラは,三条市下田北五百川,駒出川ルート左岸において,七谷層上部の明灰色塊状泥
岩中に挟在する(Fig. 3).駒出川ルートの柱状図を Fig. 4に,Kbiテフラの露頭写真を Fig. 5に示す.加茂地域でKbiテフラを確認できたのは駒出川ルートの 1地点のみであり(Figs. 2, 3),ここをKbiテフラの模式地とする(世
界測地系で北緯 37°32'29'', 東経 139°8'23''の地点).黒川ほか(1998)は,駒出川ルートにおける七谷層中のテフラを報告し(上位よりKpw, Kdh, Kpp, Khs, Kkm, Kzi, Kwsテフラ),詳細な記載を行っている(Figs. 3, 4).しかし,Kbiテフラの存在はこれまで認識されていなかった.本研究ではこれらのテフラ以外にも,駒出川ルートにお
いて層厚数 10 cm以下の数枚のテフラを確認した(Figs. 3, 4).また,七谷層泥岩中には層厚数cm以下の凝灰質泥岩薄層が数多く挟在される(Fig. 4).七谷層中のテフラは,程度の差はあれ,いずれも変質が進んでいる.火山ガラスは,
一部でオリジナルな形状を保持しているものが認められる
が,ほとんどは粘土化して原形を失っている.また,苦鉄質
鉱物も変質で失われていることが多い.そのため,これらの
特性を利用したテフラの対比は困難な場合が多い.
Kbiテフラは,黒川ほか(1998)による駒出川白色含ジルコン(Kzi)テフラの 25 cm下位に挟在する(Fig. 5).Kbiテフラは,灰色を呈する結晶質中粒~粗粒砂サイズの凝灰岩であり,最上部 1 cmでは極細粒~細粒砂サイズに正級化する.層厚は最大 9 cmであり,レンズ状で側方に尖滅する.模式地では側方に 2~3 mの範囲で認められる.肉眼で大量の比較的新鮮な黒雲母(最大で長径 1 mm程度)を確認できる.駒出川ルートにおいては,他に黒雲母を肉眼で
容易に確認できるテフラは存在しないため,判別の良い基準
となる.
試料および分析手法
Kbiテフラの記載岩石学的特性および堆積年代を明らかにするため,本テフラ試料を対象として,鉱物組成分析や軽
鉱物の屈折率測定などのテフラ分析および FT年代・FT長
Fig. 3. Route map along the Komadega-wa River. Locality of the route is shown in Fig. 2.

280 工藤 崇ほか 2011―5
測定を行った.また,微化石層序から本テフラの堆積時期を
より絞り込み,広域対比を確実なものとするために,本テフ
ラ上下層準の泥岩 7試料(Figs. 3, 4)を対象として,浮遊性有孔虫化石および石灰質ナンノ化石分析を行った.
1.テフラ分析Kbiテフラ試料 30 gをステンレス乳鉢で 1 mm以下になるように粉砕した後,超音波洗浄器を用いて極細粒物を懸濁
させ,上澄み液の濁りがなくなるまで水を替えながら取り除
いた.使い捨てメッシュ(60, 120, 250メッシュ)を用いて水中で篩い分け,各フラクションの試料を乾燥・回収し
た.120-250メッシュ(1/8-1/16 mm)の試料の一部を光硬化剤(屈折率: nd=1.54)でスライドガラス上に封入
し,偏光顕微鏡下でこの薄片を観察し,全鉱物組合せモード
分析(火山ガラス, 軽鉱物, 重鉱物, 岩片, その他を対象)と重鉱物組合せモード分析(カンラン石, 斜方輝石, 単斜輝石, 角閃石, 黒雲母, 燐灰石, ジルコン, 不透明鉱物を対象)を行った.次に,温度変化型屈折率測定装置(RIMS: 檀原, 1991; Danhara et al., 1992)を用い,軽鉱物の屈折率測定を行った.屈折率から軽鉱物は,斜長石,石英,カリ長石に分類
し,斜長石はさらに 6つの組成(アルバイト, オリゴクレース, アンデシン, ラブラドライト, バイトゥナイト, アノーサイト)に分類した.なお,火山ガラスは変質しているため屈
折率測定は不可能であった.これらの分析方法のより詳しい
説明は山下ほか(2007)に記載されている.2.FT年代および FT長測定
Kbiテフラ試料 250 gをステンレス乳鉢で粉砕し,水洗,篩分後,磁性分離と重液による比重分離を行った結果,60メッシュより細かい約 2000粒子の自形ジルコン結晶を得た.これらは赤色を呈するものと無色のものが混在し,その
割合はおおよそ半々であった.年代測定には色調による区別
を行わずランダムに約 100粒子を選び,マウント材に埋め込んだ.測定方法は外部ディテクター法(Gleadow, 1981)を採用した.本研究では当初,結晶を研磨して露出させた結
晶内部面を測定する ED1法と,結晶の自然面(外部面)を研磨せずにそのまま露出させた面を測定する ED2法を準備した.しかし予察的観察から,結晶外部面には通常存在しな
い4 μm以下の短いトラックが多く認められた.この事実は,本ジルコン試料が外部効果(Suzuki, 1988; 星ほか , 2003)の影響を受けているか,あるいは再加熱によりトラックが短
縮化していることを示唆する.そこで外部効果の影響を受け
ない ED1法のみを選択し,さらにコンファインド FT長を測定することで,再加熱の影響の有無を評価した.コンファ
インド FT(confined fission track)とは,FTの両端が結晶内部にあり,エッチングされた FTの全長が観察できるもので(Wagner, 1988),ジルコンでは 10~12 μmの長さ
Fig. 4. Geological columns of the Nanatani Formation in the Komadegawa section. Locality of the section is shown in Fig. 3. Abbreviations in boxes (Nt, Nm and Nmt) corre-spond to the geological units shown in Fig. 2. Tephra names (Kpw, Kdh, Kpp, Khs, Kkm, Kzi and Kws) are from Kurokawa et al. (1998). The asterisk represents the provisional name of the tephra bed between the Kkm and Kzi tephras. Thin tuffaceous mud beds are omitted in the left column for simplicity. Numbers at the top of columns indicate the source of biostratigraphic data: (1) Yanagisa-wa (1993); (2) and (3) the present study.
Fig. 5. Field occurrence of the Kbi tephra in the Nanatani Formation at Komadegawa. The location of this site is shown in Figs 2 and 3.

地質雑 117( 5 ) 新潟堆積盆七谷層中に見つかった中期中新世 Kbiテフラ 281
(平均値は 10.5~11.0 μm: Hasebe et al., 1994)をもつ.FTは熱を受けると短縮する性質があることから,その短縮率から敏感に熱影響を検知できる(例えば , 松崎ほか , 2004).以下では,コンファインド FT長を単に FT長と略す.
具体的な年代測定手順はDanhara et al.(1991, 2003)に,FT長測定は Iwano et al.(1996)に準拠した.ジルコン中の自発トラックのエッチングはKOH-NaOH共融液(225 °C)で 31時間行い,ジルコンマウントは 2セット用意した.誘導トラックの外部ディテクターにはDAP(dial-lyl phthalate)樹脂を用いた.熱中性子照射は日本原子力研究開発機構の JRR-3号炉気送管(Auに対する Cd比は24)で 2回行った.その際,熱中性子線量測定用の標準ガラスは NIST-SRM612を用いた.年代較正はゼータ法(Hurford and Green, 1983)で行い,ゼータ値は 414±3である(Danhara and Iwano, 2009).FT長の測定システムは Iwano et al.(1996)を利用した.
3.浮遊性有孔虫化石分析泥岩試料 100 gを秤量し,無水硫酸ナトリウム法(米谷・井上, 1973)により泥化させた後,30,120,200メッシュの篩を用いて水洗した.30および 120メッシュ上の残渣を乾燥後,その中に含まれる有孔虫化石を分析の対象とした.
産出個体数が多い場合は分割して分析を実施した.残りの試
料についても,分帯の鍵となる種の有無を確認した.
4.石灰質ナンノ化石分析石灰質ナンノ化石分析用スライドの作成については高山
(1978)に従った.偏光顕微鏡下,倍率 1600倍の条件において,単ニコルと直交ニコルの双方でスライドを観察し,1試料あたり 200個体以上を目安に石灰質ナンノ化石の検出と同定を行った.
分 析 結 果
1.テフラ分析Kbiテフラの主要構成鉱物は石英,斜長石,サニディン,
Fig. 6. Refractive index histograms of felsic minerals from the Kbi tephra, Kn-1 tephra and Muro Pyroclastic Flow De-posit (PFD). Data for the Kn-1 tephra are from Danhara et al. (2007a). Data for the Muro PFD are from Yamashita et al. (2007).
Table 1. Zircon fission track ages for the Kbi tephra.

282 工藤 崇ほか 2011―5
黒雲母からなり,斜長石の屈折率はオリゴクレース~ラブラ
ドライト組成領域に相当する(Fig. 6).さらに,重鉱物として微量のざくろ石および赤色と無色のジルコンを含む
(オープンファイル付録Fig. 1).また,本研究では黒川ほか(1998)によるKws,Kzi,
Kkm,Khs,Kpp,Kdhテフラ(Fig. 4)および KziとKkmの間に挟在する未命名テフラ(Fig. 4中に*を記した
テフラ)についても赤色・無色ジルコンの有無を調べるため
検鏡した(なお , KhsとKkmの間に挟在する未命名テフラについては検鏡を行っていない).しかし,今のところこれ
らを両方含むテフラはKbiテフラ以外には見つかっていない.
2.FT年代および FT長測定Kbiテフラに含まれるジルコンの FT年代測定を 2回行った結果,14.4±0.4 Ma(誤差は 1σ,以下同じ)と 15.0±0.5 Maが得られ,両値は誤差範囲内で一致した(Table 1).
また,両測定とも χ2検定(Galbraith, 1981)に合格した.Kbiテフラの年代の代表として,Taylor(1982)による加重平均値を求めると,14.6±0.3 Maとなった.42本の FT長は 10.4~12.4 μmに集中し,平均値として 11.1±0.5 μmが得られた.
3.浮遊性有孔虫化石分析分析に供した 7試料すべてから浮遊性有孔虫が検出された(Table 2).泥岩試料 100 gあたりの産出個体数は,Kbiテフラ直下の試料 04から 310個体と比較的少なかったが,他の試料からは 912~8640個体と非常に多かった(Table 2).全試料から,有孔虫殻の変型や破損している個体が認められた.分析結果に基づき,米谷(1978)による日本海地域新第三系の浮遊性有孔虫化石帯区分(化石帯のコード番
号は三輪ほか , 2004)を適用して,試料の化石帯を認定した.
試料 06,05,04,02,01から,Orbulina suturalisお
Table 2. Occurrence chart of planktonic foraminifer in the Komadegawa section.

地質雑 117( 5 ) 新潟堆積盆七谷層中に見つかった中期中新世 Kbiテフラ 283
よびOrbulina sp. indet.が検出された(Table 2).よって,これらの試料は少なくとも PF2帯以上である.さらに PF3帯を規定する Globorotalia peripheroacutaおよび Glo-borotalia miozea s.l.が産出しないことから,これら試料は PF2帯に認定される.また PF1帯を規定する Praeor-bulina curvaや Globigerinoides sicanusも検出されなかった.試料 04,02,01からの Praeorbulina circularis(PF1~PF2)の産出は,これら試料が PF2帯であることを支持している(Table 2).試料 07および 03から P. circularisが検出されたことから(Table 2),両試料は PF1~PF2の範囲内である.さらにO. suturalisやO. universaは検出されなかったが,P. curvaやG. sicanusも検出されなかったことと,下位にPF2帯が認定されたことから,両試料は PF2帯に相当すると考えられる.
また,試料 02および 01からの Praeorbulina glomero-sa(PF1~PF2の下部)の産出は(Table 2),両試料がPF2帯の中でも相対的に下部に相当することを示している.
PF2帯は Blow(1969)による浮遊性有孔虫化石帯区分のN.9帯に相当することから(米谷, 1978),Kbiテフラ上下層準の泥岩は PF2帯およびN.9帯に区分される(Table 2).4.石灰質ナンノ化石分析分析に供した 7試料すべてから石灰質ナンノ化石が検出された(Table 3).試料 04については産出頻度が低く,保
存状態も悪い傾向にあるが,他の試料からは比較的保存状態
が良好な石灰質ナンノ化石が普通程度の頻度で認められた
(Table 3).分析結果に基づき,Okada and Bukry(1980)による石灰質ナンノ化石帯区分を適用して,試料の化石帯を
認定した.
群集内容は Coccolithus pelagicus,Cyclicargolithus floridanus,コッコリスの長径が 5 μm以下の小型の Retic-ulofenestra 属(R. minuta, R. haqii, R. minutula),Sphenolithus heteromorphusなどを主体とする(Table 3).保存状態の悪い試料 04のみ群集内容が若干異なり,C. pelagicusの頻度が低くなる一方で,Discoaster属の頻度が高くなる(Table 3).これは試料の炭酸カルシウムの溶解による群集内容の偏りに起因すると推定される.
石灰質ナンノ化石帯認定に有効な種としては S. hetero-morphusの産出が挙げられる.7試料すべてから本種が豊富に検出されるので(Table 3),全試料ともにCN3~CN4帯に相当することは確実である.また,その消滅層準が
CN3帯とCN4帯の境界を規定するHelicosphaera ampli-apertaの産出はまったく認められない.ただし,本種が産出しないことを根拠にすべての試料がCN4帯であるという結論が直ちに得られるわけではない.なぜなら,本種の東北
日本海側の新第三系からの産出は極めて低いからである.そ
こで,佐藤ら(1991)と同様にDiscoaster属中に占めるD. deflandreiの割合の層位的変化を検討する.最下位の試料 01でD. deflandrei(D. cf. deflandreiを含む)の割合
Table 3. Occurrence chart of calcareous nannofossils in the Komadegawa section.

284 工藤 崇ほか 2011―5
がやや高いが,他の試料ではすべて 40%以下である.したがって,01以外の試料は CN4帯であると考えられる.試料 01はこれより下位のデータがないため,どちらの化石帯に相当するかの判断が困難なので,本論では試料 01のみCN3~4帯に相当するという結論にとどめる.以上より,Kbiテフラの上下層準の泥岩はCN4帯に区分される(Table 3).
考 察
1.2種類のジルコンの存在と FT年代Kbiテフラには明らかに色調の異なる赤色および無色の 2種類のジルコンが混在する(オープンファイル付録Fig. 1).赤色ジルコンは{100}柱面が発達し,無色ジルコンは{110}柱面が発達した結晶形を示す.少なくとも駒出川ルートにおいては,同様に 2種類のジルコンを含むテフラは他に見つからない.前述のように,七谷層中のテフラは変質が
進んでいるため,火山ガラスの特性や苦鉄質鉱物の組み合わ
せのみではテフラの特徴を比較するのが困難である.しか
し,ジルコンは変質に強い性質を持つため,ジルコンの特徴
の差はオリジナルなテフラの特徴の差を直接反映していると
判断できる.そのため,2種類のジルコンの存在は,Kbiテフラの独自性を際立たせる重要な特徴と言える.
これら 2種類のジルコンは両者で年代差が認められない.また,両者のもつ FT長が熱影響のない長さ(上述)と一致することから,再加熱による若返りは認められない.した
がって,赤色と無色のどちらのジルコンともKbiテフラの噴出・定置年代を記録している本質的なジルコンと考えら
れ,得られた年代: 14.6±0.3 Maは堆積年代を示すと解釈される.
2.微化石層序からみた堆積年代Kbiテフラは浮遊性有孔虫化石帯区分(Blow, 1969)の
N.9帯,石灰質ナンノ化石帯区分(Okada and Bukry, 1980)のCN4帯に含まれる(Fig. 4).これらの微化石分析の結果は,駒出川ルート北隣の祓川ルート(Fig. 2)における浮遊性有孔虫および石灰質ナンノ化石の分析結果(米谷, 1978; 佐藤, 1982; 佐藤ほか , 1991; 平松ほか , 1997)とよく調和する.N.9帯,CN4帯の化石帯区分から,ATNTS 2004年代スケール(Gradstein et al., 2004)に従うと,Kbiテフラの堆積年代は 14.2~14.7 Maの間と推定される(Fig. 7).この年代は,駒出川ルートにおいてKbiテフラの上位層準が珪藻化石帯区分(Yanagisawa and Akiba, 1998)のNPD4Bb帯に相当すること(柳沢, 1993)と調和する(Figs. 4, 7).さらに,微化石層序により推定された年代と FT年代(14.6±0.3 Ma)は,極めて良く調和する(Fig. 7).3.Kbiテフラの起源と広域対比
Kbiテフラの主要構成鉱物は,石英,斜長石,サニディン,黒雲母であり,重鉱物として無色・赤色ジルコン,微量
のざくろ石を含む.15 Ma付近でこれらの鉱物組み合わせが一致するテフラとしては,今のところ唯一紀伊半島の室生
Fig. 7. Chronostratigraphy of the Early to Middle Miocene se-quence in the Kita-imogawa area of the Kamo district, Niigata. ATNTS2004: Gradstein et al. (2004). (1) Blow (1969); (2) Oka-da and Bukry (1980); (3) Yanagi-sawa and Akiba (1998); (4) Maiya (1978), Sato (1982), and the pres-ent study; (5) Sato (1982), Sato et al . (1991), Hiramatsu et al . (1997), and the present study; (6) Yanagisawa (1993).

地質雑 117( 5 ) 新潟堆積盆七谷層中に見つかった中期中新世 Kbiテフラ 285
火砕流堆積物とその相当層およびそれらに対比される房総半
島のKn-1テフラが知られている(檀原ほか , 2007a, b).そこで以下では,Kbiテフラ,室生火砕流堆積物,Kn-1テフラの三者について対比検討を行う.これら三者の特徴を比
較した図を Fig. 8に示す.Kbiテフラ,室生火砕流堆積物,Kn-1テフラを比較すると,ジルコン FT年代が誤差の範囲内で一致し,鉱物組み合わせも一致する(Fig. 8).なお,室生火砕流堆積物は斜方輝石を含むことがあるが(Fig. 8),これは最下部の層準のみであることが判明している(山下ほか, 2007).斜長石の屈折率はいずれのテフラもオリゴクレース~ラブラドライト
組成領域に相当し,良く一致する(Figs. 6, 8).微化石層序から見ると,室生火砕流堆積物の給源と推定さ
れる熊野酸性岩は,下位の熊野層群中に浮遊性有孔虫化石帯
の Orbulina datum(Blow, 1969の化石帯における N.9/N.8境界)があるとされていることから(Saito, 1963; 池辺ほか, 1975),その境界年代よりは若いと考えられる.このことは,KbiテフラがN.9帯に挟在することと調和する(Figs. 4, 7).一方,石灰質ナンノ化石層序においては,Kn-1テフラは CN4帯に含まれることから(三田・高橋, 1998),Kn-1テフラとKbiテフラの化石帯区分は一致する(Fig. 8).なお,檀原ほか(2007a)が指摘している通り,木の根層の浮遊性有孔虫生層序(Oda, 1977)とKn-1テフラの年代には若干の矛盾がある.すなわち,木の根層のOrbulina datumはKn-1テフラよりも上位で認められている.この食い違いについて,檀原ほか(2007a)は,木の根層におけ
る浮遊性有孔虫化石の産出間隔などに問題がある可能性を指
摘している.最近,林ほか(2008)は,Oda(1977)が検討したルートよりも続成の影響が少ない別のルートで浮遊性
有孔虫生層序を検討し,Orbulina datumが従来の報告よりも 100 m以上下位に相当する層準から認められることを報告した.筆者らは,檀原ほか(2007a)と同様に,Kn-1テフラよりも下位の層準にOrbulina datumが存在する可能性があると考えているが,今後,木の根層の浮遊性有孔虫生
層序の詳細な再検討が切望される.
以上のように,Kn-1テフラについては浮遊性有孔虫化石層序の課題が残されているものの,FT年代,記載岩石学的特徴,微化石層序の検討結果から,Kbiテフラ,室生火砕流堆積物,Kn-1テフラの三者は対比できる可能性が高く,これらは熊野酸性岩の形成に関連した広域テフラの可能性が
考えられる.
4.層序学的意義と今後の展望今回の熊野酸性岩起源の可能性があるテフラの発見は,房
総半島のKn-1テフラ(檀原ほか, 2007a)に続いて 2例目となる.ただし,今後対比をより確実にするためには,
Kn-1テフラの前後の層準における浮遊性有孔虫化石層序の再検討や,黒雲母の化学組成を用いた対比の検討が必要であ
ろう.また,このテフラが示す約 15 Maという年代は,日本海拡大期に,この時期に西南日本の時計回りおよび東北日
本の反時計回り運動が起こったとされている(Otofuji et al., 1991, 1994; Hoshi and Yokoyama, 2001など).熊野酸性岩と室生火砕流堆積物の形成時期は,この西南日本の回
転運動以後であると考えられている(星, 2002; 星ほか, 2004).よって,本テフラの堆積時期は日本海拡大期末期あるいはその直後に相当する.新潟堆積盆においては,日本海
拡大に伴う活発な火山活動が一旦沈静化し,堆積盆の沈降が
進んで外洋性の漸深海となった時代に相当する(小林・立石, 1992; 津田, 1992など).このように,本テフラは層序学的・テクトニクス的に重要なタイムマーカーとなりうる.今
後,テフラ発見地点がさらに増加し,日本列島規模で広域対
比が進むことにより,異なる堆積盆間での層序対比や日本海
拡大末期のテクトニクス解明への寄与が大いに期待される.
謝 辞
加茂地域の野外調査を進めるにおいて,産業技術総合研究
所の内野隆之氏,小松原 琢氏,高橋 浩氏には諸般にわ
たってお世話になった.島根大学の林 広樹氏には,木の根
層の浮遊性有孔虫層序について御教示いただくとともに,原
稿に目を通して頂き助言を頂いた.産業技術総合研究所の植
木岳雪氏,石油資源開発株式会社の稲葉 充氏には本論を改
善する上で助言やアドバイスを頂いた.2名の査読者(黒川勝己氏と匿名査読者)および編集委員の中里裕臣氏には,本
論を改善する上で多数の有益なコメントをいただいた.ここ
に記して深く感謝申し上げます.
文 献
荒牧重雄・羽田 忍(Aramaki, S. and Hada, S.), 1965, 熊野酸性火
Fig. 8. Correlations of the Kbi tephra, the Muro Pyroclas-tic Flow Deposit (and its equivalents) and the Kn-1 tephra. Zircon fission track ages are from Nishida (1990), Ozaki et al. (2000), Hoshi et al. (2002), Iwano et al. (2007) and Danhara et al. (2007a). Petrographical data are from Nish-ioka et al. (1998, 2001), Ozaki et al. (2000) and Yamashita et al. (2007). Biochronological data are from Saito (1963), Ikebe et al. (1975), Mita and Takahashi (1998), Hayashi et al. (2008) and the present study.

286 工藤 崇ほか 2011―5
成岩類の中部および南部の地質.地質雑(Jour. Geol. Soc. Ja-pan), 71, 494–512.
Blow, W. H., 1969, Late Middle Eocene to recent planktonic fo-raminiferal biostratigraphy. In Brönnimann, P. and Renz, H. H., eds., Proc. 1st Intern. Conf. Planktonic Microfossils, Geneva 1967, 1, 199–422, E. J. Brill, Leiden.
檀原 徹(Danhara, T.), 1991, RIMSによる屈折率測定とその応用.月刊地球(Monthly Chikyu), 13, 193–200.
檀原 徹・星 博幸・岩野英樹・山下 透・三田 勲(Danhara, T., Hoshi, H., Iwano, H., Yamashita, T. and Mita, I.), 2007a, 中期中新世テフラの広域対比: 房総半島Kn-1凝灰岩と紀伊半島室生火砕流堆積物.地質雑(Jour. Geol. Soc. Japan), 113, 384–389.
Danhara, T. and Iwano, H., 2009, Determination of zeta values for fission-track age calibration using thermal neutron irra-diation at the JRR-3 reactor of JAEA, Japan. Jour. Geol. Soc. Japan, 115, 141–145.
檀原 徹・岩野英樹・星 博幸(Danhara, T., Iwano, H. and Hoshi, H.), 2007b, 紀伊半島中新世火成岩類と対比テフラ中の赤白ジルコン.地質雑(Jour. Geol. Soc. Japan), 113, ix–x.
Danhara, T., Iwano, H., Yoshioka, T. and Tsuruta, T., 2003, Zeta calibration values for fission track dating with a diallyl phthalate detector. Jour. Geol. Soc. Japan, 109, 665–668.
Danhara, T., Kasuya, M., Iwano, H. and Yamashita, T., 1991, Fission-track age calibration using internal and external sur-faces of zircon. Jour. Geol. Soc. Japan, 97, 977–985.
Danhara, T., Yamashita, T., Iwano, H. and Kasuya, M., 1992, An improved system for measuring refractive index using the thermal immersion method. Quaternary International, 13/14, 89–91.
Galbraith, R. F., 1981, On statistical models for fission track counts. Jour. Math. Geol., 13, 471–478.
Gleadow, A. J. W., 1981, Fission-track dating methods: what are the real alternatives? Nuclear Tracks, 5, 3–14.
Gradstein, F., Ogg, J. and Smith, A., eds, 2004, A geologic time scale 2004. Cambridge Univ. Press, Cambridge, 589p.
Hasebe, N., Tagami, T. and Nishimura, S., 1994, Towards zir-con fission-track thermochronology: Reference framework for confined track length measurements. Chem. Geol., 112, 169–178.
林 広樹・吉田達哉・高橋雅紀(Hayashi, H., Yoshida, T. and Takahashi, M.), 2008, 房総半島鴨川地域川谷ルートにおける安房層群木の根層の浮遊性有孔虫生層序.日本地質学会第 115年学術大会講演要旨(Abst. 115th Ann. Meet. Geol. Soc. Japan), 82.
平松 力・三輪美智子・井上洋子・深沢和恵(Hiramatsu, C., Miwa, M., Inoue, Y. and Fukasawa, K.), 1997, 東北地方の日本海沿岸地域における中新統の石灰質ナンノ化石層序.瑞浪市化石博物館研究報告(Bull. Mizunami Fossil Mus.), no. 24, 27–38.
平中宏典・松原成圭・黒川勝己(Hiranaka, H., Matsubara, S. and Kurokawa, K.), 2002, 新発田市北東の内須川層と津川町野村層の中新世火山灰層の対比.地質雑(Jour. Geol. Soc. Japan), 108, 201–204.
平中宏典・柳沢幸夫・黒川勝己(Hiranaka, H., Yanagisawa, Y. and Kurokawa, K.), 2004, 新潟県中条地域中新統内須川層のテフラ層序.地球科学(Earth Sci.), 58, 105–120.
平中宏典・柳沢幸夫・黒川勝己(Hiranaka, H., Yanagisawa, Y. and Kurokawa, K.), 2009, 新潟県中央部における後期中新世テフラの対比.地質雑(Jour. Geol. Soc. Japan), 115, 177–186.
星 博幸(Hoshi, H.), 2002, 熊野酸性火成岩類の古地磁気方位.地質調査研究報告(Bull. Geol. Surv. Japan), 53, 43–50.
星 博幸・岩野英樹・檀原 徹(Hoshi, H., Iwano, H. and Dan-hara, T), 2002, 瀬戸内火山岩類のフィッション・トラック年代測定: 近畿地方, 二上層群の例.地質雑(Jour. Geol. Soc. Ja-pan), 108, 353–365.
星 博幸・岩野英樹・檀原 徹・吉田武義(Hoshi, H., Iwano, H., Danhara, T. and Yoshida, T.), 2003, 紀伊半島, 潮岬火成複合岩類のフィッション・トラック年代測定.地質雑(Jour. Geol.
Soc. Japan), 109, 139–150.星 博 幸・ 三 輪 健 治・ 川 上 裕(Hoshi, H., Miwa, K. and
Kawakami, Y.), 2004, 古地磁気方位の比較からみた熊野酸性岩類北部と南部及び室生火砕流堆積物の時間関係.地質雑(Jour. Geol. Soc. Japan), 110, 103–118.
Hoshi, H. and Yokoyama, M., 2001, Paleomagnetism of Mio-cene dikes in the Shitara basin and the tectonic evolution of central Honshu, Japan. Earth Planets Space, 53, 731–739.
Hurford, A. J. and Green, P. F., 1983, The zeta age calibration of fission-track dating. Isotope Geosci., 1, 285–317.
池辺展生・千地万造・両角芳郎(Ikebe, N., Chiji, M. and Morozu-mi, Y.), 1975, 浮遊性有孔虫層序からみた熊野層群のLepidocy-clina層準.大阪市立自然史博物館研究報告(Bull. Osaka Mus. Nat. Hist.), no. 29, 81–89.
岩野英樹・檀原 徹・星 博幸・川上 裕・角井朝昭・新正裕尚・和田穣隆(Iwano, H., Danhara, T., Hoshi, H., Kawakami, Y., Sumii, T., Shinjoe, H. and Wada, Y.), 2007, ジ ル コ ン のフィッション・トラック年代と特徴からみた室生火砕流堆積物と熊野酸性岩類の同時性と類似性.地質雑(Jour. Geol. Soc. Ja-pan), 113, 326–339.
Iwano, H., Yamashita, T. and Danhara, T., 1996, Three-dimen-sional analysis of fission track length in minerals―A mea-suring system and its application―. Fission Track Newsl., no.9, 13–22.
岩野英樹・吉岡 哲・檀原 徹(Iwano, H., Yoshioka, T. and Dan-hara, T.), 2000, フィッション・トラック法による年代およびウラン濃度算出式の再検討: 次世代年代測定システムに向けて.フィッション・トラックニュースレター(Fission Track Newsl.), no.13, 1–10.
片平忠実(Katahira, T.), 1974, 新潟県中部・北部地域の含油新第三系の層序―新潟県中越・下越地方の石油地質学的研究(そのI)―.石油技術協会誌(Jour. Japan. Assoc. Petrol. Tech.), 39, 167–178.
加藤 進・荒木直也・片平忠実(Kato, S., Araki, N. and Katahira, T.), 1992, 新潟県中越地域の地下に発達する七谷層.瑞浪市化石博物館研究報告(Bull. Mizunami Fossil Mus.), no.19, 363–372.
川上 裕・星 博幸(Kawakami, Y. and Hoshi, H.), 2007, 火山―深成複合岩体にみられる環状岩脈とシート状貫入岩: 紀伊半島, 尾鷲―熊野地域の熊野酸性火成岩類の地質.地質雑(Jour. Geol. Soc. Japan), 113, 296–309.
Kawakami, Y., Hoshi, H. and Yamaguchi, Y., 2007, Mechanism of caldera collapse and resurgence: Observations from the northern part of the Kumano Acidic Rocks, Kii peninsula, southwest Japan. Jour. Volcanol. Geotherm. Res., 167, 163–281.
小林巌雄・立石雅昭(Kobayashi, I. and Tateishi, M.), 1992, 新潟地域における新第三系の層序と新第三紀古地理.地質学論集(Mem. Geol. Soc. Japan), no. 37, 53–70.
黒川勝己・星野勝紀・石田隆一(Kurokawa, K., Hoshino, K. and Ishida, R.), 1998, 新潟県下田村五百川周辺の七谷層相当層(中新世中期)中の凝灰岩層.新潟大学教育学部紀要自然科学編(Bull. Fac. Educ., Niigata Univ., Nat. Sci.), 39, 47–75.
黒川勝己・長橋良隆・吉川周作・里口保文(Kurokawa, K., Naga-hashi, Y., Yoshikawa, S and Satoguchi, Y.), 2008, 大阪層群の朝代テフラ層と新潟地域のTzwテフラ層の対比.第四紀研究(Quatern. Res.), 47, 93–99.
黒川勝己・大海知江子(Kurokawa, K. and Ooumi, C.), 2000, 新潟県東蒲原郡津川町周辺の花立層・野村層(中~後期中新世)のハイアロクラスタイトと火山灰層.新潟大学教育人間科学部紀要自然科学編(Mem. Fac. Educ. Hum. Sci., Niigata Univ., Nat. Sci.), 2, 33–110.
Kurokawa, K. and Tomita, Y., 1998, The Znp-Ohta Ash; an ear-ly Pliocene widespread subaqueous tephra deposit in central Japan. Jour. Geol. Soc. Japan, 104, 558–561.
町田 洋・新井房夫(Machida, H. and Arai, F.), 1976, 広域に分布する火山灰―姶良Tn火山灰の発見とその意義―.科学(Kagaku), 46, 339–347.

地質雑 117( 5 ) 新潟堆積盆七谷層中に見つかった中期中新世 Kbiテフラ 287
町田 洋・新井房夫(Machida, H. and Arai, F.), 2003, 新編火山灰アトラス–日本列島とその周辺[Atlas of tephra in and around Japan].東京大学出版会(Univ. Tokyo Press), 336p.
米谷盛寿郎(Maiya, S.), 1978, 東北日本油田地域における上部新生界の浮遊性有孔虫層序.日本の新生代地質(池辺展生教授記念論文集)(Cenozoic Geology of Japan, Prof. N. Ikebe Memori-al Volume), 35–60.
米谷盛寿郎(Maiya, S.), 1987, 裏日本油田地域における底生有孔虫化石帯区分の現状と問題点.石技誌(Jour. Japan. Assoc. Pet-rol. Tech.), 52, 351.
米谷盛寿郎(Maiya, S.), 1988, 有孔虫化石群の変遷に見られる新第三紀イベント.土 隆一ほか編, 新第三紀における生物の進化・変遷とそれに関するイベント , 大阪市立自然史博物館(Osaka Mus. Nat. Hist.), 31–48.
米谷盛寿郎・井上洋子(Maiya, S. and Inoue, Y.), 1973, 微化石研究のための効果的岩石処理法について.化石(Fossil), no.25/26, 87–96.
松崎達二・角田地文・石丸恒存・鎌田浩毅・檀原 徹・岩野英樹・吉岡 哲(Matsuzaki, T., Kakuta, C., Ishimaru, T., Kamata, H., Danhara, T., Iwano, H. and Yoshioka, T.), 2004, 大規模火砕流による基盤岩への熱的影響の検討―フィッション・トラック法による熱履歴解析―.応用地質(Jour. Japan Soc. Eng. Geol.), 45, 238–248.
三梨 ・宮下美智夫(Mitsunashi, T. and Miyashita, M.), 1970, 日本油田・ガス田図no. 9,「七谷」[Geological Maps of Oil and Gas Field of Japan, 9, Nanatani], 地質調査所(Geol. Surv. Japan).
三梨 ・宮下美智夫(Mitsunashi, T. and Miyashita, M.), 1974, 七谷・大谷川流域の層序及び構造.地質調査所報告(Rep. Geol. Surv. Japan), no. 250–1, 25–50.
三田 勲・高橋雅紀(Mita, I. and Takahashi, M.), 1998, 房総半島, 中部中新統木の根層および天津層下部の石灰質ナンノ化石層序.地質雑(Jour. Geol. Soc. Japan), 104, 877–890.
Miura, D., 1999, Arcuate pyroclastic conduits, ring faults, and coherent floor at Kumano caldera, southwest Honshu, Ja-pan. Jour. Volcanol. Geotherm. Res., 92, 271–294.
三浦大助・和田穣隆(Miura, D. and Wada, Y.), 2007, 西南日本前縁の圧縮テクトニクスと中期中新世カルデラ火山.地質雑(Jour. Geol. Soc. Japan), 113, 283–295.
三輪美智子・柳沢幸夫・山田 桂・入月俊明・庄司真弓・田中裕一郎, 2004, 新潟県北蒲原郡胎内川における鮮新統鍬江層の浮遊性有孔虫化石層序̶No. 3 Globorotalia inflata bed下限の年代について―. 石技誌, 69, 272–283.
中嶋輝允・牧本 博・平山次郎・徳橋秀一(Nakajima, T., Makimo-to, H., Hirayama, J. and Tokuhashi, S.), 1981, 鴨川地域の地質[Geology of the Kamogawa district].地域地質研究報告(5万分の 1図幅)(Quadrangle Series, scale 1: 50,000), 地質調査所(Geol. Surv. Japan), 107p.
西田史郎(Nishida, S.), 1990, 御蓋山とその周辺の地形と地質.史跡春日大社境内内地実態調査報告及び修景整備基本構想策定報告書, 春日顕彰会, 109–127.
西岡芳晴・尾崎正紀・寒川 旭・山元孝広・宮地良典(Nishioka, Y., Ozaki, M., Sangawa, A., Yamamoto, T. and Miyachi, Y.), 2001, 桜井地域の地質[Geology of the Sakurai district].地域地質研究報告(5万分の 1図幅)(Quadrangle Series, scale 1: 50,000), 地質調査所(Geol. Surv. Japan), 141p.
西岡芳晴・尾崎正紀・山元孝広・川辺孝幸(Nishioka, Y., Ozaki, M., Yamamoto, T. and Kawabe, T.), 1998, 名張地域の地質[Geol-ogy of the Nabari district].地域地質研究報告(5万分の 1図幅)(Quadrangle Series, scale 1: 50,000), 地質調査所(Geol. Surv. Japan), 72p.
Oda, M., 1977, Planktonic foraminiferal biostratigraphy of the late Cenozoic sedimentary sequence, Central Honshu, Ja-pan. Sci. Rep. Tohoku Univ., 2nd ser.(Geol.), 48, 1–72.
Okada, H. and Bukry, D., 1980, Supplementary modification and introduction of code numbers to the low-latitude coco-lith biostratigraphic zonation. Marine Micropaleont, 5, 321–325.
大村一蔵(Omura, I.), 1928, 石油地質学概要(十六).地球(Chikyu), 9, 70–78.
Otofuji, Y., Itaya, T. and Matsuda, T., 1991, Rapid rotation of sauthwest Japan-paleomagnetism and K–Ar ages of Mio-cene volcanic rocks of southwest Japan. Geophys. Jour. Int., 105, 397–405.
Otofuji, Y., Kambara, A., Matsuda, T. and Nohda, S., 1994, Counterclockwise rotation of Northeast Japan: Paleomag-netic evidence for regional extent and timing of rotation. Earth Planet. Sci. Lett., 121, 503–518.
尾崎正紀・寒川 旭・宮崎一博・西岡芳晴・宮地良典・竹内圭史・田口雄作(Ozaki, M., Sangawa, A., Miyazaki, K., Nishioka, Y., Miyachi, Y., Takeuchi, K. and Taguchi, Y.), 2000, 奈良地域の地質[Geology of the Nara district].地域地質研究報告(5万分の 1図幅)(Quadrangle Series, scale 1: 50,000), 地質調査所(Geol. Surv. Japan), 162p.
Saito, T., 1963, Miocene planktonic foraminifera from Honshu, Japan. Sci. Rep. Tohoku Univ., 2nd ser.(Geol.), 35, 123–209.
佐々木清隆(Sasaki, K.), 1973, 新潟県五百川地区の新第三系に含まれるアミノ酸類の堆積学的研究.地質雑(Jour. Geol. Soc. Ja-pan), 79, 427–439.
佐藤時幸(Sato, T.), 1982, 石灰質微化石群集に基づく七谷層と西黒沢層の生層序的考察.石技誌(Jour. Japan. Assoc. Petrol. Tech.), 47, 374–379.
佐藤時幸・馬場 敬・大口健志・高山俊昭(Sato, T., Baba, K., Oh-guchi, T. and Takayama, T.), 1991, 日本海側における海成下部中新統の発見と東北日本の台島期―西黒沢期における環境変動.石技誌(Jour. Japan. Assoc. Petrol. Tech.), 56, 263–279.
菅野耕三・中世古幸次郎(Sugano, K. and Nakaseko, K.), 1975, 新潟堆積盆地中部の化石放散虫群集について.大阪教育大学紀要(Osaka Kyoiku Univ. Repository), 24, 159–166.
Suzuki, K., 1988, Heterogeneous distribution of uranium within zircon grains: Implications for fission-track dating. Jour. Geol. Soc. Japan, 94, 1–10.
高山俊昭(Takano, T.), 1978, 石灰質ナンノプランクトン.高柳洋吉編, 微化石研究マニュアル , 朝倉書店(Asakura Publishing), 51–59.
田村糸子・山崎晴雄・水野清秀(Tamura, I., Yamazaki, H. and Mizuno, K.), 2005, 前期鮮新世 4.1 Ma頃の広域テフラ , 坂井火山灰層とその相当層.地質雑(Jour. Geol. Soc. Japan), 111, 727–736.
Taylor, J. R., 1982, An introduction to error analysis: The study of uncertainties in physical measurements. Univ. Sci. Books, Mill Valley, CA, 270p.
富田裕子・黒川勝己(Tomita, Y. and Kurokawa, K.), 1999, 中央日本における 2.7 Ma頃の広域火山灰層; 土生滝I(大阪層群)-MT2(氷見層群)-Arg-2(西山層)火山灰層の対比.地質雑(Jour. Geol. Soc. Japan), 105, 63–71.
津田禾粒・白井健裕・長谷川美行・新川 公(Tsuda, K., Shirai, T., Hasegawa, Y. and Niikawa, I.), 1984, 表層地質図「加茂」, 土地分類基本調査「加茂」説明書[Subsurface Geological Map, Kamo, explanatory text], 27–43, 新潟県(Niigata Prefecture).
津田宗茂(Tsuda, M.), 1992, 新潟・長野地域.改訂版日本の石油・天然ガス資源[Petroleum and Natural Gas Resources of Ja-pan, Revised Edition]*, 天然ガス鉱業会・大陸棚石油開発協会(Japan Nat. Gas Assoc. and Japan Offshore Petrol. Devel-opment Assoc.), 81–127.
Wagner, G. A., 1988, Apatite fission-track geochrono-thermom-eter to 60°C: Projected length studies. Chem. Geol. (Isot. Geosci. Sec.), 72 145–153.
山下 透・檀原 徹・岩野英樹・星 博幸・川上 裕・角井朝昭・新正裕尚・和田穣隆(Yamashita, T., Danhara, T., Iwano, H., Hoshi, H., Kawakami, Y., Sumii, T., Shinjoe, H. and Wada, Y.), 2007, 紀伊半島北部の室生火砕流堆積物と周辺に分布する凝灰岩の対比およびそれらの給源: 軽鉱物屈折率を用いたモード分析によるアプローチ.地質雑(Jour. Geol. Soc. Japan), 113, 340–352.

288 工藤 崇ほか 2011―5
柳沢幸夫(Yanagisawa, Y.), 1993, 新潟堆積盆地の七谷層および寺泊層相当層の炭酸塩団塊から産出した中期中新世珪藻化石群.日本珪藻学会誌(Diatom), 8, 51–62.
Yanagisawa, Y. and Akiba, F., 1998, Refined Neogene diatom biostratigraphy for the northwest Pacific around Japan, with
an introduction of code numbers for selected diatom bioho-rizons. Jour. Geol. Soc. Japan, 104, 395–414.
*English translation from the original written in Japanese
(要 旨)
工藤 崇・檀原 徹・岩野英樹・山下 透・三輪美智子・平松 力・柳沢幸夫,2011,新潟堆積盆七谷層中に見つかった中期中新世広域テフラ:Kbiテフラと紀伊半島室生火砕流堆積物の対比.地質雑,117,277–288.(Kudo, T., Danhara, T., Iwano, H., Yamashita, T., Miwa, M., Hiramatsu, C. and Yanagisawa, Y., 2011, A Middle Miocene widespread tephra in the Nanatani Formation of the Niigata sedimentary basin, northeast Japan: Correlation between the Kbi tephra and the Muro Pyroclastic Flow Deposit in Kii Pen-insula. Jour. Geol. Soc. Japan, 117, 277–288.) 新潟堆積盆加茂地域において,中部中新統の七谷層から黒雲母に富むテフラを発見し,
駒出川バイオタイト(Kbi)テフラと命名した.本テフラは灰色を呈する層厚 9 cmの結晶質中粒~粗粒砂サイズの凝灰岩で,七谷層上部の明灰色泥岩中に挟在する.本テフラの構
成鉱物は石英,斜長石(オリゴクレース~ラブラドライト組成),サニディン,黒雲母を主
体とし,微量のざくろ石,赤色および無色のジルコンを伴う.本テフラは浮遊性有孔虫化
石帯区分の N.9帯,石灰質ナンノ化石帯区分の CN4帯に含まれ,堆積年代は 14.2~14.7 Maと見積もられる.本テフラのジルコン FT年代は 14.6±0.3 Maであり,微化石層序と良く調和する.記載岩石学的特徴,FT年代,微化石層序の一致から,Kbiテフラ,紀伊半島の室生火砕流堆積物,房総半島木の根層中の Kn-1テフラの三者は対比可能であり,熊野酸性岩の形成に関連した広域テフラの可能性が高い.